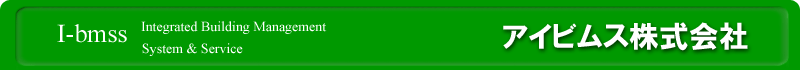
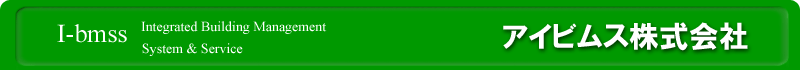 |
|||
| Topics (�ȃG�l�A���@��̏��) | |||
| ���@�@[�@2025/12�@]�@�@�� |
|
|
| ��J�p���[�A�`���E�U�� �~�o�j���ō����v�^�r�����Ő��k�͔| J�p���[�́A�_�ƎQ���x���Ȃǂ���|����v�����g�t�H�[���Ƌ����ŁA���̗���{�B�Ɛ��k�͔|���ɍs���z�^�̐H�����Y�V�X�e���̎����J�n�����Ɣ��\�����B �`���E�U���̔r�����𗘗p���ăo�j�����͔|����B�{�B���̔r������A�����h�{���z������o�N�e���A���엿�ɕ������邱�Ƃʼn��w�엿�����ŐA������Ă�A�u�A�N�A�|�j�b�N�X�v�Ƃ����z�^�V�X�e����������B�A�����h�{���z�����邱�ƂŐ�������邽�߁A�]���^�̔_�Ƃɔ�ׂĐ��̎g�p�ʂ�90%�ȏ�팸�ł���Ƃ����B�`���E�U����p�����A�N�A�|�j�b�N�X�͐��E���B���͐V���������s�ɂ���v�����g�t�H�[���̎����{�݂ōs���Ă���B �o�j���͋ߔN�A���Y�n�̋C��ϓ��ɂ����ʌ�����V�����ł̎��v�g���w�i�ɁA���ۓI�Ȏ�����i���}�����Ă���B����̋������ł́A�v�����g�t�H�[�������{�B�r�������p�����ԙ��i�����j�̊J�ԑ��i�Ɋւ�������Z�p�����p����B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���u�y���u�X�J�C�g���z�d�r�v1m���^�ϐ����w�A���N�x���ɂ����� �ϐ����w��1m���̃y���u�X�J�C�g���z�d�r��2025�N�x���ɂ����Ɖ�����B2030�N�x�̖ڕW�ł���N��1GW���Ɍ����āA�Z�p�ʂ̋l�߂�i�߂�B 2025�N�x�̎��Ɖ���ڎw���A���L�ݔ��Ő������s�����j���ł߂Ă����B�ʎY�ɐ�삯�������ݔ��ɂ�����1m���̏��ʐ��Y�ɂ��̔��ɂ��ẮA2025�N�x������2026�N�x�O����ڎw���B�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J���Ő�s����ϐ����w�������������Y�ɏ��o�����ƂŁA�{�i���y�Ɍ������������������������B ���ł�30cm���ł̃��[���E�c�[�E���[���iR2R�j�����v���Z�X���m�����Ă��邪�A1m���̐����Z�p�̊m���͂��悻3�{�̖ʐςɃ~�N�����I�[�_�[�ŋψ�ɍޗ���h��d�˂Ă������߁A��x�������Ƃ����B �ʎY�ɍۂ��ẮA�V���[�v�̖{�ЍH������p����\�肾�B�����̐ݔ��́A�����I�ɓ��H��ɏW�錩�ʂ��ł���B27�N�x�ɂ�900���~�𓊂��āA100�l�v�̑�P���Y���C���̉ғ���\��B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���~�d�r�Ď��E�f�f�T�[�r�X�A27�N�ȍ~�Ɏs��g�� �x�m�o�ς́A�u�~�d�r���Ď����A��Ԃ�f�f����Z�p�E�T�[�r�X�v�Ɋւ��鍑���s��̒������ʂ\�����B �����_�œ��s��͏��������A������v�g�傪�\�z����A2035�N�ɂ�69���~�K�͂ɐ�������Ɨ\������B���s��́A��u�p�~�d�r��������s���Ă���A2025�N�͎ԍړd�r�����������オ�����B��Ԃ̐f�f�����S�ł���A�~�d�����Ǝ҂�d�C�����ԁiEV�j���[�X��ЂȂǂł̗��p��������B2035�N�̓��s��̓���́A��u�p�~�d�r������42���~�A�ԍړd�r������27���~�Ɨ\������B ��u�p�~�d�r�̐ݒu��������̂ɔ����A���T�[�r�X�̗̍p�ɂ���Ē~�d�r�����e�i���X�̌����������܂邱�Ƃ���A���v�g�傪�\�z�����B�܂��A�����𑽂��܂�EV�̗A�o���i���Ȃǂ��i�݁A�ԍڗp���`�E���C�I���~�d�r�̗��p���g�傷��ƌ�����B�g�p�ςݎԍڗp���`�E���C�I���~�d�r�̗��p�����ɂ����v�̍��܂���s��g��ɍv�����錩�ʂ��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����{�K�C�V�uNAS�d�r�v���ƓP�ށA�������Ƃ̉��i�����Ŏ��v���ʂ��� ���{�K�C�V�́A��e�ʒ~�d�r�uNAS�d�r�v�̐����Ɣ̔����I������Ɣ��\�����B�������ɂ��ቿ�i�̃��`�E���C�I���d�r���s��ɗ������Ă��邱�Ƃ�A���ޗ����ŏ����I�Ɏ��v���m�ۂ��邱�Ƃ�����Ɣ��f�����B���Ђ�NAS�d�r��40�N�ɂ킽��J���E���Ɗ������������B���Ƃ̓P�ނɂ��2026�N3�����̘A�����Z�ɖ�180���~�̓��ʑ������v�シ��B �P�ނ̎���͉��i�����̌������B���{�K�C�V��NAS�d�r���������Ԃ̒~�d�\�͂̎��v���L�т�ƌ�����ł������A�z����������������B���̊Ԃɐ��E�I�ɓd�C�����ԁiEV�j�s�ꂪ�������A����������ʐ��Y�������`�E���C�I���d�r���~�d�r�s��ɗ����BNAS�d�r�͐��\�ʂł͗D������A���ޗ��̍���������̎Z���Ƃ邱�Ƃ�����Ȃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�ăG�l�{CO2����{�{�B�E�_�Ɓv�A�G�A�E�E�H�[�^�[�����{�s�ɉғ� �G�A�E�E�H�[�^�[�́A���쌧���{�s�ɒn��̎��������p�����o�C�I�}�X���d��CO2����E���p�A�{�B�Ɣ_�Ƃ�g�킹�������z�^�̃��f���{�݁u�n���̌b�݃t�@�[���E���{�v�����݂��A10������{�i�I�ɉғ��������B ���{�݂́u�o�C�I�}�X�E�K�X���v�����g�v�u���^�����y�v�����g�v�u�X�}�[�g����{�B�v�����g�v�u�X�}�[�g�_�ƃn�E�X�v��4�̐ݔ��ō\�������B �E�o�C�I�}�X�E�K�X���v�����g�́A�Ԕ��ނȂǂ��K�X���F�ʼnR���K�X�ɕ������A�K�X�G���W�����d�@�̔R���ɂ���B���d�o�͂�150kW�B �E���^�����y�v�����g�́A�H�i�p�����y�����ăo�C�I���^�������A�����R���ɔ��d����B�o�͂�300kW�B �E�r�M�����^�����y�v�����g��{�B�E�_�ƃn�E�X�̉��x�����Ȃǂɗ��p����B �E�X�}�[�g�_�ƃn�E�X�́A�����z���p��ʂ��������\�Ȕ_��Ɛ��Y����є_�ƋZ�p���m������B�͔|�ʐς�600m 2�A�͔|�i�ڂ̓g�}�g�A�L���E���A�C�`�S�ȂǁB �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��������d�͌v�ɂ`�h��Ձ^�G�k�r�f�B�A�A�����Q���� �Ĕ����̑��̃G�k�r�f�B�A���X�}�[�g���[�^�[����ɍ����S�������Ă���B �X�}�[�g���[�^�[�̃x���_�[���m���A�g���A�\�t�g�E�G�A���X�V���邾���ŋ@�\�̌����}���u�\�t�g�E�G�A��`�^�v�̃��[�^�[�V�X�e����z�����߂̃v���b�g�t�H�[�����\�z���A���{���܂ސ��E�e�n�Œ��Ă��������l�����B���̂قǗ��������}�[�N�E�V���s�[���[�E�O���[�o���G�l���M�[�Y�ƒS���V�j�A�}�l�[�W���O�f�B���N�^�[�́u���{�Ɠ��̐l�H�m�\���f�����v���b�g�t�H�[���̌`�ň�ĂĂ��������v�ƈӋC���݂��������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���s����K�̓r����CO2�r�o���т��u�����鉻�v�A�u�����s�L���b�v���g���[�h���x�E�_�b�V���{�[�h�v���\�J�n �����s�L���b�v���g���[�h���x�ł́A���N�x�A���Ə������o���ꂽ�f�[�^���g�����ǂ̃z�[���y�[�W�ɂČ��\���Ă����B ����A���\�̂�������������A���Ə��̃f�[�^�ɂ��āA�ߋ�����̐��ځA�s�����ϒl�⑼���Ə��Ƃ̔�r�����܂߂āA��ڂł킩��悤�Ɂu�����鉻�v�����B�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����������O�̓����Ƃ��āA�V�z���z���̊����\�����ł͂Ȃ��A�������z���ɂ�����CO2�r�o�ʂ�G�l���M�[�g�p�ʂ̃p�t�H�[�}���X�ɂ����ڂ��W�܂��Ă���B����̐V���ȁu�����鉻�v�̎�g�ɂ��A�E�Y�f���ɐϋɓI�Ȏ��Ə����A�����Ƃ���Z�@�ցA����擙����I��A�Љ�o�ϓI�ȕ]��������ɍ��܂邱�Ƃ�ڎw���Ă���B �s����K�̓r����H�ꓙ�́A�ECO2�r�o�ʂ⏰�ʐϓ�����̃G�l���M�[�g�p�ʂ̐��ڂ���ڂł킩��B.�����s���̕��ϒl���ʃ��x���Ƃ̔�r���ł���B.�����p�r�⏰�ʐς̑傫���Ȃǂ��ގ����鎖�Ə��Ɣ�r�ł���B.�Đ��\�G�l���M�[�̗��p��������ڂł킩��B �o�T�u�����s���ǁv |
|
|
| ���w�Z�v�[���ɂ����ۂ�@�E�Y�f�i�߂�z�O�s�ŗL�����p��čZ���̓d���Ȃ�2�����܂��Ȃ� �z�O�s�̏��w�Z�Ŏg��Ȃ��Ȃ����X�y�[�X�ɑ��z���p�l�����ݒu����A�E�Y�f����i�߂�ƂƂ��ɁA�q�ǂ������̊��ӎ������߂邱�Ƃɂ��Ă���B���R���w�Z�ł́A�v�[���Ɏ��t�������z���p�l���̎����^�]���n�܂����B ������2����1�̕⏕���A�����Ɣ�2500���~�ŁA���z���p�l�����v�[���̗e�ςɂ����悤��91���ݒu���܂����B����ň�ʉƒ남�悻10�����́A�N��3��2000��Wh�̔��d��������ł��āA�w�Z�̓d���Ȃǂ̓d�͂̂��悻2�����܂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�w�Z�ł͊��w�K�ɂ����p���邱�Ƃɂ��Ă���B ���R���w�Z�ł�11����{����{�i�I�Ȕ��d���n�߁A���N�x�ȍ~�͂ق��̏��w�Z�̃v�[���ł������������B �o�T�u���e���v |
|
|
| ���f�r���A�T�Ɩk�C����w�����������Ŋv�V�I��CO2��������Z�p���J�� GS���A�T�́A�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����A�k�C����w�Ƃ̋��������ŁA�d�C���͂����p�����v�V�I�� CO2��������Z�p���J�����ACO2��������V�X�e���̏��^���؋@���ғ��J�n�����B �{�Z�p�́AGS���A�T�Ǝ��� pH�X�C���O�@�\�i�d�C���w�I��pH�𐧌䂷��j���̗p���邱�Ƃō����G�l���M�[�������������A99���ȏ�̍��Z�x�� CO2�K�X������ł���_�A����ъ����ׂ��Ⴂ�_�������B CO2��������V�X�e���̏��^���؋@��CO2�����ʂ�2kg/day�܂ō��߁A����Ɏ��̃X�e�b�v�ł́A���؋@�̑�^����}��A���̏����ʂ� 1t/day���x���܂Ŋg�����邱�Ƃ�ڎw���B�{�Z�p��p���邱�ƂŁA�����ׂ��Ⴂ�������������āA�H�i�H���������Ȃǂ̒��E���K�͐ݔ��ł��������� CO2�̕���������\�ƂȂ�A���l�Ȍ���ւ̓����g�傪���҂����B �o�T�uGS���A�T�v |
|
|
| ���d���J���A�č�MIT���X�^�[�g�A�b�v�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�Z�p�ɏo�� �d���J���iJ�p���[�j�́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J������|����ăA�N�e�B�u�T�[�t�F�C�X�֏o�������Ɣ��\�����B �A�N�e�B�u�T�[�t�F�C�X�́AMIT��10�N�ȏ�̌������ʂƓ����Q����ՂƂ���2022�N�ɐݗ�����A���݂͔N��1MW�̐��Y�̐��𐮂��Ă���A2027�N����N��100MW�̐��Y��ڎw���Ă���B���Ђ̃t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A�ݒu�R�X�g���ő�10����1�ɍ팸�ł���B �܂��A�����E�����x�Ƃ����������ɂ�����ϋv���������A���d����25.2���ȏ�A�ϋv��10�N�ȏ�Ƃ������\��č��G�l���M�[�ȁE�����Đ��\�G�l���M�[����������F����Ă���B�������[���E�c�[�E���[�������Ǝ������H���ɂ��A���������܂�����������Ƃ����B�_�f�⎼�x�ɂ��ω����X�N�ɑ��镕�~�Z�p�▌�ψꐫ�ɗD�ꂽ����Z�p������A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̉ۑ�ł���ʎY���E�ϋv���E�R�X�g�������ł���Ɗ��҂���Ă���Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ����5���ȃG�l�ł���A�n���̍ăG�l�u�n���M�v�ɊS�����܂��Ă��� �n���́u�n���M�v�ɊS�����܂��Ă���B���Ȃ�����������Љ��Z�~�i�[���J����600�l�ȏオ���u�����B�n���M�����p����Ƌ�啝�ɏȃG�l���M�[���ł���B �ۑ�ƂȂ��Ă��錚���̒E�Y�f���ɈЗ͂�����B�Z�~�i�[�ł͗Z��Ȃǒn��̉ۑ�����Ɍ��т����Љ������A���y�ւ̌㉟���ƂȂ肻�����B�n���M�́A�����R�X�g���������A��5���̏ȃG�l���\�B�Ɏg���n���M�q�[�g�|���v�̗v������3000����ɂƂǂ܂�B���Ȃ͎���Z�~�i�[���J�����B �E�������W�쒬�͓��̉w�ɐݒu�����n���M�V�X�e�����Љ���B�āA���ݏグ���M�������̋ɑ���A�~�͒��ԏ�ɍ~��������A�n���M���g���ėn�����B �E���s�͑ѐ��w�~�M�V�X�e���iATES�j�𐄐i�B�M����������ɔ�ׂ�Ƒ傫�ȔM�G�l���M�[�������A��K�̓r���̋��ȃG�l���ł���B���ݏグ���n�����S�ʂ�n���ɖ߂����ƂŒn�Ւ������N�����Ȃ��Z�p���m���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���O���[�����f�����Ɍ��������{�ő��P2G�V�X�e���ɂ��G�l���M�[���v�]�������J�n �T���g���[�V�R����A���v�X���B�H��y�уT���g���[���B�������̒E�Y�f���Ɍ������u�J�[�{���j���[�g����������������K�� P2G�V�X�e���ɂ��G�l���M�[���v�]���E���p�Z�p�J���v�ɌW����Ƃ��āA�O���[�����f�̐����y�сA�V�R���H��ł̗��p���J�n�����B ����A�ݒu����O���[�����f�����ݔ��̔\�͂�16MW�Ɠ��{�ő�ł���A24����365���ғ������ꍇ�A�N��2,200t�̐��f�����A16,000t��CO2�r�o�ʂ̍팸���\���B���p�ʂł́A�������A��NOX�̐��f�{�C�����J�����A�V�R���H��Ŏg���M���̈ꕔ��V�R�K�X���琅�f�ɓ]���������i�߂�B���ؒn���u�O���[�����f�p�[�N-���B-�v�Ɩ��������B �R�������тɋZ�p�J���Q���� 10�Ђ͈��������A�J�[�{���j���[�g�����Љ�̎����Ɍ����A�ő̍����q�iPEM�j�`���d���ɂ��O���[�����f�����̋Z�p�J���ɉ����A���f�G�l���M�[�̎��v�g��֎��g�ށB �o�T�u�R�����v |
|
|
| ���@�@[�@2025/11�@]�@�@�� |
|
|
| ��UBE�O�H�Z�����g�A�������E�Z�����g�Đ��ɓV�R�K�X���p�ΒY40����� UBE�O�H�Z�����g�iMUCC�j�́A���K�X�ADaigas�G�i�W�[�A�����K�X�Ƌ����ŁAMUCC��B�H�ꍕ��n��̃Z�����g�Đ��p�L�����̔M�G�l���M�[���Ƃ��āA�V�R�K�X�����Ă�������؎����ɐ��������Ɩ��������B���Ɖ^�]���ɍ��Ă���͍̂������̎��g�݂ŁAMUCC��͍���̒�Y�f�Љ�̎����Ɍ������d�v�Ȉ���ƂȂ�ƁA���̈Ӌ`����������B �g�p�����V�R�K�X���ėp�o�[�i�[�́AMUCC�̔����Y�R�ċZ�p�Ƒ��K�X�EDaigas�G�i�W�[�̃K�X�R�ċZ�p����єR�ăV�~�����[�V�����Z�p�����p���A�V���ɋ����J���������́B���ł́A���o�[�i�[��p���āA�ΒY��40����V�R�K�X�ő�ւ��A���ƋK�͂ł̉^�]�����{�����B���̌��ʁA���Ƃ̈��萫��i�̕i���ɖ��Ȃ��A���ʂł��x�Ⴊ�Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�B �Z�����g�Đ��p�L�����Ŏg�p����ΒY�Ȃǂ���r�o�����CO2���팸�ł���B�V�R�K�X�ɑ����A�V�R�K�X����e�[���^���ւ̓]����ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������z�d�A�n���~�d�r�̎��v�{���^�^�p�T�[�r�X�� ���d�͑��z�d�́A���������s��Ōn���p�~�d�r���^�p���锭�d���ƎҁA�A�O���Q�[�^�[�̎��v��2�{�ɑ��₷�V���ȃT�[�r�X���J�n����Ɣ��\�����B ��i�o�͂Ōn���p�~�d�r���^�p����1��������̎��Ԃ́A�]���̋Z�p�ł�12���ԂɌ����邪�A�����z�d���擾���������Z�p�ł�24���ԂɊg��ł��A���v��{���ł���B �~�d�r�̎��������E����[���d�T�C�N�������啝�ɗ}���ł��A������2�{�ɉ�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���g���^���V�^�R���d�r�V�X�e�������J�q��������20�����ߏ��p�Ԍ������W�J �g���^���V�^�R���d�r�V�X�e�������J�B�ϋv����R��\�����߂����A�V���ɏ��p�ԂȂǂ̑�^�����̃��C���A�b�v���g�[�����B ���\�����R���d�r�V�X�e���́A���Ђ̒��ł͑�3����ɑ������郂�f���ƂȂ�B2019�N����͔R���d�r�V�X�e���̊O�̂��X�^�[�g�B����܂ł�MIRAI�Ȃǂ̏�p�Ԍ����A��u�p��S���A�D���Ȃǂł̗��p��z�肵���ėp������2��W�J���Ă������A����̑�3���ォ��͑�^���p�Ԍ����̃��C���A�b�v��lj������B �V�^�R���d�r�V�X�e���͑ϋv���\�Д��2�{�ɍ��߂��B��^���p�Ԍ����̃��f���̑ϋv���Əo�͂̓f�B�[�[���G���W�����������ł���A���^����}�������Ƃő����̎Ԏ�ɓW�J���\�Ƃ��Ă���B�R��\�ɂ��Ă����Д��1.2�{�Ɉ����グ�����Ƃɂ��A�q���������20���L����Ƃ����B�܂��A�R�X�g�ɂ��Ă��Z���v����v���Z�X�̉��P�ɂ��A�啝�ɍ팸����Ƃ��Ă���B2026�N�ȍ~�ɓ��{�≢�B�A�k�āA�����Ȃǂ̎s��ɓ�������v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����G�i�W�[�V�X�e���A���E�ŏ��N���X�̋z������p���j�b�g��V�����A�_�ƕ���ŏ����� ���G�i�W�[�V�X�e���́A�������z���≷���@�Ɨ�p���A�~�M���A�|���v�A�z�ǁA����@�퓙�̕t�ѐݔ������j�b�g�������A���E�ŏ��N���X�̗�p�V�X�e���������B �{�V�X�e���́A���d�@��R���v���b�T�[����r�o�����p�M���̖����p�G�l���M�[�⑾�z�M�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[���瓾���� 70���`90���̉����𗘗p����7���̗␅�����A��p���v�ɑΉ�����V�X�e�����B�ҏ��ɂ���p���v�����܂�_�ƕ�����͂��߁A�H�������{�݂ȂǑ��l�Ȍ���ł̊��p�����҂����B �O�d���̃g�}�g�͔|�p�_�ƃn�E�X�ɖ{�V�X�e���Ƒ��z�M�W�M���g�ݍ��킹���\�[���[�N�[�����O��p�V�X�e�����̗p���ꂽ�B���z�M�p�l�� 60m2��ݒu���A��90���̉������E�������z���≷���@�i17.6kW�~1��j�� 7���̗␅���B��1,930m2�̑��z���^�g�}�g�͔|�p�_�ƃn�E�X���p���A�ҏ����ł����肵���͔|���������B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| ���u���f���S�v���Y�ƋK�͂Ŏ��A�I�[�X�g���A�Œ��H �O�H�d�H�O���[�v��100���o������p�v���C���^���Y�e�N�m���W�[�Y�́A�p���E�I�[�X�g���A�̍H�ƁE������ƃ��I�e�B���g����уI�[�X�g���A�̓S�|�e�N�m���W�[��ƃt�F�X�g�A���s�[�l�Ƌ��͂��A�I�[�X�g���A�E�����c�̕~�n���ɐ��f�x�[�X�̐��S�Z�p���̗p�����Y�ƋK�͂̎��v�����g�𒅍H�����B ���v�����g�́A���f�x�[�X�̔����S�z�ΊҌ��Z�p�uHYFOR�v�ƁA���f�x�[�X�̒��ڊҌ�����ѓd�C���L�Z�p�uSmelter�v��g�ݍ��킹�ĘA�����Ƃ�����́B��i�ʂ��獂�i�ʂ܂ł�����S�z�ɑΉ��\�����A���v�����g�ł͐��E�����̑啔�����߂��.���i�ʍz�ɏd�_��u���B 2027�N���ɉғ�����\��ŁA�����\�͖͂���3t�̌����݁B HYFOR�́A�����S�z�ɑ��鐢�E���̒��ڊҌ��Z�p�ŁA�y���^�C�W���O�Ȃǂ̉��H�����s�v�ŁA���ڊҌ��S��z�b�g�u���P�b�g�A�C�A���Y����B�ሳ�̊Ҍ��K�X�A�v���Z�X���ł̕ߏW���o�̃��T�C�N���A�������������������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���A�Y�r������A�����㒴���g�������X�}�[�g���[�^�[�Ő����C���t���ۑ�����ɍv���[ Kamstrup�ЂƂ̋��ƂŁA���{�̐����C���t���ۑ�����ɍv���[ �A�Y�r������́A�X�}�[�g�������[�^�����O�̕���Ő��E�����[�h���� Kamstrup�Ёi�f���}�[�N�j�Ƌ��Ƃ��A�����㒴���g�������X�}�[�g���[�^�[��2026�N4���ȍ~�ɓ��{�s��֓W�J����ƂƂ��ɁA�@�B�w�K�Ɋ�Â��R�����m�N���E�h�T�[�r�X�����B ��̓I�Ȏ�g�݂́A�����㒴���g�������X�}�[�g���[�^�[�̓��{�s��W�J�]���^�̋@�B�����[�^�[�ɔ�ׁA�ᗬ�ʈ�ł������x�Ȓ����g�������X�}�[�g���[�^�[����{�����ɋ����ŊJ������B���[�^�[�́A���Ɍy�ʁE�R���p�N�g�ŁA�������Ȃ��\���ɂ��ϋv���ɗD��Ă���B�@�B�w�K�Ɋ�Â��R�����m�N���E�h�T�[�r�X�X�}�[�g���[�^�[�Ŏ��W�����m�C�Y�f�[�^���AKamstrup�̃N���E�h�ƘA�g���A100����ȏ���@�B�w�K�����f�[�^���͂ɂ���āA�X�}�[�g���[�^�[�̐ݒu�ꏊ����㗬���A�������̘R���G���A�x�������肷�邱�ƂŌ����I�Ȉێ��Ǘ�����������B Kamstrup�Ёi�{�ЁF�f���}�[�N�́j�X�}�[�g�������[�^�����O�̕���Ő��E�����[�h����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���H�i���X�����̏�œ��p�i�ɃA�b�v�T�C�N���BAI���ڂ�3D�v�����^�[�AMIT���J�� �A�����J�ł́A2030�N�܂łɐH���p����������Ƃ����ڕW�Ɍ����āA�H�i���X�Ɏ��g�ލ��Ɛ헪�\�����B ����ŁA�A�����J�����ɂ�����H�i�p������2023�N��7,390���g���ɒB���A����͐H�Ƌ����ʂ�31���ɑ�������B����ɁA�ƒ납��̐H�i�p�������ł������A�S�̂�35�����߂Ă���B���������H�i���X����芪������������̑ŊJ��Ƃ��āA�A�����J���̃t�[�h�e�b�N�����ڂ���Ă���B ��l��MIT�̑��Ɛ����J�������uFoodres.Ai Printer�v�́AAI�𓋍ڂ����f�X�N�g�b�v�^��3D�v�����^�[���B�uFoodres.Ai Printer�v�ɐH�i�p�������Z�b�g����ƁAAI�����p�����t���̃��o�C���A�v�����X�}�[�g�t�H���̃J������ʂ��ĐH�i�́B�����ɍ��킹�A���܂��܂ȓ��p�i���Ă���B���̌�A�H�i�p�����͈���\�ȃo�C�I�v���X�`�b�N�y�[�X�g�ɉ��H����A�R�[�X�^�[��e��Ȃǂɐ��܂�ς��Ƃ����d�g�݂��B �o�T�utable Source�v |
|
|
| �����D�D�A�k�CCCS�ɎQ��^�m���E�F�[�̂ʼnt��CO2��A�� ���D�D�́A�N�ԍő�700���g���̓�_���Y�f�iCO2�j�����ʂ����҂����m���E�F�[�̖k�C��CCS�i��_���Y�f����E�����j�v���W�F�N�g�u�n�t�X�g�C�F���l�v�̊J���ɎQ�悷��Ɣ��\�����B ���D�D�̉p���q��Ђƌ��n��CCS���Ɖ�Ђ������ŁACO2��r�o�����Ƃɉt��CO2�̗A���E�����T�[�r�X����邱�Ƃ�ڎw���B���n�̎��Ɖ�Ђ�2029�N�̒����J�n��ڕW�ɂ��Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���A�O���{���^�C�N�X�̖����^�_�Ƃւ̉e�� �A�O���{���^�C�N�X�́A�_�ƂƍăG�l�̗����������ے��I�ȋZ�p�Ƃ��Ĉʒu�Â����A�G�l���M�[����Ɣ_�Ɛ���̑o���Ɋ�^����u��Γ̑I�����v�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B ���z�����d�ł́A�y�n�̗��p���߂����Ĕ_�ƂƂ̑Η�����莋����Ă���B���d�{�݂��_�n���������鎖�Ԃ���������Ȃ���A�H�Ɗ�@�ɔ��Ԃ������Ă��܂����˂Ȃ��B ���������Ȃ��A�C�^���A�ɂ���~���m�H�ȑ�w���A�A�O���{���^�C�N�X�̉\���������������ʂ����\���ꂽ�B�����҂����̓p�l���̐ݒu�ɔ������˗ʂ̌����ɑ��A22��ނ̍앨���ǂ̂悤�ɔ������邩���V�~�����[�V�����B���܂��܂ȋC���n���I�̈�ɂ�����_�앨�̐��ݓI�Ȏ��n�ʂ�]�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�A�O���{���^�C�N�X���K�p�ł���n����������E�I�Ȓn�}������B���̌��ʁA���E���̔���_�n��22.35�����H�Ɛ��Y���p�����Ȃ���_�Ɨp�V�X�e���ɑΉ��ł���Ɛ��肳��Ă���B �o�T�utable Source�v |
|
|
| �����z��100���ʼnғ��A���E�ő�̋}���[�d�X�e�[�V�����u�e�X���E�X�[�p�[�`���[�W���[�v �ăe�X���iTesla�j�́A���E�ő�K�͂�EV�p�}���[�d�l�b�g���[�N��ăJ���t�H���j�A�B�ʼnғ��������B EV���p�҂����s���ɒZ���Ԃōq��������傫���������Ƃ��\�ɂ���B�X�[�p�[�`���[�W���[�E�l�b�g���[�N�́A�A�N�Z�X�̂��₷���A�M�����A�����Ē������[�d���d�����Đv����Ă���A���悻15���ōő�200�}�C���i��320�q�j�̍q��������lj��ł��鐫�\������Ă���B �u�v���W�F�N�g�E�I�A�V�X�v�ƌĂ��A���E�ő�K�͂̐V�^�X�[�p�[�`���[�W���[�E�X�e�[�V�����ł́A�ŏI�I��168��̏[�d�X�^���h�������v��ŁA���̂������݂͔�����84��ғ����Ă���B�[�d�X�^���h�͈�ؓd�͖Ԃɐڑ�����Ă��Ȃ��B �{�ݑS�̂ɂ͏o��11MW�̑��z���p�l�����ݒu����Ă���B10��̃e�X������u�p��^�~�d�r�u���K�p�b�N�v�ɒ��������B�e�ʂ�39MWh�B1���ɐ��S��̏[�d��d����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�_�n�ő��z�����d�v���y�փC�^���A�����@�ցA�y���u�X�J�C�g�^�Ŏ��� �C�^���A�̌����@�ւ́A�������̐V�^���z�d�r�u�y���u�X�J�C�g�^�v�̉��ō앨����Ă�ƁA�����������Ȃ邱�Ƃ��������B �������Ɏg���g���̌��������d�r�߂��ĐA���ɓ͂��B�����������K�x�Ɏ�߁A�n�ʂ̉ߔM��h���Ȃǂ��č앨�̗t��s�������ʂ�����B���z�d�r��ݒu����K�n�����钆�ŁA���d�Ɣ_�Ƃ��ɒS���V�X�e���̎����ɂȂ���B �앨�͗t��s�Ŏ����z�����G�l���M�[�Ɏg���A��_���Y�f�iCO2�j�Ɛ�����������ʼnh�{�������B�����A���z�������̋�������ƁA�������̑��x���オ��Ȃ��Ȃ�B������������Ηt�����߂���A�n�ʂ̉��x�����߂��肵�č앨�̐�����W����B����ȑ��z���̈ꕔ�z�d�r�ŎՂ��ēK�x�Ɏ�߂�A�����ɗL���ɂȂ�B �����Ŕ������̃y���u�X�J�C�g�^�ɒ��ځB�d�r�����ޗ��̐���������A�����x��F��ς�����B�܂��A�앨�͓���̔g���̉������������Ɏg���B���܂藘�p���Ȃ����͔��d�Ɏg����B �o�T�u�e���b�c�I�v |
|
|
| ���@�@[�@2025/10�@]�@�@�� |
|
|
| �����z�����d�́u�܂Ԃ����v�̖����������Z�����hῃ\�����[�V�������I ���Z���́u�����́E����WEEK 2025�v�ɏo�W���A�h῁i�ڂ�����j�d�l�̑��z���p�l����֘A�\�����[�V������W���B ��`�╨���{�݂Ȃǂ̑�^�ݔ��̉����ɑ��z�����d������P�[�X�������Ă��邪�A�����ʼnۑ�ƂȂ�̂����z���p�l���̔��ˌ��ɂ����ӊ��ւ̉e�����B �����������ˌ��̒ጸ��Ƃ��āA���Z���ł̓p�l���\�ʂɖhΈ��H���{�����d�l�̑��z���p�l����W�J���Ă���B����͑��z���p�l���\�w�ɉ��ʂ̂������K���X���̗p�������̂ŁA����ɂ������U�����܂Ԃ�����ጸ����d�g�݁B�����s����߂�A�����@�\����L���鑾�z�����d�V�X�e���̔F��i�ߘa6�N�x�F��j���Ă���A�����s�L�F�s��⒆�����ۋ�`�ȂǁA�����{�݂𒆐S�ɍ̗p����Ă���Ƃ����B���Z���ł́A�Ǝ��̃V�~�����[�V�����V�X�e���uSoGlana�i�\�O���[�i�j�v�́A���ˌ��ɂ��܂Ԃ����̔��肪�\���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���t�@�X�i�[�Ńy���u�X�J�C�g���z�d�r��e�Ղɒ��E�A��ёg�ƃA�C�V������������ ��ёg�ƃA�C�V���͋����ŁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��؎������J�n�����B�A�C�V���̃y���u�X�J�C�g���z�d�r���ёg�̊J�������{�H���@�Ɛݒu���@��p���A�{�H���̕]���┭�d�ʂ�������B �����̌����Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu����ꍇ�A�������g�p���ł��A�e�ՂɌ����\�ȃt�@�X�i�[��p�������O�����H�@���J�����A��ёg�Z�p�������{�ق̉���Ɏ{�H���s�����B ���̍H�@�̓y���u�X�J�C�g���z�d�r�t���̃V�[�g�ƁA������ǖʂɏ���̊Ԋu�ŌŒ肵�����b�V���V�[�g���t�@�X�i�[�ŌŒ肷��B�V�[�g�͒ʋC���̗ǂ����b�V���V�[�g�ŁA�t�@�X�i�[�ɂ͑ό̍�������ȃ^�C�v���̗p�B��ʐςł��t�@�X�i�[�����ŗe�ՂɘA���ł��A�����I�Ɍ������邱�Ƃ��\�ł���A�����I�ȕێ琫�ɗD���Ƃ����B����͒����ݒu�ɂ��ϋv���̌���A���ۂ̎�֍H����ʂ����{�H���̕]�����\�肵�Ă���B����̓y���u�X�J�C�g���z�d�r�̔��d�ʂ�o�N�x���r�]��������j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������v�����g���݃v���W�F�N�g�ɂ����ĕ��G�Ȗʂ�����3D�v�����g���h���ǂ�ݒu �����́A�P���ŊC�O�d�o�b�i�v�E���B�E���݁j���Ƃ�W�J��������O���[�o�������ݗp�RD�v�����^��p���Đ����������G�Ȗʂ̖h���ǂ��̗p����A�����v���W�F�N�g�̌�����Őݒu�����B ����܂ŁA�e��v���W�F�N�g�ɂ�����3D�v�����g��K�p���A���ݕ���ɂ�����3D�v�����^�̋Z�p�J����i�߂Ă����B����ݒu�����h���ǂ́A����3.0m�̕ǂ�3�X�p�����ڑ����������v9.0m�̂��́B�h���ǂ�COBOD�А��K���g���[�^���ݗp3D�v�����^��p���āA2�T�Ԃ̑��`���Ԓ���33�̕��ނɕ������Đ��������B �h���ǂ͐��C�����`�[�t�Ƃ����g�^�`����ӏ��Ɏ�����A��������㕔�Ɍ������Ĕg�^���璼���ɕω�����悤�Ȍ`��Ƃ����B�����������G�ȋȖʂ̃f�U�C�������݂Ɏ����ł��A3D�v�����^�̓K�p�\�����L����ꂽ�B �o�T�u�����v |
|
|
| �������p�v�����琶�����E�K�X�����.�`���A��t����FS���J�n �`�����v�����g�́A�Ǝ��Z�p�u�����z�������K�X���V�X�e���iICFG�Z�p�j�v��p�����P�~�J�����T�C�N���̎��؎������J�n�����B �{���Ƃ́A���Ȃ̗ߘa5�N�x�⏕���Ɓu�E�Y�f�^�z�o�σV�X�e���\�z���i���Ɓi�v���X�`�b�N�������z�V�X�e���\�z���؎��Ɓj�v�̎x�����Ă���A�Y���w�A�g�ɂ��Љ�����X�L�[���̍\�z���i�߂��Ă���B ICFG�Z�p�́A���ʂ����K�v�Ƃ��Ȃ������p�v���X�`�b�N�ڔM�������A�v���X�`�b�N���������Ƃ��čė��p�\�Ȑ������E�K�X�����������̂ł���B�]���̃P�~�J�����T�C�N���ł́A�����Ώۂ����肳��邱�Ƃ�A���ғ��̍�����ۑ�Ƃ���Ă������A���Z�p�͂����̐������������\�������B����̎��v�����g�ł́A1���������1�g���̔p�v���X�`�b�N���������A�X�P�[���A�b�v���̋Z�p���A����ғ��̊m�F�A���Ɛ��̕]���Ȃǂ��s���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���_�C�L���A�Ċ�Ɣ����Ő���AI�Ή��^DC�̗�p�Z�p������ �_�C�L���́AAI�f�[�^�Z���^�[������p�Z�p�ɋ��݂�����Dynamic Data CentersSolutions�ЁiDDCS�Ёj�̔����Ɍ����Ċ�{���ӂ����Ɣ��\�����B DDCS�Ђ́A�u�T�[�o�[���b�N�P�ʂł̌ʗ�p�Z�p�v��L���AAI�����p�r��IT��Ղ̍����x���ɔ������M�E�d�͏���̉ۑ�ɑΉ�����v�V�I�ȃ\�����[�V��������Ă���B�f�[�^�Z���^�[�́A�]���̃f�[�^�ۑ��E�����@�\����AAI�̊w�K�E���_���x����C���t���ւƐi�����Ă���A�ėp���_�^AI�f�[�^�Z���^�[�̎��v�����܂��Ă���B DDCS�Ђ̋Z�p�́A�T�[�o�[�P�ʂł̃��A���^�C����́E����������\�ɂ��A�^�]�f�[�^�̊w�K�ɂ��œK�������������ݔ��}�l�W�����g�V�X�e��������Ă���B�_�C�L���́A�f�[�^�Z���^�[�S�̗̂�p�j�[�Y�ɑΉ�����g�[�^���\�����[�V�������\�z������j���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����B�ő勉CCS���{�i�n���^���D�D�̗A���D���p ��K��CCS�v���W�F�N�g�ł́A�m���E�F�[�ɂ���h�C�c�̃Z�����g�H��ƁA�I�X���̒n��M������Ƃ��I�X���Ōv�撆�̔p�����ċp�{�݂Ȃǂ���r�o�����CO2���������B �m���E�F�[�����ʼn��B�ő勉��CCS�i��_���Y�f����E�����j�v���W�F�N�g�u�����O�V�b�v�v���{�i�I�ɓ����o�����B�Q�悷�铯���G�l���M�[���̃G�N�C�m�[���A�Ζ����W���[�̕��g�^���G�i�W�[�Y�A�p�V�F���̂R�Ђ��A�C�꒙���w�ɓ�_���Y�f�iCO2�j�̈������n�߂��Ɣ��\�����B���n�ł͐��D�D�̉t��CO2�^���D���ғ����Ă���B���v���W�F�N�g�͉��B�Y�ƊE���r�o����CO2��N�ԍő�150���g����������v�悾�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����o�ό��������d�͌n���֘A�̒�u�p�~�d�r�iESS�j���E�s��Ɋւ��钲�����ʂ\ 2024�N�̐��E�s��K�͂́A���[�J�[�o�חe�ʃx�[�X��254.498GWh�Ɛ��肵�Ă���B2024�N�͎�v���ł̍Đ��\�G�l���M�[���d�ݔ������ESS�����ɑ���x�����x�̋�����A�ăG�l���d�R�X�g�ቺ�ɂ�锄�d���v�̉��P�Ȃǂ��s��g��Ɋ�^�����Ƃ��Ă���B ���E�n��ʂł͖k�āE�����E���B�𒆐S�ɓd�͌n���֘A��ESS�̎s�ꂪ�}�g�債�Ă���A�����3�n��Ő��E�̏o�חe�ʂ�8���ȏ���߂Ă���B �ăG�l���d�ݔ��̑����ɑΉ�����`�ŁA2025�N���d�͌n���֘A�ŗp������ESS�����͈��������������錩���݁B2025�N�̓d�͌n���֘A��ESS���E�s��K�͂͑O�N��30.2������331.403GWh�ɒB���錩�ʂ��Ƃ����B 2033�N�̓d�͌n���֘AESS���E�s��K�͂́A���[�J�[�o�חe�ʃx�[�X��2025�N���1.9�{��624.253GWh�B����Ɨ\���B �o�T�uItmedia�v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g�d�r�̐��E�s��2040�N��4���~�K�͂̌��ʂ��Ɂ^�x�m�o�� ����̒����ł́A�y���u�X�J�C�g�̒P�ڍ��^�ƁA�y���u�X�J�C�g�ƌ����V���R���̃^���f���^�i���ڍ��^�j��ΏۂƂ����B�P�ڍ��^�͂��łɏ��p������Ă���A���ږʐς̏������d�q�I�D��g�ݍ��ݓd���ł̗̍p�𒆐S�Ɏs�ꂪ�L�������A2024�N�̎s��͑O�N��61.3������500���~�ƂȂ����B����A�^���f���^�͎����I���Y��T���v���o�ׂɗ��܂��Ă���2024�N�̎s��͑O�N��80.0������90���~�ƂȂ����B �{�i�I�ȗʎY�J�n�͒P�ڍ��^����s���A2020�N��㔼����^���f���^�̗ʎY���i�ތ��ʂ��B�������z�d�r����̑�ւ��i��2020�N��㔼����s��͋}�g�傷��Ɨ\�z���Ă���B�܂��A����Ȃ�ϊ������̌��オ�\�ȃ^���f���^�̊J�����i�݁A2030�N�O�ォ�甭�d���Ɨp�r�Ȃǂł̓����������҂���A�s��g����㉟������Ƃ����B2040�N�ɂ͖�6�����^���f���^����߂錩�ʂ��Ƃ����B �o�T�uItmedia�v |
|
|
| ��LED���Ƌ�Ԃ��ő劈�p�I����A�~�j�g�}�g���i���E���萶�Y�Z�p�����x�� ������w��w�@�̌����O���[�v�́ALED�A���H��ɂ�����~�j�g�}�g�̍��i���E���萶�Y�Z�p���J�������B�]���A�g�}�g�͋�������K�v�Ƃ��邽�߁A�l�H���^�A���H��ł͈琬������Ƃ���Ă������A���̏펯���ALED���݂̂ʼn����͔|������Â��Ɖh�{�������������B �����ł́A��ʓI�ȃ~�j�g�}�g�i��uCF��ʁv��p���A�����U���ɂ��I���͔|�ƁA�����U���ɂ��S�����i���͔|���r�BS���͔|�ł́A���S�̂ɋϓ��Ɍ����͂��\�����̗p���A�����������̂����}���B����ɂ��A���x�E���R�s���E�r�^�~��C�ܗʂ�������������͔|������A���_��������A���̐[�݂����サ���B����ɁA���n�܂ł̊��Ԃ���2�T�ԒZ�k����A1������ő�23�i�ʖ[�̎��n�ɐ�������ȂǁA�������萶�Y���\�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B �{�����́A�s�s���̋r����n����Ԃ����p�����n�Y�n���^�̐H�����Y��A�E�Y�f�^�_�Ƃ̎����Ɍ������Z�p�I��Ղ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���R�����ȂǁA�u�h�E�͔|�ɗL�@�������z�d�r�E�Y�f�֎��؎��� �R�����́A�u�h�E�͔|�Ɍ����ߌ^�̗L�@�������z�d�r�����p������؎������n�߂�Ɣ��\�����B�����z�K�������ȑ�w�Ƃ̋��������B���d�����d�͂Ŗ�Ԃɉʎ�������������Ǝ˂��A�ʔ�̒��F�����}��B�_�Ƃ̒E�Y�f�ɂ��Ȃ���B ���ʎ�������̃u�h�E���̉J�悯�ɁA�������ŋȂ��鑾�z�d�r��6�������[�g�����ݒu����B�����J�������ԃu�h�E�̍����i��u�T���V���C�����b�h�v�͔̍|�Ŏ������A�����F�Â���ʏ�͔|�Ɣ�r����B8�����{�̎��n���Ɍ��ʂ����炩�ɂȂ�f�U�C���\�[���[�i�_�ސ쌧���{��s�j���J�������L�@�������z�d�r�𗘗p����B���߂�����̐F��ς����A�������ɕK�v�Ȕg���ɂ��邱�ƂŔ_���ɂ����p�ł���Ƃ����B ���͔_�Ɨp�n�E�X���O���[�����f���g���ĉ���������؎�����2026�N2��������{����\��B�{�C���[�R�����d���Ȃǂ����ւ��邱�ƂŔ_�ƕ���̒E�Y�f�Ɍ����������������������l�����B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���ĉ��B�A���E�ő�K�͂́u�\�[���[�{�~�d�r�v���F �J���t�H���j�A�B�G�l���M�[�ψ���iCEC�j�́A�B�́u�I�v�g�C���F�v�v���O�����Ɋ�Â����̔F�Č��Ƃ��āA�u�_�[�f���E�N���[���E�G�l���M�[�E�v���W�F�N�g�iDCEP�j�v�����F�����B���E�ő�K�͂̒~�d�r���^���K�\�[���[�i��K�͑��z�����d���j�v���W�F�N�g���B ��310�����̑��z���p�l��������A�A�n�o��1.15GW�̑��z�����d�{�݂ƁA�ő�o��1.15GW�A�e��4.6GWh�̃G�l���M�[�����ݔ��ō\�������B �I�v�g�C���F�v���O�����́A�B�c��@�ĂɊ�Â��n�݂��ꂽ���x�ŁA�����������N���[���G�l���M�[���Ƃɑ��A�B���x���ł̓����I�ȋ��F�葱�����\�ɂ���B��̓I�ɂ́A50MW�ȏ�̑��z���܂��͗��㕗�͔��d���A200MWh�ȏ�̒~�d�e�ʂ����G�l���M�[�����V�X�e���A�֘A�������̑��d���Ȃǂ��܂܂��B�\�����F�肳��Ă���270���ȓ��Ɋ��R�����I���邱�Ƃ��`���t�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEDO��GI����y���u�X�J�C�g���A���R�[�E�G�l�R�[�g�Ȃ�3���ƍ̑� NEDO�A�u������^���z�d�r�̊J���v�̒lj�������s���A���R�[�A�G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�A�p�i�\�j�b�N�ɂ����؎��Ƃ��̑������B���Ɗ��Ԃ́A2024�N�x����2030�N�x�܂ł�7�N�ԂŁA���\�Z��378���~�B �E���R�[�́A�����@�J���Ŕ|�����L�@�����̋Z�p��C���N�W�F�b�g�w�b�h�Z�p�Ȃǂ̋Z�p���I�ɂ������킹�邱�ƂŁA���ϊ��������E���ϋv���A�����Y�����R�X�g����ڎw���B����̎��ł́A��a�n�E�X�H�ƁANTT�A�m�[�h�G�i�W�[�ƃR���\�[�V�A����g�D�B2030�N�x�ɔN�Ԑ����\��300MW�ȏ�A���d�R�X�g14�~�^kWh�B����ڎw���B �E�G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�́A�u���[��to���[���H�@�v�����A�t�B�����^�ɂ��y���u�X�J�C�g���z�d�r�s��̌`����i�߂�B���O��u��ړI�ɖ{�i�Q������B���s��w�A�����AYKK�ȂǂƘA�g�B �E�p�i�\�j�b�N�́A�K���X�^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗ʎY�Z�p�J���ƃt�B�[���h�����s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2025/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���Đ��G�l�̎��R�d�́A�~�d�r�̐���V�X�e���O�́@���z�����d��Ќ��� ���R�d�͂͑��z�����d���Ǝ҂�Đ��G�l�d�C�̔����𒇉�鎖�ƎҌ����ɔ̔�����B�~�d�r���g�����d�ʂ�d�͎��v�ɍ��킹�ď[���d���邱�ƂŎ��v�����߂������Ǝ҂̎��v����荞�ށB ���R�d�͂̎q��ЂŒ~�d�r�̈ꊇ����V�X�e�����J������ShizenConnect�i�V�[���R�l�N�g�j������B�V�X�e���ɓ��˗ʂ�C���Ȃǂ̏�����͂��邱�ƂŐl�H�m�\�iAI�j�������ŏ[���d�𐧌䂵����A���d�ʂ̌v��𗧂Ă���ł���B�ڋq�͕K�v�ȋ@�\��I��ŃC���^�[�l�b�g�o�R�ŃV�X�e�����g����B�܂��d�C�̔������肪����u�A�O���Q�[�^�[�v�Ƃ��đ啪���̔��d�����^�p����O���[���O���[�X�ɒ���B 2026�N1������^�p����B���d�ʂ������A�d�C�̎s�ꉿ�i�������Ȃ钋�Ԃ̎��ԑтɂ͓d�C�����ߍ��݁A���v�����܂艿�i���オ�鎞�ԑтɔ��d���邱�ƂŎ��v�̌��オ�����߂�Ƃ����B�~�d�r�����Ă��锭�d���Ǝ҂�A�O���Q�[�^�[��ΏۂɃV�X�e���̔̔���i�߂�B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���u�₽���Ȃ�x���`�v��H�ʑ��z���ʼnғ��A��㖜���ɐݒu �������H�H�Ƃ́A���E���������ԏ�ɁA�H�ʑ��z���p�l���uWattway�i���b�g�E�F�C�j�v��ݒu�����Ɣ��\�����B���d�����d�͂́A��p�@�\�t���x���`�̉ғ��p�d���Ƃ��Ċ��p����B Wattway�p�l��6���Ɨ�p�@�\�t���x���`1���g�ݍ��킹���V�X�e�������v3�Z�b�g��ݒu�����B �p�l��1��������̑傫����1257�~690mm�A�o��125W�ŁA6�����v��750W�ƂȂ�B��p�@�\�t���x���`�́A�e��768Wh�̃��`�E���C�I���~�d�r�ƍ��ʂ̈ꕔ�ɗ␅���z�������p�@�\�𓋍ڂ��A���ʉ��x��28���ɕۂB�x���`�T�C�Y�͕�1800mm�A����746mm�A���s��591mm��3�l�|���B Wattway�́A�t�����X�̓��H��Ђƃt�����X�������z�G�l���M�[�Z�p�������������J�������B���z���p�l���\�ʂɂ��ׂ�~�߉��H���{���A���s�҂⎩�]�ԁA��^�Ԃ̑��s�d����p���錵�����������ł����z�����d�\�͂��ێ��ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z���p�l���A���x�Ⴂ�����ɂ��ݒu�^���K�X�Ȃnjy�ʌ^�� �����K�X�Ǝ����㑾�z�d�r�J���̃X�^�[�g�A�b�v�APXP�́A�y�ʂŔ����_��ȁu�t�B�����^�J���R�p�C���C�g���z�d�r�v�ɂ��āA�ωd�̒Ⴂ�����ɂ��ݒu�ł���T�[�r�X�̊J���ɏ��o���Ɣ��\�����B PXP����|���鎟���㑾�z�d�r�𓌃K�X�̒m����������@�Ŏ{�H����B2026�N�x���ɂ����z���p�l����ݒu�ł��錚���̕����L����B ���K�X�Ƃo�w�o�ɂ��J�����A�J�[�{���j���[�g�����Ɍ����������J�����x������_�ސ쌧�̌��厖�Ƃɍ̑����ꂽ�t�B�����^�J���R�p�C���C�g���z�d�r��ωd�̒Ⴂ�����ɐݒu������g�݂͍������Ƃ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ăG�l�̗]��d�͂�M�Ƃ��Ē~����ABlossomEnergy���J���A�u�����~�M�d�r�v�̋@�\ BlossomEnergy�́A�������g�p�����~�M�d�r���J�����A���Ă���L�������Ŏ��؎������n�߂�B�Đ��\�G�l���M�[�̗]��d�͂�~�M�ނ̍����ŔM�Ƃ��Ē~����B 2025�N�x���ɕ����̎������[�U�[�̓����E����\�肵�A���ǂ�i�߂�26�N����ʎY���f���̔̔��J�n��ڎw���B�����ɗ]��ɂȂ����Đ��G�l��M�Ƃ��Ē������A�K�v�Ȏ��ɉ����≷���Ƃ��Ď��o���B ���p���f���̒~�M�d�r�ł͖�200kWh�`600kWh���\�B1��������̋������v���Z��10�`30���ѕ��̔M�ʂ��ł���B�~�M�d�r�̑傫���͏��^�R���e�i���x�B 2024�N���J�����R���Z�v�g�@�ł͂ł��Ȃ�������艷�x�̃K�X�̒����Ԉ��苟�������������B�����{�݂��K�͋�Ԃ̒g�[�A����{�B�{�݁A�H�Ɨp�����F�Ȃǂɗ��p�\�B�ݒu�������瓱���܂�3.6�J����z�肷��B���Ђ�2022�N�ɑn�ƁB�����K�X�F��M�����V�X�e���Ȃǂ̐v�E�J�����肪����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������s�A������ăG�l�x���Łu�����Z�x�����d�v�u���������d�v�̑� �����s�́A������Đ��\�G�l���M�[���d�Z�p�̎��p���Ɍ����A�s�����t�B�[���h�Ƃ������؎��Ƃ��x������u������Đ��\�G�l���M�[�Z�p�Љ�������i���Ɓv�ɂ��āA�u�����Z�x�����d�v�Ɓu���������d�v���̑������B���Ɗ��Ԃ�2028�N3��31���܂ŁB �u�����Z�x�����d�v�́A�����p�̊C���ƒW���i�r���j�̉����Z�x���𗘗p���Ĕ��d������́B�����^�����U�^�d���ƂȂ锭�d�ݔ���s���ɐݒu���A���d���\�⎖�Ɛ��Ȃǂ�������B���{�ꏊ�͓����s���̐��|�H��̗\��B��\���Ǝ҂̓u���[�E�H�[�^�[�G�i�W�[�B �܂��u���������d�v�́A���������L�@���i�H�i�E�_�Ɣp�����j������ߒ��Ő�������d�q��d�ɂő����ēd�C�ɕϊ�����d�g�݁B���ł́A�����Ȃǂɐݒu���A����I�ȓd�͋�����ЊQ���ɂ����p�ł���d���Ƃ��Ă̗L������������B���{�ꏊ�͓����s���̌����A�H�i�H��Ȃǂ̗\��B��\���Ǝ҂̓Z�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��GE�Ɠ����A�����㌴�q�FSMR���݊J�n�J�i�_�̏B���{����F�� ��GE�x���m�o�Ɠ������쏊�̋����o����ЁA��GE�x���m�o�����j���[�N���A�G�i�W�[�́A�J�i�_�Ŏ����㌴�q�́u���^���W���[���F�iSMR�j�v�̌��݂��n�߂�Ɣ��\�����B SMR�͐���AI�i�l�H�m�\�j�ő�������d�͎��v�ւ̑Ή���Ƃ��Ċ��҂����܂�B�J�i�_�E�I���^���I�B���{���猚���������ƂŌv�悪�O�i����B ���n�d�͑��̃I���^���I�E�p���[�E�W�F�l���[�V�����iOPG�j�����̃v���W�F�N�g�ŁA2030�N���܂ł̉^�]�J�n��ڎw���BOPG�̃_�[�����g�����q�͔��d���ɏ��^���W���[���F�uBWRX-300�v�����݂���B�o�͂�30��kW�ƈ�ʉƒ�30�����ѕ��ɑ�������B�J�i�_���q�͈��S�ψ��4����1���@�̌��ݍH���F���o���Ă����B OPG��1���@���܂߂đS4����v�悵�Ă���A2.4���@��2034�N����2036�N���̉^�]�J�n���v�悷��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����B�����A�ăG�l�����Ɠd�����E�Y�f���⋣���͋����̌��ƕ� ���B�����iEEA�j�́A2030�N�܂łɕK�v�Ȏ�g�͂����B����ɂ��ƁAEU�S�̂ōĐ��\�G�l���M�[�i�ăG�l�j�̕��y���g�傷��Ɠ����ɁA�M������A���A�Y�ƕ���̓d�������������邱�Ƃ��K�v�ł���B ����A�d�͕���ł͉��ΔR������̒E�p���i��ł��邪�A����ɔ�ׂ�ƁA�M�����y�їA������ɂ�����E�Y�f���̐i�W�͒x���B�܂��A�K�X���i�̃G�l���M�[�A���R�X�g�̍����ɂ��͈��GDP�̍ő�4���ɂ܂Ŗc��B���������ۑ�ɑ��A�ăG�l�i���ɑ��z���ƕ��́j��d���́A�G�l���M�[�̎����������߁A�����\�ȃG�l���M�[���i���ێ����邽�߂̏d�v�ȓ��ɂȂ�A�Ƌ�������B�������́A�G�l���M�[�����⎑�����������P���邽�߂̎�g���������Ȃ���A�����̍ăG�l���d�ɓ������邱�ƂŁA�A�����ΔR�����������ŃN���[���ȃG�l���M�[���ɒu�������邱�Ƃ��\���Ɛ������A���̂��߂ً̋}�D��ۑ�╔��ʂ̑����Ă���B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| ���ySDGs�B���x�����L���O�z���{�A2025�N�͐��E19�ʂɌ��6�ڕW���Œ�]�� ���ۓI�Ȍ����g�D�u���A�����\�ȊJ���\�����[�V�����E�l�b�g���[�N�v�iSDSN�j�͐��E�e����SDGs�̒B���x��]�������uSustainable DevelopmentReport�i�����\�ȊJ�����j�v��2025�N�ł\�����B���A�⌤���@�ւȂǂ̓��v���������ƂɁA�e����SDGs�̎��g�݂�100�_���_�œ_�������A�B���x�����\�����B 2025�N�ł�1�ʂ̓t�B�������h�i87.0�j�B5�N�A���̃g�b�v�ƂȂ����B2�ʂ̓X�E�F�[�f���i85.7�j�A3�ʂ̓f���}�[�N�i85.3�j�A4�ʂ̓h�C�c�i83.7�j�A5�ʂ̓t�����X�i83.1�j�B���{�̃����L���O�́A19�ʁi80.7�j�B2017�N�Ƀs�[�N��11�ʂ��������̂́A�ߔN��20�ʑO��ɂƂǂ܂��Ă���B ���{�́y�[���ȉۑ�z�͂U�B�E�ڕW2�u�Q����[���Ɂv�E�ڕW5�u�W�F���_�[�������������悤�v�E�ڕW12�u����ӔC�A�����ӔC�v�E�ڕW13�u�C��ϓ��ɋ�̓I�ȑ���v�E�ڕW14�u�C�̖L��������낤�v�j�E�ڕW15�u���̖L��������낤�v�j �o�T�u�����V��SDG���v |
|
|
| �������Ɠ����u2025�N�x������Ƃ̏ȃG�l�E�E�Y�f�Ɋւ�����Ԓ����v���� �G�l���M�[���i�̍����ɂ��Ė�9���i85.2���j�̊�Ƃ��u�o�c�ɉe������v�Ɖ��A��1���i7.9���j�́u�[���Ŏ��ƌp���ɕs���v�Ƃ��Ă���B����1�N�̑Ή��́u���А��i�E�T�[�r�X�̒l�グ�v�i34.2���j���ő��ŁA�ȃG�l�^�p���P�i27.7���j��ȃG�l�^�ݔ��̓����i25.1���j��3�����x�ɏ��B �E�Y�f�ւ̎�g�݂�7���i68.9���j�����{���A�ȃG�l�^�ݔ������i35.7���j�A�^�p���P�i34.5���j�����S�ŁA�r�o�ʑ���Ɏ��g�ފ�Ƃ�26.0���B����悩��E�Y�f�v�������Ƃ�2���i21.3���j�ŁA�x������̂͂���3����ɂƂǂ܂�ۑ�Ƃ��Ắu��p���S�̑傫���v�i64.5���j���ˏo�B���{�E�����̂ւ̊��҂́u�ȃG�l�ݔ���ăG�l�����ւ̎����x���v�i72.8���j���ő��ŁA���H��c���ɂ́u�Z�~�i�[���ɂ����v�i49.6���j��u�x����̏Љ�v�i44.1���j�����߂��Ă���B �o�T�u���ȁv |
|
|
| �������s�A�Ȃ��鑾�z�d�r�̈��́uAir�\�[���[�v�ɕ��y�g��� �����s�́A�����ċȂ��鎟����^�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�̈��̂��uAir�\�[���[�v�Ɍ��߂��Ɣ��\�����B���{���̋Z�p�ō����O�ŊJ���������������B�s�͐e���݂₷�����O�ŕ��y�g��ɂȂ��悤�ƁA7���Ƀl�[�~���O���I���Ɩ��ł��čL�����[���Ăт����Ă����B �����[����1��5005�[�ŁuAir�\�[���[�v��4388�[���l�����g�b�v�������B�uAir�\�[���[�v�̖��̂́u�ǂ��ł��iAnywhere�j�v�u�v�V�I�ȁiInnovative�j�v�u�Đ��\�G�l���M�[�iRenewableenergy�j�v�̓�������������B��C�̂悤�ɂ�����ꏊ�ɐݒu����邱�Ƃ��\�����B �s��2050�N�܂łɉ��g���K�X�r�o�ʂ������[���ɂ���ڕW���f����B�uAir�\�[���[�v�͏]���^�̑��z�d�r�ł͑Ή��ł��Ȃ����������̕ǖʂ�ȖʂȂǂɐݒu�ł��邱�Ƃ���A�s�s���̃|�e���V����������Z�p�Ɗ��҂��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������s�A������Ƃ�CO2�팸���ʂ��܂Ƃ߂ăJ�[�{���N���W�b�g�n�o�� �����s�́A�s��������Ƃ̏��K�͂�CO2�팸�������Ƃ�܂Ƃ߂ăJ�[�{���N���W�b�g������V���Ƃ��J�n����Ɣ��\�����B J�|�N���W�b�g���x�́u�v���O�����^�v���W�F�N�g�v�����p������̂ŁA���v���W�F�N�g���^�c���鎖�Ǝ҂̎��g�݂ɑ��A���ʘA���^�̋�����ɂ��ő�5600���~���x������B���Z�@�ցE�o�ϒc�́E�n�������̂Ȃǂ�Ώۂɓ��v���W�F�N�g�̉^�c���Ǝ҂��W���A5�����x�̑�����\�肾�B �v���W�F�N�g���̑����ꂽ���Ǝ҂́A�s�Ƌ����������A�̑��v���W�F�N�g�Ɋւ��āA�s��������ƂȂǂ̃v���W�F�N�g�ւ̗U����i�߁A2028�N1���܂ł�1��ȏ�̃N���W�b�g�F��B������B�s��������ƂȂǂƂ̕��L���l�b�g���[�N��L����o�ϒc�̂���Z�@�ւȂǂƘA�g���Ď��ƂɎ��g�ށB �����s�͍̑����ꂽ�v���W�F�N�g1���ɂ��A2025�N�x�͍ő�1600���~�A2026�E2027�N�x�͐��ʘA���^�ōő�2000���~�̋�������x�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����k���A�p�M��V�R�S������ē��͕ϊ�����v���Z�X���J�� ���k��́A�V�R�S���̒e���M�ʌ��ʂ����p�����V���ȔM�|���͕ϊ��@�\���Ă��A�H��Ȃǂ���r�o�����200�������̒ቷ�p�M���獂�����̓G�l���M�[�邱�Ƃɐ��������B �e���M�ʌ��ʂƂ́A�e���̂��}���ɕό`����ۂɔ��M�E�z�M�����ہB�]���̔M�d�ޗ��ɂ��p�M���d�͕ϊ��������Ⴍ�A��Z�p�̊J�������߂��Ă����B�{�����ł́A�V�R�S���̒e���M�ʌ��ʂ𗘗p���A�M�������ʂ��ĉ��x���䂳�ꂽ�쓮���̂��S���`���[�u�ɗ������ƂŁA�S���̐L�k�^���������A�����������^��������@�\���\�z�����B �����ł́A���x��25���A�S���̐L�ї�50%�̏������ŁA1�T�C�N��������ő�150mJ/cm3�̃G�l���M�[���x���L�^���A120mW�����̏o�͂��B����ꂽ�́i100N�ȏ�j�ƕψʗʁi20mm�ȏ�j�͊����̔��d�@�\�Ƃ̌݊���������A�M���瓮�͂��o�R���ēd�C�G�l���M�[�ւ̕ϊ����\�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2025/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���֓d�A���z���p�l���ė��p���v���ց^���ƃ��f�������� ���d�͂́A���z���p�l���̃��T�C�N�����ƃ��f�����A�p�����������Ǝ҂Ȃǂƌ�������Ɣ��\�����B �g�p�ςݑ��z���p�l������A�Ăё��z���p�l���ݏo���u�������T�C�N���v�Ɍ����A�T�v���C�`�F�[���݂̍����A���v���f���Ȃǂ������B���z���p�l���p�����}������2030�N��㔼�Ɍ����A�������T�C�N���̎��Ɖ��Ȃǂ�͍�����B �Y�Ɣp���������E���T�C�N���ő���TRE�z�[���f�B���O�X�A���w���[�J�[�̃g�N���}�ƁA���z���p�l���̃��T�C�N���Ɋւ��鋦�菑����������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ����^�ψ���A�S���ŕs���^�c�b�}�g��A�d�͎��v������ �d�͈��苟���Ɍ������Ȃ���^�ψ��킪�A�S���I�ɕs������ُ펖�Ԃ������Ă���B �����N�����p������A�f�[�^�Z���^�[�iDC�j�̐V���݂ȂǂɋN��������v������A�Đ��\�G�l���M�[�d���g��̃{�g���l�b�N�ɂȂ肩�˂Ȃ��B���[�J�[�e�Ђ̕ψ���H�ꂪ������悵�Ă���B �����N���̈������ƂȂ����̂̓��x�j���[�L���b�v�i�q�b�j���x���B�i��Ƃ⎖�Ǝ҂������Ԃɓ�������v�i����j�ɏ���i�L���b�v�j��݂��鐧�x�j�����F�߂���������Ɋ�Â���ʑ��z�d���Ǝ҂̓�����p�̉����S�ۂ���d�g�݂ŁA2023�N4���̓����܂��A���o�N�����ăG�l�Ή��𗝗R�Ƃ�����^�ψ���̔������W�������B ����ɁA�����G�i�W�[�̕ψ���́A���E�ŗ��ʂ��鍑�ۓd�C�W����c�iIEC�j�K�i�ɑΉ����Ă���B���ɁA50��V���ψ���́A�������[�J�[�������邱�Ƃ�����A�N�����ɔ��Ԃ������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��NEWGREEN�ւ̒lj��o���`����Ȃ���͔|��V���Ȏ��؏ꏊ�ŊJ�n �����d�͂́ANEWGREEN�Ɛ���̊��c���d�E�ߐ��^�͔|�i�ȉ��u�{�͔|���@�v�j�ɂ��Đ��Y�̎��Ɖ��Ɍ������Ɩ���g�ɍ��ӂ����B �{�͔|���@�ɂ�鉷�����ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�팸�ɂ���Đ��ݏo���������l���������A�����l��t�^�����ẴT�v���C�`�F�[���̍\�z��ڎw���B ��N�x���璆���G���A�ɂ����Ė{�͔|���@�̎����J�n���A���N�x�́A���m���A�O�d���A���쌧�̐V���Ȏ��؏ꏊ3�ӏ��ɂ����āA����i�߂Ă���B ���̎���ʂ��āA�͔|�ʐς̊g��Ɍ����ADX�c�[����h���[���������p���������I�ȍ͔|�̌n�̌���قȂ���������ɂ�����͔|���@�̊m�F����i�߂�B���Y���������E�Y�f�Ȗ{�͔|���@�ɂ��Đ��Y��ʂ��āA�_�ƕ���̎Љ�ۑ�̉����Ɍq����H���C���t�����\�z����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���T���g���[HD�A�O���[�����f�̐����̔��֎Q��2027�N�� �T���g���[�́A2027�N�Ɋ����ׂ��������u�O���[�����f�v�̐����̔��ɎQ������Ɣ��\�����B�R������H�ƃK�X�̔b����ȂǂƋ��Ƃ���B �����ŏ��߂Đ�������̔��܂ň�т��Ď肪���A�V���ȃr�W�l�X�@���T��B���N�ȓ��Ɏ��Ƒ��v�̍�������ڎw���B �R�����k�m�s�Ɍ��ݒ��̃O���[�����f�̐����{�݂����p����B���{�݂͔N��2,200�g���̐��f������\�͂����B�܂��͔N���ɉғ����A�E�C�X�L�[�́u���Ώ����v�Ȃǂւ̊��p��������B2027�N�ȍ~�͐��f�������u�n�Y�n�����f���v�������A�����s���̊�ƂȂǂɂ�������ڎw���B ���f�������u�́u��܂Ȃ����f��P2G�i�p���[�E�c�[�E�K�X�j�V�X�e���v�𗘗p����B�����ߒ��œ�_���Y�f�iCO2�j��r�o���Ȃ����߁A�N��1��6000�g����CO2�r�o�팸�������ށB �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���u�c�_�^���z���ŃR���┞�A�哤���v�A�N�{�^���܂��k�֓���200�J�� �N�{�^���A�c�_�^���z�����d���Ƃ�Ȗ،����錧�ȂǂŏW���I�ɓW�J���n�߂Ă���B�k������n�̂ق��A�u���ݓI�ȍk������n�\���n�v�ƌ�����y�n��ΏۂƂ��Ă���B�_�Ƃ�������ƂƂ��Ɍٗp�𑝂₷���Ă���B �܂���1�i�K�Ƃ���50�J���E���v�o�͖�5MW�̉c�_�^���z�����d�ݔ���ݒu����B2025�N2�����珇���ғ����Ă���A�H����܂ł��߂ǂɂ��ׂĂ��ғ�����\�肾�B���Ђɂ��ƁA�{���͂����������������ɂ��ׂĉғ�����\�肾�������A�_�ѐ��Y�Ȃɂ�鐧�x�ύX�̉e���ŏH����܂łɉ��т��B ���̑�2�i�K�ł�150�J���E���v�o�͖�15MW�̉c�_�^���z����ݒu����B�������2025�N12�����珇���ғ�����B �c�_�p�[�g�i�[�̃A�O���G�R���W�[�͎����\�Ȕ_�Ƃ�ڎw���A�ʏ�̔_�Ƃ��x�[�X�ɂ��Ȃ���c�_�^���z�����d�ɂ����g�݁A���n�����_�앨�����H�X��C���^�[�l�b�g��Ŕ̔�����ȂǁA������_�Ƃ�6���Y�Ɖ��ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IHI��GE�A�A�����j�A100���ɂ���^�K�X�^�[�r���ŘA�g IHI�ƕ�GE�x���m�o�́AIHI�����H��ɁA�A�����j�A100���ł̉^�]���\�ȃK�X�^�[�r���̊J���Ɍ����āA��^�R�Ď����ݔ��iLCT��Large-scale Combustion Testfacility�j��V�݂����B2025�N�Ă���A�����j�A100���R�Ď������J�n����B LCT�́AGE�x���m�o��F�^�K�X�^�[�r���̈��́A���x�A��C�E�R�����ʂȂǂ̉^�]�������ŔR�Ď��������邽�߂ɐv���ꂽ�BF�^�K�X�^�[�r���́A�o��88.300MW�K�͂ɑΉ�����B�A�����j�A�́A���f�L�����A�Ƃ��Ă̗��p�̂ق��A�Y�f���܂܂��R�Ă��Ă�CO2��r�o���Ȃ����߁A���d�ɒ��ڗ��p�ł���E�Y�f�R���Ƃ��Ă����҂���Ă���B IHI�́A2022�N�ɏo��2MW�̃A�����j�A100���R�ăK�X�^�[�r�����J�����A�R�Ď��ɔ������鉷�����ʃK�X��99���ȏ�팸���邱�Ƃɐ��������B���̋Z�p������ɐi�������A��K�͔R�ċZ�p�̊J���Ɏ��g�ށB2030�N�܂łɃA�����j�A100���ɂ��R�ăV�X�e���̎��p����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�Ăf�d�n�Ɗo���^�E�Y�f�֊�ƘA�g���i �o�ώY�ƏȂ��A���͔��d�ȂǒE�Y�f�d���̊g��Ɍ����A�đ��G�l���M�[��ƁuGE�x���m�o�v�Ɗ����ŋ��͂���g�g�݂�ݗ����邱�Ƃ��킩�����B������ƂƂ̃T�v���C�`�F�[���i�����ԁj�̍\�z��Z�p�A�g���x�����A�唼��A���ɗ��镗�Ԕ��d�ݔ��Ȃǂ̍��Y����ڎw���B (GE�x���m�o�́A�ă[�l�����E�G���N�g���b�N�iGE�j���番�Љ��������E���̃G�l���M�[���) �o�Y�Ȃ͍���̘g�g�݂�ʂ��āAGE�x���m�o�̍H���U�v����ق��A���{��ƂƂ̘A�g�ɂ�鍑���̋����ԍ\�z��}��B���{��Ƃ����ƂɎQ������ꍇ�͕⏕�����x����������B �o�Y�Ȃ͕��͈ȊO�ɂ��ACO�Q�n���ɒ�������Z�p�uCCS�v�Ȃǂł����͂���B�g�g�݂̈�Ƃ��āA���͔��d���u���[���X�G�i�W�[�v�͖k�C����GE�x���m�o�̕��͔��d�@�����A�Đ��\�G�l���M�[�ʼnғ�����f�[�^�Z���^�[����̓I�ɊJ������B�O�H�d�@�͑��z�d�V�X�e���̍��x���Ɍ����A�����̕���ŋ��͂���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���u�ߘa6�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���v�i�G�l���M�[����2025�j���t�c����
�G�l���M�[����2025�̊T�v (1) ���������̐i�� �@�R���f�u���̎����I��o����2�������B�܂��A�������ɂ��āA�C�m���o�̈��S�����m�F���ꂽ�B�A�҂���]����S�Z�����A�҂ł���悤�n�݂��ꂽ�u����A�ҋ��Z��搧�x�v�Ɋ�Â��A�����Đ��v�悪�F�肳�ꂽ�B (2) �O���[���g�����X�t�H�[���[�V�����iGX�j �@2050�N�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ�������g������G�l���M�[�v�V�Z�p�Ƃ��Ė{�����ł́u���d�Z���v�A�u�y���u�X�J�C�g�v�A�u���̎��m�㕗�́v�A�u������n�M���d�v�A�u������v�V�F�v�A�u���f���i���f�E�A�����j�A�E�����R���E�������^���j�v���̓����ɂ��ĊT�ς��Ă���B (3) ��v10�����E�n��̃J�[�{���j���[�g���������Ɍ����������Ƃ��̔w�i�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Z���g�����̏ȃG�l���ɍv���z�ǂ̒�R�ጸ�܂Ȃǐ��\������@��JIS���iJIS B 8703�j ���{�K�i����́A�I�t�B�X�r���⏤�Ǝ{�݂Ȃǂō̗p����Ă���Z���g�����V�X�e���̐��z�n�Ŏg�p������R�ጸ�܂̐��\������@�Ɋւ�����{�Y�ƋK�i�iJIS�j��V���ɐ��肵���ƌ��\�����B �z�ǒ�R�ጸ�܂�h�K�܂̐��\����������A�M���������s��n�o�Ɠ����ɁA�d�͏���ʂ�CO2�r�o�ʍ팸�ɂ��v�����A�Z���g�����V�X�e���S�̂̊����גጸ�����҂����B �Z���g�����V�X�e���̔z�ǂɂ����āA�z�|���v�̕��ׂ������邽�߂Ɏg�p����A�ȃG�l��CO2�r�o�ጸ�Ƃ��������ʂ������炷�u�z�ǒ�R�ጸ�܁v�ƁA���H��}������u�h�K�܁v�̐��\�𑪒肷�鎎�����@��I�ɋK�肷��JIS��V���ɐ��肵�A��܂̎g�p���ʂ̐M�������q�ϓI�Ɏ������������B ����܂ł́A�����̖�܂̐��\������@���W��������Ă��Ȃ��������߁A�z�ǂ̒�R�ጸ���\��h�K���\�Ƃ������A��܂̎g�p���ʂ�K�ɕ]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���w�Z�̈�ٓ��̗�[�����A�S������22.7���E�n��i�������݉� �����Ȋw�Ȃ́A�S���̌����w�Z�ɂ�����̈�ٓ��̋i��[�j�ݔ��̐ݒu�Ɋւ��钲�����ʁi�ߘa7�N5��1�����_�j�����\�����B ���Ȃ̒����́A�S���̏��w�Z�A���w�Z�A���ʎx���w�Z�i���w��Z���܂ށj��ΏۂƂ��Ă���B�����̈�ق܂��͕�����ɂ������[�ݔ��̗L�����W�v�E���͂������ʁA�S���̌��������w�Z�ɂ�����ݔ��̐ݒu����22.7���ł���A�O���i�ߘa6�N9��1�����_�j��18.9������3.8�|�C���g�㏸�����B�܂��A���w��Z�Ɍ���Ɛݒu����23.7���ł������B�����s�͏����w�Z�Ƃ���90������ݒu���������Ă������A��茧�⍲�ꌧ�Ȃǂł�1.2����ɂƂǂ܂��Ă���A�n��Ԋi���������ł���B ���y���Չ���{�v��Ɋ�Â��u�ݔ������Վ������t���v�����̈�ł���A���Y��t���̊��p�Ȃǂ�ʂ��āA2035�N�܂łɑS�����ϐݒu��95����ڎw���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������Ƃ̍Đ��v���X�`�b�N�g�p�ʂɍ����ڕW�ݒ�A�g�p���т̕`�������A���������� ���{�́A��ʂ̃v���X�`�b�N���g�p���鐻���Ƃɑ��A�Đ��ނ̎g�p�ʂ̖ڕW�ݒ��g�p���т̕��`����������j���ł߂��B �����ʼn�������g�p�ς݃v���X�`�b�N�͑唼���ċp��������Ă���A�K�������ŒE�Y�f�����㉟������B������Η��N�̒ʏ퍑��Ŏ����L�����p���i�@�̉�����ڎw���B ���݂͐��l�ڕW�̂Ȃ��w�͋`���ɂƂǂ܂��Ă���A�o�ώY�ƏȂ̗L���҉�c�͌����ɂ��A�ڕW�ʂ̐ݒ�����I�ȕ����߂���e�荞���Ԏ��܂Ƃ߂����肷����j���B �K�������̑ΏۂƂȂ�̂́A���А��i�̐����ߒ��ň��ʂ̃v���X�`�b�N���g�p���Ă���Ǝ킾�B�o�Y�ȂȂǂɂ��ƁA��E�e���d�C�E�d�q�@��A�����ԁA���ނȂǂ̋Ǝ킪�ΏۂƂ��Ďw�肳���\��������B�g�p���т̕��`���Â��A���g�݂��s�\���ȏꍇ�͉��P�������E���߂���B���߂ɏ]��Ȃ��ꍇ�͔����̓K�p����������B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���j�Z�����d�̃w���J���t���[�W�����A22���~���B�ݔ��J���̈ꕔ�� �j�Z�����g�������d�Z�p���J������HelicalFusion�i�w���J���t���[�W�����j�́A��O�Ҋ��������Ŗ�22���~�B�����Ɣ��\�����B �j�Z�������Ŕ��������G�l���M�[��M�ɕς����ݔ��̊J����p�Ȃǂɏ[�Ă�B2030�N�㑁���Ɏ���ڎw���B��O�Ҋ���������SBI�C���x�X�g�����g��c���C�m�x�[�V�����E�C�j�V�A�e�B�u�iKII�j�Ȃǂ��������B���Z�@�ւ����1���~�̎����������B �w���J���t���[�W�����͎��R�Ȋw�����@�\�E�j�Z���Ȋw�������̌����҂炪�Ɨ�����21�N�ɐݗ������X�^�[�g�A�b�v���B�u�w���J���^�i�w���I�g�����^�j�v�ƌĂ��j�Z���F���J�����Ă���B�点��\���̃R�C�����g���A����Ńv���Y�}�𐧌䂵�Ċj�Z�����N�����B 24����365���^�]�ł��A�G�l���M�[�������ǂ��A�����e�i���X�����₷���Ƃ�������������B 2030�N��̑����Ɏ��p���������������d���̏����@���ғ�������v�悾�B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2025/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���g�p�ςݑ��z���p�l���̃K���X���u�������T�C�N���v�A�z�b�g�i�C�t�@�ł��\�ɁBAGC�����p�� AGC�́A�u�z�b�g�i�C�t���v�ɂ���āA�g�p�ςݑ��z���p�l�����番���E��������J�o�[�K���X�������Ƃ����K���X�̐��������p�������Ɣ��\�����B ���Ђ́u�M�������v�ɂ���āA�K���X�̗ʎY�Ɏg�������Ɏg�������т����B�p�p�l�����������Ď����Ȃǂ�n�����u�M�������v�́A�J�o�[�K���X�̕\�ʂ������������Ȃǂ͂��ꂢ�ɏ�������邪������u�̉��i����r�I���z�Ȃ��Ƃ���A�������Ă����Ƃ͌����Ă���B �u�z�b�g�i�C�t���v�́A�J�o�[�K���X�Ǝ����̃o�b�N�V�[�g�̐ڒ��ʂɉ��M�����n���i�z�b�g�i�C�t�j����������ŕ�������B���̊ȈՂȎd�g�݂���A������u�͑��ΓI�Ɉ��������ꕔ���K���X�ɕt�������܂c��B����A���������˂��邱�Ƃɂ���Ď����Ȃǂ̎c�Ԃ��قڏ������A���̃K���X�����̔䗦�Ō����Ɋ܂߂ĔK���X������u�������T�C�N���v�����p�������B2030�N�܂łɔN�Ԑ���t�K�͂̃��T�C�N���̐��̍\�z��ڎw���Ƃ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���q���\���E�G�i�W�[�ƎO�HUFJ�M���A�����Łu�K�i���Ǝҁv�F��ڎw���B�S�N�\�[���[�\�z���Ƃ�W�J �q���\���E�G�i�W�[�ƎO�HUFJ�M����s�́A���K�͑��z�����W�Ē����^�c����������u�S�N�\�[���[�\�z�v�̎����Ɍ����Ď��{�E�Ɩ���g����o������������Ɣ��\�����B���Ђ͍���̎��{�E�Ɩ���g�ɔ����A�����ŁA�o�ώY�ƏȂɂ��u��������K�i���z�����d���Ǝҁi�K�i���Ǝҁj�v�̔F��擾��ڎw���B �q���\���E�G�i�W�[�́A�n��̋��Z�@�ւ��ƁA�����̂ƘA�g���A�A�n�o��10kW�ȏ�50kW�����̒ሳ���Ɨp���z������̂ɒ����K�͂̊������z�����d�����擾���AICT�i���ʐM�Z�p�j�����p�����u�S�N�\�[���[�v���ƂɎ��g��ł���B�R�����Ƃ̋����������Ƃ��璅�z�������g�݂ŁA��1�e���R�����Ŏ��{�����B ���K�͑��z���̏W�Ƃɂ��ẮA�o�Y�Ȃ��u��������K�i���z�����d���Ǝҁi�K�i���Ǝҁj�v���x��n�݂��Ă���B�K�F��i���Ǝ҂́AFIT�ɂ��F�蔭�d���̖��`�ύX�葱�����ȗ��������Ȃǂ̗��_������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����B�s�Ŏ��c���}�C�N���O���b�h�A���h�b�N�X�t���[�d�r���� �Z�F�d�H�́A���B�s�����݂���u���؎R���z�����d���v�̒~�d�ݔ��Ƃ��āA���h�b�N�X�t���[�~�d�r����уG�l���M�[�Ǘ��V�X�e���usEMSA�v���̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���؎R���z�����d���́A�o��1MW�̃��K�\�[���[�ŁA���B�s�����i����u�[���J�[�{���V�e�B�v�̈�Ōv�悳�ꂽ�B��������2km�̎��c���Œn��}�C�N���O���b�h���\�z���A���d�����d�͂����ӂ̎�v10�{�݂ɋ�������B �]��d�͂́A���h�b�N�X�t���[�d�r�ɒ~���Ė�Ԃɓd�͋�������ق��A��펞�ɏ��p�n������d�����ꍇ�A�����^�]�����Ď�v�Ȕ��_�ɏd�_�I�ɓd�͂���������B���h�b�N�X�t���[�d�r�̒�i�o�͂�250kW�A�e�ʂ�1125kWh�ƂȂ�B�Ⴆ�A�o��250kW��4.5���ԕ��d�ł���B �����̂̎������̌����{�݂Ń��h�b�N�X�t���[�d�r�Ǝ��c����p���ēd�͂����B�܂��A���Ȃ́u�n��E�Y�f���i�⏕���v�Ώێ��ƂƂ��āA���h�b�N�X�t���[�d�r���̗p���ꂽ���߂Ă̈Č��ɂȂ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ����ёg�A���^�o�b�e���[���p������ŋ��d����GX���@�̏I���ғ������� ��ёg�́A������ɉ��^�o�b�e���[�����AGX���@�B�̉^�p���؎������s�����B���^�o�b�e���[���ғ����̌��@�B�̋߂��ɐݒu���A���d�ł���̐��𐮂������Ƃɂ��A�d���ړ����N���[����8���ԍ�Ƃł��邱�Ƃ��m�F�B�o�b�e���[�e�ʂ�[�d�X�|�b�g�ւ̈ړ��̓���Ȃǂ���I����Ƃ����������^GX���@�B�̉ۑ�����Ɍ����O�i�����B �����ł́A��s���̌�����ɂ����ĉ��^�o�b�e���[�i�d�r�e�ʁF85.24kWh�A��i�o�́F36kW�A�[�d���ԁF4.25���ԁj�����A25t�݂�̓d���ړ����N���[���̏[�d����ы��d���@�Ȃǂ��������B��Ƌx�e���Ɍ��@���[�d������A���^�o�b�e���[���璼�ڋ��d���Č��@���ғ�������Ȃǂ̎������s�����Ƃ���A1��8���Ԃ̃N���[����Ƃ����{�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�BCO2�팸���ʂ͔N�ԂP�䓖�����32t��CO2�팸�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o���A�f�[�^�Z���^�[��p�p��������������I �o�����Y�́A�f�[�^�Z���^�[�����̗�p����o�����Ɣ��\�����B�T�[�o�[����ɐZ���ė�₷���ƂŁA���ݎ嗬�̋�C�ɂ���p�ɔ�ׂēd�͎g�p�ʂ��4�����点��Ƃ����B �o���Ƃ��ăf�[�^�Z���^�[�����̗�p����̂͏��߂āB�������Ō������琸������B�T�[�o�[����ɐZ���A�����z�����邱�ƂŔM��D���B��p���͓d�C��ʂ��Ȃ����߁A�d�q�@��͉��Ȃ��Ƃ����B���i�́A1���b�g��������2,500�~�قǃf�[�^�Z���^�[�̃T�[�o�[���₷��@�Ƃ��Ă͖����g���̂������I�ŁA�����Ő��A��C�̏��Ƃ����B�ߔN�A���ɂ���p�������ꂽ�f�[�^�Z���^�[�����X�ɉғ����n�߂��Ƃ����B�o���͓Y���܂̔z���Ȃǂɂ��A�R���ɂ����Ɨ�p���\�͋�C��30�{�̔M�`�B�������B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���������݁A������Ŕ����������푽�l�Ȕp�v���X�`�b�N���Ď����� �������݂́A������Ŕ��������v���X�`�b�N�̔p������������ނ��ƂɌ���ō��x���ʂ��A�Ď������ނƂ��ėL�����p����}�e���A�����T�C�N���X�L�[�����\�z�����B �{�X�L�[���̓����́A����ʼn���������푽�l�Ȕp�v���X�`�b�N���A����̍�ƈ����v���X�`�b�N�Z���T�[��p���ă|���G�`�����A�|���v���s�����A�|���X�`�����Ȃǂ̍ގ����x���ŕ��ʂ��A�L�����Ƃ��Ĕ��p�ł���Ď������ނ�I�ʂ���B���e�Ƃ��āA�u���{���꒚�ڒ��n�����s�X�n�ĊJ�����Ɓv�̌�����Ŗ{�X�L�[���Ɋ�Â��}�e���A�����T�C�N���̎��g�݂�i�߂Ă���B ����̔p�����ۊǏꏊ���u����������[�h�v�Ƃ��A�p�����S�ʂ̊Ǘ����s����C��ƈ��i�O���[���}�X�^�[�j��z�u�B���[�h�Ɏ������܂ꂽ�p�v���X�`�b�N�̍ގ�����ƈ����n���f�B�^�̃v���X�`�b�N�Z���T�[�Ŋm�F���A�t�����̐���≘��̒��x�Ȃǂ����܂��ėL�����p�Ώە���I�ʂ���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| �������W�A�y���u�X�J�C�g�^�V���R���E�^���f���^34.85%�A�����V���R���i�P�ڍ��^�j27.81%�� �y���u�X�J�C�g�^�V���R���E�^���f���^���z�d�r�Z���̕ϊ������ɂ����鍡��̐��E�L�^�B���́A2023�N11����33.9%�A2024�N6����34.6%��B�����Ĉȗ��A3�x�ڂƂȂ�܂��B�V���ȋL�^�ƂȂ�34.85%�́A�č������Đ��\�G�l���M�[�������iNREL�j�ɂ��F���ꂽ�B �܂��A��ʓI�Ɏg�p����Ă���P�ڍ��^�E�����V���R�����z�d�r�Z���ɂ����Ă��A����̋L�^�B���́A2022�N11���ɋƊE��5�N�Ԃ�̍X�V�ƂȂ���26.81%�Ɏn�܂�A2023�N12����27.09%�A2024�N5����27.3%�ƁA4�N�A���E4��ڂ̋L�^�X�V�ƂȂ�܂��B�����27.81%�̐V�L�^�́AHIBC�iHybrid Interdigitated-Back-Contact�j�Z�p�ɂ���ĒB������A�h�C�c�E�n�[�������̑��z�G�l���M�[�������iISFH�j�ɂ��F���ꂽ�B �o�T�u�����W�v |
|
|
| ���ăt���X�g���T���o���ATMEIC�ɍō��A���[�h�A�Y�Ƃ̒E�Y�f�ւ̍v���� TMEIC�i�e�B�[�}�C�N�j�́A�t���X�g���T���o������A�u�J���p�j�[�E�I�u�E�U�E�C���[�E�A���[�h�v����܂����Ɣ��\�����B�t���X�g&�T���o���́A�e�ƊE�œ��Ɍ��o�����Ɛт���������Ƃ�\������u�x�X�g�E�v���N�e�B�X�E�A���[�h�v�N���{���Ă���B ����ATMEIC����܂����̂́A�u�C���_�X�g���A���E�J�[�{���j���[�g�����E�\�����[�V��������v�ŁA�J���p�j�[�E�I�u�E�U�E�C���[�E�A���[�h�͍ō��ʂƂȂ�B �]��������g��ł�����K�͂ȑ��z�����d�A�G�l���M�[�����V�X�e���iESS�j�����̃p���[�R���f�B�V���i�[�iPCS�j�ɉ����A�p���[�G���N�g���j�N�X�̃R�A�Z�p�������V����ł̐��ʂ��]�����ꂽ�B��̓I�ɂ́A���f�����p�̎��㎮������A���|�p�̃A�[�N�F�����V�d���V�X�e���uCleanArc�i�N���[���A�[�N�j�v�A�ӓ��������㋋�d�V�X�e���Ȃǂ�������ꂽ�B��������A�Y�ƕ���̃J�[�{���j���[�g�����ւ̑Ή������[�h���Ă���Ƃ��ꂽ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z���p�l���̕ǖʐݒu�V�X�e���A�O����f�M�H�@�ɑΉ� �n���t�@�W���p���́A����n����܂ޓ��{�S���̐V�z�Z������ɁA�O����f�M�H�@�ɑΉ��������z���p�l���̕ǖʐݒu�ˑ�V�X�e���u�t���i�X�l�I�iFronHasNeo�j�v�\�����B���������ށA�V�l�W�b�N�A�X�����[�H�Ƃ̋��͂ɂ��J�������B �O�Ǎނƒf�M�ނ𗯂߂�ʋC�����i�G�A�z�[�������j�ɉˑ������Œ肷�邱�ƂŁA�f�M�ނ��ђʂ��Ȃ��ő��z���p�l����ݒu�ł���B�܂��A���ނ��g�p�������z���p�l��������ɒ��ڌŒ肷�郉�b�N���X�i���t����������j�Ƃ��邱�ƂŁA���z���p�l����ݒu�������ɘI�o�����Ȃ��Z��̊O�σf�U�C���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B����n��⑽��n��ł̎g�p���l�����������x�E���ϋv�v���̗p�����B���̂ق��A���Ђ��ߓ����J�\��̖hΉ@�\�����V�^���z���p�l���Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA���ӊ��ւ̌��Q���]���ȏ�ɗ}���ł���Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O�HHC�L���s�^���A���E���̏��ƋK��e-���^�m�[���������J�n �f���}�[�N�̍Đ��\�G�l���M�[���European EnergyA/S���A�ăG�l�R����e-���^�m�[���̋������J�n�����B EuropeanEnergy�͎O�HHC�L���s�^���̃O���[�v��Ђł���A���Ђ͐헪�I�p�[�g�i�[�V�b�v�̂��ƁA������G�l���M�[����ł̎��ƓW�J��i�߂Ă���B e-���^�m�[���́A�O���[�����f�ƃo�C�I�W�F�j�b�NCO2�i�����R���̓�_���Y�f�j���������ē����鍇���R���ł���A�]���̉��ΔR���R�����^�m�[���ɔ�ׂĉ������ʃK�X�̔r�o�ʂ��啝�ɗ}������B���ɁA�D���R���≻�w�i�E�v���X�`�b�N�̌����Ƃ��Ă̗��p�����҂���Ă���B ����ғ����J�n���������v�����g�́A304MW�̑��z�����d�ݔ���52MW�̐��d�u������A�N�ԍő�4.2���g����e-���^�m�[���Y�\�Ƃ���B���ƋK�͂ł̐����Ƃ��Ă͐��E�����ő�K�́B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���u�u���[�J�[�{���v�g��ցAENEOS���C�����q���� ENEOS�́A�C�m�����J���@�\����ъC��E�`�p�E�q��Z�p�������`�p��`�Z�p�������Ƌ����ŁA�C�m������ʂ��ĊC���[�C��CO2���Œ肷��u�u���[�J�[�{���v�̊g��Ɍ����A�C���ނ̋�������e���Ȃǂɂ��Ē�������B �u�u���[�J�[�{���v�́A�C���Y�E�琬���邱�ƂŁA��C������C���ɋz�����ꂽCO2��[�C�ɒ����E�Œ肷��d�g�݂ŁACO2�̐V���ȋz������Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B����̎��Ƃł́A�[�C��ɂ�����C���ނ̋�������ӊ��ɋy�ڂ��e���Ȃǂɂ��Ē������A����̉\������������B�C�m���������p����CCUS�iCO2����E���p�E�����j�ɂ��G�l���M�[�N��CO2�̍팸��ڎw���B �[�C��ł̑��ނ̋����c���Ȃǂł́A�L�l���������D�u����6500�v��p�������q�����ɂ�蓮����B�e���A�T���v�����O�ɂ�蕪�͂���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ĂōăG�l�R���E�����R���A���E���̏��p�v�����g���HJOGMEC�ƎO�H�������o�� �ăC���t�B�j�E���́A�č��e�L�T�X�B�����ŏ��ƋK�͂�e-fuel�i�����R���j�����v���W�F�N�g�ɂ��čŏI����������s���A���ݍH�����J�n�����B���Ђɂ́A�G�l���M�[�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j�ƎO�H�����������ŏo�����Ă���B �C���t�B�j�E���́A�Đ��\�G�l���M�[�R���̃O���[�����f��CO2��������e-fuel�ɂ����鐢�E���ƂȂ鏤�ƋK�͂̐��Y�҂ŁA2020�N6���ɐݗ����ꂽ�B���Ђ�����e-SAF�i�����\�ȍq��@�R���j��e-Diesel�i�����f�B�[�[���R���j��e-fuel�̂P�ŁA���̂܂܊����̔�s�@��g���b�N�A�D���ɗ��p�ł���u�h���b�v�C���R���v�ɂȂ�B���ΔR���Ɣ�r����CO2�r�o�ʂ�90���ȏ�팸�ł���B ���\�����Č��́Ae-fuel����2���Č��ƂȂ�B���Y�\�͔͂N��750���K�����i����500�o�����j�ŁA���E�ő�K�͂�e-SAF�����v�����g�ƂȂ�\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2025/6�@]�@�@�� |
|
|
| �����D�O��A�����K�X�����k�m�f�^���D�ɕ��͐��i���u�𓋍� ���D�O��́A�V�����铌���K�X������LNG�^���D�ɁA�@�ۋ����v���X�`�b�N�iFRP�j���̍d���������͐��i���u�u�E�C���h�`�������W���[�v2��𓋍ڂ���Ɣ��\�����B �E�C���h�`�������W���[�̍����͍ő�Ŗ�49���[�g���A���͖�15���[�g���B�L�k�\�Ȕ��ŊC��̕��𑨂��đD���̕⏕�I�Ȑ��i�͂Ƃ��A�q�s�R����LNG�̎g�p�ʂ����炷�B���D�O��ɂ��ƔN�Ԃ�LNG�g�p�ʂƉ������ʃK�X�r�o�ʂ���������ő��12%�팸�ł���B�E�C���h�`�������W���[�𓋍ڂ���LNG�^���D�͐��E��2�ǖڂƂȂ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Z�F�����A�ĎЂƊj�Z���Œ�g�^���{�E�A�W�A�֔h���Z�p�g�� �Z�F�����́A�j�Z���G�l���M�[�Z�p�Ƃ��̔h���Z�p�̊J������|����ăV���C���e�N�m���W�[�Y�ЂƋƖ���g�����Ɣ��\�����B �܂��͔h���Z�p�ł��钆���q�C���[�W���O�Z�p���×p�A�C�\�g�[�v����{�E�A�W�A�n��ōL�߂����l���B�j�Z���G�l���M�[�Z�p���̂ł����Ƃ�[�߂Ă����B�V���C���Ђ�2005�N�̐ݗ��B��N7�����_�ŁA�j�Z���G�l���M�[�ƊE�ł͑�R�ʂƂȂ�v�W���h���ȏ�̎����B���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����d����51�������ց^��d�A�M�d�����V�X�e������8MW���K�X�G���W���� ���d�H�Ƃ́A�����a�x�v�R���ƃZ���^�[�̃K�X�G���W���R�[�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�V�X�e���X�V�v���W�F�N�g������8MW���K�X�G���W��2��������B 2027�N2���Ɉ����n���\��B���v���W�F�N�g�͐�d��14�N�ɔ[������5MW���K�X�G���W�����d�ݔ�2���Ȃ�R�[�W�F�l�V�X�e�����X�V������̂ŁA��d�͐ݔ��̋����Ǝ��^�]�w����S������B �ݔ��͍H��̐��Y�v���Z�X�ɗp����d�C�Ə��C����������\��B���d����51.0%���������A�����I�ɉ����H�����s�����ƂŁA�̐ϔ�30%�܂ŔC�ӂ̊����Ő��f��s�s�K�X�ƍ��Ă��邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���Z���^�[�Ɋ��݂̐�d���K�X�G���W���̐M�����ƃA�t�^�[�T�[�r�X�Ή��̎��сA�����̐��f�����ʂɉ������_��ȉ^�p���\�ȓ_�������]������A����̎ɂȂ������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ϐ����w�A�w�Z�̈�ى����Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r�ݒu�����E���쌧�Ŏ��� �ϐ����w���A�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��p���Ɍ����A�����̂ƘA�g���V���Ȏ����J�n����B4���ɕ����s�ƍ��쌧�Ƃ̎��g�݂\�����B����A�e�����̂̊w�Z�̈�ى����ɓ����z�d�r��ݒu���A���d���\�Ȃǂ̌���i�߂�B ����̎��؏ꏊ�́A�u�����s�����ŕl���w�Z�v����сu���쌧���ω�����ꍂ���w�Z�v�B���̂������w�Z�ł̎��ł́A200m2���x�͈̔͂Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r��\��t����B���������ɂ�����ݒu�Ƃ��Ă͑S���ő�K�͂ɂȂ�Ƃ����B ���z�d�r�ɂ͖h���ވ�̌^���̗p�A�܂��~�d�r�݂��邱�ƂŁA���Ƃ��Ă̋@�\�������}��B���쌧�̍��Z�ł́A�A�[�`�^�����ւ̐ݒu�E�{�H���@�A�ϋv���┭�d���\��������B�ݒu�ʐς�10m2�B�����s�ł́A�E�Y�f�Љ�����A�V�Z�p�̊��p�𐄐i���Ă���B���̈���A�S���ɐ�삯���t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗��擱���ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������CO2���獇���ł��郁�^�m�[���^�p�i�\�j�b�N�n�����z���^�����J�� �p�i�\�j�b�N�G���N�g���b�N���[�N�X�́A�O�H�K�X���w�Ƌ����ŁA�R���Z���g�Ȃǂ̔z���������ɁACO2���琻���������^�m�[���������Ƃ�����z���^�����A�������J�������Ɣ��\�����B 2025�N�x�ȍ~�ɁA���������g�p�����z�����̔̔��J�n��ڎw���B �����A�����͔M�d���������̈��ŁA�σg���b�L���O����σA�[�N���ɗD��Ă���A�z�����̓d�C�Ј��S�����x����ޗ��Ƃ��āA�p�i�\�j�b�N�Ŏg�p���Ă�������̖�4����1���߂�B����ŁA��x�d������Ɖ��M���Ă��n�����A�}�e���A�����T�C�N�����ł��Ȃ��Ƃ����ۑ肪����B�����ŁA�p�i�\�j�b�N�͍���A�������̌����ł��郁�^�m�[����CO2���獇���\�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��A�J�[�{�����T�C�N���ł���V���Ȑ����X�L�[�����O�H�K�X���w�ƂƂ��Ɋm�������B�J�����������A�����́ACO2���Œ艻�������^�m�[���������Ƃ��邽�߁ACO2�r�o�ʂ͏]���Ɣ�ׂĖ�20�`30���팸�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��LIXIL�A���z���Ŕ��d���郍�[���X�N���[���֎����ݒu�ŏȁE�n�G�l LIXIL�́A�������̑��ɊȈՂɎ��t������uPV�i���z�����d�j���[���X�N���[���V�X�e���v�̎��A2025�N6�����J�n����Ɣ��\�����B �z�����X�Ŕ��d���A���d�@�\����������E���̃��[���X�N���[����̉����ݒu�^���z�����d�ݔ��ŁA�����{�݂���і@�l�����Ɋ֓��G���A�œW�J���J�n���A�����W�J�G���A���L���Ă����B �z���H�����s�v�ŁA����������e�ՂɌ�t���ݒu�ł��A�Ռ�����f�M���Ȃǂ̒ʏ�̃��[���X�N���[���Ƃ��Ă̋@�\�ɉ����A���d��~�d�@�\����ѓd�͎�o�iUSB TypeC�ADC�W���b�N�j���\�ŁA�ЊQ���̃��W���G���X������ȃG�l�Ɍ��ʂ����҂����B ���V�X�e��1��������ő�X�}�z9��A�܂���PC3�䕪��1���ŏ[�d�ł��锭�d���\�j���Ƃ����BPV�Z���ɂ͔����V���R�����g�p�B�܂��A�X�N���[���̐��n�����́u�t�@�u���b�N�d�l�v�Ɓu�X�P���g���d�l�v��2��ނ�W�J����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z���p�l����ݒu�ł��鉮���ʐς����A�o�Y�Ȃ����x�� �o�ώY�ƏȂ́A�����u�����z�����d�ݔ��̋Ɩ��p�r���ւ̐ݒu���i�Ɍ����āA���z���p�l���̐ݒu�ςݖʐς���ѐݒu�ł��鉮���ʐςȂǂɂ��Ē�����̒�o�����߂鐧�x�Ă��������B �����x�ẮA�G�l���M�[�Ǘ��w��H��Ȃǂ������莖�Ǝ҂Ȃǂɑ��A�H��Ȃǂ̉����u�����z���ݔ���ݒu�ł���ʐςƂ��āA�����̉����ʐρA�ϐk��A�ύډd�A���̂������ɉ����u�����z���ݔ����ݒu����Ă���ʐς̕����߂�B1����������̉����ʐ�1000m2�ȏ��ΏۂƂ���B �܂��A���̏������������ɂ��ĉ����ʐρA����щ����u�����z���ݔ��ݒu�ς݂̖ʐςƏo�͂ɂ��āA���ƎҒP�ʁi����\�E�F��\�j�ł̕����߂�B2027�N�x��o�̒��������K�p����B���̂ق��A���莖�Ǝ҂ɑ��A2026�N�x�ȍ~�ɒ�o���钆�����v�揑����A�����u�����z���ݔ��̐ݒu�Ɋւ���萫�I�ȖڕW�̒�o�����߂�B �o�T[���oBP�v |
|
|
| ���c�_�^���z�����d�A�����ƕi���ቺ�̍����ɕǂ��� �_�ƂƍĐ��\�G�l���M�[�̕��Y�͑����̗��_�������A�o�c�I�Ȉ����GHG�팸�Ɋ�^����ƍl�����Ă���B�������A����ł͋Z�p�I�ȉۑ�������A�Ⴆ�A���z���p�l���̐ݒu�ɂ����˗ʂ̌������앨�̐���ɉe����^���邱�Ƃ����O����Ă���B ������w��w�@�_�w�����Ȋw�����Ȃ̉���������́A�c�_�^���z�����d�A�w�\�[���[�V�F�A�����O�x�̌o�ϐ����A�t�B�[���h�����Ŗ��炩�ɂ����B���z���p�l�������c��27%�������ŁA�H�ƂƓd�͂̓������Y���s�������ʁA������ʂ͕��ς�23%�����������A�����v�͏]���̈���5�{�ȏ�ɒB�����B �������A�����n�����������A�����������ቺ����X���������A���Ē��̃^���p�N�ܗʂ�A�~���[�X�ܗʂ������Ȃ邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�{���ʂ́A�c�_�^���z�����d���c�̓������y�ɂ����ẮA���ʒቺ�̗}���ƕi�����艻�ɗ��ӂ����V�K�͔|�Ǘ��Z�p�̊J�����}���ł��邱�Ƃ������Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��������^�n�M���d�𐄐i �u��7���G�l���M�[��{�v��v�ł́A7�����߂�Η͔��d�̒E�Y�f�d���ւ̒u��������A�����������܂��d�͎��v�ɑ��āA�E�Y�f�d���̊g��͕K�v�s���ł���B ���̂����ŁA���E��3�ʂ̒n�M�����|�e���V����������A����I�ɔ��d���s�����Ƃ��\�ȃG�l���M�[���ł���A�n�掑���̗L�����p��ʂ��ĎY�ƐU����n��Љ�ɍv�����A�n�抈�����ɂ�������n�M���d�̓������i�͂��d�v�ƂȂ��Ă���B ���̂��߁A����܂ł�23.5GW�̏]���^�n�M���d�̊J���|�e���V�����ɉ����āA77GW�ȏオ���҂���鎟����^�n�M�|�e���V�����ɂ����āA�u�����̊J���\�Ȏ����ʂ̑����v�Ɋ�^���ׂ��A������^�n�M�Z�p��2030�N��̑����̎��p���A���̌��2040�N�E2050�N�̍����O�ł̕��y���̂��߁A�e�Z�p�ɂ�����ۑ�E�Z�p�J���v�f�̓���E�J���X�P�W���[���E���X�P�W���[�����ɂ��ċ�̓I�ȖڕW�E�v�擙����������̂ƂȂ��ċc�_�E���肷��B �o�T�u�����G�l���v |
|
|
| ��SDGs����ɂ�荂�܂��҂̊��ӎ��A�d�ʃJ�[�{���j���[�g�������Ԓ��� �d�ʂ́A��16��u�J�[�{���j���[�g�����Ɋւ��鐶���Ғ����v�̌��ʂ����\�����B�����ɂ��ƁA�J�[�{���j���[�g�����A�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ��������g�݂��K�v���Ɗ�����l��68.9���ŁA�O���i76.0���j����7.1�|�C���g�������A�ߋ��Œ�ƂȂ����B ��̓I�ɁA���i�̐����̒��Ōl�Ƃ��āA�J�[�{���j���[�g������E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����Ď��g��ł���l�̊�����22.7���������B����ʂł́A15�`19���ł�����36.2���B�ł��Ⴉ������50���17.0���B��N�J�Â��ꂽCOP29�̔F�m�x���q�˂��B���̌��ʁA�F�m���͑S�̖̂��i45.4%�j�B�N��ʂł́A70��i70.4%�j���ł������A������60��i52.2%�j�A15�`19�i51.3%�j�Ƒ������B ����̌��ʂł́A15�`19�̎�҂��A���g�݂̕K�v���ӎ���C���㏸�ɑ���F�m�E�[���������X��������ꂽ�B���w�Z�ł̊����炪�e�����Ă���ƕ��́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2025/5�@]�@�@�� |
|
|
| ������ESS��A�]��d�͂���ɒ~�M�����ő吔�\MWh�K�͂̎��؊J�n ���ŃG�l���M�[�V�X�e���Y�ƒ����d�͂́A����s���̓d�́E�M�̎��v���уf�[�^����ɁA��Β~�M�G�l�}�l�ݔ������Ɍ����������ƌ����J�n�����B ���Ђ����p����ڎw����Β~�M�G�l�}�l�ݔ��Ƃ́A�����ő�K�͂ƂȂ�M�e�ʐ��\MWh�K�͂̊�Β~�M�ƃG�l�}�l�Z�p��p�����v�����g�B�]��d�͂�M�ɕϊ����Ċ�Ȃǂ̒~�M�ނɒ~���A���v���������ԑтɃ^�[�r���ɂ�锭�d���s���B���{�Ɍ����A����ESS�ƒ����d�͍͂���A����s�Ɗ�Β~�M�G�l�}�l�ݔ������Ɍ������������������B2027�N�x����͋@��̐����i�߂�B ����ESS�ƒ����d�͂͑��������Β~�M�Z�p�ɒ��ڂ��A�����Ō�����i�߂Ă����B2022�N�ɂ͔M�e�ʖ�500kWh�̊�Β~�M�V�X�e���̎����ݔ����J�����A���؎��������{�����B ����s�́A2029�N�x�܂łɔp�������d�{�݂֊�Β~�M�G�l�}�l�ݔ������邱�Ƃ��v�悵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����}�s���Y�ȂǏ����͂ɖ{���A���v30MW�̊J���ڎw�� �S���ŏ����͔��d���Ƃ�W�J����X�Ƃ݂��̂�����A��ʎВc�@�lCoIU�ݗ�����A���}�s���Y����ѓ���100���q��Ђ̃��G�l�́A�����͔��d���Ƃ̊֓��E���k�n���ł̊g��A����ы���E�n�拤�n���ƂŘA�g����Ɣ��\�����B �����͔��d���Ƃ̉\���������Ƃɒ��������͎��Ƒ̂��\�����A�n��ł̎��Ɗg���ڎw���B�X�Ɛ��̂�����́A�S��1000�J���ȏ�̏����͔��d���n�����A���d���̊J�����z�x�[�X��1���~�߂��|�e���V�����𒊏o���Ă���Ƃ����B �X�Ƃ݂��̂����炪�������͔��d���Ƃ̊J���m�E�n�E�ƁA���}�s���Y����у��G�l�̑��z���E���͔��d���Ƃ�S���Ŏ��{����m���E�l�b�g���[�N�����p���A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�E�t�B�[�h�E�C���E�v���~�A���iFIP�j�𒆐S�Ƃ��������͔��d���Ƃ��g�傷��B���v�e��30MW��ڕW�Ɍf���A�ő�̏����͔��d�R���\�[�V�A����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���E�Y�f�́w�h��߂��x�ɒ��ʂ��Ă���H���n���T�[�`��Ђ��������{ �ߔN�A�����ł́A�w�h��߂��x�Ƃ���铮�������Ă𒆐S�ɋN���Ă���B�����ŁA���́A�������������������B�����̗���x�́A�ł����������̂́u�n�����g���v�i69.5���j�A�����Łu�C��ϓ��v�i54.7���j���������B�u�������l���v��3�����ɂƂǂ܂����B ���{�̎��g�݂�e���̓����Ɋւ��ẮA�u�č��̃p������̍ė��E�v��7�����̐l���F�m���Ă����B�����́w�h��߂��x�ɂ��ẮA�u�s���߂������g�݂͖����������邽�߁A�^���v�i62.5���j�A�u�h��߂��͎��g�݂����ʂɂȂ邽�߁A���v�i37.5���j�A�u�\�z����Ă����B�����͂Ȃ��v�i66.0���j�ƁA���܂��܂ȕ]�������炩�ɂȂ����B �܂��A��Ƃɑ��ẮA�u�����ւ̎��g�݂̑̍ق�������������ƍl���Ă���v�i62.1���j�A�u���ɔz�����Ă���悤�Ɍ��������鏤�i��L����ڂɂ��邱�Ƃ�����v�i52.0���j����ʂɏオ�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ܔ����ɔ��^���z���p�l���A�ωd������N���A �e�B�[�G�X�s�[�́A�[���Ê�̉�����2�J���ɔ��^�̑��z���p�l����ݒu���A�ғ������Ɣ��\�����B ���z���p�l���̍��v�o�͂�7.2kW�i400W/���~18���j��20kW�i400W/���~50���j��2�J���B�O�҂͔N�Ԕ��d��7857kWh�����݂ŁA�S�ʎ��Ə����B��҂͓�2��2740kWh�̌����݂ŁA��30�������Ə���A�]��͌Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�Ɋ�Â����d����BFIT�ɂ�锃�承�i��12�~/kWh�B�ܔ����Ɉ�ʓI�ȋ������p���Đݒu�����B �C�����̗��n�ł��d���Q�n��Ή���蓱�����\�ɂȂ����B ���z���p�l���A����3.0mm�̒P�����V���R���^�B�Ȃ��ɋ�������Ȑ����Z�p�u�V���O�����O�v���̗p���A120�x�܂ŋȂ�����B��ʓI�ȑ��z���p�l���̖�4����1�̏d���B����̂悤�ȋ�����̂ق��A���ʃe�[�v��p�����{�H�ɂ��Ή�����B ���i�ۏ�12�N�A���d�ۏ�25�N�A�{�H�ۏ�20�N�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���j�Z�R�Łu�ᔭ�d�v�A�Z��␅�s���̉������B���x�����d�̔r�M�Ő��Z�����B �ᔭ�d�̎��́A�~�̃j�Z�R�S�̂̉ۑ�ł���u����̕��S�̉����v�u���s���̉����v�Ɋ�^����B�ᔭ�d�́A���x���G�l���M�[�Ŕ��d����B�d�C�ʐM��w�Ƌ����Ō��Ɏ��g��ł���B ���d�@�ɂ́u�X�^�[�����O�G���W���v���g���Ă���B�X�^�[�����O�G���W���́A�V�����_�[���̃K�X���C�i�쓮���́j���O��������M�E��p���A���̑̐ϕω��Ńs�X�g�������B�����̔M���ɂ́A���z�M��o�C�I�}�X�M�Ȃlj��ΔR���Ɉˑ����Ȃ��R�����瓾��ꂽ�M�A�ቷ�̔M���ɂ͐�ŗ�₳�ꂽ�s���t�𗘗p���Ă���B �X�^�[�����O�G���W�����ł́A�₦���s���t���V�����_�[���̃w���E���Ƃ̔M������90���قǂɉ��M�����B���x�̏㏸�����s���t�́A�ϐ�ɖ��ߍ��ǂ𗬂�A���̍ۂ̔r�M�ɂ����n�����B�X�^�[�����O�G���W���͏o��7.0kW�B1���ɍő��168kWh�d�ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O�H�d�H�A500kW�����V�v���G���W���Ő��f100���^�]��B�� �O�H�d�H�G���W�����^�[�{�`���[�W���iMHIET�j�́A���d�p���V�v���G���W���ɐ��f100���̔R����p���Ē�i�o�͂ɂ��^�]��B�������Ɣ��\�����B���͌��H����ɐݒu�����A�o��500kW�N���X�̐��f��ăG���W�����d�E���ؐݔ��ɂ����ĒB�������B �G���W���A���d�@�A��@�ނ��܂ރV�X�e���S�̂��������B�G���W���̋N������A435kW�A1500��]�̒�i�o�͂܂ł̔��d�A����ђ�~����܂ł̎��ۂ̉^�p�Ɠ��l�̃V�[�P���X�ŁA��A�̓�������ׂĐ��f100���R���ň���I�ɉ^�]�ł��A�ُ펞�̕ی�@�\�Ȃǂ��L���ɋ@�\���邱�Ƃ��m�F�����B ���f��ăG���W���́A���ЂŐv�E��������6�C�����V�v���G���W���B��@�ނɂ́A���f�̔R�Đ��������Ód�C���x�̃G�l���M�[�Œ����R�Ĕ͈͂��L���Ƃ����������ɑ�����S�@�\��lj������B ����A�M�����]������S���]���������������{���A2026�N�x�ȍ~�̐��i����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���点��\���ŁA�����y���u�X�J�C�g���z�d�r��10�{�ȏ�̓d�����_���E����ϊ����� ����c��w�A������w�A�}�g��w��̋��������O���[�v�́A�n���Q�������y���u�X�J�C�g�̈ꎟ���点��\������єz���L�@�L�������q�i�L�����F���E��Ώ́j�ƌ��������@�ɂ���Đ��䂷���@�����o���A15V���̌��N�d�͂������邱�Ƃɐ��������B �L�������q�͌��w�����������A���ʕΌ�����]�����鐫�������邽�߁A���w�����ŏd�v�ȍ\���ƂȂ��Ă���B �ʏ�̑��z�d�r�̌��N�d�͂́Ap-n�ڍ��ɂ�����o���h�M���b�v�ŋK�肳��A1.1.5V���x�ɏo�͂����������B���̃G�l���M�[�ϊ������͖�32�������E�ŁA�V���R�����z�d�r�͂��łɗ��_���E�ɋ߂����x���ɓ��B���Ă���B�y���u�X�J�C�g���z�d�r���قږO�a��Ԃɂ���A���݂̌����J���ł͎�ɃR�X�g��ϋv���A�f�q�̏W�ω��ɏd�_���u����Ă���B���d���J�j�Y�������{�I�Ɍ������A�Ⴆ�o���h�M���b�v�ɂƂ��ꂸ���N�d�͂��\�ł���A���_���E����ϊ������̌��オ���҂ł���B �o�T[���oBP�v |
|
|
| ���S�ĂɍL����G�l���M�[�����ݔ��A���N��20GW�V�݂ցAGW�v���W�F�N�g�� �č��ł́A2025�N�ɓ�������锭�d���Ɨp�G�l���M�[�����ݔ��i�n���p�~�d�r�j�̗e�ʂ��A�P�N�ł̓����ʂōő�ɂȂ�Ɨ\������Ă���B �č��G�l���M�[���ǁiEIA�j�ŐV�́u�������d���Ɂv�f�[�^�ɂ��ƁA2025�N�ɁA65.7GW�̔��d�ݔ����č��̃O���b�h�i�d�͌n���ԁj�ɐV���ɐڑ�����A���Ɖ^�]���J�n����\��ł���B���̂����A�G�l���M�[�����ݔ��̓����\��ʂ͘A�n�o��19.8GW�ɒB���Ă���A����͑O�N��90%���ƂȂ�B �����_�ŁA�č��ő�K�͂̃G�l���M�[�����ݔ��́A690MW�̃��K�\�[���[�ɁA380MW�A�e��1520MWh�̃G�l���M�[�����ݔ������݂���Ă���B2025�N�ɂ́A���Ɖ^�]���J�n����\��̍ő�K�͂̃G�l���M�[�����ݔ��͏o��500MW�i0.5GW�j�ɒB����B�V���ȃv���W�F�N�g�ł́A�A�n�o��500MW�A�e��2000MWh�i2GWh�j�̃G�l���M�[�����ݔ����A�A�n�o��500MW�̃��K�\�[���[�ɕ��݂����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ăG�l����O&M�s��A2030�N�x�E1.5���~�K�͂� ���o�ς́A�����̍Đ��\�G�l���M�[�ݔ�����O&M�i�^�c�E�ێ�j�T�[�r�X�s��̒������ʂ\�����B2024�N�x�̓��s��K�͂�1��2100���~�̌����݂ŁA2030�N�x�ɂ�1��5265���~�ɒB����Ɨ\������B 2024�N�x�̎s��K�͂�ݔ��ʂł݂�ƁA�o�C�I�}�X���d�����ł��傫���A���z�����d���A���͔��d���A���͔��d���A�n���p�~�d�r�Ƒ����B�o�C�I�}�X���d���́A���̍ăG�l���d�ݔ��Ɣ�ׂĉ^�]�ێ��R�X�g���������Ƃ���A�s��S�̂ɐ�߂銄�����傫���Ƃ����B ����̒��ڎs��Ƃ��āA�n���p�~�d�r����O&M�T�[�r�X�s���������B�����̍ăG�l�����g��ɔ����A�ăG�l�d�͂̕ϓ��}������������̂��߂̒~�d�r�V�X�e���iESS�j�̏d�v�������܂�A�n���p�~�d�r�̐ڑ��_�}�����Ă���B�n���p�~�d������O&M�̃j�[�Y���g�債�A2024�N�x�͑O�N�x��Ŕ{���ƂȂ�46���~�������݁A2030�N�x�ɂ�272���~�ɒB����Ɨ\������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���g���i�E�X�g���[�W�A�t��V�X�e�����̗p�����~�d�r20�N���C�t�T�C�N��EPD�F���擾 �g���i�E�X�g���[�W�́A��^�Y�Ɨp�~�d�V�X�e���uElementa2�v�ɂ����āA�t��V�X�e�����̗p�����~�d�r�Ƃ��ċƊE�ŏ��߂�20�N���C�t�T�C�N�������i�錾�iEPD�j�F���擾�����B �{�F�́AUL Solutions�ɂ��R�����o�Ĕ��s���ꂽ�BEPD�iEnvironmental ProductDeclaration�A�����i�錾�j�Ƃ́AISO14025�Ɋ�Â����F�ł���A���i�̃��C�t�T�C�N���S�́i���ޗ����B�E�����E�A���E�g�p�E�Ǘ��E�p���E���T�C�N���j�ɂ���������ׂ��ʓI�ɕ]��������́B ����̔F�́A�G�l���M�[�����ƊE�ɂ�����t��V�X�e���Ƃ��ď��߂āA���i��20�N�Ԃɂ킽����e�����I�ɕ]���������́B�]���̃��C�t�T�C�N���]���ł́A��ɐ����E�g�p�E�p���̒i�K�ɏœ_�����Ă��Ă������A�ێ��E�Ǘ��╔�i�����������ׂɗ^����e�����l������Ă���A�����ۂ̉^�p�ɑ��������f�[�^�������B �o�T�u�d�g�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2025/3�@]�@�@�� |
|
|
| �������d�́A�Η͐Ւn�ɒ~�d���^�n���p�A�o�͂P���L�����b�g�ȏ���v�� �d�C���]���Ă��鎞�͒~�d���A�s�����͕��d����B �Đ��\�G�l���M�[�̕��y���i���i�ޒ��A�d�͂̈��苟���ɕK�v�Ȓ����͊m�ۂ�ʂ��Đ��\�G�l���M�[�̓����g��ɍv������B�~�d���͌����ł��������A���Ȃ��Ƃ���3�琢�т�1�����ɑ�������3��kWh�̓d�͂�~������e�ʂƂ����B�o�͂�1��kW�ȏ��z��B ���z���╗�͂Ȃǎ��R�R���̍ăG�l�͓V��╗���Ȃlje���ŋ������s����ɂȂ�ۑ肪����B�ăG�l�g���ڎw����ł͎��v�Ƃ̃o�����X���Ƃ�K�v������A���Ђ́u�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��ƁA�K�v�Ȓ����͂̊m�ۂ̗��ւŎ��g�݂�i�߂邱�ƂŃJ�[�{���j���[�g�����Љ�̎����ɍv���������v�Ƃ��Ă���B �o�T�u�R���V���v |
|
|
| ���O�H�d�@�A�u���d�Z���v�J���֖{���^DC�̓d�͌���100�{�� �O�H�d�@�́A�ʐM��d�C������ɒu����������d�Z���Z�p�̊J���ɗ͂�����B �f�[�^�Z���^�[���T�[�o�[�̊�Ԃł̗��p�ɂƂǂ܂��Ă�����ڑ����AGPU�i�摜�������u�j�𓋍ڂ����p�b�P�[�W�ԁA����уp�b�P�[�W���̃`�b�v�ԂւƊg��B 2030�N�ȍ~�ɓd�͌�����100�{�Ɉ����グ�����l���B ���ƋK�̖͂ڕW�Ȃǂ͖���B�f�[�^�Z���^�[�̑啝�ȏȃG�l���M�[���ƁA�v�Z�\�͌���̗�����ڎw���B�����J���헪������Ŗ��炩�ɂ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ʃp�l���̗p�̃\�[���[�J�[�|�[�g�A�������Ƃ��팸 ��a�n�E�X�H�Ƃ�100���q��Ђł���f�U�C���A�[�N�́A���ʎ���^���z���p�l���𓋍ڂ����\�[���[�J�[�|�[�g�i���ԏ�^���z�����d�ݔ��j�������B ���i�̓I�[�v���B���Ǝ{�݁E�q�ɁE�H��Ǘ���ЂȂǂł́A�Đ��\�G�l���M�[�����ӗ~�̍��܂��⏕�����x�̊g�[�Ȃǂɂ���ă\�[���[�J�[�|�[�g�̎��v�����܂��Ă���B ���������Ɩ��E�Y�Ǝ{�����̐��i�B���ʎ���^�p�l���̗̍p�ɂ�艮����̒��˓��������łȂ��A�H�ʂܑ̕��d�l�ɂ���Ă͔��ˌ���������d�ł��邽�߁A���ӂɍ��w�r�����Ȃ��G���A��ݒu�\�ʐς���r�I�����H��⏤�Ǝ{�݂ȂǂɓK����B���̓X�`�[���A���̓A���~�j�E�����̃n�C�u���b�h�\�����̗p�����B���C���A�b�v�́A���ԑ䐔4��p�i�x��6�{�A��i�o��13.5kW�j�A6��p�i8�{�A20.3kW�j�A8��p�i10�{�A27.0kW�j�A10��p�i12�{�A33.8kW�j�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�^�[�R�C�Y���f�v�x���`���[�A�o���Ə��D�O��n���o���^���^������G�}�Ő��f�ƌő̒Y�f�� �o���́A�u�^�[�R�C�Y���f�v�̐����Z�p���J������t�B�������h�̃x���`���[��ƃn�C�J�}�C�g�����{������O�Ҋ��������̈ꕔ���������Ɣ��\�����B�܂��A���D�O�䂪100���o������MOLPLUS�������A�o�������肵���Ɣ��\�����B �u�^�[�R�C�Y���f�v�Ƃ́A�Y�����f�����w�������Đ��f�ƌő̒Y�f�ɕϊ������@�Ő������ꂽ���f�ŁA��������CO2�������A�Y�f���ő̂̂��߉���E�����ɂ��L���Ȃǂ̗��_�����蒍�ڂ����B �n�C�J�}�C�g�́A2020�N�ɑn�Ƃ��A�V�R�K�X��o�C�I�K�X�̎听���ł��郁�^����M�������ă^�[�R�C�Y���f�ƌő̒Y�f������Z�p��ۗL����B�Ǝ��J���̐G�}�Z�p�ɂ��A�d�C�����Ŏg�p����d�͂�13���̒�G�l���M�[�Ő��f���\�B�n�C�J�}�C�g�́A�N�Y2000t�i��2880Nm3/h�j�̃^�[�R�C�Y���f�Y����v��ŁA2025�N�����̉ғ���ڎw���Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p�H�p��100���̍��YSAF��K�͐��������H�A�R�X���Ζ��獑���� �R�X���Ζ��A�����z�[���f�B���O�X�A���{�C���^�[�i�V���i���ASAFFAIRE SKY ENERGY��4�Ђ́A�p�H�p���������Ƃ����o�C�I�W�F�b�g�R���Ƃ��āA�������ƂȂ鍑�YSAF�i�����\�ȍq��R���j�̐����ݔ������H�B1����莎�^�]���J�n���A4�����ɃG�A���C���ւ�SAF�������J�n����B ���̐ݔ��́A�R�X���Ζ��䐻�������ɂĊ��H�����B���YSAF�̑�K�͐�����ڎw���A�����Ŕ�������p�H�p��100���݂̂������Ƃ����N�Ԗ�3���L�����b�g����SAF�̍��������Ɏ��g�ށB����SAF�́A���ۓI�Ȏ����\���F�ł���ISCCCORSIA�F���擾���Ă���B���̎��Ƃ́A�e�Ђ̒m���E�m�E�n�E�����W���Ĉ��S�E����̍��YSAF���������Ă����B SAFFAIRE SKY ENERGY�̓j�[�gSAF�i�����R��100���j�������A�R�X���Ζ��͍���SAF�����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���ϐ����w�^CO2����|���}�[�����AIHI��CO2������u �ϐ����w�́A�r�K�XCO2����������u�����ACCUS�iCO2�̕����E����E���p�j�̎��؎������s���Ă���B�������CO2�́A�ϐ����w���J������90���ȏ�̎����ň�_���Y�f�iCO�j�ɕϊ�����P�~�J�����[�s���O�����Z�p�ƁACO����F�������������������ɐ��Y����Z�p�Ȃǂɂ��ACO2����|���}�[�����֓]������Z�p���Ɏg�p�����B 2025�N�ɓ��{�݂���r�o�����R�Ĕr�K�X����CO�ϊ����\�Ƃ���O�����v���Z�X�̃v�����g�𒅍H�B2026�N�x�ȍ~�A�R�Ĕr�K�X����CO2��Z�k���A�P�~�J�����[�s���O�����Z�p�A�F�����������̐��Y�Z�p�ȂǂƗZ�����������Y�v���Z�X����������B���̌�A�X�P�[���A�b�v���������A2030�N�ɔN��33ton��CO2�𗘗p���������J�n����\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���J�i�f�r�A-AIST���������ACO2���璼�ڃO���[��LPG������ �J�i�f�r�A�ƎY�����́A�V���ɊJ�������G�}�ƃv���Z�X��p���āACO2���璼�ڃO���[��LPG����������Z�p���J�������B ���t�ɂ͔N�Y3�g���`4�g���K�͂̎��؎������J�n����Ƃ����B ���\�����Z�p�́A�Đ��\�G�l���M�[�R���̃O���[�����f�ƍH��Ȃǂ���r�o�����CO2��V�G�}��p���āA�ሳ�������ŃO���[��LPG�ɕϊ�������́BLPG�͎Y�Ƃ�ƒ�����̔R���Ƃ��č������v������A���R�ЊQ���ɐv���ɕ����E���p�ł���Ƃ����������b�g��L���Ă���B�������ACO2���璼��LPG����������Z�p�͉ۑ肪�����A���p���E���Ɖ�������ƍl�����Ă����B�����ŁA�J�i�f�r�A�͊��ɓW�J���Ă��鍇�����^�����Ƃ̃m�E�n�E�Ɨv�f�Z�p����ɁA�ۑ�����Ɏ��g��ł����B �O���[��LPG�̎s���2035�N�܂ł�200��ton�i�J�i�f�r�A���ׁj�B�O���[��LPG�̍����Z�p���m�����邱�ƂŁA�J�[�{�����T�C�N���^LPG�������u�̎Љ�����Ȃǂ����҂����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���G�l���A�V�݃f�[�^�Z���^�[�ɏȃG�l��^����`������ �f�[�^�ʐM�ʂ̑���ɔ����A����d�͂��}������f�[�^�Z���^�[�̃G�l���M�[���������P���邽�߁A�����G�l���M�[�����A�V���ȏȃG�l�[�u���u����B �N�ԃG�l���M�[�����1500�L�����b�g���ȏ�i�������Z�j�̃f�[�^�Z���^�[���Ǝ҂��A���K�͈ȏ�̃f�[�^�Z���^�[��V�݂���ꍇ���ΏۂƂȂ�B�f�[�^�Z���^�[�̉ғ���������Ԃ��o����ɁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��G�l���M�[��������̊�uPUE�v�iPower usageeffectiveness�F�i�f�[�^�Z���^�[�S�̂̏���d�́j���iIT�@��̏���d�́j�j�̒l��ݒ肷����������������B �G�l���́A���������G�l���M�[������ȃG�l���M�[���ψ���ŁA��������[�u�̈Ă���������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u���f�v�j�i��...�G�}1���Ō����������A�m�[�x���܋����{�l�����҂̋Ɛ� ���f�͔R���Ƃ��Ďg���邾���łȂ��A��_���Y�f�iCO2�j�Ɣ���������v���X�`�b�N���ł���B�Y�f�����ɔr�o�����A�J��Ԃ��g�����Ƃ��\���B ���̐��f�̉��i�j����N�����Ɗ��҂����̂����G�}�B���ƈꐬ�M�B��w���ʓ��C�����̓m�[�x���܋��Ƃ����p������ЃN�����x�C�g��2024�N�̈��p�h�_�܂���܂����B���܂̓m�[�x���܂̑O����ɂ��ʒu�t������B���������G�}�͎��p���܂ł��Ɛ����̂Ƃ���܂ł��Ă���B ���G�}�����͌��̋z���g�����L���A���̕������������߂�B���̓�𗼗�������K�v������B���z���̂��ׂĂ̔g����G�}���z���ł���A���̗��p���������シ��B���G�l���M�[�Ő��������I�ɕ����ł���ΐ��Y�������シ��B�O�҂͌��G�}�̕�ށA��҂͏��G�}���@�\��S���B �����Đ������Ď_�f����鏕�G�}�ƁA���f����鏕�G�}�͕������قȂ�B���̂��ߕ�ނƓ�̏��G�}�����ꂼ��J������Ă����B���Ƌ����͂������ꗱ�̐G�}�Ŏ��������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���V�̈�u���d�Z���v�ɒ��͂��钆���A�������ŕč����� �������A�����̂ƌ��ɂ��M���`������̉�����u���d�Z���i�V���R���t�H�g�j�N�X�j�v�̌����J�������������Ă���B������̍��ʓ����o�萔�ł�2022�N�ȍ~�A���E��ɖ��o���B ���d�Z���ɂ����āA�e�Ђ����̂������̂��AIC�`�b�v�₻�̎��ӂł̃f�[�^�`�����A�d�C�łȂ����ɒS�킹��Z�p�̊J�����B���ɂ��f�[�^�`���͍����ŁA�����ɂ��d�C�`���̂悤�ȑ��������Ȃ��Ƃ������_������B�d�͎��v���}������AI�i�l�H�m�\�j�f�[�^�Z���^�[�����̔����̂Ŋ��p�ł���A����d�͂̑啝�ȍ팸�ɂȂ�����B �u���d�Z���́A�����̎Y�Ƃ����ꂩ�畢���B�č��͌��݂��̋����ɏ����Ă͂��Ȃ��v�ƕč��A�M���@�c��Œ������ʈψ���ψ����͌x�����Ă���B ���d�Z������̍��ʓ����o�萔�ł́A�č������N�Ƒ����Ă����B�ω����K�ꂽ�̂�2017�N���뒆�����o�萔���}���������B2023�N�ɂ͕č���2�{�ȏ�ƂȂ��800���̏o������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���t�����X�ŁA��K�͂ȓV�R���f�i�z���C�g���f�j�z������ 1987�N�Ƀ}�����a���Ő���ˌ@���ƒ��ɓV�R���f���������ꂽ���A�p�B�ɂȂ��Ă����B2012�N����J�i�_Hydroma�Ђ��̌@���J�n�B���f�ڔR�Ă��Ĕ��d�����d�C���ߗׂ̑�����������v���W�F�N�g��i�߂Ă���B �t�����X�k�����̃O�����E�e�X�g�̒n���ɑ�K�͂ȓV�R���f�i�z���C�g���f�j�z�����������ꂽ�B���薄���ʂ�3400���g���B����̍z���ɂ����āA�V�R���f�̖����ʂ���̓I�ɐ���ł����̂͏��߂Ă��B �̌@�Ɛ����ɂ�鐅�f�����R�X�g���Z��1�`2���[��/kg�B����́A���^���K�X�R���̐��f�i�O���[���f�j����2�{�قǍ������A�Đ��\�G�l���M�[�R���̐��f�i�O���[�����f�j��1/3�`1/4���x�Ɨ\���B ���ۂ̐��Y�́A����̍̌@�Z�p�̐i�W����������B�O�����E�e�X�g�ł́A�n��3km�ɑ��݂���n�����ɁA30mg/L�ippm�j�Ƃ������Z�x�̐��f���n������ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E�ŃO���[���A�����j�A�v��}�� �Đ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂Ő���d�C�����i���d���j���đ���u�O���[�����f�v�́A���B�𒆐S�ɔ��ɐ������̐��Y�v���W�F�N�g���i�߂��Ă���B����A���̃O���[�����f����ɍ�������u�O���[���A�����j�A�v�����Y�v�悪���E�ő����n�߂� ���̑�����2030�N����ɔN��100���g���O��A��^�v���W�F�N�g�ł͓�2000���g���̐��Y�K�͂�z�肵�Ă���B���Ȃ݂ɍŋ߂̓��{�̃A�����j�A�̎��v�ʂ͔N��100���g���O��B�O���[���A�����j�A���Y�v��̋K�͂������ɑ傫������������B ���Y�K�͂̍��v�͔N�Ԗ�5600���g���i0.56���g���j�B���E�̃A�����j�A�̎��v�ʓ���1.5���g���O���4����ɒB����B �O���[���A�����j�A�̐��Y�v��}���̔w�i�́i1�j�����̉��w�엿��CO2�t���[���A�i2�j�^���A�����ۊǂ�����Ȑ��f�̑�փL�����A�B���̂܂�CO2�t���[�R���Ƃ��Ă̎��v�̍��܂肪����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �������A�X�}�[�g�ψ���̊J���̃X�^�[�g�A�b�v��ƁuIONATE�v�֏o�� �Y�ƕ���̑��z�d�����̑����ƁA���z�d�ݔ��̌������v�̍��܂���A���E�̕ψ���s���2022�N��450���ăh������A2030�N�ɂ�642���ăh���Ɋg�傷��ƌ����܂�Ă���B�����āA�Đ��\�G�l���M�[���d�́A�V���G�߂Ȃǂɂ��o�͕ϓ����傫�����Ƃ���A�d�͌n���̈��萫��ۂ��߂̃X�}�[�g�ψ���ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B IONATE�́A�X�}�[�g�ψ���HIT�iHybrid IntelligentTransformer�j��AI�Ή��X�}�[�g�O���b�h�d�͊Ď��Ǘ��V�X�e�������p���̃X�^�[�g�A�b�v��Ƃ��B �]���^�ψ��킪�d���ϊ��@�\�ɓ������Ă���̂ɑ��AHIT�́A�Ǝ��v�ɂ��S�S�z�u��@��\�����̗p���邱�ƂŁA���̊O������@��ɗ��邱�ƂȂ��e��d���E���g���E�͗��̃��A���^�C��������s�����Ƃ��\���B����ɂ��]���^�ψ���ɔ�ׂēd�͑����̌y���A���z�d�V�X�e���^�p�R�X�g�̒ጸ�A�ȃX�y�[�X���������߂�B �o�T�u�����v |
|
|
| ���@�@[�@2025/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���ϐ����w�A�y���u�X�J�C�g�ʎY��2027�N100MW�������C���ғ� �ϐ����w�́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗ʎY�����J�n����Ɣ��\�����B2027�N��100MW�������C�����ғ����ݔ��������s���B �ʎY���Ɍ����ẮA�V���[�v�̖{�ЍH��̌�����d���ݔ��A��p�ݔ��Ȃǂ�����A�Ւn�Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r�����ݔ������A�v�E�����E�̔����s���B�������z��900���~�i�⏕���܂ށj�K�͂ƂȂ錩���݂��B���Ɖ^�c�́A1��6���ɗ����グ��V��Ђ̐ϐ��\�[���[�t�B�������S���B���{����1���~�ŁA�ϐ����w��86���A���{����������s��14�����o������B����A2024�N�x�uGX�T�v���C�`�F�[���\�z�x�����Ɓv�ɍ̑����ꂽ�B ���Ђ́A�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊����i�Ɍ��������g�݂ō̑����ꂽ�B�⏕���̑��z��1572��5000���~�B����́A�C�O�W�J������ɒi�K�I�ȑ����������s���A2030�N��GW���������C���̍\�z��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�H�����Ȃ�4�ЁA��DAC�V���ɏo���^�ΊD�Η��p�ʼn�������� �O�H�����A�O�䕨�Y�A���D�O��A���{�q��́A��C����CO2�ډ������uDAC�i�_�C���N�g�E�G�A�E�L���v�`���[�j�v�Ɏ��g�ޕăG�A���[���E�J�[�{���E�e�N�m���W�[�Y�ɏo�������Ɣ��\�����B���Ђ͐ΊD�i�Y�_�J���V�E���j�𗘗p����DAC�v�����g�����N11�����瑀�ƁB��������ƃv�����g���������₵�Ă������Ƃ���A����Ȃ鐬���������܂�Ă���B �G�A���[���͍���A���{���4�Ђɉ����A�ăN�I���^���E�C�m�x�[�V�����E�t�@���h��ƃV�[�����X�E�t�B�i���V�����E�T�[�r�X�Ȃǂ��瑍�z1��4�疜�h���i��210���~�j�̎������B���s�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����K�X�A�X���[�g�����ɑ��z���^�@�l�����T�[�r�X�g�[ �����K�X�́A���z���p�l���̓��ڂ�����Ƃ����u�X���[�g�v���g���������ɁA���^�Ōy�ʂ̑��z���p�l����ݒu����V�H�@���J�������Ɣ��\�����B �X���[�g�͍H��ȂǂōL���̗p����鉮���ނŁA�ωd��{�H�̈��S�ʂƂ������ϓ_���瑾�z���p�l���̓��ڂɕs�����������B���K�X�͐V�H�@�����A�@�l�����ɑ��z����ݒu����T�[�r�X�̑Ώۂ��X���[�g�̉����������v�Ƃɂ��L����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��JR�����{�X�^�[�g�A�b�v��A�ϐᔭ�d�̎��ؓd�͂͏��Ǝ{�݂Ŋ��p JR�����{�X�^�[�g�A�b�v�́AJR�����{�X���ƊJ������уt�H���e�ƁA�X�s���ɂ��鏤�Ǝ{�݂Őϐᔭ�d�ɂ��Z��V�X�e���̎��؎������s�����Ƃ\�����B �ϐᔭ�d�́A�X�^�[�����O�G���W�������p�������d�@��p���āA���Z�������d���s���B�O������V�����_�[�����M�E��p���A�����̋C�̂�c���E���k�����ăs�X�g�������d�g�݂��B �M���Ɨ␅�̉��x���ɂ��A�ő��1kW�̔��d���\�B�]���̉��ΔR����p�����Z����R�X�g���������A�ق��̍ăG�l�Ɣ�ׂĂ������I�ɔ��d�ł���Ƃ����B���ł́AJR�����{�X���ƊJ�����^�c���鏤�Ǝ{�݁uA-FACTORY�v�ŁA�ϐᔭ�d��p�����~�n���̗Z����s���A�l���R�X�g��v���Ă�������̎�ԉ����ɒ��ށB �Ȃ��A�ϐ�őn�o�����d�͂́A2025�N2��2���܂ł̊ԂɊJ�Â����C���~�l�[�V�����C�x���g�ɂ����铔�U�̈ꕔ�̓d�͂Ɏg�p���A�n��̖��͔��M�ɖ𗧂Ă�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����p���ڎw���u�F�����z�����d�v�q��@���瑗�d������������� ������̈ϑ��ł��̍\�z��i�߂Ă���u�F���V�X�e���J�����p���i�@�\�v�́A���쌧�z�K�s�̍�����JAXA���w�̌����҂ȂǂƋ����Œ������̑��d���������߂čs�����B �����ł́A���x7000���[�g�����s����q��@�̋@�̂ɐݒu�������d�@����n��13�����ɐݒu�������悻10�Z���`�l���̑��葕�u�Ɍ����ēd�g���Ǝ˂��A���m�Ɏ�M�ł��邩�������B �q��@������ʉ߂���ƁA������̑��葕�u�ł��d�g�𐳊m�Ɏ�M�������Ƃ������\�����o��������͐������܂����B������Η��N�x�ɂ��F������̑��d�������s����\�肾�B�u�F�����z�����d�v�́A���x3��6000�L���̉F����ԂɐÎ~���������z���p�l���Ŕ��d���s���A�d�C��d�g�ɕϊ����Ēn��ɑ���\�z�ŁA2045�N�ȍ~�̎��p����ڎw���Ă���B �o�T�uNHK�j���[�X�v |
|
|
| �����ނ̗͂Łu�M�������T�C�N�����v����...���{���X�^�[�g�A�b�v�A�K���f���A�̐��E�헪 �K���f���A�����ڂ����̂��A10���N�O����n����ɑ��݂��闰�_������g���u�K���f�B�G���A�v���B ���̑��ނ͉���n�тȂǂ̍����E���_���E���Z�xCO2�Ƃ������ߍ��Ȋ��Ő����ł�����ٓI�Ȑ����͂����B���̓����ɂ��A�Y�ƃ��x���ł̔|�{�����������A����ɂ킽�镪��ł̉��p�����҂���Ă���B �K���f���A�́A���̃K���f�B�G���A�̓������������A���ɓs�s�z�R�̃��T�C�N��������ɗ͂����Ă���B�s�s�z�R�Ƃ́A�g�p�ςݓd�q�@���Ɠd�Ȃǂ���M������������A�ė��p����T�O���w���B �����œ��Ђ��J�������̂��A�K���f�B�G���A�R���̊v�V�I�ȍ����\�z���܂��B���̐��i���g���A�]���̋Z�p�ł͉�������������Z�x�����̗n�t����������I�ɋM����������ł���B�܂��V�R�R���̂��߁A�����̃C�I�������z���܂Ɣ�r���Ċ����ׂ��Ⴂ�Ƃ������_�����B �o�T�u�j���[�Y�E�B�[�N�v |
|
|
| �������d�̓~���C�Y�A�{���s�E�K��쒬�ł��ӂ邳�Ɣ[�łŒn�Y�ăG�l�d�C��� �����d�̓~���C�Y�́A���{���s�ƗK��S�K��쒬�ւ̂ӂ邳�Ɣ[�ł̕ԗ�i�Ƃ��āA�s���E�����Œ����d�͂��ۗL�E�^�]���鐅�͔��d�������p���������̎Y�uCO2�t���[�łv�̒��J�n�����B �u�{���s�YCO2�t���[�łv�A�u�K��쒬�YCO2�t���[�łv�́A���͔��d���Ŕ��d���ꂽCO2�t���[�̓d�C���A�u�ӂ邳�Ɣ[�Ł~Green�łi���́j�v��ʂ��āA�ӂ邳�Ɣ[�ł̕ԗ�i�Ƃ��Ē���B�����ڋq�́A���̃��j���[�ɂ��A�z1���~�ɂ��A�ƒ�Ŏg���d�C�̂���150kWh��CO2�t���[������ƂƂ��ɁA����2500�~��d�C�����̎x�����ɏ[���ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����7���G�l���M�[��{�v��A�u���z���E22�`29���v�ōő�d���� �o�ώY�ƏȂ́A�L���҉�c�i���������G�l���M�[������E��{�������ȉ�j���J�Â��A����̃G�l���M�[����̕��������߂鎟���i��7���j�G�l���M�[��{�v��̌��Ă����\�����B�œ_�ƂȂ��Ă���2040�N�x�ɂ�����d���\���̌��ʂ��i�ڕW�j�́A�Đ��\�G�l���M�[4�`5���A�Η�3�`4���A���q��2�����x�ƂȂ����B ���߂čăG�l���d���\���̒��ōő�̓d���ƂȂ����B �d���\���ɂ�����ăG�l�i4�`5���j�̓���́A���z��22�`29���A����4�`8���A����8�`10���A�n�M1�`2���A�o�C�I�}�X5�`6���ƂȂ����B���z���̋K�͂�200�`250GW�ɂȂ�ƌ�����B ���z����22�`29���Ƃ������ʂ��́A�P�Ƃ̓d���Ƃ��Ă�������2�����x�������Ă���A���z�����A���{�̍ő�d���ɖ��o�邱�Ƃ��Ӗ�����B�ڕW��B������ɂ́A����15�N�ŁA���݂̖�3�{�ɂ��邱�ƂɂȂ�B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�̃V�F�A�́A15���O����߂�z��ɂȂ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����l�s�A1000�˂ɐ����X�}�[�g���[�^�[�����������A���dPG�Ƌ������� ���l�s�́A�����d�̓p���[�O���b�h�ƘA�g���A�����X�}�[�g���[�^�[�����Ɍ������Z�p�����s���Ŏ��{����Ɣ��\�����B���łɃX�}�[�g���[�^�[�����Ă���d�͒ʐM�l�b�g���[�N�����p���A�ʐM�R�X�g�̍팸�⑽�l�Ȋ����ł̒ʐM���萫��������B ���p�҂́A���i�̎g�p���ʂ������ɂ킩��ߐ���R���E�̏�Ȃǂ̑��������ɖ𗧂Ă���B�����ǂƂ��Ă��A�ЊQ���̒f���G���A�̓���⌟�j�[�̃y�[�p�[���X���A���n�K��̋@��Ȃ��Ȃ邱�ƂŁACO2�팸���ʂ����҂����B ����̋������j�ł́A���ߎw��s�s�̎��g�݂Ƃ��Ă͍ő�K�͂ƂȂ��1000�˂�ΏۂɁA�����X�}�[�g���[�^�[�ւ̎��ւ������{���������j���s���B�Ȃ��A���ʂ̊Ԃ́A����̌��j���ɂ��K�⌟�j�����p����Ƃ��Ă���B����2025�N10���J�n�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r�ŕϊ�����29���A����Ȃǃ^���f���^�� ���s��w�̌����O���[�v�́A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�ȂǂƂ̋��������ɂ��A�X�Y���܂�Sn-Pb�i�X�Y�E���j�n�y���u�X�J�C�g�����̂̊E�ʍ\������@���J�����A�I�[���y���u�X�J�C�g�̃^���f���i���ڍ��j�^���z�d�r�̍����\�������������B �t�F�j���A���j����Y���܂ɗp�����P�ڍ��A2�ڍ��A3�ڍ��̊e�f�o�C�X�ŁA���ꂼ����d�ϊ�����23.9���A29.7���A28.7���̑��z�d�r���쐻�ł����B�܂��A�����p���̍���1cm2�T�C�Y��2�ڍ������3�ڍ��f�o�C�X���d�ϊ�����28.4����ꂽ�B����ɍœK�����邱�ƂŁA3�ڍ��Z����34.4���܂Ō���\�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B ����̌������ʂ́A�I�[���y���u�X�J�C�g�̑��ڍ��^���z�d�r�̃x���`�}�[�N�ƂȂ���̂ł���B����A���s��w���̃x���`���[��Ƃł���G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�ɂ��Z�p�ړ]���A�����\�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��p���Ɍ����������J����W�J���Ă����\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��GHG�팸�A35�N�x60�����E40�N�x73�������{���ڕW�Ă�� �o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ́A�n�����g����v��̌��Ă��Ƃ�܂Ƃ߂��B�V���ȍ팸�ڕW�Ƃ��āAGHG�r�o�ʂ�2013�N�x���2035�N�x��60�����A2040�N�x��73�����Ƃ���Ă������ꂽ�B ����AGHG�r�o�ʍ팸�ڕW�ƕ����āA2040�N�x�ɂ����镔��ʂ̍팸�ڕW�̓�������\�����B�Y�ƕ����57�`61���i2030�N�x�ڕW��38�����j�A���Ɗ����ȂNjƖ����̑������74�`83���i��51���j�A�ƒ땔���71�`81�����i��66�����j�A�^�A�����64�`82�����i��35�����j�A���d�Ȃǂ̃G�l���M�[�]�������81�`91�����i��47�����j�ƂȂ����B �ԃN���W�b�g���x�iJCM�j�́A�����A�g��2040�N�x�܂ł̗ݐς�2���g����CO2�r�o�팸�E�z���ʂ�ڎw�����ƂƂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I����5�ЁA���H�H�i�Ɋւ���CFP�Z����{�֔_���Ȏ��Ƃ̈�� �_�ѐ��Y�Ȃ́A2024�N�x�̉��H�H�i�Ɋւ���J�[�{���t�b�g�v�����g�iCFP�j�̎Z��������{����Ɣ��\�����B�Ώۂ́A�����˂萻�i�E�g�}�g���H�i�E�������E�Ă݂��E������������5�i�ځB�C�I���i��t����t�s�j�Ȃ�5�Ђ��Q�悷��B���Ԃ́A2024�N12������2025�N2���܂ŁB ���Ȃ́A�t�[�h�T�v���C�`�F�[���ɂ�����E�Y�f���́u�����鉻�v�Ɍ����A�t�[�h�T�v���C�`�F�[���S�̂ł̒E�Y�f���̎��H��A������i�߂邽�ߊ����ŐH�i�Y�Ƃɂ�������g�݂ɂ��ċc�_���Ă����B 2023�N�x�́A���H�H�i���ʂ�CFP�Z��K�C�h�Ă̑Ó����̊m�F�A�ۑ�̒��o�̂��߂̎����s���A2024�N8���ɂ͎Z��K�C�h�ĂƎ��،��ʂ����\�����B���N�x�́A���L�����Ǝ҂����g�݂₷���Z��K�C�h�Ƃ��邽�߁A��ɋ�����5�i�ڂɂ��āA���i�̔̔����Ɉ�̕s���Ȃ��̂��܂ތ��ޗ����B�i�K����p���E���T�C�N���i�K�܂ł�Ώ۔͈͂ɁACFP�Z����s���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���̈�ق̋����Ɍ�t���ЊQ���̔��@�\�����A���ȏ� �����Ȋw�Ȃ́A�ЊQ���ɔ��ƂȂ���������w�Z�̑̈�قɂ��āA�����鎩���̂ւ̓����t����V�݂���B �f�M���\�̊m�ۂ�v���ɂ��A�֘A�H�����܂߂���p��2����1��⏕�B�S���ōЊQ���p�����钆�A��g�[�ݔ��̓�����i�߁A���̋@�\����������B2024�N�x��\�Z�ĂɊ֘A�o��779���~���v�サ���B �w�Z�ւ̋ݒu�������ẮA�������ΏۂɊ܂߂������̌�t���Ŏx�����Ă������A�̈�قɓ������������t����ʘg�őn�݂��邱�ƂŐ���������������B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���@�@[�@2025/1�@]�@�@�� |
|
|
| ��NTT�f�[�^�AAI��p�����œK���T�[�r�X���r���Ŏ��ؓs�x������ NTT�f�[�^�́AAI�Ŏ����I�ɋ@����œK������uAI�œK���T�[�r�X�v�����p���āA�����S�̂̃G�l���M�[�œK����ڎw�����g�݂��J�n����Ɣ��\�����B �s�����Ə��r���̔M���E�̏���G�l���M�[�̍팸��ڎw���B�uAI�œK���T�[�r�X�v�ł́A�����ɉe����^��������C���v�b�g�Ƃ��āAAI�Ɋw�K�����邱�ƂŁA�����̎����\���ɉ������������������B���̓����Ƃ��āA��K�͂ȓ����s�v�ŁA���K����S�ۂ��Ȃ���A�����̃G�l���M�[����ʂ��팸���A�����Ό��ʂ������߂�ȃG�l�ł��邱�Ƃ������Ă���B ��̓I�ɂ́A�����̕ω��𖢑R�ɖh���t�B�[�h�t�H���[�h�^�̋���i�\������j�ɂ��A���K����ۂ��G�l���M�[���ő�50���팸����B�܂��A���p���̍���AI���f���A�R���p�N�g�Ȑl���Z���T�[�A�N���E�h�^�̃T�[�r�X�v�ɂ��A��K�͂ȋ@�퓱�����s�v�̂��߁A���݂̃r���ł�3�������x�̏������Ԃœ����ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���W���p���G���W���A���E���E�D���p�A�����j�A�R���G���W���̎����^�]���� �W���p���G���W���R�[�|���[�V�����́A���E���ƂȂ��^�ᑬ2�X�g���[�N�A�����j�A�R���G���W���̎����^�]�����������Ɣ��\�����B���̎����^�]�́ANEDO�́u�O���[���C�m�x�[�V����������Ɓ^������D���̊J���v�v���W�F�N�g�̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�B ����̎����ł́A�����A�����j�A���ė��ɂ��^�]�����{���ꂽ���A���g���W���̍������_�����f�iN2O�j�̔�����Ⴂ���x���ɗ}���ł��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ����B���̂ق��A�A�����j�A�R�������ݔ��Ȃǎ��ӑ��u�̋@�\�ƈ��S����e�@��̃����e�i���X���A�d���ƃA�����j�A�̔R����ւ��V�[�P���X�Ȃǂ̌��������B�A�����j�A�̈��S�Ȏ�舵���ɂ��āA�����̐��ʂ��B���݂́A�����̐��ʂ���ɁA���ۂ̑D���ɓ��ڂ���A�����j�A�R���t���X�P�[���G���W�������@�̐�����i�߂Ă���A2025�N4���ɂ́A���ۂ̑D���ɓ��ڂ���G���W���̎��^�]���J�n����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���E�Y�f���̐�D�ƂȂ邩�Y�Ɨp�q�[�g�|���v�ւ̊��ҁA���_�����f ���ۃG�l���M�[�@�ւ�2022�N�Ɍ��J�������|�[�g�uThe Futureof HeatPumps�v�ł́A�Y�Ɨp�q�[�g�|���v�͂��ł�160�������Ⴂ���x�т̔M���������邱�Ƃ��\�ŁA�H�i�E���w�ȂǎY�Ƃ𒆐S�ɔr�o�팸���\�ł���B����A�������x�т���M�\�͂��g�傷�錩���݂ƌ��y����Ă���B �����b�g�����҂���Ă���ɂ��ւ�炸�A���y��W������ꍇ������B����́u�ȃG�l���M�[�M���b�v�v�ƌĂ�A�O�q�́uThe Futureof HeatPumps�v�ŁA���v�ʂł́A�R�X�g��A���s���ȂǁB�����ʂł́A�����\�͂�T�v���C�`�F�[���ɂ��Č��y����Ă���B ������2021�N�ɐ����ƂɃA���P�[�g�����{�����Ƃ���A�ł��������������̂��u�ݔ���p�������v���Ƃ������B��R�X�g�ʂł́A�u�lj��ݒu�ꏊ���Ȃ��v�Ƃ������ł����������B������Ƃł́A�d�C�𗘗p����M�����ݔ��̔F�m�x���Ⴉ�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h���h��^�̑��z�����d�J���֗������ƂƖk�C�����R�d�͂���g ���H�ɐݒu����h���Ȃǂ��J���������闝�����ƂƍăG�l�֘A�̊����肪����k�C�����R�d�͂́A�h���h����ꂽ���z�����d��쐶������Q��������鐻�i�̊J���ȂǂŋƖ���g�_������B ���R�ЊQ�ɋ����V���ȑ��z�����d�V�X�e���̊J���ŁA�k�C�������łȂ������̑��n���C�O�ւ̎��ƓW�J����������B���Ђɂ��ƁA�������Ƃ̋��݂ł��铹�H�W�̖h���h���A�쐶���������i�Ȃǂ̊J���Z�p���A�k�C�����R�d�͂�����n�тł���k�C���Ői�߂Ă�����ɋ����������̑��z�����d�V�X�e���ȂǂƗZ���B���R�d�͂�2023�N12������k�C���̗��_�w����w�Ɛ����^���z���p�l���̋���������i�߂Ă����B �k�C���ł͑厩�R���������z���A���́A�o�C�I�}�X�Ȃǂ̍ăG�l��p�����d���J�����i�ވ���A�V�J��q�O�}�Ȃǖ쐶�����ɂ��{�ݐݔ���_�앨�̔�Q���[�������Ă���B����̋Ɩ���g���@�ɁA���Ђ͂��������Љ�ۑ�������ʼn������邱�Ƃ�ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�HUFJ��A�G�l�b�g�̏ȃG�l�x���T�[�r�X�����S��200�{�݂ʼn^�p �G�l�b�g�ƎO�HUFJ��s�́A���~����O�HUFJ��s�̑S����200�{�݂ɂ����āA�uEnneteye�i�G�l�b�g�A�C�j�v�����p�����ȃG�l�������J�n����B�e�{�݂̓d�C�g�p�������BAI�ɂ��f�f���ʂ���A���ʓI�ȏȃG�l�A�N�V�����𑣂��B �uEnneteye�v�́A�e�{�݂̓d�̓f�[�^�������I�Ɏ��W���AAI�E�f�[�^���͂ɂ��A�d�͎g�p�̉������A�e�{�B�ȃG�l�|�e���V�����̒��o��ȃG�l��Ă��s���T�[�r�X�B���T�[�r�X�����邱�ƂŁA���Ƃ�h������]���^�������A�����I�ȏȃG�l���͂Ƒs���Ȃ��G�l���M�[�g�p����r�I���Ȃ��c�ƓX�܂ɂ����Ă��A�����I�����ʓI�ȏȃG�l�����҂ł���Ƃ����B ����̉^�p�J�n�Ɍ����ẮA�O�HUFJ��s�̈ꕔ�{�݂�1�N�ԁAEnneteye�̎����^�p�����{���A�~�G����9���A�ċG����7���̓d�C�g�p�ʍ팸��B�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������d�́A�������j�_��30�����Ɂ^LP�K�X���S�Ɏg�� �����d�͂́A�X�}�[�g���[�^�[�ʐM�Ԃɂ�鎩�����j�T�[�r�X�̌_�������30�����ɓ��B�����Ɩ��炩�ɂ����B ���T�[�r�X��2021�N4���A�K�X�E�������ƎҌ����ɒ��J�n�B2023�N2���ɂ͓��T�[�r�X�̐�Ɖ�Ђ�ݗ����ALP�K�X�𒆐S�ɏ����Ɏ�L���Ă����B ��������ł͒����G���A��2����ɓ�����31�̎����̂ɃT�[�r�X����B���コ��Ɋg�債�A�����Ɍ_�����100�����A100�����̂ւ̒�ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����z���E���T�C�N�����x�A�C�O�p�l���͗A���Ǝ҂���p���S �o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ́A���z���p�l���̔p���E���T�C�N�����x�̋`�����Ɋւ���L���҉�c�̂��J�Â��A���Ă�������p���S�ɂ��Ď����LjĂ�����A���x�̑�g���ł܂����B �ő�̏œ_�������A�p�p�l����f�ނ��Ƃɕ�����������u�Ď�������p�v�����ꂪ���S����̂��A�ɂ��ẮA���Y�p�l���̏ꍇ�͐����Ǝ҂Ƃ��邪�A�C�O�Ő��Y�����p�l���ɂ��Ă͗A���Ǝ҂���p�S����Ƃ����B���ꂼ��A�������A�A�����ɑ�O�ҋ@�ւɎx�����B���������Ǝ҂̓p�l���̐����ʁA�A���Ǝ҂͗A���ʂ̐��ʒP�ʂɈ��̒P�����悶�邱�Ƃŕ��S�z���Z�o����B ��O�ҋ@�ւɎx����ꂽ��p�́A���z�����d���̔p�����ɁA�ݔ����L�ҁE��̎��Ǝ҂�ʂ��čĎ������Ǝ҂Ɏx�����A�e�f�ނ����T�C�N���i�f�ނƂ��Ă̍ė��p�j���[�g�ɉ�邱�ƂɂȂ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���ቷ�M�𐢊E�ō��̖��x�Œ~�M�A�O�H�d�@�Ɠ����Ȋw�� �O�H�d�@�Ɠ����Ȋw��w�́A�����听���̍����q�Q���𗘗p���A60���ȉ��̒ቷ�̔M�𐢊E�ō��̒~�M���x�Œ~������~�M�ނ��J�������B �H��E�����ԁE�I�t�B�X��Z����Ȃǂ����C���ɔp������Ă����ቷ�r�M�̉���E�ė��p�ɗL���Ƃ����B �r�M�̗L�����p�ɂ́A���ɒቷ�r�M�������x�ɒ~����������ȍޗ���p�����~�M�ނ����߂��邪�A��ʓI�ɒ~�M���x���Ⴍ�Ȃ�ƒ~�M���x���Ⴍ�Ȃ邽�߁A����܂łقƂ�NJJ������Ă��Ȃ������B���҂͍���A�l�̂Ȃǐ��̂̍זE���ɂ݂��鍂�����������q�Q�������{���x���ō����E�]�����A�~�M���x30�`60���i���x��30���j�ɂ�����~�M�ނ��Ƃ̒~�M���x���r�������ʁA�]���̎s�̕i�i���b�_��225kJ/L�A�p���t�B����260kJ/L�j��2�{�ȏ�ƂȂ�~�M���x562kJ/L���m�F�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ����K�X�A�W���^���z�M�V�X�e���̍��x���`���[�ɏo�� ���K�X�́A�W���^���z�M�V�X�e���̊J������|����I�[�X�g�����A�̃X�^�[�g�A�b�v���FPR Energy�iFPR�G�i�W�[�j�ɏo�������Ɣ��\�����B FPR Energy�Ђ�02023�N�ɐݗ����ꂽ�B�W���^���z�M�V�X�e���́A���z�M��}�̂ɒ������A���̔M���瓾��ꂽ���C���Y�ƕ���Ȃǂŗ��p����B���z����M�Ƃ��Ē������邱�Ƃŕϓ����������Đ��\�G�l���M�[��������I�ɋ����ł���B ���Ђ̃V�X�e���́A�M�}�̂Ƃ��ĉ��w�I�Ɉ���ȃZ���~�b�N���q�����p���A����ɓƎ��J���̃��V�[�o�[��M������Ȃǂ��̗p���邱�ƂŁA�����Z�p��荂���ƂȂ�ō�1,200���̔M�������\�Ƃ����B�R�X�g��M���������A�^�]�Ǘ��̖ʂł��D�ʐ�������Ƃ����B����1MWt�K�͂̎������������B�uMWt�v��Megawattthermal�i���K���b�g�T�[�}���j�̗��ŁA����3,600MJ�̔M������E��������e�ʂ�\���Ă���B ����A2026�N�����߂ǂ�50MWt�̋Z�p�J����i�߂�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����v�Ɗ�ƁE���z�����������L���O�A5GW�̃��^���g�b�v �đ��z�G�l���M�[�Y�Ƌ���iSEIA�j�̍ŐV���|�[�g�ɂ��ƁA���ݕč����[�f�B���O��Ƃɂ�鑾�z�����d�̓����ʂ͕č��S�̗̂ݐϓ����ʂ�18�����߂��B 2024�N5���܂ł̑��z�����d�̗ݐϓ����ʃg�b�v10������ƁA�ă��^���i���o�[�����ŁA�����ʂ̓p�l���o�͂�5.1GW�����B �ȉ��A2�ʂ̓A�}�]��4.6GW�A3�ʃO�[�O��2.6GW�A4�ʃA�b�v��1.2GW�Ƒ����B���̃��|�[�g�̑��z�����d�V�X�e���́A�u�I���T�C�g�^�v�Ɓu�I�t�T�C�g�^�v���B�I���T�C�g�^�Ƃ́A��Ƃ̉�����A�~�n���ɓ������Ď��Ə���P�[�X�A�����āA�I�t�T�C�g�^�Ƃ́A���Ə��̕~�n�O�ɍĐ��\�G�l���M�[���d�ݔ���ݒu���A���z�d����ʂ��ēd�͂B����d�g�݁B�u�I�t�T�C�g�^�v�Ɋւ��ẮA�o�[�`�����i���z�I�j�E�l�b�g���[�^�����O�A�t�B�W�J���i�����I�j�܂��̓o�[�`�����i���Z��@�ɂ��jPPA�i�d�͍w���_��j�ȂǃT�[�r�X�`�Ԃ����l�����Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����{���y���u�X�J�C�g���z�d�r�헪�A2040�N��20GW�R�X�g�z���14���~/kW�A15�~/kWh�A�������̂ŕǖʂ�1GW �o�ώY�ƏȂ́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̕��y�Ɋւ��銯�����c����J�Â��A�u�����㑾�z�d�r�헪�i�āj�v�����\�����B ����ɂ��ƁA��Ƀt�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r���������̂Ɍ����ɐݒu����P�[�X��O��ɁA�u2025�N�x���獑���s��𗧂��グ�A2040�N�ɖ�20GW�̓�����ڎw���v�Ƃ����B �����㑾�z�����d�V�X�e���̐ݔ���p�͖�14���~/kW�A20�N�Ԃł�LCOE�i�ϓ������d�����j��15�~/kWh�䔼�Ƃ������Z�l���������B �o�Y�Ȃ́A2040�N�ɂ͎��������\�ȓ�10�`14�~/kWh�̎�����ڎw���Ƃ��Ă���B�u2040�N�E20GW�v�ɂ�����ݒu�ꏊ�́A�ݒu�R�X�g�̍ł�����������ŁA�ǖʐݒu��1GW�ɗ��܂�Ƃ��Ă���B ������Ƃ́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r���K���X���Őϑw�����^���f���^�ō��������������A�����̌����V���R���^�̒u��������_���Ă���B���{�ł��A�����㑾�z�d�r�헪�ŁA�^���f���^�̊J�����i�߂�Ƃ̕��j�������ꂽ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���������x�A������d�͌v�ő��݊��^�ăZ���X�ЂƊo�� ���s�̃X�}�[�g���[�^�[��������Ԗ����ɔ����X�V�������}����2025�N�x�ȍ~�A�����ł̕��y�����҂���鎟����X�}�[�g���[�^�[�B ���̊J�������蓌�����x�����݊������߂Ă���B�d�̓f�[�^��͋Z�p�ō����Z�p������Sense�i�Z���X�j�ЂƊo��������B���ЋZ�p�̃��[�J���C�Y���������A�����d�l�̑��z�d�ݔ���Z���z�肵���t�B�[���h�ł̎��؎����ɋ��͂����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2024/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���V�����̏o�����p��CO2�����[����10������u�����|�����������v�Ɋg�� JR���C��JR�����{�EJR��B�͏o�����p���̈ړ��ɔ���CO2�r�o�ʁi�X�R�[�v3�j�������[��������T�[�r�X�ɂ��āA10�������B�V�����G���A�i�����w.�����������w�j�ɉ��L����Ɣ��\�����B��s�������Ă������C���E�R�z�V�����G���A�ƍ��킹�āA�����w���玭���������w�܂ł��Ώۋ�ԂƂȂ�B ���T�[�r�X�́AJR�e�Ђ��d�͉�Ђ���CO2�t���[�d�C���w�����A���Y�@�l����̏o�����p���ɑ���CO2�t���[�d�C���[������B���Y�@�l�ɑ�CO2�팸���ʂ̏؏��s���邱�ƂŁA�ړ��ɔ���CO2�r�o�ʂ��u�����[���v�Ƃ���T�[�r�X���B ������C���^�[�l�b�g�\��T�[�r�X�u�G�N�X�v���X�\��v�̖@�l��������T�[�r�X�Ƃ���4�����瓌�C���E�R�z�V�����G���A�Œ��Ă����B�܂��A���T�[�r�X�̖��̂��uGreenEX�i�O���[���C�[�G�b�N�X�j�v�Ɍ��肵���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IHI�A�ΒY�ἨA�����j�A���ĂɎ艞���^20%�]���A���p�i�K�� IHI�́A�ΒY�����{�C���[�R���̃A�����j�A�]�����i�Ɏ��M��[�߂Ă���B 4������6���ɂ�����JERA�ƂƂ��ɕɓ�Η͔��d��4���@(100��kW)�Ŏ��{�������؎����ł́A20%���̐ΒY���A�����j�A�ɓ]�����邱�Ƃɐ����B20%�]���̋Z�p���m�������Ƃ̊m���B�]����50%�ȏ�̑�^���؎����⏫���I�Ȑ�Ă̒B���Ɍ����Ă��艞�����`���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�������B�z��7�����_�Ŗ�80���~�ɓ��B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J������|���鋞�s��w���X�^�[�g�A�b�v��Ƃ̃G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�i���s�{�v��R���j�B�����t�@���h�̑��A�d�͉�Ђ�[�l�R���A�e�탁�[�J�[�Ɏ���܂ŗl�X�Ȋ�Ƃ���o�����A�������B�z��7�����_�Ŗ�80���~�ɓ��B�����B �o����ƂƂ̋�������������ɍs���Ă���A�y���u�X�J�C�g���z�d�r����|����X�^�[�g�A�b�v�̒��ŁA���݊��͓��������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����f�͂��Ƀ|�[�^�u���ɓ˓�!!�ł����{�d�l�́u�ԐF����Ȃ���_���v���ăi�[? �g���^����Ă����̂��J�[�g���b�W���̐��f�^���N�B�g���^�̔R���d�r������MIRAI�����ڂ��鏬�^�^���N�̖�1/5�T�C�Y�B 3.3kWh����������B �^���N���J�[�{��������ŕ����Ă��āA���������Ȃǂ��N���A�B�Β��ɓ������ރe�X�g�����{���Ă���B�}�ȉ��x�㏸�����m���o���u�������̃K�X�����ƂŔ�����h���A�e��������S�ȏ�Ԃ��ێ�����B �g�����́A�C�x���g�ł̏o�X��]�[�g�n�ȂǁA�C���t�����Ȃ��ꏊ�ւ̃G�l���M�[�����B���^�̔R���d�r�œd�͂邱�Ƃ��\���B����ɂ̓����i�C�ƃR���{�������������W�����ꂽ�B���f�J�[�g���b�W1�{�ŃO�����o�[�i�[��2���Ԕ��A��ʓI�ȃR������1���Ԕ���d�����Ƃ��ł���B�܂��J�[�g���b�W�̃T�C�Y�͒��a200mm�A�S��580mm�A�d�ʂ�8.5kg�B���f�J�[�g���b�W��"��ʍ����K�X�e��"�ƂȂ�A�o�ώY�ƏȂ̊NJ��ŗe���1/2�ȏ�͐ԐF�ŁA"���f"��"�R"�Ƃ����������K�v�ɂȂ�B �o�T�u�x�X�g�J�[�v |
|
|
| ��SwitchBot CO2�Z���T�[���K��Ԃ�n�o���鎟����X�}�[�g�f�o�C�X SwitchBotCO2�Z���T�[�̍ő�̓����́A3.66�C���`�̑�^�f�B�X�v���C�BCO2�Z�x�A���x�A���x�A���K�w���A�V�C�\��A�����ȂǁA�������Ɋւ������\���B �{���i�́A�����J���Ȑ�����NDIR����CO2�Z���T�[�ƃX�C�X�������x�Z���T�[���̗p�B���萸�x�́}50ppm CO2�Z�x���ݒ�l����ƁA�{�̂���̌x�����A�f�B�X�v���C�̐��l�_�ŁA�X�}�[�g�t�H���ւ̒ʒm�ȂǁA3��ނ̃A���[�g�@�\�Ŋ��C�̃^�C�~���O��m�点��B �_��ȓd���I�v�V�����ƃf�[�^���͋@�\�P�O�d�r �~2�{�d�r�쓮��USB���d��2WAY���d�ɑΉ��B �ő�2�N���̃f�[�^�ۑ���O���t�\���ACSV�G�N�X�|�[�g�@�\�ɂ��A�����I�Ȋ����͂��\�ł��B �o�T�u�݂K�W�F�b�g�u���O�v |
|
|
| �������K�X�Ɖ��l�s�Ae-���^���R���̊����l�ړ]�N���[���K�X�؏��� �����K�X�́A�N���[���K�X�؏����x�Ɋ�Â��A���^�l�[�V�������ؐݔ��Ő�������e-���^���R���̊����l�����l�s�Ɉړ]���A�K�X���̎g�p�R�����N���[���K�X������Ɣ��\�����B ���{���Ԃ́A10��31���̃K�X�̋L�O������F�ؗʂ��g����܂Łi�N���܂Łj�B2024�N4������^�p�J�n���ꂽ�N���[���K�X�؏����x�ɂ����āAe-���^���R���̊����l�ړ]���s���̂́A�����߂āB ���҂�2024�N7���A�u�����K�X���l�e�N�m�X�e�[�V�������^�l�[�V�������ؐݔ��v�����p���A���ݏċp�H��̔r�K�X���番���E�������CO2�ƍăG�l�R���̃O���[�����f����������J�n�B��������e-���^���́A�N���[���K�X�؏����x�Ɋ�Â��F���A�N���[���K�X�؏����擾���Ă���B �����؎{�݂́A�O�H�d�H�O���[�v�Ƌ����Ői�߂Ă��鉡�l�s�����z�ǒߌ��H��̔r�K�X���番���E�������CO2�������Ƃ��A1���ԓ�����12.5Nm3��e-���^�����ł���B �o�T�u���r�W�l�X�p |
|
|
| ��AI�Z�p���x����̂͏��^���W���[���F�H�IGoogle�̃G�l���M�[�헪 Google�́A�N���[���G�l���M�[�ڍs���������邽�߁AKairosPower���J�����鏬�^���W���[���F�iSMR�j����j�G�l���M�[���w�����鐢�E���̊�ƌ_�����������B ���̌_��ɂ��A2030�N�܂łɍŏ���SMR���I�����C�������A2035�N�܂łɒlj��̘F��W�J����Ƃ����B��������A�č��̓d�͖Ԃɍő�500MW�̐V����24����365���̃J�[�{���t���[�d�͂����������B�܂��AAI�Z�p�̐i�W���x����V�����d�͌�����A�N���[���ŐM�����̍����G�l���M�[���v�������߂̐V�Z�p������������BSMR�̊j�G�l���M�[��24����365���̃N���[���ȓd�͌�����A�d�͖Ԃ̒E�Y�f����v���ɐ��i����B Google�́A�ϓ�����Đ��\�G�l���M�[�Ƒg�ݍ��킹�āA24����365���̃J�[�{���t���[�G�l���M�[�ƃl�b�g�[���ڕW��B�����邽�߂ɁA��i�I�ȃN���[���d�͋Z�p�̊J���Ə��Ɖ��𐄐i���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����E�̍ăG�l�A2030�N�܂łɖ�3�{�AIEA�\�����z������������8���A���K�\�[���[�Ɖ����オ�}�� IEA�i���ۃG�l���M�[�@�ցj�́A���N���s���Ă���Đ��\�G�l���M�[�s�ꃌ�|�[�g�̍ŐV�Łu�Đ��\�G�l���M�[�iRenewables�j 2024�v�\�����B���E�̍ăG�l�e�ʂ�2024�N����2030�N�܂ł̊Ԃ�5,500GW�ȏ�lj�����錩���݂ŁA2017�N����2023�N�܂ł̑����ʂ̖�3�{�ɑ�������Ƃ����B �s�ꓮ���Ɛ��{�̐��������Ɋ�Â��ƁA�����͌��݂���2030�N�܂łɐ��E���Őݒu�����ăG�l�e�ʂ̖�60�����߂錩�ʂ��B���������E�̍ăG�l�e�ʂɐ�߂銄���́A2010�N�̖�3����1����A�����I���܂łɖ��܂Ŋg�傷��B ���E�̑��z�����d�����\�͂�2024�N���܂ł�1,100GW���Ɨ\������B����͗\���������v��2�{�ȏ�ɒB����B�������������ɏW�����Ă���ߏ苟���́A2023�N�������甼�z�ȉ��Ƃ������z���p�l�����i�̒ቺ���㉟���������A�����̃��[�J�[���o�c��@�Ɋׂ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����ۑS�o��A2��9042���~�v��24�N�x����35.5���� ���Ȃ́A2025�N�x�̊��ۑS�o��T�Z�v���z�����܂Ƃ߂��B���z��2��9042���~�ŁA2024�N�x�����\�Z����35.5�����������B �{���̌n�ʂł́A�u�n�����̕ۑS�v�̋敪�́A�O�N�x1��1656���~�����1.5�{�ƂȂ�1��8212���~�ŁA���ۑS�o��S�̂�62.7�����߂��B���̂ق��A�ȃG�l���ʂ̍����ݔ��E�@��ւ̍X�V��p�Ȃǂ��x������ȃG�l�⏕����n��ɂ�����E�Y�f���̎��{�̐��\�z�Ɍ������x���Ȃǂ��s���n��E�Y�f�ڍs�E�ăG�l���i��t���Ȃǂ����荞�܂ꂽ�B �n�����̕ۑS�ȊO�́A�u�������l���̕ۑS����ю����\�ȗ��p�v��1,933���~�i�O�N1,609���~�A�ȉ����j�A�u�z�^�Љ�̌`���v��784���~�i656���~�j�A�u�����A�y����A�n�Պ��A�C�m���̕ۑS�v��3,446���~�i3,140���~�j�A�u���ː������ɂ��������̖h�~�v��2,945���~�i2,811���~�j�A�u��I�ȉ��w������v��47���~�i55���~�j�ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�́g����28�x�h���������� �u��[��28�x�Ɂv�Ɛ��{�����߂������ݒ肪���Ɍ��������B ���ȂȂǂ͐��{�@�ւ�n�������̂Ȃnj�������̒E�Y�f����i�߂邽�߂̊W�Ȓ���c���J�����B���̂Ȃ��ŁA����܂Łu����28�x���x�v�ɐݒ肵�Ă������̒��ɂ̗�[���x�����������ƂɌ��߂��B ��c�����ł́A�����Ǘ��ɂ��ās�M���Ǒ�̊ϓ_����́A�K�ȋ��x�ɂ���悤�����ɌĂт����Ă���A�܂��A���Ԋ�Ƃɑ��čs���Ă���28�x��ڈ��Ƃ����^�p�̗v�������݂͍s���Ă��Ȃ��B�ȃG�l���M�[���O���ɂ������A�_��Ȏ����Ǘ��Ƃ��邱�Ƃ��d�v�t�ƋL���Ă���B�u�w��[��28�x���x�x�Ƃ����̂́A���{��2021�N�Ɋt�c���肵�����s�v��ŁA�����ւł͌�����������炵�Ă����B�������A�ߔN�͖ҏ��������Ă���A�Ȓ��̐E����������́w28�x�ݒ�ł͏�������x�Ƃ������s�����o�Ă����B2024�N�x���Ɏ��s�v������肵�A2025�N�Ă���^�p�ɂȂ�B �o�T�uFLASH�v |
|
|
| ���]��d�͂�s�L�{�݊ԂŗZ�ʓ��dHD���s����VPP�\�z�̐�s���؊J�n ����̐�s���́A�S���̎����̂ł͏��߂āA�����p�r�̓s�L�{�݊Ԃœd�͂�Z�ʂ�����g�݁u�s����VPP�v�̈�тƂ��Ď��{������́B ���l�ȓs�L�{�݂ɑ��z�����d�ݔ���~�d�r�Ȃǂ̍ăG�l�ݔ���ݒu���A�]��d�͂𑩂ˁA24���ԉғ����Ă����Î{�݂�h�Ќ����A�~�d�r�̐ݒu������Ȏ{�݂ɋ�������Ȃǂ̃G���A�G�l���M�[�}�l�W�����g���s���B�܂��A�d�͕N�����ɂ́A�d�͎s��ւ̒����͂̋��o�Ȃǂ���������Ƃ��Ă���B ��s���ł́A��Α�꒚�ڃA�p�[�g�̑��z�����d�Ŕ��d�����d�͗ʁi�N�Ԗ�9��3000kWh�j���A�����s�뉀���p�قɋ������A�����^�p��ʂ��ăf�[�^���͂��s���A�ăG�l�d�̗͂��p�������ڎw���B 2025�N�x�ȍ~�́A���g�݂��w�Z������A�����Z��Ȃǂ̂��̑��s�L�{�݂Ɋg�債�A�ݔ�������G���A�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���iAEMS�j�ɂ��G�l���M�[�̍œK�^�p���s���A�{�݊Ԃł̓d�͂̑��ݗZ�ʂ�}��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/11�@]�@�@�� |
|
|
| �����f�T�v���C�`�F�[�������p�������f�~�G�l���M�[�̎��؉^�p���J�n �������݂́A���f�G�l���M�[�̗��p�g���ړI�ɁA���f�T�v���C�`�F�[�������p�������f�~�G�l���M�[�̎��؉^�p���J�n�����B ���̎��g�݂́A�~�n�O������ꂽ���f�𐅑f�z�������^���N�ɒ������A�K�v���ɒ��o���ēd�͂ɕϊ����邱�ƂŁA����G�l���M�[�̒E�Y�f���𑣐i�����܂��B2024�N�x�́A�R�����đq�R�̃O���[�����f�����T�C�g����N��40GJ�̐��f�K�X������A���C�E�W�����̍\���{��4���̓d�̓G�l���M�[���Ƃ��Ċ��p����v�悾�B ���z�����d�̗]��d�͂𗘗p���Đ����������f���A�퉷�E�ሳ�Ő��f���z���E���o�ł��鐅�f�z�������^���N�ɒ�������B�^���N�ɓ����������f�z�������́A��������댯���Ƃ��Ďg�p�ł��邽�߁A��ʎ{�݂ɂ��e�ՂɓW�J�ł���B���f�����ݔ��́A�e��200Nm3�̕W���^�^���N�Ɨe��250Nm3�̋}���[�U�^�^���N�ō\�������B�}���[�U�^�^���N�ɂ́A�^���N���̍������p���邱�ƂŁA���f�z�������i�����B �o�T�u�������݁v |
|
|
| ���T���g���[���B�������ACO2�����x����ɐ��� �T���g���[�z�[���f�B���O�X�A�����K�X�A�����K�X�G���W�j�A�����O�\�����[�V�����Y�́A�T���g���[���B�������ɂ����āA�ő̋z���@��p����CO2������؎��������{���A�����H���Ŕ��������Z�x��CO2��99.5%�ȏ�̍����x�ŕ����E������邱�Ƃɐ��������B ���̎��g�݂͍�����ށE�����ƊE���̐��ʂł���B�ő̋z���@�́ACO2��I��I�ɋz���ł���A�~���𑽍E���x���̂ɒS�������ő̋z���ނ�p����Z�p�ŁA�ቷ�ł̕����E����ɓK���Ă���B����A3�Ђ͉������CO2�����n�ŗL�����p����I���T�C�gCCU�ɂ��Č����A�J�[�{���j���[�g�����Љ�̎����ɍv�����邱�Ƃ�ڎw���Ƃ����B ����̗p�����ő̋z���@�́ACO2�̕����E����̃v���Z�X���60���̒ቷ�Ŏ����ł��邱�Ƃ������ł��B�����I�ɂ͍H�ꓙ�Ŗ����p�̒ቷ�p�M�̊��p�ɂ��A���v���Z�X���G�l���M�[�Ŏ������邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A���k�u���[�J�[�ɒ��͑�n�k�̍ہA�ʓd�Ђɔ����� �p�i�\�j�b�N�́A���k�u���[�J�[�̑i���ɗ͂����Ă���B��n�k�����������Ƃ��ɂ́A�n�k�̗h��ɑ�������Ɠ����ɁA�h�ꂽ��̓ЊQ�ւ̔������d�v���B ���ł��ʓd�Ђ̔����ւ̊S�͍��܂��Ă���B��_�E�W�H��k�ЂⓌ���{��k�ЁA�\�o�����n�k�ł������̉Ђ��������Ă��邪�A�n�k��̒�d����d�C�����������Ƃ��ɁA�Ђ���������P�[�X�������B ���Ђ̊��k�u���[�J�[�́A�k�x5���ȏ�̗h��������x�Z���T�[�Ŋ��m���A�劲�R�d�u���[�J�[�������Ւf���ēd�����~�߂�B�n�k�����m����3���ȓ��ɒ�d���Ȃ������ꍇ��3����Ɏ����I�t���A3���ȓ��ɒ�d�����ꍇ�A��������ɃI�t�ɂ���B���А��i�́A�����x�Z���T�[���h��ƌX�������m���A�����ȗh��͐����U���Ɣ��肵�A�傫�ȗh��͒n�k�Ɣ��肷��B�܂�15�x�ȏ�̑傫�ȌX���͒n�k�Ɣ��f���Ւf����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IHI�A���z�����d�̗]��d�C�ŏ��C���A�M���p�ōăG�l�n�Y�n�������� IHI�́A���N4�����瑊�n�s����������Ŏ��؉^�]���J�n���Ă����ăG�l�M���p�V�X�e�����A����I�ȉ^�p���\�ł��邱�Ƃ��������Ɣ��\���� ���̍ăG�l�M���p�V�X�e���́A���z�����d���ŏ]���p������Ă����]��̒����d�͂��ׂĂ������ȓ����ŁA�J�[�{���t���[���C�Ƃ��ė��p����V�X�e���B�]��d�͂ʂȂ����p���A�d�͂��R�X�g�ŏ_��ɔM�G�l���M�[�ɕϊ�����Z�p�iP2H�FPower toHeat�j��p���č\�z�����B �����ł́A�N�Ԃōő�240kW�̌𗬓d�͂��g�p���Ă���A����ɑ��āA300kW�̎��Ə���^�̑��z�����d����200kW�̃p���[�R���f�B�V���i�[��ݒu�A�ő�200kW�̌𗬓d�͂̋������\���B�܂��A�~�M���d�C�{�C���[�u���C���v��7��ݒu���A�ő�189kW�i1�䂠����27kW�j�̒����d�͂��z���ł���V�X�e���Ƃ����B 4���ɊJ�n�������؉^�]�ł́A���݂܂łɔ��d�����d�͂��ׂĂ�L�����p������I�ɉ^�p�ł��邱�Ƃ��m�F�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d�R�X�g14�~�^kWh�B���ϐ����w�Ɠ��d�A�y���u�X�J�C�g�ʎY���� NEDO�́A�O���[���C�m�x�[�V����������Ɓu������^���z�d�r�̊J���v�v���W�F�N�g�̘g�g�݂ɂ����āA�u������^���z�d�r���؎��Ɓv��V���ɊJ�n���A1���̌����e�[�}���̑������Ɣ��\�����B �̑��e�[�}�́A�u�y�ʃt���L�V�u���y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗ʎY���v�B�\�Z��378���~�ŁA���{���Ԃ́A2024�N�x����2030�N�x�܂ł�7�N�ԁB ���v���W�F�N�g�́A�V���R���n���z�d�r�ɑR�����鑾�z�d�r�Ƃ��ėL�]�������y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J����i���A�s��J��̑���������ړI�Ƃ��Ă���B����̎��g�݂ł́A�i�������肳����ʐ��Y�\�ȗʎY�Z�p�̊m���Ɍ����āA��A�̐��Y���C���Ƃ��č����X���[�v�b�g�i�P�ʎ��ԓ�����ɏ����ł����Ɨʁj��A���������܂����������Z�p�J�������{����B �����̎��g�݂ɂ��A���d�R�X�g14�~�^kWh�̒B���ƁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̑����̎Љ������}��A���{�̑��z�����d�Y�Ƃ̋����͋�����ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�u��-�C���u�����{���T�v���C�`�F�[���S�̂̒E�Y�f���œ����K�X�ƘA�g �Z�u���]�C���u���́A�����K�X�Ɠ��Ђ̎��Ɗ�����X�܂��܂ރT�v���C�`�F�[���S�̂̒E�Y�f�����i�ŘA�g���Ă������j�𖾂炩�ɂ����B ���g�݂̒��S�ƂȂ�̂́A�ăG�l�̗����p�B�V�K�J���ɉ����A�J�������ăG�l���{�݂ȂǂŊ��p����B�܂��A�~�d�r�␅�f�Ȃǂ�p�����ăG�l�ϊ��⒙���E�A���A���p�Ɋւ���Z�p�J������ю��A�Đ��\�ȃK�X�̃G�l���M�[���B�Ȃǂ����{����B����ɁA�H�̉��l��BCP����ȂǃT�v���C�`�F�[���ɂ�����ݔ���T�[�r�X�̊J��������s���Ă����B �R�Ђ�2024�N3���A�֓��G���A�̖�750�X�܂ɂ����āA���z�����d�ɂ��I�t�T�C�g�R�[�|���[�gPPA�̃X�L�[���ƁA�����K�X�̔��d��������̓d�͋���������l�����p���ACO2�r�o�ʎ����[���Ɍ��������g�݂��J�n�B���̎��g�݂ł́A�����K�X�̔��d����T�[�r�X�ƂƂ��ɁA�O�䕨�Y�v�����g�V�X�e����PPA�X�L�[�������p�B����A��2000�X�܂ւ̓��X�L�[���̓K�p��ڎw���B �o�T�u���W�]��p |
|
|
| ���f�[�^�Z���^�[���X�A�G�l�����ȃG�l�}���^�u���v�ŏ������� �f�W�^�����̐i�W�ɔ����f�[�^�ʐM�ʂ̑����ɂ��A�f�[�^�Z���^�[�̏���d�͗ʂ̋}���ɑ��錜�O�����܂��Ă���B�����G�l���̓f�[�^�Z���^�[�̏ȃG�l���𑣐i������g�݂���������B �d�͍L��I�^�c���i�@�ւ̎��v�z��ł́A�ő�d�͂�2024�N�x��48��kW�A2028�N�x��376��kW�ƌ��Ⴂ�ɑ����Ă����ƌ����ށB�����̃f�[�^�Z���^�[���́A2023�N���_��510������B�啝�ȏȃG�l�́A�i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B ���ڂ��W�߂�Ő�[�Z�p�̈���A���d�Z���B�R���s���[�^�[�̌v�Z�����ɒu�������邱�Ƃŏȓd�͂��}���B����̃G�l���M�[���������I�ɍ��߂锼���̂̔����Z�p�����҂��傫���B��p�t�̓��������ɃT�[�o�[���ۂ��ƐZ���u�t�Z��p�v��A�`�b�v�Ɏ��t�������������p�t�Ń`�b�v����̔��M����菜���u�R�[���h�v���[�g��p�v�Ȃǂ��A�ȃG�l�ɗL���ȍŐ�[�ݔ��Ƃ��č���������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���l���d�́A�����_�H��w�Ȃǔ������R���d�r�Ɋւ�����؎������J�n �������R���d�r�͔��d�ۂƌĂ��������̓����ɂ��A�L�@������������Ɠ����ɓd�͂ݏo���d�g�݁B ���d�ۂƂ́A�L�@��������ۂɓd�q����o���鐫�������������̑��̂ŁA��\�I�Ȃ��̂Ƃ��āA�W�I�o�N�^�[�ۂ�V�����l���ۂ�����B�������R���d�r�́A���d�ۂ����o�����d�q���y��ɍ��������ɂɏW�߂��A�ڑ����ꂽ�Z���T�[�Ȃǂ�ʂ��Đ��ɂɈړ�����ۂɓd���������d�g�݂��B ���d�ۂ͎��R�E�̓y��ɍL�����݂��Ă���A�r���̉��D��������ł̊��p���͂��߁A�d���̂Ȃ����O�ł��d�͂ݏo����V���ȃN���[���G�l���M�[�̑n�o���@�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�l���d�́A�����_�H��w�ȂǂS�҂��A���Q�������l�s�E�ɕ����݂̂��n�ɔ������R���d�r��ݒu���A���ۂ̔_�n�ɂ����锭�d���m�F����B �������R���d�r��d���Ƃ����C����y�됅���ʓ����v������Z���T�[��_������j�^�����O����J�����Ȃǂ�ݒu���A�_�Ƃ̃X�}�[�g���Ȃł̊��p��ڎw���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������2025�N�x�T�Z�v���A���z8704���~�E�Y�f���{��ɏd�_ ���Ȃ��A�ߘa7�N�x�i2025�N�x�j�\�Z�Ă̊T�Z�v���Ƃ��āA�O�N�x���49�����ƂȂ�8704���~��v�������B ���Ȃł́A�ȉ�4�𒌂Ɏ��g�݂𐄐i���Ă������j�������Ă���B.�E�Y�f�Ń��W���G���g�����K�Ȓn��Ƃ��炵�̑n��.�o�����[�`�F�[���E�T�v���C�`�F�[���S�̂̒E�Y�f�ڍs�̑��i.�n��E���炵�̒E�Y�f���̊�ՂƂȂ�擱�Z�p���Ə���Փ�����.���E�̒E�Y�f�ڍs�ւ̕�x���ɂ�鍑�ۓW�J�E���ۍv�� ��N�x����̑啝���ɂ��ẮAGHG�r�o�팸�Ɍ����āA�E�Y�f�{��ɏd�_��u�������Ƃ���ȗv�����B����́A��L4�̎��g�݂̂����A���ɓ����z�����������u�E�Y�f�Ń��W���G���g�����K�Ȓn��Ƃ��炵�̑n���v�u�o�����[�`�F�[���E�T�v���C�`�F�[���S�̂̒E�Y�f�ڍs�̑��i�v�𒆐S�ɁA�V�K���Ƃ�d�_�{��ɂ��ĉ������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/10�@]�@�@�� |
|
|
| ����ёg�����̎��m�㕗�́A�uTLP�^�v�����C��ɐݒu ��ёg�́A�X�����ʑ��̉���3km�̊C��ɁA���̎��m�㕗�͔��d�{�݂̂����A�ْ��W��������TLP�i�e���V�����E���O�E�v���b�g�t�H�[���j�^���̂������ŏ��߂Đݒu���A1�N�Ԃ̋����ϑ����J�n�����Ɣ��\�����B ���{�͉���̊C�悪���Ȃ��A���[�̐[���C��ɓK�������̎��m�㕗�͔��d�̓��������҂����B���̎��̌W�������́A�X�p�[�^��Z�~�T�u�^�Ȃǂ̃J�e�i���[���������p��������邪�A���̓��h���傫�����d�������Ⴂ���ƂȂǂ��ۑ�ƂȂ��Ă���Ƃ����B TLP�^���̂́A�C��ɐݒu���ꂽ�A���J�[���e���h���ƌĂ��ْ��W���ނŒ蒅�����A���̂̕��͂ɂ�萶����ْ��͂𗘗p���Ċ�b�Ƃ��ċ@�\������B���h���萫�┭�d�����̍��������҂����ق��A�C��̐�L�ʐς����������Ƃւ̉e�������Ȃ��̂������B���̐���̒�R�X�g���A�ʎY���̂��߁A�S�R���N���[�g�ƍ|�����ނɂ��n�C�u���b�h�\�����̗p�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ������EV�̃o�b�e���[��Ԃ�f�f�^�t�@�u���J�E���ł炪���؎w�W�m���ڎw�� ���ÎԔ̔��̃t�@�u���J�R�~���j�P�[�V�����Y�́A���ŁA�ۍg�v���b�N�X�Ƌ����ŁA���Ód�C�����ԁiEV�j�̃o�b�e���[�d�r�̏�Ԃ�f�f������؎��Ɓu���Î�EV�d�r�f�f�v���W�F�N�g�v���J�n�����B ���ÎԎs��ɂ����āAEV�̓d�r�̗e�ʂ��Ԃ��ʓI�ɔ��f����w�W�̊m����ڎw���B3�Ђ́A2022�N4�����瓌�ł��ۗL����d�r�f�f�Z�p��p���ĕ]���w�W�̊m���Ɏ��g��ł���A����ł�B��j��d�r�f�f�T�[�r�X�����X�^�[�g�A�b�v�E�d�m�ɂ��@�ޒE�Z�p���͂ɂ��A�Z���Ԃł̐��m�Ȑf�f���������鑪���̏��^����t�B�[���h�e�X�g�̎��{�Ȃǂ�i�߂Ă����B ����̎��ł́A�J�������]���w�W�𒆌Îԏ��T�C�g�u�ԑI�уh�b�g�R���v�ɔ��N�Ԍf�ڂ��邱�ƂŎ��p����������B�w���҂ɐM�����̍���������邱�ƂŁA����EV�s��̎���������ƐM��������𐄐i���邱�Ƃ��߂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����I���l��`�ŘH�ʑ��z�������A�d��������@�̓d���� ��ѓ��H�́A��I���l�G�A�|�[�g�ƂƂ��ɁA��I���l��`�̕~�n���ɂ����āA��`���������ł͍������̎��݂ƂȂ�H�ʑ��z�����d�V�X�e���̎��؎����Ɏ��g��ł���B4���ɓ��{�ݓ��̕ۈ����H�Ɏ������[�h�̍\�z�����������B ���؎����ɗp����H�ʑ��z�����d�V�X�e���́A��ѓ��H�Ƒ����d�@�H�Ƃ������J�������u�\�[���[�E�F�C�v���̗p�����B�։d49kN�ɑς��鑾�z���p�l����g�ݍ����u���b�N�u�\�[���[�v���[�g�v�Ŕ��d���Ē~�d�r�ɏ[�d���A�d���@��ނɈ���I�ɔz�d����B �P�����V���R���^���z���p�l��4��������5mm�̋����K���X2���ɋ��\���ŁA�\�[���[�E�F�C1��������̒�i�o�͂�18W�B�\�[���[�E�F�C��12���ݒu���A�����d��������@�̓d���ɗ��p����B�����肪�K�v�Ȏ�����1������800Wh���x�̔��d�������ށB�����ѓ��ʼnғ����鎩���d��������@2��̎g�p�d�͂�100�����z�����d�Řd���B���؊��Ԃ͖�1�N�Ԃ̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��AI����ς���I�C�g�[���[�J���~�_�ˑ�w�Ƌ����ŁuAI�X�}�[�g�V�X�e���v��X�܂ɖ{�i���� �uAI�X�}�[�g�V�X�e���v�́A�X�ܓ��ɐݒu���ꂽ�J�����≷�x�v�Ȃǂ̃Z���T�[�ɂ���Ď��W���ꂽ�l���A���x�ACO2�Z�x�Ȃǂ̃f�[�^��AI����́E�w�K���邱�ƂŁA�œK�ȋǗ����s���V�X�e���B ����ɂ��A���X�q���⎺���̕ω��ɉ����������I�ȋ^�p���\�ƂȂ�A���p�q���W������t���A�������I�ɗ�p�E�g�[���s���A���p�q�����Ȃ����ԑтɂ́A�̉ғ���}�����邱�ƂŁA�啝�ȃG�l���M�[����ʂ̍팸����������B �����q�X�ł́A2024�N1������uAI�X�}�[�g�V�X�e���v�̎��؎������J�n���Ă�A�Ɋւ��G�l���M�[���40%�팸������ʂ��m�F����Ă���B���㏇���A��70�X�܂ɓ������A2024�N�x�ȍ~�ɕK�v�ȍ팸�ʂ̖�4.2%�i��2.2���g���j������������ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���H�c��`�A��2�^�[�~�i���{�قƃT�e���C�g�ڑ����ɕ��˗�p�f��PBB�ɓh��Radi-Cool ���{��`�r���f���O�́A���݂�i�߂Ă����2�^�[�~�i���{�قƖk���T�e���C�g�̐ڑ��{�݂ɁA���˗�p�f�ށuRadi-Cool�i���f�B�N�[���j�v���{�H�������拴�iPBB�j������Ɣ��\�����B ����͉H�c�Ƃ��ď��߂ēh���^�C�v�̃��f�B�N�[�������A5��Ɏ{�H����B���f�B�N�[���̓��f�B�N�[���W���p���Ђ��J���B���z���˂��A���R���ۂ̔M���˂�p���Ď����̔M�����˂��邱�ƂŁA�G�l���M�[���g�킸�Ɏ�������������B�h���ƃt�B������2��ނ���A������K���X�ʂȂǂŊ��p����B ����܂ł͉ď�ɔM��������PBB�i���拴�j�⒓�ԏ�̘A���ʘH�Ȃǂ�ΏۂɁA�t�B�����^�C�v�̐��i���{�H�����B���{��`�r���f���O�ɂ��ƁA�h���^�C�v�̐��i�͉�����ǂȂǖ�20��ނ̑f�n�ɑΉ��B�ėp�����������Ƃ���A��`�̂ق��A������ϓd�ݔ���z�e���A�a�@�A�w�Z�A���H�X�Ȃǂ̊e�{�݂ւ̊��p�����҂ł���Ƃ����B �o�T�uAviationWire�v |
|
|
| ���悸�͐H�ׂ���A���ꂪ�����Ǝv��������H�ICN�A�N�V�����̌X�� �d�ʂ͑�14��u�J�[�{���j���[�g�����Ɋւ��鐶���Ғ����v�̌��ʂ\�����B ���̒����́A���{�ɂ�����J�[�{���j���[�g�����iCN�j�̔F�m��S��c�����A����̐Z�������������ړI�ŁA�S����15�`79��5���l��ΏۂɎ��{���ꂽ�B�����ł́A2023�N�̋C�����Y�Ɗv���ȑO����1.5���㏸���������������A���R��28�̃g�s�b�N�ɕ��ނ��ĕ��́B ���ʁA�ϑ��������ڂ����m���Ă����l��1���ɂƂǂ܂�A�u�n�����Z�߂Ȃ����ɂȂ�v��u���{�E��ƁE�l�����͂��ׂ��ۑ�v�Ƃ����ӌ������������B�܂��A���Ȃ́u���炵��10�N���[�h�}�b�v�v�Ɋ�Â�CN�A�N�V�����ł́A�u�H����H�c���Ȃ��v���ł��x������A�o�ϓI�����b�g�𗝗R�Ɏ��g�ސl�����������B �o�T�u���W�]��p |
|
|
| ���i�g���E���C�I���d�r�A�ĐV������K�͍H�ꌚ�݂� �g�傪�����č��̒~�d�r�s��ł́A�傫�ȕϊv�������炷�\��������Ƃ��ăi�g���E���C�I���d�r�ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B���̓d�r���J������V����ƃi�g�����E�G�i�W�[�́A14���h���i��2100���~�j�𓊂��ăm�[�X�J�����C�i�B�ɓ��Џ��̑�K�͍H������݂���v�悾�B �i�g���E���͎�ɓ���₷���A���`�E���x�[�X�̓d�r���������ň��S�ȓd�r���ł���z���Ƃ��Ċ��҂����܂��Ă���A�i�g�����͂���܂łɓ����Ƃ����3���h���B���A�Đ��{�̎x������B�i�g�����̋Z�p�ɑ��ẮA�č����Ǝ��̓d�r�Y�Ƃ����A�d�r�⌴�ޗ��Ɋւ��钆���ւ̈ˑ��x���������Ɋ�^����Ƃ̊��҂��������Ă���B �i�g�����̓d�r�́A�R�X�g���������`�E���ł͂Ȃ��i�g���E�����g�p���Ă��邱�Ƃ����͂ƂȂ��Ă���B�R�o���g��A�A�[�X�Ƃ������z�����g�p���Ȃ����Ƃ��������B�i�g���E���C�I���d�r�͔����ɂ����A����n�ł��g�p�ł��邱�Ƃ������������������B �o�T [The Wall StreetJournal�v |
|
|
| ���r���E�Q�C�c���V����Ƃ��V�����̌����A�~�G�l���݂ň���E�_��ȓd���ڎw�� �ĂŁA�V�����̌��q�͔��d���̌��݂��n�܂����B���q�͐V����Ƃ̕�TerraPower�i�e���p���[�j����|����i�g���E����p�����F�uNatrium�i�i�g���E���j�v�̎��ؘF���B���d�@�\�����łȂ��A�n�Z�����g�����~�G�l���M�[�{�݂�g�ݍ��킹��B2030�N�̉^�]�J�n��ڎw���B ���q�͔��d�������ẮA���g���K�X��r�o���Ȃ��E�Y�f�d���Ƃ��Ă����łȂ��A�G�l���M�[���S�ۏ���������铮�����L�����Ă���B �uNatrium�v�́A�e���p���[�ƕ�GE�����j���[�N���A�E�G�i�W�[�������J������B���̍����F��~�G�l���M�[�{�݂Ƒg�ݍ��킹�Č������\������B ���Ђ��ڎw�����̂��A�����F�Ő������M��~�G�l���M�[�{�݂ɂ������߂Ă���A���C�^�[�r���Ŕ��d����d�g�݂��B�n�Z���ɂ��M�́u�o������v�����p���āA�ꎞ�I�ł͂��邪�A���q�F�����̏ꍇ�����傫�ȓd�C�o�͂����o����悤�ɂ���B �o�T�u���o�N���X�e�b�N�v |
|
|
| �����o��2030�N�x�̍������z�������K�͂�6GW���Ɨ\�� 2023�N�x�i�P�N�x�j�̑��z�����d�����K�͂�5.04GW�iAC�x�[�X���A�n�o�́j�̌����݂ŁA�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�ɂ��Č����k���������Ƃ�2022�N�x��5.823GW����啝�Ɍ�������B FIT�Č��̒��ł����Ɨp�̌����������ŁA���d���i�̒ቺ��2017�N�x�̓��D���x�J�n�ɂ��F��ʂ���������ł���B����AFIT�Ɉˑ����Ȃ����ƌ`�Ԃł���PPA�i�d�͍w���_��j�ɂ�铱�����g�債�Ă���B ���v�Ƃ̎{�݉����~�n���ɑ��z���ݔ���ݒu����I���T�C�g�^PPA�́A�E�Y�f�̒�����d�C�㍂����w�i�ɁA2020�N�x�ȍ~�ɍ����������{�i���B�����Ɋg��𑱂��Ă���A�����y�[�X�͔N�X�������Ă���B2023�N�x�̔�Z��E�I���T�C�g�^PPA�̓����K�͂�870MW�̌����݂ŁA�S�̂�17.3���܂Ŋg�傷��Ɛ��v����B 2023�N�x�̔�Z��E�I�t�T�C�g�^PPA�̓����ʂ�445MW�̌����݂ŁA�S�̂�8.8���Ɛ��v����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����[�^�[�~�A�v�������ݏo���V���n�^��炬����ݔ��ُ�\�� �X�}�[�g���[�^�[�����́u�Љ�C���t���v�ƈʒu�t���A�l�X�ȃA�v���Ƒg�ݍ��킹�āA�V���ȉ��l�ݏo�����݂��č��ȂǂŐi��ł���B2025�N�x���玟����X�}�[�g���[�^�[�̓������n�܂���{�����ł��A�S�����܂��Ă����B �X�C�X�̃����f�B�X�E�M�A�́A�X�}�[�g���[�^�[�Ƒ��ʂȃA�v����g�ݍ��킹�l�X�ȕt�����l�ݏo����������`���B�X�}�[�g���[�^�[�̋@�\���������j�i�X�}�[�g���[�^�����O�j�A�O���b�h�G�b�W�C���e���W�F���X�A�X�}�[�g�C���t���X�g���N�`���[�̂R�ɕ��ނ���B�������������̂��A���Ђ��J��������i���[�^�[�́u�q�����������i���x���j�v���B ���x���̍ő�̓����́A���b�P���S���ȏ�Ƃ����c��ȉœd���A�d���A���g���Ƃ������d�̓f�[�^���擾����_�ɂ���B�n�����[�ŏW�߂��c��ȃf�[�^�����p���A���ʂȃA�v���Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�z�d�Ԃ̋��Չ��A���v�Ƒ��̐ߓd�Ƃ������t�����l�T�[�r�X�ݏo���Ƃ����̂��A�\�z���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ������������ǖʂւ̑��z�����d�̓����ANEDO���v�E�{�H�K�C�h���C�������J �����A�Đ��\�G�l���M�[�̎��Ə���Ɍ������������������钆�A�lj��I�ȑ��z�����d�̓����G���A�Ƃ��āA���z���̉�����ǖʂւ̐ݒu�����ڂ��W�߂Ă���B������ǖʂւ̐ݒu�ɓ����������i���������s��ɓo�ꂵ�Ă���B NEDO����2030�N�x�܂łɁA���Ԋ�Ƃɂ�鎩�Ə����ړI�Ƃ��������E�ǖʂւ̑��z�����d�̓����ŁA�e�팚���Ƃ���10GW�A�����ݔ��Ƃ���6GW�A��`����ɂ�����2.3GW�A�V�z�Z��Ƃ���3.5GW���x�������܂�Ă���Ƃ����B ����ŁA�����ݒu�ł͑��z���p�l���Ȃǂ̔�U���̂Ȃǂ��������Ă���B������NEDO�͎Y�����A�\���ϗ͕]���@�\�A���z�����d����A�听���݂Ȃǂ�钲�����ʂ��܂Ƃ߁A�����ݒu�̑��z�����d�ݔ��̈��S���m�ۂ̂��߂̃K�C�h���C���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B ���z�����d�ݔ��̍\���Ɠd�C�Ɋւ���v�E�{�H�̗v��������A�����̊�E�w�j�A���������̌��ʂȂǂ����ƂɁA�v�E�{�H���@���L�ڂ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����㑾�z���́u�ݒu�]�n�v��A�o�Y�Ȃ����x���� �o�ώY�ƏȂ́A�ȃG�l�@���K�p����鎖�Ə��ɂ�����G�l���M�[�ւ̓]���𑣂��V���Ȑ�����������B��̓I�ɂ́A���Ə��̌����ɂ����āA�����㑾�z���ݔ��́u�ݒu�]�n�v����鐧�x��n�݂���B �����LjĂł́A�܂��͉����u�����z����O���ɁA�ȃG�l�@�Ɋ�Â�����̓��e�Ɂu�]�n�v�ɒ��ڂ����v�f�����邱�Ƃ��Ă����B���x�Ăł́A���莖�Ǝ҂ɑ��āA�H��Ȃǂɂ����鉮���u�����z���̐ݒu�]�n�Ƃ��āA �i1�j�����̉����ʐ� �i2�j�v���̑ωd �i3�j���̂������ɑ��z������������Ă��鉮���ʐς̕����߂�B �܂��A����A�y�ʂ̎����㑾�z�d�r�̐ݒu���������₷���悤�A�ωd�������ȉ����ɂ��Ă������߂�B���������̑Ώۂ͍̎Z���E���Ԏ��Ȃǂ̊ϓ_����e���Ǝ҂ňقȂ邽�߁A���Ǝ҂ɂ����ĉ����Ɋւ�����̏�����ݒ肵�A�������������ɂ��ĉ����ʐς���щ����u�����z���ݒu�ς݂̉����ʐς̕����߂�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/9�@]�@�@�� |
|
|
| �����dEP�A�ƒ�����ȃG�l�v���O������DR�T�[�r�X��lj� �����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i���dEP�j�́A�uTEPCO�ȃG�l�v���O�����v�ɁA�@�퐧��DR�T�[�r�X��lj������B�d�͂̎����ɉ����āA�~�d�r�@��̏[�d�E���d�̃^�C�~���O�����u���䂷��B �`�������W�f�[��d�͎����̏ɉ����āA�グDR�E����DR�����{�B����lj�����DR�T�[�r�X�̖��̂́A�u�G�R�E�ȃG�l�`�������W�@�퐧��I�v�V�����v�B�Ώۋ@������u�Ő��䂵�A���dEP�Ǝ��̃|�C���g�u���炵TEPCO�|�C���g�v��i�悷��B �Ώۋ@��̐���́A�G�R�E�ȃG�l�`�������W�̑Ώۓ���ݒ肵�A�Ώۂ̎��ԑтɁA�~�d�r�̕��d�i����DR�j�ƁA�~�d�r�̏[�d�i�グDR�j�����{����B�܂��A�G�R�E�ȃG�l�`�������W�̑Ώۓ��ȊO�ɂ����Ă��A���X�̓d�͎����̏ɉ����āA���dEP���[�d�E���d���䂷�ׂ��Ɣ��f�������ԑтɂ́A�[�d�E���d�����{����B�Ȃ��A�@�퐧��ł́AShizenConnect�i�����s������j�́u�@�퐧��^DR�x���T�[�r�X�v�����p�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ߐ��g�C���̗v�o�ב䐔��4,000�����˔j ���{���X�g���[���H�Ɖ��2024�N4���ɐߐ��g�C���̗v�o�ב䐔��4,000�����˔j�����Ɣ��\�����B �ߐ��g�C���͐�ʂ�6���b�g���ȉ��ŁA1990�N�㖖���獑���Ŕ�������A2000�N�㏉���Ƀg�C�����[�J�[�̃��C���A�b�v�ɉ�������悤�Ȃ����B�����䐔��2012�N��1,000����ł��������A2020�N�ɂ�3,000������A���̌�3�N��4,000�����˔j���Ă���B���c�̂̎��Z�ɂ��ƁA�ߐ��g�C���̕��y���͌��ݖ�48���ŁA������50���ɋ߂Â��Ă�����B����܂ł͍��̏Z������`���A�E���オ��ɕ��y���Ă������A����͎���I�Ȏ��g�݂̏d�v�����������낤�A�ƌ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���f�B�X�|�[�U�[�ƘA�g���ĉƒ�̐����݂�L�����p���^�o�C�I�K�X���d�V�X�e�����J�� ��a�n�E�X�ƃ_�C�L�A�N�V�X�́A�}���V�����ɓ��������f�B�X�|�[�U�[�ƘA�g���A�����݂𗘗p���Č������p���ɓd�͂��������鏬�^�o�C�I�K�X���d�V�X�e�����J�������B 100�ˋK�͂̃}���V��������Ή����\�B��ʓI�Ƀo�C�I�K�X���d�V�X�e���͑�^�̂��̂������A�{�ݓ��ɐݒu�ł�����̂���ɂ͏��Ǝ{�݂ȂLj��K�͈ȏ�̐����݂̔�����z�肵�����̂ɂȂ��Ă���B���Ђ́A�}���V�����Ȃǂł��Ή��ł��A�ߔN�Z��ݔ��Ƃ��Đl�C�̂���f�B�X�|�[�U�[�ƘA�g���A�����I�ɌŌ`�����������ʼnt�������u��V���ɊJ�������B���̂��߁A�]���̃K�X�����u�Ɠ����̃K�X�����\���m�ۂ��Ȃ���A�]����1/6���x�܂ő��u�̏��^�������������B100�ˋK�͂̃}���V�����ɐݒu�����ꍇ�̔��d�ʂ�1���������8kWh�ŁA���p���Ɩ��Ȃǂ̈ꕔ��d�����Ƃ��\�B �o�T�u�j���[�X���^�[�v |
|
|
| ��CO2�r�o�ʂ�c���ł��Ă��钆����Ƃ͂킸��7.8�����Ԓ������� GDX���T�[�`�������́A������ƌo�c��990�l��ΏۂƂ���ESG�o�c�Ɋւ�����Ԓ����̌��ʂ����\�����B�����̌��ʁA��2�N�O�̒�������قڕω����Ȃ��A���Ђ̎��Ԕc���Ɋւ��āA������Ƃ̎��g�݂͑傫���i��ł��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B ���Ӟ�i�X�R�[�v1�A2�j�ɂ�����CO2�r�o�ʂ̔c���ɂ��Ă̒����ł́A�u�g�p�ʂ̃f�[�^�𐔒l�Ŕc���A�L�^����ѕۑ����Ă���v�����͂킸��7.8���ŁA�u���Ԃ̔c���ɂ͎����Ă��Ȃ��v������72.5���ƂȂ����B�܂��ACO2�팸�ʂ̔c������ъǗ��ɂ��Ď��₵���Ƃ���A�uCO2�̍팸�ʂ𐔒l�Ŕc������ъǗ����ł��Ă���v������6.6���A�u��̓I�Ȏ��g�݂����Ă��Ȃ��v������66.3���������B ��Ƃ̍ł��������g�݂́A�u�ȃG�l���M�[�����i���ʂȓd�C��������̓K���ȉ��x�ݒ�Ȃǁj�v�i664�j�B�����ŁA�u�p�����팸�����i���݂̕��ʁA�����◼�ʈ���g�p�Ȃǁj�v�i630�j �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����K�X�ȂǁA�k�C���ɍ����ő�K�͂̉c�_���q�^���z���^2026�N������ ���K�X�A�O�HUFJ��s�A���������G�l���M�[�i���Ɍ����Ð�s�j��3�Ђ́A�c�_���q�^�̑��z�����d���Ƃŋ��Ƃ��� �Ɣ��\�����B�Đ��\�G�l���M�[���d���Ƃ���|���钬�������G�l���M�[���A�k�C�����f���̖q���n�ɏo��9,575kW�̃��K�\�[���[�����݁B���d�d�͂͑S�ʂ��K�X�������d�C���Ǝ҂Ƃ��Ď��v�Ƃ�s��Ŕ���\��B���K�\�[���[�ɂ������l�i��FIT�Ώ؏��j�͎O�HUFJ��s���������B���������G�l���M�[���o�����ݗ��������f�\�[���[�O���[�W���O���d���́A���z�����d�Ɖc�_���q��g�ݍ��킹���\�[���[�O���[�W���O���Ƃ��^�c����B �\�[���[�O���[�W���O�Ƃ́A���z�����d���ƂƉc�_���q���Ƃ�g�ݍ��킹�����̂ŁA�r�Ȃǂ̉ƒ{�ɂ�鏜����Ƃ��܂ސA���Ǘ����@���̗p�������z�����d���ƁB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���p�\�iHR�\�����[�V�������ȃG�l�f�f�T�[�r�X���J�n��Ƃ̒E�Y�f���𑣐i �p�\�iHR�\�����[�V�����́A���{��Ƃ̒E�Y�f�����̑��i�Ɍ������u�ȃG�l�f�f�T�[�r�X�v�̒��J�n�����B ���T�[�r�X�ł́A��Ɠ��ɂ�����C���t���ݔ��Ȃǂ̉^�p����A���݂̃G�l���M�[�g�p�ʂ�g�p���z��c�����A�ȃG�l���������邽�߂̉^�p�ύX�̒�Ă�A�V���Ȑݔ������Ƃ��̓����z�A�팸�\�G�l���M�[��팸�\�R�X�g���Z�o���čœK�ȑ���o���B�܂��A���Ƃɂ����̍쐬�ȂǁACO2�r�o�ʂ̉��P�Ɍ������ȃG�l�\�����[�V���������B ���Ђ́A2022�N3�����T�X�e�i�r���e�B�o�c�x�����Ƃ��J�n���A���{��Ƃ̃T�X�e�i�r���e�B�o�c�̐��i�Ɍ������T�[�r�X��W�J���Ă����B����̃T�[�r�X�ŁA��Ƃɂ�����E�Y�f�̎��g�݂�����������B �@Step 01�FCO2�r�o�ʉ����x�� �@Step 02�F�ȃG�l�f�f�T�[�r�X �@Step 03�FCO2�팸�\�����[�V���� �@Step 04�FJ-�N���W�b�g�w����s�T�[�r�X �o�T�u���r�W�l�X�p |
|
|
| ���k�C�����O���Ƀ}�C�N���O���b�h�ғ��A��d���ɍăG�l�d�͂����� �u���O���n��}�C�N���O���b�h�v�́A�n�k�ȂǑ�K�͂ȍЊQ�ŁA���O�����܂߂čL�͈͂���d�Ɋׂ����悤�ȃP�[�X���B ���������ً}���A�����ɉғ�����u���G�l���O���͔��d���v�ɕ��݂��ꂽ�e��130MWh�̑�^�~�d�r����A��������ӂ̎{�݂�Z��ɕ��͂ŏ[�d���ꂽ�d�͂����������B�ΏۂƂȂ�̂́A�������v�ƂƂ��ď��O������Ə��O���������Z���^�[�A�����ė������{�݂����Ԓʂ艈���Ɉʒu���鏤�X�▯�ƂȂǂ̒ሳ���v�Ƃ���56���ƂȂ�B�����������6.6kV�̍����z�d���ɘA�n����Ă���B �����ΏۂƂȂ�{�݂̎��v�z��͖�400kW�ŁA�Œ�ł�2���ԁi48���ԁj�A�~�d�r����d�͂������ł���B �_�U�����n�k�̗��N�A�~�d�r�݂����u���G�l���O���͔��d���v���ғ����n�߂��B���v�o�͂�36MW�A�~�d�r�͏o��18MW�E�e��130MWh���́A��^���͔��d�ɉ����A�ЊQ�Œn�悪��d�������ɁA�����ɓd�C�������ł��Ȃ����Ɨv�]��`���Ă����B �o�T [���r�W�l�X] |
|
|
| ���c�_�^���z���̓]�p���A2021�N�x��851���ʼnߋ��ő��A21���Ɏx��� �_�ѐ��Y�Ȃ́A�_�R�����Đ��\�G�l���M�[�@�ɂ��ăG�l���d�F�萔�̐��ڂ����\�����B �_�R�����ăG�l�@�́A�F������ăG�l�ݔ��E�����v��ɂ́A��1��_�n�̓]�p�̓���[�u������B2022�N�x�܂ł̊�{�v��̗v���萔��107�n��A���v�o�͂�151��3890kW�i1513.89MW�j�ƂȂ����B����́A���z����43��6409kW�A���͂�69��779kW�A���͂��E2030kW�A�o�C�I�}�X��38��4672kW�B���̂������d�J�n�ς݂�92�n��A117��231kW�B �c�_�^���z�����d�ݔ���ݒu���邽�߂̔_�n�̈ꎞ�]�p�́A2021�N�x�܂łɗv4349��1007.4ha�������ꂽ�B���Y�����_�앨�́A��Ȃǂ�32���A�Ϗܗp�A����31���A�ʎ���14���ȂǁA���܂��܂ȍ앨���͔|����Ă���B���̈���A2021�N�x����3314���̉c�_�^���z�����d�̂���690���Ɏx�Ⴊ�������B498���i72���j���P�������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���葱���ȑf���ɂ��A�h�C�c�ŗ��p�g��o���R�j�[�Ŏn�߂���\�[���[���d �h�C�c��2024�N4��1�����A�u�o���R�j�[�^���z�����d�@�v�̐ݒu�葱�����ȈՉ����ꂽ�B�����̂̕⏕���������A���Ə���p�̏����ȃ\�[���[�p�l�������������g�߂ɂȂ肻�����B �\�[���[�p�l���͎����ƂȂ玩��̉����ɂ����邪�A���݂̏ꍇ�͓���B�����Ŏg����̂��o���R�j�[�ݒu�^���B�o���R�j�[�ɑ��z�����d�@��ݒu���邱�Ƃ͑�Ƃɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ݎ҂͐ݒu���錠��������A��Ƃ͂ނ�݂ɋ֎~���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �ƘA�M�l�b�g���[�N�K�����iBNetzA�j�ł̊ȈՂȎ葱�������ōςށB���d�ʂ�800W�Ɉ����グ��ꂽ�B���[�^�[���g���A�����z���ڐ݂ł���B �z�[���Z���^�[�ŁA200���[���i��3���~�j���炠��B500���[���i��8���~�j���x���嗬���B����̃R���Z���g�ɍ������ނ����Ŏg���A�K���[�W�̉������A�܂������̓��̓�����Ƃ���ɒu�����Ƃ��ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r�̑�ʐω���ʎY�A���d�����ɒ��ޒ��� ���ƃv���W�F�N�g�Ƃ��ăy���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J���Ɏ��g�ޒ����ł́A�J���[�����ʐω��ȂǏ��ƊE�̃j�[�Y�ɉ����������i��ł��钆���E���]�ȍY�B�s�]�Y��ɂ����āA�]�Y�搭�{�r���ƁA�����J���Ə��ƃI�t�B�X�������Y�ƃp�[�N�̉���ɁA2,000���̃y���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu�A���d�d�͂̓r���ɋ�������B�ŔɃJ���[���z�d�r�i�y���u�X�J�C�g�ʎq�h�b�g�R�[�e�B���O���i�j���g�p�B UtmoLight�i�ɓd���\�j�̓K���X�|�K���X�\���̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��ؔ��d�������݂��Ă���B810cm2�̑�ʐσ��W���[���͑��z�d�r�̍��ۋK�i�ł���IEC61215�̃t���E�V�[�P���X�E�e�X�g�ɍ��i�����Ɣ��\���Ă���B UtmoLight�́A���Əd�_�����J���Ƃ��āu��ʐσy���u�X�J�C�g���z�d�r���W���[���̗ʎY�Z�p����є��d�����p���v���W�F�N�g�v�����F����Ɣ��\�����B �o�T�u���������V�X�e���v |
|
|
| ���Y�Ɨp�q�[�g�|���v�A�������ʐ���ȈՂɁ^�d�������V��@�A������Ƃ̕��y�㉟�� �d�͒����������́A�Y�Ɨp�q�[�g�|���v�̐��\���ȈՓI�ɐ���ł����@���J�������B���G�Ȍv�Z���s�����ƂȂ��A���������i�K�ŃG�l���ʂ̊T�Z�Ȃǂ�c���ł���̂������B���ϓI�Ȑ��\�̋@��̓����ɂ���Ċ��҂ł���COP�i�G�l���M�[��������j��10���ȓ��̐��x�Ő���ł���B�Y�ƕ���̒E�Y�f�ɏd�v�Ȗ�����S���Y�Ɨp�q�[�g�|���v�̓��������ɂȂ���B ���{�̎Y�Ɨp�q�[�g�|���v���i�i25�@��j�̃f�[�^�i588�_�j�����ƂɁA���\�����͂��A4�ɕ��ނ�����ŁA�G�l���M�[���\�𐄒肷���@���l�Ă����B�{��@�ł̓G�l���M�[���\��ΐ����ω��x���t�g�ɑΉ����郍�[�����c�����A�����COP�ŕ\������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����E�ő�O���[�����fPJ�ɁA1GW���z���p�l���^�W���R�\�[���[ �W���R�\�[���[�i�����E��C�j�́A�C���h�̌��ݑ��Larsen��Toubro�Ɛ헪�I��g�����сA�T�E�W�A���r�A�Ō��ݒ��̐��E�ő�̃O���[�����f�v���W�F�N�g�ɁA���Б��z���p�l���uTiger NeoN�^TOPCon�p�l���v1GW�������Ɣ��\�����B ���̃v���W�F�N�g�ł́A���z�����d�ƕ��͔��d��g�ݍ��킹�A2026�N���܂ł�600�g���^���̃J�[�{���t���[���f�Y���A�����A����Y�Ɨp�Ƃ��ăO���[���A�����j�A�ɕϊ�����B L��T�́A���z�����d���i2.2GW�j�A���͔��d���i1.65GW�j�̃o�����X�v�����g�A�~�d�V�X�e���i400MWh�j�̌��݂�S������B�Ȃ��A���v���W�F�N�g�ɂ́A3��380kV�ϓd����306km��380kV�ˋd���̌��݂��܂܂�Ă���B�Ȃ��A�v���W�F�N�g�̐��Y�H���ACWA Power�i�T�E�W�A���r�A�j�ANEOM�i���j�����AirProducts�i�č��j���������L����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���P�[�u������Ɂu�S���v���e�N�^�[�v�A�O�b�h�t�F���[�Y���� ���z�����d���̓��������T�C�g�u�^�C�i�r���d���v���^�c����O�b�h�t�F���[�Y�́A�X�}�[�g�p���[�V�X�e���Ƌ�����悵���A���z�����d�ݔ��̓�����������i�u�^�C�i�r�v���e�N�^�[�v�\�����B���Ђ��̔��E����钆�Ñ��z�����d���ɓ������A�^�C�i�r���d����7�����{����̔�����B �^�C�i�r�v���e�N�^�[�́A�����P�[�u���S�̂����^�̋������v���e�N�^�[�ŁA�����I�ɃP�[�u����ؒf�ł��Ȃ��悤�ɕی삷��B�ޓ��Ƃ���Ɏg�p����Ɩ��p�n�T�~�ȂǂŃP�[�u����ؒf�ł��Ȃ����邱�ƂŁA���Y���d���̐ޓ��̗D�揇�ʂ�������B�V���v���Ȑv�̂��ߊȒP�Ɏ{�H�ł���B�{�H�R�X�g��50���~���������x��z�肷��B �^�C�i�r�v���e�N�^�[�̂ق��ɂ��A�h�ƃJ������A���~�P�[�u���ȂǁA�ڋq�̗v�]�Ɨ\�Z�ɍ��킹�ē������Ă��Ă����B�ߔN�A�����i�̍�����w�i�ɁA���z�����d�ݔ����̓����P�[�u���̐ޓ��������������Ă���i2022�N�x��Q������2300���j�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z�H�ƁA�S�����������p�����~�d���u�ł̉w�v�̒~�d�ݔ��p�������{�H ���z�H�Ƃ́AJR��B��Z�F�����Ȃǂ��o������ł̉w������Ђ���A�u�ł̉w��K�v�̎{�H�����H�����Ɣ��\�����B �u�ł̉w��K�v��EV�̎g�p�ς݃o�b�e���[�����p���Ă���B�o�͂�1.5MW�ŁAEV�����[�X�o�b�e���[��350�䕪�����[����B���z�H�Ƃ͍���A���d���̒~�d�ݔ��p���������������B�����́A�����̍��g�݂ɖ��ށi���n�j��킹�Đݒu���閌�\�����̗p�B�e���g�^�̑q�ɂ͏_��Œn�k�ɋ����A�ωΐ���ϋv���ɂ��D��Ă���A�댯���q�ɂƂ��ċ@�\����Ƃ����B �ł̉w�́A��B�G���A�S���ԗ�����JR��B�̎��Ɗ�Ղ����݂ɁA�S���l�b�g���[�N��̉����n��V�x�n�����p����~�d���ƁB�ł̉w���T�[�r�X�v���b�g�t�H�[���Ƃ��A��펞�ɂ͕��݂���EV�[�d�X�|�b�g��n��ɊJ�����A�~�d�X�e�[�V��������d�͂���������ȂǁA�n��Ɉ��S�E���S��͂���n��G�l���M�[�T�[�r�X����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������V���R�����z�����Ɍy�ʉ��A���Z���ƃf���\�[���H��Ŏ��� ���Z���ƃf���\�[�́A���m�������s�̃f���\�[�������쏊�ɂ����Čy�ʃ^�C�v�̑��z�����d�V�X�e����������B�ωd�̖��ŏ]���̑��z�����d�V�X�e�����ڂ����Ȃ������H��̉����ɂ��ݒu�ł���B �f���\�[�������ɕۗL����H�ꉮ���̖ʐς͖�150��m2�ɂȂ邪�A1981�N�ȑO�̑ϐk��Őv���ꂽ�H�ꉮ���́A�]���̑��z�����d�̉d�ɑς��������Ă��Ȃ��B�����ŗ��Ђ́A�����̍H�ꉮ���ɂ��ݒu�\�ȑ��z�����d�V�X�e���̌�����i�߂Ă����B �V���R���P�����Z���i���d�f�q�j���̗p���A���z���p�l�������^�����ĉd�����̌������H�ꉮ���ɍœK�Ȍ`�ʼnd�U�ł���\���Ƃ����B����ɂ��Œ���@�Ƃ��邱�ƂŁA������e�Ղɂ��ă����e�i���X�������サ���B�Œ����Ȃǂ��܂ރV�X�e���S�̂ŏ]����2����1�̏d����ڎw�����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Ə���z���̒�ď����쐬�A���d�ʗ\���ȂǑ�s AiNERGY�i�A�C�i�W�[�j�́A���Ə���^���z�����d�̉c�Ǝx���T�[�r�X�uREKOBOSHI�i���R�{�V�j�v�\�����B ���Ǝ{�݂�H��Ȃǂ̌����Ɏ��Ə���^���z�����d��ݒu����ꍇ�A�����̌`��A�����A�X�ȂǏ������Č����Ƃɂ��ׂĈقȂ邽�߁A���x�Ȑv�͂����߂���B�܂��팸�ł���d�C�����̌v�Z���ώG�ɂȂ�A��Ă܂Ŏ��Ԃ��|�����Ă����B�܂����Ԃ��|���Ă��K�������ł���Ƃ͌��炸�A���ɒ�����EPC�T�[�r�X���Ǝ҂ł͍̎Z������Ȃ��̂��ۑ肾�����Ƃ����B REKOBOSHI�́A�Y�ƌ������Ə���^���z�����d�ݔ���ΏۂɁAEPC�T�[�r�X���Ǝ҂���Ă܂łɊ|�����Ƃ̑������A�E�g�\�[�V���O�ł���B�ڋq��1�N�Ԃ̓d�͎g�p�ʁi�f�}���h�f�[�^�j�擾�T�[�r�X�A���d�V�~�����[�V�����T�[�r�X�A��ď��쐬�T�[�r�X�Ȃǒ���B���i�Ɣ[���́A��ď��쐬�T�[�r�X��2��2000�~��2�c�Ɠ��B3D���d�V�~�����[�V�����T�[�r�X��3��3000�~��3�c�Ɠ��B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���L���m���A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̒��ԑw�ɗL�@�����̍ޗ��ŁA�ϋv���E�ʎY���萫�̌���Ɋ�^ �L���m���́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̑ϋv������їʎY���萫�̌��オ���҂���鍂�@�\�ޗ����J�������Ɣ��\�����B���킹�āA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗ʎY�Ɏ��g�ފ�ƂƂ̋��ƂɌ����āA���ޗ��̃T���v���o�ׂ��J�n�����B����A����Ȃ�Z�p�J����i�߁A2025�N�̗ʎY�J�n��ڎw���B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A�y���u�X�J�C�g�w�i���d�ϊ��w�j���̌����\������C���̐����E�M�E�_�f�Ȃǂ̉e���ɂ�蕪���E�������₷���A�ϋv���ɉۑ肪�������B�܂��A��ʐς̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�͗ʎY���萫���Ⴂ�̂��ۑ肾�����B�V�ޗ��́A�������d�ϊ��������ێ����Ȃ���A�y���u�X�J�C�g�w��100�`200nm�i�i�m���[�g���j�̌����Ŕ핢�ł���B���̂��߁A�y���u�X�J�C�g�����\���̕����E������}�����A�ϋv������ɍv������Ƃ����B���������ɂ���������ϋv�����Ŕ��d������20���ቺ����܂ł̎��Ԃ���6�{���サ�����Ƃ��m�F�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���G�A�R�����O�@�ɎՔM�h���h���T�[�r�X�^�L���O�W�� �L���O�W���ƃR�o���V�́A�@�l�����Ɂu�G�A�R�����O�@�ւ̎ՔM�h���h���T�[�r�X�v���J�n�����B �I�t�B�X�r���⏤�Ǝ{�݂Ȃǂ̃G�A�R�����O�@��ΏۂƂ��ACO2�r�o�ʁE�d�C��팸�Ɍq����B�G�A�R�����O�@�Ǝ��ӂ̏��ɎՔM�h���̓h�����s�Ȃ��A���l�̎ՔM�h����h��������p���[�o�[��ݒu����T�[�r�X�B�G�A�R���̉ғ��������グ�A�N�Ԗ�10�`20%��CO2�̔r�o�ʁE�d�C��̍팸����������B ��x�{�H�����13�`15�N�̑ϋv��������A�{�H��p�𐔔N�ʼn���ł���Ƃ��Ă���B�g�p����ՔM�h���́A���z�M�̔��˗����90���ȏ�L�[�v���Ȃ���A�h�����̒���r�[�Y�ɂ��f�M�w���`�����邱�ƂŁA�ՔM���ƒf�M���𗼗��B�ď�̎��O�@�̉��x�㏸��}����B��p���[�o�[�̐ݒu�́A�Ă����łȂ��~�ɂ����ʂ��B��p���[�o�[�ɂ͎ՔM�h�����h������Ă��邽�߁A�ď�͂Ђ�������ƂȂ�A���O�@�̉��x�㏸�}���ɂȂ���B �o�T�u�C���v���X�v |
|
|
| ���n���p�~�d�r�̐ڑ��_��A1�N��3�{���A3GW������ �o�ώY�ƏȂ́A�n���p�~�d�r�̓����̌���ƍ���̌��ʂ��ɂ��Č��\�����B�n���p�~�d�r�̐ڑ������E�ڑ��_��̌����́A����1�N�ԂŖ�R�{�ɋ}�����Ă���A������������i�ތ����݁B �n���p�~�d�r�̎�t�́A2023�N5�������_��11.89GW�A�ڑ��_��1.12GW�������̂ɑ��A2024�N3�������_�ł͐ڑ�������39.97GW�A�ڑ��_��3.31GW�ƁA���������3�{�ɑ��������B �Ȃ��A2030�N�̌n���p�~�d�r�̓������ʂ��́A�n���ڑ������\������10�������Ɖ����ꂽ�ꍇ�ŗv��14.1GWh�A20�����Ɖ����ꂽ�ꍇ�ŗv��23.8GWh�Ɛ��肷��B2023�N5�������_�̐ڑ���������ڑ��_��Ɉڍs�����Č�������10�����������Ƃ���ɁA����~�d�r�R�X�g�ጸ�ȂǂŎ��Ɖ������m�x���オ�����ꍇ�ɖ�20���Ƒz�肵���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ����4����SMR�����H�^�ăe���p���[�̎��ؘF�A2030�N�܂łɊ����� �ăe���p���[�́A���C�I�~���O�B�ŏ��^���W���[���F�iSMR�j���ؘF�̒��H�����J�����B �F�^��GE�����j���[�N���A�G�i�W�[�Ƌ����J������i�g���E����p�����F�u�i�g���E���v�i�d�C�o��34��5��kW�j�ŁA��4����F�^��SMR���H�͕č����B���T�ɂ͕ă}�C�N���\�t�g�n�Ǝ҂Ńe���p���[�̉�߂�r���E�Q�C�c���⓯�B�̃}�[�N�E�S�[�h���m���炪�o�Ȃ����B2030�N�܂ł̊�����ڎw���B ���v���W�F�N�g�ł́A�����ėn�Z���x�[�X�̃G�l���M�[�����V�X�e�����\�z���A�ő��5���ԁA�v50��kW�̏o�͂��m�ۂ���B���،�A���Ɖ^�]���s�����Ƃ�ڕW�Ƃ���B�č��G�l���M�[�ȁiDOE�j�̎����㌴�q�F���v���O�����iARDP�j�̈�Ƃ��Ė�20���h���i��3100���~�j�̕⏕������B �e���p���[�̓Q�C�c�����o����2006�N�ɐݗ��BGE�����̂ق��A���{���q�͌����J���@�\�ƎO�H�d�H�ƂƂ����͊W�����ԁB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��CO2�A�Ϗ��q�ň��蒙���^���{CCS�����A4�N���u�R��v�Ȃ� ���{CCS�����̓Ϗ��qCCS���؎����Z���^�[�̎��@��A�J���ꂽ�B���Z���^�[�ł�2016�`2019�N�x�A�o�����Y�̖k�C������������r�o������_���Y�f�iCO2�j���E������A�Ϗ��q�`�̊C�ꉺ�̒n�w�ɒ��������B ���݂͒n�w����CO2�̓���������U���E�n�k�A�C�m���Ȃǂ����j�^�����O�B�����������CO2�̘R�������Ȃ����Ƃ�n���Z�����͂��ߍ����O�̊W�҂ɍL�����M���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ����唭�x���`���[�ACO2�����E����̐V���u�J���ő�97���܂ŔZ�k ��B��w���X�^�[�g�A�b�v��JCCL�́ACO2�����E������u�̐��i���ɐ��������Ɣ��\�����B1����CO2���A75���ȏ�̔Z�x�܂ŔZ�k�ł��邱�Ƃ��m�F�����B VPSA1�A1��2kg���x��CO2��97���ȏ�ɔZ�k�E����ł���̂������B�������ꂽCO2�ܗL�K�X���ő̋z���܂ɋ������āACO2���z�������邱�ƂŁA���Ύ��x���������䂳�ꂽ�������C���ʋ�������d�g�݂��B�����̋@�\�����A�ő̋z���܁u�A�~���ܗL�Q���v���œK�����Ŏg�p�����ꍇ�A�Z�x7����CO2��97���ȏ�̔Z�x�܂ŔZ�k�ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���B���̌ő̋z���܂��g�p�����ꍇ�̃R�X�g�́A�]����@�ɔ�ׂāA�ő�4����1���x�ɂȂ�Ƃ����B�Ȃ��A���݂́A���ȃv���W�F�N�g��ʂ��āA�����̊�ƂƘA�g���A�X�P�[���A�b�v�������u�̐v�J������у��^�l�[�V�����v���Z�X�̎������{���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ߘa5�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���v�i�G�l���M�[����2024�j���t�c���� �G�l���M�[�����ł́A�G�l���M�[������A�G�l���M�[�̎����{��ɉ����A���L�ɏœ_�ĂďЉ�Ă���B (1�j���������̐i�� (2�j�J�[�{���j���[�g�����Ɨ��������G�l���M�[�Z�L�����e�B�̊m�� �E�T�v���C�`�F�[���S�̂̊ϓ_����A�u�G�l���M�[�Z�L�����e�B�̊m�ہv���d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��� �E�ΒY��V�R�K�X�̎s�ꉿ�i��2010�N��㔼��2�`3�{�̐����ƂȂ��Ă���B����̉��i���ʂ��͈ˑR�s���� (3�jGX�E�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ������ۑ�ƑΉ� �E���{�́A2030�N�x��46%�팸�ڕW�Ɍ����āA�����ɍ팸���i�����Ă��� �E2023�N7���ɁuGX���i�헪�v������A���f���ECCS�̖@���������i�W �ECOP28�Łu���E�S�̂ōăG�l���d�e��3�{/�G�l���M�[�������P��2�{�v��i�߂邱�Ɠ����L�ڂ��ꂽ �C��ϓ���Ƃ��āu���q�́v�����߂Ė��L���ꂽ�B���{�́u���q��3�{�錾�v�ɂ��^�������B �o�T�u�����G�l���v |
|
|
| ���ĎЂ�10GW�̃E�G�n�[���Y�v���P��A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�Ƃ̃^���f���^�ɕύX�� ���z�����d���[�J�[�̃L���[�r�b�NPV�iCubicPV�j�́A�č���10GW�̃V���R���E�G�n�[�i�V���R������j�H������݂���v���P�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �v�撆�~�̗��R�Ƃ��āu�E�G�n�[���i�̌��I�Ȗ\���ƌ��ݔ�̍����v���܂ގs����̕ω����������B�����͐��E�̃E�G�n�[�����{�݂�97����ۗL���Ă���A����A�W�A�ɏ��݂����Ƃ�ʂ��Đ��E�̃E�G�n�[���Y�\�͂�99���ȏ�������Ă���� ���Ă���B�č��ɂ����錚�ݔ�́A�V�^�R���i�E�C���X�̃p���f�~�b�N�ȍ~�A���ޗ���ƘJ����̏㏸�ɂ��}�����Ă���B���������Ȃ��A���Ђ̓����헪���}�W�J���Ă���B�L���[�r�b�NPV�̓V���R���e�N�m���W�[�̑���ɁA�^���f���i���ڍ��j�^���z�����d�̐��Y �Ɏ��g�ނƔ��\�����B�L���[�r�b�NPV�́A�y���u�X�J�C�g�ƃV���R���̃^���f���^���z�d�r�̃X�P�[�����O�i�����j�v�ŁA�ϋv���A���S�ȑ��z���p�l����v���邱�Ƃ�ڎw���BDOE����600���h�����x�������B �o�T�u���oTECH�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/7�@]�@�@�� |
|
|
| �������ȂǁA�y���u�X�J�C�g�����A�Ϗ��q�`�̎{�݂� �����A�G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�A�Ϗ��q�u����3�Ђ́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��p���Ɍ��������؎�����{�i�I�ɊJ�n�����B �����q�ɂ̉����ƕǖʂɃy���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu���A���d�f�[�^���擾����B�܂��A�ቷ�E�ϐ�E���Q�Ƃ�������������{�H���@���܂߂��ϋv���ƐM������]������ƂƂ��ɁA3�Ћ����ŕ��y�Ɍ����Č�������B�{�H���@�́A�����̃V�[�g�H�@���̗p�B�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̓����ł���y���E�����E�Ȃ���Ƃ������������đ���ƂȂ�ՔM�V�[�g����̉����A�ܔ�����ǖʂɌŒ肷��B�V�[�g��̂܂ܓ\��t���邽�ߏꏊ��I���ݒu�ł��A��R�X�g�Ń��v���[�X���e�ՂƂ����B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�̓G�l�R�[�g���ŁAG2�T�C�Y�i370�~470mm�j6���̃A���C���\�����A�����{�݂̉����Ɖ^�͌����쑤�ǖʂɂ��ꂼ��ݒu�����B�o�͂�12�����v��150�`200W�B���؊��Ԃ͓���2025�N3��31���܂ł�1�N�Ԃ̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�J���K���X���ވ�̌^�ɍi���Đ��i�� �p�i�\�j�b�N�́A�K���X���ވ�̌^�ɍi���āA���i����ڎw���B�����̑��⑤�ʁA�o���R�j�[�A�V���[�E�C���h�E�ȂǗp�r�͑��l�B23�N8������̎��؎����ɑ���4������1.0�~1.8���[�g���̎��색�C���𗧂��グ���B �_�ސ쌧����s��Fujisawa�T�X�e�B�i�u���E�X�}�[�g�^�E���ŁA���ވ�̌^�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�i�ȉ�PSC�j�̎��؎������J�n�����B�V�݂��ꂽ���f���n�E�X��2�K�o���R�j�[�i��3876mm�~����950mm�j�ɁA�O���f�[�V������̓��ߐ��̃K���X���ވ�̌^PSC�̃v���g�^�C�v�����^�̃��W���[���Ƒg�ݍ��킹�Ĕz�u���A�ډB�����Ɠ��ߐ��𗼗������f�U�C���Ⓑ���Ԑݒu�ɂ�锭�d���\�A�ϋv���Ȃǂ�������B �K���X���ވ�̌^PSC�Ƃ́A���z���ނł���K���X���ɒ��ځA���d�w���`���������z�d�r�B�����̑��⑤�ʁA�V���[�E�C���h�E�A�g�b�v���C�g�ȂǁA�K���X���g����ꏊ�ł���ǂ��ł��ݒu�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���z���_�A�����EV�[�d�ł���T�[�r�X�J�n�^�r�b�O�J������ENEOS�ƘA�g �{�c�Z���́A����ł�EV�[�d���T�|�[�g����e��T�[�r�X�̒��J�n����Ɣ��\�����B�T�[�r�X�̒�g��́A�r�b�N�J������ENEOS Power�ŁAHondaCars��ʂ��Ē���B �r�b�N�J�����̎���[�d��ݒu�T�[�r�X�ł́A�R���Z���g�^�C�v�AAC�NJ|���^�C�v�i3kW�A6kW�j�AV2H�iVehicle to Home�j��3��ނ̏[�d������B�S���̌ˌ��ďZ��ΏہBHondaCars�����[�U�[�̎g�p����j�[�Y�ɉ����čœK�ȏ[�d����āB �r�b�N�J�����́A���ς���{�H�A�A�t�^�[�T�[�r�X�܂ł������X�g�b�v�Œ���BENEOS�ł�����̂́A���Ђ̓d�C�������j���[�uEV��Ƃ��v�����v�B����Ȃǂ�EV�^PHEV���[�d���郆�[�U�[�����̎��ԑѕʓd�C�������j���[�ŁA�����ߑO1������5���ɐݒ肵���uEV�^�C���v�ł́A�ቿ�i�œd�C�𗘗p�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�C�I�K�X���p�����������^���A�����@��ł̎g�p���^��K�X ���K�X�́A���s�Ȃǂ̋��͂̂��ƁA2022�N4�����ăG�l�R���̐��f�ƁA�����݂y�����Đ��������o�C�I�K�X�Ƃ����^�l�[�V�����i���^�������j���A�������ꂽ���^����z�ǂŗA�����A�s�s�K�X����@��ŗ��p����Ƃ����T�v���C�`�F�[���\�z��ڎw�����؎��Ƃ����{���Ă���B ���s�̂��ݏċp�H��̕~�n���ɁA���^�l�[�V�������ؐݔ������������B�{���Ƃ́A�ăG�l�R�����f�ƒn��̖����p�o�C�I�}�X�����p���Đ�������e-���^���ɂ���_���Y�f�i�ȉ��uCO2�v�j�r�o�ʂ̒ጸ��}��A�G�l���M�[�̒n�Y�n���^���f���\�z��ڎw���B���̌�A�������̉����Ŏ����s���\��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����D�O��^�h���C�o���N�^�q�D7�ǂɃE�C���h�`�������W���[���� ���D�O��ƃO���[�v��Ђ̏��D�O��h���C�o���N�́A���D�O��h���C�o���N���^�q����V����ςݑD����ё��ړI�D�v7�ǂփE�C���h�`�������W���[�i�d���������͐��i���u�j���܂ޕ��͐��i�⏕���u�𓋍ڂ�����j�\�����B �E�C���h�`�������W���[�͏��D�O��Ƒ哇���D�������S�ƂȂ�J�������A�L�k�\�Ȕ��ɂ���ĕ��̓G�l���M�[��D�̐��i�͂ɕϊ����鑕�u�B���ɏv�H�������ڑD�u�����ہv�ł́A1���ő�17���̔R���ߌ���GHG�팸���ʂ��m�F����Ă���B ���ڂ����߂��h���C�o���N�^�q�D7�ǂ̂����A�V����ςݑD6�ǂɃE�C���h�`�������W���[��1�{�����ڂ�����j�B�����āA���D�O��h���C�o���N������p�D��\�肵�Ă���V�����ړI�D1�ǂɑ��ẮA�I�����_���̕��͐��i�⏕���u�u���F���g�t�H�C���v��2�{�𓋍ڂ��邱�Ƃ����肵���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��PXP��A�Ȃ��鑾�z�d�r�𓋍ڂ���EV�O�֎Ԃ̎��؎������J�n �����㑾�z�d�r�̊J�����肪����PXP�́A�Ȃ��鑾�z�d�r�𓋍ڂ���EV�O�֎Ԃ̎��؎������J�n�����Ɣ��\�����B ���́A�����ヂ�r���e�B�[�̊J����i�߂�EV�W�F�l�V�X�Ƌ����ōs���B���Ђ��J�n�������ł́A�����̎��p���������܂��y���u�X�J�C�g�^�J���R�p�C���C�g�̃^���f���\����p�����Ȃ��鑾�z�d�r�����p����B ���؎ԗ��̉����ɓ\��t�����p�l���́A�d��1kg�����E����1mm�ȉ��̒��y�ʁE�����^�v�B1���̑��z���ɂ�锭�d�݂̂ŁA�ő�20km���s�ł��錩���݂��B�Ȃ��A���݊J�����̃y���u�X�J�C�g�^���f���^�̋Ȃ��鑾�z�d�r�ɃA�b�v�O���[�h�����ꍇ�́A1���̔��d�ōő�30km�̑��s���\�ɂȂ�Ƃ����B���Ђ́A�Ȃ��鑾�z�d�r�̎��p���ɂ��A����̋ߗׂւ̈ړ����x�ł���A�[�d�Ȃ��ɍăG�l�݂̂ŃJ�o�[�ł���悤�ɂȂ�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������̊C�ŕ��̎����z�����d�A���}�s���Y�炪�����X�^�[�g ���}�s���Y�ƃI�����_��SolarDuck�Ђ́A�����̍`�p���ɗm�㕂�̎����z�����d�ݔ��̐ݒu�����������Ɣ��\�����B�����s�́u�����x�CeSG�v���W�F�N�g��s�v���W�F�N�g�ɍ̑����ꂽ���́B ���̐�s�v���W�F�N�g�́A�����s�ɂ�铌���x�C�G���A���琢�E�Ő�[�̔��M��ڎw�����؎��ƁB���}�s���Y��SolarDuck�Ђ́A2022�N11���ɃG�o�[�u���[�e�N�m���W�[�Y�ƂƂ��Ɂu�Ő�[�Đ��\�G�l���M�[�v�̕���ō̑�����Ă���A���Ɍ���������J���Ɏ��g��ł����B ����A�����|�ŃG���A�̍`�p���ɐݒu�����m�㕂�̎����z�����d�ݔ��́A���d�e��80�`100kW�B���̎��̉ˑ�����p�����V�X�e���ŁA�ݔ��K�͂͏c30����26���~����6���ƂȂ��Ă���B���d�����d�͂͒n��ɑ��d���A�e��60kWh�̒~�d�r�ɏ[�d���s���B���̓d�͉͂^���\�ȃ��o�C���o�b�e���[�̏[�d�Ɋ��p���A�d�����]�Ԃ��͂��߂Ƃ���d�����r���e�B�Ŋ��p����v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����_���Y�f����uCCS�v���p���֎��Ƌ����x�Ȃǂ̖@�������� �@���ł́A������_���Y�f�߂�������w�肵�������ŁA����ɂ���đI�ꂽ���Ǝ҂�CCS���Ƃ̋���^����Ƃ��Ă��܂��B ���������Ǝ҂́A��_���Y�f�߂�̂ɓK�����n�w���ǂ����m�F���邽�ߌ@�킷��u���@���v��A���ۂɓ�_���Y�f�߂���u�������v���^�����܂��B����ŁA���Ǝ҂́A��_���Y�f���R��Ă��Ȃ����Ď�����`��������A�R�����ɂ�鎖�̂Ȃǂ����������ꍇ�́A�̈ӂ�ߎ������������ǂ����ɂ�����炸�A�����ӔC���ƒ�߂��Ă��܂��B���̂ق��A������̃G�l���M�[�Ƃ��Ċ��҂���鐅�f�Ȃǂ̂���Ȃ镁�y�Ɍ����āA�V�R�K�X�ȂǂƂ̉��i���߂邽�߁A�⏕�����x�����鐧�x�̑n�݂Ȃǂ荞�@�����^�������ʼn��E���������B �o�T�uNHK�v |
|
|
| ���n���p�~�d�r�ڑ��\�����݁A�}�g��^2700���L�����b�g�ɓ��B�A�G�l���܂Ƃ� �Đ��\�G�l���M�[�̓����g����A�n���p�~�d�r�̐ڑ��\�����݂��E�����Ă���B �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���ɂ��ƁA�S��9�G���A���v��2700��kW�i2023�N�����_�j�ɒB�����B2023�N���ɖ�3�{�ɑ������Ă���B���ɁA�k�C���A�����A��B�������ŁA�������500��kW�����B �����͂̋��o�悪���������Ƃ�����A���Ɖ��ɏ��o���P�[�X���������ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r���������Ȋ����H�V�����[�J�[�̓����� �����ł́A�x���`���[��Ƃ�������z�d�r�����E�J����ƂȂǂ̎Q�����������L�@�������z�d�r��y���u�X�J�C�g���z�d�r�B�������A�������V���R�����z�d�r�Ȃǂ̎�v���i�̐��Y�ʂ����|�I�ɑ����B �����ł́A2015�N������y���u�X�J�C�g���z�d�r�֘A�̃X�^�[�g�A�b�v��Ƃ������ݗ��A2020�N�ȍ~�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̗ʎY���Ɍ��������g�݂��}���ɐi�݁A�����x���`���[��Ƃ�������z�d�r�����E�J����ƂȂǂ̎Q�������������B �����̊�Ƃ��w�����������ł̓����擾��i�߂Ă���ƌ����A�����J�������͌������A��K�͂Ȑ��Y���C���ݗ��Ɍ����A�������B�����̔��\���������B�����ɂ�����y���u�X�J�C�g����̌��������������Ă���A������ΐ��N��ɂ�GW�P�ʂ̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐��Y���C��������Ƃ����X�Əo�Ă���Ɨ\�������B �䈟猁A����D�ԂƂ����������ԃ��[�J�[��A�������q�͔��d���̒����j�H�ƏW�c���J���ɏ��o���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�Ŋ������c��A�����ڕW���쐬�� �o�ώY�Ƒ�b�́A������^���z�d�r�̓����g�储��юY�Ƌ����͂��������邽�߂̑����I�Ȑ헪�����肷�銯�����c����J�Â���ƕ\�������B �L���ҁA���[�J�[�A��`�E�S���A���ޗ��A���݁E�s���Y�Ȃǂ̊W�ƊE�c�́A����ɍĐ��\�G�l���M�[�����ɐϋɓI�Ɏ��g�ގ����̂ȂǁA���L�������W�҂̎Q�������߂Ă����B�����ڕW�≿�i�ڕW�̍���A�����T�v���C�`�F�[���̍\�z�A���v�̑n�o�A���ەW���̍���ȂǁA���O�s��̊l���Ɍ������Ή��Ȃǂ���������B �L�҉�ɂ����āu�����A�g�̉��ŁA���E�Ɉ��������Ȃ��K�͂ƃX�s�[�h�̗��ʂœ������������A�����㑾�z�d�r�̕���Ő��E�����[�h���Ă��������v�Əq�ׂ��B�o�ώY�ƏȂł́A�������y�Ɍ����āu�ʎY�Z�p�̊m���v�u���Y�̐��̐����v�u���v�̑n�o�v�B�ʎY�Z�p�̊m���ł́AGI�����i�O���[���C�m�x�[�V���������j�����p����B���Y�̐��̐����ł́A2030�N�܂ł̑�����GW�i�M�K���b�g�j���̗ʎY�̐����\�z����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��������~�d�r�A�ăG�l���y�Ŏs��g��A���h�b�N�X�t���[���L�] ���o�ό������́A������d�r�̐��E�s��Ɋւ��钲�����ʂ\�����B����ɂ��ƁA2023�N�̎s��K�͂�1��2333���~�̌����݁B�{�i�I�Ȏ��p����2025�N�܂���2030�N�ȍ~�ɂȂ�Ɨ\�z����A2035�N�ɂ�2023�N��Ŗ�6�{��7��2763���~�܂Ő�������Ɨ\������B �������̑ΏۋZ�p�́A�_�����n�S�ő̃��`�E���C�I���d�r�iLiB�j�A�������n�^�����q�n�S�ő�LiB�A�i�g���E���d�r�A���h�b�N�X�t���[�d�r�Ȃ�9��ށB 2023�N�̓��s��́A�d�͌n���p��u�p�~�d�r�̎��v���ɂ��A��^�̃��h�b�N�X�t���[�d�r���傫�Ȋ������߂錩���݁B�܂��A�_�����n�S�ő�LiB�ɂ����āA�����𒆐S�Ɍő̓d�����ɓd���t��Q���|���}�[��Y���������ő̓d�r�̐��Y���ꕔ�ŊJ�n�B�i�g���E���d�r�������C�d�r���s��`�����n�܂��Ă���B2035�N�́A��ޕʂł̓��h�b�N�X�t���[�d�r��4��4755���~�̌����݁B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���C�[���r���e�B�p���[�E�������x�A������d�u�[�d��J���� �C�[���r���e�B�p���[�Ɠ������x�́A�d�C�����Ԍ���������}���[�d��������J������Ɣ��\�����B ���E�ŏ��߂�CHAdeMO�i�`���f���j2.0�K�i�ň���ő�o�͂�350kW�Ƃ���B���ĂŌ��ݕ��y���鑼�̋K�i�̏[�d�@�Ɣ�ׂĂ������o�͂ŁA�Ή�EV��10���[�d�����ꍇ�A��400km�𑖍s�ł���v�Z�B �K�\�����ԂƓ����̎g��������m�ۂł��錩���݂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2024/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���I���b�N�X�q��ЁA�g�p�ςݑ��z���p�l���̔̔��E�����[�X�J�n �I���b�N�X���ƃI���b�N�X�E���j���[�A�u���G�i�W�[�E�}�l�W�����g�iOREM�j�́A���z�����d������r�o�����g�p�ςݑ��z���p�l���̍����̔�����эĎg�p�i�����[�X�j���J�n����Ɣ��\�����B �I���b�N�X���́A���z�����Ǝ҂Ȃǂ��甃����������܂��܂ȃ��[�J�[�E�^���̎g�p�ςݑ��z���p�l�����A���d���Ǝ҂�O&M�i�^�c�E�ێ�j���ƎҌ����ɍ����̔�����B���r�̗L���┭�d�ɖ��Ȃ����Ƃ��m�F���������Ŕ̔�����B�����[�X�s�̃p�l���̓}�e���A�����T�C�N���܂��͓K���������s���B������OREM�́AO&M��������鑾�z�����d���ɂ����Ďg�p�ςݑ��z���p�l���̍Ďg�p���J�n����B�p�l���������Ɋ��p���邱�ƂŁA���B�R�X�g�̍팸�┭�d�̑����ɍv������Ƃ��Ă���B OREM�́A��190�J���A��700MW��O&M��������Ă���B�ߋ�5�N�ԂŎ��R�ЊQ�Ȃǂɂ��j���������z���p�l����3000���A700kW�����̓���ւ����т�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���w�Z�̉��㑾�z�����I�t�T�C�gPPA�ŋ����A���l�s���ŃG�l�n�Y�n�� ���}�s���Y�Ǝq��Ђ̃��G�l�́A�I�t�T�C�g�^PPA�i�d�͍w���_��j�X�L�[�������p���āA���l�s���̊w�Z����ɐݒu�������z�����d�ݔ��ȂǂŔ��d�����d�͂��A���}�s���YSC�}�l�W�����g���^�c�Ǘ����鉡�l�s���̑�^���Ǝ{�݁u�m�[�X�|�[�g�E���[���v�Ŋ��p���n�߂��B ���}�s���Y�́A2023�N2���ɉ��l�s���̏����w�Z�E�����w�Z�E���ʎx���w�Z53�Z��ΏۂƂ����A�I�t�T�C�g�^PPA�ɂ�鑾�z�����d�������Ƃ̎��{���Ǝ҂ɑI�肳�ꂽ�B�ΏۍZ�̉���ɐݒu���ꂽ���z�����d�ݔ��̓d�͂��w�Z���Ŏg�p����ƂƂ��ɁA�w�Z���x�݂ƂȂ�x���Ȃǂ̓d�͂�L�����p���邱�ƂŁA���l�s���f����u�s�s�^�n�Y�n�����f���v�\�z����������B �u�m�[�X�|�[�g�E���[���v�ւ̃I�t�T�C�g�^PPA�ł́A�s��20�Z�̉��㑾�z�����d�ݔ����v1.5MW�ƁA�����{��4�{�݂̉��㑾�z�����d�����v2.294MW�̓d�͂���������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{���S��A���f�����p���Đ��S�v���Z�X��E�Y�f���V���ȋZ�p�J�� ���{���S�́A�����n�ޗ������J���Z���^�[�iJRCM�j�Ƌ����ŁA�S�z�̊Ҍ��ɐ��f��p�������f�Ҍ����S�Z�p�ȂǁA���S�v���Z�X�̐V���ȒE�Y�f���Z�p�m���ɂȂ��錤���J�����J�n����Ɣ��\�����B����A2030�N�܂ł�CO2�r�o�ʂ�50���ȏ�팸�ł���V�Z�p�̊J���ɒ��肷��B ��̓I�ɂ́A��i�ʂ̓S�z�̐��f���ڊҌ�����d�C�n�Z�F�A�]�F�Ɏ���܂ł̈�уv���Z�X�ɂ��A���F�@�v���Z�X���ւ����鐶�Y�����i�L�S���Y��100�g���^���Ԉȏ�j��ڎw���B �܂��A��������S�̕s�����̔Z�x�����F�@���݁i���Ƃ��A����0.015���ȉ��j�ɐ��䂷��Z�p�ƂƂ��ɁA�d�C�n�Z�F�ɂ����ĕ�������X���O�������Z�����g�p�r�����̕i���i���Ƃ��Ύ_���S3���ȉ��j�ɐ��䂷��Z�p��������B���ƋK�͖͂�384���~�ŁANEDO�̎x���K�͂̓C���Z���e�B�u�z�܂ߖ�230���~�B���Ɗ��Ԃ�2024�N�x����2028�N�x�܂ł�5�N�Ԃ̗\��B �o�T�uNEDO�v |
|
|
| �����d�H�A���f30�����Ă̑�^�K�X�G���W�����ؐݔ��̊J���J�n�@8MW�� ���d�H�Ƃ́A���d�o��8MW���̑�^�K�X�G���W�����d�ݔ��ɂ����āA���f30�����ăt���X�P�[�����ؐݔ��̌��ݍH���ɒ��肵���Ɣ��\�����B ����̍H���́A�_�ˍH��ʼnғ����̓s�s�K�X��R���Ƃ���K�X�G���W�����d�ݔ��i���d�o��7.5MW�j�𐅑f���đΉ��d�l�ɕύX����Ƃ������̂ŁA��ɐ��f�����V�X�e���̒ǐ݂ƃG���W���R�Ď��̉������s���B 2024�N5���v�H�̌����݂ŁA���N10�����琅�f���ăK�X�G���W�����d�ݔ��Ƃ��Ẳ^�p���J�n����\�肾�B �o�T�u���d�H�Ɓv |
|
|
| ���h�z���邾���ŋݔ����ȃG�l�ɁA�}�N�j�J���ՔM�f�M�h���̔̔����J�n �}�N�j�J�́A��g�[��①�A�Ⓚ�ȂǂɎg�p���鎺�O�@�����̎ՔM�f�M�h���u�}�N�j�J�b�g�v�̔̔����J�n�����Ɣ��\�����B���O�@�Ȃǂɓh�z���邾���ŁA���̏ȃG�l���ʂ������߂�Ƃ����B �}�N�j�J�b�g�͑��z����̕��ː��ɂ��M������h�����߂̎ՔM�ƁA�M��`���Ȃ��f�M�����h���B�h���̎ՔM�@�\�ő��z�G�l���M�[��90���ȏ�˂��A�����ւ̔M�̐N����}������B�܂��A�n�`�̑���ɒ���r�[�Y�w���ψ�Ɍ`�������\���ƂȂ��Ă���A���ꂪ�f�M���ʂ������炷�d�g�݂ƂȂ��Ă���B ���Ђ̎��Z�ł́A���O�@�ւ̏ȃG�l�J�o�[�̐ݒu�ƁA���O�@�{�̂���ю��ӏ��ʂɃ}�N�j�J�b�g��h�z���邱�ƂŁA�N�Ԃ̏���d�͂��10�`15���팸�ł���Ƃ��Ƃ����B�ďꂾ���łȂ��~��ɂ����ʂ������߂�Ƃ��Ă���B �܂��A���O�@�ȊO�ɂ��A�����̊O�Ǔh���i�����E�ǁE�x�����_�Ȃǁj��L���[�r�N���̔M�̏��ɂ����p�\�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p��]�v |
|
|
| ��30���Ή��̑啗�ʂȂ̂ɐÂ��A�V���[�v���́u�T�[�L�����[�^�[�v�Ɂg�l�C�`���[�e�N�m���W�[�h�̗p �V���[�v�͂��܂��܂ȉƓd���i�ɁA������A���̌`���͂����l�C�`���[�e�N�m���W�[���̗p���Ă���B�Ⴆ�ΐ�@�̉H���ɂ́A�����̂Ȃ����炩�ȕ���͂��邽�߂ɒ��E�A�T�M�}�_���̉H�̌`��A���i���̍������ނ��߂ɃA�z�E�h���̉H���̌`��Ȃǂ��̗p����Ă���B �u�T�[�L�����[�^�[�v�ő�̓����́A�t�N���E�̗���͂����H�����̗p���Ă��邱�Ƃ��B�t�N���E�͖����Ŕ�Ԃ��Ƃ��ł���B���̍\�����T�[�L�����[�^�[�Ɏ����ꂽ�B�t�N���E�́A���̒f�ʂɂ���c��݂̕����ŋ�C�𑨂��ėg�͂�~���A���̌��̕����ŕ��̐������������邱�ƂŁA�Â��ɉH�����B���̃t�N���E�̗��̃e�N�m���W�[���t�@���̒f�ʂɉ��p�����B�����悭��C�𑨂��邱�ƂŁA�D�����^�]���ő傫�ȕ��ʂ邱�Ƃ��ł����B����ɒ��i�������߂�点���K�[�h��A���H���i�邱�Ƃŕ��̐��������߂�{�̍\���ɂ��A�u�ő�50dB���^�]���v�A�����ȃs�[�N�����}���邱�Ƃ����������B�v �o�T�uITmedia�v |
|
|
| �������MIT�A�u�~�d�R���N���[�g�v���p���Ɍ����A�g ����R���N���[�g�ƕă}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j�́AMIT�������J����i�߂�d�q�`�����Y�f�Z�����g�ޗ��uec3�v�i�~�d�R���N���[�g�j�̎��p���Ɍ����ċ�����������Ɣ��\�����B�Z����͂��߂Ƃ���Y�ƕ��삨��уC���t���ւ̎��Ȕ��M�R���N���[�g�̑������p���A���H�����d�̊J�����܂ށu�~�d�R���N���[�g�v�̎��p����ڎw���B �~�d�R���N���[�g�́A�J�[�{���u���b�N�i�Y�f�����q�j���R���N���[�g�ɓY�����邱�ƂŁA�R���N���[�g�n�f�ނɎ��ȉ��M����~�d�����������邱�Ƃ��ł���B �R���N���[�g�����Ő������������邱�ƂōE���`������B����A�J�[�{���u���b�N�͑a�����̐����������A�J�[�{���u���b�N���q���E�Ƀ��C���[��̍\�����`������B���̃R���N���[�g��d�����n�t�ɐZ�Ђ���ƁA�E�ɂ��d�����n�t����������A�J�[�{���u���b�N��ɓd�q���W�܂�~�ς���B�~�d�R���N���[�g�͓d�ɊԂ�d�q���ړ����邾���Ȃ̂Œ����I�Ȋ��p�����҂ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �������|���C�~�h��p�����y���u�X�J�C�g���z�d�r�̋����J���ɒ��� �A�C.�G�X.�e�C�́A�ˈ����l��w�̋{�⌤�����ƂƂ��ɁA�����|���C�~�h��p�����y���u�X�J�C�g���z�d�r�̋����J���ɒ��肵�����Ƃ\�����B ���@�\�f�ނ̊J���A�����A�̔����s���A�C.�G�X.�e�C�́A�ˈ����l��w�̋{�⌤�����ƂƂ��ɁA�����|���C�~�h��p�����y���u�X�J�C�g���z�d�r�̋����J���ɒ��肵�����Ƃ\�����B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�̔��d��������ɂ�200���ȏ�̍����������K�v�����A�������i��PET�t�B�������p�����ꍇ�A�ϔM�����s�����\���Ȑ��\���ł��Ȃ������B �����ŁA�A�C.�G�X.�e�C�͓Ǝ��J���̐V�f�ށuTORMED�i�g�[���b�h�j�v�̓��������āA���̉ۑ���������邱�Ƃɒ��킵���B�F���ł��g�p�����|���C�~�h�����Ő������ꂽTORMED����ɍ̗p�����ꍇ�A���������ɑς��邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐��\���オ���҂ł���B �o�T�uMONOist]�v |
|
|
| �����{�̉������ʃK�X�r�o�ʂ��ߋ��Œ�ɁI 2022�N�x�̉䂪���̉������ʃK�X�r�o�E�z���ʂ����\����A�ߋ��Œ�l���L�^�������Ƃ����炩�ƂȂ����B����̕ł́A�C�m���Ԍn����̋z���ʂ���z���^�R���N���[�g��CO2�Œ�ʂȂǁA�V���Ȏ��_����̕��͂��s���A���̌��ʂ����ێЉ������ڂ���Ă���B 2022�N�x�̔r�o�ʂ́A��10��8,500���g���ł���A�O�N�x���2.3���̌������������B�����2013�N�x����̌�������22.9���ɒB���A�����\�ȁu�I���g���b�N�v�i2050�N�l�b�g�[���ւ̈ڍs�j�̐��i�������Ă��邱�Ƃ������Ă���B���ɒ��ڂ��ׂ��́A��փt�������S�K�X�̔r�o�ʂ����߂Č����������Ƃł���B HFCs�ɂ��ẮA�t�����r�o�}���@�̉����ɂ��R��������t���A�r�o�ʂ����������B�܂��A�u���[�J�[�{�����Ԍn�ɂ�����C������̋z���ʂ̕�A���z���^�R���N���[�g�̋z���ʂ̎Z��ȂǁA���E�ŏ��߂Ă̎��݂��s��ꂽ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���A�����j�A�����A�Ϗ��q�łU�ИA�g�^�k�C���d�͂Ȃ� �k�C���d�́A�k�C���O�䉻�w�AIHI�Ȃ�6�Ђ́A�Η͔��d��e�Y�Ƃ̒E�Y�f���Ɋ�^����A�����j�A�̃T�v���C�`�F�[���i�����ԁj��k�C���Ϗ��q�n��ō\�z���錟���ɓ������Ɣ��\�����B�C�O�Ő��������A�����j�A��A���E�����E�������鋒�_�̐�����A�k���{�G���A�ł̎��v�J��Ɍ�����������i�߁A2030�N�x�܂ł̋����J�n��ڎw���B �����ɂ͊ۍg�A�O�䕨�Y�A�Ϗ��q�u����������Ă���B�Ϗ��q�n�擌���̖k�C���d�͓ϓ����^���d���i�ΒY�j�ɗאڂ����40�w�N�^�[���̓y�n��A�Ϗ��q�u�������n�搼���ɕۗL���钙���^���N���������_�ɂ������l�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����{�A2040�N�̂f�w�헪����ց^�E�Y�f�d�����p�𐄐i ���{��2040�N��ΏۂƂ����G�l���M�[�A�E�Y�f�A�Y�Ɛ���̐헪�uGX2040�N�r�W�����v�����肷����j���������B �G�l���M�[��{�v��̌������̋c�_�Ƒ����݂����낦�A�Đ��\�G�l���M�[�ȂǒE�Y�f�d�����W�܂�G���A�ł̎Y�Ɨ��n��Ȃǂ���������B�f�[�^�Z���^�[�ȂǑ�K�͂ȓd�͎��v�ɑΉ����鑗�d�������݂̍�����e�[�}�Ƃ���B ���s�́uGX���i�헪�v�W�������`�Ƃ��āA�N�x���ɂ��r�W�������܂Ƃ߂�BGX���s��c�i�c�����ݓc���Y�j�Ŏ������B2040�N���^�[�Q�b�g�Ƃ����G�l���M�[�A�E�Y�f���Ɋւ���헪�͏��ƂȂ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����Ǘ�16��`�A2030�N�ɑ��z��123MW�A�~�d�r152MWh���� ���y��ʏȂ́A�����̋�`�S�̂ł̃J�[�{���j���[�g���������Ɍ����āA�����Ǘ�����S27��`�̋�`�E�Y�f�����i�v����쐬�����Ɣ��\�����B���Ǘ���`5��`�A���p��`2��`�A���Ԉϑ���`1��`�̌v8��`��2030�N�x�́A���̑��̋�`��2050�N�x�̃J�[�{���j���[�g����������ڕW�Ɍf����B �e��`�̋�`�E�Y�f�����i�v��ł́A���z�����d�ݔ�����ђ~�d�r�̓����v����߂Ă���B �����q��NJǓ�7��`�ł́A���z�����d�ݔ���2030�N�x�܂łɍ��v63.494MW�B�~�d�r�ݔ���2030�N�x�܂łɍ��v44.411MWh��ݒu����B �܂��A���q��NJǓ�9��`�ł́A���z�����d�ݔ���2030�N�x�܂łɍ��v59.606MW��ݒu�B�~�d�r�ݔ���2030�N�x�܂łɍ��v108MWh��ݒu�B���f�R���d�r�ݔ���2030�N�x�܂łɍ��v1��7850MWh��ݒu����B����A���z�����d��Ɩ��E�q��LED���ȂǂŁA�����Ǘ������`�̍X�Ȃ�CO2�팸�𐄐i���Ă����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r��ǖʂɁA�ϐ����w�ƃZ���R�[���������� �ϐ����w�́A�Z���R�[�Ƌ����ŁA�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐ݒu���@���m�����邽�߂̋������؎������J�n�����Ɣ��\�����B ���z�����d�̃|�e���V�������傫���q�ɂ�H��̕ǂ�ΏۂƂ���B ��錧�É͎s�ɂ���Z���R�[���x�X�E���PD�Z���^�[�ɂ����āA�����̓�����₷���������ǖʂ�1m�~1m�T�C�Y�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r��16���i16m2�j�ݒu�����B�V�����ȈՐݒu�@�ɂ��A�{�s��������z�����[�܂�6���ԂŊ��������B����A���d�\�͂̌��ɉ����đόA���ɑϕ����ɂ���1�N�Ԃ����Č�����B �ϐ����w�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A�Ǝ��Z�p�ɂ��30cm���̃��[���E�c�[�E���[�������v���Z�X���\�z�����B���O�ϋv��10�N�������m�F���A���d����15.0���̃t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐����ɐ��������B���݂͎��p���Ɍ����āA1m���ł̐����v���Z�X�̊m���A�ϋv����f���d�����̍X�Ȃ�����ڎw���ĊJ����i�߂Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���C��ϓ��Ή��A���{�̎�ҁu���S�v����������Ɂ^3M�������� �X���[�G���W���p���́A�č��{�Ђ����{�����C��ϓ��Ɋւ���ӎ������̌��ʂ����\�����B �u�C��ϓ��ւ̑Ή��͏d�v���v�̎���ł́A���{�l��87�����d�v�Ɖi�O���[�o������90���j�B�N��ʂł́A�u���Ɉӌ��͂Ȃ��^�C�ɂ��Ȃ��v�Ɖ�����N�w��13���ɏ�����A�i�O���[�o������5.1���j�B�u�C��ϓ��������炷�e���v�����Ƃ���A�u�ُ�C�ہv�i67���j�ŁA�����Łu�C����C�ۃp�^�[���̒����I�ȕω��v�i43���j�A�u�C��̕ω��ɋN�����錒�N���v�i37���j�Ƒ������B �u�C��ϓ��ɑΏ��v�ɂ��ẮA�u�N���[���Ȍ�ʎ�i�i���]�ԁE������ʋ@�ւȂǁj�v��65���ōł����������B�����ŁA�u�Đ��\�G�l���M�[�ƔR���i���͔��d�E���z�����d�Ȃǁj�v��63���A�u�p�����̍팸�i�v���X�`�b�N�g�p�ʂ̍팸�Ȃǁj�v54���̏��������B�u�J�[�{���t�b�g�v�����g�v�ɂ��ẮA���{�ŗ����ł��Ă���̂�10���ȉ��B�O���[�o�����ς�51���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����唭�x���`���[�A�������z���u�\�[���[�t�F���X�v��̔� ������w���x���`���[��Ƃ�Yanekara�i���l�J���j�́A�����ݒu�^�̑��z�����d�V�X�e���u�\�[���[�t�F���X�v�̔̔����J�n�����B����܂ʼn����`��̖��Ȃǂɂ�葾�z�����d�̐ݒu������������Ə��Ȃǂɂ������ł���B �\�[���[�t�F���X�́A���z���p�l���𐂒��^�ɐݒu����B�܂��A���ʎ���^���z���p�l�����̗p���A���������ɐݒu����Ώ\���Ȕ��d�ʂ��m�ۂł���B�\�[���[�J�[�|�[�g�Ƃ͈قȂ�A���z�m�F�\�����b�H�����s�v�ŁA�ėp�I�ȍY�ŋ@�Ŏ{�H�ł��邽�߈������X�s�[�f�B�[�ɐݒu�ł���Ƃ����B���z���p�l���ɐϐႵ�Ȃ����߁A�~��n��ł����d���X���h����B �����\�[���[���W���[���͍������[�J�[���J���������́B�p�l��1��������̌��̍ő�o�͂�545W�A�ϊ�������21.1���B�O�`���@��2278�~1134�~35mm�A�d����32.6kg�B�����R�X�g�͍ލH�P��20�`25���~/kW���x�ŁA�⏕���̊��p���\�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z�����f�œs�s�K�X��ցA��z�̍H���PEM�^���d�u �R�����A�����A���dEP�A�听���݂́A500kW�̌Œ荂���q�iPEM�j�^���d�u�̊J����i�߂Ă���B��1���@����ʌ���z�s�̑听���[���b�N��z�H��ɐݒu��4������ғ�����\��B �R�����A�����A���dEP��3�҂́A�ăG�l�d�͂��琅�f�K�X������uP2G�i�p���[to�K�X�j�V�X�e���v�̊�ՋZ�p���m�����Ă���A����ANEDO�̏������Ƃɍ̑�����A����ɉ��ǂ��ăp�b�P�[�W�������B ���̓d�C�����Ő����������f���{�C���[�ŔR�Ă��A����ꂽ�M�����ݗp�R���N���[�g���ނł���v���L���X�g�R���N���[�g�̐����ɂ�����{���H���ɗ��p����B�]���g�p���Ă����s�s�K�X��R���Ƃ�����C�{�C���[�̉ғ����Ԃ��팸���A�E�Y�f�ɂȂ���B ���d�u�̒�i���͂�500kW�A���f�����\�͂͒�i120Nm3/h�B����A�V�X�e�����\��]�����A�H��̓s�s�K�X�R��CO2�r�o�ʂ̖�10����u�������邱�Ƃ�ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����{���A���f�E�o�C�I�R���D�[���G�~�b�V�����q�s�ɐ��� ���{���c�́A���{���̐��f�R���d�r�𓋍ڂ����m�㕗�ԍ�ƑD�uHANARIA�i�n�i���A�j�v�ŁA��_���Y�f��r�o���Ȃ��[���G�~�b�V�����^�q�̎��؎����ɐ��������Ɣ��\�����B�m�㕗�͔��d�{�݂ւ̍�ƈ��̗A���ȂǂŊ��p����B ���S�̂�CO2�r�o�ʂ�5�����߂�i2019�N�x�j���q�^�A�̒E�Y�f����ڎw���A���c���n�������u�[���G�~�b�V�����D�v���W�F�N�g�v�̎��g�݁B �q��@���C���[�W�����f�U�C���̃n�i���A�́A20�g���ȏ�̑D���ł͓��{���ƂȂ鐅�f�ƃo�C�I�f�B�[�[���R���̃n�C�u���b�h�D�B�S��33���[�g���A�S��10���[�g���A�d��248�g���Œ����100�l�B���D�O��O���[�v�Ȃǂ��o������uMOTENA.Sea�i���e�i�V�[�j�v�i�����j�Ȃǂ��J�������B �n�i���A�́A�k��B�s�����_�Ɋό��D�Ƃ��Ă��^�q����B�ό��D�̍ۂ͐��f�ƃo�C�I�R���̃n�C�u���b�h�ōq�s���ACO2�팸����53�`100���Ƃ����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����E���̏��p�u�d�͒~�d�V�X�e���v�A������100MWh�ݔ����A�n �X�C�X�̃G�i�W�[�E�{�[���g�E�z�[���f�B���O�X�́A�����E�]�h�ȓ�ʎs�ɏo��25MW�E�e��100MWh�̏d�͒~�d�V�X�e�������݂��A2023�N12���ɒn��̌��c���d�Ԃƌn���A�n���A�[���d���\�ɂȂ����Ɣ��\�����B ���Ɖ^�]�ɂ��ďȂ���э��Ƃ���ŏI�I�ȋ��������A���E���̎��p�K�͂ɂ�鏤�p�̔�g�����d�͒~�d�V�X�e���ɂȂ�Ƃ����B���Ђ̃p�[�g�i�[��Ƃł��钆���V���iCNTY�j�ƕ�AtlasRenewable�͌��݁A������9��̏d�͒~�d�V�X�e���̃v���W�F�N�g��i�߂Ă���A���v�e�ʂ�3.7GWh�ɒB����Ƃ����B�����̃G�l���M�[����ł́A�Đ��\�G�l���M�[���d���ɑ��āA��i�o�͂�20�������Ȃ��Ƃ�2�`4���ԕ��d�ł���~�G�l���M�[�ݔ��̐ݒu�����߂Ă���B�n���ɐ�߂�ăG�l���d�̊�����������ɂ�āA���߂���~�d�e�ʂ���������Ɨ\�z�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O�[�O���A����~�d�r�Ŏ��ԒP�ʂ̍ăG�l���B������ �č��̓쐼���Ɉʒu����A���]�i�B�ŁA���B�ōő�K�͂̃G�l���M�[�����ݔ����ғ������B ���̃G�l���M�[�����ݔ��́A�o��260MW�̃��K�\�[���[�i��K�͑��z�����d���j�ɕ��݂���Ă���A1GWh���̓d�͗ʂ��[�d���邱�Ƃ��ł���B���̃v���W�F�N�g�́A�u�\�m�����z�G�l���M�[�Z���^�[�v�ƌĂ�A���B�ōł��L���s������o�b�N�A�C�s�̓암�ɓ������ꂽ�B ���̃��K�\�[���[�Ƒ�K�͂Ȓ�u�^�G�l���M�[�����ݔ��̃n�C�u���b�h�E�v���W�F�N�g���甭�d���ꂽ�N���[���d�͂́A�n��̓d�͉�Ђ�ʂ��ĕăO�[�O���iGoogle�j�ɋ��������B 2017�N�ɂ͍ăG�l100�����B�������B���݁A2030�N�܂łɂ��ׂĂ̎��Ƃƃo�����[�`�F�[���S�̂Ńl�b�g�[���J�[�{���iCO2�r�o�ʂ������I�Ƀ[���j��B�����邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���B �u�l�b�g�[���J�[�{���v�́A���ԃx�[�X�ł���B�S�Ă̎��Ə��Łu1��24���ԁE�T7���N���[���d�́v�Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���s������4���Ńg���u���A2����͖������A�����Ȃ����z�������Œ��� ���z�����d�ݔ��̓������i��ł��邪�A�ꕔ�̌���ł͏Z���������s�\���ł�������A�y�����o�̔����Ȃǂ̃g���u�����������Ă���B �Đ��\�G�l���M�[�d�C�̗��p�̑��i�Ɋւ�����ʑ[�u�@�i�ăG�l���[�@�j�̉����ŁA2024�N4������@�߈ᔽ���Ǝ҂ɑ����t���̈ꎟ���ۑ[�u�⎖�Ɠ��e�Ɋւ�����Ӓn��ւ̎��O���m�̗v�����Ȃǂ����{����邱�Ƃ܂��A����̎s������o�ώY�Əȁi�o�ώY�Ƌǁj�̑Ή��������B 861�s����������B���̂����A41.2����355�s�����ő��z�����d�ݔ��ɋN������g���u���Ȃǂ������A16.6����143�s�����Ńg���u���Ȃǂ��������ł��邱�Ƃ����������B �J���H���i�K�̃g���u���A�ғ��i�K�̃g���u�����������B �ăG�l���[�@�ᔽ�Ȃǂ̔��d���Ǝ҂ւ̎w�������͌o�Y�Ȃ������A�Z���͐g�߂Ȏs�����ɑ��k���Ă���������B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| �������s�A�C���W�����{�݂Ɂu�Z�������d�v�v�����g�� �����s�A�����n�搅����ƒc����ы��a�@�d�H�Ƃ́A�u�Z�����ہv�𗘗p�������{���̎��p�K�̓v�����g�����ɒ��肵���B�����s�͊������̓V��ɍ��E����Ȃ��������̊m�ۂɌ����āA����17�N6�����C���W�����{�݁E�܂݂��s�A���^�p���Ă���B ���{�݂́A���E�傩��搅�����C����Z�����i�t�Z�����j�Ő^���ɕς��A�ő�50,000m3/���̐����p�����m�ہA����������́B�C���W�����v���Z�X�ł́A��ʂ̔Z�k�C������������B����̎��g�݂́A����܂Ŕr������Ă����Z�k�C���Ɖ����������i�W���j�̔Z�x���𗘗p���Ĕ��d������́B������Z�����Ŋu�āA�Z�����ɂ���Ĉړ����鐅�Ő��Ԃ��A���d����d�g�݂ƂȂ��Ă���B���d�d��110kW�A�N�Ԕ��d��88��kWh��������ł���A�ߘa7�N�̉ғ���ڎw���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����E�̃G�l���M�[�]���A2020�N�㖖���牻�Ώ���͌����� �p�A�[���X�g�E�A���h�E�����O�iEY�j�̃G�l���M�[�]���Ɋւ��钲�����|�[�g�ɂ��ƁA�O���[���G�l���M�[�����E����2038�N�܂łɎ�͓d���ƂȂ�A2050�N�܂łɃG�l���M�[�\���i�~�b�N�X�j��62�����߂�Ɨ\�����Ă���B ���̈���A���݂̃G�l���M�[�]���̃X�s�[�h�́A���E�̋C���㏸��1.5�x�ȉ��ɗ}����ڕW��B������ɂ͏\���łȂ��A����ɉ���������K�v������Ǝw�E����B EY�����\�����������|�[�g�uIf every energy transition is different, which course will accelerateyours?�i�G�l���M�[�]���̋ؓ����قȂ�Ƃ���A�ǂ̃R�[�X����������̂��H�j�v�ł́A���ΔR���̎g�p�ʂ�2020�N�㖖����Ƀs�[�N���}���A���̌㌸�����錩���݁B�������AHard-to-Abate�i�y��������j�ƌĂ��E�Y�f������ȃZ�N�^�[�����݂��邽�߁A���ΔR���͗\�z��蒷���G�l���M�[�~�b�N�X�̈ꕔ�ł��葱����Ɨ\�z���Ă���B���̂��߃G�l���M�[�]���ɂ́A��Y�f���̑�֎�i�������ƂɂƂ��Ă���ɖ��͓I�ɉf��悤�Ȑ����߂���Ƃ����B �܂��A���ΔR���̎g�p���\�z�ȏ�ɒ��������邽�߁A���ƃv���Z�X�̒E�Y�f�����K�v�s���ɂȂ�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/4�@]�@�@�� |
|
|
| �������}�[���d���_�@������A�_�Ƃ̒E�Y�f�ɑΉ��� �����}�[�A�O���A�_�Ƃ�CO2�[���G�~�b�V������ڎw�������^�d���_��̃R���Z�v�g���f���������J�����B �d�����[�^�[�쓮�̔_�@�ŁA�D�ꂽ�Ïl��������ɂ���Ԃ�ߍx�_�ƁA�n�E�X���ł̍�ƌ����̉��P�����҂����B�@�̂̑O��Ƀ��[�^���[�����@�Ȃǂ̍�Ƌ@�����t���邱�Ƃŏ����E����E�k����ȂǁA���܂��܂ȍ�ƂɑΉ��ł���B �ԗւł͂Ȃ��N���[���[���̗p���邱�ƂŁA�Ζʂ�s���n�ł̈���I�ȑ��s����������B�^�]�Ȃ͂Ȃ����u����Ƃ��邱�ƂŁA�_��Ǝ��̃I�y���[�^�[�̈��S�����m�ۂ����B�����^�]�@�\�̓��ڂ�����ɓ����B �R���Z�v�g���f���̂��߁A���ڃo�b�e���[�̎�ʂ�e�ʂȂǂ͖���B����A��ƂɕK�v�ȉғ����Ԃ��m�ۂł���悤�o�b�e���[�̑I����܂߂Č�������Ƃ��Ă���B2025�N�Ɏs�ꃂ�j�^�[�J�n��ڎw���A�ʎY�@�̊J����i�߂Ă����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����c���H�ƃg���^�A��K�͐��d���������J���ց^�����O�̎s��J�� ���c���H�ƃg���^�����Ԃ́A��K�͐��d���V�X�e���̋����J������ѐ헪�I�p�[�g�i�[�V�b�v���\�z���Ă������Ƃō��ӂ��A���Ɗ�{���ӏ�����������B �g���^�����R���d�r�Z�p��p�������d���Z���E�X�^�b�N�̐��Y��ʎY�Z�p�ƁA���c���H�����v���Z�X�v�����g�v�Z�p���K�̓v�����g�̌����Z�p��Z�����A��K�͐��d���V�X�e�����J������B 5MW�������P�ʁi�ݒu�ʐ� �F 2.5m�~6m�A���f�����\�� �F ��100kg�^���ԁj�Ƃ��ĊJ�����A������g�ݍ��킹�ĕW���p�b�P�[�W�Ƃ��邱�ƂŁA��K�͂Ȑ��d���V�X�e�����\�z����B 2025�N�x����g���^�{�ЍH��̐��f�p�[�N���ɐ��d���V�X�e���̓������n�߂�B�����I�ɂ�10MW���܂Ŋg�債�A����J���Ɋ��p���Ă����\�肾�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����z���p�l���ݒu�A�����u�K�n�v�n�}��Œ��o�^�A�C�E�O���b�h�E�\�����[�V�����Y �G�l���M�[�}�l�W�����g���Ƃ���|����A�C�E�O���b�h�E�\�����[�V�����Y�́A���z���p�l����u���|�e���V���������鉮�����ȒP�ɒT����V�X�e�������N���ɂ��Г��Ŗ{�i�^�p����B �V�X�e���͉����̖ʐς⑾�z���p�l����ݒu�ł���e�ʂȂǂ���B�ʐ^�ƒn�}��番�͂ł��A���Ђ͋@�\�╪�͐��x�̌�����}���ł���B �E�Y�f�Ɏ��g�ގ����̂Ȃǂ̎��ƌv��̍���x���ɖ𗧂Ɗ��҂����B �o�T�u�d�C�V�� �v |
|
|
| ���G�l�I�X�A����p�����̃T�[�o�[�p��p�t���J���@2023�N�x���ɔ��� ENEOS�́A�T�[�o�[�p�t�Z��p�t���A2023�N�x����ړr�ɔ�������Ɣ��\�����B���Ђ̓T�[�o�[���甭������M�������I�ɋz�����A������p��������������P�����t�Z��p�ɒ��ڂ��AKDDI�A��Intel�A��GCR�Ƌ��Ƃ��t�Z��p�t�̊J����i�߂��B KDDI�́A��N�̎��؎����ɂ����āA��p�ݔ��ɂ�����e�B�A4���x���i�f�[�^�Z���^�[�Ƃ��Ă̕i�����ł������ێ�����Ă���j�ł̈���ғ��ɐ����B�T�[�o�[��p�̂��߂ɏ�����d�͂�94%�팸���Ă���A�����t�Z��p�����ɂ������ׂ�ጸ���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B ����̔����鐻�i�́A�Y�������Z�p�ɂ�荂���_�����萫��L���A�g�p���Ԃ̒���������������B���l�ȃj�[�Y�ɑΉ�����3�̃��C���i�b�v�B �E�����Γ_�i�i���Γ_250���ȏ�j �E����p�����i�i���Γ_300�������A��p������Nj��������i�j �E�J�[�{���j���[�g�����Ή��i�i�A���������j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���X�܁E�����Ȃǂ̏��K�͎{�݂̏ȃG�l���T�|�[�g �u�A�C���X�I�[���}�́A�{�݂��Ƃ̐v��ݒ肪�s�v�Ȃ��ߏ�����p��啝�ɍ팸�ł���A���K�͎{�����ȃG�l�\�����[�V�����uLiCONEX LiTE�i���C�R�l�b�N�X ���C�g�j�v���A4��10����蔭������B ���s�̗l�X�ȏƖ��ݒ���ʂ̏Ɩ����Ƃɐv�ł���uLiCONEX�v�ɑ��āA�uLiCONEX LiTE�v�́A���ԑт��ƂɎ�����������u�X�P�W���[������v��A���̖͂��邳��l�̍ݎ������m���Ď�����������u�Z���T�[����v�A�G���A���ƂɎ�����������u�O���[�v����v�A�e�V�[���ōœK�ȏƖ��ݒ��o�^�ł���u�V�[���ݒ�v�Ȃǂ̊e��ݒ���p�b�P�[�W�����邱�ƂŐv��p���팸�ł��A������p���15���A�^�p�܂ł̍H�����48���Z�k�ł���B����ɁA���X�̓d�C����]����LED�Ɩ��Ɣ�r���Ė�51���̍팸�������߂邽�߁A�Ɩ��Ɋւ��R�X�g��啝�ɍ팸�ł���B���K�͓X�܂�I�t�B�X�A�����Ȃǂ̏��K�͎{�����ɊJ�����Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���~�d�r�̎����E�d�u���s�������T�{�ȏ��2024�N�x����d���o�C�N�p���� ���K�X�q��Ђ�KRI�́AEV�Ȃǂɓ��ڂ��郊�`�E���C�I���d�r�Ō��݂�5�{�ȏ�̎�������������u���������~�d�r�v�̊J���ɁA���E�ŏ��߂Ă߂ǂ������Ɣ��\�����B EV�����y����A�d�r�̗e�ʂ����d�r���p������邱�Ƃɂ������ׂ̒ጸ���d�������Ƃ݂āA�~�d�r�̒�����������ڎw���Ă���B �~�d�r�͓����Ń��`�E���C�I�����ψ�ɗ���Ȃ����Ƃŗ��i�ށB�u�o�C���_�[�v�ƌĂ��ڒ��܂��C�I���̗����W���邱�Ƃ������Ƃ����B ���Ђ́A�����̃o�C���_�[���g��Ȃ��Ă��ދZ�p���J�����ēd�r�̋@�\���ێ����邱�Ƃɐ��������B2024�N�x�͎Г��Ŏ���i��2025�N�x����ڋq�����ɓd���o�C�N�ɓ��ڂ���e�ʂ̎���i�������B�����Ԃ�~�d�r���[�J�[�ȂǍ�����6�Ђ����������������B�J���͍ޗ����[�J�[�Ȃ�10�В��x�̓d�r�֘A��ƂƘA�g���Đi�߁A�����͋Z�p�����[�J�[�ɒ����p������B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���o�b�e���[������EV�u���A��v�I�[���W���p���Ő��i ���y��ʏȂ́A�o�b�e���[������EV�̍��A��̍�����I�[���W���p���Ő��i������j���������B ���Ȃł́A����܂ŁA�J�[�{���j���[�g�����̒B���Ɍ����A�d�C�����Ԃ̈��S�����Ɋւ��鍑�A��̍�����哱�����y�𑣐i���Ă���B�������Ȃ���A���pEV�ɂ��ẮA�q���������Z���o�b�e���[�̏[�d���Ԃ��ۑ�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A�����ԃ��[�J�[��^�����Ǝғ����A�g���A�o�b�e���[���ԗ�������O���ď[�d���\�ȃo�b�e���[������EV�̊J��������i�߂��Ă���B����A�䂪���ŊJ���E�����i�߂���o�b�e���[������EV�̋Z�p�������ꂽ���ۃ��[���i���A��j��������̂��߁A�����̋��͂ɂ��J�[�{���j���[�g�����Z���^�[�𗧂��グ�A��1�����J�Â����B �J�[�{���j���[�g�����Z���^�[�ɂ����č����O�����̏�L��W���������Ƃ̘A�g�����s���A���N���Ƀo�b�e���[������EV�̍��A��ɂ����鍑�ۋc�_���J�n���邱�Ƃ�ڎw���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ������̊C�ꉺ�ւ̓�_���Y�f����E�����ɌW��C�m���̕ۑS�݂̍�� �C�ꉺ�ւ̓�_���Y�f����E�����i�ȉ��A�u�C��CCS�v�j�ɂ��ẮA����b���p�����̊C�m�������K�����郍���h���c�菑�̒S�ۑ[�u�Ƃ��āA�C�m���ۑS�̊ϓ_����u�C�m�������h�~�@�v�Ɋ�Â�����S�����Ă���B ����A�����ł̊C��CCS�̊g��ɉ����A�C�O�ł̊C��CCS�̎��{��ړI�Ƃ���CO2�̗A�o�������܂�Ă���A�C�ꉺCCS�ɌW��C�m���̕ۑS�݂̍���Ɋւ��A�Œ�5�N�ƂȂ��Ă��鋖���ԂƋ����̑Ώ۔͈͂̌��������s���K�v���ɂ��Ď������B���s�C�m�@�ɂȂ����ƏI���̂��߂̐��x�����O���̗���Q�l�Ƃ��đn�݂��邱�ƁB���Ə��n���A�K�Ɏ��Ƃ������p�����d�g�݂�A�j�Y���ɂ�莖�Ƃ��p���ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ���ɁA���Ƃ�K�ɏI��������d�g�݂�n�݂��邱�Ɠ������߂�ꂽ�B�u�����h���c�菑�v�̎�����\�ƂȂ�悤�A�C�m���̕ۑS�̂��߂̍������x�̐����ɂ��Ă����荞�܂�Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ����p��150MW�̋��d�����^���K�\�[���[�A�{�B�r�ɑ��z���p�l�� �Đ��\�G�l���M�[���ƂȂǂɓ������s���Ă���}�[�L�����A�z�[���f�B���O�X�ƃ}�j�G�X�O���[�v�i�����s�j�́A��p�ł̃��K�\�[���[�̋����J���Ɋւ��ċƖ���g�����B ��1���Č��Ƃ��āA���Ђ������Őݗ������v���W�F�N�g�J���p�j�[��ʂ��āA��p�����n���ɂ����ăG�r��n�}�O���Ȃǂ̗{�B�r�̏�ɑ��z���p�l����ݒu���鋙�d�����^���z�����d���̊J�������擾�����B �o�͂�100�`150MW�K�́B�o���z����яo���䗦�͔���\�B2027�N�x���̊��H��ڎw���B��p���{�́A���z�����d�̓����ڕW��2025�N�܂ł�20GW�A2030�N�܂ł�30GW�Ɛݒ肵�Ă���B���ɁA���d�����^���A2025�N�܂ł�4GW�����𐭍�Ɍf���Ă���B ����A��p�ɂ�����2023�N�܂ł̑��z�����d�̓������т�10.72GW�ƁA2025�N�ڕW�̖�5�����x�ɗ��܂�B����A��p�Ŏ嗬�ɂȂ�ƌ����܂�鋙�d�����^�𒆐S�Ƃ������K�\�[���[�J�����������Ŏ擾���Ă����v��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����Ղȁu�J�[�{���j���[�g�����v�\���A���B�Ŏg�p�֎~�� ���B�c��́A���i�\���Ɍ�����������咣�̎g�p���֎~����w�߂��̑������B ����ϋv���Ɋւ���O���[���E�H�b�V���̃}�[�P�e�B���O�������҂�ی삷�邱�Ƃ��ړI���B�u�V���Ȗ@���́A�}�[�P�e�B���O�̓����������߁A���i�̑��������Ɛ키���ƂŁA�g���̂Ă̕�������̒E�p��}��v�ƁAEU�c��Ŗ{�@�Ẵ��|�[�^�[�i�쐬�A�S���c���j�̓R�����g�����B �V���Ȏw�߂́A�u���ɂ₳�����v�u�V�R�v�u�����𐫁v�u�G�R�v�ȂǁA��Ƃ���ʓI�Ȋ��咣���؋��Ȃ��g�p���邱�Ƃ��֎~����B�����ȔF�X�L�[������I�@�ւ̓��������T�X�e�i�u�����x���������g�p�\�ƂȂ�B ����҂��O���[���E�H�b�V���̃}�[�P�e�B���O��@����ی삵�A���ǂ��w���I���𑣂��B �ϋv���ɂ��Ă��A�K�v�ȏ�ɏ��Օi�̌����𑣂��\���A�C���\�ł��邩�̂悤��搂����Ƃ��֎~���A���Y�ҁE����҂̑o���ɑϋv���ւ̏d���𑣂��B�{�w�߂́AEU������̍ŏI���F���o�āA2026�N�܂ł�EU�����e���̍����@�Ɉڍs����B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| �����B��č��Ői�ށu�����ݑ͔쉻�v�A���͍��N����`���� �t�����X�ł́A���N1������́A�ƒ�⎖�Ə�����o�鐶���݂◎���t�E���Ȃǂ̗L�@�p�������A�����̂��w�肷�����ꏊ�i�{�݁j�ɏo�����A�e�����R���|�X�g�e��ő͔삷�邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ����B ��������L�@�p�����́A�������̓��������p���A�o�C�I�K�X�≻�w�엿���ւ���͔�i�L�@�엿�j�ɕς�����B �C�^���A�̃~���m�ł́A2014�N����e�ƒ�ɃR���|�X�g�e��Ƒ͔쉻�ł���܂�z�z���A�����݂��������v���O���������{���Ă���B�p����2023�N�A�ƒ납��o�鐶���݂̕��ʎ��W�Ɍ������v��\�����B���̂ق��I�[�X�g���A�A�I�����_�A�x���M�[�ł��A�����̂���̂ɐ����݂̕��ʂ��i��ł���B �č��̃o�[�����g�B��2020�N7���ɁA�g���̂ăv���X�`�b�N�̎g�p�֎~�ƂƂ��ɁA�����݂͔̑쉻���B�Z���ɋ`���Â����B2022�N1���ɂ̓J���t�H���j�A�B���L�@�p�����̃��T�C�N���i�͔쉻�j���`���Â����B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���Ϗ��q�`�̊Ǘ��g���A�p���[�G�b�N�X�ЂƋ���u�d�C�^���D�v�����p�ŒE�Y�f �Ϗ��q�`�Ǘ��g���ƃp���[�G�b�N�X�́A�d�C�^���D�ƒ~�d�n�̗����p�ɂ��Ϗ��q�`�̍`�p�E�Y�f�����i�y�ђn��̐U���Ɍ�������A�g�������������B �d�C�^���D�́A�D�ɓ��ڂ����~�d�r�ɒ~�d���A�d�C���C��A�����鐢�E���̑��d�Z�p�B�Đ��\�G�l���M�[�́A�������Ɠd�͎��v�n������Ă���ꍇ�������A���d��i�������ۑ�ł���A�d�C�^���D�͂���������ł���B�Ϗ��q�`���ӂ́A���푽�l�ȎY�Ƃ��W�ς��A��K�͓d�͂̏���G���A�ƂȂ��Ă���B �d�͎��v�̈ꕔ���A�d�C�^���D���^�ԍĐ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂Řd���A�J�[�{���j���[�g�����|�[�g�̌`���Ɗe��Y�Ƃ̒E�Y�f�Ɋ�^����B������ɂ��A�`�p�E�Y�f�����i�̂��߁A�`�p���̎ԗ�EV���A�ՊC���̒~�d�r�𗘊��p�������d�ݔ��̓�������������B���Ђ͓d�C�^���D���^�ԍĐ��\�G�l���M�[���A�Ϗ��q�`�ՊC���ɗ��n�����Ƃ�u���ŗ����p����B�ЊQ���̓d�͊m�ۂɂ��n��̃��W���G���X����Ɏ��g�ނƂ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����[�\���A�Г��Y�f���i2���~�^t��1����� ���[�\���́A�u�C���^�[�i���J�[�{���v���C�V���O�v���x�iICP�j������B�Y�f���i�́A2���~�^t-CO2�BCO2�r�o�ʂɊւ��ݔ������ɑ��āA�Г��Y�f���i��K�p���A��p���Z�������̂𓊎��̔��f�ޗ��Ƃ���B ���Ђ́A����܂łɎ��̂悤�Ȏ��g�݂𐄐i���A2022�N�ɂ�1�X�܂������CO2�r�o�ʂ��A30.6���팸��B�����Ă���B��6000�X�܂ɁACO2��}�̗Ⓚ�E�①�V�X�e�������B��2600�X�܂ɑ��z�����d�V�X�e�����B���t���I�[�v���P�[�X�̓����B�Ȃǂ����{�B ICP�Ƃ́A�Г��Y�f���i�Ƃ��Ă�鐧�x�ŁA��Ƃ�����I��CO2�r�o�ʂɉ��i�t���������́B����𓊎����f�Ȃǂɑg�ݍ��ނ��ƂŁACO2�̔r�o�����炷�Ƃ����d�g�݂��B�ߔN�AICP�������Ƃ����E���ő����B���]�����s�����ۓI�Ȕ�c���c��CDP�ɂ��ƁA2020�N�ɂ́A�����ς݁i�܂��͓����\��j�̊�Ƃ͐��E2000�Ђ��z����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������p�Ɂu�m�㕂�̎����z���v�����ڌ����A�����h�g��G���A�Ŏ��� �O��Z�F���݂́A�����s�́u�����x�CeSG�v���W�F�N�g�v�ō̑�����A�u�C�̐X���㋣�Z��v�̒����h�g��G���A�ŁA�u�m�㕂�̎����z�����d�{�݁v�̐ݒu��Ƃ����������Ɣ��\�����B ���Z�p���ł́A���̃V�X�e���Ƒ��z���p�l���̌����E�p�x��4�̈قȂ�����Őݒu���A�e��f�[�^���擾��������B�����̕��̃V�X�e���̐v�E�ݒu�A�m��ɑΉ��������̃V�X�e������ьW���V�X�e���̐v�E�ݒu�A�d�C�ݔ��ւ̉��Q�̉e���A�m��Ɨ���A�قȂ�^�C�v�̕��̃V�X�e�����d�ʂȂǂ��r��������B �O��Z�F���ݐ��t���[�g�́A�����ɔ��A�X�`���[�����[�U����Ȃǒ������萫�ɗD��A���̉e�����ɂ����`��B�L���[���N���́A�\�����ނ����Ȃ��g�ݗ��Ă��e�ՁB�X�R�g�����́A�t���[�g�{�ˑ�̃^�C�v�ŁA���R�x�̍����v���\�Ƃ����B���z���p�l���͗��ʃK���X�d�l�ŁA4���j�b�g���v�̏o�͂�55.2kW�B�N�Ԕ��d�ʂ͖�7��2500kWh�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�y���u�X�J�C�g���z�d�r�v�ϋv20�N�����ցA�ϐ����w��2025�N���Ɖ� �ϐ����w�́u�y���u�X�J�C�g���z�d�r�v�ɂ��āA2025�N�܂ł�20�N�����̑ϋv��������������j���ł߂��B ��ʓI�ɑϋv����5.10�N���x�Ƃ���A�������������p���̏�ǂ������B20�N�̑ϋv���͈�ʓI�ȃV���R���n���z�d�r�ɂ��C�G����B���łȂǓd�@�e�Ђ⒆���������p�����}���ł���A�ϐ����w�͉��O�ݒu�̎��Ȃǂ�ʂ��đϋv���������A25�N�̎��Ɖ���ڎw���B �ϐ����w�͉t���������~�ނ�K���X�p���Ԗ��ȂǂŔ|�����Ǝ��Z�p�����p���A�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r���J�����Ă���B���łɕ�30�Z���`���[�g���̃��[���E�c�[�E���[���iR2R�j�����̐����v���Z�X���\�z�B���O�ϋv��10�N�����Ŕ��d����15�E0���̓d�r�����ɐ��������B����͑ϋv���̌���ɉ����A�ʎY�����������ĕ�1���[�g���̐��Y�Z�p���m������B�܂��A���d����20���̎������ڎw���A�Z�p�I�ȗD�ʐ����m�ۂ��Ďs��`�������[�h����l�����B �o�T�u�����H�Ɓv |
|
|
| ���O��s���Y��A�����ő�E�ؑ��I�t�B�X�r�����݂փy���u�X�J�C�g������ �O��s���Y�ƒ|���H���X�́A�����ő�E�ō��w�̖ؑ����݃I�t�B�X�r�������H�����Ɣ��\�����B�n��18�K���E����84���B�������K�p�ƂȂ�ؑ��E�ωZ�p�𑽐���������ق��A�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�Ɋւ�����؎����Ȃǂ��s���B�v�H��2026�N�̗\��B ���v��́A�����ʐϖ�2��8000m2�̖ؑ����݃I�t�B�X�r�������݂�����̂ŁA�g�p����؍ޗʂ͍����ő勉��1100m3���ACO2�Œ�ʂ͖�800t-CO2�������ށB��̕����ɂ����錚�z����CO2�r�o�ʂɂ��ẮA���K�͂̈�ʓI�ȓS�����I�t�B�X�r���Ɣ�ׂāA��30���팸�ł���Ƃ��Ă���B �܂��A�s���Y����ɂ���č��肳�ꂽ�u���ݎ�GHG�r�o�ʎZ�o�}�j���A���v��K�p��CO2�r�o�ʂ��Z�o����B����ɁA�|���H���X���J�������ωE�ؑ��Z�p������B�g�p����؍ނ͍��Y�ނ��g�p����B���ŃG�l���M�[�V�X�e���Y�ƘA�g���A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̎����E�V�X�e���\�z��}��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����ёg�A�O���[�����f��S���ŗA��82����CO2�팸���� ��ёg�́A�啪���Ő��������O���[�����f�̗A���ɓS���𗘗p���A�]���̃g���b�N�A�����ɔ�ׂ�CO2�r�o�ʂ�82���팸�������Ƃ𖾂炩�ɂ����B �S���ɂ�鐅�f�A���͍����ł͏��߂Ă̎��g�݂ƂȂ�B���Ђ͌��݁ACO2�r�o�ʍ팸�����������g�݂̈�Ƃ��āA�����ꎖ�����ɐݒu�������f�R���d�r�ɂ��d�͋��������{���A���̍ۂɕK�v�ƂȂ�O���[�����f��啪��������ؒn�ł��镺�Ɍ��܂ŗA�����Ă���B ����܂ł́A���������O���[�����f����1����x�A�g���b�N�ŗA�����Ă������A�������A������CO2�r�o�ʂ��ۑ�ƂȂ��Ă����B����AJR�ݕ��A�S���ʉ^�Ȃǂ̋��͂̉��A�A���o�H�̑唼��S���ɐ�ւ��郂�[�_���V�t�g�����{�����B���̌��ʁA1����̗A���i�����n������ؒn�܂ł̕Г��j�ɂ�����CO2�r�o�ʂ�0.347�g������0.062�g���Ɍ������A8���ȏ�̍팸��B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�q�[�g�|���v�̎���ɓ˓��v�^�Ăl�h�s�̉Ȋw����2024�N�u10��Z�p�v�I�� �ă}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w(MIT)���^�c����Ȋw�Z�p���uMIT�e�N�m���W�[���r���[�v�́A2024�N�̐��E��ς���10��Z�p�Ƀq�[�g�|���v��I�肵���B �����́A2024�N���u�q�[�g�|���v�̎���ɓ˓������v�ƕ\���B���ΔR�����g���@�킩��Đ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂��g�����q�[�g�|���v�@��ɐ�ւ��邱�ƂŁA��_���Y�f(CO2)�r�o�ʂ����I�ɍ팸�ł���Ƌ������Ă���B 10��Z�p�́A���������N�I�肵�Ă���B2024�N�́A�G�l���M�[���삩�璴���������z�d�r��n�M���Y�V�X�e����10��Z�p�̈�ɑI��Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���z����EV���ESAF�����������DHL�̒E�Y�f�o�c DHL�́A�������ʃK�X�r�o�팸�����A2030�N�܂ł�70�����[���i��1���~�j�𓊎�����Ƃ����A2030�N�܂łɉ������ʃK�X�̔r�o��2900���g���ȉ��ɍ팸����ڕW���f���Ă���B 320�@�ȏ�̐�p�q��@�������A���E�ő��点��ԗ��䐔��11�������B�d�_����Ƃ���4�̒��𗧂ĂĂ���B�q�O���[�����X�g�}�C���z�B�r�́A2030�N�܂łɁA�z���ԗ���60����d��������B�q�����\�ȍq��r�ɂ����ẮA�q��R����30�����A�q��R���iSAF�j��ւ���B12�@�̓d�C���̉ݕ��q��@�����Ă���B�q�����̃J�[�{���j���[�g�������r�ɂ����ẮA���z���p�l����ݒu�B�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e�������A�{�ݑS�̂̓d�͏���ʂ̍œK����}���Ă����B�q�O���[���v���_�N�g�r�ł́A���ɔz�������A���T�[�r�X����������B�A�����ɔr�o�����CO2���Z�肵�A�N���W�b�g�ŃI�t�Z�b�g���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o�C�I�}�X���d�̐V�݁A�u�؎��v�͌����A���^�����y������ ���o�ό������́A�����o�C�I�}�X���d�s��̒������ʂ\�����B��K�͂Ȗ؎��o�C�I�}�X���d���̐V�݂������������A�H�i�p�����������Ƃ������^�̃o�C�I�K�X�ݔ����������錩�ʂ��ŁA2030�N�x�̍����o�C�I�}�X���d�ʂ�4��5988GWh�ɂȂ�Ɨ\������B �������́A�����p�؍ށE�A���ނȂǂ�R���Ƃ���؎��o�C�I�}�X���d�A�H�i�p�����Ȃǂ̗L�@�p�����������Ƃ��郁�^�����y�ɂ��o�C�I�}�X���d���Ƃɂ����锭�d�d�͗ʂ𐄌v�����B 2022�N�x�̍����o�C�I�}�X���d�ʂ�4��581GWh�Ɛ��v�B���̎����A�ݔ��e��10MW���̑�K�͖؎��o�C�I�}�X���d���������ғ��������ƂŔ��d�ʂ��啝�ɑ��������B2023�N�x�͔R���̒��B�����̌����ŐV�K���݂��݉����Ă���B����́A�H�i�p�����������Ƃ������^�����y�o�C�I�K�X���d�̓��������������܂��B�ߔN�A���Ǝ{�݂ȂǂŐ��\t�ȉ��̏��^�o�C�I�K�X�ݔ��̓�������������P�[�X�������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���E�Y�f�o�c�u������Ƃ̂X���v�����Ή��I �֓d�G�l���M�[�\�����[�V�������\�����u������Ƃɂ�����E�Y�f��̎��{�ɌW����Ԓ������ʂɂ��āv�ɂ��A�������3060�Ђ̒����ɂ��ƁA��Ɏ��g��ł��钆����Ƃ�10�В��킸��1�Ёi9.8%�j�ɂƂǂ܂邱�Ƃ��킩�����B ������Ƃ����g�ޒE�Y�f��Ƃ��ẮA�u�G�l���M�[����ʂ̍팸�v��66.0%�ƍł������A�����āu���T�C�N���Ȃǂ�3R�̐��i�i39.0%�j�v�u�Đ��\�G�l���M�[�̗��p�i31.7���j��������ꂽ�B �E�Y�f��̃����b�g�Ƃ��āA3�Ђ�1�Ёi33.3���j���u��Ɖ��l��u�����h�C���[�W�v�Ɖ��Ă���B�܂��A4�Ђ�1�Ёi26.9���j�������̐������ʂ����������ƉB �����{�̗��R�́A26.0���̊�Ƃ��u�R�X�g���v�Ɖ��A�u��Ԃ�������i17.0���j�v�u�ǂ����g�߂悢���킩��Ȃ��i16.0���j�v�Ƒ������B�����{��Ƃ̖�9���i92.0���j�́A���Ђ��⏕���̐\���ΏۂɂȂ�ƍl���Ă��Ȃ������B �o�T�u�j���[�Y�E�[�N�v |
|
|
| ��������w�A���f�ECO2���ʂɒ����������I�z�������uMOF�v�J�� ������w�́A���{���B�Ƌ����Ŋ����a�^���q�̑n�o��ړI�Ɍ������s�Ȃ��A���f���_���Y�f�iCO2�j���ʂɋz�����镨���uTrp-MOF�v�̊J���ɐ��������Ɣ��\�����B ���̍ޗ���p���邱�Ƃő�^�K�X�{���x�ɑ��鏬�^�́u���q�{���x�v�Ƃ��Ẳ��p���\�ƂȂ�B �������ʂ̃|�C���g�́A���f��CO2���ʂɋz������ޗ��̊J���B�u�n�`�̑��v�^�̎��R��Ԃɂ��A��ʂ̃K�X�z�����\�B400���ȏ�ł��������Ȃ��D�ꂽ�M�ϋv���BCO2�̉���ɁA�قƂ�ǃG�l���M�[��K�v�Ƃ��Ă��Ȃ������z���ɂ��CO2�̕����E����Z�p�����߂��Ă���B�܂��A���f�́A�����Ōy���A���S�Ɏ�舵�����Ƃ̂ł��鐅�f�����ޗ��̊J�����ؖ]����Ă���B ���E���̋����L�@�\���́AMetal-organicFramework�iMOF�j�̓X�|���W�̂悤�Ȑ�����L���A�K�X�ނ��I�ɋz�����邱�Ƃ���A���͂≷�x�ω��݂̂ŗe�ՂɃK�X���z�E���ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���u�_�����ꏊ�ɋ��d�r�[���Ǝˁv���E���E����LAN�Ƌ�������}�C�N���g���d ���ł́A�}�C�N���g���u���d�V�X�e���ɂ����āA����LAN�Ƃ̋�������������Z�p���J�������Ɣ��\�����B �H��̐�������╨���q�ɂȂǂɂ����āA�Y�ƗpIoT�Z���T�̃o�b�e���[���X���邢�͓d�r�𓋍ڂ����Z���T�ւ̉��u���d���������A�o�b�e���[�̌�����Ƃ��팸���邱�ƂŁADX�i�f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����j����Ȑl���̐i�W�ɂ�鐶�Y������ƁA�J�[�{���j���[�g�����Љ�Ɍ��������g�݂ւ̍v�������҂����B ����͍H��A�q�ɂȂǎ��ۂ̌���ł̎���i�߂�\��B�@�����̓��������܂��Ȃ���2025�N�ȍ~�̎��Ɖ���ڎw���B���ł́A���ӂ̖����M���̗L�������o���ċ��d������K�ɐ��䂷�邱�Ƃő��̖����V�X�e���ւ̊���������A�_�����ꏊ�ɋ��d�r�[���𐧌䂷��u���d�Z�p�v�Ɠd�g����d�͂����o�����Ƃ��ł���u��d�Z�p�v�𓋍ڂ����}�C�N���g���u���d�V�X�e�����J�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�����E�G�i�W�[�A���{������2GWh�~�d�r�ݒu��TMEIC����Q�� �V���K�|�[���̍ăG�l��Ƃ̃O�����E�G�i�W�[�́A���{�����ɍő�e��2GWh�̑�K�͒~�d�r��ݒu����Ɣ��\�����B �����_�ɂ�������{�S�̂̒�u�p�~�d�r�̗e�ʂ�220������������K�͂ł���A700���g����CO2�r�o���팸�ł��錩���݂��B�����z��910���~�̌��ʂ��ŁA2026�N�Ɍ��݊J�n�̗\��B ���̎��g�݂ɂ́A���ŎO�H�d�@�Y�ƃV�X�e���iTMEIC�j����K�͒�u�p�~�d�r�V�X�e���\�����[�V�������A���{�H�c�G�i�W�[�\�����[�V�����Y���Z�p�I�R���T���e�B���O��EPC���Ǝ҂Ƃ̒����S���B �O�����E�G�i�W�[�͋ߗגn��̋Z�p�҂���є�Z�p�҂�ΏۂƂ������C�v���O�����𗧂��グ�A�V���Ȍٗp�@������B���݁A��������Ȗ،��Ȃǂ����n�Ƃ��Č�������Ă���B����̎��g�݂́A�O�����E�G�i�W�[�ɂƂ��ď��̓��{�i�o�ƂȂ�B���Ђ͓����I�t�B�X���J�݂���ƂƂ��ɁA����͐ꑮ�`�[����Ґ�����\�肾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�F���w�ACO2���烁�^�m�[�����������ɐ����փp�C���b�g�ݔ��̉^�]���J�n �Z�F���w�́A�v���X�`�b�N�ȂǑ��l�Ȑ��i�̌����ł��郁�^�m�[�����ACO2���獂�����ɐ���������Ɍ������p�C���b�g�ݔ������Q�H��ɐV�݂��^�]���J�n�����Ɣ��\�����B ����A2028�N�܂łɂ͎����������A2030�N��̎��Ɖ���ڎw���Ă����B�]����CO2����̃��^�m�[�������ɂ́A�t�����i�������琶�����̕����Ɠ����ɁA���������猴���̕����ւ��i�s���锽���j�ł��邱�Ƃɂ�郁�^�m�[���̎����̒Ⴓ��A�����ŕ������鐅�ɂ��G�}�Ƃ������ۑ肪�������B �Z�F���w�́A������w�̑������H�w���̏������i������������i�߂Ă����ACO2����̍������A���R�[���ސ����ƐG�}�����̒����������҂����u�����Ïk�^������iICR�j�v�ɒ��ڂ��A�����J���𐄐i���邱�ƂŁA�����̖������������BICR�ł́A�����Z�p�ł͓��������������ł̃��^�m�[���␅�̋Ïk�������\�ł���A����ɂ��A�����̌���A�ݔ��̏��^���A�ȃG�l���M�[���ɂȂ���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����z���p�l���̔p�K���X����H�퐻���A�ΒˏɎq������ �ΒˏɎq�́A���z���p�l���̔p���J�o�[�K���X���ė��p���ăK���X�H������삷����؎��������{�����Ɣ��\�����B ����̎��؎����́A���z���p�l����10�����ɑ�������K���X�J���b�g�i�K���X���j100kg���p���ăK���X�R�b�v2��ނ�300�㎎�삵�A���z���p�l���̔p�K���X�Ő��`�\�ł��邱�Ƃ��m�F�����B�K���X�J���b�g�́A�O�H�P�~�J���O���[�v�̐V�H��������B ����쐬�����K���X�R�b�v�͊������i�Ɠ����̕i�������B����́A�����I�ȃK���X�J���b�g�̕i�����萫��A�g���̂�����K���X���i�̕i���ɗ^����e���A�����I�Ȉ��S���Ȃǂ��m�F����\��B���ɐH�탁�[�J�[�Ƃ��Ĉ��S���ɔz�����Ċm�F��i�߂Ă����Ƃ����B���Ђɂ��ƁA1t�̌��ޗ����K���X�J���b�g�֒u�������邱�ƂŖ�0.6t��CO2�팸�ɂȂ���Ƃ����B���z���p�l���͏d�ʂ�60���O����K���X����߂邱�Ƃ���A�������}�������z���p�l���̔p���ł̓K���X�̊��p���@���ۑ�ɂȂ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IHI�A���f���ă{�C���[���J���A�g���^�����ԋ�B�ʼn^�p�]�� IHI�ėp�{�C���́A�s�s�K�X��ă��[�h�Ɛ��f���ă��[�h��������Y�Ɨp���^���f���ă{�C���[���J�������Ɣ��\�����B 2024�N1������g���^�����ԋ�B�ɂ����ĉ^�p�]���������J�n����B �H����Ŏg�p�������C������{�C���[�ŁAIHI�ėp�{�C���̊ї��{�C���[����ɊJ�������B���f�R���̑̐ϔ�60���A�M�ʔ�30��������ɁA�s�s�K�X��ĂƐ��f���Ă��ւ��ĉ^�]�ł���B���f�̋����ʂɍ��킹�ă��C�����~�߂��ɏ_��Ƀ{�C���[���ғ��ł��A�v��I��CO2�r�o�ʍ팸���\�ɂȂ�B ����܂łɁA�s�s�K�X�Ɛ��f�̍��Ď��ɉۑ�ƂȂ�NOx�i���f�_�����j�̔r�o�ʂ��A�s�s�K�X��Ď��Ɠ����ɗ}���ł��邱�Ƃ��m�F�����B����A�g���^�����Ԃɔ������C��750kg�̎����@��ݒu���A�H��̑��z�����d�ݔ��Ő����������f��R���Ƃ��Ďg�p����^�p�]�����������{����B���f���Ĕ䗦�̊g��A�X�Ȃ�NOx�̒ጸ�ȂǂɎ��g�݁A2024�N�̔̔��J�n��ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r��FIT�Ŏ��v���N�A�o�Y�ȕ��j �o�ώY�ƏȂ́A2025�N�x�̒��B���i�E����i�͐����u���̕������������B 2025�N�x�̒��B���i�i�t�B�[�h�E�C���E�v���~�A����FIP�ł͊���i�j�ɂ��ẮA�Z���ƂȂ鏔��p�A�ݔ����p���̂������2024�N�x�E���B���i�̑z��l�𐘂��u�����B���̂��ߎ��Ɨp�A�Z��p�Ƃ�2025�N�x�̉��i�́A2024�N�x�Ɠ��l�A���Ɨp�̓��D�ΏۊO��9.2�~/kWh�A�ሳ���Ɨp�i10kW�`50kW�j��10�~/kWh�i�n�抈�p�v���A�c�_�^�v������j�A�����ݒu��12�~/kWh�A�Z��p��16�~/kWh�̂܂܂ƂȂ�\���������܂��A�����㑾�z���Ƃ��ĊJ�����i�ރy���u�X�J�C�g���z�d�r�ɂ�锭�d�ݔ��������A�����ɒ��肷��Ƃ����B ���{�́u2025�N����̎��Ɖ����������A2020�N��N����100MW/�N�K�́A2030�N��҂�����GW���̗ʎY�̐����\�z���邱�Ƃ�O��ɓ����x�������������v�Ƃ��Ă����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �������K�X�A�ĂŒ~�d�r���ƎQ��300���~�ʼn^�c��Д��� �����K�X�́A�č��Œ~�d�r���ƂɎQ������Ɣ��\�����B�e�L�T�X�B�Œ~�d�����J�������Ƃ��ő�2��1600���h���i��300���~�j�Ŕ�������B �Đ��\�G�l���M�[�����y���āA�d�C�̎s�ꔄ��������ȓ����Œm�������߁A���{�ł����l�̎��Ƃ�W�J�ł��邩��������B�e�L�T�X�B�Œ~�d�����J�����郍���O�{�E�x�X�Ђ�����B�N���ɑS�����̎擾��\�肷��B���Ђ�2024�N�̉ғ���ڎw���ăq���[�X�g���s�ߍx�ő�^�̒~�d�ݔ��i�e�ʂ͖�35���L�����b�g���j���J�����Ă���B���z���Ȃǂ͔��d�ʂ����肹���A���v������d�C�d���邱�Ƃ�����B�~�d�r�œd�C��~���Ď��v�̂��鎞�ԑтɔ�������A�]����z����著�d���̕��ׂ����炵���肷��r�W�l�X�������オ���Ă���B�e�L�T�X�B�͓d���̖�4�����Đ��G�l�ŁA�~�d�r�̗��p���i��ł���č��œd�͔�����̎Z�m�ۂ̃m�E�n�E�āA���{�ł̎��Ɖ��ɂȂ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���]�ː��Ƒx���s�A�ăG�l�ŋ���A�c�_�^���z�������{�݂ɒ��B �]�ː��́A��t���x���s�Ƃ̊ԂŁu�Đ��\�G�l���M�[�̊��p��ʂ����A�g����v����������B �����ő�K�͂̃\�[���[�V�F�A�����O�i�c�_�^���z�����d�ݔ��j�����x���s���̑��z�����d���Ŕ��d�����d�͂��A�]�ː��̋旧�{�݂Ŋ��p����B ������́A�x���s�őn�o�����ăG�l�d�͂����A���p�g�傷�邱�Ƃŗ������̂̒E�Y�f�Ɏ����邱�ƁA�_�Ƒ̌��Ȃǂ̏Z���𗬂��s�����ƂŒn��̊������ɂȂ��邱�Ƃ��K�肵�Ă���B��̓I�ɂ́A2024�N4������x���s���ɂ���_�n��1��m2�̉c�_�^�̎��Ɨp�ሳ���z�����d��3�`4�J���Ŕ��d�����ăG�l�d�͂��w�����A�旧���w�Z�Ŏg�p����B�N�Ԕ��d�ʂ͖�25��kWh�ŁA�����w�Z�̎g�p�d�͂̂قڑS�ʂ�d���錩���݁B �\�[���[�V�F�A�����O�̔��d���Ǝ҂͎s���G�l���M�[���i�x���s�j�ŁA���d�����d�͂́A�����d�C���Ǝ҂̂��������d�͂�ʂ��čw������B����́A�\�[���[�V�F�A�����O�݂��A�旧�{�݂ւ̗��p�g���\�肷��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���A�}�]����1GW���̕��͉ғ��A2025�N�ɍăG�l100�� 2023�N11�����_�ŁA�A�}�]�������E�œW�J���鑾�z���ƕ��͔��d�̃v���W�F�N�g����479���ŁA�����̂��ׂẴv���W�F�N�g���ғ�����ƁA�N�� 7��1900GWh�i71.9TWh�j�ȏ�̃N���[���G�l���M�[�����ݏo�����B ���̒��ɂ́A2023�N11���ɉғ���������́A���Ђōő�K�͂ƂȂ镗�͔��d�����܂܂��B�e�L�T�X�B�ɐݒu���ꂽ���̃v���W�F�N�g�́A350����镗�Ԃō\������A���o�͂�1000MW�i1GW�j����B���Ђ́A���͂Ƒ��z�����d�ɓ������A2024�N�܂łɓ��Ђ̑S���Ƃŏ����G�l���M�[��80�����ăG�l�Řd���A�����2030�N�܂ł�100���d���Ƃ����ڕW���f���Ă���B�A�}�]���̍ăG�l�v���W�F�N�g�́A���E26�J���ƕč���21�B�œW�J����Ă���B401�̃v���W�F�N�g�̂����A�{�Ђ��\����č���������200���߁A�o�͋K�͂ł�66����13.5MW���߂�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��CCS�֓��������A�e�������x�����㉟���^2050�N�A�r�o�ʂ�1���˒� ���E��CCS�i��_���Y�f����E�����j�̓����Ɍ��������������������Ă���B�e����CCS�Ɋ֘A����@���x��{�x���̐������i�݁A�o�ώY�ƏȂɂ��ƕĉ��A�����A�C���h������2050�N�܂łɔN��40���g�����̓�_���Y�f�iCO2�j�����������܂�Ă���B ����̐��E�ɂ�����r�o�ʂ̖�10���A���{�̔r�o�ʂ̖�4�{�ɑ�������K�͂ŁA���E�̑��r�o��Ƃ�CCS���p�ɓ����B���{�̓G�l���M�[�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j��CCS�̃��f�������7���̑����Ă���A�����n�J����@�����Ő�s���鉢�Ă�ǂ��B CCS�𑣂���Ȏ��g�݁E�p���F����20�N�Ԃ�200�����[���𓊎��B�EEU�F�Ζ��K�X�ƊE��2030�N�ɔN��5000���g���̒����e�ʊJ����v���B�E�č��F�C���t���}���@��CCS���Ƃ̐ōT�����g�[�B�E���{�F30�N�ɍ��v��1300�g�������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���O�Y�H�ƁA�u�M�̒E�Y�f�v�ŕăX�^�[�g�A�b�v�ƒ�g �O�Y�H�Ƃ́A�N���[���G�l���M�[�Z�p�̊J������|����ăX�^�[�g�A�b�v��ModernHydrogen�ƁA�����̃K�X�C���t�������p�����N���[���Ȑ��f��������у{�C���^�]�̒E�Y�f���Ɍ������A�헪�I���{��g�Ɋւ���_�����������Ɣ��\�����B �O�Y�H�Ƃ̐��f�{�C���Z�p��ModernHydrogen�̕��U�^���f�����Z�p��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�Y�ƔM�̒E�Y�f���ɍv������V���ȃ\�����[�V�����̊J����i�߂�B����͓s�s�K�X��LPG�Ƃ����������̃K�X�C���t�������p�����N���[���Ȑ��f�̐����ƔM���p���\�Ƃ��A���̑��̐��f�̐����E�A���Z�p��⊮������̂��Ƃ��Ă���B ModernHydrogen�́A���f����єM�Ɋւ���Z�p�J���Ɏ��g�ރX�^�[�g�A�b�v��ƁB���Ђ̕��U�^���^���M�����Z�p�́A�Ⴂ�J�[�{���t�b�g�v�����g�ŃN���[���Ȑ��f���g�p�n�_�Ő�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E���O���[�����f�ɖ{�C�A�v���2�N��100�{���̋K�͂� �Đ��\�G�l���M�[�̓d�͂Ő���d�C�������Đ��Y����u�O���[�����f�v�ɑ�����v�����܂�A���E�e�n�ł��̐��Y�v�悪�ڔ��������B�������A���Ƃ𐬗�������ɂ͐��d�u�̑啝�ȍ��ى����R�X�g�����K�v���B �����������A���{�̃��[�J�[�́A�Ǝ��̋Z�p�J���ő��Ђ��e�Ղɂ͒ǂ����Ȃ��D�ꂽ���ނ��J���B���ʂŏ��������܂鑾�z�d�r�A��^�����i�ވ���̕��͔��d�ȂǂƂ͈قȂ���{�̃��[�J�[�������c�铹���A���d�u��Z�p�ł͌����Ă��Ă���B ����܂Ő��E�ł́A�Đ��G�l�ɓ��������Ď�ɓd�͕���̒E�Y�f���Ɏ��g��ł����B�d�͕���ȊO�̕����E�Y�f�������i�Ƃ��ăO���[�����f�����ڂ���Ă���B�������A���f�͑����̏ꍇ�A��ɍăG�l�Ȃ�CO2�t���[�d�͂Ő���d�C��������Ȃǂ��Đ�������B�d�͕�������̃G�l���M�[�ʂ�1�Ƃ���ƁA����ȊO�̃G�l���M�[��3�O��ƂȂ�B�����d�����߂ɂ��A���d�u�s��͋߂������}���Ɋg�傷�錩�ʂ��ł���B �o�T�u���o�N���X�e�b�N�v |
|
|
| ���@�@[�@2024/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���t���p�l���⊴���̂̋Z�p�����W�A�V���[�v�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r �V���[�v���y���u�X�J�C�g���z�d�r�̌����J���̏⎖�Ɖ��ւ̌��ʂ��𖾂炩�ɂ����B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�̓����͔����Čy���A�����H�����P���ŁA����Ɍ����V���R���^����ϊ������̍����ւ̖��͂�����B���ꂪ������̑��z�d�r�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂闝�R�ƂȂ��Ă���B���̈���ŁA�����������M�����ɉۑ肪����B�V���[�v�́A�����̊�Ɋւ���m���Ɍ��肪�������A�K���X��ł͎��Ђ̑��z�d�r��t���p�l���Ŕ|���Ă����Z�p�����₷���B ���Ђł́A�����V���R���^�ɐϑw���ĕϊ����������߂�^���f���^�����̊J���ƁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�P�Ƃł���ʐω������p�r�Ɍ������J������s���Đi�߂Ă���B2026�N�ɂ́A��������Nj������^�C�v�̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�ɂ��ẮA�^���f���^��30���ȏ�̕ϊ������ɒB���邱�ƁB��ʐω������p�r�ɂ��ẮA���N�ɂ͕ϊ�������20�����x�ɂ͍��߂Ă��������Ƃ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��JFE�X�`�[���A�����ő勉�u�p�v�������ݔ��v�����^CO2�N��16��t�� JFE�X�`�[���́A�����{���S���ɁA�����ő�K�͂̔p�v�������ݔ�������Ɣ��\�����B �ғ��J�n��2024�N10���̗\��B���ݔ��̔p�v�������\�͔͂N��6���g���BCO2�팸���ʂ́A�N��16��t-CO2�i2030�N�x�ł̌��ʁj�������ށB�p�v���́A��ɍ��F�E�R�[�N�X�F�Ō����Y�Ȃǂ̌��ޗ��̑�֕i�Ƃ��ė��p����邪�A���p���ɉ�������K�X��������́A�u�P�~�J�����T�C�N���v�ƔF�肳��邽�߁A�v���X�`�b�N�r�o���Ǝ҂ɂƂ��ẮA�ŏI��������ጸ�ł��郁���b�g������B �����ݔ��̓����z�́A�O���[�v�S�̂�67.5���~�ƂȂ�B����̓����ɂ��āA���Ђ́A2030�N�x�܂łɂ���Ȃ�\�͑�����}��A�����\�͂��ő��2�{���x�܂ň����グ��Ƃ��Ă���B���{�S�|�A���ł́ACO2�r�o�팸�Ɋւ��鎩��s���v������肵�A�N��100���g���̔p�v���̗��p��ڕW�Ƃ��Čf���Ă��邪�A��ނƂȂ�p�v���̏W�ׂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ЁA�J�[�{���N���W�b�g�ōU���^�Z���͊C�O�A�тɏo�� ��菤�Ђ��J�[�{���N���W�b�g�i�Y�f�r�o�g�j���ƂōU���������Ă���B��_���Y�f(CO2)�̋z���Ő�����N���W�b�g���A�Z�F�����́A�V���K�|�[���̃o�����[�l�b�g���[�N�E�x���`���[�Y�E�A�h�o�C�U���[�E�T�[�r�V�Y�iVNV�j���璲�B����_�����������B VNV���C���h�l�V�A�̃X�}�g�����Ŏn�߂��}���O���[�u�A�уv���W�F�N�g��ΏۂɎ��Ǝ��������o���A20�N�Ԃ�COO2��60���g�������̃N���W�b�g�擾�������ށB���B���N���W�b�g����ɓ��n��Ƃɔ̔�����B�A�ю��Ƃł̓}���O���[�u�̈琬�Ǘ��Ȃǂɋ��͂���n��Z���ɑΉ����B �ă}�b�L���[�[�ɂ��Ζ��Ԃ̃J�[�{���N���W�b�g�s���2030�N�ɐ��E�ōő�1800���h���i��27���~�j��2020�N��600�{�Ɋg�傷�錩�ʂ��B�������Ђł͎O�H��������C����CO2�����R���̃N���W�b�g�Ȃǂ������ق��A�ۍg�͏H�c���ŐX�ъǗ��ɂ��N���W�b�g�n�o��}��Ȃ�CN�����𐄐i���铮�����L�����Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���_�C�w���AEV���C�����X�}���[�d�V�X�e���^15kW���f���J�� �_�C�w���́A15kW�o�͂́uEV�p���C�����X�}���[�d�V�X�e���v���J�������Ɣ��\�����B �����f���́A�]�����i�Ɣ�ׂĖ�5�{�̏[�d���x����������B�����Ƃ��ẮA�u��߂邾���v�ŏ[�d�A���o�́i�[�d���ԒZ�k�j�A�d�C�������ŏ����Ȃǂ���������B���V�X�e���ł́A���C�����X�}���[�d�V�X�e����ݒu�������ԏ�ɒ�߂邾���ŏ[�d�������I�ɊJ�n�����B���p�҂̓P�[�u����}����Ԃ��Ȃ��A�[�d�Y���h�~�ł���B �[�d���Ԃ́A���^�g���b�N�Ȃ��3���ԁA��^�g���b�N�͖�5���ԁA��^�o�X�͖�6.5���ԂƁA��^�����鏤�pEV�̃o�b�e���[�ɑ��Ă��Z���Ԃł̏[�d���\�B�g���b�N�̉אς݁E���낵�̎��Ԃ�o�X�̏�q�����~�肷�鎞�Ԃ��[�d�Ɋ��p�ł���B���s�\�����́A1���Ԃ̏[�d�ɂ���100km�B�܂��A15kW���j�b�g����ڑ��ŏo�͂�30kW�A45kW�ɑ����ł���B�L�����̋}���[�d�탌�x�����\�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����dHD�{�Ў��ӍĊJ���A���w�r���Ƀ��K���z���^�u�y���u�X�J�C�g�v�� �����d�͂Ȃ�6�Ђ́A1,000kW���̃t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�iPSC�j���g�������w�r���𓌋��s���c����K���̍ĊJ���G���A�Ɍ��݂���Ɣ��\�����B �ĊJ���Ō��݂���r���̂���PSC��ݒu����̂́A2028�N�x�̊�����\�肷��n��46�K���Ắu�T�E�X�^���[�v�BPSC�Ń��K�\�[���[���d�@�\�������������w�r���͐��E���ƂȂ�B�J�[�{���j���[�g�����ƃG�l���M�[�n�Y�n���̎�����ڎw���B �]���̑��z�d�r�i�ȉ��APV�j�͑ωd�╗���ւ̑Ή��A���z�ȍX�V�R�X�g�Ȃǂ̉ۑ肪���荂�w�r���Ȃǂł̐ݒu���i��ł��Ȃ��������A���ʁA������̑��z�d�r�ł���PSC�́u�����v�u�y���v�u�Ȃ�����v�Ȃǂ̓��������������V���Ȑݒu���@���l�Ă������Ƃɂ��A�Z�p�I�E�o�ϓI�ȉۑ�������ł��錩���݂ƂȂ����B �T�E�X�^���[�ł�PV�̔��d�e�ʂ͒�i��1,000kW�����v�悵�Ă���A��������Ɛ��E���́uPSC�ɂ�郁�K�\�[���[���d�@�\�������������w�r���v�ƂȂ�\�肾�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����������ԕ������^�Z��[�J�[�E�[�l�R���ȂǔM�����u�G���[�g�c���[�v��m���Ă��܂��� ������������������������ʼnԕ��ʂ͏��Ȃ����B���́u�G���[�g�c���[�v�Ɋ�Ƃ��M�������𓊂������Ă���B CO2�z���@�\�ւ̊��҂ɉ����A�X�эĐ��A�ԕ��Ǒ�Ȃǂ̐�D�Ƃ���邩�炾�B����獑�ƓI�ۑ�̉����ɃG���[�g�c���[��ʂ��Ċ�^���悤�Ɛ�����Ђ�Z��[�J�[�����ƓW�J����ق��A�[�l�R���Ȃǂ��֘A�c�̂ɎQ�悷��ȂNj����������B �G���[�g�c���[�͐�������CO2�z���ʂ���ʎ���1.5�{�A�ԕ��̗ʂ������ȉ��Ƃ����D����̂��B�������������߁A�G������������u������v�̉����点��ق��A�؍ޗ��p�ɓK������ԂƂȂ�u�����v�͖�50�N����30�N���x�ւƒZ�k�������߂�B�J���͂̌y�����͂��߁A�R�X�g�ጸ�Ⓤ������Z�k�����҂ł���B �c�ؐ��Y�ʂɐ�߂�G���[�g�c���[�̊����͌���5�����x���B�і쒡�́A������ՂɍĂѐA�т���u�đ��сv�̊g��Ɍ����A2030�N�ɂ�1���{�̕c���K�v�Ƃ��A����3�����G���[�g�c���[���S���ڕW�������Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����C����CO2���������uDAC�Z�p�v���p���։����^���A��Ƃɏo�� ��B��w�́A�o�����ݗ������V���CarbonXtract�ɏo�����A���ƂɎQ�悷��Ɣ��\�����B����w���J�����̕�������p���đ�C����CO2�ډ������Z�p�uDirect AirCapture�iDAC�j�v�̑������p����ڎw���B ��傪�J������DAC�́A�i�m��������p����DAC�Z�p�ŁA�ʏ́um-DAC�iR�j�v�ƌĂ��B��C�ł�߂��邾����CO2������E�Z�k���鐢�E���̋Z�p�ł���A���u������������A���܂��܂ȏꏊ�ł�CO2������\�ɂȂ�Ƃ����B ��B��w�́A����́ACarbonXtract�ɑ��A�]���̋���������������C�Z���X�ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�֘A�ݔ��E�{�݂̒�A�m�����x���ɂ܂œ��ݍ���A�̎x�������{����B��傪���Ԋ�Ƃɏo�������ƎQ�悷��̂́A�����߂āB2023�N�x���ɁACO2������u�̃v���g�^�C�v�����������B2020�N��㔼�ɕ����̋��Ɗ�ƂƎ����d�ˁADAC���u�̓W�J��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ĒN�����Ȃ��Ȃ�^���r�݁X�̉��Ă̗m�㕗�͎��Ǝ� ��v���́A�ăG�l�A���q�͂̔�Y�f�d���̓����A���ł��m�㕗�͂ɗ͂����Ă���B�������A�č��ł͗m�㕗�͂̎��Ǝ҂����d�_���L�����Z��������A���Ƃ���P�ނ��Ă���B ���ޗ���A�H����A�����̏㏸�ɂ�莖�Ƃ̖ړr�������Ȃ��Ȃ������߂��B���B�ł��X�E�F�[�f���̑��G�l���M�[��Ƃ͐��E�ōł��������ǂ��Ƃ���鉢�B�k�C�̎��Ƃ𒆒f�����B�V�K���Ƃł��p�����{�ɂ�鎖�Ǝҕ�W�̓��D�ɉ���҂�����Ȃ������B �R�X�g�㏸�ɂ��A���D�����ł͍̎Z���m�ۂł��Ȃ��Ǝ��Ǝ҂����f�������߂��B�m�㕗�͐ݔ������Ă��鉢�ă��[�J�[�����ޗ���̒l�グ�ɉ����������Ɍ��������f�����B�������[�J�[�Ƃ̋�������������B �����͍����ɑ傫�Ȏs������o���A�ݔ����[�J�[����āA���E�s����l������B���̎�@�ő��z�����d�A���㕗�́A�d�C�����Ԃł͐��E�̍H��ɂȂ邱�Ƃɐ��������B���͔��d�ݔ��̒������[�J�[�̃V�F�A�́A60������75���ɒB���Ă���B �o�T�uWedge�v |
|
|
| ���������H�̃o���N�v�ʃV�X�e���A�p���̎��X�܂Ő�s���[���` �������H�́A���ʏ�������̐V���ȃ\�����[�V���������p�C���b�g���Ƃ̊T�v����B�g�ʂ蔄��h�����E�e���Ō�������Ă���B �v���X�`�b�N���̃p�b�P�[�W�E��̔r���ɂȂ�B�����Ƃ̎��{��̂́A�p���̃����[�X�E���t�B���i�l�ߑւ��j���ƏW�c���R�[�f�B�l�[�g�����g�D�uUK RefillCoalition�i�p���t�B���A���j�v�B�p���t�B���A���́A���E�ő�̃{�b�N�X�X�g�A�`�F�[���EAldi��p���b�g�E�R���e�i�̘V�Y�ƁA�p�ő��̃I�����C���X�[�p�[�A�������H���͂��߂Ƃ��镡���̃V�X�e�����[�J�[����Ȃ�p�[�g�i�[�V�b�v�BAldiUK�̓X�Łg�g���̂ăv���X�`�b�N���g��Ȃ��H�i�����h�ɂ�����g�[�^���V�X�e���̎����^�p���n�܂��Ă���B���i�̕����ɂ͒ʂ��e��iVessel�j���̗p����Ă���B�������H�́u�v�V�I�ȃo���N�v�ʃV�X�e���v�������B���܈������s�v�v�ʃV�X�e���A�t�̃f�B�X�y���T�[�����Ȃǂɂ����͂��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����Ɨp�ψ���̐V���ȏȃG�l������� 2026�N�x��ڕW�Ƃ���V���Ȋ��p�����u�S�����v��444.1W/��ł���A2019�N�x��501.1W/��Ɣ�r���A��11.4%�̌��オ�����܂��B ���d�[�d�͗ʂ�2����3�������Ă���Ɛ��v����Ă��鎖�Ɨp�ψ���ɂ����āA�ȃG�l��̌������ɂ��ċc�_���s���A2023�N6���ɐV���ȖڕW�N�x��ȃG�l������������������܂Ƃ߂܂����B �ΏۂƂȂ鎖�Ɨp�ψ���͈̔͂́A��i�ꎟ�d����600V���A7,000V�ȉ��̂��́B�ڕW�N�x�́A2026�N�x�B��ʁA�����A��i���g���A��i�e�ʁA�d�l��5�̗v�f�܂����S24�敪��ݒ�B�����ڕW��l�͈ȉ��̕\���Q�ƁB �o�T�u���o�Y�ȁv |
|
|
| �����u�X�J�C�g���z�d�r�̐��Ǝ��i���V�݁A��t���J�n ���z�����d�A�h�o�C�U�[�̎��i���x���^�c������{�Z��\��������́A�u���u�X�J�C�g���z���d�r�A�h�o�C�U�[�v���i���x�̎҂��W����B �����i���x��2024�N1���J�n�̗\��B���u�X�J�C�g���z���d�r�́A�y���u�X�J�C�g�ƌĂ�錋���\�������ޗ���p�������z�d�r�B���ϊ������E��R�X�g�E�_��Ȃǂ̓���������A���z���E�ԗ��Ȃǂ̉�����O���ɓ\�������B�����i���擾����ƁA�����z�d�r�̃G�l���M�[�����┭�d�ʂ̍œK�����@�Ɋւ���A�h�o�C�X��A�N���C�A���g�̃j�[�Y�ɍ��킹���\�����[�V�����Ȃǂ��ł���悤�ɂȂ�B �����i�́A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐��m���������A���_�Ɖ��p����ɂ��ăA�h�o�C�X������s�����ƂŁA�l���Ƃ������z�d�r�����₷�����邱�Ƃ�ڎw���ĐV�݂����B�N��E�w�����킸�A�N�ł��ł���B�F��u�K��̎�u����2��9800�~�i�����e�L�X�g��܂ށj�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���X�}�[�g���[�^�[�d�̓f�[�^�����p���A�d�C�������œK���^�G�l�`�F���W �G�l�`�F���W�́A�S���̃X�}�[�g���[�^�[�̓d�̓f�[�^�����p�����V�T�[�r�X�u�G�l�`�F���W�E�}�C�G�l���M�[�v���J�n����Ɣ��\�����B���T�[�r�X�ł́A�ሳ�ƒ�����E�����@�l������2��ނ���A���p�҂̍œK�ȓd�C�̎g�����Ɠd�C�����v�����I�т��x������B �ሳ�ƒ�����T�[�r�X�́A�u�}�C�G�l���M�[�X�C�b�`�v�u�}�C�G�l���M�[�i�r�v�u�}�C�G�l���M�[�A���[�g�v��3�T�[�r�X�B���p�҂́A�ߋ��̎g�p�ʃf�[�^����A�œK�ȓd�C�����v������I���ł���B�܂��A�d�C�̎g�������ς�����Ƃ��ɂ̓A���[�g�ō��m���A�������I�ȕ��@���Ă���B �����@�l�����T�[�r�X�u�}�C�G�l���M�[������ρi�����j�v�ł́A�������߂̃v�������o�ꂵ���ꍇ��_��X�V�������߂��Ȃ�ƁA�d�C��̍팸��Ă𑗕t����B�N�X�A��r����������Ȃ����d�͉�Ђ̑����ς�����I�ɒA�d�̓f�[�^�����ƂɁA���̊�ƂɓK�����d�C��팸�v�������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o���ƃg���^�A�o�b�e���[EV�p�S�ő̓d�r�̗ʎY�����Ɍ��������Ƃ��J�n �o���ƃg���^��EV�̐i�����x���鎟����d�r�ɂ��āA�S�ő̓d�r�̗v�f�Z�p�����E�J���Ɏ��g��ł����B����̋��Ƃ́AEV�����ɍ��e�ʁE���o�͂����₷���Ƃ���Ă��闰�����n�̌ő̓d�������ΏہB ���̗������ő̓d�����́A�_�炩�����̍ޗ��Ɩ������₷�����߁A�d�r�̗ʎY�����₷���Ƃ�������������B�S�ő̓d�r���ڎԂ�2027�|2028�N�s�ꓱ�����߂����B �S�ő̓d�r�̃����b�g�́A�d�������ő̂ł��邽�߁A�d�C��`����C�I�������������邱�ƁA����ɂ��[�d���Ԃ̒Z�k�A�q�������̊g��A���o�͉����\�ɂȂ�B���x�e�����ɂ����A�����E���d���ɋ������߁A���萫�������Ƃ�������������B�d�r����菬�^�ō����\�ɂȂ邱�ƂŁA�X�|�[�c�J�[����A�}���[�d�̕p�x���������p�Ԃ܂ő��l�ȃj�[�Y�ɑΉ��ł���悤�ɂȂ�B�ő�̉ۑ�͑ϋv���B�[���d���J��Ԃ��ƁA�ő̓d�����̊ԂɋT�������A�d�r���\�̗��������A�J���ɐ��������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��9���̒�����Ƃ��E�Y�f���s���{�A�ǂ̓R�X�g���A���Ԓ��� �֓d�G�l���M�[�\�����[�V�����́A������Ƃ̌o�c��3060����ΏۂɁA�u������Ƃɂ�����E�Y�f��̎��{�ɌW����Ԓ����v���C���^�[�l�b�g�ɂĎ��{�������ʂ\�����B �����ɂ��ƁA�o�c�ҁin=3060�j�ɑ��A�u���炩�̒E�Y�f��Ɏ��g��ł���v�̂�10����1�i9.8���j�������B���g��ł��Ȃ��o�c�ҁin=100�j�́u�x��ƂȂ��Ă��闝�R�v�́u�R�X�g��������v�i26.0���j�A�u��Ԃ�������v�i17.0���j�A�u�ǂ����g�߂悢���킩��Ȃ��v�i16.0���j�A�u�K�v�ȃm�E�n�E��l�ނ��s�����Ă���v�i6.0���j�ȂǁA��p��l�ނ��s�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B�������A92.0���̊�Ƃ��A�⏕���̐\���Ώۂ�c�����Ă��Ȃ��B�u���g�݂��J�n�������R�v�́A��Ƃ̐ӔC��v���ɉ����邽�߂������B���{��ł́u�G�l���M�[����ʂ̍팸�v�i66.0���j�A�u�Đ��\�G�l���M�[�̗��p�v�i31.7���j��������ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z��p�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̋����������J�n�A�Y�w�A�g�Ńy���u�X�J�C�g���z�d�r�̎��p�������� �O��s���Y���W�f���V�����Ƌ��s��w�̃X�^�[�g�A�b�v�Ńy���u�X�J�C�g���z�d�r�̊J������|����G�l�R�[�g�e�N�m���W�[�Y�́A�Z��ɂ�����y���u�X�J�C�g���z�d�r�̊��p�Ɋւ��鋤���������J�n�����B �y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A2009�N�ɓ��{�Ŕ�������A���p���Ɍ����Đ��E���ŊJ�����i��ł���B�]���̃V���R���^���z�d�r���A���Ȃ��G�l���M�[�Ő������ł��A�������E�����E�y�ʂł��邱�Ƃ���A���܂��Ƃ��炵�̗l�X�ȋ�ԂɊ��p���ł��A��y�ɔ��d�����A���̓d�C�����p���邱�ƂɓK����B���������ł́A�O��s���Y�̃}���V�������Ŏ��؎��������{����B�}���V�����̋��p���ɂ�����f�U�C�����̍����Ɩ���Ƌ�A�������̃C���e���A�ݒu���A�����̑��z����~�d���A��ԗ��p�Ȃǂւ̊��p��\�肵�Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���X�r���A�c�_�^���K�\�[���[6�T�C�g���J���E�^�c �X�r���́A��錧�}���s�A�Q�n�ː��s�A�Ȗ؎s�ȂǍ��v6�T�C�g�ɉc�_�^���z�����d�^�̑�K�͑��z�����d�����J���E�^�c����Ɣ��\�����B 6�T�C�g�̍��v�o�͖͂�12MW�A�N�Ԕ��d�ʂ͖�1460��kWh�̌����݁B���v�ʐς͖�10ha�ŁA������哤�Ȃǂ��͔|����\��B�{�H�̓G�R�v�A�c�_�҂̓G�R�v��100���q��Ђł���G�R�v�t�@�[���B2024�N3������2025�N2���ɏ����A�^�]���J�n����\��B ���d�����d�͂́A�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i���dEP�j��ʂ��āA�I�t�T�C�g�^PPA�i�d�͍w���_��j�ɂ��A�u�Ճm��q���Y�X�^���[�v�Ȃǂ̕����ɋ�������B�g�p�d�͗ʂ�10�`15���ɑ�������B���dEP�́A�I�t�T�C�g�^PPA�ɔ������d�v����쐬�E��o���A�C���o�����X�R�X�g�����S����B�܂��A�s�����̓g���b�L���O�t�Ώ؏���t�^�����ăG�l�d�͂��������A�Ճm��q���Y�X�^���[�Ȃǂɂ�����g�p�d�͂������ăG�l100���Ƃ���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �������V���R���n���z���p�l�����r���ǖʂɁu�ڒ��v �d�I�Ђ́A���^�y�ʂŋȂ����錋���V���R���n�̑��z���p�l����{�Ѓr���ǖʂɐݒu�����B�ǖʐݒu����Ƃ���1�K�����ŁA�ǂ̂悤�ɐڒ�����Ă��邩���ԋ߂Ŋm�F�ł���B ���i���́u�t���L�V�u���\�[���[G�{�v�ŁA1��������o��370W�̃p�l����13���ݒu�����B���v�o�͂�4.8kW�A�N�Ԕ��d�ʂ�4230kWh��������ł���A�����u����8�����x�ɂȂ�Ƃ����B �����i�́A�����T���|�[�g�p���[���̑��z���p�l���ɁA�d�I�Ђ����{�ň�ʓI�Ȑܔ������◤�����ȂǂɓK�����ڒ��H�@�������J�������B�P�����V���R�����z�d�r�������t�B�����ŋ��\���ŁA����2.5mm�A�d��3kg/m2�Ə]���̃K���X���̖�4����1�̌y���Ə_��������B�d���Q�n��A���w�r���Ȃǂ���܂ő��z�����d�̐ݒu����������ꏊ�ւ̓��������҂����B �T���|�[�g�p���[�́A�y�ʃt���L�V�u���^�C�v�̑��z���p�l���ɂ����钆�������̃V�F�A��70�����߂�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���d�̓f�[�^��AI�����͂��t���C�����X�N���m�A���������N�x����Љ���� �O�d���������́A�t���C���i����j��̈�Ƃ��āA�����ɔ������Č��N�ȏ�Ԃɖ߂����߂̃��j�[�N�Ȏ��g�݂����Ă���B�X�}�[�g���[�^�[���瓾����d�͎g�p�f�[�^���A�A�g��̖��Ԋ�Ƃ��l�H�m�\�iAI�j�ŕ��́A�t���C�����X�N�̑召�肵�ă��|�[�g���쐬�B �����ی���Ђ̎����Ď���ɓ͂��A�����Č��N��Ԃ̊ώ@�ƃt���C���\�h�̎��m���s���Ƃ������̂��B1�N���J�����������؎����Ō��N��ԉ��P��AI�̕��͐��x����Ȃǂ̎��т��グ�āA����2023�N���炱�̎d�g�݂�{�ғ������Ă���B ���N�Ɨv���̒��Ԃ̏�Ԃł���t���C���̍���҂𑁊��ɔ������A�K�ȉ���E�x�����s���A���N�ɖ߂����Ƃ��ł���B�d�͂̎g�p���炤�������鍂��҂̐����Ԃ肩��A�t���C�����X�N���ǂ̒��x����AI�����f����Ƃ������̂��B�t���C���`�F�b�N�̎���\�ɂ�锻�茋�ʂƏƂ炵���킹���̂��B���ʂ́u�d�̓f�[�^�̂݁v�ł���8������v�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���}���[�V�A��CO2�z���A���o�Y�Ȃ�JOGMEC�A�y�g���i�X�ЂƊo�� �o�ώY�ƏȂ́A�G�l���M�[�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j�y�у}���[�V�A���c�Ζ���Ѓy�g���i�X�ЂƁA���{�ƃ}���[�V�A��2���Ԃʼn������ʃK�X�팸�ɍv������CCS���Ǝ����̂��߁A��_���Y�f�̉z���A���E�����Ɋւ��鋦�͊o���ɏ��������B �}���[�V�A��CO2���z���A������ɂ́A���[��������CO2�팸�ʎZ�o���@�̓ԋ��c���K�v�ɂȂ�B���Ȃ͈��������A�A�W�A�E�G�l���M�[�E�g�����W�V�����E�C�j�V�A�e�B�u�Ȃǂ܂��A�䂪���̃G�l���M�[�Z�L�����e�B�̌���ƁA�}���[�V�A���͂��߂Ƃ���A�W�A�n��ɂ����鎝���I�Ȍo�ϔ��W��J�[�{���j���[�g�����̎����ɍv������B�܂��A���{���哱����u�A�W�ACCUS�l�b�g���[�N�v��ʂ��A���{�̋Z�p��x�A�m�E�n�E�����A�A�W�A�S��ł̒m���̋��L�⎖�Ɗ������𐄐i���Ă����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����d�H�ƁA�č���CO2��������Z�p�̎��A11���J�n�\�� ���d�H�Ƃ́A�č����C�I�~���O�B�ŁACO2��������Z�p�̎��؎����ݔ����v�H�����Ɣ��\�����B���ݔ��́A���d������r�o�����r�K�X���������ۂ̃A�~���R�������̊��e���]��������������Ɏg�p�����B ���؎����Ɏg�p�����CO2��������Z�p�́A���Ђ��Ǝ��ɊJ�������A�~���ő̋z���܂�p���ĕ������������́B���ݔ��́A�ቷ���C�ɂ��CO2�̕���������\�Ȃ��߁A�]���́u�A�~���z���t�@�v�����p�����Z�p�Ɣ�ׂāA��荂���ȃG�l���M�[���ʂ����҂����B�����10�����܂łɌ��݂Ǝ��^�]���������A11������{�i�I�Ɋ��e���]���������J�n����\�肾�B �����؎����́A���Ȉϑ����Ɓu���z���^CCUS��ю��؋��_�E�T�v���C�`�F�[���\�z���ƈϑ��Ɩ��i�ő̋z���܂ɂ�镪������Z�p���j�v�Ƃ��Ď��{�����B���Ђ̂ق��A��ʍ��c�@�l�J�[�{���t�����e�B�A�@�\�i�����s�`��j���Q�悷��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����c���s���p�i�\�j�b�N�ƘA�g�A�����ݏ����@�ł��݂̌��ʉ����Ƃ��J�n ���c���s�ƃp�i�\�j�b�N�́A�u�Ȏ����E�z�^�Љ��ڎw�����܂��Â���̎����v�Ɍ��������g�݂𐄐i����Ɣ��\�����B ���̍��ӂɊ�Â��A���҂͉ƒ납��r�o����鐶���ݍ팸��ړI�Ƃ����A�����ݏ����@�����p���邲�݂̌��ʉ��Ɋւ��鎖�Ƃ����{����B���c���s�ł͌��݁A�u�ƒ�ɂ�����1�l1��������̔R�₹�邲�ݔr�o�ʁv�̍팸�ڕW��484g�ƒ�߂Ă���A�����Ƃ͂��̒B���Ɍ��������g�݂̈�ł���B �����ݏ����@��130���̉����ɂ��A�ƒ납��r�o����鐶���݂����������ėe�ς��7����1�܂Ō��e���邱�Ƃ��\�B����ɂ�萅���ʂ����������݂����ʉ��ł��邽�߁A�����I�Ȃ��݂̉^���ƁA�ċp�{�݂̕��S�y���ɂȂ���Ƃ����B���҂͍���A�����Ƃ�ʂ��Ďs��1�l�ЂƂ肪�A�����ʉ��ɊS�������A���݂��Ȃ�ׂ��r�o���Ȃ����C�t�X�^�C�����H�𑣐i���Ă����l�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���č��A���N�ғ��\��̐V�K�d�����z�������Œ~�d�r�E�K�X�Η͂����� �č��G�l���M�[���ǁiEIA�j�̔��\�ł́A2023�N1�`8���̊ԂɁA�A�n�o��23.5GW�̔��d�����č��̑��d�ԂɐV���ɐڑ�����A���Ɖ^�]���J�n���� ���z�����d���ő��37%�i8.7GW�j���߂��B�ő�Č��́A4263�G�[�J�[�̕~�n��120�����ȏ�̗��ʌ^���z���p�l������Ȃ�B�A�n�o��500MW�E�p�l���o��640MW�ŁA50MW�G�l���M�[�����V�X�e�������݂����\�肾�B ���͓V�R�K�X�Η͂ŃV�F�A��28���B����ɃG�l���M�[�����ݔ��� 16%�i3.8 GW�j�A���͔��d��14%�i3.2GW�j�B�A�n�o��1.1GW�̌��q�͔��d�����ғ������B 2023�N9�`12���̊Ԃɂ����28.5GW�̔��d�ݔ����ғ�����\��ł���B2023�N�ɂ͍��v��52GW�̔��d�����V�K�ɉғ�����B���̂���47�������z���A�~�d�r18���A�V�R�K�X�Η�17���A�����ĕ���16�����߂�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��o�͐���ő�p�b�P�[�W�A�u�グDR�v�ςݑ����ɖ{�� �o�ώY�ƏȂ́A�n�����[�L���O�O���[�v���J�Â��A�Đ��\�G�l���M�[�ɑ���o�͐���̗}���Ɍ����A��p�b�P�[�W�Ă����\�����B ��p�b�P�[�W�́A�傫���i1�j���v�ʂł̑�A�i2�j�����ʂł̑�A�i3�j�n�������A�i4�j�d�͎��v�\���E�d�͎s��\���ɂ�����Ή��i�������I�Ȍ����ۑ�j�[�[��4����ɕ����Ă܂Ƃ߂Ă���B����܂Ōo�Y�Ȃ́A�i2�j�Ɋւ��A�ăG�l���d�ݔ��̃I�����C�����A�Η͔��d�̍Œ�o�͂�50������30���ւ̈������ȂǁA�i3�j�ł́A�n��ԘA�n���̉^�p����������Ɋւ��āA�ϋɓI�Ɏ��ł��Ă����B �i1�j�̎��v�ʂ̑�Ƃ��āA�o�͐��䂪�������鎞�ԑтɎ��v��n�o����u�グDR�i�f�}���h���X�|���X�j�v�ɂ��ē����𑣂����B �ƒ�ł́A�~�d�r�E�q�[�g�|���v�����@�̓����ȂǁB�Y�Ɨp�ł́A�n���p�~�d�r�E���d�u�̓����A�d�F�ȂǓd�͑�����Y�Ƃɂ�����DR�̐��i�Ȃǂ��������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���\�j�[�A�g�d���g�m�C�Y�h���甭�d���郂�W���[��IoT�ɓd�͋��� �\�j�[�Z�~�R���_�N�^�\�����[�V�����Y(SSS)�́A�d���g�m�C�Y�G�l���M�[�𗘗p�����G�i�W�[�n�[�x�X�e�B���O(�����d)�p�̃��W���[�����J�������B ����J���������W���[���́A�u�d���g�m�C�Y�v����d�͂��������ɐ�������B�Ⴆ�A�I�t�B�X�̏Ɩ��A�X�܂�ƒ�̗①�ɂȂǂ���펞��������d���g�m�C�Y�𗘗p�B�����d�͌^��IoT�Z���T�[��ʐM�@��̉ғ��ɕK�v�ȓd�͂̋������s�Ȃ��B�J���������W���[���ł́A�d���g�m�C�Y�̔������ł���d�q�@��Ȃǂ̋��������A���e�i�̈ꕔ�Ƃ��Ċ��p�B����ɓd�C�ւ̕ϊ����������߂鐮����H���̗p�����B ����ɂ��A���^�ȃ��W���[���Ȃ���A��Hz�`100MHz�т̓d���g�m�C�Y��d�C�G�l���M�[�ɕϊ����A�����d�͌^��IoT�Z���T�[��ʐM�@��Ȃǂւ̋��d��d�r�Ȃǂւ̏[�d���\�Ƃ���B�Ɩ�������ɓ_�����Ă��邩�̌��m�A���[�^�[������������{�b�g�Ȃǂ̋@��̌̏�̗\�m�Ǘ��Ȃǂւ̉��p�����҂ł���Ƃ����B �o�T�uImpressWatch�v |
|
|
| ����B�d�͂ȂǁA�n���p�~�d�r�̖{�i�^�p���J�n ��B�d�́ANTT�A�m�[�h�G�i�W�[�A�O�H�����́A���������t���ɐݒu�����n���p�~�d�r�̉^�p���n�߂��Ɣ��\�����B �~�d�r�͗e��4,200kWh�A�o��1,400kW�B���z���̔��d�ʂ������钋�Ԃɓd�C�����߁A�Đ��\�G�l���M�[�̏o�͐���ʂ�}����B���{���d�͎�����iJEPX�j�X�|�b�g�s��Ȃǂ̓d�͎s��Ŏ��v�鎖�ƃ��f���ɂ��Ă����ۂɒ~�d�r���^�p���Č�����B 3�Ђ�2023�N6������A�n���p�~�d�r�����p���čăG�l�̏o�͐���ʂ�}���鎖�Ƃ̌������n�߂��B���̕⏕���āAGS���A�T���̃��`�E���C�I���d�r��ݒu���A���N4�`6���̎����^�p�ł�47��ŗv26��kWh�̏[���d�����{�����B 3�Ђ͒~�d�r�ɂ��߂��d�C���X�|�b�g�s�����������s��Ŏ�����鎖�Ƃɂ��Č����J�n�����B2025�N�x�ȍ~�͗e�ʎs��ւ̋����͋��o���\�肷��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��NTT�f�[�^�A�A AI�����p�����V���ȏȃG�l���M�[�{��̌��� NTT�f�[�^�́A�����K�X�s���Y���Ǘ����镨���ɂ����āAAI��p�����œK���T�[�r�X�̗L���g���C�A�����s���B �{�T�[�r�X�́A�����ɍł��e����^����l���ƊO�C���̕ω���AI�����͂��邱�Ƃɂ��A�����̕ω��𖢑R�ɖh���t�B�[�h�t�H���[�h�^�̋R���g���[������������B�����K�X�̊Ǘ������ɂ�����ċG���ԁi2023�N8���`9���j�̃G�l���M�[�팸���ʂ̌����s���B���Ђ͂���܂ŁA�ȃG�l�Ɖ��K�Ȋ��𗼗����邽�߂�AI�����p�����̃R���g���[���V�X�e���̊J���E���؎�����i�߂Ă����B�����K�X�ƁAAI��p�����œK���T�[�r�X�̃g���C�A�������{���邱�ƂŁA�����K�X�s���Y���ڎw�����ɂ₳�����s���Y�̎������x������B ��̓I�ɂ́A�r���̑啔�����߂�G�l���M�[�ɂ��āA�]���̋@����C�ł͂Ȃ��ANTT�f�[�^��AI�����p���邱�Ƃŏ��������E�^�p�R�X�g��}���A�ȃG�l������V���Ȏ{��̗L������������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���a�@���W�I�l���ǁA���ӏZ����11�l�������ۂ��܂ޔ��ݔ�����g�U���{��E��� �{�錧���s�̉i�m��a�@�ŋN�������W�I�l���ǂ̏W�c�����ŁA�{�錧�́A�a�@���ӂ̏Z����11�l�̃��W�I�l���ǂւ̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B �a�@�̋ݔ��Ō��o���ꂽ���̖ڈ��l���郌�W�I�l���ۂ��܂ޔ��@�������łȂ��~�n�O�ɂ��g�U���A�������L�����\��������B���ɂ��Ƒ��ی����Ǔ���7����{�`8�����{�A�i�m��a�@�̗��p�����Ȃ�13�l�����W�I�l���ǂɂ��������ƈ�Ë@�ւ���͂��o������A����40�`80��̒j��11�l���a�@���甼�a3�L���ȓ��Ɏ����Ζ��悪����Ɣ��������B�c��2�l�͕a�@�Ƃ͖��W�̊����Ƃ݂���B11�l��4�l����̎悵�����W�I�l���ۂƁA�a�@�̋ݔ��̃��W�I�l���ۂ̈�`�q�p�^�[������v�����B ���͍�����ƂȂ����u��p���v�ƌĂ��ݔ������錧���{�݂ɑ��A����I�Ȑ��|�ȂǓK���Ǘ��̓O����Ăт����Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���ܔ������̃\�[���[�J�[�|�[�g�A��4���10.2kW�̑��z�� �f�U�C���A�[�N�́A�\�[���[�J�[�|�[�g�i���ԏ�^���z�����d�ݔ��j������Ɣ��\�����B�f�U�C���A�[�N�͑�a�n�E�X�H�Ƃ�100���q��ЂŁA�C���e���A�E���ނ̐v�E�����E�̔��Ȃǂ���|����B �ܔ����̏�ɑ��z���p�l���𓋍ڂ���J�[�|�[�g�ŁA��2��p�i���z���p�l��12���A�ő�5.1kW�j��4��p�i��24���A�ő�10.2kW�j�����C���A�b�v�����B�ڋq�̗v�]�ɉ����Ċe���[�J�[�̑��z���p�l���ɑΉ��ł���B�����g���i�E�\�[���[���ƃV���[�v���Őݒu���m�F�ς݂Ƃ����B �\�����ɃX�`�[�����̗p���邱�ƂŁA�h�Βn��E���h�Βn��ɐݒu�\�B�ϕ����\��46m/s�A�ϐϐᐫ�\��900N/m2�i30cm�����j�ŁA���ϐ�n��E���Q�n���������ʒn��ɑΉ�����B�{�̃t���[���̓u���b�N�A�@�B���̓u���b�N�܂��̓V���o�[�A�ܔ����̓V���o�[�̔z�F�ŁA���z�ӏ��˂Ȃ��V���v���ȃf�U�C�����̗p�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u������C�d�r�v���d�r�̐V���ȓ����J���\�� �X�}�[�g�t�H����d�C�����ԂȂǂɂ́u���`�E���C�I���d�r�v���p�����Ă��邪�A���`�E���̌͊��Ȃǂ̖�肪�������邱�Ƃ���A�V���ȓd�r���i�߂��Ă��钆�A�u������C�d�r�v�ŐV���Ȓm��������ꂽ�B ������C�d�r�͕��ɂɈ������g���A���ɂɊO�������荞��C���̎_�f���g�����Ƃœd�͂���̂ŁA�ޗ��������Ȃ��Ƃ��烊�`�E���ɑ����i�Ƃ��Ẳ\�������҂���Ă��邪�A�d�����Ⴂ�Ƃ�����肪�������B�G�f�B�X�E�R�[������w�����̃A�Y�n������́A���ɂ̍ޗ����������A�R�o���g�A�j�b�P���A�S���܂ރi�m�����ޗ���V���ɍ��������B ���̈�����C�d�r�́A1.48V�Ƃ��������J�H�d���������A�[���d���ɓd�����x5mAcm��0.77V�Ƃ����Ⴂ�d�ʍ������������B���̍ޗ��ł́A�ő�950���Ԉȏ���肵�����\���������B�V�����v�͔��Ɍ����I�ŁA�d�r�̓�����R��}�����A���̓d���͗��_�d���ɋ߂��A�����d�͖��x�ƒ������Ԃ̈��萫�������炷�B �o�T�uGIGAZINE�v |
|
|
| �������s�s��A�u�y���u�X�J�C�g�{�V���R���v�ł��Ȃ����鑾�z�d�r �y�ʂŔ����A�Ȃ��邱�Ƃ��\�ȃt���L�V�u���������y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A����܂ňȏ�ɑ��z�����d�̗��p���𑝂₹��Z�p�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B ����A�y���u�X�J�C�g���z�d�r�͂��ł�25%�ȏ�̍����ϊ��������B������Ă��邪�A����Ȃ鍂�������̃A�v���[�`�Ƃ��ăy���u�X�J�C�g���z�d�r�ƕʂ̑��z�d�r��g�ݍ��킹��^���f���������ڂ���Ă���B�V���R���E�F�n�𔖂����Ă����\�������V���R���w�e���ڍ����z�d�r���쐻����A���̏�Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r��ϑw�����邱�ƂŁA�u�y���ċȂ�����y���u�X�J�C�g/�V���R���^���f�����z�d�r�v�̊J���ɐ��������B�g�b�v���̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�͌���1��m���x�ŁA�{�g�����̃V���R�����z�d�r�̌�����83��m���x�̂��߁A�^���f�����z�d�r�ɂ��Ă��Ȃ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�ϊ������̓Z���ʐ�1cm2������26.5%���B�����ꂽ�B�ŏI�I��35%�ȏ�̕ϊ������̎�����ڎw���Ƃ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o���Ɠ����_�H��A�c�_�^���z���ɂ������������� �o�����Y�́A�����_�H��w�Ǝ�����\�[���[�V�F�A�����O�i�c�_�^���z�����d�ݔ��j�ɂ�����앨�̐���E���n�ʂ̕]����ړI�Ƃ��������������J�n�����Ɣ��\�����B ���Ђ́A��t���؍X�Îs�̐��c��1���^�ǔ����ˑ�Ɨ��ʎ���^���z���p�l�����̗p����������\�[���[�V�F�A�����O��ݒu���A�����J�n�����B�_����ɂ̓p�l�����ō͔|����_�앨�ւ̑��z���Ǝ˂�D�悷�邱�ƂŁA�_�앨�̎��n�ʂƕi�����ێ��E���シ��B ���z���p�l���̏o�͂�45kW�A�ʏ�̑��z�����d�̏ꍇ�̔N�Ԕ��d�ʂ�4��5000kWh���x�ƌ����ށB�V�~�����[�V�����ł͔_����̔��d�ʂ�50�����x�Ǝ��Z���Ă���A���ʎ���p�l���Ŕ_�앨�ւ̌��Ǝ˂�D�悵���ۂ̈편���d�ʂ�ʔN�ŕ₤�B �����_�H��w�Ƃ̋��������ł́A�����ؔ_�n�ɍ�t����������ɂ��āA������Ԓ��̓��˗ʁE���x�i�ώZ�j�Ȃǂ̐�����ɂ�鐬���A���n�ʂւ̉e�����ʓI�ɕ]������B���n��͕i���E�H���Ȃǂ̑�O�ҕ]�������{����B�܂��A���g���ɂ�鉊�V���ł̌��Ă̔����Ȃǂ̍����o�n��Q�̔����h�~�ɂ��Ă���������B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ����u�p�~�d�r�̐��E�s��A2040�N��8���~�A�n���p������ �x�m�o�ς́AESS�iEnergy StorageSystem���G�l���M�[�����V�X�e���j�E��u�p�~�d�V�X�e�������d�r�̐��E�s��Ɋւ��钲�����ʂ\�����B ����ɂ��ƁA2023�N�̓��s��́A���z�x�[�X��2022�N��47.3������3��4191���~�A�e�ʃx�[�X��42.7������109.7GWh�̌����݁B2040�N�ɂ́A��3.6�{��8��741���~�A��5.5�{��421.7GWh�܂Ő�������Ɨ\������B 2022�N�͌��ޗ����i�̍����Ȃǂɂ��~�d�r���i���㏸�������A���Ə���̎��v�����A�n���p�~�d�r�Ȃǂ̑�K�̓v���W�F�N�g�̑����A�f�[�^�Z���^�[��5G�ʐM�Ȃǂւ̐ݔ����������������ƂȂǂɂ��s��͊g�債���B2023�N�������������v�͉����ŁA�����I�ɂ͍Đ��\�G�l���M�[�̕��y�ɔ�����u�p�~�d�r�̊��p�V�[������������Ƒz�肳���B�܂��AEV�i�d�C�����ԁj����ESS�ւ̃����[�X�d�r�̊��p�Ȃǂ��L����A�z�^�d�r�s��̌`�������҂����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/10�@]�@�@�� |
|
|
| ���ϐ����w�A���E�������Ńy���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu �ϐ����w�H�Ƃ́A2025�N�̊������́u�����V���[�P�[�X���Ɓi�O���[�������j�v�ɋ��^���A�J�����̃t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�����Ɣ��\�����B �����V���[�P�[�X���Ƃ́A��Ƃ�����[�Z�p��V�X�e����p���āA�����Ŏ�������A�ݒu�����肷����́B��ʃ^�[�~�i���̃o�X�V�F���^�[��������1km�̂�����250m�Ƀy���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu����B���z���p�l���̏o�͖͂�50kW�B���d�����d�͂́A�~�d�r�ɒ��߂ăo�X�V�F���^�[�S�̖̂��LED�Ɩ��Ɋ��p����B ���Ђ̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A���O�ϋv��10�N�������m�F���A30cm���̃��[���E�c�[�E���[�������v���Z�X���\�z�����B���v���Z�X�ɂ�蔭�d����15.0���̃t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐����ɐ��������B ���݂͎��p���Ɍ����āA1m���ł̐����v���Z�X�̊m���A�ϋv���┭�d�����̂���Ȃ�����ڎw���A�O���[���C�m�x�[�V������������p���ĊJ�����������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z�����d���̔��p�˗����}���A�o�͐���̑����� ���z�����d���̓��������T�C�g�u�^�C�i�r���d���v���^�c����O�b�h�t�F���[�Y�́A���z�����d���̔��p�˗��f�[�^�͂����u2023�N�x���z�����d�����p�s�ꓮ���v�\�����B ���z�����d���̔��p�����́A2022�N�͊ɂ₩�ɑ����Ă������A2023�N����}���ɑ��������B�������͍�N��2�{�y�[�X�ŁA����3�J���i2023�N4�`6���j��392���ŁA�O�N������138���ɔ�ׂŖ�3�{�Ɋg�債���B�C���{�C�X���x�̊J�n�A��K�͏o�͗}���A�o�͗}���G���A�̊g�傪�e�������Ƃ����B �Œ艿�i���搧�x(FIT)�̔��d�P���ʂ̔��p�˗��䗦�́A�S�̂�5����18�~�`21�~�Č��ɏW�����Ă���B�A�n�N�x�Ɋւ��Ă�2018�N�`2020�N�ɘA�n�����������S�̂�5�����߁A2013�N����̍���FIT�J�n�����ɉғ����������P���̈Č��͂��܂�������Ă��Ȃ��X��������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����˗�p��PCS�p�G�A�R���̓d�͍팸�A���K�\�[���[�Ŏ��� ���˗�p���ʂ̂���f�ނ��A�̔�����SPACECOOL�Ђ́A�����s�ƘA�g���āu�匴���K�\�[���[���d���v�ɂ����āA���Ђ̑f�ނ����p���邱�ƂŃp���[�R���f�B�V���i�[�iPCS�j�p�R���e�i�ɐݒu�����G�A�R���̏���d�͍팸��ڎw�������؎������J�n����Ɣ��\�����B ���˗�p���ʂ̂���f�ނ̏��i���́uSPACECOOL�v�B���˓������ő��z���Ƒ�C����̔M���Օ�����ق��A���˗�p�̌����ɂ����͂ɔM�������ƂŁA�G�l���M�[��p�����ɋC���������x���ቺ����Ƃ����B���˗��E���˗��Ƃ�95���ȏ�ŁA��ʓI�ȎՔM��Ɠ����̃R�X�g�Ŏ{�H�ł���Ƃ��Ă���B �{�c�Z���H�ƂƂ̋����v���W�F�N�g�ł́A���f�ނ����H�����R���e�i�ƁA�ՔM�h�����{�����R���e�i�A��ʃR���e�i��3��ނ�ݒu���A�ď�ɋ̏���d�͂��v���������ʁA�ՔM�h�����{�����R���e�i�ɑ���33���A��ʃR���e�i�ɑ���46���̏���d�͂̍팸���ʂ��m�F�����Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ۍg�ƕl�c�A�p�l���E���T�C�N���ō��فA�������ƂƂ̂��ݕ������ۑ肩�H �ۍg�ƁA�p�����̕��ʁE�K�������Ȃǂ���|����l�c�́A�����ŐV��ЁE���N�V�A��ݗ����A�g�p�ςݑ��z���p�l���̃����[�X�E���T�C�N���֘A�T�[�r�X�̒��J�n�����Ɣ��\�����B �ۍg�̓l�b�g���[�N�͂����Ċ֘A�Ǝ�̊�ƂƍL���A�g���āA���Ǘ��v���b�g�t�H�[���܂Ŋ܂߂Ĉꌳ�����邱�Ƃ�͍����Ă����B2023�N�H����ɖ{�i�I�ɃT�[�r�X�̒��n�߂�ӌ��ŁA����̐V��Ђ����̋�̉��Ɍ����������Ƃ�����B �V��Ђł́A�g�p�ςݑ��z���p�l���̃����[�X�E���T�C�N���葱�����ꊇ���čs���郏���X�g�b�v�T�[�r�X�����B�����[�X�ł���g�p�ς݃p�l���͐V��Ђ��������A�����[�X�ł��Ȃ��p�l���́A���T�C�N����O��ɑf�ނ��Ƃɕ����E���������p�����������Ǝ҂����S����B�ۍg�́A�����[�X�̑��z���p�l���̕ۏ��d�����Ă���A���ۃW���p�������r�ۏؐӔC�ی���t�ۂ���d�g�݂ƂȂ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����E���́u�d�C�^���D�v�J���n���ŗ]��Đ��\�G�l�A�s��� �����s�̐V����Ɓu�p���[�G�b�N�X�v���A��������ΐ��E���ƂȂ�u�d�C�^���D�v�̊J���Ɏ��g��ł���B �n���ł͑��z���╗�͂ȂǍĐ��\�G�l���M�[�R���̓d�C���]�邱�Ƃ������A�D�ɓ��ڂ���~�d�r�ɂ��߂āA�s������ɗA������v�悾�B���{��4���Ɋt�c���肵���C�m��{�v��Ŏx������������Ɩ��L���A��菤�Ђ�d�͉�Ђ��o���Ȃǂ�ʂ��Č㉟�����Ă���B �ăG�l�̊g�傪�i�ޖk�C���Ⓦ�k�A��B�Ȃǂ𒆐S�ɁA�d�͉�Ђ��d�C�̉ߏ苟��������邽�ߎ��Ǝ҂Ɉꎞ�I�Ȕ��d��~���w������u�o�͐���v���}�����Ă���B�d�C�^���D�����p���ł���A�ăG�l�̗L�����p�ɂȂ���Ɗ��ҁB �������D���v���A2025�N�̊�����ڎw���B��x�ɉ^�ׂ�d�C�͖�24����Wh�ŁA2��4�琢�т�1�����̎g�p�ʂɑ�������B26�N������؎�����\�肵�Ă���A��B�d�͂≡�l�s�`�p�ǂ��Q�����ēd�C�̏o�ׂ�����������B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���u�d�͒~�d�v���p���֑O�i�^�X�C�X�V���A�����ő�^�ݔ������^�]�J�n �X�C�X�̃G�i�W�[�{�[���g�́A���E���̏��p�d�̓G�l���M�[�����V�X�e���̎��^�]�𒆍��ŊJ�n�����B ���Ђ͌n���d�͂̎����ɘa���ɗ]��d�͂���͂��ďd�ʕ��������ɏグ�A�����N�����ɂ��̏d�ʕ��̍~���G�l���M�[�Ŕ��d�@���ēd�͂����o���u�d�͒~�d�v����|����X�^�[�g�A�b�v�B ����g�p����V�X�e���͏o��2��5��L�����b�g�A�e��10���L�����b�g���B�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��o�͕ϓ������ړI�Ƃ��āA���n��ƂȂǂ��o�����č\�z��i�߂Ă���B���Ђ͎��^�]��ʂ��đ��̒~�d�����Ɣ�r�����ꍇ�̗D�ʐ��������A�d�͒~�d�̕��y�ɂȂ������l�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ߘa�R�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̊�b�r�o�W���E������r�o�W�����i�ꕔ�lj��E�X�V�j�̌��\ ���Ȃ́A�ߘa4�N�x�A3�N�x���ɐV�K�Q�������d�C���Ǝ҂̌W���lj��A����ȊO�̓d�C���Ǝ҂ŗߘa4�N�x�̓d�̓��j���[�ɉ������r�o�W���̌��\����]����d�C���Ǝ҂̌W���X�V�̂��߁A�ꕔ�lj��E�X�V�����B �����́A����r�o�҂��ߘa�T�N�x�V��20���ȍ~�ɗߘa�S�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂ��Z�肷��ۂɗp����W���ɂȂ�B |
|
|
| �����{�͐��f�Ɉˑ������u�l�b�g�[���v���\�B���́E���z����2050�N�E689GW �u���[���o�[�O�́A�u�����G�l���M�[���ʂ��F���{�Łv�\�����B���{�͐��f�Ȃǂ̍��R�X�g�ȋZ�p�ɗ��炸2050�N�܂łɉ������ʃK�X�r�o�ʂ������[���ɂ��邱�Ƃ��\�ŁA�l�b�g�[���o�ςɈڍs����̂ɔ���6.7���h���ȏ�̓����@����܂��Ƃ����B ���{�ő�̉������ʃK�X�r�o�͓d�͕���ŁA���z���ƕ��͂̓������ő剻�����A�~�d�r��Η͂ɂ�����CCS�iCO2����E�����j���������A�����̌��q�͂��ĉғ������邱�Ƃ��A�ł������ȒE�Y�f�̕��@�ƕ��͂���B���͂Ƒ��z���̑��e�ʂ�2050�N�܂ł�689GW�ɒB���A2021�N��8�{�ȏ�Ɋg�傷�錩�ʂ��B2050�N�ɋ��������d�͂́A���͂Ƒ��z����79�����A���q�͂�11�����߂錩���݁B �c��̎��v�́A���́A�n�M�ACCS�t���Η͂Řd���ƍl������B���������Y�̖�3.8���ƂȂ�N�ԕ���2,390���h���̓������K�v�BEV�ւ̓������ő�̊������߁A3.8���h������₳��錩�ʂ��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ĉ��B�A�n���p�~�d�r�̗v�����ʂ�5GW���Ɂu2026�N��10GW�v�ŃO���b�h�̃X�g���X������ 2023�N6�����{�A�ăJ���t�H���j�A�B�ɂ����āA�v�o��5GW�̌n���p�~�d�r�����B�̃O���b�h�i�d�͌n���j�ɓ�������A�I�����C���ɂ���ď[���d���䂪�\�ɂȂ����B 2020�N�Ă̓����ʂ�500MW�ɉ߂��Ȃ������̂ŁA�킸��3�N�Ԃ�10�{�Ɋg�債�����ƂɂȂ�B �J���t�H���j�A�B�̑��d�n�����Ǘ�����J���t�H���j�A�B�Ɨ��n���ƎҁiCalifornia Independent SystemOperator�A�ȉ�CAISO�j�ɂ����\�l�ł��A�����_�ŁA���ۂɘA�n����~�d�r�̑��o�͂� 5.6GW�ɒB�����Ƃ��Ă��� ���Ȃ݂ɁA�����d�������s���Ă���J���t�H���j�A�B�ł́A���d�n���̉^�p�͓d�͉�Ђł͂Ȃ��Ɨ�������c���g�D�ł���CAISO���S���Ă��āA���@�ւ́A���B�̖� 8������їׂ̃l�o�_�B�̈ꕔ�n��̌n���^�p���S�����Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��ANA�A�ĎЂ���CO2����R���̒Y�f�N���W�b�g�w�� �S���{��A(ANA)�́A��C���̓�_���Y�f(CO2)�ډ���A��������ă����|�C���g�t�@�C�u����J�[�{���N���W�b�g���w������Ɣ��\�����B�����|�C���g�t�@�C�u�ƒ��B�_������Ԃ̂͐��E�̍q���Ђŏ��߂Ă��Ƃ����B ANA�́ACO2�����iCDR�j�R���̃J�[�{���N���W�b�g��2025�N����3�N�ԂŌv3���g���ȏ�w������\�肾�B�N���W�b�g�w������ANA��CO2�����������ƌ��Ȃ��B ��C����CO2�ډ������Z�p�́u���ڋ�C����iDAC�j�v�ƌĂ�A�ĉ����Z�p�J���Ő�s���Ă���B�����|�C���g�t�@�C�u�͕ĐΖ��E�K�X���I�L�V�f���^���E�y�g�����A���̎q��ЂŁA25�N���ɂ͕ăe�L�T�X�B�ő�K�͂�DAC�v�����g���ғ�������\�肾�B�����|�C���g�t�@�C�u�ɂ͕ă��i�C�e�b�h�q��Ȃǂ��o�����Ă���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���_�ސ��w�ɂ��C���\�[���[���d�̎��؎����i���l�E�݂ȂƂ݂炢�n��j ���l�s�́A�_�ސ��w�ɂ��C���\�[���[���d�̎��؎����J�n�ɂ��Ĕ��\�����B�C���\�[���[���d�́A�\�[���[�p�l���̗�p�≘��h�~���ɂ�锭�d�����̌��オ���҂ł��A�C�Ɉ͂܂ꂽ���{���n�߂Ƃ����n���K�͂ł̑��z�����d�̉\��������B �_�ސ��w�̌����O���[�v�Ɖ��l�s�́A�ߘa3�N12��24���Ɂu�ՊC���ɂ����錻��I�E��[�I�ۑ�̌����A���l�`�̋@�\�����y�ѐl�ނ̈琬�Ɍ����������͂Ɋւ��鋦��v��������Ă���B ����A������Ɋ�Â��A�݂ȂƂ݂炢�n����{�ۃ������A���p�[�N�t�߂̐���ɂ����āA���{���ƂȂ�C���\�[���[�p�l���̔��d���؎������s���B�����́A�N���[���G�l���M�[�Ƃ��Ċ��҂����\�[���[���d�̓K�n�g��Ɍ����������ŁA�\�[���[�p�l�����C���ɒ��߂邱�ƂŁA���d�����̌���ƁA�t�W�c�{���͂��߂Ƃ����C�����������̕t���h�~�̋@�\�������z�����d�V�X�e���̉\������������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������r�����C�ŏȃG�l��グ�������G�A�R���ȂǕ⏕���ȕ��j ���Ȃ�2024�N�x�A�ȃG�l���M�[�x��Ă�������r�������ɁA�������G�A�R���̓�����f�M���C�Ȃǂ𑣂��⏕���Ƃ�V�݂�����j���ł߂��B �����r���S�̂̏ȃG�l���\���グ����_���ŁA���N�x�\�Z�T�Z�v���ɋ��z�������Ȃ��u�����v���v�Ƃ��Đ��荞�ށB�����\�ȏȃG�l�^�C�v�̋┭���_�C�I�[�h�iLED�j���g�����Ɩ��@��A�f�M���Ȃǂ̓������ΏۂƂȂ錩�ʂ��B �[�l�R�����e�Ђ͋ߔN�A�H�����ł��r�����̋Ɩ��ւ̉e�����ŏ����ɗ}��������C�H������|���Ă���A�x�Ƃ̕K�v�͂Ȃ��Ƃ����B�r���̏ȃG�l�ł́A���Ɣ��d�ݔ��Ȃǂ�����ēd�͂Ȃǂ̃G�l���M�[����������[���ɂ��邱�Ƃ�ڎw���u�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���iZEB�j�v���m���Ă���B����̎��Ƃ́A������ZEB�̊�����Ȃ��Ă��⏕��F�߂�������B�⏕���Ȃǂ̏ڍׂ͔N���̗\�Z�Ґ��ߒ��ŋl�߂�B�ȃG�l���C���K�v�Ȋ����r����22�N���_�Ŗ�110�����ɏ��Ɛ��v�B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���u�f�M���v�����Z��̉��C�ɒǂ����c�������z�⏕�A�ȃG�l�E�E�Y�f�Ɍ��� �Z��ݔ��֘A���[�J�[�����̉��C�r�W�l�X�ɗ͂����Ă���B���N3���ɍ����n�߂��f�M���\�����̂��߂̉��C��p��⏕���鐧�x���ǂ����ƂȂ�A�K���X��g�̎��v���}�����Ă��邩�炾�B ���̒f�M���ɂ��ȃG�l�⌒�N��ւ̌��ʂ͑傫���Ƃ���邪�A�����Z��̑唼�����Ή��ŁA�s��g��̗]�n�͑傫���B�e�Ђ͐��Y�̐������⍂���\�i�̊J�����������Ă���B ���v�̋N���܂ƂȂ��Ă���̂́A���̉��C�H����p��2����1��1�˂�����ő�200���~�⏕���鍑�̐��x���B���B�����Ȃǂ��x��Ă���Z��̒f�M���\�̌���𑣂����Ƃ�ړI�ɓ������ꂽ�B���{���ށE�Z��ݔ��Y�Ƌ���ɂ��ƁA�Ă͉��O�̔M�̖�7��������h�A�Ȃǂ̊J�����������A�~�͎����̔M�̖�6�����O�ɏo�Ă����Ƃ����B ���������̒n�悪�����Z��̒ʋC�����d������Ă��������ł́A�����Z���5000���˂̂����A�ŐV�̏ȃG�l������f�M���\������Ă���͖̂�1���ɂƂǂ܂�B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���@�@[�@2023/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���u���E�̃G�l���M�[�̔�����߂�̂ł́v���������f�֘A����グ600���~�� �����͐��f�֘A���Ƃ̔���グ�ɂ��āA�u�����o�c�v��v�̍ŏI�N�x�ł���2025�N�x�ɁA2022�N�x��3�{��600���~��ڎw���B ���Ђ͔R���d�r�����̓d�Ɋ�ނ̂ق��A���f�����鐅�d�u�̒��j���ނł���d�������Ȃǂ��肪���Ă���B���f�֘A���Ƃ��܂ރT�X�e�i�r���e�B�C�m�x�[�V�������ƑS�̂ł́A2025�N�x��2022�N�x��1.2�{��1��6000���~�̔���グ��ڎw�����A�N���[���G�l���M�[�Ƃ��Ē��ڂ���鐅�f�����Ɋւ�鐻�i�Q�ōU����������B �R���d�r�֘A�̎��v����\�����Ă������A���f�X�e�[�V�����Ȃǂ̃C���t�������Ȃ��A��p�Ԃ̕��y�ɂ͎��Ԃ�������B�G�l���M�[�Ƃ��Ă̐��f�̕����L�тĂ���ƔF���B2050�N�ɐ��E�̃G�l���M�[�̔������߂�̂ł͂Ȃ����Ƃ��\�z����B �������W�J���鍂�����̓d�������ɂ��ő̍����q�i�o�d�l�j�^���d������́A��s����A���J���^���d������Ɣ�ׁA��舵�����e�ՂȂǂ̃����b�g������A���v�����܂�Ƃ݂Ă���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���u���ʔ��d�p�l���v�̃V�F�A�}�g��A���d���Ɨp��8���Ɂ^�t�@�[�X�g�E�\�[���[�����E���A�����̗��ʃp�l����ʎY�� �����V���R���n�̑��z�d�r�ł́An�^�Z���̗̍p�ɂ��A�������痼�ʔ��d�^���z���p�l�������i������Ă���B����A�K���X���ɉ����������̂ŃZ�����`�����锖�����z���p�l���̗��ʔ��d�^�C�v�͐��i������Ă��Ȃ������B ���ʔ��d�^���z���p�l���́A�\�ʁE���ʂǂ���ł����d���\�ŁA�n�ʂȂǂ���̔��ˌ������ʂɓ����邱�Ƃɂ���Ĕ��d�ʂ���悹�����B���̗��ʂ̔��d�ɂ��]���̕Жʔ��d�p�l���Ɣ�ׂ�5�`20�����̔��d�ʂ̑������ʂ����҂ł���Ƃ����Ă���B���Ђ́A�J�h�~�E���e�����iCdTe�j�^�������n�������z���p�l���̐����E�̔��Ő��E�g�b�v�̃��[�J�[�ł���B�v�V�I�ȓ����o�b�N�R���^�N�g������Ƃ��Ă��邽�߁A�ԊO�g���̓��߂ɂ��A�p�l���̓��쉷�x��������A�ϊ������̌��オ���҂ł���B�������z���p�l���̊J���A���Y�̂��߂ɁA��3��7000���h���Ō����J���Z���^�[�����݂���Ɣ��\�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���E�Y�f���x���@�\�A������p���[�^�~�d�r���肪����G�N�Z���M�[�Ђ֏o�� �E�Y�f���x���@�\�iJICN�j�́A�G�N�Z���M�[�E�p���[�E�V�X�e���Y�֏o�������s�����B �G�N�Z���M�[�E�p���[�E�V�X�e���Y�́A�Ǝ��Z�p�̎�����p���[�^�~�d�r�V�X�e�������A�Z���Ԃɍ��o�͂ŏ[���d���鍂�������̓T�[�r�X�y�уo�b�N�A�b�v�d���T�[�r�X�����B�܂��A�d�͂̒����͎���s�ꂪ��s���Ă���A�C�������h��p���ł̃T�[�r�X��W�J���Ă���A����Ɋg����v�撆�B����A���{�ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�̔䗦�����܂�ƂƂ��ɁA�K�v���������d�͌n���̒����͂Ƃ��ăT�[�r�X��ł���悤����Ȃ�J�������{����Ƃ����B JICN�́A�L���Ŏ����\�Ȗ�����n�邱�Ƃ�ڎw���A�J�[�{���j���[�g�����ɒ��킷�鑽�푽�l�Ȏ��Ƃɑ��A���L���X�e�[�N�z���_�[�ƘA�g�����x�����s���Ă����Ƃ��Ă���A�G�N�Z���M�[�Ђ����{���鎖�Ƃ̃��j�^�����O��ʂ��AGHG�팸�Ɍ�������g�ݓ����m�F���Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����z���Łu���d�E�~�d���铹�H�v������MIRAI-LABO�����؊J�n MIRAI-LABO�́ANEDO�̎��Ƃɂ����āA���H�ʂɕ~�݂ł��鑾�z�����d�p�l���ƒ~�d�r��g�ݍ��킹�A�Z���V���O�E�ʐM�E�Ɩ��ȂǂɎ��������d�͂���������u�����^�G�l���M�[�C���t��AIR�v�̎��؎������J�n����Ɣ��\�����B �����́A�I���G���^�������h�{�Е~�n���ɁA�u�����^�G�l���M�[�C���t��AIR�iAutonomous IntelligentRoad�F�����^�m�I���H�j�v��ݒu���A�o�b�e���[�R���g���[���[�Ǝ����d���V�X�e����������B���Ԃ�7��18������2024�N7��17���܂ł�1�N�ԁB2025�N�x�̎��Ɖ���ڎw���B���p�x�ȏ�̌�ʂŐ�����e�̃f�[�^�����W���邽�߁A�����E�ԓ���ɖ�100m2�i���v��200m2�j�̔��d���H��ݒu�B�[���d���ɍs�����u�f�Ƀo�b�e���[���ւ��邱�Ƃ��\�ȃo�b�e���[�R���g���[���[�̋@�\�����m�F����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���V�d�͂̎��ƓP�ނ̓s�[�N�A�E�g�^�ꕔ�T�[�r�X�ĊJ����3���Łu�l�グ�v���� �d�͏�����Ёi�V�d�͉�Ёj�́A���މ��i��G�l���M�[���A�d�͉��s��̍����ňꎞ�t�U����ԂƂȂ�Ȃnjo�c��@�ɂ��炳��Ă���B 2023�N3�����_�̒����ł́A706�Ђ̂����v195�Ђ��u�_���~�A�P�ށA�|�Y�A�p�Ɓv�ƂȂ����B���d�͉�Ђł��A10�В�8�Ђ��ŏI�Ԏ����v�サ���B����������擾�������d��7�Ђ��l�グ�����{���A�V�d�͉�Ђ����i�]�łɓ����Ă���B 2021�N4�����_�œo�^�̂������u�V�d�͉�Ёv706�Ђ̂����A2023�N6�����_�Łu�d�͎��Ƃ̌_���~��P�ށA�|�Y��p�Ɓv�����������̂�180�ЂƂȂ�A3�����_��195�Ђ���15�Ќ��������B 3�����_�Łu�_���~�v�ƂȂ��Ă���112�Ђ̂���31�Ђ��T�[�r�X���ĊJ�������ƂŁA�u�_���~�v��Ƃ����������B�d�͉��s��̓d�͎�����i�́A2022�N�͕���22.4�~�ƍ��l�Ő��ڂ��Ă������A2023�N6�����_�ł͕���11.5�~�Ƃقڔ��l�ɉ������Ă���B �o�T�u�鍑�f�[�^�o���N�v |
|
|
| ��e-dash�A������Ƃ̊��֘A���ɃA�N�Z�X�ł��閳��DB���J e-dash�́A������Ƃ̊��֘A������ł���uaccel.DB�v��J�n�����B �o�^�͕s�v�A�����ŃA�N�Z�X�ł���B���f�[�^�x�[�X�́A������Ƃ̊��f�[�^�⍑�ۓI�ȃC�j�V�A�`�u�ւ̎^���ȂǂɊւ�����J�����W��B ����J�n�����f�[�^�x�[�X�́A�e��Ƃ̓�������T�X�e�i�r���e�B�y�[�W�Ȃǂ̏����t�H�[�}�b�g�Ōf�ڂ���Ă��邽�߁A�f�[�^�̈ꗗ�����������Ƃ������B�Ǝ�┄��E�]�ƈ����Ȃǂ��ގ������Ƃ����f�I�Ɍ����ł��邽�߁A���Ђł�CO2�r�o�ʂ̍팸�ڕW����g�݂��l����ہA���Ƒ��Ђ̗���Q�l�ɂ��邱�Ƃ��\���B ���Ђ͎O�䕨�Y��100���q��ЂŁACO2�r�o�ʉ����̃N���E�h�T�[�r�X�ue-dash�v��W�J���Ă���B�d�C�E�K�X�Ȃǂ̐��������A�b�v���[�h���邱�Ƃɂ��A���Ƃ�ʂ���CO2�r�o�ʁi�X�R�[�v1�E2�j�������ŎZ�o�B�T�v���C�`�F�[���r�o�ʁi�X�R�[�v3�j���A�\�t�g�E�F�A��ŎZ�o�E�����ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���{�錧�c��A�u�ăG�l�V�Łv���A�X�ъJ���Č��ɉې� �{�錧�́A��K�͐X�ъJ�����Đ��\�G�l���M�[�J�����Ƃɑ��ĉېł���u�ăG�l�n�拤�����i�ŏ��v��S���v�ʼn������B �����́A�ăG�l�̍ő�������Ɗ��ۑS�̗�����ړI�Ƃ������́B�X�уG���A�ɐݒu�������z�����d���ɉېł��邱�ƂŁA��K�͂ȐX�ъJ����}�����A���i���ɗU�����邱�ƂōăG�l���ő���ɓ������n��Ƌ�������������̂���g�g�݂��\�z����B�X�ъJ���}����ړI�Ƃ����ăG�l�V�ł�ڎw�������͑S�����ɂȂ�B ����������V�łł́A�ېőΏۂƂȂ�ăG�l���d�́A���z���A���́A�o�C�I�}�X�Ƃ����B�ݒu�ꏊ�������K�n�U�����s�\�Ȑ��͂ƒn�M�͑ΏۊO�Ƃ����B�ŗ��́A�c�Ɨ��v�ɑ��ĊT��20�������Ƃ��A�ăG�l��ʂ��Ƃɐݒ肷��B �ΏۂƂȂ�X�т́A���L�т���ђn��X�ьv��Ώۖ��L�тƂ��A0.5ha�ȉ��͉ېőΏۊO�A0.5ha����ꍇ�͎{�ݑS�̂��ېőΏۂƂȂ�B�J����悪�ېőΏۊO�̓y�n���܂����ꍇ�͖ʐςɉ����Ĉ�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p���{�A�Y�Ɨp�G�l���M�[���̃N���[�����Ɍ����������\ �p�����{�́A�Y�Ɨp�̃G�l���M�[���̉��ΔR������N���[���ȑ�֔R���ւ̓]���x���Ɍ����A��Ƃւ̎����\�����B �����̋K�͂�8,290���|���h�i��151��7,070���~�j�B�p���̒�Y�f�Z�p�̊g��Ɍ����đn�݂��ꂽ���z10���|���h�́u�l�b�g�[���E�C�m�x�[�V�����E�|�[�g�t�H���I�v��ʂ��Ď��{�����B �����̓���́A.�Y�Ɨp�R���]���R���y�e�B�V�����i5,250���|���h�j�F�����H���K���X���[�J�[�Ȃǂ̊�Ƃɂ��A���f��o�C�I�R���Ȃlj��ΔR���ɑ����Y�f�R���̊J���v���W�F�N�g13��.���f�E�Y�f����E�����^�o�C�I�}�X���d�C�m�x�[�V�����v���O�����i�t�F�[�Y2�A,120���|���h�j�F�o�C�I�}�X�Ȃǂ̔p������Y�f������Ȃ��琅�f�ɕϊ�����v���W�F�N�g5��.�Y�f����E�L�����p�E�����iCCUS�j�C�m�x�[�V�����i920���|���h�j�F��_���Y�f�iCO2�j��엿���Y�ɍė��p����Ȃǂ̃v���W�F�N�g11���B �o�T�uJETRO�v |
|
|
| ���I�[�X�e�b�h�A�f���}�[�N��CCS���Ǝ�26�N�ɔN43��t����E���� �m�㕗�͔��d���I�[�X�e�b�h���f���}�[�N�G�l���M�[���̒Y�f����E�����v���W�F�N�g�������Ɣ��\�����B���v���W�F�N�g�ł́A2026�N�����ɔN��43���g���̐����N���Y�f������E�������邱�Ƃ�ڎw���B �I�[�X�e�b�h�̒�Ă����Y�f����E�����iCCS�j�v���W�F�N�g�ɂ��āA�f���}�[�N�G�l���M�[���iDEA�j��20�N�_����������B2023�N6�����瓯�����̔M�d�������d���ł���A�X�l�X���d���i�؎��`�b�v�����j�ƃA���F�f�[�����d���̂�異���{�C���[�ŒY�f������u�̌��݂��J�n�B2025�N���������E�������J�n����v�悾�B �����2��̔M�d�������d������r�o����鐶���N���Y�f���A�k�C�̃m���E�F�[�n��ɂ���NorthernLights��_���Y�f�����{�݂ɗA������B2026�N�����ɂ́A�N�Ԗ�43���g���i�A�X�l�X28���g���A�A���F�f�[��15���g���j�̐����N���Y�f������E��������v�悾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c�Ō�49���[���i��7400�~�j�ō����̓S����H���o�X�Ȃǂ�������ƂȂ�u�h�C�c�`�P�b�g�v�̔̔����X�^�[�g �h�C�c�ł́A2022�N6������8���̉ċx�݂�3�J���ԁA��9���[���i��1340�~�j�őS�y�̌�����ʏ���������{���Ă���A���̊��Ԓ�5200�����̃`�P�b�g��グ�A��10���p���ꂽ�B �������A�����ʂŎ����s�\�ł��邱�Ƃ��������A���i�������ƂȂ����B��49���[���́u�h�C�c�`�P�b�g�v�͒������S���������A�قڑS�Ă̌�����ʋ@�ւŗ��p�ł���B ���̎��g�݂́A���ɂ₳�����S���̗��p�҂𑝂₵�A�K�\�����̏�������炷�Ɗ��҂���Ă���B�u�h�C�c�`�P�b�g�v�̓X�}�[�g�t�H��������w���ł���B�h�C�c���S�́uDB�i�r�Q�[�^�[�v�̑��A�h�C�c�̑S���e�n�ŕ��y���Ă���g�����nMaaS�iMobility as aService�j�A�v���h������w���\���B �o�T�u���oXtrend�v |
|
|
| ���r���E�Q�C�c���F�߂��u�n�����f�v���@�킷��X�^�[�g�A�b�v ���E�̃G�l���M�[�̐��Ƃ��ߔN���ڂ���̂��A�n���[���̎��R�ȃv���Z�X�Ŕ�������n�����f�igeologichydrogen�j���B�R�����h�B�̃X�^�[�g�A�b�v�́uKoloma�i�R���}�j�v�́A��������o�����@�������Ǝ咣���Ă���B ���Ђ̋����n�Ǝ҂ŃI�n�C�I�B����w�̒n���Ȋw�̋����߂�g���E�_���[�iTomDarrah�j�́A���f�̔����ƌ����I�Ȓ��o�Ɋւ��������16���o�肵�Ă���A�Ζ���K�X�Ɠ��l�ɐ��f���@�킷�関�����v�悵�Ă���B 2�N�O�ɂЂ�����Ɛݗ�����A�閧���Ɋ������Ă����R���}�́A�������ōŏ��̌@����s���A��������̎悵����ƃK�X�̃T���v�����������Ńe�X�g���A�ǂ̏ꏊ�̐��f���ł��D��Ă��邩�ׂĂ���B ���Ђ́A�r���E�Q�C�c���͂��߂Ƃ��铊���Ƃ���9100���h���i��127���~�j�̏o�����Ă���B�č��G�l���M�[�Ȃ̉Ȋw�҂����́A�n�����f�����ΔR���ɑ���V���ȑI�����ɂȂ�ƍl���Ă���B �o�T�uForbsJapan�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/8�@]�@�@�� |
|
|
| ��CO2���Œ肷�铹�H�ܑ��I�V�~�Y�ȂǑ������p����ڎw�� �������݂Ɠ��{���H�́A�J�[�{���l�K�e�B�u����������A�X�t�@���g�ܑ��Z�p�̊J���ɒ��肵���B ���{�̓��H�̑啔���̓A�X�t�@���g�ŕܑ�����Ă���B�A�X�t�@���g�ܑ��ޗ���H���Ŏg�p����{�C���E�o�[�i�ނ̃G�l���M�[�������P�Ȃǂ�����Ă��邪�ACO2�팸���ʂ�15�`20%�ǂ܂�B�J�[�{���j���[�g�����ȕܑ��ނ̑�������������Ă����B ���Ђ́A�R���N���[�g����Ŕ|�������ނւ̃o�C�I�Y�̍����m�E�n�E�ƃA�X�t�@���g���ނ̐����Z�p��Z�����邱�ƂŁA�������̒i�K�E�J�[�{���l�K�e�B�u��ڎw���B�I�K���������Ƃ���o�C�I�Y�i�I�K�Y�j�͕���������͗���ɂ��č��� 1�g�������� 25 kg�ȏ㍬�����邱�ƂŁA�ڕW�B���ł���ƌ��Ă���B�g�E�Y�f�A�X�t�@���g�ܑ��Z�p�h�̊m���Ɍ����āA�{�H����ϋv���������A2023�N�x����ړr�ɓ��H�ܑ��H���ւ̎��K�p�Ɉڍs����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���A�T�q�����A�uCO2��H�ׂ鎩�̋@�v�̎��؊J�n�֓��E�����S��30�� �A�T�q�����́A�����ŏ��߂āA��C����CO2���z�����鎩���̔��@�����p����CO2�����z���f���̎��؎������J�n�����B 1�䓖�����CO2�z���ʂ͉ғ��d�͗R����CO2�r�o�ʂ̍ő�20����������ł���A�X�M�i�ї�56�`60�N�j�ɒu��������Ɩ�20�{���̔N�ԋz���ʂɑ�������Ƃ����B�z������CO2�͔엿��R���N���[�g�Ȃǂ̍H�ƌ����Ɋ��p����B�����̔��@�̌ɓ���CO2���z���������ނ𓋍ڂ����B�֓��E���G���A�𒆐S�ɖ�30��ݒu���ACO2�z���ʂ�z���X�s�[�h�Ȃǂ��r�E������B 2024�N����A���̎����̔��@�̖{�i�W�J��\�肵�Ă���B�z������CO2�́A�e�����̂��ƂƋ��n���Ȃ���A���܂��܂ȍH�ƌ����Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��v�悵�Ă���B�z���ނ�엿�ɔz�����y��ɎU�z���邱�Ƃ�CO2�̓y�뒙����}��ق��A�R���N���[�g�̌����ɔz����CO2�̌Œ艻��C���ł̑��ꑢ���ȂǂɊ��p����v��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ������ł�A�`�h�g���œK����^�������Ő�[�Z�p���A���K���ƏȃG�l���� ����ł�́A2025�N���E�����������Ő�[�Z�p�����E��������u�����Љ�V���[�P�[�X���Əo�W�v�̈�ŁA�{�G�l���M�[�}�l�W�����g�̎��Ɏ��g�ނƔ��\�����B ���Ђ̃G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X�uEMS.AI�v��p���A�������e�{�݂̋Ȃǂ��œK���䂵���K���ƏȃG�l�𗼗�������B�����x�◈��҂̍s���E�̉��f�[�^��AI�ʼn�́B���K���������u�G�G�����l�v�Ƃ��Đ��l�����邱�Ƃʼn����̉��K�ȋ�Ԃ�ꏊ�𗈏�҂Ɂu�����鉻�v������������čs���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�c�_�^���z���{�ό��v�A������̌��_���Ńu���[�x���[�͔| �����݂��t�@�[���́A�\�[���[�V�F�A�����O������������̌��_���u�����݂��x���[�K�[�f���v��{�i�I�ɃI�[�v�������B 4�̔��d������\������A���d�����d�͂́A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�Ɋ�Â������d�̓p���[�O���b�h�ɔ��d����B���承�i��18�~/kWh�B���z���p�l�����ɂ�36���1100�{�̃u���[�x���[���͔|����B�u���[�x���[�̓E�ݎ��E�H�ו�����͂��߁A�H��E���R�̌��E�G�l���M�[�̌���ʂ��Ďq�ǂ������l�܂�SDGs�i�����\�J���ڕW�j���w�ׂ�@������ �k������n�����p���A�\�[���[�V�F�A�����O�Ɗό��⋳��̎��_���玖�ƓW�J���Ă���B2021�N�̓v���������̊J���ŔN��1000�l�̗������������B�����G�l���M�[���̗ߘa4�N�x�u�n�拤���^�Đ��\�G�l���M�[���ƌ����v����܂����B���݂͐V�������z�����d�����v�撆�ŁA���d�Ɣ_�Ƃ���̂ƂȂ������Ƃ�W�J����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z���Ŕ��d����u���[���X�N���[���v�A����������a�炰����ʂ� LIXIL�́A���z�r���Ɏ����₷���u���z�����d���[���X�N���[���V�X�e���v���J�������B ���Ђ̃I�t�B�X�r����2022�N4���`2023�N1���̊ԁA�ݒu���Ď��؎��������{�����B����̑��z�����d���[���X�N���[���V�X�e���́A����Ɋ����郍�[�����̃u���C���h�ɑ��z�����d�̋@�\��t�����B���ł́A99���̑��z�����d���[���X�N���[���������̃I�t�B�X�r���̑��̓����Ɍ�t�������B���z�����d���[���X�N���[���́A�z�n�ɂ�郍�[���X�N���[���̎���ʑ��ɑ��z�d�r�Z��������Ă���B �����t�B�����̊�ɔ����V���R���̃Z�����`���������̂ŁA�d�ɂ�d���Ȃǂ��ʂ̎����t�B������Ɍ`�����ĔM�����i���~�l�[�g�j�����@�ŃZ����g���E���~�����B�~�d�r��USB�̒[�q���p�ӂ����B 1.22m2�̃��[���X�N���[���̒���0.84m2�̑��z�d�r�Z����݂����B���d���\�́A�P�K���X�z����54.5W�B���d����90.7%�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IHI�Η͔��d�p�{�C�������o�[�i�̃A�����j�A��Ăɐ��� IHI�͂��̂��сA�����H����̏��^�R�Ď����ݔ��ɂāA��C���������ł��钂�f�_�����iNOx�j��}��������Ԃł̃A�����j�A��Ăɐ��������B �G�l���M�[����ł́A���d����CO2�������Ȃ����f�̗��p�g�傪���҂���Ă���B����ŁA���̕��y�Ɍ����ẮA�^���E�����̃R�X�g���ۑ�ł���A�l�X�Ȍ����J�����s���Ă���B ���̒��ł��A�A�����j�A�iNH3�j�́A���f�ܗL�ʂ̍����A�t���E�^���E�����̗e�Ղ��A�܂��A���w�����Ƃ��Ċ��ɗ��ʂ��Ă���A�A���C���t�������ɐ����Ă��邱�ƂȂǂ���A��Y�f�Љ�̑����������\�ɂ���V���ȃG�l���M�[���Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�����A�A�����j�A�͔R�Ă���ۂɂ�NOx�̔r�o�Z�x���㏸���錜�O������ق��A��R���ł��邽�߁A����R�Ă��ۑ�ƂȂ�B �o�[�i�̍\����A�����j�A�̋������@���H�v���邱�ƂŁA�ΒY��Ď��Ɠ����x��NOx�̔r�o�Z�x��}�����邱�Ƃɐ��������B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| ���u�J�[�{���t�b�g�v�����g���H�K�C�h�v���쐬 ���ȋy�ьo�ώY�ƏȂ́A�u�T�v���C�`�F�[���S�̂ł̃J�[�{���j���[�g�����Ɍ������J�[�{���t�b�g�v�����g�̎Z��E���ؓ��Ɋւ��錟����v�܂��A�J�[�{���t�b�g�v�����g�̎Z��E�\�����Ɏ��g�ނ��߂̎��H�I�ȃK�C�h���쐬�����B �{���H�K�C�h�ł́A�J�[�{���t�b�g�v�����g�K�C�h���C����2���́u��b�v���v�����Z����@�A�\���E�J�����@��r�o�팸�̌������@�ɂ��ĉ�����܂��B�܂��A���̎Z����@�ōs�������f�����Ƃł̍H�v��Appendix�Ɏ����ƂƂ��ɁA�������瓾��ꂽ�m�����܂߁A���H�K�C�h�Ƃ��Đ������Ă���B |
|
|
| ���d�̓f�[�^�̗L�����p�A10�����痘�p�{�i���^24�N11���߂ǁA�S���W�J �X�}�[�g���[�^�[����擾�����d�̓f�[�^�͗l�X�Ȋ��p���@�������܂��B �S����8�疜��̃X�}�[�g���[�^�[����擾�����d�̓f�[�^�̗L�����p���A10���Ɏn�܂�B�d�̓f�[�^���g�����T�[�r�X����鎖�Ǝ҂́A�d�̓f�[�^�Ǘ������ʂ��ē��������ꂽ���v�f�[�^��A�{�l���ӂ��ʃf�[�^���擾�ł���B���ʂ͂P���O�̃f�[�^���ΏہB�����A�����A���G���A����n�߂ɁA2024�N11���܂łɑS��10�G���A�֓W�J����\�肾�B�d�̓f�[�^�������Љ�ۑ�̉�����A�V���ȉ��l�̑n�o�ɂȂ���Ɗ��҂����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��CO2�팸�͂����܂ł����I�t�����X�S��2���Ԕ��ȓ��́u�������֎~�v �t�����X�ŁA�����S���ňړ��ł���Z������Ԃł̍q��@���p���֎~����@�����{�s���ꂽ�B �������ʃK�X�̔r�o�팸��_�������̂ŁA�@�Ă��K�p�����̂́A�����S����2���Ԕ��ȓ��ɓ��B�\�ł��邱�ƁB���̓s�s��8���Ԃ��߂�������ɓ��A��\�ł��邱�Ƃ����ꍇ���B���̖@�Ăɂ��A�p���암�Ɉʒu����I�����[��`�����̃t�����X�������{���h�[�A�i���g�A��������3�H�����֎~�ƂȂ�B ���̑��ɂ��A���ԍq��@�̖�20�{�̓�_���Y�f��r�o����v���C�x�[�g�W�F�b�g�̐�����A�o�C�I�R���Ȃǂ̎����\�ȍq��R���iSAF�j�̊��p�Ȃǂ��B�X�L�|�[����`��2025�N����2026�N�܂ŁA�v���C�x�[�g�W�F�b�g�Ə��^�̃r�W�l�X�@�̏�����̋֎~�\���Ă���B�m���ɉ������ʃK�X�̔r�o�팸�Ƃ����ړI�ւ̉e�������Ō���ƌ���I�����A�������ɒZ�����Ԃ̍q��@�����X�ɔp�~���闬�ꂪ�n�܂������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�Г��Y�f���i2���~�^t�����s�����X�R�[�v3��CO2�팸�� �p�i�\�j�b�N�́A���Ѓo�����[�`�F�[���S�̂ɂ�����X�R�[�v3��CO2�r�o�팸�ƁA�Љ�ւ�CO2�팸�v���ʂ𓊎��̔��f��Ƃ���C���^�[�i���J�[�{���v���C�V���O�iICP�j���x���A2023�N�x���玎�s��������Ɣ��\�����B ����ɂ��A�u�J�[�{���j���[�g�����v�i�E�Y�f�j�Ɓu�T�[�L�����[�G�R�m�~�[�v�i�z�o�ρj�ɍv�����鎖�Ƃ̋����͋���������������Ƃ��Ă���B�Y�f���i��20,000�~�^t-CO2�ɐݒ肵�A2023�N�x���ɁA�Ɠd���Ƃ�S������u���炵�A�v���C�A���X�Ёv�Ő�s��������B�E�Y�f�Əz�o�ςɍv�����鎖�ƂɗD��I�ɒ������������s���A���ʌ����s���Ȃ���A���x�̂���Ȃ�����}��B2024�N�x�ɂ́A�����I�ȑS�Г����Ɍ����āA�����g�債�Ă����\��B����A�O���[�v���ʂ̃X�R�[�v1�A2�ɂ�����ݔ��������f�ɂ�����ICP�ɉ����āA���Ɠ����ɍ��킹�ēƎ��ɓ�������ICP���x�����s��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Ј�1���l�ɁuCO2�r�o�ʎZ��v���i��K�{���A���������j�b�Z�C���a���� ���������j�b�Z�C���a���ۂ́A�Љ�E�n��ۑ�̉����Ɍ������l�ނ̈琬��ړI�ɁA��1���l�̎Ј���ΏۂƂ��āACO2�r�o�ʂ̎Z���@�Ɋւ��閯�Ԏ��i�u�Y�f��v�A�h�o�C�U�[���i���x�v3�����i�̎擾��K�{�ɂ���Ɣ��\�����B ���̎��i�́A�E�F�C�X�g�{�b�N�X�A�����d�̓~���C�Y�A�L�c�ʏ��A���{�����A���������j�b�Z�C���a���ۂ�5�Ђ�2022�N�ɐݗ������u�Y�f��v�A�h�o�C�U�[����v�����E�^�c���s�����́B��Փx�ɉ����Ď��i��3�ɋ敪����邪�A����擾��K�{�Ƃ���̂́A1��Ƃ�CO2�r�o�ʂ̊T�Z���Z��ł���3�����i���B�擾������2024�N�x���B �Ȃ��A2���E1�����i�ɂ��ẮA�擾��K�{�Ƃ����ɁA�L�����A�`���x�����x�̑Ώۂɑg�ݍ��ނƂ����B���̎��i�擾���_�@�ɁA�ڋq�ɑ��A���ۓI�ȃ��[���̗�����O��Ƃ���CO2�팸�x�����j���[�Ȃǂ���Ă����Ƃ��Ă���B �o�T����r�W�l�X� |
|
|
| �����ł������^�M�`���^CO2����Z�p���J�� ���ł��A�H�ꂩ��r�o������_���Y�f�iCO2�j�Ȃ�3��ވȏ�̍����K�X�̔Z�x�������ő����ɑ���ł���Z�p���J�������B �]���̑��u�Ɣ�ׂđ傫����200����1�ȉ��ɏ��^�����\�ȏ�A���莞�Ԃ�1.7�b��150�{�ȏ㑬���Ȃ�B�������ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�ʂ��K�X���Ƃɒ��ڑ���ł��A���M�����̍����f�[�^���擾�ł���B2026�N���߂ǂɎ��p����ڎw���B ���ł̓Ǝ���MEMS�Z�p�����p���A�����^�`�b�v��ɐV�^�̔M�`���^�̃K�X�Z���T�[���ꊇ���Č`�������B�}�C�N���q�[�^�[�Ń����u�����i���j���Ǐ����M���A�K�X�̔M�`�����̕ω��ɂ�郁���u�����̉��x�ω��ɂ���ăK�X�𑪒肷��B�V�����Z���T�[�ł͈قȂ銴�x�̑f�q���p���ĉ��x�ω��̈Ⴂ�����邱�ƂŎ��͂̃K�X�Z�x�𐄒肷��B�Z���T�[�̊e�o�͂Ƃ��ꂼ��̎��O���ʐ�����A�K�X�Z�x�����߂�B����ɂ��3��ވȏ�̍����K�X�̊e�Z�x�𑪒肷�邱�Ƃ��\�ɂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���g�i�~�^�A�A�A����CO2�r�o�ʂ��E�F�u��ŎZ�� �g�i�~�z�[���f�B���O�X�́A�O���[�v�̒��j���Ɖ�Ђł���g�i�~�^�A�̃E�F�u�T�C�g��ŁA�z������CO2�r�o�ʂ��Z�o�ł���T�[�r�X�̒��J�n�����Ɣ��\�����B �g�i�~�^�A�̏W�\�G���A���N�_�ɁA���n�E���n�̗X�֔ԍ���d�ʁE�e�ςȂǂ̉ݕ�������͂���ƁA�����悻��CO2�r�o�ʂ��Z�o�����BCO2�̃T�v���C�`�F�[���r�o�ʂɂ�����X�R�[�v3�̗A���E�z���i�J�e�S��4�A9�j�̎Z��Ɋ��p�ł���B CO2�r�o�ʂ̎Z�o���ʂ́u���W�X�e�B�N�X����ɂ�����CO2�r�o�ʎZ����@�����K�C�h���C��Ver.3.1�v���g�p���ĉ��ǃg���L���@�i�ύڗ��Ǝԗ��̔R����ށA�ő�ύڗʕʂ̗A���g���L������G�l���M�[�g�p�ʂ��Z��j�ŎZ�o����B�u�g�i�~�ցi���ς݁j�̏ꍇ�v�͓��Ўԗ��̐ύڗ��Ȃǂ̎����l���A�u�K�C�h���C����p�����ꍇ�v�́A�K�C�h���C���̎Q�l�l��p���ĎZ�o����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�ƃV�F���A�����H���CO2���C�O�ɒ�����CCS�̌����J�n ���K�X�́A�V�F���E�V���K�|�[���ƁACCS�iCO2����E�����j�o�����[�`�F�[���\�z�Ɋւ��鋤���������J�n����Ɣ��\�����B ���{�����̍H��Ȃǂ�CO2�r�o������CO2��������A�C�O�̒����n�ɒ������邱�Ƃ�ڎw���B CO2�̔r�o�팸�ɉۑ���������{�����̓S�|�E�Z�����g�E���w�Y�Ƃ̍H��Ȃǂ�CO2�r�o������������CO2���W��E�t��������A�A�W�A�����m�n��̒����n�܂őD���A�����A�n���Ɉ����E�������邱�Ƃ�z�肵���ACCS�o�����[�`�F�[���S�̂̎��Ɛ��]�������{����B ���Ђ�2022�N6���A�E�Y�f�Љ�����Ɍ����������������J�n���ACO2����E���p�E�����iCCUS�j�ɂ��Ă����������Ɍ��������c��i�߂Ă����B����̎��g�݂ł́ACO2��r�o����H��ȂǂɊւ�����K�X�̒m���ƁACO2�t���A����CCS�Ɋւ���V�F���̒m����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����I��CCS�o�����[�`�F�[���\�z�̎����\����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IHI���Z�����g���g��Ȃ��R���N���[�g���J���ACO2�r�o�ʂ�80���팸 IHI�́A���l����ȂǂƋ����ŁA�Z�����g�R���N���[�g�Ɠ����̋��x������������W�I�|���}�[�R���N���[�g�u�Z���m���v���J�������B �Z���m���́A�]���̃Z�����g�R���N���[�g�ɔ�ׂ�CO2�r�o�ʂ��ő�Ŗ�80%�팸�ł���B �Z���m���ł̓A���~�i�V���J�����ɃJ���V�E���������قƂ�NJ܂܂Ȃ����^�J�I�������g�p���Ă���B�Z�����g�R���N���[�g�ɑ��āA�ώ_������15�{�����Ƃ������������邽�߁A�������{�݂≷��{�݂Ȃǎ_�������ł��\�����̎g�p���Ԃ�啝�ɒ����ł���B ����ɃZ���m���͔����k���Ȕ��\���������Ƃ���A���Ȃǂ̕����N����R�������ɍ�������������B�Z���m���ŃV�[���h�Z�O�����g�����삵�Ď�����ډ����Ȃǂ̎Љ�����ɕK�v�Ȏ������ς܂��A���i�Ƃ��Ē\�ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���B����A�V������g�u���b�N�A�Z�������i�̖h���ǁA�����p�̊e�핔�ނȂǂւ̓W�J���͂����Ă����\�肾�B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| ���O�Y�H�ƁA�u�M�̒E�Y�f�v�ŕăX�^�[�g�A�b�v�ƒ�g �O�Y�H�Ƃ́A�N���[���G�l���M�[�Z�p�̊J������|����ăX�^�[�g�A�b�v��ModernHydrogen�ƁA�����̃K�X�C���t�������p�����N���[���Ȑ��f��������у{�C���^�]�̒E�Y�f���Ɍ������A�헪�I���{��g�Ɋւ���_�����������Ɣ��\�����B �O�Y�H�Ƃ̐��f�{�C���Z�p��ModernHydrogen�̕��U�^���f�����Z�p��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�Y�ƔM�̒E�Y�f���ɍv������V���ȃ\�����[�V�����̊J����i�߂�B����͓s�s�K�X��LPG�Ƃ����������̃K�X�C���t�������p�������f�̐����ƔM���p���\�Ƃ��A���̑��̐��f�̐����E�A���Z�p��⊮������̂��Ƃ��Ă���B���U�^���^���M�����Z�p�́A���^���iCH4�j�𐅑f�iH2�j�ƌő̒Y�f�iC�j�ɕ������鉻�w�����B�����o�蒆�̋Z�p�͐G�}���g�p�����A�v���Z�X�ɕK�v�ȔM��d�����߂̓d�͂��s�v���Ƃ����B���U�^���f�����ւ̐V���ȃA�v���[�`�́A���f�̋����Ԃ�҂����ɐ��f�ւ̃A�N�Z�X���\�ɂ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��ENEOS�ƃp�X�R�A�X�їR���N���W�b�g�n�o�ŘA�g�A�q�[�U�[�v�� ENEOS�ƃp�X�R�́A�q�[�U�[�v�������p�����X�їR��J.�N���W�b�g�n�o�Ɋւ����{���ӏ�����������B ENEOS�̐X�їR��J-�N���W�b�g�n�o���Ƃɑ���m�E�n�E�ƁA�p�X�R�̍q�[�U�[�v����q�����j�^�����O�Z�p�����W���A�����́E�ыƌ��ЂȂǂ̐X�я��L�ҁE�Ǘ��҂ɑ���A�N���W�b�g�n�o�̎x���Ɍ����������Ə����������s���Ă����B���Ђ̘A�g�ɂ��CO2�z���ʎZ���Ƃ̌�������}��A1���w�N�^�[���K�͂̍L��ȐX�т�ΏۂƂ����X�їR��J-�N���W�b�g�n�o��ڎw���BENEOS�̓X�R�[�v1�A2��CO2�r�o�ʂ��A2030�N�x�܂ł�2013�N�x���46%�팸�A2040�N�x�܂łɃJ�[�{���j���[�g���������Ƃ����ڕW���f���Ă���B �B���Ɍ����āA�X�я��L�ҁE�Ǘ��҂ƐX�їR��J.�N���W�b�g��n�o�����p������g�݂𐄐i�B2022�N11���ɂ́A�V�����_�ь��ЂƘA�g�������������Ɣ��\�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d��94���팸�A�O�H�d�H����������Ɉʒu�Â���u�T�[�o�[��p�Z�p�v�̒��g �O�H�d�H����M�@��̒m�������A�f�[�^�Z���^�[�iDC�j�̃T�[�o�[��p�Z�p�𐬒�����Ɉʒu�Â��Ă���B�T�[�o�[����ɐZ���t�Z��p�����ɂ��A��ʓI��DC�ɔ�ׂė�p�̓d�͂�94���팸����Z�p���J�������B KDDI�ANEC�l�b�c�G�X�A�C�Ƃ̋��������̐��ʂ��BKDDI�Ȃ�DC���Ǝ҂ɓ������Ă���B3�Ђ�KDDI��DC�u���R�l�b�g���[�N�Z���^�[�v�ŁA�t�Z��p������12���܂Ŏ��ؒ����B �������ENEOS�z�[���f�B���O�X�Ȃ�18�Ђ����͂���BDC��p�̏d�v���͍��܂�A�T�[�o�[�̍����\�����i�݁A�r�M����������Ȃ��Ă���B�t�Z��p�͊O�C�ŗ�p����]�������ɉt�Z��g�ݍ��킹���B�T�[�o�[��Y�����f�n��p���ɐZ���ė�p���A���ɔM���ړ������M������ŔM�𐅂Ɉڂ��B���̌��ʁA��p�d�͂�啝�팸���A�d�͌����w�W�iPUE�j��1.05�����������B��ʓI��DC�ł�1.7�O�ゾ�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����z�����d�{�\�o�͔|�A2MW�̃\�[���[�V�F�A�����O�����^�É��K�X���p���[ �É��K�X���p���[�Ɨ鐶�́A���z�����d�ƃ\�o�͔|��g�ݍ��킹���A�c�_�^���z�����d�����J�������B ���d�e�ʂ͖�1,980kW�A�N�Ԕ��d�d�͗ʂ͖�242��kWh��������ł���B �����d���́A���炭�k�삪�Ȃ���Ă��Ȃ������ʐϖ�2.5�w�N�^�[���̓y�n�����p�B���z�����d�ݔ���4���ɐݒu���A���łɉ^�]���J�n���Ă���B�É��K�X&�p���[�����z�����d���Ƃ̊Ǘ��E�^�c��S���A�É����𒆐S�ɖ�̐��Y�Ȃǂ���|����鐶���A���̃m�E�n�E�����p���A���z���p�l���̉��Ŕ_�앨�͔̍|�E�琬�E�̔����s���B �_�앨�ł���\�o�́A2023�N�H����ɂ͍͔|���J�n���A�N���ɏ���̎��n��\�肵�Ă���B�N�Ԏ��n�ʂ͖�1.2�g����z��B���n�����\�o�͐H�i��Ђɔ̔�����ق��A�É��K�X�̃G�l���A�V���[���[���ōs���u���Αł������v�Ȃǂ̗��������ł����p���Ă����l���B�É��K�X�O���[�v�́A������A������Đ��\�G�l���M�[�̊J���Ɩ��k��̊��p�ɂ����g�ށB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ڗʂT�{�E�R�X�g10���̂P�A�g���^�����f�Љ�֎�����u�������W���[���v�̑S�e �g���^�����Ԃ͐��f�����S�E���S�ɉ^�сA�g�����߁u���f�������W���[���v�̎��ɏ��o�����B �ߗׂɐ��f�X�e�[�V�������Ȃ��ꍇ�ł��������A��R�X�g�ʼn^�p�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���B���f���p�̊��҂͍��܂���̂́A�n���ȂǂŐ��f�����p����ɂ͉^���������Ēʂ�Ȃ��B�^���e��Ƃ��ċ������̃^���N�����邪�A�d����ɑΉ����鈳�͂��Ⴂ�̂��ۑ肾�����B �g���^�ɂ�FCV�uMIRAI�i�~���C�j�v�Ŕ|�����������^���N������A����ɃZ���T�[�⎩���Ւf�قȂǂ̈��S�@�\��g�ݍ��킹���̂����f�������W���[�����B���f���ڗʂ�4kg�`36kg�܂ł�4��ނ�p�ӁB�^�u���b�g�[���ȂǂŐ��f�R��Ȃǂُ̈���Ď�������A���f�X�e�[�V�������璼�ڏ[�U�����肷��@�\�����B�����̋������^���N�ɔ�א��f���ڗʂ�5.5�{�B�g���[���[�^���嗬�̈ړ������f�X�e�[�V�����ɔ�׃R�X�g�͖�10���̂P�ɒጸ�ł���Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���}�C�N���\�t�g�A�j�Z���d�͍w���Ő��E���̌_��28�N���狟�� �j�Z�����d���肪����ăw���I���E�G�i�W�[�Ђ́A�}�C�N���\�t�g�Ɠd�͋����_������킵���Ɣ��\�����B��5�N��̋����J�n��������ł���B �w���I���̔��d�v�����g��2028�N�܂łɉғ�����v��ŁA1�N��ɂ�50MW�ȏ�̔��d�ʂ�ڎw���B �w���I����CEO��50MW�͏��ƋK�͂̊j�Z���̑傫�ȑ������Ƃ��Ă���B�w���I���E�G�i�W�[�Ђ́A�}�C�N���\�t�g�Ɛ��E���̊j�Z�����d�ɂ��d�͋����_������킵�����Ƃ\�����B�w���I���̔��d����2028�N�܂łɉғ����A1�N��ɂ�50MW�ȏ�̔��d��ڎw���B Helion�ł́A�u���ׂ����Ƃ͂܂��܂���R����v�Ƃ��Ă��邪�A���E���̊j�Z�����d�{�݂̒ɂ͎��M������Ƃ��Ă���B�j�Z�����d�͔��d���ɓŐ��̋������ː��p������CO2�����������A��R�X�g�Ȃ̂������Ƃ��Ă���A���Ђɂ��Ɗj�Z�����d�̔��d�R�X�g�͌����_��1kWh������0.01�h���Ƃ��Ă���B �o�T�u���C�^�[�v |
|
|
| ���o���A���B�ȃG�l�����C�O�ŒE�Y�f���Ɗg��� �o���́A�ݔ��v�E�{�H����яȃG�l���Ƃ��肪���鍋�B��Ellis Air Group PtyLtd������Ɣ��\�����B ����̓G���X�G�A�Ђ�ʂ��āA���B�ɂ����āACO2�r�o�ʍ팸�ɍv������ݔ��v�E�{�H�����{����B �G���X�G�A�Ђ͍��B�r�N�g���A�B�E�N�C�[���Y�����h�B�𒆐S�Ɏ��Ƃ�W�J�B�ȃG�l���ʂ�R�X�g�팸�Ɋւ���ݔ��v�Z�p�ł́A���B�g�b�v�N���X���ւ�A����܂łɏ��ƃr���E�a�@�Ȃǂ̌��z�����͂��߁A�g���l���E�f�[�^�Z���^�[�Ȃǂ̂�����Љ�C���t���ݔ��Ɍg����Ă���B ���B�ɂ�����ݔ��v�E�{�H�A�ێ烁���e�i���X�T�[�r�X�𒆐S�Ƃ����ȃG�l���Ƃ̐ϋɓW�J�ɂ��A�G�l���M�[����ʂ�ێ���̍팸�E�������ɂ��CO2�r�o�ʍ팸�ɍv�����Ă����B�܂��AEaaS�iEnergy as aService�j���Ɨ̈�ւ̊g��Ȃǂɂ����肷��l�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ۍg�A��Y�f�r�o�^���^�m�[���̔̔��J�nCCU���Ɗg�� �ۍg�́A��Y�f�r�o�^���^�m�[���uCircularMethanol�v�̃A�W�A�i�����������j�ɂ�����̔������擾�����Ɣ��\�����B ���̃��^�m�[���́A�̔�����L������z�����ۉȋZ�L�����i�i�����j������������́B�����i�́A�����̍H��ɂ����āACarbon Recycling International�Ђ�CO2�Ɛ��f���烁�^�m�[��������Z�p�iEmissions toLiquids�Z�p�j���g�p����������B ��̓I�ɂ́A�ߗׂ̎_���J���V�E���H��Ŕr�o�����CO2�ƁA�R�[�N�X�����H�ꂩ��r�o�����R�[�N�X�F�K�X���̐��f���������Đ�������B �V�R�K�X��ΒY���琻�����郁�^�m�[���Ƃ͈قȂ�A�����ߒ��ł�CO2�z���E���p�ʂ��r�o�ʂ����郁�^�m�[�������邱�Ƃ��ł���B�Ȃ����H��́ACO2�Ɛ��f�݂̂��烁�^�m�[���������������鐢�E���̏��Ƒ�^�v�����g�ŁA�����\�͔͂N��11���g���ɋy�ԂƂ����B �o�T����W�]�� |
|
|
| ���@�@[�@2023/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r�A2020�N�㔼�ΗʎY�A2035�N��1���~�K�́^�x�m�o�ς��\�� �x�m�o�ς́A�V�^�E�����㑾�z�d�r�̐��E�s�꒲�����ʂ\�����B����ɂ��ƁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�iPSC�j�́A2020�N�㔼�ɗʎY���{�i�I�ɐi�ނƌ����A2035�N�ɂ�1���~�̎s��K�͂ɂȂ�Ɨ\�����Ă���B 2023�N�̎s��K�͂�630���~�̌����݂ŁA�ꕔ�ŏ��p�����i��ł�����̂̎��ؒi�K�̃��[�J�[�������B�ʎY�Ɍ����āA���B�⒆���𒆐S�ɓ��������������Ă���A���ɒ������[�J�[�͐��{�@�ւȂǂ̎x�����āA�M�KW�K�͂̐��Y�̐��\�z�Ɍ����Đi�߂Ă���B �����V���R�����z�d�r�ɏd�ˍ��킹�邱�ƂŔ��d�����̌��オ���҂����^���f���^���L�]�Ƃ���A���t�����l���i�Ƃ��Đ��Y�̐��̊m�����\�Ȃ��Ƃ���A�^���f���^���s��g������������ƌ�����B �F�f�������z�d�r�iDSC�j�́AIoT�f�o�C�X�p�Z���T�[�d���Ƃ��āA�W�J����Ă���B2023�N��140���~�ƌ����݁A2035�N��350���~�Ɨ\������B�����A�R�X�g�D�ʐ����Ȃ��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u���z���Ń����o�v�ŕ~�n���͂�����������A�P�H�̊�Ƃ������T�[�r�X ���Ɍ������s�ɁA�������s�^�́u���{�b�g�����@�v����������Ȃ���~�n��������Ă��鑾�z�����d��������B �H��̗Βn������A�Z��̒�ȂǂŎg���Ă��郍�{�b�g�^�u�Ŋ��@�v�́A�X�E�F�[�f���̗ыƁE�_�ƁE���������@�탁�[�J�[�ł���n�X�N�o�[�i�����B�ݒ莞�ԑсA�~�n���𑖂��葐������B�[�d�ʂ�����Ώ[�d��܂Ŗ߂�A�[�d������ɁA�Ăѓr���̎�����ɖ߂��đ�������n�߂�Ƃ����A��Ԃ��炸�̏������������Ă���B �P�H�C���U�C�ł́A�ߗגn��̑��z�����d�������ɎG���̏����T�[�r�X����n�߂��B���������@��1���1��600�`5,000m2�̏������\�B����50cm���x�܂Ŋ�����B���i��10���`60���~�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���d����l�����ŋꋫ�́u�n��V�d�́v�A�o�c���艻�̃J�M�͂ǂ��� �����̂�n����Ƃ��o�����Đݗ������n��V�d�͂��ꋫ�ɗ�������Ă���B�d�C�̎d���ꉿ�i���������A�o�c�����������Ă���B �Đ��\�G�l���M�[�d�C�̒��B�g�傪�o�c���艻�̌����Ɛ��Ƃ��w�E���Ă���B�n��V�d�͂͒n���̒�����ƂƋ��͂��A�Đ��G�l�̕��y��i�߂邱�Ƃň���I��CO2�r�o�[���̓d�C���w���ł��郁���b�g������\��������B �������A�鍑�f�[�^�o���N�ɂ��A�V�d�͑S�̂�27.6%�ɓ�����195�Ђ��_���~��P�ށA�|�Y�̏ɂ���B�n��V�d�͂͒n��v�����d�����A�n������x���Ă���X��������B�n��V�d�͂͌o�c�w�͂��d�ˁA�d�͗����̒l�グ��d�͂̐敨����ȂǂőΉ����Ă���B�܂��A�ăG�l���d���Ǝ҂Ƃ̑��Ύ���𑝂₷���݂��s���Ă���B����͒n��Ƃ̋��͂Ŏ��O�̍Đ��G�l���d�ݔ��𑝂₷���Ƃ��ۑ�ƂȂ�B����ɁA�n���D��ŏ���邱�ƂŒn��o�ς̊�������E�Y�f����i�߂邱�Ƃ���Ă���Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ��UBE�O�H�Z�����g�A�Z�����g�����v���Z�X�ŃA�����j�A���Ď��@���� UBE�O�H�Z�����g�́A�Z�����g�����v���Z�X�����CO2�r�o�팸��ړI�ɁA�F���Z�����g�H��̃Z�����g�L�����i�Đ��F�j�Ɖ��ĘF�ŁA�A�����j�A��M�G�l���M�[���Ƃ��Ďg�p���鍬�Ď����ɒ��肵���Ɣ��\�����B����A30����ڕW�ɍ��ė���i�K�I�Ɉ����グ�A�G�l���M�[�]���Ɋւ��ۑ蒊�o�ƁA�Ή���̋����i�߂�B �Z�����g�̒��Ԑ��i�ł���N�����J�[�̐����ɂ́A�M�G�l���M�[���Ƃ��Ď�ɐΒY���g�p����B����܂ł��A���z�p�ނ�p�v���X�`�b�N�����Ă���ȂǁACO2�r�o�ʍ팸�Ɍ����Ă��܂��܂Ȏ��g�݂�i�߂Ă����B���Ђ�2014�N����2018�N�헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����ɎQ��B �u�A�����j�A���ăZ�����g�L�����̋Z�p�J���v�Ɏ��g�B�������ł̓Z�����g�����v���Z�X�ɂ����鉻�ΗR���G�l���M�[�����A�����j�A�ɒu�������錤���J�������{�B���^�H�ƘF�ł̔R�Ď����␔�l��͂�ʂ��āA�Z�����g�N�����J�[�Đ��ւ̎g�p�ɐ������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������z���p�l����JR�w�\���Ŏ��A�ԊO���Ǝ��O���Ŕ��d ENEOS�AJR�����{�AYKK�A���{�Ɏq�iNSG�j�́AJR���փQ�[�g�E�F�C�w�\���ɂ����āA�������z�����d���p�l���uUE Power�v���g�p�������؎������s���Ɣ��\�����B UE Power�́A��ʓI�ȑ��Ɠ����x�̓����x���ێ����Ȃ���A���O���ƐԊO�����G�l���M�[���ɍ������Ȕ��d���\�ŁA�ՔM���ƒf�M���ɂ��D���BENEOS���o������ă��r�L�^�X�G�i�W�[�iUE�AUbiquitousEnergy�j��NSG�������J�������B ENEOS��NSG�́A2021�N9������1�N�Ԃɂ킽���ĉ��O�ł̎g�p�����؎������A���d����9.8���A�o��100W/1m2��B�������B ����͑�2�e�̎��؎����Ƃ��āA�����g�p���̔��d���\�ɂ��Č�����B���փQ�[�g�E�F�C�w�\���̊��ݑ��K���X�̓�����UEPower��ݒu���A���K���X�Ō������������ɑ��锭�d���\��]������B���؊��Ԃ�5��8���`7��14���̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o���A�p�����R���̃O���[�����f�����ֈ���ő��300t������ �o�����Y�́A�č���Ƃ�H.Cycle�ЂƋ����ŁA���{�����Ŕr�o�����s�s���݂Ȃǂ̔p�����������Ƃ������Y�O���[�����f�����̎��Ɖ��������J�n�����Ɣ��\�����B HC�Ђ����{�����œƐ�I�ɓW�J���Ă���u�v���Y�}�����v�ɂ��K�X�������F���g�p���A�p�������������Ő��f�ɕϊ��A���{�̊e�n��ł̐��f�����E���p��ڎw���Ƃ������̂��B �o�����Y�͍���A���p��������i�߁A2030�N��O���ɖ�200�`300�g���^���̔p�������������Đ��f�����鏉���v�����g�����݂��邱�Ƃ�ڎw���B���̃K�X�������F�́A���݂��K�X���������ē����鍇���K�X������A�D����n�Z����V�X�e���ŁA���܂��܂Ȕp�����������Ƃ��ď������邱�Ƃ��ł���B�p�����Ɋ܂܂�鐶���݂Ȃǂ̃o�C�I�}�X�����́A���f��������CO2�r�o�E���邱�Ƃ���A�]���̐��f�����ɔ��CO2�r�o�ʂ̏��Ȃ��������@�Ƃ�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�H��菉�A���YSAF����������680�X�܂̔p�H�p�������S���K�͂� FOOD & LIFE COMPANIES�́A�u�X�V���[�v�Ȃnjv��680�X�܂ɂ�����g�p�ςݐH�p���i�p�H�p���j���A�q��R���iSAF�j�����̌����Ƃ��ċ�������Ɣ��\�����B �p�H�p���̗ʂ͔N�Ԃ��悻90��L��������ł���BF&LC�́A�����z�[���f�B���O�X�A���{�C���^�[�i�V���i���ASAFFAIRE SKY ENERGY�ƁA���YSAF�����Ɍ����S���K�͂Ŕp�H�p���̋����ɋ��͂����{���ӏ�����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ሳ���z���̎��́A6�����p���R���ANITE���̕� ���i�]���Z�p��Ջ@�\�iNITE�j�́A10kW�ȏ�50kW�����̒ሳ���Ɨp�敪�̑��z�����d�ݔ��A20kW�����̕��͔��d�ݔ��Ɋւ��鎖�̕����\�����B�������ɂ��ƁA2021�N�x�̏��o�͔��d�ݔ��̎��̕�220���A�������z����213���A���͂�7���������B ���z�����d�ݔ��̔j���������̔�Q�����͌v260���B���̓���́A�p���[�R���f�B�V���i�[�iPCS�j��159����61�����߂��B�܂��A���z���p�l����53��20���A�x�����i�ˑ�j��46��18���A�x�����i��b�j��2��1���������B ���̌����́A���R��136��52���ŁA���PCS�̔j����Q�����������B�����Ŏ��R�ЊQ��101��39���ŁA�X�Ⴊ57���A���J��19���A���Q��12���A�R����E�����10���A����3���B���z���p�l����ˑ�̕X��╗�J�ɂ��j����Q�����������B ���͔��d�ݔ��̎��̔�Q�����͌v7���ŁA�x�����i�^���[�j��4���A�i�Z����2�����́B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���~���`���z�d�r�ŁA�s�s�^�ǖʔ��d�̗L�������֓����s �����s�́A�d�C�ʐM��w�ƁA�~���`���z�d�r�ɂ��s�s�^�ǖʔ��d�̗L�������ƁA�~���`���z�d�r��p�����V�X�e���ɂ��C�m�x�[�V�����n�o�Ɍ������A�g���Ƃ��J�n����Ɣ��\�����B �~���`���z�d�r�́A�t�B�����^���z�d�r���u�����̂悤�ȍג����~���`�̃K���X�ǂɑ}�����Ċ��S���~�������́B���^���z�d�r�͒��B���ƈꕔ�̎U������ʂŎ�����邪�A�~���`���z�d�r�͕ǖʂȂǂ���̔��ˌ����܂ޗl�X�Ȋp�x�̎�����\�ŁA���o������v�܂ł̔��d�ʂ̕ϓ����������A�����d�ʂ��傫���Ȃ�Ƃ����B �܂��A1�{�P�ʂ̏C�����\�ŁA�����͂̉e�������������Ƃ���ˑ���y�ʉ��ł��邽�߁A�ݒu�̎��R�x�������B �����s�̓s�s���̌��z���ɂ����鑾�z�����d�̑����d�ʂ��A�����݂̂ɑ��z�d�r��ݒu���čs���]���̔��d���@�ɑ���2�{�ȏ�ɑ��������邱�Ƃ�ڎw���B���Ǝ��{���Ԃ�4��1������2026�N3��31���܂ŁB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ő�U������G�l���M�[�팸�A���H�傪�ቷ�ŃA�����j�A�����ɐ��������Ӌ` �����H�Ƒ�w�́A�����ȓS�G�}��200���ȉ��̒ቷ�ŃA�����j�A���������邱�Ƃɐ��������B 200���ł̓A�����j�A��������7���ɏオ��A4.6���قǏ���G�l���M�[���팸�ł���B�R���A�����j�A��엿�����ȂǃR�X�g�̌���������ɒ�Ă��Ă����B �ԎK�̎听���̎O�_����S��G�}�Ƃ��ė��p����B�O�_����S�̕����Ƀo���E����n���������n�t�������ĊҌ����A���f���o���E���̔����q���S�̕\�ʂɕt�������G�}���쐻�����B���f���o���E�����S�ɓd�q���������ď��G�}�Ƃ��ē����B���f���q�␅�f���q���S�G�}�\�ʂŌ��q�ɕʂ�A���f�Ɛ��f���������A�����j�A�ƂȂ��ĕ��o�����B 10�C��100���ŐG�}1�O�����A1���ԓ�����0.1�~�������B180���ł͓�0.4�~�������̑��x�ō����ł����B�����̓S�G�}��200���ȉ��ł͔������Ȃ��B�V�G�}�ŏ���G�l���M�[�͔�������B�S�G�}�͂����ɔ�����B�G���W�j�A�����O��ЂƘA�g���A���p����ڎw���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����J�[�{���j���[�g�����R���r�i�[�g�\�z �䂪����2050�N�̃J�[�{���j���[�g�����Љ������ڎw�����ŁA���ՊC�����Љ�o�Ϗ̕ω���Љ�I�v���ɓK�ɑΉ����A���{�̃J�[�{���j���[�g���������������郂�f���n��ɂȂ�ƂƂ��ɁA2050�N�ȍ~����Ɠ��ɑI�ꑱ���A�Y�Ƌ����͂̂���R���r�i�[�g�ł��葱����悤�A����ׂ��������Ƃ��̎����Ɍ������헪���������߁A�u���J�[�{���j���[�g�����R���r�i�[�g�\�z�v�����肵���B �o�T�u���s�v |
|
|
| ���w�Z�{�݂�ZEB�����i�A���ȏȂ������Ƃ�܂Ƃ� �����Ȋw�Ȃ́u2050�N�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɏ�����w�Z�{�݂�ZEB���̐��i�ɂ��āv�Ƒ肷��������\�����B ���Ȃ́A�G�R�X�N�[���ƒ�`����1994�N����u�����l�����Đv�E���݂���A�����l�����ĉ^�c����A������ɂ����������w�Z�{�݁v�������A���̊�{�I�ȍl��������Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂�Ȃǐ����[����}���Ă����B �w�Z�{�ݐ��́A�����{�݂̖�4�����߂�B���Ȃł́A�q�������⋳�E���ɂƂ��Ẳ��K�Ō��N�I�ȉ��M���̊m�ۂƒE�Y�f���𐄐i���邽�߁A�w�Z�{�݂�ZEB���̐��i�������ɂ��āA�L���҉�c�ɂ����ċc�_��i�߁A����̕����܂Ƃ߂܂Ɏ������B�w�Z�{�݂�������̋��ނƂ��Đ������邱�Ƃɂ��A���E���̊�����̎�g��n��̊��ۑS�̑���̓`���Ƃ̑�����ʂɂ��A�q��������n��̊��ɑ���ӎ��̕ϗe�A�n��̊��ۑS�A�Ђ��Ă͒n�����̕ۑS�ւƂȂ����Ă����Ƃ����҂����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���l�ł��w��OK�I�V�����A100�~�P�ʂŃJ�[�{���I�t�Z�b�g�ł���T�[�r�X�J�n �V�����́A�J�[�{���E�I�t�Z�b�g�N���W�b�g�̌l�������z�w���T�[�r�X���J�n����B���̐��x�ł́A�X�т��z��������_���Y�f�ɗR������N���W�b�g���w�����邱�ƂŁA�����̐X�Â���E�n�����g����ɍv�����邱�Ƃ��o����B����܂ŁA�N���W�b�g�̍w���͎��Ǝ҂𒆐S��1�g���P�ʂŎ������Ă������A���x�̈�w�̕��y��}�邽�߁A��l�ЂƂ肪�����̐X�Â���ւ̎Q����ʂ��ĉ��g����̎�g�ɍv���ł���d�g�݂�Sustineri�ЂƊJ���B�l�����ɐ��L���P�ʂ̃N���W�b�g�w�����\�ƂȂ�WEB�A�v���ŃT�[�r�X�̉^�p���J�n�����B�o�^���ꂽ6�̐X�їR���N���W�b�g�ɂ��āA100�~�A500�~�A1,000�~�P�ʂōw�����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�B�N���W�b�g�̔���́A�V�������̐X�ѐ����ɗ��p����A�n�����g����ɖ𗧂Ă���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2023/5�@]�@�@�� |
|
|
| ��JFE�X�`�[���ɏ��^���f�������u��7����ցA�O�H���H�@�ANEDO���Ƃ� ����̎��́ANEDO�́u�O���[���C�m�x�[�V����������Ɛ��S�v���Z�X�ɂ����鐅�f���p�v���W�F�N�g�v�̊O�����f�⍂�F�r�K�X�Ɋ܂܂��CO2�����p������Y�f���Z�p���̊J���Ɋ��p�����B �������f�������u�́A�V�R�K�X�ł���13A�s�s�K�X��LPG�������ɁA�����C�����@�ō����x�i99.999vol.%�ȏ�j�̐��f�K�X������B���݂́A���f�X�e�[�V������Y�Ɨp�r�Ƃ��āA���܂��܂Ȋ�Ƃ��̗p���Ă���B �S�|�Ƃ͂�����Y�Ƃ̊�Ղ�S������ŁA�����ߒ��Ŕr�o�����CO2�͓��{�̎Y�ƕ���S�̂�40%���߂Ă���BJFE�X�`�[���͌��݁A�r�K�X�Ɋ܂܂��CO2�𐅑f��p���ă��^���ɕϊ����A�Ҍ��ނƂ��ČJ��Ԃ����p�ł���u�J�[�{�����T�C�N�����F�v�Ȃǂ̊J���ɒ��肵�A���S�v���Z�X�����CO2�r�o��50%�ȏ�팸���邱�Ƃ�ڎw���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���r�M80����180���ɏ����A�X�S�������q�[�g�|���v���J�����ꂽ �O�쐻�쏊�́A80���̔r�M���������180���ɏ������鍂���q�[�g�|���v���J�������B 80�`100���̔M�͍H��ő����̂Ă��Ă���B������ō�200���܂ň����グ��B�{�C���̒������ɔ�ׂ�1.75�{�̃G�l���M�[�����ɂȂ錩�ʂ��B�����Ԃ̓h�������H���Ȃǂɒ�Ă��Ă����B �H�ꂩ�甭������80���̉������������ō̔M����B��}��c���قŌ������ď�����ɓ���ĉ����̔M���z��������B�����4�i�̃^�[�{���k�@�ō��������ɂ��ĉ��M��ŔM�}���ɔM���ڂ��B�M�}���͂W�O������180���ƁA100�����������B�M�������100���̉��x����15�N���̔M��J�������N���A�����B�����q�[�g�|���v�Ƃ��Ă�COP�i���ьW���j��3.5��B�����錩�ʂ��B�{�C����1.75�{�̃G�l���M�[�����ɂȂ�B ����A���ۂ̐��Y���C���Ŏ����Ē����M������ʎY�@���m�����A2025�N�x�̔�����ڎw���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���f���\�[�ƃg���^�A�ăG�l���f���H��Ő����E���p�n�Y�n�����f���\�z�� �f���\�[�́A�g���^�Ƌ����ŁA�f���\�[�����̍H����ł̃O���[�����f�̐����ƁA�����������f�̍H��K�X�F���ł̊��p�̎����J�n����Ɣ��\�����B ����̎���ʂ��āA���f�������痘���p�܂ł̃p�b�P�[�W���\�z���A���̃p�b�P�[�W���g�ݍ��킹�邱�ƂōH��̋K�͂ɉ����ĕK�v�Ƃ��鐅�f�ʂ��œK�ɓ����ł���u���f�n�Y�n���v���f�����\�z���Ă����B ���̎��ł́A�u����Z�p�v�u�����Z�p�v�u�͂��ԁv��3�̕���ł��܂��܂Ȑ��ʂ�ڎw���B���f���u����Z�p�v�ł́A�g���^���J���������d�u�����A�f���\�[�����̍Đ��\�G�l���M�[���g�p���Đ��f�������s���B���f���u�����Z�p�v�ł́A���������r�o�K�X�Q������A�t�^�[�o�[�i�[�F�ɂ����ď]���g�p���Ă���LP�K�X���A�����������f�ɒu��������B����ɁA���f���u�͂��ԁv�ۂ̗A���R�X�g�ɂ��ẮA�����������f�����Ə����u���f�n�Y�n���v�ɂ��R�X�g�ጸ���\�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�t����C�G�l���M�[�����V�X�e���v���ғ��ցA�Z�F�d�@�ƍL���K�X�����p���v�����g �Z�F�d�@�B�H�Ƃ́A���Ђ̓����s�H����Ɂu�t����C�G�l���M�[�����iLiquid Air EnergyStorage�ALAES�j�v�V�X�e���̏��p���v�����g�����݂��A���؉^�]���J�n����Ɣ��\�����B�L���K�X�Ƌ����Ŏ��{����v���W�F�N�g LAES�Ƃ́A�d�͂𗘗p���Ĉ��k�E��p���ĉt��������C��ሳ�f�M�^���N�ɒ������Ă����A�K�v�ɉ����čĂыC�����A���̖c���G�l���M�[�𗘗p���ă^�[�r�����d�@���ғ������Ĕ��d����Z�p�B ���ł́A��C�̉t���v���Z�X��LNG�̗�M�𗘗p���邱�ƂŁA�[�d���������߂�Ƃ����B���d���̗e�ʂ�4.99MW�~4���ԂŁA�[�d���̕��ׂ�4MW�ƂȂ��Ă���B��̓I�Ȍ��؍��ڂƂ��ẮA�v�E���݂ɂ�����@�߁E�K�i�ւ̑Ή��A���{�̌n���^�c��d�͎����s��ւ̑Ή��ƍ������A�����p��M�̑��ݗ��p�ɂ��������P�E�ȃG�l���ʂ̌��Ȃǂ�\�肵�Ă���B���v�����g�̉ғ���2024�N��\��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���|���H���X�A�o�[�`�����Z���T�[��p�������Ԃ̋���V�X�e�����J�� �|���H���X�́A���Ԃ̍œK�ȋ�����s���V���Ȏ�@�Ƃ��ăo�[�`�����Z���T�[��p�����f�W�^���c�C���i�������E������W�����l�X�ȃf�[�^���f�W�^����ԏ�ɃR�s�[�B���A���^�C���ɍČ�����Z�p�j�ɂ�����V�X�e�����J�����u���É��s���ۓW����V��1�W���فv�ɏ��K�p�����B �����̋������Ő��䂷��ꍇ�A�ʏ�A�������Ɏ��t�����Z���T�[���瓾����v���f�[�^�ƁA�������̉��K���̎w�W�Ƃ��Đݒ肵���ڕW�l����v��������@�������̗p����Ă���B���������Ԃ̏ꍇ�A��ԗ��p�̏�Q�ƂȂ�Ȃ��悤�ɁA�ǖʂ�_�N�g���ɃZ���T�[��ݒu���邱�Ƃ���A���ߍׂ��Ȑ�����s�����Ƃ�����B �J�������V�X�e���́A�V�~�����[�V�����Z�p�̉��p�ɂ��쐬���������̉�͌��ʂ��瓾����o�[�`�����Z���T�[����Ɏ�������c�����A���A����Ԃ𐧌䂷��B�ʏ�̕����Ɣ�r���Ė�30�`70%���x�̋���G�l���M�[�̍팸���\���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�����f�d�r�ōH��ɔM�E�d�C�����A�����Ŏ�����_�� �p�i�\�j�b�N�͒������n�@�l�i�]�h�ȁj�ŁA�����f�^�R���d�r�ɂ���čH��ɔM�Ɠd�C������������؎������n�߂��B�����s��ɓ��d�r��4���������邱�Ƃ���A���؎����𐅑f���p�̃V���[�P�[�X�Ƃ��Ċ��p�B�ԍڌ��������S�̒����̔R���d�r�s��ŁA�������̒�u�^�V�X�e���𓊓����A���ʉ���_���B���ł͏o��5kW�̏��^��u�^�R���d�r��8�䓱������B�H��̐��Y���C�������ɔM�Ɠd�C����������ق��A�ď�͏L�����`�E���Ⓚ�@�։������������ė�M������[�ɂ����p����B�p�i�\�j�b�N�Ƃ��Ă͔R���d�r���g���ė�[�A�g�[�A�d�͂Ɋ��p���鏉�߂Ă̎��؎����ƂȂ�B�p�i�\�j�b�N�ł�2022�N4���Ɏ��ꌧ���Îs�̔R���d�r�H��ł���u�^�R���d�r99������A���z�d�r��~�d�r�Ƒg�ݍ��킹�����Ɣ��d�ōH����̓d�͂̍Đ��\�G�l���M�[���Ɍ����������n�߂Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����ː����p�̗�[�V�X�e����16���̐ߓd���ʂ��m�F�i���䌧�j �V�A�^�[�n�E�X�́A���̂قǐV�H������݂����ۂɓƎ��̗�[�V�X�e���������B �|���v�ł��ݏグ���₽����ː���Lj�ʂɐݒu�����p�C�v�⏰���ɒ��菄�点���z�[�X�ɒ���I�ɗ������ƂŁA�G�A�R���̓d�C�̎g�p�ʂ�}���Ȃ���A��N��ʂ��Ď�����25������26���ɕۂĂ�Ƃ����B ���H�ƋZ�p�Z���^�[���������Ƃ���A�V�X�e���ɔ�ׂ�15.9���̐ߓd���ʂ��m�F�ł����Ƃ����B����ɒf�M�V�[�g�̎{�H�����킹��A�N�Ԃ�90���̏ȃG�l�ɂȂ��邱�Ƃ�������A���Ђ͗��p�҂̊g���}�肽���Ƃ��Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���J�i�_���{�A�I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g���p�ɂ��Ⓚ�V�X�e���̉������ʃK�X�팸���x�� �J�i�_�́A�������ʃK�X�E�I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g���x�̂��ƁA��_���Y�f�Ⓚ�V�X�e���ȂǁA�n�����g���W���̒Ⴂ��}���g�p�����Ⓚ�V�X�e���ւ̈ڍs�����サ�A�Q����Ƃ��������ʃK�X�r�o���팸���邱�ƂŎ�����v���g�R���ɂ��ĉ�������B ���̐��x�́A�������ʃK�X�̔r�o��h���A�܂��͑�C���珜�����邱�ƂŁA�@�I�v����ʏ�Ɩ��ȏ�̉������ʃK�X�팸�v���W�F�N�g�����Ŏ��{���邽�߂̃C���Z���e�B�u�������̂ŁA�J�[�{���v���C�V���O�̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��B���v���g�R���́A�v���W�F�N�g�������I�A�lj��I�A��ʓI�A���؉\�A�ŗL�A�P�v�I�ȉ������ʃK�X�팸���m���ɐ�������悤�A�Z�p���Ƃ̃`�[���ɂ���Đv����A�H�i���H�H��A�A�C�X�X�P�[�g�����N�A�V���b�s���O�Z���^�[�A�I�t�B�X�r���A�①�q�ɂȂǁA���Ǝ{�݂�Y�Ǝ{�݂ł̗��p���\�ŁA�ΏۂƂȂ�Ⓚ�V�X�e���͏W���^�Ⓚ�@�A�Ɩ��p�G�A�R���A�q�[�g�|���v�Ȃǂł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����E�o����A��C����CO2�ډ���E���p���鑕�u�̊��p���� �o���Ƌ�B��w�A��B�d�͂́A��B��w���J����i�߂镪������p���đ�C������CO2�ډ���iDirect Air Capture�FDAC�j���A��������̏�ŔR�����֎������E���p����uCO2����E���p�iDAC-U�j���u�v�̗p�r�������J���E������Ɣ��\�����B ��B��w�ł́A�������^CO2����umembrane-basedDAC�im-DACTM�j���u�ƁA�������CO2��R�����֕ϊ������p���鑕�u��g�ݍ��킹�A�uDAC-U���u�v�̊J����i�߂Ă���B ����w�������J����i�߂�m-DACTM�Z�p�́A�]����CO2�������Ɣ�ׂċɂ߂č���CO2���ߐ��������Ƃ�����Ƃ��Ă���B���̂��ߏ]���Z�p�̐��\����1�ȉ��̖ʐςŁA����G�l���M�[�Ŏ����ł���\�������܂����B ��������CO2�z���t�Ȃǂ̖�܂��g�킸�A�������̃��W���[�����ŁA�K�v�ɉ�����CO2����ʂ�C�ӂɒ������邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ǔ����̉c�_�^���z�����d�g�̂��ƁA�m�[�^�X�ЂƃT���t�����e�B�A�s���Y �c�_�^���z�����d�̊��E�R���T���e�B���O�̃T���t�����e�B�A�s���Y�́A3�����ǔ����z�����d�Z�p��g�ݓ��ꂽ�ˑ�V�X�e���̔̔��Ȃǂ��s���m�[�^�X�\�[���[�W���p���Ǝ��{�Ɩ���g����Ɣ��\�����B ����A�S���̎����́E���Ԋ�Ƃփ\�[���[�V�F�A�����O�̊��p���Ă��A2030�N�܂ł�400�w�N�^�[���̔_�n�ɍ��v200MW�̃m�[�^�X�А��V�X�e����ݒu���A�N��3��kWh�ȏ�̔��d��ڎw���B�m�[�^�X�\�[���[�W���p�����v�E����u�m�[�^�X�\�[���[�V�X�e���v�́A�����̑��z���p�l���ŎՌ��R���g���[�����s����@�\������A�\�[���[�V�F�A�����O�̎��g�݂Ō��O�����A���z���p�l���ɂ��_�앨�͔|�ւ̉e����}������Ƃ����B �����āA���z����3�����Œǔ�����v���O�����ɂ���āA�������d�����������B������ϐᓙ�̍ЊQ���ɂ͎����I�ɑ��z���p�l���̃|�W�V������ύX�����邱�ƂŔj�����ɂ���Q��h�����Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���M���g�F���Ɂh�������t�B�����^�V�f�ޓ\��ƍH������x���ő�15���ቺ ���K�X�̕��˗�p�f�ނɊւ��錤�����ʂ���ɃX�s���A�E�g����SPACECOOL�͏Ǝ˂��ꂽ���z���̔M��h���ƂƂ��ɁA���f�ނ�t�^�������̓����̔M�����ė�p���ʂށB �f�ނ̔M�̔��˗��ƕ��˗��͋��ɖ�95���B�ՔM�f�ނ̏ꍇ�͑��z����������ƔM�̓`���Ȃǂœ��������܂邪�ASPACECOOL�͂����h���A�������O�C���ቷ�ɂȂ邱�Ƃ�����B ���؎����ɂ����čH��ւ�SPACECOOL�������ʂ̌��،��ʁA���f�ނ̎{�H�ӏ��Ɣ�{�H�ӏ��œV������̉��x�ɖ�15���̈Ⴂ������ꂽ�Ƃ����B�܂��A���d�ՂɎ{�H�����ꍇ�́A�{�H�O��ŋݔ��̏���d�͂����V���Ŗ�21���A�J�V����ܓV�����܂߂Ă���20���팸�ł���Ɗm�F����SPACECOOL�̕��˗�p�Z�p�́A�ԊO����8�`13��m�̔g����i������u��C�̑��v�j�ŕ��o����B����ȑ��w�\���̃t�B�����ɂ��A���̓����̔M����o�����₷�����Ă���B�t�B�����^��1m2������Ŗ�6000�~�B �o�T�uMonoist�v |
|
|
| �����ŎO�H�d�@�Y�ƃV�X�e���iTMEIC�j���u�d�͒~�d�V�X�e���v�A2025�N�ɂ����؊J�n�� TMEIC�́A�u�d�͒~�d�V�X�e���v�̎��p���Ɍ����A���؎��ƂɎ��g�ށB�d�͒~�d�V�X�e����2025�N������v���W�F�N�g���J�n���A2027�N�ɏ��p����ڎw���B �d�͒~�d�V�X�e���Ƃ́A�ʒu�G�l���M�[�𗘗p�����~�G�l�Z�p�ŁA���C���[�Ɏ��t�����d������[�^�[�Ŋ����グ�邱�ƂŃG�l���M�[��~���A�d�͂ŏd�肪��������ۂɃ��[�^�[�̉G�l���M�[��d�C�ɕϊ����邱�Ƃŕ��d����B���łɗv�f�Z�p�͊m������Ă���A�C�O�ł�MW�N���X�̎��v���W�F�N�g�������o���Ă���B TMEIC�ł́A�R�Ԃ̊R��J�Ȃ�100m���x�̗������m�ۂł���n�`�ɒ~�d�ݔ������݂��A�d������t�������C���[���{�A�݂艺����V�X�e����z�肵�Ă���B�n���p�~�d�r���ƂƂ��Ă̓������������ڎw���ƁA10MW����40MW�K�͂̒~�d�V�X�e�����L�]�ƌ��Ă���B ���Ђł́A���ɓK�����ꏊ�ƃp�[�g�i�[��Ƃ�T���Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Γ]���A�����Ɖƒ���^�G�l���A�c�_�ɒ��� �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���́A������ƁA�ƒ��ΏۂƂ����ȃG�l�E�Γ]������̌�����{�i�I�Ɏn�߂��B ������Ƃ�ƒ�͏ȃG�l�@�ɂ�����̑ΏۊO�ŁA���̕���̎��g�݂�2050�N�J�[�{���j���[�g�����B���̃|�C���g�ƂȂ��Ă���B�G�l���M�[����@���ʂ�����A�G�l���M�[�������Ǝ҂�ʂ�����̗��ʂ���c�_��[�߂�B�u�@��v�Ɓu�����v���ʂł܂������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ȃG�l�ݔ������u�e�Ղł͂Ȃ��v�G�l���i�����A������Ƃ���؎��Ȉӌ��� �S�����H��A����́A�����E���K�͎��Ǝ҂�ΏۂƂ����A�G�l���M�[���i�������o�c�ɗ^����e���ɂ��Ă̒������ʂ����\�����B ���̌��ʁA���v���������Ă��鎖�Ǝ҂�79.4���������B������ƁE���K�͎��Ǝ҂���́A�u���i�]�ł͌��E�v�u�ȃG�l�ݔ��̓����͗e�Ղł͂Ȃ��v�Ȃǂ̐��������ꂽ�B 2022�N2����2023�N�����ɂ����锄��E���v�ɂ��āA�u�G�l���M�[���i�����ɂ��R�X�g�����ǂ̂悤�ɉe�����Ă��邩�v�����Ƃ���A�u����͑������Ă��邪���v���������Ă���v�Ƃ̉�79.4���B�u����͉����������v���������Ă���v��78.5���A�u����Ɨ��v���������Ă���v��94.2���������B����̓R���i�БO�ɖ߂���邪�A�G�l���M�[�R�X�g�㏸�ɂ��A������E�ێ��ł��Ă����v���m�ۂ��ɂ����ɂ��邱�Ƃ����������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2023/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���p�V�t�B�R�E�G�i�W�[�̌n���p�~�d�r�A�G�i���X��������x�� �G�i���X�́A�p�V�t�B�R�E�G�i�W�[���p�C���b�g�Č��Ƃ��Đ��i���鍂���K�͂̒~�d�r�v���W�F�N�g�����ɁA4������n���p�~�d�r����x���T�[�r�X�����Ɣ��\�����B �n���p�~�d�r�́A�d�͌n���ɒ��ڐڑ����A�d�͌n���̈��艻�̂��߂ɉ^�p�����^�~�d�r�B�V��ɍ��E����₷���Đ��\�G�l���M�[�̉ߕs����d�͌n�����ŋz�����ăo�����X�����A�ăG�l��͓d�����Ɠd�͈��苟���𗼗�������C���t���Ƃ��Ċ��҂����B ���ۂ̉^�p�ł́A�e�ʎs�����������s��ɎQ�����Ď��v���Ƃ���ƂƂ��ɁA���d�͎s��ł̉��i���𗘗p��������Ŏ��v��ȂǁA��含���������G�Ȑ��䂪�K�v�ɂȂ�B ����A�p�V�t�B�R�E�G�i�W�[���k�C���ƕ������ɏ��L����n���p�~�d�r��ΏۂɁA�Ǝ��̕��U�^�d������V�X�e���̒A�^�p�Ɩ���s�A�d�͔̔���s�A�^�p�R���T���e�B���O�ȂǁA�n���p�~�d�r�̉^�p���I�ɃT�|�[�g����T�[�r�X�����B�n���p�~�d�r�p�r�ł̒͏��߂ĂƂȂ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���J���X��ɐV����A�����������Ȃ��u�Ђ�Ђ�����v�Ńp�l�����ꂪ�[���� ���K�\�[���[�̓J���X�ɂ���Q�ɔY�܂���Ă����B�܂��t���ɂ���đ��z���p�l�������ꂽ��A�J���X�������킦�Ĕ��ł��āA�p�l����痎�Ƃ��āA�J�o�[�K���X��������Q���r�傾�����B ���ꂽ���z���p�l���̌����ɗv�����p�͑��Q�ی��Řd���Ă�����̂́A���̕ی������̂��N�X�l�オ�肵�Ă���B����܂łɂ����܂��܂ȑ�����݂Ă������A����������ʂ������Ă����B ����̎�@�́A�����̔������g���B���d�f�q���g���A�d�����������ƁA�J���X�ɂƂ��Ă͋����h�������͂ɐ�����B����͐l�Ԃɂ͊������Ȃ����̂̂悤�ŁA�J���X�ɂ͊�������悤�ȋ����C�z��g���̂悤�Ȃ��̂��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����B�J���X�����\�H�ƌQ����Ȃ��ă��K�\�[���[���ӂɏW�܂��Ă��鎞�ɁA���̃V�X�e�����g���B2�`3���Ԏg���Ă���ƁA���̌�A1�`2�J���Ԃ͑��z���p�l���̊�����قڃ[���ɗ}���邱�Ƃ��ł��Ă���Ƃ����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���z���_���`�����f���Ƃ̖����}�A������R���d�r�V�X�e��30�N��6����̔� �z���_�́A2020�N�㔼�ɔR���d�r�iFC�j�V�X�e���̊O�̂��n�߁A���f���Ƃ��g�傷��B �K�p�͈͂��^�A�����łȂ��A�Y�ƕ���ɂ��L����B�܂���2023�N����GM�ƊJ�����Ă��鎟����FC�V�X�e����ʎY����B2020�N�㔼�ɔN2000����x����̔����n�߁A2030�N�ɓ�6����A2030�N��㔼�ɓ����\����̔̔���ڎw���B �̔��̎�ȗ̈�͔R���d�r�ԁiFCV�j�A���p�ԁA��u�d���A���@�B�̎l��z�肷��B����A�R�X�g�̍팸�Ƒϋv���̌����}��BGM�Ƌ����J�������2�����FC�V�X�e���ł́A�z���_��2016�N�ɔ�������FCV�ɓ��ڂ���]���̃V�X�e���ɔ�ׁA�R�X�g��3����1�A�ϋv����2�{�܂ō��߂�B 2030�N���̓�����ڎw����3����ł́A��2����ɔ�ׂăR�X�g���A�ϋv����2�{�܂Ō��コ����B�R�X�g�팸��FC�Ɏg�������G�}�����炷�ƂƂ��ɁAFC�X�^�b�N�̍\�����ȑf�����邱�ƂȂǂŎ�������B���Y�v���Z�X������������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���L���[�s�[�A�u�}���l�[�Y���d�v��CO2�N980t�팸�A2022�N�x���т\ �L���[�s�[�́A�����ߒ��Ŕ�������H�i�c�����o�C�I�K�X���d�Ɋ��p������g�݂ɂ����āA2022�N�x�i2021�N12���`2022�N11���j��5�H�ꍇ�v��CO2�r�o�ʂ��980�g���팸�����Ɣ��\�����B ���ЍH��ł́A���i��̃}���l�[�Y�����钆�ŁA�قȂ鏤�i�̐����ւ̐�ւ����ɔz�ǂ���r�o�����}���l�[�Y���A�o�C�I�K�X���d�Ɋ��p���Ă���B���݃L���[�s�[��5�H��ƃO���[�v��Ђ̃P�C�p�b�N�Ŏ��{���Ă���B���̎��g�݂�5�N�ڂ��}�����B�L���[�s�[�O���[�v�́A�H�i���[�J�[�̐Ӗ��Ƃ��āA�H�i���X�̍팸�E�L�����p�Ɍ����A�H�i�c���팸�A��ؖ����p���̗L�����p�A���i�p���̍팸�ɒ��͂��Ă���B ������H�i���X�̔�����}������w�͂𑱂���ƂƂ��ɁA�����ɂȂ��鎑���̗L�����p��z���l���A���ւ̃}�C�i�X�v�f���v���X�ɕς��Ă����w�͂𑱂��Ă����Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���y���u�X�J�C�g���z�d�r�A�����O�ǂŎ��ANTT�f�[�^�Ɛϐ����w NTT�f�[�^�Ɛϐ����w�́A�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�������O�ǂɐݒu������؎�����4������J�n����Ɣ��\�����B ���؎����ł́A�s���̊��������̊O�ǖʂւ̐ݒu��@��ϊ�������������B�ϐ����w���J�������t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A�Ǝ��́u���~�A�����A�ޗ��A�v���Z�X�Z�p�v�����p���A�ϊ�����15.0���̐����ɐ�������ƂƂ��ɁA���O�ϋv����10�N�������m�F�����B ���i�K�ł́A�O�ǂւ̐ݒu���̉ۑ蒊�o��ڕW�Ƃ��āA�ϐ����w�̌������̊O�ǂɏ��K�͖ʐςŐݒu���A�����͂��܂ލ\�����S�����m�ۂ����ݒu���@���m�F����B�������Ԃ́A4��������2024�N3�����܂ŁB ��2�i�K�ł́ANTT�̃f�[�^���̊O�ǂɐݒu���A�ϊ��������܂߂Ď��p����������B�������Ԃ́A2024�N4��������2029�N3�����܂ōs�BNTT�f�[�^�͏����A�S��16���_�̃f�[�^�Z���^�[����уI�t�B�X�ւƓ����g���ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d�H�ACO2�r�o�[���̃K�X�R�[�W�F�l�J���� ���d�H�̓h�C�c�̃O���t�H�[�X�ƁACO2��r�o���Ȃ��K�X�R�[�W�F�l�̊J����i�߂Ă���B �O���t�H�[�X�͍����g�v���Y�}�d�C�����ŒY�����f�𐅑f�ƌő̒Y�f�ɕ�������Z�p�����B���Y�������f����d�H�̃K�X�^�[�r���ŔR�āE���d���ACO2�r�o�[���Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���B�O���t�H�[�X�̃v���Y�}�d�C�����Z�p��4�L���O�����̃��^������1�L���O�����̐��f��3�L���O�����̌ő̒Y�f�Y�ł��A���̍ۂ̏���d�͗ʂ�10kWh�Ƃ����B �ő̒Y�f�͎������i��d�r�ޗ��A�H�ՍނȂǂƂ��Ĉ���I�ɗ��p���邱�Ƃ��ł��A��C�ɂ͕��o����Ȃ��B�����J�����̃K�X�R�[�W�F�l�́A���f��R�₵�Ĕ��d���邽�߁ACO2��r�o���Ȃ��B�d�͂̈ꕔ�̓v���Y�}�d�C���u�ł̐��f�����ɍė��p�����BCO2���܂܂Ȃ������̔r�K�X�͍H�ƃv���Z�X�ɗp���邱�Ƃ�z�肷��B���ɁA�����M�Ƒ�ʂ̌ő̒Y�f��K�v�Ƃ��鉻�w�Y�ƌ����ɓ�������Ό��ʂ��傫���Ƃ݂���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Ē�����ЁA�E�Y�f�V��100�Ђ�I�o�^���f�A�G�l��������ɋr��
�N���[���e�b�N�̐�咲����Ђł���ăN���[���e�b�N�O���[�v�́A�L�]�ȃN���[���e�b�N100�Ђ��܂Ƃ߂��u�O���[�o���N���[���e�b�N100�iGCT100�j�v��2023�N�ł\�����B ���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����A���f��G�l���M�[�����Ɋ֘A�����Z�p������Ƃ𐔑����I�o�BCCUS�i��_���Y�f����E���p�E�����j��Y�f��v�̊�Ƃ����X�g���肵���B �N���[���e�b�N�O���[�v��2009�N����GCT100�����\���Ă���B�I��҂̓N���[���e�b�N�O���[�v�̃A�i���X�g��x���`���[�L���s�^���iVC�j�Ȃǂō\�������B�����93�J���̃N���[���e�b�N�v1��5752�Ђ̒�����A5�`10�N��Ɏs��֏d�v�ȉe����^����Ɨ\�z�����100�Ђ�I�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���_�C�L���u���C��p�G�A�R���v���p���ց^��փt�����g�킸����d��2���� �_�C�L���H�Ƃ́A�Y�����Ƌ����ŁA2030�N���߂ǂɁA���̗͂ʼn��x��ω�������u���C��p���ʁv�����p����������G�A�R���̎��p����ڎw�����j�𖾂炩�ɂ����B ��_���Y�f�iCO2�j�����鉷�����ʂ������}��K�v�Ƃ����A����d�͂�2�����x���点��Ƃ����B�n�����g�������E�I�ȉۑ�ƂȂ钆�A�����ׂ̒Ⴂ�V�Z�p�̊J�����}���B ���C��p�͎��C��������ƔM�������A��菜���Ɨ₦��������������f�ށu�����́v��p����Z�p���B�����߂Â����藣�����肵�ĉ��x��ω������A���ɓ`���ė�g�[�Ɏg���B���s�����͗�}�̈��k�E�c���ɔ������x�ω��𗘗p���Ă���B�V�Z�p�͗�}���s�v�ƂȂ邱�Ƃ���A��}�̎嗬�ƂȂ��Ă���u��փt�����v���g�킸�ɍςށB����Ɉ��k�@���K�v�Ȃ����߁A����d�͂����Ȃ��A�U��������}������Ƃ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����l�s53�Z��PPA�ő��z�������x�݂̓��ɂ͏��Ǝ{�݂� ���}�s���Y�́A���l�s���̏����w�Z�E�����w�Z�E���ʎx���w�Z53�Z�ɁAPPA�����p�������z�����d�ݔ�������Ɣ��\�����B ���̎��g�݂ɂ��A��26���i�ΏۍZ���v�Ŗ�1,780�g��-CO2�^�N�j��CO2���팸�ł��錩���݂��B���l�s�͌��݁A2050�N�܂ł̒E�Y�f����ڎw���A�ȃG�l�{��E�ăG�l�g��{���i�߂Ă���B���Ђ͍���A���s�ɂ�����u�s�s�^�n�Y�n�����f���v�̃��f���P�[�X��ڎw���A�ΏۍZ�̉��㕔�������p�����ăG�l�ݔ��̓�������эăG�l�d�͂̊��p���Ă����B ���Ђ����z�����d�ݔ��ƒ~�d�r������B���d�����d�͂��A���Ԃ͊w�Z�Ŏg�p����ق��A�]�蕪�͒~�d�r�ɏ[�d���A��Ԃ�J�V���A��펞�Ȃǂɓd�͂��g�p�ł���悤�ɂ���B�w�Z���x�݂̓��ɂ́A�s���̏��Ǝ{�݂�z�e���֔��d�����d�͂��������邱�ƂŁA�ăG�l�d�͂��ő���n����Ŋ��p���A�s���̍ăG�l�d�C�䗦����ɍv�����Ă����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���ȃG�l�@�̏ڍאv�������A�S���{�s�֖ڕW�l�ݒ�^�����G�l�� ���������G�l���M�[������i�o�ώY�Ƒ��̎���@�ցj�ȃG�l���M�[���ψ����15���A�����ȃG�l�@�{�s�Ɍ������ڍאv���܂Ƃ߂��B �����Ԑ����Ƃ�d�F���[�J�[�́A2030�N�x�̎g�p�d�C�S�̂ɐ�߂�Ί����̖ڈ���59���ɐݒ肳�ꂽ�B�f�}���h���X�|���X�iDR�j�𑣐i���邽�߁A����Ɏ��{����{�ʂ��L��������d�g�݂��݂���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����E���̑��z���~�M�V�X�e���{�݉��|���R���[���A�b�n�Q�r�o�[�����\�� ���s�ŁA�����p�̔_�ƃn�E�X�����݂���A���k�ŃC�`�S���͔|����Ă���B���z���ŔM������邱�̃n�E�X�ł́A�R�����܂������g���Ă��Ȃ��B ���k��Ȃǂ̌����O���[�v���J���������E���́u�͔|�p���R�G�l���M�[���p�M���V�X�e���v�Ŏ��������߂��Ă���B���z�M�W�M�p�l���ŏW�߂��M��~�M���ɂ��߁A��Ԃł����̔M�𗘗p���Ď�����g�߂�d�g�݂��B �C�`�S�͔̍|�͒��Ԃ�25���ȉ��A��Ԃ�8���x�ȏ�̋C�����K�v�Ƃ����B���z���o�Ă��钋�Ԃ͂قƂ�ǖ��Ȃ����A��Ԃ̔M�̊m�ۂ���������B���ǁA�R�����g�킴������Ȃ��������Ă����B ����܂ŔM�����߂���M�~�M�ށi�|�_�i�g���E���E�O�����j�́A�M�̎�荞�݂�1���قǂ����ł��Ȃ������B���k��́A�M�����@����]�����邱�Ƃʼn��P�ł��A��]�����邱�ƂŁA�ȑO��80�`100�{�̔M�ʂ���荞�߂�悤�ɂȂ����Ƃ����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���ϐ�Ŕj���̑��z���p�l����4�N�Ԃ�7.5�����ѕ��ANITE�����͌��ʂ����\ ���i�]���Z�p��Ջ@�\�iNITE�j�́A2018�N�x����2021�N�x�܂ł̎��̕��͂��s�����B�X��ɂ��j�����̂�4�N�Ԃ�43������Ă���Ƃ����B ���k�n����k�C���𒆐S��12������4���̊Ԃɔ������Ă���A2�����ł������Ȃ��Ă���B���ɑS���ŋL�^�I�ȑ�Ⴊ�m�F���ꂽ2020�N�x�A2021�N�x�͑������Ă���A2018�N�x��1���A2019�N�x��0���������̂ɑ��A2020�N�x��28���i���R�ЊQ�ɌW��N�Ԕj�����̖̂�45���j�A2021�N�x��14���i����26���j�������Ă����B2018�N�x����2021�N�x�̊Ԃɔ�������43���̔j�����̂ɂ����鑾�z�����d�ݔ��̔�Q��30MW���A����͏Z��p�\�[���[�p�l���̖�7.5�����ѕ��̔��d�o�͂ɑ����B �܂��A�X��ɂ�鎖�̂ɂ����Ă̓\�[���[�p�l�����x����ˑ�̑��������Ƃ������A�X��ɂ��j�����̖̂�8�����߂Ă���Ƃ����B �o�T�uIT���f�B�A�v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA�����n�M�V�X�e���Ɋւ���v���W�F�N�g�Ɏ����� �A�����J�G�l���M�[�Ȃ́A�����n�M�V�X�e���iEGS�FEnhancedGeothermal Systems�j�̗L�����Ɗg������������7���̃p�C���b�g�v���W�F�N�g�ɑ��A�ő�7,400���h���̎������s�����Ƃ\�����B �n�M�G�l���M�[�͌��݁A�����Ŗ�3.7�M�K���b�g�̓d�͂d���Ă��邪�A2050�N�܂ł�90�M�K���b�g�̈��肵���d�͂����̓d�͖Ԃɋ����ł���悤�ɂȂ�Ɛ����ł���B�������A���������傫�Ȓn�M�G�l���M�[�̐��ݔ\�͂́A�]���̒n�M�Z�p�ł͂قƂ�Ǘ��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�n�M��d�C�Ƃ��ė��p����ɂ́u�M�v�A�u���́v�A�u�n�k�̓������v��3�v�f���K�v�ŁA�M�͒n���ɂ��邪�A�����̏ꏊ�͐��ⓧ�������\���ł͂Ȃ��B EGS�́A�n�M�����o�����߂ɕK�v�ȗ��̂�l�H�̒n�������w�ō��o���A�����Œn�M��������Ĕ��d����BEGS�̐i���ɂ��A�ŋ߂܂ōĐ��\�ȓd���̗��p���s�\�ƍl�����Ă����n��ł��A�n�M�G�l���M�[�����������悤�ɂȂ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2023/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���}���V�����Ɉꊇ��d�E�~�d�r�AEV�[�d�V�X�e����������؊J�n �����d�͂́A�������s�ɂ�����В��ݏZ��ɒ~�d�r��ݒu���A���U�^�G�l���M�[���\�[�X�̊��p�Ɍ��������؎������J�n����Ɣ��\�����B �����؎����͌o�ώY�Əȁu���U�^�G�l���M�[���\�[�X�̍X�Ȃ銈�p�Ɍ��������؎��Ɓv�̈�Ƃ��Ď��{�����B�~�d�r�Ɠ����ɑ��z�����d�V�X�e����ݒu���A��Ԃ����z���R���̍ăG�l���g�p�ł���悤�ɂ���B�܂�EV�[�d���ݒu���邱�ƂŁA�I��EV�EPHEV�̏[�d���\�ɂ���B ���ł́A��ʌ����̕ʂ̃}���V�����i2�����j�ɂ��~�d�r��ݒu���������s���B�܂�EV�[�d�T�|�[�g�V�X�e���������ɓ������A�E�Y�f��}��B ����Ɂu�}���V�����ꊇ��d�T�[�r�X�v�����ăG�l�̑n�o��}��ƂƂ��ɁA�Ǝ��ɑ��z�����d�݂̂ł͘d������Ȃ���L���̓d�͂��S�ʍăG�l�ɂ���B�ЊQ���ɂ͋��Z�҂ɑ��A�~�d�r���J������\�肾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���s�[�N���ɋ���A�d�u�����p�^�ȃG�l�ŗ����ጸ�ցu�k��B���ߓd�v �k��B�s�̓_�C�L���ȂǂƘA�g���A�d�C�g�p�ʂ������鎞�ԑтɁA�s�̌����{�݂▯�Ԋ�Ƃ̋@��̏o�͂�}���ēd�C�̏�������炷���EV�ɂ��܂����d�C�����p����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���̍\�z�ɏ��o���B�ȃG�l�𗿋��ጸ�ɂȂ���̂��_�����B2023�N�x�Ɏ��؎��ƁA2024�N�x�̎��Ɖ���ڎw���B ���؎��Ƃ́A�s���̌����{�ݖ�10�����▯�Ԑ��ЂŎ��{����B�����{�݂ł͒��[�ȂǓd�͎��v�̑������\������鎞�ԑтɁA�G�A�R�������u���삵�A�o�͂�}����B �̊����x�ɉe�����Ȃ��͈͂Ŏ��x�Ȃǂ��R���g���[�����A�g�p�d�͂����炷�B�Q�������Ƃ̃G�A�R���ɂ̓_�C�L��������@���������B�܂��A�s��EV����ƌ����{�݂��Ȃ��A�G�A�R���̏o�͗}���Ɠ������ԑтɁA���z�����d�ŏ[�d�����d�C����d���Ďg���B���唭�̐V����ƁuYanekara�v���Q�悵�A���̎d�g�݂�S������B�S�̂�5���O��̗����ጸ���ڕW�B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����}���݁A������Ƀo�[�`����PPA�ōăG�l����45�J���ɒሳ���z�� ���}���݂́A�N���[���G�i�W�[�R�l�N�g�ƁA�������ΏۂƂ����o�[�`����PPA�T�[�r�X�_�����������Ɣ��\�����B ���}���݂̌�����ɂ�����g�p�d�͂ɑ��āA�lj����̂���ăG�l�̊����l���N���[���G�i�W�[�R�l�N�g���璷���Œ���B2023�N3���܂łɍ���45�J���ɁA���z�����d�p�l���e�ʁi�v4MW-DC�j�̓��}���ݐ�p�̔�FIT�ሳ���z�����d�����J������B�N���[���G�i�W�[�R�l�N�g�́A�o�[�`����PPA�T�[�r�X�̃X�L�[�������p���A���d�����d�͉͂��d�͎���s��֔��p�A���}���݂ɑ��d�͂̊����l��20�N�Ԃɂ킽���Ē���B ���̌v�悪��������A�lj����̂���ăG�l�ɂ���āA�N�Ԗ�440��kWh���̓d�͂̊����l�ݏo���A��1,900t-CO2��CO2�팸�ɍv���ł���Ƃ����B����͓��}���݂̌�����ɂ�����d�͎g�p�ɔ����N��CO2�r�o�ʂ̖�20���ɑ�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����˔M��80���ȏ�}���\�ȁu����ːܔ�(�����ς�)�����v��{�i�^�p�J�n ��a�n�E�X�́A�����̏����̌����ƂȂ鉮���̕��˔M����ʓI�Ȑܔ����Ɣ�r����80���ȏ�}������u����ːܔ����v���J�����A2023�N1������{�i�^�p���J�n�����B �H���q�ɂȂǂō�Ƃ��鐻���Ƃł́A�M���ǂ̖���46����������Ǝ��ɔ��ǂ��Ă���B���̈�����A��������̋������˔M���B �u����ːܔ����v�́A�ܔ����̉��ʂɒ���˗��\�ނ�ڒ����邱�Ƃŕ��˔M��}���邱�Ƃ��ł��鉮���ށB�A���~�n�ՔM�V�[�g�ƃK���X�@�یn�f�M�ނ�g�ݍ��킹���Ǝ��̒���˗��\�ނ��A���˂ō����ɂȂ��������̕��˔M��}����B ���؎����ł́A�u����ːܔ����v���̗p���������̑̊����x�́A��ʓI�Ȑܔ����̎����Ɣ�r����3���ጸ�ł��邱�Ƃ��m�F�����B��d�f�M�ܔ����i�ܔ������㉺��d�Ɏ{�H���A�㉺�ܔ̊Ԃɒf�M�ނ��������j�Ɣ�r����ƁA�����̌y�����ʂ͓����ł���Ȃ���A������p��7�����x�ɗ}���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u��a�n�E�X�v |
|
|
| ���ɓ����A�ƒ�p�~�d�r��1.7�����DR���؍��~�̎����Ђ���������� �ɓ����́A�ƒ�p�~�d�r�����u�Ő��䂵�ēd�͂̎����o�����X������f�}���h���X�|���X�iDR�j�̎����J�n����B���~�ɗ\�z�����d�͎����Ђ����̉���ƁA�ăG�l��ʓ�������ɂ�����d�͎����̍œK����ڎw���B ���̎��́A���Ђ̎q��ЂŒ~�d�V�X�e���ƘA�g����AI�����O���b�h�V�F�A�W���p����ʂ��čs���BNF�u���b�T���e�N�m���W�[�Y�������̔�����ƒ�p�~�d�r�����u�Ő��䂷��B ��̓I�ɂ́A�����̓d�͎��v�E������\�����A�d�͋������s������Ɨ\������A�s�ꉿ�i�������Ȃ鎞�ԑтɁA��g���鏬���d�C���Ǝ҂̗v���ɉ����āA���u�Œ~�d�r���[���d���邱�ƂŁA���Ǝ҂̓d�͂̎g�p��}�����A�d�͂̎����o�����X����������B�����̎Q���҂ɂ͂��̑Ή����x������B��51MW�^167MWh�K�͂̓d�͂��R���g���[������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���֓d�A�S���ɉ��z���d���̐V��В~�d�r��ăG�l�̎���œK�� ���d�͂́A��Ƃ̎��Ɣ��d�ݔ��Ȃǂ̕��U�����d�������u�Ő��䂵�A��̔��d���̂悤�ɋ@�\�����鉼�z���d���iVPP�j��S���Ŏ�|����V��ЁuE-Flow�i�C�[�t���[�j�v���A4����{�ɐݗ�����Ɣ��\�����B �~�d�r��A���z�����d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�̍œK�Ȏs�����̑�s���s���B�ߘa12�N�x�܂łɉΗ͔��d�ݔ��T��ɑ�������s������250���L�����b�g�A���㍂300���~��ڎw���B �֓d�͂���܂ł�VPP���Ƃ�W�J���Ă������A�V��Ђł͓d���̉ғ���d�͂̎����\���A�s�����Ȃǂ̒~�σf�[�^����ɁAAI��g�ݓ��ꂽ�Ǝ��V�X�e���u���U�^�T�[�r�X�v���b�g�t�H�[���v���\�z����B ��ʂ̑��d�Ԃɐڑ����Ă���u�n���p�~�d�r�v�ƁA���z���╗�͂Ȃǂ̍ăG�l�̎s����D�Ȃǂ��s����B�~�d�r�ɑ��ẮA�s��̒l�����ɉ����ė]��d�͂̏[�d�A�d�͕s�����̕��d�𑣂��A���ʓI�Ȏs�����ɂȂ���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���u500���ԌJ��Ԃ��g����I�d�r�s�v�̘R���Z���T�[ �~�l�x�A�~�c�~�O���[�v�̃G�C�u���b�N�́A�J�R���R�������m���Ė����Œm�点�鎩�Ɣ��d���̘R���Z���T�[�̐V���i�������B �o�b�e���[���X�R���Z���T�[�́A�R�������m����Z���T�[���{���ƁA�d�g�M���閳���^�O�ō\���B2��ނ̋�����g�ݍ��Z���T�[���{���ɐ��H���G���Ɛ��������ȓd�͂�~�d�E�������A�����^�O����d�g�M�B �R���̔������Ԃ�ʒu��m�点��B�]���i�̓��{�������Ɏ���ɂ����Q��ނ̋�����g�ݍ���ł��邪�A�V���i�͂��̂���1��ނ��ɕύX�B�����̑̐ς𑝂₵�A���{�������ɂʂ�Ă���500���ԌJ��Ԃ��g�p�ł���悤�ɂ����B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���m���[���h�G�i�W�[�n���f�����p�̍ăG�l�A2027�N�܂łɖ�T�疜�L�����b�g ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A��N12���Ɍ��\�������ŁA���f�����p�̍Đ��\�G�l���M�[��2027�N�܂łɖ�5�疜�L�����b�g�����������Ƃ̌��ʂ����������B ���ʂł͒������ł�������1800���L�����b�g�������������B�������S��������ȂǑ�K�͑��z�����d�ݔ��̐��������҂����G���A�ŁA���d�u�̐ݒu����������ƌ����ށB�����̋K�͈͂��|�I�ŁA�Q�ʈȉ��̓I�[�X�g�����A��`���A�č��Ƒ������A������������̔����ȉ��̐ݒu�ʂƂȂ��Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����l�s�������E�Y�f�v��������2030�N�uGHG�����v�f���� ���l�s�����͎s��̉������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʂ̖�5�����߂�s���ő勉�̔r�o���Ǝ҂ł��邱�Ƃ���A�r�o�팸���ۑ�Ƒ����Ă���B���������Ƃ́A��ʔp�����������ƂɎ�����2�Ԗڂɑ����A�s�������Ƃ̖�2�����߂Ă���B ����́u�v�����v�ł́A2030�N�x��GHG50%�팸�A2050�N�x�ɔr�o�ʎ����[���i�J�[�{���j���[�g�����j���f����B���̍팸�ڕW�B���̂��߁A��g���u4�̎��_�v�ɑ̌n�������B2030�N�܂ŁuGHG���o���Ȃ��v�u���ɗD�����d�C�̗��p�v�ɒ��́A����ȍ~�uGHG�����p�v�u�r�o�ʂ̖��ߍ��킹�v�����{����B��̓I�ɂ́ACO2�̖�300�{�̉������ʂ������_���f�iN2O�j�r�o��ጸ�ł��鉘�D�ċp�F�ւ̍X�V��A���z�����d�ݔ��̓����g�傷��B�܂��A�����^���N�Ŕ������̊����ɕK�v�Ȏ_�f����������U�C���u���A�������ȁu�ሳ���^�����u�����p�l�����v�ɍX�V����ȂǁA���ɔz�������ȃG�l�@�������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��ANA��JAL�A�č��x���`���[��SAF���ɓ������璲�B10�N�ڂ�20��t ���Ђ͍���10�N�ԁA�č��̃x���`���[���Raven��SAF�̋�������B���N�x�ɂ�����2025�N�̋����ʂ�5���g���ŁA���̌�͒i�K�I�ɑ��₵�A10�N�ڂ͔N��20���g���B����\�肾�B SAF�𒇉��ɓ��������́A���E�ɕ��L���A�q�l�b�g���[�N�������Ђɋ������邱�ƂŁA2030�N�q��R���S�̂�10����SAF�ɒu��������Ƃ������{�ڕW�̎����ɑ傫����^�ł���ƍl���Ă���BANA�́A�t�B�������h�̊��Neste��ʂ���SAF�̒��B���J�n���A���{���̍��ې�����ւŏ��߂ē��R�����g�p�����B�܂�Neste����̒��B�ɐ旧���ASAF�̗A���E�i���Ǘ��E��`�ւ̔����Ɏ���܂ł̃T�v���C�`�F�[�����ɓ��������Ƌ����Ő��i���Ă���BJAL�́ANeste�A�ɓ��������Ƌ��Ƃ��J�n�B�b���������Ƃ���SAF���H�p�g�E�����R�V�������Ƃ���SAF�̋������B��\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z����2024�N�x�E���B���i�����ݒu��12�~�A�n��ݒu��9.2�~ �o�ώY�ƏȂ́A2024�N�x��FIT�̒��B���i�AFIP�̊���i�Ă����\�����B 2023�N�x�ɂ����鑾�z���̒��B���i�E����i�́A�A�n�o��50kW�ȏ���D�Ώۖ�����9.5�~/kWh�A�ሳ���Ɨp�i10kW�ȏ�50kW�����j�Œn�抈�p�v���i���Ə���c�_�^�j��������Č���10�~/kWh�B 2024�N�ɂ��ẮA10kW�����̏Z��z���ɂ��ẮA2024�N�x�E16�~/kWh�Ƃ���2023�N�x�Ɠ����i�Ƃ����B 10kW�ȏ�̎��Ɨp���z���ɂ��ẮA2024�N�x����V���Ɂu�����ݒu�v�敪��n�݂��A�ሳ���Ɨp�i10kW�ȏ�50kW�����j���܂߂Ē��B���i��12�~/kWh�Ƃ����B���Ɨp���z���̒n��ݒu�ɂ��ẮA�ሳ���Ɨp�i10kW�ȏ�50kW�����j�͒n�抈�p�^���v����10�~/kWh�Ƃ�2023�N�x�Ɠ����i�B50kW�ȏ�ɂ��Ă�9.2�~/kWh�Ƃ��A2023�N�x��9.5�~/kWh����0.3�~�����������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���J�[�{���j���[�g�����\����229�����̂�2030�N�팸�ڕW�ݒ��55�� ���o�ς́A�J�[�{���j���[�g�����Ɍ������{��̓����Ɋւ��鎩���̃A���P�[�g���ʂ\�����B�n��̍Đ��G�l�d�͂̓����ɂ��ẮA71.6���̎����̂��u�����u�����z���v���ς݁A21.4���������������ƉB 2050�N�J�[�{���j���[�g������\�����Ă���229�����́i19�s���{���A210�s�撬���j�ւ̃A���P�[�g�����ł́A2030�N�x�̍팸�ڕW�̐ݒu�ɂ��ẮA55.0�����u���łɖڕW������v�Ɖ����B2050�N�J�[�{���j���[�g�����Ƃ��������ڕW�ɑ��āA2030�N�x�̍팸�ڕW��ݒ肷�铮�����L�����Ă��邱�Ƃ��f����B 210�s�撬���ɍăG�l���i���̐ݒ�ɂ��ẮA40.6�����u�ݒ肷�邩�ǂ����������v�A52.2�����u���̂Ƃ���ݒ肷��\��͖����v�Ɖ����B���i�K�ł͑��i���̐ݒ�ɐT�d�Ȏ����̂����������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���b�n�Q���C�O�Œ����ցA���{���S�ƎO�H�������ăG�N�\���Ɗo�� ���{���S�A�O�H�����A�ĐΖ����W���[�̃G�N�\�����[�r����26���ACCS��o�����[�`�F�[���i���l�A���j�̍\�z�Ɍ������o������������Ɣ��\�����B�������F�̐��S�Ŕ�������CO2���C�O�Œ������邽�߂̃v���W�F�N�g�̌����ɓ���B ���v���W�F�N�g�ł́A���S�̍������S������r�o�����CO2���E������A�G�N�\�����Q�悷�鍋�B��}���[�V�A�Ȃǂ�CCS�{�݂Œ�������B�O�H�����́A�t������CO2���^������Ȃǂ̃T�v���C�`�F�[���̍\�z��S���B���S�͍����Ŕr�o���ꂽCO2��������C�O�Œ������邽�߂̃o�����[�`�F�[���\�z�̌������s���B����A��_���Y�f�̍��ۊԗA�o���ɂ��Ă����c������������Ƃ����B �ɓ���������O�H�d�H�ƂȂǂS�Ђ̊�ƘA���������A�D���A����p����CCS�o�����[�`�F�[���̎��{�\�����������邽�߁A�����X�^�f�B�̎��{�Ɋւ���o������������ƌ��\�����B�S�|�Ƃ�CO2�r�o�ʂō����Y�Ƃ̖�4���A�S�̂�14�����߂�B �o�T�u���C�^�[�v |
|
|
| ���@�@[�@2023/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�}�e�ƃG���r�v���A���`�E���C�I���d�r���烌�A���^������@�����J���J�n �O�H�}�e���A���ƃG���r�v���E�z�[���f�B���O�X�́A���`�E���C�I���d�r�iLIB�j����̃��A���^������E�����̎��Ɖ��Ɍ����āA���T�C�N���Z�p�̋����J�����J�n�����B ���Ђ́A�G���r�v��HD�̎q��ЂŁA�[�d���d�r�̃��T�C�N�����Ƃ��s��VOLTA�Ƌ����ŁALIB�̃��T�C�N���H���Ő��������u���b�N�}�X�Ɋ܂܂�郊�`�E���A�R�o���g�A�j�b�P��������E�������鎼�����B�Z�p�̊J���ɒ��肵���B�u���b�N�}�X�́ALIB����d�E�����E�j�ӁE�I�ʂ��邱�ƂŐ�������郊�`�E���A�R�o���g�A�j�b�P���̔Z�k��������B 3�Ђ́A���݂ɔ|���Ă����m�E�n�E�ƁA�������B�Z�p��Z�����邱�ƂŊJ�����������A�u���b�N�}�X�������Ƃ������A���^���̉���E�����̎��Ɖ��Ɍ������Z�p�J���Ɏ��g�ށB����烌�A���^�����������ʼn�����郊�T�C�N���Z�p�̊m���ɂ��ALIB�̏������烊�`�E���C�I���d�r�ޗ��̈��苟���܂ň�т������T�C�N���V�X�e���̍\�z�ɍv�����Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����d�A���f���Ƃ̔��㍂������C��2030�N�x��4000���~ ���d�H�Ƃ́A������G�l���M�[�Ƃ��ĊJ����i�߂鐅�f���ƂɊւ��A2030�N�x�̔��㍂��4000���~�Ƃ̌��ʂ��\�����B �]����3000���~�Ƃ��Ă����ڕW������C�������B�O�N�̔��\���_�������f�֘A���Ƃ��[�����A�u���N��萸�k�Ȍv��ɂȂ��Ă����v���Ƃ��w�i�ɂ���B ���d�H�͐��f�Y�E�^���E�����p����Z�p��g�g�݂Â���Ŏ��Ɖ���ڎw���Ă���B�r�o����CO2���o���Ȃ��O���[���G�l���M�[�⊌�Y���琅�f�Y���鎖�Ƃ��I�[�X�g�����A�Ō��ؒ����B�t�����f���^�ԑD�������A����ɑ�^�������D�̊J�����i�߂Ă���B���d�͂Ƒg�݁A���Ɍ��Ő��f�̗A���◘�p��ڎw���Ȃǂ̎��Ƃ������オ���Ă���B ��C������CO2���������Z�p�ł�2030�N�܂łɊC�O�����̎��Ɖ���ڎw���B�������CO2��n���������鍑���ł̎��؎�����24�N�Ɏn�߂邱�Ƃ�ڎw���AINPEX�Ǝ����\�������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�[�A�g�p�ς�EV�d�r�{���ݑ��z���Ŏ��؎���EV�EHEV�d�r��g���� ���R�[�́A�G�b�W�f�[�^�[�Z���^�[�i���^�f�[�^�[�Z���T�[�j�̒E�Y�f���Ɍ����āA�g�p�ςݎԍړd�r���ė��p�����T�[�L�����[�^�̒~�d�V�X�e�����\�z���A���݂̑��z�����d�iPV�j�ݔ��Ɛڑ����������J�n����Ɣ��\�����B ���̎��Ƃ́A�d�C�����ԁiEV�j�ƃn�C�u���b�h�ԁiHEV�j��2��ނ̓d�r��g�ݍ��킹�A�ăG�l���p�ɂ�����ۑ�ł���o�͂̋}�ςɑΉ��ł�������ȑg�d�r�Z�p���J�����邱�ƂŁA�ăG�l���p�𑣐i���ACO2�r�o�ʍ팸�ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B ���̎��ł́A�A���V�X�e�����ɓ��ꂵ�AHEV�d�r�̍��o�͓�����EV�d�r�̑�e�ʓ����������d�͕ϊ������̌���������B�܂������[�X�ɂ���R�X�g�����A�ăG�l���p�ɒ~�d�r�������ɓ����ł���悤�ɂ����B�d�������i�ގԗ��̎g�p�ς݃��`�E���C�I���d�r�iLIB�j�������[�X���A�Ԏ킲�ƂɈقȂ�d�l������iHEV�F���o�́AEV�F��e�ʁj�����d�r�����݂��Ē~�d�V�X�e�����J�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����J�Y�Ƃ�A���f���ăo�[�i���@0�`100���܂Ő�ւ� ��J�Y�ƂƏZ�F�d�C�H�ƃO���[�v�̃T�����[��M�́A���f�Ɠs�s�K�X�^LP�K�X�̍��Ĕ䗦��0�`100���͈̔͂Œi�K�I�ɐ�ւ�����u���f���ăo�[�i�[�v�������J�������Ɣ��\�����B �p�r�͍H�ƘF�i�����F�A���M�F�A�E�L�F�A�Č��F�Ȃǁj��z�肵�Ă���A�o�[�i�[�̃T�C�Y�͏��^���璆�^�i349�`2907kW�j�����C���i�b�v�����B���f�̎��u�R�đ��x�������v�u�Ή����x�������v�Ƃ����R�ē����ɑΉ������\���Ƃ��āA�������S�������������Ƃ��Ă���B ��J�Y�Ƃ�1941�N���琅�f�̎戵�����J�n�A���f�̐����E�A���E�����E�����ȂǃT�v���C�`�F�[�����\�z�B���݁A���f�G�l���M�[�̗��p�g��Ɍ����āA���f�̃A�v���P�[�V�����J����i�߂Ă���A����̋����J���͂��̈�Ƃ��Ď��{�����B�T�����[��M�͑n�ƈȗ��A�o�[�i�[�̔R�ċZ�p����ɓw�߂Ă����B����̋����J���ł́A��NOx�A�ȃG�l���M�[�A�N���[���R�ăV�X�e���Ɋւ���Z�p�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������ESS�A��ɒ~�M�E���d�Ɋ��p�������E��500kWh�̎����ݔ����p ���ŃG�l���M�[�V�X�e���Y�i����ESS�j�́A��Β~�M�Z�p��p�����~�G�l���M�[�Z�p�̊J���ɂ����āA�������ƂȂ�M�e�ʖ�500kWh�̎����ݔ��𓌎ʼn��l���Ə����ɐݒu���A�{�i�I�ȋZ�p�J���E�����J�n�����Ɣ��\�����B ����ESS�́A�����d�́A�ۍg�ƂƂ��ɁA���Ȃ̈ϑ��Ɩ��ɂ����āA��Β~�M�Z�p��p�����~�G�l���M�[�T�[�r�X���Ƃ̋Z�p�J���Ɏ��g��ł���B����܂ŁA���`�E���C�I���d�r�A���f�ɔ�ׁA�����A�o�ϐ��A�ݔ��M�����ɂ����ėD�ʐ��������܂���Β~�M�Z�p�ɒ��ڂ��A��b������i�߂Ă����B���̌������ʂ���A��Β~�M�Z�p��p�������d�V�X�e���́A���������ɂ����Ď����\�������邱�Ƃ��o�ϓI�Ɍ��o�����Ƃ��ł����Ƃ����B700���ȏ�̍����~�M�\�Ȏ����ݔ��Ƃ��邱�ƂŁA���M�~�M�ށi�ӐA�����A�n�Z���A�R���N���[�g�A�Z���~�b�N�X���j�Ƃ��Ĕ�r�I�����~�M���x��B�����A�~�M���̏��^�����\�Ƃ����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�d�r�p�l����ʔp������ɋ��������A���T�C�N������������V�Z�p�̒��g�^�V�Ջ��Y���J�� �V�Ջ��Y�́A���z�d�r�̃Z���ƃJ�o�[�K���X���A�������Ő��˂���E�I�[�^�[�W�F�b�g�ŕ�������Z�p���J�������B �J�o�[�K���X�����`�T�C�Y�̂܂ܔ����ł��A�������I�ȑ��z�d�r���T�C�N���ɂȂ���B���Ђ͑��z�d�r�p�l���̑�ʔp�����\�z�����5�N�ゲ��̎��Ɖ���ڎw���A�E�I�[�^�[�W�F�b�g���u���[�J�[�̃X�M�m�}�V���Ƌ����Ŏ��������u���J������B �V�Z�p�ł́A���z�d�r�p�l���̗��ʂ��獂�����˂��ēd�r�Z�������ӂ��A�d�x�̍����J�o�[�K���X�͔j�ӂ����c���B�Z���Ɋ܂܂�鉔��Z�����A�J�h�~�E���Ȃǂ̗L�Q�����������ł��A�K���X�����T�C�N�����p���₷���Ȃ�B����A�����鑾�z�d�r���[�J�[�̃p�l���ɑΉ��ł���悤�Ɏ����𑱂��Ȃ���A���������u�̊J����i�߂�B���z�d�r�̎�����20�`30�N�B�����ł�2036�N��17���`28���g�����p�������Ɨ\�z����Ă���A���T�C�N�����Ƃւ̎Q����_���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���Ɠx�����ƁA���{�b�g����s�^��d�H�A��B��Ƌ����J�� ��d�H�͋�B��w�Ƃ̋��������ɂ��A�v�H�O�̌�����Ől���s���Ɠx��������{�b�g�ő�s����Z�p���J�������B �����̃��{�b�g�������������u�X���[�����{�e�B�N�X�v�Z�p�����p���A�L�͈͂̑���������I�ɐi�߂���B�Ɠx����͖�ԂɎ��{����Ⴊ�����A��������ƂƂȂ邽�߁A���{�b�g�ɂ�鎩��������������Ό���̕��S�y���ɂȂ���Ɗ��҂���Ă���B �Ɠx����́A���z���̏Ɩ��ݔ������{�Y�ƋK�i����ѐv�҂����߂�Ɠx�����Ă��邩���m�F���邽�߂ɍs���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���p���[�G�b�N�X�̋}��EV�[�d��A���s�s�̎��؎��Ƃɍ̗p �p���[�G�b�N�X�́A���s�s�̌����A�g�E�ۑ�������i���ƁuKYOTOCITYOPENLABO�v�ɂ����āA���Ђ�EV�[�d��uHypercharger�v���̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���Ђ�EV�[�d��́A�[�d�ő�o��240kW�A�t���[�d�܂ł̎��Ԃ�啝�ɒZ�k����B320kWh�̑�^�~�d�r�𓋍ڂ��Ă���A������d�ݔ���K�v�Ƃ��Ȃ��ሳ�ł̐ڑ����ȒP�ɂł���B ���Ђ͋��s�s�ƘA�g���A���݉ғ����̌����pEV�[�d�ݔ���EV���[�U�[�̃j�[�Y�Ɋւ��钲�������{���������ŁA2023�N�x���ɋ��s�s���ɓ��Ђ�EV�[�d���ݒu�B���s�s����EV���p�j�[�Y��c������ƂƂ��ɁA���Ԏ��Ǝ҂ɂ��EV�[�d�ݔ��̐����E�^�p���f�����\�z����B���݁AEV�[�d���2030�N�܂ł�7,000�J����ݒu���A�S���ŏ[�d�X�e�[�V������W�J������g�݂��s���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���č��q�[�g�|���v�ƃN���[���E�G�l���M�[�@������邽�߂ɍ��h���Y�@�iDPA�j�� �č��o�C�f���哝�̂́A�N���[���E�G�l���M�[�֘A�@��̍������Y���g�傷�邽�߂ɁA���h���Y�@�iDPA�j�������B �i�P�j�q�[�g�|���v�A�i�Q�j�\�[���[�A�i�R�j�f�M�A�i�S�j�ψ���Ƒ��d���i�A�y�сi�T�j�d�u�A�R���d�r�A�y�є�����������5�̕�����J�o�[���Ă���B �哝�͖̂��Ԋ�Ƃɑ��āA�A�M���{�Ƃ̌_���D��I�Ɏ��s���邱�Ƃ�v�����邱�Ƃ��ł���B���h���Y�@�ɂ���ăo�C�f�������̓q�[�g�|���v�̐��Y�𖽂��邱�Ƃ��ł��A���{�͍w����ۏ��邱�ƂɂȂ�B���h���Y�@�ŃJ�o�[���ꂽ���ׂĂ̋@��͕č������Ő������ꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B ���h���Y�@�͕č��̃N���[���E�G�l���M�[�̓Ɨ��������߂Ȃ���A�A�M���{�̃N���[���E�G�l���M�[�֘A�@��ւ̓������g�債�A�@��̗A���Ɖ��ΔR���ւ̈ˑ������炷�Ƃ�����d�̖ړI�������Ă���B�X�ɁA�o�C�f�������̌v��ł́A2029�N�ɂ͎����K�X�����@�̔p�~��ڎw���Ă���B �o�T�uJRAIA�v |
|
|
| �����z���Łu���d����J�[�e���v�A����ŋZ�p�͊m�� ���䌧�H�ƋZ�p�Z���^�[���u���z�����d�ł��鎅�v�Ƃ��Ď��g�݁A�J�[�e���ւ̉��p���������Ă����B����̃V���R���ɂ�鑾�z�d�r�Z�����A���d���̋ɍׂ̎��ŋ���łȂ��ō���Ă���B����̑��z�d�r�Z���̓X�t�F���[�p���[���ł���B ���a��1.2mm�ŁA����1�ł����d�ł���B���̗����d���̋ɍׂ̎��ŋ���łȂ��Ŕ��d�E���d���鎅���`�����A1�{�̒����H�ƂȂ��Ă���B�����ʂ̓��d���̎��ƕ҂ݍ����1���ň��̔��d���\�ȕz�n�����B ����V���R���̌����ɂ���ā{�Ɓ|�̋ɂ��ς��B���Ǝ������́{�Ɓ|�̋ɂ��K�ɐG��Ă���悤�ɐD��K�v������B���z�����d���鎅���o���i���Ď��j�Ɏg���ĕ҂ޏꍇ�ɖ��ɂȂ������ɂƕ��ɂ̌����̑���́A���̌����𐮂��郆�j�b�g��lj�����B���z�����d�ɂ��ẮA�Ȑ����q�iFF�j�l�Ŗ�0.65�ƁA���z���p�l���Ƃ��Ĉ��ȏ�̐������������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z���ݒu�`���Ő�s������B�A���x�ύX�Œ~�d�r�𐄐i �č��J���t�H���j�A�B�́A�u�V�z�Z��ւ̑��z�����d�ݒu�̋`���t���v��2020�N��1��������{�����B �܂��A2018�N�ɁA���B�̓d�C���Ǝ҂ɁA�u2030�N�܂łɓd�͔̔��ʂ�50�����ăG�l���璲�B���邱�Ɓv�A����Ɂu2045�N�܂łɓd�͔̔��ʂ�100�����J�[�{���t���[�d���Œ��B���邱�Ɓv��V���ɋ`���t�����B �č����U�^���z�����d�s����x���Ă����̂́u�l�b�g���[�^�����O�inet-metering�j�v���B�Z��p�Ȃǂ̕��U�^���z�����d�V�X�e���̔��d�ʂ���A�d�͏���ʂ����������ė]��d�͗ʂ����������ꍇ�A�]�蕪�����̌��ɌJ��z����d�g�݂��B�����A�]��d�͂́A�������i�ōw�����ꂽ�B���̌�A�o�ϓI�s�����v�i�C���t���ێ��̃R�X�g���S�Ȃǁj�̂��ߌ������A�N�ԗ]��d�͂́A�����i�Ŕ������ꂽ�B����ɁA�n���ڑ���Ƃ���132�ăh���i�Z��p�j�A�����̎g�p�ʂɒP��2�ăZ���g/kWh���ۂ����Ȃǂ̌�����������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����z�����d�̍ő�������u�����Ɏ��g�ށvGX���s��c����{���j ���{�́A�uGX�i�O���[���E�g�����X�t�H�[���[�V�����j���s��c�v���J���A����10�N�����������G�l���M�[������E�Y�f�̎��g�݂Ȃǂɂ��Ď����u��{���j�v���������B �G�l���M�[�ɂ��ẮA���v���ł̓O�ꂵ���ȃG�l����Ƃ̔R���]����i�߂�ƂƂ��ɁA�������ł͍Đ��\�G�l���M�[�⌴�q�͂Ƃ������A�G�l���M�[���S�ۏ�Ɋ�^���E�Y�f���ʂ̍����d�����ő�����p����Ƃ̍l�������������B �ݓc�́uGX�͌o�ώЉ�S�̂̑�ϊv�ł���A�Z�p�i����e���̎��g�ݎ���ŏ��ς��v�Ƃ��āA�č������z�̃G�l���M�[�����x�����ł��o���AEU���Y�f���i�̍��������[�u�ɂ��č��ӂ������Ƃɂ��Č��y�B�u���{��150���~����GX�����������Ŏ������Ă������߁A���Ƃ���20���~�K�͂̑�_�Ȑ�s�����x�������s����B�e�v���W�F�N�g�̐i�������r���[���A��{���j�̃o�[�W�����A�b�v��A���I�ɍs���Ă����v�Əq�ׂ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������̂b�n�Q�A�Z���T�[�Łu�����鉻�v�ڈ�������Ί��C������ ���l�s�́A�s���w�Z�̑S�w����CO2�Z�x�𑪒肷��Z���T�[��ݒu����B1��10������^�p�����B�e�Z�̃f�[�^�͎s�̃z�[���y�[�W�Ō��J����\��ŁA�s�́u�s���̊��C���i�ɂ��Ȃ�v�Ɗ��҂��Ă���B �Z���T�[�͋����̕ǂ�I�Ȃǂɐݒu����A�f���Ɋ܂܂��CO2�𑪒肵�Ď����̋�C�̏�Ԃ��m�F�ł���悤�ɂ���B�����J���Ȃ����C�̖ڈ��Ƃ��Ă���CO2�Z�x0.1���i1000ppm�j����ƁA���C�𑣂�������B �ꕔ�̊w�Z�ł��łɓ�������Ă������A�s��1��71���V���ɐݒu�B�s���̏������Z�Ƌ`������A���ʎx���w�Z�S507�Z�̑S�w���ɔz�������B�e�Z�̋����ł͌��݁A�����J�����芷�C��������肵�Ċ��C���Ă��邪�A�s�̓Z���T�[�̃f�[�^�Ɋ�Â��Đݔ����X�V����ȂNj����̊����P�ɐ����������Ƃ����B�܂��A�S�����̎��g�݂Ƃ��āA�ݒu�����Z���T�[�̂����e�Z��4����C���^�[�l�b�g�ɐڑ����ACO2�Z�x�Ȃǂ̃f�[�^�����\����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA�A�M���{�̌����ɂ�����r�o��Ă\ DOE�́A�A�M���{�̌����̐V�z�E���z���ɂ�����d���Ɣr�o�ʍ팸�̋K���Ă\�����B 2025�N�ȍ~�A�V�z�E���z�����A�M���{�̎{�݂́A�����̔r�o�ʂ�2003�N���90%�팸���邱�Ƃ����߂���B2030�N�A���̊�ɂ��A�A�M���{�̌����̐V�z����ё�K�͉��C�ɂ����錻��ł̔r�o�����S�ɒE�Y�f������B�����̑[�u�́A2045�N�܂łɂ��ׂĂ̘A�M���{�̌����̔r�o�ʂ��l�b�g�[���ɂ���Ƃ����ڕW�B���ɂ��N���[���ȋZ�p�̗̍p�𑣐i����B�܂��A������30���˂̘A�M���{�̌����Ɋւ���G�l���M�[�E�C�\����A���߂Ĕ��\���ꂽ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2023/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���_�C�L���̃G�A�R���V���i�ƊE�g�b�v���̏����� �_�C�L���H�Ƃ́A�ƒ�p�G�A�R���̍ŏ�ʋ@��u���邳��X�iR�V���[�Y�j�v�̐V�@��\�����B �Ǝ��̉^�]����Ń_�C�L���j��ō��̏����ʂ����������ق��A�x�m�t�C�����̋z���Z�p���̗p���邱�Ƃʼn^�]����}���A�����E���C�̐��\�����サ���B���Ђɂ��ƁA�����ł͍��C���E���f�M�Z��̕��y�������B�C���A�f�M���̍����Z��͋̏���d�͂��}���������ŁA24���Ԋ��C�Ő₦���O�C��������邽�߁A�]���̃G�A�R���ł͏������ǂ��t���Ȃ��Ƃ����ۑ肪����Ƃ����B�����Ń_�C�L���̂��邳��X�͔M������Ȃǂ̓Ǝ�����ɂ���đO�N���f�����珜���ʂ�20������B�_�C�L���j��ō��̏����ʂ����������B�����������\�����A�����̃J�r�ۂ̔ɐB��}����V�@�\�u���ǃN���[���^�]�v�����ڂ����B���O�@�ɋz���}�t���[�����邱�ƂŁA�^�]����ς����ɕ��ʂ��A�b�v���A���C�ʂ͑O�N���f������10�����サ���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���z���_�AEV�o�C�N�̃o�b�e���[�V�F�A�ݔ������s���ɍ�����1���@ �{�c�Z���́A�d����֎Ԃ̃o�b�e���[�����X�e�[�V�����uHonda Power Pack Exchangere�v�̔̔����J�n�����B �d����֎Ԃ̃o�b�e���[�V�F�A�����O���Ƃ��s��Gachaco�i�`��j�ɔ[�i����A���{��1��ڂƂȂ�ʎY�@�̉ғ����n�܂����B���̃o�b�e���[�����X�e�[�V�����́A�������o�b�e���[�������ɏ[�d���A�X���[�Y�ȃo�b�e���[�������\�ɂ���B���[�U�[�͊X�̒��̃X�e�[�V�����ŕK�v�Ȏ��ɏ[�d�ς݃o�b�e���[�ɃA�N�Z�X�ł��A�[�d���Ԃ�҂��ƂȂ��A�d�����r���e�B�𗘗p�\�ɂȂ�B �o�b�e���[�������A���[�U�[���{�@�㕔�̃p�l����IC�J�[�h���^�b�`���邱�ƂŔF�����{�B�܂��A�o�^���ꂽ���[�U�[ID�ɕR�Â����p���r���e�B�̏��A�K�ȏ[�d�σo�b�e���[�f���ALED�\���Ń��[�U�[�ɒm�点�邱�ƂŃX���[�Y�Ȍ�����Ƃ𑣂��B�ԋp���̓o�b�e���[���X���b�g�ɍ������ނ����ŁA�����ŏ[�d���J�n����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���V�i�l��HD�A�c�_���d���ƂɎQ���m�[�^�X�ЂƋ��� �V�i�l��HD�́A�c�_�^���z�����d���肪����m�[�^�X�\�[���[�W���p���Ƌ��Ƃ��J�n����Ɣ��\�����B �m�[�^�X�\�[���[�W���p���́A�C�^���A��REMTEC�Ђ����ۓ�����L����3�����ǔ����z�����d�Z�p�u�A�O���{���^�C�R�v�̍����Ɛ�W�J�����擾�B���{�e�n�̔_�Ǝ���ɍ��킹�čœK�������c�_�^���z�����d�V�X�e���u�m�[�^�X�\�[���[�V�X�e���v��v�A���Ă���B ���Ђ͍���A�S���̎����́E���Ԋ�ƂȂǂɌ����ĉc�_�^���z�����d���Ă���B���d���ꂽ�d�͂́A�����́E���Ԋ�ƁE�V�d�͂ȂǂɁA�I���T�C�gPPA��I�t�T�C�gPPA�A���Ɣ��d���f���Ȃǂ̕��@���g���āA�lj����̂���Đ��\�G�l���M�[�Ƃ��ċ�������B �g�ݍ��܂�Ă��鑾�z�����d�Z�p�́A�L���c�_��Ԃ��m�ۂł��A�������̑��z���p�l����C�ӂɓ��������Ƃɂ��Ռ����R���g���[������B�c�_�^���z�����d�Ō��O���������z���p�l���ɂ��_�앨�͔|�ւ̉e����}���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���x�m�d�@�A�ȃG�l���̋@������d��20%�팸 �x�m�d�@�́A�啝�ȏȃG�l����������u�T�X�e�i���̋@�V���[�Y�v��2023�N1���ɔ�������Ɣ��\�����B �R���v���b�T�i���k�@�j�̋쓮����ɃC���o�[�^��K�p���邱�ƂŏȃG�l�^�]�������B�܂��ɓ��\����^��f�M�ނ̔z�u���œK������ƂƂ��ɁA�C������͂���C��g�C�����ʓI�ɐ��䂷�邱�ƂŁA�ɓ��̗�p�E�������������コ�����B�����ɂ��A�]���@�i2022�N�x�@�j605kWh�^�N����V���i�i2023�N�x�@�j485kWh�^�N�ƁA�N�ԏ���d�͗ʂД�ōő�20%�팸����B ����ɁA�����ɂȂǂ̃f�[�^�����u�n���烊�A���^�C���Ŋm�F�ł��A���i�̕�[�p�x�����炷���ƂŁA�I�y���[�^�̍�ƌ��������コ���A�Ȑl�E�ȗ͉��ɍv������B������@���������A����ނ̎g�p�ʂ�7�����炷�B�܂����Ђ�2023�N���߂ǂɁA�ɏ�ܖ������Ȃǂ̏������ƂɁA�̔����i��ϓ�������_�C�i�~�b�N�v���C�V���O�̓K�p��\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�́u���̒��v�̃V���{���ցA�R�`���������́u��C�_�Ёv�ƃR���{ �p�i�\�j�b�N�Ђ́A���{���C�����ꂢ�ȎR�`���ɂ��钩�����́u��C�_�Ёv�ƃR���{���[�V�������܂��B�@��ALED�Ɩ��A�N���[���G�l���M�[�֘A���i�Ȃǂ����p���āA��C�_�Ђ������ڎw���u���̒��v�̃V���{�����Ɍ����ăT�|�[�g����B �R�`����4�N�A���APM2.5�Z�x�ōŗǂ̓s���{���ɑI�o����A�������͐��E�ŗB��A���ꂢ�ȋ�C�Ɋ��ӂ��J��A�@�����̂Ȃ��A�����j�������g�u��C�_�Ёv��L���Ă���B��C�_�Ђ́A�������u�R�Ŏd��������ƁA���n�̎��������ɂ����B����͖L���Ȏ��R�����o�����ꂢ�ȋ�C�̉��b�ł���B��C�Ƃ���ݏo�����R�Ɋ��ӂ���_�Ђ��������悤�v�ƒ�Ă������Ƃ����������ŁA1990�N�ɒa�������B �������͋�C�_�Ў��ӊϑ��n�ŁA�u�S������p���ώ@�v�ɂ����āA1989�N�����S��6�ʂ̎��т�����B�����\�ȎЉ�Â���ɒʂ��āA��C�_�Ђ����{�L���̌i���n�ƂȂ邽�߂ɓw�߂Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���b�b�r���Ɖ��ցA�r�o�҂ɂb�n�Q���L���^�G�l���A�u����E���~�v�\�� �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���́ACCS�i��_���Y�f����E�����j���s���ۂ̓�_���Y�f�iCO2�j�̎�舵���ɂ��ĕ��������������B �N���W�b�g���x�Ŕ����ł��邱�Ƃ⏫���I�Ɏ����ƂȂ蓾�邱�Ƃ����āB��������r�o�҂�CO2�̏��L�����c���Ď��Ɨ��p�┄�p���\�ɂ���B�����Ԃ̌o�ߌ�͐��{�ɏ��L�����ڊǂ��A�����G�l���M�[�����Ƃ��Ĕ��~���s�����Ƃ������BCCS�̎��Ɖ��Ɍ����ẮA�����̍z�Ɩ@��z�R�ۈ��@���Q�Ƃ��ĐV�����@���̘g�g�݂�����B �����J�����uCCS���ƁE�����@�������[�L���O�O���[�v�v�i�v�f�A���������c�M��E����w��w�@�����j�Ŏ����ǂ������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�H�ʈ�̌^�v���z���p�l���������J���ABASF�ƃ\�[���[�A�[�X �h�C�c�̉��w���BASF�ƃJ�i�_�̃\�[���[�A�[�X�E�e�N�m���W�[�Y�iSolarEarth Technologies�j�́A�V�݁E���݂̓��H�Ȃǂ̕\�ʂɐݒu�ł���H�ʈ�̌^���z�����d�iPIPV�j�p�l���������J�������Ɣ��\�����B �\�[���[�A�[�X�E�e�N�m���W�[�Y�́A����̃C���t�����G�l���M�[���ɕϊ����邱�Ƃ�ړI�ɁAPIPV�p�l���̊J����i�߂Ă���B���Ђ�PIPV�p�l���́A����₷�����z�d�r�Z���i���d�f�q�j���d���Ēe�͐��̂���\�ʑf�ނɖ��ߍ����̂ŁA���V��ⓐ��A�j��s�ׂɑς��A�g���b�N�̏d�ʂ��������Ă��������Ȃ����ϋv���������B�����⓹�H�A���ԏ�A����Ȃǂ̃C���t���ɐݒu���邱�Ƃő��z�����d���\�ɂ���B�y�n�̃X�y�[�X��ߖȂ���Đ��\�G�l���M�[�𑗓d�Ԃ�d�C�����ԁiEV�j�A�Ɩ��A���X�Ȃǂ̗p�r�ɒł���B�\�[���[�A�[�X�E�e�N�m���W�[�Y�̑ϖ��Ր��Ƌ@�B�I����������A�|���E���^����v�E�œK�������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���f�[�^�Z���^�[�̋}�g��ɔ����d�͖��A��p�V�X�e����AI���p�ȃG�l���ʂ�20���ȏ� �u�_�n���i�iQuarkdata�j�v�́AAI�𓋍ڂ����G�b�W�R���g���[���V�X�e���uDeepCooling�v���J�����A�f�[�^�Z���^�[��I�t�B�X�r���Ȃǂ̃G�l���M�[���p���œK�����āA20�`25���̏ȃG�l���ʂ��������Ă���B 2025�N�ɂ͐��E�̃G�l���M�[����̂����A�f�[�^�Z���^�[�̐�߂銄�����ł��傫���A33���ɒB����Ɨ\�z����Ă���B ���Ђɂ��ƁA�f�[�^�Z���^�[�̈�ʓI�ȗ�p�v���Z�X�̏���d�͂͑S�̂�40�`45�����߂�Ƃ����B�f�[�^�Z���^�[�ł͈�ʓI�ɒ����M���������Ƃ��Ă��āA������26�x����24�x�ɉ����邽�߃f�[�^���s���Ă������B�_�n���i�́uXeon�v��GPGPU���̗p���A���Z�\�̖͂������������B�f�[�^�Z���^�[��1�`2�T�Ԃ̊������Ƀ��f�����O���s���A�C���⎼�x�A�̉ғ���c�����āA���䍀�ڂ��ƂɍœK�ȃp�����[�^�������A��p�V�X�e���̏���d�͂�20�`25���팸���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u36KrJapan�v |
|
|
| ���A�E�f�B�ACO2�����t�B���^�[�������J�� ��AUDI AG�́A�I�[�X�g���A�̊��KrajeteGmbH�Ƌ����Ŏ��{���Ă���A��C������CO2���������邽�߂̐V�Z�p�J���ɂ��Ĕ��\�����B ���Ђ����g�ސV�Z�p�́A�����\�ȋz���ނɉ����āADAC�i�_�C���N�g�G�A�L���v�`�������O�j���̗p���邱�ƂŁA�啝�ȃG�l���M�[�ƃR�X�g�̍팸����������B ���Z�p�́A�ꏊ���킸��C�����璼��CO2�������ł���̂��������B�܂����W���[���v�ɂ��A�V�X�e�����g�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �ŐV����ł́A�I�[�X�g���A�ɐV�v�����g�����݁B���C�̉e�����ɂ߂Ďɂ������@�t�B���^�[�f�ނ��g�p���Ă���A��߂����C�����O�Ɋ���������K�v���Ȃ����߁A���������サ�R�X�g���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ����B���Ђ̐����ɂ��ƁA��_���Y�f1�g��������̃R�X�g�͂��łɐ��S���[���܂ʼn������Ă���A�����CO2�̎Y�ƖړI�ł̗��p������ɊJ���𑱂�����j���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�A�R���≷����A��������@�\�̓��ڐ����֕N�����̋@���I�Ȏ��v�}���Ɋ��� �����G�l���́A�G�A�R����d�C������ւ�DR�i�f�}���h���X�|���X�j�@�\���ڂ��A�ȃG�l�g�b�v�����i�[���x�̒��Ń��[�J�[�ɐ�������d�g�݂��������Ă���B ���y����ЊQ��̎����N���Ȃǂ̍ہA�@���I�Ȏ��v�팸�����҂ł���B�G�R�L���[�g�͑��z���̓d�͂��]�钋�Ԃɓ����グ��@��Ȃǂ̕��y��_���B�G�A�R����DR�@�\�́u�������U�^���א���v�ƌĂ�A�ꕔ�̍����@��Ɏ�������Ă����B���g����0.8�w���c�ȏ�ቺ�����ꍇ�A�G�A�R���̏���d�͂�������5���ቺ����10���ԕێ�����B�G�A�R�����l�b�g�ɐڑ�����K�v������ق��A���v�Ƃ̎��O�����������ƂȂ�B �I�[�X�g�����A�ł́A���������ƒ�p�G�A�R���⋋����AEV�i�d�C�����ԁj�[�d��Ȃǂ�DR�@�\���ڂ��`�������Ă���BWG�ł́A�ǂ��܂ł̋��x�Ŏ��Ǝ҂ɑΉ������߂邩�A�V���Ȏd�g�݂̐�����܂߂ċc�_����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��GHG�Z��ɌW�鎑�i���x��������J�Ê��� ���Ȃ́A�������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʎZ��ɌW�鎑�i���x��������J�Â���Ɣ��\�����B �킪���S�̂Ƃ��ĒE�Y�f���Ɍ������v�������܂钆�A���Ɖ�Ђł͎��Ђ̊����ɔ���GHG�r�o�ʂ��Z��E���J���铮�����L�����Ă���A�r�o�ʎZ��Ɋւ���x���j�[�Y�̋��܂肩��A�֘A�T�[�r�X�̎s����g��X���ɂ���B���Z�@�֓��A�h�o�C�X�����߂�������̒E�Y�f���Ɍ������l�ވ琬��x���̐���������AGHG�r�o�ʂ̎Z���E�Y�f�o�c�x���Ɋւ��閯�Ԃ̎��i���x�����p���铮���������邪�A�l�X�ȓ��e�̎��i���x�����݂���Ȃ��A�擾�����シ�ׂ����i��I�肷�邽�߂̊�����߂鐺��������Ă���B���������܂��AGHG�r�o�ʂ̎Z���E�Y�f�o�c�x���Ɋւ��閯�Ԏ��i���x���������ׂ��������ɂ��Č������s���A���̌��ʂ��K�C�h���C���Ƃ��Ď��܂Ƃ߂邽�߁AGHG�r�o�ʎZ��ɌW�鎑�i���x��������J�Â���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���uCO2�r�o�[���錾�v�ɐM�����E�����ӔC�����A���Ƃ��� ���A�̐��ƃO���[�v�́A��Ƃ⎩���̂��uCO2�r�o�[���i�l�b�g�[���j�v��錾����ꍇ�̏����ɂ��Ē��܂Ƃߌ��\�����B ���̒ł́A�������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʂ������[���ɂ���ڕW��錾������Ƃ⎩���̂Ȃǂɑ��āA���N�̐i�������ɂ��邱�Ƃ�A���ΔR���̎g�p�E�x�����~���邽�߂̋�̓I�ȖڕW���߂邱�ƂȂǂ荞��ł���B2015�N�Ƀp�����肪�̑�����Ĉȗ��A���E�ł́A��ƁE�����̂ɂ��l�b�g�[���錾�̐����������Ă���B����A���錾�ł́A����ׂ������ɔz�����Ă���悤�ɑ����u�O���[���E�H�b�V���O�v�ւ̑Ή����ۑ�ƂȂ��Ă���B���ł́A�l�b�g�[���錾�̔��\�A�ڕW�ݒ�A�N���W�b�g�̊��p�A�ڍs�v��̍���A�E���ΔR�R���ƍĐ��\�G�l���M�[�̊g��A�������Ɛ����ӔC�̌���A�����Ȉڍs�ւ̓����ȂǁA10�̒��܂Ƃ߂Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2022/12�@]�@�@�� |
|
|
| �������Ɂu�t���L�V�u�����z���p�l���v�A�{�H�ۏɑΉ� �d�C�ݔ����ЁE�d�C�H����Ђ̓d�I�Ђ́A�����^�Ńt���L�V�u���ȑ��z���p�l���̔̔��E�{�H���s���Ɣ��\�����B �����^���z�����d�V�X�e���̎{�H�ۏɑΉ�����B�t���L�V�u�����z���p�l���́A�P�����V���R�����z�����d�Z���i���d�f�q�j���������t�B�����ŋ��\���ɂȂ�B�]���̃K���X��̑��z���p�l���Ɣ�r����3����1���x�̌y�ʂŁA����܂őωd�̖��ő��z���p�l����ݒu�ł��Ȃ����������ɂ��ݒu�ł���B �ϊ������͖�21���ƁA�]���̑��z���p�l���Ƃقړ����̔��d�\�͂������Ƃ����B�܂��A�S���̗��������ł��K���X��̑��z���p�l���Ƃقړ����̑ϋv�������������B�������[�J�[���ŁA25�N�Ԃ̏o�͕ۏ��t���B�{�H�́A�ˑ��p�����p�l���ڐڒ�����B���Ђł́A�p�l���o�͕ۏɂقڏ�����`�ł̃V�X�e���{�H�ۏɑΉ�����\��B���Ђł̎{�H�ɉ����āA�����I�ɂ͔̔��㗝�X��{�H�Ǝ҂�ΏۂƂ������C�Z���X���x����������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����{�s�[�G�X�A�{�ЍH��ɑ��z���ƃ��h�b�N�X�t���[�d�r�� �����Ȃǎ�|���錚�݉�Ђł�����{�s�[�G�X�́A4���ɏv�H�����V�H��Ɏ��Ə���^���z�����d�ݔ��ƃ��h�b�N�X�t���[�d�r������B2023�N2���ɉғ�����\��B ���z���p�l����1960���ݒu���A���z���p�l���̏o�͂�931kW�A�N�Ԕ��d�ʂ�97��3000kWh�̌����݁B���z���p�l���͒����W���R�E�\�[���[���A�p���[�R���f�B�V���i�[�iPCS�j�͒����t�@�[�E�F�C�����̗p����B�܂��A���h�b�N�X�t���[�d�r�͏Z�F�d�C�H�Ɛ��ŁA�o�͂�250kW�A�e�ʂ�750kWh�B���z�����d�ƃ��h�b�N�X�t���[�d�r�̕��p�ɂ��A�{�ЍH��ɂ�����d�͂̎��Ə���ɂ��Đ��\�G�l���M�[�䗦50���ȏ����������B���h�b�N�X�t���[�d�r�́A�ϋv����20�N�Ə]���̒~�d�r��荂�����ł���A�퉷�ʼn^�]�\�Ȃ��߉Ђ̉\�����ɂ߂ĒႭ���S���������̂������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��JAL�A�������uCO2�����[���v�t���C�g�A�o�C�I�}�X�R���Ȃǂ� ���{�q��iJAL�j�́A�����i�H�c�j�|����i�ߔe�j���ɂ����āA11��18���ɍ������ƂȂ�uCO2�r�o�ʎ����[���v�̃t���C�g���^�q����B �`���[�^�[�t���C�g�ł́A�]���@�Ɣ�r����CO2�r�o�ʂ�15�`25�����x�팸�ł���G�A�o�XA350�^�@���g�p����B�^�]�̍H�v�A�o�C�I�}�X�R�������ɂ��SAF�i�����\�ȑ�֍q��R���j�̓��ځAJAL�J�[�{���I�t�Z�b�g�����p����CO2�r�o�ʎ����[���̃t���C�g����������BSAF�̒��B���g�p�ʂȂǂ͒������B �܂��A����q�ɂ́A��ו��y�ʉ��ɂ��CO2�r�o�ʂ̍팸�Ȃǂ̋��́A�����ׂ̗}����h�{�ɔz�����������̐H�ނ��g�p�����@���H��F���擾���������̒���\��B ���Ђ́A�ȔR��@�ނւ̍X�V�A�^�q�̍H�v�ASAF�̊��p�𐄐i���Ă���B2030�N�ɂ�CO2���r�o�ʂ�2019�N�x��90���ɗ}���邽�߁A�S�R����10����SAF�ɒu�������邱�Ƃ�ڎw���Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���K�����i���Ŋ�H�A���{�̋��[�J�[�J���}�� ���B�ł́A���N4���ɂ͑�փt�����팸������������K�������Ă����\���ꂽ�B���̂��߁A���{�̋��[�J�[���Z�p�J�����}���ł���B �p�i�\�j�b�N�́A�n�����g���ւ̉e����}�������}���g�����g�[�@�̐V���i�\�����B�p�i�\�j�b�N��3���A�p���Ŏn�܂������B�ő�K�͂̋��{�s�u�C���^�[�N���}�v�ŁA���g���ւ̉e�����������u���R��}�v�̃v���p�����g�����q�[�g�|���v���g�[�@�\�����B�����̋@��͗�}�Ƃ��đ�փt�������g�����A���g���ւ̉e�����A��_���Y�f�ɔ�ׂĂ����ɑ傫���A���E�ŋK�����i��ł���B �����Ńp�i�\�j�b�N�́A��C�ɕ��o����Ă����R��������A���g���ւ̉e�����������Ƃ���鎩�R��}���g�����@�̊J��������i�߂Ă����B����܂Ŏ��R��}�́A�R����Ő������邽�߉����̗�g�[�@�����Ɏg���ɂ����A�Ȃǂ̉ۑ肪���������A����A�v���p�����R��Ȃ��\���̎����ɐ��������Ƃ����B�e���[�J�[���V���i�J�����}���ł���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �����N���g�A�Г��Y�f���i��1�g��3��7000�~ ���N���g�́A��Ɠ����œƎ��ɒY�f�ɉ��i��t����CO2�r�o�ʂ����z�I�ɔ�p���Z����u�C���^�[�i���J�[�{���v���C�V���O���x�iICP���x�j�v������B�������Ə���ΏۂƂ���CO2�r�o�ʂ̑������ݔ��������ΏہB�Г��Y�f���i��37,000�~�^t.CO2�B ICP���x��CO2�r�o�ʂ����z�I�ɔ�p���Z���ACO2�r�o�ʍ팸�Ɍ������o�ϓI�ȃC���Z���e�B�u��n�o���邱�ƂŁA��Y�f������C��ϓ���𐄐i����d�g�݁B�P�ʂƂ��āAt�|CO2�iCO2�r�o1�g��������j��p����B���Ђł�10���ȍ~�A�ΏۂƂȂ�ݔ������ɔ���CO2�r�o�ʂɑ��A�Г��Y�f���i�̓K�p�ɂ���p���Z�������̂𓊎����f�̎Q�l�Ƃ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���g���i�A�r���O�ǂւ̑��z���p�l���ݒu���� �g���i�E�\�[���[�E�W���p���́A�W����ŁA�r���O�ǂ⒓�ԏ�̖����p�X�y�[�X�ɐݒu�ł��鑾�z�����d�V�X�e���uCARTS�i�J�[�c�j�v��W�������B���V�X�e���́A���z���p�l�����Z���r���̊O�ǂɒ��p�ŌŒ�ł���ǐݒu�^�C�v��A�d�����]�ԗp�̒��֏�̏�ɐݒu�ł���T�C�N���|�[�g������B�ǖʂ≮���ɐݒu���Ă����ΓI�ɖڗ����Ȃ��A�ᔽ�˃K���X���̗p�����t���u���b�N�d�l�̐V�^���z���p�l�����W�������B CARTS�́A�I�[�X�g�����A�̑��z���p�l���p�ˑ䃁�[�J�[�A�N���[���G�i�W�[�W���p���A�N���b�v�Ȃǃt�@�[�X�j���O�i���߁j�Z�p�������C�����W���p���Ƌ����J�������B���z���p�l�����{���g���X�̃N���b�v��p���ėe�Ղ����łɐݒu�ł���Ƃ����B�܂��A���܂��܂ȏ����ł̐ݒu�Č��ɑΉ�����B�ǐݒu�̏ꍇ�A���C�����W���p�����̃N���b�v���g���āA�}���V������{�݂̓�ǖʂɑ��z���p�l����ݒu�ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���b�b�r���Ɖ��ցA�r�o�҂ɂb�n�Q���L���^�G�l���A�u����E���~�v�\�� �����G�l���M�[���́ACCS�i��_���Y�f����E�����j���s���ۂ̓�_���Y�f�iCO2�j�̎�舵���ɂ��āA���������������B �N���W�b�g���x�Ŕ����ł��邱�Ƃ⏫���I�Ɏ����ƂȂ蓾�邱�Ƃ����āB��������r�o�҂�CO2�̏��L�����c���Ď��Ɨ��p�┄�p���\�ɂ���B�����Ԃ̌o�ߌ�͐��{�ɏ��L�����ڊǂ��A�����G�l���M�[�����Ƃ��Ĕ��~���s�����Ƃ������BCCS�̎��Ɖ��Ɍ����ẮA�����̍z�Ɩ@��z�R�ۈ��@���Q�Ƃ��ĐV�����@���̘g�g�݂�����B�uCCS���ƁE�����@�������[�L���O�O���[�v�v�Ŏ����ǂ������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����f���d�̉ۑ�́u�����ԁv�^����ʑ�����[�Ɏ��ԁA�f�s�J���͌o�ϐ��ӎ� ���f�����Ԃ̍\�z��GT�̊J�������E���������B�K�X�^�[�r���iGT�j���[�J�[�e�ЂŁA���f�����Ԃ̍\�z�ɊS���W�܂��Ă���B�e�ЂƂ����f���ė��̈����グ�����ĂɌ����āAGT�ɂ��R�ċZ�p�̊J����i�߂邪�A���ɑ�^���d���ł͐��f����ʂ��c��B�v��̗����オ������ʂ��ɂ����A�����J����̓����y�[�X��Y�܂���B���{��������������Η͔R���Ƃ̒l����U�̎d�g�݂����ɂȂ肻�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����q�͉^�]���Ԃ݂̍���A�@�I�����u���p���v�Ɂ^�d���@�ƘF�K�@�����H �K���ς͉^�]���Ԃ݂̍���̓G�l�����̋c�_�Ɉς˂�Ƃ̔F���ň�v�������q�F���K���@�i�F�K�@�j����������ɓ��ꂽ���q�͔��d���̉^�]���Ԃ̌��������{�i�����������B �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[�����A���q�͋K���ψ���̒���Ō��q�͔��d���̉^�]���Ԃɂ��āu���p�������̖@�̌n�Ō�������v�Ƃ̕��j���������B�@�����Ɋւ����̈Ă͔N���܂łɋl�߂邪�A�F�K�@�ɂ���u�^�]�J�n���猴��40�N�v�u1��Ɍ���ő�20�N�̉�����F�߂�v�Ƃ�����|�̕������폜���A�o�Y�ȏ��ǖ@�߂ɉ^�]���Ԃ��������ނ��Ƃ��z�肳���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ăn���C�A�Ō�̐ΒY�Η͂��u�n���p�~�d�r�v�ő�ցu2045�N�܂ł�100���v��@���ɖ��L �č��ɂ́A���K�\�[���[�ł͂Ȃ��A�����u���Ȃǂ̕��U�^���z�����d�V�X�e���ōăG�l�������g�債�Ă���B������B����́A���{�̂悤�ɓ��X�ō\������A�A���������ΔR���Ɉˑ�����n���C�B�ł���B �n���C�B�́A�����㑾�z���̕��y���ŕč��g�b�v�ł���n���C�B�̊���d�Ԃ́A�Ɨ������d�͌n���i�O���b�h�j�ŁA���Ɠ����m���C�ꑗ�d�P�[�u���Ō���Ă��Ȃ��B���̂��ߓ��B�́A�G�l���M�[�����5����4�ȏオ�Ζ���A���Řd���Ă���B���̂��߁A�n���C�̓d�͏������i�͂ǂ̏B���������A�č��̕��ϓI�ȓd�C�����̂ق� 3�{�ƂȂ��Ă���B�n���C�B�́A���ΔR���ˑ�����̒E�p�ƋC��ϓ���̈�Ƃ��āA2014�N�Ɂu�ăG�l100���v�𐭍��ڕW�Ƃ��čŏ��ɖ@���ɖ��L�����B2045�N�܂ł̒B����ڎw���Ă���B���ԖڕW�́A�u2030�N�܂ł�40���v�A�u2040�N�܂ł�70���v�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Đ��\�G�l���M�[�̊g����x����g���~�d �����ō�N����g���~�d�ւ̓����u�[�����n�܂����B�����̗g���~�d�̗e�ʂ�2021�N�����_��3639��kW�ƁA���E�g�b�v���������A���N���ɂ�4500��kW�A2025�N�ɂ�6200��kW�A2030�N�ɂ�1.2��kW�ƁA�}���ɗe�ʂ𑝂₷�����݂ł���B ����͍Đ��\�G�l���M�[�̓������g�傷�邽�߂��B�������{�́A2020�N���_�ŕ��͔��d2.8��kW�A���z�����d2.5��kW�������̂��A2030�N�ɂ͗��ҍ��킹��12��kW�ɑ��₷�v��ł���B�Đ��G�l���M�[������͓d���Ƃ��邽�߂ɂ́A�����̕ϓ����Ȃ炷�K�v������B���낢��Ȓ~�d��i�����邪�A����ł̓R�X�g��������_������B �����ł̗g���~�d�u�[���́A�g���~�d���r�W�l�X�Ƃ��Đ��藧�悤�Ȑ��x�����ꂽ���Ƃɂ��B�g���~�d�̃r�W�l�X�Ƃ́A�ȒP�Ɍ����A�d�C���]���Ă��鎞�Ɉ��������Đ������ݏグ�A�d�C������Ȃ����ɔ��d���ēd�C���������邱�Ƃŗ��U�����҂����Ƃł���B �o�T�u�j���[�Y�E�C�[�N�v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȂȂǁA���E�̃N���[���G�l���M�[�ւ̈ڍs�����Ɍ������I�����𓊓� �A�����J�G�l���M�[�ȁiDOE�j�́A��������Â����t�H�[�����ŁA�����̂ق��A�I�[�X�g�����A�A�J�i�_�A���B�ψ���iEC�j�A�t�B�������h�A���{�A�|�[�����h�A�؍��A�V���K�|�[���A�X�E�F�[�f���A�A���u���A�M�A�C�M���X�Ȃ�16���������͂��A�N���[���G�l���M�[�̎��v���W�F�N�g��940���h�������o����Ɣ��\�����B ���̃t�H�[�����̓N���[���G�l���M�[�Ɋւ���s���v��ɂ��ċ��c���鏉�̍��ۃt�H�[�����ŁA34�����̐��{�t���A400���߂���CEO�A�Ⴂ���ƂȂǁA�N���[���G�l���M�[�̃��[�_�[����l���Q�������B���Ȃ́A�R�X�g�����͂̂���Y�ƔM�̒E�Y�f���Z�p���J�����A2035�N�܂łɉ������ʃK�X�r�o�ʂ�85%�ȏ�팸����v��ł���B �܂��A�I�[�X�g�����A�A�J�i�_�A�h�C�c�A�C�X���G���A�j���[�W�[�����h�A�m���E�F�[�́A2035�N�܂łɊe�����{���擾���ĉ^�p���鏬�^�Ԃ�100%�[���G�~�b�V�����ԂƂ��邱�Ƃ�����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������s�A���ވ�̌^���z����s�L�{�݂ɁA���f�����Ƃő听���݂ƃJ�l�J��I�� �u�s�L�{�݂ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�����鉻���f�����Ɓi���ވ�̌^���z�����d�ݔ��j�v�́A���y�����i�K�̌��ވ�̌^���z�����d�ݔ���s�L�ݔ��ɐݒu���A�u�����鉻�v�ɂ��F�m�x���グ�邱�ƂŁA���Ԏ{�݂ւ̕��y���i�ɂȂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ������́B �ݒu�ݔ��̑n�G�l���M�[���ʂ𑪒肷��ق��A�ݒu�ꏊ�t�߂Ŏ��Ɠ��e����₷���f�����A���w�҂Ȃǂւ̃A���P�[�g�����{����B�܂��AWeb�T�C�g�ȂǂŎ��Ɠ��e���L�����M���邱�ƂŁA���ވ�̌^���z�����d�ݔ��̕��y�𑣂��B ���{�ꏊ�́A�������ۓW�����1�J���ƁA���������Ɨ̂ӂꂠ���ق�2�J���B�ݒu���錚�ވ�̌^���z�����d�ݔ��̎d�l�͌��������B2023�N3�����܂łɐݔ���ݒu���A���ʑ���Ȃǂ��J�n����B�ݒu���Ԃ�2027�N3�����܂ł̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ������s�Łu�n��}�C�N���O���b�h�v�\�z������ �_�C�������h�d�@�������@�\�������s�ɂ����āA�n��ƈ�̂ƂȂ��ĒE�Y�f�Ɏ��g�݁A�G�l���M�[�̒n�Y�n������������B����ɁA�n��h�ЁE�n�抈���ɂ��œ_�āA�n��̔��W�ɍv������v�����̍쐬��ڎw���B ���v���W�F�N�g�͎����G�l���M�[����2022�N�x�u�n�拤���^�Đ��\�G�l���M�[�����y���i���Ɣ�⏕���i�n��}�C�N���O���b�h�\�z�x�����Ƃ̂����A�� .�v�����쐬���Ɓj�v�̍̑������{����B ���Ǝ�̂͋����g������S�H�Z���^�[�B�_�C�������h�d�@����\�Ƃ��Đ\�����s���A�������Ǝ҂Ƃ��Ē���K�X�ABIPROGY�A�f�W�^���O���b�h�A����s���Q�悷��B �f�W�^���O���b�h�́A���{���̖��Ԃɂ�鎩�R�ȓd�͎���s��u�f�W�^���O���b�h�v���b�g�t�H�[���v�iDGP�j��ʂ��Ď��v�ƂƔ��d�Ƃ����ѕt����P2P�������Ă���B����̎��Ƃւ̎Q���ʂ��āA�n���Ƃ��锭�d�ƂƎ��v�Ƃ�P2P�̎�������������邱�ƂŎ����̒n�Y�n��������������X�L�[���̌����𐄐i���Ă����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���V���[�v�A�u�t���[�^������C�d�r�v�J���A�ăG�l�������Ɋ��p �V���[�v�́A��K�͂ȓd�͒����Ɍ����u�t���[�^������C�d�r�v��p�����~�G�l���M�[�Z�p�̊J���Ɏ��g�ނƔ��\�����B ���Ђ�2015�N���납�猤���J����i�߂Ă���������C�d�r�Z�p���x�[�X�ɁA�V���Ƀt���[�^�������̗p���邱�ƂŁA��R�X�g����e�ʂ̒~�G�l���M�[�Z�p�̊m����ڎw���B ��C���̎_�f�����p���ď[�d����d���s����C�d�r�̈��ŁA��C��~����~�G�l���M�[�����Ɉ����iZn�j�𗘗p����B�_�������iZnO�j�������ɉ��w�ω�����ۂɓd�q��~���A��C���Ɋ܂܂��_�f�Ƃ̍�p�ɂ���Ĉ������_�������ɖ߂�ۂɓd�q����o���邱�Ƃœd�C�����o�����Ƃ��ł���B�����́A�����ŋ��������肵�Ă���B�[���d��S���Z���ƈ����̒��������Ɨ����Ă���t���[�^�������̗p���A�������̑�^���ɂ���ėe�Ղɑ�e�ʉ��ł���B������Z���Ă���d���t�ɂ͐��n�̉t�̂��g�p���邽�߁A���̉\�����ɂ߂ĒႭ�������S�����m�ۂ���Ă���Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����R��}�ɂ��Ⓚ�①�q�ɁA����ɑ��z���p�l�� �����փL���s�^���́A2030�N�̃t�����K�����������A���ɔz���������R��}��p�������^�Ⓚ�①�q�ɂ��J�������B����ɑ��z�����d�ݔ���ݒu����\��B ���z���p�l���̏o�͂�194.04kW�A�p���[�R���f�B�V���i�[�iPCS�j�̏o�͂�150kW�B���d�����d�͂̈ꕔ�͓����e�i���g�ɋ��������\��B�n��4�K���ēS�����i�ω\���j�ŁA���ݎؖʐς�8633.95m2�B�S��LED�Ɩ����̗p����B ���Ђ��J���p�n�̃]�[�j���O����ъ�旧�Ă��s���A���[�V���O�}�l�W�����g�Ɩ�����������{�݂ɂȂ�B�H�i������SBS�[���c�E���e�i���g�Ƃ��ē������u�s��R�[���h�Z���^�[�i���́j�v�Ƃ���10������^�p�J�n����B �����փL���s�^���ɂƂ��ėⓀ�①�q�ɊJ���̑�1���ƂȂ�B2030�N�̃t�����K���ɔ����A�����q�ɂ͗��Ē�����ݔ��̍ē����𔗂��Ă������A���R��}�𗘗p�������^�Ⓚ�①�q�ɂ̊J����i�߂Ă����B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ���T���g���[�A�����ő�16MW�K�͂̐��d���V�X�e������ �T���g���[�́A��K�͂Ȑ��d���V�X�e�����A�R�����k�m�s�ɂ���u�T���g���[�V�R����A���v�X���B�H��v����сu�T���g���[���B�������v�ɓ�������B�R���������Ԋ�ƂƂƂ��ɊJ����i�߂Ă��鐅�f�����Z�p�u��܂Ȃ����f��P2G�iPower toGas�j�V�X�e���v�̈�ŁA�R�����Ɗ�{���ӏ�����������B �����ő�ƂȂ�16MW�K�͂̐��̓d�C�����ɂ�鐅�f�������u�iP2G�V�X�e���j���A2024�N�x���ɓ������邱�Ƃ�ڎw���B�O���[�����f������Đ��\�G�l���M�[�d�͂ɂ��ẮA�����̍ăG�l�d���B����\��B���H��Ŏg�p��������H���̔M�����ăG�l�R�����f�ɓ]�����邾���łȂ��A���Ӓn��Ȃǂł̐��f���p�ɂ��Ă��R�����ƂƂ��Ɍ��������g��ł����B �u��܂Ȃ����f��P2G�V�X�e���v�́A�R�����A�����A�����d�̓z�[���f�B���O�X�A�������x��4�҂������J�����Ă����ő̍����q�iPEM�j�^�̐��d�u�ɂ�鐅�f�����Z�p�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����K�X�A�����[�X�d�r�ɂ��u�n���p�~�d�r�v���� ���K�X�́A�~�d�r�̐���Z�p������NExT-eSolutions�Ǝ��{�Ɩ���g���A���r���e�B�R���̃����[�X�~�d�r�����p�����u�n���p�~�d�r�v�̎��Ɖ���ڎw���Ɣ��\�����B���e�Ƃ���2023�N3������A�d�C�����ԁiEV�j�����[�X�~�d�r�Ȃǂō\�z�����~�d�r�V�X�e���ɂ����؎������J�n����B ���؎����ł́AEV�ƃt�H�[�N���t�g���������������[�X�i�ƐV�i�̒~�d�r���g�p���Ē~�d�r�V�X�e�����\�z���A���قȂ�~�d�r��g�ݍ��킹�ĉ^�]�����ۂ̃����[�X�~�d�r�̗L������������B���ɂ́ANExT-eS�̐���Z�p��KRI�Ђ̗f�f�Z�p�����p����B����ɁA�����K�X�̓d�̓g���[�f�B���O�m�������p���A���d�͎s��E���������s��E�e�ʎs���3�̓d�͎s��Ƃ̎����z�肵�Čo�ϐ����ő剻����^�p�����s���B����́A�����œ���ꂽ�m������ɁA�K�͂��g�債���`�ł̎��Ɖ���ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I�����[��31�{�݂Ɏ��ȑ����A�ሳ740�J��65MW�̑��z������ �C�I�����[���A�G�R�X�^�C���A�݂��كO���[�v�́A5���ɒ���������{���ӂɊ�Â��A�S���̃C�I�����[��31�{�݂ɍĐ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂���������B�ሳ�A�n�ɂ�鏬�K�͕��U�^���z�����d���u�C�I�����[���܂��̔��d���v�̊J����i�߂Ă���B9������ăG�l�d�͂̋����������A�J�n�����B �S����740�J���A���v��65MW�K�͂̒ሳ�E���U�^���z�����d�����J�����A���d�����d�͂��u���ȑ������x�v�����p���āA�S���̃C�I�����[��31�{�݂ɓd�͂���������B �C�I�����[�������d���ƎҁA�d�͎��v�ƂƂȂ�A�G�R�X�^�C�������d���p�n�̎��W�E�J���AEPC�i�v�E���B�E�{�H�j�EO&M�i�^�c�A�ێ�j�T�[�r�X�A���ȑ����̓����E�^�p�̃T�|�[�g��S������B�܂��A�݂��كO���[�v�e�Ђ��t�@�C�i���X�A�����W�̒A�X�L�[���\�z�ȂǂɊւ��鏕���A���X�N�}�l�[�g�̐ݒ�Ȃǂ��s���B 1�{�݂����蕽�ϖ�1�����x�̓d�͂z�����d�Řd���錩���݁B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ����^�Ⓚ�Ԃɑ��z���p�l�����ځA5���̔R����P���� �Зp�ԁE���p�Ԃ̉^�s�Ǘ��V�X�e���Ȃǂ��J������V�X�e�b�N�́A�i�K�T�L���W�X�e�B�N�X�̋��͂̂��ƁA��^�Ⓚ�ԁi25t�j�̉ב��ɑ��z���p�l�������A���؎������J�n�����B �ă~�A�\�����̏o��125W/���̔������z���p�l����4���A���v500W��ݒu�����B�����i�́ACIGS�����������̌n�ŁA�����V���R���^�p�l���ƈقȂ�A���^�y�ʂŋȖʂɂ��ݒu�ł���̂������B����̎��ł́A�ב�㕔�ɉˑ�Ȃ��Őݒu�ł���ȂǍH�����e�ՂȂ��Ƃ�A�y�ʂ̂��ߎԌ��Ȃǂ���蒼���K�v���Ȃ����ƂȂǂ̗��_��]�����č̗p�����B ���d�����d�͂́A�ԗ��p�o�b�e���[�̏[�d�ɗp����B��ʓI�Ɏԗ��͒ʏ펞0.4kWh���x�̓d�͏�����邱�Ƃ���A�I���^�l�[�^�[�i�_�C�i���j�̕��y���ɂ���5���̔R����P�ACO2�팸�A�o�b�e���[���������Ȃǂ����҂����B�܂��A�ԑ̉����ɐݒu�����`���[�W�R���g���[���[�ɂ��f�[�^�ʐM���s���A���z���p�l���̔��d�ʂ𐏎����j�^�����O�ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p���ō��v100MW�̌n���~�d�r�v���W�F�N�g���H�A�k�āE���{�̎s��g��ɔ����� ���{�H�c�Ɠ��ŎO�H�d�@�Y�ƃV�X�e���iTMEIC�j�ȂǓ��n���5�Ђ́A�p���ő�K�͂Ȓ~�d�r���g�����n�����艻���Ƃɏ��o���B���v��100MW�̒~�d�r��d�͌n���ɐڑ����A���z���E���͔��d�̑���ŕs����ɂȂ�����o�����X�����艻������T�[�r�X�Ȃǂ����B ���K�\�[���[���^���͂ɕ��݂����~�d�r�����߂���B��ʓI�ɕϓ����Đ��\�G�l���M�[�iVRE�j�䗦��20�����Ă���ƌn���S�̂̉^�p���s����ɂȂ��Ă���B�p���́AVRE�䗦�������A����ɑΉ������e��̓d�͎s�ꂪ�����オ��A���������Ă���B ��i�I�Ȏs����Ōn���~�d�r�̃r�W�l�X�Ɏ��g�ނ��ƂŁA����A�~�d�r�V�X�e���ɋ��߂��鐧��̍������A���x���̃j�[�Y��c������B�ăG�l�̓����ɔM�S�Ȑ�i���ł́A���z���E���͂̓������i��ł���A����ɂ��n���^�p�ւ̉e����}�����邽�߁A�u�������艻�s��v�Ƃ�������V�r�W�l�X�������オ���Ă��Ă���B |
|
|
| ���u����I�~�d�r�v�u�p�l���o�͑��v�A���[���ύX�ʼn��ւ� �L���҉�c�i�Đ��\�G�l���M�[��ʓ����E������d�̓l�b�g���[�N���ψ���j�J�Â��A���z�����d�̂���Ȃ铱���Ɍ��������x�ʂł̑Ή��ȂǂɊւ��ē��c���A�������z�����d���́u�p�l���̏o�͑����v�𐄐i����ق��A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j����t�B�[�h�C���E�C���E�v���~�A���iFIP�j�ւ̈ڍs�ɔ����A����܂ŗ}���I�Ȏd�g�݂ɂ��Ă����u����I�~�d�r�v�Ɋւ��āA���i����������������B ����c�Ŏ����ǁi�o�Y�ȁj�́A2021�N�x�̑��z���̔F��ʂ�2.4GW�ƌ��\�����B2020�N�x��1.7GW�Ɣ�ב����������̂́A�u�K�n�̌����Ȃǂɂ��A�F��ʂ͔N�X�A�k���X���ɂ���v�Ƃ��A����A�u���i��ɂ���āA5�`6GW�܂ʼn����邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����@�T�C�Y��CO2�ő̋z���ނ̕]���ɒ���B��C����CO2�ډ������Z�p�̊J�� NEDO��RITE�A�O�H�d�H�͋����ŁA�u���[���V���b�g�^�����J�����Ɓv�Ɏ��g��ł���B���ʁA1�������萔�L���O�����K�͂ő�C�������_���Y�f�iCO2�j�ډ���ł��鏬�^�̎������u���J�����A�����������CO2�ő̋z���ނ̕]���ɒ��肵���B �{���u�����p���邱�ƂŁA���@�T�C�Y��CO2�ő̋z���ނ�]���ł���悤�ɂȂ�A���u�̑�^���E���p���Ɍ������f�[�^�̎擾�A�m���̒~�ς��\�ƂȂ�܂����B����ɂ��A��C����CO2�ډ������DAC�iDirect AirCapture�j�Z�p�̊J�����傫���O�i�����B����A2020�N��㔼�Ƀp�C���b�g�X�P�[����DAC�������u�̐v�ƌo�ϐ��]�������{�\��ŁA�����̎Љ������ڎw���B����A1�������萔�L���O�����K�͂ő�C������CO2�ډ�����鏬�^�̎������u���J�����A�{���u�����p���邱�ƂŁA���@�T�C�Y��CO2�ő̋z���ނ�]���ł���悤�ɂȂ�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���q��R���uSAF�v���Y���ցA�����Ȃ��֘A��Ƃ��x���A�F�؎葱���Ȃǂ̏����W ���y��ʏȂ́A��_���Y�f�iCO2�j�̔r�o�ʂ�啝�Ɍ��点��q��R���uSAF�v�iSustainable AviationFuel�j�̍��Y���Ɍ����A�֘A��Ƃ̎x���ɏ��o���B�Ζ��≻�w���[�J�[�ȂǏ\���Ђ��Q�������ƕ����ݒu���ASAF�̍��۔F�؎擾�Ɍ��������͑̐������B2025�N�x�̍��Y�J�n��ڎw���B �q���Ђ�SAF���g���ĒE�Y�f�Ɏ��g�ƔF�߂���ɂ́A���A�̐��@�ցE���ۖ��ԍq��@�ցiICAO�j���w�肷�閯�ԋ@�ւ���F����K�v������B������Y�ߒ��̐R�����������A�葱�������G�ŁA�F�܂łR�N�ȏォ���邱�Ƃ�����B������Ƃɂ͔F�邽�߂̃m�E�n�E���R�������߁A�����Ȃ����ʎx������B �����Ȃ́A2030�N�܂ł�10����SAF�ɒu��������ڕW���f����B�����ASAF�̐��Y�◘�p�ł͉��B����s���Ă���A�R���̈�芄����SAF�ɐ�ւ���悤�`���Â��鍑������B���i�̓W�F�b�g�R����3�`4�{�Ƃ����B ����͍����O�̍q���Ђɂ��r�`�e�̑��D�킪�\�z�����B�����̋�`��SAF�̋��������Ȃ���A���B�̗��q�@�����{�ւ̒��������炵���˂Ȃ��Ƃ̌��O������B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���h�C�c�A�d�C��ɏ�������ց^���z�͍������Ǝ҂ɕ�U �h�C�c�A�M���{�́A���ƈψ�����������������K�X�����̏���ݒ��@���A�d�C����������ɂ��K�p����ӌ����B �A�M���{�́A�ő�Q�牭���[���K�͂̃K�X���i�}������u����Ɣ��\�B���̖ڋʂƂ��ăK�X���i�ɏ����݂���Ƃ����B��̓I�ɂ́A���v�Ƃ��ƂɃx�[�X�ƂȂ�K�X�g�p�ʂ��߁A���̂�����芄���͏���z���Ȃ��悤�ɂ���B�������Ǝ҂ɍ��z�����U��������B�d�C��̏���ݒ�ɂ��Ă��A����������@����������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����f���d�̉ۑ�́u�����ԁv�^����ʑ�����[�Ɏ��ԁA�f�s�J���͌o�ϐ��ӎ� �K�X�^�[�r���iGT�j���[�J�[�e�ЂŁA���f�����Ԃ̍\�z�ɊS���W�܂��Ă���B �e�ЂƂ����f���ė��̈����グ�����ĂɌ����āAGT�ɂ��R�ċZ�p�̊J����i�߂邪�A���ɑ�^���d���ł͐��f����ʂ��c��B�v��̗����オ������ʂ��ɂ����A�����J����̓����y�[�X��Y�܂���B���{��������������Η͔R���Ƃ̒l����U�̎d�g�݂����ɂȂ肻�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2022/10�@]�@�@�� |
|
|
| �����ACO2�팸�����X�R�A�ʼn����g���^��Q�� ���́A�����҈�l�ЂƂ�̃A�N�V�����ŒE�Y�f�Љ�𐄐i���鋤�n�^�v���b�g�t�H�[���uEarth hacks�v�ɂ����āA���i�E�T�[�r�X��CO2e�iCO2�����ʂɊ��Z�����l�j�팸���������ł���}�[�N�u�f�J�{�X�R�A�v�̒��J�n����Ɣ��\�����B �uEarth hacks�v�͔��ƎO�䕨�Y�̋����v���W�F�N�g�BZ������͂��߂Ƃ���E�Y�f�ɊS�����郆�[�U�[��A�u�܂��悭�m��Ȃ��v�Ƃ������[�U�[�ɂ��E�Y�f�Ɍ�����������g�߂Ɋ����Ă��炦��悤�A�����҂̐������ƂɁA�E�Y�f�֘A���i�E�T�[�r�X�⎖�Ƃ̊J����ڎw�����n�^�̃v���b�g�t�H�[�����BCO2e��}�������i�̏Љ��]���i�Ɣ�r���č팸�ʂ���ڂŕ�����d�g�݂���Ă����B ����V���ɁA�X�E�F�[�f����Ƃ�CO2e�r�o�ʉ����c�[���Ȃǂ����p���A�uCO2e�팸���v���u�f�J�{�X�R�A�v�Ƃ��ĎZ�o�B��ƁE�c�̌����ɒ���Ƃ����B�g���^�A���{�q��AUCC�㓇����Ȃǂ��Q���A���p�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�͂܂��Â��HEU�͊����r���ɂ����z���`������ EU�̓��V�A�Y���ΔR������̒E�p�v��u���p���[EU�v�𐄐i���Ă���B�E���V�A�𑁋}�Ɏ���������EU�ɂƂ��āA�G�l���M�[�]���́u�v�����v���d�v���B ����ŁAEU�ɂ́u�E�Y�f�̂��߂ɂ͕ω������Ƃ�Ȃ��v�Ƃ����������ӂ����邽�߁A�ΒY�Ȃǂ̉��ΔR���ւ̉�A�͑I�����ɓ���Ȃ��B���{�Řb��ɏ�邱�Ƃ̑������q�͂��A�f�����g��Ƃ����_�ł͑��̃G�l���M�[���ɗ���Ă���B ���ǁA�u�E�Y�f�Ɛv���ȒE���V�A�v�𗼗�������I�����́A�ăG�l�ȊO�ɂ͂Ȃ��̂��B10�N�ȓ��Ƃ����g��Ȃ̂悤�ȃX�s�[�h�h�ōăG�l�ւ̃G�l���M�[�]����i�߂�B���̖ڋʂƂȂ����̂��A�����̏�ɐݒu���鉮�㑾�z�����d�ł���B �uEU�̓d�͂�25�����܂��Ȃ���\��������B�����̌����𗘗p���邽�߁A���㑾�z���͎��ӊ��ȂǂƂ̏Փ˂�����邱�Ƃ��ł���B������A���ɑf�����W�J�ł���v�B���B�ψ���́u���z���ւ̑��z�����d�̐ݒu�`�����v���A���p���[EU�Ɠ����ɒ�Ă��Ă���B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ���O�䕨�Y�̐V�T�[�r�X���i�ʂ�GHG�r�o�ʂ����� �O�䕨�Y�́A�T�X�e�i�u���o�c���i�@�\�Ƌ����J�������A���C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j��@�Ɋ�Â����i�P�ʉ������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʉ����v���b�g�t�H�[���uLCA Plus�v�̒��J�n�����Ɣ��\�����B ���v���b�g�t�H�[���́A���C�t�T�C�N���v�l�Ɋ�Â������i�̊��}�l�W�����g���\�Ƃ���ISO14040�AISO14044�Ɋ�Â��Z��@�\��L�������i�P�ʂ�GHG�r�o�ʂ�����������́B������Ƃ͎��А��i�̃��C�t�T�C�N����ʂ��Ĕr�o�����GHG�r�o�ʂ�e�ՂɎZ�肷�邱�Ƃ��ł��A�܂��T�v���C�`�F�[����GHG���̎��W�A���i�̔���ւ̕A���Г��ł�GHG�r�o�팸�Ɍ������V�~�����[�V������i���Ǘ��Ȃǂ��\�ƂȂ�B�Ȃ����v���b�g�t�H�[���͍������̎��g�݂Ƃ��Č��݁A�������o�肵�Ă���B�����ԃ��[�J�[�E����ރ��[�J�[�Ȃǖ�30�Ђ̊�ƂƎ��؎������s���A����̃v���b�g�t�H�[���������������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d������������CO2���t���E�A���g�}�g�͔|�� �d���J���ƒ����d�͂������Őݗ��������N�[���W�F���́A�����؉��A���{�t�Y�Ȃ�5�ЂƁA���d������������CO2���t���E�^�����A�g�}�g�����ł̗L�����p�̉\��������������J�n�����B ���N�[���W�F���́A�������萫�ɗD���ΒY�Η͂������ɂ킽���Ċ��p���Ă������߁A�ΒY�K�X���R���d�r�������d�iIGFC�j��CO2�����E�����g�ݍ��킹���v�V�I��Y�f�ΒY�Η͔��d�̎�����ڎw���Ă���B����̎��؎����́A����CO2�����E����^�ΒY�K�X���R���d�r�������d�������������t��CO2��A���E�L�����p������g�݁B �����؉��̃g�}�g�����ł́A����܂ł��������𑣂����߂�CO2�𗘗p���Ă����B ����̎��ł́A���N�[���W�F���ɂ����Ĕ�������CO2������E�t�����A���{�t�Y�������؉��̃g�}�g�����Ɉڑ�����B �o�T�u�܂��ǂȃj���[�X�v |
|
|
| ���ϐ����w�A�����㑾�z�d�r����̐V�w�ɐݒu�� �ϐ����w�́A�����{���q�S�����J�Ƃ�ڎw���u���߂����i���j�w�v�ɁA�t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r��A�ݒu����Ɣ��\�����B ���w�̍L�ꕔ���Ƀt�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r��ݒu�BJR�����{���́u�d�͗R��CO2�[���̉w�v�̎����Ɍ����āA�uJR WEST LABO�v�̃p�[�g�i�[�Ƃ��ċ��n����B �t�B�����^�y���u�X�J�C�g���z�d�r�́A�y�ʂŏ_��Ƃ��������������A�r���̕ǖʂ�ωd�̏����������A���邢�͎ԑ̂Ȃǂ̋ȖʂƂ������A���܂��܂ȏꏊ�ɐݒu���\���B�܂��A�h�z�Ȃǂɂ��A�����Y���\�ł��邱�ƁA���A���^����K�v�Ƃ��Ȃ����ƂȂǁA�����̃V���R�����z�d�r�̐��Y�ʂł̉ۑ�������������܂��Ƃ����B���Ђ́A�Ǝ��Z�p�ł���u���~�A�����A�ޗ��A�v���Z�X�Z�p�v�ɂ��A�ƊE�ɐ�삯�ĉ��O�ϋv��10�N�������m�F���A30cm���̃��[���E�c�[�E���[�������v���Z�X���\�z�����B����ɁA�������v���Z�X�ɂ�锭�d����15.0���ɐ������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����s�������ւ̑��z���ݒu�`�����ցA2024�N4���{�s�ڎw�� ���s�́A���s�s�A�����s�ɑ����A���z�����d�̌����ւ̐ݒu�`�����Ɏ��g�ށB���z���ւ̍Đ��\�G�l���M�[�ݔ��̐ݒu���`��������u�ăG�l�`���E�x�������i���Ƃ̑f�ẮA�����ʐ�2000m2�ȏ�̑�K�͌��z���̐V�z�E���z�ɑ���ݔ��ݒu�`���A��2000m2�����̒����K�͌��z���̐V�z�ɑ���ݔ��ݒu�`���A��10m2�ȏ�̐V�z�E���z���z���ɑ�������`����3��ނ̋`�����x����\�������B �`���Ώێ҂͌��z��B�`���ʂ́A�M�ʊ��Z��1�N�Ԃɉ����ʐς�m2���~20MJ�ȏ�ŁA45��MJ������Ƃ���B�����ʐ�2000m2�̏ꍇ��6��MJ�i��5.5kW�j�A1��5000m2�̏ꍇ�ŏ����45��MJ�i��41kW�j��z�肷��B �Ώېݔ��́A���z�����d�ݔ��A���z�M���p�ݔ��A�o�C�I�}�X���p�ݔ��A���͔��d�ݔ��ȂǁB2024�N4��1����ړr�Ɏ{�s����\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IEA�A2022�N�͐��E�̐ΒY����ʂ��ߋ��ō��̋L�^�ɕ��Ԃƕ� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A���E�̐ΒY����ʂ�2022�N�ɑ������A��10�N�O�̋L�^�I�Ȑ����ɖ߂錩���݂ł���Ƃ̕��\�����B ���݂̌o�ρE�s�ꓮ���Ɋ�Â��A�����o�ς��������ɉ���Ɖ��肵���ꍇ�A2022�N�̐��E�̐ΒY����ʂ�80���g���ɂȂ�Ɨ\������A����ɂ��2013�N�̔N�ԋL�^�ɕ��Ԃ��ƂƂȂ�B2023�N�̐ΒY���v�͂���ɑ������A�ߋ��ō����X�V����\���������B���E�̐ΒY���v�̑����ɂ́A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����V�R�K�X���i�̍����ɂ��A�����̍��ŃK�X����ΒY�ւ̓]�����i���Ƃ�A�C���h�̌o�ϐ�������^���Ă���B �����ƃC���h�����킹���ΒY����ʂ͐��E�̑��̒n��̍��v��2�{�ł���A���������Ő��E�̎��v�̔����ȏ���߂Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA���͔��d����̏d�v����� �A�����J�G�l���M�[�ȁiDOE�j�́A���͔��d���ߋ��ō��̐��Y�ʂ��L�^���A�ˑR�Ƃ��ē����ōł��}���ɐ������Ă���G�l���M�[����1�ł���A���̍����ٗp�ݏo�����̂ł��邱�Ƃ��������\�����B 2021�N�A���͔��d�͓����̃G�l���M�[�e�ʑ�����32%���߁A12���l�̌ٗp��n�o���A���݁A4,000�����тɓd�͂��������Ă���B�܂��A���͔��d�͑S�Ă̑��d�͗ʂ�9%�ȏ���߁A50%�ȏ���߂�B������A2021�N�A22�̏B���d�͎��ƋK�̗͂��㕗�̓^�[�r����V�K�ɐݒu�����B�����́u�C���t���}���@�v�ɂ́A����E�m��E���U�^���͂̓W�J���x����d�v�ȐŐ��D���[�u�̒��������ƁA����E�m�㕗�̗͂����ŏd�v�ƂȂ鍂�����d���̐ݒu�E���݂��x������V�����v���O�������܂܂�Ă���B �܂��A���͔��d�̕��i��ݔ��̍��������E�����ɑ���Ŋz�T�������荞�܂�Ă���A�����̋C��ϓ���E�Y�f���̖ڕW�B���ɏd�v�Ȗ������ʂ������͔��d�Y�Ƃɒ����I�Ȋm������^���A������̋}�������㉟������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���g�C���̐ߐ��Ɋւ���JIS�������o�Y�� �o�ώY�ƏȂ́A�g�C���̐ߐ��Ɋւ���JIS�����������B�g�C���̐��̐ߐ��ɂ��Ă͍��ۋK�i�����肳��Ă���B �����JIS�����́A�g�C���i���֊�j�̐�ʂɂ��āA�ߐ�����Ă���ꍇ�̋敪��A���̐��\������������@�̕W�����ɂ��Ă��B��ʂ̋敪�m�ɂ��A���̎������@�ꂷ�邱�ƂŁA�ߐ��^�̐��i��I������ڈ����ł���悤�ɂȂ�B����A����JIS�Ɋ�Â��C�O���ƋK�i�̊J�����͂Ȃǂɂ��A�䂪���̗D�ꂽ�ߐ����ʋy�щq�����𗼗��������i�̕��y�����i����A�Ђ��Ă͎����\�Ȑ����p�̐��E�v���Ɏ����邱�Ƃ����҂����Ƃ����B ��ȉ����_�́A�@���֊�̐ߐ��̓x������������ʋ敪�̐V�ݐ�ʂ��SL�ȉ��� I�`�A�y�т��ߐ����ʂ̍��� 2L�ȉ��� II�`�̂Q�敪��ݒ�B�A��ʂ������ő�������@��ɂ��āA��ʂ́A�ŏ����ʋy�эő吅�ʂ͈̔͂L����B���\�����͍ŏ����ʂŎ��{����B �o�T�u�o�ώY�Əȁv |
|
|
| �����B�[�i�E�G�i�W�[�A�O���[�����f����{�ɋ��� �ăG�l���Ƃ̃��B�[�i�E�G�i�W�[�i�V���K�|�[���j�́A�����Ƃ̊�ƂƃR���\�[�V�A����g�݁A���B�ŃO���[�����f���A���{�ɋ������鎖�Ƃɏ��o���B ���c���H�A�h�C�c�̑�茚�݉�ЂƃG���W�j�A�����O��Ђ��Q������B���B�[�i�����B�Ŕ��d��������ȍĐ��G�l���g���ċ����͂̂��鐅�f������A�����̓d�͉�ЂȂǂɈ���I�ɋ�������_�����B���B�ł̐��f��������o�ׂ܂ł̓��B�[�i�E�G�i�W�[���B�����{�B���̂قǘA�M���{����N���[�����f�̕⏕��300�����h�������B�܂���2024�N�܂łɎ��v�����g��ݒu���d�͊��Z��1���L�����b�g�����̐��f�����B�����ŏ����B����26-27�N���߂ǂɓ�10���L�����b�g�����������`���V�N���w�L�T���iMCH�j�Ȃǂ̐��f�L�����A�Ƃ��ē��{�ɗA���A�Η͔��d���ł̍��ėp�ɋ�������B�ŏI�I�ɂ�30�N��ɓ�45���L�����b�g���������A���{�̓d�͉�Ђ̐��f��R���d�ɋ�������l���B �o�T�u�����H�Ɓv |
|
|
| �������c�A�A�������p�㉟���K���s���������_�� �����}�́u�d�͈��苟�����i�c���A���v�i��E�דc���V�O�@�c���j�́A������ʼn���J���A���q�͔��d���̐V���݂��܂߁A�����̐ϋɓI�Ȋ��p�Ɍ����Đ��{���㉟�����邱�Ƃ��m�F�����B �o�Ȏ҂���́A�����̈��S�R�����s�����q�͋K���ψ�����͂��߂Ƃ���K���s���݂̍�����������ׂ����Ƃ̈ӌ����o���B��̖`���A�דc���́u�E�N���C�i��肪�������A�G�l���M�[���i���㏸���Ă���B�������~�����B�C���t���⋟���s���̌��O������B���S�����m�ۂ��Ȃ���d���̑��l����}�邱�Ƃ��d�v���v�Ƌ��������B�o�Ȏ҂���́A���q�͋K���ψ���ɂ��āu�ψ���̎w���̂��ƂɋƎ҂�����u���Ă���ɂ�������炸�A��ɂȂ��āw����ł͕s�����x�Ƃ����Ă�蒼���悤�Ȍ���͂������Ȃ��̂��v�u�K���s���Ɍg���l�ނ̈琬���K�v���v�u�K���s���݂̍���ɂ��āA�������ݍ��ނׂ����v�Ȃǂ̈ӌ����o���Ƃ����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ����Google���ˁA������̍ăG�l���B�u24/7�J�[�{���t���[�d�́v�ɂǂ��Ή����邩 ��Google���n�߂��ăG�l�d�͒��B�̐V��@�u24/7�J�[�{���t���[�d�́v�����E�Œ��ڂ𗁂юn�߂Ă���B �����Ԃœd�͂̎��v�Ƌ��������킹��T�O���u24/7CFE�v�ł���B�O�[�O����2020�N9���A2030�N�܂łɎ��Ў��Ƃ̓d�͂�24����365���A�J�[�{���t���[�ȓd�͂ɂ���Ɣ��\�����B24/7CFE�i�u24����365���v�Ɠ��`�j�́A���v�Ƃ̎{�ݒP�ʂŁA1���ԁi�܂���1���Ԃ��Z�����ԁj�P�ʂœd�͏���ʂ̎��уf�[�^�Ƌ����d�͗ʂ̎��уf�[�^����v�����邱�Ƃ��B �����č��A�́A�u24/7 Carbon Free EnergyCompact�v�Ƃ����C�j�V�A�e�B�u��2021�N9���Ɏn���������B2022�N8��10�����݂Ő��E������78�̑g�D���������Ă���B�O�[�O����}�C�N���\�t�g�A�č��A�M���{�̂悤�ɃJ�[�{���t���[����ڎw�����v�Ƃ����łȂ��A�G�l���M�[�������Ǝ҂�e�N�m���W�[��Ƃ��Q�����Ă���B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/9�@]�@�@�� |
|
|
| �����d����u���[���X�N���[���v�ALIXIL������ LIXIL�́A���z�r���̑��Ɍ�t���ݒu�ł���u���z�����d�iPV�j���[���X�N���[���V�X�e���v���J�����A4�����瓯�ЃI�t�B�X�r���ɂ����Ď��؎�����i�߂Ă���B ���[���X�N���[���̎���ʂɃt���L�V�u���ȑ��z�d�r�Z���i���d�f�q�j��z�u�����B�]���̃��[���X�N���[���Ɠ��l�Ɋ�������Ď��E���m�ۂł���B1��������̏o�͂�80.9W�i1.8m2�̃��[���X�N���[�����A���z�d�r�Z���ʐ�1.26m2�j�B�����r���̑��K���X�ɑ��p�����P�K���X�z����z�肵���ꍇ��54.5W�i1.22m2�̃��[���X�N���[�����A���z���Z���ʐ�0.84m2�j�A1m2���Z�ł�64.8W/m2�������B ���d�����d�͂́A�J�o�[�t���[�����̒~�d�r�֏[�d���AUSB�[�q����d�͂����o�����Ƃ��ł���B���d��~�d�A���[���X�N���[���̊J��Ԃ́AWi-Fi��ʂ��Ċm�F�ł���B�J����������R���ɉ����āA�p�\�R���Ȃǂ̒[������s����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��20��𒆐S�Ɏ��R�G�l���M�[�R���̓d�̓v�������p�҂������� �V�i�l���z�[���f�B���O�X���S����20��ȏ�̎Љ�l1,112�l��ΏۂɃC���^�[�l�b�g���������{�����Ƃ���A20��̔����߂�47.7�������R�G�l���M�[�R���̓d�̓v�����𗘗p���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���̂�����9���͒��߂�1�N�ȓ��ɓd�̓v�������ւ��Ă���B ���R�G�l���M�[�R���̓d�̓v�����𗘗p���Ă��銄����27.3���������B20��ɑ����Ċ��������������̂�30��ŁA������40��A60��ȏ�A50��̏��ł���B�ł��Ⴂ50��ł͖�13���ɂƂǂ܂�A20��Ƃ̍����傫���B�������u�d�̓v���������������ƂŁA�n�����g���̖h�~�ɍv���ł���Ȃ�A���ɂ₳�����d�̓v������I�т����Ǝv���܂����v�Ƃ����₢�ɑ��ẮA�ґS�̂�8���߂�79.1�����u�͂��v�Ɠ����Ă���B�v�����������̂�������������A���R�G�l���M�[�R���̓d�̓v������I������l��������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��IHI�A�t�̃A�����j�A100%��CO2�t���[���d�B��GHG99�����팸 IHI�́A2,000kW���K�X�^�[�r���ʼnt�̃A�����j�A�݂̂�R���Ƃ���uCO2�t���[���d�v���������A�R�Ď��ɔ������鉷�����ʃK�X�iGHG�j��99%�ȏ�팸���邱�Ƃɐ��������Ɣ��\�����B �t�̃A�����j�A�́A�V�R�K�X��A�����j�A�K�X�����R�Đ����Ⴍ�R���ɂ������߁A�A�����j�A���ė������߂��ہA����I�ȃA�����j�A�R�ĂƔr�C�K�X����GHG�̔r�o�}�����ۑ�ł������B����܂ł�70%���鍂���A�����j�A���ė��ł̉^�]���ɁA�������ʃK�X�̈���CO2�̖�300�{�̉������ʂ������_�����f(N2O)���������邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă����B ����A�V���ɊJ�������R�Ċ�𓋍ڂ��Ď��������{�B���̌��ʁA70�`100%�̍����A�����j�A���ė��ł��������ʃK�X�팸��99%�ȏ��B�����A�t�̃A�����j�A�݂̂̔R�Ă�2,000kW�̔��d���ł��邱�Ƃ��������Ƃ����B2025�N�̉t�̃A�����j�A100%�R�ăK�X�^�[�r�����p�����߂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���R���i�Łu��ڐG���^�b�`���X�v�ɕς��w�Z�g�C���c�����Ǒ�ő�����u��̎����������v TOTO�Ȃǃg�C���֘A6�Ђɂ�錤�������g�D�́u�w�Z�̃g�C��������v���A���̂قǁu�w�Z�̃g�C���Ɋւ���S�������̃A���P�[�g�����v�\�����B�w�Z�g�C���̉��C���Ɂu�����Ǒ�v�Ƃ��Ď��{���Ă��邱�Ƃ����Ƃ���A����2�N�Łu��̎����������v�Ɍ����ȐL�т�����ꂽ�Ƃ����B �u���֊�̎�����v�u�g�C���Ɩ��̎������v�Ƃ������u��ڐG���^�b�`���X�v�Ɋւ��鍀�ڂ��N�X�����X���ɂ���B���C���A�u�֊�̗m�����v�i90���j�A�u��̎����������v�i67%�j�A�u�����g�C���̊������v�i65���j�B���Ɂu��̎����������v�́A����2�N��32�|�C���g�������A�傫�ȐL�т�����ꂽ�B�܂��A����ȊO�ɂ���ڐG���^�b�`���X�Ɋւ��鍀�ڂ��N�X�����X���ɂ���Ƃ����A�u���֊�̎�����v�i50���j�A�u�g�C���Ɩ��̎������v�i45���j�ƂȂ��Ă���B����L���Ǝv������̂́A�u��̎����������v�i87%�j�A�u���֊�̎�����v�i69���j �o�T�u�܂��ǂȃj���[�X�v |
|
|
| ���o�Ώꏊ�ɉ����Đi���֎~��\����������U�������J���`�V�X�e���]�����擾 �|���H���X�A���Ń��C�e�b�N�A�z�[�`�L�́A�Ђ̔����ꏊ�ɉ����Ċ댯�Ȍo�H�ɐl���i�����Ȃ��悤�ȕ\�����s�������U�����������J�����A��ʍ��c�@�l���{���h�ݔ����S�Z���^�[�̃V�X�e���]�����擾�����B �{�V�X�e���́A�v�H�������É��s���ۓW����V��1�W���ِ������Ƃɏ��K�p�����B�{�V�X�e���́A���o�H��ʼnЂ����������ꍇ�ɁA�Ђɂ��g�p�ł��Ȃ��Ȃ������o�H��̔����U�����ɐi���֎~�i�~��j�̕\�������邱�ƂŁA�Џɉ��������S�Ȕ����֗U������V�X�e�����B ���K�͈ȏ�̌����ł́A�Ђ�ЊQ�̔������A�����ɂ���l�X�����₩�����S�ɔ��ł���悤�A�����̔��o�H���v�悳��Ă���B�{�V�X�e���ł́A�Џɉ��������\�ɂȂ�A�������p�҂̈��S�������コ����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���r���⏤�Ǝ{�݂̐ݔ��Ǘ��Ɩ���DX�x���N���E�h�^�r���Ǘ��V�X�e����V���� �_�C�L���́A�r���⏤�Ǝ{�݁A�H��A�w�Z�A�a�@�Ȃǂɂ�����ݔ��Ǘ��Ɩ��̕i������ƌ����̉��l������T�|�[�g����N���E�h�^�r���Ɩ��Ǘ��V�X�e���wDK-CONNECTBM�x�������B ��̓I�ɂ́A���͂��ߓd�C�␅���ȂǁA�ۗL����ݔ��@��̎�ނ�䐔�A���������A�}�ʂ�ݒu�ꏊ�A�ݔ��_���̌����v��◚���A�_����̕��Ȃǂ��N���E�h��ňꌳ�Ǘ����A���u����ł��f�[�^�̉{����쐬���\�ɂ���B���ɋ@�ɂ����Ă͈ꌳ�Ǘ��ł����L�x�ŁA���Ђ̃N���E�h�^�R���g���[���T�[�r�X�wDK-CONNECT�x��Ɩ��p�@�̃h�����p�����u�_���T�[�r�X�wKirei�E�H�b�`�x�ƘA�g���邱�ƂŁA�@�̉ғ���G���[���A�����e�i���X�̗����������Ŏ擾����B �o�T�u�_�C�L���v |
|
|
| ��������CO2�Z�x���قڃ��A���^�C���Ń��j�^�����O����Z���T�[ BB�\�t�g�T�[�r�X�́A������CO2�Z�x�E���x�E���x�ʼnƓd���Ǘ��ł���u�{Style�Z���T�[�iCO2�E�����x�j�v�Ƌ@�\���i�����ቿ�i���i�u�{Style�Z���T�[�i�����x�j�v��̔��J�n�����B �{Style�Z���T�[�iCO2�E�����x�j�́ACO2�Z�x���قڃ��A���^�C���Ń��j�^�����O���A�ɉ����ĉƓd���R���g���[�����邱�Ƃ��ł���B�����J���Ȑ�����NDIR�������̗p���Ă���A�����l��3�b���Ƃɕ\������ق��ACO2�Z�x��49999ppm�͈̔͂�4�i�K�ő��肵�A�ʒm����B�����x�Z���T�[�����ڂ��Ă���ACO2�Z�x�≷�x�E���x�ŋǗ����s�����Ƃ��\�B�덷�͉��x���}0.3���A���x���}3���ŁA�����l��3�b���Ƃɕ\������B�{Style�Z���T�[�iCO2�E�����x�j��1��5800�~�A�{Style�Z���T�[�i�����x�j��4,980�~�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�J�[�{���E�N���W�b�g�E���|�[�g�v�ƃJ�[�{���E�N���W�b�g�s��̎��؎��ƂɌW�鐧�x���q�����\ �u�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ������J�[�{���E�N���W�b�g�̓K�Ȋ��p�̂��߂̊������Ɋւ��錟����v�́A�J�[�{���E�N���W�b�g�̊��p�Ɋւ��Ċ�{�ƂȂ���⍡��̂�����������u�J�[�{���E�N���W�b�g�E���|�[�g�v�����\�����B �{������Ɋ֘A���Čo�ώY�ƏȂ����{����J�[�{���E�N���W�b�g�̎s�����Ɋւ�����؎��Ƃɂ��āA�ϑ���ł��铌���،���������A���x���q�̌��\�y�ю��؎Q���҂̉�����J�n�����B �o�T�u�o�ώY�Əȁv |
|
|
| �����w�r���̃G���x�[�^�[��~�d�V�X�e���Ƃ��Ďg���Z�p�A�d�͂��ʒu�G�l���M�[�ɕϊ� �I�[�X�g���A�̌����@��IIASA�́A���w�r���̃G���x�[�^�[��~�d�V�X�e���Ƃ��Ċ��p����Z�p�iLEST�j���l�Ă����B�g�p���Ă��Ȃ���Ԃ̃G���x�[�^�[���r���̏㕔�ֈړ������邱�ƂŁA�d�C�G�l���M�[���ʒu�G�l���M�[�ɕϊ����Ē~����d�g�݂��B �G���x�[�^�[��g�����d�_���̂悤�Ɏg���A�d�͂��]���Ă��鎞�ɒ~�d�A����Ȃ����ɕ��d���悤�Ƃ����A�C�f�A���ALEST�ł���B�o�b�e���[�Ƃ��Ďg���G���x�[�^�[�́g�����h�ɂ́A���ʂ𑝂₷���߂̏d����ڂ��Ă����B�����āA�~�d����ɂ́A��������w�K�ֈړ������邱�ƂŁA�ʒu�G�l���M�[�𑝂₷�B�t�ɁA���d����ɂ́A�������~�낷�ۂɉu���[�L�Ŕ��d����B�Ȃ��A�d��������I�ɍڂ�����A��������~�낵����ł���悤�A���u����ňړ����鑕�u�̗��p����Ă��Ă���B�u���[�L�Ȃǂ̗��p�ŁA�lj��R�X�g���������Ȃ��B �o�T�uCNETJapan�v |
|
|
| ���ĘA�M�ō��فA���d���̔r�o�K���F�߂��^��ĒT���}���� �ĘA�M�ō��ق́A���d���ɂ������_���Y�f�iCO2�j�̔r�o������A�A�M���{�ɂ��K����F�߂Ȃ����f���������B �ΒY�Y�n�̃E�F�X�g�o�[�W�j�A�B�̎i�@�����炪�����ƂȂ�A���d���̔r�o�𐧌����錠�����Ċ��ی�ǁiEPA�j�ɂ͂Ȃ��Ƒi���Ă����B�o�C�f���������f����r�o�팸�̒����ڕW�l�́A���d���ɂ�����팸��D�荞��Őݒ肵�Ă���B���̂��ߌ��n�́u�o�C�f���́A�r�o�팸�̕ʂ̕��@��������K�v������v�ȂǂƓ`���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���č��A�B�ʁE�ƒ�̃G�l���M�[�����f�[�^�����J �č�EIA�́A�B���ƂɏZ��̃G�l���M�[������̃f�[�^�����߂Č��\�����B���悻1��2350�����т�ΏۂɂƂ��āA2020�N�㔼����2021�N�O���܂łɎ��W���ꂽ�B �f�[�^�́A�ƒ�ɂ������g�[�A�����A�Ɠd�A�d�q�@�퓙�̃G�l���M�[�g�p�������Ă���A�G�l���M�[�������č��̏B���Ƃɂǂ̂悤�ɈقȂ邩�͂��邽�߂Ɋ��p���ꂽ�B���͓��e�́A 1.�G�A�R���͑S��88%�̉ƒ�Ŏg�p����Ă��邪�A��ނ͏B�ɂ���ĈقȂ�B�t�����_�ł̓G�A�R���g�p�҂�90%����������C���a���u���g�p�B�j���[���[�N�ł͔����ȏ��61%���NJ|���G�A�R���ݔ����g�p���Ă���B 2.�č��̃I�[���d���Z��̔䗦�́A�B�ɂ���đ傫���قȂ�B�S�̂��݂��26%���x�����A�t�����_�ƃn���C�ł͂��ꂼ��77%��72%�ƍł������������B�J���t�H���j�A�ł̓I�[���d������8%���x�ŁA�s����75%�������ɓV�R�K�X���g���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���̍��ۃ��[���`���c�_�C�L���͏ȃG�l�s��̎哱��������邩 �_�C�L���H�Ƃ��̓d�͏���Ɨ�}���K������K�i���̍��ۃ��[���������[�h���A�ȃG�l���M�[�Ɖ��g���h�~�̎Љ�ۑ�����ɒ���ł���B 2025�N�x�܂ł̒����v��ł̓��[�����ɂ��u�s�ꉿ�l�`���v��ł��o�����B�����ǎ҂�w�p�@�ւȂǂƂ̃p�C�v���������A���E�̋ő��Ƃ��ċK���ւ̊֗^��}��B���{��Ƃ͊��֘A�̃��[���ŋ�t���Ȃ߂Ă������A�ł͎哱���������̂��B 2023�N�ɓ��{�ŊJ�����f�V��]��c���@��ɁA���Ƒ��k���A�������ʃK�X�팸�v���ʂ̃��[�����Ɋ֗^���Ă��������ӌ��B �_�C�L���ɂƂ�A���ۃ��[���͎������B���B�ł͂O�T�N�ɗ�}�̑�փt�����֎~�@�Ă���o����A���S�̊�@�ɗ������ꂽ�B�K���̃��r�[�����Ŕp�ĂƂȂ������A���[�����ɐ[���肷�錴�̌��ƂȂ����B ���ꂩ�甽���ɓ]���A�Đ��\�G�l�g�p���i�w�߂̉���������A�����ɓ������J�����A������̕W���Ƃ��ă��[���`����}���Ă����B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���u�i�m���́v�����p���ցA���a�R���T���^���c�Ȃ� ���a�R���T���^���c�A���v���A���R�[��3�Ђ́A�_�Ɨp�̐����{�݂𗘗p�������o�͂̔��d���u�u�i�m���͔��d���u�v�̌����J�����J�n�����B�S���̔_���n��ł̓����𑣐i����ƂƂ��ɁA�_�R�����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iVEMS�j�̑���������ڎw���B �����Ƃł́A����܂Œ�o�͂̂��ߖ����p�������_�Ɨp���H�����H�i����1.0m�j��_�Ɨp�p�C�v���C���������i���a150mm�ȉ��j�Ŕ��d�ł���i�m���͔��d���u���J������B�S���̔_���n��ɂ����čL���n��Z����_�Ƃ����琅�͔��d���s�����Ƃ��\�ɂȂ�B �_�Ɨp���H�����H�𗘗p���鑕�u������0.15m3/s�A����1.0m�ŏo��500W�B�_�Ɨp�p�C�v���C���������𗘗p���鑕�u������20L/s�ōő�o��1kW�A����18.5L/s�Œ�i�o��800W�A����15L/s�ōŒ�o��400W�B���d�d�͂Ŕ_�Ɨp�r�j�[���n�E�X�A�b�Q�d�C��A�X�}�[�g�_�Ƌ@��̓d���ɗ��p����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��NITE�A�u�X�}�[�g�ۈ��Z�p�v�����J�A��1����IoT�Z���T�[ �Ɨ��s���@�l�E���i�]���Z�p��Ջ@�\�iNITE�j�́A�d�C�ݔ��̒���_����ُ�L���̊m�F�Ȃǂ��������E���x���ł���u�X�}�[�g�ۈ��Z�p�J�^���O�i�d�C�ۈ��j�v���쐬���A���J�����B �d�C�ۈ��̕���ł́A���v�ݔ��̍��o�N��d�C�ۈ��l�ނ̍���E�l�ޕs���A�䕗�⎩�R�ЊQ�ȂǁA���܂��܂ȉۑ������Ă���B���������ۑ�̉����Ɍ����āAIoT�i���m�̃C���^�[�l�b�g�j��AI�i�l�H�m�\�j�A�h���[���i���l���^��s�́j�Ȃǂ̐V���ȋZ�p�����ɂ��ۈ����x���̈ێ��E����ƕۈ��Ɩ��̌������𗼗�����u�X�}�[�g�ۈ��v�̕��y�E���i���}���ƂȂ��Ă���B �X�}�[�g�ۈ��v�����[�V�����ψ���́A�\���̂������Z�p�v���̑���E�������E�o�ϐ��Ȃǂ�]�����A�u�X�}�[�g�ۈ��Z�p�v�Ƃ��đÓ��Ɣ��f�����Z�p�J�^���O�Ɍf�ڂ���B����A��1���Č��Ƃ��āu�����≏�ݔ��̏펞�Ď��i�Z�p�敪�FIoT�Z���T�[�j�v���Z�p�J�^���O�Ɍf�ڂ����B |
|
|
| ���@�@[�@2022/8�@]�@�@�� |
|
|
| �����{���̍��w���ؑ��ωΌ��z���uPortPlusR�v�i������^���C�{�݁j������ ��ёg�͌��C�{�݂Ƃ��āA�S�Ă̒n��\�����ނ�؍ނƂ������w���ؑ��ωΌ��z�������݂����B ���͌������ɂ��CO2���z�����Ă��邽�߁A���z���ւ̖؍ޗ��p�́ACO2���ԌŒ肷�邱�ƂŒE�Y�f�Љ�̎����ɍv�����邾���łȂ��A�u�g���E�A����E��Ă�v�Ƃ����T�[�L�����[�G�R�m�~�[�i�z�^�o�ρj�̊ϓ_��������ڂ���Ă���B �����́A1,990m3�̖؍ނ��g�p�A����ɂ���1,652t��CO2���ԁA����I�ɌŒ肷�邱�Ƃ��ł���B����ɁA�ޗ����삩�猚�݁A��́E�p���܂ł̃��C�t�T�C�N���S�̂ł́A�S�����Ɣ�ׂāA��1,700t�i��40���j��CO2�팸���ʂ�����B �؍ނ̑ωΐ��⍂�w���ɂ��ϐk���ւ̉ۑ�ɑ��A3���ԑω����������\���ނ�A�S������RC���ƕς��Ȃ����x�E�������m�ۂ��邽�߂̐ڍ��@�ȂǁA�Ǝ��̊J���Z�p���̗p�����B�����ʐρF3,502.87m2�A�K�́F�n��1�K�A�n��11�K�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���ƒ�p������ɂ����Đ��E�ŏ��߂Đ��f100%�R�Ă̋Z�p�J���ɐ��� �����i�C�́A�ƒ�p������ɂ����Đ��E�ŏ��߂Đ��f100%�R�ċZ�p�̊J���ɐ��������B�ۑ�Ƃ���Ă����u�����̊댯���v�u�s����ȔR�āv�ɑ��āA�����~�ς��Ă����R�ċZ�p�◬�̐���Z�p����g���Ă��̖����N���A���A����J���ɐ��������B CO2�r�o�팸�̎��g�݂̒��ŁA�g�p���ɔr�o�����CO2��95%�ƈ��|�I�ɑ����ACO2��r�o���Ȃ����i���J�����邱�Ƃ���ƂƂ��đ傫�ȖڕW�ƂȂ��Ă����B�����ŁA���f�G�l���M�[��R�Ă��邱�Ƃł�������������̊J����i�߂Ă����B �R�ċZ�p���C�E�R���Ƃ������C�̂��R���g���[������Z�p�����p�����Ă����Ƃ����o�����������A����̐��f100%������̊J���ւƌq����ꂽ�B���̋Z�p�́A�g�p��������茵�����ƒ���̗p�r�Ŏ��������B�I�[�X�g�����A�ł́A���f100%���ƒ�p�G�l���M�[�Ƃ��ė��p���邽�߂̏����i�K�ɓ����Ă���A�����i�C�͂��̎������̂��߂�2022�N�����납����؎������X�^�[�g����\�肾�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���G�A�E�E�H�[�^�[�^���^CO2����E�h���C�A�C�X�������u�J�� ���Ђ́A�{�C����H�ƘF���̔R�Ĕr�K�X��z�肵����Z�x��CO2�i�R�Ĕr�K�X��CO2�Z�x��10%���x�j���������ɉ���ł��鑕�u���J�������B �܂��A2022�N 4�������{�C���ԕ�H��ɖ{���u��ݒu�A�o�C�I�}�X���d���̔R�Ĕr�K�X����CO2��99%���x������A����������Ƀh���C�A�C�X���A���鎖�Ǝ����s�����B ���N�|���Ă����K�X�����E�G���W�j�A�����O�Z�p��Y�_�K�X�E�h���C�A�C�X���[�J�[�Ƃ��Ă̒m�����������ACO2��������A�L�����p�iCCUS�j���邽�߂̋Z�p�J���ɒ��́B�����������A�Ǝ��̋z�������Z�p��p����CO2������u���J�������B�{���u�́A�{�C����H�ƘF���̔R�Ĕr�K�X�ɓK�p�����v�ƂȂ��Ă��āACO2�Z�x10�����x�̔R�Ĕr�K�X���� CO2���������ɉ�����邱�Ƃ��\���B�܂��A�{���u�ł̓h���C�A�C�X�����@�\�����A�������CO2�������Ƃ��ăh���C�A�C�X�����邱�Ƃ��ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���V�d�͂̌_���~�E�P�ނ��}���A�u�t����v�����ł����^�鍑�c�a �|�Y�E�p�ƁA�d�͎��Ƃ̓P�ށA�_���~�i�ꕔ�V�K�\�����ݒ�~���܂ށj�ɒǂ����܂ꂽ�V�d�͂��Q�J���ԂłR�{���ɋ}���������Ƃ��A�鍑�f�[�^�o���N�̒����ŕ��������B ��N4�����_�̓o�^�����d�C���Ǝ�706�Ђ̂����A6��8�����_��104�Ёi��15���j�ɒB����B3��30���̑O���ł�31�Ђ������B�����i�����ȂǂŖc��d�͂̒��B�R�X�g��̔����i�ɏ\���]�łł��Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���B �鍑�f�[�^�o���N�����\����104�Ђ̂����A�|�Y�E�p�Ƃ�19�ЁA�P�ނ�16�ЁA�_���~��69�ЁB�O������V����IS�G�i�W�[�A�v���O���X�G�i�W�[�A�S��G�l���M�[�Ȃ�4�Ђ̓|�Y�����������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����h�b�N�X�t���[�d�r�A�Q�O�Q�T�N�x�܂łɔ��㍂�P�O�O���~�^�Z�F�d�H �Z�F�d�C�H�Ƃ́A���h�b�N�X�t���[�iRF�j�d�r�̔��㍂��2025�N�x�܂ł�100�O���~�ֈ����グ��B 2021�N�x���т����6�{�̋K�͂ɂȂ�Ƃ݂���B���E�I�ȍĐ��\�G�l���M�[�̓����g��ɔ����A�d�͂̎��������p�Ƃ��Ď��v�����܂�ƌ�����ł���B�č��𒆐S�ɊC�O�Ń}�C�N���O���b�h�����Ȃǂ̎��v���J��B�l�X�ȗp�r�Ɋ��p�ł���u���p�r�v��ɁA�����O�Ŕ̔���L���헪���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������A���X�s�ʼnc�_�^���z���A�C�`�S��T�c�}�C���A�z�E�����\�E ���������g����t�́A�����N���u�Ƌ����^�c�����t�����X�s�̔_��u�����N���u�E���ƕ��̃t�@�[���v�ɁA�\�[���[�V�F�A�����O�i�c�_�^���z�����d���j��ݒu�����d���J�n�����B 45m�~22.5m�̕~�n�ɑ��z���p�l����208���ݒu�B���z���p�l���̏o�͂�71.76kW�A�A�n�o�͂�49.5kW�B�N�Ԕ��d�ʂ�7��4665kWh�̌����݁B ���z���p�l���̓l�N�X�g�G�i�W�[���A�p���[�R���f�B�V���i�[�̓I�����������̗p�����BPCS�̈ꕔ�i9��̂���1��j�͎����^�]�@�\������A��d���Ɍg�ѓd�b�̏[�d�Ȃǔ��d���Ƃ��Ēn��Z���ɒł���B ���d�����d�͂́AFIT�Ő����N���u�G�i�W�[�֑S�ʔ��d���A�����N���u��������ɓd�͂���������B���d�P����15.4�~/kWh�B���z���p�l���̍����͒n��378.3cm�A�c�_��Ԃ͒n��280cm�A�Ռ����͖�30���B�p�l�����ł͍���3�N�ԁA���H�p�C�`�S�A�T�c�}�C���A�z�E�����\�E����t������v��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O��Ζ��J���Ɠ��dRP�^�n���̍�����̂���M��������A�V�^�n�M���d�ŘA�g �O��Ζ��J���Ɠ����d�̓��j���[�A�u���p���[�́A��Ɋ֓��n���ΏۂƂ����A�V���ȔM����Z�p��K�p�����n�M���d���Ƃ������������邱�Ƃō��ӂ����Ɣ��\�����B �V�Z�p�́A�n���̍�����̑w�Ɉ�˂̃��[�v���`�����A�n�ォ�琅�Ȃǂ��z�����邱�ƂŒn���̔M�݂̂�������Ĕ��d�ɗ��p����B�]�����獑���O�Ŏ��،�������Ă���u������̔��d�v�ł́A�����ō�����̑w��j�ӂ��Đ���ʂ����A�V�Z�p�ł͎O��Ζ��J�����V�F�[���K�X��V�F�[���I�C���̍̌@�ɗp���Ă��鐅���@��̋Z�p�����p����B �]���^�n�M���d�ł͒n���̕K�v�����ƂȂ��Ă��铧�����i���̒ʂ蓹�ƂȂ�T�����j��K�v�Ƃ��Ȃ����߁A�T����Փx�������A�������Ԃ���ъJ���܂ł̃��[�h�^�C����Z�k�ł���B ����A���N�Ԃ����Ē����Ώی��n���I�肵�A�������2025�N�ɂ��������肵�đ����̎��p����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���č��ݐ�65GW�̑��z�����ғ��ցA����x���ƃR�X�g�ቺ�ʼn��� �č��G�l���M�[�ȁiDOE�j�E�G�l���M�[���ǁiEIA�j�́A���̉āA���z���ƕ��͂��č��̂��傫�Ȕ��d���ɂȂ�Ƃ����\���\�����B 2022�N�Ă̔��d�ʂ́A��N�Ă��1000��MWh�������A���͔��d��800��MWh��������Ɨ\������Ă���B �ăG�l�Ƌt�ɁA�ΒY�Η͂ƓV�R�K�X�Η͂̔��d�ʂ́A���N�̉Ă�2600��MWh��������Ɨ\������Ă���B�V�R�K�X���i�̏㏸�ƐΒY�Η͂̔p�F�ɂ��B���N�A65GW�̑��z�����d���ғ����A��N�ɔ�ׂ�31�����ɂȂ�B���͂͑O�N���12������138GW�ɒB����Ƃ����B�A�M���{�ɂ�鐶�Y����ѓ����Ŋz�T���̂ق��A�B���x���ŃN���[���G�l���M�[�]����B������ł��d�v�Ȑ����1�ł���ăG�l�E�|�[�g�t�H���I��A�����ĕ��́E���z�����d�̌��ݔ�̒ቺ�ɂ��A�č��ł́A�ăG�l�ݔ��̐V�݂������Ŕ��d�ʂ��������Ă���B���N�̉Ăɂ́A�ăG�l���d�̃V�F�A��11.1���ɑ�������Ɨ\������Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���g�p�ςݑ��z���p�l�����Ď��������ȁA�`���t������ ���Ȃ́A�g�p�ςݑ��z���p�l���̃��T�C�N�����`�������錟���ɓ������B2011�N�̓����{��k�Ќ�Ɋe�n�ōL�������p�l�����������}���đ�ʂɔr�o�����2030�N��㔼���������A�K�ȏ������x������̂��_���B ���{��2050�N�E�Y�f�Љ�̎������f���Ă���A���z�����d�̓����g�傪�����܂��B�K�ɏ�������Ȃ���A���ߗ��ď�����̕N���ɂȂ���Ƃ̌��O���w�i�ɂ���B���݃��T�C�N���@���������đΏەi�ڂɒlj����A��̋Ǝ҂ȂǂɍĎ����������߂�Ă����ɐ��x�v��i�߂�B���z���p�l���ɓ��������V�@���������ɓ����B�@�Ă�2024�N�̒ʏ퍑��ɂ���o�������l�����B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���ߘa4�N�Łu�������v�̃|�C���g��������� ���Ȃ́A�ߘa4�N�Ŋ������E�z�^�Љ���E�������l�����������\���A���̃|�C���g���Љ���B3�̔����́A�����̑S�̑�����₷���������߂ɕҏW���A1�̔����Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă���B ���ł́u�O���[���Љ�̎����Ɍ����ĕς��鎄�����̒n��ƃ��C�t�X�^�C���`�������̕ϊv����N�����E�Y�f�h�~�m�`�v���e�[�}�ɁA�E�Y�f�A�����z�A���U�E���R�����Ƃ������p�I�ȃA�v���[�`�ɂ���ăO���[���Љ�̎�����ڎw�����Ƃ��L���`������e�ƂȂ��Ă���B�C��ϓ��⎑���̑�ʏ���A�������l���̑������̊�@�ɑ��āA��@�I�𐢊E�S�̂ŏ��z���邽�߂̍��ۓ������Љ�A�n�掑�������ĒE�Y�f����}��A�o�ϊ������E�Љ�ۑ�̉�����ڎw���n��Â����A�u�t�@�b�V�����E�H�E�Z�܂��E�ړ��v�����l�ЂƂ�̃��C�t�X�^�C���̕ϊv�ɂ��A�����\�ŏ������オ�A��]�������Ƃ��ł���Љ�������p���邱�Ƃ�ڎw�����Ƃ��L�q���Ă���B �o�T�u���W����v |
|
|
| �����ׂĂ̐V�z�̌����ɏȃG�l����`���Â�������@������ �E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����ďZ��̏ȃG�l����i�߂邽�߁A2025�N�x�ȍ~�A���ׂĂ̐V�z�̌����ɒf�M���\�Ȃǂ̏ȃG�l��������Ƃ��`���Â���������e�荞�@�������������B ����̉����@�́A�����̗�g�[�ɔ����d�͂�K�X�Ȃǂ̃G�l���M�[�g�p�ʂ����炷���Ƃ��ړI���B���̂��߁A����܂ŃI�t�B�X�r���ȂLjꕔ�̌�����Ώۂɒ�߂Ă����ȃG�l�̊�ɂ��Ĕ͈͂��g�債�A2025�N�x�ȍ~�A�Z����܂ށA���ׂĂ̐V�z�̌����Ŋ�������Ƃ��`���Â��Ă���B ��̓I�ɂ́A�V�z�̏Z���A���K�͂ȃI�t�B�X�r�����ȃG�l���\�����߂邽�߁A�f�M�ނ̌�����̍\���Ȃǂ̊�������Ƃ����߂���B�܂��A�����̏Z��ŏȃG�l��̍H�����s���ꍇ�ɗ��p�ł���A�Z����Z�x���@�\�ɂ�������̗Z�����x���V���ɐ݂���B �o�T�uImpress�v |
|
|
| ���ߓd�����ƒ���ƂɃ|�C���g�Ҍ����{�A���x�̌����J�n ���{�́A�d�͗����̏㏸�̕��S���y�����邽�߁A�ߓd�������ƒ���ƂɃ|�C���g���Ҍ����鐧�x�����錟�����n�߂��B�d�͉�Ђ��A�v���Ȃǂ��g���Ċ��Ɏ��{���Ă���Ҍ����x�𗘗p�B�O�N���ߓd�����ƒ�ȂǂɃ|�C���g���Ҍ����邱�Ƃ�z�肵�Ă���B ���{�́A7�N�Ԃ�ɉƒ���Ƃɑ��Đߓd��v���B�ƒ�ł̎�����28�x�ɂ��邱�ƂȂǂ��Ăт������B���{���ߓd�|�C���g�Ҍ����x�̓�������������̂́A�d�͎����N���ɂ���K�͒�d���N�����˂Ȃ��Ƃ�����@�����炾�B�x�~���̉Η͔��d���ĊJ�ȂNj����T�C�h�̑���}�����A�܂��͎��v�ʂ��瓭�������Ď����������߂�_��������B ���{�͐ߓd��v���������A���l�ڕW�͎����Ă��炸�A�|�C���g�Ҍ����x�̓����Őߓd�ւ̃C���Z���e�B�u�i���@�t���j�����߂�ƂƂ��ɁA�d�C�����l�グ�Ȃǂ̕�������ɂ��Ȃ���_��������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���g�E�b�h�V���b�N�h�̓�̕����A�o�C�I�}�X���d�R���u�؎��y���b�g�v�A���}���Ō��O �o�C�I�}�X���d�̔R���ƂȂ�؎��y���b�g�i�Ō`�R���j�̗A�����}�����Ă���B2021�N�͑O�N��53.7������312���g�����A������A�����̃o�C�I�}�X���d���Ŏg��ꂽ�B��^���d���̌��݃��b�V�����T���Ă���A����������錩�ʂ��B�����ɖL�x�ȐX�ю���������Ȃ���C�O�ɔR�����ˑ�����\�}�ɁA�؍މ��i�����ˏオ�����g�E�b�h�V���b�N�h�̓�̕����x�����鐺���o�Ă���B �؎��y���b�g�͗A���z�����������B�����Ȗf�Փ��v�ɂ��ƁA2021�N�̗A���z�͓�67.9������617���~�B�C�O����̗A���ł͂Ȃ��A�����Y�̖؍ނ𗘗p���Ă�����A���z�������̊e�n��Ɏx����ꂽ�v�Z�ɂȂ�B ��^�̔��d���ɂȂ�ƍ����̋����̐��ł͔R���̖؍ނ�d�����A�C�O���B�ɗ����Ă���B�������C�O�Ɉˑ����郊�X�N����������ƂȂ��Ă���B�o�C�I�}�X���d�����g����ɍv�����邽�߂ɁA�ыƂ̐U�����܂߂����Y�R���̋����Ԃ̐������K�v���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| �����E�����[�h����J���t�H���j�A�̌��z�E�Y�f����^���z�����d�{�~�d�r�ݒu�`���̐i�W �J���t�H���j�A�B���E�Y�f�Ɍ����āA�܂����������������������B�J���t�H���j�A�B�́A����2019�N�̌��z�ȃG�l���M�[������ŁA�S�Ă̒�w�Z��ɑ��A�V�z���ɑ��z���V�X�e���̓��������߂邱�Ƃ��߁A2020�N1��1������{�s���Ă���B ���z��̉�����3�N���Ƃɍs���Ă��邪�A��N���肳�ꂽ2022�N�����ł́A���z�����d�����`���́A��w�Z����łȂ��A�قڑS�Ă̔�Z��z���A��w�ȊO�̏W���Z��Ɋg�傳�ꂽ�B����̉���ł́A����ɁA�~�d�r�̓����`����A�d�C�q�[�g�|���v�@�퓱���̋`���E����A�����āu�I�[���d�����f�B�v�i�K�X�@����g���ꍇ�ɂ́A���ł��d�����ł���悤�ɔz�����̓d�C�ݔ��𐮂��Ă����j�`���������A�I���T�C�g�̎��R�G�l���M�[���ő���Ɋ��p���A�K�X���g��Ȃ��I�[���d���փX�e�b�v�ݏo�����B ���̉����͐V�E���E���z���z����Ώۂ�2023�N1��1������{�s�����B �o�T�u���R�G�l���M�[���c�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/7�@]�@�@�� |
|
|
| �����}�s���Y�A��ʂʼnc�_�^���z�����d�̎��؎{�݊J���A�G�N�V�I�O���[�v�ƘA�g ���}�s���Y�́A�G�N�V�I�O���[�v�Ƌ��ɍ�ʌ������R�s�ɂă\�[���[�V�F�A�i�c�_�^���z�����d�j�𒆐S�Ƃ����Đ��\�G�l���M�[�̎��؎{�݁u���G�l�\�[���[�t�@�[�������R�v�����݂���Ɣ��\�����B ���̎{�݂ł́A�\�[���[�V�F�A���؎����G���A�Ɛ����E�Z�p�W���G���A��2�J���Ńv���b�g�t�H�[�������B������̑��z�����d���ƂƔ��d�X�L�[���̌��ȂǁA�������S���ăG�l���ƂƔ_�Ƃ̎��؎����v���b�g�t�H�[���𓌋}�s���Y�����A�Q���^���؎{�݂Ƃ��Ă��܂��܂ȊW�҂Ƌ�������B �c�_�ɂ��Ă͉c�_�҂Ƌ��͂��A�āA�l�Q�A�u���[�x���[�A�}���Ȃǂ��͔|����B���g�݂̊J�n��2022�N6����\�肵�Ă���B ���z�����d���̔��d�o�͂�DC378.78kW�AAC249kW�B2022�N12���̉ғ��J�n��ڎw���B�앨�̎��n�̌��┭�d���̌��w�����A�d�C�̊��p���@�ȂǂL���������Ă��炤���߂̓W���Ȃǒn�拤���^�ăG�l�{�݂̊J�Ƃ�\�肵�Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���V�d�͂�2021�N���Z�A�Ԏ�������������u�傫�Ȋ�H�Ɂv�������H���T�[�` �������H���T�[�`�́A�V�d�͐�Ɗ��212�Ђɂ��āA2021�N�̋Ɛѓ������������ʂ\�����B �ŐV�̌��Z��3���A����r���\��137�Ђ̔��㍂�̍��v�́A2021�N����1��8,699���~�ŁA�O����2,348���~���A14.3�����Ƒ����������B����A�������v�̍��v��593���~�̐Ԏ��ŁA�O���i326���~�̍����j����啝�ɗ������݁A�Ԏ��ɓ]�������B 2021�N1���ȍ~�̓d�͎����Ђ����ŁA���B���i�̍������e���A���v�������������ƕ��͂��Ă���B�ŐV�̑��v����������181�Ђ̂����A�Ԏ���102�Ђ�6���ɔ������B���O�̔��d�{�݂�Œ艿�i�̒��B����������AJPEX�ւ̎���ˑ��x�������V�d�͂قǎ��Ɗ����������A���v�m�ۂ���������B ���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ȂǂŃG�l���M�[���i�̍����������Ȃ��A���Ɗ��̈����͔�����ꂸ�A�V�d�͋ƊE�͓������X�N�����܂�A�傫�Ȋ�H�ɗ�������Ă���v�ƌx����炵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���uYahoo! MAP�v�ɐV�@�\EV�[�d�X�|�b�g�̕\���J�n ���t�[�́A�uYahoo!MAP�v�iiOS�ŁAAndroid�Łj�ɂ����āA�S���ɖ�2���J������d�C�����ԁiEV�j�p�̏[�d���������[�d�X�|�b�g�̏ꏊ��[�d�����Ȃǂ��m�F�ł���uEV�[�d�X�|�b�g�}�b�v�v�@�\�̒��J�n�����B ���@�\�ɂ��A���[�U�[�́A�uYahoo!MAP�v���N�����āuEV�[�d�X�|�b�g�}�b�v�v���^�b�v���邾���ŁAEV�[�d�X�|�b�g�̏ꏊ��[�d�^�C�v��n�}��Ŋm�F�ł���ق��A�ڍׂ�m�肽���[�d�X�|�b�g��I������ƁA�[�d������c�Ǝ��Ԃɉ����A�[�d���ɕK�v�Ȓ��ԗ����A���O�A���̕K�v�L���Ȃǂ̏�m�F�ł���B �܂��A���Ђ�����J�[�i�r�A�v���uYahoo!�J�[�i�r�v�ɂ����Ă��A�ړI�n������ʂŁuEV�[�d�X�|�b�g�v��uEV�[�d��v�Ȃǂƌ�������ƁAEV�[�d�X�|�b�g�̏ꏊ�◿���Ȃǂ̏����m�F�ł���悤�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���I�������A�ƊE���u����v�ʐ��x�v�Ή��Y�ƌ������z�����d�p�p���R������ �I��������6����{����A2022�N4���{�s�́u����v�ʐ��x�v�ɑΉ������Y�ƌ������z�����d�p�p���[�R���f�B�V���i�uKPW-A-2-M�v�̔������J�n����Ɣ��\�����B �ߔN�APPA�i�d�͔̔��_��j�Ȃǂ̐V���ȓd�̓r�W�l�X���f���ɂ�鑾�z�����d�ݔ��̓������i��ł���B2022�N4���ɂ́APPA�r�W�l�X�ւ̕��y�𑣂��ړI�ŁA���̏����������ꍇ�ɃX�}�[�g���[�^�[�Ȃǂ̓d�͌v���@��̎�t�`����Ə�����@����i����v�ʐ��x�̐V�݁j���{�s���ꂽ�B���Ђ͂��̐V���x�̊J�n���A�ƊE�ŏ��߂āA�X�}�[�g���[�^�[�����̐��x��L����p���[�R���f�B�V���i�̓d�͌v���@�\���J���B �v�����x���X�}�[�g���[�^�[������2���ȓ��Ƃ��鍂���x�v�������������B���̋@�\�lj��ɂ��APPA�r�W�l�X�ɕK�v�ȃX�}�[�g���[�^�[���ʂɎ��t����K�v���Ȃ��Ȃ�A�@��R�X�g���팸�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���˓c���݁A�S����350�̍�Ə��ɒ~�d�r��W�������A�d�͂Ђ������ւ̑Ή� �˓c���݂́A�S����350�J���̍�Ə���ΏۂɁA���z���^�~�d�r�̕W���������J�n�����B���̎��g�݂ɂ��A�d�͎g�p���Ђ������鍡�Ẵs�[�N�V�t�g��A���R�ЊQ�Ȃǂً̋}���Ԕ������̎��ƌp���iBCP�j�ɑΉ�����B �����������z���^�~�d�r�́AREBGLO���J�����������^�тł��鎖�Ɨp�̍ė��p�o�b�e���[�i���`�E���C�I���d�r�j�B�d�C�����ԁiEV�j�Ŏg�p���Ă����o�b�e���[���ė��p���Đ��삳�ꂽ�B�ʏ펞�̓R���Z���g����d���������Ȃ���[�d�ł��A4.6���Ԃ̏[�d�i���[�d�j�ŃX�}�[�g�t�H���Ȃ��300��[�d�A1kW�̏Ɩ��ł����4.2���Ԏg�p�ł���i4,200Wh�j�B ���Ƃɂ����Ă��A�ً}���Ԕ������A�e��Ə��ɂ�������Ӓn��Ɍ������x�������͏d�v�Ȗ����̂ЂƂƂȂ��Ă���A���Ђ́A���~�d�r�̕W���̗p�����肵���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C��e�b�N�x���`���[�̃A�X�G�l�������ɒ���18���~�B�A���̖ړI�� �A�X�G�l�̓N���[���d�̓T�[�r�X�u�A�X�G�l�v�ɉ����A2021�N8�����CO2�r�o�ʌ����鉻�E�팸�N���E�h�T�[�r�X�u�A�X�[���v��W�J�B ����̃��E���h�ł́A�V���K�|�[�����{�P���̓�����ЁA�A�W�A��PE Fund�ȂNJ��G�l���M�[������6�ЁA����ɏ��H�g���������ɂ����2���~�̗Z�����A���킹��18���~�B�����B���B������D�G�l�ނ̗̍p�����ɏ[�āA�X�R�[�v1-3�̃T�v���C�`�F�[���r�o�ʂ܂ŊȒP�Ɍ����鉻�ł���A�N���E�h�V�X�e���J���Ɍ������@�\�g�[��A�O���[�o���W�J���߂����B �A�X�[���̃T�[�r�X�̓����́i1�j�X�L�������邾���Ŏ����Ō����鉻�A�i2�j�V���v����UI�EUX�ŋƖ��������A�i3�jCO2�팸���܂Ƃ߂Ă��܂�����3�_�B 3�̓����ŒE�Y�f�o�c�̋Ɩ��H�����ő�70���팸�ł���Ƃ����B�����CO2�r�o�ʂ̌����鉻�����ɏI��炸�ACO2�r�o�ʍ팸�̎��s�܂ŁA�u�E�Y�f�̃����X�g�b�v�\�����[�V�����v�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A���dHD�֊���E�~�d�@�\�g���d�͈��艻�Ȃ� �����s�́A�����d�͂�1.2%�����劔��B�E�N���C�i��̉e���ɂ��A���{�̓��V�A�Y�ΒY�A���֎~�\����ȂǁA�G�l���M�[���߂��錵�������E��͒������̋��ꂪ����A��s���̓d�͂̈��苟���Ɏx������������Ƃ����O����Ă���B�܂��A�s���ɓd�͎����Ђ����x���߂��ꂽ�ۂɂ́A�s���E���Ǝ҂̋��͂ɂ�蓖�ʂ̎����o�����X�͊ɘa���ꂽ���A���������n�k�ɂ�锭�d���̒�~���̉e�����p�����Ă���B ������͍��āA���~�ɂ�����d�͎����ɂ��Ă̌��������ʂ����������ȂǁA�d�͎�������w�Ђ�������\��������Ƃ����B��s���ɂ�����d�͎����̖��́A�s���E���Ǝ҂̐����E�Ɩ��ɒ������邱�Ƃ���A�E�Y�f���̎��_�����܂��A�m���ɓd�͂̈��苟�����m�ۂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ����A�s�́A�����d�͂ɑ��A�u�d�͂̈��苟���v��u���͔��d��~�d�r�A���f�������p�����~�d�@�\���̑n�o�v�Ȃǂ̊����Ă��s�����B�܂��A���Ђɋ�������Ɍ��������c�̐\��������s�����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���s����w��A��C����CO2�������������Z�p���J��������99%�ȏ� �����s����w�A���s��w��̌����`�[���́A�������𗘗p���邱�Ƃ�CO2�z�����x�̌���Ɣ����n����̐������̕������������A�K�X���ʉ��ł�CO2�i400ppm�j��99%�ȏ㏜���ł���V����DAC�V�X�e���i��C�����CO2��������Z�p�j�̊J���ɐ��������Ɣ��\�����B ����J�������������ɂ��CO2�z���E����V�X�e���́A�H��̔r�C�K�X�Ȃǂ����CO2����ɂ����p�\�Ȕėp���̍����V���ȃV�X�e���Ƃ��Ă̎��p�������҂����B �J���̃|�C���g�́A �@�t�̂̃A�~����CO2���������Ăł���J���o�~���_���ő̂Ƃ��āw�������x����B �A�ő̂̃J���o�~���_�������������n�t��60�����x�ɉ��M����Ƌz������CO2��E���E����ł��邱�Ƃ����o�����B �B�ő̂̃J���o�~���_������A�~���ł���ΓK�p�\�B �C��C���̒�Z�xCO2�������ŋz���ł���B�A�~���z���@�̖�5�{�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăG�l���M�[�ȁACO2��������23���h�����𓊎� �č��G�l���M�[�ȁiDOE)�́ACCS�i��_���Y�f����E�����j���Ƃ̉����Ɍ�����3�̎��g�݂�23���h���ȏ�̓������s���Ɣ��\�����B �܂��A2021�N11���ɐ�������1���h���K�͂́u�C���t�������@�v�Ɋ�Â��A22��5000���h���𓊂���CCS���Ƃ̒����E�]���Ȃǂ����{����B�����Ƃɂ��A���Ȃ��Ƃ�5000���g���K�͂�CO2���ł��錩���݁B �����āACO2�����T�C�g�������A�Y�f�Ǘ��Z�p�̊J���𑣐i���邽��9100���h�����o������B���ƋK�͂�CO2�����T�C�g�����S�Ō����I�E�����ɒ�`�E�]������菇�̉��P��ړI�Ƃ������Ƃ�4500���h���A�Y�Ƃ��C����CO2�������E�ߑ��E�ϊ��E��������Z�p�̊J����ړI��4600���h���𓊎�����B���̎��g�݂ŁA��C������CO2��������A100�h��/�g���ȉ��̉i���I�����ɂȂ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�A�R���̏ȃG�l��A�ő�3�������グ�� �o�Y�Ȃ́A�ƒ�p�G�A�R���̐V���Ȋ�G�l���M�[�������(�ȃG�l�)�ɂ��Ē�߂����������z�����B�{�s��6��1���B �G�A�R���͉ƒ���̃G�l���M�[����ɐ�߂銄������3���Ƒ傫�����Ƃ���A���̏ȃG�l����������グ�邱�ƂŁACO2�r�o�ʍ팸�Ȃǂ̑��i��}����́B 2���Ɏ��܂Ƃ߂��Ă������܂��A5��31���ɍ��������z���ꂽ�B�ΏۂƂȂ�ƒ�p�G�A�R���́A�NJ|�`�A�NJ|�`�ȊO�A�}���`�^�C�v�̂��́B�V������ׂ��Ƃ���ڕW�N�x�́A�NJ|�`��2027�N�x�A�NJ|�`�ȊO�ƃ}���`�^�C�v��2029�N�x�B���j�b�g�̌`�Ԃ�A��[�\�́A�d�l(��ʒn/����n)�ɉ�����10�敪��ݒ�B�NJ|�`�ɂ�����ȃG�l��́A��[�\��2.2kW�̏ꍇ�͌��s��APF(�ʔN�G�l���M�[�������)5.8�ɑ��A�V���6.6�ʼn��P��13.8%�B��[�\��4.0kW�ł�34.7%���P�B �o�T�uImpress�v |
|
|
| ���o�c�A�u�O���[���g�����X�t�H�[���[�V�����iGX�j�Ɍ����āv �o�c�A�́A���{�ɑ��A�f�w�Ɍ������O�����h�f�U�C���ƂȂ�u�f�w����p�b�P�[�W�v�̍��������B���ɁA���g�݂��x��Ă���A���v���[�X�E�V���݂��܂ތ��q�͗��p�̐ϋɓI���i�A�O���[���f�B�[���A�J�[�{���v���C�V���O���͂��߂Ƃ��鑽�l�Ș_�_�ɂ��āA�o�c�A�̌����_�ł̍l�����������ƂƂ��ɁA���{�ɑ��Đ���̑��₩�Ȏ��s�����߂��B �o�T�u�o�c�A�v |
|
|
| ��JPX�A�r�o�ʎ���̎��؎�������A���Ɏs��J�� ���{������O���[�v�iJPX�j�́A�o�Y�Ȃ���CO2�r�o�ʂ��������s��̊J�݂Ɍ��������؎�������������Ɣ��\�����B �����،�������̒��ɐ�p�s���݂���9������r�o�ʎ�������s����B�����܂��ĉۑ��o���A�r�o�ʎ���̃��[��������B2023�N�x�̎s��̖{�i�ғ��ɂȂ���B�o�Y�Ȃ͒E�Y�f�Ɏ��g�ފ�Ƃō\������uGX�i�O���[���g�����X�t�H�[���[�V�����j���[�O�v�\�z���f���A���{���S�Ȃ�440�Ђ��^�����Ă���B���؎�����GX���[�O�ɎQ�������Ƃ�Ώۂɂ���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ��2022�N�x���������\�u�E�Y�f�h�~�m�֑��p�I�ȃA�v���[�`���v ���{�́A2022�N�Ŋ������E�z�^�Љ���E�������l���������t�c���肵���B ����̃e�[�}�́A�u�O���[���Љ�̎����Ɍ����ĕς��鎄�����̒n��ƃ��C�t�X�^�C���`�������̕ϊv����N�����E�Y�f�h�~�m�`�v�B2030�N�܂łɁA�����O�Łw�E�Y�f�h�~�m�x���N�������߁A�E�Y�f�݂̂Ȃ炸�A�u�����z�v�u���U�E���R�����v�Ƃ������p�I�ȃA�v���[�`�ɂ��A�O���[���Љ�̎�����ڎw�����ƂȂǂ��L�ڂ��ꂽ�B�u�����z�v�ł́A��l���z�^�Љ�`�����i��{�v��ɂ��āA�]���E�_�����ʂ��A�z�o�ύH���\�Ƃ��Ď��܂Ƃ߁A���C�t�T�C�N���S�̂ł̎����z�Ɋ�Â��E�Y�f���̎��g�݂𐄐i���Ă����B�n�����g����v��ɂ����āA�T�[�L�����[�G�R�m�~�[�ւ̈ڍs���������邽�߂̍H���\�̍���Ɍ�������̓I�������s�����Ƃ��߂Ă���A��l���z�^�Љ�`�����i��{�v��i2022�N�x�\��j�̕]���E�_�����ʂ��z�o�ύH���\�Ƃ��Ď��܂Ƃ߂邱�ƂƂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/6�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�A�G�R�L���[�g���u�������グ�v�ɓ]���A�������������^�]�@�𓊓� �����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i���dEP�j�́A���v�̖�V�t�g�𑣂����߂ɐݒ肵�Ă��������v�������������ăq�[�g�|���v�����@�i�G�R�L���[�g�j�̖�ԉ^�]���̊�����p�~�������A�~�d�r�ƒ~�M�@��ɂ�葾�z�����d�̎��Ə���𑣂��V�����v���������\�����B �����d��EP�́A2011�N�̎��̂Ō�������~����O�܂ŁA��Ԃ̗����P����啝�Ɉ������A�q�[�g�|���v�����@�̖�^�]�i��ԕ����グ�j���ɗ�������������Ă����B�����A������~���������Ȃ��A�������������̌n�̏ꍇ�A�o�c�I�ɋt���₪�������邱�Ƃ��������B���̂��߁A�q�[�g�|���v�����@�̖�ғ��������ɂ��闿�����j���[���������āA��Ԃ̗����P����2�~53�K�`2�~64�K/kWh�l�グ����ƂƂ��ɁA���Ԃ̗����P����2�~40�K�`5�~28�K/kWh���������A�q�[�g�|���v�����@�Ȃǒʓd����^��Ԓ~�M���@�����������p�~����B2022�N10��������肷��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���X�܂�I�t�B�X�ɓK�����Ɩ��p�G�A�R���̃T�u�X�N���v�V�����^�T�[�r�X���J�n �_�C�L���́A�Ɩ��p�G�A�R�����T�u�X�N���v�V�����^�Œ���X�܁E�I�t�B�X�G�A�R����z���p�T�[�r�X�wZEAS Connect�i�W�A�X�R�l�N�g�j�x���O��Z�F�t�@�C�i���X�����[�X�����SMFL�����^���Ƌ����ŊJ�����A2022�N5��27�������J�n����B �wZEAS Connect�x�́A�X�܂�I�t�B�X�ɓK�����Ɩ��p�G�A�R���w�X�J�C�G�A�x��wmachi�}���`�x���̒�z�����Œ���T�u�X�N���v�V�����^�̃T�[�r�X�B �@��{�̂��t�H���A�ُ�ʒm���[���@�\��C���T�[�r�X�������p�b�P�[�W�����Č��X�̎x�����ɕ������邱�ƂŁA�G�A�R���̐V�K������X�V�ɂ����鏉����p���Ȃ����ƂƂ��ɁA���X�̈���I�ȃG�A�R���̉^�p���T�|�[�g����B�܂��A�����@�̃t�B���^�[�Ȃǂ𐴑|����I�v�V�������j���[���p�ӁB�d�͏���̗}���ɂ��v������B�_����Ԃ̍Œ�7�N���ƂɁA�ŐV�̃G�A�R���ɓ���ւ���B �o�T�u�_�C�L���v |
|
|
| ���R�}�c���o��1,000�L�����b�g���̐��f�R���d�r�iFC�j�����{�݂�ݒu �R�}�c�͏��R�H����ɏo��1,000��W���̐��f�R���d�r�iFC�j�����{�݂�2022�N�x�ɐݒu����B���݂͐_�ސ쌧�̌����{�݂�16kW�̏��o��FC��ݒu���A�e��������s���Ă���B �z�R����Ŏg������^�_���v�g���b�N�̏ꍇ�A���Ȃ��Ƃ�1,000kW�̏o�͂��K�v�B2029�N�x��FC�_���v�J���Ɍ����A���i���ɕK�v�ȃf�[�^��~�ς���B FC�͐��f�G���W���ƂƂ��ɁA���@�B�̏����̓��͌����̈�B����^�_���v��V���x���͏�p�Ԃ��d�ʂ�U���A�쓮�p���[�����Ⴂ�ɑ傫���B���̂��߁A�����_�œ��͌��ɂ��Ă̓��`�E���C�I���d�r����FC�̕����\���������Ƃ݂Ă���B FC�_���v�̏��i�J���ł́AFC���L�̐����o�́A���ׂȂǂ̓��������@�f�[�^�Ŋm���߂�K�v������BFC�̐�����R�}�c�����ЂŎ肪���邩�A���ЂƑg�ނ��͌������B�ԍڂ�z�肵�����؎����ɑ����A�_���v��FC�𓋍ڂ��Ă��܂��܂Ȏԍڃe�X�g��i�߁A���i�̊����x�����߂�B �o�T�u�����H�Ɓv |
|
|
| ���@�̌v��I��~�A���䎞��CO2�r�o�ʂ𑪒肷��Z�x�f�f�T�[�r�X�E�Y�f NEC�t�@�V���e�B�[�Y�́A�G�A�R���v���b�T�[�̃G�A�R���f�f����u�G�A���[�N�f�f�T�[�r�X�v�ƁA�@�Ȃǂɂ���Ĕ�������CO2�̔Z�x�𑪒肷��uCO2�Z�x�f�f�T�[�r�X�v���A�����ƌ����ɒJ�n�����B �G�A���[�N�f�f�T�[�r�X�ł́A�����g�Z���T�[��p���čH����̈��k��C�p�z�ǂ̃G�A�R��ӏ�����肷��B�����g�Z���T�[��p���ĒZ���ԂŐf�f���A������V�䗠�A�����Ȃǂ��܂߂��z�ǑS�̂�f�f�ł���BCO2�Z�x�f�f�T�[�r�X�́A�����̓�_���Y�f�Z�x�𑪒肷��B�u�ȃG�l�̂��ߋ@�̌v��I��~�A����ɂ��CO2�Z�x�̔c���j�[�Y�ɉ����A�J�n�����B���C�ݔ��̐Ǝ�ȍH��ɂ�����ߓd��̍ۂ�CO2�Z�x�̏�Ԕc���ɓK���Ă���A���C�ݔ����܂߂��g�[�^���v�̒�Ă��s���B�����́A�G�A���[�N�f�f�T�[�r�X��38���~����i�ŕʁA�z�ǒ�800m�܂Łj�ŁACO2�Z�x�f�f�T�[�r�X��18���~����i�ŕʁA����ӏ�40�J���܂Łj�B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���Y�Ǝ{�݂ɂ�����G�l���M�[����ʂ̎��Ԓ������ʂ\�E�Y�f �x�m�o�ς́A�o�ώY�ƏȂ́u2050�J�[�{���j���[�g�����ɔ����O���[�������헪�v�œd���A���f���ACO2����̕������������ꂽ���Ƃ��āA�Y�Ǝ{�݂ɂ�����G�l���M�[�����CO2�r�o�ʂ̎��Ԃ𑨂��A������W�]���Ă���B �ŏI�G�l���M�[�ʂ̖�94�����Ǝ�v20�Ǝ킪��߂�B�d���Z�p�́A��S�������i�̗n����v���X�`�b�N���i�̐��`�\�M�Ȃǂ̈ꕔ�v���Z�X�Ői�ށB�Z�����I�ɒE�Y�f�̒��S�I�Ȗ�����S���B �G�l���M�[������^�̓S�|�Ƃ�L�@���w�A�Ζ����i�E�ΒY���i�́A�G�l���M�[����ʂ��c��Ȃ��߁A2019�N�x�̓d���Z�p�̕��y����1�������B�d���Z�p��J�[�{���j���[�g�����iCN�j�R���œS�|�Ƃ̃G�l���M�[����ʂ�8.3�����A�A���p�@�B���i�����ԁj��CO2�r�o�ʂ�40.2�����Ɨ\������B�v���X�`�b�N���i��38.8�����B CO2�r�o�팸�팸�Ɍ����u�ݔ��@�퓱���E�X�V�ɑ��鎑�����B�v�u�r�o�팸���@�ɑ����l�܂芴�v��4���ɒB�����B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���`�����쏊�ACO2��r�o���Ȃ��u�^�[�R�C�Y���f�v�����Z�p�J���������� �`�����쏊��NEDO�̈ϑ����Ɓu���f���p���擱�����J������/�Y�����f�������p����CO2��r�o���Ȃ����f�����Z�p�J��/���^���������ƒY�f�͏o�̔����ꕪ���ɂ�鐅�f�����v�����{����A�����E�ޗ������@�\�E�É���w�E���z�z�H�Ƌ����������J�n�����B �]������̓`���I�Ȑ��f�����@�i�O���[���f�j�́ACO2�𑽂�����������B�܂��A���̓d�C����@�i�O���[�����f�j�̓G�l���M�[�𑽂��K�v�Ƃ��邽�߃R�X�g�������Ȃ�B�����ɑ��āA�V�R�K�X�ȂǂɊ܂܂�郁�^���K�X���A�G�}�̉��ʼn��M�������̓v���Y�}�Ǝ˂ɂ���Čő̒Y�f�Ɛ��f�iH2�j�ɕ������邱�ƂŐ��f�K�X��u���^���M�����v�i�^�[�R�C�Y���f�j�́ACO2���������A���̓d�C��������R�X�g�Ő��f���ł���Z�p�Ƃ��āA���ڂ𗁂тĂ���B�u���^���M�����v�̓��^���������������Đ��f�����o���v���Z�X�ƒY�f�����o���v���Z�X����ԓI�ɕ������A800���ȉ��̔�r�I�ቷ��Ŏ��{�ł���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| �����z���Ƒ�C���̐����琅�f�����A���v���W�F�N�g�ɑ�K�X���Q�� ���K�X�́A�I�[�X�g�����A�̐��f�֘A��ƃA�N�A�G�A�����ƁA���z�����d�̓d�͂Ƒ�C���������������������ɐ��f������u�f�U�[�g�u���[���n�C�h���W�F���v���W�F�N�g�v�ɂ��ċ����J���Ɋւ���_�����������B �A�N�A�G�A�����́A��C������̐�����Z�p�œ������擾���Ă���x���`���[��ƁB���݁A���Ђ̕M������ł���T���O�C���ƂƂ��Ɂu�����Y���j�b�g�v�̎��؎�����i�߂Ă���B����A���K�X�Ƌ����ŁA�O���[�����f�����v�����g�̐v����������f�̋�����ȂǂɊւ��Č�������\��v�����g���ݒn�̃I�[�X�g�����A�k�����B�́A���˗ʂ��������z�����d�ɓK�������A�����n�тŐ������ɖR�����n��ɂȂ�B�A�N�A�G�A�����̓Ǝ��Z�p�ɂ���C�����琅��������邱�ƂŁA�O���[�����f�̐������\�ɂȂ�Ƃ��Ă���B�܂�2023�N����8MW�K�͂̑��z�����d�ɂ��N��400t�̐��f������v�����g�̌��݂�ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�ȃG�l�R�~���j�P�[�V�����E�����L���O���x��{�i�^�p �o�ώY�ƏȂ́A�ߘa4�N�x���u�ȃG�l�R�~���j�P�[�V�����E�����L���O���x�v��{�i�^�p����B �����x�́A�d�́E�K�X��Г��̃G�l���M�[�������Ǝ҂ɂ��ȃG�l�Ɋւ����ʏ���Ҍ����̏���T�[�r�X�̏[���x�����A��g��]���E���\������́B�u�G�l���M�[�̎g�p�̍��������Ɋւ���@���v�ɂ����āA�G�l���M�[�������Ǝ҂́A��ʏ���҂ɑ��A�u�G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɏ�����������悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă���B���̋K��Ɋ�Â��A�G�l���M�[�������Ǝ҂ɂ��ȃG�l�Ɋւ�������̏[���x�����A��g�N�x�]���E���\���鐧�x��݂����B���̐��ŃG�l���M�[�������Ǝ҂̏���T�[�r�X�̏[���x��������悤�ɂȂ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���A��6���]�����̑�3��ƕ���������\ �C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�́A��6���]�����iAR6�j��3��ƕ�����u�C��ϓ�2022�F�C��ϓ��̊ɘa�v�̐������ĎҌ����v�A2022�N4��4���ɓ��p�l������195�����̐��{�ɂ�菳�F���ꂽ���Ƃ\�����B �E��X�́A���g����1.5���ɗ}������o�H��ɂȂ��B2010�`2019�N�̉������ʃK�X�r�o�ʂ̔N���ϒl�́A�l�ގj��ō��ƂȂ����B �E2030�N�������������邽�߂̑�I�v�V�����͑��݂���B�S�Ă̕���E�n��ɂ����đ����ɖ�S�I�ȍ팸�����{���Ȃ���1.5����B�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �E���㐔�N�Ԃ����O��ɂȂ�B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���Ăf�d�A�A���o�}�B�̉ғ����Η͂łb�b�t�r���^�����95���ڎw�� ��GE�́ACCUS�i��_���Y�f����E���p�E�����j�̕��y�ցA�ăA���o�}�B�̃W�F�[���X�EM�E�o���[�Η͔��d���Ŏ����n�߂��B ��_���Y�f�iCO2�j����Z�p��ۗL���郊���f�E�G���W�j�A�����O�ȂǂƋ��͂��ACO2����̐��x��@��̉^�p�R�X�g��������B���d������o��r�K�X�����CO2�������95����ڎw���B �č��G�l���M�[�Ȃ́A�����̓V�R�K�X�Η͔��d����CCUS��g�ݍ��ދZ�p��V���Ɍ�����ӌ��ŁACCUS�̃R�X�g�팸���@��T�����577���h���̏����������^����B���͖�1�N���ɂ킽���Đi�߂�B �o�T�uT�d�C�V���v |
|
|
| ���ăA�b�v���̃T�v���C���[�A213�Ђ�10GW�ȏ�̍ăG�l���� Apple�́A���Ђ̃T�v���C���[�ɂ��Đ��\�G�l���M�[�d�͎g�p�ʂ���N1�N�Ԃ�2�{�ȏ�Ɋg�債�A���㐔�N�Ԃ̎��g�ݑS�̂ŒB�����錩���݂̖�16GW�̂����A�����_��10GW�ȏ��B�������Ɣ��\�����B �A�b�v���́A2020�N�ɃO���[�o���Ȏ��Ɗ����ɂ�����J�[�{���j���[�g������B�����Ă���A2030�N�܂łɃT�v���C�`�F�[���S�̂ŃJ�[�{���j���[�g������B������Ƃ����ڕW���f���Ă���B�����_�ŁA���Ђ̃T�v���C���[�̂���213�Ђ�25�J���œ��А��i�̐��������ׂčăG�l�d�͂Řd�����Ƃ���Ă���B ���{�ł́A2021�N�ɃL�I�N�V�A��V���[�v�ȂǐV����20�Ђ̃T�v���C���[���ăG�l�ւ̎��g�݂�\�������B���B�ł́A11�Ђ̃T�v���C���[���V���ɍăG�l�ւ̎��g�݂�\�����A���v��25�ЂɂȂ����B�����ł́A�V����23�Ђ����v���O�����ɎQ�悵���B�؍��ł́A���v13�Ђ̃T�v���C���[���ăG�l���p�Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O�@�{��c�ŃG�l�W���˖@�Ă��� �ȃG�l�@�����ĂȂǂ̃G�l���M�[�W���˖@�Ă�4��26���O�c�@��ʉ߂����B�����̖{��c�Ŏ^�������ɂ���Č��Ēʂ�����ꂽ�B���@�ẮA�G�l���M�[�ւ̓]��������̕ϓ��ɉ������d�͎��v�V�t�g�Ȃǂ�ڎw���B �������ł́A���f�E�A�����j�A�Ƃ������E�Y�f�R���̗��p���i�ACCS�i��_���Y�f�E����E�����j�ȂǒE�Y�f�Z�p�̎Љ�����𑣐i����B����A�Q�c�@�ŐR�c�ɓ���B�Ζ��V�R�K�X�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j�����f�E�A�����j�A�֘A���Ƃ��x���ł�������@�ĂȂǂ��ΏہB���{���i�߂�E�Y�f�̍����ڕW�̎����̂��߁A��Ƃ̎��g�݂��㉟������B2023�N�t�̎{�s��ڎw���B �ȃG�l�����@�F�G�l���M�[�̎g�p�ʂ̑�����ƂɔG�l���M�[�g�p�ʂ̖ڕW�ݒ���`�����B�d�C���Ɩ@�F���`�̑��z���E���͔��d�ݒu�̓͂��o�A���S�m�F�B�Η͔��d�̉ߓx�̔p�~��h�����ߔp�~�̎��O�͂��o�`�����BJOGMEC�@�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���t���C�����m�ւ`�h���p���{�s�����d�ƘA�g�A�d�̓f�[�^���� ���{�s�͒����d�͂ȂǂƘA�g���āA1�l��炵�̍���Ґ��т̎g�p�d�̓f�[�^�͂��āA���N�ȏ�ԂƗv����Ԃ̒��ԂƂȂ�u�t���C���v�\�h�ɂȂ�����؎������T�����{�Ɏn�߂�B ������ꂽ�ꍇ�A�s�̕ی��t�Ȃǂ��Ή�����v��ŁA�a�c�A�V���A�g�c�A����A���܁A�ސ��6�n�悩��100���тقǕ��A���N�R�����܂Ō��ʂ�������B �s�ƁA�����d�́A�l�R���R�AJDSC��3�Ђ����g�ށB����҂̊O�o�̕p�x��A�Q���ԁA�������ԂȂǂ�d�̓f�[�^����l�H�m�\(AI)�����͂��A�t���C������̑���������ڎw���B 3�Ђ͂��łɎO�d���������∤�m���L���s�A��t���s���s�œ��l�̃V�X�e�����g�����������s���Ă���B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���@�@[�@2022/5�@]�@�@�� |
|
|
| ��UCC��A�R�[�q�[�����ɐ��f���p�R�����f���œd��������ȕ����E�Y�f�� �R�����Ⓦ���d�͓��́A�đq�R�d�͒����Z�p�����T�C�g�ŁA�ăG�l�̗]��d�͂Ő��f������������P2G�V�X�e���̋����J����i�߂Ă���B �u��܂Ȃ����f���v�Z�p�J�����Ƃł́A�V���ɏ��K�̓p�b�P�[�W������P2G�V�X�e�����J�����A�����̕����n�_�ɐ������邱�Ƃ�ڎw���BNEDO�̏������Ƃ̍̑������Ƃ��J�n�����B���Ɗ��Ԃ�2021�N�x�`2025�N�x�i5�N�ԁj�B ��̓I�ɂ́A���d�u��p�������U�^�ΔR�������V�X�e�����������邽�߁A 500kW�������p�b�NPEM�i�ő̍����q�j�`P2G�V�X�e�����J���E������B�����C���t���Ɛ��f�G�l���M�[�����p�������f���̒�āE���ɂ����g�ށB����ɁA�R�[�q�[�������ȂǓ�Փx�̍������f���p�̋Z�p��ʂ��āA�H�i���H����̒E�Y�f����ڎw���B UCC�㓇����́A�V���ɎR����������V�݂��A�u�J�[�{���j���[�g�����ȃR�[�q�[�����v�Ƀ`�������W���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������Ŕ��d�ɒ��ރX�^�[�g�A�b�v�^�f�b�d�C���X�e�B�`���[�g �M�G�l���M�[��d�͂ɕς����@�Ƃ��ẮA���C���g���ă^�[�r�������@�ƁA���x�����g���u�[�[�x�b�N�f�q�v����\�I���B�ǂ�����M���ɉ����āA�ق��̐ݔ������d�ɂ͕K�v�ɂȂ�B����A���Ђ��J������f�o�C�X�́A25���̎����Ŗ�0.5���b�g�̓d�͂ݏo���B�M���ȊO�̏�����K�v�Ƃ��Ȃ��_���������B �ʏ�A�����ɂ͂��ꂼ��A��������d�q�����o���̂ɕK�v�ȍŏ��G�l���M�[�u�d�����v������A���̐��l�͈قȂ��Ă���B���Ђ̃f�o�C�X�́A���̈قȂ�����̊ԂɁA���a3�`5�i�m���[�g���̋����i�m���q�����ݍ��ށB �M�d�q���f�o�C�X���̋����i�m���q��ʂ��ēd�ɂֈړ�����u�z�b�s���O�`���v���g���A�d�C�ݏo���d�g�݂��B�����ł����d�ł��邪�A���x�������قǍ��d���ݏo����B�܂����p������������̂�150���ȓ��̔r�M���B2023�N���߂ǂɃZ���T�[��E�G�A���u���f�o�C�X�����ɔ��d�ł���f�o�C�X����������\��B �o�T�u�f�b�d�C���X�e�B�`���[�g�v |
|
|
| ��TMEIC�����f��������������A���i���́u�����v���� ���ŎO�H�d�@�Y�ƃV�X�e���iTMEIC�j�́A���f�����v�����g�����̐V�^��������J�����A�̔����J�n�����Ɣ��\�����B ����d�C�������Đ��f�����鑕�u�͒����̓d���ʼnғ����邽�߁A�����I�ɗ���̌������ς��u�𗬁v���A�������̗���ł���u�����v�ɕϊ����鐮����iAC/DC�R���o�[�^�j���K�v�ɂȂ�B�����A�]���̐�����ł́A�����I�ɖ���ł𗬂����S�ɕ������ł����A����i�������������b�v���j���c��A�������������́A�d�𑅂�d�͌n���ɂƂ��ăX�g���X�ɂȂ�B �܂��A������H�ł́A�d���̂Ђ��݂��獂���g�i���g���̍����d���j���������邱�Ƃ������A������n����d�C�@��ȂǂɈ��e�����y�ڂ��B�V�^������ł́A�����������b�v���A�����g�̔����ɑ���{���A���i���́u�����v�����������B �Đ��\�G�l���M�[�R���̃O���[�����f�����v�����g�ł̎g�p�ɂ��K���Ă���Ƃ����B100MW���̑�^���f�v�����g�ɑ��Ă��Ή��ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���m�㕗�͂���d�C���^�ԁu�d�C�^���D�v�ŋ��Ɓ^�p���[�G�b�N�X�Ɠ��{�C������ �p���[�G�b�N�X�́A���{�̊C��ɂ���m�㕗�͔��d������C�݂Ɏ��R�G�l���M�[��A������u�d�C�^���D�v�̐v�J���E�����^�q�Ɍ����A���{�C������Ƌ��ƂɊւ���{���ӏ�����������Ɣ��\�����B �p���[�G�b�N�X�́A�d�C�^���D�̏����D�v���W�F�N�g��i�߂Ă���A2025�N�̎��؎����Ɩ{�i�ғ��Ɍ����A�D�̐v�E�J���̃t�F�[�Y�ɓ����Ă���B����̍��ӂ�ʂ��āA�D���̍\���E�ݔ��̐v�A���S�Ǘ��V�X�e���A�\�t�g�E�F�A���ɂ����ē��{�C������ƒ�g���A2025�N���܂ł�ڕW�ɁA�d�C�^���D�uPowerARK�v�̏����D�̊�������������B �d�C�^���D�́A�m�㕗�͂ł���ꂽ�d�͂��o�b�e���[�ɒ��ڒ~�d���A�m�ォ�琢�E���̕ϓd�ݔ��܂ʼn^������B�C��̌@�퓙�A��K�͂ȕ~�ݍH�����K�v�ƂȂ�C��P�[�u������������邱�ƂŁA�m�㕗�͔��d���̐ݒu�ꏊ�̎��R�x���傫�����シ��Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���l�N�X�g�G�i�W�[�A�������P�������z�d�r���W���[���̌y�ʔŁ^���ωd�Ŕ��� �l�N�X�g�G�i�W�[�́A�������P�������z�d�r���W���[���̌y�ʔŃ��W���[���ƍ��ωd�ł̔̔����J�n�����B ���z�����d�̎��Ə���s��͊g��X���ɂ��邪�A�����̑ωd�s���P�[�X��A�����䕗�̑����Ȃǂ̑ωd�����肸�ݒu���ł��Ȃ��n������݂��Ă���B���Ђ́A���������j�[�Y�ɑΉ����邽�߂ɁA�y�ʔŁE���ωd�ł̐V���i���J�������B�y�ʔł́A�]���̃��W���[���̕ϊ������ƕi����ێ������܂܁A�d8.3kg/m2�Ə]���i�i��11kg/m2�j�����25���̌y�ʉ������������B��ʓI�Ȑܔ����̗]�͉d��10kg�^m2���x�Ƃ����Ă���A�]���i�ł͐ݒu���ł��Ȃ��Ƃ�����߂Ă��������ւ��ݒu���\���B���ωd�ł́A�]���i�̃t���[�������ǂ��邱�ƂŁA�ϐ�ωd�ƕ����ωd�����サ���B�ϐ�ωd8000Pa�^�����ωd4000Pa�����������B���W���[���Ƃ��Ă͍ő�ϐ��2.6m�A�ő啗��46m/s�A�ݒu����30m�ɑΉ��\���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���I�������A���^�E�y�ʂ̎Y�ƌ����~�d�V�X�e���������[�X ���^�E�y�ʂ̎Y�ƌ����~�d�V�X�e���i�Y�Ɨp�~�d�p���[�R���f�B�V���i�o�́F5.6kW�A�~�d�e�ʁF16.4kWh�E9.8kWh�j�̒�ʂ��A����܂Œ~�d�V�X�e���̓������i��ł��Ȃ����������̂◬�ʏ����ƁA�����ƂȂǂɂ����郌�W���G���X�����ɍv������B �Y�ƌ����̒~�d�V�X�e���́A�{�̉��i�����z�A�{�̃T�C�Y���傫���A�ݒu�X�y�[�X�̊m�ۂȂǂ��W���ƂȂ��Ă���B���ݒ��Ă���ƒ�p�~�d�V�X�e�����x�[�X�ɊJ�����s�����ƂŁA���i�����͂�ێ����A�ݒu�ꏊ�̑I�������L���鏬�^�E�y�ʉ��Ǝ{�H�̂��₷�������������Y�ƌ����~�d�V�X�e���̒��J�n����B�{�V�X�e���́A���S���Ə����p�p���[�R���f�B�V���i�ƕ��݂��A�����ē��삳���邱�Ƃō����E�����x�̕��גǏ]�����ʂ������X�̏��Ȃ����Ə�����s���B �o�T�u�I�������v |
|
|
| ���p�\�i�O���[�v��ƁA���o�c�x���T�[�r�X�J�n�]�ƈ���SDGs����x���� �p�\�i�O���[�v�̃L���v�����́A�C�X�N�Ȃǂ̊J����CO2�r�o�ʂ̍팸�ȂǁAGX�i�O���[���g�����X�t�H�[���[�V�����j��ڎw����Ƃ�ΏۂɁA�w���o�c�x���g�[�^���T�[�r�X�x���J�n�����B���̃T�[�r�X�ł́ACO2�r�o�ʂ̉�����֘A�Ɩ����x������uBPO�i�r�W�l�X�v���Z�X�E�A�E�g�\�[�V���O�j�T�[�r�X�v�ƁA�]�ƈ��ւ́u�����C�T�[�r�X�v�����B �uBPO�T�[�r�X�v�ł́A�[���{�[�h�ƘA�g���A�������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�����N���E�h�T�[�r�X�ƁA�p�\�i�O���[�v�̗L����BPO�T�[�r�X�̃m�E�n�E��g�ݍ��킹�邱�ƂŁACO2�r�o�ʂ̉������V�X�e���ƃI�y���[�V�����̗��ʂ���x������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���T�b�V�y�ѕ��w�K���X�̐V���ȏȃG�l������܂Ƃ߂� �����G�l���́A�T�b�V�y�ѕ��w�K���X�̌��ރg�b�v�����i�[���x�ɂ�����V���ȖڕW��l���ɂ��Ď��܂Ƃ߂��B �V���ȖڕW��l�ɂ��ẮA2030�N�ȍ~�ɐV�z�����Z��ɋ��߂���ȃG�l���M�[���\���瑋�ɋ��߂���f�M���\���t�Z���邱�Ƃɂ�苁�߂Ă���A�T�b�V�ƕ��w�K���X��g�ݍ��킹�����Ƃ��ẮA�ڕW��l���4�������グ�邱�ƂƂȂ�B�ڕW��l�́A2030�N�ɑ��ɋ��߂���f�M���\��2.08�iW/(m2�EK)�j�B ��Ɍˌ��E��w�����Z��ɗp����B�T�b�V�ɂ��Ă͖ؐ��̃T�b�V��V���ɉ����A�J�`�� 5��A�ގ� 5��B�܂��A���w�K���X�ɂ��ẮA�K���X�����݂� 10�o���̂��̂������A �@�K���X������ 10�o�ȉ��̕��w�K���X �A�K���X������ 10�o���̕��w�K���X�̂����Б��� 3�o�`4�o�̃K���X���g�p���Ă������ �B�O�w�ȏ�̕��w�K���X�Ƃ���B �o�T�u�o�ώY�Əȁv |
|
|
| ��2021�NCO2�r�o�ʁA�ߋ��ō���IEA�u������33����߂�v IEA�́A2021�N�̐��E�S�̂̓�_���Y�f�r�o�ʂ�363���g���ƂȂ�A�ߋ��ō��ɂȂ����Ɣ��\�����B 2019�N�����錋�ʂŁA���@�ւ́u��ɒ����ɂ����́v�ƕ��͂����B�n��ʂł́A�قƂ�ǂ̒n��ő������m�F���ꂽ�B���ł������́A2020�N��2021�N��2�N�Ԃ̑����ʂ�5%�����A�����Ԃɂ����鐢�E�̑��̒n�悪�����������ʂE���镪�ɑ�������B2021�N�̒�����CO2�r�o�ʂ�119���g�����A���E�S�̂�33�����߂��B�Ȃ��č��Ɖ��B�A���iEU�j��7%���x�A���{�̑�������1%�ɂ������Ȃ������B ���@�ւ́A�����̔r�o�ʑ����͐ΒY�Η͔��d�Ɉˑ������d�͎��v�̋}������ȗv���ł���Ǝw�E�B�G�l���M�[�ʂł͐ΒY�̐L�т������ł������B ���E�S�̂̔r�o��������40%�ȏ��ΒY����߁A�ߋ��ō����L�^�����B 2021�N�̐��E�̔��d�ʂɐ�߂�Đ��\�G�l���M�[���ƌ��q�͂̊����́A�ΒY���������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���_�ѐ��Y�ȁA�_�сE���ƕ���̏ȃG�l�@�퓱���x�����g�[�������i������ �_�ѐ��Y�Ȃ́A�_�ы��ƕ���̌������i�����ɑ���ً}��ɂ��Ĕ��\�����B�R�����i���������������ق��A�ȃG�l�@��̓����x���ɂ��āA�x���ΏہE�x���g�̊g�[�Ȃǂ�}��B ���ƁF���ƌo�c�Z�[�t�e�B�[�l�b�g�\�z���Ɓi�������i�����̊���ď㏸�����ꍇ�ɁA���Ǝ҂ɑ���.�����x��������́j�A�����͋����^�@�퓙�����ً}�ƁB �_�ыƁF�{�݉��|���̔R�����i������ɂ��āA�Z�[�t�e�B�[�l�b�g�@�\�̋�������}��B�܂��A�{�݉��|�_�Ƃ̏ȃG�l�@��̓����x���ɂ��āA�x���g�����g�[����B�q�[�g�|���v���̏ȃG�l�@��E�ݔ��̓� .�ɂ��R���g�p�ʂ̍팸��Ƃ��āA�{�݉��|�G�l���M�[�]���g��10���~����20���~�Ɋg�[�B�܂��A����܂ŕ⏕�̑ΏۊO�������ݒu���⏕�Ώۂɒlj�����B�܂��A���̂����Y�҂�؍މ��H���Ǝ҂̏ȃG�l�@��̓����x���ɂ��āA�v���̈ꕔ��������x���Ώۂ̊g�[���s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����C���g�����鉻�h���Ċ��C�𑣐i���c�J�悪���؎��� �����E���c�J�悪�ۈ牀�Ȃǂŋ�C���̓�_���Y�f�Z�x�𑪂��@������p�������؎������n�߂��B �ۈ牀�Ō��ւ����ƁA�G���g�����X�ɐݒu����Ă���̂��A��C���̐����Ȃǂ𑪒肵�g�����鉻�h���Ă����v���킾�B�l�����W���邱�Ƃō��܂��_���Y�f�̔Z�x�≷�x�A���x�APM2.5�Ȃǂ̐��l�������Ƃ������̌v�����ۈ牀�ȂNj�����悻70�J���ɐݒu��i�߂Ă���B���c�J��́u���ꂾ�����x���������Ă���A���x���オ���Ă���A���邢��CO2���オ���Ă���Ƃ������Ƃ�������B �ϑ����ꂽ��C�̃f�[�^�͐��������ŋL�^����A�p�\�R���ȂǂŊm�F���邱�Ƃ��ł��A���C���K�v�Ȓl�ɂȂ�Ɗ��C�𑣂����[�������M�����d�g�݂��B����1�N�Ԃ͎��؎������ăf�[�^��~�ς���B�{�݂̎�ނ�K�͂ɂ���čœK�Ȋ��C�̃^�C�~���O����@��T��A�L�����L���Ă����v�悾�B �o�T�uTOKYO�@MX�v |
|
|
| �������s�A�E�N���C�i��ɌW�钆����Ƃ̏ȃG�l����㉟�� �����s�́A�E�N���C�i��@�ɔ����ً}��Ƃ��āA������Ƃ̏ȃG�l���ʂ����o�c���P���x������B ���V�A�̃E�N���C�i�ւ̐N�U�ɂ��A�����⍒���Ȃǂ̗l�X�Ȏ����̈��苟���ւ̌��O���L����A���̉��i�̈�w�̍������뜜����Ă���B�s�́A������ƌ����̐V���ȗZ�����x��A�_�ы��ƎҌ����̐V���ȋ��Z�x���△���y��f�f�A����ɂ͌������i�̍������ŗ��E��]�V�Ȃ����ꂽ���X��ΏۂɌٗp�Ɛ��������T�|�[�g�����{����B �ȃG�l��Ƃ��ẮA���ߌ��Z���̔��㍂���O���i���͑O�X���j�̌��Z���Ɣ�r���Č������Ă���i�܂��͒��ߌ��Z���ɂ����đ������v�サ�Ă���j�l���Ǝ���܂ޒ�����Ǝ҂ɑ��A 1)���Ɣh���i200�Ёj 2)�ȃG�l���M�[�@�퓙�̓����̏����i�������x�z�F100���~�A�������F1/2�j���s���B ������Ƃ�_�ѐ��Y�̎��Ǝ҂ɋ��Z�ƌo�c�̗��ʂ���̎x�����s���Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������@�\�A������Ƃ�SDGs���i�Ɋւ�����Ԓ����̌��ʂ����\ ������Ɗ�Ր����@�\�́A������Ƃ� SDGs���i�Ɋւ���A���P�[�g�����̌��ʂ����\�����B SDGs�ւ̎�g�݂��x��Ă���Ƃ����钆���E���K�͊�Ƃɂ������g��ӎ���c������ƂƂ��ɁA���g�ނ��߂̉ۑ����҂���x��������邱�ƂŁA�e�x���@�ցA������Ǝғ�������̑Ή����j���������邽�߂̊�ƂȂ�f�[�^����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A������ƌo�c�҂Ȃ�2000�Ђ�����B��9���̒�����Ƃ� SDGs��F�m���Ă�����̂́A���e�܂ŗ������Ă����Ƃ͖�4���ɂƂǂ܂��Ă����B����x�������قǎ�g��Ƃ���������X���ɂ���B�������A�ǂ����Ă悢���킩��Ȃ��B��g�݂̎菇����b�g��������Ȃ��Ƃ������ۑ肪����B�܂��A�⏕������A��g����̌��\�Ɋւ���j�[�Y�������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��IPCC��6���]�����̑�3��ƕ���������\ ������2022�N4��4���ɉ���195�����̐��{�ɂ�菳�F���ꂽ�B���F���ꂽAR6/WG3���̐���Ҍ����v��iSPM�j�ɂ��ẮA���{���{�ɂ����ē��{�����쐬���A��ӌ�����߂ǂɌo�ώY�ƏȂ̃E�F�u�T�C�g�ɂČ��J����\��B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���@�@[�@2022/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���n�C���]�A�f�[�^�Z���^�[�̋d��9���팸�G�A�R���g�킸���x�E���x�Ǘ� �n�C���]�́A�ΐ쌧�u�꒬�̑�1�f�[�^�Z���^�[�ł̓G�A�R�����g��Ȃ����Ƃŋd�͂�90%�팸���Ă���Ƃ����B ���Ђ́A�����ő勉��GPU�i�摜�������j�b�g�j��p�f�[�^�Z���^�[�̉^�c���肪����B���n��Ői�߂Ă����2�f�[�^�Z���^�[�ł́A����܂ł̔p�M�����Ɋւ���m���ƌo�������ƂɁA�u�Ⴂ�I���������v�Ɩ��t�����i����p���������ɂ��p�M�����ɗD�ꂽ���z���̈ӏ����ƁA�O�C�ƃT�[�o�[�̔p�M�����p�������x�E���x�����Ɋւ��������\�������B ��1�f�[�^�Z���^�[�͋d�͂�90%�팸���A�d�͎g�p����������PUE�������ō�������1.1�����ƂȂ��Ă���Ƃ����i������v�f�[�^�Z���^�[��PUE���ς�1.4�j�B ��2�f�[�^�Z���^�[�͂���ɏ���PUE�ƂȂ錩���݁B�Ȃ��APUE�Ƃ́A�f�[�^�Z���^�[�S�̂̏���d�͂��T�[�o�[�Ȃǂ�ICT�@��̏���d�͂Ŋ��������l�ŁA1.0�ɋ߂��قnj����I�Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����}�s���Y�A�����̂ƘA�g���}�C�N���O���b�h���ƊJ�n�u�ЊQ�ɋ������v�� ��펞�Ɍn������̓d�͋������Ւf���ꂽ�Ƃ��Ă��A�d�C�̎����������\�ɂ���n��}�C�N���O���b�h���ߔN���ڂ��W�߂Ă���B ���}�s���Y�́A�n��}�C�N���O���b�h���Ƃ̑��e�Ƃ��āA�k�C�����O�S���O���Ƣ�ăG�l�ɂ��n�抈������Ɋւ��鋦�����������B���G�l���O���͔��d���i��i�o��40.8MW�A�~�d�r�e�ʖ�130MWh�j�Ŕ��d���ꂽ�ăG�l�����p���A�ЊQ���W���G���X�̋�����n��o�ς̔��W�Ɏ��g��ł���B �o�Y�Ȃ̒n��}�C�N���O���b�h�\�z�x�����Ƃ̈�Ƃ��āA 2020�N�x�}�X�^�[�v�������쐬�B�k�C���d�̓l�b�g���[�N�̑��z�d�Ԃ����p���A��d���ɓ�����v���ɓd�͋������s����V�X�e���̍\�z��}���Ă���B �d�g�݂Ƃ��ẮA���Ђ��ۗL���镗�͔��d�ݔ��ƒ~�d�r�����O�ϓd���ɐڑ��B�d�͋������Ւf���ꂽ�ۂ͓��ϓd����ʂ��āA�~�d�r�ɒ��߂��d�C��������ƂȂ鏬���w�Z�A�a�@�Ȃǂ̎�v����ꕔ�̈�ʉƒ�ɋ�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��30���̐����Ŕ]�̋L���͂Ə������x�̉��P���ʂ������鎺���̉��M������m�F �_�C�L���́A���ʓI�ȒZ���Ԑ����ɂ�鐶�Y������̎������߂����āA�d�C�ʐM��w�Ƌ����Łu�����̉����ɂ�����œK���M����v�̌�����i�߂Ă����B ������27���ɂ���Ɠ����܂ł̎��Ԃ��Z���Ȃ�X��������A�������26���ɒቺ�������10����ɂ̓m�����������i�����i�K2�j�ɓ��B�����B �N����3���O��27���ȏ�ɂ���Ɛ����[�x���Ȃ�X�������������̉����ɓK�������M����������o�����B 30���̐������Ԃł��N����̔]�̏������x�ƋL���͂����P������ʂ������邱�Ƃ��m�F�����B ���҂͉���^�R���[�L���O�X�y�[�X�wpoint 0marunouchi�x�̉����u�[�X�ɒu���ꂽ�x�b�h�ɐ�����Ԃ����m���鈳�d���̃o�C�^���Z���T�[��ݒu����ƂƂ��ɁA������Ԃɉ����Ċ����̋@�̐ݒ艷�x�𐧌䂷��u�����̌��V�X�e���v���\�z�������O��̃A���P�[�g���ʂ����ƂɎ���Ԃł̗L��������������؎������J�n����B �o�T�u�_�C�L���v |
|
|
| ���A�X�}�[�N�ƎO�䕨�Y�A���CO2�팸�̎��Ԓ����u�S���҂̖�9������Y�v �A�X�}�[�N�́A�O�䕨�Y�Ƃ̋��������Ƃ��āACO2�팸�Ɩ�����g�݂Ɍg����Ă���20��`60��̉�Ј��E�������̒j��400���ɑ��A���Y�Ɩ��ւ̎��g�ݎ��Ԃƈӎ��Ɋւ��钲�������{�����B �������ʁA�u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�Ɍ����A�������Ƃ�CO2�r�o�ʂ̍팸�����߂��Ă��闠���ŁA�e��Ƃ̒S���҂������̉ۑ��s��������Ȃ���Ɩ��Ɍ��������Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ����B CO2�팸�Ɩ��E���g�݂ł́A�S���҂̖�9�����A�w��������t���ėǂ��̂�������Ȃ��x�ƉB�����̒S���҂��u�E�Y�f��v��ԂɊׂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�����ɂ��ƁA2�l��1�l��CO2�팸�֘A�Ɩ����S�҂ŁA7���ȏオ�m���E����s�����ۑ�Ƃ��Čf�����B �܂��A�u�E�Y�f��v��Ԃ̒S���҂̂������悻2�l��1�l���AESG�ESDGs��G�l���M�[���B�Ȃǂ�CO2�팸�֘A�Ɩ����o���Ō��݂̒S���ɏA���Ă��邱�Ƃ����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ԏ�ɘH�ʔ��d�p�l���AMIRAI-LABO�Ɠ��{�p�[�L���O����g MIRAI-LABO�̑��z���H�ʔ��d�p�l������{�p�[�L���O�̉^�c���钓�ԏ��2022�N�t������؎������J�n����\��B ���؎����ł́A���{�p�[�L���O���ۗL���锪���q�s���̗��̒��ԏ�ƕ��ʒ��ԏ��2�J���ɑ��z���H�ʔ��d�p�l����ݒu����B1�J��������50m2�ȏ�̐ݒu�������ށB���p�l���̏o�͂�1���i��1m2�j������40W�ŁA���؎����ł�1�J��������2kW���x�̏o�͂�z�肷��BMIRAI-LABO�ɂ��ƁA���؎����̋K�͂ł͒��ԏ�̓d�͂����ׂĘd�����Ƃ͂ł��Ȃ����A�{�i�I�ȍ̗p���ɂ�100���ȏ�̓d�͗ʂ��m�ۂł��錩���݁B ���̂ق��ɂ��A���z���H�ʔ��d�p�l���ƃ����[�XEV�~�d�r��g�ݍ��킹�������^�G�l���M�[�C���t���uAIR�v�̗̍p����������BZEP�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�p�[�L���O�j�̎�����ڎw���Ƃ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���͂Ȃ܂邤�ǂ�S�X�܂ɍ������o�[�i���ڂ�Ŗˊ퓱��CO2�N��3��g���� ���M�K�X�́A���p���쏊�ƋƖ��p�������o�[�i���J���A�܂��A�}���[���Ɠ��o�[�i�𓋍ڂ����V�^��Ŗˊ�������J�������B �V���i�́A���C���@�����ǂ����o�[�i�𓋍ڂ��A�R�Č�̍����r�C���ʂ闬�H�E�r�C���̉��ǂɂ�����M���֔M���`���₷���\���Ƃ��邱�ƂŁA�]���i���M���������サ�ACO2���25���팸�����B�����i�́A�u�͂Ȃ܂邤�ǂ�v�S�X�܁i��460�X�܁j�ɏ������������B���̎��g�݂ɂ��A�u�͂Ȃ܂邤�ǂ�v�S�X�܂ł́A�N�Ԗ�3,000�g����CO2�팸���ʂ������܂��B ����J�������o�[�i�́A��C�̋�����������C�t�@���ɂ��@�B���C�ɕύX�����B�܂��A�R�Č�̍����r�C���ʂ闬�H�Ɣr�C�������߁A�����r�C������M���̋߂��𗬂��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�����r�C�̑ؗ����Ԃ����A�`�M���\�����コ���Ă���i�`�M���\�̌���ɂ��A�@����ӂ̉��x�͖�5���ቺ�j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����Ƃ̔r�o�ʌ����鉻���ăG�l�ؑւ܂ň�юx���^�G�l�`�F���W�ƃ[���{�[�h �G�l�`�F���W�́A�������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʎZ��E�����N���E�h�T�[�r�X���J���E����[���{�[�h�ƁA�Ɩ���g�_�����������Ɣ��\�����BGHG�r�o�ʂ̌����鉻�ƍăG�l�d�͂ւ̐�ւ��������X�g�b�v�Œ��邱�ƂŁA��Ƃ̒E�Y�f���ւ̎��g�݂��x������B �G�l�`�F���W�͖@�l�����̓d�͐�ւ��T�[�r�X�ɉ����A�ȃG�l���i�̓����A�ȃG�l�⏕���\���̃T�|�[�g��A�g���b�L���O�tFIT�Ώ؏��Ƃ����������l�؏�����舵���ăG�l�����x���T�[�r�X��W�J���Ă���B�[���{�[�h�Ђ̃T�[�r�X��GHG�r�o�ʂ������鉻���A�ăG�l�Ŕ��d�����d�̓v�����ւ̐�ւ��T�[�r�X������l�؏��̒Ȃǂ����B��Ǝ��g�̔r�o�ʂ݂̂Ȃ炸�A���ꂩ��J�������߂��Ă���T�v���C�`�F�[���r�o�ʂ̎Z��x�����s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������w�Z�̉���ɑ��z���p�l���ݒu�Z���ɂ͒~�d�r���_�ސ�E���l ���l�s�ɂ��ƁA�����K�X�����z�����d�ݔ����w�Z�̉���ɐݒu���A�w�Z���������ō��ꂽ�d�C���w������d�g�݁B �w�Z���͐ݒu�̂��߂̏�����p���S��ێ��Ǘ��������ɍĐ��\�G�l���M�[�𗘗p���邱�Ƃ��ł���B���^�]���̒��쐼���w�Z�̉���ɂ́A81���̑��z���p�l�����~���l�߂��Ă���B�ő�o�͂�28kW�ŁA�N��2��9��kWh�̔��d�������ށB���Z���g���d�̖͂�15%���܂��Ȃ���Ƃ����BCO2�͔N��12.8�g���팸�����Ƃ����B �Z���ɂ͒~�d�r���ݒu����Ă���B�ЊQ�ȂǂŒ�d�����ۂɂ͒~�d�r����̋����Ŗh�Ж�����ꕔ�Ɩ��A�R���Z���g�Ȃǂ�72���Ԓ��x�g�p�ł���Ƃ����B4������́A�T���Ⓑ���x�ɂȂNJw�Z���x�݂̊Ԃɔ��d�����d�͂��s���̑��̌����{�݂ɋ������Ă����B���N�x����11�Z�A���N�x���ɂ͍ő�65�Z�ɂ܂Őݒu�Ώۂ��L����\��Ƃ����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ��COOL CHOICE�[���c�[���u�n�����g���h�~�n���h�u�b�N�v���쐬 �J�[�{���j���[�g�����ւ̒���́A�Љ�o�ς�傫���ϊv���A�����𑣂��A��Ƃ̐��Y�������コ���A�Y�ƍ\���̑�]���Ɨ͋��������ݏo���`�����X�ł���A�܂��A���̃`�����X��n��o�ς̐����ɂ��Ȃ��Ă������Ƃ��K�v���B ���̑傫�Ȓ����̒��ŁA������Ɠ��̒n���Ƃ́A�R�X�g���S�̑�����[���`�F���W�ɂ�郊�X�N�̑��ʂ��ӎ������A�J�[�{���j���[�g�����ւ̒���𐬒��̋@��Ƒ����āA���Y���̌����V���Ƃ̑n�o�ȂǁA����̉҂��͂̋����ɂȂ��Ă������Ƃ��d�v���B �W�@�ւƂ̘A�g�ɂ��x���l�b�g���[�N���`�����A�J�[�{���j���[�g�����ɔ������Ɗ��̕ω����̏���I�m�ɒn��ɓ͂��A�n���Ƃ⎩���̓��Ɋ��Y���Ȃ���A��Ƃ̃C�m�x�[�V�����n�o�⎩���̂̒E�Y�f���ɂ��n�抈�����ɂȂ����g���T�|�[�g����B�n���Ƃ��x����x���@�ւƂٖ̋��ȘA�g�ɂ��A�x���̐��̍\�z��ڎw���Ă���B������A�X�Ȃ�x���l�b�g���[�N�̊g�[��}���Ă����B �o�T�u�֓��o�ώY�Ƌǁv |
|
|
| ���}�b�L���[�[���u�E�Y�f���[�h�}�b�v�v�A���z��192GW�A�~�d�r50GW�� �}�b�L���[�[�́A2050�N�E�J�[�{���j���[�g�����ڕW��B�����邽�߂̃V�i���I�����\�����B �d�͕���ł́A�ΒY�Η͔��d�����������K�X�Η͂ɒu�������A���q�͔��d�����ĉғ����������ŁA�Đ��\�G�l���M�[��61���A���f�E�A�����j�A���d��9���A�c������ΉΗ͂�CCS�iCO2�����E�Œ�j�Řd���Ƃ����B�ăG�l�̎�̂ƂȂ鑾�z���ƕ��͂͌��݂�3�{�ƂȂ�275GW�܂Ŋg�傷��B�����킯�́A���z��192GW�A�m�㕗��70GW�A���㕗��13GW�ɂȂ�Ƃ����B ���z���ƕ��͂�275GW�Ƃ����e�ʂ́A�n���w�I�A�Љ�I�Ȑ�������������B���z���̏ꍇ�A�|�e���V������278GW�ɒB���邪�A�R�x�n�т������Ȃǂ̐����192GW�ɗ��܂�B ���z���E���͂̔䗦�����܂邱�ƂŁA�d�͌n���̈���I�ȉ^�p�ɒ~�d�r�̖��������܂�A2050�N�ɂ͐V����50GW����~�d�r�̊m�ہi�����d�ʂ�9���j���K�v�Ɨ\�z�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ��IPCC���u�C��ϓ����L�͈͂Ɉ��e���v�K���́u���E�v���w�E ���A�̋C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�́A�C��ϓ��̉e����K���E�Ǝ㐫�ɂ��āA�ŐV�̉Ȋw�I�m�����܂Ƃ߂���6���]�����iAR6�j��2��ƕ�����iWG2�j�̐���Ҍ����v��iSPM�j�����\�����B �����ł́A�l�N���̋C��ϓ������R�̋C��ϓ��͈̔͂��āA���R��l�Ԃɑ��u�L�͈͂ɂ킽�鈫�e���Ƃ���Ɋ֘A���������Ƒ��Q�������N�����Ă���v�Ə��߂Ė��L�����B ���ł́A�n�����g���̐i�s�ɔ����A�����Ƒ��Q���������A�����̎��R�E�Љ�V�X�e�����u�K���̌��E�v�ɒB����\�����������Ƃ��������B �܂��A�n�����g�����Z���̂�����1.5���ɒB������Ǝw�E�B�u�����̋C��n�U�[�h�̕s���ȑ����������N�����A���Ԍn�Ɛl�Ԃɑ��ĕ����̃��X�N�������炷�\���������v�ƌx����炵���BIPCC�ł͍���A4���̑���ŁAAR6��3��ƕ�����i�ɘa��j�����F�E����A9���̑����AR6�����������F�E�̑�����\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�L���b�v���g���[�h���x�i���v����ԁj�ɂ�����CO2���ʍ팸���ʂ\ �����s�́A��K�͎��Ə��ɑ���u�������ʃK�X�r�o���ʍ팸�`���Ɣr�o�ʎ�����x�i�L���b�v���g���[�h���x�j�v���v����Ԃɂ����đS�Ă̑Ώێ��Ə������ʍ팸�`����B���������Ƃ\�����B �����x�́A��K�͎��Ə�(�O�N�x�̔R���E�M�E�d�C�̎g�p�ʂ��A�������Z�ŔN��1,500kL�ȏ�̎��Ə�)��CO2�r�o�ʂ̍팸�`�����ۂ����E���̓s�s�^�L���b�v�E�A���h�E�g���[�h���x�B�Ώێ��Ə��͎���̏ȃG�l�����ɂ���č팸����ق��A�r�o�ʎ�������p���đ��̎��Ə��̍팸�ʁi�N���W�b�g�j�����擾���ċ`���𗚍s���邱�Ƃ��ł���B�ΏۂƂȂ��Ă����̂́A��1200���Ə��ŁA����27�N�x����ߘa���N�x�̑��v����ԂŁA�������ʃK�X��17%�i�܂���15%�j�팸���邱�Ƃ��`���t�����Ă����B�Ώێ��Ə��̖�85��������̑�ɂ���č팸�`����B�����A��15���̑Ώێ��Ə����N���W�b�g�������p���č팸�`���𗚍s���A�S���Ə��ŋ`�������s���ꂽ�Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����dEP�A���K�͎��ƎҌ����Ɂu�X�}�[�g���[�^�[�v���p���ȃG�l�A�h�o�C�X �����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��l�̈ړ��⊈���̐����Ȃǂɂ��A����̒���⊴���h�~��̕��S�Ȃǂ̉e�����Ă��鎖�Ǝ҂��x������uTEPCO�o�c�T�|�[�g�v�̎��g�݂Ƃ��āA�u�X�}�[�g���[�^�[���|�[�g�v���J�n�����Ɣ��\�����B �u�X�}�[�g���[�^�[���|�[�g�v�́A�d�͒����������̒m�������p���A���K�͎��ƎҌ����ɒ���B�֓��𒆐S�Ƃ������H�X�⏬���X�܁A�a�@�A�h���{�݂Ȃǂɑ��ďȃG�l���M�[�̃A�h�o�C�X�����B��̓I�ɂ́A�ڋq�̃X�}�[�g���[�^�[��30�����Ƃ̓d�C�g�p�ʃf�[�^�����p���A�ݔ����̎g�p������A�ʏ�ƈقȂ�d�C�̎g�p���������鉻����B�܂��A�d�C�̎g�p�ʂ����E����C���Ƃ̑��ւ�c���ł���B�ȂǁA�ȃG�l���M�[�̃A�h�o�C�X���\���Ƃ����B�܂��A�N���ɂ́A�X�}�z�ɂ��d�C�̌����鉻��ȃG�l�R���T���Ȃǂ��[��������Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������r���̏ȃG�l�|�e���V�������v�c�[�������\ �������r���̏ȃG�l�|�e���V�������v�c�[���́A���݂̏ȃG�l�|�e���V�����i�ȃG�l�]�n�j���ǂ̒��x���邩���v�Z����B �ݎ������r���A���Ѓr���̏ȃG�l�|�e���V�������v�Z���邱�Ƃ��ł���B����̏ȃG�l�v������������ŁA�����{�̏ȃG�l��̌��ʂ��A�ő�5�P�[�X�A�Z���Ԃœ����Ɍv�Z�ł���B �o�T�uECCJ�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�ACO2�Z���T�[���ڃ_�N�g�p���C��u�@��A�g�^�C�v�v�V���� ���Ђ́ACO2�Z���T�[���ڃ_�N�g�p���C��̐V���i�Ƃ��āu�@��A�g�^�C�v�v��2022�N5���ɔ�������B���Ѓp�b�P�[�W�G�A�R���⊷�C��Ƃ̘A�g�^�]���\�ɂ������ƂŁA�Z�{�݂𒆐S�Ƃ���������Ԃɂ�������K������ƌ��ʓI�Ȋ��C�̗�������������B �_�N�g�p���C�CO2�Z�x�̏㏸�����m���A���C���ʂ���������ƃp�b�P�[�W�G�A�R���������ŋ̉^�]���������邱�ƂŁA�����ϓ���}���B�����̉��K������ƌ��ʓI�Ȋ��C�𗼗��B������CO2�Z�x���ݒ�l�����ꍇ�ɂ́A���C���ʂ��������Ă��邱�Ƃ��p�b�P�[�W�G�A�R���̃����R����A�v���ɕ\���B CO2�Z���T�|�ڋ@��Ƃ̘A�g�ɂ�銷�C���ʐ���@�\��V���ɓ��ځBCO2�Z�x�ɉ����Ċ��C��m���A�g���Ċ��C���ʂ������Ő�ւ��A���C�ݔ���������^�]���Ă����ԂŁA������CO2�Z�x�ɉ����������I�Ȋ��C�������B CO2�Z���T�[���ڊ��C��F82,300�~ �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��NTT�f�[�^�AGHG�r�o�ʂ̌����鉻�����x�������ƌ����ɐV�T�[�r�X�J�n NTT�f�[�^�́A�Љ�S�̂ł̃J�[�{���j���[�g���������Ɍ����āA�O�H�d�H��AI�\�����[�V�����uENERGY CLOUD�v�����p�����A�����ƌ����O���[���R���T���e�B���O�T�[�r�X�̒��J�n�����B �O�H�d�H�́uENERGY CLOUD�v�́A�����v�����g�̃��A���^�C�������f�[�^����A�^�]�̃f�W�^���c�C�����f�����쐬���邱�ƂŁA���x��GHG�r�o�ʂ̉�������������B ����A���V�X�e�����ANTT�f�[�^�̐����ƌ����̃O���[���R���T���e�B���O�T�[�r�X�Ɋ��p���邱�ƂŁA���i�P�ʂɗ��܂炸�A���Y�����A���C�����Ƃ�CFP�iCarbon FootPrint�j�̔c�����\�ƂȂ�B �܂��A�f�W�^���c�C�����f�����g����AI�����p���AGHG�r�o�ʍ팸�̂��߂̐ݔ������v��̗��Ă�Y�Ɨp���Ɨp���d�̉^�]�v����œK�����ė]��d�͂ݏo���A�V�d�͎��Ǝ҂ƘA�g���邱�ƂŁA�V���Ȏ��v���Ƃ���Ȃǂ̌������x������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���E�F�U�[�j���[�YAI�ő��z�����d�ʗ\���A�C���o�����X���X�N�ጸ���x�� ���Ђ́A�C�ۃf�[�^�E���̓T�[�r�X�uWxTech�i�E�F�U�[�e�b�N�j�v�ɂ����āA�d�C���ƎҌ����ɁA1km���b�V���̍��𑜓x�ȓ��˗ʗ\����p�������z�����d�ʗ\���f�[�^��API���J�n�����Ɣ��\�����B AI��p�������z�����d�ʗ\���ɂ��A�C���o�����X���X�N�̒ጸ���x������B���Ђ͓��˗ʗ\�����f���̉��P�ɂ���Ĉ�ʓI�ȗ\���Ɣ�ׂė\�����x��11%���コ���A���̓��˗ʃf�[�^��p���������x�ȑ��z�����d�ʗ\�����f�����J�������B���T�[�r�X�ł́A�d�͎���ɓK����30�����Ƃ̑��z�����d�ʂ̗\���f�[�^��72���Ԑ�܂ŒB�\�����@�́A���d���̈ܓx�o�x�̂ق��A�\�[���[�p�l���̏o�͂�ݒu�p�x�ȂǁA���d���̏������ƂɃs���|�C���g�ȑ��z�����d�ʗ\���f�[�^���Z�o����u�������f���v�ƁA�ߋ��̔��d�ʎ��уf�[�^�ƋC�ۃf�[�^��AI�Ŋw�K�����邱�Ƃł���ɍ����x�ɗ\������u���v���f���v����I���ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������A���f���߉\�ȍ��������������W���[���J��CO2�r�o50%�ȏ�팸 �����́A���f���܂ލ����K�X����A���f��I��I���������ɓ��߉\�ȍ����q���������W���[�����J�������Ɣ��\�������Ђ͍���A�t�Z���iRO�j���Ŕ|�����Z�p�����p���A���f�e�a���ޗ������邱�Ƃɂ��A�E�\�������x�ɐ��䂵����������V���ɊJ���B���̊J��������������p�������f�����ɂ����āA���E�ō����x���̓��ߐ��f���x98%�����������B ����܂œ��ߐ��f���x�����߂邽�߂ɂ͕�����̂�߂��K�v���������A�����W���[����1��̕����ŏ��x�����߂邱�Ƃ��ł��A�]���̕��������W���[���Ɣ�ׁA�����������팸�ł��邾���łȂ��A�ȃG�l���M�[�����\�ƂȂ����B���Ђɂ��ƁA���Z�p��CO2�r�o�ʂ�50%�ȏ�팸���邱�Ƃ����҂ł���Ƃ����B ����ɁA���H�ނ̗�����R��ጸ���邱�ƂŁA�]�����W���[���Ɣ�ׂāA2�{�ȏ�̍����ʐω������������B����ɂ��A���W���[��1�{������̐��f���ߐ������サ�A�K�v�ȃ��W���[���{����50%�ȉ��ɍ팸�ł���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���x�m�t�C�����ƃ_�C�L�����@�̐V���ȐÉ����Z�p�����p�� �@�̐V���ȐÉ����Z�p�́A�x�m�t�C�������A�g���͒ʂ��A���͒ʂ��Ȃ��h�Ƃ����R���Z�v�g�ŊJ�������ʕ��h���ނɂ��É����Z�p���B�_�C�L�����A�{�Z�p�̎��p���Ɍ����āA�����E���C�@�\�t���G�A�R���ɒʕ��h���ނ������������ʁA�����E���C�ʂ��m�ۂ��Ȃ���^�]���̑�������20���ȏ�ጸ���邱�Ƃ��ł����B �x�m�t�C�������A���^�}�e���A���i�g�����������ȍ\���̂Ŏ��R�E�̕����ł͐������Ȃ��g��������l�H�����j��p���Č��̔g���𐧌䂷��Z�p�i���^�}�e���A���Z�p�j����������ɉ��p���Ēʕ��h���ނɂ��É����Z�p���J���B����܂ō���ł������A���C�ɕK�v�Ȓʕ��ʂ̊m�ۂƂ���ɂ���Ĕ������鑗�����̒ጸ�̗��������������B �ʕ��h���ނ́A�L�ш�̖h�����\�Ƃ��A�h�����ʂ́A��10dB�ጸ�����؍ς݁B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���x�m�s������ق̃G�l���M�[�������ECO2�r�o�ʍ팸�ɑ傫���v�� �W�����\���R���g���[���Y�́A���Ђ̃A�W�A�����m�n��ɂ�����ESG�ڕW����уl�b�g�E�[���E�J�[�{�������Ɋւ��鎖��\�����B �x�m�s������ك��[�V�A�^�[�͊J�Ƃ���25�N�ȏオ�o�߂��A�V���������ݔ��̏ȃG�l�Ɖ^�c�̌�������ړI��ESCO���Ƃ����p�������C�H�������{�����B���Ђ�15�N�Ԃ̌_����Ԃɘj��ESCO���Ƃɂ����āA�r���I�[�g���[�V�����V�X�e�����͂��߁AAHU�i�G�A�n���h�����O���j�b�g�j�C���o�[�^�[���Ɩ{�̂̃I�[�o�[�z�[���ACO2����V�X�e���A�������M���ȂǑ��푽�l�ȏȃG�l�ݔ��A�\�����[�V�����������B���C�O�Ɣ�r���āA1���G�l���M�[�ʂ�39%�ACO2�r�o�ʂ�42%�A�G�l���M�[�R�X�g��40%�팸�ł��錩���݂��Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��AI�����p��������œK���Z�p���J���`�ėp���̍���AI���p�ŃT�X�e�i�r���e�B����ց` �V���{�́A�����z�K�������ȑ�w�Ƌ����ŁA�Ȑl���ƏȃG�l�Ɋ�^����AAI�����p��������Z�p���J�������BAI�����p���邱�Ƃ�CO2�̔r�o�ʍ팸�Ɖ^�]�R�X�g�팸�������ł��A�T�X�e�i�r���e�B����ɂȂ���B �V�݂ł́A���^�]���������������A�l�̎�������邱�ƂȂ��^�]�ɉ����č����x�ȋ��䂪�\�ƂȂ�B���^�]���̏ȗ͉��ɉ����A�^�]�p�����[�^�̍œK���Ǝ����`���[�j���O�ɂ���āA�ȃG�l���ɂ���^����B������́A���K���̌���Ƒ���@��̏��Ղ�}����Ȏ������ɂ��v������B�����̋ݔ���AI�𓋍ڂ����ėp���^�R���s���[�^���Ȃ������ŁA��y�����[�Y�i�u���ɓ����\�ƂȂ�B2022�N�x����̎��p�W�J��\�肵�A����J�͂̒ጸ��ȃG�l���𐄐i����Љ�j�[�Y�ɓK������Z�p�Ƃ��Ē�Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���č��̑��z���A���d���Ɨp�u�I�t�T�C�gPPA�v�̌_�i���}�ቺ �č��ɂ����锭�d���Ɨp�̑��z�����d�s��Ɋւ���ŐV�̕��̓��|�[�g��ă��[�����X�E�o�[�N���[�����������iLawrence Berkeley National Laboratory�FLBNL�j�����\�����B ���̃��|�[�g�ɂ��ƁA���d���Ɨp�̑��z�����d����PPA�ɂ�锄�d���i�́A�ߋ�10�N�Ԃŕ��ϖ�85�����ቺ�����Ƃ����B���˗ʂɌb�܂�A���z�����d�̓������ł��i�č������̃v���W�F�N�g�ɂ�����PPA���i�́A��20�h��/ MWh�i��2�Z���g/kWh�j�܂ʼn��������B����ɁA���݁A�č��̑����̒n��ŁA���z�����d��PPA���i�͕��͔��d���������ɂȂ��Ă���Ƃ����B���̃��|�[�g�́A�d�͉�Ђ̊Ԃŕ��y���Ă���u�t�B�W�J���i�����I�jPPA�v���ΏہB����ɁA�~�n�O�ɂ���ăG�l����d�͂��w������u�I�t�T�C�g�^�v���قƂ�ǂƂ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����R�G�l���c�A�u�d�͒��B�K�C�h�u�b�N��5�Łi2022�N�Łj�v�����\ �����d�C���Ǝ҂����R�G�l���M�[100���̓d�͂����Ŕ̔�����悤�ɂȂ����B���̈���ő��z�����d�̃R�X�g���ቺ���āA���d�����d�͂����Ə���郁���b�g�����܂��Ă���B���l�̗��R����d�͂��_��ōw������R�[�|���[�gPPA�i�d�͍w���_��j���̗p�����Ƃ��č��≢�B�ɑ����ē��{�ł������Ă����B ���̃K�C�h�u�b�N�ł́A���R�G�l���M�[�̓d�͂B����4��ނ̕��@�i���Ɣ��d�A�������j���[�A�؏��A�R�[�|���[�gPPA�j�ɂ��Ď��������������Ă���B��5�łł́A���ꂼ��̒��B���@�̓��������ƂɁA���B�v��̍���菇��d�͂̑I�������̓I�Ɏ������B��i�I�Ȋ�Ƃ��d������I����Ƃ��Ēlj�����n��v���ɂ��Đ������Ă���B����Ɏ��R�G�l���M�[100���̓d�̓��j���[��Ώ؏��̍ŐV�����������B�R�[�|���[�gPPA�ɂ��Ă�3��ނ̌_��`�ԁi�I���T�C�g�A�t�B�W�J���A�o�[�`�����j�̃����b�g��ۑ�𒆐S�ɓ��e�����V�����B |
|
|
| �����{�A�d�͕s�����ɑ�K�͒~�d�r���p�ցc�@�����Łu���d���Ɓv������ ���{�́A���z���╗�͂Ƃ������Đ��\�G�l���M�[���d�̕��y�ő����������܂���K�͂Ȓ~�d�r�ɂ��āA�d�͂̈��苟���Ɍ������V���[����݂���B�d�C���Ɩ@�Œ�߂�u���d���Ɓv�Ɉʒu�t���A�d�͂��s�������ꍇ�Ɏ��Ǝ҂ɋ��������߂�ȂǁA����֘A�@�ւ̉e���͂����߂�B �d���@�̉����Ă�ʏ퍑��ɒ�o�B�P�Ƃʼn^�p������K�͒~�d�r���u�~�d���i���́j�v�Ɩ��t����B�d���@�͏�����p�ɋ����ł���d�͂��P��kW�ȏ�̔��d�{�݂d���ƂƂ��Ă���A�~�d���ɂ��������K�p����B���d���Ƃɕ��ނ����ƁA���Ǝ҂͉Η͔��d���ȂǂƓ��l�ɍ��֍H���v����o����K�v������B���̂��������ꍇ�́A�����߂���B���͑S���̔��d�\�͂�c���ł���悤�ɂȂ�B�����������⏋���œd�͂̕s�������O�����ꍇ�́A�d�͉�ЂȂǂł���F�@�l���~�d���ɓd�͂���������悤�w���ł���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����f�E�A�����j�A�A�u�G�l�v�Ɉʒu�t���^���x���@�����Ă� �o�ώY�ƏȂ́A���f�E�A�����j�A���G�l���M�[�����\�����x���@��̔G�l���M�[���Ɉʒu�t���A�ʏ퍑��ɒ�o�\��̉����Ăɐ��荞�ވӌ����B��_���Y�f����E�����iCCS�j�t���Η͂����x���@��Ɉʒu�t���A���p�𑣂��B �������ɓ�_���Y�f��r�o����O���[���f�E�A�����j�A���A�R�Ă̏u�Ԃ�CO2���o���Ȃ����Ƃ���G�l���M�[���ɒ�`����B�Γd���䗦�g44���ȏ�h�����߂錻�s�ڕW�����グ�̗L���́u���x���@�^�p�̒��Ō�������v�Ƃ��Ă���B ���x���@�̂ق��A�d�C���Ɩ@�A�ȃG�l�@�AJOGMEC�@�A�z�Ɩ@�𑩂˂��u����I�ȃG�l���M�[�����\���̊m����}�邽�߂̃G�l���M�[�̎g�p�̍��������Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���āv���A�����}�o�ώY�ƕ���ɒ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���h�C�c�r�o�ʎ�����x�ɂ��125�����[���̎��v���L�^�A�V���ȋC��ϓ���Ɠd�͗����̌y���ɓ��� �h�C�c�����iUBA�j�́A���B�r�o�ʎ�����x�iEU-ETS�j�ɂ��A2021�N�A���{��53�����[���̃I�[�N�V�������v���A�����2021�N�ɊJ�n�����M�E�^�A�����ΏۂƂ��������r�o�ʎ�����x�inEHS�j�ɂ�����؏��̔��ɂ���72�����[���̎��v�����Ƃ����\�����B �����x�ɂ��2021�N�̎��v�͍��킹�Ė�125�����[���ƂȂ�A�����́A�G�l���M�[�E�C�����iEKF�j�Ƃ��ĉ^�p�����B����ł́A�Đ��\�G�l���M�[��G�l���M�[�������A�����O�̋C��ی�v���W�F�N�g�A�d�C�����ԂȂǂ̋C��ی����x�����Ă���B�܂��A2021�N�́A�����r�o�ʎ�����x�̎��v����47�����[�����������ʂ��čĐ��\�G�l���M�[�@���ۋ��̌y���Ɏg���A�d�͗����̍����}�������������B �o�T�uEIC�j���[�X�v |
|
|
| �����̒f�M�������߂�u�^��K���X�v��JIS���萫�\�����鉻�ŕ��y���i �o�ώY�ƏȂ́A���̒f�M����傫�����߂�u�^��K���X�v�ɂ��āA�f�M���E�����̏�ԁE�όȂǁA���̕i�����m�ۂ��邽�߂̎����E�������@���ڍׂɐ��荞��JIS�𐧒肵���Ɣ��\�����B �^��K���X�́A2���̃K���X�ɋ��܂ꂽ��Ԃ�^���ԂɌ������邱�ƂŔM���Ւf���邽�߁A�u���ɂ̒f�M���\�����K���X�v�Ƃ��Ă�Ă���B ���Ȃ́A�^��K���X�̎s��ł̐M���Ɗg���B�����A�ȃG�l���M�[�𐄐i���Ȃ���A�Ă͗������A�~�͒g����������ۂ��Ƃ̂ł�����K�E���N�Ȑ����̎����Ɋ��҂��AJIS R 3225�𐧒肵���B ��ȃ|�C���g�̔M�ї����w�K���X�Ɋւ��鍑���K�i�iJIS R 3209�j�̍ō������ł���M�ї���1.1W�^m2K�ȉ����A����ɍ����f�M������0.7W�^mm2K�ȉ���ݒ肵���B�����x�̎������@��V���ɊJ�������B�ό��������Ƃ��āA�Ή����ۋK�i���̗p�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���u�A�����j�A�����v�ɂP�O�O�N�Ԃ�̊v���^�߂a�g�a���K�͂ŃA�����j�A���� ���L���p�r�Ŏg����A�����j�A�̎�Ȑ������@��100�N�ȏ�O�Ƀh�C�c�Ő��܂ꂽ�n�[�o�[�E�{�b�V���@�͔_�Ɛ��Y�̔���I�Ȍ���ɍv�������B ����A��C���̒��f�Ɛ��f��������200.350�C���A500����K�v�Ƃ��邽�߁A�G�l���M�[���ׂ������A��K�̓v�����g��K�v�Ƃ���B ��BHB���J�������̂́A���H��̍ז싳�������������uC12A7�G���N�g���C�h�G�}�v��p���āA�u�ቷ�A��C���v�ŃA�����j�A������v�����g���B �u�A�����j�A�̉��i�̂قƂ�ǂ͗A���ƕۑ��ɃR�X�g���₵�Ă���v�B ���ہA�A�����j�A���Y�͏����A�G�l���M�[���̓V�R�K�X���Y�n�ɏW�����Ă���B���p�n��Ő��Y���邱�ƂŁA�A���ɂ������_���Y�f���팸�ł���B���łɃp�C���b�g�v�����g�ŔN��20�g���̐��Y�\�͂������Ă���B���̑f�A�����ƁA���{�X�D�Ȃǂƒ�g�B �o�T�u�j���[�X�e�b�N�v |
|
|
| ��������GE�A�J�i�_�ŏ��^���q�F���u�E�Y�f�v�̗��_���� ������GE�̌��q�͎��ƍ��ى�Ђ́uGE�����j���[�N���A�E�G�i�W�[�v�́A�]���̌����������K�͂ȏ��^���W���[���F�iSMR�j���J�i�_�̓d�͉�Ђ�������Ɣ��\�����B ���n��Ƃ����p��SMR������̂͏��߂ĂƂ����B2028�N�̊������߂����Ă���B�ő�4��݂��錩�ʂ����B2022�N���܂łɃJ�i�_���ǂɌ�����\������B�H��őg�ݗ��Ă����̂��^��Őݒu����B ��ɉ��ĂŊJ�����i�ށB���{��Ƃł�GE�����̂ق��ɎO�H�d�H�Ƃ��J�����悤�Ƃ��Ă���BIHI���č��̐V����Ƃ̎��ƂɎQ�����Ă���B��Ƒ��́u�E�Y�f�v�ɂ��Ȃ����SMR�̗��_���������邪�A���ː��p�������o�邱�Ƃ͏]���̌����Ɠ������B ���̃G�l���M�[��{�v��ɂ́A������̌����J���ւ́u�ϋɓI�x���v�����荞�܂ꂽ�BSMR�̊J���Ȃǂ������������̂��B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����㊷�C��u���[�t�t�@���v�̏ȃG�l�`�t�@���a 105�p�̑�^�^�C�v���� �t�@���a 105�p�̑�^�^�C�v�uRF-42E�v��2021�N12�����lj���������B�W���`�Ɣ�r������d�͂�26.49���ጸ�A������1.9dB�ጸ�����������B �ȓd�́E�ᑛ������������\���t�[�h�ɐV�^�K�C�h���A�I���t�B�X���Ƀx���}�E�X�\�����̗p���A���̗�������Ȃ߂炩�ɂ����B��ȗp�r�F��ʍH��A�q�ɂȂǂɂ�����r�C�B����d�́i�d�C�����j�ጸ���d�������ꍇ��A���Ƃ��߂��ȂǑ��������ɂȂ�n��ł̂��g�p�ɍœK�B�艿 1,048,000�~�i����ŕʁE�����ʁj�B �o�T�u���q���쏊�v |
|
|
| �����j�f�[�^�łb�n�Q�r�o�Z��^�O��Z�F��A�V�T�[�r�X�ɓK�p �������x��A�Y�r���Ȃ�4�Ђ́A��Ɗ����ɔ���CO2�r�o�ʂ𑪒肷��N���E�h�V�X�e�����J�������B �X�}�[�g���[�^�[�ƃK�X���[�^�[�œ���ꂽ�f�[�^����CO2�r�o�ʂ������ŎZ�肷��V�X�e���ŁA�O��Z�F��s�����ЃT�[�r�X�ւ̊��p������BCO2�r�o�ʑ���T�[�r�X�Ƃ��āA�����ɂ���50�Ђ�ΏۂɎ����^�p���n�߂�B���Ђ̓V�X�e���̉��P�_��o���A2022�N5������{�i�W�J����v��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���O�H�����A���[�\����3600�X�ɍăG�l�����A�����ő勉�I�t�T�C�gPPA�� �O�H�����ƃ��[�\���́A�����ő勉�̃I�t�T�C�gPPA�i�d�͍w���_��j�ɂ��ăG�l�����[�\���X�܂�������Ɣ��\�����B �E�G�X�g�z�[���f�B���O�X���V���ɖ�45MW�̑��z�����d�ݔ������݁B�O�H���������[�\���X�܂ɍăG�l����������B2022�N4������֓��b�M�n��E���C�n��̖�3,600�X�܂ɋ������J�n����\��B���̌�A���v��8,200�X�܂ւ̓�������������B ���[�\���́A1�X�ܓ������CO2�r�o�ʂ�2013�N�Δ��2030�N��50���팸�A2050�N�ɂ�100���팸���邱�Ƃ�ڎw���Ă���B�E�G�X�g�O���[�v�ƎO�H�����̋��Ƃ́AAmazon�����̍ăG�l�����ŃR�[�|���[�gPPA�i�������d�_��j��������Ă���B22MW�̑��z�����d���A�}�]�����w������Ƃ������́B���̑��z�����d�v���W�F�N�g�́A��s���Ɠ��k�n���ɂ����Đi�߂��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Đ��G�l���M�[�����A����1.2���ЂɖڕW������`���t���� ���{�́A������1��2000�ЂɁA���z���ȂǁA��_���Y�f��r�o���Ȃ��G�l���M�[�̓����ڕW�̍�����`���t������j���ł߂��B���ΔR���ɑ����čĐ��\�G�l���M�[�̊��p�𑣂��A�E�Y�f�Ɍ�������Ƃ̎��g�݂��㉟������B �ΏۂɂȂ�̂́A�G�l���M�[�̎g�p�ʂ������Ɋ��Z���āA�N��1500�L���E���b�g���ȏ�̊�ƁB���N�̒ʏ퍑��ɁA�ȃG�l�@�̉����Ă��o����B�ŒZ��2023�N�t�̎{�s��ڎw���B �Ώۊ�Ƃ́A�G�l���M�[�̎g�p�ʂɐ�߂�Đ��G�l�Ȃǂ̊������������ڕW���߂�K�v������B��Ƃ͔N�P��A���{�Ɏ��g�ݏ����B�G�l���M�[�̎g�p�ʂ��v�Z���鎞�ɁA�d�͎g�p�̃s�[�N�����炷���g�݂������]������B�Đ��G�l�̋����ɗ]�T�����鎞�ԑтɓd�C���g���A�g�p�ʂ��]����菭�Ȃ����Z�ł���B ���Ƃ��ŏ�ʂ́u�D�ǎ��Ǝҁv�ɂȂ�ƁA�֘A����⏕�����\���ł���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���u�h�C�c�̒E�Y�f�헪���R�G�l���M�[�g��ƒE�ΒY�E�E�����ɂނ�������Ɩ@���� �h�C�c�́A�����P���������ŁA2022�N���ɒE�����̊����A�x���Ƃ�2038�N�ɂ͒E�ΒY�������A2030�N�ɂ͎��R�G�l���M�[���d�ő��d�͏����65�����܂��Ȃ����Ƃ�@���������B����ɁA2045�N�ɂ͉������ʃK�X�r�o�������[���Ƃ���C���B����ڎw�����Ƃ����߁A�����̖ڕW��@���������B ������2021�N9���̃h�C�c�A�M�c��I�����o�āA11���ɁA�Љ��}�iSPD�j�E�̓}�E���R����}�iFDP�j��3�}���A������\�����B ���̘A������ł́A�E�ΒY�̊����������u���z�I�ɂ́v2030�N�ɑO�|�����ƁA2030�N�Ɏ��R�G�l���M�[�ő��d�͎��v��80������������ȂǁA�����P�������ȏ�ɖ�S�I�ȋC��ϓ��f�����Ă���B �o�T�u���R�G�l���M�[���c�v |
|
|
| ���u�o�[�`����PPA�v�����ւցA�o�Y�Ȃ������X�^�[�g �Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�𗘗p���Ȃ���FIT���z�����d������̓d�͂��A��Ƃ������Œ��B����_������ԁu�R�[�|���[�gPPA�v�ɂ́A�ăG�l�d�C�Ɗ����l����̂Ƃ��Ď������u�t�B�W�J��PPA�v�ƁA�ăG�l�d�C�Ɗ����l�����Ď������u�o�[�`����PPA�v������B�C�O�ł̓o�[�`����PPA��PPA�X�L�[���̎嗬�ɂȂ��Ă���B �o�[�`����PPA�́A���v�Ɗ�Ƃ��lj����̂�������l������I�Ɋm�ۂł������A���ۂ̓d�͒��B�ɏ_�������_��A���d���Ǝ҂ɂƂ��Ă��ăG�l�d�C�̃o�����V���O���e�ՂɂȂ�Ȃǂ̗��_������B ��̓I�ɂ́A��FIT�ăG�l����̓d�C���R�[�|���[�gPPA�Ŏ�������ꍇ�A���̗v�������A�ăG�l���d���Ǝ҂Ǝ��v�Ƃ̊ԂŁu��FIT�ăG�l�؏��v�̒��ڎ����F�߂�B���̍ہA�؏��̃_�u���J�E���g��������邽�߂ɔ�FIT�ăG�l���d���Ǝ҂Ǝ��v�Ƃ̑o�������{���d�͎�����ɏ؏��̌������J�݂���Ȃǂ̎d�g�݂���Ă��ꂽ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u����45���m�㕗�͂Ŕ��d�v���{���{�̑�_�ȖڕW�ɊC�O�������_���𐂂炷���P ���{�͉Η͔��d��7�������߂�B���{�����ڂ����̂��u�m�㕗�́v���B�m�㕗�͔��d�̋K�͂�2030�N�܂ł�1000���A2040�N�܂ł�3000���`4500����W�Ƃ����ڕW�����߂��B�����Ɋ��Z�����45��ɂȂ�B�������A���O���ׂ��_�́A���B�̑�����ɂȂ鋰�ꂪ����B ���ł������̌o�ϕ����̌��ƈʒu�t����C�M���X�͐ϋɓI�ɓW�J���낤�B �C�M���X�́A2000�N��������m�㕗�͂ɒ��͂��鐭��𐄐i���Ă����B�����_��2,200��ȏ�ŁA�d�͂�1����d���B�m�㕗�͂̔��d�ʂ͐��E�g�b�v�i10,424MW�j���B(���{��10�ԖځA85MW)�B���E�L���̃R���T���e�B���O��G���W�j�A�����O�A������Ƃ�L����B �����ł́A2019�N�ɓ������I�����A���Ԃ��܂ߊ��S�ɓP�ނ����B �܂��A�Œ艿�i���搧�x�̓K�p���z�肳���B���承�i��1kWh������20�~��㔼�ȏ�ɂȂ錩���݂��B�����20�N�Ƃ��������ۏ̃r�W�l�X���f�����B �o�T�u�v���W�f���g�v |
|
|
| �����f�E�A�����j�A���d�̉ۑ�F���ΔR���̌@���g�傳���A�ΒY�ELNG�Η͂�����������I�����\ ���{�́u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v��\�������B���́A���̓��ƍB���{�́A2050�N�Ɍ�������̓I�Ȍv���ݒ肵�Ă��Ȃ���A�V���ȋZ�p�����邱�Ƃ�CO2�r�o�̑傫�ȉΗ͔��d�A���ɐΒY�Η͔��d���ێ����悤�Ƃ��Ă���B ��n�߂ɐΒY��K�X�Ƃ̍��āA��͐��f�E�A�����j�A�̐�Ă�CO2�팸��ڎw���Ƃ��Ă���B�������A���f�E�A�����j�A�̂قƂ�ǂ́A����A�W�A��k�āA���V�A�A�I�[�X�g�����A�ȂǂœV�R�K�X��ΒY�i���Y�j���琻������Ă���̂�����ł���A���̗��p�𑣐i���邱�Ƃ͒E�ΒY�Ɍ�������ł̉�蓹�ƂȂ��Ă��܂��B �y�[�p�[�ł́A���f�E�A�����j�A�̉Η͔��d�̈ʒu�Â��A�㉟�����鐭��A�ۑ�ɂ��Ă܂Ƃ߂��B �E��������CO2��CCUS�ō팸����Ƃ��Ă��邪�A���p���܂łɉۑ肪�����B�E���Ăł��A�c��̉��ΔR������CO2�r�o�������B �E���R�X�g�ȋZ�p�B�ăG�l�R�X�g���ቺ����A���ʎ��Y���X�N������B �o�T�u�C��l�b�g���[�N�v |
|
|
| ���N�ԏ���d�͗ʂ��ł���u�n���M��g�[�V�X�e���v���i��NEDO���Ƃ� NEDO�́A�x���e�N�X�ƃG�R�E�v�����i�[���J�������u���C�j���O�n���M��g�[�V�X�e���v�i�������Ɣ��\�����B �����~�M�������ǂ����p���邱�ƂŒ�����2����1�ɂ����u���C�j���O�n���M������v�ƁA�G�A�R���̏o�͂ɍ��킹���z���ʂ̒����ɂ���āA�K�v�Ȓn���M�݂̗̂��p�ƍ̔M�����̌�����\�ɂ����u�M���x���䃆�j�b�g�v���J�������B 2020�N�x�܂ł̎��؎������ʁA���V�X�e�����O�C�M���g���]���̋�⎮�G�A�R���ɔ�הN�Ԃ̏���d�͗ʂ��50���팸�ł��錩���݂ł��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2022/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�Y�H��G�̐������E����Z�p���Z�������T�C�N���ŔM�Ɛ����팸 �O�Y�H�Ƃ́A�Ɩ��p����@�E�����@���̔�����O���[�v��Ђ̃A�C�i�b�N�X��{�ƁA���l���T�v���C�H����̐ߐ���CO2�팸����������u�����T�C�N�����j�b�g�v�������J�������Ɣ��\�����B 1��100m3/��߂�����������A��������@����r�o����鉷�r�����ė��p����B����ɂ��A�ߐ��ƁA���r���̔M����ɂ��ȃG�l�ŁA�N��CO2�r�o�팸�ʂ͖�50t�ƂȂ�Ǝ��Z���Ă���B �A��������@��60���ɋ߂����r�������T�C�N���ɓK���������ɉ������āA�\�����Ƃ��čė��p����B��ߏ����́A�����t��@�\��L�����f�B�X�N�t�B���^�i�a�̓������f�B�X�N��ϑw�����Ă�ߑw���`�����Ă���t�B���^�j��p���čs���B �ߐ��Ŗ�40���̐V���팸�B�܂��A���r���̔M����ɂ��ȃG�l�ŁA�����Ɏg������C�̖�30���팸��������ł���B1���������1���̏��C�ʍ팸�A�N��300���A170���~�̍팸�Ǝ��Z���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�^�W���Z������d�u�[�d�J�n��1,100�~��225km���s�� �����K�X�́A�֓��G���A�̏W���Z���Ώۂɓd�C�����ԁi�d�u�j�̏[�d�T�[�r�X���J�n�����Ɣ��\�����B ���p�҂��_�Ă��钓�ԏ�ɐ�p�̃R���Z���g��ݒu���A�ˌ��ďZ��Ɠ��l�̊�������B�g�p�d�͗ʂ��A�v����Q�q�R�[�h�łЂ��t���A�ʂ̏[�d���т��Ǘ��ł���悤�ɂ����B�[�d�ʂɉ����ĉۋ������{���O�~�̃v������A���s�ڈ��ɉ�������z���v������p�ӁB���ƊJ�n����R�N���߂ǂɁA�����x�̐ݔ�������ڎw���B �����K�X�͍��N6���ɁA���r�d�Ǝ��{�Ɩ���g��������A��s���G���A�ɂ����ďW���Z������d�C�����ԁiEV�j�[�d�T�[�r�X���J�n��ڎw���Ă����B���r�d�́A����g��ʂ��ďW���Z��Łu�������[�d�v�ł���[�d�������A�܂��A�����Ɏ���ȊO�Łu�����Ə[�d�v�ł���[�d�X�|�b�g���z�e�����فA�I�t�B�X�r���A���Ǝ{�݁A��`���𒆐S�Ɋg�[���Ă��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���b�n�Q���������A�g�����������"�̗L�����p ��_���Y�f�iCO2�j��H�ׂđ�����ہB������g���āACO2�������������iCO2���j������ς����≻�w���i�̍��o�����J�����Ă���B CO2�����g�p����͓̂Ǝ��̐��f�ہuUCDI���v�BCO2�Ɛ��f���g���A�����ő��B����B�����ׂ��͂��̑��x���B1�����̋ۂ�24���Ԃ�16�g���ɂ����B����B �ۂɂ͉h�{�f�ɂȂ�CO2�Ɛ��f����ׂȖA�ɂ��ċ�������B�ۂ��ł����炷��̂ɓK�������x5����ۂ��߂ɓd�C������邪�ACO2��Ɏg�����ߑS�̂�CO2�r�o�ʂ͌��炷���Ƃ��ł���Ƃ����B �ăL�x���f�B�ȂNj��������邪�ACO2���́u���B�̑��x�͈��|�I�ɗD�ʐ�������v�Ǝ��M��������B���Ђ͂��̐��f�ۂ��g���A����ς�����|���G�`�����iPE�j�Ȃǂ����v�悾�B���łɃv���e�C�����J�����Ă���B����ς����̊ܗL�ʂ���83���ƍ����B�v���e�C���ƃ|�����_�Ƃ���2024�N����̗ʎY���v�悷��B������PE�̐��Y�ɏ��o���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�^�G�ꂸ�ɏƖ����I��/�I�t�ł���u��ڐG�X�C�b�`�v �p�i�\�j�b�N�́A����������ĐG�炸�ɏƖ����̃I��/�I�t���ł���u��ڐG�X�C�b�`�v���A2022�N3��21���ɔ�������B ���i��10,450�~(�H�����)�B���ɉq���ʂւ̔z�������߂���A�a�@�⍂��Ҏ{�݁A�ۈ珊�A�����̐l�����p����w�Z��I�t�B�X�Ȃǂւ̐ݒu���������߂�Ƃ����B�܂��Z��ɂ����Ă��A���ꂽ���G�ꂽ��ő��삷��p�x�������A���ւ���ʏ��A�L�b�`���Ȃǂɂ��������߁B��������������m���邽�߂̐ԊO���Z���T�[�ƁA�\���pLED�t���B���m�����̐�ւ����\�B���m�����͌�쓮�h�~�̖�5cm�́u�Z�v�Ɩ�10cm�Ō��m����u���v�ɒ��߂��ł���B �o�T�uImpress�v |
|
|
| ��BIGLOBE�^�r����CO2�r�o�ʍ팸�\�����[�V�������ƂɎQ�� �r�b�O���[�u�́AX1Studio�ƂƂ��ɃN���E�h��AI�����p�����r����CO2�r�o�ʍ팸�\�����[�V�����֎Q������Ɣ��\�����B��������A�r���̋Ɋւ��d�C�ʂ��팸�ł���u�N���E�h�^��������\�����[�V�����v�����B ���\�����[�V�����́A�r���̊�����BEMS�i�r���E�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���j�ɐڑ����AAI�ōœK�ȋ��Ǘ�����uBRAINBOX AI�v�����p����uBRAINBOX AI�v�́A�č����͂��ߐ��E150�s�s�E250�J���ȏ�̌����œ������т�����A�̕���25%�̏���d�͂��팸���Ă���Ƃ����B�܂��A�uBRAINBOX AI�v�͓��@����g�p���Ȃ������ꍇ�̓d�C����A���S���Y������Z�o����B�����ɂ������Ă̋@���⓱����p�Ȃǂ͕s�v�ŁA�ڋq�́uBRAINBOX AI�v�ɂ���č팸�ł����d�C��̔��z�����x���������݂��Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�F�s���Y�^�ƊE���E�e�i���g�P�ʂŁu�O���[���d�́v�v�����̑I�����\�� �Z�F�s���Y�́A�^�c������݃I�t�B�X�r���ɂ����āA�e�i���g��Ƃ��Ƃ̃j�[�Y�ɍ��킹���u�O���[���d�́v�v�������Ă���̐����\�z�����Ɣ��\�����B �Ώ؏������p�������O���[���d�͉�����v�����ɉ����A�e�i���g���L�̔��d���R���̃O���[���d�͂B����v�����A���d����V�݂��lj����̂���u���O���[���d�́v�B����v������3��ނ����B�œK�ȃO���[���d�̓v������I���ł���悤�ɂ������ƂŁA�e�i���g��Ƃ̑��l������E�Y�f�j�[�Y�ɍL���Ή�����B ���Ѓr���ɔ�ׁA�e�i���g�r���ł͌����̊J���E�^�p�҂Ǝg�p�҂��قȂ邱�Ƃ���A�E�Y�f���̓�Փx�������Ƃ����Ă���B���Ȃ́A�e�i���g��Ƃ̒E�Y�f���𐄐i����ׂ��u���[�f�B���O�e�i���g�s�����j�v�����肵���B�����j�ł͌����ȃG�l���A�Đ��\�G�l���M�[�̊��p�����j�ɐ������Ă���B �o�T�u�Z�F�s���Y�v |
|
|
| ���d�C�����Ԃ̑��s�����d�V�X�e���Ɋւ���Z�p�J�� ���d�́A�_�C�w���A��ёg�́A��ڐG�ŋ��d�\�Ȃd�u�̑��s�����d�V�X�e���Ɠs�s�S�̂ւ̃G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���i�ȉ��AEMS�j�̋Z�p�J���Ɏ��g�ށB ���s���Ȃ���̋��d���\�Ƃ��邱�ƂŁA���s�����̉����Ə[�d�̗����̌����ڎw���ƂƂ��ɁA���EV�Ɠd�͌n����ڑ����邱�ƂŁA���Ԃɗ]��ƂȂ�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��d�C�̗L�����p��ڎw���B�J���ɂ������Ă͎Y�w�A�g�Ŏ��g�ށB����ɁA���{�����ԍH�Ɖ���Q��B����AEV���s�����d�V�X�e�������EMS�̋Z�p�J����i�߁AEMS����̋��d���䎎����d���g���̈��S���A���d�V�X�e���̓��H���݂Ɋւ���ۑ蒊�o���s���B�{�Z�p�J���̐��ʂ��A���E�������ł̎�����ڎw���ĐϋɓI�Ɏ��g�ށB �o�T�u�_�C�w���v |
|
|
| ���u���f�ہv�Ńo�C�I�W�F�b�g�R�������A�����������J�n�^���z�Ζ� ���z�Ζ��́ACO2�������������iUCDI�Ёj�ƁA�o�C�I�W�F�b�g�R���̌����ł���C�\�u�^�m�[�������Ɋւ��鋤�������_������\�����B UCDI�Ђ�H2��G�}��CO2��L�@�����Ƃ��đ��B�������Ȑ��f�ہuUCDI���f��(R)�v���J���B�܂��A�o�C�I�R���̌����ł���C�\�u�^�m�[���𐅑f�ۂɂ��CO2���琻������Z�p�Ƃ��̓�����L���Ă���B���������ł́AUCDI�Ђۗ̕L�����ՋZ�p�ƁA���z�Ζ��̐Ζ������Ɋւ���m����Z�����A���f��CO2�������Ƃ���SAF�iSustainable AviationFuel�^�����\�ȍq��R���j�����̎��؉��Ɍ������Z�p�J�����s���B �q��A������ł��o�C�I�}�X��p�H�����������Ƃ���SAF�̐����E�������i�߂��Ă���B����A�����̔R���́A�H�ƂƂ̋����A��������n�����ۑS�ւ̉e���A�����m�ۂƂ������ۑ肪�w�E����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��J�p���[�^��e�ʒ~�d�r�V�X�e���ɂ��VPP���Ƃ��J�n �d���J���iJ�p���[�j�́A�d�͏������Ƃ��s���q��Ђ�ʂ��āA��e�ʒ~�d�r�V�X�e�������p����VPP���Ƃ��J�n�����Ɣ��\�����B �O���[�v��Ђ̍\���ɐݒu������e�ʒ~�d�r�V�X�e���U�^�G�l���M�[���\�[�X�Ƃ��āA�f�W�^���Z�p��g�ݍ��킹���d�͉��i�Ɠd�͎��v�̗\�����s���ƂƂ��ɁA�����Ǝ҂��ۗL���郊�\�[�X�L�����p���A�A�O���Q�[�V�����r�W�l�X�̂���Ȃ�g�[��}��B ��ʑ��z�d���Ǝ҂������o�����X���������{���邱�Ƃ�ړI�ɒ����͂B����u�����͌���v�ł́A�A�O���Q�[�V�����R�[�f�B�l�[�^�[�i���v�Ƃ��ۗL���郊�\�[�X�𑩂ˈ�ʑ��z�d���Ǝ҂ƒ��ړd�͎�����s�����Ǝҁj�Ƃ��āA���܂��܂ȃ^�C�v�̃��\�[�X�̉^�p�m�E�n�E�̒~�ς�i�߂Ă���B�����̒m�������ƂɁA��e�ʒ~�d�r�V�X�e�������p����VPP���Ƃ����{����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցA�������ʃK�X�r�o�𐳖��[���ɂ��邽�߂ɂƂ�ׂ��s���̕ω����Љ� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A2050�N�܂łɉ������ʃK�X�r�o�𐳖��[���ɂ��邽�߂ɂ́A�l�X�̍s���̕ω����d�v�ȗv�f�ƂȂ�Ƃ����V�i���I���Љ���B �d�C�����Ԃ̍w����t�g�̒f�M�H���Ȃǒ�Y�f�Z�p�Ɛl�X�̊֗^�����݂����v�f�̂ق��A�G�l���M�[��������炷���߂̓��퐶���̒������K�v�ł���B�Ⴆ�A�Ԃ��g�킸�Ɏ��]�Ԃ�k���ňړ�������A�g�[�̉��x����������A�x���͉Ƃ̋߂��ʼn߂�������Ƃ������s���̕ω��ł���A�G�l���M�[���ʂɏ����L���Ȓn��ł́A���ɏd�v�Ȃ��Ƃł���B�s���̕ω����r�o�ʂ��팸���A�����A���H�A�q���ʂɂ�����G�l���M�[���v���팸����B ���V�i���I�ł́A2050�N�Ɍ��݂�2�{�̋K�͂̐��E�o�ς��x���邽�߂ɁA�N���[���G�l���M�[�Z�p�̓�����G�l���M�[�����̌���ȂǁA���E�̃G�l���M�[�V�X�e���ɑ啝�ȕϊv�����߂Ă��邪�A�Z�p�����ł͏\���ł͂Ȃ��A2050�N�̔r�o�����[���͐l�X�̓��ӂƎx���Ȃ��ɂ͎������Ȃ��B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��2021�N�ʼnc�_�^���z�����d��g�x���K�C�h�u�b�N�쐬 ���̃K�C�h�u�b�N�́A�_�n��L�����p���A�c�_�^���z�����d���n�߂����ƍl�����Ă���݂Ȃ��܂��A�~���Ɏ��g�ނ��߂̎�����Ƃ��ė��p���Ă����������Ƃ�ړI�Ƃ���ق��A���̎��g�݂��x������n�������̂���Z�@�ւ̊F�l�̎Q�l�Ƃ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B ���̂��߁A�c�_�^���z�����d�̎�g�����K�v�Ȏ葱���A��g���x�����邽�߂̐��x�����Љ�Ă���B����30�N�x�E�ߘa���N�x�ɏH�c���E�É����Ŏ��{�����u�c�_�^���z�����d�̍����v�_�Ƃ̎��؎��Ɓv�̊T�v���f�ځB �o�T�u�_���ȁv |
|
|
| ���_�ސ쌧������ƁE�c�̌����ɍăG�l�d�͒��B�̂��߂́A�����I�[�N�V���������{ ���ł́A�ăG�l�d�̗͂��p���i��ړI�ɁA�ăG�l�d�͂𗘗p������������ƁE�c�̂���A�܂Ƃ߂ē��D���s���u���Ȃ���ăG�l�����I�[�N�V�����v�i���艺���������D�j�����{����B�����œ��D���s�����ƂŁA�ăG�l�d�͂��A�ȒP�ɁA�������B�ł���B���D�ɌW���p�͖����B ���D�Q����Ƃ��A�d�͂̎g�p�X���ɂ���ăO���[�v��������B�O���[�v�����́A�e�O���[�v��1���̓d�͎g�p�ʂ������������悤�ɍs���B����ɂ��A���d�R�X�g���y�����邱�Ƃ��ł��A�d�C�����������Ȃ�\�����A�b�v����B�G�i�[�o���N�̓����i�œK�����d�͗ʐ��ڑI��V�X�e���j�����p���A�œK�ɃO���[�v�������s���B �o�T�u�_�ސ쌧�v |
|
|
| ���Y�f�ŁA�S�N�x�����͌����蕉�S���A�Y�ƊE���x�� �Y�f�̔r�o�ɉ��i��t����J�[�{���v���C�V���O�iCP�j���߂���A���{�E�^�}�́A4�N�x�Ő�������CO2�̔r�o�ʂɉ����ĉېł���u�Y�f�Łv�Ȃǂ̓�������������j���ł߂��B ���S�����x������Y�ƊE�̐��Ȃǂ��ď��ǂ̌o�ώY�ƁA�����Ȃł���̓I�ȕ��������ł܂��Ă��炸�A5�N�x�����̉ۑ�ɐ摗�肳��邱�ƂɂȂ肻�����BCP���߂����ẮA���Ȃ��E�Y�f�Љ�����̗L�͎�i�Ƃ��ĒY�f�ł̋c�_��i�߂�悤���߂Ă���B�����ł͕���24�N�{�s�̒n�����g�����Łi���ΐŁj�Ŏ�Ɋ�Ƃ̉��ΔR���̗��p�Ŕr�o�����CO2�@1�g��������289�~���ېł��Ă��邪�A��1���~���邱�Ƃ����鉢�B�Ȃǂɔ�ׂĕ��S���y���Ƃ̎w�E������B �ߘa3�N�x�Ő�������j�ł��u�Ő��ʂɂ����Ă��K�v�Ȏx�������Ă����v�Ƃ̍l�������荞�܂�A�Y�f�ł���K�����ɂ�������̗A���i�Ɏ�����ł��ۂ��u�����Y�f�Łv�Ƃ������V�ł̑n�݂ƁA���ΐő��ł��ۑ�ɋ������Ă����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���f���}�[�N�C��E�G�l���M�[�E�����ȁA�C�O�̉��G�l���M�[�ւ̌��I�Z�����I�� �f���}�[�N�C��E�G�l���M�[�E�����Ȃ́A2022�N1��1���t���ŁA�C�O�ɂ����鉻�ΔR���Ɋւ�����I�Z������їA�o���i���Ƃ��I�����邱�Ƃ����肵���B �C�O�̃G�l���M�[����ʼn��ΔR���𐄐i���銈���́A�ȍ~�A�x�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���E�̓�_���Y�f�r�o�ʂ��팸���邽�߂ɂ́A�e���͎������B�����ΔR������O���[���E�G�l���M�[�ւƈڍs�����Ȃ���Ȃ炸�A�����́A�C�O�̃G�l���M�[����ɂ����鉻�ΔR���Ɋ֘A������I�Z����A�o���i���I������ŏ��̍��̈�ƂȂ�B�����͂��ł�2020�N�A�ΒY�Η͔��d�ƈ�ʒY�ɑ���C�O�����Z�����I�����邱�Ƃ����肵�Ă���A�܂��A�J���r�㍑������������⑽���ԋ�s��ʂ��āA�r�㍑�ɂ�����O���[���ڍs�ƃO���[���d�͂ւ̃A�N�Z�X���}���ɉ��������邽�߂̌㉟�������Ă����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2021/12�@]�@�@�� |
|
|
| ��INPEX�E���K�X�^���E�ő勉�̃��^�l�[�V�����ݔ��Ŏ��p���Z�p�J���� INPEX�Ƒ��K�X�́A�s�s�K�X�̃J�[�{���j���[�g�������Ɍ����āA���E�ő勉�̋K�͂̃��^�l�[�V�����i�������^�������\�́F��400Nm3�^h�j�ɂ��CO2�r�o�팸�E�L�����p���p���Z�p�J�����Ƃ��J�n����Ɣ��\�����B INPEX��NEDO�ɍ̑����ꂽ�������Ƃ̂��ƁA�G�}�����CO2�Ɛ��f�������ēs�s�K�X�̎听���ł��郁�^���i�������^���j������uCO2-���^�l�[�V�����V�X�e���v�ɂ��āA�ݔ��̑�K�͉����A���p����ڎw�����Z�p�J�����Ƃ������ŊJ�n����B ���Ԃ�2021�N�x�����`2025�N�x���B�G�}�����CO2�Ɛ��f���������^��������u�T�o�e�B�G�����v��p����CO2-���^�l�[�V�����́A��{�I�ȗv�f�Z�p�͊m������Ă���BINPEX��2017�N���獇�����^�������\��8Nm3�^h�ł�CO2-���^�l�[�V������ՋZ�p�J�����s���Ă���B���K�X�́ACO2-���^�l�[�V�����ݔ��̐v�ƃv���Z�X�̍œK����S���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�ʉ^�^�e��A�����[�h��CO2�r�o�ʂ��Z�o�E��r�ł���V�T�[�r�X���J�n ���{�ʉ^�́ACO2�r�o�ʂ�^���A���[�h�^�C���ȂǗl�X�Ȏ��_�ŁA�����̍œK�A�����[�h���ꊇ�����ł���u�����X�g�b�v�E�i�r�v�̃T�[�r�X���J�n�����B���Ђɂ��ƁA�ƊE�ŏ��߂āA�e��A�����[�h��CO2�r�o�ʂ����f�I�ɔ�r�E�Z�o�ł���Ƃ����B ���̃T�[�r�X�ł́A�A�����ɈقȂ�W�z������n�}�f�[�^�ƘA�g���ċ������v�Z����CO2�r�o�ʂ��Z�o���A�ڋq��CO2�팸�ɂނ������g�݂��T�|�[�g����B���̎d�g�݂͕����ƊE�ŏ��߂đ�O�ҋ@�ւ�SGS�W���p���ɂ�錟���Ă���A�Z�o���ꂽCO2�r�o�ʃf�[�^�͍s���Ȃǂւ̌��I�Ȏ葱���ɗ��p�ł���B �u�����X�g�b�v�E�i�r�v�́APC��X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�g�[�����甭���n�E���E�d�ʂ���͂��邾���ŁA���ł��A�ǂ��ł����p�\�ȗA�����[�h���u���ɔ�r�E�����ł���T�[�r�X���B���̃T�[�r�X�ł͗A������CO2�r�o�ʂ𐳊m�ɔc������CO2�́u�����鉻�v�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��EV�q�������A�ő�5�����^�_�C�L�����p�ȃG�l��} �_�C�L���H�Ƃ͓d�C�����ԁiEV�j�̃G�A�R���Ɏg���ȃG�l���\�̍�����}���J�������B�G�A�R���Ɏg���d�͂�啝�Ɍ��炵�AEV�̍q���������ő�5���L����Ƃ����B 2025�N���߂ǂɎ��p������B�g�p�ɂ��EV�̏���d�͂�5�����߂邱�Ƃ�����̋Z�p�v�V�́A�^�A����̉��g���K�X�r�o�팸�ɂȂ���B �G�A�R���͗�}�����k���邱�ƂŔ�������M�Ȃǂ𗘗p���ċ�C�����߂����₵���肷��B�_�C�L���̐V���ȗ�}�͐����̍H�v�ɂ�蕦�_���Z���뉺40�����x�Ə]���i���10�`15���Ⴍ�����B���k�ɕK�v�ȓd�͂����点��B���{�̓s�s���ȂǂŃG�A�R�����g��������ꍇ�A�t���[�d��200km����EV�Ȃ�A�������ő�100km�L����Ƃ݂Ă���B EV�p�G�A�R���̗�}�͌��݁A�ăn�l�E�F���ƕăP�}�[�Y�i���f���|���j�������J���������i���嗬���B���i��EV1�䕪��3���~�O��B���p���ɕK�v�ȔF���č��̋@�ւɐ\�������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���u�j�Z���E�M�v�ɂ��{�C���[�����p���ցA�����ϑw�`�b�v�ŔM�����o�� �N���[���v���l�b�g�ƎO�Y�H�Ƃ��u�ʎq���f�G�l���M�[�𗘗p�����Y�Ɨp�{�C���[�̋����J���_�����������v�Ɣ��\�����B �u�ʎq���f�G�l���M�[�v�Ƃ́A���f���q���Z������ۂɕ��o�����c��ȔM�𗘗p����Z�p�B1000�x�ȉ��̉��x�ŁA�����ȋ������q�ɐ��f���z���������̏������Ŏh���������邱�ƂŁA�j�Z����U��������B �����������ۂ́A���āu�퉷�j�Z���iColdFusion�j�v�ƌĂꂽ���A�ے�I�Ȍ��������\���ꂽ�B�������A�ꕔ�̌����҂��n���Ɍ����𑱂��A�Č��������܂��Ă��Ă���B�N���[���v���l�b�g�́A���k��w�Ƌ����Ŏ��p���Ɏ��g��ł���B���M���ۂ̍Č����͊m�ۂ��Ă��āA���̌���A�����Ɍ������i�݁A�O�Y�H�ƂƎY�Ɨp�{�C���[�ւ̉��p�Ɋւ��ċ����J����{�i�������邱�ƂɂȂ����B2023�N�ɂ͐��i������\��B�������u�ł́A���������G�l���M�[����M���o��������B���̍ۂ�COP��12����Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o���^�u���b�N�y���b�g���x�g�i���ŗʎY���^���N����N12���g�� �o�����Y�́A�؎��y���b�g�Y�������u�u���b�N�y���b�g�v�̐��Y��{�i�I�ɊJ�n����Ɣ��\�����B�N�Y12���g���̃v�����g���x�g�i���Ɍ��݂��A���N����ɉғ�������B���Ӎ��ɂ��v�����g��W�J���A2023�N�܂łɔN�Y30���g����ڎw���B�u���b�N�y���b�g�͐ΒY�R�Đݔ������������ɍ��Ăł���B�o���͌����I�ȉ������ʃK�X�r�o�팸��Ƃ��āA���{�̐ΒY�Η͔��d����H��Ȃǂɔ̔�����l�����B2030�N�܂łɔN�Y200���g���K�͂̋����̐����\�z����B �ΒY�Ƃ̍������p�����łȂ��A�����I�ɂ̓u���b�N�y���b�g�������R���Ƃ��Ďg����\��������Ƃ݂�B�����ƂȂ�؎��y���b�g�̒��B�̐���������B���������̉ߒ��ł́A�^�C��x�g�i���ŗL�����p����Ă��Ȃ��[�ނ��g�����؎��y���b�g�����p���Ă���B����͕č��Ȃǂ���̒��B����������B���Ђ��I�[�X�g�����A�Ō��v��ۗL����ΒY�z�R�ł��A���������̐A���̎����͔|���n�߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ������6����1�̌y���ŋ�C��荂���f�M���A�V�J����CNF�����ނ��X�S�C�^KRI���J�� ���K�X�q��Ђ�KRI�́A��C��荂���f�M�������V���J�G�A���Q���ƃZ�����[�X�i�m�t�@�C�o�[�iCNF�j�̕����ނ��J�������B �V���J�G�A���Q����1�`3nm�̃V���J�łł������i�Ƌ�Ԃ���Ȃ�A��Ԕ䗦�i�C�E���j��90�`95���̑��E�́B���i���̋�Ԃ���������C���Η������A�M�̓`�����}������BCNF�̓Z�����[�X�@�ۂ̌��������������a5�`20nm�قǂ̑@�ۂŁA�y�����x�������A�M�ɂ�鐡�@�ω������Ȃ��B KRI�͑a���������V���J�G�A���Q�����q��CNF�̖Ԃŕ��Ő��n�t���ɕ��U���邱�Ƃɐ����B���n�t���������ăV�[�g��̕����ނ������@���J�������B�J�����������ނ̔M�`������0.0150�`0.022W�^m�EK�ƁA��C��0.024W�^m�EK��菬�����B�f�M�ނƂ��Ė�150���܂ł̘A���g�p�ɑς����A�h�z���Ďg�����Ƃ��\�B�̔����i�́A�f�M�ނ�����0.5mm��1�������[�g��������3,000�~���x�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���r�p�_�n�ւ̑��z���p�l���ݒu���K���ɘa�Ő��i �Đ��\�G�l���M�[�̐��i�Ɍ����A�_���Ȃ��Đ��\�G�l���M�[���y���i�ɂȂ���K���ɘa�ɏ��o�����B�S���ɍr�p�_�n�͂��悻28��ha����B ���̂����A���z�����d�ݔ����ݒu�\�Ȗʐςɂ��Ă�13��ha�Ƃ̎��Z������B�������A���z���p�l�����ݒu���ꂽ�_�n�́A�v�ł��悻1��ha�ɂƂǂ܂��Ă���B �_�n�̊��p���i�܂Ȃ��������R�́A�y�n�g�p�ړI�u�n�ځv�ɂ�肪���肳��Ă����B�n�ڂ��c�┨�Ƃ������u�_�n�v�̓y�n�ł́A�_�n�]�p�̐R������������������z�����d��ݒu�ł��Ȃ��������A����̋K���ɘa�ɂ��A�r�p�_�n�z�����d���̌��ݗp�n�Ƃ��ē]�p���Ղ��Ȃ����B �����ЂƂ́A�c�_�^���z�����d�ł́A���z���p�l���̎x�������͔_�n�̈ꎞ�]�p�̋����K�v�ŁA�u���ӂ̔_�n�̕��ϐ����Ɣ��8���ȏ�v�̎��n�ʂ�ۂ��Ƃ��v���ƂȂ��Ă����B�r�p�_�n�ɂ��Ă͂����̋K�����P�p���ꂽ�B �o�T�uNTT�t�@�V���e�B�[�Y�v |
|
|
| ���ăG�l�̎��ȑ����A���҂���̒��B�����ց^�G�l�����w�j���� �����G�l���́A���ȑ����̎w�j���������A�I�t�T�C�g�^PPA�i�d�͍w���_��j�̑��ЗZ�ʂ��H�ɉ��ւ���B ���v�ƂƔ��d���Ǝ҂������őg����ݗ�����̂������ƂȂ�B���v�Ƃ͑��҂�������u�n�̍Đ��\�G�l���M�[�ڒ��B�ł���悤�ɂȂ�B�G�l����FIT�i�Đ��\�G�l���M�[�Œ艿�i���搧�x�j�ɗ���Ȃ��Đ��\�G�l�̓����g���Ƃ��Đ��i����l�����B ���ȑ����Ƃ́A�u���ȑ����ɂ�����w�j�v�ɂ��u���Ɨp���d�ݔ���ݒu����҂��A���d�����d�C����ʓd�C���Ǝ҂��ێ��A�^�p���鑗�z�d�l�b�g���[�N����āA���Y���Ɨp���d�ݔ���ݒu����҂̕ʂ̏ꏊ�ɂ���H�ꓙ�ɑ��d����ۂɁA���Y��ʓd�C���Ǝ҂����鑗�d�T�[�r�X�v�Ƃ���B�ȒP�Ɍ����A���u�n�Ɏ��Ɣ��d�ݔ��Ƃ��đ��z�����d����ݒu�A�d�͉�Ђ��ۗL���鑗�z�d�l�b�g���[�N�𗘗p���A���Е����֑��d���郂�f���B 2013�N11�����z�u�d�C���Ɩ@�̈ꕔ����������@���v�Ő��x�����ꂽ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ����6���G�l���M�[��{�v�悪�t�c���肳��܂��� �����Ȃ鎖��������S�����ŗD��Ƃ��邱�Ƃ́A�G�l���M�[�����i�߂��ő�O��B �܂��A�G�l���M�[�����i�߂��ł́A���S���iSafety�j��O��Ƃ�����ŁA�G�l���M�[�̈��苟���iEnergySecurity�j����Ƃ��A�o�ό������̌���iEconomicEfficiency�j�ɂ���R�X�g�ł̃G�l���M�[�������������A�����ɁA���ւ̓K���iEnvironment�j��}��AS+3E�̎��_���d�v�B ���̏�ŁA��6���G�l���M�[��{�v��ł́A���L��2���d�v�ȃe�[�}�Ƃ��č��肵���B�E��N10���ɕ\�����ꂽ�u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�⍡�N4���ɕ\�����ꂽ�V���ȉ������ʃK�X�r�o�팸�ڕW�̎����Ɍ������G�l���M�[����̓����������ƁB�E�C��ϓ����i�߂Ȃ���A���{�̃G�l���M�[�����\����������ۑ�̍����Ɍ����A���S���̊m�ۂ��O��Ɉ��苟���̊m�ۂ�G�l���M�[�R�X�g�̒ጸ�Ɍ�������g���������ƁB �o�T�u�o�Y�ȁv |
|
|
| ��WWF�^�o�C�I�}�X���d�Ɋւ����ƌ����A���P�[�g�������ʂ��Љ� WWF�W���p���́ASBTi��RE100�ɉ���������144�ЂɃo�C�I�}�X���d�̃A���P�[�g�������s�����B95�Ђ���āA �@1)�o�C�I�}�X���d�͐ΒY�Η͔��d���AGHG�r�o�ʂ������Ȃ�\�������邱�Ƃ�F�����Ă����Ɓi79%�j �@2)GHG�r�o�ʂ������Ȃ�\����F�����Ȃ���o�C�I�}�X�R���d�͂��w�����Ă����Ɓi33���j �@3)GHG�팸���ʂ����҂��ăo�C�I�}�X�R���d�͂B���Ă����Ɓi76%�j �@4)�R�����m�F���Ă��Ȃ���Ɓi28%�j �@5)�R���̃��C�t�T�C�N��GHG��c�����Ă����Ɓi17%�j �Ȃǂ����炩�ɂȂ����B�����̊�Ƃ��o�C�I�}�X���d�̃��X�N�ɂ��Ă͉��ƂȂ��F�����Ă��邱�Ƃ������ł�������ŁA�o�C�I�}�X���d�R���̓d�͂��w�����Ă���3���̊�Ƃ̂����A76����GHG�팸���ʂ����҂��ăo�C�I�}�X���d�R���̓d�͂��w�����Ă���Ƃ������ʂł������B �o�T�uWWF�v |
|
|
| ���u���[�J�[�{���̔r�o��������x�n�݂ց^�����ȁA�����CO2�팸���Ŏ��� �C�m�����̍�p�ŊC���Ɏ�荞�܂��Y�f�u�u���[�J�[�{���v������A���y��ʏȂ͑���⊱���̕ی슈���ɂ���ē�����CO2�̍팸����r�o���Ƃ��Ď�����鐧�x��n�݂���B 2021�N�x��3�J���Ŏ���i�߂�ƂƂ��ɔr�o������̎�������쐬�B�S���̍`�p�ŊC���Ȃǂ��ǂ̒��xCO2���z�����邩����������B�u���[�J�[�{���̕��y�����ɂ��͂�����B�u���[�J�[�{���͊C����C���A�v�����N�g���ȂNJC�m�����̓����ŋz�������b�n�Q�̂��Ƃ��w���B�������ʃK�X�̍팸��ڎw����ŁA�V���ȋz�����Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��CO2�R���̑f�ނ�CO2�L���b�`�����E�툳�E�����ō����\�^���s��w�Ȃ� �n�����g���̌����ƂȂ�CO2���ʂɒ����ł���f�ނ��ACO2���̂��g���č쐻���邱�ƂɁA���s��w�Ȃǂ̌����`�[�������������B�����⍂���ȂǁA���ʂȊ���K�v�Ƃ����A�����ɍ���Ƃ����ACO2���팸����Z�p�Ƃ��Ċ��҂ł���Ƃ����B �x�яy������́ACO2���ޗ��ɁA�A�~�����Ȃ����ɂ��āA�ޗ����Ɋi�q��̋�Ԃ����u���E���ޗ��v�̍����āB�A�~���ƁA�����ȋ����̈������\�������肳���邽�߂ɂ܂����n�t������ACO2���퉷�툳�Ő������Ƃ���ACO2�ƃA�~���ƈ��������i�ƂȂ����A�V�������E���ޗ����ł����BCO2�Z�x��0.04%�̑�C���g���Ă��A���̗n�t��ʂ��ΐV�ޗ��͍����\���Ƃ����B �V�ޗ��͏d�ʂ�30%�ȏオCO2�B����ɁA�����C���������邱�Ƃœ����̋�ԂɋC�̂�CO2������߂邱�Ƃ��ł���B���i�Ɏg�����ʈȏ���ł���Ƃ����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����E46�J���œ����ς݂́u�J�[�{���v���C�V���O�v�Ƃ� �J�[�{���v���C�V���O�Ƃ́ACO2��r�o�����ʂɉ����āA��Ƃ�ƒ낪���K�I�ȃR�X�g�S����d�g�݂��B ���{��ł́u�Y�f�̉��i�t���v�Ƃ��Ă�Ă���B���̑_���́A�o�ϓI�Ȏ�@�ɂ���Ċ�Ƃ����҂̍s����E�Y�f���ւƓ������Ƃɂ���B�J�[�{���v���C�V���O�̑�\�I�Ȑ��x�ɂ́A�u�Y�f�Łv�Ɓu�r�o�ʎ���v������B �Y�f�ł́A��Ƃ��r�o����CO2��ΏۂƂ����ł��BCO2�r�o��1�g���ɂ��ĐŊz��ݒ肵�A��������B�J�[�{���v���C�V���O�́A�t�B�������h��1990�N�ɒY�f�ł𐧒�BEU�������ɍL�������B�r�o�ʎ�����x�́A2005�N��EU���������A�A�����J�̏B���{��I�[�X�g�����A�Ȃǂɂ��L�������B �����ł��A2020�N����n�܂��Ă���AOECD��46�̍���35�̒n�悪�������Ă���B���{�ł��A�����I�ȒY�f�łł���u�n�����g�����Łv����������Ă���B289�~/�g���B�ŋ߂ł͔N�Ԃ�2500���~���x�̐Ŏ�������BEU�̔r�o�ʎ���ł�50�h��/�g���B |
|
|
| ���@�@[�@2021/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���C�[���b�N�X�^�������̐��f���d���A2022�N3���ɉғ��� �V�d�͑��̃C�[���b�N�X�́A2022�N3���ɎR�����Ő��f���d�����ғ�����Ɣ��\�����B �����G�l���M�[���ɂ��ƁA���f��Ĕ��d���̏��Ɖ^�]�͍����ŏ��߂āB��ʉƒ��100���ѕ��̓d�͂ɑ�������o��360kW�̔��d�������݂���\��B���Ɣ�͖�3���~�B ���f�����ł̓X�^�[�g�A�b�v�̃n�C�h���Q���E�e�N�m���W�[�ƒ�g���A���j�₩�����Ȃǂ́u���}�t�B�b�N��v�Ɛ��������Đ��f������B1���ԓ�����300Nm3�i�m���}�������[�x=�W����Ԃł̋C�̂̑̐ρj�����A���f��ăK�X�G���W���œd�C������B���d�����d�C�͎��Ə��Ȃǂɋ�������B���݂̐��f���i��100�~/m3���x�ŁA���y�ɂ͂���Ȃ�R�X�g�ቺ���J�M�ƂȂ�B�C�[���b�N�X��30�~/m3�Œ��B����v��B�����I�ɂ͔��d���̑�^���Ȃǂɂ��A��10�`20�~/m3�܂ň������������Ƃ��Ă���B �o�T�u���o�V���v |
|
|
| ���听���݁^ZEB���E�ȃG�l���̒������ɂ�Ɩ�����V�X�e�����J�� �听���݂́A���K�Ȏ��������������Ȃ�������G�l���M�[���[���ɂ��邱�Ƃ�ڎw���������i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���j�̕��y�g����ɂ�݁A�u���R�̌��v�ɂ���ԑS�̖̂��邳����Ɩ��𐧌䂷��V�X�e�����J�������B �]���̃I�t�B�X�ł́A�����҂̊���ʂ̏Ɠx�ɉ����ďƖ��𐧌䂷��d�g�݂��̗p����Ă���A���R�̌��̖��邳��ߏ�ȓd�͏���ɔz���������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ������B���Ђ́A���R�̌����܂ގ����̌��̗ʂ��v�����A�팱�Ҏ����ɂ���ē��o�����u���邳�̊��o�l�v��ڈ��Ɏ����Ɩ��̏o�͂𐧌䂵�A�������ێ�����d�g�݂ƂȂ��Ă���B���R�̌��̕ω��ɑ��ďo�͂𐧌䂷�邱�ƂŁA�N�Ԗ�11���̏ȃG�l���ʂ������邱�Ƃ��m�F����Ă���i���ЃV�~�����[�V�����l�j�B�V�z�E���C���킸�A�I�t�B�X��a�@�Ȃǂɂ����Y�V�X�e����ϋɓI�ɒ�Ă��Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���L�c�����^�Ǝ��́u�M�d���d�v�Z�p�����X�^�[�g�A�b�v��Ƃɏo�� �L�c�����́A�M��d�͂ɕϊ�����u�M�d���d�v�̓Ǝ��Z�p�����X�^�[�g�A�b�v��ƁAE�T�[���W�F���e�b�N�ɏo���������Ƃ\�����B �d�T�[���W�F���e�b�N�̔��^�E�_��ȔM�d���d���W���[���u�t���L�[�i�iR)�v�B�z�ǂ�ݔ��Ȃǂ̗֊s�ɉ����đ����\�ł��邽�߁A�M�������ǂ��d�͂ɕϊ��ł���Ƃ����B �L�c������2050�N�܂ł̃J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����A�ŐV�̏ȃG�l�ݔ��Ȃǂւ̐�ւ��ɉ����A�Đ��\�G�l���M�[�̗��p�g���i�߂Ă���A���̈�Ƃ��đ��z����n�M�Ȃǂ�p�������O���d�̓����𐄐i���Ă���B ����̏o���ɂ��AE�T�[���W�F���e�b�N�ЂƘA�g���邱�ƂŁA���Ђ̎�v���i�ł���S���E�����̐��`�E���H���ɔr�o����M�G�l���M�[�̗L�����p�Ɍ����A���d�V�X�e���̊J����i�߂Ă����Ƃ��Ă���B70������10W/10cm2 �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���uSQPV�v�����p�������F�������d�K���X�̔̔��J�n NTT�A�h�o���X�e�N�m���W�́AinQs���J������SQPV�iSolar QuartzPhotovoltaic�F���F�����^�����d�f�q�Z�p�j�����p�������F�������d�K���X�i���d�K���X�j�̔̔����J�n���A�C��w���ɏ��߂ē��������B ���Z���V���Ɍ��z�����T�C�G���X�Z���^�[�i���Ȋفj����̉����ɁA������������t��������Ƃ��ē��������B���d�K���X�͖��F�����ł���A���ʂ���̓��˂ɑ��Ĕ��d�ł��邽�߁A���������̓����ɐݒu���Ă��̌���J�����ւ̉e����^���邱�ƂȂ����d���\�ŁA�V�����܂߂��܂��܂Ȋp�x����̓��˂ł����d���\���B SQPV�́A�������ő�����߂����d����Z�p�ł���A��ʂ̃K���X���g����S�Ă̗p�r�ɔ��d�ƎՔM�Ƃ����@�\�����ė��p�ł���B���d���\��28cm�p���d�K���X�Ő��\mW���x�����A����Ȃ鐫�\����Ɍ������Z�p�J�����p�����Ă����B �o�T�uNTT�A�h�o���X�e�N�m���W�v |
|
|
| ���[���O�������p�����_�N�g�ݒu����C����@�u�x�X�gUV�G�A�[�v�̊J�� �ؑ��H�@�A�����d�̓~���C�Y�́A��ɑ�E���K�͂̓X�܂�I�t�B�X�A�a�@��z�e�������ɁA��C���̕a�����E�C���X���������s�����E�E�ۂ���_�N�g�ݒu����C����@�������J�������B �X�܂�I�t�B�X���̐l�������W�܂�ꏊ�ɂ����ẮA�]���̐ݔ��ɂ�銷�C�ɉ����A���̊J���ɂ�鎩�R���C���C����@�̐ݒu���̊����h�~�K�v�s���ƂȂ��Ă���B �u�����\�t�B���^�v�ŋ�C���̃E�C���X����ߑ�����ƂƂ��ɁA�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��L���ȁu�[���O��LED�v���Ǝ˂��邱�Ƃɂ��A�����̃E�C���X�����55����99%�팸�����C����@���J�������B �܂��A�{�J���i�͋_�N�g���ɐݒu���邽�߁A�����̐v��Ōv�Z���ꂽ�C���𗘗p���A�����̋�C�������ǂ��ψ�ɏz�����邱�ƂŁA���Ԃɂ��Ή��\�ł��B�X�ɁA���R���C�Ɣ�ׁA�N�ԋG�l���M�[����ʂ�22%�팸�ł���B�V�݂����łȂ��A�����̊��݂̃_�N�g�ɂ��ݒu���邱�Ƃ��\���B �o�T�u�ؑ��H�@�v |
|
|
| ���u���v�x���̂b�n�Q�Z���T�[�A�e���i�o���c�a�H�X�o�c�ҁu�����ɔ������Čx�v �V�^�R���i�E�C���X�̊�����ŁA���H�X��{�݂ŗ��p�����CO2�̔Z�x�𑪒肷��Z���T�[�̒��ɁACO2�ɔ������Ȃ����̂����邱�Ƃ��d�C�ʐM��̌����O���[�v�̌��ł킩�����B �Z���T�[�́A�l���f�����Ɋ܂܂��CO2�𑪒肵�A�������u���v�ɂȂ��Ă��邩���m�F�ł��鑕�u�B�����J���Ȃ́ACO2�Z�x1000ppm�i�����C�̖ڈ��Ƃ��Ă���B ���J�Ȃ́A�ԊO�����g���đ��肷��uNDIR�v�����̐��x�������Ƃ��Đ����B�l�i����r�I�����B����w���s�̂���Ă���12��i2,900�`4,999�~�j�̐��x�����������ʁA��ƂȂ�Y�Ɨp�Z���T�[������ppm�ɏ㏸���Ă��S���������Ȃ��A���m�Ȃ̂�1�䂾���������B ���{�̓Z���T�[���w���������H�X��10���~������ɕ⏕���Ă���A7�����܂ł�2��8200���̐\�����������Ƃ����B�_�ސ쌧�͍�N12�����疳���ݗ^���n�߁A����܂łɖ�7,600���݂��o�����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ��NTT�h�R�����d�͎��ƂɎQ�������ăG�l�Ȃ�2�v�����A2022�N3������ NTT�h�R���́A�d�͎��Ƃ֎Q������Ɣ��\�����B2022�N3������V���Ɂu�h�R���łv�����B �T�[�r�X�J�n���_�ł́A�����I�ɍĐ��\�G�l���M�[100���̓d�C����������u�h�R���ł� Green�v�ƁAd�|�C���g�Ƃ̘A�g�Ȃǂɂ�芄���ȗ����ŗ��p�ł���u�h�R���ł�Basic�v��2�̃v���������\�肾�B ���Ђ͂���܂ŁA�u�ʐM�v��u���ρv�Ȃǂ̃C���t���T�[�r�X����Ă����B����A�V���Ɂu�h�R���łv�̒��J�n���邱�ƂŁA��蕝�L�������C���t���T�[�r�X�������X�g�b�v�Œ��A�ڋq�̂���Ȃ闘������̎������߂����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ȏȁA�w�Z�ɂ�����ăG�l�ݔ��̐ݒu�����\ �����Ȋw�Ȃ́A�����w�Z�{�݂ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�ݔ����̐ݒu�Ɋւ��钲�����ʂ����\�����B �������́A����21�N�x���璲�������{���Ă���A�S���̌����w�Z�{��(�c�ۘA�g�^�F�肱�ǂ����E���w�Z�E���w�Z�E�`������w�Z�E�����w�Z�E��������w�Z�E���ʎx���w�Z)��ΏۂɁA�Đ��\�G�l���M�[�ݔ����̐ݒu�y�ѐݔ��e��(���z�����d�ݔ��A���͔��d�ݔ��A���z�M���p�ݔ��A�o�C�I�}�X�M���p�ݔ��A�n���M���p�ݔ��A�R���d�r�A��X�M���p�ݔ��A�����͔��d�ݔ�)�����A���ʂ����\���Ă���B �ߘa3�N5��1�����݁A�����̏����w�Z�ɂ����鑾�z�����d�ݔ��̐ݒu���A34.1��(�O������3.1�|�C���g��)�ƂȂ��Ă���B���㓯�Ȃł́A�n�������c�̂̃j�[�Y�܂��A�����w�Z�{�݂ւ̑��z�����d�ݔ����A�Đ��\�G�l���M�[�ݔ��̓����𐄐i���A�J�[�{���j���[�g�����������ł���悤�����ʂ��܂߁A���������x�����Ă����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���w�Z�̋E�����͓d�C���A�̈�ق̓K�X���s�A�ЊQ���ɔ������U�� �s�́A��N�x����5�N�v��őS�Ă̎s�������w�Z���܂�72�̑̈�قɁA�K�X���̋̐ݒu��i�߂Ă���B ����܂őS�����w�Z�̕��ʋ����Ɠ��ʋ����ɓd�C���̋�ݒu�������A�䕗�Ȃǂ̍ЊQ�ɔ����ăG�l���M�[���̕��U��}��B�̈�ق̋́A�ď�ɉ����A�ЊQ���̔��������鑤�ʂ�����B��N9�����_�̏����w�Z�̕��ʋ����ւ̋ݒu���́A�����ł�99.5���Ƒ唼�̎s�������ݒu���I�����B ����A�����w�Z�̑̈�قւ̐ݒu���͂킸��3.5���Ɛi��ł��Ȃ��B�ЊQ�̍ہA�s�͔��Ґ��ɉ����Ĕ��������فA���w�Z�A���w�Z�̏��ɊJ�݂���B�d�C�ƃK�X�̂ǂ��炩����̃G�l���M�[���₽��Ă��A�w�Z�̔��͋��g����悤�ɂ���B�ŏ���3�N�Ԃŏ��w�Z�ɐݒu���A���w�Z��2023�N�x����2�N�ԂŐ݂���B���w�Z�͊e�n��ɔz�u����w�苒�_���Ƃ��Ă̖���������B �o�T�u�V���v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA���͔��d�̋L�^�I�Ȑ����ƃR�X�g�팸�������V���ȕ��\ �A�����J�G�l���M�[�ȁiDOE�j�́A���㕗�͔��d�ʂ̋L�^�I�ȑ����A�m�㕗�͔��d�v���W�F�N�g�̃p�C�v���C���̑啝�Ȋg��A���͔��d�R�X�g�̌p���I�Ȓቺ������B 2020�N�ɐݒu���ꂽ���͔��d�e�ʂ͑��̂ǂ̃G�l���M�[�����������A�����̐V�K���d�e�ʂ�42%���߂Ă���B2020�N�ɐV�݂��ꂽ��K�͗��㕗�͔��d�e�ʂ͉ߋ��ō����L�^���A�m�㕗�͔��d�̃p�C�v���C����24%���������B ���͔��d��16�̏B�ŏB���̑����d�ʂ�10%�ȏ���߂Ă���A���ɃA�C�I���B�ł́A57%�͔��d����߂Ă���B�������ł̕��͔��d�̕��y�Ɍ��������g�݂̍X�Ȃ鋭���ƂƂ��ɁA�^�[�r�����������Ō����I�Ȃ��̂ɂ��邽�߂̋Z�p���オ���҂����B �o�C�f��������2035�N�܂łɃN���[���ȓd�͂�100%��������Ƃ����ڕW��B�����邽�߂ɍĐ��\�G�l���M�[�̓������}���ɐi�߂Ă��钆�ŁA���͔��d�̐����ƃR�X�g�팸�́A�����I�ɑ傫�Ȑ��ʂ��グ�邽�߂̊�ՂƂȂ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���J���t�H���j�A�B���u���z���ւ̏o�͗}���v�}���A���������X �����d�������s���Ă���J���t�H���j�A�B�ł́A���d�n���̉^�p�E�����o�����X�̊Ǘ��͔�c���g�D�ł���CAISO���S���Ă��āA���̋����ʂ͓��B�d�͎��v�̖�80���ɒB����B ���z���ւ̏o�͗}���ʂ��������R�́A�t�ɗ�g�[���v�������������A���z�����d�̏o�͂����ΓI�ɐL�т邩�炾�BCAISO�́A�ăG�l�ɑ���o�͗}���ʂ�ጸ�E������邽�߂ɁA�č��������B�Ɋg�傳���ăG�l�̓d�͌n���ւ̘A�n�A�n���̐M�����Ɣ��d�R�X�g�팸�𑣐i���邽�߁A���B�ʼn^�c����C���o�����X�s��̉^�c�G���A���g�����A8�B�̓d�͎��Ǝ҂��Q�����鐼���G�l���M�[�C���o�����X�s��iWestern Energy ImbalanceMarket��WEIM�j���^�c���Ă���B ���̑��ɂ��ACAISO��2021�N��2.5GW�̃G�l���M�[�����ݔ���lj�����\��ł���B���f���d�Ɛ��f�x�[�X�̃G�l���M�[�������A���z���̏o�͗}�������炷�̂ɖ𗧂Ƃ���Ă���B �o�T�u���K�\�[���[�v |
|
|
| ���h�C�c�^�ΒY�Η͔��d�����n�n��ւ̎x�����J�n �h�C�c�A�M���{�ƊW�e�B�́A�ΒY�Ɋւ���s������ɏ��������B ���̍s������͐ΒY�n�擊���@��2���ɋK�肳��Ă���\�����v�x����̋��^�̏ڍׂ��K�肷����̂ł���A�ΒY�Y�Ƃ����݂���B���x���̑ΏۂƂȂ�B 2038�N�܂ő��z10��9000�����[�����p�ӂ���Ă���A�B���{�́A�����̎����̂قƂ�ǂ������x���̂��߂Ɏg�p�ł��A�Ǝ��̃v���W�F�N�g��o�σC���t���̉��P��̎��s���\�ƂȂ�B�k�X�o�E���A�M�o�σG�l���M�[�Ȏ��������́A�u����́A�ΒY�Η͔��d���̗��n�n���l�X�ƋC��ی쑣�i�Ɍ����������V�O�i���ł���B����ɂ�莑���̗��ꂪ�ł��A�v���W�F�N�g���J�n���A�����\�ȍ\�����v�ɐi�ނ��Ƃ��ł���v�Əq�ׂ��B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����Ȃ��u�ăG�l���i���v���x�A���F�Ȃǃ����X�g�b�v�� �s�����́A�������Ζ@�ɂ�艷�g������s�v��̍��肪�`���t�����A���̒��Łu�ăG�l�����ʂ̖ڕW�v�Ɓu�ăG�l���i���v��ݒ肷��B ���Ԏ��Ǝ҂͍ăG�l���ƌv����s�����ɐ\�����A���̌v�悪�s��������F�肳�ꂽ�ꍇ�A���F�葱���ȂǂɊւ��A�s�����𑋌��Ƀ����X�g�b�v�Ői�߂���Ȃǂ̓���[�u������B�s�����ɂ��ăG�l���ƌv��́u�F��v��́A���g������s�v��ɉ����Ă��邱�Ƃɉ����A�u�n��̊��ۑS�v�u�o�ρE�Љ�̎����I�Ȕ��W�v�ւ̍v�����v���ƂȂ�B �u�ăG�l���i���v�̐ݒ�́A�u�|�W�e�B�u�]�[�j���O�v�ƌĂ�A�������N�A�s���������ōăG�l�}������ݒ肷��P�[�X�������Ă��钆�A�t�Ɂu�ăG�l�𐄐i������v��ݒ肵�āA�ϋɓI�ɍăG�l�̐V�K�J���𑣂��_��������B���Ȃ́A�ăG�l���Ƃ��F�肳����Ƃ��āu�n��ۑ�����v�u�n��o�ρv�u�h�Ёv�ւ̍v���Ȃǂ������A�ތ^�����Ă������������������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����r�s�m���A���z�����d�u�V�z�Z��ւ̐ݒu�`�����������v �����s�̏��r�m���́A�s���ŐV�z����Z��ɑ��z�����d�ݔ��̐ݒu���`���Â��邱�Ƃ���������ӌ��𖾂炩�ɂ����B �`���Â��錚���̋K�͂�ʐρA���x�̊J�n�����Ȃǂ��A������Ƃ�̈ӌ����Ȃ���c�_����B���{��2030�N�ɐV�z�ˌ��ďZ���6���ɑ��z�����d�ݔ���ݒu����ڕW��݂�����j�������Ă���B�s���ł̍Đ��\�G�l���M�[�̕��y�Ɍ����A���ݍ��Ή���T��B���M�\���Łu���̐V�z���z���ɑ��z�����d�̐ݒu���`���Â���A�s�Ǝ��̐��x�̓����Ɍ������������J�n����v�Əq�ׂ��B���z�����d�ݔ��̓����ɓK�p�ł���⏕���Ȃǂ̎x�������������Ƃ����B�s�͓s���̎g�p�d�͂ɐ�߂�Đ��\�G�l���M�[�d�͂̊�����30�N�܂ł�50%�ɍ��߂�ڕW���f���Ă���B�s�͌��݁A�Z��ɑ��z���Ŕ��d�����d�C��~����~�d�r��ݒu����ہA�@���p�̔��z�i���42���~�j��⏕���鐧�x�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2021/10�@]�@�@�� |
|
|
| �����{���́u�~�d�r���d���v�A��Ύs�ɗe��6MWh �O���[�o���G���W�j�A�����O�ƕăe�X���́A�k�C����Ύs�ɓ��{���̒~�d�r���d���u�k�C���E��o�b�e���[�p���[�p�[�N�v�����݂��A2022�N�č��ɉғ�����B ���p�[�N�ł́A�e�X���̑�^�~�d�V�X�e���uMegapack�v������B�V�X�e���K�͂͏o��1523.8kW�A�e��6095.2kWh�B��e�ʁA�n�������߂�d�͓����A�l�b�g���[�N�ɂ��24���ԊĎ�����Ȃǂ̓��������p���A�d�͉����s��E���������s��E�e�ʎs��֎Q�����邱�ƂŎ��v�������ށB �O���[�o���G���W�j�A�����O���A�O���Q�[�^�[���Ǝ҂Ƃ��āA�S���ɓ_�݂��鑾�z�����d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�d�́A�ߓd�Ȃǂɂ�萶�܂ꂽ�l�K���b�g�d�́A���Ɣ��d�ݔ��ɂ��d�́AMegapack�̒����d�͂�O���[�v���Ńo�����V���O���A���������P����B��d���͒n��Z���Ɩ��������^�c���s���\��BEPC�i�v�E���B�E�{�H�j�T�[�r�X�́A�G�l�E�r�W�������S������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���H��ɂ�����Ǐ��r�C�Z�p�uT�|�g���l�[�h�r�C���j�b�g�v���J�� �H�Ƌ@�B���甭������I�C���~�X�g���������ǂ��ߏW�E�r�C���A������C�������P�B �听���݂́A�N���t�Ƌ����ŁA�H����ɂ�����H�Ƌ@�B�Ȃǂ̐��Y�@�킩�甭������I�C���~�X�g�����܂މ��ꂽ��C�������悭�ߏW���Ĕr�C����Ǐ��r�C�Z�p�uT�|�g���l�[�h�r�C���j�b�g�v���J�������B ����́A�_�N�g��t�[�h�Ȃǂ̕��@���]������p�����Ă���B�������A���Y�@��̍X�V�E�ڐ݂ɍۂ��ă_�N�g�Ȃǂ̎�O����Ƃ���������ȂǏ_��ȑΉ��Ɍ�����Ƃ����ۑ肪����B �����œ��Ђ́A���Y�@��ɔr�C�_�N�g�Ȃǂ�ڑ����邱�ƂȂ��A���ꂽ��C�������ǂ��ߏW���Ĕr�C���邽�߁A�_�N�g�������ł̔r�C�Ƃ��̎��͂���~����ɋ�C�𐁂��o�����C��g�����邱�ƂŁA�g���l�[�h�i���j��Ԃ������A���ꂽ��C�̔r�C���������コ�����Ǐ��r�C�Z�p�uT�|�g���l�[�h�r�C���j�b�g�v���J�������B�r�C�����̌���ɂ��A�{�����ł͑啝�Ȕr�C�����̌���i��75�����x�j�������ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B�r�C���j�b�g�́A�V�䂩��݉����Đݒu����B �o�T�u�听���݁v |
|
|
| �����͓d�@�A���^�l�[�V�����Z�p���Ɖ��ց^���������p�������I�� ���͓d�@��2030�N�܂ł�ڕW�ɁA���������g�������^�l�[�V�����Z�p�̎��Ɖ���ڎw���B ���Ђ̐���Z�p�����A�����������^�����������ɐ��ݏo����|�{�����\�z����B�H��Ȃǂ���o��CO2�ƍĐ��\�G�l���M�[�R���̐��f��������ɗ^���A�����������^���d�ȂǂɊ��p����N���[���ȏz�V�X�e���Ƃ��āA�r�W�l�X���f�����m��������B���^������������u���^�������ہv�́ACO2�Ɛ��f��̓��Ɏ�荞�݁A���^����r�o����B�|�{���x�͎���70�����x�B�n����ɍL�����݂��Ă���B��C���ɕ��o�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����łȂ�6�ЁA�W�F�b�g�R�������𒆐S�ɒY�f�n��z���Ȏ��Ƃ� ���ŃG�l���M�[�V�X�e���Y�A���m�G���W�j�A�����O�A�o�����Y�Ȃ�6�Ђ́A�u�l�H�������Z�p��p�����d���ɂ��n���CO2�������������Ɓv�\�����B �u�����\�ȍq��R���iSAF�j�v�����𒆐S�Ƃ����A�n��̊������Ȃǂɂ��Č�������B���Ō����J���Z���^�[���J������CO2��CO�ɓ]������CO2�d���Z�p��p�����uP2C�iPower to Chemicals�j�v���Z�X�v�ɂ��A�r�K�X�Ȃǂ����CO2��SAF�ɍė��p����A�J�[�{�����T�C�N���̃r�W�l�X���f�����B���؎��Ƃ̊��Ԃ�2021�N9���`2025�N3�����B P2C�v�����g�́A�����������CO2���A�l�H�������Z�p�����p����CO�ɊҌ����AFT�����v���Z�X�iCO�Ɛ��f����G�}������p���ĉt��̒Y�����f�����������A�̋Z�p�j��p����CO�ƍăG�l�R���̐��f�������A�����̐Ζ������v���Z�X�𗘗p���āA�W�F�b�g�R����y�����̉t�̔R����������́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{���S�A�툳��_���Y�f����v���X�`�b�N�̒��ڍ����ɐ��E�ŏ��߂Đ��� ���s����w�A���k��w�A���{���S��́A�E���܂�p�����ɁA�툳��_���Y�f�ƃW�I�[�����玉�b���|���J�[�{�l�[�g�W�I�[���̒��ڍ������s���G�}�v���Z�X�̊J���ɐ��E�ŏ��߂Đ������A�_���Z���E���G�}��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����������I�𗦂Ŏ��b���|���J�[�{�l�[�g�W�I�[���������ł��邱�Ƃ\�����B �|���J�[�{�l�[�g�W�I�[���́A�v���X�`�b�N�ɑ�\�����|���E���^�������̏d�v���ԑ́B�V���Ȏ�@�́A�_���Z���E���G�}��p���A�W�I�[���ɏ툳�̓�_���Y�f�𐁂����ނ��Ƃɂ��A�������������n�O�ɏ������邱�Ƃ��\�ŁA�ړI�̃|���J�[�{�l�[�g�W�I�[�������I�𗦂��������œ��邱�Ƃɐ��������B ��_���Y�f����L�@�J�[�{�l�[�g�A�J�[�o���[�g�A�A�f�Ȃǂ̍����ɂ��W�J�\�ƍl�����A�l�X�ȉ��w�i�������[�g���m�����邱�ƂŁA��_���Y�f�̉��w�Œ艻�Ɋ�^����G�}�v���Z�X�ɂȂ�Ɗ��҂����B �o�T�u�G�R�i�r�v |
|
|
| ��ENEOS�̐��f�X�e�[�V�����ɐ��d�u��[���ACO2�t���[���f���� �_�|���\�����[�V�����́A�g�L�R�V�X�e���\�����[�V�����Y��ʂ���ENEOS�ɐ��d�������f�������u��[�������Ɣ��\�����B ����[�������u���d���������x���f�������u�v�́A�X�e�[�V�������ɐݒu�������z���p�l���Ŕ��d�����d�C�ƌn�������d�����ăG�l�d�́iENEOS CO2�t���[�d�̓��j���[�A�O���[�v��FIT�d�C�{�g���b�L���O�t���Ώ؏������p�j�𗘗p����CO2�t���[���f������B �[���������d�u�͌ő̍����q�d�������𗘗p���ď�����d�C������������iPEM���j�B�\�́F���f�����ʁF30Nm3/h���f�������́F 0.82MPa���f���x�F99.999�����f�I�_�F-70���i��C�����j���@�F2200mm W�~6500mm�k�~2500mm H �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���f�c�a�k�A�d�̓f�[�^�łb�n�Q�Z��^�����̌����T�[�r�X������ �O���b�h�f�[�^�o���N�E���{�iGDBL�j�́A�X�}�[�g���[�^�[�œ�����d�̓f�[�^�����_���Y�f�r�o�ʂ��Z�肷���@�̌�����i�߂Ă���B 2022�N�x�ȍ~�ɂ��T�[�r�X���\��B�J�[�{���j���[�g�����̐헪���Ă��s�������̂ȂǂŃj�[�Y�����܂肻�����B���Ȃɂ��ƁA2050�N��CO2�r�o�������[���ɂ���ƕ\�����Ă��鎩���̂�40�s���{���A256�s�A�ɒB����B�e�����̂͂��ꂼ���CO2�r�o�팸�v������肵�A���g�ނ��ƂɂȂ邪�A�v��̍������s�̂��߂ɂ́A�ǂ̕����G���A�ł�CO2�r�o��m��K�v������B�O���b�h�f�[�^�o���N�E���{�́A�����d�́A�����d�́A���d�́ANTT�f�[�^���ݗ������B�X�}�[�g���[�^�[���͂��߂Ƃ���d�̓f�[�^�����p���A�Љ�ۑ�̉�����Y�Ƃ̔��W�ɍv�����ׂ��A���̎Љ�����Ɍ��������[�X�P�[�X��������s���g�D�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Z��z���A�u�ݒu�`�����v������A�u2030�N�E�V�z��6���v���L �Z��̉����㑾�z����{�i�I�ɐ��i������������m�ɂȂ��Ă����B2030�N�ɐV�z�Z���6���ɑ��z����ݒu����ڕW���Ȓ��A�g�Őݒ肵���ق��A�����I�ɏZ��z���́u�ݒu�`�����v���I������1�Ƃ����B ���y��ʏȂƌo�ώY�ƏȁA���Ȃ́A��6��u�E�Y�f�Љ�Ɍ������Z��E���z���̏ȃG�l�����̂����������v���J�Â����B2030�N�̏Z��E���z���̎p�Ƃ��ẮA2030�N�x�̉������ʃK�X�r�o��46���팸�ڕW�̎����Ɍ����ċZ�p�I���o�ϓI�ɗ��p�\�ȋZ�p���ő�����p���A�V�z�Z��E���z����ZEH�EZEB��̐����̏ȃG�l���\���m�ۂ����ƂƂ��ɁA�u�V�z�ˌ��Z���6���ɑ��z�����d�ݔ�����������Ă��邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ����B ���z�����d�ݔ��ɂ��ẮA�����@�ւ����z��ƂȂ�Z��E���z���́A�V�z�ɂ����鑾�z�����d�ݒu��W��������ƂƂ��ɁA�����X�g�b�N����L�n�Ȃǂʼn\�Ȍ���̑��z�����d�ݔ��̐ݒu�𐄐i����ȂǗ��悵�Ď��g�ނ��Ƃ��f�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ăG�l����{�̎�̓G�l���M�[�ɁI�uFIP���x�v��2022�N4���X�^�[�g �ăG�l�́A2012�N�Ɂu�Œ艿�i����iFIT�j���x�v���������ꂽ�B����A�V����2022�N4������uFIP���x�v���X�^�[�g����B�uFIT���x�v�̉ۑ�́A���������S����u���ۋ��v���B2021�N�x�̌����݂ł͑��z2.7���~�ɂ���ԁB �܂��A���R������͐藣����Ă����B�uFIP���x�v�Ƃ́u�t�B�[�h�C���v���~�A���iFeed-inPremium�j�v�̗��̂ŁA�ăG�l�̓������i�މ��B�Ȃǂł́A���łɎ�������Ă��鐧�x���B����́A�ăG�l���d���Ǝ҂����s��ȂǂŔ��d�����Ƃ��A���̔��d���i�ɑ��Ĉ��̃v���~�A���i�⏕�z�j����悹���邱�ƂōăG�l�����𑣐i����B�u����i�iFIP���i�j�v�́A������l�����āA���炩���ߐݒ肳���B�����́AFIT���x���������ɂ���B���킹�āA�s�ꉿ�i�ɘA������u�Q�Ɖ��i�v�������߂���B�u����i�v�Ɓu�Q�Ɖ��i�v�̍����A�u�v���~�A���v�Ƃ��čăG�l���d���Ǝ҂����B �o�T�u�����G�l���v |
|
|
| �����ȁA�����Q���ɂ��C��ϓ������W�E���͎��Ɓi�ߘa3�N�x�j�����{ ���Ȃ́A�����Q���ɂ��C��ϓ������W�E���͎��Ƃ��s���Ɣ��\�����B �n��̋C��ϓ��e����c�����A�e���ɉ������K������v��A���{���߂����B���X�̐����⊈���̒��ŋC��ϓ��e�����������Ă���l�͑����A�����̏ڍׂȏ���f�[�^�����W���A�Ȋw�I�ȗ��t���ɂ���Ēn����L�̋C��ϓ��e������肷�邱�Ƃ́A���ߍׂ₩�ȓK��������{�����ŕK�v�s���Ƃ����B �����Ƃ́A�C��ϓ��K���@�Ɋ�Â��ݒu�����n��C��ϓ��K���Z���^�[����̂ƂȂ��āA�q�A�����O��A���P�[�g����ʂ����Z���Q���^�̏����W���s���ƂƂ��ɁA���W�������ɂ��ĕ��͓������{���邱�ƂŁA�n��̋C��ϓ��e����c������B�ߘa3�N�x�́A��錧�⋞�s�{�Ȃ�12�{�������2�s�Ɉϑ�����B���ʂ́A�V���|�W�E���̊J�ÁE�z�[���y�[�W�ւ̌f�ڂȂǂ�ʂ��A�n��̋C��ϓ��e���̗�����[�߂邽�߂Ɏg�p����Ƃ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����Ȃ��V���x�A�b�n�Q���炷�قǕ⏕���A�b�v�^��Ƃ̏ȃG�l�������i ���Ȃ�2022�N�x�A��_���Y�f���팸����قǕ⏕�����オ��ȃG�l�x�����Ƃ��n�߂�B CO2��1�g��������5��~�Ōv�Z���A�@��{�C���[�Ȃǂ̓�����p���ő��50���⏕����B�ʏ�̕⏕����3����1���x���������A�C���Z���e�B�u�^�̎d�g�݂�݂��邱�Ƃō����ȍ��@�\�ݔ��̓����𑣂��B�⏕�����5�疜�~�ɐݒ肵�A������ƂɊ��p�𑣂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���s�ꓮ���F2030�N�̔��d�R�X�g�A���z����8.2�~/kWh�`�ōň��� ���d�R�X�g�̌��،��ʂ����\���ꂽ�B2030�N�̔��d�ݔ��̃R�X�g�ł́A���Ɨp�̑��z�����x�X�g�P�[�X8.2�~/kWh�ōł������ɂȂ�B �����ŏZ��p�̑��z����8.7�~�A�K�X�R�[�W�F�l��9.5�~�A���㕗�͂�9.9�~�ɂȂ�A10�~��錩�ʂ��ł���B ����ALNG�i�t���V�R�K�X�j�Η͂�10.7�~�A���q�͂�11.7�~�A�ΒY�Η͂�13.6�~�ŁA�R�X�g�����͂ŗ�錋�ʂɂȂ����B ���z���ƕ��͂𒆐S�ɁA���R�G�l���M�[�̔��d�R�X�g���Η͂⌴�q�͂����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ𐭕{���������Ӌ`�͑傫���B���������z���ƕ��͂̓d�͂��g��ɔ����g�����d�Ȃǂ̑����������A�d���ʂ̌��E��p�i�d��1kWh��lj����邽�߂ɕK�v�ȃR�X�g�j�����킹�Ď��Z�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E���A�l�H�������ɂ��100m2�K�͂Ń\�[���[���f�������؎����ɐ��� NEDO�Ɛl�H���������w�v���Z�X�Z�p�����g���iARPChem�j�́A�l�H�������V�X�e���̎Љ�����Ɍ����A100m2�K�͂̑��z������^���G�}�������p�l��������i���G�}�p�l��������j�Ɛ��f�E�_�f�K�X�������W���[����A���������G�}�p�l�������V�X�e�����J�����A���E�ŏ��߂Ď��؎����ɐ��������Ɣ��\�����B ���؎����ɂ́A������w�A�x�m�t�C�����ATOTO�ȂǂƎ��g�B2019�N8���ɉ��O�̎��R���z�����ł̌��G�}�p�l�������V�X�e���̎��؎����ɒ��肵�A�����������������f�Ǝ_�f�̍����C�̂���A�����x�̃\�[���[���f���E������邱�Ƃɐ����B����ɃK�X���H��K�ɐv���邱�ƂŁA�����C�̂��Ԉ��S�Ɏ�舵���邱�Ƃ��m�F�����B�����ɂ��A�\�[���[���f��������G�}�p�l�������V�X�e���̑�K�͉���A�\�[���[���f�����v���Z�X�̈��S�v�̎����Ɋ�^����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������22�N�x�T�Z�v���A�����̂̒E�Y�f���x����200���~������Ǝx���� ���Ȃ�2022�N�x�\�Z�̊T�Z�v���z�����\�����B2050�N�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����A�E�Y�f���ƂɈӗ~�I�Ɏ��g�ގ����̓����p���I�Ɏx�������t���i�V�݁j��200���~���v��B �܂��A�Ő������v�]�Ɂu�J�[�{���j���[�g�����Ɍ������J�[�{���v���C�V���O���܂ރ|���V�[�~�b�N�X�̐��i�v�荞�B ���́u�n��E�Y�f�ڍs�E�ăG�l���i��t���v�ł́A���Ȃ��Ƃ�100�����́u�E�Y�f��s�n��v�ŁA��������̓d�͏���ɔ���CO2�r�o�����[������2030�N�x�܂łɎ�����ڎw���B�E�Y�f��s�n��ł̖ڕW�B���Ɍ������ăG�l���ݔ��A�~�d�r�E���c�����̊�ՃC���t���ݔ��̓����Ȃǂ��x������B�܂��A���Ə���^���z�����d�ȂǑS���Ŏ��g�ނׂ���d�_����ɐ�i�I�Ɏ��g�ޒn�������c�̓����x������B��t����3�^4�`1�^2���B���Ɗ��Ԃ�2022�N�x�`2030�N�x�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2021/9�@]�@�@�� |
|
|
| ��ENEOS�^�����R���ʎY�����ɑ�K�͎{�� ENEOS�z�[���f�B���O�X�͍����ɍ����R���̑�K�̓v�����g�����݂�����j���ł߂��B ���N��ɒ��H���A2030�N��̑��������ɓ��Y1���o�����K�͂Ɋg�傷��B�����z�͐��S���~�B�����R���͊����̓��R�@�ւ��g�����_���Y�f�iCO2�j�t���[�R���Ƃ��Đ��E�Ō����J�����i�ނ��A���������̌�����ѐ����v���Z�X�̖��m���Ȃljۑ�������B �����ƂȂ鐅�f�͊C�O����Đ��\�G�l���M�[�Ő����������d���O���[�����f�B����BCO2�͎��Ў{�݂Ȃǂ���r�o�������̂���������p����B���f��CO2���A�G�}��p�������������Ő������鍇���R���iefuel�j�́A�����Ԃ�q��@�̓��R�@�ւ����̂܂g�p�ł��A�����̃T�v���C�`�F�[�������p�ł���BCO2�t���[���f�ƁA���d����H�ꂩ��r�o�����CO2���C���璼��CO2���E�������DAC�i�_�C���N�g�G�A�L���v�`���[�j���g�����ƂŒE�Y�f�R������������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ��RFID�^�O�ɂ�鎺�����Z���V���O�V�X�e�����J�� �|���H���X�A���{�A�C�E�r�[�E�G���A�}�X�v���d�H�ANTT�R�~���j�P�[�V�����Y��4�Ђ́ARFID�^�O�ɂ�鎺�����Z���V���O�V�X�e���������J�����A���l�s�����ANOK�{�Ѓr���ɓ��������B �{�V�X�e���́ARFID�^�O��d�g�ɂ��N�d���邱�Ƃɂ��A�������ł���Ȃ���d�r�������s�v�ƂȂ鎺�����Z���V���O�V�X�e�����B�d�g�͈͓̔��ł���Ί�{�I�ɂǂ��ł��Z���V���O���\�BRFID�^�O�̕��������ǎ�A�ړ����Ă���RFID�^�O�̓ǎ悪�\RFID�^�O�ƕ����̃Z���T��g�������}���`�Z���T�̑Ή����\�B �������f�[�^��l�̍ݕs�݃f�[�^�Ȃǂ������I�Ɏ��W���邱�Ƃ��ł���B����A�{�V�X�e���̓W�J��i�߁A���W�����r�b�O�f�[�^��p�����V�����ݔ�����݂̍����n�o���A����Ȃ�ȃG�l���M�[���A���K���A�m�I���Y���̌���Ɋ��p����B �o�T�u�|���H���X�v |
|
|
| ���听���݁^���������z���R����p�����V�[���h�Z�O�����g�T-eCon/Segment������ꓱ�� �听���݊�����Ђ́A���z���R���N���[�g���g�p�����V�[���h�Z�O�����g�uT-eCon/Segment�v���J�����A���̓x�A�������ƂȂ鉺����������̊ǘH�{�ݍH���ւ̓��������肵���B �{�Z�O�����g�́A�Z�����g��S���g�p���Ă��Ȃ����߁A�R���N���[�g�ޗ������ߒ��Ŕ�������CO2�r�o�ʂ��7������팸���邱�Ƃ��ł��A�]���i�Ɠ����ȏ�̐��\��L���Ă���B�܂����F�X���O�Ȃǂ��ʂɎg�p���邱�Ƃ���A�����̗L�����p�ɂ��v������B ���Ђ́A���z���R���N���[�g��p�����V�[���h�H���̍\�����ނł���Z�O�����g�uT-eCon/Segment�v���J�����A���s���̉���������V�[���h�g���l���H���ɂ����āA�O�a6.4���̃V�[���h�g���l���ŗp����Z�O�����g5�����O���i����6m�j�̎{�H�����{���邱�ƂƂȂ����B�Z�����g���g��Ȃ��R���N���[�g�Z�O�����g�̃V�[���h�g���l���ւ̓K�p�́A�������ƂȂ�B �o�T�u�听���݁v |
|
|
| �������^�f�[�^�Z���^�[�̐V���ȏȃG�l�Z�p�ԐڊO�C��[�^�̋V�X�e���J�� ���Ђ́A�u�ԐڊO�C��[�^�̋V�X�e���v���J�������Ɣ��\�����B �O�C�������ɒ��ړ������Ȃ��V���ȊO�C��[�R���Z�v�g���̗p���A�T�[�o���̏ȃG�l���M�[���Ǝ������x���x�Ɋւ��ċ��߂���ݔ��̈ێ��Ǘ��̕��S�y���𗼗�������B ������C���^�[�l�b�g�Ύ�f�[�^�Z���^�[�ɓ��V�X�e�����������A�f�[�^�Z���^�[�ɂ����鍑���g�b�v�N���X�̏ȃG�l���\�up.PUE=1.116�v�����������Ƃ����B ���V�X�e���́A�O�C�ڎ����֓��������A���O�@�ɔ��������W�G�[�^�^�̔M�����R�C���ŊO�C��[���s���B�@�͉Ċ��Ɍ���I�Ɏg�p����M���p�̗␅�R�C���ƊO�C��[�R�C���̑o����L���A�O�C���x���p���ׂɉ�����3�̉^�]���[�h���ւ��A�ȃG�l���M�[��A�œK�Ȑ�����s���B �O�C�������ɓ������Ȃ����ƂŃT�[�o�����̎��x�����肷�邽�߁A���ڊO��V�X�e���ŕK�v�ƂȂ�����ݔ��A�����ݔ��������Ƃ��ł��A�ێ��Ǘ��̕��S�y�����\���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������K�X�^�ƒ����DR���؊J�n�ߓd���͂Ń|�C���g�t�^ �����K�X�́A���Ђ̒ሳ�d�C�̗��p�҂�ΏۂɁA8��24������ƒ�����f�}���h���X�|���X�̎����J�n����Ɣ��\�����B ���Ђ��O���ɍ��m����Ώێ��Ԃł̐ߓd���тɉ����A�|�C���g�Ҍ����s�����ƂŁA�ڋq�̎����I�Ȑߓd�s���𑣂��u�s���ϗe�^�v�̃f�}���h���X�|���X�����s���B����ɂ��A�d�͎��v�̗}���E�n�����ׂ̕������̎�����ڎw���B �����́u�Ă̐ߓd�L�����y�[���v�Ƃ���9��30���܂Ŏ��{����B�Q�����ѐ���10������\��B�܂��A�L�����y�[���ɂ�ENECHANGE�i�G�l�`�F���W�^�����s���c��j�̉p���q���SMAP ENERGY�i�p�������h���j������ƒ�����f�}���h���X�|���X�T�[�r�X�uSMAP DR�v�����p����B �O���܂łɐݒ肳�ꂽ����̎��ԑтɂ����āA�ƒ낲�ƂɎZ�肷��W���I�Ȏg�p�ʂ������ۂ̎g�p�ʂ������ꍇ�ɁA�ߓd��1kWh������5�ߓd�|�C���g�܂���10�ߓd�|�C���g��t�^����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I�������R�G�l���M�[�����������A2030�N�ɍ���50���� ���{�̊�Ƃœd�͎g�p�ʂ��ő�̃C�I�����A���R�G�l���M�[�̓����v���啝�ɑO�|�����Đi�߂邱�Ƃ\�����B �O���[�v�S�̂̓d�͎g�p�ʂ̑唼���߂鍑���̓X�܂ɂ����āA2030�N�܂łɎ��R�G�l���M�[�̓d�͂̎g�p����50���ɍ��߂�B2020�N�x�̓d�͎g�p�ʂ͍��v�Ŗ�71��kWh�ɂ̂ڂ�B2030�N�̓d�͎g�p�ʂ��x�Ƒz�肷��ƁA�N�Ԃɖ�35��kWh�K�͂̎��R�G�l���M�[�̓d�͂B���邱�ƂɂȂ�B ���B���@�́A��1�ɓX�܂̉����Ȃǂɑ��z�����d�����Ď��Ə���邢�̓I���T�C�gPPA�i�d�͍w���_��j�����{����B��2�ɌŒ艿�i���搧�x�iFIT�j�̔�����Ԃ��I��������FIT�d�͂̔���ʂ𑝂₷�B��3�̒��B���@�Ƃ��āA�X�܂�����n�悲�ƂɃI�t�T�C�gPPA�Ȃǂɂ���Ď��R�G�l���M�[�̓d�͂ڌ_��B �o�T�u�C�I���v |
|
|
| �����B�ψ���A���B�s���̋C��ϓ��ɑ��鐢�_�������ʂ\ ���B�ψ���iEC�j�́A���B�s���̋C��ϓ��Ɋւ��鐢�_�����̌��ʂ\�����B ���̐��_�����u���ʃ��[���o�����[�^�[513�v�́AEU�S27�������̂��܂��܂ȎЉ�I�O���[�v�ɑ�����26,669�l��ΏۂɁA2021�N3��15�����瓯�N4��14���ɂ����Ď��{���ꂽ�B�����Ώێ҂�93%���C��ϓ��͐[���Ȗ��ł���ƍl���Ă���A�S�̂Ƃ��Đ��E�����ʂ��Ă���ł��[���Ȗ����ЂƂ����Ă��炤�ƁA�C��ϓ��i18%�j�A���R���̈����i7%�j�A�����ɂ�錒�N���i4%�j�A�̂����ꂩ���I�����ꂽ�B �����ʂł́A�������ʃK�X�̔r�o�ʂ��ŏ����ɗ}���c��̔r�o�ʂE����EU���C���Ƃ��邱�Ƃ�90%�����ӂ����B�܂��A�C��ϓ��Ƃ̐킢�́AEU�s���Ɖ��B�o�ςɃ`�����X�������炷�Ƃ������m�ȔF��������A78%���C��ϓ��ւ̑���Ƃ邱�Ƃ��A���B��Ƃ̋����͂����߂�C�m�x�[�V�����ɂȂ���ƍl���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���ߘa���N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̊�b�r�o�W���E������r�o�W�����i�ꕔ�lj��E�X�V�j�̌��\ �ߘa���N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̊�b�r�o�W���E������r�o�W�����i�ߘa�R�N�P���V�����\�j�ɂ��āA�ߘa�Q�N�x�V�K�Q���̓d�C���Ǝ҂̌W���lj��A�ߘa���N�x�V�K�Q���̓d�C���Ǝ҂̌W���X�V�A�������j���[�ɉ������r�o�W���i���j���[�ʔr�o�W���j�̌��\����]����d�C���Ǝ҂̌W���X�V�̂��߁A�ꕔ�lj��E�X�V�����B �n�����g����̐��i�Ɋւ���@���Ɋ�Â��������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�E���\���x�ɂ��A��_���Y�f���̉������ʃK�X�����ʈȏ�r�o���鎖�Ǝҁi�ȉ��u����r�o�ҁv�Ƃ����B�j�́A���N�x�������ʃK�X�Z��r�o�ʕ��тɍ����F�ؔr�o�팸�ʋy�ъC�O�F�ؔr�o�팸�ʓ��f���������㉷�����ʃK�X�r�o�ʂ����Ə��Ǒ�b�ɕ��邱�Ƃ��`���t�����Ă���B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���n�����g���ւ̐l�Ԃ̉e���u�^���]�n�Ȃ��v1.5���㏸�A2040�N�܂ł� IPCC�́AIPCC��6���]�����i���R�Ȋw�I�����j�����\�����B �l�Ԃ̉e������C�E�C�m�E��������g�������Ă��邱�Ƃ́u�^���]�n���Ȃ��v�Ǝ����ƂƂ��ɁA�H�Ɖ��ȑO�Ɣ�ׂ����E�̕��ϋC���́A�������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʂ��ł����Ȃ��V�i���I�ł�2021�N�`2040�N�܂łɖ�1.5�x�㏸����Ɛ��肵���B �ŋ�10�N�Ԃɔ������������Ɋւ���ɒ[���ۂ̂������́A�l�Ԃ̉e���Ȃ��ł́A�������Ă����\�����ɂ߂ĒႢ�ƕB�l�Ԃ̉e�����A�M�g�Ɗ��̓��������E�Ђ̔������₷���C�ۏ����E�����I�ȍ^���i�ɒ[�ȍ~�J��͐�×��ƍ����̑g�ݍ��킹�j�Ƃ������A�����I�ȋɒ[���ۂ̔����m�������߂Ă���Ƃ����B IPCC�͍���A2022�N2���ɑ�2��ƕ�����i�e���A�K���A�Ǝ㐫�j�A���N3���ɑ�3��ƕ�����i�ɘa��j�A���N9���̓������̏��F�E�̑���\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���J�i�_���{�A��S�I�ȉ������ʃK�X�r�o�팸�̐V�����ڕW�����F �J�i�_���E�C��ϓ��Ȃ́A�u���������肷��v���iNDC�j�v�����A�����ɒ�o���A2030�N�܂łɉ������ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�ʂ�2005�N���40�`45%�팸���邱�Ƃ�����A�Ɣ��\�����B �����o����NDC�́A��S�I�ȖڕW��B�����邽�߂ɓ��������{�����A�̓����A�K���A�{��̊T�v�������Ă���B�܂��A��NDC�͏B�A���B�A��Z���̃p�[�g�i�[����̈ӌ����܂܂�Ă���B�V���Ɍ��\���ꂽ�uCanada's Climate Actions for a Healthy Environment and a HealthyEconomy�v�ɂ����Ă��ڏq����Ă���B�����́A�B�A���B�A��Z���̃p�[�g�i�[�Ƃ������W�҂Ƌ��͂��āAGHG�r�o�ʂ�2005�N���30%�팸����Ƃ����O���2030�N�ڕW������ׂ��������p�����Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ����ʌ��A�������CO2�팸��܂Ɂu�ؑ����`�{�X�O�F�H��v��I�� ��ʌ��́ACO2�r�o�팸�̗D�ǂȎ��g�݂����{���钆����Ƃ̕\�����x��n�݂��A��1��̑Ώۂɖؑ����`�{�X�̎O�F�H���I�肵���Ɣ��\�����B ���́A2020�N�x����A��K�͎��Ə��̑Ώێ��Ə��̂����A������Ƃ��ݒu���鎖�Ə��ɂ��āACO2�r�o�팸�̎x���E���i�u�팸���鉻�x�����Ɓv���J�n�����B ����A2020�N�x�̑Ώێ��Ə��i�H���i�E���������ƁA�Ɩ��E���ƃr���j�̒�����A�D�ǂȎ�g�����{���鎖�Ǝ҂��u�ʂ̍���ʒ������CO2�팸��܁v�Ƃ��đI�肵���B �Ȃ��A�u��܁v�́A������݂Ȃ����ƂɊY�����Ȃ�������ƂɁA�u�D�G�܁v�Ɓu����܁v�́A�݂Ȃ����Ƃ��܂ޒ�����Ƃ�ΏۂƂ��Ă���B��܁F�ؑ����`�{�X�O�F�H��M���ݔ��̔R���g�p�ʁA���C�����ʓ����ׂ₩�Ɍv�����A�����I�ȉ^�]�B���C�z�ǂ��E�������s���A�G�l���M�[�̖��ʂ��팸�������ƂŁA�R���g�p�ʂ�啝�ɍ팸�����B�D�G�܁F�z�h������Y�a�r���A�v���}�H�i �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2030�N�r�o�ʁA�Y�ƕ����37���E�Ɩ������50���팸���Όv��f�� �o�Y�ȂƊ��Ȃ́A���{�̋C��ϓ���ɂ��Č������闼�Ȃ̍�����ŁA�u�n�����g����v��v�̑f�Ă��������B 2030�N�x�ɉ������ʃK�X��2013�N�x����46���팸����ڕW�L���A�G�l���M�[�N��CO2�ɂ��āA�ƒ땔��Ŗ�66���팸�A�Y�ƕ���Ŗ�37���팸�A�Ɩ����̑������50���팸���邱�ƂȂǂ��f�����B�������ʃK�X�z�����ɂ��ẮA�X�ыz�����͖�3800��t-CO2�̋z���ʂ��A�����āA�_�n�y��Y�f�z������Ɠs�s�Ή����̐��i�ɂ���970��t-CO2�̋z���ʂ̊m�ۂ�ڕW�Ƃ��Ď������B �r�o�ʂ�����x�[�X�i�J�[�{���t�b�g�v�����g�j�Ō���ƁA�S�̖̂�6�����ƌv�ɂ����̂Ƃ������Љ�A�u������l��l���n�����g����Ɏ��g��ł����K�v������v�Ƃ��āu�E�Y�f�^���C�t�X�^�C���ւ̓]���v��i�߂邱�Ƃ����荞�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�G���N�g���q�[�g�Z���^�[�F�Y�Ɠd���̌��ł���q�[�g�|���v�͂��ꂩ��啝�ɕ��y�g��ł��邩�H
�d�C�V���i�[�~�i�[��(���v�ƃT�[�r�X)�j�ɂR��V���[�Y�Ōf�ڂ��ꂽ�B �E���Y�H���ł̉��M�v���Z�X�̔M����ݔ��Ƃ��Ă̊��p�E�����q�[�g�|���v�̕K�v���A �E���B�ł̎Y�ƃv���Z�X�ւ̓�������E�����H���p�̃q�[�g�|���v�A �E�v���Z�X�̔M���v��r�M�́E���������邽�߂́u�S����v�i�v���[���[�j�̕K�v���Ȃǂ�������₷���������Ă���B �o�T�u�d�C�V���[�~�i�[�� �v |
|
|
| ���@�@[�@2021/8�@]�@�@�� |
|
|
| ��Looop�A�ሳ����DR�v���O�����u�^�Ă̐ߓd����v���{�� Looop�́A�d�͏������ƁuLooop�łv�̒ሳ�����_�̌ڋq��ΏۂɁALooopDR�v���O�����u�^�Ă̐ߓd����v�̎Q���҂��W�J�n�����B�v���O�������{���Ԃ�9��6���܂ł�48���ԁB �ΏۃG���A�͑S���i����A���������j�B���L�����y�[���ł́A�d�͂̎������Ђ�������Ɨ\�z����鎞�ԑт��u�ߓd�^�C���v�Ƃ��Đݒ肵�A���{�̑O���Ƀ��[���Œʒm�B�Q���҂͐ߓd�^�C�����ɐߓd�Ɏ��g�݁A�ߓd�ʂɉ����� Amazon�M�t�g����i�悷��B����ɐߓd�ʂ̏�ʃ����N�ҁi�ő�1,000�ʂ܂Łj�ɂ́A�����L���O��V�Ƃ��āA�lj��ōő� 1���~����Amazon�M�t�g��i�悷��B �ċG��DR�̎��{�͍����3��ځB����u�X�[�p�[�ߓd�^�C���v�ɂ�������T���A2�{�i1kWh������20�_�j�Ɋg�債�A�L�����y�[�����Ԃ������������B2020�N�Ăł́A15,119���т��Q�����A���v113,578.14kWh�̎��сB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������Ƃ́g�E�Y�f���h�����g���^�̖{�C�x�B�T�v���C���[��CO2�팸�v�� �g���^�����Ԃ��A�T�v���C�`�F�[���i�����ԁj�S�̂ł̃J�[�{���j���[�g�����B���Ɍ����A�{�i�I�ɓ��������B ���̂قǎ�v1�������ɑ��A2021�N��CO2�r�o�ʂ̍팸�ڕW�Ƃ���2020�N����1�|�C���g�������A�O�N��3������v�������B�d�_�ƊE�╔�i���Ƃ̖ڕW�Ȃǂ��߂���e�ŁA�����ƈ�̂ł̊����Ɏ�����u���B�Y�Ƃ̐���̍L���g���^�̎��g�݂́A�������[�J�[�̒E�Y�f���𑣂����������ɂ��Ȃ肻�����B �g���^�������Ɏ��������j�ł́A���ʂ̐��Y�����Ŕr�o�����CO2�팸�ڕW�ɉ����A�T�v���C�`�F�[���S�̂ł̔r�o�ʂ̌����鉻�ƁA�S���ʂł̔r�o�ʒጸ�����̓�����ꂽ�B�����ACO2�팸�ʂ���������ƂȂ��ł͂Ȃ��B�r�o�ʒ����ł͈ȑO������{�����ƑS�̂̑��ʃx�[�X�ƂƂ��ɁA�č����߂ǂɋ쓮���i����d�C�n�A�ԑ̕��i�܂Ŗ�W�O�i�ڂ̔r�o�ʂ������鉻����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����t���ݒu�ɓK�����Ɩ��p�E�S�M�������j�b�g�E�I�o�ݒu�`���A���� ���ŃL�����A�́A�����̉��x�⎼�x�����K�ɕۂ��A�ȃG�l���������Ȃ�������I�Ȋ��C���ł���Ɩ��p�E�S�M�������j�b�g�ɁA��t���ݒu�ɓK�����u�I�o�ݒu�`�v��2021�N8��1���ɔ�������B �����̑_���́A��N���A�����NJg��h�~��̂ЂƂƂ��āA�����K�͂̈��H�X�Ȃǂ̓X�܂⎖�����Ȃǂł̊��C�ݔ��̑��݂ɗe�Ղɐݒu���邱�Ƃ��ł���B��ȓ����́A �E��i����150/250/350m3/h��3�^�C�v�B �E�����ȃG�l���\���m�ہB���ʊ��C��ݒu�̏ꍇ�Ɣ�ׂĒg�[���� 23%�̏ȃG�l�����҂ł���B �E���r�C�o�����X�̒������\�B �E�������x�ƊO�C���x������̉��x�Z���T�[�����m���A�S�M���C�ƕ��ʊ��C�������I�ɐ芷���A���_��}����B �E�Ԍ��^�]�ɂ��ᕗ�ʂ� 24���Ԋ��C�@�\�ݒ肪�\�B �E�@�ƘA���ڑ����邱�ƂŁA�@�̉^�]��ԁA�ݒ艷�x�A�������x�A�O�C���x�̏����ɂ��A�����I�Ƀi�C�g�p�[�W�^�]�ƂȂ�B �o�T�u���ŃL�����A�v |
|
|
| ���E�C���X�A�ۑ��p�u�v���Y�}�N���X�^�[�C�I���������u�v���_�C�A���Д��� �V���[�v���A�_�C�A���Ђƒ�g���ċ�C�Z�p�ł���v���Y�}�N���X�^�[�Z�p�𗘗p�����u�v���Y�}�N���X�^�[�C�I���������u�v���J�������B ���̋Z�p�́A�v���X�iH�{�j�ƃ}�C�i�X�iO2�\�j�̃C�I�����v���Y�}���d�Ŕ��������A��C���ɕ��V���Ă���E�C���X��ۂȂǂɕt���������邱�Ƃŋ�C������B�R���p�N�g�ŋݔ��̐����o�����Ɏ��t���A�C���Ƀv���Y�}�C�I������o����B�����郁�[�J�̓V�J�A�A�l���ȂǁA�قڂ��ׂĂ̋ݔ��Ɏ��t�����\���B�����o�������ꂼ��Ɏ��t�����ł���B�K�ȃC�I���Z�x���m�ۂɂ� 10m2��1��̊��Őݒu����B �_�C�A���Ђ́A�q���ʂ̔z�������߂����Ë@�ւ���H�X�A�H�i�H��ȂǂɎ�ɓW�J���B�d���F100V�A����d�́F2.5W�A�d�ʁF950g�A���@�F90mm�~515mm�~90mm�C�I���������j�b�g�����F19,000���� �o�T�u�_�C�A���Ёv |
|
|
| �������K�X�̃J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�v�����A��O�Ҍ��ؕ������ �����K�X�́A2019�N�x��2020�N�x�̃J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�i CN�s�s�K�X�j�v�����̉^�p�ɂ��āA���ۓI�Ȋ���Q�Ƃ�����O�҂ɂ�錟���A�Z�胋�[���ɏ������K���ł���Ƃ̌����āA���ؕ�����̂����Ɣ��\�����B �����K�X�́A����̌��ؕ���̂܂��A2019�N�x�����2020�N�x��CN�s�s�K�X�𗘗p�����ڋq�ɑ��ACN�s�s�K�X�����ؖ������������s����B�����́A�����������ʃK�X�i GHG�j�r�o�ʂ̌��؋@�ւł�����{�i���ۏ؋@�\���A��O�҂Ƃ��āAGHG�v���g�R���̐��������ƁA�u�J�[�{���j���[�g�����e�B���̂��߂̎d�l�v���Q�Ƃ��A���{�������́B CN�s�s�K�X�́A�V�R�K�X�̍̌@����R�ĂɎ���܂ł̍H���Ŕ������鉷�����ʃK�X���A CO2�N���W�b�g�ő��E�i�J�[�{���E�I�t�Z�b�g�j���A�R�Ă��Ă��n���K�͂ł�CO2���������Ȃ��Ƃ݂Ȃ�LNG�iCNL�j�����p�������́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���X�r���ȂǁA�������E�����M��n���g�[�Ɋ��p�Ճm��E���z��ĊJ��PJ �X�r���ƌՃm��G�l���M�[�l�b�g���[�N�́A 2023�N�ɊJ�Ƃ�\�肷��Ճm��E���z��G���A�̍ĊJ�����Ƃɂ����āA�����p�E�Đ��\�G�l���M�[�ł��鉺���M��n���g�[�Ɋ��p������g�݂����{����Ɣ��\�����B �����ǘH���ꕔ�ɐݒu�����M������ɂ��M�������s���u�ǒ�ݒu�����v�ɂ�艺���M�̒n���g�[�ւ̊��p����B ��̓I�ɂ́A�C���ɔ�ׁu�Ă͗₽���A�~�͒g�����v�Ƃ������x�������������̔M������A�q�[�g�|���v��p���ĉ�������M�������I�Ɉړ����A�G���A���̃I�t�B�X�r�����̗�g�[�̔M���̈ꕔ�Ƃ��ė��p����B ���̎��Ƃł̉����M�𗘗p�����V�X�e���́A��ʓI�ȃV�X�e���Ɣ�r���� CO2�r�o�ʂ�N�Ԗ�70t-CO2�팸�ł���Ǝ��Z����B ����A2021�N9���ɔM�����퓙�ݒu�H�����J�n�A 2023�N3���Ɂu�Ճm��E���z��v���W�F�N�g�v���v�H�A 2023�N4���ɉ����M���p���Ƃ��J�n����\��B �o�T�u�X�r���v |
|
|
| ���C�^�̒E�Y�f���ցACO2�������E���l������SaaS�^PF�J�����J�n Marindows�́A�Ö�d�C�ƂƂ��ɁA 2040�N�܂ł̊C�^���S�E�Y�f����ڎw���u�K�C�A�N���[���A�N�V�����v�̎n���ƁA CO2�̔r�o�ƍ팸�������E���l����������D�����v���b�g�t�H�[���u�K�C�A�N���[�i�[�v���J������Ɣ��\�����B �K�C�A�N���[�i�[��CO2�̔r�o�E�팸�������E���l������SaaS�iSoftware as aService�j�^�v���b�g�t�H�[���B2022�N�Ƀ����[�X�\��B�K�C�A�N���[�i�[�̍\���́i1�j�D�����CO2�r�o�E�팸�ʂ����܂Ƃ߂�ʐM�EIoT���W���[���A�i2�jCO2�r�o�E�팸�ʂ��L�^����N���E�h�E�u���b�N�`�F�[�����W���[���A�i3�jCO2�r�o�E�팸�ʂ������鉻���A����ɂ͉��l�����邽�߂̃_�b�V���{�[�h�\��3�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������b���u�ăG�l���n��t���v�Ɍ��y�A�����̂ւ̎����x���Ɉ�� ���@����Â���u���E�n���E�Y�f������c�v�Łu�n��E�Y�f���[�h�}�b�v�v�����\���ꂽ�B �����[�h�}�b�v�́A�Đ��\�G�l���M�[�̓����ȂǁA�����̂ƍ����A�g���ĒE�Y�f�Ɏ��g�ނ��ƂŁA�o�ϐ����ƒn�抈������ڎw�����́B�ڋʂ̂P�Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ��S�� 100�J���Ɂu�E�Y�f��s�n��v��݂��A�ăG�l���ő���ɒlj��������邱�ƂȂǂ��f���Ă���B��̓I�ȖڕW�Ƃ��āA�u���{�y�ю����̂̌��z���y�ѓy�n�ł́A 2030�N�ɐݒu�\�Ȍ��z�����̖�50���ɑ��z������������A2040�N�ɂ�100����������Ă��邱�Ɓv�Ȃǂ��L�ڂ����B �����āA�������������̎哱�̍ăG�l�������x���闠�t���Ƃ��āA�u�����x���̎d�g�݂{�I�Ɍ������A�����N�x�ɂ킽��p���I����I�Ɏx������X�L�[�����\�z����v�Ɩ��L�����B����c��A�������b�͉�ŁA�u�ăG�l���n��t���̂悤�ȃC���[�W������B�ăG�l�������Ύx�����o��Ƃ����d�g�݁v�ƌ��y���Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ăG�l100�������f����u��w���[�O�v�ݗ��B�Q�������X��w�̂Ȃ���́H ��t���ȑ�w�A��q��w�A���쌧����w�A�L����w�ȂǂX��w�̓L�����p�X�Ŏg�p����d�͗ʂ̍Đ��\�G�l���M�[100�������f����u���R�G�l���M�[��w���[�O�v��ݗ������B ��i��w�̃m�E�n�E��m�������L���A�g�p����d�͂̃[���J�[�{���ɒ��킵�B�������w�𑝂₷�B���g�݂ɊS�������E���E�w���̌l�������w��n��Љ�����W�J�����҂��Ă���B �����[�O�͐�t����ȂǂS��w�̂ق��A���ۊ����w�A�a�m���q��w�A���S���q��w�A�����O�����w�A������Ȏ��ȑ�w�B�Q�������́u2030�`40�N�̎����߂�N���܂łɁA�g�p�d�͗ʂ����R�G�l���M�[�d�͂Ő��Y�E���B���邱�Ƃ����\�A���s����v�ƂȂ��Ă���B ���łɐ�t����ȂǂR��w���Đ��\�G�l���M�[100������B���B����͏���o�������L�����A�Q����w�𑝂₷�B�x���c�̉���ɕăp�^�S�j�A�̓��{�x�ЂȂǖ�T�c�̂�\�肷��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���S�ő̂̎��͂�����u�������d�r�v�A�Y��������_�����ɒ��� �E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����A���̂�������͓d�C�����ԁiEV�j�ł���A���ł����\�����E����d�r�Z�p�����ڂ����B ������̑S�ő̓d�r�����łȂ��A���`�E���C�I���d�r�����̂��u�v�V�^�~�d�r�v�̊J�����i�ށB�d�r�J����擱���A��Ƃɋ��n�����Ă����Y�ƋZ�p�������������Z���^�[���v�V�^�~�d�r�Ɏ��g�ށB ���Z���^�[�ł�EV�p������d�r�ŕ����̊J���v���W�F�N�g���i�ށB���ڂ́A�u������C�d�r�v�u�R���o�[�W�����d�r�v�ȂǂS�̊v�V�^�~�d�r���^�[�Q�b�g�ɁA���s��w�Ɠ��Z���^�[�����j�J�����_�ƂȂ����BEV�p�d�r�̊J���ڕW�́A�G�l���M�[���x��1kg������500Wh�ȏ�A1�[�d���s�����ł�500km�ȏゾ�B ���ɂɗ����ƃo�i�W�E���Ȃǂ̋������A���ɂɂ̓��`�E�����g���u�������d�r�v�͗��_�G�l���M�[���x�Ō��s�̃��`�E���C�I���d�r��4�{���x�Ƃ����B�u����Z���ł�1 kg������A500Wh�ɂ߂ǂ������v�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȁE���ȁu�Y�f���i�t���v�A�܂��N���W�b�g����������� �o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ̃J�[�{���v���C�V���O�i�Y�f�̉��i�t���j�c�_�ŕ��������o�Ă����B �o�Y�Ȃ͂܂��N���W�b�g����̊�������ʂ��Ė��Ԃ̎���I�Ȏ��g�݂��x������B�i�����i�܂Ȃ���Δr�o�ʎ�����x�ȂǂŋK������������j���A�L���҉�Ŏ������B���Ȃ������ŃN���W�b�g����𐄐i���Ă���A�r�o�ʎ�����x�͐��x�v�Ɏ��Ԃ�v���邽�ߏ����I�ȓ�����ڎw���B����A�o�Y�Ȃ��������I�ȑI�����Ƃ��Ď������u���{�ɂ��v���C�V���O�v������A�Y�ƊE����x���̐����オ��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�O���[�����f�A�ݔ�����v�C�X���G����H2Pro �C��ϓ���Ɏ��g�ނȂ��Ő��f���L�v���Ɣ��f�����Ƙb���^�������E�}���R���B���E���悭����d���������������B�C��ϓ���Ɏ��g�ނ̂���ԂƎv���A�l�X�Ȏ�i�̂Ȃ��Ő��f���L�v���Ɣ��f�����B����d�C�������Đ��f������ꍇ�A���嗬�̋Z�p�͐����琅�f�Ǝ_�f���Ɏ��o���A���҂�������Ȃ��悤�ɖ����g���B���̖��͈����Â炭�ĉ��i�������A�����u�̉��i�������グ�Ă���B H2Pro�Ђ̐��d���V�X�e���͐��f�Ǝ_�f��ʁX�Ɏ��o���B�����g���K�v���Ȃ����ߐv���P���ŁA���d�u�̐ݔ���������ɂł���B�d�ɂ̕Е��̉A�ɂŐ��f�����o���ԁA�_�f�͂����Е��̗z�ɂɏW�܂�B ���d���Ɏg���Đ��G�l��1��Wh������1.5�Z���g�i��1.6�~�j�ɉ����A���f�̐��Y�e�ʂ� 20���K���b�g�ȏ�ɍ��߂���A 2020�N��㔼�ɂ̓O���[�����f��1�L���O����������1�h���Ő��Y�ł���B���N�ɂ̓��K���b�g���̃V�X�e���œ� 500�L���O���������\��B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���������A�������ƂȂ�p�����z���p�l���̉���V�X�e�����J�� �������́A���������T�C�N�������������Ɖ��Z���^�[�Ƌ����ŁA�S�����́u�p�����z���p�l���X�}�[�g����V�X�e���v���J�������Ɣ��\�����B ���z�����d�̓������}���ɐi�W���A����A�g�p�ςݑ��z���p�l���̔r�o�ʂ������x�I�ɑ������邱�Ƃ��\�z����Ă���B�����ɂ͑S���I�ɂ������Ȃ����z���p�l���̍��x�ȏ����Z�p�������T�C�N���Ǝ҂�����A�����I�ȉ���V�X�e��������A�p�l���̃��T�C�N�����i���\�Ȋ��������Ă����B ���V�X�e���́A�p���p�l����ʔ��������ɔ������g�������h�̏z�^�V�X�e���Ƃ��āA�����e�i���X�Ǝғ��̔r�o�ҁA���W�^���ƎҁA���T�C�N���Ǝғ����A�p���p�l���Ɋւ���ۊǗʁA�ۊǏꏊ�A��ޓ��̏����N���E�h��̎x���\�t�g�ŋ��L���A�_�݂���p���p�l���������I�ɉ���A�Ď�������}��A�z�^�Љ�𐄐i����Ƃ��Ă���B���V�X�e���̗��p�ɂ��ẮA���� 30�N7��18���ɐݗ����ꂽ�A�u���������z�����d�iPV�j�ێ�E���T�C�N�����i���c��v�ւ̉������K�v�ł���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Y�����ƃg���^�A�t���L�V�u�����́u���z�d�r�v�Ő��E�ō��̌��d�ϊ�������B�� �Y�����ƁA�g���^�̌����O���[�v�́A�t���L�V�u�����ɓ��E�C���W�E���E�Z�����̉������iCIS�j�n���z�d�r���쐻�B 18�E6���̌��d�ϊ�������B�������B �t���L�V�u�����ł͐��E�ō��̐��l���Ƃ����B�y���Ȗʂɓ\��邽�ߑ��z�d�r�̓K�p�͈͂��L������t���L�V�u���Ōy�ʂȃZ���~�b�N�V�[�g���CIS�n���z�d�r���`�������B�K���X���ɍ��ꍇ�́A�K���X����i�g���E���Ȃǂ̃A���J�����������z�d�r�̌��z���w�Ɋg�U���Đ��\���オ��B����A�_��ȃZ���~�b�N��Ɍ`������ꍇ�̓A���J��������₤�K�v���������B �����ŃA���J���������������锖���̏�ɓd�ɑw�����A���̏�Ɍ��z���w���쐻�����B�d�ɑw�߂��ăA���J�����������������B���z���w�̐�����ɂ��A���J��������Y�����Đ��\�����߂��B���z�d�r�̐��\��\��FF��72���B�����1���b�g������35�~�̐����R�X�g��ڎw���ĊJ����i�߂�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2021/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���A�L�����z�[���A�Z��́u���M��\�����x�v���J�n�S��1�N�ԍ��z��ۏ� �Z��[�J�[�̃A�L�����z�[���O���[�v�ƁA�n��r���_�[�ō\�����ꂽ�g�D�E�X�}�[�g�A���C�A���X�r���_�[�iSABM�j�́A�Z��z�̍ۂɌ��z���M��i�d�C�����ƃK�X�����j��\������u�Z��̔R��\�����x�v���J�n�����B �����x�ł́A1�N�Ԃ̌��M����V�~�����[�V�����������l�����ɕۏB�Z��̃G�l���M�[�������鉻����ƂƂ��ɁA���M��������}����قnj��z��ɊҌ������d�g�݂ɂ��A�ȃG�l��E�Y�f�Љ�ւ̏���҈ӎ������߂邱�Ƃ�ڎw���B�V�z�Z��ɂ͏ȃG�l�����Ȃǂ�BELS�\�����x�͂�����̂́A���ی��M����X�����炩����̂��\�����鐧�x�͂Ȃ��B �܂����ЃO���[�v�͌��z�傩�����閈���̌��M��f�[�^��~�ρB�l�X�ȉƒ�̃P�[�X�ł̌��M��f�[�^�����W���A����̏Z�܂��Â���Ɋ��p����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�C�オ�オ��ƃG�A�R���̐ݒ艷�x��ς��郊���R�� �X�}�[�g�����R���uNatureRemo�v�i�l�C�`���[�����j���̔�����Nature�́A���̎��̓d�C��ɉ����ĉƓd���������삷��V�@�\�uSmart EcoMode�v�̒��n�߂��B Nature������d�C�����v�����uNature�X�}�[�g�d�C�v�ƘA�g���A�d�C�オ�����Ȃ鎞�ԑтɃG�A�R���ݒ艷�x���������߂���d�g�݁B���݂̓G�A�R���݂̂����A����Ή�����Ɠd��@�\��lj�����B�u�{�^��1�Ŏ�y�ɐߓd�E�ߖ�̌��ʂ�������v�Ƃ����B�Ɠd���������������u�I�[�g���[�V�����@�\�v�ɂ�30�����Ƃɕω�����d�͗ʗ����P���ɂ���ĉƓd���������삷��@�\��lj������B�\�ߐݒ肵���d�C�����P��������ƃG�A�R����Ɩ��������Ƃ������ݒ肪�ł���B�A�v���ɂ͒ʒm�@�\���������B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| ���f���\�[�^�H�����CO2�z�A���z���Ŕr�K�X���烁�^������ �f���\�[�́A�H�ꂩ��r�o�����CO2��������ďz���p������؎{�݁uCO2�z�v�����g�v���A���ЁE���鐻�쏊���Ɍ��݂��A���؎�����i�߂Ă���B ���\�����Z�p�́A�K�X���g�p����@�킩��̔r�K�X�Ƒ��z�����d�̓d�͂�p���Đ����������f���烁�^�����������A�K�X�g�p�@��ōė��p����d�g�݁B�L�c�����������Ƃ̋����J���ŁA2020�N7����������J�n�����B ���ؐݔ��́A�r�K�X�Ɋ܂܂�鐅������������E����A�f���\�[�̎����Ԕr�K�X�Z�p�����p����CO2�����A�������CO2�ƍ������鐅�f�����鐅�f�������u�A���^����CO2�Ɛ��f���獇�����郁�^����������A���z�����d�ݔ��Ȃǂō\�������B�����I�ɂ́A�f���\�[�̐��Y�ݔ���CO2�z�T�C�N���̓�����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���G�l�`�F���W�A���{���R�G�l���M�[�^�O���[���d�͏؏����l�b�g�̔� �G�l�`�F���W�Ɠ��{���R�G�l���M�[�́A�O���[���d�͏؏��I�����C�����s�v���b�g�t�H�[���u�O���[���E�J�[�g�v�̋����^�c���J�n�����Ɣ��\�����B �O���[���d�͏؏��̃I�����C���w���Ƒ������s���\�ɂȂ�A�\�����ݎ��̎�Ԃ�X�g���X���y�������B�؏��̍w�����i�͂P�L�����b�g��������S�~�B���B����ăG�l�͓��ʁA�o�C�I�}�X���d�݂̂����A���X�ɑ��z���╗�͂Ȃǂɂ��L����B ����܂ŃO���[���d�͏؏��͌����@�l�݂̂�ΏۂɃ��[���ȂǂŐ\�����݂��t���Ă���A�؏��̎�̂܂łP�J�����x�������Ă����B�V�T�[�r�X�͌l�ł��\�����߁A�؏����������s�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�ȂǓ����́u�S�M�����@�v�D�������ۂ��Ȃ��犷�C�A������� �V�^�R���i�E�C���X�̊�����ŁA�Ɠd�E���[�J�[���u�S�M������v�̔̔��ɒ��͂��Ă���B �X�܂�a�@�����ȂǂŋƖ��p�̔̔����D�����B�Ɩ��p�̖{�̉��i�͂P�O�����~���嗬�ŁA�������i�͐��\���~������̂�����B�Z��p�͐����~���炠��B�O�H�d�@�́u���X�i�C�v�̓r����X�܁A�Z��p�Ȃǂƃ��C���A�b�v�����낦�A���ĂȂǂł��W�J���Ă���B �����V�F�A�͋Ɩ��p�łV���A�Z��p�łT�����߂�B���X�i�C�ɂ͌ċz�ō��܂��_���Y�f�iCO2�j�Z�x���Z���T�[�ő��肵�Ċ��C���ʂ��������䂷�鐻�i������B����A�p�i�\�j�b�N�́A�S�M������ɃE�C���X�̔�U��}��������@�\�������A�ƘA�g����Z������V�X�e�����J�������B�������f�_���n�t�̐������u���g�ݍ��߂�B�_�C�L���́A�I�o���Đݒu����^�C�v�̑S�M������������B�V��ȂǂɉB���Ă������u��z�ǂ��A�����Ď{�݂̗��p�҂Ɍ�����悤�ݒu���A��������Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A�s�[���ł���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���X�^�[�o�b�N�X�A���ГX�܂Ŏg�p����d�͂�100���Đ��\�G�l���M�[�� �X�^�[�o�b�N�X�́A�X�܂Ŏg�p����d�͂�CO2�r�o�ʃ[����100���Đ��\�G�l���M�[��ւ���i�߂Ă���B �k�C���A���k�A����������A�H�ʂ̒��c�X301�X�܂�2021�N4�����܂łɐ�ւ����������A10�����ɂ͖k�C���A���k�A������܂߂���350�X�܂֍L����B����ɂ��A���{�����̃X�^�[�o�b�N�X�̖�2���ɂ�����A���ړd�͂̌_�\�ȘH�ʂ̒��c�X�ɂ����āA�Đ��\�G�l���M�[�ւ̐�ւ�����������B �܂��A�X�^�[�o�b�N�X�͓d�͂̋�����̑I��ł́A�u�n��̓d�͂��A�n��̓X�܂Łv�z�ł��邱�Ƃ��ӎ����Ă���B���̎��g�݂́A2020�N1���A�u���\�[�X�|�W�e�B�u�J���p�j�[�v��ڎw���A�N�V�����̈�Ƃ��ăO���[�o���Ŕ��\�����A2030�N�܂ł�CO2��50���팸����ڕW�B����Nj�������́B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���n�����g�����L�����p�X����l���悤��s���Ȃǂ̂X��w���u���R�G�l���M�[��w���[�O�v �[��������n�����g���ɃL�����p�X�����Ɏ��g�����ƁA��s���Ȃǂ̂X��w���u���R�G�l���M�[��w���[�O�v�������B �ݗ�����ŁA��\���b�l�̐�t���ȑ�w�����u2030�N����40�N���߂ǂɑ�w���Đ��\�G�l���M�[100�����������Ă������Ƃ��A�Љ�̕ω�����������v�ƘA�g��i�����B ����ł͖싅�O���E���h�Ւn�ł̑�K�͑��z�����d�����݂�w���̏ȃG�l�����ȂǂŁA���d�ʂƏ���d�͗ʂ����x���ɂ��邱�Ƃ��������Ă���B ��q��w�́u���[�O�i�O���[�v�j�����邱�ƂŁA�����A�w�����𗬂��A�ȃG�l�Ɍ��������܂��܂Ȏ��g�݂��ł���H�v�����Ă��������v�Ɛ��������B�Q���Z�͂��̂ق��A������Ȏ��ȑ�A���S���q��A�����O�����A���ۊ����A�a�m���q��A���쌧����A�L���� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���Ζ����V�F����CO2�팸���߁A�I�����_�̍ٔ���2030�N�܂ł�45���A�ڋq��̔r�o�ɂ��ӔC ���ۓI�Ȋ�NGO�i�{�g�D�j��FoE�I�����_���I�����_�s��1��7000�l�̋�����������ё���6���c�̂ƂƂ��ɋN�������i�ׂɂ����āA�I�����_�E�n�[�O�̒n���ٔ����́A���ېΖ����{�E�p�����C�����E�_�b�`�E�V�F���̋C��ϓ����ɑ���ӔC��F�߂锻�����������BFoE�I�����_��5��26���i���n���ԁj�ɔ��\�����B �����ł́A�V�F���̌��݂̋C��\���łȂ��ƔF�肵�A2030�N���܂ł�CO2�r�o�ʂ�����45���팸���邱�Ƃ𖽂����B�܂��A�ڋq�i�X�R�[�v3�j����уT�v���C���[����̔r�o�ɂ��Ă��ӔC���Ƃ��A�V�F���ɑ��Ē����ɂ��̔��f�ɏ]���悤���߂��B FoE�I�����_�̔��\�ɂ��ƁA�ٔ������������������N�����Ă�����Ƃɑ��ăp������̏���𖽂����̂͏��߂ĂƂ����B����̔����́A��K�͂Ȋ������������炵�Ă��鑼�̑��Ƃɂ��e����^����\��������Ƃ��Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�[���G�~�b�V���������헪2020 Update &Report�v������ 2019�N12���ɁA�s��2050�NCO2�r�o�����[���Ɍ������u�[���G�~�b�V���������헪�v�����\���Ă���1�N���܂�A�V�^�R���i�̖҈Ђɂ�萢�E�����]�L�̊�@�ɒ��ʂ��钆�ŁA�C���@�͈̏�w�[�������Ă���B ���̂��߁A�s�́A2030�N�J�[�{���n�[�t�Ɍ����ĕK�v�ȎЉ�ϊv�̎p�E�r�W�����Ƃ��āu2030�E�J�[�{���n�[�t�X�^�C���v���N�B�g�������A�s�����������鎞�FTIME TO ACT�h�������t�ɁA�����O�̂������̂ɍs���̉������Ăт����A�u�E�Y�f�v�Ƃ������E���ʂ̃S�[���Ɍ����čX�Ȃ�A�g�E������i�߂Ă����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����ۑS�ɂ��������I�N���E�h�t�@���f�B���O�𐬌��ɓ��� ���ۑS�E�Ǘ��ɂ����鎑���s���͐��E�e�n�Ŏ��R���̏����������N�����Ă���B�������������́A��500���̊��ۑS�Ɋւ���N���E�h�t�@���f�B���O�v���W�F�N�g�͂��A�������B�̐����v���𖾂炩�ɂ����B |
|
|
| �������ȁA�Z��́u�����f�M���C�v�ɕ⏕���⏕��1�^2�E�ő�100���~ ���y��ʏȂ́A�����Z��̈ꕔ��f�M���C������؎��Ƃ̕�W���J�n�����B���C�O��̒����E�]�����s�����Ƃ������ɉ��C���Ǝ҂��x������B�⏕�̏���z��1�˂�����ő�100���~�i�ΏۍH�����1�^2�ȉ��j�B��W���Ԃ�7��21���܂ŁB �Ώە�����1999�N�ȑO�Ɍ��݂��ꂽ�ˌ��ďZ��ΏۂŁA���N�̏ȃG�l����݂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ������B�Z��S�̂ł͂Ȃ�������t���A�P�ʂʼn��C����BLDK��Q���Ȃǂ̋����̂ق��A���܂��A�L�������܂ސ�����Ԃ�ΏۂƂ������C��ԓ��ɂ����āA����̗v���̒f�M���C�����߂�B �܂��A���C���ʂ𖾂炩�ɂ��邽�߁A���C�����̏��L�҂́A���C�O��Ɍ��ʂ������邽�߂̒����⑪��ɋ��͂���K�v������B��̓I�ɂ͎������x���z�̒�����G�l���M�[����ʒ����ȂǁB�ǂ̂悤�Ȓ����E������s�����ɂ��Ă͕⏕�̑����ɁA�Ώە������ƂɎw�肷��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2021�N�Łu�G�l���M�[�����v���t�c����2050�N�E�Y�f�ւ̓��� �G�l���M�[����2021���t�c���肵���B��1���ł́A��N�̕��������̐i���ɉ����A2050�N�J�[�{���j���[�g���������Ɍ������ۑ�Ǝ��g�݁A�G�l���M�[�Z�L�����e�B�̕ϗe�ɂ��āA���͂������ʂ��܂Ƃ߂Ă���B 2050�N�J�[�{���j���[�g���������Ɍ����ẮA�d�͕���ł͔Γd���̊g��A��d�́i�Y�ƁE�����E�^�A�j����ł̓G�l���M�[�̓d���A���f���A�c��CO2�̉���E�����p��ʂ����E�Y�f����i�߂邱�Ƃ��K�v�Ƃ��Ă���B �܂��A�u���{�̎Y�ƁE�Z�p�����́v�Ƃ��āA2050�N�J�[�{���j���[�g�����ɔ����O���[�������헪��14����̊e���̓��������͂͂������ʂ��܂Ƃ߂Ă���B���{�̒m�������͂́A4����Ŏ�ʁB�Љ�����i�K�ŕ����Ȃ��悤�A�x������K�v������Ƃ����B�܂��ACO2�������Ƃ��Ċ��p����u�J�[�{�����T�C�N���v���������B �ăG�l��ʓ����ɕK�v�ȏ_��ݏo�����߁A�~�d�e�ʊg�傪�d�v�ɂȂ�Ǝw�E�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�����K�͎��Ə��̏ȃG�l����x�������R���T���ʼn^�p���P �����s�����Ђ́A�ȃG�l��T�|�[�g���Ǝ҂̏ȃG�l�R���T���e�B���O��A�ȃG�l�R���T���e�B���O����������Ǝғ������H����^�p���P�̈ꕔ�ɑ��ď�������2021�N�x�u�n��̑��l�Ȏ�̂ƘA�g���������K�͎��Ə��ȃG�l�x�����Ɓv�̐\����t���J�n�����B ��t���Ԃ�2022�N1��14���܂ŁB�����Ƃ́A�ȃG�l��T�|�[�g���Ǝ҂���̒�����Ǝғ��ւ̖����̏ȃG�l�R���T���e�B���O�ɂ��A������Ǝғ��̋�̓I�ȏȃG�l���M�[�s���̎��H�̕��y���i��ڎw���B �����i1�j�ȃG�l�R���T���e�B���O�����ΏێҏȃG�l��T�|�[�g���Ǝҏ����Ώیo�����Ǝғ��ւ̏ȃG�l�R���T���e�B���O�ɌW��o����z�������Ώیo���10�^10�i����z��100���~�j �����i2�j�^�p���P�̎��H�x�������ΏێҒ�����Ǝғ������Ώیo��^�p���P�̎�g�ɌW��o��̈ꕔ�����z�������Ώیo���1�^2�i����z��50���~�j �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2021/6�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�X�A�w�Z�ł̏ȃG�l����ʼnƒ��CO2�r�o�ʂ�5���팸���邱�Ƃ��m�F �����K�X�́A�i�b�W���_����p�����w�Z�����u�ȃG�l����v���O�����v���J�����A2017�N�x����2020�N�x�̊��Ȃ̎��؎��Ƃ�ʂ��āA�ȃG�l���炪�ƒ��CO2�r�o�ʂ��5���팸���邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�����B ���v���O������2017�N4���`2021�N3���ɂ����āA�S���̏��w�Z30�Z�A���w�Z21�Z�A�����w�Z19�Z�A��w14�Z�̌v84�Z�i�Q���ЁF9,899�l�j�Ŏ��{�B��u�������������w�Z�̎����E���k�̉ƒ�ŁA�d�C�ƃK�X�̎g�p�ɔ���CO2�r�o�ʂ�5.1���팸������ʂ��݂�ꂽ�ق��A�ȃG�l�s�����H����21���|�C���g���シ�邱�ƁA���������ʂ̎����������邱�ƁA�����E���k�ւ̋��炪�ԐړI�ɉƑ��ɂ��e����^���邱�ƂȂǂ��m�F�����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�F�����A���{�ƃA�W�A�Łu�_�n�Y�f�����v���Ɛ��i��Indigo�ЂƋ��� �Z�F�����́A�A�O���e�b�N�n���j�R�[����Ƃł���IndigoAgriculture�i�č��}�T�`���[�Z�b�c�B�j�ƁA���{�ƃA�W�A�𒆐S�Ƃ����u�_�n�Y�f�����v���Ƃ̐��i��ړI�ɁA���ƂɌ������o��������������Ƃ����\�����B �]���A�_�n��CO2�̔r�o���Ƃ���Ă������A�_�@����ł�CO2�̔r�o��}���A��C����CO2��n���ɌŒ肷�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�_�n�ւ̒Y�f�����ʂ̊g��ɂ́A�֍��Δ�Ȃǂ̊��ۑS�^�_�Ƃ̓������L�������A�_�Ƃ̘J�͂ƃR�X�g���傪�ۑ�ƂȂ�B Indigo�Ђ́A��C����CO2�̍팸�Ǝ����\�Ȕ_�Ƃ̗�����ړI�Ƃ��āA�_�n�ւ̒Y�f�����𐄐i���鎖�ƁuIndigoCarbon�v��W�J�B���ۑS�^�_�Ƃ̓����ɂ�葝�������Y�f�̒����ʂ��A��O�ҔF�ؕt���̔r�o���Ƃ��Ĕ������A��ƂȂǂ֔̔�����d�g�݂��\�z���邱�ƂŁA�_�Ƃ̃R�X�g���S���y���������\�Ȕ_�Ƃւ̃V�t�g�Ɏ��g��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ACO2�r�o�ʂ̎Z��x������T�[�r�X ���Ђ́A��Ƃ̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ̎Z����x������T�[�r�X���n�߂��Ɣ��\�����B �T�v���C�`�F�[���i�����ԁj�S�̂̃f�[�^���W���V�X�e�������āA�ڋq�̃R�X�g���ƕ��S���y������B���J�������₷���Ȃ�AESG�i���E�Љ�E��Ɠ����j�����̌Ăэ��݂ɂ��Ȃ���B�����R���T���e�B���O�ƘA�g���A�����̊����Ǘ��V�X�e���u�G�R�A�V�X�g�E�G���^�[�v���C�Y�v�Œ���B �@�֓����Ƃ��d�v�w�W�Ƃ��Ċ��p�����������̊J���x����A��Ƃ̒E�Y�f�Ɍ������R���T���e�B���O�Ɩ����Z�b�g�Ŕ��荞�ށB �E�Y�f�ւ̊S�����܂�Ȃ��A�����}�l�[��ESG�̊ϓ_�őI�ʂ����߂Ă���B���J�����s�\�����ƕK�v�ȓ��������Ȃ��Ȃ鋰�������B�r�o�ʂ̎Z��ɖ��N���S���~�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�T�[�r�X������f�[�^�̃`�F�b�N�Ȃǂ��������ł��A�����������������^�p�R�X�g�����x�ɗ}������B �o�T�u�G���N�g���j�N�X�v |
|
|
| ��TPT�A���z���p�l�����T�C�N�����ƂɎQ���^��ё̐��Ŏ��v���ɐ�� �����p���[�e�N�m���W�[�iTPT�j��4�����瑾�z���p�l���̃��T�C�N�����Ƃ��J�n�����B �֓��n���𒆐S�Ɍ��꒲�������́A�^���A���T�C�N���܂ł̃g�[�^���T�[�r�X��W�J����B�V������FIT���������Ԃ̏I���Ńp�l���P���E�������{�i������2030�N����������Đ���ł��A�s��ł̑��݊������߂�B��胊�T�C�N���Z���^�[�̏����\�͂�9.6t/��(��480��/��) TPT�ł�2016�N���璌��ψ���⒆��^�@���PCB�i�|�������r�t�F�j�[���j�������Ƃ���|���Ă���B����܂łɒ���ψ����35����A2�`35�g�����̕ψ���Ȃǒ���^�@���400������������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������A�v�VCO2��������n�o���E���Y�f�@�ۂŕ������\�ƍ��ϋv���𗼗� �����́A���E���Y�f�@�ۂ�p���āA�D�ꂽCO2�̕������\�ƍ��ϋv�������˔������v�VCO2��������n�o�����Ɣ��\�����B ���������͓V�R�K�X��o�C�I�K�X�̐����ɓK�p�\�ŁA����ɁA�����ΏۃK�X�ɍ��킹�āA�l�X�ȕ����@�\�w��I�����邱�Ƃ��ł���������������āA���f�����E�����A�r�C�K�X��CO2�����Ȃǂ̃K�X�����p�r�ւ̉��p���\���Ƃ����B ���������́A���a300�}�C�N�����[�g�������ׂ̍�����̑��E���Y�f�@�ۂ��x���̂Ƃ��A���̕\�ʂɐ��}�C�N�����[�g���̔��ɔ����Y�f���̕����@�\�w���ψ�Ɍ`�������A�I�[���J�[�{����2�w�\����L����B �x���̂ƕ����@�\�w�����ꂼ��Ɨ����Đv���邱�ƂŗD�ꂽCO2�������\�ƍ��ϋv���𗼗������Ƃ����B�܂��A�_��Ŕ��ɍׂ����߁A�ʏ�̑@�ۂƓ����悤�ɘA�����Y���\�ŁA�����x�[�U�ł��邱�Ƃ��烂�W���[���̏��^�����\�ŁA�]���̖��@�nCO2���������W���[���Ɣ�ׂāA����̐ςōő�5�{��CO2���ߗʂ���������Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������̎_�����n�S�ő̓d�r�A�d�ʃG�l���M�[���x500���b�g����_���Z�F���w �Z�F���w�͋��s��w�Ƃ̋��������ŁA�_�����n�̌ő̓d�������g���ăL���O����������̏d�ʃG�l���M�[���x500���b�g������������S�ő̓d�r�Z�p�̊J����ڎw�����Ƃ𖾂炩�ɂ����B �d���t���g�����`�E���C�I���d�r�̌��E�l�Ƃ�����S���\���b�g����2�{�߂��̐����B2023�N3�����߂ǂɊ�{�Z�p�����������A���̌�͎��p���Ɍ����đ��ЂƂ̘A�g������ɓ����B �S�ő̓d�r�̓d�����͗������n�̌�������s���A��ʓI�Ɏ_�����n�͎��̐���Ɩڂ����B�����Ɣ�������ƗL�łȗ������f�K�X�������闰�����̌��O�ɑ��A�_�����n�͂��ꂪ�Ȃ��B�������n�ɂ͗�邪�C�I���`�����̗D�ꂽ�������������Ă���A���������ŊJ������������B ����A��s����V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO�j�ȂǎY�w���̑S�ő̓d�r�v���W�F�N�g�ł́A2025�N���y���f���Ƃ��ďd�ʃG�l���x300���b�g���A2030�N���y���f���Ƃ��ē�400���b�g���̓d�r��ڎw���Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������@�B�ȂǁA�啪�̉���������ŏ����K�X���d���ƊJ�n�^���ݖ��cFIT���� �����@�B�Ɠ����Z���`�����[�́A�����}�[�G�l���M�[�V�X�e���Ƌ����ŁA���Îs�ɂ����āA����������Ŕ�����������K�X�i�o�C�I�K�X�j�����p�������d���Ƃ��J�n�����B �ݒu�����̂́A�����K�X���d�ݔ�1���i�ݔ��e��49kW�A�K�X�G���W��24.5kW�~2��j�B�N�Ԕ��d�ʂ͖�42��kWh�B���d���Ɗ��Ԃ�20�N�Ԃ�\��B ���Îs���玖�Ɨp�n�̒���ƂƂ��ɁA����������Ŕ�����������K�X�i�o�C�I�K�X�j�𒆒Îs����w�����A20�N�Ԃ̔��d���Ƃ��s���B���Ԃ̎����ƃm�E�n�E�����p�������ݖ��c�����ɂ�鉺��������ł̏����K�X���d���ƂŁA�����@�B�����Ȏ����Ŕ��d�ݔ������݂��A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�𗘗p���ēd�C���Ǝ҂ɔ��p����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�����J�q��F���ǁA�������ʃK�X�̑�ʂȕ��o�����鑕�u���J�� �A�����J�q��F���ǂ́A�F�����烁�^���Ɠ�_���Y�f�iCO2�j�̔���������肵�đ��肷�鑕�u���J�������B ��c���c�́uCarbonMapper�v�̏����@��2023�N�̑ł��グ��ڎw���Ă���A�Ő�[�̃C���[�W���O�X�y�N�g�����[�^�[��p���ċ�C���̃��^����CO2�Ȃǂ̕��q�ŗL�̃X�y�N�g���T�C�����ϑ�����B �]���̃C���[�W���O�X�y�N�g�����[�^�[�́A�𑜓x���Ⴉ�������߁A�V�R�K�X�̃p�C�v���C���̋T��̘R��ȂǁA�������ʃK�X�iGHG�j�������̐��m�Ȉʒu����肷�邱�Ƃ�����ł������B���̂��߁A����J�����ꂽ�C���[�W���O�X�y�N�g�����[�^�[�œ����鍂�𑜓x�摜�𗘗p����AGHG�r�o���̓���ɖ𗧂��A���͏��Ȃ������^����CO2�r�o�ʂ̕ϓ��̑啔�����߂�u�X�[�p�[�G�~�b�^�[�v�̔����ɍv������B����̎��g�݂́A��c���c�́A��w�A�J���t�H���j�A�B����\�������R���\�[�V�A���Ƌ����ʼnF���~�b�V�������s�����߂Ă̎��݂ł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ����������z�ʉ݂̓d�͏��Ő����鋐�僊�X�N CO2�r�o��2024�N�ɂ�1.3���g���ɒB����\�� �����Ȋw�@�Ɛ��ؑ�w�̌����҃O���[�v���A�Ȋw�G���w�l�C�`���[�R�~���j�P�[�V�����Y�x��ɁA�����ɂ����鉼�z�ʉ݂̓d�͏���ʂ�2024�N�ɂ̓s�[�N�l��296��5900��Wh(���b�g��)�ɒB���A1��3000���g������CO2(��_���Y�f)���r�o�����Ƃ̗\���\�����B �r�b�g�R�C���̃}�C�j���O��A�u���b�N�`�F�[���Z�p�̊��p�ɂ͑�ʂ̓d�͂��K�v�Ƃ����B������1�N�Ԃ̑��d�͏���ʂ̓f���}�[�N�A�A�C�������h�A�o���O���f�V���Ȃǂ̒������Ƃ̓d�͏���ʂɕC�G���ACO2�̖c��Ȕr�o�ɂ��Ȃ����Ă���B �����ł͂����̖�肪�[�������Ă���B�Ƃ��ɔ_���n��́A�d�C�����������A�}�C�j���O�{�݂ɓK�������J���̓y�n����ʂɑ��݂��邽�߁A�u�}�C�j���O�̗��z�I�ȗ��n�ł���v�ƋƊE�W�҂��璍�ڂ���Ă���B���̌��ʁA�����ɂ�����r�b�g�R�C���̃}�C�j���O���s���v�Z�\�͂�2020�N4�����_�Ő��E�S�̂�78.89�����߂Ă���B�Ȃ�炩�̐����I������K�v�B �o�T�u���V Biz��Tech�v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA�\�[���[���d�R�X�g��2030�N�܂ł�60���팸����ڕW�\ �A�����J�G�l���M�[�Ȃ́A2030�N�܂łɃ\�[���[���d�R�X�g��60���팸����Ƃ����V���ȖڕW�\���A�\�[���[�Z�p�̃v���W�F�N�g�ɑ��z1��2800���h�����������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B ���݂̃R�X�g��kWh������4.6�Z���g�ł��邪�A2025�N�܂ł�3�Z���g�ɁA2030�N�܂ł�2�Z���g�ɂ܂ʼn����邱�Ƃ��߂����B ���z�����d����ł́A�V���ȑ��z�d�r�f�ނł���y���u�X�J�C�g�ƃe�������J�h�~�E���iCdTe�j�̌����J���A�n�Ǝ����ɂ��N�ƉƎx���A�V���R����p����PV�V�X�e���̒��������̃v���W�F�N�g����������B�W���^���z�M���d�iCSP�j����ł́A���u�̐M�����Ɛ��\�̌���A�����㑕�u�̎��Ȃǂ��ΏۂƂȂ��Ă���B�o�C�f��������2035�N�܂łɓd�͕�������S�ɒE�Y�f������ڕW���f���Ă���A����̓����ɂ���ă\�[���[�Z�p�̃R�X�g�팸�A�����\���A�v���ȓW�J��i�߁A�ቿ�i�̃N���[���d�͂̕��y���߂����Ƃ����B �o�T�u�G�R�i�r�v |
|
|
| �����ȂȂǁA2019�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʁi�m��l�j�����\ ���Ȃƍ������������́A2019�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʁi�m��l�j�Ȃǂ����\�����B ���̊m��l�́A�C��ϓ��Ɋւ��鍑�ۘA���g�g���Ɋ�Â��A���{�̉������ʃK�X�̔r�o�E�z���ژ^�Ƃ��ď���ǂɐ����ɒ�o������́B 2019�N�x�̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂ�12��1,200���g���iCO2���Z�j�ŁA2018�N�x��2.9%���A2013�N�x��14.0%���A2005�N�x��12.3%���ƂȂ����B���Ȃł́A��}����ɂ�����n�C�h���t���I���J�[�{���ނ̔r�o�ʂ������������̂́A1)�G�l���M�[����ʂ̌����i�����Ƃɂ����鐶�Y�ʌ������j�A2)�d�͂̒�Y�f���i�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��j�ɔ����d�͗R����CO2�r�o�ʂ̌������������v���B�Ȃ��A2019�N�x�̋z���������ɂ��r�o�E�z���ʂ́A�X�ыz������ɂ��4,290���g���A�_�n�Ǘ��E�q���n�Ǘ��E�s�s�Ή������ɂ��300���g���ƕ���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��30�N�ăG�l�ő�Q�����ց^�G�l���A���s�ڕW��E�����ʌ��ʂ���� �����G�l���M�[���́A2030�N�̍Đ��\�G�l���M�[�����ʂ̌��ʂ����������B �����̓����y�[�X���ێ������ꍇ�̔��d�d�͗ʂ�2707���L�����b�g���ƁA���s�̃G�l���M�[�~�b�N�X�i2030�N�x�̓d���\���j�����Ɣ�ׁA7�`14��������Ǝ��Z�B����ɐ�������������ꍇ�́A��15�`22������2903���L�����b�g���܂Ŋg�傷�錩�ʂ����܂Ƃ߂��B�����_�Œ�ʓI�Ȍ��ʂ�����\�����s���m�Ȑ���͐D�荞��ł��Ȃ����߁A������[�߁A����Ȃ��ς݂�T��B ���������G�l���M�[������̍Đ��\�G�l���M�[��ʓ����E������d�̓l�b�g���[�N���ψ���Ŏ����ǂ��������BFIT�ɂ��F��E�����y�[�X�ƁA����܂ł̉�ł̃q�A�����O�����ƂɌ��ʂ����܂Ƃ߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���č��ő������u�K�X�֎~�v���ACO2�팸�Ɍ������H�K�X�ƊE�͖Ҕ����A�K�X�֎~�Ă��֎~����B�� �J���t�H���j�A�B�̃o�[�N���[�s�c��A2019�N�āA�قƂ�ǂ̐V�z�̌����ɑ��ēV�R�K�X�ݔ��̐ݒu���֎~�����B CO2�̔r�o���ׂ��Ƃ���A�����ł̓V�R�K�X�̎g�p���傫���A���̔r�o�ʂ͎s�S�̂̔r�o�ʂ̎���37%���߂Ă����B�o�[�N���[�s�̐��I�ȏ����A�����̓s�s�����l�̋K���ɏ��o�����B2019�N�ȍ~�A�J���t�H���j�A�B��40�ȏ�̓s�s�����l�̏��������Ă���B���݁A�R�����h�B�A���V���g���B�A�}�T�`���[�Z�b�c�B���A�K�X�̎g�p���֎~�����Ă��������Ă���B����A����܂łɁA�A���]�i�B�Ȃ�6�̏B�ŁA�V�R�K�X�֎~���̐�����֎~����@�Ă�������Ă���B �܂��A�ق���14�B�ł����l�̖@�Ă���������Ă���B�����̔r�o�ʂ����炷�ɂ́A���ڔr�o����g�[�A�������I�[���d�����邱�Ƃ��B�V�R�K�X���ߏ����d�C�́A����A�ăG�l���������I�ɐi�ށB �o�T�u�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���{�Łv |
|
|
| �����ۊC�^�́u2050�N�[���G�~�v�֊e�����A�g�C��ϓ���̋������m�F �A�����J���O������Â����]��u�C��ϓ��T�~�b�g�v�ɂ��킹�A���{���Ԃ�4��21���A�C�^�E�C�m����Ɋւ�����ʃZ�b�V������Web�`���ŊJ�Â��ꂽ�B ���ē�10�J���̊t�������o�Ȃ��A�č��̃P���[�C��ϓ����g�́A���ۊC�^��2050�N�܂łɃ[���G�~�b�V�����������ł���悤�A�e���ƘA�g���A���ۊC���@�ցiIMO�j�ɂ����Ė�S�I�ȍ팸�ڕW�Ƃ��̎����̂��߂̑���Ɏ��g�ނƕ\�������B���{����́AIMO�C�m���ی�ψ���c���߂鍑�y��ʏȂ̍֓��p���Z�p�R�c�����o�ȁB�C�^�E���D�卑�Ƃ��āA�[���G�~�b�V�����D��2028�N�܂łɎ������A���ۊC�^�̒E�Y�f�������[�h����ƂƂ��ɁA�e���ƘA�g���AIMO�ɂ����Ė�S�I�����ʓI�ȍ��ۃ��[���̍���Ɏ��g�ނƏq�ׂ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2021/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���C�[���b�N�X�^�u�������A���f��Ĕ��d�����Ɖ^�]���֒��� �C�[���b�N�X�́AHydrogenTechnology�iHT�Ёj�ƁA���f��Ăɂ�锭�d�A�y�єR���d�r�����ԁi�ȉ��uFCV�v�j�ւ̐��f�����Ɋւ��鋤�����ƊJ�������i�ȉ��A�u�{�v���W�F�N�g�v�j�Ɋւ���o������������B �{�v���W�F�N�g�́AHT�ГƎ��J���́u���v�Ɓu��ΗR���̐G�}�v�݂̂ɂ��퉷�E�ሳ�̉��A�u���f�v�����o���Ƃ����V�Z�p�ɂ������Ȑ��f��p���āA���d���ƁA�R���d�r�����Ԏ��ƂȂǕ��L�����f���p�ɂ��Č����A��g�ށB ����1st�X�e�b�v�Ƃ��āAHT�Ђ̋Z�p��p���āA���f��Ĕ��d���s���ׂɏ\���Ȑ��f�������A�A���I�ɓ�����Ƃ��������s�����߁A�����d�̓p���[�O���b�h���ɂR�SkW���̐��f���d���̌��݂��A2021�N�x���̉^�]�J�n��ڎw���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����K�X�^�@�l������CO2�[���̓d�C�ƃK�X��̔��E�Y�f�o�c���x�� ���K�X�́A�u�J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�v�ƁA�Đ��\�G�l���M�[100���̐V�d�C�������j���[�̐\���ݎ�t���J�n�����B �u�J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�v�́A�V�R�K�X�̍̌@�A�A���A�����A�R�Ă̂��ꂼ��̍H���Ŕ�������CO2��CO2�N���W�b�g�ő��E�����u�J�[�{���j���[�g����LNG�v�����p����B��ɋƖ��p�E�H�Ɨp����̌ڋq��Ώۂɔ̔����Ă����v��B �܂��A�ăG�l100���d�C���j���[�̂����uD-GreenPremium�v�́A�Đ��\�G�l���M�[��FIT���x�𗘗p�����A�d���̔Ώ؏����ăG�l�d�C�ƂƂ��ɋ�������d�C�������j���[�B�Ώ؏��ɔ��d���̖��̂⏊�ݒn�A���d���@�A���d�ʁA���d�����Ȃǂ��L�ڂ�����������t�^���邱�ƂŁA���ۓI�C�j�V�A�e�B�u�̈�ł���RE100�̗v�������Ƃ����B �܂��A��]����ڋq�ɂ́A�Ώ؏��̗R���ƂȂ锭�d����Daigas�O���[�v���\�ȓd�����X�g�̒�����s���{���P�ʂŎw��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�u���]�C���u���^40�X�܂Ȃǂ��ăG�l100����NTT����p���d����V�� �Z�u�����A�C�́ANTT�O���[�v�ƘA�g���A�Z�u���]�C���u��40�X�܂̉^�c�ɂ�����g�p�d�͂�100���Đ��\�G�l���M�[������Ɣ��\�����B NTT�A�m�[�h�G�i�W�[���A�I�t�T�C�gPPA�i�d�͍w���_��j�̎d�g�݂�2�̑��z�����d����V�݂��A���z�d�Ԃ���ēd�͋������s���B�I�t�T�C�gPPA�����ł͕s������d�͂́ANTT�O���[�v�����L����O���[���d�͔��d������̓d�́i�O���[���d�́j�����p����B�g���b�L���O�t�Ώ؏���t�^���邱�ƂŁA���d������肵���`�ł�100���Đ��\�G�l���M�[�g�p�X�܂���������B �Z�u�����A�C��4����菇���A�ăG�l�d�͂����Ă����B�Z�u��-�C���u��40�X�܂ł́A6������O���[���d�͂ƃI�t�T�C�gPPA�iNTTAE��t��t���z�����d���j�ɂ�鋟�����J�n����\��B �Z�u�����A�C��2019�N�Ɋ��錾�ŁACO2�r�o�ʍ팸���d�_�e�[�}��1�ɒ�߁A2050�N�܂ł�CO2�r�o�ʂ������[���ɂ���ڕW���f���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�v�\���O���[�v�^2023�N�܂łɍăG�l100���A������2021�N�Ɏ����� �Z�C�R�[�G�v�\���́A�S���E�̃G�v�\���O���[�v���_�ɂ����Ďg�p����d�͂��A2023�N�ɂ�100���Đ��\�G�l���M�[�Ƃ��邱�Ƃ����肵���Ɣ��\�����B �܂��A�����Ƃő��Ђɐ�삯�āA���{�������ׂĂ̋��_�ɂ�����100���ăG�l����2021�N�Ɏ�������ڕW���f�����B 2019�N�x��2017�N�x��ŁA18���̉������ʃK�X�r�o�ʍ팸�i�X�R�[�v1�E2�j��B�������B���̂�����6����ɓ������6��2��g���̍팸�́A��ɍ����̐��͔��d���͂��߂Ƃ�����Y�f�d�͂̒������B�_��Ȃǂɂ������������̂ŁA����ɂ��ăG�l�̔䗦���12���܂ō��߂Ă���Ƃ����i�d�̓x�[�X�ł͖�16���j�B �����ł́A2020�N4���ɖ{�ЂȂǍ���3���_��100���ăG�l�������B�C�O���_�ł́A�p���A�č��A�t�B���s���̐��Y���_�A�p���E�h�C�c�Ȃǂ��ׂẲ��B�̎Ђ̖{�Ћ��_�Ŏg�p����d�͂����ׂčăG�l�Řd���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���b�n�Q����b�n�����A��^�G�}�d�ɂō������^���� ���ł́A��_���Y�f�iCO2�j�����w�i�̌����ƂȂ��_���Y�f�iCO�j�ɕ�������Z�p�ŁA�]����60�{�̏������x��B�������B �����ɗp����G�}�d�ɂ��^������Ƌ��ɁA�S���̐G�}�d�ɂ�ϑw����Z�p���J���B���ؑ��u��CO2��N�ԂP�g�����x�����ł���Ƃ����B ���ł͐G�}�d�ɂ̖ʐϊg��Ɏ��g�݁A2020�N��㔼�̎��p����ڎw���BCO2��r�o���邲�ݏ����H���Η͔��d���ւ̓K�p������ɓ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������K�X�^���l�s��65�Z�֑��z�����d�E�~�d�r���������{�݂֎��ȑ����� �����K�X�A���l�s��65�Z�֑��z�����d�E�~�d�r���������{�݂֎��ȑ����������K�X�Ǝq��Ђ̓����K�X�G���W�j�A�����O�\�����[�V�����Y�iTGES�j�́A65�Z�ɑ��z�����d�ݔ��i���ϖ�60kW/�Z�j�ƒ~�d�r�i���ϖ�20kWh/�Z�j��ݒu���A�œK�^�p����A�ێ�Ǘ��ȂLj�т��Ď��{����B ���d�d�͂͏����w�Z�Ŏ��Ə����ƂƂ��ɗ]�蕪��~�d�r�ɏ[�d���A���J�V���ɗL�����p���邱�ƂŁA1�Z�������2����CO2�팸�A���ƑS�̂ŔN��1,700�g����CO2�팸�������ށB��d���ɂ͑��z�����d�ݔ��ƒ~�d�r����p�d���Ƃ��Ċ��p���A����̏Ɩ���R���Z���g�Ȃǂɓd�͂���������B�Đ��\�G�l���M�[�̗]�蕪���A���̉��l�s�������{�݂֎��ȑ������A�w�Z�Ŕ��d�����ăG�l�d�C�́u100���n�Y�n���v��ڎw�����g�݂����{����B ���{���Ǝ҂�2021�N�x����2022�N�x�ɂ����Đݔ������A�ݒu�������z�����d�ݔ��ɂ��d�͂��w�Z��������B���Ɗ��Ԃ͍Œ�20�N�ԁB �o�T�u�����r�W�l�X�v |
|
|
| ���`�h���p�̐������[�^�[�A�R�ꌟ�m�Ŕ�Q�h�~���E�ō̗p�L���� �C�X���G���̐V����Ƃ��l�H�m�\�iAI�j�����p�����������[�^�[���J�����A���E�ō̗p���L�����Ă���B AI���g�����������[�^�[�uWINT�v�͊����̔z�ǃV�X�e���ɑg�ݍ���Ŏg���B �ʏ�̐��̗�����w�K���A�ُ킪����Ό��m���A��Q���o��O�ɕs��̉ӏ����Ւf����BWINT�̓Z�����[�l�b�g���[�N����ăN���E�h�ɐڑ����A�A�v�����g���ă��A���^�C���̕��͂�x���̏���ʒm����B ���J�n����2012�N�ɂ͏Z�������z�肵�Ă������A���̌㐅�̔�Q�␅�R��ɂ�閳�ʂ�h��������Ƃ��ΏۂƂȂ����B�s��Q������9�N�����A�A���S���Y���̉��ǂ��d�˂�WINT�́u�ߐ��e�b�N�v�Ƃ��ĔF�m���l���B 2019�N�ɂ͕č��≢�B�ɐi�o���A���Ƀ}�C�N���\�t�g��HP�A�}�X�^�[�J�[�h�Ƃ���������Ƃ��̗p���Ă���B�r���̐���25���͗��ꑱ����g�C���������̐��R��Ŏ����Ă���Ƃ����B �o�T�uCNNnews�v |
|
|
| �����z�����d�Ŏ���ꂽ���A�l�H�̗сE�����Ȃǁu���R�v�����S ���oBP�������������́A���z�����d�ɂ��y�n���ς̎��Ԃ𖾂炩�Ƃ��邽�߂ɁA�o��500kW�ȏ�̑��z�����d����n�}�����A�K�͂╪�z�̓����������Ɣ��\�����B ���̌��ʁA������500kW�ȏ�̑��z�����d����8725�{�݂��m�F����A���R�̊��ɊY������ꏊ�ł̌��݂��������Ƃ����������B �Đ��\�G�l���M�[���d�{�݂́A���̏ꏊ�̐����E���Ԍn�E�����Ȃǂ̎��R���ւ̉e����ʂ��āA���R���{�̑������������ꂪ����B���ɑ��z�����d�́A�L���ڒn�ʐς�K�v�Ƃ��邽�߁A���ւ̉e�������O�����B �����`�[���͍���A500kW�ȏ�̂��ׂĂ̑��z�����d����ΏۂɁA�q���摜��q��ʐ^�����p���A���z�����d�ݒu�O�̐��Ԍn�̔c�����A���R�I�E�Љ�I�������������f�����\�z�����B���̌��ʁA���{�S�̂ŁA66.36���𒆋K�́i500kW�`10MW�j�{�݂���߂��B����ꂽ���Ԍn�́A�сE�l�H�сA�l�H�����A���A���c�ȂǗ��R�̊��������X���ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2019�N�x�������ʃK�X�r�o�ʂ�12��1300���g�����g����v��i�� ���Ȃ́A�u2019�N�x�ɂ�����n�����g����v��̐i���v�����\�����B ���{�̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂ́A2019�N�x����l�ŁA��12��1300���g���i��_���Y�f���Z�j�ŁA�O�N�x���2.7%�����A2013�N�x���14.0%�����A2005�N�x���12.2%���������B 2019�N�x�̔r�o�ʂ��O�N�x�̔r�o�ʂƔ�ׂČ��������v���Ƃ��ẮA�G�l���M�[����ʂ̌����i�����Ƃɂ����鐶�Y�ʌ������j��A�d�͂̒�Y�f���i�ăG�l�g��j�ɔ����d�͗R����CO2�r�o�ʂ̌�������������ꂽ�B �������ʃK�X�iGHG�j�̂����G�l���M�[�N��CO2��2019�N�x�r�o�ʂ́A10��2900���g���B�O�N�x��ł�3.4���������A2013�N�x��ł�16.7%���A2005�N�x���14.2�����������B ����ʂ̔r�o�ʂ́A�Y�ƕ���i�H��Ȃǁj�F�r�o�ʂ�3��8600���g���B�O�N�x��3.0�����B�Ɩ����̑�����i�������Ȃǁj�F�r�o�ʂ́A1��9200���g���B�O�N�x��4.7�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������o���u�ꗥ�R�N�ȏ�v�^�d�C�H���m�@���� �d�C�H���m�@�{�s�K���ɂ��A��P��d�C�H���m�Ə�������Ŏ擾����ꍇ�ɂ́A�������i�ɉ����A��w�E����̓d�C�H�w�n���̎҂łR�N�ȏ�A����ȊO�̎҂łT�N�ȏ�̎����o�����K�v�Ƃ���Ă����B ���ʁA�d�C�H���̎{�H���@���ƍH��̋Z�p�i�����ɂ���Ƃ̌������Ȃǂ̊��ω��܂��A���Ԓ������s������ŁA�d�C�ۈ����x���[�L���O�O���[�v�ɂ����ċc�_�����Ƃ���A���Y�����o���͑�w�E����̓d�C�H�w�n���̗L�����킸�A�ꗥ�R�N�ȏ�Ƃ��邱�Ƃ��Ó��Ƃ̌��_������ꂽ���߁A�d�C�H���m�@�{�s�K���̈ꕔ�������s�����B ����ɂ���āA�ߘa�R�N�S���P���ȍ~�ɑ�P��d�C�H���m�Ə�̌�t�\�����s���ꍇ�A��P��d�C�H���m�����̍��i���Ɋւ�炸�A���i���ꂽ�S�Ă̕��̕K�v�Ȏ����o�����R�N�ȏ�ƂȂ�B �o�T�u�o�ώY�Əȁv |
|
|
| ���h�C�c�A�M���ȁA���E�̐����̌���ƍ���̎��g�݂�� �h�C�c�A�M���ȁiBMU�j�́A3��22���́u���E���̓��v�ɂ�����A���E�̐����̌���ƍ���̎��g�݂�����B �o�ϐ����Ɛ��E�l���̑����ɔ����Đ��̎��v�͑����̈�r�����ǂ��Ă���A�ߋ�100�N�ԂŐ��E�̐�����ʂ�6�{�ɑ������A���N��1%�������������Ă���B ����ŁA�C��ϓ��ɂ�葽���̒n��Ŋ����Ԃ����тĂ���A���E�l���̖�3����1�ɂ�����22���l�́A���܂��Ɉ��S�Ȉ����������I�ɓ��邱�Ƃ��ł����A42���l�͈��S�ȉq���{�݂𗘗p�ł����ɂ���B���̂悤�Ȕw�i���獑�A����́u�����\�ȊJ���̂��߂�2030�A�W�F���_�v�̐��Ɋւ���ڕW�̎��{�Ɍ��������g�݂𐄐i���邽�߁A�u���̍��ۍs����10�N�iWater ActionDecade�j�v�i2018�`2028�N�j��錾�����B 2023�N�ɂ͍��A�̉�c�Ői���̒��ԃ��r���[���s���邪�A����͍��A�ɂ�鐅���ɓ���������c�Ƃ��Ă�2��ڂł���A46�N�Ԃ�̊J�ÂƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������A�g�ɂ�鉺�����M���p�𑣐i�`�����M���p�}�j���A���������` �����̐����͈�N��ʂ��Ĕ�r�I���肵�Ă���A��C�̉��x�Ɣ�Ă͒Ⴍ�A�~�͍���������L���Ă��܂��B ���̂��߁A���̍Đ��\�G�l���M�[�M�ł��鉺���M���g�[�⋋�����ɗ��p���邱�Ƃɂ���āA�啝�ȏȃG�l�E��CO2����}�邱�Ƃ��ł���B ���y��ʏȂł́A����27�N�ɉ������@���������s���A���Ԏ��Ǝ҂ɂ�鉺�����Ǔ��ւ̔M������̐ݒu�Ɋւ���K���ɘa���s���ƂƂ��ɁA�u�����M�}�j���A���i�āj�i����27�N�V���j�v�������A�s���E���Ԏ��Ǝ҂ɂ�鉺���M�̊��p�g��𐄐i���Ă����B ���ʁA�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����������̏܂��A�����M�}�j���A�������Ɍ������ӌ�������i�ߘa�Q�N�x�J�Áj�̋c�_���o�āA�ȉ��̉������s���A�u�����M���p�}�j���A���i�āj�v�Ƃ��Č��\�B �o�T�u�����ȁv |
|
|
| �����z��CO2�ʼn��w�i������u�l�H�������v�A���ǂ��܂Ői��ł�H �A�����A���z�G�l���M�[�𗘗p����CO2�Ɛ�����L�@���i�ł�Ղ�j�Ǝ_�f�ݏo���u�������v�B ���{���ڎw���u�J�[�{���j���[�g�����v�ɂ����Ă��ACO2�팸�Ɋ�^����A���̂������������͏d������Ă���B���̌�������͂��āA���z�G�l���M�[��CO2�ʼn��w�i���������悤�Ƃ��Ă���̂��u�l�H�������v�Z�p���B �J�������A�u���G�}�v�ɂ�����u���z�G�l���M�[�ϊ������v�́A�A���̌������Ɠ������炢�i0.2�`0.3%�j�������B���f�Ǝ_�f��ʁX�̌��G�}�Ő�������u�^���f���Z���^���G�{�v�Ƃ������@�ŁA2017�N�x�Ɍ�����3.7���܂ŏ㏸���Ă���B2019�N�ɂ�5.5����B�������B���݂͂����7.0���܂ŏ㏸���Ă���A2021�N�x�̍ŏI�ڕW�ł���10���܂ŁA���Ə����ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���E���̋Z�p�ł���A�����ɒu���đ��z�������Ă�ΐ��f�Ǝ_�f�����邱�Ƃ��ł���V�[�g�u���������^���G�}�V�[�g�v�́A���݂́A���z�G�l���M�[�ϊ�����1.1����B�����Ă���B �o�T�u�����G�l���v |
|
|
| ���@�@[�@2021/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���J�[�{���j���[�g����LNG�o�C���[�Y�A���C�A���X�ݗ��ɂ��� �����K�X�A�A�T�q�O���[�v�z�[���f�B���O�X�A�����U�����ԂȂ�15�Ђ́A�J�[�{���j���[�g����LNG�i�ȉ��uCNL�v�j�o�C���[�Y�A���C�A���X��ݗ������B �{�A���C�A���X�́ACNL�̕��y�g��Ƃ��̗��p���l����̎�����ړI�Ƃ��Đݗ������B�C��ϓ����SDGs�ւ̍v���AESG��ƌo�c�ɒ�������d�v�ȃ\�����[�V�����̈�ƂȂ�B �Q��e�Ђ́A2050�N�́u�J�[�{���j���[�g�����Љ�̎����v�ɍv�����邱�Ƃ�ڎw���ACNL�𐢂̒��ɍL���F�m������ƂƂ��ɁA�����@�ւɂ��]������⍑���e�퐧�x�ɂ�����ʒu�Â��̊m���Ɍ����Ď��g�݂𐄐i����BCNL�́A�V�R�K�X�̍̌@����R�ĂɎ���܂ł̍H���Ŕ������鉷�����ʃK�X���ACO2�N���W�b�g�ő��E�i�J�[�{���E�I�t�Z�b�g�j���A�R�Ă����Ă��n���K�͂ł�CO2���������Ȃ��Ƃ݂Ȃ�LNG�B�����K�X��2019�N�ɗA�����J�n���A�J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�Ƃ��ċ������J�n�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������K�X�^���N���g�ɃJ�[�{���j���[�g�����s�s�K�X���������ƊE�֏� �����K�X�̓��N���g�{�ЂƃJ�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�̋����Ɋւ����{���ӏ�����������B 2021�N4������2026�N3�����܂ł�5�N�ԁA���N���g�{�В����������ɋ�������s�s�K�X�̑S�ʂ��J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�ɐ�ւ��邱�ƂŁA��11,500�g����CO2�팸�ɍv������Ƃ����B�����ʂ͔N��80��m3�B �Ȃ��A�����K�X�������ƊE�����ɃJ�[�{���j���[�g�����s�s�K�X����������͍̂����߂āB��������J�[�{���j���[�g�����s�s�K�X�́A�����K�X���V�F���O���[�v����w�������J�[�{���j���[�g����LNG�iCNL�j�����p�������́B�V�R�K�X�̍̌@����R�ĂɎ���܂ł̍H���Ŕ������鉷�����ʃK�X���A�V�F���ۗ̕L����CO2�N���W�b�g�ő��E�i�J�[�{���E�I�t�Z�b�g�j����Ă���B���N���g�́u�R�[�|���[�g�X���[�K���w�l���n�������N�Ɂx�̂Ƃ���A�n�����S�̂̌��N������ɓ��ꂽ���Ɗ����𐄐i���Ă����v�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������^�I�t�B�X�r���Ɂu�J�[�{���j���[�g�����v�d�͂��^�s���Y�Đ����Ƃ� �T���t�����e�B�A�s���Y�́A���Ђ���|����s���Y�Đ����Ƃɂ����āA�X�їR����J-�N���W�b�g�����p�����d�́u�O�ێR�т̐X�̂łv�i�ȉ��A�X�̂łj���uPORT ONESHIMBASHI�v�lj����������Ɣ��\�����B 100���J�[�{���j���[�g�����iCO .�r�o�[���j�����������r���͌v3���ƂȂ����B ���Ђ́A�z�N���o�߂����s�S�̒����^�r���̍Đ����Ƃ�W�J���Ă���B2020�N12������A�s���Y�Đ������̐V���ȕt�����l�Ƃ��āA���{�ȓd��ʂ��u�X�̂łv�̒��B���J�n�B�����s������̃r��2���ɓ��������B�_�ސ쌧�R�k���O�ێR�т̈�сA�Ԕ��Ȃǂɂ��A�z�����ꂽ�����l���w�����邱�Ƃɂ���āA����Ȃ�X�т̕ۑS���x��������̂��B����ɂ��A�r���ɓ������邱�ƂŐX�ѕۑS�ւ̎Q�悪�\�ƂȂ�A�u�X�̂łv�𗘗p���ăJ�[�{���j���[�g�����Ŏ��Ƃ��s���Ă��邱�Ƃɂ��āA���Ζ@�ւ̕ɂ����p�ł���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���听���݁^�J�[�{�����T�C�N���E�R���N���[�g�J��CO2���x���}�C�i�X�� �听���݁ACO2���x���}�C�i�X�ɂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�J�[�{�����T�C�N���E�R���N���[�g�uT-eConcrete�^Carbon-Recycle�v���J�������Ɣ��\�����B �����ߒ��Ŕr�o�����CO2�ʂɑ��āA�H��̔r�C�K�X�Ȃǂ��������CO2���琻�����������u�J�[�{�����T�C�N���ޗ��v�̒Y�_�J���V�E�����A���F�X���O��̂̌����ނɂ��ʼn������邱�ƂŁA�R���N���[�g������CO2���Œ肷��Z�p���J�������B �Y�_�J���V�E������āA�R���N���[�g1m3������70.170kg��CO2�̌Œ肪�\�B�Œ肷�������CCS�ɕC�G����Ƃ����B�����ߒ��ɂ�����CO2���x���|55kg/m3�`�|5kg/m3�ƃ}�C�i�X�ɂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ����i���ʃR���N���[�g��CO2�r�o�ʂ�250�`330kg/m3�j�B�R���N���[�g�����A���J������ێ����A�R���N���[�g�����̓S�̕� .��h�����Ƃ��ł��A�]���ۑ�ł������R���N���[�g�\�����̑ϋv�����ێ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ቷ�p�M�A���߂čė��p�^���d�d�o�Ȃǂ��V�X�e���̔��A����������̂b�n�Q�팸 NEDO�A�����M�w�H�ƁA�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�iEP�j�Ȃ�8�҂́A�ቷ�p�M�𗘗p�����~�M�V�X�e���̎��؎��������{�����B ��^�g���[���[�ŗ��ꂽ�ꏊ�ɔp�M��A������I�t���C���M�A���^�ƁA��u�^��2�����Ō��B����܂Ŗ����p�̂܂ܔr�o���Ă����ቷ�p�M���H��̊����H���≷���v�[���̉����Ɋ��p���A��_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ�7�`8���팸�����B����A�V�X�e�����s��W�J���R�X�g�ጸ��}��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���J���r�[�^�o�C�I�}�X�C���L�̓����\��Ȃǂ\ �J���r�[�́A�o�C�I�}�XPET��ށE�o�C�I�}�X�C���L��K�p������ށi�ȉ��u���z����ށv�j�Ƃ��鏤�i��AFSC�F�؎���p�����o�חp�i�{�[�����̎g�p���g������Ɣ��\�����B ���Ђ́A��̃X�i�b�N�َq�̈ꕔ�ɂ����āA2020�N12��������z����ނ̓������J�n���Ă���B2021�N2�����A�u�����i�v�ɂ����āA����p�C���L�̊�{���F5�F�i�n�E�ԁE�E���E���j�������o�C�I�}�X�C���L�ɐ�ւ���B�܂��A���N3�����ȍ~�́A�p�b�P�[�W���ʂɂ�����u�o�C�I�}�X�}�[�N10�i�F��@�ցF���{�L�@��������j�v�̕\���i�u�n�v�ȊO�̓h�F����j�AFSC�F�؎���p�����o�חp�i�{�[���ւ̐�ւ��A�i�{�[���\�ʂ̔F�}�[�N����A�O���̂��鏤�i�ɂ�����FSC�F�؎��̎g�p�g��Ȃǂ��������{����B2020�N9���Ɍ��\�������Ђ́u�v���X�`�b�N�����z�̐��i�ڕW�v�Ɋ�Â���g�ł���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���_�C�_���^�C�X�w�N���}�`�F�A�x�̔��J�n �_�C�_���̓I�J�����Ƌ����J����i�߂Ă����C�X�w�N���}�`�F�A�x�̖{�i�̔����J�n�����B �C�X�́A��[���[�h�ƒg�[���[�h������Ă���B ����[���[�h�����ʂ�ʋC���̂���f�ނƂ��A���ʂ����C���z������ō��ʗ����ɐݒu�������o�����琁���o���B ���g�[���[�h�����ʂɓ��������q�[�^�[���ڗ����������߂邱�Ƃɂ��A�����̗₦���ɘa����B ��[���[�h�ł͑̊����x��1�����x��������ʂ������A�g�[���[�h�ł͑̊����x��1�����x�グ����ʂ�������B�w�N���}�`�F�A�x�́A�^�X�N���A���r�G���g�̃^�X�N�p�r�Ƃ��Ă����łȂ��A�N���E�h�^��������V�X�e���ƘA�g���邱�ƂŁA�̏ȃG�l���M�[�ɂ��Ȃ���B��̓I�ɂ́A�����Z���T�[�ɂ�获���҂̍݁A�s�݂����m���A�s�ݎ��ɂ͕����S�̂̃A���r�G���g�𐧌䂪�\���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���u�[���J�[�{���V�e�B�v130�s�撬�������c��������⍑�֒� �E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����������⍑�ɒ��s�����Ƃ�ړI�ɁA2050�N��_���Y�f�r�o�����[����\�����Ă���S����130�s�撬���i�[���J�[�{���V�e�B�j���A�u�[���J�[�{���s�撬�����c��v�i��F�ѕ��q���l�s���j��ݗ������B ���l�s�́A��s�s�Ƃ��ē����c��̂Ƃ�܂Ƃ߂��s���ƂƂ��ɁA���s���o�Ȃ���u���E�n���E�Y�f������c�v�Ȃǂɂ����āA�[���J�[�{���s�撬���̈ӌ��M���Ă����Ɣ��\�����B ���ʂ́A�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ�������̓I�Ȏ��g�݂̂��߂̋c�_�A��������̂̈ӌ��̏W��Ȃǂ����{���A2021�N3�����{�ɍ��ւ̒��s�����Ƃ�ڎw���B�����E�����Җڐ��ł�2050�N�E�Y�f�Љ�����Ɍ��������[�h�}�b�v�̍��蓙�ɂ��āA���ƒn���Ō����E�c�_����u���E�n���E�Y�f������c�v�������B2020�N12��25���ɑ�1���c���J�Â��ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����t��^���ŃJ�[�{���j���[�g���������������铹���� ��t��w�̌����O���[�v�́A���G�l���M�[�𗘗p����CO2��R�������锽���i�ȉ��uCO2���R�����v�j�������I�Ɏ��������B CO2�̕����͗e�Ղł͂Ȃ��A�����œ����G�l���M�[�̏��Ȃ��Ď������Z�p���͍�����Ă���B�������O���[�v�́A��s�����̐��ʂɊ�Â��A�V���ȃj�b�P��.�_���W���R�j�E�����G�}�i�ȉ��u�V�K���G�}�v�j���쐻�����B 2���Ԃɂ킽��A13C���ʑ̂�W������13CO2�������Ɍ����āA�V�K���G�}�Ɏ��O���Ɖ��������Ǝ˂��Ȃ���A���A���^�C���ŐG�}������ǐՂ��A���I�Ƀ��^���i13CH4�j�����̗l�q���ϑ������B���̌��ʁACO2��1)�_���W���R�j�E���\�ʂŒY�_���f�Ƃ��ċz�����A2)���O���̍�p�����܂��ĒY�_���f���Ҍ�����A��_���Y�f�iCO�j�������A3)���f��CO���j�b�P���̕\�ʂʼn���������ϊ����ꂽ�M�ɂ�蔽�����ă��^���iCH4�j���������锽�����i�s���邱�Ƃ����������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������s�L���b�v���g���[�h���x�A21�N�x�̒�Y�f�d�́E�M�������Ǝ҂����\ �����s�́A��K�͎��Ə���CO2�r�o�ʂ̍팸���`���t�����L���b�v���g���[�h���x�ɂ����āACO2�팸�ʂɎZ��ł���i2021�N�x����ʁj�ACO2�r�o�W���̏������u��Y�f�d�́v�E�u��Y�f�M�v����������2021�N�x�̔F�苟�����Ǝ҂����\�����B 2021�N�x�̒�Y�f�d�͔F�苟�����Ǝ҂�19���Ǝ҂ŁA�O�N�x�ɔ��7���Ǝґ������B�܂��A��Y�f�M�F�苟������44���ŁA�O�N�x�ɔ��2��摝�ƂȂ����B�F��ΏۂƂȂ鋟�����Ǝ҂̗v���́A��3�v����ԁi2020�`2024�N�x�j�ł́A�d�g�݂̊g�[��}���Ă���B���Ƃ��A�u��Y�f�d�́v�ł́A�Ή��l�؏����́u�����l�v�����p�����d�͂�u�d�̓��j���[�i0.370 t-CO2�^��kWh�ȉ��j�v�ʂ̔r�o�W�����F��̑Ώۂɒlj�����ȂǁA���v���̑I�������g�傷��ƂƂ��ɁA�Ώێ��Ə�����Y�f�d�͂̋��������ꍇ�ɎZ��ł���팸�ʂ��g�[���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�u�J�[�{���v���C�V���O�v���x�v�����J�n���������[�u�������� �o�ώY�ƏȂ́A�Y�f�r�o�ɉ��i�����r�o�҂̍s����ϗe�����鐭���@�u�J�[�{���v���C�V���O�v�ɂ��āA���x�v�̕��������c�_���錤����̏�����J�����B �Y�f�ł�r�o�ʎ�����x�݂̂Ȃ炸�A���������[�u�A�N���W�b�g����Ȃǂ��܂߂��L�����_�ŋc�_��i�߂�Ƃ����B5���܂ł�5����x�J�Â��A�Ă�����߂ǂɒ��Ԑ����A�N���Ɉ��̕������̎��܂Ƃ߂��s���\��B 2020�N12���Ɍ��\���ꂽ�u�O���[�������헪�v�ł́A�u�����헪�Ɏ�������́v�ɂ��ẮA�������x�̋�����Ώۂ̊g�[�A�V���Ȑ��x���܂ߑΉ����������邱�ƂL���Ă���B������ł́A���{�ɂƂ��āu�����Ɏ�����J�[�{���v���C�V���O�v�Ƃ͉����A�L���҂�o�ϊE����̃q�A�����O����ʂ����A�t�@�N�g�x�[�X�ł̋c�_��i�߂�l���B���Ă��A�C��ϓ���̕s�\���ȍ�����̗A���i�ɑ��A�Y�f�r�o�ʂɉ����Đ��ۂŒ����[�u���u����u���������[�u�v�ɂ��Č�����i�߂�Ȃ��A�����ȋ����������m�ۂ���ϓ_���K�v���Ǝw�E�����B��1�E�S�̂ł̃J�[�{���j���[�g���������̂��߂̌o�ϓI��@���̂�����Ɋւ��錤����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����̃Q�b�v��鉷�����ʃK�X�������Y������27�`40���팸 ���̎����ł́A��������̃z���X�^�C���E�t���[�V�A����64�����ΏۂƂ��āA�z���̈قȂ鎔���ɂ��ꂼ�ꃁ�^���}���܂�⋋�A���^���̍팸�ʂ������B���̌��ʁA�����̎�ނ�Bovaer�̓Y���ʂɂ���ĕς�邪�A��1��������̃��^���K�X�r�o�ʂ�27�`40���팸�ł��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ����B �I�����_�̑������w���[�J�[Royal DSM�́A�I�����_�Ŏ��{���������ŁA���Ђ��J�������V���������Y�����uBovaer(R)�v������̎����ɉ����邱�ƂŁA�����ɂ�郁�^���̔r�o�ʂ��팸�ł��邱�Ƃ������ꂽ�Ɣ��\�����B ���݁A�e���̗��_�E�����o�����[�`�F�[���e�ЂƂ̋��Ƃɂ��A��s�Ɍ�����������i�߂Ă���B��̓I�ɂ́A���n�̃r�W�l�X�V�X�e���ɂ�����L�������m�F���邽�߂̋��������A��Y�f���_���i�̋����J���A�r�W�l�X���f���̊m���ȂǂɎ��g��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���E�Y�f���Ɍ������ݔ������ɐŐ��D���Y�Ƌ����͋����@�̉����@�Ă��t�c���� ���{�́A�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ������E�Y�f����i�߂�ݔ��ɑ��铊����A�f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����iDX�j�̎����ɕK�v�ȓ������x������Ő��D���[�u���荞�Y�Ƌ����͋����@�Ȃǂ̉����@�Ă��t�c���肵���B ����̉����@�ẮA�|�X�g�R���i�ɂ����鐬���̌���ƂȂ� �@�i1�j�u�O���[���Љ�v�ւ̓]�� �@�i2�j�u�f�W�^�����v�ւ̑Ή� �@�i3�j�u�f�W�^�����v�Ɍ��������ƍč\�z �@�i4�j������Ƃ̑����������𑣐i���邽�߂̑[�u���u������́B ����ɂ��A�u�V���ȓ���v�Ɍ�������g����肵�A�������_�ɗ�������Ƃ̕ϊv���㉟�����邱�ƂƂ��Ă���B�u�O���[���Љ�v�ւ̓]���ł́A�J�[�{���j���[�g���������Ɍ��������Ǝ҂̌v����喱��b���F�肵�A�ȉ��̎x����[�u����B�u���r�W�l�X�v�E�E�Y�f�����ʂ��������i�̐��Y�ݔ��̓������i�E���Y�H�����̒E�Y�f����i�߂�ݔ��̓������i�E���Z�x���i���q�⋋���j |
|
|
| ���@�@[�@2021/3�@]�@�@�� |
|
|
| ��ENEOS�A�r�M�𗘗p�����M�d���d�V�X�e���������J���� ENEOS�́A�l�X�ȍH��ȂǂŔ�������r�M��d�͂ɕϊ����A���̓d�͂����Ə���邱�Ƃōw���d�͂̍팸���\�ɂ���M�d���d�V�X�e���Z�p�̊m���Ɗ��p�Ɍ����������J�����J�n����Ɣ��\�����B �V�R�K�X�ɓ������ėN�o���邩�i��80���j��A������z�Ǖ\�ʂɔM�d���d���W���[����ݒu���A�����̖�ԏƖ��̈ꕔ�ɋ�����Ƌ��ɁA���d�ʂ��v����������s���B ���ɂ����ẮAE�T�[���W�F���e�b�N���J�������A�p�ȉ\�ȔM�d���W���[�����̗p����B���̔M�d���W���[����p���Ĕz�lj��x�ƊO�C���Ƃ̉��x���𗘗p���Ĕ��d����BENEOS��E�T�[���W�F���e�b�N�́A���d�ʂ̌v�����s���A�Ό��܂߂��ϋv���≮�O�ł̔��d�ʂɊւ���Z�p���ƔM�d���d�V�X�e���J�����s���B2023�N��ړr�ɍœK�ȑ��u�\���A�V�X�e�����̐v�E�\�z���s���A�������E��R�X�g�ȔM�d���d�Z�p�̒�ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�H�d�H�A�ăG�l��CO2����R��������ăX�^�[�g�A�b�v�ɏo�� �O�H�d�H�Ƃ́ACO2�ƍĐ��\�G�l���M�[����N���[���R���u�G���N�g���t���[�G���v������v�V�I�Z�p�����āu�C���t�B�j�E���v�Ђɏo�������Ɣ��\�����B �C���t�B�j�E���Ђ́A�q��@��D���A�g���b�N�Ȃǂ̔R�����l�b�g�[���J�[�{���R���ɓ]���ł���Ǝ��Z�p�����B ����A��ʕ���Ȃǂɂ�����E�Y�f���Ɍ��������p�K�͂̃N���[���R�������ݔ����J�����邽�ߎ������B�����{�B�č��̃A�}�]���iAmazon's Climate PledgeFund�j�A�p���̓����t�@���h�ł���AP�x���`���[�Y�iAP Ventures�j���܂ޕ����̃����o�[�ƂƂ��ɏo������Ƃ����B �G���N�g���t���[�G���\�����[�V�����́A�Đ��\�G�l���M�[��p���ăO���[�����f�����A���̃O���[�����f��CO2���g�p���āA�����̉t�̔R���ɑ���l�b�g�[���J�[�{���R���Y������́B���p���ł���A�A�����ɂ�����CO2�̔r�o�ڍ팸���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����҂���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�A�V�^SOEC�̎���ɐ����u���^�l�[�V�����v�Z�p�̎����̃J�M�� ���K�X�́ACO2�Ɛ��f����s�s�K�X�̎听���ł��郁�^������������u���^�l�[�V�����v�Z�p�̎����̃L�[�ƂȂ�A�V�^SOEC�i Solid Oxide ElectrolysisCell�j�̎��p�T�C�Y�Z���̎���ɐ��������Ɣ��\�����B SOEC�͐����C��CO2�������œd�C��������f�q�ŁA�����G�l���M�[�ϊ������Ń��^���������ł���\��������B ���́uSOEC���^�l�[�V�����v�Z�p�́ASOEC��p���āA����CO2�ƂƂ��ɓd�C�������邱�Ƃɂ���Đ��f��CO�����A����ɐG�}�����ɂ���ă��^��������������́B���^���������̔r�M��L�����p�ł��邽�߃G�l���M�[�������������A�]���Ɣ�ׁA��85�`90���ƍ����G�l���M�[�ϊ����������҂���A��R�X�g�������҂����Ƃ����B�V�^SOEC�͏]���^�ɔ�ׁA�ϏՌ������������x�ł���A�X�P�[���A�b�v�̎������e�Ղƍl���Ă���B����A�����J�����������A2030�N���ɋZ�p�m�����邱�Ƃ�ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����l�A�Г��́u�Y�f���i�v��6,000�~�^���ɐݒ�ݔ������̔��f��� ��l�́A��l�O���[�v�̐ݔ�������ΏۂƂ��āA�C���^�[�i���J�[�{���v���C�V���O�iICP�j���x�������B ����ACO2�̔r�o�������ݔ������v��ɂ��ẮA�ݒ肵���Г��Y�f���i�u50���[���^t.CO2�i6,000�~�j�v��K�p����Ƃ����B ICP���x�Ƃ́A�Г��ɂ�����Y�f���i��ݒ肵�ACO2�r�o�ʂ��p���Z���邱�ƂŁA�r�o�ʍ팸�ɑ���o�ϓI�C���Z���e�B�u��n�o���A�Г��ŋC��ϓ��ւ̑Ή��𑣂��d�g�݂̂��ƁB����ݒ肵���Г��Y�f���i�͒�l�O���[�v���O���[�o�����ʉ��i�B�ΏۂƂȂ�ݔ������v��ɔ���CO2�r�o�ʂɑ��A�Г��Y�f���i�̓K�p�ɂ���p���Z�������̂��A�������f�̎Q�l�Ƃ���B ���Ђ́A����ICP���x�̓����ɂ��ACO2�r�o�팸�ɍv������ݔ������v����㉟�����ACO2�r�o�팸�Ɋւ��钷���ڕW�̒B����ڎw���ƂƂ��ɁA�����\�z�����O���[�o���ł̒Y�f���i�̏㏸�ɔ�������ɂ���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������݁A���U�t�@���ɂ��ȃG�l�V�X�e���uOCTPUS�v���J�� �_�C�L���H�Ɗ�����ЂƋ����ŊJ�������{�V�X�e���́A��K�͂ȃI�t�B�X�r���Ȃǂō̗p�����Z���g���������ɂ����āA�]�[�����ɕ��U�ݒu�����t�@���t���ʐ��䑕�u�iFPU�j�Ƌ@���̋��C�t�@����A�g���Đ��䂷�邱�ƂŁA�]�[�����̔M���ׂɍ��킹�ĕK�v�ŏ����ʂ̋�C���œK�ȉ��x�ŋ�������BFPU�̉^�]�ɂ�蕪��_�N�g�o�H���ɑ���������s�����߁A�G�l���M�[���X��h�����Ƃ��ł���B OCTPUS�ł́A�@��FPU�̗����𐧌�ł��邽�߁A�������ׂ��M�ʂ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�@���~��FPU�݂̂ŋ��C���邱�Ƃ��\�B����ɂ�萧�䉺�����ʂ�10�����x�܂ōi�邱�Ƃ��ł���B��ʓI�ȃI�t�B�X�r�������f���Ƃ����V�~�����[�V�����ł́AVAV�V�X�e���ɔ�ׂāA�N�ԋ�C�����G�l���M�[����ʂ��ő��44���팸�\�Ǝ��Z�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���O�H�d�@�A���ƎҌ������C�@���X�i�C�̃u���b�N���f���B��t���ȒP�ȕNJ|���^�C�v ��t���ݒu���e�ՂȕNJ|��t�^�C�v�̃u���b�N���f�����B10���p�ƁA18���p��2�@������C���i�b�v�B ���ƎҌ������i�͏���41,800�~�A79,800�~�B�M�����@�\�Ƌ�C����t�B���^�[�𓋍ڂ����������r���C��B 1��ŋ��C�Ɣr�C���ɍs�Ȃ��A�����̉��ꂽ��C��r�o����ƂƂ��ɁA��C����t�B���^�[�ʼn��O�̋�C���L���C�ɂ��ċ��C����B�܂��M�����@�\�ɂ��A���C�ɂ���Ď������g�[�G�l���M�[��������A�ȃG�l������������B�V���i�́A�O�ςɃu���b�N���̗p���邱�Ƃŗ�����������Ԃ����o������H�X�╨�̓X�܂Ȃǂɒ��a����B�ǂɐ��t���鐻�i�̂��߁A�_�N�g�z�ǂ̎{�H�͕s�v�B������{�݂̓V��������ƂȂ��A��t���ݒu���e�Ղȓ_�������Ƃ��Ă���B �o�T�u�C���v���X�v |
|
|
| �����������ȂǁA�I�t�B�X�̋�AI�Ő����5���̏ȃG�l���ʂ��m�F ���������A���c�m�s�Ȃǂ́A�I�t�B�X�̋�AI�Ő��䂷����؎��������{���A���x�����̉����Ɩ�5���̏���G�l���M�[�팸���ʂ��m�F�����Ɣ��\�����B �����������d�F�r��7�K�̃I�t�B�X�t���A�ʼnĂƏH�̋�ΏۂɎ��{�B�I�t�B�X�t���A��65�̖����Z���T�[��ݒu���A�����̃f�[�^�����AI���t���A��39��̋@������s�����B AI�̎��O�w�K���s������A2020�N7��27���`11��27���̊��ԂɁA�t���A�S�̂�26���𒆐S�Ɂ}2���͈̔͂��ێ�����悤�ɃV�X�e����v�E�^�p�B�����Z���T�[��p���āA�d���̌`�Ԃ�d��������ꏊ�Ȃǂɍ��킹�āA�Ј������x��̊��ł���ʒu�ɐݒu�����B���̌��ʁA�u�Ċ��ɂ����鉷�x�����̉����v�Ɓu�H���ɂ��������G�l���M�[�̍팸�v��B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������o�ϘA����u�J�[�{���j���[�g�����Ɋւ���A���P�[�g�����v�\ �J�[�{���j���[�g�����̒B���ɂ́A���o�A�Ƃ��Ă��A�����ƁE�c�̂ւ̏�M���A�l�X�Ȍ`�ł̎x�����s���ƂƂ��ɁA�����ƁE�c�̂̈ӌ��f���������܂Ƃ߁A���{���W���ʂɌ��c���邱�Ƃ��l���Ă���B�����ŁA�u2050�N���g���K�X�r�o�[����ڎw�����ƂɊւ���A���P�[�g�v�����{�����B �J�[�{���j���[�g�����̒B���͓���i23%�j�A�r�W�l�X�`�����X�i75%�j�A�B���Ɍ����ĉ������邩�i�ȃG�l�A���������v�j�A�B���Ɍ����ĉۑ�i�Z�p�v�V�A�R�X�g�j���ɒ��Ăق������Ɓi�⏕���A�D���Ő��A�Z�p�x���j�A�Љ�A����ƁA����҂Ɋ��҂��邱�ƁiCO2�r�o�[�����i�̍w���A�C�m�x�[�V�����j���Ɋւ��āA�{�A���P�[�g�̌��ʂ����܂��A����A���̃J�[�{���j���[�g�����ɔ����O���[�������헪��G�l���M�[��{�v��ɑ��鎞�X�ɉ��������s���Ă����B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| �����E�ő�u�M�K�\�[���[�{�~�d�r�v�v���W�F�N�g���ĉ��B�ɒ��H �ăJ���t�H���j�A�B�ŁA�M�K���b�g���鋐��ȑ��z�����d�Ƒ�K�͂ȃG�l���M�[�����v���W�F�N�g�̌��݂��n�܂낤�Ƃ��Ă���B �u�G�h���[�Y���T���{�[���E�\�[���[�E�G�l���M�[�����v�v���W�F�N�g�́A�čăG�l�f�B�x���b�p�[�ł���e���W�F���Ђ��J�����A���z�����d��EPC�i�v�E���B�E�{�H�j�T�[�r�X���Ǝ҂ł��郂�[�e���\���ЂɎ{�H���ϑ������B �v���W�F�N�g�́A�o��1,118MW�́u�M�K�\�[���[�v�Ɨe��2,165MWh�́u�M�K�X�g���[�W�v����\������A���z���p�l����250�����z�A11���ȏ�̃��`�E���C�I���d�r���W���[�����g�p�����B ���݂͍��N��1�l�����i1�`3���j����J�n���A���N��2022�N��4�l�����i10�`12���j�Ɋ��H����\�肾�B���̖ʐς͓��C�݂̃j���[�W���[�W�[�B�ɕC�G����B�X�^�[�o�b�N�X����d�́A�n��V�d�͂��d�͍w���_��iPPA�j��������Ă���B �o�T�u���oVtech�v |
|
|
| �����ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցA�O���[�����f�̃R�X�g�팸�헪��� ���ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցiIRENA�j�́A�Đ��\�d�͂Ő��Y�����O���[�����f�́A2030�N�܂łɂ͉��ΔR���𗘗p���Đ��������u���[���f�ƃR�X�g�ʂŋ�����悤�ɂȂ�\��������ƁA���u�O���[�����f�R�X�g�팸�F1.5���̋C��ڕW��B�����邽�߂̐��d�u�̃X�P�[���A�b�v�v�̒��ŕ����B �O���[�����f�́A��_���Y�f����E�����iCCS�j�Ƒg�ݍ��킹�ĉ��ΔR�����琻�������u���[���f��2�`3�{�̃R�X�g���������Ă���B�O���[�����f�̐����R�X�g�́A�Đ��\�G�l���M�[�̉��i�A���d�u�̓����R�X�g�A�ғ����Ԃɂ���Č��܂邽�߁A�Đ��\�G�l���M�[�̒�R�X�g���ɉ����āA�]���̃��K���b�g�K�͂��琔�M�K���b�g�iGW�j�K�͂ւ̐��d�u�̃X�P�[���A�b�v�Ɛ��\�����ʂ��āA���d�u�̃R�X�g���팸���邽�߂̐헪�Ɛ���𖾂炩�ɂ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���_���Ȃ��ăG�l�����ڕW�A�u�r�p�_�n�v�̑��z�����p�𐄐i �ăG�l�����ɂ�����_�n�̗L�����p�Ɋւ��A�L���҂���v�]���o���ꂽ�B��ȋK�����v�̒�ẮA �i1�j�Đ�����ȍr�p�_�n�������I�ɔ�_�n�Ƃ���d�g�� �i2�j�ė��p�\�ȍr�p�_�n���ăG�l�ɗ��p�������Ƃ̗v�]���������ꍇ�A���̔_�n��_�n�ɗ��p���邩�A�ăG�l�ɗ��p���邩�A�v���ɔ��f����d�g�� �i3�j�_�R�����ăG�l�@�̖{�i�I�ȉ^�p�A�V���ȖڕW�̐ݒ� �i4�j�c�_�^���z���ɂ��Ă͓]�p���i���z���ˑ��b�����̈ꎞ�]�p�j��s�v�ɂ��āA�P���v���i���ϓI�ȒP�ʎ��ʂ�8���ȏ���m�ہj�A���Ԑ����i�ő�10�N���ƂɍX�V�j�Ȃǂ̗v�����O�� �i5�j�_�n�]�p�葱���̓������Ȃǂ�������ꂽ�B ����������Ă��A�_�ѐ��Y�Ȃ���A�u�_�R�����n��ɂ�����ăG�l�̐V���ȓ����ڕW��ݒ肷��v�Ƃ̕��j�������ꂽ�B���Ȃ́A���݁A�ڕW�l�Ƃ��āu�ăG�l�� .�Ȃǂ̌o�ϋK�͂�2023�N�܂ł�600���~�Ƃ���v�ƌf���Ă���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����ȓd�C���Ǝ҂̔r�o�W���i2019�N�x�j�����\ �r�o�W���́A��_���Y�f���̉������ʃK�X�����ʈȏ�r�o����ҁi����r�o�ҁj���A�n�����g�������i�@�Ɋ�Â��A2020�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂ��Z��E����ۂɗp������́B��2021�N�x�ɍs���B ������\���ꂽ�����ł́A�����̓d�C���Ǝ҂̃��j���[�ʒ�����r�o�W�����f�ڂ���Ă���B���̂����A�u�Đ��\�G�l���M�[100���v�̓d�C����������A�݂�ȓd�͂�G�l�b�g�A�������D�A�f�W�^���O���b�h�A����G�i�W�[�Ȃǂ̃��j���[�ʒ�����r�o�W���͂�������[���i0.00000�g���|CO2�^kWh�j�ƂȂ��Ă���B �p�������SDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�Ȃǂ�w�i�ɁA����ɁA���u2050�N�܂łɉ������ʃK�X�����[���v��錾�������Ƃ��āA�����ׂ̒Ⴂ�d�C�̃j�[�Y�����܂��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NPO�̂��߂�SDGs���p�K�C�h�u�b�N�̔��s�`SDGs�Œn��̊�����낤�` ���Ȃ����ۘA����w�Ƌ����^�c���Ă���n�����p�[�g�i�[�V�b�v�v���U�iGEOC�j�́A�uNPO�̂��߂�SDGs���p�K�C�h�u�b�N�v�s�����B �uNPO�̂��߂�SDGs���p�K�C�h�u�b�N�v�́ASDGs�Ɏ��g�ނ��Ƃɂ����NPO�̊����̊�������p�[�g�i�[�V�b�v�̑��i���߂����č쐬�����BSDGs�̐����w�i�A���̑������A�B���Ɍ����Ċ��҂����NPO�̖�������g�ވӋ`�Ɖ\������A����܂ł̊����ɉ�����SDGs�B���ɂ��Ȃ���q���g��������悤�ɂȂ��Ă���BSDGs��g�߂Ȃ��̂łЂ��Ƃ��������A���g�̊�����SDGs�̂Ȃ�����l�����莖�Ɛ��̊g������������肷�邽�߂̃��[�N���f�ڂ��Ă���B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ������s�A���ݔ��d�̊����l��d�q�؏����ցA�u���b�N�`�F�[���Z�p���p ����s�Achaintope�A�݂�܃p���[HD�́A����s���ł̃G�l���M�[���̒n����z���������A���ݔ��d�d�͂̒n�Y�n���ɂ������l��d�q�؏�������V�X�e��������A���؍�Ƃ��s���Ɣ��\�����B 2050�N�E�Y�f�Љ�̎����𐄐i���鍲��s�ɂ����āA�n��z���������ł̉��l�̏z���A�u���b�N�`�F�[���Z�p�𗘗p���ĉ�������B����ɂ��A����ɑ����̎s���̍s���ϗe�𑣂��A�E�Y�f�ƒn��o�ϊ������ɂȂ������l���B ����s�ł́A���ݔ��d�ɂ��ăG�l���s���̌����{�݂������u�d�͂̒n�Y�n���v��i�߂�ق��A���{�ŏ��߂āA���ݏċp�{�݂ɂ�����CCU�i��_���Y�f�̕�������ɂ�闘���p�j�v�����g��ݒu���A�אڊ�Ƃ�CO2���������Ă���B�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����A���̊����ɂ���Đ��܂ꂽ�����l��chaintope�̃u���b�N�`�F�[��Tapyrus�𗘗p���A�d�q�؏��Ƃ��Č��J������g�݂����{����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2021/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���k�C���Ɂu24���Ԕ��d�^�v���K�\�[���[�A��Ԃ͒~�d�r������d �u���[�L���s�^���}�l�W�����g�́A�~�d�r���^���K�\�[���[�uBlue Power�k�C���Ԉ�씭�d���v�̊J����i�߂Ă���B �o��845kW�̘A�n�o�͂ɑ��A��6MW�̑��z���p�l����ݒu�����B�~�n�ʐς͓����h�[����18���ɑ�������85��1890.00m2�B���z���p�l���͒����g���i�E�\�[���[���ō��v�o�͂�5995.84kW�A�p���[�R���f�B�V���i�[�ƒ~�d�r�͒����T���O���E���ŁA�~�d�r�̗e�ʂ�2��1000kWh�BEPC�i�v�E���B�E�{�H�j�́ABlue PowerConstruction���S�������B ��e�ʂ̒~�d�r�V�X�e���݂��邱�ƂŁA�����ɔ��d�����d�͂d����ق��A�A�n�o�͂����]��d�͂�~�d�r�ɏ[�d���Ė�Ԃɔ��d����B����ɂ��24���ԁA���d���邱�Ƃ��\�ɂȂ�A�\�z���d�ʂ͖�705��1287kWh�������ށB�A�n�ݔ��̐ݔ����p����95���ɒB����B�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�̔��d�P����21�~/kWh�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Z�u���[�C���u���E�W���p���A�X�܂̏ȃG�l���Ɍ�������s�I�Ȏ��؎������Љ� �Z�u���[�C���u���́A�����s�~�s��CO2�r�o�ʍ팸�̎��ؓX�܂��I�[�v�������B ���̓X�܂́A�Z�u��&�A�C�O���[�v�̊��錾�Ɋ�Â��A�X�܉^�c�ɔ���CO2�r�o�팸�����g�̈�B���Ђ͂���܂ŁA�X�܂̉����ɑ��z���p�l���̐ݒu��i�߁A�z���ɔR���d�r�Ԃ�����Ȃ�CO2�r�o�ʍ팸�Ɏ�g��ł����B ����ACO2�팸�Ɍ������܂��܂ȋZ�p���̗p�������ؓX�܂��I�[�v���B��̓I�ɂ́A�u�����Z���T�v����t���A�����t�@������X���ɋ�C���������A�X���C�����O�����������u�����v�̏�Ԃɂ��邱�ƂŁA�����h�A����̊O�C�̐N����h���A�����̉��P����ق��A���z���p�l���E�~�d�r�̐ݒu�A�ؑ����z�A�`���h�P�[�X�̃G�A�J�[�e�����\����Ȃǂ�}���Ă���B ����ɂ��A�O�����B�d��43%�팸�ACO2�r�o��54%�팸(�������2013�N�x��)�������܂��Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����z���ƒ~�d�r���ڂ́u�X�}�[�g�o�X��v�A���u�Ŏ����\���X�V �V���[�v�́AYE DIGITAL�ƁA���z���p�l���ƒ~�d�r�𓋍ڂ����p�d���ɐڑ����Ȃ��Ă����삷��u�X�}�[�g�o�X��v�������J�������B �o��50W�̑��z���p�l���Ɨe��132Wh�̃��`�E���C�I���~�d�r�𓋍ڂ����B���Ԃɔ��d�����d�C��~�d�r�ɒ~���邱�ƂŁA���Ɨʂ̏��Ȃ������Ԃɂ����p�ł���B�~�d�r�����[�d�̏ꍇ�A���z�����d���s���Ȃ��Ă���5���ԓ��삷��B �\�����ɂ́A��ʃT�C�Y31.5V�^�̔��ˌ^�J���[IGZO�t���f�B�X�v���C���̗p�����B���˓������ł��N���A�ȉ�ʕ\���ŁA�O���̏��Ȃ���Ԏ��Ȃǂ̓o�b�N���C�g��_������B�ʐM�@�\�����ڂ��A���u����Ŏ����\�Ȃǂ�e�Ղɏ��������\�B�f�����̒���ւ���Ƃɂ�����R�X�g���팸�ł���B�{�̐��@�͍���180cm�~��50.3cm�A�d����40.7kg�i�{�̂̂݁j�B���i�̓I�[�v���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���A�}�]���A���E�ő�̍ăG�l�w���@�l�Ɍv6.5GW�̕��́E���z���֓��� Amazon�́A���v���d�e��3.4GW�K�͂̕��́E���z���G�l���M�[�V�K�v���W�F�N�g26���\�����B ���Ђ�2020�N�ɍs�����ăG�l�v���W�F�N�g�ւ̓����͍��v35���A���d�e��4GW�ȏ�ƂȂ�B�����̐V�K�v���W�F�N�g�ɂ��A�j��ő�K�͂̍ăG�l�@�l�w���҂ƂȂ����Ƃ����B ���݁A6.5GW�̕��́E���z���v���W�F�N�g�֓������s���Ă���A���Ў��Ƃɑ��N��1800��MWh�ȏ�̍ăG�l�ɂ��d�͋������\�B�ăG�l�͓��Ў��Ə��ƃt���t�B�������g�E�Z���^�[�i�z���Z���^�[�j�A�A�}�]���E�F�u�T�[�r�X�iAWS�j�f�[�^�Z���^�[��������B ���Ђ�2040�N�܂łɁA���ƑS�̂Ńl�b�g�[���E�J�[�{������������Ƃ����ڕW���f���Ă���B���̈�Ƃ��ē����A2030�N�܂łɎ��Ƃ̓d�͂�100���ăG�l�Řd���Ƃ����ڕW���f���Ă������A�����5�N�O�|���āA2025�N�ɂ܂ł̒B���Ɍ������g�݂�i�߂�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�̎Љ�A�f���C�g�g�[�}�c������ ���Ђ́A2050�N�ɃJ�[�{���j���[�g�������������ꂽ���_�ł̓��{�̌o�ώЉ�̂�����Ɋւ���V�~�����[�V�������ʂ����J�����B ���|�[�g�ł́A�d�͗����̑��z���ŏ����ɗ}���A���q�͔��d���̐V�݂��s��Ȃ��Ȃǐ��{���j�܂�����ŁA�J�[�{���j���[�g���������������ꍇ�̓d���\���A�ăG�l�̑�ʓ������x����G�l���M�[�C���t�����A���r���e�B�d�����A���f���p���̃G�l���M�[�Љ���ʓI�Ɏ������B �d���\���́A�ăG�l�ƌ��q�͔��d�ŃV�F�A�͂ق�100���B�܂��A�ăG�l��ʓ������x���邽�߂ɁA��40GW�ȏ�̒~�d�ݔ����K�v�B�d�̓R�X�g�㏸��}���邽�߁A���f���d��CCS�̓����A�~�d�ݔ��̑�ւƂ��Ċ��p���邽�߂̓d�C�����ԁiEV�j�Ȃǂ̕��y�AVPP�Ȃǂɂ��A�n���Ԃ̕��ׂ��y������K�v������Ǝw�E�����B �Ȃ��ACCS�␅�f���d�����邱�Ƃɂ���āA�~�d�r��n���Ԃւ̓����́A�������Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׂ�1�^3�`1�^4�ɗ}���ł��镪�͌��ʂƂȂ��Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ቷ�g����}R32��p�����@�̔̔��ɂ�����r�c�f�����[�X�̎�舵���J�n �O��Z�F�t�@�C�i���X�����[�X�iSMFL�j�ƃ_�C�L���́ASMFL��舵���́w�݂炢2030�x�i��t�^�j�i�ȉ��uSDGs���[�X�v�j�ɂ����āA�_�C�L���H�Ƃ��̔�����ቷ�g����}R32��p�����@��2021�N1�����V����SDGs���[�X�̑Ώۂɉ����邱�ƂɂȂ����B SDGs���[�X�ɂ�����R32�@�w�����z��0.1�������z�����v���c�@�l�m�����c�i�u�m�����c�v�j�Ɋ�t���܂��BSDGs���[�X�́ASMFL�����[�X�����̈ꕔ��SDGs�B���Ɏ�������v���c�@�l���Ɋ�t���邱�ƂŁA���[�U�[�����[�X��ʂ���SDGs�B���ɍv���ł��郊�[�X����BSMFL�ƃ_�C�L���H�Ƃ́A����̎��g�݂ɂ��n�����g���ɗ^����e�����]���̖�3����1�ŁA�G�l���M�[��������ɗD��Ă���ቷ�g����}R32�̕��y�𑣐i����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ƒ{�ӂ�A�E�K�X��LPG�ɕϊ��A�É͓d�H���V�G�} �É͓d�C�H�Ƃ́A�k�C����w�Ƃ̋��������ɂ��A�����G�}�̌Œ�Z�p�����p���A�ƒ{�̂ӂ�A���瓾����o�C�I�K�X�i�听����CO2�ƃ��^���K�X�j��LPG�ɕϊ�����Z�p���J�������B �]���A�������Ⴍ�Z���Ԃ����������Ȃ������G�}������啝�ɉ��P�����B ���Ђ��|���Ă������^���ƃ|���}�[�̐����E���H�Z�p��p���āA���E���ޗ��̓����ɐ�nm�T�C�Y�̋����G�}�i�j�b�P����G�}�Ƃ��ė��p�j���Œ肵���u�����l�G�}�v���J�������B�]���̐G�}�ʼnۑ�Ƃ���Ă����ϋÏW���E�σR�[�L���O���������A�ӂ�A����o��o�C�I�K�X�iCO2�ACH4�j�������K�X�iCO�AH2�j�ɕϊ�����h���C���t�H�[�~���O�����ɂ����āA���_���E�ɋ߂��������ƒ����������������B �����K�X����́ALPG���������ɂ��LP�K�X�Y�ł���B2023�N�܂łɏ��^�����@�ɂ����A2030�N�̎��p����ڎw���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| �����ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցA��g�[�̃G�l���M�[�]���Ɍ������ً}�K�v�ƕ� ���ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցiIRENA�j�́A���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j���Ƃ̋������u�]�����ɂ���Đ��\�G�l���M�[����F�g�[�Ɨ�[�v�����J���A�Đ��G�l���x�[�X�Ƃ���d�́A�Đ��\�K�X�A�o�C�I�}�X�A���z�M����сA�n�M�̒��ڗ��p���܂ރG�l���M�[�]���Ɍ�����5�̓����Љ���B ��g�[���v�͐��E�̍ŏI�G�l���M�[����ʂ̖����߂Ă���A���̂قƂ�ǂ��Y�Ɨp�ŁA�����ŏZ��p�A�_�Ɨp�ƂȂ��Ă���B���̑����͉��ΔR���ɗR�����Ă��邽�߁A��C�����̌����ƂȂ�A���E�ɂ�����G�l���M�[�֘A�̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ�40%�ȏ���߂�B ���E�̗�[���v��1990�N�ȍ~�A�C��ϓ��ɂ��M�g�̐[�����������A����3�{�ɑ������Ă���B2019�N���܂łɍĐ��\�ȗ�g�[�Ɋւ��鍑�ƖڕW��ݒ肵�Ă���̂́AEU���܂�49�����ɉ߂����A166�������Đ��\�Ȕ��d�ڕW��ݒ肵�Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���u���{�݁A�ăG�l30���ȏ�̓d�͒��B���v�͖�E����b���v�� �͖�s�����v��b�Ə������b��12���ɋ�������J���A�e�{�Ȃɑ��A2021�N�x�ɒ��B����d�͂ɂ��čăG�l�䗦30���ȏ�Ƃ���悤�v������ƕ\�������B ����b�́A�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����āA���{������������ʃK�X�̔r�o�팸�ɗ��悵�Ď��g��ł����K�v������Ƃ��āA�e�{�Ȃɑ��A�������̊m�ہE����ȓd�͉��i�Ȃǂ̎����Ȃǂɗ��ӂ�������ŁA�ăG�l�䗦30���ȏ�̓d�͒��B�����{����悤�˗������B �͖��b�́u�e�{�Ȃ̍ăG�l�d�͂̒��B���A�K�����v�̗��ꂩ����s�����v�̎��_������㉟�����Ă��������v�Ɣ����B �����b�́u����܂Ŋ��Ȃ��~�ς��Ă����o����m�E�n�E����A�ăG�l�̐ϋɓI�Ȓ��B���~���ɍs����悤�x�����邱�ƂŁA���{�S�̂Ƃ��Ă̍ăG�l���B�������コ����B���{�����悵�Ă܂��͎��g�ނ��ƂŁA2050�N�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ������Љ�I�ȋ@�^���������Ă��������v�Ƙb�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2021�N�x�Ő������A�J�[�{���j���[�g�����Ɍ������ݔ������x������n�� ���{�^�}�́A2021�N�x�́u�Ő�������j�v�����肵���B �������o�c�������x�����邽�߂̐Ő��[�u��A�u�f�W�^�����v�u�O���[�����v�̕��j�ɉ������V���ȐŐ��̑n�݂荞�B�J�[�{���j���[�g�����Ɍ������Ő��[�u�̑n�ݐ��Y�v���Z�X�̒E�Y�f���Ɋ�^����ݔ���A�V���Ȏ��v�̊J��ւ̊�^�������܂��E�Y�f�����������鐻�i�Y����ݔ��ɑ��āA�Ő��㋭�͂Ɏx������[�u��n�݂���B �����̐ݔ��̎擾�������āA���̎擾���z��50���̓��ʏ��p�Ƃ��̎擾���z��5���i�������ʃK�X�̍팸�ɒ�������������̂ɂ����Ă�10���j�̐Ŋz�T���Ƃ̑I��K�p���ł���B �����ԏd�ʐł̃G�R�J�[���ŁA���Ȃ̐Ő��S�̂̃O���[�����𐄐i�A�ȃG�l��A�ăG�l���y�Ȃǂ̃G�l���M�[�N����_���Y�f�r�o�}���ɏ[������u�n�����g����̂��߂̐Łv�𒅎��Ɏ��{���邱�ƁB�R���d�r�����Ԑ��f�[�Ă�ݔ��̌Œ莑�Y�ł�2�N�ԉ�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����A�E�Y�f���Z�p�x����2���~�̊���n�ݎ����Ԃ̔r�oCO2�[�����\�� �������́A2050�N�J�[�{���j���[�g�����̖ڕW�B���Ɍ����A�u2���~�̊����n�݁B�C�m�x�[�V�����ɒ��킷���Ƃ�����10�N�Ԍp�����Ďx������v�ƕ\�������B ��̓I�ɂ́A��K�͂Œ�R�X�g�̐��f�������u�̎�����ڎw���B�܂��A���f��s�@�␅�f�̉^���D���J������B����ɁA�E�Y�f�̌��ƂȂ�u�d���v�ɂ��ẮA��R�X�g�̒~�d�r�̊J����i�߂�B�r�o������_���Y�f�́A�u�J�[�{�����T�C�N���v�ɂ��A�v���X�`�b�N��R���Ƃ��čė��p���邱���������g�݂Ŗ��ԓ������㉟������B ���́u240���~�̌��a���̊��p�𑣂��A3,000���~�Ƃ������鐢�E���̊��֘A�̓�����������{�ɌĂэ��݁A�ٗp�Ɛ����ݏo���v�ƕ\�������B����ɁA�u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�ڕW�ɂ��āA���{�����E�̗���ɒǂ����A�����邽�߂ɂǂ����Ă����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ڕW�ł���Əq�ׂ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�A�O���[�������헪��14����̖ڕW��ݒ�m�㕗��40�N��45GW ���{�́A�u2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�̎����Ɍ����āA�u�o�ςƊ��̍D�z�v�ɂȂ��邽�߂̎Y�Ɛ�����܂Ƃ߂����s�v��u�O���[�������헪�v�����\�����B �������헪�ł́A14�̏d�v�������肵�A�����ڕW���f������ŁA����̉ۑ�ƍ���̑Ή��L�B�\�Z�A�ŁA�K�����v�A�W�����A���ۘA�g�ȂǁA�����鐭��荞���s�v������肵�A2050�N�܂ł̍H���\������B�d�v����̂����A�ꕔ�̎�ȖڕW���͈ȉ��̒ʂ�B �E�m�㕗�͎Y�Ɠ����ڕW��2030�N10GW�A2040�N30�`45GW�B2030�`2035�N�܂łɁA8�`9�~�^kWh�ɂ���B �E�R���A�����j�A�Y�ƐΒY�Η͂ւ�20�����Ă̓����E�g��B �E���f�Y�Ɠ����ʂ�2050�N��2,000���g�����x�ɁB���f�R�X�g�F20�~�^Nm3���x�ȉ��B�E���q�͎Y�ƒ����ȍĉғ��Ǝ�����v�V�F�̊J���𐄐i�B �E�����ԁA�~�d�r�Y��2030�N�㔼�܂�100���d���� �E�����́A���ʐM�Y��2040�N�ɃJ�[�{���j���[�g�����ɁB �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| �����g����2050�N�ɂ͐X�т�CO2���o���ɁA���� �l�Ԃ̊����Ŕr�o�����CO2��30�����z�����Ă���X�тȂǗ���̐��Ԍn���A�}���ȉ��g���ɂ��A����20�`30�N�ȓ��ɁuCO2�z�����v����u���o���v�ɕς���Ă��܂����ꂪ����Ƃ̌������ʂ����\���ꂽ�B �C��ϓ��Ƃ̓����ɂ�����V���ȓ�ǂ̓����ɁA�����҂�͌x����炵�Ă���B �ĉȊw���T�C�G���X�E�A�h�o���V�Y�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ɂ��ƁA�C�������̍�������ƐA����CO2�z���\�͂��ቺ���邱�Ƃ����������B�\�͒ቺ�̌��E���x�͒n���A����ɂ���ĈقȂ邪�A����̉������ʃK�X�r�o�X���������A�����I���ɂ͒n����̐A���̔�������C����CO2��r�o����悤�ɂȂ�Ƃ����B �o�T�uAFPBB News�v |
|
|
| ���C�ے��u���{�̋C��ϓ�2020�v�����\ �����Ȋw�ȂƋC�ے��́A���{�̋C��ϓ��ɂ��āA����܂łɊϑ����ꂽ������A�p�������2���ڕW���B�����ꂽ�ꍇ�y�ь����_����lj��I�Ȋɘa������Ȃ������ꍇ�ɂ��蓾�鏫���\����Ή������ĂƂ�܂Ƃ߂��u���{�̋C��ϓ�2020.��C�Ɨ��E�C�m�Ɋւ���ϑ��E�\���]�����v�����\�����B ����̕��ϋC����2���㏸�V�i���I�y��4���㏸�V�i���I�Ő��ڂ����ꍇ�̏����\�� 2���㏸�V�i���I�\���ł́A�C���͖�1.4���㏸�A���~����200�o�ȏ�̓����͖�1.5�{�A�~��ʂ͖�30�������A�C�����x�͖�1.14���㏸�B |
|
|
| ���@�@[�@2021/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���C�[�����u���N�A�e�X���ŏȃG�l�̉ƒ�p�G�A�R������邩���v �e�X�����A�G�A�R�������Ƃ����\������A�_�C�L���ȂNJ����̃��[�J�[�炪�g�\���Ă���A�ƕ��Ă���B ���呍��ŃC�[�����E�}�X�N���u���N�ƒ�p�G�A�R�����Ƃ��n�߂邩���v�ƌ������̂����������ƂȂ��Ă���B ����܂ŁA�����Ԃ̃G�A�R���͂��Ƃ��A�ƒ�p�̑��z���p�l���ɏ[�d�r�A�l�H�ċz��Ȃǂ�������o��������A���܂��܂ȋZ�p��ۗL���Ă���B�ŋ߂ł́A�X�}�[�g�z�[���̂��߂�HVAC�iHeating, Ventilation, and AirConditioning�j�Ƃ����g�[�A���C�A�V�X�e���ɂ��Ă�����������B �ƒ�p�G�A�R���͂��̈�Ƃ݂���B2�N�O�ɁA�uModel Y�v�̒��Ƀq�[�g�|���v���̃G�A�R������������A�Â��Ō����I�ŁA���x�Ǘ���HEPA�t�B���^�[�����̉ƒ�pHVAC�����ӗ~�����������Ƃ�����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���_�C�L���ɕ������g�N�Ŋ����Ȃ����C���@�A�ǂ�V������߂Ă��犷�C �_�C�L���́A�S����20��`50���529�l��ΏۂɁu���C�ɑ���ӎ������v���s�����B ���ʂ́A�u�~�ɉƂő��J�����C���������v�Ƃ����l��75.0���ƁA4�l��3�l�������B�~�ł��Ƃő��J�����C���������l�ɗ��R���ƁA�u�R���i��Ŋ��C���d�v���Ǝv������v��71.3���Ńg�b�v�B ����ŁA�u�~�ɉƂő��J�����C���������Ȃ��v�Ƃ����l�̖�8�����u�����Ȃ�v�A��4�����u�g�[�̓d�C�オ�����Ȃ�v�ƁA�~����L�̊��C���̉ۑ�𗝗R�ɋ����Ă���B ���Ђł́A�������߂̊��C�̕��@�ɂ��āu�N������A��́A�^�C�}�[�Ŏ��O�ɒg�[�����A������g�������Ă��瑋�J�����C������v�u�~��́A�܂��G�A�R���̒g�[�����A�������g�����Ȃ��Ă���G�A�R�����^�]�����܂ܑ��J�����C������v�Ȃǂ��Љ�B �₦���ǂ⏰�A�V���g�߂Ă������ƂŁA���J�����C�����Ă������̉��x��������ɂ����Ȃ�A���K�ɉ߂�����Ƃ����B �o�T�u�I�[���H�v |
|
|
| �����ŁA�R���ɂ����d�r�V�^�u���n���`�E���C�I���v�Z��E��ЁA�ݒu�e�Ղ� ���ł͔R���ɂ����A���S�������߂��V�^�̃��`�E���C�I���d�r���J�������Ɣ��\�����B ����܂Őݒu�����ɂ��������Z��̋߂���I�t�B�X�r���ɂ��ݒu���₷���Ȃ�B���z���ȂǍĐ��\�G�l���M�[�����߂�~�d�r�Ƃ��āA2020�N�㒆�̎��p����ڎw���B �J�������̂́u���n���`�E���C�I���d�r�v�B��ʓI�ȃ��`�E���C�I���d�r�͓d���t�ɔR���₷���������g�����A�R���ɂ������n�t�n�̓d���t���̗p�����B�ቷ�ł�����Ȃ��d���t���g�����ƂŁA�}�C�i�X30�x�̒ቷ���ł��g�p�ł���B���z���ȂǍăG�l�͓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʒጸ�ɂȂ��邪�A���d�ʂ����ԑт�V��ɂ���č��E�����B ���肵�ĉ^�p���邽�߂ɂ͒~�d�r���s�����B���{��2050�N�܂ł̉��g���K�X�����[����V���ȖڕW�Ƃ��Čf����ȂǁA�E�Y�f�Ɍ��������g�݂������B���ł͐V���ɐݒu�̎��R�x�������d�r���J�����邱�ƂŁA���㐬���������ލăG�l���Ɗg��ɂȂ���B �o�T�u���K�\�[���[�r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����d�{NAS�d�r���p��BCP�V�X�e���A�R��d�@�ʼnғ��^�I������G �I�������t�B�[���h�G���W�j�A�����O�́A�R��d�@��BCP�V�X�e����10���ɉ^�]���J�n�����Ɣ��\�����B ��������BCP�V�X�e���́A���z�����d�V�X�e���i�e��670kW�j�ƁA���{�K�C�V��NAS�d�r�i��i�o��400kW�A��i�e��2,400kWh�j�AEMS�R���g���[���[�ō\�������B NAS�d�r�́A��e�ʁA���G�l���M�[���x�A�������������B���z�����d�V�X�e����NAS�d�r��EMS�R���g���[���[�ōœK�ɐ��䂵�A��d�E�ЊQ�ɑ���H���BCP�i���ƌp���v��j��A�n��̖h�Ћ��_�ւ̓d�͋����ɁA�܂��A���펞�͑��z�����d�̎��Ə���̊g��Ɋ��p�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����ア���ݎs�������A�u�ăG�l100�錾�v�ɎQ��CO2�A�r�o�ʃ[���X�֓]�� ��ア���ݎs�����������g���́A�g�p�d�͂��Đ��\�G�l���M�[��100���]�����邱�Ƃ�錾����u�ăG�l100�錾 RE Action�v�ɎQ������Ɣ��\�����B �ăG�l�ɂ�锭�d�𐄐i����ƂƂ��ɁA�ăG�l�̓d���m�ۂ�i�߂�B�܂��A�g�p�d�͂�100���ăG�l�ɓ]�������uCO2�r�o�ʃ[���̎{�݁v���v��I�ɑ��₵�A2050�N�܂łɂ͎��Ƃ̎g�p�d�͂�100���Đ��\�G�l���M�[�ɓ]������B�K�v�ɉ����Ĕr�o���N���W�b�g���w������B����ɁA�X�܂�{�݁E�ݔ��̏ȃG�l���������߂Ă����B �������ł́A���n��4�J���ɔ��d�K�͍��v10.75MW�̑��z�����d�������L����ق��A���Ə��̉����֑��z�����d�p�l���̐ݒu��i�߂Ă���B�܂��A�S���̐����ɐ�삯��2016�N4�����d�C�������Ƃ��J�n���A4�����т̑g�����ɁA�Đ��\�G�l���M�[�䗦�̍����u�R�[�v�łv���������A�Đ��\�G�l���M�[�̕��y�Ǝ����\�Ȓn��Â���ւ̍v�����߂����Ă���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�u���A�X���������̖ؑ��ȃG�l�X�܁BCO2�r�o54%�팸 �ȃG�l�����E�ݔ�����ёn�G�l�E�{�G�l�ݔ��������A�ȃG�l�̎��ؓX�܁u�Z�u���]�C���u���~�V���X�v���I�[�v�������B �O���́A�u��e�ʑ��z���p�l���v�A�u���w�K���X�v�u�ؑ��X�܁v�B��e�ʑ��z���p�l���́A�X�܉�����̐ݒu�\�Ȕ͈͂ɍő���ݒu�B35.6kW�̏o�͂������B�������̃p�l���ŁA�]�����3�{�̔��d�ʂ������ށB �܂��~�d�r��ݒu���A�ؑ��X�܂́A���g�ݍH�@���̗p�B�܂���X�p���̋�ԂÂ��肪�\��LVL�ނ��̗p�B�]���H�@�ɔ�גf�M���E�C���������シ��Ƃ����B�����̐ݔ��́A�u�X���������v�A�u�I�[�g�N���[���t�B���^�[�v�A�u�`���h�P�[�X�G�A�J�[�e���v�A�u�E�H�[�N�C�������d�l�v�A�uLED�z���������v�B�X���������́A�u�����Z���T�[�v�����t���A�����t�@������X���ɋ�C���������A�X���C�����O�����������u�����v�̏�Ԃɂ���Ƃ������́B�X���������ɂ��A�O�C�̐N����h���A�����̉��P��}��B �o�T�uImpress�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�ăG�l����100���̓d�͂��]�ƈ������ɋ���10�����珇�� �p�i�\�j�b�N�́A�ăG�l�w��̔Ώ؏����g�p�����A�Đ��\�G�l���M�[����100���̓d�͗��p�v�������\�z�����Ɣ��\�����B 10�����]�ƈ���Ώۂɓ��v�����̕�W���J�n���A�_�������A�������n�߂Ă���Ƃ����B���Ђ́A2005�N��莩�ЍH���I�t�B�X�ւ̓d�͋������J�n���A2016�N�ɏ����d�C���Ǝ҂̓o�^���A�]�ƈ���ΏۂƂ����d�͋������J�n�����B �]�ƈ����������ăG�l100���̓d�͂̒́A����܂Ŕ|���Ă����d�͒��B�E�d�͎���̃m�E�n�E��o�������������A�u���ǂ����炵�v�Ɓu�����\�Ȓn���Љ�v�̗����Ɍ��������A�N�V�����̈�ƈʒu�Â��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������ʃK�X�r�o�ʁA��ƕ̌��\���P�N�Z�k�^���ȁA�d�r�f�����Ăэ��� ���Ȃ́A��Ƃ���̉������ʃK�X�r�o�ʂ̕葱�����V�X�e�������A�f�[�^���\��1�N���߂�B ���݂͎��}�̒��S�̎葱���Ŏ�����ƂɎ��Ԃ�v���A���Ȃ���Ƃ̕��Ă�����\����܂łɖ�2�N������B�f�W�^�����ɂ��1�N�͒Z�k�ł���ƌ����ށB�V�X�e����x���Ƃ�2023�N5���܂łɍ\�z����B�f�[�^���\�𑁂߁A�����Ƃ���Ƃ�]�����₷������_�����B �u�f�W�^���E�K�o�����g�������v��v�Ƃ��āA2018�N�x����i�߂Ă���B�n�����g�������i�@�Ɋ�Â���Ƃɉۂ����鉷�����ʃK�X�̎Z��E�E���\���x�����łȂ��A�n�������c�̂̎��s�v����萧�x�A�t�����r�o�}���@�A�o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[�����ǂ̏ȃG�l���M�[�@�ȂǁA�����̕Ɩ����܂Ƃ߂ăV�X�e��������v�悾�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�c�A���V�����헪2050�N�r�o�[���ցA�Z�p�v�V�E�����͂���ăG�l�x���� 2020�N11��11���o�c�A�́A�u�T�X�e�C�i�u���Ȏ��{��`�v�̊m������{�R���Z�v�g�ɐ������V�����헪�\�����B���헪�ł́A�O���[�������̎����Ɍ����Đ��{�A�o�ϊE�Ȃǂ��Ƃ�ׂ��A�N�V�����Ƃ��āA�ȉ���5������B (1)�E�Y�f�Љ��ڎw�����C�m�x�[�V�����̉�����e�ʁE�ቿ�i�ň��S�Ȏ�����~�d�r�̓����A�����Ȑ��f�̑�ʋ����ƎY�ƃv���Z�X�E���d�����܂ގ��v���Z�p�̊J���ACO2���Œ�E�ė��p���邽�߂�CCUS�̏��p���ȂǁB (2)�����͂���ăG�l�ւ̎x���d�_�������u�����̑��z���A��K�͗m�㕗�͔��d�Ȃǂɏd�_�B�ăG�l�����𑣐i���鑗�z�d�Ԃ̍X�V�E�����B (3)�E�Y�f���ƌo�ϐ��𗼗����錴�q�͂̊��p2030�N�܂łɂ͐V�^�F�̌��݂ɒ���B���ƃv���W�F�N�g�Ƃ��Ă̎��g�݁B (4)�d�����̌���B (5)�O���[���������ƘA���̌`���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z����6����D�A�Œᗎ�D���i10.00�~�^kWh���v368MW���D ��Y�f�������i�@�\�́A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�@�j�ɂ����D���x�Ɋ�Â��Ď��{�������Ɨp���z�����d�̑�6����D�i2020�N�x����j�̌��ʂ����\�����B ���Ɨp���z�����d�̓��D�Ώۂ�2020�N�x����o��250kW�ȏ�Ɋg�傳�ꂽ�B��6��̓��D�ʁi��W�e�ʁj��750MW�i750,000kW�j�ŁA������i����\�Ƃ��Ď��{���ꂽ�B �J�����ꂽ������i��12.00�~�^kWh�B��5����D�̏�����i��13.00�~�^kWh�������B���D�̌��ʁA254�������D�B���D���ꂽ�o�͂̍��v��368,373.5kW�B �Œᗎ�D���i��10.00�~�^kWh�A�ō����D���i��12.00�~�^kWh�B���d���ϗ��D���i��11.48�~�^kWh�������B �Œᗎ�D���i�́A���z����5����D�i10.99�~�^kWh�j���0.99�~�^kWh���ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u100���ăG�l�v���͒ʏ�d�́A���Ȑ��f�X�e�[�V�������Ɓ@��v�����@ ���z�����d�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�݂̂𗘗p���A���f������u�ăG�l���f�X�e�[�V�����v�y������Ȃ̕⏕���Ƃ́A�⏕�������قƂ�ǂ̎{�݂��ʏ�d�͂��w�����Ă������Ƃ����������B �ăG�l���f�X�e�[�V�����́A����d�C�������Đ����������f��R���d�r�ԁiFCV�j�ɋ�������{�݁B���f�����̓d�͂ɍăG�l�݂̂𗘗p���邱�Ƃ��⏕���̗v���Ƃ���A���Ƃ��n�܂���2015�N�x�ȍ~�A27�J���ݒu���ꂽ�B ���̂����^�p�J�n����1�N�ȏ�o�߂��Ă���19�J�����������ʁA�����̍ăG�l���d�ݔ��𗘗p����12�J���S�ĂŒʏ�d�͂��w�����Ă������Ƃ������B�V�݂���7�J����5�J���ł��A�ăG�l�̊�����20�D4�`93�D5���ŁA����Ȃ����͒ʏ�d�͂��w�����Ă����B 17�J���̕⏕���͖�19��3200���~�B�R�����s�K�B���Ƃ̌p���̉ۂ��܂ߌ��������s���K�v������v�Ǝw�E�B���Ȃ�2020�N�x�̐V�K��W������߂��B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ��NEDO�A�u�J�[�{�����T�C�N���v�ɓK����CO2��������E���d�Z�p�J���� NEDO�́A�J�[�{�����T�C�N���ɓK�����A���d��CO2�����E����v���Z�X����̉������V�X�e���̌����J���ɒ��肷��Ɣ��\�����B ���̎��Ƃɂ��ACO2�����E����R�X�g�������4,000�~���x�^�g��CO2����1,000�~��܂Œጸ���锭�d�Z�p�̊m����ڎw���A�J�[�{�����T�C�N���Z�p�̎��p���ɍv������l���B ����A2���̃e�[�}���̑������B���d�V�X�e���ɔR�����K�X������v���Z�X�����ACO2�̕����E����܂ł���̉����邱�ƂŃG�l���M�[���������コ���ACO2�̕����E����R�X�g�̒ጸ�Ɏ��g�ށB�܂��A�o�C�I�}�X��p�����i�p�v���X�`�b�N�Ȃǁj�A�ΒY��R���Ƃ��ė��p���A���f�≻�w�i�Ƃ������L�����Y����|���W�F�l���[�V�����V�X�e���̍\�z�ɂ����g�ށB ����ɂ��A�V�X�e���̌o�ϐ������߂�CO2�����E����R�X�g�̒ጸ�ɂȂ��邾���łȂ��A�����K�͔��d���܂߂����p���E���Ɖ�������ɓ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�l���A�A�����j�A�R���g��ց^���p�����Ɍ����S�{������ �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[����7���A�A�����j�A�̔R�������g��Ɍ������������荞�u���_�v���������B �ΒY�Η͂ւ̍��ĂȂǂ𒆐S��2020�N��㔼�̏��p�����Ɍ����A�u���苟���v�u�o�ϐ��v�u���v�u�C�O�W�J�v��4�𒌂Ƃ����B �A�����j�A���Y���̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o���ۑ�̈�����A���ʂ͕��y�ɏd�_��u�����j�B�����u�u���[�v�u�O���[���v�ȂǁA�����I�ȃR�X�g�ł�CO2�}����i�߂�B���N�t�܂łɊJ�������Œ��Ԏ��܂Ƃ߂Ƃ��Đ������肷��B 2��ڂ́u�R���A�����j�A�����������c��v�Œ����B4�̎��_�́A�W�҂����ʓI�ɃA�����j�A�̔R���������g��ł���悤�쐬�B���苟���Ɍ����A�������Ɠ��l�ɒ��B��̐����I���萫��n���I�����ɗ��ӂ���B�����͌���������B�A���Y�A�A���E�����A���p�A�t�@�C�i���X�Ȃǂ̖ʂŃR�X�g�ጸ���d�v���Ǝw�E�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2020/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���_�C�L�����G�A�R���Ɋ��C�{�^���̗p�u���邳��X�v�B�Q���Ɂu���邳��mini�v�� �_�C�L���H�Ƃ́A�Ǝ��̊��C�@�\����������[���G�A�R���\�����B ���i�̓I�[�v���v���C�X�ŁA��[�\��2.2kW���f���̓X���\�z���i�́A���邳��X��24���~�O��A���邳��mini��17���~�O��AV�V���[�Y��15���~�O��(��������ō�)�B �NJ|���^�ȊO�̃��f���ɂ����C�@�\��W�J�B�g�[�^�]���[�^�]�����Ȃ��犷�C����Ǝ��̋@�\�𓋍ځB�~�͉���/�g�[�����O�C���A�Ă͏���/��[�����O�C�������Ɏ�荞�ށB�܂��AV�V���[�Y�́A�g�[�ʼn��߂���C�⏜��/��[�����O�C�����C�ł���B ���邳��X�́A�l�̍ݎ������m����Ɗ��C�t�@���̕��ʂ��10%��������u�Z���T�[���C�v�@�\��V���ɓ��ځB�l�����m���Ċ��C�ʂ�����u�Z���T�[���C�v�𓋍ڂ��A�ݎ��ɍ��킹�Ċ��C�ʂ��m�ہB�����@�̃t�@���̕��ʂ�ς����Ɏ��O�@�̊��C�t�@���̕��ʂ��グ�A���C�ʂ��10%����������B �o�T�u�C���v���X�v |
|
|
| �����C�̃^�C�~���O��������CO2�Z�x����� �����Y�Ƃ́A�����̓�_���Y�f�Z�x���v���ł���A�R���p�N�gCO2�Z�x�v���@�uCO2 Manager�v��12��15���ɔ̔�����B ���i��12,800�~�B�f�B�X�v���C�ɓ�_���Y�f�̔Z�x��F�Ɛ��l�ŕ\������v����B��_���Y�f�Ɠ����Ɏ��x�≷�x�����A���^�C���ŕ\������B �{�̃T�C�Y��72�~42�~93mm(���~���s���~����)�ŁA�R���p�N�g�Ȍ`��ɂ��w�Z��I�t�B�X�A���H�X�Ȃǂ̗l�X�ȏꏊ�Ŏg�p�ł���Ƃ����B CO2�̑���͈͂�400�`5,000ppm�A���x����͈͂�-10�`60��(�}2��)�A���x����͈͂�5%�`99%RH(�}5%RH)�B �\���Ȋ��C���������Ŋ������m���ɗ\�h�ł���킯�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă���B �o�T�u�ƓdWatch�v |
|
|
| ���[�J�s�ŐA���H������A���z�����d�œd�͎��� DMM.com�ƃO���[�����o�[�z�[���f�B���O�X�iGRHD�j�́A���R�����p�^�̐A���H��uVeggie�v����ʌ��[�J�s�ɐݒu���A�ړ��\�Ȑ��k�͔|���u�̎��؎�����2021�N1�����s���B Veggie�́A20�t�B�[�g�R���e�i�Ɠ����̑傫���ɏc�^���k�͔|���u�A�{�t�Ǘ����u�A�ݔ��Ȃǂ𓋍ڂ������^�_�Ɨp�S���n�E�X�B�g���b�N�Ȃǂňړ��\�ŁA�ݒu�ꏊ��I�Ԃ��ƂȂ����k�͔|���\�B �[�JPoC�ł́AVeggie��10��ݒu����ق��A���z�����d�ݔ���ݒu���A�G�l���M�[�̎�����������є��p�d���Ƃ��ė��p����B���^���k�͔|���u�̉\����A���Ə���^�ăG�l���p�̐A���H��Ƃ��Ă̎�������]������B���؊��Ԃ͖�2�N�Ԃ̗\��B �o�T�u���K�\�[���[�r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�쐻�쏊�A�H�i�H��̃G�l���M�[�L�����p���ăq�[�g�|���v�K�p�p�r�g�� �O�쐻�쏊�A�H�i�H��̃G�l���M�[����ʍ팸�ECO2�r�o�ʍ팸�Ɍ����ACO2���̒�GWP�i�n�����g���W���j��}��p�����q�[�g�|���v�ɂ��G�l���M�[�L�����p�\�����[�V�������Ƃ���������Ɣ��\�����B �H�i�H��̊����E���M�E��p�E�����Ɋւ���q�[�g�|���v�s��ɂ����āA�N��20���~�̔���A�N��1���g���ȏ��CO2�r�o�ʍ팸���ʂ̒B����ڎw���B �V���ƌv��̑� .�e�Ƃ��āA�u�≷�����������ɂ����M�Ɨ�p�̍������v�u�����H���ɂ����鋟���M���̏ȃG�l���M�[�v�u�ቷ�����ɂ����鏜���v�Ɋւ���\�����[�V�����E�K���s��ւ̎��g�݂���������B���݁A�H�i�H��̉��M�E�����H���́A���C���g���₷���G�l���M�[�����A�����ߒ��ő����̃��X���������A���̗L�����p���͕���54���Ǝ��Z����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z���œ��삷��u�X�}�[�g�S�~���v�A�\�Q���ʼn^�p ���z�����d��IoT�����p�����u�X�}�[�g�S�~���ESmaGO�v���\�Q�������̕����ɐݒu����A�����ɉ^�p���n�߂��B �I�t�B�V�����p�[�g�i�[�̐X�i���ق����\�����B��BigBellySolar���J���B���{�ւ̗A���E�ێ�E�N���E�h�̊Ǘ��́A���{�V�X�e���E�G�A���S������B�X�}�[�g�S�~���́A3G�����ʂ��ăS�~�̒~�Ϗ��N���E�h��Ń��A���^�C���ɔc���ł���B �܂��A�S�~�������t�ɂȂ�Ǝ����I�Ɉ��k����A��5�`6�{�̗e�ʂ����e�ł���B����ɕK�v�ȓd�͂͂��ׂď㕔�̑��z���p�l���Řd���\�Q�������̕�����13�J��34��i��ʉR�p21��A�������ݗp13��j��ݒu�����B BigBellySolar���̃X�}�[�g�S�~���́A�ăj���[���[�N�̃^�C���Y�X�N�G�A��t�����X�A�p���A�A�C�������h�A�h�C�c�Ȃǐ��E50�J���ȏ�̎����̂œ�������Ă���B �o�T�u���K�\�[���[�v |
|
|
| ���e�X���̒~�d�r�p���[�E�H�[���͐��E��ς��鐢�E�I�G���W�j�A���]�����郏�P �ăe�X���Ђ��p���ŐV���ȃr�W�l�X�v�����uVirtual PowerPlant�T�[�r�X�v�����������邽�߂ɓ����n�߂��B �e�ƒ�ɐݒu�����p���[�E�H�[���i�������̓e�X���ԁj�̃��`�E���C�I���d�r�����z�I�Ɍq���āA�d���Ԃɑ���~�d�{�݂Ƃ��Ďg���A�C�f�A�B�e�X������d�͂̍w����]�҂́A�p���[�E�H�[��������ɐݒu����B �p���[�E�H�[���́A��d���̃o�b�N�A�b�v�d���Ƃ��Ĕ̔�����ė����B�e�X������d�͂��w������ƁA���X�̊�{�����������ɂȂ��ɁA1kWh������̒l�i��2�`3�������Ȃ邽�߁A�S�̂ł͔��z�ȉ��ɂȂ�Ǝ��Z����Ă���B�e�X���́A�_�Ă���ƒ�ɐݒu���Ă���p���[�E�H�[����~�d�{�݂Ƃ��ė��p���A�d�͂̈������ɂ͍w�����Ē~�ς��A�d�͂��������Ɏ��o���Ĕ��p���邱�Ƃɂ��A���̍����ŗ��v��B 11�y���X/ kWh�`8�y���X/kWh�i���{�~�ɒ����� 10.8�~�B�����d�͂̉��i1kWh������ 19.88�~�j�œd�͂��w���ł���B �o�T�uMAGMAG�v |
|
|
| ���I�������A������d�̑��z���u���S���Ə���v�ɑΉ���p�ی�p�d�� �I�������́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�⒆���K�͂̍H��ȂǂŁA���Ǝ҂����z���Ŕ��d�����d�͂d�����ɑS�Ă��{�ݓ��ŗ��p����u���S���Ə���v��p�̕ی�p�d��uKP�|PRRV�v��2021�N2���ɔ�������Ɣ��\�����B �����i�́A������d�����̑��z���V�X�e���̈��S��S�ۂ��A���d�Ԃ̌̏�⎖�̔������ɂ��̉e�����ŏ����ɗ}���邽�߂̋@��B2020�N�Ĕ����̊��S���Ə���Ή��p���[�R���f�B�V���i�uKPW�|A�|2�v�Ƒg�ݍ����邱�ƂŁA������d�̎{�݂ɂ����āA����d�͂ɑ���99%���x�̍����x�ŒǏ]���Ĕ��d�B ���X���ŏ������A�ő���ɔ��d���銮�S���Ə���V�X�e������������Ƃ����B�܂��A������d�ł̊��S���Ə���ɕK�v��4�̋@�\�i�t�d�͌��m�@�\�A�n���ߓd�����m�@�\�A�o�b�N�A�b�v�d���A�d�͌v���@�\�j���ЂƂɂ܂Ƃߏ��^�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E�����������A�č��̉^�A����̔r�o�ʍ팸��擱����J���t�H���j�A�B�̎��g�݂��Љ� ���E�����������iWRI�j�́A�J���t�H���j�A�B���B���Ŕ̔�����邷�ׂĂ̐V�Ԃ̏�p�Ԃƃg���b�N�̔r�o�K�X��2035�N�܂łɃ[���ɂ���悤�`���Â��锭�\���s�������Ƃ��āA�č��̉^�A����ł̉������ʃK�X�iGHG�j�r�o�ʍ팸�̏d�v�����w�E�����B �唼�̏B�ł́A���d���Ǝ҂������ŃN���[���ȓd�͌��ւ̓]����i�߂ĐΒY�Η͔��d���ւ̈ˑ��x���ቺ�������߁A2016�N�ɂ͉^�A���傪�d�͕�����čő�̓�_���Y�f�r�o���ƂȂ����B �č��̉^�A����ɂ�����ő�̔r�o���́A��ɃK�\�������g�����^�ԂŁA2018�N�̉^�A����ɂ�����GHG�r�o�ʂ�59%���߂��B��Ƀf�B�[�[���R�����g�����^�E��^�g���b�N��23%�A�q��@��9%�ł������B�ŋ߁A15�̏B�ƃR�����r�A���ʋ悪�o�X�ƃg���b�N�̓d�������������邽�߂̍s���v��������ō��肷��Ɩ������Ƃ́A�d�v�ȑO�i�ƂȂ����B���S�ŃN���[���Ȍ�ʃV�X�e�����\�z���鎞�����Ă���A�J���t�H���j�A�B�����̓��������Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���o�C�I�v���A�����@�ے����̑ϔM���ԕ��i�ɂ����p�� �������k����[�Ȋw�Z�p��w�@��Ȃǂ̃`�[���́A���̌����ł���p���v����A��C���Ŗ�500���܂őς�����ϔM���̍����v���X�`�b�N�̊J���ɐ��������B �ϔM���̖��ŗp�r�������Ă����o�C�I�v���X�`�b�N�̗��p���L���邫�������ɂȂ肻�����B �z�^�Љ�ŕ��y�����҂����o�C�I�v���́A�g�E�����R�V��T�g�E�L�r�̑@�ۂɕς��Ă��甭�y������Ȃǂ��č���邪�A�ϔM�����Ⴉ�����B ���l�̌������g���Ȃ�����A���������g���H�����H�v���ĉ��w�\�����܂������قȂ�o�C�I�v���̍����ɐ��������B���f���������ŕ������鉷�x��743���ŁA���ϔM�̍����@�ۂ̃U�C�����i71���x�j�Ȃǂ��������B �o����Ă���o�C�I�v���́A�ϔM�����������̂ł�200���ŗp�r�������Ă����B����̃o�C�I�v���́A�A���~�j�E����}�O�l�V�E�����n���鉷�x�ɂ��ς����邽�߁A�����Ƒg�ݍ��킹�Ď����ԕ��i�⌚�z���ނɂ����p���ł���Ƃ����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���C�M���X���E�H�ƁE�_���n��ȁA�v���X�`�b�N���X�g���[���̋����֎~�[�u���{�s �C�M���X���E�H�ƁE�_���n��Ȃ́A�C���O�����h�ɂ�����v���X�`�b�N���̃X�g���[�A�}�h���[�A�Ȗ_�̋������֎~����[�u��2020�N10��1���ɔ��������Ɣ��\�����B �C���O�����h�ł͐����1�N�ԂɃv���X�`�b�N���̃X�g���[47���{�A�}�h���[3��1600���{�A�Ȗ_18���{���g�p����A���̑������C�֗��o���A�[���Ȋ����������N�����Ă���B���̋֎~�[�u�ɂ��A25���N���v�悪�f����C�m�����̕ی�ƃv���X�`�b�N���݂̔����h�~�Ƃ����ڕW�Ɍ������O�i�����҂����B �C�M���X�͐��E�ɐ�삯���v���X�`�b�N��������u���Ă���A�}�C�N���r�[�Y�̋֎~�A�g���̂ă��W�ܗL�����Ȃǂ����{���Ă����B���W�܂́A2021�N4�������1��10�y���X�ւ̒l�グ�ƑS�����X�ւ̑Ώۊg��\���Ă���B�܂��g���̂Ĉ����e��̃f�|�W�b�g�������A�v���X�`�b�N�p�����̔�OECD�����ւ̗A�o�֎~�A�Đ��v���X�`�b�N�ފܗL��30���ɓK�����Ȃ���ւ̉ېłȂǂ��\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�@�̒�����A2021�N�x����WEB���x���`�}�[�N���x�ꕔ�������� �����G�l���M�[���́A�H�ꓙ���f����[�L���O�O���[�v�iWG�j���J�Â��A�ꕔ�Ǝ�ł́A�x���`�}�[�N�w�W�������ɂ��ċc�_���J�n�����B �܂��A2021�N5���̉^�p�J�n���߂ǂɁA�ȃG�l�@�Ɋ�Â�������ɂ��ĐV���ȓd�q�V�X�e�����J�����A���N�x�ł̃I�����C����100����ڎw�����Ƃ�����B WG�ł́A���ƎҊԂ̃x���`�}�[�N���ђl�̂�����傫���ꕔ�̋Ǝ�ɂ��āA�K�Ȏw�W�ݒ�Ƃ��ׂ��A�����������{����B����A�Y�ƕ���̂����u�d�F���ʍ|�����Ɓv�u�d�F����|�����Ɓv�u�m�������Ɓv�u�������Ɓv��4�Ǝ�ƁA�u�ȃG�l�]�n�v�ŖڕW���Z�o���Ă���u�ݎ������Ɓv�Ō������̌�����i�߂�B �ȃG�l�@�̒�����⒆�����v�揑�́A2021�N�x����́AWEB�c�[���ɂ�����������쐬���A���̂܂܃I�����C����o���\�Ƃ��邱�ƂƂ����B�I�����C����o���s�����߂ɂ́A���O�Ɂu�d�q����g�D�g�p�͏o���v�̒�o���K�v�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IEA�A���E�G�l���M�[�W�]2020���\���z�����u�d�͋����̐V���ȉ��v�� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A�u���E�G�l���M�[�W�]2020�N�v�iWorld Energy Outlook2020�j�\�����B �V�^�R���i��@�̉e���ŁA2020�N�̐��E�̃G�l���M�[���v��5�������A�G�l���M�[�֘ACO2�r�o�ʂ�7���������A�G�l���M�[������18����������Ƃ̌��ʂ����������B �܂��A2021�N�ɐ��E�o�ς��R���i��@�ȑO�̃��x���ɖ߂邱�Ƃ�O��ɁA�e�����{�̌��݂̌v���g�ݍ����\����V�i���I�iSTEPS�j�ɂ����āA�Đ��\�G�l���M�[�d����2030�N�܂ł�10�N�ԂŁA���E�̓d�͎��v������80�������Ɨ\���B 2025�N�܂łɓd�͂Y�����v�Ȏ�i�Ƃ��ĐΒY��ǂ������Ƃ����B���ł����z�����d��2030�N�ɂ����ĔN����13���������u�d�͋����̐V���ȉ��ɂȂ�v�Ƃ̌������������B����A���E�̔��d�ʂɐ�߂�ΒY�̃V�F�A�́A2019�N��37������A2020�N��35���A2030�N�ɂ�28���ɒቺ���錩�ʂ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E�ő�6.2kW�̔M�G�l���M�[�d�͂ŗA�����[�v�q�[�g�p�C�v�J�� NEDO�́A�����p�M�G�l���M�[�v�V�I���p�Z�p�����g���iTherMAT�j�A���É���w�ƂƂ��ɁA���E�ő�6.2kW�̔M�G�l���M�[�d�͂�2.5m�A���ł��郋�[�v�q�[�g�p�C�v���J���������Ƃ\�����B �J���������[�v�q�[�g�p�C�v�̋쓮���́A���E�̂��t���z���グ��ъnj��ۂŁA�����p�M���̂͌��Ƃ��ċ쓮���邱�Ƃ��ł���B�d�͕s�v�̔M�A���Z�p�Ƃ��Ċ��҂���Ă���A��ʂ̔M�A�����\�ɂ��邽�߁A������\�����{�b�N�X�\���ɉ��ǁB����ɋÏk��̍œK����}�邱�ƂŁA���肵��������\�ɂ����B����A�����Ԃ̃G���W����H�ꂩ��̔r�M���p�A�d�C�����Ԃ�f�[�^�Z���^�[�̋@��ނ̔M�}�l�W�����g�A��^���M�@��̗�p�Ȃǂւ̓K�p��}��A���{�I�ȏȃG�l���M�[����ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l���M�[�Z���^�[���ȃG�l����W2020�łs �J�^���O�E�p���t���b�g���X�g �E�ȃG�l�x���T�[�r�X�̂��ē� �E�ȃG�l���M�[�K�C�h�u�b�N�H��ҁA�r���� �E�ȃG�l����W2016�N�Ł`2020�N�� �E�G�l���M�[�̌����鉻 �E�ׂ��ɂȂ���ȃG�l�p�̂��ē� �E�I�t�B�X�r���̏ȃG�l���M�[ �E���Ǝ{�݂̏ȃG�l���M�[ �E�z�e���̏ȃG�l���M�[ �E�a�@�̏ȃG�l���M�[ |
|
|
| ���@�@[�@2020/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�m�����A��́u���y�ʓ����f�M�ށv���Ɖ��֑f�ތn�x���`���[�ɏo�� �O�m�����H�ƁA��̒��y�ʓ����f�M��SUFA�i=SuperFunctional Air�j�̎��Ɖ���i�߂�f�ތn�x���`���[�A�e�B�G���t�@�N�g���ɏo�������B ���Ђ̊E�ʐ���Z�p��E���^���t�H�[���Ƃ̕������Ȃǂ̒m����A�e�B�G���t�@�N�g���̖��@�f�ތn�Ɋւ���Z�p�m����m�E�n�E�����L���ASUFA�̉��l����⎖�Ɖ����i���߂����B SUFA�̓e�B�G���t�@�N�g�������s��w�Ƃ̋��������ɂ��J�������G�A���Q���B�]���G�A���Q���̍쐻�ɂ͒��ՊE�������u�ƌĂ�鍂���ȑ��u���K�v�Ƃ���Ă������A���Ђ͓Ǝ��̃��V�s���J�����A��R�X�g�������������B �e�B�G���t�@�N�g����SUFA�̔M�`�����ɂ��āA���m���X�^�C�v��0.012�`0.014W�^m�EK���x�ƒႭ�A�f�M�ނƂ��Ă̐��\�́u���E�ō����x���v���Ƃ��Ă���B�܂��A�����Ōy�ʂł��邽�߁A����܂Œf�M������������ⓧ�����̒f�M���ł���悤�ɂȂ�A�l�X�ȕ���ł̏ȃG�l���M�[�������҂ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����|�H���CO2���烁�^�������A�������D�Ȃǎ��� �������D�́A�G�b�N�X�s�s�������Ƌ����Łu���|�H�ꂩ��������CO2�̎������ɂ��Y�f�z���f���̍\�z���؎��Ɓv�Ɏ��g��ł���B CO2�Ɛ��f�������ă��^�����������郁�^�l�[�V�����ݔ���10���ɒ��H����B ���Ȃ�2018�N�x�����{����uCO2�̎�������ʂ����Y�f�z�Љ�f���\�z���i���Ɓv�̈�Ƃ��āA��Ă��̑����ꂽ�B���c���s�̊����ƃZ���^�[�̃X�g�[�J�[���ċp�F�̂���75t/���̘F1���ΏۂɁA���^�����ݔ���CO2����ݔ��Ȃǂ�ݒu����B ���^�������ʂ́A���Ɨp�V�R�K�X�̃T�e���C�g�����ݔ��ɕC�G�����125Nm3-CH4/h���v��B���؎����ł́ACO2�팸���ʂ����E�]������ƂƂ��ɁA�{�i�I�ȕ��y�Ɍ������ۑ�𖾂炩�ɂ���B���؊��Ԃ�2022�N�܂ł̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ������h�~�Ɍ��ʂ���H���K�\�[���[���d���ɃA���~�P�[�u���̗p�^�É͓d�H �É͓d�H�́A���ЂƌÉ͓d�H�Y�Ɠd�����J���E�������鍂�@�\�^�ሳ�A���~����CV�P�[�u�����A�R�������̃��K�\�[���[���d���ɍ̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���Ђ́u�ߔN�������铺���̓���ɑ���h�~��ɂ��L�p�v�Ƃ��Ă���B ����A�R�������̃��K�\�[���[���d���ŃP�[�u�������Q���������A���������E����h�~��ړI�ɓ����i���̗p���ꂽ�B�Y�Ɨp���z�����d���͕~�n���L����ɖ��l�ŁA�ߗׂɐl�Ƃ�l�ʂ�̏��Ȃ����n���������Ƃ���A�����̓]����_�����P�[�u���̓���������A�ۑ�ƂȂ��Ă���B ���Ђɂ��ƁA���̂ɃA���~�j�E�����̗p���A�P�[�u���V�[�X�����A������CV�P�[�u���Ƃ̎��ʂ��e�Ղȁu�炭�炭�A���~�P�[�u���v�ɂ͓���h�~���ʂ����҂ł���Ƃ����B�܂��A�u���邢�v�u����v�u�_�炩���v�Ƃ����������ɂ��A����������]�ތ���̍�ƌ������P�ɍv������Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o���^�o�C�I�}�X���d�R���p�u�\���K���v���͔|�E�y���b�g���A���Ŏ������J�n �o�����Y�́A�I�[�X�g�����A�ɂ����āA�ΒY�ƍ��Ă��\�ȃo�C�I�}�X���d�R���p�A���̐A�������Ɩ؎��y���b�g���������J�n�����Ɣ��\�����B ���̃v���W�F�N�g�ł́A���v85�����������̃G���V�����ΒY�z�R�̗V�x�n�E�p��ݔ��������p���A�o�C�I�}�X���d�R���p�Ƃ��āu�\���K���v���͔|�B�\���K���́A�~�J�ʂ����Ȃ��A���̃G���A�ł̐���ɓK���Ă���A7���܂łɏ����Ȑ��炪�m�F������n���s�����B ���݁A�\���K���̖؎��y���b�g���������s���Ă���A2020�N�㔼�ɂ͖؎��y���b�g�̔��Y���i�u���b�N�y���b�g���j������\�肵�Ă���B�؎��y���b�g�Y�������u���b�N�y���b�g�́A�]���̖؎��y���b�g�ɔ�ׂđϐ����E���Ӑ��ȂǂɗD��A�ΒY�Ɠ��l�Ɏ�舵�����Ƃ��ł��邽�߁A�ΒY�Η͔��d�ɂ�����CO2�r�o�ʒጸ�����҂ł���B �\���K���́A�C�l�Ȃ̈�N���ŁA�����⎔���Ƃ��č͔|����Ă���B���Y�����������A�o�C�I�}�X���d�R���p�A���Ƃ��Ċ��҂���Ă���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��200�x�̔M�����A�Y�ƗpHP�Ł^�O�쐻�쏊�A2023�N�x�����֊J�����X �O�쐻�쏊�́A�ō�200���̔M�������ł��鍂�����ȎY�Ɨp�q�[�g�|���v�̊J����i�߂Ă���B �H����̖����p�M��M���Ƃ��鍂����HP�Y�v���Z�X�ɓ������邱�ƂŁA�ȃG�l���M�[�≷�����ʃK�X�̍팸�������߂�B���݂͎���@�̐���⌟�ؒ��ŁA2023�N�x�ɂ͎��ۂ̍H��ւ̓�����ڎw���B ���Ђ́ANEDO�Őݗ����ꂽ�����p�M�G�l���M�[�v�V�I���p�Z�p�����g���iTherMAT�j�̎Q���ƂƂ��āA�ō����M���x200���A����M�}�̂�80������180���ɉ��M���\�ȎY�Ɨp�q�[�g�|���v�̊J�������{���Ă���B �{���g�݂̈�Ƃ��āA���Ђ͍ō�200�����M����������Y�Ɨp�����������q�[�g�|���v�J���ɒ���B�܂��A�ʓr�����J�����Ă���Y�Ɨp�q�[�g�|���v�V�~�����[�^�[����g���A�q�[�g�|���v�̕��y�A�Ђ��Ă͓����H��̏ȃG�l�𐄐i����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���V�^�R���i���s��A��4�����u�����v�ɑO�����ȕω��A���Ɏq���c������ ���Ɏq���c�́A�u��1����{�l�̊���@�ӎ������v�̌��ʂ\���A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s��A43�����H�i���X�팸��ȃG�l�Ȃǂ́u�����ւ̈ӎ���s���ɑO�����ȕω����������v�Ɖ������Ƃ����������B ����A��22�����u�ƒ낲�݂��������v�u�g�p�d�͗ʂ��������v�Ɖ����B�܂��A2020�N7���̃��W�ܗL����A74.3���������ւ̈ӎ���s���ɕω����������ƉB�u�ω��v�̓��e�����Ƃ���A�ł����������̂́u�}�C�o�b�O�����������悤�ɂȂ����v�i60.7���j�ŁA�S�̖̂�6���ƂȂ����B �u���W�܂̔�L���X�܂ł��f��v�i23.4���j�A�u���݂̕��ʂ��ӎ�����ɂ悤�ɂȂ����v�i13.9���j�A�u�}�C�{�g�������Q����悤�ɂȂ����v�i12.7���j�Ȃǂ���������B �����̈ӎ���s�����i��ł��鍑�́A1�ʁu���{�v�A2�ʁu�X�E�F�[�f���v�A3�ʁu�I�[�X�g�����A�v1�ʂɓ��{��I���R�́A�u���݂̕��ʂ��ł��Ă���v�u���W�܂��L���ɂȂ����v�Ȃǂ̉���������ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�H�^�_�N�g�p���C��uCO2�Z���T�[���ڃ^�C�v�v���� �O�H�d�@������Ђ́A�_�N�g�p���C��̐V���i�Ƃ��āACO2�Z���T�[�𓋍ڂ����uCO2�Z���T�[���ڃ^�C�v�v2�@���11���ɔ�������B �l�̖��W�ɂ��CO2�Z�x�̏㏸�����m���A���C���ʂ������Ő�ւ��邱�ƂŁA���ʓI�Ȋ��C�������B���C��{�̂ɓ��ڂ���CO2�Z���T�[���A�l�̖��W�ɂ�鎺����CO2�Z�x�̏㏸�����m����ƁA���ʂ��}���^�]�Ɏ����Ő�ւ��Č����I�Ɋ��C���C���ʂ̎����ؑւƍ�����DC�u���V���X���[�^�[�ɂ��A�@�Ɗ��C��̃g�[�^�������j���O�R�X�g��N�Ԗ�22,580�~�팸�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ̊T�Z�v���A�����E�G�l�W��8365���~�ăG�l��͓d�����𐄐i �T�Z�v���ł́A�ăG�l�̎�͓d������H��E���r���e�B���̏ȃG�l���A���f�Љ�̎����Ɍ��������g�݂��x������ƂƂ��ɁA�n��}�C�N���O���b�h�̍\�z���x������B �V�K���ƂƂ��āA�~�d�r���̒n�敪�U�d���������L��I�Ȓn��O���b�h�̎����������̐���Z�p���̎��؎��Ƃ�60.0���~���v�サ���B�܂��A���K�͂Ŏ����\�ȓd�͌n���ԁi�n��}�C�N���O���b�h�j�̑S����ł̎������x���i�S�����\�J���j���邽�߁A2020�N�x��2.7�{�ƂȂ�46.8���~���v�サ���B ���̂ق��A�V�K���Ƃł́A�ăG�l�R�����f�����{�݁u�������f�G�l���M�[�����t�B�[���h�iFH2R�j�v�Ő����������f���������{�ݥ�w��H��ȂǂŎ��ؓ������{���鎖�Ƃ�78.5���~���v��B�J�[�{�����T�C�N����������������o�C�I�R�����i���Y�Z�p�̊J�����Ƃ�45.0���~���v�サ���B �܂��A�؎��o�C�I�}�X�R�����̈���I�E�����I�ȋ����E���p�Ɍ����āA15.0���~���v�サ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Ȃ�21�N�x�T�Z�v���A�G�l����2254���~PPA���ōăG�l���i�ጸ ���Ȃ�2021�N�x�\�Z�̊T�Z�v���z���Ƃ�܂Ƃߌ��\�����B �u�E�Y�f�Љ�v�u�z�o�ρv�u���U�^�Љ�v�ւ�3�̈ڍs�Ɍ��������g�݂��x���E���i����B���̒��u�E�Y�f�Ń��W���G���g�����K�Ȓn��Ƃ��炵�̑n���v�̗v���z��1384���~�i1034���~�j�B�����E���U�^�n��G�l���M�[�V�X�e���\�z���x������B �܂��A�ˌ��Z���ZEH�����x�����Ƃ�65.5���~���v��A���f�M���ɂ��ȃG�l�E��CO2�����x������B�܂��A��CO2�^�̃v���X�`�b�N���x���T�C�N���E�Đ��\�����R���f�ނ̐����ݔ��̓����Ȃǂ��x������B ���̒��u�E�Y�f�̂��߂̋Z�p�C�m�x�[�V�����̉������v�̗v���z��414���~�i334���~�j�B�ăG�l�R�����f�A�[���G�~�b�V�����Η͂ȂǒE�Y�f���Ɍ������v�V�Z�p�̊J���E���𐄐i����B ��O�̒��u�O���[���t�@�C�i���X�Ɗ�Ƃ̒E�Y�f�o�c�̍D�z�̎����A�Љ�o�σV�X�e���C�m�x�[�V�����̑n�o�v�̗v���z��218���~�i216���~�j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ыƁE�؎��o�C�I�}�X���d�́u�����Y�Ɖ��v�����A��������^�o�Y�ȁE�_���� �o�Y�ȂƔ_���Ȃ́A�ыƁE�؎��o�C�I�}�X���d�̐����Y�Ɖ��Ɍ�����������������B �؎��o�C�I�}�X���d�̔��d���ƂƂ��Ă̎������ƁA�R���̋������Ƃ��Ă̐X�т̎������m�ۂ𗼗������邽�߁A�ۑ�����Ɍ���������������A�g�ɂ�茟������B�����ǂ͔_���Ȃƌo�Y�Ȃ����߂�B �o�C�I�}�X���d�́A�G�l���M�[�������̌���A�ЊQ���Ȃǂɂ����郌�W���G���X�̌���A���{�̐X�ѐ����E�ыƊ������Ȃǂ̖�����S���Ă���B�n��̌o�ρE�ٗp�ւ̔g�y���ʂ��傫���ȂǑ��l�ȉ��l��L�������A���d�R�X�g��7�����߂�R����̒ጸ��A�R���̈��苟���ɂ����鎝���\���m�ۂ̊ϓ_����ۑ肪���݂��Ă���B ��������_�_�́A���d�R�X�g��7�����߂�R���R�X�g�̒ጸ�ƁA�ыƎ҂̐X�ьo�c�̈��艻�𗼗��B�X�т̊Ǘ���@�̕ϊv�ȂǁB���ɁA�؍ނ̉^���E���H�V�X�e���̍œK����A�L�t���⑁�����̗����p�Ȃǂ̎��g�݁B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������31�N�x�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����̌��ʁi����l�j ���Ȃ́A3��ڂƂȂ镽��31�N�x(�ߘa���N�x)�̒������ʁi����l�j�����܂Ƃ߂��B �������ʂ̂P�ł��鐢�т�����̔N��CO2�r�o�ʂ́A2.80t-CO2�ŁA�O�N�x��3.4�����������B ���̒����ł́A�Ɩ��A������A�①�ɓ��̋@��̎g�p�ɂ��Ă��������Ă���B������CO2�r�o�ʂƂ̏ڍׂȗv�����͂͊m��l�ɂ����čs���\�肾�B�d�C�̎g�p�ɂ��CO2�r�o�ʂ��G�l���M�[��ʂōő��67.1�����߂Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��NEDO�ȂǁA�u���̉ԁv���������ɂ�艷�Ή��̔M��������J�� NEDO�A���k��w�A�n���H�Ə�����я��l����G�l���M�[�́A�u���̉ԁv�Ƃ���Ō`��(����X�P�[��)���͏o���Ă������������邱�Ƃʼn��ɂ��Ή������M��������J�������B �]���̔M������́A�J���V�E���◰���Ȃǂ̗n�𐬕����܂މ��Ŏg�p�����ꍇ�A����X�P�[�����͏o���M������j�Q���邽�߁A�p�ɂȐ��|��v�������e�i���X�R�X�g�������Ȃ邱�Ƃ��ۑ�ƍl�����Ă����B ����A�uNEDO�擱�����v���O����/�G�l���M�[�E���V�Z�p�擱�����v���O�����v�ɂ����āA�`�M�ʂ���]�����A�����ɉH�����������Ă邱�Ƃœ`�M�ʂɐ͏o��������X�P�[��������悤�ɂ����M��������J�������B ���ۂɁA����X�P�[�����������������ƂŒm���鏬�l����(���茧�_��s)��1�����̔M�����������s�������ʁA�`�M�ʂ���̉���X�P�[���̏����ƔM���������̒ቺ�}���ɐ��������Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����O���u�}�C�N���O���b�h�v�\�z�ցA���͂ƒ~�d�r�őS������ ���O���́A���ƁE���Y�Ƃ𒆐S�ɖ�7000�l����炵�Ă���B���O���Ɠ��}�s���Y�́A�u�}�C�N���O���b�h�v�\�z�Ɍ������}�X�^�[�v�����쐬���Ƃɒ��肷��A�Ɣ��\�����B �}�C�N���O���b�h�Ƃ́A��ʑ��z�d���Ǝ҂̓d�͌n������Ɨ����A�����������U�d������d�C����������V�X�e�����B���O���̃}�C�N���O���b�h�v��ł́A�ЊQ���Ȃǖk�C���d�̓l�b�g���[�N�̌n������d�Ɋׂ����ہA���}�s���Y�������ɕۗL����o�͖�41MW�̕��͔��d���ƁA��i�o��18MW�E�e�ʖ�130MWh�̑�^�~�d�r��d���ɁA�����S��ɓd�C���������邱�Ƃ�z�肵�Ă���B �ЊQ���Ɏ������ēd�͂������ł���}�C�N���O���b�h�Ƃ��ẮA��s���Ⴊ���邪�A�����������ꂽ�X��Ɍ��肳�ꂽ���̂ŁA��͓d���̓G���W�����d�@���g���Ă���B���S�́A����l�K�͂�ΏۂɁA�������S�ʍĐ��\�G�l���M�[�Řd���}�C�N���O���b�h�͗�����Ȃ��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���{�̏Z��u�g�[���Ă������v���{�I�ȗ��R �� �u���f�M���C���Z��v�Ƃ������t������悤�ɁA�Ƃ͂ǂ�ǂ�g�����Ȃ��Ă���͂������A���҂����قǂł��Ȃ��B �{���A���f�M���C���Z��Ƃ����̂́A�G�A�R��1���������2�䂾���ʼn��K�ȋ�Ԃ����邱�Ƃ��ł���B���{�̒f�M���\�̊�͎c�O�Ȃ��琢�E�ɔ�ׂ�ƒ������Ⴂ�B 2020�N�ɏ��K�͂̏Z��ł����Ă��f�M���`���������͂����������A�������Ă��܂����B��������20�N�ȏ�̂�1999�N�ɒ�߂�ꂽ����u������ȃG�l��v�Ƃ��āA���܂��ɏZ��ƊE�Ō����ł��邱�Ǝ��̂����������ł͂Ȃ����B �������A���̌Â��ȃG�l��ō�����Ƃ��u���f�M�Z��v�ɂ��悤�Ƃ�������ɂ��Ȃ��Ă���B����قǗD�G�ł��Ȃ��Z����A���f�M���C���Z��ƌĂ�ł���̂ł���B �o�T�u���m�o�ρv |
|
|
| ���@�@[�@2020/10�@]�@�@�� |
|
|
| ����C�Ё^�A�����Ȃǂ̊u���a���������Ȃ��a�@��f�Ï��ȂǂɊȒP�ɐݒu�ł���A�ړ��������\�G�A�o���A���j�b�g���J�� ��C�Ђ́A�E�C���X�������X�N�ጸ�������ł���ړ��������\�G�A�o���A���j�b�g�uAir Infection BlockPlus�i�ʏ�AIB.�j�v���J�������B �d��J�����̃G�A�J�[�e���őo�����̋�C���Ւf�B�⏕�����̕��p�ƁA�z�C���ւ̐ϋɓI�U���ɂ��C���Ւf���s���A���҂̌ċC�E�P���Ζʂ̈�Ï]���҂̏㔼�g�ɐڐG���邱�Ƃ�h�~�G�A�J�[�e���Ƌz�C�������ґ��ɏW��������u������C���v�ň�Ï]���҂��K�[�h����p�[�e�[�V�������G�A�o���A���j�b�g�B �⏕�����Ƌz�C���ւ̐ϋɗU�����s���Ȃǂ̋C������Z�p����g���A�����a�E�j�ɂ�鉘���Z�x��啝�ɒጸ���A��C�̃J�[�e������Ï]���҂����B�܂��A�E�ی��ʂ��v���X����HEPA�t�B���^�[�̗̍p��2��������}������B ��Ï]���҂Ɗ��҂��ΖʂƂȂ�f�@���APCR�����ȑc���̍̎掞�Ɍ��ʂ������ł���B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| ������r�M�ʼnғ����鏬�^�o�C�i���[���d�A�z�K�s�ɓ��� �����}�[�́A����p�M�𗘗p�������^�́u�L�@�i�I�[�K�j�b�N�j�����L���T�C�N�������d�@�iORC���d�@�j�v���J�����A�����@�쌧�z�K�s�́u����ߌ����v�ɐݒu�����Ɣ��\�����B ORC���d�@�́A���������_�̒Ⴂ�}�́i�쓮���́j��p���邱�ƂŁA�ቷ�̏��C��M���d�ɗ��p�ł���̂������B�M���n�Ɣ}�̌n��2�̔M�T�C�N���ō\������邱�Ƃ���A�u�o�C�i���[���d�v�Ƃ��Ă��B �J�����u�́A��i�o��9.0kW�i�M��90�x�A��p��20�x�̏ꍇ�j�A��807�~���s��2009�~����1675mm�B�M�������n���A�n�ɕK�v�ȋ@����p�b�P�[�W�ɂ��邱�ƂŎ{�H�������コ�����B �z�ǁE�z���ڑ��݂̂Őݒu�ł���B�܂��A������̐ݒu���e�ՂŁA�Č����ƂɍœK�ȗe�ʂŒ�Ăł���Ƃ����B�N�Ԕ��d�ʂ͖�7��kWh�̌����݁B8��4�����甭�d���J�n���A���؊��Ԃ�1�N�Ԃ̗\��B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���o���A�Ǘp�t�B�����^�Ǝ����ԗp�̑��z�d�r���J���� ���Ђ̒�Ă���u�t�B�����^���y�ʃ��W���[�����z�d�r�̊J���i�d�ʐ���̂��鉮�������j�v����сu�ړ��̗p���z�d�r�̌����J���v��2�����ANEDO�́u���z�����d�̐V�s��n���Z�p�J���v�����������ƂƂ��č̑����ꂽ�Ɣ��\�����B �����J���e�[�}�u�t�B�����^���y�ʃ��W���[�����z�d�r�̊J���i�d�ʐ���̂��鉮�������j�v�ł́A�]���̑��z���p�l���ɕC�G���锭�d���\�������A�y�ʂ��L�͈͂̉����`��ɓK�����Đݒu�\�ȑ��z�d�r���J������B �܂��u�ړ��̗p���z�d�r�̌����J���v�ł́A�����Ԃ̎ԑ̌`��ɓ��ډ\�ō������E��R�X�g�̑��z�d�r���W���[���J���ɂ�����CIS�{�g���Z���̋Z�p�J���A��̓I�ɂ͕ϊ��������エ���3D�Ȗʃ��W���[�������Ɍ������Z�p�J����S������B�\�[���[�t�����e�B�A��CIS���z�d�r�̋Z�p�����p����B���Ɗ��Ԃ�2020�N�x����2024�N�x�܂ł�5�N�ԁB �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�v���@�\���W��^�I�������\�[�V�A���A�r���E�H������d�͗ʃ��j�^�[ �I�������\�[�V�A���\�����[�V�����Y�́A�r����H������̓d�͗ʃ��j�^�[�̐V���i������Ɣ��\�����B �l�b�g���[�N�ʐM��v���f�[�^�̋L�^�@�\���P��ɏW���B�����̏ȃG�l���M�[���ɕK�v�Ȍv���Ɩ��̌��������P����B���i�̓I�[�v���B �V���i�̖��̂́uKMD1�v�B�������̐ݔ��Ɏ��t����d�͗ʌv��15��܂Őڑ��ł���B�R�d��̗��ʂ��v���ł���I�v�V�����@�\�����ڂ���B�d����OA�@��ȂǒP���ōő�4��H�A�@�Ȃǂ̓��͌n�͍ő�2��H�ڑ��ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ������̎��Ɏ��t���邾���ŁA���������ɂł���u�^�b�`���X�����^�b�v�v �D�S�́A����̐����^�b�v�ɊȒP�Ɏ��t������Z���T�[���^�b�`���X�����^�b�v�uieUSE(�C�G���[�X)�v�������B ��ʔ̔��̉��i��8,980�~�B�Z���T�[��������A���{�@�̉����܂��͑��ʂɂ����������ŁA�����o�Ă���^�b�`���X�����^�b�v�B�^�]���[�h�́u�C���X�^���g���[�h�v�Ɓu�A���������[�h�v��2��ޗp�ӁB �u�C���X�^���g���[�h�v�ł́A�����Ɏ�����������ƂŁA�������J�n�A��~����B �u�A���������[�h�v�̓^�b�v���ʂɎ���������Ɨ������J�n�B�܂��A�����ɋ�C�𒍓����邱�ƂŐߐ�����������B ��C�����ɂ�萅�����Ȃ߂炩�ɂȂ�A�����˂��}������Ƃ���B�Œ莮�����^�b�v�ƁA�z�[�X�̈����o���鐅���^�b�v�ɑΉ�����B�{�̃T�C�Y��47�~79mm(���a�~����)�B�Z���T�[�͈͂́A����1�`6cm�A���1�`10cm�B�K��������0.05�`0.8MPa�B�e��400mAh�̃��`�E���d�r���������B�[�d��microUSB�B �o�T�uImpressWatch�v |
|
|
| �����d�C�A���`LED������33W�E14W�^�C�v�� �����i���Z���t�o���X�g������v�Ɣ�r�����ꍇ�A33W�^�C�v��300W�Ɠ����̖��邳�Ŗ�88���A14W�^�C�v��160W�Ɠ����̖��邳�Ŗ�91���̐ߓd���\���Ƃ����B ��i������60,000���ԁB��ʓI�ȃ����v�z���_�Ɣ�r���āA33W�^�C�v��79���̏��`�����������A�d�����j�b�g�����̂��ߏȎ{�H�B�Ɩ����̑��݊����ŏ����ɗ}���ďƖ�����B ���݂̐�����v��10�N�ȏ�o�߂���LED�����v�̌����ɂ��Ή�����B�I�v�V��������Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŒ��t����Ǖt���E�|�[�����t���Ȃǂ��\�B�t�@�T�[�h��G���g�����X�Ȃǂ̌��z�O�\�A���ԏ��L��Ȃǂ̃G���A�Ɩ��ɂ��Ή�����B��]�������i�́A33W�^�C�v��32,000�~(�Ŕ�)�A14W�^�C�v��19,000�~(�Ŕ�)�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEC��NTT Com�A�V��}��p�����f�[�^�Z���^�[�̗�p�V�X�e�����J���A����d�͂� ���Ђ́A�V��}�uR1224yd�v���g�p���A�u��(�C�̉t��)�ω���p�Z�p�v�𗘗p�����ሳ��p�V�X�e�����J���B �V�X�e���̔z�Ǔ��̋C�̂Ɖt�̂����邱�ƂŁA��}���C�̗�����X���[�Y�ɂ��A�ሳ��}��嗬�ʂŗ�����悤�ɂ����B�܂��A��M���\��2�{�ȏ���コ���A��M���̏��^��(����2����1)�������B�V�䍂���Ⴂ�t���A�ւ̋Ǐ��Ƃ��āA�����̌�����ݔ��ւ̌�Â��̓�����e�ՂƂ����B���݉^�p����NTT Com�̃f�[�^�Z���^�[�Ŏ��؎������s�Ȃ����Ƃ���A����d�͂������ł���(��^�@������40kW�̗�p�\�͂��ȉ��ɍ팸)���Ƃ�A�����t���A/�T�[�o�[���[���ւ̐ݒu���e�Ղł��邱�Ƃ��m�F�����B |
|
|
| �����A�u���g����x�点��ɂ̓G�A�R���̍����������}���v ���A�̐V�������ɂ��ƁA�u�G�l���M�[�����������ċC��ɗD�����G�A�R���v�ɐ�ւ���A����40�N�Ԃōő�4,600���g���̉������ʃK�X�𐢊E�S�̂Őߖ�ł���B ���݁A���E�S�̂�36����̗①�ɁA�Ⓚ�ɁA�G�A�R���Ȃǂ̗�[�@�킪�g�p����Ă���B���E���̐l�ɗ�[�{�݂���邽�߂ɂ́A2050�N�܂łɍő�140���䂪�K�v�ɂȂ�B�������A���̗�p�Z�p�ł́A�G�A�R�����������ʃK�X���ʂɔr�o���A�C��ϓ�������Ɉ���������B2019�N�Ɋe���́AHFC�̎g�p��i�K�I�ɔp�~���邱�Ƃō��ӂ����B���̏C���Ă����s�����ƁA�C���㏸��0.4�����}����\��������B�������A�����_�ŁA�A�����J�A�����Ȃǂ̉������ʃK�X��ʔr�o�����܂ސ��E��95�J�����܂��C���Ăɏ������Ă��Ȃ��B���ɂ��ƁA2050�N�܂łɃG�A�R���̌�����2�{�ɂ���A���E����1,300�M�K���b�g�̓d�͂�ߖ�ł���Ƃ̂��ƁB �o�T�uGIZMODO�v |
|
|
| �����Ǝ҂́u�ȃG�l�`���v�c�_�^�����G�l�����ρA�ƒ땔�叄�� ����̉ƒ땔��̏ȃG�l���M�[�������A���ẴG�l���M�[�����ҋ`�����x���Q�l����ɋ��������B ���{�̎��Ǝ҂͏ȃG�l���̒ɂƂǂ܂�A��̎��s�͎��v�Ƃ̔��f�Ɉς˂��Ă���B���̂��߁A�`�����ۂ����x�����������A�ȃG�l�̂���Ȃ�[�@�肪���҂����B ����A��̔�p���S�̌�������C���Z���e�B�u�݂̍���Ȃljۑ�͉��Ċe���ɂ������A��������ꍇ�ɂ͐T�d�ŏڍׂȐ��x�v�����߂���B���������G�l���M�[������i�o�ώY�Ƒ��̎����c�j�ȃG�l���M�[���ψ���ŁA���{�G�l���M�[�o�ό��������A�e���̉ƒ�E�Ɩ�����ɂ�����ȃG�l����̓���������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���čő�E250MW�̃G�l���M�[�����v���W�F�N�g�A���B�œ����o���B�u�J�[�{���t���[�n���v�ڎw���A�V�R�K�X�Η͂��փw �ăJ���t�H���j�A�B�̓Ɨ��n���^�c�@�ցiCAISO�j�́A�V�����{�ɑS�Ăōő�K�͂̃G�l���M�[�����ݔ����d�͌n���ɐڑ����ꂽ�Ɣ��\�����B ���̃v���W�F�N�g�́A�u�Q�C�g�E�F�C�E�G�l���M�[�����v���W�F�N�g�v�ƌĂ�A�ڑ����ꂽ�o�͋K�͂́A�v���W�F�N�g�̈ꕔ�ɂ�����62.5MW�ł���ANEC�̃��`�E���C�I���~�d�r�����p���Ă���B���̃v���W�F�N�g�̑S�Ă������������ɂ́A���̏o�͋K�͂́A250MW�܂Ŋg�債�A���d����4���Ԃ�1000MWh�̓d�͗e�ʂ��������邱�ƂɂȂ��Ă���B ���Ȃ݂ɁA�����d�������s���Ă���J���t�H���j�A�B�ł́A���d�n���̉^�p�͔�c���g�D�ł���CAISO���S���Ă��āA���@�ւ́A���B�̖�8����S�����Ă���B ���݁ACAISO�ɂ͗ݐ�216MW����G�l���M�[�����ݔ����ڑ�����Ă���B���v�撆�̑S�v���W�F�N�g���A�ڑ������ƁA���̋K�͍͂��N���܂ł�923MW�ɒB����Ƃ����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���R���i�ƔM���Nj����͂v���S�M�����`���C����A���K�����L�[�v ��N�x�A�����Ð�s�̑S�����w�Z30�Z�ɏȃG�l��ɖ𗧂Ă悤�Ƌݔ��ƃZ�b�g�Ń��X�i�C��ݒu���A�����\�h�ƔM���Ǒ�̗�����}���Ă���B �O�H�d�@���ċG�Ɠ~�G�ɂ������1�J���ԁA�������ƕ��p�ɂ����ʂ̕��͒������s�����B���̊w�Z���q���Ǘ��}�j���A���ł́A��_���Y�f�Z�x��1500ppm�ȉ����]�܂����Ƃ��Ă���B �������ʂɂ��ƁA���X�i�C�̎g�p�ɂ���ē�_���Y�f�Z�x�͏�Ɋ�l�ȉ��ŁA������ʂ���l����������B�E�C���X�ɑ�����ʂ͖��炩�ł͂Ȃ����̂́A��_���Y�f�Z�x�̏㏸��}�����Ă���A�E�C���X�̒ጸ�ɂ��Ȃ����Ă���ƕ��͂��Ă���B ���w�Z�ł͐V�^�R���i��ŋ����ɂ���L�����Ɖ^���ꑤ�ɂ���4���̑���15�Z���`���x�J���Ċ��C���������A���������������Ԃɕۂ��Ă���B�s���ς͑��J�����C�̉��ƁA�C���t���G���U�����s����~�G�̊��C�Ɍ��ʂ������Ƃ݂Ă���B �o�T�u�V���v |
|
|
| ���h�C�c�A�Đ��\�G�l���M�[�̊g����p���� �h�C�c�A�M�����iUBA�j�ɂ��ƁA�h�C�c�̍Đ��\�G�l���M�[�͊g��𑱂��Ă���A2020�N�㔼���͖�1,380���L�����b�g�������d����A2019�N�̓������Ɣ�r����Ɩ�8%�i��100���L�����b�g���j���������B �܂��A�R���i�E�C���X�̗��s�ɂ��d�͏���ʂ������������߁A���d�͏���ʂɐ�߂�Đ��\�G�l���M�[�̊����͑啝�ɑ������A2019�N�㔼����44%����2020�N�̏㔼���͏��߂Ė�50%�ɒB�����B���͂́A�ΒY�A�V�R�K�X�A���q�́A����сA���̑����ׂĂ̍Đ��\�G�l���M�[�����āA�h�C�c�̓d���\���ɂ����čł��d�v�ȃG�l���M�[���ƂȂ��Ă���A2019�N�̓����Ɣ�ׂ�Ɩ�10%���������B�h�C�c�ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�̔����ȏ�͕��͂���߂Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����k��A�Ï��ł����d����퉷���d�f�o�C�X�J�� �J�������퉷���d�f�o�C�X�́A�u�M�d���d�f�q�v�Ɓu�~�M���v�u���M���v�Ȃǂō\������Ă���B �M�d���d�f�q�́ABi2Te3��Sb2Te3�́A�����̑���Ȃ�M�d�f�q���߂����Z�p�ō쐻���A�V���R����ŋ��ݍ��\���ł���B�M�d���d�f�q�͕Жʂ��~�M���ɁA��������̖ʂ����M���ɐڐG���Ă���B ���͂̉��x�����ω�����ƁA�M���~�M���ɋz�����ꂽ��A�~�M��������M���ꂽ�肷��B���̎��A�M�d���d�f�q�̗����ɉ��x���������Ĕ��d����d�g�݁B �����ɗp�����퉷���d���j�b�g�̃v���g�^�C�v�ɂ́A�~�d�̂��߂̃L���p�V�^�[�≷�x�Z���T�[�A�}�C�R���A�������j�b�g�Ȃǂ��g�ݍ��܂�Ă���B���̏퉷���d���j�b�g�����������ɐݒu���A�����x�ω��ɑ��锭�d�ʂȂǂɂ��Č��������s�����B1���̂����ʼn��x���傫���ω����钩��[���ɁA���d�ʂ��傫���Ȃ邱�Ƃ����������B���x�Z���T�[�Ŏ擾�����f�[�^���A�o�b�e���[�Ȃ��ł��K�v�ɉ����Ė����ʐM���邱�Ƃ��\�ƂȂ����B �o�T�uEE Times Japan�v |
|
|
| �����E�����������A�������O���[���{���h�s�ꂩ��u�N���[���E�R�[���v�����O���钛���� ���E�����������iWRI�j�ɂ��ƁA�����̋K�����ǂ�2020�N5���ɁA������ւ̒��g�݂ɓ��������������B�̂��߂̋��Z���i�ł���O���[���{���h���g���Ď����B�ł���v���W�F�N�g����A�u�N���[���E�R�[���i���ᕉ�^�̐ΒY���p�j�v�����O���邱�Ƃ��Ă����B �������ꂪ��������A�����̔��d�ʂ̔����ȏ�𖢂��ɋ������Ă���ΒY���d����̒E�p�ɂȂ���\��������B�ꕔ�̓����Ƃ́A�����̃O���[���{���h�̃��[�����`�����ۊ����O��Ă���̂ł͂Ȃ����ƌ��O��\�����Ă����B�N���[���E�R�[���́A�����ȊO�ł̓O���[���{���h�̑Ώۂ���͏��O����Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2020/9�@]�@�@�� |
|
|
| �����z�����d�́u���Ə���v�Ŋ�Ƃ�SDGs�������x������T�[�r�X�J�n �����d�̓~���C�Y�́A��Ƃ�SDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�������T�|�[�g����T�[�r�X���J�n�����B ���̃T�[�r�X�ł́A�����d�̓~���C�Y���A���z���̎��Ə���Ƃ̕��y�ƃA�t���J���̓r�㍑�ł̓d���������ڎw�����v���W�F�N�g�����{����GOOD ON ROOFS�ƘA�g�B�ڋq��CO2�r�o�ʂ̍팸���ł��鑾�z�����d�̎��Ə���T�[�r�X�𗘗p���Ă��炢�Ȃ���A�r�㍑�ɂ�����d�������㓙��SDGs�����ɎQ���ł���Ƃ������́B �����d�̓~���C�Y�ƒ�g��Ƃ��A���z�����d�ݔ���ݒu�E�^�c���邱�Ƃɂ��A�ڋq�͏�����p�[���ő��z�����d�ɂ��CO2�t���[�̓d�C�𗘗p�i���Ə���j�ł���B���̎��Ə���T�[�r�X����Ƃɗ��p���Ă��炢�A���̑Ή��Ƃ��Ďx������T�[�r�X�����̈ꕔ��GOOD ON ROOFS�ւ̊�t���Ƃ��Ċ��p����B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���剤�����^���Q�Ŗ�63MW�̃o�C�I�}�X���d�{�݂��ғ��p���v�p�t�����p �剤�����́A�O���H��Ńo�C�I�}�X���d�ݔ��̐V�ݍH�����������A�Œ艿�i���搧�x�iFIT���x�j�𗘗p�����d�͔̔����J�n�����Ɣ��\�����B �N���t�g�p���v�����H���Ŕ�������p���v�p�t�i���t�j�����p����B���C�^�[�r���̔��d�ʂ�62,920kW�B ���H��͂���܂ŁA���t���{�C���[�ŔR�Ă����A�G�l���M�[�Ƃ��Ċ��p����o�C�I�}�X���d���s���Ă����B����V���ɍ��t����{�C���[�����݁B�����ݔ��Ɣ�r����5���̌������P�ɂ��25,000�g���^�N��CO2�r�o�ʍ팸�i��ʉƒ�̖�7,200���ѕ��ɑ����j���\�ɂȂ�ƂƂ��ɁA�l���n���ɂ�����d�͎��v�ɑ���Đ��\�G�l���M�[�䗦����ɍv������B�ݔ������z�͖�220���~�A���㍂�͔N�Ԗ�70���~��������ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������݁^����Ŗ�2MW�̖؎��o�C�I�}�X���d���ғ��Q����Q�ނ����p �������݂́A���쌧����s�Ɍ��݂����o��1,990kW�̖؎��o�C�I�}�X���d�����ғ����J�n���A�Œ艿�i���搧�x�iFIT���x�j�ɂ�锄�d���J�n�����B ���Ђƃg���^���[�E�O���[�v�̍��َ��Ɖ�ЁE�M�B�E�b�h�p���[�ɂ�锭�d���ƂŁA�Ԕ��ނȂǂ̖����p�؍ނ̂ق��A���n�Ŗ�艻���Ă���}�c�N�C���V��Q�ނȂǂ�R���ɂ���B �����d���̔��d�ʂ͔N�Ԗ�1350��kWh�A���㍂�͓�5.4���~���x��������ł���B�R���ƂȂ錴�؎g�p�ʂ͔N�Ԗ�3���g���B�n���̐X�ю{�ƎҁA�X�ёg���A�R�я��L�ғ�����̌��ؔ����z�͔N��1��5000���~�ɒB���錩���݂��Ƃ����B�܂��A���d���̉^�p�ƃ`�b�v�����̂��߂�12�l��V�K�ٗp�����B ���Ђ͍���A�؎��o�C�I�}�X���d�̓K�n�������p�����{����ƂƂ��ɁA2MW�N���X�̔��d�����t���p�b�P�[�W�����A���A��O�̔��d���Ƃ̗����グ��ڎw���Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��Apple�^2030�N�܂łɃT�v���C�`�F�[���Łu�J�[�{���j���[�g�����v�B���� Apple�́A���ƑS�́E�����T�v���C�`�F�[���E���i���C�t�T�C�N���̂��ׂĂ�ʂ��āA2030�N�܂łɋC��ւ̉e���u�l�b�g�[���i�����[���j�v��ڎw���Ɣ��\�����B ���Ђ͂��łɃO���[�o���Ȋ�Ɖ^�c�ɂ����ăJ�[�{���j���[�g������B�����Ă��邪�A�V���ȖڕW�ł͔̔�����邷�ׂĂ�Apple�̃f�o�C�X�ɂ��Ă��A2030�N�܂łɋC��ւ̉e�����l�b�g�[���ɂ��邱�Ƃ��߂����B ���J�����u���Ɋւ���2020�N�̐i�����v�ł́A���БS�̂̉������ʃK�X�̔r�o�ʁi�J�[�{���t�b�g�v�����g�j��2030�N�܂łɌ��݂�75%���Ƃ���v��ɂ��ďڏq����ƂƂ��ɁA�c��25%�̓�_���Y�f���������邽�߂̊v�V�I�ȃ\�����[�V�����̊J���ɂ��Ă����y�����B �T�v�́A��Y�f�̍Đ��ޗ��̎g�p�B����I�ȃ��T�C�N����@�Ȃǂɂ���Y�f�̐��i�f�U�C���B�T�v���C�`�F�[���ł̐V���Ȏ�@�ɂ��G�l���M�[�����̊g��B�T�v���C�`�F�[���S�̂��Đ��\�G�l���M�[�Ɉڍs�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ݔ���Ё^�C���R���g���[���Ŋ����\�h�^�Z�p�E�m�E�n�E��������������� �V�^�R���i�E�C���X�̊����g����_�@�ɁA�ݔ��H����Ђ��ۗL���鎺����C��������Z�p�ւ̊S�����܂��Ă���B �����Ǘ\�h��̋��������߂����Î{�݂Ȃǂ��璍����₢���킹�������B�R���i�Ђɂ��i�C��������O����钆�A�~�ς��Ă����Z�p��m�E�n�E�����鐬������Ƃ������A���l�ȃj�[�Y�ɑΉ����悤�ƐV�Z�p�J���ɏ�肾����Ђ��o�Ă����B �����M�w�̈�×p�N���[���u�[�X�́A�A���Ɨz�����ȒP�ɐ�ւ��A�ۂ̗��o��}����C�����̖h�~�ɂȂ���B��C���̋ۂ������ł���t�B���^�[�𓋍ڂ��A�����ȋ�C��r�o����B �_�C�_���́A��C����Ɠ����Ɏ������A���ɂł���u��C����E�A�������j�b�g�v��̔������B�܂��A�f�@���⌟�����ł̃N���X�^�[�i�W�c�����j������h���V���j�b�g�̊J���ɒ��肵���B �V���{�A��C�Ђ��V���i���J�����Ƃ����B �o�T�u���ݍH�ƐV���v |
|
|
| ���G�A�R���̎����@�̃t�B���^�[�ɏ��ی��ʂ���������J�����i��ł��� �uASHRAE�v���R���i�̊����o�H�ɂ��āA�i�Ђ܂j��ڐG�̂ق��A�ۂ��t�������o����Ă̊����̊댯���\�������Ƃ���A�ݔ��p�t�B���^�[�̐�������Đ�����|���郆�j�p�b�N�́A�V�^�R���i�E�C���X�����g��̗}�~��Ƃ��āA�����̋�ԏ��ۂȂǓV��^�G�A�R���Ɏ��t����V�t�B���^�[���J�������B ��ԏ��ۂ́A�R���i�E�C���X��s������������͂����莩�R�E�ɂ����݂���I�]���K�X�����p�B��ʓI�ȃt�B���^�[�ł͔��ׂȕ��o�Ȃǂ͕ߏW�ł��Ȃ��Ƃ�����B�V�t�B���^�[�ł͍L��ȕ\�ʐςȂǂɂ��A�G�A�R���ғ��ŋ�C1��̒ʉ߂Ŗ�10�~�N�����̕��o��9���ȏ�A��5�~�N������6���ȏ�ߏW���\�B ��������Ԃŋۂ�E�C���X���t���������o���ߏW����A�t�B���^�[�ɋ�C�I�������ݍ���ł���A�����Ɉ��S�ȋ�C�����m�ۂł���悤�ɂȂ�Ƃ����B �o�T�u��ʐV���v |
|
|
| ���u2030�N�̍ăG�l�䗦40���Ɂv�o�ϓ��F��� 2018�N�x�̍ăG�l�䗦��17���ŁA�d���̔䗦�z���E���͔��d��30���A���́E�o�C�I�}�X�E�n�M����10���܂ō��߁A�ăG�l�䗦40�����߂����ׂ��Ƃ����B ����́A����̉�������ł͓��ꓞ�B�ł��Ȃ��B�����̍ĉғ����i��ł��Ȃ����ł́A�p������ɂ�����2030�N�̉������ʃK�X26���팸�̒����ڕW�A2050�N�܂ł�80�����팸����Ƃ��������r�W�����Ɍ������őP�̓����Ɛ����B ����Ɂu�ăG�l�̎�͓d�����́A�n���̎����\���̊m�ہA�����ē��{�̌o�ϔ��W�̂��߂ɁA�ۑ�����Ɏ��g�ނׂ��ŗD��ۑ�v���Ƃ܂Ƃ߂��B�d�͎��v��������݂ɐ��ڂ���Ɖ��肵�āA�ăG�l�䗦40���B���ɂ́A���z�����d��1��2000��kW�̐ݔ��e�ʁA���͔��d��6000��kW�̐ݔ��e�ʂ��K�v�Ǝ��Z�B���z�����d�ɂ��ẮA�������̉������ւ̐V�ݗU���Ȃǂɂ��N��500��kW�̃y�[�X�œ����𑱂��邱�Ƃ��ł���ΖڕW�͏\���ɒB���\���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�Z��̑��E�h�A�̒f�M���C��M���p�@��̐ݒu�ɏ����� �����s�́A2020�N�x��������Z��ɐݒu����Ă���M�̏o���肪�傫�����E�h�A���A���f�M���E���f�M�h�A�ɉ��C�����g�݂�A�Z��ɍĐ��\�G�l���M�[�R���̔M���p�@��������g�݂ɑ��鏕�����Ƃ��J�n����B �����Ώۂ́A���f�M���i�����Z��̂݁j�A���f�M�h�A�i�����Z��̂݁j�A���z�M���p�@��A�n���M���p�@��B�����Ώێ҂́A�ˌ��E�W���Z��̏��L�ҁA�W���Z��̊Ǘ��g�����i���E�n�������c�̓��̌��I�Ȓc�̂͏����j�B ���Ɩ��́u�ƒ�ɂ�����M�̗L�����p���i���Ɓv�B��W���Ԃ�2020�N�x�`2021�N�x�B2020�N�x�̐\����t��7��15������J�n�����B2020�N�x�̗\�Z�z�͖�12���~�B�s���ł́A�G�l���M�[����ʂ̖�3�����ƒ땔�傪��߂�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IEA�T�~�b�g�A�u�w�N���[���G�l���M�[�]���x�����o�ωւ̎�v�{��Ɂv ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j����Â���N���[���G�l���M�[�]���T�~�b�g���J�Â��ꂽ�B��ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�I�����g�傩��̎����\�Ȍo�ωɌ����āA�N���[���G�l���M�[�]���̏d�v���ɂ��āA�Q�������e���t�����Ƃ̋��͂��m�F���A�c�����������\���ꂽ�B ����̉�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ�関�\�L�̊�@����̒E�p�Ɍ����A�u�N���[���G�l���M�[�]���v�����A����̌o�ωɌ�������v�Ȏ{��Ɉʒu�t����ׂ��A�Ƃ����ϓ_����J�Â��ꂽ�B ����A���R��b�́A���Ղ��N���[���ȃG�l���M�[�V�X�e�����\�z���Ă������Ƃ̏d�v���Ɍ��y�����B���̏�ŁA�G�l���M�[�]���͊e���ŗL�̎���ɉ����Đi�߂Ă������Ƃ��K�v�ł���Ƃ�����{���j�������A�ăG�l�̎�͓d�����A������ȐΒY�Η͂̃t�F�[�h�A�E�g�Ɍ��������{�̋�̓I�Ȏ��g�݂��Љ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��CO2��������R�X�g�팸�����҂����u�ő̋z���@�v�A���d���ł̎��ɒ��� NEDO�́ACO2�����E����R�X�g�̑啝�Ȓጸ�����҂����ő̋z���@�ɂ��āA���ۂ̐ΒY�Η͔��d���ŔR�Ĕr�K�X��p�����p�C���b�g�K�͂̎������s�������J���ɒ��肷��Ɣ��\�����B �ϑ���Ƃ��āA���d�H�Ƃƒn�����Y�ƋZ�p�����@�\���̑������B���Ɗ��Ԃ�2020�N�x�`2024�N�x�B�\�Z��63.5���~�B2030�N�܂łɌő̋z���@�̋Z�p�m����ڎw���B �ő̋z���@�́ACO2�̋z���Ɍő̋z���ނ𗘗p����BNEDO�ł́A�ő̋z���ނƂ��āACO2�����w�I�ɋz������A�~���𑽍E���x���̂ɒS���������^�C�v�������J�����Ă���B �ő̋z���@�́A�z������CO2�̒E���ɗv����G�l���M�[����ʂ�ጸ�ł��邱�Ƃ���G�l���M�[�����̍����Z�p�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B�܂��A��������R�X�g�������4,000�~���x�^tCO2����2,000�~��^tCO2�ɒጸ�ł���\��������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������s�E���l�s��5�s�s�A�u�ăG�l�����w���v�ŘA�g�Ώۂ�1150���]���� �����s�A�_�ސ쌧�A���l�s�A���s�A���͌��s�̎�s��5�s�s�͘A�g���āA�ƒ�E���X�E���K�̓I�t�B�X��ΏۂɁA���z���╗�͂ȂǍĐ��\�G�l���M�[�����p�����d�͂̍w����]�҂��W���A�ăG�l�d�͂̍w���𑣂��L�����y�[���u�݂�Ȃł�������Ɏ��R�̓d�C�v�i�݂��d�j���J�n�����B ���̃L�����y�[���ł́A�Q���҂��W�܂�قǃX�P�[�������b�g�����܂�A�����ȗ����ōăG�l�d�͂𗘗p�ł���悤�ɂȂ�B�Q���o�^���Ԃ�9��30���܂ŁB�Q���o�^�͖����B �Q���o�^�̒��،�A�L�����y�[�������ǂ��I�[�N�V�����ɂ��ł������ȓd�͉�Ђ̗������j���[�����肷��B�Q���҂͌��ς��͂�����A�d�C�̌_���ؑւ��邩���f���邱�Ƃ��ł���B �܂��A�L�����y�[�����Ԓ��ɁA�I�[�N�V�����ɎQ������d�͉�Ёi�����d�C���Ǝҁj�̕�W���s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�Đ��G�l���Ɍo�ύ\�z�E�Y�f�Љ�֔N���߂ǐV�v�� �o�ώY�ƏȂ́A�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����āu�ăG�l�o�ϑn���v�����v�̍���ɏ��o���B ������ȐΒY�Η͔��d���̒i�K�I�ȋx�p�~��\���������ōĐ��\�G�l���M�[���j�Ƃ����o�ς̍\�z��}�邽�߁A�Y�ƁA�Љ��ՁA�n��Љ�����ɗL���҉�c�Ō������A�N�����߂ǂɎ��܂Ƃ߂�B ���d�R�X�g�ጸ�ɂ��Đ��G�l�����𑣂����߁A�Œ艿�i������萧�x�iFIT�j�ɑ��d�͎s��ƘA�������u�t�B�[�h�E�C���E�v���~�A���iFIP�j�v�̓������c�_����B ���U�^�d�̓V�X�e���̑��i�Ɍ����A�A�O���Q�[�^�[�i�z�d���Ǝҁj�̖@����̈ʒu�t�����i�߂�B�~�d�r���y�ȂǓd���̓����ɉ��������x�\�z�ŁA�����ł̍Đ��G�l�Y�Ƃ̋����͋�����_���B�Đ��G�l�̎�͓d�����̐�D�Ƃ��ėm�㕗�͔��d�̓����c�_���i�߂�B�����I�ɕ⏕���Ɉˑ����Ȃ����B�����f���ɂ����W�J��`���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���S���m����A�ăG�l�E�ȃG�l�֘A�̎{��E�\�Z�ɂ��Ď����G�l���ɗv�] �S���m����́A2021�N�x�ɂ�����G�l���M�[�W�̍��̎{��E�\�Z�Ɋւ����āE�v�]�����܂Ƃ߁A�����G�l���M�[���ɑ��v�������B �Đ��\�G�l���M�[�̓����g������A�e�s���{������悲�Ƃ̍Đ��\�G�l���M�[���d�o�͂�d�͎��v�ʂ����ɔc�����A�ăG�l���y�g��̎��g�݂��v��I�ɐi�߂邱�Ƃ��ł���悤�A���ɂ����āA�e�s���{�����d�C���Ǝғ��ۗ̕L������̒����p�ł���d�g�݂��\�z���邱�ƂȂǂ�v�]�����B �v�����e�́u�����G�l���M�[��̐��i�v�Ɓu�d�͎��������̐��i�v�𒌂Ƃ���B�����G�l���M�[��̐��i�ɂ��ẮA�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��␅�f�G�l���M�[���y�E�����g��̉������A�G�l���M�[�ɌW�鑽�l�ȃC���t�������Ȃ�8�̃e�[�}�ł܂Ƃ߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/8�@]�@�@�� |
|
|
| �����o�b�e���[�����`�E���C�I���d�r����A�É͓d�H���o�C�|�[���^�~�d�r�� �É͓d�H�ƌÉ͓d�r�́A���o�b�e���[���x�[�X�ɂ����u�o�C�|�[���^�~�d�r�v�������J�������B �Đ��\�G�l���M�[�̔��d�ʕϓ��}���ɗp�����钷���������ŁA�d�͒����p�~�d�V�X�e�����\�z����ꍇ�Ƀ��`�E���C�I���d�r�Ɣ�ׂăg�[�^���R�X�g���ł���B2021�N�x���ɃT���v���o�ׁA2022�N�x�ɐ��i�o�ׂ��J�n����\�肾�B �Ǝ��̃��^���E�|���}�[�f�ޗ͂����p���A�����v���[�g�ɔ���������ڍ������d�Ɋ�̍\�����������邱�Ƃɐ��������B�d�l�́A�O�`���@���c300�~��300�~����250mm�A�e�ʂ�50Ah�A��i�d����48V�B������4500�T�C�N���ŁA1���ɏ[���d��1�T�C�N���s�������������d�͒����p�d�r�ł���Ζ�15�N�ƂȂ�B�]���̓d�͒����p���o�b�e���[�Ƃ̔�r�ł́A�̐σG�l���M�[���x����1.5�{�A�d�ʃG�l���M�[���x����2�{�B�d�r���g�ݍ��킹�邱�ƂŁAMW���̒~�d�r�e�ʂɂ��Ή��ł���Ƃ����B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���e�����[�N���ԑт̓d�C�g�p�ʂ�94�������^�G�l�`�F���W��Looop������ �d�́E�K�X��r�T�C�g���^�c����ENECHANGE�i�G�l�`�F���W�j�́A�d�̓f�[�^�����p�����T�[�r�X�̋����J����i�߂Ă���Looop�̋��͂̂��ƁA�ً}���Ԑ錾���o�O��̃��[�U�[�̓d�C�g�p�ʂ̕ω��������B �ً}���Ԑ錾���͏o�O��ŁA�e�����[�N���ԑтɂ�����9������18���܂ł̕��ϓd�C�g�p��94%�A������3,493�~�������Ă������Ƃ��킩�����B �܂��AENECHANGE�̃����}�K����ɑ��u�R���i�Ђɂ�����d�C��̕ω��ɂ��āv���e�[�}�ɃA���P�[�g�����{�����B�e�����[�N�̓�����w�Z��c�t�����x�Z�E�x���ɂȂ������ƂŁA79%���ݑ�Ԃ��������ƉB58%���u��N���d�C�オ�オ�����v�Ǝ������Ă���A���̗��R�Ƃ��āu�Ɩ��̓_�����Ԃ��������v�u����ł̃p�\�R���̎g�p���Ԃ��������v�Ȃǃe�����[�N�����ɂ��e����A�u�e���r�̎������Ԃ��������v�Ȃǐ��ѓ��̍ݑ�l�������������Ƃ����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o���A��q��w�Ɂu�����ăG�l100���v�d�͂������N�Ԗ�2000��kWh �o���O���[���p���[�A��q�w�@�l�J�L�����p�X�ɍĐ��\�G�l���M�[100���̓d�́v�̋������J�n�����B ���Ђ́u�v���~�A���[���v�����v�́AFIT�d�C���܂ލăG�l100%�̓d���\���ɁA�g���b�L���O�t�Ώ؏���g�ݍ��킹�邱�ƂŁA��������d�͂�CO2�r�o�ʂ������[���ƂȂ�v�����B���v���������ɂ���q��w�l�J�L�����p�X�S�̂Ŏg�p����d�͗ʂ̖�95���ɂ�����N�Ԗ�2000��kWh�̓d�C���Đ��\�G�l���M�[�R���ƂȂ�A��9300t��CO2�팸�ɍv������Ƃ����B �o���O���[���p���[�́A�o���O���[�v�ŕ��́A�n�M�A�o�C�I�}�X�A���z���A���͂Ƃ��������푽�l�ȍăG�l�d����ۗL���鋭�݂����A�Đ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂��A���ɐϋɓI�Ɏ��g�ފ�ƁE�c�̂������Ă���B�܂��A�����s��CO2�r�o�ʍ팸��ڕW�Ƃ����{���Ă���u�����s�L���b�v���g���[�h���x�v�̒�Y�f�d�͂̋������Ǝ҂�6�N�A���ŔF�肳��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ؑ��H�@���HP���I�[���t���b�V���O���@1200V�^�lj� ���HP���I�[���t���b�V���O���@�ɁA�R���p�N�g��5HP�E1200m3/h�̒蕗�ʌ^�@���lj������B �u���K�Ȋ��C�v�̂��߂́A�V���v���ȋ@�\�݂̂𓋍ڂ��Ă���B�x�O�^�X�܂⏬�K�͂̍H��ȂǂɓK�����A���O�@��̌`�̃R���p�N�g�ȊO���@�ŁA����I�ȊO�C�����ŁA�����̗z�����⎺���M���ׂ�}�������K�Ȋ��C�������Ȃ���B ��d�\���T���h�C�b�`�p�l���Œᑛ���ŁA�����\�t�B���^�W�������B�O�C������͖h���ԕt�ŏ㕔�ݒu���q���ʂɔz���B�ݔ��p���O�@��̌`�ŁA��}�z�ǍH�����s�v�B���C�̍ۂɔr�C�ʂ������������A���ɂȂ�ƁA���Ԃ�J�������牷�x��������O�C�⚺�Ȃǂ��N�����邪�A�O���@�ɂ�����I�ɐV�N�ȋ�C���������邱�Ƃʼn������邱�Ƃ��ł��A���K�����ۂ��Ƃ��ł���B�܂��A���Ԋ��⎞�ԑтɂ���Ă͊O���@�̒P�Ɖ^�]�A�O�C��[���\�B �o�T�u�j���[�X�����|�X�v |
|
|
| �����d�H�A�������[�J�[���u���f�t���@�v��99.999%�̍����x���� ���d�H�́A�������[�J�[�����́u���f�t���@�v�������B1��������5�g���̉t�����f�i�R���d�r��1,000�䑊���j�̐������\�ŁA���d�p�K�X�^�[�r����q��@�p�W�F�b�g�G���W���Ȃǂ̍�����]�@�B�̊J���Ŕ|�����Z�p�����p���A�Ǝ��ɊJ�������t���H���ɂ��ƊE�g�b�v�N���X�̉t��������B�������Ƃ��Ă���B ���Ђ́A���f�������悭�����E�A�����邽�߂̎�i�̈�Ƃ��āA�}�C�i�X253���ʼnt�����邱�Ƃő̐ς�800����1�ɂȂ鐅�f�̐����ɒ��ڂ��ĉt���Z�p�̌����J���Ɏ��g�݁A�̔��J�n�������f�t���@�́A���̏]���@�̐��\�������20�����コ�������́B �����i�́A���f�̉t���H���ŕs�����̍�����r�����邱�Ƃɂ��A99.999%�̍����x�ȉt�����f������B�N�����A24���Ԉȓ��ɉt���^�]���\���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����I�R�[�A�X�܂̑��z���d�͂�EV���[�d����T�[�r�X�� VPP Japan�́A�X�܂ɓ������ꂽ���z�����d�V�X�e���̓d�͂𗈓X����ڋq�ɏ[�d�T�[�r�X�Ƃ��Ē���R-EV�[�d�X�e�[�V�����uSOLA�v���A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̃��I�R�[���������X�ɓ����A�T�[�r�X���J�n�����Ɣ��\�����B �����������S�Ȃ��ŁA�X�[�p�[�}�[�P�b�g���n�߂Ƃ����^�{�݂��ƂȂǂ̉����ɃI�t�O���b�h���d���i���Ə���z�����d�V�X�e���j�����A�����Ŕ��d�����d�͂��{�݂Ɉ����ɒ��ڋ�������PPA�i�d�͔̔��_��j�T�[�r�X�u�I�t�O���d��(R)�v��W�J����BR??EV�[�d�X�e�[�V�����́A�u�I�t�O���d��(R)�v�������{�݂ō�������z���d�͂����p���A�d�C�����ԁiEV�j�̏[�d�X�e�[�V�����̉^�p���\�ɂ���T�[�r�X�B2021�N�܂łɗv500�{�݂ւ̓����𐄐i�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���c���ȂǁA�����̃G�l���M�[�I�D�Ɋւ��v���𑽊p�I�ɒ������� �c��`�m��w�Ȃǂ̍��ۋ��������O���[�v�́A�G�l���M�[�~�b�N�X�̑I�D�ɂ����āA�l(�ƌv)�̎Љ�I�E�o�ϓI�ȏ݂̂Ȃ炸�A���܂��܂Ȍl�������֗^���Ă��邱�Ƃ��𖾂����B �������O���[�v�́A�G�l���M�[�o�ςɊւ��錤���Ɏ��g��ł���A�Љ�Ȋw�I�ȑ��ʂ���A�G�l���M�[�����̂���ׂ��p�Ȃǂ��������Ă���B����A2013�E2014�N�Ɏ��{�����p�l�������̉��ʂ������Ƃ���A3�̓d��(���R�G�l���M�[�A���ΔR���A���q��)�̗��z�I�ȍ\���䗦���z�́A���R�G�l���M�[�ɂ��ẮA��r�I�����̐l��50���ȏ�Ɖ��A���ΔR����20�`40���A���q�͂�0�`10���Ɖ����l�����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁA�C�m���݂̖h�~�ƍĐ��\�G�l���M�[�̊J���Ɍ��������g�݂��Љ� �A�����J�G�l���M�[�ȁiDOE�j�̊C�m�֘A�̎��g�݂́A���ɔz�����Ȃ���V���Ȍٗp��n�o���邱�Ƃ�ڎw���u�v���X�`�b�N�E�C�m�x�[�V�����E�`�������W�v�ŁA�����������A��w�A�Y�ƊE���v���X�`�b�N���T�C�N���Z�p�J���̎��g�݂ł���B ���̍ŏ��̖ڕW�́A�v���X�`�b�N�����H�ɗ�������̂�h���A�C�Ȃǂ���v���X�`�b�N����������Z�p���J�����邱�Ƃł���B�ݗ����́uBOTTLE�iBio-Optimized Technologies to Keep Thermoplastics out of Landfill and the Environment�j�C�j�V�A�`�u�v�́A���T�C�N���\�ȐV�����v���X�`�b�N�̌����I�Ȑ����𐄐i����B �܂��A���ꂢ�Ȑ����m�ۂ��邽�߂ɁA�z���C�g�n�E�X�Ƌ����Łu�����S�ۏ�O�����h�`�������W�v�𗧂��グ�āA�g�͂𗘗p�����C���W�����V�X�e�����J�����邽�߂̎��g�݂��s���Ă���B |
|
|
| �����E�����������A���R�ɍ����������s�s�C���t���̌��ɂȂ�ƏЉ� ���E�����������iWRI�j�́A�C��ϓ��̉e�������邽�߂̓s�s�����͔���Ȕ�p��������Ƃ��āA���R�C���t���̊��p�����߂Ă���B ���A���n�сA�����A�I�[�v���X�y�[�X�A����Ή��Ȃǂ̎��R����ՂƂ����\�����[�V�����ƂȂ�u�O���[���C���t���v�́A���̖��̑����������ł���B�O���[���C���t���̍\�z�́A�R���N���[�g�\�����ő�����u�O���[�C���t���v�ɔ�ׂăR�X�g��}���邱�Ƃ��ł���B�O���[���C���t���̓�����Ƃ��āA�V���K�|�[���̃r�V�����E�A�����L�I�iBishan-Ang Mo Kio�j�����̃R���N���[�g���H�̕�C���Ⴊ����B�R���N���[�g���H�蒼�����A�͏������R�ɖ߂����ɂ��āA��p�։v�̕��͂����{���ăO���[���C���t����I�����邱�Ƃɂ����B���̌��ʁA�R���N���[�g���H�蒼���قڔ����̔�p�ōςނ��肩�A�l�X�Ǝ��R�̂��߂̋�Ԃ�n�o�������ƂŁA�N�Ԑ���7,400���h���̗��v�������炵�A�����z�ȏ�̌��ʂ������炵���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��2020�N�Ŋ������A�u�E�Y�f�^�̃��C�t�X�^�C���v�ւ̕ϊv�Ƀt�H�[�J�X ���{�́A2020�N�Łu�������E�z�^�Љ���E�������l�������v���t�c���肵���B �����̃e�[�}�́u�C��ϓ�����ɂ����鎄�����̖����v�B���{�A�����́A��ƁA�l�ɂ��E�Y�f�^�A�������U�^�̎Љ�Â���Ɍ�������̓I�Ȏ��g�݂ƐV�^�R���i�E�C���X�����ǂɑ�����s���̑Ή��ɂ��ċL�ڂ��Ă���B ��l��l�ɋ��߂�u�E�Y�f�^�̃��C�t�X�^�C���v�ւ̕ϊv�����ɂ����ẮA��l��l���ł����g�̈�ł���H��G�l���M�[�́u�n�Y�n���v�Ȃǎ������U�^�̎Љ�Â���Ɍ�������g������ƂƂ��ɏЉ�Ă���B �Љ�ϊv�ɂ��n�����̊�@�ւ̑Ή����s���C��ϓ����ɂ��ẮA���E�̉������ʃK�X�r�o�ʂ��������Ă���ƁA����܂��������O�̎�g�݂ɂ��ďЉ�B�C�m�v���X�`�b�N���݉�����������l���̑����ɂ��Ă����グ�Ă���B ���̂ق��A���E���ʂ̖ڕW�ł���uSDGs�v�Ȃǂ̎��g�݂����グ�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����f��CO2������R�X�g������V�Z�p�A�J�[�{�����T�C�N�̕��y���㉟�� ���É���w�̌����O���[�v�́A���f�𗘗p���ĉΗ͔��d���Ȃǂ̔r�K�X�Ɋ܂܂��CO2���������Z�p���J�������Ɣ��\�����B �]����@���啝�ȏȃG�l����Z�p�ŁACO2��Y�f�������Ƃ��čė��p����J�[�{�����T�C�N���ւ̍v�������҂ł���B �]����CO2����E���p�v���Z�X�́A�r�K�X����CO2�݂̂�������A���f�ƍ������邱�Ƃ�CO2�Ҍ��������s���BCO2�̉���ɂ̓A�~���Ȃǂ̋z���t�𗘗p���Ă���B�����A�z���t��40�����x��CO2���z�����A100�����̉��x�ŏ�CO2���Đ�����̂���ʓI�ŁA�����̃G�l���M�[���K�v�Ƃ����ۑ肪�������B ����A�Đ����ɐ��f�ڋ�������H2�X�g���b�s���O�Đ��Z�p���J���B����ɂ��ACO2��85���̒ቷ�ōĐ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �����90���̒ቷ�ōĐ��ł���ŐV�̑������^�z���܂�g�ݍ��킹��AH2/CO2��4�i���^�����������j�ŋz����50���A�Đ���60���ƁA���ቷ�ł̉^�]���\�ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�c�A�A�E�Y�f�Љ�ڎw���u�`�������W�E�[���v���X�^�[�g137�ЁE�c�̂� �u�`�������W�E�[���i�`�������W�l�b�g�E�[���J�[�{���C�m�x�[�V�����j�v�́A�o�c�A�����{���{�ƘA�g���A�C��ϓ���̍��ۘg�g�݁u�p������v�������I�ȃS�[���ƈʒu�Â���u�E�Y�f�Љ�v�̎������߂����V���ȃC�j�V�A�`�u�B137�ЁE�c�̂̎Q���ăX�^�[�g�����B �Q����ƁE�c�̂́A�E�Y�f�Љ�Ɍ������C�m�x�[�V�����ɒ��킷��u�`�������W�E�[���錾�v�ւ̎^����\�����A���ꂼ�ꂪ���킷��l�b�g�E�[���G�~�b�V�����Z�p�̊J����A���̐ϋɓI�Ȏ����E���y�A�܂��A�����Ɏ��g�ފ�Ƃւ̃t�@�C�i���X�Ȃǂ����{����B�u�`�������W�E�[���v�����E�F�u�T�C�g���J�݂��A�����������g�݂ɂ��āA305�̋�̓I�Ȏ�������\�����B �o�c�A�́A�`�������W�E�[���̐��i�ɂ��A�E�Y�f�Љ�Ɍ������C�m�x�[�V�����ɒ��킷���Ƃւ�ESG�����̌Ăэ��݁A�C�m�x�[�V�����n�o�Ɍ��������Ǝ�E�ًƎ�E�Y�w���̘A�g��}���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցA�ăG�l���ΒY�������d�R�X�g�������ɂȂ����ƕ� �Đ��\�G�l���M�[�@�ցiIRENA�j�́A2019�N�ɒlj����ꂽ�Đ��\���d�e�ʂ̔����ȏ�́A�ł������ȐV�K�ΒY�Η͔��d�������Ⴂ�d�̓R�X�g��B�������ƕ����B �Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�R�X�g�́A�Z�p�̐i���A�K�͂̊g��A�T�v���C�`�F�[���̋����͋����A�J����Ƃɂ��o���̒~�ςɂ��A�ߋ�10�N�Ԃő傫���ቺ�����B���@�ւɂ�钲�ׂł́A���z�����d�̃R�X�g��2010�N����82%�ቺ���A�W���^���z�����d�iCSP�j��47%�A���㕗�͔��d��39%�A�m�㕗�͔��d��29%�ቺ�����B�ł��R�X�g�̂����������500�M�K���b�g�̐ΒY�Η͔��d��2021�N�ɒ�~���A����z�����d����ї��㕗�͔��d�ő�ւ����ꍇ�A���d�R�X�g����ђlj��I�ɕ��S����R�X�g�͔N�Ԃōő�230���h���}���ł��ACO2�r�o�ʂ�N�Ԗ�1.8�M�K�g���팸�ł���B�܂��A���E��GDP�̖�1%�ɑ�������9,400���h���̌o�ώh�����ʂ����҂ł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2020/7�@]�@�@�� |
|
|
| ��JR�����{�A2050�N�x��CO2�r�o�ʁu�[���v�ɍăG�l�J���Ɛ��f�����p JR�����{�́A�V���Ɋ������ڕW�u�[���J�[�{���E�`�������W2050�v�����肵�A2050�N�x�̓S�����Ƃɂ�����CO2�r�o�ʁu�����[���v��ڎw���Ɣ��\�����B ����ɂ��I����ʋ@�ւƂ��āA�����ɂ킽��S���̊��D�ʐ��̌����}��ƂƂ��ɁA�ڕW�B���Ɍ��������g�݂�ʂ��A�E�Y�f�Љ�̎����ɍv������B �ڕW�B���Ɍ����āu����`����E���߂�`�g���v�܂ł̃G�l���M�[�l�b�g���[�N�́A���ׂẴt�F�C�Y�ŋ�̓I�Ȏ�g�݂�i�߂Ă����B �u����v�ł́A�Đ��\�G�l���M�[�̊J���𐄐i���A�u�Ώ؏��v�����p���A���k�G���A�̉w��d�Ԃɋ������邱�ƂŁA2030�N�x�܂łɓ��k�G���A�ɂ�����CO2�r�o�ʃ[����ڎw���B �u����E���߂�v�ł́A�d�͒������u�Ȃǂɂ��G�l���M�[�̗L�����p��i�߂Ă����B�u�g���v�ł́A�ԗ���w�E�I�t�B�X�̏ȃG�l���A�R���d�r�Ԃ�R���d�r�o�X�Ȃǐ��f�̗����p���s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}�A�uLED�����L�b�g�v�������݊��̎g�p�ŏ�����p�팸 �A�C���X�I�[���}�́A�uLED�����L�b�g�O���b�h�Ɩ��p�v������B���݂̌u�������{�̂����O�����ɁA�����̌����iFPL55�`�^FHP45�`�j�ƃ\�P�b�g��[�q��ȂǘV���������d�C���ނ����ւ��邱�Ƃ�LED�����\�B����ɂ�菉����p��啝�ɍ팸�ł���Ƃ��Ă���B ���݂̌u�������{�̂Ɣ��˔̂܂�LED���ł��邽�߁A�������ɂ������p�ƍ�Ǝ��Ԃ��팸�ł���B�����O�̌Â����̔p�����s�v�ɂȂ邽�߁A�p����p��p�������팸�ł���B ����ɍ��Ɠx�^�C�v�̏ꍇ��146lm�^W�Ɣ��������������A����d�͖͂�67���팸�ł���B�܂��A���ГƎ��J���̖�������V�X�e���uLiCONEX�v�ɂ��Ή��B�^�u���b�g��X�}�[�g�t�H���Ȃǂ��疳���ʐM�ŏƖ��𑀍�ł��A�Ɩ�1�䂲�ƁA�G���A���Ƃ̏Ɩ�����ɂ��A�s�K�v�ȓ_���𐧌䂷�邱�Ƃł���Ȃ�ȃG�l���ʂ������ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ł����z���Ŕ��d����K���X�ANTT-AT��2020�N�H����̔��� NTT�A�h�o���X�e�N�m���W�́A���F�����^�����d�f�q�uSQPV�iSolar Quartz Photovoltaic�j�v�Z�p���g�p���Đ����������@�\�K���X���i�̔̔��ɂ����āA���̋Z�p���J������inQs�Ɠ��{�����Ɛ�̔��_�����������Ɣ��\�����B �����Ȉӏ�����ۂ����܂܁A�ԊO�����z�������d���鑾�z�d�r�̋@�\�����������@�\���ރK���X�Ƃ��āA2020�N10������̔����J�n����v�悾�B SQPV�͎��O���ƐԊO�����z�������d����Z�p�B�����͓��߂��邽�߈�ʂ̃K���X���g����S�Ă̗p�r�ɂ����āA�ՔM�Ɣ��d�Ƃ����@�\��t���ł���Ƃ����B���̈�ʂ̃K���X���ɉ����߂����A�ԊO�����z���i�ՔM�j������������A�f�U�C�����̍����ȃG�l���M�[�ՔM�E���d�K���X�ޗ��Ƃ��Ă̗p�r�J�\�ł���A���ɎՔM���ʂ̓r���ȂǏȃG�l�ɗL���Ƃ����B ���Ђ́A�ɒ�Ɠx�^�����d�f�q�𗘗p����IoT�@������Ɨ��d���Ȃǂ��J�����Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���g���݁h���G�^�m�[���ɂł���v�V�Z�p�A�ϐ����w�����p���֖{�� �ϐ����w�H�ƂƊ����t�@���h��INCJ�́A�č��x���`���[���LanzaTech�ЂƋ����J�������������G�}�����p���ĉR�����݂��G�^�m�[���ɕϊ�����Z�p�̎��Ɖ��Ɍ����A���؎����ƍ��ى�Ёu�ϐ��o�C�I�t�@�C�i���[�v��ݗ�����Ɣ��\�����B �G�^�m�[���ϊ��Z�p�́A���ݏ����{�݂Ɏ��W���ꂽ���݂���ؕ��ʂ��邱�ƂȂ��K�X�����A���̃K�X��������ɂ���ăG�^�m�[��������Z�p�B �傫�ȔM�∳�͂�K�v�Ƃ����A�����v���Z�X�Ɣ�ׂĂ��\���ɃR�X�g�����͂�����Ƃ����B���Ђ�2014�N���狤���J����i�߂Ă����B ����A�ݗ����鍇�ى�Ђł͂��̃G�^�m�[�����Z�p�̎��p���E���Ɖ��Ɍ������ŏI�i�K�̎����s�����߁A�܂��A��茧�v���s�Ɏ��v�����g��V�݂���B2021�N�x���ɉғ����J�n����\�肾�B���v�����g�́A��20t/���̂��݂��������A�G�^�m�[���Y�B��Ƃɒ��A���܂��܂Ȑ��i�E���ƂɊ��p���Ă��炤���Ƃ��ڎw���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������E�_�C�L���A�g�g�D�^�ݒ肪�q�g�̔�J�ɗ^����e������ �����w�������ƃ_�C�L���̘A�g�g�D�ł���u����BDR-�_�C�L���H�ƘA�g�Z���^�[�v�́A�ċG�̋ݒ肪���K�������コ���A�q�g�̔�J�y����������ʂ�L�����Ƃ𖾂炩�ɂ����B ���҂́u�R��J��Ԃ̍\�z�v�̋��������𐄐i���Ă����B�]���A���x�E���x���l�ɗ^����e���̌��ɂ��ẮA�S���I�ȕ]�������S�ƂȂ��Ă������A����̎����ł́u��J�v�ւ̉e���ɒ��ڂ��A�S���ϓ����琄�肳��鎩���_�o�����Ȃǂ̐����I�]���������čs�����B�ċG�ɑz�肳�����ɂ����āA�����̏㏸�ŐS�����⎩���_�o�����Ȃǐ����I�ȕ��S�͍��܂邪�A���x�������邱�ƂŐS�g�̕��S���y������邱�Ƃ������ꂽ�B���ɏ����������₷����(28���A30��)�ɂ����ẮA���x55%�ȉ���ۂ��Ƃʼn��K�������サ�A40%�ȉ��ł͔�J���y�����邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����l���f�U�C���A�X�}�[�gPV���[�^�[���J�� �X�}�[�gPV���[�^�[�̎{�H����f�U�C���i�T�C�Y���j�A��p�ɂ��āu�œK�Ȃ��̂��Ȃ������Ă����v�Ƃ����B�����ō���A���[�J�[�ƂƂ��ɁA�V���ȃX�}�[�gPV���[�^�[���J�������B �E����t���X�}�[�g���[�^�[�ő��z�����d�d�͗ʂ��v�� �EWi-SUN��B���[�g���̎擾 �E�d���A�d���A���g���ȂǓd�͕i�����擾 �ERS485�ʐM�Őڑ��\ �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���l�̓����Ŕ��d�A�R�ې��\������@�ۂ��J���^���c���쏊�ƒ�l�t�����e�B�A ���Ђ́A���d�@�ہuPIECLEX�i�s�G�N���b�N�X�j�v�̌����J������ѐ����A�̔����s���B�R�ې��\�ȊO�̊J�����i�߁A2025�N�x�ɔ��㍂100���~��ڎw���B PIECLEX�́A���d�����q�ł���L�^�|�����_�iPLLA�j�������Ƃ��ĊJ�����ꂽ���d�@�ہBPIECLEX���ߕ��ȂǂƂ��Ē��p�����ہA�l�̓����ɂ���đ@�ۂɈ��͂�������Ɠd�C�G�l���M�[���������A�R�ی��ʂ�����Ƃ����B ��̓I�ɂ́A�l�����p�����ꍇ�A1V�O��̓d���i�����Ƃ����{���g�j���@�ۂ��甭������Ƃ����B���̓d���͐l�̂ɂ͉e���Ȃ����A�u�@�ۊԂ͋ߐڂ��Ă��邱�Ƃ���A�ۂɂƂ��Ă͔��ɑ傫�ȓd�ꂪ�����邱�ƂɂȂ�B����ɂ���čזE���Ɍ�����������A�ۂ��זE�ێ��̂��߂ɔ�����d�C�M���ɉe����^���邱�Ƃŋۂ�����������v�Ɛ������Ă���B�V�^�R���i�ɂ��ẮA���炩�̌��ʂ�����̂ł͂Ƒz�肵�Ă���B �o�T�uEE Times �v |
|
|
| ���V�H��M�H�Ɓ^�@�����������S�ɕۂA���C�̌��������� ���Ђ́A�����Ǒ�̏d�v���̍��܂���A�n��̊�a�@���Î{�݂Ȃǂ𒆐S�ɁA�@�����������S�ɕۂA���C�̌�������Ă��n�߂��B��ẮA�c�ƂƐv�S���҂ɂ��u���C�������`�[���v��Ґ����Ă�����B ���C�̌������ɂ́A���l���̃V�~�����[�V�����iCFD�j�Z�p�ŁA����̊��C�̏�Ԃ��Č����A�@����C�́u��ǂ݁v�������ĕ��̗���𖾂炩�ɂ��A������I�ɋ�C�����ւ��郊�j���[�A���v����Ă���B���C�̏�Ԃ������x�ɍČ��\��CFD�Z�p�́A�G�A���]�����q�̔Z�x���z���V�~�����[�V�������邱�Ƃ��\�ŁA�a���̂Ȃǂ̋�C���ł̋������Č��ł���ق��A���j���[�A���O��̊����P���ʂ̔�r���\�B��͐��x�͌덷�}5�`10%�ȓ��ƍ����A�����������x�ɍČ����邱�Ƃ��ł���B���Ђ́ACFD�⎺������V�X�e���̍\�z�Z�p�̂ق��A�����Ǒ�̑��u��Z�p����g���A�g�[�^���v�����j���O����Ă��Ă����\��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���G�l���M�[�̍ė��p������90���AEV�p�V�^���[�^�[���J���B2020�N���ɐ��i�� �A�C�G���A�C�́A�R���G���W�j�A�����O�Ƌ����œd�C�����ԁiEV�j��n�C�u���b�h�ԁiHV�j�����̐V�^���[�^�[���J�������B���[�^�[�ƃX�e�[�^�[�����ɉ�]����V�\�����̗p�B�G�l���M�[������啝�ɍ��߂��B �V�^���[�^�[�͒ʏ�̑��s���ɒ��S���̃��[�^�[����]���A�����E��~���ɊO���̃X�e�[�^�[����]���ăG�l���M�[��~�ρB�Ĕ��i���ɂ̓��[�^�[�ƃX�e�[�^�[������ɉ�]�����A�~�ς�����]�G�l���M�[�ƃo�b�e���[����̓d���o�͂������������^���G�l���M�[�Ƃ��ĉ���B �����o�͂������A�d��\������ł���B���[�^�[�̍\�����ȑf�Ōy�ʉ��⏬�^����}���B�����R�X�g�̒ጸ�ɂȂ���A�i�v���ߍ��\���ō������́uIPM���[�^�[�v�ł������\�Ƃ����B �G�l���M�[�̍ė��p�����͖�90���BEV��HV�����Ŏ嗬�ƂȂ郂�[�^�[�ɔ�ׁA���s�q�������͊����o�b�e���[�̂܂܂�2�{���x�Ɍ���ł���B����A�ԍڂɂ��ϋv���\�����Ȃǂ����{����v��B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���h�C�c�ƒ�ɂ�����G�l���M�[����̑����Ƃ��̑�ɂ��Ď��������v���W�F�N�g�����{ �h�C�c�A�M�����́A�h�C�c�����̉ƒ�ɂ�����G�l���M�[����̑����̗v����l�X�̍s�����ȃG�l���M�[�ɗ^����e���ɂ��Ē������A�����i���Ă����������ʂ����\�����B ����ɂ��ƁA�d�q�d�C�@��̌������͐i�ވ���ŁA�@��̌��̑����A�@��̑�^���A���тɈ�l������̏Z�ʐς̑����ɂ��G�l���M�[��������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�����̎s�����s��������ꍇ�ɂ̂݁A��葽���̃G�l���M�[����̍팸���\�ł���A��K�͂ȍ����I�C���Z���e�B�u��A�h�o�C�X�̒A�ȃG�l�̋`������ʂ��āA���ꂪ�B���ł���Ƃ��Ă���B �G�l���M�[����̍팸�ɂ̓G�l���M�[���������ł͂Ȃ��A�①�ɂ�Ⓚ�ɂȂǂ̉Ɠd���i�̓K�ȑ傫���␔�A�g�p���@���d�v�ł���B�ȃG�l���M�[�́A�G�l���M�[�����̌����Đ��\�G�l���M�[�̊g��ɉ����āA���ɍs���̕ω��𑣂��d�v�ł��邱�Ƃm�Ɏ����Ă���B �o�T�u�G�R�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���t�����X���{�A�Y�f�����Ɍ������G�l���M�[�E�C��헪�\ �t�����X���{�́A���̂قǍ����E�Y�f�Љ�ւƐi�ނ��߂̘g�g�݂ƂȂ�G�l���M�[�E�C��헪�\�����B �헪���\������v�f�Ƃ��āu���ƒ�Y�f�헪�iSNBC�j�v�Ɓu�����N�G�l���M�[�v��iPPE�j�v������BSNBC�́u2050�N�܂łɒY�f��������������v�Ƃ������̖ڕW�Ɍ��������[�h�}�b�v�ŁA���݁A�A���A�_�ƁA�G�l���M�[�A�p�����ȂǕ��傲�Ƃ̕��j���������B�A���i�̔r�o�팸�ȂǏ���̒Y�f�t�b�g�v�����g�팸���ڕW�Ƃ��Ă���BSNBC�����s���邽�߁APPE�ł̓G�l���M�[����̍���10�N�̌v��������Ă���B�d���\���̑��l����i�߁A�Đ��\�G�l���M�[�̔䗦��33���i2030�N�j�ɐL������Ō��q�͂�50���i2035�N�j�ɉ����A���ΔR���̏����40���팸�i2030�N�j����Ƃ��Ă���B�헪�̈Ă�2018�N11���ɔ��\����A���̌�G�l���M�[�E�C��@�̎{���e���ʂ̈ӌ����ӂ܂��č��肳�ꂽ�B �o�T�u�G�R�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���C�O����A���������f�A�������̔��d���p���J�n�^AHEAD �����㐅�f�G�l���M�[�`�F�[���Z�p�����g���iAHEAD�j�́A���s�ɂ����āA�C�O����A���������f�ɂ�鍑�����̔��d���p���J�n�����Ɣ��\���s�ՊC���ɂ��铌���Ζ��E���l�������~�n���́u�E���f�v�����g�v�ɂ����āA�u���l�C�Ő����������`���V�N���w�L�T���iMCH�j���番���������f���A���]���d���i�Η͔��d���j�̃K�X�^�[�r���Ɍ����������n�߂��B ����ɂ��A�u���l�C�ł�MCH�����A�C��A���A���{�ł�MCH���琅�f�̕����Ƃ�����A�̗��ꂩ��Ȃ鍑�ۊԐ��f�T�v���C�`�F�[���ɁA�����̑�K�͐��f���v�̈�Ƃ��Ċ��҂���锭�d�R�����v������邱�ƂŁA���g�����ڎw���u�C�O����A���������f�ɂ��d�͋����v���B������A���f���d���p�ɂ���Ɉ���߂Â����Ƃ��āA�u���f�Љ�̎����Ɍ������d�v�ȃ}�C���X�g�[����B�������v�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C��ϓ��C�j�V�A�e�B�u�A�R���i��@���������A�C���@�ɒ��ށu�̉v��� �C��ϓ��C�j�V�A�e�B�u�^�c�ψ���́A�V�^�R���i�E�C���X�����g�傪�����N�����Ă��鐢�E�A���{�ł̐[�����l�X�ȉe���܂��A���ꂩ�犈��������o�ωɌ������o�ϑ�̂�����ɂ��āA�u�E�Y�f�Љ�ւ̓]���v�Ƃ������b�Z�[�W�\�����B �ł��d�v�Ȃ̂́A�ꍏ�����������g������������邱�Ƃł���Ƃ������ŁA�u�l�ނ̒��ʂ�������ЂƂ̊�@�ł���A�C���@�̍����Ɍ��������g�݂̌p���A�������Y��Ă͂����Ȃ��v�Ƌ������Ă���B �����g�傪�����N�����o�ϊ����̒�́A���߂̃G�l���M�[�����}�����ACO2�r�o�ʂ�����������Ɨ\������邪�A�C���@�̍����ɕK�v�Ȃ̂́A�o�ϊ����̏k���ɂ��Z���I�Ȕr�o�팸�ł͂Ȃ��A�w�E�Y�f�^�̎Љ�E�o�σV�X�e���ւ̓]���x�ɂ��A�����Ɨ�������p���I�ő啝�Ȕr�o�팸�ł���Ǝ咣���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/6�@]�@�@�� |
|
|
| �������v��A�Z���T�[�E�ݔ��̓�������Łu�ȃG�l�v��u���������v�v�������� �����v�A���a�G�N�V�I�Ȃ�5�Ђ́A���������v��E�Y�f�Љ�̎����̂��߂ɁA��Ɩ��Ȃǂ̐ݔ��œƎ��ɃZ���T�[��ݒu�E���䂵�Ă����V�X�e�������A��ԑS�̂��œK������V�X�e���̊J���ɋ����Ŏ��g�ނƔ��\�����B ���̋��n�́A�l�b�g���[�N�A�Z���T�[�A�ݔ�����A���z�v�Ȃǂ̊e����̘A�g�ɂ�錚�z��Ԃ����܂��܂ȑ��ʂ��瓝���I�ɑS�̍œK�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B ����̎��g�݂ł́A�������ɃZ���V���O��p�̃l�b�g���[�N���\�z�A�����Z���T�[�̃f�[�^���N���E�h�v���b�g�t�H�[���ɃA�b�v���[�h�A�}�b�V���A�b�v�i2�ȏ�̂��̂��~�b�N�X���邱�Ɓj���A�S�̍œK����T�����邽�ߑ��̓I�ɉ�́A�ݔ�����Ƀt�B�[�h�o�b�N�\�Ȑݔ�����l�b�g���[�N�V�X�e���̍\�z��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��YKK AP���獂���\�g���v���K���X��������s�s���ł̊��p�Ɋ��� YKK�͍��y��ʑ�b�F����擾���������\�g���v���K���X�������uAPW 430�h�Α��v�̑S���������J�n�����B �����i�͖h�Α��ł���Ȃ���A�����f�M���\�ƃN���A�Ȓ��]�������������B�܂������i�́A�Z��̊J�����v�ɂ����āA����܂Ŗh�ΐ��\���m�ۂł��Ȃ����߂Ƀg���v���K���X�������̗̍p����߂Ă����n��ł��̗p���\�ƂȂ邽�߁A�h�Α������ɕK�v�ƂȂ�֓��E���E�������ȂǑ�s�s���ł̊��p�����҂����B �����i�̓����́A �E�h�ΐ��\�ƍ����f�M���\�A���f�M�����t���[���ƁA�����\�ȑϔM�����g���v���K���X��g�ݍ����邱�ƂŁA�����g�b�v�N���X�̒f�M���\�i�j���[�g�����F�A�M�ї���U�l1.04W�^m2�EK�j�������B �E�ϔM���������K���X�ŃN���A�Ȓ��]���A�w�Ԗځx�̂Ȃ��ϔM�����g���v���K���X���̗p�B������̒��]���N���A�ɉ��o����B �E�h�I���\�ɗD��A�~��̌��I��}���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������R���d�r�̎d�g�݂�CO2�����^���ϊ��A�������݂炪�J���ɐ��� �������݂́A�Q�n��w�Ƌ����ŁA�������R���d�r�iMicrobial Fuel Cells�A�ȉ�MFC�j�����p����CO2�ϊ��Z���ɂ�郁�^�������ɐ��������Ɣ��\�����B MFC�̎d�g�݂����p���č\�z�����A�m�[�h�i���Ɂj���ƁA�d�q�������CO2���烁�^��������������Q��A�킵���J�\�[�h�i���Ɂj����g�ݍ��킹��CO2�ϊ��Z�������삵�A���������d����50%�߂��𗘗p���ĊO�����狟������CO2�����^���ɕϊ��ł����Ƃ����B MFC�Ƃ́A�Ⴆ�w�h���Ȃǒꎿ���̌��C�����d�ۂɂ��L�@�����̕����i��Ӂj�Ő������d�q���A�ꎿ���ɐݒu�����A�m�[�h���o�R���A�����ɐݒu�����J�\�[�h�i���Ɂj��ŗn���_�f�Ɣ��������Ĕ��d����Z�p�B ����͂���Ȃ锭�d������CO2�ϊ������̌����ڎw���Č����J�����p�����Ă������j���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ԉ��A�����w���d�͂̍ăG�l��50���ɐ��E14�H��ōăG�l100���B�� �ԉ��́A2019�N�����_�ł̍w���d�͂̍Đ��\�G�l���M�[�̔䗦���A���{��50���A�O���[�o���S�̂�31���ɒB�����Ɣ��\�����B�܂��A����4�H��ƊC�O10�H��̌v14�H��ɂ����āA�w���d�͂̍Đ��\�G�l���M�[�䗦100����B�������B ���Ђ͒n�����g���̌����ƂȂ鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̍팸��ϋɓI�ɐi�߂Ă���A�O���[�o���S���_�̉������ʃK�X�r�o�ʂ�2030�N�܂ł�22���팸�i2017�N��j���邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���B���̉������ʃK�X�팸�ڕW�́AScience Based Targets�iSBT�j�C�j�V�A�`�u���A�u�p������v�ɂ�����Ȋw�I�ȍ����Ɋ�Â����ڕW�Ƃ��ĔF�肳��Ă���B �ڕW�B���̂��߂̎��g�݂Ƃ��āA���Ə���p���z�����d�ݔ��̓����ƁA�w���d�͂̍ăG�l���𐄐i���Ă����B�w���d�͂ɂ��ẮA�܂���2025�N�܂łɓ��{�A2030�N�܂łɂ̓O���[�o���S�̂ŁA���ׂĂ��ăG�l�ɂ��邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���Ď��g�݂�i�߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����փQ�[�g�E�F�C�̉w�z�[���Ɩ��͓d�͐��Ő���AG3-PLC������IC���̗p ���l�T�X�́A�d�͐��ʐM�iPLC�j�pIC���A�p�i�\�j�b�N�̉w�z�[���p�Ɩ�����V�X�e���ɍ̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���ш�i�ᑬ�j����PLC�i10�`450kHz�j�p���f��IC�ŁAPLC�K�i��1�uG3-PLC�v�ɏ�������B�d�͐��ʐM�̕����w����������DSP�R�A�ƁA��ʂ̃v���g�R������������uArm Cortex-M3�vMCU�R�A�𓋍ڂ��A�ʐM�p�\�t�g�E�F�A�̏������\�ƍ����m�C�Y�ϐ��������B �p�i�\�j�b�N��JR�����{�Ƌ��ɁA���ԑт�V��ɂ���ĉw�z�[���p�Ɩ��̒����⒲�F�𐧌䂷��V�X�e�����J�����Ă���BG3-PLC�������̗p�������ƂŁA�������F��p�̐M������~�݂���K�v���Ȃ��Ȃ�A�d�͐��݂̂Ő���M���𑗂��B ���l�T�X�́APLC-IC�ȊO�ɂ��A���H�̒�Ă���ǁA���t�@�����X�p�ʐM�\�t�g�E�F�A�A�\�t�g�E�F�A�̊J���x���A�ʐM��Ԃ̕]���c�[���Ƃ������Z�p�T�|�[�g����Ă���B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���݂���FG�A�ΒY�Η͔��d�������^�M�c���팸��錾50�N�܂łɎc���[���� �݂��ق͍���A�O���[�v�S�̂ŃT�X�e�i�r���e�B����ъ��E�C��ϓ��ւ̎��g�݂��������Ă������j�\�����B ���ЃO���[�v�̍���̖ڕW�́A�T�X�e�i�u���t�@�C�i���X�E���t�@�C�i���X�ڕW�F2019 �N�x�`2030 �N�x�v25 ���~�i�������t�@�C�i���X12 ���~�j�B �E�ΒY�Η͔��d�������^�M�c���팸�ڕW�F2030 �N�x�܂ł�2019 �N�x��50���ɍ팸���A2050 �N�x�܂łɎc���[���Ƃ��铯�ЃO���[�v�́A���ۑS��SDGs�B���Ɍ����������̗�������������ϋɓI�ɉʂ����Ă����Ƃ���B �C��ϓ��l�b�g���[�N�́A���݂̓��ЃO���[�v�̗Z���Ɋւ��āA�u�C�X�N�̊Ǘ����s���Ă���Ƃ͂����Ȃ��v�Əq�ׂ���ŁA�u�ΒY���Ǝ҂ɑ��鐢�E�ő�̑ݕt���s���Ă���@�ցv�Ǝw�E���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���T���G�X�I�v�e�b�N���x�Z���T�[�t80���E100���Ή��\�Ȑ��ⓔ���LED�Ɩ��\ ���\���ꂽ���i�́A�V���ɉ��x�Z���T�[�����ڂ���Ă���A���͂̉��x�㏸�����������L���b�`���ALED�Ɩ��S�̂̔j����h�����Ƃ��ł������������B���o��I�C���~�X�g�Ȃǂ���������ȍH���A���F������悤�ȍH��A�����H��Ȃǂł�100���̊����̂��ƁA24���ԉғ������Ă���B���������������̍H��Ȃǂł́ALED�Ɩ��̋��e�l�i100���j���Ďg�p����邱�Ƃ������A�ڋq����͖�����̂��Ƃ��l�����A���i�ɂ����x�Z���T�[��t���Ăق����Ƃ����v�]�������o�Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{��ESCO���ƁA�{�L�{��55�{�݂ɓ����ȃG�l��30����B�� ���{�́AESCO���Ƃ̋�̓I�Ȑ��i���@���߂��u�V�E���{ESCO�A�N�V�����v�����v�i2015�N�`2024�N�j�ɂ��āA�v�����̒��ԔN���}����ɂ�����A�i���E���ʂ����������ʂƁA���i����̌������ɂ��ĂƂ�܂Ƃߌ��\�����B�܂��A���킹�ē��v���������肵���B ���{�ł́A����܂łɕ{�L�{�݉���108�{�݂Ŏ��Ɖ����A����ɂ����M����팸�z��2018�N�x���܂ł̗v�Ŗ�90���~��B�����Ă���Ƃ����B�{�L�{��82�{�݂�ESCO���Ƃ�����ڕW���f���Ă���B����55�{�݂ɓ����ρA�����ē����̈ꗗ�ɂ͋L�ڂ̂Ȃ�22�{�݁i�v77�{�݁j�ɓ�������Ă���A�����ɐi�����Ă���i2019�N�x���j�BESCO���Ɠ������ʁi���сj���m�F�����i2018�N�x�����_�j�Ƃ���A�ڕW�ȃG�l��15���ɑ��āA30�����ȃG�l����B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2018�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʁA�ߋ�29�N�ōŏ���5�N�A���Ō����i�m��l�j ���Ȃ́A2018�N�x�̓��{�̉������ʃK�X���r�o�ʁiCO2���Z�j��12��4000���g���ŁA�O�N�x��3.9�����ƂȂ�A5�N�A���Ō��������Ɣ��\�����B 1990�N�x�ɔr�o�ʂ̎Z����J�n���Ĉȍ~�A�ߋ�29�N�ōŏ��ƂȂ�A�܂��A����GDP������̑��r�o�ʂ�2013�N�x�ȍ~6�N�A���Ō����ƂȂ����B �O�N�x��2013�N�x�Ɣ�ׂČ��������v���Ƃ��āA�d�͂̒�Y�f���ɔ����d�͗R����CO2�r�o�ʂ̌�����A�ȃG�l�̐i�W�E�g�~�ȂǃG�l���M�[����ʂ̌����ɂ��A�G�l���M�[�N����CO2�r�o�ʂ������������Ɠ����������B 2018�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂ́A2013�N�x���12.0�����i2005�N�x���10.2�����j�B����ʃV�F�A���݂�ƁA�Y�ƕ��傪37.6���A�^�A���傪19.9���A�Ɩ����̑����傪18.5���A�ƒ땔�傪15.6���A�G�l���M�[�]�����傪8.4���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c�A�M�����A�d�͂̃L�����b�g���������CO2�r�o�ʂ�2019�N�ɂ���Ɍ����ƕ� �h�C�c�A�M�����iUBA�j���s����2019�N�̌v�Z�ɂ��ƁA�h�C�c�Ŕ��d�����d�͂̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�W���͌����X���������Ă���A1990�N�Ɣ�ׂ��36�����������B ��ȗv���́A�Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ʂ̑����A�ΒY�Η͔��d�ʂ̌����A����єr�o������̉��i�ł���B�h�C�c��2017�N��CO2���ϔr�o�ʂ́A�ŏI����d��1�L�����b�g���ikWh�j�̔��d�ɔ������ڔr�o�ʂ�485�O�����ł���A1990�N����279�O�����i36���j�������A2018�N�͎b��f�[�^�ɂ����̂ł��邪468�O�����i��38�����j�A2019�N��401�O�����i��47�����j�̗\���ƂȂ��Ă���B �h�C�c�̔��d�ɂ�����2017�N~2019�N��CO2�r�o�ʂ͂��ꂼ��2��8,300���g���A2��6,900���g���A2��1,900���g���i�\���l�j�ł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���u���{�͑��}�ɐΒY�Η͗A�o����𒆎~�v���߂�A���R�G�l���M�[���c ���R�G�l���M�[���c�́A���{�ɑ����}�ɐΒY�Η͗A�o����𒆎~���邱�Ƃ����߂鐺�������\�����B ���Ȑݒu�́u�ΒY�Η͔��d�A�o�ւ̌��I�x���Ɋւ���L���҃t�@�N�g������v�ɓ��Ȃ̈˗��Œ�o�����A�C���t�H�p�b�N�u�A�W�A�Ői�ޒE�ΒY�Η͂̓����v�̂Ȃ��Ŗ��炩�ɂ������́B ���c�́A�����ł̐ΒY�Η͗A�o�v���W�F�N�g�ڍ���A�؍��̐ΒY�Η͐��i����̌������A�܂��A����A�W�A�ōL����ΒY�Η͂���̒E�p�̓�����������������ŁA�u�w����Ђ낢�x�r�W�l�X�ł͂Ȃ��A�����ɂȂ���G�l���M�[�r�W�l�X�ւ̓]�����K�v�v�ƒ��Ă���B ��̓I�ɂ́A���{���l�ɐΒY�Η͂�A�o���Ă����؍��A�����̕ω����Љ�B�܂��A���{�̎�v�A�o��ł���x�g�i����C���h�l�V�A�ł̍ŐV�̓����������Ă���B����ɁAIEA�������V�i���I�̂����́u�����\�V�i���I�v���ɂƂ�A����A�W�A�S�̂Ŏ��R�G�l���M�[�g�傪�����������邱�Ƃ��L���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����H�X�ɍ��@�\���C�ݔ��R���i��A���g�����}������ ���Ȃ́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�Ɍ����āA���H�X�Ȃǂɑ����@�\���C�ݔ��̓�����p��⏕����B �O�C�Ɠ�������r�o�����C�̊ԂŔM�������A������ۂ^�C�v���ΏہB��g�[���ʂ̖��ʂ�h���A�ȃG�l��n�����g���̗}���������ɐi�߂�B �V�^�R���i�́A���C�̈�������ԂŊ������L����₷���Ƃ���A���H�X�������l�������Ă���B�O�o�̎��l���d�Ȃ�A�o�c�ւ̑Ō����[���ɂȂ��Ă���B ��̓I�ɂ́A�s���葽�����W�܂�Ɩ��p�̎{�݂�ΏۂɁA������p��2����1�`3����2����������B��p��1�䓖�����50���~�ŁA�S��800�`1000�J���̌v3000����x��z�肵�Ă���B �V�^�R���i�I����ɗ��p�q�̓�����������B�Ⴆ�A���@�\���C�ݔ����������H�X�̓�����ɁA���C���ǂ����Ƃ������X�e�b�J�[��\��Ȃǂ��A�\���Ă��Ȃ��X�Ƌq�̓�����r����Ƃ��������@���������Ă���B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ��Google�A24����365���f�[�^�Z���^�[��100%���R�G�l�����ʼn^�p ���Ђ�2012�N����A���ƂŎg�p����d�͂����R�G�l���M�[�ɐ�ւ����n�߂��B���Ђ��S���E�Ŏg�p����d�͗ʂ�2017�N���_��76��kWh�B �C��ϓ��̗}�������߂��钆�ŁA�d�͎g�p�ʂ̑������\�Ȍ���}����ƂƂ��ɁACO2��r�o���Ȃ����R�G�l���M�[�d�͂ւ̐ؑւ��A���ЂɂƂ��Ď��Ƃ������\�Ȃ��̂ɂ��邤���ŏd�v�Ȏ��g�݂ɂȂ��Ă����B ���Ђɂ��ƁA����̎��g�݂ł́A�G���W�j�A�`�[���ɂ���ĊJ�����ꂽ�V���ȃV�X�e�����d�v�Ȗ�����S���Ă���Əq�ׂĂ���B���͂⑾�z���Ȃǂ��ł��L�x�ȏꍇ�ɁA���ׂ̑傫���v�Z�^�X�N���V�t�g���邱�Ƃ��ł���B ����A�^�X�N���f�[�^�Z���^�[�Ԃňړ������邱�ƂŁA���ԁE�ꏊ�̗����ŕ��ׂ��y�����A�O���b�h���x����CO2�r�o�ʂ̍팸���ő剻���邱�Ƃ�ڎw���Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�C�ۋ���A��FIT���т́u�d�͎��v�v�u�]��d�́v�\�����J�n ���{�C�ۋ���́A�u��FIT���сv��\���ΏۂƂ����]��d�͔��掖�ƎҌ����u�]��d�͗\���T�[�r�X�v�ɂ����āA�u���z�����d�o�͗\���v�ɉ����A�u�d�͎��v�\���v�Ɓu�]��d�͗\���v�̏����J�n����Ɣ��\�����B ������́A��FIT���т̗]��d�͔�����s�����\�[�X�A�O���Q�[�^�[�⏬���d�C���Ǝ҂Ȃǂ��x�����邽�߁A2019�N11������A��FIT���тɓ��������]��d�͗\���T�[�r�X���J�n�����B���e�Ƃ��āu���z�����d�o�͗\���v�̒��n�߁A���e�Ƃ��āu�d�͎��v�\���v�Ɓu�]��d�͗\���v�̒�\�肵�Ă����B ����̃T�[�r�X�g�[�ɂ��A�\�肵�Ă������ׂĂ̗\������p�ł���悤�ɂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/5�@]�@�@�� |
|
|
| �������ő勉�A��75MW�̖؎��o�C�I�}�X���d�����v�H�^�C�[���b�N�X�� �C�[���b�N�X�́A���Ђ炪�o�����鍑���ő勉�̖؎��o�C�I�}�X���d���u�L�O�o�C�I�}�X���d���v�̏v�H�����J�Â����Ɣ��\�����B �����d���̔��d�o�͂�74,950kW�ŁA��R���̓p�[�����q�k�iPKS�j�Ɩ؎��y���b�g�B�C�[���b�N�X�E��d�݂炢�G�i�W�[�E��d�H��3�Ђ������o������u�L�O�j���[�G�i�W�[������Ёv���^�c���A���ł�2020�N1��1������c�Ɖ^�]���J�n���Ă���B 3�Ђ́A����������O�ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�����p�������Ƃ�ϋɓI�ɐ��i���邱�ƂŁA�n�����g���h�~�ƒ�Y�f�Љ�̎����ɍv�����Ă����Ƃ��Ă���B ���d���T�v�F�N�Ԕ��d�ʁF��50��MWh�i��ʉƒ��15 �����ѕ��̔N�ԏ���d�͂ɑ����j�ACO2�팸���ʖ�F20��t-CO2�^�N(����)�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������U�����ԁA100%��։\�ȃ~�h�����V�R��BD�R���ɂ��o�X�^�s���J�n �����U������(��)�́A100%�Ζ��R���̌y���ɑ�։\�ȁA���[�O���i(�a���F�~�h�����V)���������o�C�I�f�B�[�[���R��(�ȉ��A�u������BD�R���v)���A���Г���H��(�_�ސ쌧����s)�̃V���g���o�X�Ŏg�p����B 2014�N�A���Ђ�(��)���[�O���i(�ȉ��A�u���[�O���i�Ёv)�̊J������BD�R���̃V���g���o�X�g�p���J�n���A�ܗL��100���ł��ԗ��̃G���W���ɕ��S�������邱�ƂȂ��g�p���邱�Ƃ��ł��鎟����BD�R���̋��������ɒ��肵�Ă����B 2018�N�ɂ́A���[�O���i�Ђ����삵��������BD�R���̐��\����(�S���א��\�����AWHTC�r�o�K�X����)�����{���A�Ζ��R���̌y���Ɠ����̐��\�ł��鎖���m�F�����B2020�N3���A���[�O���i�Ђ��犮������������BD�R���̋������������A2020�N4��1�����V���g���o�X�ł̎g�p���J�n����Ƃ���(�^�s��ԁF���c�}�d�S�Ó��w�|�����U����H��)�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����{���A�݂���FG�Ɂu�C��ϓ��v�Ɋւ��銔���Ă��o�C��l�b�g���[�N �C��l�b�g���[�N�́A�݂��كt�B�i���V�����O���[�v�ɑ��A�C��֘A���X�N�ƃp������̖ڕW�ɐ��������������s�����߂̌v��̊J���������ĂƂ��Ē�o�����B ���{�ɂ�����C��ϓ��Ɋւ��銔���Ă͏��߂ĂŁA���l�b�g���[�N�̔��\�ɂ��ƁA�݂���FG�͒�Ă����錩���݁B ���̊����ẮA�݂���FG���^������u�C��֘A�������J���^�X�N�t�H�[�X(TCFD)�v�̒ɏ]���āA�p������̋C��ڕW�ɐ��������������s�����߂̌o�c�헪�̌v����J������悤���߂���́B ���݂݂̂���FG�̗Z���́u�C�X�N�̊Ǘ����s���Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂�����v�i���l�b�g���[�N�j���Ƃ����B�ΒY�֘A�Y�ƂɊW���鐢�E�I���Z�@�ւ��܂Ƃ߂�2019�N12���̃��|�[�g�ɂ��ƁA�݂���FG�̐ΒY�֘A�Y�Ƃւ̑ݕt��2017�N����2019�N�܂ł�2�N�Ԃ�168���ăh���ɏ��u�ΒY���Ǝ҂ɑ��鐢�E�ő�̑ݕt���s���Ă���@�ցv�Ǝw�E����Ă���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���g���^�ACO2�r�o�ʂ̍팸�Ɋ�^����u�G�A���X�h���@�v���J�� �g���^�����Ԃ́A�Ód�C�����p����C���g��Ȃ��h���@�u�G�A���X�h���@�v���J�������B���̓h���@�̊J���́A���Ђ́u�g���^���`�������W2050�v�ɂ�����u�H��CO2�[���`�������W�v�̎����Ɍ�������g�̈�B ���������ꂽ�h���̗��q��Ód�C�Ŏԑ̂ɓh�������邱�Ƃɐ������A����ɓd�����������䂷�邱�Ƃŋߐړh�����\�Ƃ����B�����̋Z�p�ɂ��A���������h���ɑ��Ď��ۂɎԑ̂ɓh������h���̊����������u�h�������v�́A�]���̃G�A�X�v���[��(60�`70%)����A95%�ȏ�Ɍ��サ���B ���̓h���@�̓����ŁA�g���^�O���[�v�̓h���H���ɂ�����CO2�r�o�ʂ�7�����x�팸�ł��錩���݁B����A���m���L�c�s����2�H��(�����H��A��H��)�ɓ������A�����A���H��֓W�J����ƂƂ��ɁA�O���[�v��Ђł̓�����O���[�v�O�ւ̋Z�p���^���������Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���݂�ȓd�́A�u��C�̌����鉻�v���Ƃ��X�^�[�g19��ނ̕��V�ې��� �݂�ȓd�͂́A��C���Ɓu�݂�ȃG�A�[�v���J�n����Ɣ��\�����B��C���Ɋ܂܂��ۗނ��������A�I�t�B�X��X�܂̋�C����c�����邱�ƂŁA����s�Ȃ���悤�T�|�[�g������́B �����̋�C���ɂ͂��܂��܂ȕ��������V���Ă���APM2.5�Ȃǂ̗L�Q������C���t���G���U�E�C���X�A�u�h�E���ۂȂǁA�l�̂ɉe�����y�ڂ��\���̂��镨���������܂܂�Ă���B�����̋�C���ɎЉ�I�S�����܂錻�݁A��C���̋ۗނ��������A���̑���Ă��邱�ƂŁA�����\�ȎЉ�Â���ɍv�����Ă��������l���B ���V�ی����F�I�t�B�X��X�ܓ��̋�C���z�����A�l�̂ɉe�����y�ڂ��Ƃ�����u�h�E���ہA����l�^�ہA�~�N���R�b�J�X���A19��ނ̕��V�ې����B�������ʂ���ɂ����\�����[�V�����F�u����Ԃɂ����镂�V�ی�����89.6%�v�Əؖ����ꂽ�Ƃ����A��Ԃ̋ۂ�E�C���X��s�������鎇�O���E�ۏƎˑ��u��p���A��C���̉��P�Ɍq����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�����A�A2030�N�܂łɖ�4��kWh�̍Đ��\�G�l���M�[��n�o�� ���{���������g���A����́A�E�Y�f���Љ�̎����ƌ��q�͔��d�ɗ���Ȃ��Љ���߂������g�݂̈�Ƃ��āA�S��12�̐����ƂƂ��ɁA2030�N�܂łɔN�Ԕ��d�ʂŖ�4��kWh�̍Đ��\�G�l���M�[��n�o����ڕW���܂Ƃ߂��Ɣ��\�����B �܂��͐��������L����X�܂��z�E�����{�݁A�����{�݂ɑ��z�����d�ݔ����ő���ݒu���A���̂����Ő����g����������̎{�݂����p���Ă����B����ɁA�����\�ȎЉ�Â���Ƃ����r�W���������L���鐶�Y�҂�����A�s����Љ���@�l�A�s���c�̂���c�̂ƂƂ��ɁA�H�i�c�Ԃ����p�����o�C�I�K�X���d�⏬���͔��d�A�m�㕗�͔��d�Ȃǂ��������Ă����l���B ����܂ŁA���z�����d�E���͔��d�ȂǔN�Ԕ��d��1.8��kWh�ݏo���A�Đ��\�G�l���M�[�̊g��Ɏ��g��ł����B���������10�N�Ō����2�{�ɑ��₷�B�ڕW�Ƃ���N�Ԕ��d��4��kWh�i�o�͋K��200MW�����j�́A2030�N���_�̐����S�̂̐���d�͎g�p�ʂ̖�40���ɂ�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�c�_�^���z�����d�v�̉ˑ�J���X�Βn�ɐݒu�ł��A��^�_�@������� ��t�G�R�E�G�l���M�[�ƃN���[���G�i�W�[�W���p���́A�c�_�^���z�����d�i�\�[���[�V�F�A�����O�j�̂���Ȃ镁�y�Ɍ����A�X�Βn�ł̍�Ƃ��^�_�@�̎g�p�Ƃ������ۑ����������V���ȉˑ�������ŊJ�������Ɣ��\�����B ����܂ł̐ݔ��̎��R�x���Ⴍ�A��^�_�@���g���Ȃ��A�X�Βn�ɐݒu�ł��Ȃ��A�Ƃ������ۑ������Ă����B���҂��V���ɊJ���������i�ł́A1�{���̎x���ɂ��ĉˑ�ݒu�̎��R�x�𑝂����Ƃ��A�����̖������������B �o�T�uCNET JAPAN �v |
|
|
| �������X�}�[�g���[�^�[�ʼn��u���j�S�N�x������؎����s�m���\�� �ߘa4�N�x���琅���̎g�p�ʂȂǂ����u�Ō��j���鐅���̃X�}�[�g���[�^�[�̎��؎������J�n������j���������B���j�Ɩ��̕��S�����炵�A�R���̑��������A�V���������ݔ��Ǘ��Ȃǂ̏����W�ɐ������_���B2030�N��܂łɓs���S�˂ւ̓�����ڎw���B �����ł͗ߘa6�N�x�܂łɁA�s�S��x�O�ȂǕ����̒n��ɐ����̃X�}�[�g���[�^�[��10����ݒu�B�I�葺�̓]�p�Z���6��˂̂ق��A4�N�x�ȍ~�Ɍ��đւ�����s�c�Z��A�s���̏����w�Z������Ȃǂɓ�������\�肾�B ���ɐ݂����Ă��鎩�����j�V�X�e�������p���A�����␅���A�g�p�ʂȂǂ̏�Ԃ����A���^�C���Ŋm�F�ł��錩���݁B�s�ɂ��ƁA�R���̑���������ЊQ���̒f������̐v���ȕ��������łȂ��A�����̗��p���獂��҂̌����T�[�r�X�Ȃǂւ̊��p�����҂ł���Ƃ����B�_��҂̃p�\�R����X�}�z�ɁA���j�[������Ȃǂ𑗂�y�[�p�[���X�������{������j���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �����{�̉������ʃK�X�팸�ڕW�A�����u���ō��A�֒�o2030�N�x26���팸 ���{�́A�p������Ɋ�Â��A���A�C��ϓ��g�g����ǂ֍Ē�o���鉷�����ʃK�X�팸�ڕW�ɂ��āA2015�N�Ɏ������u2030�N�x��2013�N�x��26�����v�𐘂��u�����Ƃ����肵���B���̍팸�ڕW�́A���{�́u���������肷��v���iNDC�j�v�Ƃ��āA�����ǂ֒�o����\��B ���肵��NDC���Đ��{�́u���݂̒n�����g����̐�������A����Ȃ�팸�w�͂̒Nj��Ɍ������������J�n���邱�Ƃ�\��������́v�Ɛ��������B �܂��A�u�n�����g����v��v�̌������ɒ��肵�A�lj������A���A�֒�o���邱�ƁA�܂��A���̌�̍팸�ڕW�̌����́A�G�l���M�[�~�b�N�X�̉���Ɛ����I�ɁA����Ȃ��S�I�ȍ팸�w�͂f�����ӗ~�I�Ȑ��l��ڎw���A����̃p��������5�N���Ƃ̒�o������҂��ƂȂ����{���邱�Ƃ荞�B�����ڕW�Ɋւ��ẮA2019�N6���Ɍ��肵���u�p������Ɋ�Â������헪�Ƃ��Ă̒����헪�v�Ɋ�Â��A2050�N�ɂł��邾���߂������ɒE�Y�f�Љ�������ł���悤�w�͂��Ă����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������G�l���A�ȃG�l�D�ǎ��Ǝ҂����\ �����G�l���M�[���́A�ȃG�l�@�̓��莖�Ǝғ��ɂ�����2018�N�x�G�l���M�[�g�p���Ɋ�Â��ȃG�l�D�ǎ��ƎҁiS�N���X���Ǝҁj�����J�����B ���������\����2018�N�x�̎��ѕɂ��ƁAS�N���X��57���i�O�N���j�AA�N���X��33���i��4.9�����j�AB�N���X��11���i��4.8�����j�ŁA��6����D�ǎ��Ǝ�S�N���X����߁A�ȃG�l��؎��Ǝ�B�N���X�͌����X���ɂ������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��2020�N�x�Ɋ֓��ŗ��p�ł���G�l���M�[�E���g��������⏕�����K�C�h���J �֓��o�ώY�Ƌǂ́A2020�N�x�ɗ��p�ł��鍑�Ɗ֓��n��̒n�������́i�s���E���ߎs�j�̃G�l���M�[�E���g����̂��߂̕⏕���E�������Ȃǂ̎x�����x���Ƃ�܂Ƃ߂��K�C�h�u�b�N���E�F�u�T�C�g�Ō��J���A���p���Ăт����Ă���B ���̎x�����x�ɂ��ẮA�u�ڎ��v�ŁA���Ɩ��ƑΏێ��Ǝ��ƎҁA�{��Ȃɂ��Čf�ځB�����u�t�F�[�Y���ށv�ŁA�u���z�����d�v�u���͔��d�v�u�ȃG�l���v�u�p�����v�Ȃǂ̕���ʂɁA�t�F�[�Y�ɕ����āA���Ɩ��ƑΏێ��Ǝ��ƎҁA�{��ȁA�Y���y�[�W���f�ڂ��Ă���B�t�F�[�Y��9�ɕ��ނ���Ă���B �n�������̂̎x����͈ꗗ�\�Ōf�� �֓��n��n�������̂̃G�l���M�[�E���g����Ɋւ���x�����x�́A�s���@�֖��A�{�����A��ށA�x���T�v�A�x������A�x���ΏہA�t�F�[�Y�A�₢���킹�悪�ꗗ�ŏЉ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��EV�����y���Ă��Η͔��d�ˑ��̂܂܂ł�CO2�r�o�ʂ͕ς��Ȃ� ���s��w�ƍL����w�̌����O���[�v�́A�����̓d�C�����ԁiEV�j�̊��S���y�ɂ��CO2�r�o�ʍ팸���ʂ��𖾂����Ɣ��\�����B �����Ԃ̓d�������ł̓p�������2���ڕW�ɂ͒������A�ڕW�B���̂��߂ɂ͉ƒ�E�Y�ƁE��ʂ̃G�l���M�[���v���S�̂ƁA���d���܂ރG�l���M�[�������������ŒE���ΔR��������K�v������Ƃ����������ʂ��������B �������ł́AEV�̓����ƌ�ʕ���ȊO�̔r�o�팸�w�͂̐i�W�x�����ɂ����6�ʂ�̃V�i���I��ݒ肵�A�R���s���[�^�[�V�~�����[�V�������s�����B ���̌��ʁAEV�̓����ɂ��A��ʕ���R���̃G�l���M�[����ʂ͑傫���������A�����ԗR���̒���CO2�r�o�ʂ��}������邱�Ƃ��킩�������A���d�V�X�e�����Η͔��d�Ɉˑ����錻��̂܂܂ł͏�����CO2�r�o�ʂ͂قƂ�Ǖς�炸�A�S�̂Ƃ��Ă͐����ő������邱�Ƃ��킩�����B ����ɁA���ɔ��d�V�X�e���ɍĐ��\�G�l���M�[���K�͂ɓ��������Ɖ��肵�Ă��A2�����x��CO2�팸�ɂƂǂ܂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�ȃG�l�^�m���t�����@�퓙�̓������x�� �����s�́A�ȃG�l�^�m���t�����@�퓙�̓������x������Ɣ��\�����i�\�����ԁF2020�N4��1���`2021�N2��26���j�B�s�ł́A�m���t�����@�퓙�̕��y���㉟�����邽�߁A��}�Ƀt�������g�p���Ȃ��u�ȃG�l�^�m���t�����Ⓚ�①�V���[�P�[�X�v�ɉ����A�ߘa2�N�x�\�����牷�����ʂ̒Ⴂ�t�������g�p�����u�ȃG�l�^��GWP�r���p�}���`�G�A�R���v�̓����ɑ���⏕���J�n����B �⏕�Ώێ҂́A�������Ǝҋy�ьl�̎��Ǝҁi���[�X����ꍇ���܂ށj�ŁA�ȉ��̕⏕�v����S�Ė��������́B �@1)�s���̎��Ə��ɐݒu����邱�ƁA �@2)���g�p�i�ł��邱�ƁA �@3)2021�N3��12���܂łɐݒu����������B �⏕�Ώیo��́A�⏕�Ώۋ@��̍w����y�эH����ŁA�⏕���͐ݒu�ɌW��o���1/3�`1/4�i�����̕⏕������ꍇ�́A���̊z���������z�j�ŁA���x�z��1�䂠����500���~�A1���Ǝ҂�����1,500���~�܂łƂȂ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������r�b�O�T�C�g�ɕܑ��^���z���p�l���E�U�����d��ݒu�ăG�l�u�����鉻�v �s�L�{�݂ɂ����āA���y�̏����i�K�ɂ���ăG�l�Z�p�𗦐悵�ē������A�����鉻��}�邱�ƂŁA���Ԏ{�݂̎��g�݊g��ɂȂ��邱�Ƃ��ړI�ݒu���Ԃ�2021�N3��31���܂ł̗\��ŁA���ʑ��蓙�����{����B �ܑ��^���z���p�l���F�ܑ��H�ʁi���ʃK���X�̉��j�ɐݒu���鑾�z���p�l���A�N�ԑz�蔭�d�ʖ�750kWh�^�N�B�U�����d�iLED�_���^�C�v�E��M�^�C�v�j�F���s�҂��ړ��̍ۂɏ��֗^����U���𗘗p���Ĕ��d���d�����d�C��p���āA�}�b�g�[��LED�̓_���A�X�}�[�g�t�H���A�v���iLINE�j�ւ̏�M�A�S����16���[�g���~��0.6���[�g���B���d�ʁi�u�Ԓl�A1���v�l�j�ACO2�팸�ʂ�\������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���Z�F�ыƁA�d�͏�����̎��؎������J�n�������̖��ԓd�͎�������p �Z�F�ыƂ́A�������̖��ԓd�͎�����ł���f�W�^���O���b�h�v���b�g�t�H�[���iDGP�j�𗘗p�����d�͏�����̎��؎������J�n����B DGP�͍������̖��ԓd�͎�����ŁA���Ђ����߂Ă̊��p��ƁBDGP�����p�����d��ƂƉ������_������Ԃ��ƂŁu���v�ƃT�[�r�X�v���o�C�_�v�ƂȂ�A�Z��W����5����P2P�i���d�ƂƎ��v�Ƃ̊Ԃœd�͂ڔ������邱�Ɓj�œd�͂������肷��B�����ADGP�����p�����d�͂ɐ�ւ���B ���Ђ͒i�K�I�Ɏ��؎�����i�߂Čڋq�ւ̐V�K�T�[�r�X����������B�܂��A���̎d�g�݂𗘗p���A2020�N�x�ɂ͍Đ��\�G�l���M�[�̓d�������ʂ��ēd�͏����肷������s���v��B DGP��AI�����p�������x�̍��������\���Ǝ����}�b�`���O�V�X�e�����������A�Ǘ��R�X�g�팸�����҂����BDGP�͏����A�s����d�������������\�ɂ���V�X�e���������A�Đ��\�G�l���M�[�̕��y�E���p�ɂȂ������l���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��1����Ȃ��Ă����\�ێ��A���S�����S�ہF�؍����̘p�ȁ^�܂��݂ł��锖�^�o�b�e���[�A�ʎY�� �؍�Jenax�́A�t���L�V�u�����`�E���C�I���|���}�[�d�r�uJ.Flex�v���J���A2020�N�Ă���ʎY���J�n����B J.Flex�́A�Ȃ���A�����A�܂��ނȂǂ̕ω��ɂ��Ή�����_������������`�E���C�I���|���}�[�d�r�B����0.5mm�܂Ŕ��^�ɂł���ق��A�����`��x���g��Ȃnjڋq�̗v�]�ɉ����Ď��R�Ȍ`��A�T�C�Y�Œ��\���B ���̓d����3.8V�A�쓮���x�́|20�`�{60���B31�~83�~0.7mm�̃��f���ł́A60mAh�ŁA200�~200mm�̃T�C�Y�ł����5000mAh�̗e�ʂ���������B�܂��A�Ȃ����a20mm�̏�Ԃ�1����܂�Ȃ�����ł�89���ȏ�̗e�ʈێ�����ۂB ���ۂɒZ���A�ߏ[�d�A�ߕ��d�A�ߓd���Ȃǂ̓d�C�I�����A�����A��C���A�ߔM�Ȃǂ̊���������сA�Ռ��A�����A�������������Ȃǂ̋@�B�����ɂ����i�B�o�b�e���[�̈��S���Ɋւ��鍑�ۋK�iIEC62133���擾���Ă���B �o�T�uEE Times�v |
|
|
| ���J���t���A���������������F���E���A�u���S�ő̌^�v�F�f�������z�d�r���� ���R�[�́A�d���t���ő̍ޗ��݂̂ō\���������S�ő̌^�F�f�������z�d�r���W���[�����J�������B2020�N2�����{���珇���̔����J�n����\��B �F�f�������z�d�r�Ƃ́A�F�f�̉����z���𗘗p���Ĕ��d����f�o�C�X�ŁA����Ȍ��ł������悭���d���邱�Ƃ��ł���B��ʓI�ȍ\���ł́A�t�̂̓d���t��p���邱�Ƃ��烈�E�f��L�@�n�}�̊����A�d���t�R��Ȃǂ̈��S���^�ϋv���ɉۑ肪�������B �]���̓d���t�����ɁA�L�@�����̍ޗ��Ɨގ������u�L�@P�^�����́v�ƌő̓Y���܂��z�[���A�����ޗ��Ƃ��ė��p�B�Ǝ��̐����Z�p��p���A�_���`�^�����q�̑��E���������ɂ��̃z�[���A�����ޗ��������x�ɏ[�U���邱�Ƃɐ������A�S�ő̉������������B ����ɂ��A���S���A�ϋv��������B�ϋv���ɂ��ẮA�A�����t�@�X���z�d�r�Ɠ����ŁA5�`10�N�͗��p�ł���Ƃ����B ���R�[�͉����^�����O�p���C�����X�Z���T�[�m�[�h�̎����d�������ɓW�J���Ă������j�Ƃ����B �o�T�uEE Times�v |
|
|
| ���A�Y�r���A�r�������ŐV�ԊO���Z���T�[�̔�������c�������������� �A�Y�r���́A�̉��K���A�ȃG�l���M�[������������r�������̐V�V�X�e���u�ԊO���A���C�Z���T�V�X�e���v�̔̔����J�n�����B ���V�X�e���́A�����̓V���ǖʂɐݒu�����ԊO���Z���T�[�̏������ƂɁA���x�ω��̗v���ƂȂ锭�M�ʁA�l�̈ʒu�␄��l���Ȃǂ��Z�o����R���g���[���ō\������Ă���B�ݎ��҂̕ω��Ȃǂ����A���^�C���ɑ����邱�ƂŁA�������ω��������E������������O�ɋ����邱�Ƃ��ł���B �܂��A�l�̈ʒu�Ɛ���l�������Ƃɂ�������ɂ��A�s�݃G���A�͋���߁A�Ɩ����Â�����ȂǁA�ȃG�l���M�[����}�邱�Ƃ��ł���B���Ђ͍���A���V�X�e�������p���A�h�Ƒ��f�[�^�Z���^�[�̉��M���ُ̈�f�f�ȂǁA���S�E���S�����߂���p�r�ւ̓W�J���\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���V�i�l���A�����ł����d�ł���u�}�C�N�����ԁv�Ŕ��d���ƂɎQ�� �V�i�l���́A�O���[�o���G�i�W�[�ЂƋ��Ƃ��A�}�C�N�����͔��d���ƂɎQ�������B �O���[�o���G�i�W�[�Ђ��J�������u�}�C�N�����ԁv�̓����́A���������ˑ��������y�ʃu���[�h�ƁA�����I�ɔ��d�ł������Ȍ`��B����ɂ��A�J��������������Ԏ��̂̌y�ʉ��Ɣ��d�����̌���A���S���̊m�ۂ��\�ƂȂ����B ���ϕ������悻1m�^�b�̔����ʼn�]���A���ϕ������悻2���^�b�Ŕ��d�\�ȃ}�C�N�����Ԃ̊J���ɐ��������B �Ȃ����Ђ́A2020�N2����Sinagy Revo��ݗ����A�}�C�N�����ԓ��ڐ��i�̊J���E�����E�v�E�̔��E�ێ�E�����e�i���X���Ƃ�W�J���Ă���B����A�|�[���^���S�Ɨ��d�����u�Ɖ���p���͔��d���u�̊J���E�̔����s���Ă����Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�G�A�R���̃t�����ޓ��ւ��v���\�ɒ��ӂ��o�Y�ȁE���ȁu��؊W�Ȃ��v �ŋ߁A�u���ȁE�o�ώY�ƏȂ̎w���ɂ��A�G�A�R���Ɏg�p����Ă���t�����ނ̓���ւ����K�v���v�Ƃ��āA���ݎg���Ă���G�A�R���ɏ[�U����Ă���t�����ނ̓���ւ������U���Ă���B �o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ́A���ݎg�p����Ă���G�A�R���ɗ�}�Ƃ��ď[�U����Ă���t�����ނ��A�t�����ވȊO�̂��̂ɓ���ւ���悤�w�����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A�܂��A�@��̓_�����������Ǝ҂Ɉϑ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��Ɛ����B�܂��A����A���̎��Ⴊ�N�����w�i�ƂȂ�@�ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɉ�����Ă���B �t�����ނ̈��A�q-22�Ȃǂ�HCFC�i�n�C�h���N�����t���I���J�[�{���j�ɂ��ẮA�I�]���w�ی�@�Ɋ�Â��A2020�N�܂łɂ��̐��Y�Ə���i���Y�{�A���|�A�o�j��S�p���邱�ƂƂ���Ă���B�����܂Ő��Y��A�o�����K��������̂ł���A���ݎg�p����Ă���G�A�R����Ⓚ�①�@��̃t�����ނ��A2020�N�܂łɃt�����ވȊO�̂��̂ɓ���ւ���悤�K�肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��B �o�T�u�d�C�ʐM�v |
|
|
| ���N���[���d���P�O�O���A�ĂŖ@�����B������ �E�Y�f���Ɍ����āA���d����CO2��r�o���Ȃ��d����2040�`50�N�ɑS�d�͂�d�����Ƃ�@��������č��̏B�����X�ɑ����Ă���B �o�[�W�j�A�B�Ō��n����6���ɖ@�Ă��������A�S50�B�̂���8�B�ɂȂ����B�B�ɂ���āu�N���[���G�l���M�[�v�u�J�[�{���t���[�v�ȂnjĂѕ��͈Ⴄ���A��^���͂��܂ލĐ��\�G�l���M�[�ɓd��������B�ƁA���K��̏B�ɕ������B ���K��B�̑唼�́A�Đ��\�G�l�őS�d�͂�d���邩���̒i�K�ł͌��ʂ��Ȃ����߁A���̓d����V���ȃG�l���M�[�Z�p�𗘗p����I�������c���Ă���i�D���B �o�T�u�d�C�ʐM�v |
|
|
| �������s�A�u��Y�f�d�́v�E�u��Y�f�M�v�̔F�苟�����Ǝ҂����� �s�ł́A�L���b�v���g���[�h���x�ɂ����āA2015�N�x����A�s���F�肷��CO2�r�o�W���̏������������Ǝ҂���Ώێ��Ə����d�C���͔M�B�����ꍇ�ɁACO2�팸�����Ƃ��ĔF�߂�u��Y�f�d�́E�M�̑I���̎d�g�݁v�����Ă���B 2020�N�x�����3�v����Ԃ��}����ɂ�����A�E�Y�f�Љ���������A�Đ��\�G�l���M�[�̈�w�̗��p�g���}��ϓ_����A�F��v�����̉������s���A���N�x�ɑΏۂƂȂ鋟�����Ǝ҂����肵���B ����A�F�苟�����Ǝҁi���j���i2020�N�x����ʂɓK�p�j�Ƃ��āA �@1)��Y�f�d�́F12���Ǝ� �@2)��Y�f�M�F42��� ��F�肵���B �s�ł͍�����A���d�g�݂�ʂ��āA���ɔz�������G�l���M�[���p�𑣂����Ƃɂ��A�G�l���M�[����ʂ̍팸��Đ��\�G�l���M�[�̓����g��𐄐i���Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ������w�̌����`�[�����`�����C�I���d�r��5�{���A�V�^���`�E��-�����d�r�J�� �I�[�X�g�����A�̃��i�V����w���A���`�E���C�I���d�r��5�{�̗e�ʂ��������郊�`�E��-�����iLiS�j�d�r���J�������Ɣ��\�����B ����ɂ��A�d�C�����Ԃ̑啝�Ȓቿ�i����A��d���̑�K�̓X�g���[�W�Ȃǂ������ł���\�����L����B���̃��`�E��-�����d�r�́A200��ȏ�̏[���d�T�C�N�����o�Ă�99���̓d�͌������ێ����邱�Ƃ��\�ȑ��A�X�}�[�g�t�H���ɓ��ڂ����ꍇ�́A5���ԘA���Ŏg�p�ł���悤�ɂȂ�Ƃ����B ���`�E��-�����d�r�́A�[���d�T�C�N�����Z���A�����d�ɂ̑̐ς��c������Ƃ������_���A�ۑ�Ƃ��Ďw�E����Ă����B�����O���[�v�́A�������q�����ɉ��w�������x���ŃX�y�[�X���m�ۂ��ׂ��A���ʂ̍����q�ޗ���p���āA�d�ɂ̒��ɗ��q��ێ����邱�ƂŁA�������q�̊Ԋu���L���m�ۂ���Ƃ����\�������������B �o�T�uEE Times�v |
|
|
| �����E�ő勉�A���z�����d���p�̐��f�������_���ғ�����2020���ł����p �������Q�]���ɂ����āA���E�ő勉�̍Đ��\�G�l���M�[�����p�������f�������_�u�������f�G�l���M�[�����t�B�[���h�iFH2R�j�v��3�����ғ����J�n�B �אڂ��鑾�z�����d�i20MW�j�ƌn������̓d�͂��g�p�A10MW�̐��f�������u�ɂ��A�N�ԍő�900�g���K�͂̐��f���E�����E�������\�ƂȂ�B �o�ώY�ƏȂ�NEDO�Ő�����i�߂Ă���FH2R�̉ғ��J�n�����B����A�]��d�͂𐅑f�ɕϊ����A�����E���p����Z�p�iPower-to-Gas�j�̋Z�p����i�߂�B�܂��A�������ꂽ���f�́A����2020���̍ۂɔR���d�r�ԓ��̔R���Ƃ��Ċ��p����B���Α�ƈꕔ�̐������[�g�[�`�̔R���Ƃ��Ă����p�����B���v�\���Ɋ�Â��Đ��������ʒ��߂Ōn���̎����o�����X���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�ƒ�̓d�͌_���ؑւ���葱�������m�������ƎҔj�Y�Œ��ӊ��N�� �o�ώY�ƏȂ́A��ʉƒ낪�d�͂̍w�����ύX����葱���ɂ����āA�K���������_�̓d�͉�Ёi�����d�C���Ǝҁj�ɘA��������K�v�͂Ȃ��Ȃǂ́A��ʓI�Ȓሳ�̌_��ؑւ��i�X�C�b�`���O�j�葱�����@�ȃE�F�u�T�C�g�Ŏ��m�����B �d�͎��R���ɂ��A��ʉƒ�����i�ሳ�j�̌_��ؑւ������������A���k�����Ă��邱�Ƃ��Ď��{�����B �܂��A�����d�C���Ǝ҂̂����уR�~���j�P�[�V�����Y�i�����s�a�J��j���j�Y�葱���J�n���邽�߁A���Ђƌ_�Ă���d�C�̗��p�҂ɑ��A���݂₩�ɁA�V���Ɍ_����s���������Ǝ҂ɘA�������A�X�C�b�`���O�̎葱�����s���悤�Ăт����Ă���B ��ʉƒ�ɂ�����X�C�b�`���O�̎葱���i���̏����d�C���Ǝ҂Ɠd�C�̋����̂��߂̌_������Ԏ葱���j�ł́A����_����s�����������d�C���Ǝ҂Ǝ葱��������Α����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c�A�M�����A�������H�̑��x������CO2�r�o�팸�ɗL���ƕ� �h�C�c�A�M�����iUBA�j�́A�A�E�g�o�[���i���������ԓ��j�ő��s���x�𐧌������ꍇ�̉������ʃK�X�iGHG�j�r�o�팸���ʂ̎Z�茋�ʂ����\�����B ����ɂ��ƌ��ʂ͑傫���A�Ⴆ�Α��x����������100�L�����[�g���ɂ����GHG�r�o�ʂ�CO2���Z�ŔN��540���g���A����120�L�����[�g���ł͔N��260���g���A����130�L�����[�g���ł��N��190���g�����팸�ł���Ƃ����B ���̌��ʂ́A��p�ԂƏ��^���p�Ԃ̔R������f�[�^�A����јA�M���H�������̃A�E�g�o�[���ł̑��x�f�[�^�Ɋ�Â��Čv�Z���ꂽ�B 2018�N�̃f�[�^�ł́A���x������120�L�����[�g���ɐ��������ꍇ�̔r�o�팸����6.6%�ɂȂ�BUBA�́A���x�������A�^�A����̑��̋C��ی��Ɣ�ד��Ɍ����I���Ƃ��Ă���B�Ⴆ�A�S���ݕ��A���̋�����������H�̊J����200���g���̔r�o���팸�ł��邪�A�����ɐ��\�����[���̓������K�v�ŁA���̎�����2030�N�ɂȂ�B����A���s���x�����́A�����̌��ʂł����Ă����{�ɔ�p�͂قƂ�ǂ����炸�A�������Ɏ��s�Ɉڂ����Ƃ��ł���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���������������u�n�����g���̂��Ƃ��b�������Ȃ�I�v�����������������̓����z�M �����������̉������u�Ƃ������ɘb�������Ȃ�I�n�����g���̃��A���v�̃C���^�[�l�b�g�z�M���n�߂��B �uYoutube�v�Ŗ����Ō��邱�Ƃ��ł���B�����3��13���ɐ��z�M����A�e�[�}�́u�n�����g���̃E�\�H�z���g�H�v�B ���������n���������Z���^�[�������Z���^�[���̍]�琳��������B��45���Ԃ̐��z�M�ł́A�����҂Ƃ����ڂ��Ƃ�B�u�Ȋw�҂͉��g���͎~�߂��Ȃ��Ǝv���Ă���H�v�Ƃ̎���ɂ́u������߂Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ԃł͂Ȃ��B�l�Ԃɂ�鉷�����ʃK�X�̔r�o�ʂ����炵�Ď~�߂܂��傤�v�ƌĂъ|�����B �z�M�͂���2���\��B�����3��18���A�e�[�}�́u���g�����ă��o���́H�v�B3��ڂ�3��23�� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���u2030�N�܂łɃJ�[�{���E�l�K�e�B�u�ɂȂ�v�ă}�C�N���\�t�g �ă}�C�N���\�t�g��2030�N�܂łɁA�u�J�[�{���E�l�K�e�B�u�v�ɂȂ�Ƃ\���A�J���x���Ƃ���10���h���𓊎�����Ɣ��\�����B �J�[�{���E�l�K�e�B�u�Ƃ́A�������ʃK�X�r�o�ʂ�������CO2���������邱�ƁB2012�N�Ɂu�J�[�{���E�j���[�g�����v��B�����Ă��邪�A�ԐړI�Ȃ��̂ł��������߁u�s�\���v�ł���A�u��C����Y�f���������邱�Ƃ��}���ł���v�Ƃ��Ă���B ���Ђ͂܂��A�u2050�N�܂łɁA1975�N�ݗ��ȗ��A���ڂ܂��͓d�͏���ɂ���Ĕr�o���Ă������ׂĂ̒Y�f����������v���Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���B ���v��ł́ACO2�i���З\�z��1600���g���j�r�o�ʂ��A�T�v���C�`�F�[�����܂߂Ĕ����ȏ�팸����B�r�o�ʍ팸�̎�i�Ƃ��ẮA�d�͏����2025�N�܂łɍĐ��\�G�l���M�[�����A2030�N�܂łɐ��E�̕~�n���Ŏg�p����Ԃ����ׂēd�C�����Ԃɐ�ւ���\�肾�B����ɁA����4�N�Ԃ�10���h���𓊎����A�Y�f�̍팸�E�����̋Z�p���x������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�[�^�q�ɂł����d���郂�W���[��2�������A���Z���T�[�̉ғ����\ ���R�[�́A�����Ɩ��ł����d�ł��鑾�z�d�r���W���[���\�����B ���\���ꂽ���W���[���͐F�f�������z�d�r���W���[���ŁA����Ȍ��ł����d�\�B�����A�����R�X�g�Ȃǂ̓A�����t�@�X�V���R���Ɠ����x�ŁA����A�Z���V���O�f�o�C�X�̓d���Ƃ��Ă̊��p�������܂��B ���Ђɂ��ƁA�����������W���[���ɂ͔��d�����ɉۑ肪���������A�����i��10�Z���`�l���ȉ��̃T�C�Y�ŁA������CO2�Z���T�[���ғ������邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �܂��]���̐F�f�������z�d�r�͉t�̌^�ŁA�d���t��p����d�r���L�̉t�R��╅�H�ȂLj��S����ϋv���ɉۑ肪�������B����A���Ђ͓d���t���ő̍ޗ��݂̂Ő��i���\�����邱�Ƃʼnۑ�����������B�Ȃ��A�ő̌^�̐F�f�������z�d�r���W���[���̔����͐��E�ŏ��߂āB �Ɠx�̒Ⴂ�������̔g���ɂ���������L�@�F�f��I�肵�����ƂŁA�q�ɂ�H��ȂǁA�Ɩ����狗���̂���悤�ȏ\���Ȗ��邳���m�ۂł��Ȃ��ꏊ�ł��A�������̔��d���\�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����[�O���i�^���Y�o�C�I�W�F�b�g�R���̎��p���Ɍ����đO�i ���[�O���i�́A���Ђ��̗p���Ă���o�C�I�W�F�b�g�R�������v���Z�X�����ەW������@�ւ̐V�K�i���擾���A���Y�o�C�I�W�F�b�g�R���̖��ԍq��@�ւ̓��ڂ��\�ɂȂ����Ɣ��\�����B ���Ђ́A�~�h�����V�̑�ʔ|�{�Z�p����ՂƂ���H�i�≻�ϕi�̊J���E�̔�����|�������ŁA�o�C�I�R���Ɋւ��錤����i�߂Ă���A2018�N10���Ƀo�C�I�W�F�b�g�R�����̐������v�����g��z�������B�����ʁF125kL/�N�B ���̃v�����g�ɂ́A�č��̐Ζ��֘A�W���C���g�E�x���`���[�ƃG���W�j�A�����O��Ƃ������J�������v���Z�X���̗p����Ă���B����A�v�����g�Ƀ��C�Z���X��t�^����G���W�j�A�����O��Ƃ����ۋK�i�̐\�����s���A�V�K�i�̎擾�����������B�K�i�ɏ������Đ������ꂽ�o�C�I�W�F�b�g�R���́A�q��@��G���W���̉��C��K�v�Ƃ����A�]���̔R�����ւł���u�h���b�v�C���v�R���̗v�������Ă���A��փW�F�b�g�R���Ɋւ���ʒB�̈ꕔ�����E�{�s���o�āA�����g�p���\�ɂȂ����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���Z�u�����u�G�R�o�b�O�ɂȂ�n���J�`�v���� �Z�u��-�C���u���̓G�R�o�b�O�ɂȂ�n���J�`��s���̃Z�u��-�C���u���Ŕ�������B �����Ɏ�����̃e�[�v�������В��^�C�v�i����ō���638�~�j�́A�傫�����c45cm�~��35cm�B���n�̃X���b�g������������ɂȂ��^�C�v�i��550�~�j�͏c36cm�~��24cm�B ���{�͂V������v���X�`�b�N�����W�܂̗L�������`���Â���Ƃ��Ă���A�����ɔ�ׂăG�R�o�b�N�̌g�ї����Ⴂ�j���ł��C�y�Ɏ��Ă�悤�A�n���J�`��ό`���ăG�R�o�b�O�ɂł���悤�ɂ����B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
| ���������̊��S�o�b�e���[�D�A�f�r���A�T�̃��`�E���d�r�̗p �f�r���A�T�́A���А��̎Y�Ɨp���`�E���C�I���d�r���A�哇���D���������^�q���n�߂��������̊��S�o�b�e���[���i�D�̓��͌��ɍ̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���D�u��-e-Oshima�v�͑S��35m�A���g����340�g���B�~�d�r�݂̂͌��Ƃ��邽�߁A�q�s���E�┑���Ƃ���_���Y�f�iCO2�j��r�o���Ȃ��B���D�̃o�b�e���[���i�V�X�e���Ŗ�600�L�����b�g���̑�e�ʃ��`�E���C�I���d�r����d�����u�Ƃ��Ďg����B���d�r�͍q�s�p�̓��͌��ȊO�ɁA�ʐM��q�C�A�����@��A�Ɩ��A�Ȃǂɂ��d�͂���������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���r�c�f�����i�͂P�������̒����^���t�{ ���A���f����C��ϓ���Ȃ�17���ڂ̎����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�̒B���Ɍ������g��ł��鎩���̂́A�S�̖̂�13���ɂƂǂ܂邱�Ƃ����t�{�̒����ŕ��������B ���t�{�́A��̓I�Ȏ��g�݂𐄐i���鎩���̂̊����ɂ��āA2024�N�x�܂ł�60���Ɉ����グ�邱�Ƃ�ڎw���Ă���A�x�����������Ă����B �����́A�S���̓s���{���Ǝs�撬����1788�c�̂�ΏۂɎ��{�B�S�̖̂�69���ɓ�����1237�c�̂�����B ���̌��ʁA���g�݂��u���i���Ă���v�Ɠ������̂�241�c�́B���g�݂Ƃ��ẮA�����̓����̕����n��Z�������̃Z�~�i�[�̊J�Â̑��A�����̔ł̒n���n�������헪�����{�v��ւ̔��f�Ȃǂ��������������B ����ASDGs�ɊS������Ɠ������͖̂�58���B���t�{�́A���ۂ̍s���ɂȂ����Ă��Ȃ�����Ȃǂ��A�u��̓I�ɂǂ����Ă����̂�������Ȃ������̂������v�ƕ��́B ����A��i�I�Ȏ��g�݂�i�߂�uSDGs�����s�s�v�̑I��ȂNJ֘A�{���i�߂�B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| �����{���c�^18�Έӎ�����(�e�[�}�F�C��ϓ��ɂ���)�̌��ʂM ���{���c�́A��21��u18�Έӎ������v�̌��ʂ����\�����B ����A�u�C��ϓ��ɂ��āv���e�[�}�Ɍf���A���g���̌�����X�N�A���g����̒S����A�p���������芪�����ȂǂɊւ���ݖ�𗧂Ă��������s��ꂽ(���{���ԁF2019�N12��6���`9��)�B�N��E���ʂ��ϓ��Ɋ���t�������v1,000�l�̉��W�v�����Ƃ���A���g���̎�Ȍ����͐l�Ԃ̎Љ���ɔ����������ʃK�X�̔r�o�ł���(63.7%)�A���g���̃��X�N��m���Ă���(67.0%)�A���{�͓�_���Y�f�r�o�ʂ��팸���ׂ���(68.8%)�A���g����͎Љ�S�̂Ői�߂�ׂ�(48.8%)�A�p������ɂ�������{�̍팸�ڕW�͏\���ł͂Ȃ�(29.4%)�A�g�����v�đ哝�̂̃p�����肩��̗��E�ʍ��͗����ł��Ȃ�(38.4%)�A�����g���Ɍ������O���^����̍R�c�s���Ăъ|���ɋ�������(29.6%)�Ƃ��������ʂɂȂ����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���H��ݔ��̔r�M���Ԓ����������\�A�����p�M�̊��p�ŏȃG�l���𑣐i NEDO�Ɩ����p�M�G�l���M�[�v�V�I���p�Z�p�����g���iTherMAT�j�́A�M���p�ʂ̑���15�Ǝ�ɑ��A�����p�M�̔r�o�⊈�p�Ɋւ���A���P�[�g�����{�B�S��1273���Ə����瓾��ꂽ�͂��A���ɂ܂Ƃ߂��B ���ł́A15�Ǝ�̔r�K�X�M�ʂ̍��v��743�y�^�E�W���[���^�N�iPJ�^y�j�ŁA���̂���76���ɑ�������565PJ�^y��200�������̔r�K�X�M�ʂł��邱�Ƃ����������i�y�^�E�W���[����1000���W���[���B1�W���[����0.239�J�����[�j�B ���̂��Ƃ���A200�������̖����p�M��L���Ɋ��p����Z�p���J�������A�����̎Y�ƕ���̃G�l���M�[����ʂ�傫���팸�ł���\��������B NEDO�͍���A�ȃG�l���M�[���ʂ���ւ̉e���x�A�����p�M���p�Z�p�̓��������b�g�╁�y�g�傳���邽�߂̕���m�ɂ���B����ɁA200�������𒆐S�Ƃ��関���p�M��L���Ɋ��p����Z�p���J�����A�Y�ƕ���֕��y������Ȃǂ��āA�ȃG�l����i�߂Ă����B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���r���̗�[�Ɏg���z���Ⓚ�@���ԍڌ����ɉ��p�A�R��12�����P�ڎw�� NEDO�Ɩ����p�M�G�l���M�[�v�V�I���p�Z�p�����g���A�A�C�V�����@�A�Y�������A������w��2020�N1��23���A���p�Ԃ̗�[�Ƃ��ē��ڂł��鏬�^�z���Ⓚ�@���J�������Ɣ��\�����B ��ʓI�ȋz���Ⓚ�@�͑�^�V�X�e�������S�ŁA�I�t�B�X�r���̋ȂǂŎg���Ă���B�ԗ��ɓ��ڂ��邽�߂ɏ��^�y�ʉ�����ƂƂ��ɁA���s���̌X��h��Ȃǂ̉e����h���Z�p���J�������B�����Ԃ̔R�������M�G�l���M�[�̂���60���������p�Ŏ̂Ă��Ă���A�M�G�l���M�[���z���Ⓚ�@�ɂ���[�Ɋ��p�ł���A�N�Ԃ�12���̔R����オ���҂ł��A�G���W���Ԃ̗�[�^�]���̔R���啝�ɉ��P�ł���Ƃ��Ă���B 2020�N1������z���Ⓚ�@�����p�Ԃɓ��ڂ��ĕ]�����J�n�A�Ԏ����̋̐��\��ԗ��ɓ��ڂ���ۂ̉ۑ��o���B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���x���`�}�[�N���x�������Č��\�A�ڕW���B�ł��w�͂�]�����邵���ݓ��� �o�ώY�ƏȂ́A�Y�ƕ���ɂ�����x���`�}�[�N���x�̌������̕������Ȃǎ��܂Ƃ߂����i�āj���������B �E�Y�ƕ���̌��s�x���`�}�[�N�w�W�̖ڕW�N�x��2030�N�x�u�Y�ƕ���ƋƖ�����i�ݎ������Ɓj�ɂ�����x���`�}�[�N���x�v�̌������̊T�v�Ƃ��āA�������v��ƒ������p���A�x���`�}�[�N�ڕW��B���ł��Ă��Ȃ����Ǝ҂��ڕW�B���Ɍ����ēw�͂���ߒ��ɂ��Ă͕]�����A�⏕�����̎x�����s�����Ƃ��Ă��Ă���B �܂����Ǝ҂Ɛ��{��PDCA�T�C�N���ŁA�ȃG�l���������邱�Ƃ������E�u�ȃG�l�|�e���V�������v�c�[���v�̓��쌟�Ǝd�l���P�𑁋}�ɍs���B �E�H�ꓙ���f��ƒ������v��쐬�w�j�̌����� �E���ȑ����͎g�p�����R���̌W���Œ���� �E���Ǝ҃N���X�����]�����x��S�]���̕]��������i�� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����H��^���z���G�l���M�[�����w�G�l���M�[�Ƃ��Ē�������R���d�r���J�� ���É��H�Ƒ�w�̌����O���[�v�́A���z���G�l���M�[�����w�G�l���M�[�Ƃ��Ē�������R���d�r���J�������Ɣ��\�����B �]���̔R���d�r�͐��f�K�X��R���Ƃ��Ă���A�������ɐ������r�o���Ȃ����_�͂�����̂́A�댯���������A�܂��A�d�C�͒~�����Ȃ������B�������O���[�v���J�������̂́A�A��������������d�g�݂ɗނ������w�����ɂ��A���d�E�~�d����R���d�r�ŁAAQDS (9,10-�A���g���L�m��-2,7-�W�X���z���_��)�ɑ��z�����Ǝ˂���ƁAAQDS-H2�Ƃ������q�ɕϊ�����A�d�r�S�̂Ƃ��ď[�d��ԂƂȂ���́B ���Ǝ˂����łȂ��A�O���d����p�����d�C���w�����ł��\�ł��邱�Ƃ���A�X�}�[�g�O���b�g�Ƃ̒��a���������A���z���Ǝ˂Œ��ڏ[�d���邾���łȂ��A���͂�n�M�Ŕ��d�����d�͂������\�ƂȂ�B�����_�ł́A�o�͓d�͂�0.5V���x�ł��邱�Ƃ���A�N�d�͂̌���┽���ߓd���̒ጸ���ۑ�ƂȂ�Ƃ����A����AQDS�̉��ǂ�Z���\���̍œK�����s�����ŁA���p���Ɍ��������������������Ă����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���r�����h�E�[������������Z�p�v�V���{�̐V�헪������ ���{�́A�G�l���M�[�E������ɂ�����Z�p�v�V�ŁA���{�Ɛ��E��CO2�r�o�팸��ڎw���u�v�V�I���C�m�x�[�V�����헪�v�����肵���B ���E�̃J�[�{���j���[�g�����A����ɂ͉ߋ��̃X�g�b�N�x�[�X�ł�CO2�팸�i�r�����h�E�[���j���\�Ƃ���v�V�I�Z�p��2050�N�܂łɊm�����邱�Ƃ�ڎw���B ���̐헪�́A��̓I�ȍs���v��i5����16�ۑ�j���������u�C�m�x�[�V�����E�A�N�V�����v�����v�A������������邽�߂́u�A�N�Z�����[�V�����v�����v�A�Љ�K�p�Ɍ����Ắu�[���G�~�b�V�����E�C�j�V�A�e�B�u�Y�v�ō\�������B���E�G�l���M�[�̋Z�p�v�V��10�N�Ԃ�30���~�𓊎� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2020/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�d�@�A�u��Ɩ��v��ʎY���R�����Č� �O�H�d�@�́A��⎩�R����\���ł���LED�Ɩ��u��Ɩ��v�̗ʎY��2020�N�x���Ɏn�߂�B�����i�͉����̉��K������ɑ����̎��v�������܂�Ă���B �u�����Ɩ��p�̃����v�����Y���Ă����H�ꂪ�A2020�N3���ɏI���\��B�������C���̐Ւn���Ɩ��p�ɏ[�Ă�v�悾�B ���Ђ�2018�N�ɐ�Ɩ��̋Z�p���J���B�p�l���̓����ɐ�����d�g�݂Ɠ����u���C���[�U���v���N�������U���̂�����LED���Ă邱�ƂŔ��������U�����Ő��\������B ���݂͐��i�̔��^���BLED�������p�l���̒[�ɔz�u����������̗p���Ă���A�Ɩ��\��������100�~�����[�g���ȉ��ɗ}�������B�������p�l���㕔�ɔz�u����]�������ł͐��i�̑�^�����ۑ肾�����B�����E���F�@�\�������Ă���A�[�Ă��⒩�Ă���\���ł���B������3000���[�������x���邽�߁A�f�B�X�v���[���ƈقȂ�P�̂ŏƓx���m�ۂ��邽�߂̏Ɩ��Ƃ��Ďg�p�ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ƊE�g�b�v�N���X�̍������AR32��}�̗p�̋��q�[�g�|���v�`���[���� �O�H�d�H�͉Ăɂ����āA���q�[�g�|���v�`���[40�`70�n�̓��f����4�^�C�v���s�������B �V�����J������e�|3D�X�N���[�����k�@�ɓƎ��Z�p��g�ݍ��킹�A�ƊE�g�b�v�N���X�̃G�l���M�[��������iCOP�j�������B�����ɁA��n�����g���W���iGWP�j������}R32���̗p�����B���Ђł͂������r���̗≷���ݔ���r���Ȃǂɓ������邱�Ƃɂ��A�啝�ȏȃG�l���\�ɂȂ�Ƃ��Ă���B 60�n�̓��f����3.46�i��i��p�����j��COP�A70�n�̓��f���ł�3.33�A60�n�̓��f���ł͍����K�X�ۈ��@�̓͏o���s�v�B ��}�Ƀ��[���G�A�R���ȂǂŐ�s���y����R32�iGWP675�j���̗p�B�]���ɔ�ׁA��}������28%���AGWP�͖�3����1�ACO2���Z�l��77%���ƂȂ����B����ɁA70�n�̓��f�������C���A�b�v���邱�Ƃɂ��A����܂ŕ�����ݒu���K�v���������̂�1��ōςނ��߁A�ȃX�y�[�X���������邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���J�l�J�Ƒ听���݁A�O�ǂ�Ŕ��d�ł���O���V�X�e�����J�� �J�l�J�Ƒ听���݂͌����̊O�ǂ�ƈ�̉����������z�d�r���W���[���Ŕ��d����O���V�X�e���uT�|Green Multi Solar�v���J�������B ����܂Ō����̉���Ȃǂɑ��z�����d�ݔ����v�悷��ꍇ�A�ݒu�X�y�[�X�������Ă��邽�߁A���d�ݔ��̓����g�傪����ł������B����A���Ђ́A�听���݂̌��ވ�̌^���z�d�r�̐v�{�H�m�E�n�E�ƁA�Z���Ŋ���̌^���z�d�r�̓������тȂǂ�L����J�l�J�̑��z�d�r���W���[����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�O�ǁE���Ŕ��d���鑽�@�\�ňӏ�����������O���V�X�e�������������B ����A�{�V�X�e����s�s�^ZEB����������n�G�l�Z�p�Ƃ��āA���o�c�ɐϋɓI�Ɏ��g�ފ�ƁABCP�����������ƁA�ЊQ���̊������_�ƂȂ�����{�݂Ȃǂɑ��A�ϋɓI�ɒ�Ă��Ă����Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���z���G�A�_�N�g�V�X�e���ŃR�X�g�팸 ���{�}�O�l�e�B�b�N�X������Ђ́A��DuctSox�Ђ̃t�@�u���b�N�G�A�_�N�g��̔��B ��R���̃|���G�X�e������ȑf�ނƂ���G�A�_�N�g�ŕz���Ȃ���UL2518�ABritish Standard BS 5867�AGB8624�Ƃ������e���̖h�Њ���N���A���Ă���A�H��⏤�Ǝ{�݂̋{�݂ŗv�������d�l���Ă���B ��ʓI�Ȕ����G�A�_�N�g�ɔ�ׂāA������A���A�ݒu�R�X�g��50�`80���팸�ł��A�y�ʂȂ��߂Ɏ{�H���Ԃɂ��Ă��팸���\�ƂȂ�B�H�i���H�H������ɍR�ۏ������{�������f���Ȃǂ�����B �z�����p���邱�ƂŁA���I�̃��X�N���Ȃ��A���̕t�����}������A�������_�N�g�̂悤�ɋ����������������É����ɂ���^����Ƃ��������_����������B�@�ۂ͐������z�����Ȃ��悤��������Ă���B �_�N�g���m��ڑ�����p��̓W�b�p�[�ɂ��ڑ�����邽�߁A���O���Đ���@�ŊȒP�ɃN���[�j���O�ł��郁���b�g������B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
| ��9��ނ̃Z���T�[�𓋍ڂ��������p��C�i���Ď����j�^�[ �t�H�[�J���|�C���g�́A���A���^�C���Ŏ����̋�C�͂��A��C�i�������������ꍇ�ɃX�}�z�֒ʒm���鎺���p��C�i���Z���T�[�������B���i��39,800�~(�ō�)�B 9��ނ̃Z���T�[�Ŏ����̋�C�����A���^�C���ŕ��͂��A��C�i�����L�^����B����LAN�𓋍ڂ��Ă���B�X�}�[�g�t�H���A�v���A�Ɠd��A�v���ƘA�g�\�B ���ڂ���Z���T�[�͋C���A���x�A�C���A��_���Y�f�ATVOC(���������L�@��������)�APM2.5�A��_���Y�f�A��_�����f�A�I�]���B�X�}�[�g�t�H����p�A�v���ƘA�g�����邱�ƂŁA��C�i���̈������X�}�z�ɒʒm�A�Ώ��@���\�������BIFTTT�Ή��̉Ɠd��A�v���Ƃ��A�g�ł��邽�߁A�{�̃T�C�Y�͖�85�~162mm(���a�~����)�A�d�ʂ͖�278g�B �o�T�uImpress Watch �v |
|
|
| ���I�t�B�X�r�������ɉ��⊴�V�X�e����̔��J�n �A�Y�r���́A�I�t�B�X�r�������Ɏ����҂̕��̊������̈Ⴂ�i�ŗL�̑̊��j�����ꂼ��ɔ��f���ĉ��K�ȋ�Ԃ��������A���Y������ɍv������V�V�X�e���u���⊴�V�X�e���v�̔̔����J�n�����B �V�V�X�e���́A�����҂��Ј��P�[�X�Ɏ��[�\�ȃJ�[�h�^�u���⊴�\���J�[�h�v�́u�����v�u�����v�Ȃǂ̃{�^���ő̊�����\������ƁA�J�[�h�̖����M������A�����҂ɍł��߂��ݔ������A�\���ɉ��������M�������B �܂��A�{�V�X�e���́A�����҂���̗v�����ꎞ�I���P��I���ʂ���@�\�𓋍ڂ��Ă���A�ꎞ�I�ȗv���ł���ꍇ�ɂ͈�莞�Ԍo�ߌ�ɐݒ�l��߂��܂��B�Ⴆ�A�o�Ύ��⒋�H��ȂǑ�ӗʂ��オ���ď��������鎞�ԑт̐\���͈ꎞ�I�Ɣ��ʂ��A��ӗʂ������邱��ɐݒ�l�����ɖ߂����ƂŁA���K����ۂ����܂܋̖��ʂ��Ȃ����Ƃ��ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������s�A2050�NCO2�r�o�����[���헪�����\�u�C���@�s���錾�v�\�� �����s�́A2050�N��CO2�r�o�����[���ɍv������u�[���G�~�b�V���������v�̎����Ɍ������r�W�����Ƌ�̓I�Ȏ��g�݁E���[�h�}�b�v���܂Ƃ߂��헪�����肵���\�����B �����́w�C���펖�ԁx�̕\�����āw�C���@�s���錾�x��\�����A�C���@�������F�����ċ�̓I�ȑ���u����ƂƂ��ɁA���ׂĂ̓s���ɋ����ƍs�����Ăт����Ă����v�Ƃ����B ����u�[���G�~�b�V���������헪�v�̍���ɕ����āA�d�_�I�K�v��3�̕���ɂ��āA���ڍׂȎ��g�ݓ��e�Ȃǂ��L�����u�����s�C��ϓ��K�����j�v�u�v���X�`�b�N�팸�v���O�����v�uZEV���y�v���O�����v�����肵���B �u�v���X�`�b�N�팸�v���O�����v�ł́A2050�N�ɊC�m�v���X�`�b�N�[���̎����\�ȃv���X�`�b�N���p�Ɍ��������[�h�}�b�v��{�����������Ă���B�uZEV���y�v���O�����v�ł́A�����Ԃ����CO2�r�o�����[���Ɍ��������[�h�}�b�v��2030�N�ڕW�̒B���Ɍ�������Ȏ{����܂Ƃ߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���n�����ȂǁA�H�̃J�[�{���t�b�g�v�����g�팸�Ɍ������V��������X�^�C����� �����n�����w�������ق�����2��w����уm���E�F�[�����Ȋw��w�̌����O���[�v�́A�H�̃J�[�{���t�b�g�v�����g�i�ȉ��uCFP�v�j�͂��ACFP�̑��ǂɉ������팸���������B CFP�팸��}�邽�߂ɁA�����E�ؓ��̏�������炵�A�{���E��ؒ��S�̐H�����ւ̓]�����K�v�Ƃ����F�����L�������B�������O���[�v�́A���������H�����ւ̓]���̌��ʂ��ƌv����x���ʼn𖾂��邽�߂ɁA�u�S��������Ԓ����i�����ȁj�v�̃f�[�^��p����CFP�𐄌v���ACFP�̑傫���Ɋ�Â��ăO���[�v�������s���A����ڂ��r���������B ���̌��ʁA���ޏ���ʂɂ��Ă̓O���[�v�ԂɌ����ȍ��������Ȃ��������ACFP�̑����O���[�v�ł̓A���R�[��������َq�ނ̏����A���X�g�������p�p�x���������Ƃ����������B�����̐��тŌ{�����ؓ����S�̐H�����ւ̓]����i�߂�ƂƂ��ɁACFP�̑������тɂ����Ă̓A���R�[����������̒ጸ����}�邱�Ƃ��L���ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���d�C���Ǝ҂̔r�o�W���i2018�N�x�j �u�r�o�W���[���v���j���[�͂قڔ{�� ���Ȃ́A2018�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̊�b�r�o�W���ƒ�����r�o�W���������\�����B ����r�o�҂́A���̌W����2020�N�x�̕Ŏg�p���鍡����\���ꂽ�����ł́A�G�l�b�g��~�c�E���R�O���[���G�l���M�[�ALooop�Ȃǂ̃��j���[�ʂ̒�����r�o�W�����f�ڂ���Ă���B�܂��A�e�Ђ̌W���̂������j���[A�ł́A������r�o�W���[���i0.00000�g���|CO2�^kWh�j�ƂȂ��Ă���B �p�������SDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�Ȃǂ����������ɁA��Ƃ�ESG�i���E�Љ�E�K�o�i���X�j�v�f�ɔz������ESG�������L�����Ă���B �����������A�����ׂ̒Ⴂ�d�C�̃j�[�Y�����܂��Ă���A�����I�ɍĐ��\�G�l���M�[100���ŁA������r�o�W���[���ƂȂ�d�̓��j���[�����d�C���Ǝ҂������Ă���B 2018�N�x�̎����ł́A������r�o�W���[���̓d�̓��j���[�����d�C���Ǝ҂́A2017�N�x��20�Ўォ��قڔ{����35�ЂƂȂ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����{�͐E����Ƃ���������! �d�����͂��ǂ薽�����u�����v�Ƃ́H WHO��2018�N�Z��ƌ��N�ɂ��ĐV�����K�C�h���C���\���A�u�����v���ċz��n��S���ǎ����̜늳�E���S���X�N���グ��ƌ��y�B���N�ւ̈��e�����狏�Z�҂���邽�߁u�~�G�̎������x��18���ȏ�i�q�ǂ��ƍ���҂͂���ɒg�����j�v�Ƌ������������B ���{�ł͖k�C���́A�~�G���S���������S���ň�ԒႢ�B���{�̒f�M�Z��̕��y���͖�24���B�k�C����80�������B�~�G�̎��S�������Ƃ̊֘A��������B ���y��ʏȂ̒����ł́A���Ԃł̓~�G���x�̒��镽�ς́A16.7���B18�������Ă��Ȃ��Ƃ�6���ȏ�B�E�ߏ��Ɏ����Ă�9����������Ă��Ȃ��B����Ŗk�C���ł͓~�̎�����21�x�ɕۂ���Ă���Z��قƂ�ǂ��B �o�T�uAERA�v |
|
|
| �����w�@��ȂǁA���Ɛ�����u���f�v�������鑽�E���������J�� ���w�@��w�Ȃǂ̌����O���[�v�́A�����Ǝ˂��邱�ƂŐ������Đ��f�������鑽�E������(MOF)���J�������B MOF�́A���f�≷�����ʃK�X�̒����╪�����ɗL�p�ȍޗ��Ƃ��Ē��ڂ���Ă��邪�A�d�C�𗬂��A���G�l���M�[���z������悤�Ȕ����̐��������̂͂���܂Ŗ��������B����ŁA�������܂�MOF�̍����͓���Ƃ���Ă���A���̓����͏\���ɗ�������Ă��Ȃ������B ����A�Y�f�ƒ��f���܂�����������p���邱�ƂŁA�����܂�MOF�̊J���ɐ��������B����MOF�̍\���́A���P�x���Ȋw�����Z���^�[�̕��ˌ�(SPring-8)��p���������ɂ�薾�炩�ɂȂ�A�܂��֊w�͂���MOF�̍E�ɂ͐��݂̂���荞�܂�A�A���R�[���Ȃǂ̗L�@���q�͓���Ȃ����Ƃ��m�F�����B����ɑ���w�Ƌ����ŁA����MOF�������z�����邱�Ƃœd�C�𗬂��A�E�Ɏ�荞�܂�Ă��鐅�𐅑f�ɕ������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c�A�M�����A2019�N�͍Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�����߂ĐΒY���������ƕ� �h�C�c�A�M����(UBA)�́A2019�N�̍Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ʂ͑O�N���8%�������A�ΒY�ɂ�锭�d�ʂ����߂ď���Ƃ���Đ��\�G�l���M�[���v��ƕ���̑���l�����\�����B �Đ��\�G�l���M�[�ɂ�荇�v��2430��kWh�̓d�͂����d����A�d�͏���S�̂�42%���������錩���݂��Ƃ����i2018�N��37.8%�j�B �m��E���㕗�͔��d��1260��kWh�i�O�N��15%���j�A���z�����d�͖�470��kWh�i��2%���j�A���͔��d�͖�190��kWh�i��4%���j�A�o�C�I�}�X�E�����n�p�����̔��d�͌v500��kWh�i�O�N�����⌸���j�ƂȂ�B ����̑���ł́A���㕗�͔��d�̐L�т��ߋ�20�N�ԂōŒᐅ���ɂȂ�\�����w�E���ꂽ�B2019�N�̐V�K�ݔ��̔��d�e�ʂ͖�700���K���b�g�ő����d�e�ʂ̑����͑O�N��1%�ɂƂǂ܂�B�V�K���������Ȃ���Β����I�ɗ��㕗�͔��d�ʂ͑啝�Ɍ�������\��������A�m�㕗�͔��d�ݔ��̑������Đ��\�G�l���M�[�@�̖ڕW��B�����Ă��s�\�����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2020/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���Ј�������������C�ŋN�����A���Y��UP �_�C�L����NEC�A�I�t�B�X�p�V�X�e���J�� �����ł́B�����Ȃ�₷���^�X�N�i2�P�^�̑����Z�̈ÎZ�j���s���Ă���l�̊o���x�ƁA�E�Ɩ��E�A���}�i�F���j�̎h���̊W�ׂ��B ���̌��ʁA�̉��x���ꎞ�I�ɉ�����i27����24����27���j�Ɗo���x�������ɏオ��A�Ɩ��h���i�Ɠx150���N�X��1500���N�X��150���N�X�j��A���}�ɂ��h���i��30���ԘA�������j�ł��A�o���x��������x�㏸���邱�Ƃ����������B �܂��A�o���x�̕ω��́A�܂Ԃ��̗h�炬�i�܂Ԃ��̏d���ɑς��铮���j�ɒ��ڂ��邱�ƂŁA���b5�t���[���̉f���ł����x�悭�o���x�𐄒�ł����B �����̌��ʂ���ɁA�܂Ԃ��̊J���������疰�C�̒��������m���A�E�Ɩ���g�ݍ��킹���h����^���鐧��V�X�e���̃v���g�^�C�v���\�z�B 7�����痼�Ђ̌��ؗp�I�t�B�X�Ŏ������̊o���x�f�[�^���擾���ċE�Ɩ��̊�������s���t�B�[���h�������J�n���Ă���B �o�T�uITmedia �v |
|
|
| ���d�r�s�v�A�����Ɩ��Ŕ��d���f�X�N��IoT������V�[�g���J���^��l ��l�̓Z���N���X�A�^�O�L���X�g�Ƌ����ŁA�����Ɩ��Ŕ��d���A�d�r�������s�v��IoT�V�[�g���J�������Ɣ��\�����B ����IoT�V�[�g�́A3�Ђ������J�������V�[�g�^�̕��ʔF�r�[�R���u�y�[�p�[�r�[�R���v�ɁA�V���[�v���J���������E�ō����x���̔��d���������������F�f�������z�d�r��d���ɍ̗p�����r�[�R�����W���[���𓋍ڂ��Ă���B�����̔�퓔�̉��Ȃ�50���N�X���x�̈Ï��ł����肵�ē��삷��B �u�y�[�p�[�r�[�R���v�́A�\�ʐ�cm��ɋ����d�g���锖�^�r�[�R���ŁA�f�X�N��e�[�u���Ɏ��t���邾���ŁA���݂̉Ƌ��IoT�����邱�Ƃ��ł���B���̐��i�����̑��e�Ƃ��āA�v���X�́A�I�t�B�X�ɂ����鑽�l�ȓ��������T�|�[�g������ȊǗ��V�X�e���ɑΉ������A���p���Ɍ��������؎������J�n����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�l�e�N�ALP�K�X+���z��+�~�d�r�̃n�C�u���b�h���d��R�X�g�ōЊQ�� ���Ђɂ��ƁA���̃V�X�e�����_��d��250kW�̌ڋq����������ꍇ�A���z�����d�E�~�d�r�ELP�K�X���d�@�̕���^�]�ɂ��d�C��̑啝�ȍ팸�ƁA��d��140kW�̓d�͂��ԋ����ł���Ƃ����B �⏕���K�p���̔�p�͖�4000���~�B���҂���铊�������10�N�������Ƃ����B ���펞�́A�����ɂ͑��z���Ŕ��d�����d�͂��g�p���]�蕪�͒~�d�r�ɏ[�d�A���v��ɒ~�d�r���狋�d���A�s�����͓d�͉�Ђ���w������u���Ə���^�v�̑��z�����d�ݔ��Ƃ��ė��p����B ����ŁA��d�����������ۂɂ́ALP�K�X���d���ғ������A�����Ԉ���d�͂���������I�t�O���b�h�^�p�ɐ�ւ���B���Ǝ��͕��펞�Ɠ��l�A���z���Ŕ��d�����d�͂�����A�]�蕪��~�d�r�ɒ��߂�B�d�͂��s������ꍇ��LP�K�X���d�@���狋�d����B���v��∫�V�͒~�d�r��LP�K�X���d�@�œd�͂���������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������A100�����ЍăG�l��2025�N�uRE100�v�B���ց^�q���[���b�N �s���Y���̃q���[���b�N�́A11���ɁuRE100�v�ɉ������A100�����ЕۗL�Đ��\�G�l���M�[�ݔ��ɂ��A2025�N�ɍăG�l100���ł̎��Ɖ^�c�uRE100�v��B������Ɛ錾�����B ����܂Ŕ|�������z�����d���Ƃ̃m�E�n�E�ƃl�b�g���[�N�ɂ��A2020�N�����FIT���z�����d�ݔ��̊J���𐄐i����B2020�N�ȍ~�ɁA�J��������FIT���z�����d�ݔ��ɂ��d�͂��O���[�v��Ђ̏����d�C���ƎҁiPPS�j�ɂ��A�{�Ѓr�����͂��߁A�q���[���b�N�O���[�v�̃I�t�B�X�������邱�ƂŁA���ЕۗL�̔�FIT�d���ɂ��uRE100�v�B����ڎw���B ���O���[�v�ł́A2012�N���瑾�z�����d���ƂɎQ�����Ă���B�r���̉���ɑ��z�����d�p�l����ݒu���A���z�����d�ɂ��CO2�r�o�ʍ팸�Ɏ��g��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E���E�C�m�ł����������郌�W�܂��J���A���Ăɔ̔��ց^�����H�� �y����ރ��[�J�[�̕����H�Ƃ́A�C�m�ł��y��ł��������̓����ɂ�萶�������郌�W�܂��J�������Ɣ��\�����B2020�N7�����琔�ʂ����肵���̔��J�n��ڎw���B ����J�������y��E�C�m�����𐫃��W�܂́A�����@�ւŐ����𐫂��m�F����A���݁ATUV�I�[�X�g���A�F�̎擾��\�������B�F�̗v����30���̊C������6�J���ȓ���90���ȏ㐶�������邱�Ƃ��B ���݁A���E�I�Ȑ����𐫃|���}�[�̎������N�����Ă���A���Ђ́A�y��E�C�m���𐫃��W�܂̗ʎY���ɂ��ẮA��������̗���������҂��ď����g�債�Ă����\��B�܂��A�g�p�̈�g���ڎw���A���s���ē��ɗp������V�[�����g�̊J���ɂ����g�ލl�����B���Ђ͂���܂ł��A���Ή��^���i�Ƃ��āA�g�E�����R�V�Ȃǂ̐A�������������Ƃ��鐶���𐫎����ō�����܁u�G�R���b�N�X�v��W�J���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��ESCO���i���ASDGs�Ή����x���^�R���\�[�V�A���𗈔N4���ݗ� �����\�����́A�ȃG�l��ʂ���SDGs�����ɍv������ӗ~���������BESCO�E�G�l���M�[�}�l�W�����g���i���c��iJAESCO�j��2020�N4���A�uSDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�R���\�[�V�A���v��ݗ�����B ���R���\�[�V�A���̓G�l���M�[���𒆐S�Ɋ�Ƃ̃r�W�l�X�ɂ�����SDGs�̊��p���@��͍�����B�C��ϓ��ւ̖��ӎ��������A�V���ȃr�W�l�X�`�����X�ƍl�����Ƃ��㉟������_���BJAESCO����ȊO�ɂ����L���Q�����Ăъ|���ASDGs�B���ւ̑����͂�[�߂����l�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����Ə���̍ăG�l���l�A�ȒP�ɏ؏����^�f�W�^���O���b�h �f�W�^���O���b�h�́A���Ə�����Đ��\�G�l���M�[�̊����l�������悭�؏������A����ł����@���m�������Ɣ��\�����B �u���b�N�`�F�[���i���U�^�䒠�j�Z�p���g���A�ƒ�⎖�����Ŏ��Ə�������z�����d�ʂȂǂ��v���B�����ӏ����܂Ƃ߂āA�����^�c����uJ-�N���W�b�g�v�̔F������悤�ɂ���B��P�w�Ƃ��ē����K�X�O���[�v�A���M�K�X�A�������쏊���Q����\�������B �V��@�́A�d�̓f�[�^�Ȃǂ��v�����邽�߂ɊJ������ICT�@����e�n�̑��z���p�l���Ȃǂɐݒu����B���Ə�������d�ʂ́A�����I�Ƀu���b�N�`�F�[���ɋL�^����A�l�������f�[�^�������悭���S�ɊǗ��ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���l�ށE���ԕs�����ۑ蒆����Ƃ̖�9�����ȃG�l�ɊS�A�֓��o�ώY�Ƌ� �֓��o�ώY�Ƌǂ́A������Ƃ̏ȃG�l���M�[�ւ̎��g�݂ɌW����Ԓ����̌��ʂ��Ƃ�܂Ƃ߁A���\�����B ������Ƃ̏ȃG�l���M�[�ւ̊S�͍����A�ȃG�l�Ɋւ�����g�݂��s���Ă���A�܂��͎��g��ł��������Ƃ����͖�89�����߂��B���g�݂��s���Ă����Ƃ̑����Ŏ��g�݂��R�X�g�팸���Ɍq�����Ă����B �܂��A���g��ł��Ȃ����R�Ƃ��āA�l�ޕs����J�́E���ԕs�����ۑ�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���������ƂȂ����B���܂��܂Ȓc�̂őΉ����Ă���u�ȃG�l���M�[�f�f�v�ɂ��ẮA�m��Ȃ��Ɖ���������Ƃ�45���������B����ŁA53�����ȃG�l���M�[�f�f��F�m���Ă������̂́A27�������p�������Ƃ��Ȃ��A���̗��R�Ƃ��āu�c�Ɗ��������肻���v�u�ǂ��ɘA����������ǂ��̂�������Ȃ��v�Ƃ̉����������B �ȃG�l���M�[�ւ̓����ł���G�l���M�[�g�p�̌����鉻�ɂ��ẮA68���̒�����Ƃ����{���Ă������̂́A24%�̊�Ƃł͂�������p���Ă��Ȃ��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�������ʃK�X�팸�ڕW�ɂ������p�͂����Ə��Ȃ��v����Ȃnj����ʼn� ���{�́A���g����̒����I�ȖڕW�Ƃ���2050�N��GHG�r�o�ʂ�80���팸����Ƃ����ڕW���f���Ă���B���̖ڕW�B���̂��߂ɂ͍ăG�l��ʓ����Ȃǂ̃G�l���M�[�V�X�e���̑啝�ȕϊv���K�v�Ƃ���Ă���B ���̍팸������{�����ꍇ�A�}�N���o�ϑ����iGDP�����j��2�`8���Ƃ������l������AGHG�팸�͑傫�Ȍo�ϕ��S�Ƃ����������������B �������A����A�V�������v�ł́A�}�N���o��GDP�ւ̉e����0.8���ƂȂ�A�}�N���o�ϑ����i��p�j���]���̒l�Ɣ�ׂđ啝�ɏ��������Ƃ��킩�����B���̏ꍇ�A���́E���z���͍��킹��50�����x�̓d�͂�d�����ƂɂȂ����B�܂��A���ԒP�ʂ���P�ʂł̕ϓ��ɑΉ����邽�߂̒~�d�r��f�}���h���X�|���X�Ȃǂ��K�v�ƂȂ�A2050�N�ɂ͌��݂̗g�����d�̔��d�e�ʂ���قǂ̒~�d�r�̓������K�v�ƂȂ邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���f���}�[�N�A2030�N�܂ł�1990�N��70%�r�o�팸����C��@���� �f���}�[�N�C��E�G�l���M�[�E�����Ȃ́A�����c��Ŗ@�I�S���͂̂��鍑�ƋC��@�������ꂽ�ƕ��B���̎�ȓ��e�́A 1�j�������ʃK�X�r�o�ʂ�2050�N�܂łɎ����[���Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���A2030�N�܂ł�1990�N���70%�팸 2�j10�N��܂ł̖ڕW��5�N���ɐݒ� 3�j���ׂĂ̕���i�^�A�A�_�ƁA�G�l���M�[���j�ŒE�Y�f����}���̓I�����[�u���܂Ƃ߂��C��s���v��N�쐬 4�j���v��̎�g���u�C��]�c��v�����I�ɕ]�� 5�j���ۊC�^�E�q��֘A�̔r�o���ւ̓����̉e���Ɋւ�������쐬���ł���B �������{�́A���E���̗m��E�B���h�t�@�[���ŃO���[���������������o�����������A�����I���f�ɂ����ċC����l�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����ψ����ݒu����ƂƂ��ɁA����̎����\�ȑ�𐄐i���邽�ߎ�v���ԑg�D��13�̃p�[�g�i�[�V�b�v��������Ă���B���A���v��iUNEP�j�̕ɂ��ƁA�p������̍��ʖڕW�iNDC�j���B������Ă����E�̕��ϋC����3.2���ȏ�㏸����Ɨ\�z����A���}�ȋC��s���̊g�傪���߂��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���u�Ԃ̔p�M��d�C�ɕϊ��\�v�����s�s�傪�V�f�ނ��J�� �����s�s��w�́A���x���𗘗p���Ĕ��d�ł���M�d�ޗ��Ɏg�p�\�ȁu�Y���z�E�f�v��p���āA�]�����300���ቷ�ō����ł���V�f�ނ��J���������Ƃ\�����B �u�Y���z�E�f�v�Ȃǂ̃z�E�f�n�ޗ��́A���������x���ł͍����M�d���\���m�F����Ă��邪�A�u�Ƃ��v�u�Ă��ł܂�ɂ����v�Ƃ������������邽�߁A���p�I�ȃT�C�Y�̕��ނ��쐻����ɂ́A�]���̐��@�ł�2,000���߂��������K�v�������B����J�������V�f�ނ́A���������ɏd�ʔ��10�`15���̋����������邱�Ƃɂ��A�Č����x���1,700���܂ʼn�����ƂƂ��ɁA�d�C�`���x���1.5�{���コ���邱�Ƃɐ��������B ���̍ޗ��́A���p������Ă���M�d�ޗ����y�ʂōd���Ƃ��������������Ă��邱�Ƃ���A����A�����ԃG���W�����͂��߁A�H��̔M�@�֓��ɂ��K�p�͈͂̊g�傪���҂���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2018�N�x�G�l�N��CO2�r�o�ʁA�O�N�x��4.5�����G�l���M�[����͑O�N�x��2.9���� �����G�l���M�[���́A2018�N�x�G�l���M�[�������сi����j�����܂Ƃ߂��B�ꎟ�G�l���M�[���������͑O�N�x��1.9�����B�G�l���M�[���ʂɂ݂�ƁA���ΔR����5�N�A���Ō����������A�ăG�l�E���q�͂Ȃǂ̔ΔR����6�N�A���ő��������B �G�l���M�[�N��CO2�r�o�ʂ�10.6���g���ŁA�O�N�x��4.5������5�N�A���������A2013�N�x��14.2�����ƂȂ����B����ʂɂ݂�ƁA��ƁE���Ə������O�N�x��4.2�����A�ƒ낪��11.1�����A�^�A����1.4�����B �G�l���M�[�N��CO2�̔r�o�ʂ�2013�N�x�܂�4�N�A���ő����������A���̌�̎��v���A�ăG�l���y�⌴���ĉғ��ɂ��d�͒�Y�f�����ɂ��A�����X���ɂ���B�d�͂�CO2�r�o���P�ʂ́A�O�N�x��4.8�����P���A0.49kg- CO2�^kWh�ƂȂ����B�G�l���M�[�������́A�O�N�x��2.3���|�C���g����11.8���iIEA�x�[�X�j�ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c�A�G�l���M�[�W��^�Y�Ƃ̒E�Y�f���𑣐i����R���s�e���X�Z���^�[��ݗ� �h�C�c�A�M���ȁiBMU�j�́A�G�l���M�[�W��^�Y�Ƃ̒E�Y�f����i�߂邽�߂Ɂu�C��ی�R���s�e���X�Z���^�[�iKEI�j�v��ݗ������B KEI�́A���ɓS�|�A�Z�����g�A�ΊD�A���w�Y�Ƃ̈ꕔ�A��S����ȂǃG�l���M�[�W��^�Y�Ƃ̐����v���Z�X�ɂ�����CO2�̔r�o�팸��ڎw���A���ۓI�����剡�f�I�E�w�ۓI�Ȓm���v���b�g�t�H�[���Ƃ��āA�����̃j�[�Y�̓���A�����N���X�^�[�̌`���A�������B���s���Ă����B����b�́A�u�C��j���[�g��������������Z�p�̎��v�͐��E���ő�������B���̂Ȃ��ŎY�Ƃ̒E�Y�f���͉ۑ�ł���Ɠ����Ƀ`�����X�ł�����BKEI�́A�Y�ƊE�����̎s��ɂ����ă`�����X���l�����A�����ɉ������ʃK�X�̔r�o���팸����悤�x������v�Əq�ׂ��B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2019/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���p�H����100���R��������{�C���V�X�e���R����ő��65���팸 IHI�ėp�{�C���́A�H�i���H�H��ȂǂŔ�������p�H����100���R���Ƃ��ė��p�ł���p�H�����{�C����g�ݍ��V�V�X�e�����J�����A�{�i�̔����J�n�����B ���̐V�V�X�e���ł́A�H�i���H�ߒ��Ŕ��������p�H�������Ђɐݒu�����p�����u�őS�ʐ��A���̂܂܃{�C���̔R���Ƃ��čė��p�ł���B ���Ђ͐V���ɔR�����w������̂ɔ�ׁA�ő��65���̃R�X�g�팸���\�ɂȂ�Ǝ��Z�B�p�H�����o�C�I�}�X�R���Ƃ��čė��p���邱�Ƃɂ��A�Ȏ�������CO2�팸�ɍv���ł���Ƃ��Ă���B ���̐V�V�X�e���́A�ї��{�C���Ƀ}���`�R���Ή��o�[�i�[���̗p���邱�Ƃ�100���p�H����R���Ƃ��ĉ^�]���邱�Ƃ��\�ɂ����B���^�{�C���Ƃ��Ă͑�e�ʂŁA�����ʂ�1,000kg/h���B�{�C��������88���B�R�Ďl�ʒu����ƍ��@�\�^�}�C�R�������W�������������������������ق��A�R���p�N�g�v�ɂ��ȃX�y�[�X�Őݒu�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����d���ł��ƒ��̃R���Z���g�����p�\�ɐV�~�d�V�X�e���\�A�V���[�v �V�V�X�e���̖��̂́u�N���E�h�~�d�r�V�X�e���v�B��d���̏o�͓d����200V�ɂ��A���z�����d�V�X�e���Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA��d���̍ő�o�͓d�͂�5.5kVA�܂Ō��コ�����B ��Ȏd�l�� �E�\���i�F���`�E���C�I���~�d�r�A�~�d�r�A�g�^�p���[�R���f�B�V���i�A�~�d�r�p�R���o�[�^ �E���̗e�F6.5kWh�^5.5kW�i���펞�j5.5kVA�i��d���j �@���~�d�r�݂̂̏ꍇ�́A2.0kW�i���펞�j�^2.0kVA�i��d���j ��]�������i�F�ŕ�260���~ �]���@�ł́A��d���ɗ��p�ł���̂�����̃R���Z���g�݂̂ł��������A���@�̓V�X�e���S�̗̂e�ʂ��A�b�v�������Ƃɂ��A�ƒ��̃R���Z���g���g����悤�ɂȂ�A��葽���̋@����g�p���邱�Ƃ��ł���B �܂����V�X�e���́A���z�����d�Ƒg�݂킹���ꍇ6.5kWh�̒~�d�r��2��g�p��13.0kWh�܂ő�e�ʉ����\�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��JR�����{�ASDGs�B���փ��W�܂�X�g���[���֑f�ނɃO���[�v25�Ђ� JR�����{�O���[�v�A�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�B���Ɍ������V���Ȏ��g�݂\�����B 1.�G�L�i�J��z�e���ȂǂŎg�p����v���X�`�b�N�̍팸 �E���W�܂̓o�C�I�}�X�f�ނȂǂ��g�p�������W�܂֒u��������B2020�N9��30���܂łɊ����\��B �E�X�g���[��������𐫑f�ނȂǂ��g�p�����X�g���[�֒u��������B2020�N3��31���܂łɊ����\��B 2.���h��|�X�^�[�Ȃǎ��̍팸 �E���h�����f�ނ���ΊD���匴���Ƃ���LIMEX�i���C���b�N�X�j���g�p�����f�ނɏ�����ւ���B2019�N�x�͓��Ж{�ЂɂĎ��s�I�ɓ�����\�肵�A2020�N�x�ȍ~�A���������\�� �EPOP�Ȃǂ̍L�������ALIMEX�Ő���i�ꕔ�A���f�ނ��g�p�j�B�f���I����ɉ�����ăA�b�v�T�C�N���i�Đ��i���j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���e�X���A100���~���ƒ�p�~�d�r������ �e�X���͉ƒ�p�~�d�r�̔̔��A�ݒu��2020�N�t���J�n����Ɣ��\�����B �̔����i�́A�~�d�r�{�̂Ǝ��Ӌ@�킠�킹��990,000�~�i�Ŕ����j�B�Ȃ��A�{�H��͕ʁB �~�d�e�ʂ́A13.5kWh�A�ō��o�͂�5kW�i�A���^�]�j�A7kW�i�s�[�N�j�B�G�A�R����IH������Ȃ�200V�@��ɂ��Ή����Ă���B���Ђɂ��ƁA4�l���т�������1�����̓d�C��~�d�\���Ƃ����B �~�d�r�{�̓����Ƀp���R������������Ă���B�Ȃ����Ӌ@��́A�[���d�̐���ƒʐM�@�\�Ȃǂ�S���B��p�̃X�}�z�A�v�����瑾�z�����d�V�X�e���̉ғ��A�ƒ���̓d�C�g�p�Ȃǂ����j�^�[�ł��A����ؑւ�^�]���[�h�̐ݒ�ύX���\�B ���@��1,150mm�~755mm�~155mm�A�d�ʂ�114kg�A�ݒu�͏��u���A�NJ|���ɑΉ��A���쉷�x��-20�x����50�x�B10��܂Ŋg�����\�ŁA�ۏ؊��Ԃ�10�N�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�m�����A����ɐV�H�������150���~�����V�^���`�E���d�r�ʎY 12�����߂ǂɐV�H������肷��B�p�n�⌚���A���Y�ݔ��ȂǂŌv��150���~�𓊂���v��B �ڍׂ͍���l�߂邪�A���Y�\�͂ŃM�K���b�g�����̃v�����g��2021�N�x�ɉғ��\�肾�B���݂͈��m�����̃p�C���b�g�v�����g�Ŏ��삵�A���Ђ̌������Ȃǂœ��d�r�̕]�����������{���B ���d�r�̗̍p�����������Ƃ̗p�r�ɑ���]�������Ȃǂ��o�āA�ŏI���肷��B �ʎY����̂́A�d�r�J���x���`���[��APB�ȂǂƋ����ŊJ�������A�d�ɁA�W�d�́A�Z�p���[�^�[�����ׂĎ����̑S�����d�r�B �d�C�e�ʂ��]���^�d�r��2�{�ȏ�ɂł���B �������̂��߁A�`��̎��R�x�������A�����J���Ă��ؒf���Ă��������A���S���������B ���d�r���u���S�E�t���L�V�u���E�R�X�g�ʂɂ����āA�S�ő̓d�r�����D�ʐ�������v�Ƃ��A����̓r���Ȃǂ̑�^�ݔ��p�d����~�d�{�����Ȃǂւ̗̍p��ڎw�������l�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ��������Ƃ�2���������ƎQ���ɊSSDGs�F�m�x��13���A�哯�������� �哯�����ی��́A�u������Ƃɂ�������ω��ƌo�c�ۑ�v�ɂ��Ē����������ʂ����\�����B�S���̒�����ƌo�c�҂�ΏۂƂ����A���P�[�g�����{�����B �V���Ȏ��ƕ���i�̈�j���J��ꍇ�ɁA��S�̂��鎖�ƕ��죂́A���E���T�C�N�����삪19���ƍł������A�G�l���M�[���삪11���Ǝ��ɑ��������B ��d���������|�C���g��́A��������������܂�飂�38���ƍł������A�����Ţ�������Ƃ̋Z�p�E�m�E�n�E�����p�ł��飂�26���������B SDGs�̔F�m�x�i���́E���e�Ƃ��ɒm���Ă���j��13���ƒႢ�����������B�܂��A�]�ƈ��K�͂��傫���قǔF�m�x�������A�Ǝ�ʂł͢�����ƣ�ōł��F�m�x�������B����ɁA70����SDGs�ɂ��āu���g�ވӌ�������v�Ɖ������̂́A���̂���36�����u���g�݂�������������悢���킩��Ȃ��v�Ɖ������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ăG�l100�錾RE Action�v����5�N���1���c�̂̎Q���ڎw�� �O���[���w���l�b�g���[�N�iGPN�j�A�C�N���C���{�iICLEI�j�A�n�����헪�����@�ցiIGES�j�A���{�C�[�_�[�Y�E�p�[�g�i�[�V�b�v�iJCLP�j��4�҂́A�g�p�d��100���Đ��\�G�l���M�[���Ɍ������g�g�݁u�ăG�l100�錾RE Action�v���������B 28�҂��Q���BRE100�C�j�V�A�e�B�u�̑ΏۊO�̍����̏���d�͗�1000��kWh�����̊�ƁA�s���E����@�ցA�a�@�Ȃǂ�ΏۂɁA�g�p�d�͂̍Đ��\�G�l���M�[100�����Ɍ����ċ��ɍs���������Ă����C�j�V�A�e�B�u���B5�N���1���c�̂̎Q����ڎw���B �R�~�b�g�����g�̗v���́A�E�x���Ƃ�2050�N�܂łɏ���d�͂�100�����ăG�l������ڕW��ݒ肵�A�ΊO�I�Ɍ��\���邱�ƁE���N�̐i���i����d�͗ʁE�ăG�l���j �Q����p�i�N�z�j�́A��Ƃɂ��Ă�25,000�~�i10�l�ȉ��j�`200,000�~�i1,000�l�ȏ�j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցA�N3���̃G�l���M�[����������������u3�p�[�Z���g�E�N���u�v�𗧂��グ ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A�j���[���[�N�ŊJ���ꂽ���A�C��s���T�~�b�g�ŁA���E�̃G�l���M�[���x��N3�����P���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����V���ȘA���u3�p�[�Z���g�E�N���u�v��15�J�����Q���\�������Ɣ��\�����B ���E�̃G�l���M�[��������2015�N�ȍ~�������Ă���A2018�N�͂킸��1.3���������B������IEA�̕��͂ł́A�����̋Z�p�Ɣ�p���ʂ̍������������p���G�l���M�[������N3�����P����A�p������̖ڕW�B���ɕK�v�ȉ������ʃK�X�r�o�팸�ɑ���Ȍ��ʂ�����Ƃ����B���̎����ɂ͐��{�Ɩ��ԕ��傪�A�g�����������}�ɍs������K�v������Ƃ��A����̘A�����ݗ����ꂽ�B �V�A���̎Q�����́A�������̋�̍�����ƌv��ɑg�ݍ��ނ��Ƃ�A�����ւ̎����E�Z�p�x������B�܂��Q�������ƁE�x���g�D�́A���Ў��Ƃł̑啝�Ȍ������ƎQ�����̉��P��̍���E���{�x��������B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| ���ԎK���g���Đ��Ƒ��z�����琅�f���_�ˑ�w�����`�[�����V���ȊJ�� �_�ˑ�w�Ɩ��É���w�Ƃ̋��������ɂ��A���z����p���Đ����琅�f���������ɐ����ł�����G�}�d�Ɂi�w�}�^�C�g���\�������G�}�d�Ɂj�̊J���ɐ��������Ɣ��\�����B �w�}�^�C�g�i�ԎK�j�́A���S�E�����E����Ȍ��G�}�ޗ��ł���A�Â����瑾�z���𗘗p�������f�����ւ̉��p�����҂���Ă����B����ŁA���̏Ǝ˂ɂ���Đ��������d�q���A�Č������A�������Ă��܂����߁A���G�l���M�[�ϊ��������Ⴂ�Ƃ����ۑ肪�������B ����A�����`�[���́A�i�m���q���ɕ��ׂ邱�ƂŁA�d�q�Ɛ��E�̗���𐧌䂷��u���\�����Z�p�v�W������ƂƂ��ɁA�ԎK�Ƃ��Ēm����w�}�^�C�g�������ɂ��邱�ƂŁA�������������ȃ��\�������G�}�d�ɂ̊J���ɐ��������B ����́A�Y�w�����Ńw�}�^�C�g���\�������G�}�d�ɂ̂���Ȃ鍂�������ƃf�o�C�X����i�߂�Ɠ����ɁA���\�����Z�p�𑼂̌��G�}�ޗ��ɓK�p���邱�ƂŁA���z�����f�����V�X�e���̑���������ڎw���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C��ϓ��A�N�V�������{�T�~�b�g2019 ���C��ϓ��C�j�V�A�e�B�u(JCI)���J�� ��u���ɂ́ASBT�ARE100�ACDSB�Ƃ�������ƂⓊ���Ƃ̐��I�ȋC��ϓ���𐄐i���Ă���uWe Mean Business�vCEO �i�C�W�F���E�g�b�s���O�����}�����B �g�b�s���O������́A�E�Y�f�������r�W�l�X�̍��ۓI�ȍŐV���������Љ�B���{�̊�ƁA�����̂Ȃǔ{�A�N�^�[���߂����ׂ������ɂ��ču���B ��ƁA�����̂̃g�b�v���[�_�[�ɂ��Z�b�V�����ɂ́A�ۈ�O���[�v�A�Z�F�ыƂȂǂ��o�d�B�܂��A�����Ŋ����Ƃ⎩���̂Ȃǂ��o�d�B �u�C��ϓ��A�N�V�����őO��2019�v��N���C���[�g�X�g���C�L�ȂNJ����ɂȂ��Ă����҂ɂ��p�l���f�B�X�J�b�V���������{�B �C��ϓ��ւ̊�@�ӎ������L���A�p�����肪�f����1.5���ڕW�̒B���Ɍ������@�^�����߂�d�v�ȋ@��ƂȂ����B �o�T�u�C��ϓ��C�j�V�A�e�B�u�v |
|
|
| ������30�N�x�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����̌��ʁi����l�j�ɂ��� ���Ȃł́A�ƒ땔��̏ڍׂ�CO2�r�o���ԓ���c�����A�n�����g����̊��E���ĂɎ������b�����邱�Ƃ�ړI�ɁA�u�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����v�����{���Ă���B ���̒����́A�e���т̐��э\���A�Z��̌��ĕ��A�d�C�E�K�X���̃G�l���M�[����ʂ�Ɠd���i�ʂ̎g�p���A����496���ڂɂ킽���ďڍׂɒ������Ă���B �������ʂ�1�ł��鐢�т�����̔N��CO2�r�o�ʂ́A3.04 t-CO2�ŁA�O�N�x����T�����������B���̒����ł́A��d�T�b�V�܂��͕��w�K���X�̑��̗L�����̏Z�����A�①�ɁA�Ɩ����̋@��̎g�p�ɂ��Ă��������Ă���A������CO2�r�o�ʂƂ̏ڍׂȗv�����͂͊m��l�ɂ����čs���\��B���ѓ�����̔N��CO2�r�o�ʂ�3.04 t-CO2�ŁA�d�C�̎g�p�ɂ��CO2�r�o�ʂ�68.8�����߂Ă��܂��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���P�H�s�����ݒ�25���x�ŐE����8�����u�����オ�����v ���Ȃ͗�[���̎����ڈ���28���Ƃ��A�S���̎����̂������Ă���B �P�H�s�́u������25������28���ɏオ��ƍ�ƌ�����6���ቺ����v�Ƃ̐��Ƃ̕��͂���ɁA7��16���`8��31���A�s�����{���ɂŎ�����25���ɂ��ĐE���̘J�����ւ̉e���ׂ��B �O�N�Ƃ̔�r�ŐE��1�l������̌����ώc�Ǝ��Ԃ�21.6���Ԃ���18.7���ԂɌ������B�Ɩ������̃A���P�[�g�ł��A�u�ƂĂ����サ���v�Ɓu�������サ���v�ƂŌv85�����߂��B ���M��͑O�N�����7���~���������A�c�Ǝ��Ԍ����Ől����͖�4�疜�~�팸���ꂽ�B�������ʃK�X�̔r�o�ʂ������ɂƂǂ܂����Ƃ����B���s�́A�C���Ɩ��ʂ̕ϓ��܂��A���Ă����؎����Ƃ��Čp�����A�f�[�^��ςݏd�˂���j�B�o������q���Z���^�[�Ȃǂ̏o��@�ւɂ��Ώێ{�݂��L����Ƃ����B �o�T�u�_�ːV��NEXT �v |
|
|
| ���@�@[�@2019/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���|�ɂ��ORC �M�d�����ݔ���g�ݍ��킹���o�C�I�}�X�v�����g������ NEDO�ƃo���u�[�G�i�W�[�́A�������̒|�ɂ��ORC�M�d�����ݔ���g�ݍ��킹���o�C�I�}�X�v�����g�������������Ɣ��\�����B 2019�N10������{�i�I�Ɏ��؉^�]���J�n�A2023 �N���̎��Ɖ���ڎw���B �|�т̍r�p�ʼnۑ�ƂȂ��Ă���|�ƁA�����p�����Ƃ��ėL�����p���ۑ�ƂȂ��Ă���o�[�N�i����j�������ɔM�Ɠd�C�����o���A�אڂ���|�ނ̐��i���H�H��ōő�����p����B�����p�G�l���M�[�̗L�����p�ƒn��ۑ�̉����𗼗����A�n��o�Ϗz��������������G�l���M�[�V�X�e���̍\�z��������������g�݂��B �v�����g�ł͔N�Ԗ�8750t���x�̒|�𗘗p����v��ŁA�d�C�o�͂� 995kW�A�M�o�͂�6795kW�i�|���H�H��ւ̔M�}������ 2800kW�A�������� 3995kW�j�B ���Ĕ䗦�i�|30���A�o�[�N70���j�ƔR�ĉ��x�E�^�]���[�h���œK�����邱�ƂŁA�|�̔R�Ď��̍ő�̉ۑ�Ƃ���Ă����N�����J�\�ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X �v |
|
|
| �����d�́A��FIT ���z���́u���z�a����v3�v�������\/11���J�n �u���߃g�N�T�[�r�X�v�́A�ڋq�̗]��d�͂Ђ��a����A���̓d�C�������ɕԂ��Ƃ����u���z�a����v�̃T�[�r�X���B�~�d�r�̍w���E�ݒu���s�v�Ƃ��������b�g������B ���̓d�͉�Ђ��A�]��d�͂����z�I�ɗa����v�����Ƃ��āA�l�X�Ȏd�g�݂Œ�Ă��Ă���B �T�[�r�X�ł́A�]��d�͂߂���u���߃g�NBOX �v��e�ʂɉ����� 3 ��ނ�p�ӂ����B �����u���߃g�NBOX �v�ŗa�������d�͗ʂ́A �@(1)�����̍w���d�͗ʂɂ����ɏ[������B �@(2)�u���߃g�N BOX �v�̗e�ʂ߂����d�͗ʂƁA�u���߃g�N BOX �v�ɗa�������d�͗ʂ̂����w���d�͗ʂ߂����d�͗ʂ́A�P���i8�~/kWh �j�Ŕ������B �����̐��Z�͂���܂œ��l�ɐ������A���킹�āA���߃g�N�T�[�r�X�̃T�[�r�X���p������������B���߃g�N�T�[�r�X���p�ɂ��Ҍ��z(1)+(2)�́A�ʓr�w������U�荞�ށB �o�T�u���r�W�l�X �v |
|
|
| ���p�V�t�B�R���l�A�H�i�p�������甭�d�����d�͂����p����G�R�V�X�e���� �p�V�t�B�R���l�́A�A�[�o���G�i�W�[�́w �n�d���i�����ł���(R) �x �����p���A�{�ݓ��Ŕr�o�����H�i�p���������^�����y���Ĕ��d���A���̓d�͂�Ս`�p�[�N��������z�^�G�R�V�X�e���ւ̎��g�݂��J�n�����B�܂��A���̎��ƌn�H�i�p�����̎��W�E�^���ɂ́A�d�r�����^ EV�p�b�J�[�ԂŎg�p����B ���̎��g�݂̃X�L�[���́A�p�V�t�B�R���l�̑S�{�ݓ��Ŕr�o�����H�i�p�������AJ&T����EV�p�b�J�[�ԂŎ��W�E�^�����s���B�^�э��܂ꂽ�H�i�p�����́AJ�o�C�I�t�[�h���T�C�N���̃��T�C�N���H��Ń��^�����y�����d�B���̓d�͂��A�[�o���G�i�W�[���������A�p�����̗ʂɉ����ēd�͗������������ �w �n�d��(R) �x �ɂ��A�p�V�t�B�R���l���Ǘ�����Ս`�p�[�N�ɓd�͂���������B �_��d�́F55kW �r�o�p�����ʐH�i�p�����r�o�� ��20t/�N�i�\��j�B�H�i�p��������̔��d�ʂɂ��A�d�͎g�p�ʖ� 8,700kWh �����i�_��d�̖͂�4���j��d���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��TOTO�Ȃ�4�ЁA�R���d�r�̍��ى�Аݗ� ���}�ȏ��i���֘A�g �m���^�P�ATOTO �A���{�K�C�V�A���{���ꓩ�Ƃ̐X���O���[�v4�Ђ́A�ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j�Ɋւ��鍇�ى�Ђ̊T�v�����肵���\�����B 4�Ђ͂���܂Ŕ|���Ă���SOFC�Ɋւ���Z�p�E�m�E�n�E�Ȃǂ��������A���ꂼ��̗L����o�c������Z�����邱�Ƃő��}�ȏ��i���̎�����ڎw���B ��Ж��́u�X��SOFC�e�N�m���W�[�v�B�ݗ�����8��9���B���Ɠ��e�́A�ƒ�p�E�Ɩ��p�E�Y�Ɨp�i�ԍڗp�������j��SOFC �̃Z���A�X�^�b�N�A���W���[���A�V�X�e���̌����E�J���E�����E�̔��ɌW��BSOFC�̃Z���̑f�ނƕ��i�̔̔����Ƃ͍s��Ȃ��B12��3���̎��ƊJ�n�\��B���{����1���~�B �o���䗦�̓m���^�P��5���ATOTO��20���A���{�K�C�V��8���A���{���ꓩ�Ƃ�67���B�����Y�Ƒ����Y�͂Ƃ���49��1400���~�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������p���uEV �D�v�����関���ցA�O�H�����ȂǐV��� �O�H�����⏤�D�O��A���^���J�[�A�A�G�N�Z�m���}�~�Y���d�C���i(EV)�D���J������V��ЂƂ��āu���T�i�C�[�t�@�C�u�j���{�v��ݗ������B 2021�N���܂łɓ����p���ʼn^�q������q�^���J�[���A��e�ʓd�r�쓮�ɂ���ē�_���Y�f��r�o���Ȃ��g�[���G�~�b�V�����^���J�[�h�Ƃ���EV�����邱�Ƃ�ڎw���B �D���̒ʐM�������P����Ȃǂ��đD���s���̉ۑ�Ɏ��g�ނق��A���x�ȃZ���T�[�Z�p�����p���A��������D�������S�ɉ^�q���邽�߂̕ێ�Ǘ��Ȃǂɂ��Ή����Ă����B �o�T�u�d�C�V�� �v |
|
|
| ���V���[�v�A�F�f�����𓋍ځ@�Â��ꏊ�ł����z�d�r�ŐM�����M�̎d�g�� �V���[�v�́A�����̔�퓔�̉��ȂLjÂ��ꏊ�ł��A�M�������肵�Ĕ��M�ł���r�[�R�����J�������Ɣ��\�����B ���d�������ƊE�ō����x���ɍ��߂��Ǝ��̐F�f�������z�d�r�𓋍ځB�������݂��肪���鉮���O�����i�r�Q�[�V�����T�[�r�X�p�Ƃ��ē��Ђ�7�����ɔ[�������B ���ڂ����F�f�������z�d�r�́A��ʓI�ȃA�����t�@�X�V���R�����z�d�r�Ɣ�ׁA��2�{�̔��d���������������B����ɂ��50���N�X���x�̈Â��ꏊ�ł��A�ߋ��������ʐM�K�i�u�u���[�g�D�[�X�v�Ȃǂ̐M����1�b�Ԃ�1��̊Ԋu�ň��肵�Ĕ��M�ł���B ���݁A�r�[�R���̓d���͈ꎟ�d�r�̗̍p�������B���Ђ̐F�f�������z�d�r���̗p���邱�ƂŁA�d�r�����Ƃ����������e�i���X��Ƃ��s�v�ɂł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���J���e�b�N�A�g�C���Ȃǂ���ɒE�L�ł���LED �d�� �`�Ǝ��̌��G�}�ŒE�L�E���� �J���e�b�N�́A�E�L�E���ۋ@�\�t��LED �d�����A10���ɔ�������B���i�̓I�[�v���v���C�X�B�X���\�z���i��10,000�~�O�� �Ŕ��B E26�����A40W������LED�d���B�Ǝ��̌��G�}�Z�p�ɂ��A�E�L�E���ۋ@�\�𓋍ڂ��Ă���_�������B�K����Ԗ�1��ŁA�g�C����L�b�`���A�N���[�[�b�g�Ȃǂ̏���Ԃ�24 ���ԏ�ɒE�L�ł���Ƃ����B�l���Z���T�[������A�_�������̎�Ԃ��Ȃ���B�S������485lm �B�F���x��2,700K�B����d�͍͂ő�10W�A�ŏ�5.4W �B �t�B���^�[�͌��G�}����������ƁA�G�}�Ŕ����J�X ���o�ĕt�����邽�߁A����I�ɐ����K�v������B�����@��80�� �̂����Ŗ�15���̂������ŁA���N�Ɉ�x�̎����𐄏��B��邾���ŁA�E�L�E���ی��ʂ����i�v�I�Ɏ�������Ƃ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���m�d�c�n��A�C�V�����@�Ȃǂ������ȍޗ��ō\������u�M�d���d�v���W���[�����J�� NEDO�A�����E�ޗ������@�\�A�A�C�V�����@�A����w�́A�S�ƃA���~�j�E���A�V���R���Ƃ��������肵�₷�����f�̍����ō\������A���x����d�C�ɕϊ�����u�M�d���d�v�̃��W���[�����J�������Ɣ��\�����B ���x�E���x�Z���T�[��M�d���d���W���[���Ȃǂ���������c76mm�~��58mm�~����10mm�̃f�����X�g���[�V�����@�����삵�A5���̉��x���Ŕ��d���A�u�u���[�g�D�[�X�v�ʼn��x�Ǝ��x�̏��𑗐M���A�^�u���b�g�[����ʏ�Ƀ��A���^�C���ŕ\�������邱�Ƃɐ��������B ��������200���̒ቷ��̔M���𗘗p���AIoT�@��̎����d���V�X�e���̊J�������҂����B�r�X�}�X�ƓŐ��������e�������܂މ������𗘗p�����]���̔M�d�ޗ��ɔ�ׁA�ޗ��R�X�g��1/5�ȉ��Ɍ��点��Ɗ��҂����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������G�l���A��d���̑��z�����d�V�X�e�������^�]�@�\�̎g���������m �����G�l���M�[���́A��d���̏Z��p���z�����d�p�l���̎����^�]�@�\�ɂ��āA�E�F�u�T�C�g��Ŏ��m�����B �g�����͉��L�̒ʂ�B (1)�����^�]�p�R���Z���g�̈ʒu���m�F����B (2)�戵���������Łu�����^�]���[�h�v�ւ̐�ւ����@���m���߂�B (3)��d���u���[�J�[���I�t�ɂ���B (4)���z�����d�u���[�J�[���I�t�ɂ���B (5)�u�����^�]���[�h�v�ɐ�ւ���B (6)�����^�]�p�R���Z���g�ɕK�v�ȋ@���ڑ����Ďg�p����B (7)��d�����������ۂ́A�K�����ɖ߂��B�i�����^�]���[�h���������z�����d�p�u���[�J�[���I������d���u���[�J�[���I���̏��ŕ��A�j ���[�J�[��@��ɂ�葀����@���قȂ�ꍇ�����邽�߁A���z�����d����ł́A��L�̐����ɉ����A���z�����d�V�X�e���e�Ђ́u�����^�]�@�\�v�Ɋւ�����ւ̃����N�W�����J���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������A�y�ʉ��E�ȃG�l�ɂȂ���K���X��v���X�`�b�N�̔����ޗ����J�� ������w�́A�����Ԃ�r���̑���10����1�߂��܂Ōy���ł��锖���ޗ����J�������Ɣ��\�����B �ߔN�A�K���X�\�ʂ̍d�������߂邽�߁A�\�ʂɍd��CeO2(�t�b�f�������܂ގ_���Z���E��)�𐬖����錤�����s���Ă���B������CeO2�͍d�����Ƃ����߁A�ό`�ɂ���ăN���b�N���������������肪����B ����A�V����CeO2�̔����f�ނƐ����Z�p���J�����A�K���X��ɐ��������Ƃ���A�\�ʂ̍d������3�{�Ɍ��サ���Ƃ����B�܂��A�v���X�`�b�N�t�B�����ւ̐����ɂ���ĕ\�ʂ̍d�����ق�10�{�Ɍ��シ��f�[�^�����Ă���A����10����1�܂Ōy�ʂɂ��邱�ƂŁA�G�l���M�[�̍팸�ȂǂɂȂ��邱�Ƃ����҂����Ƃ����B�Ȃ��A���̌����́A�Ȋw�Z�p�U���@�\�́u�������ʍœK�W�J�x���v���O�����v�ɍ̑�����A���p���Ɍ������������s���Ă������ƂɂȂ��Ă���(���ԁF2019�N10��~2023�N3��) �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����x�ω��œ����x����ւ��t�������ޗ����J���Y�����Ȃ� �Y�����Ɛ_�ˍ���A���L�@���w�H�Ƃ́A���x�ɉ����đ��z���̓��ߌ��ʂ���������ł���t�������ޗ����A�����J�������Ɣ��\�����B �J�����ꂽ�M�����^�����K���X�B�ቷ���i��25���j�ɓ����A�������i��50���j�ɔ���������ԁB30�`40���t�߂œ����Ɣ������芷���B ���ޗ��́A�̃K���X��̊Ԍ��ɍ������������d�������č쐻���邱�Ƃ��ł��A�\�����P���ō쐻���e�Ղł��邽�߁A�����K���X�Ȃǂɉ��p�\���B�܂��A���x�ω��ɂ���ē����x���芷���i�ቷ�œ����A�����Ŕ����j�A�����Ɍ��̑O���U�����x���ω����鐫����L����B����ɂ��A�ߐԊO�̈���܂ތ��̑S���ߗʂ��t�I��20%�ȏ�ς��邱�Ƃ��ł���B ���ޗ��́A�����ւ̑��z���N���ʂ�d�͖����Œ����ł���ȃG�l���K���X�Ȃǂɉ��p�ł��A�Z���ړ��̂Ȃǂ̒g��[���ׂ�}����ȃG�l���ނƂ��Ċ��҂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IPCC�A�n�����g���ɂ��C�m�E��X���ւ̉e���Ɋւ���������\ IPCC�́A�n�����g���ɂ��C�m�E��X���ւ̉e����A����ɂ���ė\�������ω��E���X�N�Ȃǂ��܂Ƃ߂��������\�����B���Ȃ͐���Ҍ����v��iSPM�j�̊T�v�\�����B �T�v�ɂ��ƁA1993�N���A�C�m�̏������x��2�{���ĉ������A�C�m�M�g�́A1982�N����p�x��2�{�ɑ��債���\�������ɍ����A���̋��x�͑��債�Ă���B�C�m����葽����CO2���z�����邱�Ƃɂ���āA�C�ʁi�\�ʊC���j�̎_�������i�s���Ă���B ���E���ϊC�ʐ��ʂ́A�O���[�������h�Ɠ�ɂ̕X������X���������鑬�x�̑���B�ɒ[�ȊC�ʐ��ʂ̌��ۂƉ��݈�̃n�U�[�h�������B����������X���ƊC�m�ɂ�����ω��́A���݈���܂߂āA�C�m���Ԍn��Ԍn�T�[�r�X�ɉe����^���Ă����B ����́A���㐔�\�N�ɂ����鉷�����ʃK�X�̔r�o�ʂ̑啝�ȍ팸�ɂ���āA2050�N�ȍ~�̂���Ȃ�ω����ጸ�����Ɨ\������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�H�i���X�̍팸�̐��i�Ɋւ���@���v�̎{�s�y�і{�N10���̐H�i���X�팸���Ԃ̎�g�ɂ��� �u�H�i���X�̍팸�̐��i�Ɋւ���@���v�i�{�N5��31�����z�j��10��1������{�s���ꂽ�B ���̖@���́A�H�i���X�̍팸�Ɋւ��A���A�n�������c�̓��̐Ӗ����𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA��{���j�̍��肻�̑��H�i���X�̍팸�Ɋւ���{��̊�{�ƂȂ鎖�����߂邱�Ɠ��ɂ��A�H�i���X�̍팸�𑍍��I�ɐ��i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���N10���́u�H�i���X�팸���ԁv�A10��30���́u�H�i���X�팸�̓��v�ɒ�߂�ꂽ�B ������āA���Ȃł͖{�N10���̐H�i���X�팸���ԂɁA�E�[�����ނ̒A�E3��H�i���X�팸�S�����A�E�H�i���X�팸�V���|�W�E���ȂǐH�i���X�팸�̎�g���s���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/10�@]�@�@�� |
|
|
| ���ăG�l�@��s��A2030�N�x�ɔ������^�x�m�o�ς������AFIT�������e�� �x�m�o�ς͍Đ��\�G�l���M�[���d�V�X�e���̍����s�꒲�����ʂ��܂Ƃ߂��B2030�N�x�̍����s���2017�N�x��47.9������1��521���~�ƂȂ錩�ʂ��B ����܂Ŏs����������Ă������z���́AFIT�i�Đ��\�G�l���M�[�Œ艿�i���搧�x�j�������Ȃǂ�w�i��2018�N�x��3���ȉ��܂ŏk������Ɨ\�������B ���͂Ɛ��͎͂s�ꂪ����������Ƃ݂�B���̑��A�Đ��\�G�l�̗v�����ʂ��܂Ƃ߂��B2018�N�x�i�����݁j��7183��kW����A2030�N�x��1��2687��kW�܂ŐL�т錩�ʂ��������Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ����a�n�E�X�ƎO�����R���A���H��V�X�e�����J���E�̔��A�͔|�T�|�[�g�� ��a�n�E�X�H�ƂƎO�����R�͔_�Ƃ̍H�Ɖ���ړI�ɐA���H��V�X�e���������J���B��a�n�E�X�H�Ƃ��S���Ŕ̔�����B�O�����R�͍͔|�Z�p�E�T�|�[�g�̒�S���B ���V�X�e���� �@(1)���K�͂����K�͂܂ŐA���H�����]����ڋq�̑��l�Ȏ��ƌv��ɑΉ� �@(2)��̐����ɕs���ȕ�������ψ�ɓ����鑗���V�X�e����LED�Ɩ����̗p �@(3)�͔|�T�|�[�g�v���O�����̒� �������B �I�[�_�[���C�h�ōH���q�ɂȂǂɐݒu���\�B���Y�i�ڂ̓��[�t���^�X�A�o�W���A�ق���ȂǑ��l�ȕi��ɑΉ�����B �̔����i(�ŕ�)�͊�{���f����1�������[�g��������30���~����ƂȂ�B ���ЂƂ̒�g�ɂ��A�A���H��́u���݁v����u�͔|�E�^�c�T�|�[�g�v�܂Ń����X�g�b�v�T�[�r�X�����B ���K�͂ȐA���H��ɂ��͔|���E���Ƃ���������ڋq����A��K�͂ȐA���H�����]����ڋq�܂ŕ��L�����ƌv��ɑΉ�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��NEC�AESG�̎��g�݂Ɋւ���i�������J NEC��2020�����o�c�v��Ɋ�Â����肵��ESG�i���E�Љ�E�K�o�i���X�j���_�ɂ��o�c�D��e�[�}�̎��g�݂̐i�������J�����B �E������F2050�N�uCO2�r�o�ʁw�����[���x�v��ڎw�����g�݂̈�ō��肵���A���ЃO���[�v�ɂ�����2030�N�x�̉������ʃK�X�r�o�팸�ڕW���A2018�N10����SBT�C�j�V�A�`�u����SBT�F������B �E�Љ��FAI�̎Љ������̏����͂��߂Ƃ���f�[�^�̗����p�ɂ����ẮA�e���E�n��̊֘A�@�߂Ȃǂ̏��炾���łȂ��A�Ј��s���̎w�j�Ƃ��āuNEC�O���[�vAI�Ɛl���Ɋւ���|���V�[�v�����\�����B �E�K�o�i���X����F 2017�N�x�ɐ��肵���uNEC�R���v���C�A���X�̓��v�ɍ��킹�A���Ђ���э����A���q��Ђ�ΏۂɊ�Ɨϗ��t�H�[�������J�Â���ȂǁA�R���v���C�A���X�̓O��Ɍ���������E�[�������Ɍp�����Ď��g��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������̃X�}�z�ő���ł���I�t�B�X��"�}�C�����a�k�d" �O�H�n���v�́A�l�̃X�}�[�g�t�H����p���āA�r���p�}���`�@�𑀍삵�A����̃G�A�R���̂悤�ȃp�[�\�i������������V�X�e�����l�Ă��A�O�H�d�@�ɂ�BLE�iBluetooth Low Energy�j�ʐM�Z�p��p�����u�}�C�����a�k�d�v���J���A�Q�Ћ����Ŏ��؎������s�����B �u�}�C�����a�k�d�v�́A�����̃r���p�}���`�@�Ɏ�M�@��ݒu���A�I�t�B�X�r���̃��[�U�[���X�}�[�g�t�H������@���茳�ő���ł���V�X�e���B���ɂ̃p�[�\�i���c�[���ł���X�}�[�g�t�H���������R���ɂ��ċ߂��̋@����y�ɑ���ł��邽�߁A�X�̉��K���Ɛ��Y���̌���A����ɂ͏ȃG�l���M�[����ъԎd��ύX���̍H����팸�ɂȂ���B��t���\�A���݃r���p�}���`�@�ɂ��ȈՑΉ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�C�z�����x52���ł̗�[�^�]��������⎮�q�[�g�|���v�`���[��V���i�����^�O�H�d�@ �O�H�d�@�́A�r����H��Ȃǂŗ≷�����g�p���ė�g�[���s����⎮�q�[�g�|���v�`���[�̐V���i�Ƃ��āA�O�C�z�����x52���ł̗�[�^�]���������A�ƊE�g�b�v�N���X�̏ȃG�l���ƏȃX�y�[�X�������������B2020�N�t�ɔ�������B �����́A�M�������������߂��A���~�G���ǔM������̗̍p�ɂ��A�O�C�z�����x52���ł̗�[�^�]�������B�ҏ���s�s���̃q�[�g�A�C�����h���ۂȂǂɂ��ݒu�ꏊ�̊O�C���������Ȃ��Ă���[�^�]���p���B�n�����g���W����R410A��}�Ɣ�ׂĖ�3����1��R32��}���̗p���A�����גጸ�ɍv���B�A���~�G���ǔM������̗̍p�ɂ��A��}�����ʂ��]����Ŗ�33���팸�ACO2���Z�l�Ŗ�78���팸�B�V�^���k�@�̓��ڂɂ��A��pCOP3.28�������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���\�j�[�g����G�A�R���h�u���I���|�P�b�g�v���J����
���I���|�P�b�g�ɂ͓d���������邱�Ƃɂ�蔭�M�^�z�M�i��p�j����y���`�F�f�q���g���Ă���B �{�̂ɂ͕����̃Z���T�[�𓋍ڂ��A�펞�f�o�C�X�̉��x�����m�B�≷����̓\�t�g�E�F�A�ōs���Ă���B�\�t�g���_�E�������ꍇ�̓n�[�h�E�F�A�I�ɓd���������V���b�g�_�E������B�傫����PC�̃}�E�X���炢�ŁA�d���͖�85�O�����B�����C���^�[�i�V���i���Ƌ����J��������p�̃C���i�[�E�F�A�iT�V���c�j�͔w���̎�ɋ߂��ꏊ�Ƀ|�P�b�g������A�����ɖ{�̂����ČŒ肷��d�g�݂ɂȂ��Ă���B �d�����I���ɂ��ăN�[�����O���[�h�ɂ���ƁA�u���ɔ��ƐG��Ă���ꏊ���₽���Ȃ�B �[�d����Ή��x���J��Ԃ��g����B���߂邱�Ƃ��ł���B �����o�b�e���[�́A�t���[�d�̏�Ԃ���1��15����6��܂Ŏg����B�A�������≷���Ԃ͍Œ�30���ƂȂ��Ă���B �o�T�uItmedia�v |
|
|
| ���Ώ؏��A���̂P���L�����b�g�����O���30�{�A��藦0.6�� ���{���d�͎�����iJEPX�j�́A2019�N�x1��ڂƂȂ�Ώ؏��̎�����ʂ����\�����B ���ʂ�1��637��6433kWh�ƂȂ�A���߂�1��kWh�����B������D�ʂɑ����藦�͂܂�0.6���ɂƂǂ܂邪�AESG�i���A�Љ�A��Ɠ����j�����̏d�v�������܂钆�A�����I�ɓ�_���Y�f�iCO2�j�t���[�̓d�C�����߂���v�Ƃ������Ă����Ƃ����������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Y�f���p�A���y�ɖ{���^�u�b�n�Q���R���v�A�o�Y�Ȃ����N�x���� �o�ώY�ƏȂ́A��_���Y�f�iCOS�j��R���E���i�Ȃǂɍė��p����u�J�[�{�����T�C�N���v�ɂ��āA���y�Ɍ��������g�݂𗈔N�x����{�i��������B �Η͔��d�̍����������_���Y�f����E�����iCCS�j�̑�K�͎��؎����Ƃ����������̎��ƂW�����A�������CO2����R����������Ȃǂɒ��肷��BCCS���ł́A���j�^�����O��@�̊m���Ȃǂ��ڎw���B2020�N�x�\�Z�̊T�Z�v���ł́A�J�[�{�����T�C�N���֘A��p�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Čv�シ�錩���݁B �����d�͂Ƃi�p���[�i�d���J���j�������o��������N�[���W�F���ɂ��ΒY�K�X���R���d�r�������d�iIGFC�j�̎��؎��Ƃ�ʂ��A���������Ɍ��������g�݂��p���B�o�Y�Ȃ�6���ɂ܂Ƃ߂��u�J�[�{�����T�C�N���Z�p���[�h�}�b�v�v�܂��A�������CO2����o�C�I�R���Ȃǂ�����Z�p�̎��ɂ����o���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ȁA�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j��50��̌��ʂ\ �X�C�X�̃W���l�[�u�ŊJ�Â��ꂽ�u�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j��50��v�̌��ʂ����\�����B ��������ł́A�y�n�W���ʕ��Ɋւ���c�_�����s���A����Ҍ����v��iSPM�j�����F�����ƂƂ��ɁA���{�҂�������ꂽ�B�����́A���搶�Ԍn�ɂ����鉷�����ʃK�X�iGHG�j�̗���i�t���b�N�X�j�A���тɋC��ւ̓K���y�ъɘa�A�������A�y�n�̗y�ѐH�����S�ۏ�Ɋ֘A����A�����\�ȓy�n�Ǘ��Ɋւ���Ȋw�I�m����]�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������́B �o�Ȏ҂́A�e�����{�̑�\�A���E�C�ۋ@�ցiWMO�j�A���A���v��iUNEP�j�A�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�j���̍��ۋ@�֓��̊W�҂ƁA�䂪������́A�����Ȋw�ȁA�_�ѐ��Y�ȁA�o�ώY�ƏȁA�C�ے��A���ȂȂǂ���v13�����o�Ȃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��NEDO�A�������ʃK�X�̒����팸��A��̉��ց^���{�A�߂��Z�p�헪����ɒ���
�p������Ɋ�Â��A���{���{�����A�֒�o����������r�o���W�헪�i�����헪�j�̋�̉��Ɍ������������{�i������B ���{�́A���f�G�l���M�[�̃R�X�g�팸���_���Y�f�iCO2�j�̗L�����p�Ȃǂ��c�_����L���҉�c���߂��ݒu���A�u�v�V�I���C�m�x�[�V�����헪�v�̍���Ɍ������������J�n����B��𐔉�J���A�Љ�����̉������⍑�ۘA�g�A�����������i�̕����T��B�ŏI�I�ɓ��t�{�̑����Ȋw�Z�p�E�C�m�x�[�V������c�iCSTI�j�ł܂Ƃ߂���j���B �P�ɋc�_�����邾���łȂ��A��̓I�ȃv���W�F�N�g�̑g���ɂȂ���헪��ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ߘa���N�x�̍H�ꓙ���n�����̎��{���j �o�ώY�ƏȂł́A�u���莖�Ǝғ��v��ΏۂƂ��āu���f��v�̏���Ɋւ��钲�������{����B �ߘa���N�x�́A���Ǝ҃N���X�����]�����x�Ɋ�Â��u�H�ꓙ���n�����v�Ƃ��āA�w��H�ꓙ�y�юw��H�ꓙ�������Ȃ����莖�Ǝғ��ɑ��钲���ɂ��Ď��{����B 1�D�H�ꓙ���n�����i�w��H�ꓙ�j�F��250���Ə� 2�D�{�ЁA���������ւ̒����F��50���Ǝ� 3�D�H�ꓙ���n�����i�w��H�ꓙ�������Ȃ����莖�Ǝғ��j�F��100���Ə� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���t�B�������h���������A�H������ς��邱�Ƃʼn��g����}������@�� ���ɂ��ƁA����������炷�ȂǐH������ς��A�k��n�̒Y�f�����@�\�ɔz�����邱�ƂŁA�H�������C��ɋy�ڂ��e����30�`40%���y���ł��邪�A���̂��߂ɂ͐H�ƃV�X�e���̑�K�͂ȉ��v���K�v�ɂȂ�Ƃ����B ����܂œ����̐H�Ɛ���͐H�ƕ���̎���I�[�u���d�����Ă������A�v���W�F�N�g�ɂ�������������I�[�u�ɂ͍��ӂɊ�Â������̖ڕW�ƋK���A���E�����ʂ̎x�����K�v���Ƃ����B�܂��A�_�Ǝx�����ƐŐ��͊��y�ь��N�ւ̉e���̊ϓ_���琸������K�v������A�A���R���̐H�Ɛ��Y�ւ̓�����V���ȉ��l�`�F�[���̑n�o�����߂���B ����A����������炷���Ƃ���ʉ����āA����H�މƒ{�̓�������������ꍇ�́A�앨���l����֍�Ȃǂ̑���u���ēy��̒Y�f�����ʂ𑝂₷���Ƃ���w�d�v�ɂȂ�B �h�{�Ɋւ��ẮA�C��ɗD�����H�����Ɉڍs���邱�Ƃ́A�h�{�ʂȂǁA���P�����ۑ�����邪�A�V���ɐ��܂��ۑ�����邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������s�A�Ɠd�ɔ����ւ��Ń|�C���g�t�^�ȃG�l���i�̍w�����i�� �����s�́A�ƒ�̏ȃG�l�s���𑣂����߁A�ݒu�ς݂̃G�A�R���E�①�ɁE��������A�ȃG�l���\�̍����@��ɔ����������s���ɑ��āA�����[���G�~�|�C���g��t�^����ƂƂ��ɏȃG�l�A�h�o�C�X���s���u�ƒ�̃[���G�~�b�V�����s�����i���Ɓv�i2019�N�x�`2020�N�x�j�����{����Ɣ��\�����B �����Ƃł́A�|�C���g�̌����i�Ƃ��āA���i���ɉ����A���炩���ߓo�^���ꂽ�戵�X�iLED�������戵�X�j�ɂ�����LED�Ɩ����w������ۂ�1,000�~���Ƃ��Ďg�p�ł���uLED�������v�s����B �|�C���g�̐\����t�́A2019�N10��1�����J�n�����B�����Ƃ�2019�N�x�\�Z��37.4���~�i�|�C���g�������j�����ǂ́A�����n�C�j�V�A�`�u�iSII�j�B �����Ƃ��J�n����ɂ�����A�s�͉Ɠd�̔��X�Ȃǂ̎��Ǝ҂�ΏۂƂ�������������{����B�܂��ALED�������戵�X�̓o�^��t���J�n�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�Z���^�[���u�H��̏ȃG�l���M�[�K�C�h�u�b�N2019�v�A�u�r���̏ȃG�l���M�[�K�C�h�u�b�N2019�v�����J �{�K�C�h�u�b�N�ł́A�H��A�r���̏ȃG�l�̊�{�I�ȏȃG�l����ƌ��ʎ��Z�A�`���[�j���O���@�A��v�G�l���M�[�g�p�ݔ����ɂ������\�I�ȏȃG�l���P��Ď�����Љ�Ă��܂��B�M�Ђ̏ȃG�l���i�A�ڋq�ւ̏ȃG�l��ē��ɂ����p���������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/8�@]�@�@�� |
|
|
| �����Ə���̃j�[�Y���܂�Y�Ɨp���z�����d�c�Ɨp�̎��Z�c�[�����V�@�\�lj� �G�i�W�[�E�\�����[�V�����Y�̎x���T�[�r�X�u�Y�Ɨp�\�[���[�}�X�^�[�v�́A���z�d�r���W���[���̐ݒu�������玩���Ŕ��d�ʂ��V�~�����[�V�������A�����ݒu��p�ɑ���d�C�����팸���ʂ���邱�Ƃ��ł���T�[�r�X���B ���̃T�[�r�X�ł́AGoogleMap���̍q��ʐ^��ɑ��z�d�r���W���[���̐ݒu�g���L�ڂ��邾���Ŕ��d�ʂ��V�~�����[�V��������B�����Ŕ̔�����Ă���140�Ђ̑��z�d�r���W���[�����[�J�[�ɑΉ����i2018�N9�����_�j�A�N���E�h�T�[�r�X�ɂ���ď����G�N�Z����ɍ쐬����B ����A���T�[�r�X�ɐݒu���鑾�z�����d�V�X�e���̔��d�V�~�����[�V�����ƁA30���w���d�͎��уf�[�^�����ƂɁA�t�����d�͗ʂ̎Z�o���ł���@�\���lj����ꂽ�B ����ɂ��A���z�����d�d�͂��A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�Ŕ��d�����ۂ̂ق��A���Ə���p�Ƃ��Đݒu����ꍇ���܂߂Ē�ď����쐬�ł���悤�ɂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Z����SBT�F��擾�A�������ʃK�X��2013�N��2030�N��30���팸 ���Z���i���s�{���s�s�j�́A2030�N�x�Ɍ����Đݒ肵���������ʃK�X�팸�ڕW���A���ۓI�Ȋ��c�̂ł���SBT�C�j�V�A�`�u���uSBT�iScience Based Targets�j�v�̔F����擾�����Ɣ��\�����B ���O���[�v��SBT�F������A�������ʃK�X�̔r�o�팸�ڕW�́A���L�̒ʂ�B �E�X�R�[�v1�A2�̉������ʃK�X�r�o�ʂ�2030�N�܂ł�2013�N���30���팸���� �E�X�R�[�v3�̉������ʃK�X�r�o�ʂ�2030�N�܂ł�2013�N���30���팸���� �Ȃ��A�X�R�[�v1�Ƃ͎��Ђł̔R���g�p��Y�v���Z�X����̒��ڔr�o�ʁB�X�R�[�v2�Ƃ͎��Ђ��w�������d�C��M�̎g�p�ɂ��Ԑڔr�o�ʁB�X�R�[�v3�Ƃ́A�X�R�[�v1�A2�ȊO�̊Ԑڔr�o�ʁi�������B�A���i�A���E�g�p�E�p���A�Ј��̒ʋE�o�����j�̂��Ƃ��B ���Y�����ɂ�����ăG�l�����ʂ�10�{�ɁB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��RE100�������20�ЁA���{���{�ɒăG�l�d���ւ̕]���A�ӗ~�I�Ȑ��� �A�X�N���ȂǓ��{��Ƃ�20�Ђō\�������uRE100�����o�[��v�́A�u�ăG�l100����ڎw�����v�Ƃ���̒v�����\�����B���{�̓d���\���ɂ��āA�u2030�N�ɍăG�l�䗦50���v�̒B����ڎw���A����������邱�Ƃ����߂Ă���B ���̊T�v�͎��̒ʂ�B 1�D�ăG�l�̎Љ�I�։v�̓K�ȕ]���ƁA����Ɋ�Â��������čăG�l�̎Љ�I�։v��K�ɕ]������ƂƂ��ɁA���S�̂ł��������L���邱�ƁB�d���Ƃ��Ă̈ʒu�Â�����I�x���ɂ��Ă���Ȃ�c�_���K�v�ł���B 2�D���{�̓d���\���ɂ��āA�u2030�N�ɍăG�l�䗦50���v���f���邱�ƁB�������m���ӗ~�I�ȕ��������������Ƃ��A�v������K�͂ȍăG�l���y���͂��邽�߂̑O��ɂȂ�B2020�N��㔼�ɂ͑��z�����d���ł������ȓd���ɂȂ�Ɨ\������Ă��� 3�D���̓d���ɑ��ċ����͂�L����ăG�l��������������� 2030�N�ɂ�����ăG�l�䗦50���������\�Ƃ��鑗�z�d�Ԑ��������߂�B �o�T�u�����r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�[�����̌��ł����d���鑾�z�d�r�A�I�t�B�X�����f�X�N�ɓ��ڒ~�d�r������ �J���������S�ő̌^�F�f�������z�d�r�́A�����@�̊J���Ŕ|�����L�@�����̂̋Z�p�����p���邱�ƂŁA�d�������ő̍ޗ��݂̂ō\�����邱�Ƃɐ��������B ����ɂ��A�d�����ɉt�̂�p����d�r��������t�R��╅�H�Ƃ��������S����ϋv���ɑ���ۑ�������B�����ɁA���������g���ɓK�����L�@�ޗ��̐v��A�f�o�C�X�\���̍œK�����������邱�Ƃɂ��A���d���\��啝�Ɍ��コ���邱�Ƃ��ł����B �����z�d�r�𓋍ڂ����uLOOPLINE T1�v�́A�f�U�C���I�t�B�X���C��������u�����iShi-An�j�v�Ƃ����f�U�C���R���Z�v�g�ɂ�鎆���̃I�t�B�X�f�X�N�̓V�ɁA���d�r��48�����ڂ������̂��B144Wh���A289Wh�̃��`�E���C�I���~�d�r��I�ׂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�X�}�[�g�t�H�����p�^���[�^�[�����ǂݎ��T�[�r�X�v��̔��J�n�A�����V�X�e���Y �H���r���A�v�����g�Ȃǂɐݒu����Ă���e�탁�[�^�[�̉摜�Ɛ��l�f�[�^���A�X�}�[�g�t�H���̃J���������p���Ď��W����T�[�r�X��7������J�n����B ���T�[�r�X�́A�X�}�[�g�t�H���ɐ�p�A�v�����C���X�g�[�����A�����ݒ���s�������ň����ɗ��p�J�n�ł���B�B�e�����摜�͐�p�A�v����Ŏ�����͂���A���l�f�[�^�ɕϊ�����邽�߁A�_�����ʂ̓]�L����͂����邱�ƂȂ��W�v�⒠�[�����ȒP�Ɏ��{�\���B ����ɂ��A�Œ�J������ݒu�ł��Ȃ��ꏊ�ɂ���e�ݔ��̃��[�^�[�̓_���Ɩ������������A�m�F������͎��ɔ������₷���_�����ʂ̋L�^�~�X��h�~����ƂƂ��ɁA�e�ݔ��̐v���ȏc�����x������B����ɁA�B�e�����摜�f�[�^���T�[�o�[�ɕۑ�����邱�Ƃɂ��A�_���f�[�^���ؐՂƂ��Ďc��A��肪���������ۂɂ͑k���Ċm�F���邱�Ƃ��\���B�f�[�^�̎擾�Ԋu��b�P�ʂŐݒ�ł���B �o�T�u�����V�X�e���Y�v |
|
|
| �����c���쏊�A�S�ő̓d�r��N�x���ʎY�E�G�A���u������ ���c���쏊�́A2019�N�x���ɃZ���~�b�N�X�Z�p�����p�����S�ő̓d�r�̗ʎY�ɏ��o���Ƃ����B��F���Ə��i���ꌧ��F�s�j�̓d�r�W�̐��Y���ɗʎY���C����V�݁B ���ʂ̐��Y�\�͂͌�10����\�肷��B����i�̗e�ʂ͑��А��i�Ɣ�ׂĂP�O�O�{�̂P�O�~���A���A�����ƋƊE�ō����x�����Ƃ����B ��ɃE�G�A���u���[���ł̗̍p��z��B���ł����ɑ�������u�q�A���u���@��v�����Ɏ��v���L����Ƃ݂�B���`�E���C�I���d�r�ƈႢ�A��R���ŁA�M���Ȃ�ɂ����B |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��uSDGs�o�c�v�K�C�h�u�b�N���\ESG�������Ăэ��ޕ��@���킩�� �o�ώY�ƏȂ́A��Ƃ�SDGs�Ɏ��g�ށuSDGs�o�c�v�̃G�b�Z���X�Ⓤ���Ƃ������]�����鎋�������܂Ƃ߂��uSDGs�o�c�K�C�h�v�����܂Ƃߌ��\�����B ���̃K�C�h�́A���{��Ƃ����łȂ��ASDGs�̌o�c�ւ̎捞�݂�͍����鐢�E���̊�ƁA�܂��A���̊�Ɗ������x���鍑���O�̓����ƁE�W�@�ցE�e�����{�ɁA����̎��g�݂̗��j�Ղ������̂��B����ɁA���{��Ƃ́uSDGs�o�c�v�̗D�ꂽ���g�݂𐢊E��PR���邱�ƂŁA�C�O������{��Ƃւ̓����𑣂����Ƃ���ȑ_�����B �����A��Ƃɂ����āA���A������uSDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�j�v�������ɂ��Ċ�ƌo�c�Ɏ�荞�݁A��������ł͂Ȃ��A��Ƃ�ESG�i���E�Љ�E�K�o�i���X�j�Ɋւ�����g�݂��l�������uESG�����v���Ăэ���ł������́A�����I�Ȋ�Ɖ��l�̌���̊ϓ_����d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����m���A�u������E�������ƂÂ���n���h�u�b�N�v���Љ� ���̃n���h�u�b�N�́A�����̘A�g�E���������ΏۂƂ����q�A�����O�������ʓ�����ɁA����28�N2������12���ɂ����Ĉ��m�������瓙���i���c��i�����A���ƎҁANPO�A�w���o���ҁA�w�Z����W�ҁA�Љ��W�ҁA�s���@�ւō\���j�Ō�������A���m�����w�K���s���v��i����25�N2������j�Ɏ����u������g�̃K�C�h���C���v�Ƃ��č쐬���ꂽ���́B ���n���h�u�b�N�́A1)�����E�ۈ�Ҍ����F��y�Ɉ˗��ł���u�t�E�v���O�����Љ�A2)���ƎҁENPO�E��������@�ցE�s���������F���ƎҁENPO���̋��݂��������Ƃ̎����ʂ����A�����E���k�̐[���w�тɂȂ��������ʂ�|�C���g�Љ�Ȃǂ��f�ڂ����\���ƂȂ��Ă���B�����ł́A���n���h�u�b�N���A���������i�ۂŔz�z����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������s����̌������E���w�Z�A�d�C��CO2�r�o�ʃ[���B�����z�����d���ݒu �n��V�d�͂̂߂���ł́A����Ƌ���Ɋ�Â��A������̂��ׂĂ̌������E���w�Z73�Z�ɁACO2�r�o�ʂ��[���ƂȂ�d�C�u�E�Y�f���d�C�v�̋�����4������J�n�����Ɣ��\�����B CO2�r�o�ʂ��[���̓d�C�́A�G�i���X�E�p���[�E�}�[�P�e�B���O�Ƃ̎掟�_��ɂ�苟������B���̎��g�݂ɂ��A2019�N�x�̔���̌������E���w�Z����r�o�����d�͗R����CO2���A6,555�g���|CO2�i2017�N�x���ђl�j��������[���|CO2�ɂ��邱�Ƃ��ł��錩�ʂ����B �܂��A�߂���ł���L�{�݂̉����Ȃǂɑ��z�����d�ݔ���ݒu���A�Œ艿�i���搧�x�iFIT���x�j�𗘗p�����A���d�ݔ����璼�ځA��L�{�ݓ��ɓd�͂��������鎖�ƂȂǂ����i����B�u��FIT���d�v�́A��L�{�݂ɐݒu���鑾�z�����d�ݔ��Ŕ��d�����d�C�ڋ�������B�u�n�~�A�g�v�́A�~�d�r�ɒ~�����d�C���s�[�N�J�b�g��h�Гd���Ɋ��p����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăj���[���[�N�A���w�r���ɏȃG�l�����߂�V�@�łǂ��ς��H �j���[���[�N�s�c��͍��N4���A2050�N�܂łɓ�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ�80���팸����u�C�r���C�[�[�V�����@�iClimate Mobilization Act�j�v�����B�K���Ώۂ͐��\�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ�������B ���@�́A2300�������[�g���ȏ�̌����̃I�[�i�[�ɑ��A2030�N�܂ł�CO2�r�o�ʂ�2005�N���x������40���팸���邱�Ƃ��`�����B�j���[���[�N�s�̉������ʃK�X��3����1��r�o���Ă����5�������ΏۂƂȂ�B 1931�N�ɏv�H�����G���p�C�A�X�e�[�g�r���́A2009�N�����600���~�������đ�K�͂ȉ��C�H����i�߂Ă���A�G�l���M�[����ʂ�40���ȏ�팸����Ƃ��Ă���B�����̒f�M�������߁A6500���ȏ�̑��K���X��300���̓d���A67��̃G���x�[�^�[��S�ĉ��C�B����ɍŐV���̃G�l���M�[�Ǘ��V�X�e�����B ����ł���Ⴊ�A1984�N�v�H��58�K���Ă̑��K���X����̃g�����v�^���[���B�������A�o�ϓI�ɂ͈Ӗ�������ƁA���Ƃ͕��͂��Ă���B �o�T�uAFP News�v |
|
|
| �����k��ȂǁA�������g�o�̐V���������^�i�m�X�|���W�Ɛ������p ���k��w�A���Y�����ԁA�M�B��w�A���s��w�A���R��w�̌����O���[�v�́A���R��}��p�����V�����q�[�g�|���v�̌������Ă����B �{�����ł́A�_��ɕό`����i�m���E�́u�i�m�X�|���W�v�ɁA�t�̏�Ԃ̗�}���܂܂��Ă��牟���t���ĕό`������ƁA��}���������ċC�̂ƂȂ��ĕ��o����A�C���M�ɂ���ė�p���\�ł��邱�Ƃ����o�����B���Ƀi�m�X�|���W��������ƁA�C�̂��t�̂ƂȂ��Ď�荞�܂ꔭ�M����B���͂ɂ��C�t���]�ڂ𗘗p���邽�߁A��}�ɂ͐���A���R�[���Ȃǂ̊��ɗD���������𗘗p�\���B�i�m�X�|���W�͉��x�ł��J��Ԃ���}����荞�݁A���o���邱�Ƃ��ł����ɁA�i�m�X�|���W�������t���邽�߂ɕK�v�ȓ��͂͂���قǑ傫���Ȃ����߁A�G�l���M�[�����̍����q�[�g�|���v�̐v���\�ƂȂ�B �o�T�u���k��w�v |
|
|
| ���I������IoT�ŔՓ����x���펞�Ď����A�ݔ��ُ��\�����鉷�x��ԊĎ��@�픭�� ���x��ԊĎ��@��́A����ՁA��d�ՁA�z�d�ՁA���͔ՂȂǂ̔Փ����x��IoT�ɂ���ď펞���u�Ď����A�Ǝ��̃A���S���Y���ňُ픭�M��\������B���u�ُ̈��~���X�N���ጸ���A�ۑS���̑���Ɉُ���Ď����邱�ƂŁA�ݔ��ۑS���Ȑl���ł���B �Փ����x�́A�Փ��ɐݒu������ڐG���x�Z���T�[�ŊĎ�����B���Z���T�[�͏��^�ŁA90�x�~90�x�ƍL����p�ł��邽�߁A���s���̂Ȃ�����Փ��ɂ��ݒu�ł��A���Ȃ��Z���T�[���őS�ʂ̉��x�𑪒肷��B���u����̊Ď����\�ŁA�ۑS�������x�����_���̂��߂ɏ���K�v���Ȃ��Ȃ�B ���肵���f�[�^�́A�\�m�ۑS�Ɋ��p�ł���B���x�㏸�X���͂��ē��B���x��\������u���B�\���A���S���Y���v��A�Ώۋ@��̉��x�㏸�݂̂��m�F����u�������o�A���S���Y���v�ɂ��A�ُ�X���𑁊��ɔc���ł���B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/7�@]�@�@�� |
|
|
| ��GMO�N���E�h�A���[�^�[�_���Ɩ��x���T�[�r�X�uhakaru.ai�v���@�\���� GMO�N���E�h�́AAI�Ń��[�^�[�_���Ɩ����x������T�[�r�X�ɁA4�̐V�@�\��lj������B ���T�[�r�X�́A���[�^�[���X�}�[�g�t�H���ŎB�e���邾���ŁAAI���摜��F�����Ēl��ǂݎ��A�����ő䒠�L���܂ōs���Ă����T�[�r�X�B���[�^�[�̎B�e�E�摜�ǂݎ��͐�p�̃X�}�z�A�v���𗘗p����B�A�v���̎g���������̂��ߋ@�\������s�����B �n���ȂǓd�g���͂��ɂ����ꏊ�ł����p�ł���悤�ɃI�t���C�����[�h��lj������B�d�g�̂���ꏊ�ɖ߂��Ă���B�e�����ʐ^�𑗐M����ƁAhakaru.ai�Ɠ������A�f�[�^�����s����B �܂��A�u�����ǂݏグ�v�@�\���lj����ꂽ�B����ɁA�V���Ɂu�A�i���O�p�l�����[�^�[�i�d���v�j�v�u�������[�^�[�v�Ɏ����i�x�[�^�Łj�Ή������B�����C���t���̓_ ���Ɩ��̂قڂ��ׂĂŊ��p�ł���悤�ɂȂ����Ƃ̂��ƁB ���i(�ŕ�)�́A�V�X�e�����p�������z3���~�ƁA�ǂݎ�郁�[�^�[1��ɂ����z300�~�B �o�T�uImpress Watch �v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A"�Ɩ����̂悤�Ɍ����Ȃ�" �I�t�B�X�Ɩ� SmartArchi�́A�u���z�Ɏ��R��^����B�v���R���Z�v�g�ɓW�J���Ă��錚�z�Ɩ����B ����V����600�O���b�h�V������Ȃ���A���R�ȃ��C�A�E�g���ł���Square+Type��lj����A�i���낦���g�[����B �Ǝ��̌��w�v�Z�p�ɂ�铱���p�l�����̗p���A��Ԃɐݒu�����ۂɁA�Ɩ����ł���Ȃ���A�Ɩ����̂悤�Ɍ����Ȃ��A���z���Ɩ��̂��炦�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�܂��A�c����}�������˔E�{�̓h��(�����ˍ��g�U���F���̓h��)�ɂ��A�f�荞�݂����Ȃ��A�C���e���A�Ɏ��R�ɗn�����ނƂ��Ă���BSquare+Type�́A�I�t�B�X�r���ɗ\�ߐݒu���ꂽ600�O���b�h�̃V�X�e���V��ɓK�����A�V�䂷�ׂĂ�ւ���K�v���Ȃ��A�Ɩ��������ւ��邾���ŁA���ɂ���ԉ��o���\�Ƃ��Ă���B����������40,000����(�����ێ���85%)�B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
| ���g�C���̉����s��������I�u���P�v�̕��y���� �g�C�����̉���ɍł����ʓI�Ȃ̂��ATOTO�́u���P�v���͂��߂Ƃ����[���@�̎g�p���B�ɂ�������炸�A�����p�ɔ�גj���p�g�C���ɂ͋[���@���ݒu����Ă��Ȃ����Ƃ������B �ЂƐ̑O�Ȃ�A�����B�����߂ɐ���2�`3���Ă������A�������̖��ʂ��������邽�߂ɋ[���@�����܂ꂽ�BTOTO�̎��Z�ɂ��A�[���@����������邱�ƂŁA1000�l��(��������400�l)�K�͂̃I�t�B�X�Ȃ�A�N�Ԗ�551�����b�g���̐ߐ��A��386���~�̐ߖ�ɂȂ�Ƃ����B �j���̑����͔r�����������܂ŋC�ɂ��Ă��Ȃ��悤�����A�ŋ߂́i�n�l����h�~���܂߁j�j���ł��֍��ɍ����ėp�𑫂��l�������Ă��Ă���B�w�[���@���g���j���������Ă���x�Ƃ̘b������B �s��̐��Ƃ��āA�u�����͂��ƂȂ��������Ă���v�A�u�����ĂȂ��v�A�u�ꏏ�ɐ��������ĉ���2�d�ŏ����Ă�v�ƁA���܂��܂Ȋ��z������B�g�C���̍\���Ȃǂɂ��A�[���@�����ł͌��E������B �o�T�uYahoo �j���[�X�v |
|
|
| �����z�����d�Łu��C���琅�𒊏o�v���鎩���_�Ɛ��Y�V�X�e�����J�� �l�C�`���[�_�C���́A���z�����d�V�X�e���Ƃ��ꂩ�瓾���d�͂ŋ�C�����琅�𒊏o����V�X�e���𗘗p���������_�Ɛ��Y�V�X�e�����J�������B ��̓I�Ȏd�g�݂́A���z�̓��˔M�ɂ���C�̖c���Ǝ��k�̈��͂𗘗p���āA�V�R�|�n�ɐ������R�̃��Y���ŏz������Ƃ������́B����ɂ��V�R�̔|�n�����������āA���R�Ɠ����ɉh�{�f�����R�ɐ�������A���R�̐ۗ��ɂ���čœK�Ȑ�����������Ő��������Ƃ����B �͔|���тł́A���ʃg�}�g1����Ă�̂ɐ�2���b�g����������Ȃ����������A�I�n�͔|�ł̒���ƒP����r����Ǝ���95���ȏ�̐���ߖ�ł��鎖�ɂȂ�B ���V�X�e���̓\�[���[���d�V�X�e���Ɛ��������u�Ƃ�A�����������̂��B�������u�́A�ƒ�p�̏��^�①�ɒ��x�̑傫���ŁA1��100���b�g���i����d��1.3kWh�j�̐�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����u�̓������M�ڗ�p����t��V�X�e�����J���B���Y�{�݂̏ȃG�l�ƍ�Ɗ��̉��P������ �听���݂́A�H��ȂǂŎg�p����Ă��鐶�Y���u���甭������������M�������Ɋg�U����O�ɒ�����p���i20�����x�j��p���Ē��ڗ�p����t��V�X�e�����J�������B �{�V�X�e���̓����ɂ��A���Y����ɂ�����G�l���M�[�̍팸�ƍ�Ɗ����P���\�ƂȂ�B �H��Ȃǂ̐��Y�{�݂ł́A�l�X�Ȑ��Y���u�̉ғ��ɔ������u���̂����ʂ̔M���������Ă���B�����̔M�͎{�ݓ��ɂ����ċ̕��ׂɂȂ���A�]�ƈ��̍�Ɗ��ɉe�����y�ڂ��Ă���B�]���͒ቷ��p���i7�����x�j���z����19�����x�܂ŋ�C���p��������̗Ⓚ�@��p���Ď����S�̂��p���Ă����A��p���̐����ɑ����̃G�l���M�[���K�v�ƂȂ�B�܂��A�������ψ�ɕۂ��Ƃ���������B ���V�X�e���́A�z�ǂ݂����������p�l���Y���u�̕\�ʉ��x�����������Ɏ��t���A������p���𗬂����ƂŁA���Y���u�̓������M�ڂ������悭��p����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����d�ł��鑋�K���X�A���{�Ɏq���ăx���`���[�Ƌ����J���� ���{�Ɏq�͓����ȑ��z�����d�Z�p��L����ă��r�L�^�X�G�i�W�[�ЂƁA���z�����d���\�Ȍ��z�p���K���X�̋����J���ɍ��ӂ����Ɣ��\�����B ���Ђ́A�i�s���̌����J���ƋZ�p�T�|�[�g�ɂ�苤���J���ɎQ�悷��B ���r�L�^�X�G�i�W�[�̓����ȑ��z���R�[�e�B���O�́A�����߂��Ȃ���A������i���O���ƐԊO���j��I��I�ɋz�����A���E���Ղ炸�Ɏ��͂̌���d�C�ɕϊ�����B ���̑��K���X�́A�W���I�ȃK���X�����ߒ��Ō��z�p���ɂ��̂܂g�p���邱�Ƃ��ł���B���Ђ́A���̋Z�p��p���āA������̌^���z�����d�̓����\�[���[�E�C���h�E�������J������B�ԊO�����z�M���Ւf���A�����̃G�l���M�[�������グ�邱�ƂŁA�[���G�l���M�[�����̎����Ɋ�^����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�R�}�[�N�u�z�e���E����Version2�v�F���ł̏��̔F��{�ݒa�� �G�R�}�[�N�ł͏]���́u�z�e���E���فv�F����S�ʓI�Ɍ������A�V�o�[�W�����Ƃ��Đ��肵���u�z�e���E����Version2�v�F���ɂ����āA���̃G�R�}�[�N�F��{��4�ЁA5�{�݁i���É��ό��z�e���A�z�e���i�S���L���b�X���A�L���b�X���v���U�A�˓c�ƁA�z�e���O�������B�A���R�j���a�������B �ȃG�l�E�ߐ��Ȃǂ̊�{�I�Ȋ���ɉ����āA�H�i���X�팸�A�n���Љ�ւ̍v���ȂǑ��l�Ȏ��g�݂�]������V�o�[�W�����̔F���Ɋ�Â��A����ɂ킽����ւ̎��g�݂��������x���Ŏ��{����Ă���z�e���E���ق��F����擾�����B����ɂ��A�G�R�}�[�N�F��z�e���E���ق�Version1�ł̔F��{��7�{�݂ɉ����āA���v12�{�݂ƂȂ����B�h���{�݂𗘗p�������҂������������S�̂ł̊��ӎ��̍��܂�֍L�����Ă������Ƃ����҂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������z���ȃG�l�@�������^�Z��̑�A�p�������� �ȃG�l���M�[��ւ̓K���`���̑Ώ۔͈͂��L���A�V���ɒ��K�́i�����ʐ�300�������[�g���ȏ�`2�畽�����[�g�������j�̔�Z��z����lj����邱�ƂȂǂ𒌂Ƃ������z���ȃG�l�@�̉����Ă��Q�c�@�{��c�ō̌�����A�S���v�ʼn��A���������B�ȃG�l��ւ̓K���`�����ۂ��ꂽ���K�͂̔�Z��z���͌����_�œK������91���ł��邱�Ƃ���A�s��̍��������Ȃ��Ƃ����B �����@�ł́A�����Z��̏ȃG�l�𑣐i����Z��g�b�v�����i�[���x�̑Ώۂ��g�傷��B�V���ɑ��n�E�X���[�J�[�����z�𐿂����������Z�����݃A�p�[�g��lj������B���z�m���猚�z��ɑ��ďȃG�l���\�Ɋւ�������`�������荞�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���C��ϓ���A�X���̃j���[���[�N��ɒ��ځ^�s�ꃁ�J�j�Y�����œ_ ���E�̋C��ϓ���́A2015�N12���ɐV���ȍ��ۘg�g�݂ł���p�����肪�̑����ꂽ���Ƃő傫�ȓ]���_���}�����B �p�������2020�N������{�t�F�[�Y�ɓ��邱�Ƃ�����A�������ʃK�X�r�o�팸��̋����Ɍ������@�^�����܂��Ă���B���N�ɓ���A���A�̋C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j���������ʃK�X�Z��̂��߂̃K�C�h���C��������B����A���{���c�����߂�20�J���E�n��iG20�j�G�l���M�[�E���W�t����̊J�Â��T����ق��A9���̍��A����ɍ��킹�j���[���[�N�ŊJ�Â����2�̎�]����ɂ����ڂ��W�܂肻�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��������ʌv�Ȃǂ̓d�̓f�[�^�A�p�r�ő������x�敪�^�G�l�������� �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���́u������Z�p�����p�����V���ȓd�̓v���b�g�t�H�[���݂̍��������v�́A�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j�ɑ�\�����d�̓f�[�^�𗘗p�����ł̃��[���������c�_�����B ��p���S�ɂ��Ă͑��z�d�֘A���ƂȂnj��v���̍������̂ƁA���Y�Ƃł̃r�W�l�X�ɐ���������̂��A�������x��̈������敪���邱�ƂȂǂ���N���ꂽ�B �d�̓f�[�^�͉^���ƂŊ��p���邱�Ƃő�z����������������A�Ɠd�Ɛl�H�m�\�iAI�j��g�ݍ��킹�A�^�]�̍œK����}��ȂǑ��Ǝ�ł̊��p�j�[�Y�����܂��Ă���B�������Ԃ܂��A�h�Ќv��̍���ɖ𗧂Ă���\��������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��EU������A�g���̂ăv���X�`�b�N�팸�ւ̎w�߂��̑� EU������́A�v���X�`�b�N�ɂ����A���ɊC�m�̉�����}�����邽�߉��B�ψ����Ă��Ă����g���̂ăv���X�`�b�N�w�߈Ă��ŏI�I�ɍ̑������B�w�߂̓��e�́A 1�j��֕i�����ɑ��݂���g���̂ăv���X�`�b�N���i�̔̔����֎~�B�Ώې��i�ɂ́A�Ȗ_�̐c�A�t�H�[�N��X�v�[���A�M�A�X�g���[�A���A�X�`���[���i�|���X�`�����j���̐H�i�ƈ����̗e��E�J�b�v�ޓ��B 2�j�v���X�`�b�N���̐H�i�E�����e��A�J�b�v�ނ̏���}���[�u�B 3�j�g�吶�Y�ҐӔC�������t�B���^�[�⋙��ɓK�p���A���݂̐��|��p�ɏ[�Ă�B 4�j�v���X�`�b�N�{�g���ɂ��āA���ʉ���ڕW�Ƃ���2025�N�܂ł�77%�A2029�N�܂ł�90%��ݒ�B�{�g�����痣��Ȃ��L���b�v�̐v��A�������@�Ȃǂ̕\�����`�����B���T�C�N���ނ̎g�p�䗦��PET�{�g����2025�N�ȍ~25%�A���ׂẴv���X�`�b�N�{�g����2030�N�ȍ~30%�ƒ�߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������t�����r�o�}���@�����������g���h�~�։���O�� �������ʂ��ɂ߂č����t�����ނ̓K�ȉ�������𑣂������t�����r�o�}���@�����������B �Ɩ��p�̗①�ɂ�@��̔p�����ɗ�}�̑�փt�����Ȃǂ���C���ɕ��o����Ȃ��悤�A�r�����L�҂�ւ̔�������������B �@���p������ۂɃt�����ނ�K�ɉ�����Ȃ��r�����L�҂�ւ̔����́A�s���{���̊����▽�߂ɏ]�킸�A�ᔽ�s�ׂ��d�˂Ă����ꍇ�Ɍ���K�p���Ă����B�����@�́A�ᔽ����x�ł��m�F����A�i�K�܂���50���~�ȉ��̔������Ȃ��B�����̉�̍H���̏���s���{���̃��T�C�N���S�����c�����A�������茟���ł���K����݂����B ���ȂȂǂɂ��ƌ��݁A�Ɩ��p�@���p������ۂ̃t�����ނ̉������4����ɂƂǂ܂��Ă���B��փt�����̓I�]���w��j�Ȃ����ߋߔN�����g���Ă��邪�A�������ʂ͓�_���Y�f�̍ő�1���{������Ƃ����B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ������30�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[����2019�j ���{�͍��A�p�����鎩�R�ЊQ�ւ̑Ή��Ƒ�A�܂������̕����Ƃ��������ł̎��g�݂�i�߂Ȃ���A�n�����g���Ƃ������E�K�̖͂��Ɏ��g�ނׂ��AGHG�팸�Ɍ����Ă��܂��܂Ȏ{��𗧂āA�����Ɏ��s���Ă���B�u�G�l���M�[����2019�v�ł́A�����������{�̃G�l���M�[����̌���ƖڕW�A����ɂ̓G�l���M�[���߂��鐢�E�̓�����m�邱�Ƃ��ł���B��v�|�C���g�́A �@�����̕����E�Đ��Ɍ������ŋ߂̎��g�� �A�p��������ӂ܂����n�����g����E�G�l���M�[���� �B�d�́E�K�X�E�R�������̃��W���G���X�i�u�����v�A���邢�́u�́v��u�e�͐��v�j��̏d�v���B�����O�̏����Ɍ������G�l���M�[����̏d�v���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2019/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���Ɩ����y�ѓd���̐V�����ȃG�l������� �Ɩ����y�ѓd���ɂ��Ă��ꂼ��2020�N�x�A2027�N�x��ڕW�N�x�Ƃ���V�����ȃG�l������߂�ȗߋy�э��������z���ꂽ�B �Ɩ����̏ȃG�l��́A����܂Ōu�������݂̂�ΏۂƂ��Ă������A�V����LED�d������Ώۂɉ�����2020�N�x��ڕW�N�x�Ƃ���V���Ȋ���߂��B ����܂ł́u�Ɩ����̌����̖��邳�i�S�����j�v�̕\���ɕς��āA�V���Ɂu�Ɩ����̖��邳�i�Ɩ����S�����j�v�̕\�����`���t������B����̌u�������ł����Ă��A�u�Ɩ����S�����v�́u�S�����v�����l���������Ȃ�B �d���̏ȃG�l��́A����܂Ōu�������v��LED�����v��ΏۂƂ��Ă������A�V���ɔ��M�d����Ώۂɉ�����2027�N�x��ڕW�N�x�Ƃ���V���Ȋ���߂��B����Ɠ��l�ɏ���d�͗ʂ�����́u�����v�̌����̖��邳�v���G�l���M�[��������Ƃ��Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���O�H�d�H�A�V������}R454C�����^�G�A�R���ɍ̗pEU�K������� ���Ђ́A�n�����g���W��GWP���ɂ߂ĒႢ��}R454C���A���E�ŏ��߂�1�n�͋��̏��^�G�A�R���ɍ̗p����Ɣ��\�����B ����A���^�G�A�R���ɍ̗p����R454C��}�́A�I�]���w�j��W�����[���ŁAGWP��146�B�����^�@��p��}�Ƃ��Č��ݍL���g���Ă���R410A�iGWP�F2090�j��R32�i��675�j�Ɣ�ׂ�Ƃ��ꂼ���1�^14�A1�^5�ł���B �܂��A���؋@�ɂ�鉷�g���e���iGWP�~��}�ʂŁA��}�ł̉��g���e�����Z�o�������́j�́A�]���@�ɔ��91.3���̍팸�ƂȂ�B����}�́A������}�䂦�ɔM�������\�ɗ��Ȃǂ̉ۑ������Ă������A�M������œK���ʉ��Z�p�Ȃǂ̑�ɂ�肻�̉ۑ�����������B �M�K�������i�I�]���w�͔j�Ȃ����n�����g���ɂ͈��e���������փt�����iHFC�j�܂Œi�K�I�ɍ팸��������j�Ȃǂ�w�i�ɊJ��EU�́AGWP150�ȏ��HFC���܂ޒn�����g�������̔̔��E�g�p�K���͈͂�2015�N��菇���g�債�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���S�ő̌^�̃A���~�j�E����C�d�r�A�y�m�F�f���J������ �������w���[�J�[�̕y�m�F�f�́A�d�����ɃC�I���t�̗ގ��̐[�����n�}��p���āA�œK�ȓY���܂��������邱�Ƃɂ��d�������ő̉����A�S�ő̌^�̃A���~�j�E����C�d�r����邱�Ƃɐ��������Ɣ��\�����B ����ɂ��A�������₷���A��蒷���Ԃɂ����Ĉ���ȃA���~�j�E����C�d�r�����p���ł���\�������܂����B�A���~�j�E����C�d�r�̗��_�e�ʂ�8,100Wh�^Kg�ł���A���s�̃��`�E���C�I���d�r��30�`40�{�̓d�r�e�ʂ������Ă���B�A���~�j�E���͋�C���ł�����ŁA���ʂł��D��Ă���B���̂��߁A�A���~�j�E����C�d�r�́A���}�Ȏ��p�������҂���Ă���B ����̌����ł́A���ɂɃA���~�j�E���A��C�ɂɒY�f�n�A�`�^���n�Ȃǂ̍ޗ���p�����B����ɁA�d�����ɃC�I���t�̗ގ��̐[�����n�}�n�̓d���t��p���āA�S�ő̌^�̃A���~�j�E����C�d�r����邱�Ƃɐ��������B �����_�ɂ����ẮA�A���~�j�E�����ɂ̏d�ʂɑ��āA�ʏ�̎����A��C���ɂ����ď������œK�������500mAh�^g�ȏ�̓d�r�e�ʂ��m�F����n�߂Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����40���~�̏Z��p���z�����d�V�X�e�������A���W���[��1������ݒu�\ �G�N�\���̃R���p�N�g���f���́A���z�d�r���W���[����1������ݒu�ł���A�V���z�̃V�X�e���B �]���͂ł��Ȃ��������z�d�r���W���[��3���ȉ��ł̑��z�����d�V�X�e���̐ݒu���������A�ƂŎg������������y�Ȕ�p���S�Őݒu�\�ɂ����B �V�z���ɁA���z�d�r���W���[��3����ݒu����ꍇ�̗\�z�������i�E�Ŕ��i�H����p�܂ށj��39��8000�~�O��ƂȂ�B ���̃��f���ł́A��d���ɑΉ�����}�C�N���C���o�[�^�����z�d�r���W���[���ƃZ�b�g�œ��삷�邽�߁A1������ݒu�ł���B���ꂼ��̑��z�d�r���W���[�����Ɨ����Ĕ��d���s���̂ŁA�e�̉e�������Ȃ��A���ʂɊW�Ȃ��ݒu�ł���B�ݒu���̓d�C�w���ʍ팸���ʂ͖�30�� ���Ђ̎��Z�ł́A���z�d�r���W���[��3�����ł��A��ʓI�ȉƒ�i�����̐��ꂽ���ŁA���d�͂�300kWh�^���g�p����ƒ��z��j�̓����̓d�͎g�p�ʂ��قژd�����Ƃ��ł��邽�߁A�d�C�w���ʂ��30���팸���邱�Ƃ��ł���B�V�X�e���ɂ�20�N�ۏ�W���t�сB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I���A200�X�܂�PPA���f�������։����ɑ��z�����d���ݒu PPA���f���Ƃ́A�uPower Purchase Agreement�i�d�͔̔��_��j���f���v�̗��ŁA�d�͂̎��v�Ƃ�PPA���Ǝ҂ɕ~�n�≮���Ȃǂ̃X�y�[�X����APPA���Ǝ҂����z�����d�V�X�e���Ȃǂ̔��d�ݔ��̖����ݒu�Ɖ^�p�E�ێ���s�����́B �܂������ɁAPPA���Ǝ҂͔��d�����d�͂̎��Ə���ʂ����j�E�������A���v�Ƒ��͂��̓d�C�������x�����B���Ђ͂���PPA���f���̓����̑�1�e�Ƃ��āA�C�I���^�E���Γ삪�����X�y�[�X��B������PAA���Ǝ҂��o�͋K��1,161.6kW�����̑��z�����d�p�l����ݒu����B�����Ŕ��d���ꂽ�d�͂́A�C�I���^�E���Γ삪���Ə���Ƃ��čw���E���p����B����ɂ��A�d�͂�2����������ł���Ǝ��Z���Ă���BPPA���Ǝ҂́A�O�HUFJ���[�X�B �C�I�����O���[�v�e�Ђ̏��Ǝ{�݂̃X�y�[�X��L�����p���A�uRE100�v��E�Y�f���̖ڕW�B���Ɍ��������g�݂̈�Ƃ��Ď��{����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���s�S���̍��w�I�t�B�X�r����ZEB Ready�����G�l���M�[����ʖ�61���팸 �听���݂́A���{���s�k�l�G���A�ɁA�ߋE�Y�ƐM�p�g���̐V�{�X�r�������������A����܂œs�S���̍��w�r���ł͎���������Ƃ���Ă���ZEB Ready��B�������B ���r���́A�_�u���X�L���̊O���ŁA�����\�ɂ��D�ꂽZEB�Ή��̓s�s�^���w�����ł���B���z�ʐς�658.76m2�A�����ʐς͖�11,000m2�B �O�ς̓����ƂȂ�O���̃K���X�ɂ́A�l�ՔM�E�f�M���\�ɗD�ꂽLow�|E���w�K���X���g�p���Ă���B���ӂɂ͑��z�������ǔ��^�u���C���h��ݒu���A���ʓI�ɓ��ˎՕ����s���B���̑��ɂ��A�_�u���X�L�����̔M�𗘗p�����V�X�e����l���m�Z���T�[�𗘗p�����Ɩ�������B���C�g�A�b�v�ɂ�LED�Ɩ����g�p����ȂǗl�X�ȏȃG�l�Z�p����g���邱�ƂŁA�]���̃I�t�B�X�r���ɔ�ׁA��61���̔N�Ԉꎟ�G�l���M�[����ʂ��팸���AZEB Ready�����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2017�N�x�A�G�l���M�[����ʂ͑����Ă�����k�Јȍ~�A���߂đ��� �����G�l���́A�e��G�l���M�[�W���v������ɁA2017�N�x�̑����G�l���M�[���v�m����쐬���A�G�l���M�[�������тƂ��Ď��܂Ƃߌ��\�����B 2017�N�x�̍ŏI�G�l���M�[����́A2016�N�x��0.9�����ŁA�����{��k�Јȍ~���߂đ��������B�d�͓͂�1.5�����������B ����ʂɂ݂�ƁA�ƒ땔��͌��~���e�����A��4.2�����Ƒ啝�ɑ��������B��ƁE���Ə�������͊����Ȍo�ϊ����ɂ�蓯0.8�����i���������Ƃ͓�0.8�����A�Ɩ����͓�0.9�����j��4�N�Ԃ�̑����ƂȂ����B�^�A�͓�0.8�����B�^�A��������v�S����ő��������B �d�͏���́A�ƒ��5�N�Ԃ�̑����ƂȂ铯2.3�����A��Ǝ��Ə����͓�1.2�����������B�ăG�l�d�͂̋���������16���������B �G�l���M�[�N��CO2�r�o�ʂ́A2016�N�x��1.6������4�N�A�����������B����ʂł́A��ƁE���Ə�������1.8�����A�^�A����1.0�����̈���A�ƒ�͓�0.6�����ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�ȃG�l�^�m���t�����V���[�P�[�X�̓������x�� �Ɩ��p�Ⓚ�①�@��Ȃǂɗ�}�Ƃ��Ďg�p����Ă���t�����ނ̘R�����́A�I�]���w�̔j���n�����g���ւ̈��e�����y�ڂ����Ƃ��m�F����Ă���B �s�ł́A�t�����ނ̘R������Ƃ��āu�ȃG�l�^�m���t�����Ⓚ�①�V���[�P�[�X�v�̕��y���㉟�����邽�߁A����26�N�x���瓖�Y�@��̓����E�ݒu�ɑ���⏕�����{���Ă���B�⏕�Ώێ҂́A�������Ǝҋy�ьl�̎��Ǝҁi���[�X����ꍇ���܂ށj�ŁA�ȉ��̕⏕�v����S�Ė��������́B �@�E�s���̎��Ə��ɐݒu����邱�� �@�E���g�p�i�ł��邱�� �@�E2020�N3��13���܂łɐݒu����������B �⏕���͐ݒu�ɌW��o���1/3 �ŁA���x�z��1�䂠����500���~�A1���Ǝ҂�����1,500���~�܂łƂȂ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���uEV��CO2�����v���h�C�c�����G�R�m�~�X�g�咣�Ř_�� �u���d��d�r�����̉ߒ����l������A�d�C�����ԁiEV�j�̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ͍ŐV�̃f�B�[�[���Ԃ�葽���v�B �h�C�c�̒����G�R�m�~�X�g�炪����Ȍ������\���A�_���ɂȂ��Ă���B�f�B�[�[���Ԃ̔r�K�X�s�����A�Ǝ����ԋƊE���i�߂�EV�V�t�g�ɗ�␅�𗁂т����˂Ȃ����e���B �����܂Ƃ߂��̂́A�h�C�c���\����V���N�^���N�AIFO�o�ό������̃W���O������B�T�C�Y�Ȃǂ����ʂ��郁���Z�f�X�E�x���c�̃f�B�[�[���ԁuC220�v�ƁA�ăe�X���̂d�u�u���f��3�v��CO2�r�o�ʂ��A���s�ɕK�v�Ȕ��d�ʂȂǂ��l�����Ĕ�r�����B �h�C�c�ł�CO2�𑽂��r�o����ΒY�Η͔��d���d���S�̂ɐ�߂銄���������A���f��3�̔r�o�ʂ��ő�28�������Ȃ����Ƃ����B�G�R�m�~�X�g��͕��ŁA�uEV��r�o�[���Ƃ������̂́A�����I���܂������v�Ƒi�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ȁA�Z�܂��̉��C�K�C�h���C��������A��̗��� ���y��ʏȏZ��Lj��S���Z���i�ۂ����J�����u������̌��N�ʼn��K�ȕ�炵�̂��߂̏Z�܂��̉��C�K�C�h���C���v�ɂ��ƁA���C�̍ۂɔz�����ׂ��|�C���g�i�z�������j�́u�g���������v�u�g���₷�������v�Ȃ�8�B�Ԏ��̕ύX�ȊO�A�������IoT�Z�p��ŐV�Ɠd�̊��p�E�����ł���Ȃ���P�������߂�B �z�����ڂƂ��āu���M���v�u�O�o�̂��₷���v�u�g�C���E�����̗��p�̂��₷���v�u���퐶����Ԃ̍������v�u��v������̃o���A�t���[�v�u�ݔ��̓����E�X�V�v�u���E���E�����E���x�Ȃǁv�u�]���Ԃ̊��p�v�������A���ꂼ���̍��B�Ⴆ�u���M���v�ɂ��ẮA�u�����⍂�f�M�T�b�V�Ȃǂ�ݒu���ċ����J�����̒f�M����}��A�����ɒg��[�ݔ���K�ɐݒu����v�u�����Ɣ��i�L���A�g�C���A�����Ȃǁj�̊Ԃʼnߓx�ȉ��x���������Ȃ��v�Ȃǂ𐄏����Ă���B�܂��u�g�C���A�����A�䏊�̐ݔ��@��̍X�V�v�Ȃǂ𐄏����Ă���B �o�T�uBCN�v |
|
|
| ��2050�N�������ʃK�X8���팸�B���ɂ͌��q��2900��kW�K�v�� �d�͒����������́A�������ʃK�X��2050�N�܂ł�80���팸���鐭�{�ڕW�̒B���ɕK�v�ȃG�l���M�[�����̕��͌��ʂ��������B 2013 �N�x��œ�_���Y�f�iCO2�j��80�����炷�ꍇ�̓d���\���́A���ȂȂNJe�@�ւ̎��Z�ɉ����čő���̍Đ��\�G�l���M�[�����Ă��A2900���L�����b�g�̌��q�͔��d���K�v�ɂȂ�Ǝw�E�B60�N�^�]��86�����̍����ݔ����p����O��ɒu���Ă��A���ݘF�����ł͑��肸�A�V���݂��s���Ƌ��������B�V���݂ɂ͒������Ԃ������邱�Ƃ���A���{�ɂ͋i�ق̔��f�����߂���Ǝw�E�����B �Đ��\�G�l�̔��d�d�͗ʔ䗦��66���ɂȂ邪�A�����18���������q�͂ŕ₢�A�Γd���䗦��84���܂ō��߂�K�v������B�c��16���͎��g�������p��LNG�i�t���V�R�K�X�j�Η͂���������B �܂��A���z���╗�͂̏o�͐�����[���ɂ���ꍇ�A�~�d�r��2��1�疜�L�����b�g���K�v�ɂȂ�ƕ��͂����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցA2018�N�ɍăG�l���d�e�ʂ͑S�d�͂�3����1�ɐ����ƕ� ���ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցiIRENA�j�́A�u2019�N�Đ��\�G�l���M�[���d�e�ʓ��v�v�ŁA���E�̍Đ��\�G�l���M�[�i�ăG�l�j���d�e�ʂ�2018�N��171�M�K���b�g�iGW�j�������A�S���d�e�ʂ�3����1�ɐ��������ƕ����B �����v�ɂ��ƁA���ɕ��͂Ƒ��z���̑��݂��������A�e�ʑ�������84%���߂��B���͔��d�e�ʂ�49GW�������A�����i20GW�j�ƃA�����J�i7GW�j�����������B���z�����d�e�ʂ�94GW�������A���ɃA�W�A�����i64GW�j�A�����ŃA�����J�i8.4GW�j�A�I�[�X�g�����A�i3.8GW�j�A�h�C�c�i3.6GW�j�ő������ڗ������B�ăG�l�ȊO�̔��d�e�ʁi��ɉ��ΔR���ƌ��q�́j�́A2000�N�ȍ~�A���E�S�̂ł͖��N��115GW�g�債�Ă��葝�����͂قڈ�肾���A�n��ʂɂ݂�ƁA2010�N�ȍ~�A���B�A�k�āA�I�Z�A�j�A�Ō������A�A�W�A�A�����ő������Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2019/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���V���{�@���Ԍ����^�X�N�]�[���ȃG�l�V�X�e�����J�� ���V�X�e���́A���Ԃɂ����ċ��K�v�Ƃ�����ƈ�݂̂�����u���������v�ɂ��A�]���̎����S�̂�������������A�����G�l���M�[��M�G�l���M�[���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�Ǝ��ɊJ���������o�����̗p���邱�ƂŁA��ƈ�̉��x�����P�ƏȃG�l���M�[����������B ��������ю��������̌��ʂ��u���������v���������Ă��邱�Ƃ��m�F���A40���ȏ�̑����G�l���M�[�팸���ʂ����҂ł��邱�Ƃ�������A�X�ɁA���ւ̍v��(E)��l�ɑ����Ɗ����P�ɂ��Љ���̌���(S)�Ƃ������AESG�����ڕW�̒B���Ɋ�^�ł���V�X�e���ł�����̂ŁA2019�N4�����A�{�i�I�ȓ�����i�߂�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���̂̕s���R�ȕ��ł��A�����E�����݂̂ŕa�@�╟���{�ݓ��̐ݔ��@��𑀍�ł���V�X�e�����J�� �|���H���X�́A�_�c�ʐM�@�Ƌ����ŁA�����E�����F��AI����V�X�e�����J�������B �{�V�X�e���͕a�@�╟���{�݂ɉ����I�t�B�X�ł̎g�p���z�肵�����̂ŁA�X�}�[�g�X�s�[�J�[��X�}�[�g�t�H������������E������AI���F���E��͂��邱�Ƃɂ��A�̂̕s���R�ȕ��ł���Ɩ��Ȃǂ̐ݔ��@��𑀍삷�邱�Ƃ��\�ɂ����B ��ʂ̐ݔ��@�킪�ݒu�����I�t�B�X�E�a�@�E�����{�݂Ȃǂ̌������ɂ����āA�X�}�[�g�X�s�[�J�[��X�}�[�g�t�H������������E�������A�N���E�h���AI�iGoogle Assistant�j���F���E��͂�����ADialog flow�ő���w�߂ɕϊ���BACnet�Q�[�g�E�F�C����e�ݔ��@��ɑ���w�߂𑗐M����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���M������E�z�ǁu�p�M�v���d�͂ɂm�d�b�A�S�n�ޗ����J�� NEC�͔p�M��d�͂Ɋ�����S�n�ޗ��i�S�p�C�v�j���J�������B�M�̗����d���ɕϊ�����B 10���̉��x����1m2������0.4mW�̔��d���\�B�����R�X�g���Ⴍ�A���d�ʐς��L���₷���̂������B�ޗ��J���ł͐l�H�m�\(AI)�Z�p���g����������@���˔j���ɂȂ����B�����A�M������≷���z�ǂ��d���ɂȂ铹�������B�����ԃ��[�J�[�Ƃ̋��c���n�߂Ă���A���p����ڎw���B �X�s���[�[�x�b�N�M�d�ϊ��Ƃ����M�����A�X�s��������ēd���ɕϊ�����ޗ����J�������B�S�̃o���N�ނŏo�͖��x��0.4mW�ɒB�����B�Ǎނɉ��H���Ď��������A�����𗬂��ƊǍނ̒�������ɓd���������B �M������┭�d���̔r���Ȃǔz�ǂɗ��p����ƁA�z�ǂ̓����ƊO���̉��x�����������z�ǂ̑S�ʐςŔ��d����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ƒ���Ő��z�ł���Z�p����98���ė��p�ł���ЊQ�p�V�����[ �������p�\�t�g�E�G�A���J������WOTA���������鋆�ɂ̎p�́A�g�ƒ�P�ʂł̐��z�h���B �Z���T�[��AI�ʼn����ɉ������œK�ȏ����Ŕ������������邱�ƂŁA�����鐅�ɑ��Ď����ł���A�����Ȑ��������u�̎����������ăR�X�g��������������B �܂��A����̎�ނ��V���v���ŏ������₷���V�����[���̏z���璅�肵���B�F�{�n�k�ȂǑS���e�n�̔��Ŏ���@�̎��؎������d�ˁA�ЊQ�p�V�����[�p�b�P�[�W�Ƃ��Ĕ��������B1�x�g��������98���ȏ���ė��p���A100���b�g���̐��ŁA�ʏ��50�{�ƂȂ��100��̃V�����[�������ł���B ���g�݂͎����̂�������ڂ���Ă���B�_�ސ쌧�ƘA�g���A�ЊQ�p�V�����[�p�b�P�[�W�̓����␅�����{�݂ւ�AI�����̉\���ɂ��Ă̋��c���n�߂��B �����ȏ������������䂷�鍂�x�Ȑ��������ł���A�]���̏W����������A���U�^�̏㉺�����ւ̉\�����J�������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���H��r�o��CO2��CO�ɁA���ł��]����450�{�̕ϊ����x������ ���ł́A�H��Ȃǂ���r�o������_���Y�f�iCO2�j����_���Y�f�iCO�j�ɕϊ�����ۂ̕ϊ����x���A�]���Z�p�̖�450�{�ɍ��߂邱�Ƃɐ��������B �V�J���̐G�}�d�ɂ�p�����d�C���w�����ɂ��B���������̂ŁACO2�r�o�ʂ��팸���Ȃ���A�����E�h���E���i�Ȃǂ̉��w�i��R���̌����ƂȂ�CO���������Ő����ł���悤�ɂȂ�B���Ђ͐V�Z�p�ɂ��āA2020�N��㔼�̎��p����ڎw���B ���Ђ́A�d�C���w�����̔������x�������d�����x�i�d��/�d�ɖʐρj�����コ���邽�߂ɁA��������CO2���C�̂̂܂ܗ��p�ł���G�}�d�ɂ��J�������B��̓I�ɂ́A�ő́i�G�}�j�ƋC�́iCO2�j�A�t�́i���j��3�����ɔ���������3���E�ʔ������\�ȐG�}�d�ɂ������BCO2�Ɛ����ɔ��������邱�Ƃɂ����CO2�̒��ڗ��p�ɐ�������Ɠ����ɁA�ϊ������̒��d�����x�̒ቺ��}�����Ƃ����B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���_�C�L���AAI�E���o�r��g���������}�J�����K���ɑΉ� �_�C�L���H�Ƃ͗�}�Ȃlj��w�i�̊J���ŁAAI�Ƃ��o�r�זE�̊��p���n�߂��B�V�K�̉�������T������ہAAI�����E���̉Ȋw�������Q�l�ɗL�]�Ȍ������B����ɂ��o�r�זE���g�����ƂŁA�l�̂ւ̈��S���Ȃǂ�]������ہA���O�Ɋȑf�Ȍ����ł���B�ƊE�ł́A2030�N����̊��K���ɑΉ����鎟�����}�̊J������q���Ă���B����̐�i�Z�p�ɂ���}�J��������������B ���ЊJ�������������T���V�X�e���́A���߂��������͂���ƁAAI���Ȋw�_���̏����ƂȂ镪�q�\���Ȃǂ�T���B�����I�ɗ�}�J���Ɏ����ꂽ�Ƃ���A�����҂ł͔��z���ɂ����V�K���̍�����₪���������B���̐��ʂ��A���V�X�e���̉��p����̐������u�⎩���ԕ��i�ȂǂɎg���t�b�f���w�i�S�̂ւƍL���邱�Ƃɂ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���������A���`�E���C�I���~�d�r�p�Z�p���[�^�̐��Y�̐���������300���~���� �������́A�}���ɐ������Ă��郊�`�E���C�I���d�r�iLIB�j�s��ɑΉ����邽�߁A���ĂŖ�300���~�̐ݔ��������s���ALIB�p�Z�p���[�^�̐��Y�̐�����������Ɣ��\�����B ����̐ݔ������ł́ALIB�p�Z�p���[�^�u�n�C�|�A�v�i�������j�Ɓu�Z���K�[�h�v�i�������j�Y���鎠�ꌧ��R�s�ƕč��m�[�X�J�����C�i�B�̊��ݕ~�n���ɁA�V�K�ɐ��Y�ݔ��݂���B�V���Y�ݔ��́A2021�N�x����ɏ��Ɖ^�]���J�n���A���Y�\�͂�2�{�ɂ���\��B �V�K���Y�ݔ��̑��݂Ɛ��Y��������ʂ��āA�������Ɗ������̍��v�ŁA2021�N�x�ɖ�15.5��m2�^�N�ƂȂ錩���݁B ��������v���������ɂ߂A2025�N���ɂ́A�������E���������킹�Ė�30��m2�^�N�̐��Y�̐��𐮂��A�ڋq�̃j�[�Y�ɉ����Ă����B �������E�������̃V�i�W�[�Ŏ��Ɗg��BLIB�s�ꐬ���̌��́A�d�C�����ԓ��̎ԍڗp�r��d�͒����p�r���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���t���N�^���A�����ǂ̔j���AI���\�� �ăt���N�^���č��œW�J����AI�́A�ߋ��̔z�ǔj������f�[�^�����ƂɁA�z�ǔj����ŏ����ł���X�V�������w�삷��B�z�ǍX�V�ɂ������p�͔��ɑ傫���A���Ђ̋Z�p�Ȃ炱����u30�`40�����点��v�Ǝ��M���݂���B �t���N�^��2018�N5���ɐ��������̌I�c�H�Ƃ����40���~�̏o�����A�I�c���ߔ��̊������擾�����B������@�ɁA�t���N�^�͓��{�ł̎��Ɖ����������Ă���B �ŋ߂͐����z�ǂȂǂ�̔�������{���S�ǂƁA���s�㉺�����ɂ����鐅���ǂ̗\���Z�p�̌��ɒ��肵���B�č��Ɠ��{�ł́A�V���y����͂��ߐ����ǂ̗ɊW����������قȂ�B���s�̐����ǘH����e��f�[�^�����W�E���͂��邱�ƂŁA2019�N���܂łɓ��{�ŃA���S���Y���̍\�z��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������A�Ɠd�̔��X�����ȃG�l�������d�@���H�g���Ƌ������ �������ƕ������d�@���H�g���́A�Ɠd�̔��X�̔̔������X���ȂǂŏȃG�l�ɂ��ċq�ɏ�������u�ӂ����܃G�R���C�t�}�C�X�^�[���Ɓv���n�߂��B�ȃG�l���\�̍����Ɠd�̍w���𐄏�����Ȃǂ��āA�ƒ�̉������ʃK�X�r�o�팸��}��B ���Ɠ��g���́A�n�����g����̐��i�Ɋւ��鋦�������B���g���ɉ�������Ɠd�̔��X�̔̔����̂����A�������{���錤�C���C�����A���{�d�������Â���u�X�}�[�g���C�t�R���V�F���W�����x�v�ōŏ�ʂ́u�S�[���h�v�̎��i���擾�����̔������ӂ����܃G�R���C�t�}�C�X�^�[�Ƃ��ēo�^����B �}�C�X�^�[�́A�X����c�Ɛ�ŋq�ɑ��A�ȃG�l���\�̍����Ɠd�̍w���𐄏�������A�ƒ�łł���g�߂ȏȃG�l�̎��g�݂��Љ���肷��B �B�܂��A�������{���Ă��鉷�g����̎��g�݂����m���A���͂��Ăт�����B1�����݁A72�X�܁A88�l���o�^���Ă���B �o�T�u���{�H�ƐV���v |
|
|
| �����z�����d���W���[���̗iPID�j���ۂ��ȒP�E��R�X�g�ŗ}������V�Z�p ��w�́A�����V���R���n���z�d�r���W���[���̔��d�\�͂�Z���ɑ啝�ɗ����錻�ۂł���u�d���U�N�iPID�FPotential Induced Degradation�j�v���A�ȕցE��R�X�g�ŗ}��������@�������Ɣ��\�����B �ߔN�APID�̔������J�j�Y���Ƃ��āA�Z���\�ʂ̔��˖h�~���iARC�j�ɍ����d��������邱�Ƃ��ɑ傫���W���Ă���Ƌc�_����Ă���B�����ŁAARC�ɍ����d��������邱�Ƃ�h�����߂ɁA�t�̃K���X�ō쐻�����K���X�w������R�w�Ƃ��đ��z�d�r���W���[���ɑ}�����A����ɓd�E���W����������@�𒅑z�����B ��̓I�ɂ́A���z�d�r���W���[���̐��Y�H���ɂ�����EVA�ƃJ�o�[�K���X�̊ԂɃK���X�w��}������PID�}�����H��A�ݒu�ς݂̃��K�\�[���[���d�{�݂̃J�o�[�K���X�\�ʂɃK���X�w��h�z����PID�}����Ƃ��ē�������邱�Ƃ��z�肳���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���H�i���X�팸�@�āA�����֒��}�h�c�A����o�t�[�h�o���N�x���`���Â� �u�H�i���X�v�����炷���߂̊�{����荞�H�i���X�팸���i�@�Ă��A������Ő������錩�ʂ��ɂȂ����B �u�����^���v�Ƃ��Ď��g�ނ��ƂL���A����n�������́A���Ǝ҂̐Ӗ��m�ɂ���B���}�h�̋c���A�����A�O�@����Җ����ʈψ���ɗ^��}8�}��v�̈ψ�����ĂƂ��Ē�o������j�����߁A�������4�����ɂ���������B �u�t�[�h�o���N�v�����ւ̎x�����`���Â���B���{�͕K�v�Ȏ{����܂Ƃ߂���{���j���t�c���肵�A�s���{���E�s�����͐H�i���X�팸���i�v������B�����̗����ƊS��[�߂邽�߁A���N10�����u�H�i���X�팸���ԁv�Ƃ���B ���{�̐H�i���X�͔N�Ԗ�646���g���i2015�N�x�j�B1�l������̗ʂ�51�L���B2015�N�ɍ��A�ō̑����ꂽ�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�́A2030�N�܂łɐ��E�S�̂�1�l������̐H���p����������ƌf���Ă���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���u�r���V�X�e���ɂ�����T�C�o�[�E�t�B�W�J���E�Z�L�����e�B��K�C�h���C����1�Łi�āj�v �G���x�[�^�[��ȂǑ����̐���n�@���L����r������Ɋւ��āA�r���V�X�e���Ɋւ���T�C�o�[�Z�L�����e�B�̊m�ۂ�ړI�Ƃ����u��K�C�h���C����1�Łi�āj�v���Ƃ�܂Ƃ߁A�p�u���b�N�R�����g���J�n���܂����B �o�ώY�ƏȂł́A���N�䂪���̎Y�ƊE�����ʂ���T�C�o�[�Z�L�����e�B�̉ۑ��o���A�֘A����𐄐i���Ă������߂Ɂu�Y�ƃT�C�o�[�Z�L�����e�B������v���J�Â����B�܂��A��N2���ɂ́A�T�v���C�`�F�[���S�̂̃T�C�o�[�Z�L�����e�B�m�ۂ�ړI�Ƃ��āA�u�T�C�o�[�E�t�B�W�J���E�Z�L�����e�B��t���[�����[�N�v�̌������J�n�����B �r���T�u���[�L���O�O���[�v�́A�r���V�X�e���Ɋւ���T�C�o�[�Z�L�����e�B��ɂ��āA�c�_�������ʂ��u�r���V�X�e���ɂ�����T�C�o�[�E�t�B�W�J���E�Z�L�����e�B��K�C�h���C����1�Łi�āj�v�Ƃ��Ď��܂Ƃ߂��B �o�T�u�o�ώY�Əȁv |
|
|
| ���r�����|���{�A�i�h�r����o�Y�Ȃ�2020�N�x�߂� �o�ώY�ƏȂ�2020�N�x���߂ǂɁA�Ɩ��p�r�����|���{�b�g�̐��\����S���ȂǂɊւ�����{�H�ƋK�i�iJIS�j�����肷��B �r�����|�̐l��s�����[�������钆�A�������ɖ𗧂��{�b�g�̕��y�ɂȂ���B�V���ȋK�i�ŗv���������{�b�g���i�Ɂg���n�t���h��^���A���[�U�[�����i��I�肵�₷������B�Ɩ��p�r�����|���{�b�g�̋K�i�͊C�O�ł��܂����݂��Ȃ��ƌ����A�����͍��ەW���ւ̒�Ă�����ɓ����B �V�K�i�́A�I�t�B�X�r�����Ŏ����ړ����A�o����菜�����o�^���|���{�b�g���ΏہB���o�A�ړ��Ƃ������e�@�\�̔\�͕]���@��A���S��Ȃǂ��K�i�ɐ��荞�܂�錩���݂��B �A�}�m���͂��߂Ƃ������|���{�b�g���[�J�[�A�r���̊Ǘ���Ђ�J����ЂȂǂ��R���\�[�V�A���i�������Ƒ́j��g�݁AJIS���Ă��쐬����B�����A��ɖ�ԍ�ƂɂȂ邽�ߐ��Y���ƈ��S�������߂���ȂǁA���[�U�[���̗v�������͍����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2019/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���V���{�A������p�����Z���V���O�V�X�e�����J��������1/2 �̏ȗ͉� �����ʐM�ɂ��v���ō��X�ƕω������Ԃ̉��x�⎼�x�Ƃ������f�[�^�����A���^�C���ɉ������L�^�ł���B�ݔ��̏v�H�O������A���C�O��̌��z���ōs��������̌������ɖ𗧂Ă�B�]���̗L�������ɔ�ׂĐݒu��f�[�^���͎��ɂ������Ԃ������ɂȂ�Ƃ����B �f�W�^���Z���T�[�ƁA�����𐧌䂷��}�C�R������̉������v�����j�b�g�A�Q�[�g�E�F�C�A�A�v���ō\������B�v�����j�b�g�́����x�����x����_���Y�f�iCO2�j�Z�x���Ɠx�����V������Z�x�������l�|���Ɍv���ł���B �v���l�̓X�}�[�g�t�H���Ȃǂ̃��o�C���[���ŕ\���E�L�^�B�����ʐM�ɂ́A920MHz�т̓��菬�d�͖����������̗p�B�ő�50�J���ɐݒu�����v�����j�b�g�̌v���l���ŒZ1�b�Ԋu�Ŕc�����A����̃��o�C���[���Ńf�[�^���{���ł���B �o�T�u���ݍH�ƐV���v |
|
|
| ���_�C�L���A�^�Ẳ��O�ɗ���������͂��A���K�ȋ�Ԃ�n�����鉮�O�p�G�A�R����V���� �^�ẴJ�t�F�̃e���X�Ȃ������ԂȂǁA�������ۑ�ƂȂ鉮�O��Ԃ����K�ɂ��鉮�O�p�G�A�R���B �{���i�́A�^���[�`�̖{�̂̑��ʒ�������╗��O�㍶�E��4�����Ɍ����Ė�3m��܂œ͂��邱�ƂŁA���O�ɗ�������ԁi�N�[���X�|�b�g�j��n�����܂��B���͂̋C����艷�x��8���Ⴍ�A���������╗�����B��ʓI�ȃG�A�R���ɂ����鎺���@�Ǝ��O�@����̂ƂȂ����\���ɂȂ��Ă���A�����@�Ǝ��O�@���Ȃ���}�z�ǍH�����s�v�̂��߁A�ݒu���ȒP�ŁA�ꏊ���I�Ȃ��B�܂��A�^���[�`�̌`����̗p���A���O�̊J���I�ȕ��͋C�ƒ��a����B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| �����ŁA�����̑��z�����d�̗]��d�͂������C�̓������Ɋ��p�ł���V�^�G�R�L���[�g�AHEMS�����̓���Ƃɂ��ݒu�\ ���ŃL�����A�́A���R��}CO2�q�[�g�|���v�����@�̉ƒ�p�G�R�L���[�g�����������B�v���~�A��/�n�C�O���[�h/�X�^���_�[�g/�x�[�V�b�N/������p�^�C�v��5���f���v47�@���W�J����B���i��708,000�`1,075,000�~(�Ŕ�)�B �����̑��z�����d�̗]��d�͂������悭���������Ɋ��p�ł���A�u���̉^�]�\��v�@�\�𓋍ڂ������ЃG�R�L���[�g�̐V�V���[�Y�B�]���͎�ɗ����̈�����ԓd�͂𗘗p���Ă��������Ă������A�V�V���[�Y�ł͑��z�����d�̗]��d�͂���������Ɨ\�z����鎞�Ԃɍ��킹�āA�����グ�J�n�����Ɖ^�]���Ԃ�30�����݂Őݒ�\�B�܂������グ�^�]���Ԃ����R�ɐݒ�ł��邽�߁A���Ԃ͊O�o���Ă��ēd�C���g��Ȃ����[�U�[�ɂ��K���Ă���A���z�����d�̌����I�Ȏ��Ə���ɍv���ł���Ƃ��Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����d�C�A�Ɩ��@��̎��ւ��Ȃ��ŃX�}�[�g�Ɩ����ł���ǃX�C�b�`�uLink-S2�v �ƒ�p�ɂ��l���Z���T�[���������V��Ɩ����s�̂���Ă��邪�ALink-S2�́A�Ɩ��@��͂��̂܂܂ɃX�}�[�g�Ɩ��ɂł��鉮���p�ǃX�C�b�`�B �A�i���O�X�C�b�`�i2��H�j�ɉ����Đl���Z���T�[��Wi-Fi�@�\��������A�X�}�z��^�u���b�g���g���ăI���^�I�t�A�l�����m���Ă̎����_���Ȃǂ��\�B�܂��A�Ɩ��ȊO�i���C��Ȃǁj�ɂ����p�\�Ƃ��Ă���B ��p�A�v���͖����Ń_�E�����[�h�ł��A�O�o�悩��ł�����\�B�ڑ�����Ă���Ɩ��@��̃O���[�v����X�P�W���[�����w�肵�Ă̓_���E����������s�Ȃ���B�܂��A�l���Z���T�[�����p���ĊO�o��≓�u�n����Ƒ��̐����������T�[�r�X�i�L���I�v�V�����j���p�ӂ���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ����B�d�́A�ҏ���ELED���Ȃǂ̖@�l�����T�[�r�X���u�����h�� ��B�d�͂́A��d�O���[�v�̎戵�����i���A�����̂��Ƃ�ΏۂɁu�E�B�Y�L���[�v�Ƃ��Ĕ̔����J�n�����B 4�̃J�e�S���[�ɂ��Ċ֘A���i����葵�����B����ɂ�莩�R�ЊQ�̑������E���r����A�Z�p�v�V���̊��ω��ɂ��l�X�ȃ��X�N�ւ̑Ή����T�|�[�g����B �@�h�Б�F�d�C�A�g�C���E�A���H�A�A���ɔ�����F���z�����d�p�l���ƒ~�d�r�A���p�q�ɂ���̉������K���[�W��A��u�~�d�r�Ɠd�C�����ԁiEV�j�E�v���O�C���n�C�u���b�h�iPHV�j�p�}���[�d����Z�b�g�ɂ����V�X�e���Ȃǂ��Ă���B �A�ҏ���F�����̎ՔM�E�f�M���\�̌���F�����̎ՔM�E�f�M���\�̌��コ����邱�Ƃɂ��A�K�ȉ��x�Ǘ��Ƌɂ��G�l���M�[�̏���}�����ł���B �BLED���F�I�[�_�[���C�h�̏Ɩ��v �C���Z�L�����e�B�F�T�C�o�[�U���ւ̑�F���ނ�f�[�^�̕ۊǁA�@�������̔p�������Ȃǂ̃T�[�r�X�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăG�l�������֒~�d�r�^�o�Y�ȁA�����⏕ �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[���d�ݔ��ւ̒~�d�r�������x������B��N���������k�C���_�U�����n�k�ł́A���z���╗�͂̕ϓ��^�Đ��\�G�l�������I�ɉ�A�ꕔ�������Ē����͂�S���Η͔��d�������A����܂ŋ����͂Ƃ��Č����߂Ȃ������B �����������ۂ܂��A�~�d�r�̐������㉟���A�ЊQ���ɂ��������p���ł���Đ��\�G�l�̋����͂��A6��kW���x�m�ۂ���B����ɁA�����I�ɓd�͋������p���ł���u�n��}�C�N���O���b�h�v�̍\�z���x������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����E�ő�̒~�d�V�X�e���A1�N�Ԃ̉ғ���45���~�̐ߖ�A�ݒu��p��75���~ ���E�ő�̒~�d�r���Ǘ�����Aurecon���A���̃p�t�H�[�}���X�Ǝs��ւ̉e���Ȃǂ��L�������|�[�g�\���܂����B��N�Ԃ̉^�p�ɂ��A��4000���h���̐ߖ�ɂȂ������ق��A�d�̓C���t���̐M�����̌���ɂ���^�����Ƃ��Ă���B �ߔN�A�ăG�l�̕��y�ƋZ�p����ɔ����A�~�d�r���n�����艻�Ɋ��p����Ƃ������g�݂ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B���݁A���E�ő�Ƃ�����~�d�{�݂́A�Đ��\�G�l���M�[���Ǝ҂ł���Neoen�����L���ATesla������uHornsdale Power Reserve�iHPR�j�v�ł���B�o�͂�100MW�A�e�ʂ�129MWh���ւ�B�s�[�N�o�͂Ŕ�������ꍇ�A�o�b�e���[��3���˂ɑ�������d�͂������\���B 2017�N12�����{�i�ғ����J�n����HPR�́A�����������\�Ȓ~�d�V�X�e���ɂ��A���i�ʂ̃����b�g�����ł͂Ȃ��A�d�̓C���t���V�X�e���̐M�����̌���ɂ���^���邱�Ƃ𖾂炩�ɂȂ����B �o�T�u�G�l���M�[���Z���^�[�v |
|
|
| �������s�A�L���b�v���g���[�h���x�A��Y�f�d�́��M�������Ǝ҂�2019�N�x�F�� 2019�N�x�̒�Y�f�d�͔F�苟�����Ǝ҂�17���Ǝ҂ŁA��N�x�ɔ��2���Ǝґ��ƂȂ����B�܂��A��Y�f�M�F�苟������37���ŁA��N�x�ɔ��4��摝�B �s�͂��̐��x�ŁA2015�N�x����A�s���F�肷��CO2�r�o�W���̏������������Ǝ҂���Ώێ��Ə����d�C�܂��͔M�B�����ꍇ�ɁACO2�팸�����Ƃ��ĔF�߂�u��Y�f�d�́E�M�̑I���̎d�g�݁v�����Ă���B ���̎d�g�݂́A���Ə��́u��Y�f�d�́v�E�u��Y�f�M�v���������鎖�Ǝ҂�I������s���𑣂����߁A���Ə����I�������d�C���ƎҁE�M�������Ǝ҂̔r�o�W���̈Ⴂ���A���͈̔͂Ŏ��Ə��̔r�o�ʎZ��ɔ��f�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������̂��B �F��ΏۂƂȂ鋟�����Ǝ҂̗v���́A�u��Y�f�d�́v�́ACO2�r�o�W����0.4t�|CO2�^��kWh�ȉ��A�u��Y�f�M�v�́ACO2�r�o�W����0.058t�|CO2�^GJ�ȉ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEDO�Ɗ�A�n���M���p�V�X�e���̒�R�X�g���Z�p���Љ� �u�n���M�v�͗L�]�ȍĐ��\�G�l���M�[�����ƌ����Ă��邪�A�V�X�e���̌�����R�X�g�����p���i�̖W���ƂȂ��Ă���B ����A���҂́A �@1)�n���M���p�V�X�e�������̓K�n�I��Z�p�̐��x�����}�� �@2)�ݒu�R�X�g�������A�n�����̔M�ڗ��p����V�X�e���i�I�[�v�����[�v�^�j�̎��؉^�]���s�����B �]�������n�����x�̊ϑ��ӏ��𑝂₵�A�n�����̗���𐳊m�ɔc�����邱�ƂŁA�����L���n��i�n�������x���ċG�ɒቺ���A�~�G�ɏ㏸������������n��j�̐��x�ǂ����o���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���M�n���i���j�ق�2�ЂƋ��ɉғ��f�[�^�̃��j�^�����O��V�X�e�������Ȃǂ��������Ƃ���A�q�[�g�|���v�ɂ�鍂�������i31���j�A�n�����M�������j�b�g�ɂ��|���v���͍팸���ʁi42���j�ɂ�荇�v73���̉^�p�R�X�g�팸���B���ł����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����ԑ�^���A���Ăő��X�^�m������P���L�����b�g���J�� ���Ă̕��͔��d�@���[�J�[��肪��������1��1��kW���̒������m�㕗�Ԃ��J�����Ă���B�X�y�C���̃V�[�����X�E�K���T�́A�o��1��kW�̕��Ԃ�2019�N�Ɏ��삵�A2022�N�ɂ��s�������\��B�ă[�l�����E�G���N�g���b�N�iGE�j���q��Ђ�GE���j���[�A�u���G�i�W�[��1��2��kW�̗m�㕗�Ԃ̎���@���I�����_�Ɍ��݂���B���{�ł�1��kW���̑�^���Ԃ̓�����͂Ȃ����̂́A�m�㕗�͌v��͎����玖�Ɖ��̒i�K�Ɉڂ��Ă���B ���݁A���p������Ă���m�㕗�Ԃ̏o�͂́A�O�H�d�H�Ƃƃx�X�^�X���ܔ��o������MHI�x�X�^�X�E�I�t�V���A�E�E�C���h��9500kW���ő勉�B���̕��Ԃ͉��B�k���̖k�C�Ői�߂��鍇�v�o��100��kW��̑�^�E�C���h�t�@�[���ō̗p����錩�ʂ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���d�C�A�K�X�A�������������j�B�r�b�O�f�[�^�̊��p�����҂����k���d�͂̎��� �k���d�͂́A�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j�p�ʐM�V�X�e����p�����d�C�A�K�X�A�����̋������j�Ɍ����A2018�N12������ڋq��ł̎����J�n�����B ���ɐ������[�^�[�́A�d�q���A�@�B���̑��l�Ȑ��i�Őڑ����������{�B����A�ϐ�␅�v�Ƃ������ߍ��ȏ��ł̒ʐM���m�F���Ă����B �܂��A�t�����l�T�[�r�X�Ƃ��Ďg�p�ʂ́u�����鉻�v�����B�����Ŏ���i�߂�NTT�e���R���̊����T�[�r�X�𗘗p���A�d�C�A�K�X�A�������Ƃ̎g�p�ʂ̃O���t���E�F�u��ɕ\���ł���悤�ɂ����B�����T�[�r�X�����p���邱�ƂŃV�X�e���J�����啝�ɒጸ�ł���̂��������B �X�}�[�g���[�^�[�ʐM�ł́A���u�Ď��E����̓���m�F���i�߂Ă���B���Ǝґ��Ōڋq���Ƃ̎g�p�ʂ�c���ł��邽�߁A�ُ�Ȏg�p�ʂ����m�����ۂ́u�K�X�E�����R��v�Ɣ��f���A���u�ŕ��ł���B�d�C�͉��u�ł̃u���[�J�[�J���\���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ����t��w���@��t��w���\�[���[�V�F�A�����O�̌����앨�I��ɉۑ�A�_�ƈψ���͋ꗶ �������ɂ��A�\�[���[�V�F�A�����O�ł́A���������ȂǎՌ���100���Ő��炷��i��̍�t����A�Ռ����������Ă����炷�����̍앨���I���X��������Ƃ����B���̌��ʁA�c�_�ɂȂ���Ȃ��Č�������ƌ��_�Â����B �\�[���[�V�F�A�����O�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��K���ǂ����^�₪�����Ƃ��āA�G����̂��ߎłɂ����O�����h�J�o�[�Ƃ��Ĉ琬�����i��̃_�C�J���h����b�h�N���[�o�[�̍�t���A�����������p�j���W���ȂǎՌ���100���̕i��̍�t����������B���̂悤�ɏ]���̍�t���i��Ƃ͂܂������قȂ�i�킪�I��邱�Ƃ���肾�Ƃ����B ����\�[���[�V�F�A�����O�ɂ��āA�����c�_�ɂȂ���Ȃ��Č���}��������g�݂�i�߂�ƂƂ��ɁA���⌧����������i��ƓK���ȎՌ��������Ȃǂ�n�悲�ƂɎ����A���S�Ɉ琬������g�݂��K�v���ƒ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��Apple�A�S���E�Ŏ��R�G�l���M�[100���B���A20�В��̃T�v���C���[��Apple�����ɑΉ� Apple��2018�N�ɁA�S���E�̎��Ɗ����Ŏg�p����d�͂����R�G�l���M�[100���ɐ�ւ��邱�Ƃ��ł����B���E43�J���ɓW�J����I�t�B�X�A�X�܁A�f�[�^�Z���^�[�̓d�͎g�p�ʂ����v�����18��kWh���Ă���B �J���t�H���j�A�B�ɂ���{�Ѓr���̃r���̉���ɂ́A17MW���z���p�l����S�ʂɐݒu�B����Ƀo�C�I�K�X���p�̏o��4MW�̔R���d�r�V�X�e���������B��^�̒~�d�r���ݒu���āA�r�����ŏ����d�͂����R�G�l���M�[100���ŋ����ł���̐��ɂȂ��Ă���B �č��ȊO�̒n��ł��A�V���K�|�[���ł�800�ȏ�̃r���̉���ɑ��z�����d�ݔ���W�J���Ă���B���{�ł����d�͂ƒ�g���đ�s�s���ɂ����300�J���̃r���̉���ɑ��z�����d�ݔ�������Ȃǐ��E�e���Ŏ��g��ł���B �o�T�u���R�G�l���M�[���c�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���l�ԂŔ����̎���֓d�͑�肪��ՂÂ��� �d�͑��e�Ђ��A�l���Ƃɂ��d�͂̒��ڎ��������������ՂÂ���ɏ��o���Ă���B�ƒ�p���z�����d�ŗ]�����d�͂Ȃǂ����R�ɔ��蔃���ł���悤�ɂȂ�A�����̓d�̓V�X�e����傫���ς���\�����߂Ă��邽�߂��B �J�M�ƂȂ�̂��u�u���b�N�`�F�[���v�Z�p�ŁA�e�Ђ͊֘A��Ƃւ̏o������؎����Ȃǂ��������Ă���B �����d�̓z�[���f�B���O�X�́A�Ɠd�͑��C�m�W�[�̎q��Ђ�300�����[���i��3.6���~�j���o�����A�h�C�c�Ńu���b�N�`�F�[���ɂ��d�͒��ڎ���̊�Ղ���鎖�Ƃ��J�n�B���d�͂�����ƂƋ����ŁA�u���b�N�`�F�[�������p�����d�͒��ڎ���̎��،������n�߂��ق��A��B�d�͂��A���ڎ���ȂǐV���Ȏ��Ƒn�o�Ɍ����āA������w���̃x���`���[��ƁA�f�W�^���O���b�h�ɏo�������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���a�m����AOKI�ȂǁA�t���L�V�u�����z�d�r�������u���d�X�[�c�v������ �����w�������́AAOKI�ȂǂƋ����ŁA�t���L�V�u���L�@���z�d�r��a�m���̏㒅�ɑ������A���d����a�m���u���d�X�[�c�v�̎���ɐ��������Ɣ��\�����B ���d�X�[�c�ł́A���E��5���i���v10�j�̑��z�d�r���W���[�����a�m���̏㒅�̔w�ʂɑ�������Ă���B1�̃��W���[���ɂ��āA�^�����z�����ōő�28mW�̔��d�ʂ�B�������B���d�X�[�c�Ƃ��Ă̔��d�ʂ�280mW�ɑ�������B�܂��A���W���[���̌��݂���15��m�����Ȃ� ���߁A�Ȃ��邱�Ƃ��ł���B���̗L�@���z�d�r��a�m���㒅�ɓ\����A�a�m���̐����H���ʼn��ɐ��n�Ɏ������邱�Ƃɂ���āA�z�n�̕������Ȃ�Ȃ��f�U�C�����Ƌ@�\���̗������\�ƂȂ����B �J�����ꂽ�Z�p�́A���낢��Ȕ��d����A�p�����ݏo�����Ƃ����҂����B�܂��A�A�p����������āA���d����J�[�e���A�e���g�A���C�~�Ȃǂւ̉��p�������܂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������p�̓[���A���ƎҌ����̑��z�����d�����ݒu�T�[�r�X�����d�͂Ȃǒ� �����d�͂́A�ڋq�̂��܂��܂ȃj�[�Y�ɉ����邽�߁A�V���ɍĐ��\�G�l���M�[�����p�����T�[�r�X�J�n����Ɣ��\�����B ���z�����d���ݒu�����Ə���ł���T�[�r�X�ł́A�X�܂�H��Ȃǂ̉�������āA�����d�͂̕��S�ɂ��A���ЂƓ��Ђ̒�g��Ƃ��A���z�����d�ݔ���ݒu�E�^�c������́B�ڋq�͏�����p�[���œd�C�����Ə���ł���B�]��d�͂��������ꍇ�́A�����d�͂��d�͋������Ɋ��p����B�Ȃ��A�ڋq�́A�����T�[�r�X�������x�����B �����b�g���o�₷���̂́A�x�O�̃X�[�p�[����H�X�A�H��Ȃǂ������Ă���B�ݒu�ڈ��́A�ݔ��e��100kW�ȏ�A�����ʐ�700m2�B CO2�t���[�d�C�������j���[�́A�����d�͂��ۗL����Đ��\�G�l���M�[�d���i���͔��d�Ȃǁj��A���������Ԃ��������}����Đ��\�G�l���M�[�d���̊��p�ɂ��A��Ƃ�ƒ��CO2�t���[���l�t���̓d�C��͂��闿�����j���[���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���_�C�_���A�C�X���I�J�����ƊJ�� �]���A���ʂ��s�\���ȏꍇ�ɂ́A�Ⴆ�Η�[���Ȃ���t�@���A�g�[���Ȃ�Ђ������̎g�p�ȂǁA�l�ŗ�[�E�g�[��⏕�����i���g���Ă��邱�Ƃ������B �I�t�B�X�Ŏ����҂̋ւ̉��K�������ړI�Ƃ����C�X�́A�֎q���ʂ̍��E�����ɐ݂������o����著�����邱�Ƃŗ�[���ʂ�₢�A�܂����ʂ̓����q�[�^�[�ɂ��g�[���ʂ�₤�B�d���̓��`�E���C�I���o�b�e���[�B �N�[���r�Y��̂��߁A��[�ݒ艷�x����⍂�߂ɐݒ肳�ꂽ�I�t�B�X���ł��A�̊����x����������ʂ�A�~�G�ɂ͒g�[��⏕������ʂ�������B�I�t�B�X�œ������̉��K���Ȃ����ƂȂ��A�I�t�B�X�̏ȃG�l���M�[�����i�Ɋ�^����B ���N�x���̈�ʔ̔���ڎw���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���_�C�L����2020�N�x�߂ǂɊ��C�ł���ƒ�p�G�A�R����A�W���͂��ێ��ɖ𗧂� �_�C�L���H�Ƃ͉ƒ�p�G�A�R���̍����@��ɁA��������K�v���Ȃ������@�\���̗p���Ă���B ���̋Z�p�����C�̋@�\�ɉ��p����B�E�C���X��z�R�����������A�����Ɏ��x�̍�����C�𑗂�z�ǂ����C�p�Ɏg���B���C��قǂ̔\�͂͂Ȃ����̂́A�q�ǂ��������܂ތ���Q���ȂǁA����������CO2�Z�x�̗}���ɖ𗧂B �����x��������q���iPM2�E5�j�ɉ����ACO2�Z�x�����K���Ɋւ��v���Ƃ��Ē��ڂ��Ă���B���Ɏd��������A�N������CO2�Z�x���Ⴂ�����]�܂����Ƃ����B���̂ق��A2020�N�x��CO2�Z�x���v���ł��鉷���x�Z���T�[��f�U�C�����̍������C�����������v��B �ȃG�l���M�[���\�̍����Z��͋@�����������A�M���O�ɓ����ɂ����B���̂��ߊ��C���Ȃ���CO2�Z�x�����܂�₷���ۑ�������Ă���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���H��̐��Y������ƁA�`�h�Ō������^�O�H�d�@�ȂǁA�n����Ǝ҂��� �O�H�d�@�ƎY�����́A�n����Ǝ҂��S���H��̐��Y������Ƃ��`�h�Ō���������Z�p���J�������Ɣ��\�����B �H�샍�{�b�g�Ȃǂ��Ɉʒu���߂���u�T�[�{�V�X�e���v��������A���������[�U�[�ō��i���ɉ��H���邽�߂̏�����Z���ԂŌ����o�����肷��B�Y�Ɨp���{�b�g�ُ̈퓮�����������v���O�������Z���Ԃō쐬�ł���Ƃ����B�V�Z�p��p����Ό���̕��S���y���ł��A�n����Ǝ҂����葱����Ƃ������ۑ�̉����ɂ��Ȃ��肻�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ϐ��n�E�X�A�Z��I�[�i�[���瑲FIT�d�͔���莩�Ђ�RE100�B���̂��� �����T�[�r�X�̎��O�\���ݎ�t��3��1������n�߁A11����莖�Ƃ��J�n����B�J�n�����̓d�͔���P����11�~�^kWh�B ���Ђ́A2017�N10���ɁA���Ɗ����ɂ����Ďg�p����d�͂�100���ăG�l�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���C�j�V�A�`�u�uRE100�v�ɉ��������B���̖ڕW�Ƃ��āA���Ɗ����ŏ����d�͂ɂ��āA2030�N�܂ł�50�����A2040�N�܂ł�100�����ăG�l�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���Ă���B ����A���Ђł͂���܂łɌˌ��Z�����ݏZ��Ȃǂɗv��700MW�ȏ�̑��z�����d�V�X�e����ݒu���Ă���A���̔N�Ԕ��d�ʂ͖�700GWh�ɒB����B�����̖�2�`3���̑�FIT�d�͂�邱�ƂŔN�Ԗ�120GWh�ЃO���[�v�̎��Ɨp�d�͂Ƃ��Ęd�����Ƃ��ł��A�uRE100�v�̒B�����\�Ǝ��Z���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�@�x���`�}�[�N���x�V�Ώۂ̑�w�E�p�`���R�E�������{�݂̊�Ă܂Ƃ� �o�ώY�ƏȂ́A2018�N�x�́A��w�A�p�`���R�z�[���ƁA���ƌ����ɂ��āA�x���`�}�[�N���x�����ɂ������R�c���s�����B �E��w�ɂ�����x���`�}�[�N���x �@�u�w���E��w�@�̎{�y�ѐݔ��v�Ɍ���B �@���n�w���A���n�w���A��n�w���A���̑��w���ɑ�����{�݂̃G�l���M�[�g�p�ʂ̍��v��1500kl�ȏ�̎��Ƃ�ΏۂƂ���B �@�G�l���M�[�g�p�p�̗\���l���i���n�{���̑��w���ʐρi m2�j�j�~0.022�{�i���n�{��n�ʐρim2�j�j�~0.047 �E�p�`���R�z�[���Ƃɂ�����x���`�}�[�N���x �@�p�`���R�X�ƃp�`�X���X�̃G�l���M�[�g�p�ʂ̍��v��1500kl�ȏ�̎��Ƃ�ΏۂƂ���B �@�G�l���M�[�g�p�ʂ̗\���l�������ʐρ~0.061�{�䐔���N�ԉc�Ǝ���/103�~0.061�{���䐔���N�ԉc�Ǝ���/103�~0.0763�~0.061 �E���ƌ����ɂ�����x���`�}�[�N���x �@���ɂ̂����A�����A�����A�������W�E�ۊǁE�W�����̕����������B �@�G�l���M�[�g�p�ʂ̗\���������ʐρ~0.023�{�E�����~0.191 |
|
|
| ���d�͎g�p�f�[�^�J�����{�������������V�r�W�l�X�Ɋ��p ���{�́A���d�͉�Ђ����ƒ���ƂȂǑ��z�d��̓d�͎g�p�f�[�^����ʊJ�����錟���ɓ������B �ڋq�f�[�^�����ł��Ȃ��悤�����������߂���ő�O�ҋ@�ւɏW��A�g�p�����Η��p�ł���悤�ɂ���l�����B ���ʂ��c��Ȃ��߁u���̏���l�H�m�\�iAI�j�Z�p�ȂǂƑg�ݍ��킹�邱�ƂŐV�r�W�l�X���a������v�Ƃ̊��҂�����B �f�[�^���p�ɂ��A�܂��͓d�͏�����e�Ђ��ׂ₩�ȗ����v�����Ȃǂ�����ق��A�l�����Ԃ������邽�߈��H�X�⏬���Ǝ҂������I�ȏo�X�v��𗧂Ă��A������J�[�V�F�A�ȂǃV�F�A�r�W�l�X�ɂ����p�ł���B�ڋq���玩��̏�p�ɂ��ċ���d�g�݂��ł���A����҂̌�������ۊm�F�Ȃǂ̃T�[�r�X���\�ɂȂ�B ����A���d�͂��f�[�^�œ������v���A���������̒l���������ɏ[�Ă�ĂȂǂ��ۑ�ƂȂ肻�����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����쌧�A�u�ȃG�l���C�T�|�[�g���Ǝҁv��W�����̃G�l���M�[���\���ȈՐf�f ���쌧�́A���z���̏ȃG�l���C�𑣐i���邽�߁A�����������p�c�[����p���ďZ��̃G�l���M�[���\���ŊȈՓI�ɐf�f����u�ȃG�l���C�T�|�[�g���Ǝҁv�̔F���]���Ǝ҂̕�W���J�n�����B �����x�ɂ����Č��ɓo�^���ꂽ�u�ȃG�l���C�A�h�o�C�U�[�v�́A�u�ȃG�l���C�T�|�[�g���Ǝҁv�ɏ������A�ʏ�Ɩ��̒��Ō����Ɛڂ���@���f�f�̊�]���������ۂɁA��p�̊ȈՐf�f�c�[����p���Č����̃G�l���M�[���\�̊ȈՐf�f���s���A�����Z��̏��L�ғ��ɏȃG�l���C�̌����ɕK�v�ȏ������B �ȃG�l���C�T�|�[�g���Ǝ҂̎�Ȗ����͈ȉ��̒ʂ�B �E�����o�^����ȃG�l���C�A�h�o�C�U�[�̊m�ہA�h�� �E�ȈՐf�f�̎�f��]�҂̕�W�A��t �E���z���̃G�l���M�[���\�̌���Ɍ������A�h�o�C�X�A���y�[�� �E����������ȈՐf�f�c�[���̊Ǘ��A���ւ̊������ѕ� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăG�l�������֒~�d�r�^�o�Y�ȁA�����⏕�łR������J�n �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[���d�ݔ��ւ̒~�d�r�������x������B ��N���������k�C���_�U�����n�k�ł́A���z���╗�͂̕ϓ��^�Đ��\�G�l�������I�ɉ�A�ꕔ�������Ē����͂�S���Η͔��d�������A����܂ŋ����͂Ƃ��Č����߂Ȃ������B �����������ۂ܂��A�~�d�r�̐������㉟���A�ЊQ���ɂ��������p���ł���Đ��\�G�l�̋����͂��A6��kW���x�m�ۂ���B����ɁA�����I�ɓd�͋������p���ł���u�n��}�C�N���O���b�h�v�̍\�z���x������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցA�S���̓G�l���M�[�Ɗ��̉ۑ�����ɍv���ƕ� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A���ꂩ��̎���ɂ͓S�����G�l���M�[����Ɗ��̑o���ɖ𗧂Ƃ���������\�����B �S���͐��E�̗��q�A����8%�A�ݕ��A����7%���߂Ă��邪�A�G�l���M�[���v�͗A������S�̂�2%�ɉ߂����A�G�l���M�[�����������B���ł́A2050�N�܂ł̓S������̎p���A�����̐���Ɋ�Â���{�V�i���I�ƁA�S���ւ̓�����60%���₷�S���d�_���V�i���I�ƂŔ�r���Ă���B �S���d�_���V�i���I�̏ꍇ�A���E�̗A�������CO2�r�o��2030�N��㔼�Ƀs�[�N�A�E�g���A��C�����̊ɘa�ƐΖ����v�}���ɂȂ���Ƃ����B���ɓr�㍑�ł͐l���⏊���̑����ƂƂ��ɓs�s�����}���ɐi��ł���A�����I�Ŋ��ɗD������ʎ�i�����߂��Ă���B���x�Ə_������߂����҂͎Ԃ̏��L��q��@�̗��p�ɖڂ������₷�����A����҂͓S���������炷�։v�ɉ��߂Ē��ڂ���K�v������Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��������Z��|�C���g���x�ɂ��� ������Z��|�C���g���x�́A2019�N10���̏���ŗ����グ�ɔ����A�ǎ��ȏZ��X�g�b�N�̌`���Ɏ�����Z����̊��N��ʂ��āA����҂̎��v�����N���A����ŗ����グ�O��̎��v�ϓ��̕�������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�ŗ�10%�ň��̐��\��L����Z��̐V�z��t�H�[���ɑ��āA�l�X�ȏ��i���ƌ����ł���|�C���g�s���鐧�x�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���Z�F�����A�t�����X�̗m�㕗�͔��d�t�@�[���ɏo���Q�捇�v992MW �Z�F�����́A�p���C���m�㉫����15km�̃��E�g���|�[���m�㕗�͔��d���ƂƁA�t�����X�E�r�X�P�[�p������12km�̃m���[�����[�e�B�G�m�㕗�͔��d���Ƃ�2�Č��ɂ��āA���ꂼ��̊�����29.5�����擾���A���ƎQ�悵���B �����̗m�㕗�͔��d���Ƃ́A�t�����X�̑��d�C�E�K�X���Ǝ҂ł���Engie�ЂƁA�X�y�C���̍Đ��\�G�l���M�[���ƊJ���^�c�҂ł���EDPRenewable�Ђ��J���������߂Ă�����́B2�Č��̑����d�e�ʂ͍��v992MW�i496MW�~2�Č��j�B���Ɗ��Ԃ�25�N�ԂŁA�����Ԃ̔��d�_��Ɋ�Â��A��164���l���ɑ�������d�C����������B �����Ɣ�͍��v��5000���~�������ށB�J���̏����X�e�[�W����Q��A�m�E�n�E�z�����߂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�A�R���ȃG�l���u�J���A���ʏ��Ɨ�����w20���d�͍팸 �ȃG�l���i�̔̔���{�H����|���鉫�ʏ����A�G�A�R���̎��O�@�Ɏ��t���Č������グ�A����d�͂��팸����u�����G�R�V�X�e���iRES�j�v�𗮋���Ƌ����ŊJ�������B �����ɂ��ő��28���A���ϖ�20���̓d�͂��팸�ł����Ƃ����B2019�N2�����猧���Ŕ̔�����B RES�́A�����̃G�A�R�����O�@�ɊO�t�����A��}�̉t�̃K�X���ɔ�������C�A��}������B�C�A�������Ȃ����Ƃɂ��A�K�X�����k����R���v���b�T�[�̌��������コ���A�g�p�d�͗ʂ̍팸�⎺�O�@�̒����������\�ɂȂ�Ƃ����B�Ɩ��p��3�`10�n�͂̃G�A�R����ΏۂƂ��Ă���B ���i�͍H�����25���`30���~�B��ɋ��ғ������Ă���H���X�܂ȂǂŌ��ʓI���B �o�T�u�����V��v |
|
|
| ������M�A�U���ȂǗl�X�Ȋ����d�̓d�͂����܂����p�A�V�����̓d�q��� ���l�T�X�G���N�g���j�N�X�́AIoT�@��̓d�r�����S�ɕs�v�ƂȂ�G�i�W�[�n�[�x�X�g��p�̑g�ݍ��݃R���g���[�����J�������Ɣ��\�����B ���̃R���g���[���ɂ́A���Ђ��Ǝ��ɊJ����i�߂Ă���SOTB�iSilicon On Thin Buried Oxide�j�v���Z�X�Z�p���̗p�����B����ɂ������̃}�C�R�����p�̃R���g���[���ł͕s�\��������A�N�e�B�u�d���ƒ�X�^���o�C�d���̗��������������B �Ȃ��ASOTB�v���Z�X�Ƃ́A�]���g���[�h�I�t�̊W�ɂ������A�N�e�B�u���̏���d�͂ƃX���[�v���̏���d�͂��A�ǂ�������炷���Ƃ��ł��铯�ГƎ��̃v���Z�X�Z�p�B ���̋Z�p�̗��p�ɂ��A���E�M�E�U���E�d�g�E���E���d�P�[�u���̓d���g�Ȃǂ̃G�l���M�[��d�͂ɕϊ�����B���̃R���g���[���̃A�N�e�B�u�ƃX�^���o�C�d���́A��ʓI�Ȋ����d�R���g���[���ɔ��1�^10�ƂȂ薳�d�r�������������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���p�C�I�j�A���H�ƒ����A���O�@�ɕ��͔��d���u�J�� ���Ђ͒����w�Ƌ����ŁA�Ɩ��p�ݔ��̎��O�@�ɐݒu�\�ȕ��͔��d���u�����삵���B���u�̉H���`����H�v���A���O�@�̔r�C�������p���Ĕ��d�ł���B���ݎ��؎������ŁA�������2019�N12���ɕ���7m��20W���d�ł��鑕�u�Ƃ��Ĕ�������v�悾�B ���͔��d���u�͎��O�@���͂ގx���̏㕔�Ɏ��t����B3���̉H���̕��T�C�Y�͂قړ����ŁA�t���������[�Ɍ����L����`��B���O�@�̔r�C���Ǝ��R���̂�������H�������A���d����B����Ŕ����̉��i�͑��u�{�̂ƃR���g���[���[�̃Z�b�g��20���~���x�B�x���͐ݒu�����ɉ����Čʌ��ς��肷��B �����u�Ŕ��d�����d�C�́A�r���̏Ɩ���Ƃ������⏕�d���̗p�r�������ށB�@�탁�[�J�[��[�l�R�����[�J�[�ɒ�Ă��A���N�x5000�Z�b�g�̔̔���ڎw���B �o�T�u�����H�Ɓv |
|
|
| �����s��w�ȂǂƐV�d�̓R���T����Ƃ��A�g�A�d�̓r�b�N�f�[�^��͂Ńi�b�W���p ���{�V�d�͑����������́A���s��w�A�V�J�S��w�A�����h����w�ȂǂƘA�g���A�G�l���M�[��w���X�P�A���쓙�ł̎Љ�ۑ�̉�����r�W�l�X�̑n�o�Ɍ����A�d�͗��p�ɂ�����r�b�N�f�[�^����͂��錤�����u�X�}�[�g���C�t���{�v��{�i�n������Ɣ��\�����B ��̓f�[�^�����p���A�s���Ȋw���̗��_�Ɋ�Â���M�i�i�b�W�j���ɂ��A�v���[�`�ň�l�ЂƂ�ɋC�Â���^���A�l�X�����������ɂƂ��Ă��ǂ��I�����ł���悤�ȍs���ϗe�𑣂��B ���Ƃ��A�e�����d�C���Ǝ҂̓X�}�[�g���C�t���{�ƘA�g���邱�ƂŁA�d�͗��p����ڋq�̃��C�t�X�^�C���ɉ������œK�ȓd�̓v�������Ăł���悤�ɂȂ�B���̂ق��A�d�̓f�[�^���p�C���[�W��Ƃ��āA�d�͗��p�f�[�^�ɂ��ݑ��c�����A�Ĕz�B�̃��X�N��ጸ���邱�Ƃ�A�N���E�A�Q���Ԃ̔c���ɂ��V���ȃw���X�P�A���i�̑n�o�������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������̋Z�p�����������_�C�L���A����ƘA�g���� �_�C�L���H�Ƃ́A������w�ƕ�I�ȎY�w�A�g��������Ɣ��\�����B�o���̌����҂̌𗬂�[�߁A����̎�����Z�p�ȂǂɊւ��鋤���������n�߂�B�_�C�L���͍���10�N�Ŗ�100���~�̎��������o����B ����̌����w�̐��m�������A�G�A�R���̉^�]���������コ����Z�p��A�l�H�m�\�iAI�j��p�����@��̌̏�\�m�Z�p�Ȃǂ���������B �_�C�L���̈���́u���O��`����̒E�p��ʂ��āA�f�W�^���v���ɑΉ����Ă��������v�Ƙb�����B�����҂Ɋ�Ƃł̌�����F�߂�u�N���X�A�|�C���g�����g���x�v�����p���āA�l�ތ𗬂����i�B����̋����⌤���҂��_�C�L���Г��ɐϋɓI�ɏ��������B�_�C�L���̎��Z�p�҂𓌑�̌������ɔh�������������B����̌����҂�w���炪�ݗ������x���`���[��ƂƂ̋��Ƃɂ��͂�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������x���ω�����IoT�����K���X�A���ɍ��킹�Ď����������\�� AGC�ƃL�l�X�g�����E�e�N�m���W�[�Y�Ђ̍��ٔ̔���Ђ������@�\��L���铧���K���X�����B �ʏ�̃K���X���l�ɃN���A����A���������ő�99.9���Ւf����_�[�N�܂ŁA�����Ȃ��ψ�ɕς��̂ŁA�K���X�̐F���D�݂̒������x���ɕς��邱�Ƃ��ł���B�N���A�X�e�[�W�͈�ʓI��Low-E�K���X�Ɠ��������x�ŁA�_�[�N�̓j���[�g�����O���[�̋�ԃf�U�C���Ȃ�Ȃ��F���ƂȂ��Ă���B �K���X�́A�X�}�[�g�����f�o�C�X��4mm�̍����ߔM�����K���X�ŋ����w�K���X�B�܂Ԃ������˓������V���b�g�A�E�g���A�����ɓ��荞�ޓ������̔M��啝�ɒጸ�B�����̏ȃG�l���ʂ����߁A�R�X�g�̍팸�������߂�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������̎ՔM�t�B�����A���\�����E�ō������Ɂ^���������m�� ������15���A���E�ō����x���̎ՔM�������ՔM�t�B�������J�������Ɣ��\�����B�K���X���݂̓��������m�ۂ��A���S����w�̌��݂�1�w���Ƃ�1�i�m���[�g���i10������1���[�g���j�P�ʂŐ��䂷��V���ȑw�z��f�U�C�����B �K�ȃt�B�����\�����������A���z���̐ԊO���˂��鐫�\�����߂��B�������s�����Ƃ���A�ʏ�̃K���X�Ɣ�ׂČ����̗�[���ׂ�39���팸�ł�����ʂ��m�F�B2022�N���̎��p����ڎw���č���������\���̌�����i�߂�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�C�I�}�X���d�̔䗦�ύX�A2019�N4�����琧�� �����G�l���́AFIT�ɂ����āA�o�C�I�}�X���d���F����擾��ɁA�o�C�I�}�X�䗦�������グ��ꍇ�́A�o�C�I�}�X�S�̂ɂ��čŐV�̒��B���i�ɕύX����ȂǁA�o�C�I�}�X�䗦�̕ύX�i�����j�Ɉ��̐����݂���Ɣ��\�����B ���̑[�u�ɂ������ȗ߁E����������2019�N4��1������{�s����B���������āA2019�N4��1�����_�̔F��ɂ������o�C�I�}�X�䗦����Ƃ��āA����̑[�u��K�p����B FIT�F������o�C�I�}�X���d�ݔ��ɂ��ẮA�����̑����d�ʂ̂����A�o�C�I�}�X�R���̓����䗦���悶�������A���d�ʂƂȂ�B����AFIT�F��擾��̕ύX�i�����j�ɐ��x��̐���݂͐����Ă��炸�A�͏o�ɂ���ĕύX���ł��A�������S������I�ɐ����邱�ƂƂȂ�B�܂��A�o�C�I�}�X�Ɋ֘A����Y�ƑS�̂̈��萫�����߂鐧�x�̎�|�ɔ�����B�����������Ƃ���A�V���ȑ[�u���u���邱�ƂƂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ꌧ��Îs�A�K�X�E�d�͏������Ƃc���A���K�X�Ȃǂ֊������n ���ꌧ��Îs�́A���K�X�AJFE�G���W�j�A�����O�A�����@�H��3�Ђ��\������R���\�[�V�A���ɁA��Îs��100���o������V��ЂƂ��Đݗ������т�u���[�G�i�W�[�̊������n���s�����B ����ɔ����A���s�͂т�u���[�G�i�W�[�Ƒ�Îs�K�X����^�c���Ɠ������{�ݓ��^�c�����{�_�̒������s�����B ���㓯�Ђ́A���s����K�X�������Ƃ������p���A���Ƃ����{����B��̓I�ɂ́A�d�C�E�K�X�@��Ȃǂ̔̔�����I�ȃT�[�r�X�̒̑��A�K�X���ǁELP�K�X�E�����ɂ��Ă̕ۈ��Ɩ����s���Ă����B���ۂ̉^�c�ɍۂ��ẮA���Ԋ�Ƃ̃m�E�n�E�����p���A���s�̌ڋq�ɑ��đ��l�ȃT�[�r�X��W�J���Ă����\�����B �܂��A�d�C�����ɂ��ẮA2019�N1�����A��Îs�K�X�𗘗p����ڋq��ΏۂɁA���K�X�̓d�C�������j���[���K�p�ł���悤�ɂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���U�c�̂��u�ȃG�l��K���`�����v���߂鋤������ �Z��̏ȃG�l���M�[���\����Ȃǂɓw�߂�6�c�̂͂��̂قǁA���y��ʏȂ���W�����u����̏Z��E���z���̏ȃG�l���M�[��̂�����ɂ��āi��āj�v�Ɋւ���p�u���b�N�R�����g�ɋ����������o�����B ���������ł́A�ȃG�l���M�[��̂�����ɂ��ďZ��擾�҂̈ӌ��𒆐S�ɋc�_���ׂ��Ǝ咣�B�u�Z��̐V�z�E�w�����̏ȃG�l���\�̌����̈ӌ��v��94.5�����O�����ł��邱�Ƃ���A2020�N�̏ȃG�l��K���ɂ��āA����ҕی�̊ϓ_����\��ʂ�`�������ׂ��ł���Ƒi�����B ���Z�҂̌��N�m�ۂւ̋�̍��@���Ă��錻���A���{�����������������ɔ����āA���K�͏Z��ł��lj��I�R�X�g�̔�p�Ό��ʂ͍������ƁA�`���������肱�����M��̑����ɂ�钷���I�ȏ���ӗ~�����ɂȂ���A�i�C����ނ����邱�Ƃ��A�`���������߂�v���Ƃ��Ďw�E�B �o�T�u�V���n�E�W���O�v |
|
|
| ��2019�N�x��FIT���承�i�A���Ɨp���z�����d��14�~ �o�ώY�ƏȂ́A�Œ艿�i���搧�x�iFIT���x�j�ɂ�����2019�N�x�̎��Ɨp���z�����d�i10kW�ȏ�500kW�����j�̒��B���i��14�~�^kWh�Ƃ���ψ����Ă����܂Ƃ߂��B�܂��A2019�N�x�̎��Ɨp���z�����d�̓��D�Ώ۔͈͂�500kW�ȏ�Ƃ����B 2018�N�x�̎��Ɨp���z�����d�̒��B���i��18�~�^kWh�B2019�N�x�̒��B���i14�~�^kWh�́A22����������v�Z���B�����2018�N�x�Ɏ��{���ꂽ���z�����d�̑�2��E��3����D�ɂ����������i15.50�~�^kWh�������B ������i������J�ōs��ꂽ��2����D�ł́A���ׂĂ̎��Ƃ�������i�����������߁A���D�҂͂��Ȃ������B���l�ɍs��ꂽ��3����D�ł́A7�������D�������A�Œᗎ�D���i��14.25�~�^kWh�E���d���ϗ��D���i15.17�~�^kWh�B�����������Ⴉ��A���Ǝ҂͂���Ȃ�R�X�g�ጸ�̎��g�݂����߂���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2018�N�xSII�G�l���⏕���̐��ʕ�A���᎑�����J�H��P�ʂ̏ȃG�l����22.4���� ���ʕ����ł́A�\���E�̑̏�A���ϏȃG�l���M�[���ȂǁA���Ƌ敪���Ƃɕ��͂������ʂ��܂Ƃ߂Ă���B �V�K���Ƃ̍̑������i�\�������j�́A�H��E���Ə�P�ʂ�356���i577���j�A�ݔ��P�ʂ�2,115���i3,004���j�B�̑����z�i�\�����z�j�́A�H��E���Ə�P�ʂ�117���~�i198���~�j�A�ݔ��P�ʂ�74���~�i103���~�j�B������Ƃ̊����́A�\���Č���55���A�̑��Č���61���B �H��E���Ə�P�ʂ̕��ϏȃG�l���M�[���́A�\���Č��ł�20.7���A�̑��Č��ł�22.4���ŁA�̑��Č���1.7�|�C���g�����Ȃ��Ă��� �H��E���Ə�P�ʂ̍X�V�ݔ��䗦���݂�ƁA�g�b�v�͏Ɩ��i30���j�A2�ʂ͋i20���j�B 2018�N�x�͐V���Ƀg�b�v�����i�[���x�̑ΏۂƂȂ����V���[�P�[�X�̐\�����������A11���i2017�N�x6���j�ƂȂ��Ă���B �ݔ��P�ʂ̕��ϔ�p�Ό��ʃg�b�v�́u�������Ɩ��v �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2019/1�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�d�o�A�������̏グ�c�q���{�^�f�ނR�ЂłQ�D�T�����v ���dEP��2���ԁA�������̏グDR�i�f�}���h���X�|���X�j�����{�����B ���z�����d�̏o�͑����������߂����œd�͎��v�����Ȃ����ԑтɁA�d�͎g�p�ʂ𑝂₵�Ă��炤�悤�ڋq�ɗv������B ����͎���ړI�Ƃ��āA�f�ތn3�Ђ̍H��ōs���A2��5�番�̎��v�𑝂₵���B�����A���������s���DR�̌�������������邱�Ƃ����܂��A�グDR�ɔ����ۑ�Ȃǂ�o���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�悭������C�v�Ȃǃ_�C�L����20�̎���@�����o�W �uCEATEC JAPAN2018�v�ł́A�������[�J�[�̃_�C�L���H�Ƃ����o�W�B�]���̗�[��g�[�ɂ��u�₽����C�v��u��������C�v�ɂƂǂ܂炸�A�u�悭������C�v��u�W���ł����C�v�ȂǁA�����V�[���ɂ�����V���ȋ�C�̉��l���A2020�N�̏��i��������ɓ��ꂽ20�̎���@�ƂƂ��ɒ�Ă����B �uSheep Sleep�v�́A�V�䂩���C�C�̂悤�ȋ�C�̂����܂�𐁂��o���A�Q�悤�Ƃ��Ă���l�̊�ɂӂ���Ƌ�C�Ă邱�Ƃʼn��K�ȓ�����U���B�ڊo�߂̃^�C�~���O�ł́A�������߂̋�C�����˂���āA���R�ȐS�n�ǂ��ڊo�߂��}����B�Ɩ��⎺���̉��x�Ȃǂ��A�����Đ��䂳���d�g�݂��B�܂��A�uOuterTower�v�͉��O�C�x���g��J�t�F�A�����{�݂ȂǂŃN�[���X�|�b�g������鉮�O�p�̃X�^���h�A���[���̃G�A�R�����B���O�@�Ǝ����@���R���p�N�g�Ɏ��[���Ă���B�܂��A�d����������A�ǂ��ł��ݒu���\�ł���B �o�T�uBCN�v |
|
|
| ���x�m�o��2030�N�x�̑��z�����y����9.7���A�g��FIT�h�̊�����47���Ɨ\�� �x�m�o�ς́A�Z��z�����d��I�[���d���Z��Ȃǂ̕��y�Ɋւ��钲�������{���A�u2018�N�ŏZ��G�l���M�[�E�T�[�r�X�E�֘A�@��G���A�ʕ��y�\�������v�ɂ܂Ƃ߂��B ���z�����d�V�X�e����ݒu���Ă���Z��i�X�g�b�N�Z��j��2018�N�x��322���ˁA���y����6.0���������܂��B2018�N�x�ȍ~�͖��N�x18�����x�̓����ƁA�������\�z�����B�Ȃ��A�X�g�b�N�Z��͑����𑱂�2030�N�x��520���ˁA���y����9.7���Ɨ\�����Ă���B 2030�N�x�̑�FIT�̃X�g�b�N�Z���242���ˁA���z�����d�V�X�e����ݒu����Z���47���Ɨ\�������B ��FIT���_�@�Ƃ��Ĕ��d���玩�Ə���ւ̓]�����i�݁A�Z��p�~�d�r��G�R�L���[�g�Ȃǂ̊��p���z�肳���B���̑��ɂ��A�V�d�͂��d�͏�����Ɨ]��d�͔������̃Z�b�g��Ă��s���ȂǁA��FIT�Z��̗]��d�̗͂����p���߂���c�Ɗ��������������Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���g���^���u���f�o�[�i�[�v��V�J���A�H��CO2�[���ֈ���O�i �g���^�́A���f��R���Ƃ���o�[�i�[�𒆊O�F�H�Ƃ̋��͂ɂ��V���ɊJ�����A�L�c�s�̖{�ЍH��b�����C���ɓ��������Ɣ��\�����B �]���A���f�o�[�i�[�́A���f�_�����iNOx�j��������������邽�߂ɁA���p���͍���Ƃ���Ă����B����A����J���������f�o�[�i�[�́A���f���ɂ₩�ɔR�Ă�����u���f�Ǝ_�f��������Ȃ��悤�ɂ���@�\�v�Ɓu�_�f�Z�x��������@�\�v��2�̐V�@�\�����ACO2�r�o�[���ɉ����āA���K�͂̓s�s�K�X�o�[�i�[���x���ȉ��܂�NOx�r�o��啝�ɒጸ������ȂǁA���������\�𗼗������Ƃ����B 1�ڂ̐��f�Ǝ_�f��������Ȃ��悤�ɂ���@�\�́A���f�Ǝ_�f���o�[�i�[���ŕ��s�ɗ����A���S�ɍ������Ă��Ȃ���ԂŊɖ��ɔR�Ă����邱�ƂŁA�Ή����x��������B ����1�̎_�f�Z�x��������@�\�́A���f���o�[�i�[���ɋ�������p�C�v�̒����ɏ����Ȍ����A���ʂ̐��f�Ǝ_�f�����炩���ߔR�Ă����A�_�f�Z�x��K���l�ɉ�������ԂŎ�R�Ă��n�܂�悤�ɂ��ĉΉ����x��������Ƃ����d�g�݂��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���_���͑�FIT�̏Z��z���A�~�d�r�̌��z�^�p�T�[�r�X�o�� �ɓ����́A�����d�̓z�[���f�B���O�X�P����TRENDE�ȂǂƋ����ŊJ�������ƒ�����~�d�V�X�e���ƁA�~�d�r�Ƒ��z�����d�̗��p��O��Ƃ�����p�̓d�C�����v���������Ɣ��\�����B ��FIT�̏Z��z�����d���[�U�[���^�[�Q�b�g�ɂ����T�[�r�X���B2018�N11��������J�n�B �ɓ����́A�G�k�G�t��H�������J�������~�d�r�́A��i�e��9.8kWh�̃��`�E���C�I���~�d�r�B�u�S���^�v�̂��߁A��d���ɑ���̑S�ẴR���Z���g�ɑ��ēd�͂������ł��A200V�̏o�͂��\�B ���\�����~�d�V�X�e���ł́AMoixa���J������AI�����p����d�͍œK���\�t�g�E�F�A��g�ݍ��킹��B�����́A�C�ۏ���A���[�U�[�̏���d�͗ʁA���z�����d�̔��d�ʂȂǂ̏��́E�w�K����_���B���̕��͌��ʂɍ��킹�āA�e�ƒ�ɍ��킹���œK�Ȓ~�d�r�̏[���d���\�ɂȂ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�G�A�R���̎��v�̐헪�����A�_�C�L�������z�������\ �_�C�L���̓I�[�X�g���A�̋Ɩ��p�①�E�Ⓚ�@�탁�[�J�[�uAHT �N�[�����O�V�X�e���Y�v��8��8100�����[���i1127���~�j�Ŕ�������Ɣ��\�����B �C�O�𒆐S�Ɋ�Ɣ��������������A�G�A�R���ȊO�̎��Ƃ��g�傷��헪���B AHT�Ђ�1983�N�ݗ��B���B�̃R���r�j��X�[�p�[�����ɁA���N�H�i��A�C�X�N���[������ׂ�V���[�P�[�X�������Ă���B�]�ƈ���1600�l�A���㍂��600���~�B �_�C�L���́AAHT�Ђ����R���r�j�Ȃǂւ̘̔H���g���A�Ɩ��p�G�A�R���̔̔����L���_��������B ���ĂȂǐ��E�̎�v�s��ł͂��łɁA�G�A�R���̐L�т͓݂�n�߂Ă���B�_���������̂��A�①�E�Ⓚ�@�펖�Ƃ��B �o�T�u�����V���f�W�^���v |
|
|
| ���d�C�g�p�́g�H�v�h�����A�q�[�g�|���v����������p����DR�T�[�r�X�o�� �����d�͂ƃf���\�[�́A�ƒ�p�G�R�L���[�g��S�ً����p���Ēn��̓d�͎��v������f�}���h���X�|���X�T�[�r�X��2019�N2��1������J�n����B ���T�[�r�X�́A���Ђ������J�������G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e�������p���A�d�C�̎g�����̍H�v�������̂��B��̓I�ɂ́A�d�͎g�p�ʂ̑����ď�̎��ԑт�A���z�����d�̔��d�ʂ��������ԑтȂǁA�����d�͂��d�͂̎��v�Ƌ����̃o�����X���������ꍇ�ɁA�ƒ�ɐݒu���ꂽ�f���\�[��HEMS����āA�G�R�L���[�g�̉^�]���Ԃ�A�S�ً̉��x�������ŃR���g���[������B ���p�҂ɂ́A�R���g���[�����Ԃɉ������Ή����u�������z�v�Ƃ��āA���X���̓d�C�����ɏ[������B ���p�҂ɂ́A�@����R���g���[����������Ȃǂ����O�ɒm�点����ŁA�����ŃR���g���[�����s�����Ƃ���A��������K���͑��Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����ȏȃG�l���i�̍ō������ꗗ2018�N�x��L2�|Tech�����i�āj���\ ���Ȃł́A�G�l���M�[�N��CO2�̔r�o�팸�ɍő�̌��ʂ������炷�擱�I�iLeading�j�Ȓ�Y�f�Z�p�iLow�|carbon Technology�jL2�|Tech�i�G���c�|�e�b�N�j�̕��y���i��i�߂Ă���B �����x�ł́A�ł��擱�I�Ō����̗D�ꂽ�ݔ��E�@�퓙�̏����uL2�|Tech���X�g�v�uL2�|Tech�����\�v�uL2�|Tech�F�ؐ��i�ꗗ�v��3�̃��X�g�ɂ܂Ƃ߂Ă���B ���Ȃ́A���������������b���̎��W���p�����A�u2018�N�xL2�|Tech�����\�i�m��Łj�v�A�u2018�N�xL2�|Tech�F�ؐ��i�ꗗ�v�����肵���\����\��B����ɂ����������g�݂�ʂ��ă��X�g�̏[����}��Ȃ���A���Ȃ̋Z�p�����x���A�Z�p�J���E���؎��Ɠ��̎{��Ɋ��p���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ꂩ��̍ăG�l���d���ƂɕK�v�ȃ|�C���g4�o�ώY�ƏȂ��� �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[��ʓ����E������d�̓l�b�g���[�N���ψ���ŁA��5���G�l���M�[��{�v�悪���肳�ꂽ���Ƃ܂��A���̃X�e�b�v�ƂȂ�Đ��\�G�l���M�[�̎�͓d�����Ɍ���������̘_�_���������B �ăG�l�̎�͓d�����Ɍ��������ʂ̘_�_�Ƃ��āA�ȉ�4�_���������Ă��� �@(1)�R�X�g�_�E���̉�����FIT����̓Ɨ� �@(2)��������I�Ȏ��Ɖ^�c�̊m�� �@(3)������d�̓l�b�g���[�N�̍\�z �@(4)�Y�Ƌ����͂ƋZ�p�v�V�̒Njy �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���w�Z�̏ȃG�l�A�ǂ��i�߂�H ���ȏȁA�G�l���M�[���P�ʂ̍l�����Ȃǎ��� �����Ȋw�Ȃ͌��������w�Z�E���Z�ɂ�����ȃG�l���i����������Ă���L���҉�c�ɂ����āA�w�Z���ɂ�����G�l���M�[�g�p���Ԃ܂����G�l���M�[����P�ʂ̐ݒ�̍l������A�ȃG�l��̑f�ĂȂǂ��������B �ߔN�A�w�Z�{�݂ł́A�G�A�R���̐ݒu��ICT�@��̓����ɂ�鍂�@�\���A�����E��ԁE�x�����ɍs����w�Z����ȊO�̑��ړI���p�ɂ��G�l���M�[�g�p�ʂ͑����X���ɂ���B�������A�ȃG�l�@�ɂ����ẮA�w�Z���ȃG�l�ɓw�߂邱�Ƃ����߂��Ă���B�܂�����ψ���́A�@�߂Ɋ�Â��w�Z���̃G�l���M�[���Ǘ�����ӔC������B ���̂��ߋ���ψ���ł́A�w�Z���̏ȃG�l��Ɏ��g��ł��邪�A�����ʐς�P�ʂƂ����A�G�l���M�[����P�ʂ̉��P�ɋꗶ���Ă�����w�E����Ă���B�܂��A�w�Z�̏ȃG�l�𐄐i���邽�߂ɂ́A����ψ�����S�ƂȂ�A�w�Z�A���ǂȂǂƂ̑g�D�I�ȘA�g�����߂��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l��A���K�͌����̋`���������� ���y��ʏȂ́A�I�t�B�X�r����z�e���ȂǐV�z�̒��K�͌����i�����ʐ�300�������[�g���ȏ�2000�������[�g�������j�ɏȃG�l��ւ̓K�����`���t���邱�Ƃ����߂��B ���݂̑�K�͌�������Ώۂ��L����B�}���V�������܂ޏZ��Ə��K�͌����i��300�������[�g�������j�ւ̋`���t���͌�����B �`������2020�N�ȍ~�̌��ʂ��ŁA���z��͒f�M���⍂�����̋A�����_�C�I�[�h�iLED�j�Ɩ��Ƃ������ݔ��̓��������߂���B���N�̒ʏ퍑��Ɍ��z���ȃG�l�@�����Ă��o����B ���K�͌����͏ȃG�l��ւ̓K����������91���ƍ����A����̗L���҂�́A�`�������Ă������̋���͂Ȃ��Ɣ��f�����B ����A�Z��⏬�K�͌����͓K������50�`60����ƒᐅ���ȏ�A2020�N10���ɂ͏���ő��ł��T���Ă��邽�߁u�R�X�g�����K��������ƁA�Z����ւ̉e�������O�����v�Ǝw�E�����B �o�T�uSankeibiz�v |
|
|
| ���h�C�c�������̃\�[���[���]�ԓ������� �h�C�c�́A�P�����ߍx�ɂ����āA�������ƂȂ鑾�z�d�r���W���[���ɂ���ĕܑ����ꂽ�\�[���[���]�ԓ����J�ʂ������Ƃ����\�����B �����Ŕ��d���ꂽ�d�͎͂��]�ԓ��̏Ɩ��Ƃ��Ďg�p����邾���łȂ��A���j�^�����O�X�e�[�V�����̉^�c�₻�̑��̌����{�݂ɂ����Ďg�p�����B ���̃v���W�F�N�g�͍��ƋC��ی�C�j�V�A�e�B�u�iNKI�j���i�߂�A�M�R���e�X�g�u���]�Ԍ�ʂɂ��C��ی�v�ɂ����đI�o���ꂽ�v���W�F�N�g�̈�ŁA��78��4000���[�����������ꂽ�B���������\�[���[���]�ԓ��͕�2.5���[�g���A����90���[�g���ƂȂ�A���z�d�r�̕\�ʐς͖�200�������[�g���ɂ��A�N��12���K���b�g���̔��d�������܂�Ă���B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| �������̏����w�Z�A���z�����d�̐ݒu����2018�N5�����_��31�� ���{������ �����Ȋw�Ȃ́A�n�����g����̎��g�ݐ��i��ړI�ɍs�����A2018�N5��1�����_�ł̌����w�Z�{�݂ɂ�����Đ��\�G�l���M�[�ݔ����̐ݒu�̒������ʂ����\�����B �����Ώۂ͑S���̌����w�Z�{�݁B��̓I�ɂ́A�c�t�����珬�w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�ȂǁB �������ڂ́A�Đ��\�G�l���M�[�ݔ����̐ݒu�B�����Ώېݔ��́A���z�����d�ݔ��A���͔��d�ݔ��A���z�M���p�ݔ��ȂǁB �Đ��\�G�l���M�[�ݔ����ݒu�̒������ʂ́A���L�̒ʂ�B �E2018�N5��1�����݁A�����̏����w�Z�ɂ����鑾�z�����d�ݔ��̐ݒu����31.0���i�O������6.4�|�C���g���j �E�����̏����w�Z�ɐݒu����Ă���Đ��\�G�l���M�[�ݔ����̂����A��d���ł��g�p�\�ȋ@�\��L���Ă���ݔ��̊����́A58.6���i�O������14.1�|�C���g���j ��ޕʂ̐ݔ��ݒu���̍��v�́A���z�����d�ݔ�10,657�Z�A���͔��d�ݔ�711�Z�A���z�M���p�ݔ�240�Z �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2018/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���u���͂P�O�O���d�C�A��ƂŊg�咆�^���d�d�o�́u�A�N�A�v���~�A���v �����d��EP�̓d�C�������j���[�u�A�N�A�v���~�A���v�����铮�����A��Ƃ̊ԂōL�����Ă���B�A�N�A�v���~�A���́AFIT�i�Đ��\�G�l���M�[�Œ艿�i���搧�x�j���x�𗘗p���Ȃ����͔��d100%�ō\���B�����͒ʏ�������������A�C�I����ԉ��ȂNJ��ӎ��̍�����Ƃ���������芷�����B�m���ő������̂���CO2�i��_���Y�f�j�}����Ƃ��āA��������������������Ƃ������������B �A�N�A�v���~�A����2017�N�x������J�n�����B�����͎O�H�n���́u�V�ۂ̓��r���f�B���O�v�A�\�j�[�̖{�ЂƁu�\�j�[�V�e�B���v�ō̗p�B���̌�A�C�I����t�W�N���̖{�ЁA�L�����O���[�v��ԉ��̍H��ɓ������L�������B���݂͈�O�ł̗̍p������o�Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���X�ȃG�l�A�`�h���p�^���d�͂ƃA�C�O���b�h�A�j�g���Ŏ������� ���d�͂ƃA�C�E�O���b�h�E�\�����[�V�����Y�́A�l�H�m�\�iAI�j��r�b�O�f�[�^�����p���āA�X�܂̏ȃG�l��R�X�g�팸�Ɋ�^����V�T�[�r�X�������J������Ɣ��\�����B ��Ɩ��Ȃǂ̐ݔ���d�͂̎g�p��C��A���q�Ȃǂɉ����āA�œK�ɉ^�p�E���C�ł���悤�㉟������B�����͗ʔ̓X��R���r�j�Ȃǂ̓X�܂��Ώۂ����A�Ǝ�͒i�K�I�ɍL���Ă����B �T�[�r�X�̖��̂́u�G�i�b�W2.0�v�B�^�u���b�g�[���Ŏg�p�ł��A�X�܂��Ƃ�1�������B�A�C�E�O���b�h���J������AI�ɂ��ȃG�l�T�[�r�X�u�G�i�b�W�v�W������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���x�m�ʌ������f�[�^�Z���^�[�̋d�͂�啝�ɍ팸�������Z�p���J�� �f�[�^�Z���^�[�ł́A����܂��܂�����d�͂̑����������܂��B���̂��߁A�S�d�͗ʂ�30������50�����߂�ݔ��̏ȓd�͉������ɋ��߂��Ă���B ����A�����̋@�ߕӂ≮�O�ɉ����x�𑪒肷��Z���T�[��ݒu���A�@�̐ݒ�l�ɑ��āA���C�z������ъO�C�������̗�p�E�����ɗv�������d�͂��v�Z����B���̏�ŁA����d�͂��ł��������Ȃ�悤�ɁA���C�z�ƊO�C�����̔䗦�𐧌�\�ȋZ�p���J�������B����ɂ��A���x����ю��x������d�͂œK�ɊǗ����邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A29���̋d�͍팸���m�F���邱�Ƃ��ł����B �ݒ艷�x��ύX�����ۂɁA�ߋ��̎������x���z�̕ω��͂��A�@���Ƃ̊e�G���A�ւ̉e���̑傫�����Z�o����B����G���A�̃T�[�o���x���オ�������ɁA�T�[�o���ݒu����Ă���G���A�ւ̉e�����傫���@�̐ݒ艷�x�𐧌䂷�邱�ƂŁA�Œ���̏���d�͂ł̉��x�Ǘ����\�ƂȂ�B �o�T�y�j���[�X�����[�X�z |
|
|
| �����S�ȃo�C�I�R���ʎY�ց^���V�k�ȂǒY���Łu���Q���v �p�[�����̐��Y�ߒ��Ŕ������郄�V�k�iPKS�j���ʖ[�iEFB�j�A�ÖiOPT�j�̓o�C�I�}�X���d�̔R���Ƃ��Ē��ڂ���邪�A�L�Q�������Y�݂̎킾�BDSJ�z�[���f�B���O�X�ƃK�C�A���Z�p�������́A�����S�ĂQ�����ĒY���R���ɂ���Z�p�𐢊E�ŏ��߂ĊJ�������B 12������C���h�l�V�A�Ŏ����I�ɐ��Y���J�n����B�����O�Ōv�悪�������o�C�I�}�X���d���̎��v����荞�݁A��_���Y�f�iCO2�j�팸�ɍv������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���n��Ȃ��u�����̓d�C�v�^�@�h�����A���N���狟�� �����̏Z�E���В��߂�ِF�̐V�d�́uTERA Energy�v�iTERA�G�i�W�[�A���s�s�j���A���s�s���̎��@�Őݗ�����s�����B ���݁A�����d�C���Ƃ̓o�^�\�����ŁA���N�S������̔����n�߂�\��B�܂��͒����E�l���G���A�Ŏ��@��h�Ɓi���j�Ȃǂɓd�͂�̔����A2020�N�x����S���W�J��ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��HIS�ŗ��s����ƁA���̌��̓d�C��{�����������ɂȂ�V�T�[�r�X H.I.S.�Ɠ��ЃO���[�v�̐V�d��HTB�G�i�W�[�́A���s�v�悪�d�C��ߖ���l���邫�������ƂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āAH.I.S.�𗘗p���ė��s�ɍs���l�̓d�C�オ���ɂȂ�AHTB�G�i�W�[�̓d�̓��j���[�u���̂����łv�̐V�d�̓v�����\����t��11��1���i�j����J�n����B �ƒ�̓d�C���u���̂����łEH.I.S.���g�N�R�[�X�v�Ɍ_�邱�Ƃɂ��A�o�����̓d�C��̊�{�������N4��E�ő�4�J���Ԃ܂Ŗ����ɂȂ�Ƃ����T�[�r�X���B�Ȃ��A�_��\�����݂́uH.I.S.�łvWEB�T�C�g����s���B ���Ƃ��A40�A���y�A�̌_��̏ꍇ�A�o�����́A��{����1023.23�~�������ɂȂ�B40�A���y�A�Ō�350kWh���p�ŁA�N��4�s�ɍs�����ꍇ�A�����d�̗͂������N�Ԗ�6,440�~�����Ȃ�Ƃ����i�����[�X���_�̓����d�͂̏]�ʓd��B�Ƃ̔�r�j�B�܂��͓����G���A�Ő�s�̔����A���G���A�ւ̊g��������s���Ă����\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�H�����A���[�\���łu�o�o�^�֓��Q�O�O�X�܁A���v�팸�����Z �O�H�����́A�O���[�v�̐V�d�͂�MC���e�[���G�i�W�[��ʂ��āA���[�\���X�܂�VPP�i���z���d���j���ƂɎQ�������Ɣ��\�����B�d�͏������Ƃ̎����Ǘ��ŁA���d�͎���s�ꂪ�����������Ȏ��ԑт�\�z���A���[�\�������\�[�X�A�O���Q�[�^�Ƃ��ēX�܂̋Ȃǂ����u�Ő��䂷��B �d�͂̒��B�R�X�g�𐔁��팸���A�ꕔ��d�C��Ƃ��ĊҌ�����B���[�\����2020�N�ɑS��5��X�܂�VPP�̓�����ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Z�F�d�H�A���h�b�N�X�t���[�d�r�ň����ȓd���t�J���� �Z�F�d�C�H�Ƃ́A�~�d�r�̈�ł���u���h�b�N�X�t���[�d�r�v���g�̂��邽�ߌ����ጸ�Ɏ��g�ށB �d���t�̌����Ɉ����ȃ`�^���ƃ}���K���𗘗p�B����������}���Čڋq���������₷�����𐮂���l�����B���݂̓d���t�����̓o�i�W�E���B�����Ȃ̂Ō���������A���i�R�X�g�������グ�Ă���B�����ȃ`�^���E�}���K���n�d���t���J�����đ����̏��p����ڎw�����j���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ������ȂǁA�u���b�N�`�F�[���Z�p�����p�����d�͒��ڎ���̎��؊T�v���Љ� ������w�A���{���j�V�X�A���d�͂���юO�HUFJ�́A�u���b�N�`�F�[���Z�p�����p�����d�͒��ڎ���̎��؊T�v���Љ���B���̎��i�����j�́A�Đ��\�G�l���M�[�̕��y���i�ނȂ��A�d�͋����V�X�e������K�͏W��^����u�������U�^�v�ɕω����A�d�͂̏���҂Ɓu�v���V���[�}�[�i���Y����ҁj�v�ɂ��d�͒��ڎ���̏������W�]����邱�Ƃ��痧�Ă��ꂽ���́B ���z�����d�ݔ���ݒu�����v���V���[�}�[��ɂ����Ĕ��������]��d�͂��A�u�u���b�N�`�F�[���Z�p�v�����p�����͋[�I�Ȏ���ɂ��A�����̓d�͏���ґ�֑��d����v���b�g�t�H�[���ɂ��āA �@1)�����̕]������ё����A �@2)�V�X�e���̊J���A �@3)���V�X�e���̍\�z����ю��A �@4)���ς����ւ̃u���b�N�`�F�[���K�p�Ɋւ��鏕�����������{���A����ꂽ�m���܂������H�I�Ȏ��ɂȂ��Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����k�o�ώY�Ƒ��u�o�͐���͍ăG�l��͓d�����ɕK�v�s���v �o�ώY�Ƒ�b�́A��B�d�͂�10��13���A14���Ɏ��{�����ꕔ�̑��z�����d���Ǝ҂ɑ���o�͐���ɂ��āA�u�o�͐���Ƃ����͍̂Đ��\�G�l���M�[����͓d�������Ă������߂ɁA�K�v�s���Ȏ��g�݁v�Ƃ̔F�����������B ����́A��B�d�͂̏o�͐���ɂ��āA�ꕔ�V�X�e���s��ŕK�v�̂Ȃ����d���~�߂����Ƃ�A�~�d�r�E�A�n���̋��������߂鐺�����邱�Ƃ܂��A�L�҂����b�̌��������߂��ē������B ��B�d�͂́A�D�V�ő��z�����d�̏o�͂����������A�T���͓d�͎��v���������A�����͂��d�͎��v������������܂ꂽ���߁A�d�͂̈��苟�����m�ۂ��邽�߁A��B�S�y�ő��z�����d�ɑ��ďo�͐�������{�����B�o�͐�����w�������̂́A13����32��kW�A14����54��kW�̑��z�����d�B �X�y�C����A�C�������h�ł��A�ϓ�����ăG�l�ɓK�Ȑ����O��Ƃ��邱�Ƃɂ���āA���d���ւ̐ڑ��ʂ𑝂₵�Ă���Ƃ����ʂ�����Ɛ��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���k�C���n�k�ŏ��������u���z�����d�̎����^�]�@�\�vJPEA�̒������ʂ܂Ƃ� ���z�����d����iJPEA�j�́A�k�C���_�U�����n�k�ɂ���Ĕ���������K�͒�d�ɍۂ��A�u���z�����d�̎����^�]�@�\�v�̊��p�ɂ��ăA���P�[�g���������{�����B �����̌��ʁA�Z��p���z�����d�V�X�e����ݒu���Ă���l�͒~�d�r�݂��Ă��Ȃ��P�[�X�ł��A���ʂ̒n�k�ɂ����Ė�85���������^�]�@�\�𗘗p�A��d���ɗL���Ɋ��p�ł����Ƃ̐����������������Ƃ��킩�����B �u�①�ɂ����ъ���g�����~�d�r������Ζ�2���Ԗ��i�V�v �u�①�ɂ̒��̐H�ނ点���ɍςv �u���ъ�ł��т𐆂����Ƃ��ł����v�Ȃǂ̐�����ꂽ�B�Ƃ��ɒ~�d�@�\�݂��Ă��郆�[�U�[����́A�u��2���Ԗ��Ȃ������ł����B�v�ȂǁA���i�Ɠ����������ł����Ƃ̐�����ꂽ�B �Ȃ��A�u�����^�]�@�\��m��Ȃ������v�u�g����������Ȃ������v�Ƃ����ӌ����������B �o�T�y���r�W�l�X�z |
|
|
| ���J�i�_�A�I���^���I�Ȃ�4�B�ŒY�f�Œ���������j�\�� �J�i�_�̃g���h�[�́A�������ʃK�X�̔r�o�K����ł��o���Ă��Ȃ�4�̏B��ΏۂɁA�Y�f�ł�������j��\�������B�l���̑����I���^���I�B�͔������Ă���B ���N4������Y�f1�g��������20�J�i�_�h���i15.27�ăh���j������B2022�N��50�J�i�_�h���ɂȂ�܂ŁA���N10�J�i�_�h���������グ��B�J�i�_���{�͓��Ă�2016�N�Ɍ��\���Ă����B �g���h�[�́u�����̑Ή����x���킹�邱�Ƃ��C��ϓ���Ƃ��čł����ʂ�����v�Ƌ��������B �o�T�u���C�^�[�v |
|
|
| ����B����z���Ŕ��d��������裂Ƃ͉��Ȃ̂����������̍ăG�l���d�ʂɂ��Ȃ���� �s����ȍăG�l�d�͂�����d��������H�v���K�v���B���d�Ԃ̊g�[�E�L�扻�A�~�d�r�̐ϋɓI���p�A���̂��߂̃R�X�g�ጸ���K�v���B �����������A�]��d�͂��g���Đ���d�C�������A���f�ɕς��ăG�l���M�[��������uP2G�v�V�X�e�������ڂ���Ă���B �h�C�c�͍���������P2G�Ɏ��g��ł���A���݁A������30����P2G���v���W�F�N�g�����{����Ă���B�]��d�͂𐅑f�Œ������ēx�d�͂ɖ߂��Ƃ�����{�`�����łȂ��A���f�̂��낢��ȗp�r�ɑΉ��������l�ȋZ�p�����s���Ă���B �ł������͓̂V�R�K�X�O���b�h�ւ̒������B���f�̂܂܃p�C�v���C���ɒ������A�����K�X�Ƃ��ĔM���p�����ق����������悢�Ƃ������z���B ���^�����v���W�F�N�g������������B�ăG�l�R���̐��f��CO2�Ɣ��������ă��^���K�X�����A�p�C�v���C���ɒ�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ȁA���z�ݔ��v��̂����u�Ɩ��v�̏ȃG�l���ɌW�錟�����J�n ���y��ʏȂ́A�u���z�ݔ��v��v�̂����u�Ɩ��v�̏ȃG�l��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�ȃG�l�Ɖ��K�������˂��Ȃ����Ɩ��v�ɌW�錟�����J�n�����B ����́A���z�ݔ��̎��{�v�Ɋւ���W���I�Ȏ�@���߁A�u�����{�݂̊�{�I���\��v�ɒ�߂鐫�\�̐������m�ۂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����́B�w���o���ҁA�W�w��i���z�A�Ɩ��A�d�C�ݔ��j�Ȃǂ���Ȃ�u�����{�݂ɂ�����Ɩ��ݔ��v��@�̍��x���Ɋւ��錟����v��ݒu���A����30�N10��17���ɑ�1������J�Â����B������ł́A �@1)�Ɩ��ݔ��̈�w�̏ȃG�l�Ɍ������ݔ��̃C���[�W�i����Ƃ̂��߂̏Ɩ��̕ʌ����j�A �@2)�����ȏƖ����̋ϓ��z�u�Ɣ������m�`�Z���T���̊��p�A �@3)�Ɠx�▾�邳���̊T�O�����A4)�P�x�x�[�X�̍l�����⒋���̍l���A �@4)�ŐV�̋Z�p��T�O��Ɏ������ۂ̌������j�ɌW��ӌ������o���ꂽ�Ƃ����i�����F 12���J�×\��j�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2018/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���ō��i�g���h���������ŐV�G�A�R���A�k���Ȏ��x����̗��� �_�C�L���H�Ƃ́A�ƒ�p�G�A�R���̍ŐV���f���u���邳��7�iR�V���[�Y�j�v�\�����B���@��̓��[�U�[���D�މ��M�����w�K�A�L�����A�����ɉ����Ď��x��2�ʂ�����œK��������V�J���́uAI���K����v�@�\�𓋍ڂ������Ƃ��ő�̓������B �ڋʂƂȂ�AI���K����́A����܂ł����݂Ƃ��Ă������x������x�[�X�Ƃ��āA������⊦����Ƃ������l�ő��l������̃j�[�Y�ɓ�����@�\���B���@�\�́A�G�A�R���^�]�J�n30���ȍ~�Ƀ��[�U�[���s���������R������𒀎��ɕ��͂��A���M���̍D�݂��w�K�B���ГƎ��̋���w�W�ƂȂ�u���K�w�W�v�̂������l�i���K�]�[���j�����[�U�[�ŗL�ɐݒ肷��B �܂��A���@��̎����@�ɂ͐ԊO���Z���T�[���V���ɓ��ڂ���Ă���A�����ɂ���l���t�˔M���v�����A�p�����[�^�[�̉��x�Ǝ��x�ɉ����āA�t�˂��l�����ĉ��K�w�W���Z�o�ł��A�}�ȋC���ω�����˂��ȂǁA���ω��ɒǏ]���ă��[�U�[�̍D�݂̉��M��Ԃ���������B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���G���[�p���[�AVPP���؎��ƂŒ~�d�r500�����ē�������� �G���[�p���[�́A�~�d�r�̃}���`���[�X����i�߂邽�߁A�����d�͂���d�͂ȂǍ���9�ЂƘA�g���A��K�͂ȃo�[�`�����p���[�v�����g�iVPP�j�\�z���؎������A10���㔼���J�n����Ɣ��\�����B��̓I�ɂ́A��ʂœ������䂷��A�O���Q�[�V�����R�[�f�B�l�[�^�[�iAC�j�̊�V�X�e������̎w�߂Ɋ�Â��A9��400�䒴�ƈ�ʉƒ�ő�80���ɐݒu���ꂽ�A���v��500��i�~�d�e��1.6MWh�^�o��780kW�����j�̒~�d�r�̏[���d������s���B �܂��A�����������ɕ��U���Đݒu���ꂽ���^�~�d�V�X�e�����S��i��a�n�E�X�H�Ƒ��{�Ѓr����200��A�����{�Ѓr����100��j�̓���������s���B ���̎��؎����v���W�F�N�g�ɂ����āA���Ђ͎��v�Ƃ�VPP�T�[�r�X�_��ڒ������ă��\�[�X������s�����\�[�X�A�O���Q�[�^�[�iRA�j�Ƃ��ĎQ������B�܂��A���dHD�Ɗ��d�͂́A���ꂼ��AC�Ƃ��ĎQ������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ŁA���C�h�ȉ^�]�\���O���x�͈�(���50���`�����}�C�i�X27��)�̋� ���ŃL�����A�́A�]���@���Ŏ���22���̏��^�E�y�ʉ���}��Ȃ��獂���ȃG�l���\������V�J����DC�c�C�����[�^���[�R���v���b�T�[���ɂ��A��[�^�]���̎��O���x����u50���v�A�g�[�^�]���̎��O���x�����u-27���v�Ƃ𗼗������A�ƊE�ōł����C�h�Ȏ��O���x�͈͂ł̉^�]���\�B ����ɂ��ҏ��⌵�����~�̊����ɕ����Ȃ��^�t�ň��S�̐M�������m�ۂ��Ȃ���A�ȃG�l�@2015�N��l�N���A�͂������A�X�^���_�[�h�N���X�ł�����APF(�ʔN�G�l���M�[�������)��B�����A�����ȃG�l���\�������B �܂��A�M�����퓙�̌y�ʉ��Ɏ��g�݁A�ƊE�Ōy��34kg�����������B�X��1�t�@�����ő啝�Ȍy�ʉ��ƁA������50cm�ጸ�����B�����̉��P�͉^���E�ݒu���̌����Ƃ̕��S�y���ɂȂ���B�S�@���ʂ��A�����ׂ̏��Ȃ��V��}R32���̗p�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�����G���W�Œ����s��ɎQ���B160���~���v���@��N���� �p�i�\�j�b�N��2019�N�x���ɒ����ŁA�r�K�X�E�r��������y��E���Ƃ��������G���W�j�A�����O���ƂɎQ������B���Ђ̍H�ꂪ����A�d�v�ڋq�����������암�Ɏ��Ƌ��_��݂���B �������{�͓s�s�J���Ɍ����A���q���iPM2.5�j�ɂ���C�������ɉ����A�y���͐�̏ɗ͂�����B�����Ŕ��^�f�B�X�v���[��d�r�̍H��ȂǂŔ|������������A2020�N�ɖ�160���~�K�͂Ɨ\������钆���̊�����v����荞�ށB �����ŁA�H�ꂩ��o��r�K�X�E�r���̏V�X�e����v�E�{�H����ق��A�s�s�J����H�ꌚ�݂̍ہA�y��␅���̉��������ď���T�[�r�X���n�߂�B�g���l�������C����V�X�e���̈�������������Ƃ����B ������������̋Z�p�҂��ݐЂ��鋒�_���A�����암�ɐV�݂�����j�B2025�N�x����ɔN��100���~�K�͂�ڎw���Ƃ݂���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���u�d�C�� �n�Z���v�̎�����^�~�G�l���M�[�Z�p�@�ۍg�Ȃǂ��o�ϐ��]���Ȃǎ��{�� �ۍg�A�G�l���M�[�����H�w���������u�M�����p����������^�~�G�l���M�[�Z�p�̊J���E���v�̈ꕔ�Ɩ�����������Ɣ��\�����B ���̎��؎��Ƃ́A��R�X�g�Ȓ~�G�l���M�[��i�Ƃ��āu�M�v�ɒ��ڂ��A�n�Z���i�퉷�Ōő̂̉��ނ𐔕S�x�ɉ��M���t�̏�ԂƂ������́j�Ȃǂ�p���ēd�͂�M�ɕϊ����Ē~���A�K�v�Ȏ��ɍēx�d�C�ɕϊ�����Ƃ����V���Ȏ����E���U�^�̎�����~�M�Z�p�̊J���E�����s���B ���Ђ́A���̎��؎��Ƃ̒��ŁA�Y�ƊE�ɂ�����M�G�l���M�[���p�̒�����~�M�V�X�e���̌o�ϐ��]���A���؏I����̏��ƓW�J�Ɍ����������Ȃǂ�S������B �����Ƃɂ��~�M�Z�p���i�ɂ��A���z���E���͔��d�Ȃǂ̓d�͂��R�X�g�ň���I�ɗ��p�ł���Ƌ��ɁA�Đ��\�G�l���M�[�R���̔M���p�ɂ��M���̒�Y�f�����������邱�ƂŁACO2�r�o�ʍ팸�ւ̍v�������҂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���_�|���A���d�������f�������u�ɐV���f����lj��B �_�|���\�����[�V�����́A�I���T�C�g�^���d�������f�������u�̂����A�e�\���@����x�[�X�A�t���[���ɔz�u�����^�C�v�ł���u�X�L�b�h�}�E���g�^�C�v�v���u���b�V���A�b�v���A�V�^�u�X�L�b�h�}�E���g�^�C�v�v�Ƃ���2018�N10���ɔ�������B �V�^�X�L�b�h�}�E���g�^�C�v�́A���f�K�X�����ʂ�����20�`60Nm3�ł���A�R�X�g�_�E���ƏȃX�y�[�X���A����d�͂̒ጸ��B�������Ƃ����B �]���@�Ɣ�r���A��30���̃R�X�g�_�E���������B�ݒu�X�y�[�X�́A�ݒu�ʐϔ�Ŗ�20���̍팸���\�ƂȂ�B����ɁA����d�͂��10���Ⴍ�}�����d�C�������W���[���̗̍p�ɂ��A���f���������̌����}�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����������u���z2���~�v����ցH �l�グ�ƒn��i���g��̔w�i �������̂��钬�ł͐������������z4370�~�i2015�N�j����2��2239�~�i2040�N�j�ɂȂ鄟���Ƃ����V���b�L���O�ȃf�[�^�����\����Ă���B����́u�l����������̐��������͂ǂ��Ȃ�̂��H�i�����Łj�v�Ƃ��������̈ꕔ�� ���̐��l�͖�20�N��̗\���l�B���{�̐����C���t��������͂��Ȃ�[���ȏɂ���A�Ή��ɂ���Ă͑��Ӕj�]���邱�Ƃ𐭕{���d�X�F�����Ă���B���ہA���������͔N�X�オ�葱���Ă��āA���{��������ɂ��ƁA�����l�グ�ɓ��ݐ��������̂͂���1�N��47�ɂ̂ڂ�B�ƒ�p�̐���������10�N�O�ɔ�ׂ�Ɩ�160�~�l�グ����A���z��3228�~�ƂȂ��Ă���i20�������[�g��������̑S�����ρj�B �܂��A�����̂��Ƃ̗����i�����傫���A���Ɍ��ԕ�s�����z853�~�Ȃ̂ɑ��A�k�C���[���s�͌��z6841�~�B���Ɍ��z��6000�~�A�N�z�ɂ���7��2000�~�߂��̋��z���������Ă���B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| ������29�N�x�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����̌��ʁi����l�j ���̒����́A�e���т̐��э\���A�Z��̌��ĕ��A�d�C�A�K�X���̃G�l���M�[����ʂ�Ɠd���i�ʂ̎g�p���A����496���ڂɂ킽���ďڍׂɒ��������B �������ʂ̂P�Ƃ��āA����т́A�ᒆ�N���тɔ�ׁACO2�r�o�ʂ��������Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A�������ʂ����p���A�Ⴆ�A��d�T�b�V�܂��͕��w�K���X�̗L���ʂŃG�l���M�[����ʂ͂���ƁA�g�[�ɂ��G�l���M�[����ʂ͖�24%���Ȃ��Ȃ��Ă���A�f�M��̗L�p�����m�F�ł����B �������ڊT�v �@�Z��ɂ��āi�����ʐρA�������A��d�T�b�V�E���w�K���X�̑��̗L���Ȃǁj �A�Ɠd���i���ɂ��āi�e���r�E�①�ɁE�G�A�R���A�Ɩ����̎g�p�A�ȃG�l�s���j �B�����ɂ��āi�~�ƉĂ̓����A�����₨���̎g�p�Ɋւ��ȃG�l�s���j �C�R�����E�����ɂ��āi�R�����̎�ޒ����Ɋւ���ȃG�l�s���j �D�ԗ��ɂ��āi�����ԓ��̎g�p�A�r�C�ʁA���R��A�N�ԑ��s�����A�ȃG�l�s���j �E �g�[�@��ɂ��āi�ۗL�A�g�p�j �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���_���ȁA�H�i���X�팸�Ɏ����鏬���X�ܓ��ɂ�����[�����������{ ���{�́u�H�i���X�v�͔N�Ԗ�646���g���i����27�N�x���v�j�������Ă���A���̂�����357���g�����H�i�Y�Ƃ��甭�������Ɛ��v����Ă���B �H�i�Y�Ƃ���̐H�i���X�ɂ͏������Ǝ҂���̔p�����������x�܂܂�Ă���A���ȂƂ��āA�S���̏����X�ܓ��ɂĐϋɓI�ɐH�i���X�팸�̂��߂̌[���������s�����Ƃ𐄐i���Ă���B ����A����30�N10����H�i���X�팸�̌[�����ԂƂ��āA�S���e�n�̋��͂ł���e�����X�ܓ��ɂ����āA�|�X�^�[���ɂ��[�����������{�B�Ȃ��A�[����@�ɂ��ẮA���ȂɂČ��\���Ă���[�����ނ̊��p�ȊO�ɁA��ƓƎ��̌[����@���ɂ������g�����{����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���A1.5�����ʕ������F �C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�́A�؍��̐m��ɂ����鑍���1.5�����ʕ��̐���Ҍ����v����̑������B ����ɂ�菳�F���ꂽ����2018�N12���Ƀ|�[�����h�ŊJ�Â���鍑�A�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�j��24�����c�iCOP24�j�ɒ�o����B���́A�ɒ[�C�ہA�C�ʏ㏸�A�k�ɂ̊C�X���������ł�1���㏸�̉e��������Ă��錻�݁A�Љ�̑S�̈�ō��ꂩ��̉��v���}���ł���Ƃ��A�p������̓w�͖ڕW�ł���1.5���ڕW�̗��_���������Ă���B 2100�N�ɂ����āA2���ڕW�ɔ�ׁA�C�ʏ㏸��10�p�Ⴍ�A�ċG�ɖk�ɊC�����X�ƂȂ�\���́u10�N��1��v�ɑ��u1���I��1��v�A�T���S�ʂ́u�قƂ�ǑS�Łv�ɑ��u70�`90%�̏����v�ł���B1.5���ڕW�̒B���͎����\�ȎЉ�̎����ƕs���ł���B�{���́AIPCC�̑�6���]���̍ŏ��̓��ʕ��ƂȂ�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����ȁAIPCC�u1.5�����ʕ��v��SPM�T�v�i����t�j�����\ ���Ȃ́A�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�u1.5�����ʕ��v�́u����Ҍ����v��iSPM�j�v�����\�����B2015�N�̍��A�C��ϓ��g�g����������c�iCOP21�j�ɂ����ē��ʕ��̒���������A2016�N10���ȍ~�A�����M�҂̕�W�A��\���M�҉�E���ƃ��r���[�Ȃǂ��J��Ԃ��s���A2018�N10��1������6���ɂ����Ċ؍��ŊJ�Â��ꂽIPCC��48��ɂ����ē����ʕ��̖{�҂��������ASPM�����F���ꂽ�B���YSPM�́A4�̃Z�N�V�����ō\������Ă���B �@1.5���̒n�����g���̗��� �@�\�������C��ϓ��E���ݓI�ȉe���y�ъ֘A���郊�X�N �@1.5���̒n�����g���ɐ�������r�o�o�H�ƃV�X�e���̈ڍs �@�����\�ȊJ���y�ѕn���o�łւ̓w�͂̕����ɂ����鐢�E�I�ȑΉ��̋��� �����IPCC����i��49��j��2019�N5���ɋ��s�ŊJ�Â����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����ȁA���z�������A�Z�X�^�u�����̏��ȏ�v���� ���Ȃ̗L���Ҍ�����́A����܂őΏۊO���������z�����d�ɂ����e���]���i�A�Z�X�����g�j�����邱�Ƃő�ň�v�����B�����ǂ͑����␅���A�n�ՂȂǂ̍��ڂ��Ƃɑz�肳�����e�����B ���A�Z�X�̕]�����ڂƂ��Đݒ肷���ł̍l�������������B�ΏۂƂȂ锭�d���̋K�͂ȂNj�̓I�ȗv���ɂ��ẮA�n�������̂���߂���e���]�����ȏ���x�[�X�Ɍ�����i�߂�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցA2018�`2023�N�ɍł���������Đ��\�G�l���M�[�͐V�^�o�C�I�G�l���M�[�Ɨ\�� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A�Đ��\�G�l���M�[�s��Ɋւ��镪�͋y�ї\���\���A2018�N����2023�N�ɂ����čăG�l�̒��ŐV�^�o�C�I�G�l���M�[�i�d��ؒY���̍ݗ��^�o�C�I�}�X�ȊO�j�̐������ł��������Ƃ̌��ʂ����������B 2017�N�ɂ́A�M�y�щ^�A����ł̕��y�g���w�i�ɍăG�l����ʑS�̖̂���V�^�o�C�I�G�l���M�[����߂��Ƃ����B IEA�ɂ��ƁA�ăG�l�S�̂��d�͕���𒆐S�ɐ����������A2017�N�͔��d�����ʂ��ߋ��ō���178�M�K���b�g�ɒB���A���E�̔��d�����ʂɐ�߂銄�������߂�3����2�����B2023�N�ɂ͍ăG�l�����E�̃G�l���M�[����ʑ�������4�������d�ʑS�̖̂�3����1���߂錩�ʂ��ł���BIEA�́A�C��ڕW����B������ɂ́A�����3����ōăG�l�̕��y������������K�v������ƕ��Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���f���}�[�N�A��C�ƋC��ւ̈��e���̂Ȃ����ɂȂ��̍��� �f���}�[�N�́A����ȑ�C�ƈ��肵���C�����������38�̋�̓I�Ȏ�g���������v��āu�����ɗD���������̂��߂̒c���v�����\�����B �����́A2050�N�܂łɋC������������Ƃ����ӗ~�I�ȖڕW���f���Ă���B�v��Ăł�2030�N�̋C��ڕW�B���ɓ�����Ȏ�g�Ƃ��āA 1�j2030�N�܂łɃK�\�����E�f�B�[�[���̐V�Ԕ̔���i�K�I�ɔp�~ 2�j2030�N�܂łɓs�s���̃o�X����̒Y�f�r�o�Ƒ�C�������[���ɂ��� 3�j�C��E�������̗ǂ��_�Ƃ̌������i 4�j�����̌��i���ɂ���s�s�̑�C���� 5�j�Y�ƂƏZ���̔r�o�팸 6�j�C�x�����O�ɂ��s�����N 7�j���X�тɂ�����Y�f��������Z�p�̌����J������B ���̑��A�R���K���ᔽ�̑D���̊Ď��A��r�o�Ԃ̒��Ԋ����A40���f���}�[�N�E�N���[�l�i��700���~�j�ɖ����Ȃ��d�C�����Ԃ̍���2�N�Ԃ̔�ېœ��̋�̍���������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2018/10�@]�@�@�� |
|
|
| ��TOKAI HD�A�݂�ȓd�͂Ǝ��{�Ɩ���g�ăG�l���Ƃ̐V��Аݗ��� TOKAI�z�[���f�B���O�X�́A�ăG�l�䗦�̍����d�͂��������A���Ђ̃u�����h���l�����߂Ă������߁A�V�d�̓x���`���[�݂̂�ȓd�͂Ǝ��{�Ɩ���g���s�������Ƃ\�����B ��̓I�ɂ́A�݂�ȓd�͂̑�O�Ҋ���������������ƂƂ��ɁA�ăG�l�䗦�̍������Ђ̓d�͂⓯�Ђ̃u���b�N�`�F�[�������p�����ăG�l���ƂŐV��Ђ�ݗ�����B 2019�N4�����ăG�l�d�͂̔̔���~�d�r�̔��E�����e�i���X�ȂNJ֘A�T�[�r�X���J�n����\��B ���Ђ́AFIT���x�������������z�����d�d�͂Ȃǂ��E�̔���i�߂Ă����B�ăG�l�̒n�Y�n�����f���Ƃ��āA�n��G�l���M�[�Ɛ����C���t���̐����E�^�c��S�����K�͂̒n�斧���^���Ƒ̂��\�z����B�܂��A�@�l�����T�[�r�X�u�n���RE100�̑S���W�J�v���B���ӎ��̍����@�l��Ɓi RE100������Ɠ��j�A�����́A�c�̌����ɍăG�l�䗦�̍����d�͂����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�~�^�A�ăG�l�R���d�C�ɐ�ւ����Ј��ƉƑ��Ɂu���ݓd�蓖�v�x�� �A�~�^�́A�Ј��₻�̉Ƒ�������̐����ł��A�����\�Љ��ڎw���s���ł�������\�z���邽�߁A2018�N7���ɁA�Ј��Ƃ��̉Ƒ��̎����ΏۂɍĐ��\�G�l���M�[�R���̓d�C�ւ̐�ւ��𑣐i����V�����蓖���x�u���ݓd�蓖�v��ݗ������B �܂��A8�����A�p������100�����T�C�N�����Ƃ��s���������А������Ǝ��ЃI�t�B�X�ɂ��āA�݂�ȓd�͂�����ăG�l�R���䗦�̍����d�͂ɐ�ւ���Ɣ��\�����B �u���ݓd�蓖�v�i�����炵���݂炢�̂��߂̓d�͎蓖�j�́A�O���[�v���Ј���Ƒ��̎���ŁA�d�͌_����ăG�l�R���䗦�̍����w��d�͉�Ђɐ�ւ����ꍇ�A�����蓖���x������Ƃ������́B�x���z�́A����1���т�����200�~�i2,400�~�^�N�j�B �w��d�͉�Ђ́A�݂�ȓd�́A���R�d�͂�2�ЁB�Ȃ��A���̎w��d�͉�Ђ͔N��1�x�A�lj��〈�������s����\�肾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IoT�Ńf�[�^���W�A�H����ȃG�l�E���x���O�H�d�H���T�[�r�X�X�^�[�g �O�H�d�H�Ƃ́A�Ǝ���AI�EIoT�Z�p�����p�����H������G�l���M�[�\�����[�V�����T�[�r�X�̒��J�n���A�O�H�����p���[�V�X�e���Y�̍����H��ւ̓W�J���J�n�����Ɣ��\�����B ������ꂽ�\�����[�V�����T�[�r�X�́A��s���Ď��،����ɓ��������O�H�d�H�q��G���W���̖{�ЍH��œ���ꂽ���ʂf�������H������p�b�P�[�W�B����̓G�l���M�[�̗L�����p�ƃ��m�n��̃m�E�n�E��Z�������A�H��Ǘ��̍��x��������������̂��B IoT�c�[���i�H��̊e���ɐݒu���ꂽ�A�ݔ��ғ��f�[�^���W�V�X�e���j�ɂ��擾�����ݔ��ғ��f�[�^�ɂ��ƂÂ��A���Y����G�l���M�[����������鉻���A������Z��������KPI�i�d�v�Ɛѕ]���w�W�j�Ƃ��Đݒ肵���u�G�i�W�[�N���E�h�X�R�A�v�ŁA�H��p�t�H�[�}���X��]������B �����AI�Z�p�ŁA�ߋ��f�[�^���珫����KPI�ω���\�����A�\�h�ۑS�⑀�ƍœK���ȂǍH��Ǘ������x�����A�Ő�[�̒�R�X�g�E�ȃG�l�H���ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�A�C�ۗ\��r�W�l�X�Q���֏��i�̔���s���\���A���d�\���Ȃǂ� ���K�X�́A���Ђ̋C�ۗ\��m���C�ۗ\����s���T�[�r�X�J�n�Ɍ����A�K�X��ЂƂ��ď��߂āA�C�ے��̒�߂�C�ۗ\��Ɩ��̋����擾�����B ���Ђł́A�G�l���M�[���Ƃɂ����ċC�ۏ������p���Ă����Z�p��m�E�n�E���������A����A�C������˗ʓ��A�C�ۗ\����K�v�Ƃ���ڋq�Ǝ���ςݏd�ˁA�����I�ɂ͗L���T�[�r�X�̒�ڎw���B ���Ђ̋C�ۗ\���̓����Ƃ��ẮA�\���Ώےn���2.2�L�����[�g���l���Ƃ��������ȃ��b�V���ɋ���ăf�[�^��͂��s�����ƂŒn�`�e�������l���������ߍׂ₩�ȗ\�����s�����Ƃ��ł��邱�ƁA�ϑ��f�[�^�Ɋ�Â��@�B�w�K���g�ݍ��킹�č����x����}���Ă��邱�Ƃ���������B �����Ƃ�T�[�r�X�Ƃ͋C����V�C�ɂ���ċq���┄����ς��A�_�Ƃ⋙�Ƃ͎��n�⋙�l�ʼne������ȂǁA�C�ۃr�W�l�X�̒��ړx�͍��܂��Ă���B�C�ۗ\��T�[�r�X�̒ɂ͂��������w�i������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���k���d�͂ȂǂR�ЁA������ʌv�V�X�e���Ŏ��؊J�n �k���d�͂́A���m�K�X���[�^�[�Ɠ��{�G���N�g���j�N�X�E�T�[�r�X�̂R�ЂŁA�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j�̒ʐM�V�X�e�������p�������؎������J�n����Ɣ��\�����B �K�X���u���j�ƒ��ԏ�\��Ǘ��̂Q�̃T�[�r�X��ΏۂɁA�k���d�͂��ۗL����ʐM�V�X�e���Ƃ̃f�[�^�A�g�△���@�̒ʐM�Ȃǂ����ꂼ��m�F����B�K�X���[�^�[�Ȃnjڋq�̎��@���g�������͑S���ł����߂ĂƂ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����O�@�P��ŋƏ��g�[�^�R���i�ȂǂR�� ���J�H�ƎO�H�P�~�J���A�R���i�̂R�Ђ͏W���Z���ZEH�i�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j���ɓK�����@������i�������B �q�[�g�|���v���������1��̎��O�@�ɃG�A�R���Ə��g�[���Ȃ������̂��B �q�[�g�|���v�͏ȃG�l���M�[���\���������߁A�V���i�͂P�V�[�Y���̏��g�[�ɕK�v�ȉ^�]��p���d�M�������̏��g�[�ɔ�ׂ�75���팸�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������l�ɔ������Ȃ������h�A��Ẩ�ЊJ�� ��ʓI�Ȏ����h�A�̃Z���T�[�́A�ԊO���Ȃǂ����̃G���A�ɏƎ˂��A�ߕt���l�ɓ������Ĕ��˂��Ă���g���L���b�`���ĊJ����B�����A�G���A���ɐl������h�A�̑O�����邾���ł��������邽�߁A�s�v�ȊJ��������B �J�������Z���T�[�́A���ʂȊJ���������邽�߁A�]���̃Z���T�[�ɉ����ď��^�J�����𓋍ځB�h�A�ɋߕt���l�̕��������⑬�x����͂��A�������ɓ���l���ǂ����肷�邱�ƂŁA�h�A�̑O�����邾���̐l�ɂ͊J���Ȃ��d�g�݂��\�ɂ����B�h�A�Ɍ������Ă���l�̑��x�𐳊m�ɔF���ł��邱�Ƃ���A���p�҂̕����X�s�[�h�ɍ��킹�čœK�ȃ^�C�~���O�Ńh�A���J���邽�߁A���p�҂ւ̃X�g���X�����点��Ƃ����B ���Ђɂ��ƁA�V�����Z���T�[�Ŗ��ʂȊJ����3���}�����邽�߁A�����̗�g�[���������サ�A�d�͏���ʂ��3���팸�ł���Ƃ����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����ȁA�N�[���V�F�A�Ɋւ���A���P�[�g�����̌��ʂ����\ ���̒����́A���Ȃ́u�n���̂ƂȂ����N�[���V�F�A���i���f�����Ɓi�����s��������{���n��j�v�̈�Ƃ��čs��ꂽ���́B����30�N8��1���`8��3���̊ԁA5�̃N�[���V�F�A�X�|�b�g�i�S�ݓX�A���Z�@�ցA�����{�ݓ��j�̗��p�҂ɒ����[��z�z���A6�̐ݖ�ɂ��ĒP���W�v���s�����B ���ʁA �@1)�N�[���V�F�A��m���Ă������2����� �@2)�N�[���V�F�A�ɌW�郂�f���I��g���u���Ђ��ׂ��A���ׂ��v�Ɖ������͖�9������ �@3)�N�[���V�F�A�̎�g���S���ɍL�������ꍇ�u���ЎQ���������A�Q���������v�Ɖ������͖�7���ł��邱�Ƃ����������B�܂��A �@4)�N�[���V�F�A�X�|�b�g���u�����Ƒ��₷�ׂ��i 47%�j�v �@5)�I���p��2020�������E�}���\�����Z���ւ̑Ή��Ƃ��āu�ƂĂ��ǂ��A�ǂ��i 91%�j�v�Ƃ������ʂ������A �@6)�N�[���V�F�A�̎��m�������ƍs���ׂ��Ƃ̐��Ȃǂ����Ă���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����z�����d���Ƃ��K���ǂ������m�F�ł���`�F�b�N�V�[�gJPEA�����J ���z�����d����iJPEA�j�́A���z�����d���Ƃ��K�ɍs���Ă��邩�ǂ������ȈՂɕ]���E�m�F�ł���u�`�F�b�N�V�[�g�v���쐬�����J�����B ���`�F�b�N�V�[�g�́A�u���z�����d���Ƃ̕]���K�C�h�v�i���z�����d���Ƃ̕]���K�C�h����ψ����j���Q�l�ɍ쐬���ꂽ���̂ŁA���z�����d���Ƃɂ���������̑��������E�����̏����Ƃ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B ���`�F�b�N�V�[�g�́A�u�ݒu�ꏊ�E�@�ߎ葱�Ȃǁv�u�y�E�\�����v�u���d�ݔ��v��3�̃W�������ŁA���X�g�̍��ڂɉ����ă`�F�b�N�ł���悤�\������Ă���B ����ɁA�u�`���Â����Ă���W���̐ݒu�v��u�~�n�̉J�����H�ɕ�������ɂ͐��H�Ǘ��҂̋����K�v�ł��邱�Ɓv�ȂǁA�悭�݂����������Ǝ҂Ɛ��Ƃ̑Θb�`���ŏЉ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ѐ��w�~�M���p�̕��y�Ɍ��������Ɛ헪����̋K���ɘa��� ���s�́A�ѐ��w�~�M���p�Z�p�̕��y�Ɍ����āA���t�{�ɑ��āA���Ɛ헪����ɂ�����V���ȓ���[�u�ɌW���Ă��s�����B �Y�w���A�g�ɂ�莝���\�Ȓn�������p�Z�p�Ƃ��đѐ��w�~�M���p�Z�p���J������A���s��ɂ����Ď����s���A�ȃG�l���M�[�A��CO2���ʓ��ƒn�Ւ����h�~���ʂ��m�F���ꂽ���Ƃ���A���Y�Z�p�����ł������[�u�����߂�B ���s��́A��O�y�ѐ��̍��x�o�ϐ������ɒn�����̉ߏ�ȋ��ݏグ�ɂ��n�Ւ������A���É����������Ȃ��A�n�����̍̎�K�����~����Ă���B���w�k���̍ĊJ���n��ŁA�n�������g�[�Ɋ��p������؎������s�����Ƃ���A�R�T���̃G�l���M�[�팸���ʂ��邱�Ƃ������ꂽ�B ��[�ʼn��x�̏オ�����n�������܂��n���ɖ߂��A�~�M���ꂽ�n������~�̒g�[�Ɋ��p������̂ŁA�M���O���ɔr�o���Ȃ����߁A�q�[�g�A�C�����h���ۂ̊ɘa�ɂ��v���ł���B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| ���Ɩ��p�q�[�g�|���v�����@�̕ێ�E�_���ɂ���(���)���{�Ⓚ�H�Ɖ� �Ɩ��p�q�[�g�|���v�����@�́A�Ɩ��p�����ɂ�������ʁA�����A���Ȃljq���p�r�ɗp���鋋���ݔ��̎�v�ȋ@��Ƃ��Ďg�p����Ă���B �����悭�A�������S���Ďg�p���邽�߂ɂ͒���I�ȓ_���ƕ��i�����Ȃǂ��s���ƂȂ�B �ˑR�̌̏�ɂ�肨�����łȂ��Ȃ邱�Ƃ�A�����̈����^�]�𑱂��邱�ƂŖ��ʂȏo������ނ��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�w�ێ�E�_���K�C�h���C���x���쐬�����B���̃K�C�h���C���́A�Ɩ��p�q�[�g�|���v�����@��ΏۂƂ��āA�K�v�ȁg�ێ�E�_���̓��e�Ǝ����h�̕W���I�Ȏw�W���܂Ƃ߂��B �p���t���b�g�̓��e�́A�ێ�E�_���̗L�����ɂ��āA�Ɩ��p�q�[�g�|���v�����@�z�njn���}��\��A�Ɩ��p�q�[�g�|���v�����@�A��v���i�̕ێ�E�_���K�C�h���C���A�֘A�@�K�E��ɂ��ĂȂǁB �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����Ɨp���z���A2022�N�x�ɂ�������艿�i�����ց^�G�l�������j �����G�l���M�[���͗L���҉�ŁA���Ɨp���z�����d��FIT�ɂ��āA�������2022�N�x�ɂ�������艿�i�����݂̔��z�ɂ�����j���������B �Z��p��2025�N�x�ȍ~�A���s����݂�11�~���x�ɗ}����B ����̈�Ƃ��Č��ݏo�͂Q��L�����b�g�ȏ�̃��K�\�[���[�Ɍ��肵�Ă�����D���̋敪��P�p�B���Ɨp�S�Ă�ΏۂƂ��邱�Ƃ�����Ɍ�����[�߂�B �����̑��������G�l���M�[������́u�Đ��\�G�l���M�[��ʓ����E������d�̓l�b�g���[�N���ψ���v�ŃG�l���������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�������u���z���̎��R���C�v�̂��߂̕����W���f�[�^�x�[�X�v�̌��\ �����͐���ɕK�v�ƂȂ镽�ϕ����W���́A���R���C�E�ʕ��v��ɂ����āA�����ɓ������镗�ʂ��Z�肷�邽�߂̋��E�����Ƃ��āA���R���C�E�ʕ��̉\���̌����Ɏn�܂��{�v��i�K����A�J����(���A���R���C���A�r�C����)�A�ʋC�o�H�̐v�i�K�܂ł̌����Ɍ������Ȃ��B �������A���R���C�E�ʕ��̐v�Ɋ��p�ł���悤�ȁA���l�Ȍ����A���ӏɑΉ��������ϕ����W���f�[�^�̐����͏\���Ƃ͌�����ɂ���܂����B�����ŁA���R���C�E�ʕ��v�Ɏ����镗���W���f�[�^�x�[�X�\�z��ڕW�ɁA���_�I�����A�����̌�������A�n���I�ȕ������������{���Ă����Ƃ���ł��B�{�����́A�����̌����ɂ�萮���������ϕ����W���f�[�^���Ƃ�܂Ƃ߂��B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ������27�i2015�j�N�x�������ʃK�X�r�o�ʂ̏W�v���ʂ̌��\ (1)���莖�Ə��r�o�ҕ��ƎҐ��iH27�N�x�j12,432���ƎҁiH26�N�x�j12,521���Ǝ� �@�@�@�r�o�ʂ̍��v�iH27�N�x�j6��6,244��tCO2 �iH26�N�x�j6��8,086��tCO2 (2)����A���r�o�ҕ��ƎҐ��iH27�N�x�j1,353���ƎҁiH26�N�x�j1,352���Ǝ� �@�@�@�r�o�ʂ̍��v�iH27�N�x�j3,216��tCO2 �iH26�N�x�j3,208��tCO2 |
|
|
| ���@�@[�@2018/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���T�v���C�`�F�[���r�o�ʁq�X�R�[�v3�r�o�ʁr�d���̓����L�܂�B ���E���E�Y�f�Ɍ����傫���ǂ��Ȃ��ASBT�i��Ɣ�2���ڕW�j��RE100�i100���ăG�l�����j�ɐϋɓI�Ɏ��g�ފ�Ƃ������Ă���B����ŁA�T�v���C�`�F�[���r�o�ʂɂ��ẮA���ЂŒ��ڔr�o����X�R�[�v1�A2�ɉ����A�X�R�[�v3�����ڂ����悤�ɂȂ��Ă���B �T�v���C�`�F�[���r�o�ʂƂ͌������B�A�����A�o���A�ʋȂǂ̎��Ǝ҂̑g�D�����S�̂�ΏۂƂ����������ʃK�X�r�o�ʂ������A��Ƃ̊��o�c�w�W��@�֓����Ƃ̎��⍀�ڂƂ��Ďg�p����铮����������B �T�v���C�`�F�[���r�o�ʂ́A�X�R�[�v1�i���ڔr�o�ʁF���Ђ̍H��E�I�t�B�X�E�ԗ��Ȃǁj�ƃX�R�[�v2�i�G�l���M�[�N���Ԑڔr�o�ʁF�d�͂Ȃǎ��Ђŏ�����G�l���M�[�j�A�����ăX�R�[�v3�i���̑��̊Ԑڔr�o�ʁj����\�������B ����܂ŁA�X�R�[�v1�A2�ɂ�����r�o�ʂ̎Z���팸�w�͂͐i��ł����B����ŁA�ߔN�A�X�R�[�v3���܂ފ�Ɗ����̏㗬���牺���Ɋւ����e�̎Z����d�����铮�����L�����Ă��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��JFE�̐V�d�́A�ăG�l100���d�C�̃v������̔��֎Y�p�Ŋ����� �V�d�͂̃A�[�o���G�i�W�[�́A���ӎ��̍�����Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��A�V���ɍĐ��\�G�l���M�[100���̓d�̓��j���[�̔̔����J�n�����B ���̃v�����́A�Đ��\�G�l���M�[�䗦��100���ŁACO2�r�o�W�����[���̓d�͂����v�Ƃɒ�����̂ŁA���i�����łȂ������l���d�������Ƃ�c�̂�Ώۂɒ����B ���Ђ̑S���B�d�͗ʂ̂��悻40���͑��z���E���́E�o�C�I�}�X�i��āA�p�����j�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[���d�Řd���Ă���B ���Ђ�����d�C�́A�ڋq���Ƃɗ������j���[���قȂ�B��̓I�ɂ́A�ڋq�̓d�͎g�p�f�[�^�����ƂɌ��ϋ��z�����B���Ђ̓d���\����A����ʂ��Ĉ��ʂ��g�p����ڋq�����A�s�[�N�̎g�p�d�͗ʂɑ��Ďg�p�ʂ����Ȃ��ڋq�ɑ��āA��芄���ȗ����œd�C�����B�܂��A�p�����������Z�b�g�����d�͔̔��u�n�d���v�Ȃǂ���Ă��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����c�}�d�S�A�d�́{�~�d�r�����œd�Ԃ𑖍s�����邱�Ƃɐ��� ���c�}�d�S�́A��K�͒�d�������ɒ�Ԃ�����Ԃ��Ŋ��w�܂ňړ������邽�߁A�d�͒������u�̒~�d�r�݂̂̓d�͂Ŏ��͑��s���錟���s���A����ɐ��������Ɣ��\�����B ���̌��́A��K�͒�d�̔����ɂ���X�؏㌴�w�`�~���u�w�i���X���n����ԁj�Œ�Ԃ�����ԓ��̏�q���A���S�����₩�ɍŊ��w�ō~�Ԃł���悤�A�����u�̒~�d�r�݂̂̓d�͂Ŏ��͑��s���邽�߂ɍs�������́B ��̓I�ɂ́A�I�d��A��Ԃ��e�w��w�Ԃ̌��z�ӏ��Ɉ�U��Ԃ�������A�N�������Ď��w�܂Ŏ��͑��s���������B�����ł́A����}�s���A���ɍs����1�����𑖍s���A�v8��̋N���A��~�����{�����B ����Ԃɂ͓��Ѝő��35�p�[�~���i��F1�L�����[�g����35���[�g���������ω�������z�̒P�ʁj�̌��z�����邪�A����̌��،��ʂł́A���ɁA���̌��z��Œ�Ԃ�������Ԃ��~�d�r�݂̂̓d�͂Ŏ��͑��s�i�N���j�\�ł��邱�Ƃ��m�F�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����dPG�A�d�͐��ő��IoT�^�p�i�\�j�b�N�ƘA�g�� �����d�̓p���[�O���b�h�iPG�j�Ǝq��Ђ̃G�i�W�[�Q�[�g�E�F�C�i�����s�`��A�є��V�В��j �A�p�i�\�j�b�N��19���A�Z�����IoT�i���m�̃C���^�[�l�b�g�j�T�[�r�X�Ɋւ��鋦�c���J�n�����Ɣ��\�����B�G�i�W�[�Q�[�g�E�F�C�́u�d�̓Z���T�[�v�ƃp�i�\�j�b�N�̍����d�͐��ʐM�����uHD-PLC�v��g�ݍ��킹���u�V�f�o�C�X�v���J�����A�N���Ɏ��Ɖ�����l�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���g�ѓd�b����g�p�̃X�}�[�g���[�^�[�x�m�ʁA��������T�[�r�X �x�m�ʂ́A�ƒ��I�t�B�X�Ȃǂ̓d�͎g�p�ʂ��������W����u�X�}�[�g���[�^�[�v�̃T�[�r�X��8���������Ɣ��\�����B���̂����Ɍg�ѓd�b�����p���邱�ƂŁA�e���[�^�[�̃f�[�^���W�鑕�u��s�v�ɂ������߁A�Œ�P�䂩�瓱���ł���B �X�}�[�g���[�^�[�́A�ʐM�ɖ�����d�͐����g���ꍇ�͏W�u���K�v�ŁA���[�^�[�����Ȃ��ƃR�X�g���ɂȂ�̂��A�x�m�ʂ̃T�[�r�X�͐ݒu���[�^�[�����\��̋K�͂Ȃ犄���Ƃ����B��Ƀr����}���V�����Ȃǂňꊇ��d����Ǘ���Ђł̓�����z�肷��B������p100���~����ŁA���z7���~����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �� LIXIL�ASDGs�ڕW�u���S�Ȑ��ƃg�C���v�ŐV���ƃ��j�Z�t�ƘA�g ���j�Z�t��LIXIL�́A�u�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�v�Ōf����ڕW�u���S�Ȑ��ƃg�C���𐢊E���Ɂv�̎����Ɍ����A���E�̎q�ǂ������̉q���������P���邽�߁A�V�����A�v���[�`�Ŏ��g�ރO���[�o���p�[�g�i�[�V�b�v����������B �uMake a Splash�I�݂�ȂɃg�C�����v�Ɩ��t����ꂽ���̃p�[�g�i�[�V�b�v�́A���j�Z�t��LIXIL�����ꂼ��̋��݂��������Ȃ���ASDGs�̃^�[�Q�b�g�̂ЂƂu2030�N�܂łɁA���ׂĂ̐l�тƂ́A�K�������ȉ����{�݁E�q���{�݂ւ̃A�N�Z�X��B�����A��O�ł̔r�����Ȃ����B��������я����A�Ȃ�тɐƎ�ȗ���ɂ���l�тƂ̃j�[�Y�ɓ��ɒ��ӂ��v�̎�����ڎw�����̂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ƒ납�玩�R�ɔ��d�A�]��V�F�A�\�Ɂ^�����d�͂����H�T�[�r�X�J�n�� �����d�͂́A�ڋq�Q���^�̓d�͎���T�[�r�X�u���ꂩ��f���L�v���n�߂�Ɣ��\�����B�X�̉ƒ�Ȃǂ����z�����d�ł������d�C��ʂ̎��ԂɎg������A����ĕ�炷�Ƒ��Ƃ̃V�F�A�⒆���d�͂ւ̔��d�Ƃ�����������B���ۂ̃T�[�r�X�J�n������2019�N11���̗\��B����ɐ旧���A���N8�������p�̃A�v���P�[�V�����△���[�d����g���āA�u���ꂩ��f���L�v���^���̌��ł���T�[�r�X���n�߂�B �����d�͂�2019�N11���ȍ~�AFIT�i�Đ��\�G�l���M�[�Œ艿�i���搧�x�j�ɂ��ƒ�p���z���Ȃǂ̗]��d�͔��������Ԃ������I�����邱�Ƃ��������A�ڋq���]�����d�C�����R�Ɏ���ł���T�[�r�X�̑n�o��ڎw���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������I�����s�b�N�A�uCO2�r�o���̊�t�v��t�J�n �����s�́A2020�N�ɊJ�Â���铌���I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���i����2020���j�Ɋ֘A����J�[�{���I�t�Z�b�g�̋�̓I���g�݂Ƃ��āACO2�r�o���̊�t����J�Â�2�N�O�ƂȂ�A2018�N7��24������t���Ă���B ���̎��g�݂́A�����s�L���b�v���g���[�h���x�̑Ώێ��Ǝ҂ȂǂցA�ۗL����N���W�b�g�̋��͂��Ăъ|������́B���ꂽ�N���W�b�g�́A�s�ɂ��u�����[���J�[�{��4�f�C�Yin 2020�v�ƁA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���Z���g�D�ψ���ɂ��u����2020���̃J�[�{���I�t�Z�b�g�v�ɏ[������B ����2020���̊J��E��̌v4���ԕ��A�s���Ŕr�o����邷�ׂĂ�CO2���I�t�Z�b�g���ă[���ɂ���B4���ԕ��̓s���SCO2�r�o�ʂ̎��Z�͖�72���g���i1���������18���g���~4���ԁj���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ǔ��^���z�����d�~���d���v�ő��z���G�l���M�[��18.8���𐅑f�ɕϊ� �{���w�ȂǂŌ����J����i�߂Ă��鍂�����W���^���z�d�r�i�o��470W�j��蓾��ꂽ�d�͂Ő���d�C�������A1�����ςő��z���G�l���M�[��18.8%�𐅑f�G�l���M�[�ɕϊ����邱�Ƃɐ��������Ɣ��\�����B �W���^���z�d�r����1���̑����˗ʂƐ����������f�G�l���M�[�ʂ��瑾�z���f�G�l���M�[�ϊ��������Z�o�����B ���̃V�X�e���ł́A�V�^�������W���^���z�d�r�Ɍő̍����q����p�������d�u�ƁA���z�d�r���瓾����d�͂𐅓d�u�Ɍ����悭��������d�͕ϊ����u�iDC�^DC�R���o�[�^�j��ڑ��B���ۂ̑��z������1����ʂ��č�����������I�ɐ��f�����邱�Ƃɐ��������B �d���E�d���𐧌䂵�āA���z�d�r���琅�d�u�ւ̍����G�l���M�[�`�B�����i90.0���j�����������B�����x�̒ǔ��ˑ�Ŕ��d����27.2����B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�A���d�͉�Ђ́u���߂��c�Ɓv���K��������j�������J�n �o�ώY�Ƒ�b�́A���d�͉�Ђɂ��u��߂��c�Ɓv���K��������j�ɂ��Č��y�����B �d�C�̎g�p�҂��A���d�͉�Ёi����ʓd�C���Ǝҁj����V�d�͂Ɍ_�����ւ���i�X�C�b�`���O�j������ӎv�����������ɁA2�J�����x�̃X�C�b�`���O���Ԃ�����B���̊��Ԃ𗘗p���āA�ڋq��D��ꂽ���d�͉�Ђ��V�d�͂ɂ͑R�ł��Ȃ������������i���Ă���ȂǁA�u��߂��c�Ɓv���s�����Ⴊ�����Ǝw�E����Ă���B����ŁA���̎�߂��c�Ƃւ̑Ή��ւ̌������J�n�����B ��������������ɂ��ċ���ʓd�C���Ǝ҂����d�R�X�g�̒Ⴂ���d���̑唼��ۗL���Ă���Ƃ����_�A�����ĐV�d�͂��\���ȃR�X�g�����͂��m�ۂł��Ă��Ȃ��Ƃ�������ɂ����鍷�ʓI�ȗ����Ƃ����̂́A�����ȋ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ȃǂ��܂��܂ȋc�_�����Ă���B�ł��邾�������A�������������������悤�ɂ������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�E�Y�f���m���ő��݊����v���g�������ڕW�B�����{�L���ҍ���� ���{��3���A�n�����g����̃p������Ōf�����ڕW�B���Ɍ����A�����헪����������L���ҍ��k��̏�����J�����B �u2050�N�ɉ������ʃK�X80�����v�Ƃ̖ڕW���m���ɒB�����A�o�ϐ����ɂ��Ȃ����̓I������c�_���A2018�N�x���ɒ��܂Ƃ߂�B �w���o���҂�o�ϊE�Ȃǂ���I�ꂽ�ψ����A����J�ŋc�_�����B�����ɂ��ƁA�����̈ψ������g���̌����̓�_���Y�f��啝�Ɍ��炷�u�E�Y�f�v�̎p���m�Ɏ����ׂ����Ƌ����B �����I�ȉ��g����́A���Ȃ͍Đ��\�G�l���M�[�g��ȂǍ���������ɐi�߂����l�������A�o�ώY�ƏȂ͍������̔��d�ݔ��̗A�o�Ȃǂ�ʂ��ĊC�O�ō팸���������A���{�̖ڕW�B���ɏ[�Ă�d�g�݂��d������B �����헪��2020�N�܂łɍ��A�ɒ�o���邱�ƂɂȂ��Ă���B��i7�J���iG7�j�ł͓��{�ƃC�^���A����������o�B �o�T�uSankeiBiz�v |
|
|
| �����Ȃ��uSDGs���p�K�C�h�v���s������ƌ����Ƀ����b�g�⎖��ȂǏЉ� ���Ȃ́A�����K�͂̊�ƁE���ƎҌ����ɁA�u�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�v�Ɏ��g�ވӋ`�Ƌ�̓I�Ȏ��g�݂̐i�ߕ����Љ�����p�K�C�h���쐬�������̃K�C�h�́ASDGs�ɂ��Ă���܂œ��i�̎��g�݂��s���Ă��Ȃ��A���邢��SDGs�ɊS�������������g�݂��n�߂Ă݂悤�ƍl���Ă���E�����⊈���͈̔͂������K�͂̎��Ǝ҂Ȃǂ���ȑΏۂƂ������́B���̂��߁A�n��o�ς��x���A�n��̊��͂̒��S�ƂȂ��Ċ������Ă���l�B�̖ڐ��ɗ����A�g���₷�����e�ō\������Ă���B �Ȃ��ASDGs�ɂ�17�̃S�[���i�ڕW�j�����邪�A���K�C�h�̓��e�́A���ۑS�ƊW�̐[���S�[������g�݂𒆐S�Ƃ��Ă���B�Ⴆ�A4�i����j�A6�i���E�q���j�A7�i�G�l���M�[�j�A11�i�s�s�j�A12�i�����\�Ȑ��Y�Ə���j�A13�i�C��ϓ��j�A14�i�C�m�j�A15�i���搶�Ԍn�E�������l���j�A17�i���{��i�E�p�[�g�i�[�V�b�v�j�ɂ��������̂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăG�l���d���ƂɐV�`���u�p����p�Ɋւ���v10kW�������z���͕s�v �o�ώY�ƏȂ́A�Œ艿�i���搧�x�iFIT���x�j�ɂ����āA����i�^�]��p�j�ɔp����p�Ɋւ��鍀�ڂ�lj����AFIT�F��������ׂĂ̍Đ��\�G�l���M�[���d���Ɓi10kW�����̑��z�����d�ݔ��������j�ɔp����p�Ɋւ�����`���������B FIT�F�莖�Ǝ҂ɑ��āA�^�]��p�̍ۂɁA�p����p�̕��Ăъ|���Ă���B FIT�F��������Ƃɂ��ẮA���d�ݔ��̐ݒu�ɗv������p�̕i�ݒu��p�j�ƁA�F�蔭�d�ݔ��̔N�Ԃ̉^�]�ɗv������p�̕i�^�]��p�j���s�����Ƃ��A�`���t�����Ă���B�p����p�Ɋւ��鍀�ڂ́A�^�]��p�̍��ڂɒlj����ꂽ�B �Đ��\�G�l���M�[����������I�ȓd���ƂȂ邽�߂ɂ́A���z�����d�̃p�l���p���ɌW�錜�O���͂��߁A�����̉ۑ�ɑ�������𒅎��ɍs�����Ƃ��d�v�ł���B���̂��߂ɁA���d�ݔ��̔p����p�i�P���E������p�j�̊m�ۂ����߂��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2018/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���n�Y�n���̐��f�z�e�����A�U���P���J�ƃL���O�X�J�C�t�����g�X�J�� �H�c��`�ɋߐڂ��A�����@�ւ��W�ς��鍑�ې헪���_�u�L���O�X�J�C�t�����g�v�ŁA�g�p�ς݃v���X�`�b�N�������ɐ��Y�������f�����p�������E���̃z�e���⌤�������J�Ƃ����B �n��z�^�́u���f�̒n�Y�n�����f���v�M����z�e���͎g�p�ς݃v���X�`�b�N�������ɂ������f�����p���A�d�C��M�̋�������̂́u���L���O�X�J�C�t�����g���}REI�z�e���v�i�T�K���āA�����ʐϖ�7500�������[�g���j�B�z�e���S�̖̂�3���̃G�l���M�[�ʂ𐅑f�Řd���v��ɂȂ��Ă���B ���f����������̂́A���a�d�H��莖�Ə��B2003�N����s���ʼn�������g�p�ς݃v���X�`�b�N�������ɃA�����j�A�̐����H���Ő��f�Y�B�g�߂ȋ������T���Ă����Ƃ���A����̃v���W�F�N�g�Ɍ��т����B�n���p�C�v���C���Ńz�e���~�n���ɂ����^�����f�R���d�r�ɐ��f�����������d����B �o�T�u�J�i�R���v |
|
|
| ���~�d�r�̎��v�͋}���A2030�N�̎s��K�͂�1.2���~�ȏ�ɕx�m�o�ϗ\�� �x�m�o�ς́A�ቿ�i���ɂ�胊�`�E���C�I���d�r�̗̍p����������d�͒����E���͕���ɂ����鐻�i�ʓd�r�̐��E�s�꒲�����s�����B 2030�N�̃O���[�o���s��K�͂́A2017�N��6.6�{��1��2585���~�܂Ŋg�傷��Ɨ\�����Ă���B �Đ��\�G�l���M�[�̑�ʓ����ɂ��d�͌n���̉^�p�ɂ����钲���͂̊m�ۂ�z�d�Ԃ̐������ۑ�ƂȂ��Ă���B�ۑ�̉�����i�Ƃ��ēd�͒����V�X�e�����L�]������Ă���A�n�����ł̎��g���������������A�Đ��\�G�l���M�[�̏o�͕ϓ����p�r�A���v�Ƒ��ł̃s�[�N�J�b�g�A�s�[�N�V�t�g�A�f�}���h���X�|���X�iDR�j���͂��߂Ƃ����G�l���M�[�T�[�r�X�p�d���p�r�ȂǁA���p�V�[�����L�����Ă����B ���i�ʂɂ݂�ƁA2017�N���т͉��d�r203���~�A���`�E���C�I���d�r413���~�ƂȂ����B��������z�����d�̎��Ə���g�����h�̊g���w�i�ɁA2030�N�ɂ̓��`�E���C�I���d�r��2453���~�Ɋg�傷��Ɨ\������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����d�Ղ���g�p�ʕ��́A�Z���T�[�Ńf�[�^���W�^���d�o�f�q��� �����d�̓p���[�O���b�h�q��Ђ̃G�i�W�[�Q�[�g�E�F�C�́A�d�̓Z���T�[�Ɛl�H�m�\�iAI�j�ɂ��@�핪���Z�p��p���ĉƓd�Ȃǂ̓d�C�̎g�p�ʂ��u�����鉻�v����T�[�r�X�E�C���[�W��{�ЃV���[���[���Ō��J�����B ���d�Ղɐڑ������Z���T�[�Ŏ��W�����d�͔g�`����A�G�A�R���A�①�ɁA�|���@�ȂnjX�̉Ɠd�̎g�p�́B���Z�҂̐�����c�����邱�ƂŁA�G�l���M�[�}�l�W�����g��x���E�����A���Q�ی��A��ÂȂǂ̐V�T�[�r�X�n�o�ɂȂ���B �C���t�H���e�B�X���J�������@�핪���Z�p�́A�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�A��a���r���O�A�哌�����Ȃǂ֒���Ă���B�����2020�N�x���߂ǂɁA100�����тɓ��Ђ̋@�핪���Z�p�����p�����Z���T�[�̓�����ڎw�����j�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��������ƁA���B�����̋������uGHG�̔r�o�팸���сv�ɘA�������� �I�����_�̑������w���[�J�[Royal DSM�iDSM�j�́A���Ђ̉������ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�팸�������ɘA��������A�V����10�����[���̃��{���r���O�E�N���W�b�g�E�t�@�V���e�B������������Ƃ\�����B ���{���r���O�E�N���W�b�g�E�t�@�V���e�B�́A���Z�@�ւ��萔�����������Ŋ�ƂɈ��̗^�M��^���A�ݕt�����s�����Z��@�BDSM�́A�����\���Ȑ��E�̎����ɍv�����邱�Ƃ��A���Ƃ̃R�A�o�����[�i��{�I���l�ρj�Ƃ��Čf���Ă���B �C��ϓ��ւ̎��g�݂ɂ�����������ɖ��m�ɂ��邽�߁ADSM�́A���̃N���W�b�g�E�t�@�V���e�B�̋�����GHG�̔r�o�팸���сA��̓I�ɂ͗ݐϓI��GHG�̌������P�A�G�l���M�[�����w�W�iEEI�j�̉��P�A�Đ��\�G�l���M�[����̓d�͗��p�̑��ʂƂ���3�̗v�f�ɘA�������邱�ƂƂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Đ��G�l�d�C��I��ōw���ł���������ɏW�܂�o�� �O�H�����A�d�̓x���`���[��Looop�A�����q��ЂȂǂ�4�Ђ́A�ƒ���Ƃ��Đ��\�G�l���M�[�ł������d�͂�����ł����Ս\�z��ڎw���f�W�^���O���b�h�ɏo�������B ����Ńf�W�^���O���b�h�ւ̏o����17�ЁA���o���z2��7000���~�ƂȂ����B���łɎQ�悵�Ă��铌���K�X�⋞�Z���ȂLjًƎ킪�A�g���A��Ƃ��Đ��G�l�d�C�B�ł���������Ɏ��g�ށB �f�W�^���O���b�h��2017�N10���ɐݗ��B�J�������d�͗Z�ʋZ�p�͓d�q���[���̂悤�ɓd�C��͂������ꏊ�ɑ�������A�Đ��G�l�d�C��I��ōw���ł����肷��B���Ђ͗Z�ʋZ�p�𓋍ڂ�����p���u��ݒu�����Z���r���Ȃǂ��l�b�g���[�N�����A�ƒ�ŗ]�������z���p�l���̓d�C����Ƃ��܂Ƃ߂Ē��B�ł��� ��Ղ�2019�N�t�ɊJ�݂���B�O�H�����͔��d��d�͔̔����ƁALooop�͍Đ��G�l�d�C�̔̔���G�l���M�[�Ǘ����Ƃ̃m�E�n�E����Չ^�c�Ɋ��p����B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| ���\�[���[�V�F�A�����O���Ƃ̉ۑ�������A�c�_�҂̃}�b�`���O�T�[�r�X�o�� �G�R�E�}�C�t�@�[���i���s�s�j�́A�\�[���[�V�F�A�����O�i�c�_�^���z�����d�j�̕��y���x�����邽�߁A�\�[���[�V�F�A�����O�ݔ��ւ̉c�_�҃}�b�`���O�T�[�r�X����щc�_�T�|�[�g�T�[�r�X���J�n�����B �G�R�E�}�C�t�@�[����2�̃T�[�r�X���J�n����B����1�ł���c�_�҃}�b�`���O�T�[�r�X�́A�ݔ����ł̉c�_�҂������������Ǝ҂ƁA���Ɗg���ڎw���_�ƌo�c�҂�_�n���L�K�i�@�l�A�V�K�A�_��]�҂Ȃǂ̃}�b�`���O���s���B����1�̉c�_�T�|�[�g�T�[�r�X�ł́A�ݔ����ł̉c�_���̂��̂Ђ����ڃT�|�[�g����B �G�R�E�}�C�t�@�[���́A�\�[���[�V�F�A�����O���т�����t�G�R�E�G�l���M�[�ƁA�S����5�J���̔_�Ɛ��w�Z�ƁA�_�Ɛ��Y�T�|�[�g�Ȃǂ����{����}�C�t�@�[�����A�\�[���[�V�F�A�����O�ɓ��������R���T���e�B���O�T�[�r�X�̒�ړI�ɁA2017�N5��19���ɐݗ��������ى�ЁB �o�T�uIT���f�B�A�v |
|
|
| ���x�m�d�@�A�����ŏȃG�l��Ċg��^��A�s�ɐV��� �x�m�d�@�͒����ŃV�X�e���\�����[�V�������Ƃ��g�傷�邽�߁A�H��Ȃǂ֏ȃG�l���M�[���Ă���V��Ђ̐ݗ��\�B �ɔJ�ȑ�A�s�ɗ����グ��V��Ђ͐ݔ����Ƃ̏���d�͂�ڂŌ�����`�Ōڋq�Ɏ����A�ȃG�l���ɗD���C���o�[�^�[���ϓd�@��Ȃǂ�g�ݍ��킹���V�X�e���Ƃ��Ē�Ă���B�o�ϐ����ɔ��������̃G�l���M�[����ʂ͋}���B�ȃG�l�s����L�тĂ���B�x�m�d�@�͐V��Ђ�ʂ��Ċg�傷�钆���̏ȃG�l���v����荞�ލl�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���n���M���R�X�g�ɗ�g�[�Ɋ��p�A�V�^�~�M�V�X�e�����J�� NEDO�Ɠ��{�n�����J���́A�H�c��w�ƂƂ��ɁA�n���ѐ��w�ɗ�M�E���M��~���A��g�[�ɗL�����p�ł��鍂�����ѐ��w�~�M�V�X�e�����J�������Ɣ��\�����B ���V�X�e�����R�`�s���̎����������̋ɓ������A���؎������s�������ʁA�]���V�X�e���Ɣ�ׂď��������R�X�g��23���팸�ƁA1�N�Ԃ̉^�p�R�X�g��31���팸��B���ł��錩���݂����邱�Ƃ��m�F�����Ƃ��Ă���B �������ѐ��w�~�M�V�X�e���́A2�{�̈�˂�~���ƉĊ��Ō��ݗ��p���A�n�����̗���̒x���n���ѐ��w�ɓ~���̗�M�A�Ċ��̉��M�����ꂼ��~����B �Ċ��́A��[���p���邱�Ƃɂ�艷�߂�ꂽ�n�������A����ɑ��z�M�ɂ��������A���M�Ƃ��Ēn���ѐ��w�ɒ~����B�~���́A���̒g�����n������g�[���p���A����ɏ���̔M���Ƃ��ė��p���邱�ƂŒቷ�ƂȂ����n�������M���Ƃ��Ēn���ѐ��w�ɒ~����B���������n���ѐ��w�̊��p�ɂ��A�V�X�e�����������コ���đ啝�ȏȃG�l���������ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������29�N�x�G�l���M�[�������t�c���肳�ꂽ �{�N�̔����ł́A�ŋ߂̃G�l���M�[������������̓����܂��A�ȉ��̎����ɂ��ďЉ�Ă���B 1.�����ېV��̃G�l���M�[���߂���䂪���̗��j 2.���������̐i�� 3.�G�l���M�[���߂�����O�̏�Ɖۑ�ω� �E2030�N�̃G�l���M�[�~�b�N�X�̐i���Ɖۑ� �E2050�N�Ɍ������G�l���M�[��̕ω��Ɖۑ� �i��v���̉��g����̏A�䂪���̃G�l���M�[�Z�L�����e�B�̌���A�G�l���M�[�Z�p�Ɖ䂪����Ƃ̉\�����j �E���̑��A�G�l���M�[����������O�N�x�i����29�N�x�j�ɍu�����{��̊T���ɂ��Ă��L�q���Ă���B �o�T�u�G�l���v |
|
|
| �����r�W�l�X�̓����c���E�U���������Ɋւ���������\ ���Ȃł́A�u�o�ρE�Љ�̃O���[�����v��u�O���[�������v��S�����r�W�l�X�ɂ��āA�����ɖ𗧂�����邽�߁A���r�W�l�X�̎��ԂɊւ��钲�����͂��s���Ă���B���̓x�A����29�N�x���u���ւ̎�g���G���W���Ƃ����o�ϐ����Ɍ����āv�����܂Ƃ߂܂����B OECD���ɂ����Y�Ƃ̒�`�E�l��������ɁA���Y�Ƃ́A�u�������鐻�i�E�T�[�r�X���A���ی�y�ю����Ǘ��ɁA���ړI�܂��͊ԐړI�Ɋ�^���A�����\�ȎЉ�̎����ɍv������Y�Ɓv�ƒ�`���Ă���B��̓I�ɂ́A�u�������h�~�v�A�u�n�����g����v�A�u�p���������E�����L�����p�v�A�u���R���ۑS�v�S�̕���B ����29�N�x�́A���r�W�l�X��W�J�����Ƃ̂����A�u�����̓����i�\����@�\���j�����i��T�[�r�X�Ɋ��p�����r�W�l�X��W�J�����Ɓv�́u���ʂ�ۑ�v�A�u�����v���v���ɂ��Č������s�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���d�u�q���������Q�{�ɁH�I����v���W�F�N�g�̑S�e �S�ő̓d�r�̒~�d�ʂɒ�������̐σG�l���M�[���x���A�����x�[�X�ŁA2022�N�Ɏԍڗp���`�E���C�I���d�r�̖�2�{�Ɉ����グ��Y�w���̋���v���W�F�N�g���n�������B �����傫���̓d�r�ł���q��������2�{�ƂȂ�B�W�܂����W�҂̊Ԃɂ́A�S�ő̓d�r�ւ̑傫�Ȋ��҂Ɠ����ɁA1�ВP�ƂŎ����͓���Ƃ�����@��������B����23�ЂƑ�w�E�����@��15�@�l�͂ǂ�����č����ڕW����������̂��B �g���^�����Ԃ�p�i�\�j�b�N�A�������Ƃ����������Ԃƒ~�d�r�A�ޗ����ꂼ��̋ƊE���\�����Ƃ��猤���҂��W�܂�A�O���̌������ƍ��킹�č��v100�l���v���W�F�N�g�ɎQ������B ���E�ōł������̑S�ő̓d�r�̓��������g���^�����Ԃ͕ۗL��������̈ꕔ���A�K�v�Ȃ��̂̓v���W�F�N�g�����o�[�Ƌ��L����l�����Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���̉��Ƒ�C�̉��x���Ŕ��d�g���Ă��Ȃ������G�l���M�[��d�͂ɕϊ� ����c��w�Ƒ���w�A�É���w�̌����O���[�v�́A�̉��Ƒ�C�Ȃǂ̂킸���ȉ��x���Ŕ��d�ł���Z�p���J�������B �M�d���d�f�q�Ƃ��������̂̈��B�����ȉ��x���Ŕ��d�ł��A��R�X�g�Ő��Y�ł���悤�ɐV�\�����Ă����B5���̉��x���ŁA1cm2������12��W�̓d�͂��ł���B �V�Z�p�́A�����ɉ��x�������邱�ƂŔ��d����d�g�݂����ƂɂȂ��Ă���B�����̏W�ω�H��̃V���R���́A�i�m���[�g���T�C�Y�̑����̃��C���[�`��i�i�m���C���[�j�ɔ����H���邱�Ƃʼn��x��������o����B�V���R����𔖂����A��̕\�ʂ��痠�ʂ֓K�ɔM�̗���𐧌䂷�邱�ƂŁA�Z���i�m���C���[���ɑ傫�ȉ��x����������B��ɋ�������H�͕K�v�Ȃ��A�ʏ�̔����̏W�ω�H�Ɠ������@�ō쐬�ł��邽�߁A��ʐ��Y�ɂ�萻���R�X�g��ጸ�ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����Z���A2018�N�x��VPP�\�z���ł́u�ƒ�p�~�d�r��15�����ɐ���v ���Z���́A�o�ώY�ƏȂ́u���v�Ƒ��G�l���M�[���\�[�X�����p�����o�[�`�����p���[�v�����g�i VPP�j�\�z���؎��Ɓv�ɂ����āA���\�[�X�A�O���Q�[�^�[�Ƃ��ĎQ�悷��B���̎��g�݂̊T�v�\�����B �����Ƃ̂����A�A�O���Q�[�V�����R�[�f�B�l�[�^�[����f�B�}���h���X�|���X�i DR�j�̎w�����āAVPP�����s���B���Z���́A�A�O���Q�[�V�����R�[�f�B�l�[�^�[�̊��d�́A�G�i���X�EKDDI�A�����d�̓O���[�v�ƘA�g���A�_����ʉƒ�̒~�d�r�ɑ��AHEMS��ʂ��ĉ��u��葬�₩�ɃG�l���M�[���\�[�X�̐���Ǘ����s���B ��̓I�ɂ́A�~�d�r�ƁA�Ǝ��̑����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���ɂ��d�͐�����s���BDR�̔�������5���܂���15���ȉ��Ƃ����Z���Ԃœd�͐�����s���A���Ђ��ݒu�����e���v�ƃT�C�h�ɂ��镪�U�G�l���M�[���\�[�X�𑩂˂āA��ʑ��z�d���Ǝ҂̗��p���钲���͓d����n�o������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2018/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���X�}�z�ŏܖ�������h��NTT�h�R���A�H�i���X�팸�ɏ��@ �d�g�݂́A������ɂȂ鋰�ꂪ����Ώۂ̏��i���w�������ڋq�́A�X�}�z�̃A�v���𗘗p���āA���V�[�g�Ə��i�̃p�b�P�[�W�Ɉ���Ă���ܖ������E����������B�e�����ʐ^���A�b�v���[�h���A�|�C���g��\������B�F�߂���Ɓud�|�C���g�v�����炦��B �|�C���g�Ҍ�����20���B�|�C���g�̌����͓X�܂����S����B���X�ł́A�|�C���g�𗘗p����20�`50���l���������ɔ����A�ނ��뗘�v�𑽂��m�ۂł���B�H�i���X�ɂ���ĔN�Ԃ�300���~���x�̑��������点��Ӌ`�͑傫���B ���i������c��ƁA�X�������i�̃o�[�R�[�g��1�_1�_�X�L�������đ������L�^�����Ƃ��������邽�߁A�H�i���X������Δp���Ɋւ���Ƃ�����̂ŁA�J�����̉��P��l����̍팸�ɂȂ���Ɗ��҂���B �J�������H�i���X�팸�A�v���ł́A�w���������i����������ǂ����܂ŒǐՂ���B����Ă��Ȃ��ꍇ�͂��̐H�i���g���������̃��V�s����ă��X��h���B �o�T�u���o�r�W�l�X�v |
|
|
| ���x�m�d�@�A�T�O�L�����b�g���r�n�e�b�����^�Ɩ��p�R���d�r���g�[�� ���Ђ́A50kW���̋Ɩ��p�ő̎_�����^�R���d�r�iSOFC�j��2018�N�x���ɔ�������Ɣ��\�����B ���Ђ�1998�N����M��������ɗD�ꂽ100kW�̃����_�^�R���d�r�iPAFC�j��̔����Ă���B����͔��d������55���ƍ���SOFC�̊J���ɂ��߂ǂ�t���A�Ɩ��p�R���d�r�̐��i�Q���g�[����헪���B SOFC�̖ڕW���i��5�疜�~�B�z�e����a�@�Ȃǂɒ�Ă��APAFC�ƍ��킹��2018�N�x��20�`30��A2023�N�x��50��̔̔���ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������𗘗p�����C�����d�����ցA�h�g�h���������� IHI��NEDO�̏������A2017�N��100kW���̊C�����d���؋@�u������イ�v���J���B���������̌��V�����Ŏ��؎������s�����B ���̎��͑D���Ŏ��؋@���������邦���q�����ƁA�C��Ɏ��؋@�����[�v�ŌW�����č���������鐅�[30�`50���[�g���t�߂ɕ��V��������؎������e1�T�Ԓ��x���{���Ă���B �����Ŕ��d���\����S���Ȃǂ��m�F�ł������߁A��蒷���̎��ɏ��o�����Ƃɂ����B����3�N�Ԃ̎��ł́A�܂����C��̊��ω���n���ɐڑ����邽�߂̒����Ȃǂ��s��FS�����{�B���p���̉\���Ǝ��Ɛ��������Ɣ��f����Β������Ɉڍs����\�肾�BNEDO�͑����Ɣ��3����2�ɑ�������22���~�S����B ��������1�N�ȏ�ɂ킽�锭�d�\�͂�ݔ��̑ϋv���A�o�ϐ��Ȃǂ�������B���������d���Ƃ��ĂQ�O�R�O�N�ȍ~�̎��p����ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���}���[�d�Ή��̏Z��p�~�d�r�V�X�e���i�W�D�SkWh�j �V���[�v����V���� ���Ђ́A�}���[�d�ɑΉ������Z��p�u�N���E�h�~�d�r�V�X�e���v��7����菇����������B���V�X�e���́A�������w�̊g�傪�����܂�鑾�z�����d�̎��Ə���j�[�Y�ɑΉ������\�����[�V�����Ƃ��ĊJ�����ꂽ���́B ���̃V�X�e���́A�u���`�E���C�I���~�d�r�v�Ɓu�p���[�R���f�B�V���i�v�ō\�������B�܂��A���̃��`�E���C�I���~�d�r�͑�e��8.4kWh�ő��z�d�r�Ŕ��d�����d�C���\���ɂ��߂邱�Ƃ��ł���B����ɁA�}���[�d�ɑΉ����A���[�d�ɂ����鎞�ԂЏ]���@�䔼���̖�2.5���ԂɒZ�k�B����Ԃ��Z���Ă������悭�d�C�����߂���Ƃ����B �u�p���[�R���f�B�V���i�v��2�@��B���ꂼ��96.0���A95.5���̍����ϊ���������������B ��d�̍ۂ̎����^�]���̏o�͂��ő�2.0kW�Ɋg�債���B�Ɩ���①�ɂȂǂ̓d���m�ۂɉ����A�d�C�P�g�����@�Ȃǂ������Ɏg�p�ł���B�V�X�e���̉��i�i�ŕʁj��2,910,000�~ �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z���Ɛ��f�œ����R���r�j�A�g���^�ƃZ�u���������J�� �Z�u�����A�C�O���[�v�ł͎��Ƃɂ�����Đ��\�G�l���M�[�̊��p�ɒ��͂��Ă���B2030�N�܂łɓX�܂ł̍Đ��\�G�l���M�[�̗��p�䗦��20���ɁACO2�r�o�ʂ�2013�N�x��Ŗ�27���팸����v�悾�B �Z�u���]�C���u���͂��̖ڕW�B���Ɍ����āA�X�܂ɂ�����ȃG�l��Đ��\�G�l���M�[�̊��p�Ɍ������Z�p���ACO2�r�o�ʂ̏��Ȃ��z���ԗ��̓����ȂǂɎ��g��ł����B ���Ђ������J�����鎟����X�܂͑��z�����d�V�X�e���̑��A�o�͂�10kW�i�L�����b�g�j�̔R���d�r���d�@�B�n�C�u���b�h�Ԃ̎g�p�ς݃o�b�e���[���ė��p�����~�d�V�X�e���A���d�@�\�t���[�d��Ȃǂ�ݒu�B�X�܂̃G�l���M�[���v�ɍ��킹�Ă����̋@������䂷��BEMS����������B �R���d�r���d�@�͒�u���ŁA�R���d�r�ԁuMIRAI�v�ɍ̗p����Ă���Z���𗘗p���Ă���B���d�@�\�t���[�d��́A�d�C�����Ԃ�n�C�u���b�h�Ԃɏ[�d���s���鑼�A��펞�ɂ͎ԗ�����X�܂ɓd�͋������s����d�g�݁B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������Ȏ��o�C�I�}�X���烊�`�E�������d�r���A���`�E���C�I���d�r��2�{�ȏ��~�d�\ �����Z���[�H�ȑ�w�́A�������L�x�ɑ��݂��鎆�o�C�I�}�X���g�p���ă��`�E�������d�r��������@���J�������Ɣ��\�����B ���`�E�������d�r�́A���ݎ嗬�ł��郊�`�E���C�I���d�r��2�{�ȏ�̃G�l���M�[��~�ςł���Ƃ���Ă���B ���`�E�������d�r�ł́A�J�\�[�h�͗����Y�f�}�g���b�N�X����\������A�A�m�[�h�ɂ̓R�o���g�_���`�E�����g�p����Ă���B �����`�[���́A����������̏ꏊ�ɕ����߂邽�߂ɁA���܂��܂Ȍ`�̒Y�f���g�p���܂����B���̒��ŁA���O�j���X���z���_���܂ޔp�t��p���A���̊��F�t���������A�����Ŗ�700���ɉ��M����B ���M�v���Z�X���J��Ԃ����ƂŁA�K�ȗʂ̗������Y�f�}�g���b�N�X���ɕ����߂���B�����ōޗ��ӂ��A�s�����|���}�[�ƍ������ĉA�ɃR�[�e�B���O���쐬����B�������āA��200����̏[���d�T�C�N�����\�Ȏ��v�p�o�b�e���[�T�C�Y�ł��郊�`�E�������d�r�v���g�^�C�v���쐬�����B �o�T�u�G�l���M�[���Z���^�[�v |
|
|
| ������œ��{�̋����͗������Ȃ�H�����̗�[�u30�x�v���u28�x�v�ȉ��� 4���A�k�C���̑эL�s�ōō��C��34���A�����s�S��29.1�����L�^���A�S��800�n�_�ȏ�ʼnē��ƂȂ����B���N�̉Ă��S���I�ɏ����Ȃ肻�����B ����Ȓ��A�����Ȋw�Ȃ́A����܂Łu30���ȉ��v���]�܂����Ƃ��Ă��������w�Z�⍂�Z�A��w�̋����̎������u28���ȉ��v�ɕύX�����B1964�N�ȗ����߂Ă̌��������B �X�̐l�ɕ����Ă݂�ƁA�u�Ă͏����Ă���ǂ������v�i20��j���j�A�u���g���ɂȂ�����Ƃ��A���낢������������̂œ��R���Ǝv���܂���v�i60�㏗���j�Ȃǂ̐��������ꂽ�B �o�T�uFNN PRIME�v |
|
|
| �������䗦20�`22�� �G�l��{�v��A30�N�ڕW���ێ� �G�l���M�[��{�v��͒������I�ȓ��{�̃G�l���M�[���������A���ʂ̐������Ă̓y��ƂȂ�B�f�Ă͓��Ȃ̑��������G�l���M�[������̕��ȉ�ŗ������ꂽ�B �d���\���̌��ʂ���2015�N�ɂ܂Ƃ߂��u�����G�l���M�[�������ʂ��v�̐��l��ς��Ă��Ȃ��B ���q�͂͒�����킸����I�ɔ��d�ł���u�d�v�ȃx�[�X���[�h�d���v�Ƃ̈ʒu�Â��P����B��{�v��̉�����A��~���̌����͍ĉғ������������ڎw�����ƂɂȂ�B �����̎g�p�ς݊j�R�����ď������A���o�����v���g�j�E����E�������ĂєR���Ƃ��ė��p���鍑�́u�j�R���T�C�N���v������ێ�����B 2050�N�Ɍ����Ă͐��E�̒E�Y�f���̗���܂��A�Đ��G�l�ɂ��ď����́u��͓d�����v��ڎw�����j������B���z���╗�͔��d�V�X�e���̃R�X�g�ጸ���͂���ق��A�ۑ�ł��鑗�d���Ԃ̉��v���i�߂�B �o�T�u�G�l���v |
|
|
| ���Ή��l����s�ꂪ�����D�A���ʂ킸���^�Œቿ�i���ǂ� ���{���d�͎�����iJEPX�j���J�݂����Ή��l����s��̏����D���s���A�ᒲ�Ȗ��ɏI������B FIT�d���̔Ώ؏��̔�����D��500��kW�����ɑ��A���ʂ�515��5738kW���ŁA��藦��0.01���������BFIT���ۋ��ɏ[�Ă�������͖�670���~�ŁA�������S�̒ጸ���ʂ͂قڂȂ������B�o�ώY�ƏȂ̐R�c��Ō��߂��Œ���D���i���A���̊��N���W�b�g�̎�����i��荂�����ƂȂǂ���A��p�Ό��ʂ����Ă��ĉ��D�������������Ǝ҂����������悤���B ���s��́A���d���ɓ�_���Y�f�iCO2�j��r�o���Ȃ�FIT�d���̔Ή��l���؏������A�d�C�̌����s��ƕ������Ď������B������͏����d�C���Ǝ҂��B�d�C�Ə؏���g�ݍ��킹�čĐ��\�G�l���M�[�䗦�����߂��������j���[���ڋq�ɒ�����A���Ђ�CO2�r�o�W����������̂Ɏg����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Q�O�T�O�N�̓d�͏���A�l�����E�ȃG�l�Z���Ō���̂S���̂R������ ���{�����������́A2050�N�̓d�͏���ʂ�2016�N���є�23.5������7268��kWh�ƂȂ�A1990�N�㏉���̐����������Ƃ̎��Z���܂Ƃ߂��B �l���E���ѐ��̌�����ȃG�l���M�[�@��̐Z���ɂ��A�ƒ땔��ƋƖ�����̓d�͏���ʂ�3��������5������Ɨ\���B����A�d�C�����ԁiEV�j��v���O�C���n�C�u���b�h�ԁiPHEV�j�̕��y���d�͏���ʂ̉����グ�v���ɂȂ邪�A�S�̂̏���ʂɐ�߂銄���͒Ⴍ�A�e���͌���I�Ƃ����B ���ѐ���2023�N��5419�����т��s�[�N�Ɍ����Ɍ������B���ꂪ�ƒ�ƋƖ�����̓d�͏�������炷�傫�ȗv���Ƃ����B �Ɩ�����̓d�͏���ʂ�2050�N��2016�N�x����������ށB�ƒ땔��͉Ɠd�@��̏ȃG�l���e�����A2050�N��3�����̍팸�Ɨ\���B�����Ƃ�2016�N�Ƃقډ����ƌ����ށB�o�ϐ����Ɛ��Y��������Ȃǂ̌��ʂ����E�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���p���[�����́A�����K���E���ō��������d�͑����A�X������ ���É���w�́A�d�͂̕ϊ��������i�i�ɍ����p���[�����̂����邽�߂̗v�f�Z�p���J�������B �����K���E���iGaN�j�Ŕ����̂̊���`������Z�p�ƁA���̔����̂̊e�w�����H����Z�p��2�{���Ă��B ���p���Ɏ���Όϊ����Ȃǂ̓d�͑������]���^�p���[�����̂�1�����x�ōςށB�p���[�����͓̂d���Ԃ�S���ԗ��ȂǎЉ�ōL�����y�B�����K���E����̃p���[�����̂ɒu�������ΐ��ȏȃG�l���ʂ������߂�B�V�싳�����2022�N�ɂ����p���������l�����B �V���R����ʂɒ����K���E���w���`������p���[�����̂͑��݂�����̂́A����̌������ʂ͒����K���E�����̂��̂Ŋ���`������Z�p�B�������@��������߁A�����Ȋw�Ȃ������K���E���Ŋ�����鎟���㔼���̂̌����v���W�F�N�g�Ƃ��ĊJ���ɏ��o���Ă����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���V�J���́u���z���o�C�I�R���d�r�vCO2���z�����Ȃ��瑾�z�����d ���s����w�́A�X�s�����i�̎_�f�����^�������@�\�ɂ�鑾�z���G�l���M�[�𗘗p���āA���������ɂ���CO2���팸���Ȃ��甭�d���A�����ɋa�_������@�\�����o�C�I�R���d�r�̊J���ɐ��������B ���̌����́ACO2���܂ޗn�t���Ō��������Œ�d�ɂƋa�_�E���f�y�f�Œ�d�ɂƂ�A���������u�ɁA���������������Œ�d�ɂɏƎ˂���Ɖ�H�Ɉ��̓d��������A����A�a�_�E���f�y�f�Œ�d�ɏ�ł͓�_���Y�f���Ҍ�����ċa�_���������邱�Ƃ����o�������́B�Ȃ��A�d����55�}�C�N���A���y�A�i��A�j���v�������B ���̌����ɂ��ē���w�́A���z���G�l���M�[�ɂ��CO2��L�@���q�֕��q�ϊ��ł���V���ȃo�C�I�G�l���M�[�n���Z�p�ł���ACO2���L�p�Ȍ����Ɉʒu�t���������I�Ȑ��ʂ��Ɛ������Ă���B����ACO2���u�r�o�ł͂Ȃ����p���팸�v���Ȃ���G�l���M�[��n�o���鋆�ɂ̃o�C�I�G�l���M�[�n���@�\�������z�d�r�ւ̓W�J�����҂���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E�̃G�A�R�����v�A2050�N�܂ł�3�{��IEA�� IEA�̕��ɂ��ƁA�G�A�R�����ݒu���ꂽ�����͌��݁A���E�ɖ�16�������݂��邪�A���̐�����2050�N�܂ł�56�����ɂ܂ő������錩�ʂ��ŁA����́u����30�N�Ԃɖ��b10��̃y�[�X�ŐV�����G�A�R���������v�Z�ɂȂ�v�Ƃ����B ���͂܂��A����\�z����鉮����[���u�̋}���ɉ����邽�߂ɕK�v�ƂȂ�d�͗ʂ́A�č��Ɖ��B�A���iEU�j�Ɠ��{�̌��݂̔��d�\�͂̍��v�Ƃقړ����ɂȂ�Ƃ��Ă���B ���́A�G�A�R���̃G�l���M�[���������u�ɂ���Ă�����傫�����Ƃ��B���B����{�Ŕ̔�����Ă���G�A�R���́A�č��⒆���Ŕ̔�����Ă���G�A�R���ɔ�ׂăG�l���M�[������25���ȏ㍂���X��������B ��[�ݔ��̃G�l���M�[������̈����グ�́A���d���V�݂̕K�v�����y������Ɠ����ɉ������ʃK�X�r�o�ʂƃR�X�g�̍팸���\�ɂ��邽�߂Ɋe�����{���u���邱�Ƃ̂ł���ł��ȒP�ȑ[�u�̈���Ƃ����B �o�T�uAFPBB News�v |
|
|
| ���@�@[�@2018/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���h�g�h���A�����j�A���Ăɐ����A�Η͔��d�R���Ɏ��p���߂� ���Ђ́A�ΒY�Η͔��d�̔R���ł�������Y�ƃA�����j�A�̍����R�Ď����ŁA���E�ō������ƂȂ�M�ʔ䗦20���̃A�����j�A���Ăɐ��������B �������ŐΒY�Η͔��d���̔R���Ƃ��ăA�����j�A�𗘗p����R�ċZ�p�̎��p���ɂ߂ǂ������B����̓{�C�����\�ɗ^����e���̕]����^�]�����̑I��ɂ��A���f�_�����iNOx�j�̔r�o�ጸ��ڎw���B���؎����͓��t�{�̐헪�I�C�m�x�[�V�����n���v���O�����̈ϑ������Ƃ��āA�����H����ɂ����e�ʔR�Ď����ݔ��i�����M��1��kW�j�Ŏ��{�����B ��^�{�C���Ŕ|�����Z�p�����p���A�����̔��d���ɑ��鏬�K�͂ȉ����ŁANOx�r�o�Z�x���]���̐ΒY�Η͔��d���Ɠ����x�ɗ}���邱�Ƃɐ��������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����{�x�l�b�N�X�ƏZ���A�����[�X�~�d�r���ғ��^�u�X�}�[�g�H��v������ �Y�ƁE�d�C�@�퐻���̓��{�x�l�b�N�X�ƏZ�F�����A���Y�����Ԃ́A�x�l�b�N�X�̖{�ЍH��ŁA�V�^�����[�X�i�ė��p�j�~�d�r�V�X�e���̊��H�����J�Â����B �d�C�����ԁiEV�j�Ŏg���I������~�d�r���ė��p������̂ŁA�e�ʂ�100kWh�B�x�l�b�N�X�̓V�X�e�����H���@�ɁA���H����̑��z���p�l���i��600kW�j�ƁA���Y��������EV10����g�ݍ��킹�ė��p����u�݂炢�̍H��v�v���W�F�N�g���J�n�����B �V�^�~�d�r�V�X�e���́A�x�l�b�N�X�A�Z���A�x�m�d�@�������J�������B�����@���x�l�b�N�X�{�ЍH��ɐݒu���A���N�Q���ɉғ������B�x�m�d�@�͓��V�X�e�������i�����A6������Y�Ɨp�V�X�e���Ƃ��Ĕ̔�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������l���u���b�N�`�F�[���Z�p��CtoC����\�t�g�o���N�Ȃǂ����� �d�̓V�F�A�����O�́A�u���b�N�`�F�[���Z�p�i���U�^�䒠�Z�p�j�����p���A�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��CO2�팸���l��CtoC�i����Ҋԁj�Ŏ�������邱�ƂɌ�����������6������J�n����Ɣ��\�����B �������́A���Ȃɂ�鎖�Ƃ̍̑����āA�\�t�g�o���N�O���[�v�Ȃǂ̋��͂̂��Ǝ��{�����B�ƒ�Ŏ��Ə���ꂽ���z�����d�ɂ��CO2�팸���l��PS�\�����[�V�����Y���������A���쌧�L���Ŏ��{����d���o�C�N�̃����^���T�[�r�X���Ƃɂ����ė��p����B���̓d���o�C�N�̏[�d�ŏ�����d�͂ɁA����CO2�팸���l�����p���邱�ƂŒ�Y�f���Ƃ�������B CO2�팸���l�̔����ΏۂƂȂ�ƒ�́A�֓����𒆐S��10�����x�B������2019�N3�����܂ł�\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u���`�E����C�d�r�v�J����C���̎_�f�g���g���ɂ̒~�d�r�h �\�t�g�o���N�ƕ����E�ޗ������@�\�iNIMS�j�́AIoT�@������ɁA��C���̎_�f�Ɖ��w�������ăG�l���M�[������u���`�E����C�d�r�v�������J������Ɣ��\�����B ��������A�]���̃��`�E���C�I���d�r�Ɣ�ׂāA�d�ʃG�l���M�[���x�i�d��1�L��������̓d�r�e�ʁj��5�{�ȏ�ɂȂ�Ƃ����B2025�N����̎��p����ڎw���B ���`�E����C�d�r�́A�d�ɍޗ��̈ꕔ�i���Ɋ������j�ɋ�C���̎_�f���g���B������₷�����Ɋ�������d�r���ɔ�����K�v���Ȃ��Ȃ�A�y�ʉ������҂ł����A�G�l���M�[�R�X�g��Ⴍ�}������u���_�㋆�ɂ̒~�d�r�v�ƌ����Ă���B �J������d�r�́A�Z���T�[��E�F�A���u���f�o�C�X�ȂǂŒ����ԓ��ځA�쓮�ł��邱�Ƃɉ����A��e�ʂ����ăh���[����{�b�g�Ȃǂ̕���ł����p�������܂��Ƃ��Ă���B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| �����d�d�o�A�V�d�͂Ə����荇�ِݗ��^�Q�O�N�x�A�P�T�O�����_�� �����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i�d�o�j�ƐV�d�͂̃p�l�C���́A�S���œd�́E�K�X�̔̔����s���V��Ђ������o���ŗ����グ�A�T�[�r�X�������n�߂�Ɣ��\�����B 2020�N�x���܂ł�150�����̓d�͌_��l����ڎw���B�ƒ�����̊������������łȂ��A�S���̕s���Y�Ǘ���Ќ����ɁA�����̃}���V�����_��Ɉꊇ�Ή��ł���V�T�[�r�X��ł��o���A���ЂƂ̍��ى���}��B ���Ђ��p�l�C���̓d�͏�����q��Ђɒlj��o������`�ŁA4��2���ɍ��ى�ЁuPinT�v�𗧂��グ���B���{���z��8���~�ŁA�o���䗦�͓��dEP��6���A�p�l�C����4���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��FIT���g�킸�A���ڑ��d���鑾�z�����d��NTT�t�@�V���e�B�[�Y���\�z�� ���Ђ́A�ۗL���鑾�z�����d���Ŕ��d�����O���[���d�͂��������z�d�Ԃ��g���A�@�l�����ɓd�͂ړ͂���T�[�r�X���J�n����ɂ�����A�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�i FIT�j�����p���Ȃ����z�����d���̍\�z�ɒ��肷��Ɣ��\�����B 2018�N7���Ɋ�Ƃɑ��ē��T�[�r�X�̉c�Ƃ�{�i�I�ɊJ�n����\��B����ɐ�삯�A�K�v�ƂȂ�y�n�̑I���i�߂Ă������߂̊J���p�[�g�i�[�̕�W���J�n�����B ���ƂȂ�y�n�̏����́A�S���G���A�i����A�����啔�������j�ŁA5,000�������[�g���ȏ�̕��R�ȓy�n�B���z�����d���p�n�̒���]����n���҂�A�V�x�n����L����{�H��ЁA���z�����d���̍\�z�o�������{�H��ЂȂǂɓy�n���̒����߂Ă���B ��ƂȂǂ���u�Đ��\�G�l���M�[�̗��p�ɂ�莩�Ђ�CO2�팸�ɖ𗧂Ă����v�Ƃ����������Ă���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A���E�̖��d���n��̂��ߎЉ�ۑ�����v���W�F�N�g���J�n ���Ђ́A�\���ȓd�͋������Ȃ��n��ɁA���z�����d�E�~�d�V�X�e���Ȃǂ̊ɉ����A�m���E�Z�p�̌��C��ʂ����l�ވ琬��d�C�����p�����n��Y�ƃ��f���̊J���x���Ȃǂ��s���A�V���ȃv���W�F�N�g���n�߂��Ɣ��\�����B ���́u���d���\�����[�V�����v���W�F�N�g�v�́A�Љ�v�������̈�Ƃ��āA���Ђ̑n��100���N���@�Ɏ��g�ނ��́B���v���W�F�N�g�ɂ��A���d���n��ɂ����鋳���Ղ̊m���Ǝ������ɍv�����A�R�~���j�e�B�̎������x������ƂƂ��ɁA���A�́u�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�v�̒B���ɂ��Ȃ��Ă����B �v���W�F�N�g�̑Ώۂ́A���ɖ��d���l���̑����A�W�A��A�t���J�B���E�A�����ăN���[���Ɂv�u���̍���������݂�ȂɁv�u�n�����Ȃ������v�Ȃ�6��SDGs�̒B�����f���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�M���X�A�p�A�M��擱���v���X�`�b�N���X�g���[�A�}�h���[�A�Ȗ_�̔̔��֎~�� �C�M���X���{�̓C�M���X�A�M��]��c�`���ŁA�v���X�`�b�N���̃X�g���[�ƃ}�h���[�A�v���X�`�b�N�c�̖Ȗ_�̔̔����֎~����ӌ���\�������B �����͂���܂ł��}�C�N���r�[�Y�̋֎~�A�g���̂ă��W�܂̗L�����A�����e��̃f�|�W�b�g�������{���Ă������A����͔N��85���{�������Ŏg���̂Ă����v���X�`�b�N���X�g���[���K���ΏۂɊ܂߂邱�ƂŁA�͐��C�m�ɗ�������v���X�`�b�N�p�����̂��������̍팸���߂����B ���E�̊C�m���ɕY���v���X�`�b�N�p������1��5000���g�����A�C�m�����ɂƂ��đ傫�ȋ��ЂƂȂ��Ă���B����c�ɂ����āA���C�̓v���X�`�b�N�p�������u���E�����ʂ���ő�̊����̂ЂƂv�ƈʒu�Â��A�V���ɐݗ����ꂽ�u�C�M���X�A�M�N���[���E�I�[�V���������iCCOA�j�v�ւ̎Q�����Ăт�����ƂƂ��ɁA���E�K�͂̌���������������̃v���X�`�b�N�p�����̊C�m���o��x����6140���|���h�����o���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����́E�n�M�̊��A�Z�X���Ԃ������@�ANEDO�����J NEDO�́A���͔��d�{�݂ƒn�M���d�{�݂�ΏۂƂ������A�Z�X�����g���Ԃ̔����ɖ𗧂�@�����܂Ƃߌ��\�����B ���͔��d���A�n�M���d���ł́A���K�͈ȏ�̔��d�ݔ������݁E���݂���ۂɂ́A���A�Z�X�����g�����{���邱�Ƃ����e���]���@�ɂ���߂��Ă���B �������A���̎葱���ɂ�4�N���x��v���邱�Ƃ���A���͔��d�ƒn�M���d�̍X�Ȃ铱�����y�̂��߂ɂ́A�A�Z�X�����g�̎��𗎂Ƃ����Ɏ葱�����Ԃ�Z�k���邱�Ƃ����߂��Ă���B ��̓I�ɂ́A���@���葱���ɂ����Ē����̑Ώۂ���@���m�肵����ɍs���錻�n�����E�\���E�]�����A�z�����葱������@���葱���ɐ�s���A���邢�͓������s�Ői�߂�u�O�|�������v�����{���邱�ƂŁA���e�������̊��ԒZ�k��}����́B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Ή��l����A�i�d�o�w���T�����{�J�n�� ���{���d�͎�����iJEPX�j�́A�Ή��l����s��̐�������J�����B�؏��w���œ�����Ή��l�̌��p��Q�����i�A������@�Ȃǂ�����B2017�N4���`12���̔��d�ʂɑ�������؏����D��5��14������18���ɍs���B �Ή��l�́A�Γd���䗦�Ɍv��ł��ACO2�r�o�W������������B����A�؏����w�������17�N�x��C02�r�o�W���ጸ�Ɋ��p�ł���B�؏��̍w������]���鏬���d�C���Ǝ҂�JEPX�̎������ɂȂ�K�v������B������A�N���A�M�F���͒ʏ�̎������Ɠ��z�B������̎��Ǝ҂͏،������p��ID�͏o�����o����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����ȂȂǁA2016�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʁi�m��l�j�Ȃǂ����\ ���̊m��l�́A�C��ϓ��Ɋւ��鍑�ۘA���g�g���Ɋ�Â��A���{�̉������ʃK�X�̔r�o�E�z���ژ^�Ƃ��ď���ǂɐ����ɒ�o������́B 2016�N�x�̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂ�13��700���g���iCO2���Z�j�ŁA2015�N�x��1.2%���A2013�N�x��7.3%���A2005�N�x��5.2%���ƂȂ����B ���Ȃł́A��}����ɂ�����n�C�h���t���I���J�[�{���ނ̔r�o�ʂ������������̂́A �@1)�ȃG�l���ɂ��G�l���M�[����ʂ̌����A �@2)���z�����d�y�ѕ��͔��d���̓����g��A �@3)���q�͔��d�̍ĉғ����ɂ��G�l���M�[�̍��������ʂɐ�߂�ΔR���̊����̑��������A2013�N�x�ȍ~�̃G�l���M�[�N��CO2�r�o�ʂ̌����v���ɋ����Ă���B �Ȃ��A2016�N�x�̋��s�c�菑�Ɋ�Â��z���������ɂ��r�o�E�z���ʂ́A5,540���g���ŁA����͐X�ыz������ɂ��4,750���g���A�_�n�Ǘ��E�q���n�Ǘ��E�s�s�Ή������ɂ��780���g���ƕ���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ������5�N�Ԃ̐��݂���I ��5������{�v��A�t�c���� ���{�́A�����5�N�ԂŎ��g�ފ��{��̊�{�I�ȕ��j���߂�A�u�������{�v��v���t�c���肵���B �ăG�l�E�ȃG�l�����g����̒��ɁA���v��ɂ�����{��̓W�J�ł́A�o�ρE���y�E�n��E��炵�E�Z�p�E���ۂ��e�[�}�ɁA6�̏d�_�헪��ݒ肵���B �@�@�O���[���Ȍo�σV�X�e���̍\�z���r�W�l�X�̐U����}��A�O���[���Ȑ��i�E�T�[�r�X�̋����g��𑣂� �@�A���y�̃X�g�b�N�Ƃ��Ẳ��l�̌���X�ѐ����E�ۑS�A�R���p�N�g�V�e�B �@�B�n�掑�������p���������\�Ȓn��Â���n��̃G�l���M�[�E�o�C�I�}�X�����̍ő���̊��p �@�C���N�ŐS�L���ȕ�炵�̎��� �@�D�Z�p�E���ۍv���̏d�_�헪 �@�E�헪�I�p�[�g�i�[�V�b�v�̍\�z �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����M�i�i�b�W�j�ɂ��ƒ듙�̎����I�����i���Ƃ̌��ʁi����j ���Ȃł́A�i�b�W���܂ލs���Ȋw�̒m���Ɋ�Â���g�������I�ɕ��y���邱�Ƃ�ڕW�ɁA�V���Ȑ����@�������Ă���B �ƒ땔��̎�g�ł́A�ȃG�l�A�h�o�C�X�����L�ڂ������|�[�g����ʐ��тɑ��t���āA���̌�̓d�C��K�X�̎g�p�ʂɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ��\��邩�v�w�I�ɑ��茟�����B �J�n��2�����ԂŁA�n��ɂ����1�`2�����̏ȃG�l�E��CO2���ʂ��m�F���ꂽ�B�܂��A�g�p�ʂ̌����鉻��g�p�ʂ̕ω��Ɋւ���A���[�g���b�Z�[�W�𑗂����肷�邱�Ƃɂ��A3�����̏ȃG�l�E��CO2���ʂ��m�F���ꂽ�B �^�A����̎�g�ł́A���ɔR��̉��P��G�R�h���C�u�̊ϓ_����A�����x�A���x�A�R������ʓ��̎��^�]�f�[�^��_�������A�h���C�o�[�Ƀt�B�[�h�o�b�N���邱�Ƃɂ��A�}�u���[�L��}���i���}������A�R��̖ʂł�1�����x���P����X��������ꂽ�B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���@�@[�@2018/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���f�[�^�Z���^�[�����AIoT�EAI���p�̏ȃG�l����T�[�r�X �O�J�Y�ƂƐ������݁A�T�[�o���̏ȃG�l�T�[�r�X��������ŊJ�n����Ɣ��\�����B �ȃG�l����T�[�r�X�́A�T�[�o���ɐݒu����IoT�Z���T�ނ����x���f�[�^�����W�AAI�͓��Y�f�[�^��~�ρE�w�K���ċ@��̉^�]�ƃT�[�o���e���̉��x�Ƃ̊W�����f�������A�œK�ȉ��x����K�v�ŏ����̃G�l���M�[�Ŏ������鐧������@��ɑ��M����B�����ɃT�[�o�����̉��x���������鉻����B ���T�[�r�X�̗��p���́A100���b�N�K�͂�120���~�^�N�i������p�͕ʁj�B�ȃG�l���ʂ́A�ő�25�����x�������܂��B �T�[�o���̃R���T���e�B���O�E�T�[�r�X�́A�ŏ��ɃT�[�o���̋@��̐��\�͂��A�@��̃x�X�g�`���[�j���O������̕ύX�A�N���E�h����Ƃ������ȃG�l��Ă��s���B��p�́A�T�[�r�X�̃x�[�X�ƂȂ�@��̐��\���͂ŁA100���b�N�K��80���~���x�i��Ĕ�p�͕ʓr�j�B�S����600���̒���K�̓f�[�^�Z���^�[���ΏہB �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���t�W�N���A���ЍH��̏���d�͂�100���ăG�l�d�͂�2050�N�ɂ������ڕW �t�W�N���A�q��Ђ̕���H��ŁA�g�p����d�͂̍Đ��\�G�l���M�[���p��100�������������Ɣ��\�����B ���H��́A�����P�[�u���A�����R�l�N�^�A�R�k�����P�[�u���Ȃǂ�����H��B�Ȃ��A���łɃt�W�N���{�Ѓr���̎g�p�d�͂́A100���Đ��\�G�l���M�[�Řd���Ă���B ���Ђ͍�����Đ��\�G�l���M�[�̓�����ʂ���CO2�팸�Ɍp�����Ď��g�݁A�n�����ی�ɓw�߂Ă����B ���Ђ́A2016�N�Ɂu�t�W�N���O���[�v�������r�W����2050�v�𐧒肵��4�̖ڕW���f���A2050�N�ɍH�ꂩ���CO2�r�o�[���Ɍ����Ď��g�݂�i�߂Ă����B���\���ꂽ���ЃO���[�v�H��ł̍Đ��\�G�l���M�[���p��100���B���́A���̎��g�݂̈���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ăA�b�v���A���ɑS���E�̎��Ў{�݂̓d��100%�ăG�l����B�� ���E�e�n�ɂ��铯�Ђ̎{�݂ɂ́A�č��A�p���A�����A�����ăC���h���܂ސ��E43�J���ɂ��钼�c�X�A�I�t�B�X�A�f�[�^�Z���^�[�A�����ċ��p�{�݂��܂܂��B ���Ђ́A�����9�Ђ̐����p�[�g�i�[���A�b�v�������̐��Y��100���Đ��\�G�l���M�[���g���Đ��Y���邱�Ƃ�������Ƃ����\�����B����ɂ��Đ��\�G�l���M�[�ł̐��Y��������Ђ̃T�v���C���[�̐��͑S����23�ЂƂȂ����B �A�b�v���͌��݁A���E�e�n��25�̍Đ��\�G�l���M�[�v���W�F�N�g�������Ă���A���d�e�ʂ͌v626MW�ɏ��B2017�N�ɂ�286MW�̑��z�����d���ғ����J�n���A�����1�N�Ԃ̔��d�e�ʂƂ��Ă͉ߋ��ō��ƂȂ����B�����15�̃v���W�F�N�g�����ݒ��ŁA���������1.4GW����Đ��\�G�l���M�[���d��11�J���œW�J���邱�ƂɂȂ�B Apple�̐V�����{�Ђ́A17MW�̃I���T�C�g���㑾�z�����d�p�l���ݔ���4MW�̃o�C�I�K�X�R���d�r���܂ޕ����̃G�l���M�[������100���Đ��\�G�l���M�[�œd�͂�d���A�d�r���������}�C�N���O���b�h�Ő��䂳��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ϐ��n�E�X�ACO2�팸�ڕW���u�Ȋw�I�����Ɋ�Â��Ă���v�ƔF�߂��� �ϐ��n�E�X�́A���Ђ��ݒ肵���������ʃK�X�̍팸�ڕW���A�p������́u2���ڕW�v��B�����邽�߂ɉȊw�I�ɍ����̂��鐅���ł���ƔF�߂��A���ۓI�ȃC�j�V�A�`�u�ł���uSBT�iScience Based Targets�j�C�j�V�A�`�u�v����F����擾�����Ɣ��\�����B ����͏Z��ƊE�ł͍������Ƃ����B ���Ђ͎����\�ȎЉ�\�z�̂��߂�2008�N�A2050�N��ڕW�Ƃ����E�Y�f�錾�\�BZEH�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j�̕��y��A���Ɗ����Ŕ������鉷�����ʃK�X���팸������g�݂�i�߂Ă����B �܂��A���ێЉ���ʂ��Ă���C��ϓ��̋��Ђ�F���B���鐻�i�̒E�Y�f��������ɐ��i���邱�Ƃɉ����āA���Ɗ����Ŏg�p����d�͂�100���Đ��\�G�l���M�[�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���uRE100�C�j�V�A�`�u�v�ɉ�������ȂǁA�E�Y�f���̎��g�݂�i�߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����肪�V�d�͂����ݍ��݁DLooop���֓d�̎掟�ɁA���k�d�͓��}�p���[�T�v���C�ɏo�� �V�d�̓x���`���[��Looop���A���G���A�̍�������Ŋ��d�͂̎掟�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B Looop��2016�N4���̓d�͑S�ʎ��R�����_�@�ɓd�C���ƂɎQ���B�ƒ�����Ȃǒሳ����Ŋ�{�����[���̗������j���[�𓊓����A��C�ɒm���x���グ���B���G�ȓd�C�����Ƃ͈�����悵��������₷���ƈ����ŁA�����Ɍڋq��L���Ă����B ���G���A�͍����̉��i�����͌������A2018�N4��1������͊֓d�̎掟�ɂȂ�ALooop�̊��G���A�̍����ڋq�ɂ́A�֓d��������������B�ሳ�́A��������Looop����������B���������ȊO�̃G���A�ł́A���Ђŋ����𑱂���B ���}�p���[�T�v���C�́A���k�d�͂���33.3���̏o���������Ɣ��\�����B ���݁A���}�p���[�T�v���C�̓d�����B�́A��9���𓌖k�d�𒆐S�Ƃ������Ό_��Řd���Ă���B���k�d�͓��}�ւ̏o���ŁA��s���ɂЂƂ������肪�ł����ƌ����������B��s���ւ̑�������Ƃ��āA�����d��2013�N�ɎO�H�����n�́A�_�C�������h�p���[�����Ă���B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ���u���b�N�`�F�[���Z�p�Łu�ăG�l���l�v��������B�C�I�������؎��� �C�I���f�B���C�g�̓f�W�^���O���b�h�ƘA�g���A�ƒ��I�t�B�X�r���A�H��Ȃǂł̍ăG�l���d�̎��ȏ���ɂ��CO2�팸���l���A�u���b�N�`�F�[���Z�p�i���U�^�䒠�Z�p�j��p���Ď��Ǝ҂Ȃnj����Ɏ���E���ς���V�X�e�����\�z���邽�߂̎��؎��Ƃ��J�n����Ɣ��\�����B ������ʂ��āA���U�^�Đ��\�G�l���M�[�̌����I�ȗ��p��A�u���b�N�`�F�[���Z�p���p�̔��d��������肵���d�͎���Ɋւ��錟��i�߂Ă����B ��̓I�ɂ́A�C�I���O���[�v�̓X�܂ɐ�p�@��i�f�W�^���O���b�h���[�^�[�j��ݒu���A�ăG�l�́u�g���[�T�r���e�B�[�v����G�l���M�[�̊Ǘ��E�������s���Ă����B ���̃V�X�e���̊m���ɂ��A�C�I���f�B���C�g�́A�ăG�l�ɓK���ȉ��l�����A�C�I���e�ЁE��ʉƒ�̗]��d�́A�ăG�l���d���Ǝ҂Ȃǂɂ��N���[���G�l���M�[����Ƃ�e�ƒ�ɔ̔����鎖�Ƃ��A2019�N4������J�n����\�肾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I���A�E�Y�f�r�W�����\2050�N�܂łɍăG�l�d��100�� �C�I���́A�X�܂Ŕr�o���鉷�����ʃK�X��2050�N�܂łɑ��ʂŃ[���ɂ���u�C�I���E�Y�f�r�W����2050�v�����肵���\�����B �܂��A���r�W����������@�ɁA100���Đ��\�G�l���M�[�ł̎��Ɖ^�c��ڕW�Ɍf���鍑�ۃC�j�V�A�e�B�u�uRE100�v�ɁA���{�̑�菬����ƂƂ��ď��߂ĎQ�悵���B RE100�̉����ɂ������ẮA2050�N�܂łɎ��Ɖ^�c�ɕK�v�ȓd�͂�100�����Đ��\�G�l���M�[�ɐ�ւ��邱�Ƃ�錾�����B�܂��A�ăG�l�ւ̓]���̎��g�݂̂ЂƂƂ��āA2018�N3�����A�{�Ђ̎g�p�d�͂��A�����d�͂ɂ��CO2��r�o���Ȃ����͔��d�R���̍ăG�l�d�͂𗘗p���A100���ăG�l������B�C�I���O���[�v�X�܂ł́A�����̂ȂǂƂ̘A�g������ɁA���푽�l�Ȓn��̍ăG�l�����p���A100���ăG�l���ɒ��킵�Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����A���v��A���z���G�l���M�[�̓�����������2017�N�̐V�K���d�e�ʂ͑��R�����������ƕ� ���A���v��iUNEP�j���́A�Đ��\�G�l���M�[�i�ăG�l�j�ւ̐��E�I�ȓ��������Ɋւ���������\�����B ����ɂ��ƁA2017�N�̐��E�̑��z���G�l���M�[�̐V�K���d�e�ʂ͉ߋ��ō���98GW�ƂȂ�A���̑��̍ăG�l�≻�ΔR���A���q�͂�傫���������B 2017�N�̐��E�̑��z���G�l���M�[������18%����1608���h���ƂȂ��āA�ΒY�E�K�X�Η͔��d�ւ̐��蓊���z1030���h�����������ق��A�ăG�l�S�́i���́A���z���A�o�C�I�}�X�A�p�����A�n�M�A���K�͐��́j�ɑ��铊���z2798���h����57%���߂��B ���E�̍ăG�l�����́A2004�N����v��2.9���h���ɒB���Ă���A2017�N�̍ăG�l�̐V�K���d�e�ʂ͉ߋ��ō���157GW���L�^�����B���E�̑����d�ʂɐ�߂�ăG�l���d�̔䗦���A2007�N��5.2%����2017�N��12.1%�ւƑ��L���Ă���B���z���G�l���M�[�̖��i���������������́A2017�N�̐V�K���z�����d�e�ʂ�53GW�Ɛ��E�̔����ȏ���߁A�����z��58%����865���h���Ɋg�債���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����A�A2018�N���u�C��J�I�X�v�����������݂ŋC���̉������K�v�ƌx�� ���A�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�j�ɂ��ƁA�O�e�[���X���A���������́A���A�{���ł̋L�Ҕ��\�ɂāA2017�N�͋C��ϓ��ɂ��ɒ[�C�ۂƂ��̔�Q�����������u�C��J�I�X�i��������ԁj�v�������Əq�ׁA2018�N�����l�̏ɂȂ��Ă��Ă���ƌx����炵���B �����āA�Ȋw�҂炪�A2020�N�܂łɋC��ϓ�������������Ȃ���p������̖ڕW��B���ł��Ȃ����ꂪ����A�ƌ��O��\�����Ă��邱�ƂɐG��A���E��CO2�r�o�ʂ�����2�N�ԂōŒ�ł�25%�팸���邱�Ƃ��Y�f�o�ςւ̈ڍs���K�v���Ɛ������B���E�C�ۋ@�ցA���E��s�A���ۃG�l���M�[�@�ւ�����ACO2�r�o�ʂ̑����A�C��ϓ��ɋN�����鎩�R�ЊQ�Ƃ��̔�Q�̊g��A�k�ɊC�X�ʐς̏k���A�C�m�̉��g����_�����̐i�s���ɂ��ċL�^�I�ȃf�[�^������Ă���B�����������́A�u�l�ނ����ʂ���ő�̋��Ёv�ł���C��ϓ�����X�̎�g�̏���s�������Ői�s���Ă���Ǝw�E���A2019�N�ɊJ�Â���C��T�~�b�g�Ő��E�I�Ȏ�g�̋�����ڎw���ӌ��𖾂炩�ɂ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���o�Y�ȁu�G�l���M�[�������Ǝ҂̏ȃG�l�K�C�h���C��������v�̋c�_���܂Ƃ� ����27�N�ɍ��肳�ꂽ�����G�l���M�[�������ʂ��ɂ����ẮA�ƒ땔��ő��O��1,160��kL�i�������Z�j���x�̏ȃG�l���M�[�������܂�Ă���A�ƒ땔����܂ގ��v�Ƃ̏ȃG�l���M�[�̓G�l���M�[�~�b�N�X�̎����Ɍ����ďd�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă���B ����A�G�l���M�[�̏����S�ʎ��R���̒��ő��l�Ȑ��i�E�T�[�r�X���o�ꂵ�A���v�Ƃ̃G�l���M�[�̎g�����͑傫���ω�����ƍl�����邪�A���R�������ɂ����Ă����v�Ƃ��K�ɏȃG�l�𐄐i�ł�����������K�v�ł���A�G�l���M�[�������Ǝҁi���Ɏ��v�Ƃƒ��ړI�ɐړ_��L����G�l���M�[�������Ǝҁj���ʂ��������͑傫���ƍl������B �G�l���M�[�������Ǝ҂̏ȃG�l�K�C�h���C��������ł́A��L�܂��Ē����E�������s���A�R�c���e�����܂Ƃ߂��B���܂Ƃ߂̃|�C���g 1.�d�C���Ǝ҂ɂ�����҂̓d�C���v�������̎�g�Ɏ�����[�u�̂���� 2.�G�l���M�[�������Ǝ҂ɂ�����҂̏ȃG�l�Ɏ�������̂���� 3.�G�l���M�[�������Ǝ҂ɂ��ȃG�l���i�E�T�[�r�X�̂���� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����f�E�R���d�r�̍����O�̓����E�W�]���킩��C�x���gNEDO�A3�����ŊJ�� �\����t���J�n���ꂽ�C�x���g�́A�u��29�ې��f�E�R���d�r�p�[�g�i�[�V�b�v�iIPHE�j�^�c�ψ����ʌ��J�Z�b�V�����F���E�ɂ����鐅�f�E�R���d�r�̍ŐV�����v�i�_�ˎs�^2018�N5��11���j�ƁA���̋@��ɍ��킹�Ď��{���鐅�f�E�R���d�r�̕��y��ڎw�����uIPHE���l�t�H�[�������f�Љ�̎����Ɍ����āv�i�����l�s�^5��8���j�A�uIPHE�S�R���[�N�V���b�vCO2�t���[���f�̃T�v���C�`�F�[���\�z�Ɍ����āv�i�S�R�s�^ 5��9���j�̌v3�B�Q����͖����B �����̃C�x���g�ɂ́A���E�̎�v�e�����琅�f�E�R���d�r�֘A�̐���W�҂��o�Ȃ���\��B��ʎQ���҂́A������ɂ����鍑���O�̓����⏫���W�]�ɂ��āA�e���̗L���҂ɂ��ŐV���̕ڒ��u���邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A�Q���\���͓��݃E�F�u�T�C�g�Ȃǂ���s���A����ɂȂ莟����ߐ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���E�Y�f���֕����V�i���I�^�Q�O�T�O�N�G�l�헪�A�G�l������f�� �o�ώY�ƏȂ́A2050�N�����������G�l���M�[�헪�̑f�Ă��܂Ƃ߂��B �s�m��v�f�ɔ����A������d���E�Z�p��g�ݍ��킹�������V�i���I�ŏ_���S�ہB�Đ��\�G�l���M�[���u����������͓d���v�ƈʒu�t���A���q�͂͏����I�ȃ[���G�~�b�V�����̒B���ɕK�v�ȑI�����Ƃ��āA�ˑ��x�͉�������������B4���ɒƂ��Ď��܂Ƃ߁A�o�Y���ɕ�����ŁA�G�l���M�[��{�v��̌����������ɐ������B �f�Ăł͒E�Y�f����Đ��\�G�l�̉��i�����Ƃ��������E�K�͂̃G�l���M�[�]���ɔ����A�s�m���������܂��Ă���Ƃ��A��̎�i�Ɍ��肳��Ȃ�����I�V�i���I�̕K�v����ł��o�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2018/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���Ɩ��p�E��M�@��́u���u�Ď��V�X�e���v�Ɂu�\���f�f�v�@�\���I�v�V�����Œlj� �����A�v���C�A���X�́A�Ɩ��p�E��M�@�킩�瓾����^�]�f�[�^(��}���́E���x�E�d���l�Ȃ�)�����łȂ��AIoT�Z�p�����p���ē���������⑼�@��Ȃǂ̂��܂��܂ȃf�[�^��~�ρE��́E���p���邱�ƂŁA���q���܂ɐV���ȉ��l�����T�[�r�X������W�J���Ă����B ���e�Ƃ��āA�Ⓚ�@�E�`���[���j�b�g��ΏۂɌ̏�ɂȂ���ω������O�Ɍ��o����u�\���f�f�v�@�\�i�^�]�f�[�^�̕ω������}�R�k�A���k�@�E�c���فE�d���فE�M������Ȃǂ̌̏�ɂȂ���ω������o����T�[�r�X�j���A�u���u�Ď��V�X�e���v�̃I�v�V�����ɒlj����A���J�n����B �܂��A�m�s�s�Ɠ����A�v���C�A���X�́A�Ⓚ�@�E�`���[���j�b�g�̉^�]����͂ɂ��X�N�����[���k�@�̎����Ռ��m�̓K�p���������Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����E�ō����x���̏ȃG�l���M�[���\�ƍ����t���L�V�r���e�B����������f�[�^�Z���^�[�v�Z�p���J�� ��ёg���J�������̂́A���ڊO�C��[�����ŁA�O�ǂ��d�ɐ݂��ăX�y�[�X�����A���̓����ɔ�������㏸�C���𗘗p���邱�ƂŁA���㕔���玺���̋�C���͂ŕ��o���A�r�C�t�@���̏���d�͂��팸����B �܂�����A�}���ɐi������ICT�Z�p�̊��p�ɑΉ����邽�߁A�f�[�^�Z���^�[�ɂ͏����̔\�͑����ɏ_��ɑΉ��ł���\���Ƃ��āA�T�[�o�[���G���A�̒��w�K�Ɏ��R�x�̍����z�����\�Ƃ���d�͋�����p�t���A��݂��A�㉺�K�̃T�[�o�[���ɋ��d����\���ŁA�C�ӂ̈ʒu�ɃT�[�o�[����z�u�ł��A�����̑��z�ɂ��e�ՂɑΉ����\���B����ɖ{�\���ɂ��A�T�[�o�[���Ɠd�͋�����p�t���A���������ꂽ���C�A�E�g�ƂȂ邽�߁A�����e�i���X���ł������Z�L�����e�B�[�����m�ۂł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������d�͂Ƒ��K�X�A��s���d�́E�K�X������ŐV��� �����d�͂Ƒ��K�X�́A��s���œd�͂�K�X��̔�����V��Ёu�b�c�G�i�W�[�_�C���N�g�v��4��2���t�Őݗ�����Ɣ��\�����B �V��Ђ͉ƒ��@�l�����̓d�́E�K�X�ƁA��炵��r�W�l�X�Ɋւ���T�[�r�X��̔�����B���F�̎擾��V�X�e�������Ȃǂ̏�����i�߂���A14�l�̐��ŋƖ����J�n����\��B�V��Ђł�2030�N���ɔ̔��d�͗ʂ�200��kWh�A�K�X�͖�100���g���A�����I�Ɍڋq��300�������l���������l���B �V��Ђ̎��{����17��5�疜�~�ŁA�����d�͂Ƒ�K�X���ܔ��o������B�̔��p�̓d�͂ƃK�X�́A�����d�͂Ɠ����d�̓t���G�����p���[�i�e���o�j�̍��ى�Ђi�d�q�`��O������̒��B��z�肵�Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��TEPCO�z�[���e�b�N�Aweb�ʼnƒ�����d�C�E�K�X�����E�ȃG�l�f�f TEPCO�z�[���e�b�N�ƁA�d�́E�K�X��r�T�C�g���^�c����G�l�`�F���W�́A�ȃG�l�f�f�Ɠd�C�E�K�X�����v�����f�f���ɍs������ʃR���e���c�́u�R���{�f�f�T�C�g�v���J���J�n�����B ���ł�TEPCO�z�[���e�b�N���s���Ă��鑍���ȃG�l�T�[�r�X�́A�ȃG�l�v�����i�[���ȃG�l�f�f���ōs���A����҂̓d�͎g�p��Z��`�Ԃ�Ƒ��\���Ȃǂ���A�œK�ȓd�C�����v�������Ă�����́B�����ɁAIH�N�b�L���O�q�[�^�[��G�R�L���[�g�ȂǁA�@������̒�Ă��s���B �܂��A�G�l�`�F���W�́A���Ђ��^�c����d�͔�r�T�C�g�u�G�l�`�F���W�v�ŁA���p�҂����Z����n��Ɛ��ѐl������͂���ƁA���C�t�X�^�C���ɍ��킹���d�͉�ЂƗ����v�������������T�[�r�X����A���p�҂̌��M��팸��}���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��������Ԃ̉��M�E�C�����z���uHoloLens�v�ɉ����\�\�x�m�\�t�g�ƈ����n�U�}���V�Z�p�J�� ���Ђ́AMicrosoft�́uHoloLens�v�����p���������������Z�p�u���E�H�b�`�v�������ŊJ�������Ɣ��\�����B �g������(AR)�Z�p�ɂ���Ď����̉��M��C�������o�I�ɔc�����邱�ƂŁA�����̋v�҂�{�H�ҁA�������p�҂̊Ԃŋv��Ȃǂ̃C���[�W�����L���₷������B ���E�H�b�`�́A���O�ɉ�́A�v�������u���M�v��u�C���v�Ȃǂ̃f�[�^���A������W�n���g���A������ԂɎ��X�P�[���Ō��ѕt���ĕ\���BHoloLens��t�������p�҂���Ԃ����ƁA���̕\��������ɒǏ]���ē���ւ��d�g�݂��B���x��C���̃f�[�^�𑽗l�ȃt�@�C���`���Ŏ�荞�߂�悤�ɂ������ƂŁA�u�R�X�g�v��u�ޗ��v�Ȃǂ̏���t������������3����CG���f���Ƃ̐e�a�������߂��B ����A���A���^�C���ł̉��x���z�̉����Ɏ��g�ށB�܂��A�u���x��C�������łȂ��A���������̊g�U�Ȃǂɂ��\���Ώۂ��L����v�Ƃ��Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���Ɠd�Ɋւ������Ғ����u�ȃG�l�^�ɔ����ւ��������ǂ����Ȃ��v KDDI�́A20��`60��̒j��400����ΏۂɁA�Ɠd�̔����ւ��Ɋւ���ӎ����������{�����B �܂��A�u�����ւ������Ɠd������v�l�ɔ����ւ��������R�����Ƃ���A��ԑ��������̂́u�ŐV�Ɠd�̕����ȃG�l������v�i39.3���j�B ���ɑ��������̂́u�Ɠd�̎������߂�����v�i38.3���j�ŁA�����āu���삪�����Ȃ�������v�i31.2���j�������B �u�����ւ������Ɠd�����邪�܂������ւ��Ă��Ȃ����R�v�ɂ��ẮA�����ȏオ�u���K�I���R�v�i50.2���j���������B�܂��A15.6�����u�ŐV�Ɠd���܂���������v�Ɖ��Ă���B�Ɠd�����ɏȃG�l���ӎ����邩�ɂ��ẮA46.9�����u���Ă͂܂�v�A19.5�����u��₠�Ă͂܂�v�Ɖ��Ă���A�Ɠd�����ւ����́u�ȃG�l�v�ɑ���ӎ����������Ƃ��S�̌X���Ƃ��Ă݂�ꂽ�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���O�H�d�H�A�V�^�̍H�������M�@�i�q�[�g�|���v�j�Œ�GWP��}���̗p �O�H�d�H�ƒ����d�͂́A�H������ɒn�����g���W���iGWP�j���]���̖�10����1�ƂȂ��}R454C���̗p�����A��C�M���z�����q�[�g�|���v�������J�������B �܂��A���̊J���@�ł͊O�C���x�}�C�i�X20������75���̉������o�������������B�J���@�́A�O�H�d�H�T�[�}���V�X�e���Y��2018�N8�����̔����J�n����B �{�C������̍X�V�ŔN�ԃ����j���O�R�X�g���67���팸�B����J��������C�M���z�����q�[�g�|���v�ł́A���B�Ő�s��������Ă���GWP�̋K���l150���N���A����R454C�iGWP146�j���A���{�����ŏ��߂č̗p���A�����ׂ�啝�ɒጸ�����B��i���k�Ⓚ�T�C�N�����̗p���邱�ƂŁA���O���x�}�C�i�X20�`43���̍L���͈͂�75���̉����������\�Ƃ����A �z�����q�[�g�|���v�Ƃ��č����G�l���M�[�����iCOP3.3�j��B�������B���Ƃ��A�H��p�{�C������̍X�V�̏ꍇ�A�N�ԃG�l���M�[�ʂ͖�51���팸�A�N�ԃ����j���O�R�X�g�͖�67���팸�ł���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������d�́A����҂̓d�C���p�����O������V��Ђ�ݗ� �����d�̓p���[�O���b�h�i���dPG�j�́A�Z����Ȃǂ̓d�C�g�p�Ȃǂ̏������W�E���́E���H���邱�Ƃ̂ł���IoT�v���b�g�t�H�[�����A���܂��܂ȃT�[�r�X���Ǝ҂ɒ��A�g����V��ЃG�i�W�[�Q�[�g�E�F�C��ݗ������B4��1�����c�Ƃ��J�n����B �V��Ђ́A����܂Œ��ݏZ��Ǝ҂ȂǂƎ��؎������s���Ă���IoT�v���b�g�t�H�[���ɂ��A�d�͂Ȃǂ̃Z���T�[�f�[�^�̎��W�Ƃ��̉��H���ʂ̒�A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�Ƃ̘A�g�ɂ��V���ȃT�[�r�X�Ȃǂ����B ��̓I�ɂ́A�Ɠd���i�̎�ނ��Ƃ̓d�͂̎g�p�₻�������H�����d�C�̎g�p�ʗ\����ݑ�Ȃǂ̏����A�T�[�r�X���Ǝ҂ɒB ����ɂ��A�T�[�r�X���Ǝ҂́A�Ⴆ�A�d�C�̎g�p�ɉ����ĉƓd���i�������ʼn^�]�E���䂷�邱�Ƃɂ����K�ȏZ������������Z��T�[�r�X��A�����E���ۊm�F�Ȃǂ̃Z�L�����e�B�[�T�[�r�X�ȂǗl�X�ȃT�[�r�X���\�ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�J�[�{���v���C�V���O�̂�����Ɋւ��錟����v�̎��܂Ƃ� �E�Y�f�����������Čo�ρE�Љ�S�̂̑傫�ȓ]���𐬂������A�����̐����̎��̌����}���ł́A�Љ�̍L�͈͂ɂ킽��Y�f�̔r�o�ɑ��ĉ��i�����邱�Ƃɂ��A�����啝�팸�Ɍ������C�m�x�[�V�����ݏo���u�J�[�{���v���C�V���O�i�Y�f�̉��i�t���j�v���ʂ��������͑傫���ƍl�����Ă���B ���Ȃ́A����29�N6���Ɂu�J�[�{���v���C�V���O�̂�����Ɋւ��錟����v��ݒu���A�L���ҁA�o�ϊE������̈ӌ������悵�A�����啝�팸�ƌo�ρE�Љ�I�ۑ�̓��������Ɏ�����悤�ȉ䂪���̃J�[�{���v���C�V���O�̊��p�̂�����ɂ��āA����܂ł̋c�_�܂��A���ʁA������ɂ����錟�����ʂ����܂Ƃ߂��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����ȂƃG�l���A�K�\�����������ɔ�����������K�X������u�̐ݒu�𐄐i ���ȂƎ����G�l���M�[���́A�����ԂɃK�\��������������ۂɔ�������R�������K�X��������鑕�u�̐ݒu�𐄐i���鐧�x��n�݂����B �����x�́A�����w�I�L�V�_���g��PM2.5�̌��������̈�ł���R�������K�X�̍팸��}��A��C���̕ۑS��}�邽�߂ɁA���Y�����@��ݒu���Ă��鋋�����iSS�j���u��C���z���^SS�i���́Fe��AS�i�C�[�A�X�j�j�v�Ƃ��ĔF�肵�A�L�����\������́B�F����4�i�K�ƂȂ��Ă���ASS�S�̂̔R�������K�X������ɉ����āA�F��ƃ��S�}�[�N����t�����i���x�{�s�O��SS���܂ށj�B����30�N6�����ɔF��v�̂�F���������肵�A���N�č�����F��\���̎�t���J�n����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���d�͒��B�E���������𑼎Ђɂ܂�����V�d�͂������o�Y�Ȃ̃��|�[�g �o�ώY�ƏȂ̒��ׂŁA�o�^�\���x�[�X�ŐV�d�͂̓d�����B������݂�ƁA2015�N11���ɓo�^�̂��������Ǝ҂͑��Ό_��6�����߂Ă������A2017�N12���ɓo�^�����������Ǝ҂͎s�꒲�B��8�����A���ɑ��҈ϑ��ɂ��s�꒲�B�䗦��5�����ƂȂ����B ���҈ϑ��Ƃ́A���d�͎�����̉���ł��鑼�҂�ʂ����d�͂̎s�꒲�B�������B���̑��҂́A�o�����V���O�O���[�v�iBG�j��ʂ��A�������Ǝ҂̎����������܂Ƃ߂čs���Ă���ꍇ�������Ƃ����B �Ȃ��A���vBG�́A�����̏����d�C���Ǝ҂���\���������������̒P�ʂ������B��\�ƂȂ鏬���d�C���Ǝ҂��A�����̏����d�C���Ǝ҂����܂Ƃ߂āA��ʓd�C���Ǝ҂���̑��������_������Ԏd�g�݂��B���K�͂̎��Ǝ҂��ʂɎ����������s���ꍇ�ɔ�ׁA�����I�ň���I�Ȏ������������҂ł���Ƃ���Ă���B�����d�͊Ǔ���75���̐V�d�͂�BG�ɉ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�A�u���{�̋C��ϓ��Ɖe���v��2018�N�Œ������|�[�g���\ ���ȁA�_�ѐ��Y�ȂȂ�5�Ȓ��́A���{��ΏۂƂ����C��ϓ��̊ϑ��E�\���E�e���]���Ɋւ���m�������܂Ƃ߂����|�[�g�u�C��ϓ��̊ϑ��E�\���E�e���]���Ɋւ��铝�����|�[�g2018 �`���{�̋C��ϓ��Ƃ��̉e���`�v���쐬�����B ���̃��|�[�g�́A���܂��܂Ȏ��R�V�X�e�����C��ϓ��ɂ��e�������钆�ŁA����n���̍s���@�ցA�������C��ϓ��ւ̑���l����ۂɖ𗧂A�ŐV�̉Ȋw�I�m������邱�Ƃ�ړI�Ƃ������́B 2018�N�ł̃��|�[�g�ł́A�ϑ����ʂɊ�Â��C��ϓ��̌���Ə����̗\�����ʂɂ��āA�ŐV�̒m���荞�ނƂƂ��ɁA�C��ϓ��ɂ�茻�ݐ����Ă���e���A�����\�������e���ɂ��Ă̋L�q��啝�Ɋg�[���Ă���B����ɂ��A�C��ϓ��ւ̓K������l����ۂɖ𗧂����ɂȂ��Ă���B �����|�[�g�̑S���ƊT�v���܂Ƃ߂��p���t���b�g�́A����HP�ɂă_�E�����[�h�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�A�u��Y�f�d�́v�E�u��Y�f�M�v�̔F�苟�����Ǝ҂����� �s�ł́A�L���b�v���g���[�h���x�ɂ����āA2015�N�x����A�s���F�肷��CO2�r�o�W���̏������������Ǝ҂���Ώێ��Ə����d�C���͔M�B�����ꍇ�ɁACO2�팸�����Ƃ��ĔF�߂�u��Y�f�d�́E�M�̑I���̎d�g�݁v�����Ă���B�ΏۂƂȂ鋟�����Ǝ҂̗v���́A 1�j��Y�f�d�́F CO2�r�o�W����0.4t-CO2/��kW���ȉ����Đ��\�G�l���M�[�̓������������ʃx�[�X��20%�ȏ㖔�͒�Y�f�Η͂̓������������ʃx�[�X��40%�ȏ� 2�j��Y�f�M�FCO2�r�o�W����0.058t-CO2/GJ�i�M�K�W���[���j�ȉ� �ƂȂ��Ă���B����A���d�g�݂ɂ�����2018�N�x�ɑΏۂƂȂ鋟�����Ǝ҂Ƃ��āA1�j15���ƎҁA2�j33���Ǝҁi���j��F�肵���B�s�ł͍�����A���d�g�݂�ʂ��āA���ɔz�������G�l���M�[���p�𑣂����Ƃɂ��A�G�l���M�[����ʂ̍팸��Đ��\�G�l���M�[�̓����g��𐄐i���Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2018/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���G�l�b�g�̂`�h�f�f�A�R�X�g�팸�̑�����Ɂ^�ȃG�l�ȊO�ɂ����p�� �G�l�b�g���l�H�m�\(AI)�����p�����ȃG�l�f�f�T�[�r�X�œd�͏������Ƃ̕t�����l�����߂Ă���B AI�œd�͂̎g�p�͂��A�ڋq�ɏȃG�l��������B�R���T���Ȃǂ̐f�f�Ɣ�����ŁA�f�f�����܂ł̃X�s�[�h�������݂��B���������̒l�������������E�ɋ߂Â����A�g�p�ʂ�}�����邱�Ƃœd�C��팸�j�[�Y�Ɉ������������Ă����B��͌��ʂ��ȃG�l�ȊO�̃T�[�r�X�Ɋ��p���邱�Ƃ��ɂ�ށB �G�l�b�g�́A�I�[�X�g�����A�̃x���`���[�ACO�[���z�[���f�B���O�X�ƒ�g���A�����Ɩ��p�����ȃG�l�f�f�T�[�r�X�u�G�l�b�g�E�A�C�v�̒�2017�N7������n�߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����[�\���A�ȃG�l�E��CO2����ڎw�����z�����f���X�܂��Q�n���ɊJ�X ���Ђ́A�f�M���\�̍���CLT�iCross Laminated Timber�F�����W���A�ȉ�CLT�j���A�X�܂̍\��������Ɏg�p�����A�ؑ��̊��z�����f���X�܂��I�[�v�������B CLT�́A���݂̂���ؔ�ؖڂ���������悤�ɕ����w�d�ˁA�ڒ��܂Œ��荇�킹���؎����z�ޗ��ŁA���x�������A�f�M���ɗD��Ă���B���z���̏ȃG�l�E��CO2�������҂ł��邱�Ƃ���A���͕���32�N�x��CLT�̕��y��ڎw���Ă��܂��B �{�X�܂ł́A���Y�����g�p����CLT �⍑�Y�̖؍ނ�X�܂̍\��������Ɏg�p���邱�ƂŌ��z�f�M���\�����コ���A�d�C�g�p�ʂ̍팸�ɂ��ȃG�l�ƁA�X�܌��ݎ���CO2�r�o�ʂ̍팸��ڎw���B���̂ق��A�ŐV�̏ȃG�l�{��⑾�z�����d�ݔ��ɂ��n�G�l�{������邱�ƂŁA�O�����B����d�͗ʂ�2016�N�x�̕W���I�ȓX�ܑΔ�Ŗ�6���팸���錩���݁B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| ���V���������c�n�Ń��[�J��VPP�\�z�C���t�������ɏW���Z����Đ� �x�m�ʑ����́A�n��̏Z��c�n��W���Z��Ȃǂ̍����ꊇ��d���ɂ����āA���z�d�r�⏬�^�~�d�r�Ȃǂ����p���ēd�͗Z�ʂ��������A�������U�^�G�l���M�[�Ƃ��ċ@�\������u���[�J��VPP�i�o�[�`�����p���[�v�����g�j�v�̊J���Ɍ��������g�݂��J�n�����B ���̑��e�Ƃ��āA���l�s�Z������ЂƁA�V���������c�n�E�}���V�����̍Đ���Ƃ��āA���[�J��VPP�����̌������n�߂��B ���[�J��VPP�ł́A�n��̏Z��c�n��W���Z��ȂǁA�œK�K�͂Ŏ����\���܂��ē��肳�ꂽ�G���A��W���̂�ΏۂɁA���z�d�r�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�⏬�^�~�d�r�AIoT��u���b�N�`�F�[���Ȃǂ̐V���ȋZ�p�����p�����������U�^�G�l���M�[�T�[�r�X�i�����[�J��VPP�j���J�����A�����ɎЉ�������Ă������Ƃ�ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ԍڗp�d�r�̍ė��p���ƁA���ց^�����d�͂ƃg���^ �����d�͂ƃg���^�����Ԃ́A�d���ԗp�d�r�̃����[�X�E���T�C�N�����Ƃ̎����J�n����Ɣ��\�����B ���Ђ͓d���Ԃ̎g�p�ς쓮�p�d�r��g�ݍ��킹�āA��e�ʒ~�d�r�V�X�e�����\�z�B�����d�͓͂��V�X�e��������������d�͌n���̎��g���E�d���ϓ��ւ̑Ή��Ɋ��p����B���Ŏg�p�����d�r���烌�A���^���Ȃǂ̍ޗ���������A���T�C�N������d�g�݂��m���������l���B ����2018�N�x����J�n���A���d�o�͖�50kW�i�j�b�P�����f�d�r50�䑊���j�̃V�X�e�����\�z����B���̐��ʂ܂��A2020�N�x�ɂ�1��kW�K�͂ł̎��p����ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���v�i�K�ŏȃG�l�Z�p�̌��ʂf�A�[�l�R��6�Ђ�ZEB�]���c�[���J�� �����Ȃ댚�݂Ȃǂ̃[�l�R��6�Ђ́A�ȃG�l���M�[�Z�p�̓������ʂ�v�i�K�ŕ]���ł���uZEB�]���c�[���v���J�������Ɣ��\�����B �V���ɊJ�������c�[���́A�p��1���G�l���M�[����ʌv�Z�ɁA���z�ݔ��Z�p�ҋ�����Ă���uHASP�v���O�����v���̗p�B����ɁAZEB�ɗL���Ő�i�I�Z�p�Ƃ����u�_�u���X�L���v�u���R���C�v�u�n���M���p�v�Ȃǂ̋̏ȃG�l���M�[�]�����s����B�����āAZEB�]���̑ΏۂƂȂ��Ă������ݔ��i�A���C�A�Ɩ��A�����A���~�@�j�ɂ��Ă̔N��1���G�l���M�[����ʁv�̎Z�o��A���z���ȃG�l�@�Œ�߂�ꂽ���\���f��ł���uBEI�iBuilding Energy Index�j�v�̎Z�o���s����悤�ɂ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��SOFC��MGT�̃n�C�u���b�h�V�X�e�����Ɩ��E�Y�Ɨp���U�^�d���Ƃ��ď��E���H �O�H�����p���[�V�X�e���Y�́A�Ɩ��E�Y�Ɨp�Ɏs��������ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j�ƃ}�C�N���K�X�^�[�r���iMGT�j�̑g�ݍ��킹�ɂ������^�������d�V�X�e�����A�ۃr�������ɐݒu�H���ɒ��肵���B���d�@���C�H������������2019�N2���̗\��B ���̃V�X�e���́A�s�s�K�X��R���Ƃ��A��900���̍����ō쓮����Z���~�b�N�X��SOFC��MGT�̗����Ŕ��d������́B�R����R�Ă����邱�ƂȂ��ASOFC�����œs�s�K�X���������Đ��f���_���Y�f�����o���A��C���̎_�f�Ɖ��w���������邱�ƂŔ��d����B����ɁA��s����MGT���g���Ĕ��d���邱�ƂŔR����L�����p����B�܂��A�R�[�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�̏ꍇ�ɂ́A�c��̔r�M�����C�܂��͉����Ƃ��ĉ�����邽�߁A���������͂��ꂼ��65%�A73%�ȏ�ɒB����ƂƂ��ɁA�]���̔��d�V�X�e���ɔ�ׂČڋq�̍H��E�r�������CO2�r�o�ʂ��47%�팸�ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���q�[�g�V���b�N�\��v�@�l�������i�L���j�J�n �u�q�[�g�V���b�N�\��v�Ƃ́A�����K�X������ЂƋ����ŊJ�������@�l�����\��ł���A�C�ۗ\�����Ɋ�Â��Ƃ̒��Ő����鉷�x���Ȃǂ���Z�肵���u�q�[�g�V���b�N�̃��X�N�̖ڈ��v��m�点����B �q�[�g�V���b�N�\��ł́A�����Ƃ̏��ł���u�T�Ԏw�����v�ƁA���Ԃ��Ƃ̏��ł���u�Z���w�����v��2��ނ̏�A�Z���ʁi5��ށj�ɉ����ė��p�ł���B �Z���ʂ�1���܂���1���ԂƂ��������ԒP�ʂ̑I�����\�ƂȂ邽�߁A�l�ɃJ�X�^�}�C�Y�����q�[�g�V���b�N�\��̕\�����\�ɂȂ�B�X�V�p�x��12��^���A�G���A�P�ʂ͎s�撬������1968�_�B�����F��7���`17���~���x�A���Ԃ́A2017�N�x��2018�N2��1���i�j�`2018�N3��31���i�y�j�̗\��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���t�����X���ȁA�Đ��\�G�l���M�[�d�͂�3�̒��Ő��i �t�����X���Ȃ́A�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��d�͂̕��y���i�̂��߁A�u�ȑf���v�u���d�ʂ̊g��v�u�Z�p�v�V�v��3�𒌂Ƃ��āA���{���܂��͍���̎�g�\�����B �ȑf���ɂ��ẮA���͔��d�J���̎葱���ʂ⎑�����B���@�Ȃǂ̌�������ƕ���ŊJ�n�������A���㓯�l�̌��������^�������Ƒ��z���G�l���M�[�ɂ��Ă��J�n����B �ʂ̘g�g�݂ŗm�㕗�͔��d�̋��F�̏_��[�u�A�����i�K�ł̈ӌ������Ȃǂ̊ȑf�������Ă����B���d�ʊg��ɂ��ẮA���z�����d�̔��d�e�ʂ�2023�N�܂ł�18.2GW�`20.2GW�Ƃ���ڕW��ݒ肵�A���d�v���W�F�N�g�̓��D��ϋɓI�ɐi�߂�B �����̑��z�����d�ݔ��̓��D�ł́A���̂قǐV����283�v���W�F�N�g�i150MW�j��I�肵���B�Z�p�v�V�ɂ��Ă��A���{�����Ȃǂ�ʂ������J����i�߂�B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������K�X�r�o�팸�����헪�A�e�Ȍ������قȂ�v�f 2050�N�̒��������������������ʃK�X�r�o�팸�̒����헪�����铮�����L�����Ă����B�o�ώY�ƏȂ̓G�l���M�[��{�v��̌�������ƂƂƂ��ɁA2050�N�̃G�l���M�[����݂̍���Ɋւ��錟����i�߂Ă���A���̐��ʂ��헪�̋c�_�ɂȂ������l���B �o�Y�ȂƊ��Ȃ͊��ɒ����헪�Ɍ����A�����������Ă�����̂́A�r�o�팸�̎�@�Ɋu���肪����ق��A�O���Ȃ����N����Ǝ��̌����ɓ����o�����B ���N�x�̑����i�K�Ő��{�����̂��荇�킹��Ƃ��n�܂錩�ʂ������A�����ɂ͋Ȑ܂��\�z�����B �������ʃK�X�r�o�팸�Ɍ������V���ȍ��ۘg�g�݂ł���p������ł́A�Y�Ɗv���O�Ɣ�ׂ������I���̋C���㏸���Q�x�ȓ��ɗ}����u2�x�ڕW�v�����荞�܂ꂽ�B����2050�N����z�肵���u������r�o���W�헪�v��2020�N�܂łɍ��A�ɒ�o����K�v������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��IRENA��2020�N�ɂ͑��z���ƕ��͔��d�̈ꕔ�́A���ΔR���������R�X�g����������Ɨ\�� ���E150�J���ȏオ��������IRENA�i���ۍĐ��\�G�l���M�[�@�ցF International Renewable Energy Agency�j�́A�Đ��\�G�l���M�[�d���̃R�X�g�������܂Ƃ߂��������\�����B 2010�N���猻�݂܂ł̖�7�N�ԂŁA���z�����d�̃R�X�g��73���A���㕗�͔��d�̃R�X�g�͖�25���ቺ���Ă���A�Đ��\�G�l���M�[�͒����ɋ����͂̂���d���ɂȂ����Ƃ����B 2017�N�̐��E�ɂ����鑾�z�����d�̉��d���ςɂ��ϓ������d�����iLCOE�j��10�Z���g/kWh�A���㕗�͔��d��6�Z���g/kWh�A���͔��d��5�Z���g/kWh�A�o�C�I�}�X����ђn�M���d��7�Z���g/kWh�������Ǝ��Z�����B ���ł́A���z�����d�ɂ��ẮA�����2020�N�܂łɃR�X�g���������錩�ʂ����Ƃ����B����ɁA���㕗�͔��d�����N�܂ł�5�Z���g/kWh�܂ʼn�������Ƃ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������ȁA�Z��̎������ƌ����Ȃnj��N�֘A���ۂ̌��،��ʂȂǂ��Љ� ���y��ʏȂ́A�Z��̎������ƌ����Ȃnj��N�֘A���ۂɂ��āA�����f�[�^�Ɋ�Â��A���،��ʁi��2��j�Ȃǂ��Љ���B ���Ȃ́A����26�N�x����J�n�����X�}�[�g�E�F���l�X�Z����i���Ƃɂ����āA�u�Z��̒f�M���Ƌ��Z�҂̌��N�ւ̉e���Ɋւ��钲���v�ւ̎x�����s���Ă���B���\�������،��ʂ́A�����̒��ԕ̈ꕔ�B����28�N�x�܂łɓ���ꂽ�����f�[�^�i���C�O3,441�l�E���C��676�l�j����A �@1�j�N�����̎����̒ቺ�ɂ�錌���㏸�ւ̉e���́A����ɂȂ�قǑ傫������ �@2�j�����̒Ⴂ�ƂɏZ�ސl�قǁA�N�����̌������������ƂȂ�m������������ �@3�j�����̒Ⴂ�ƂɏZ�ސl�قǁA�����d���w���ƐS�d�}�ُ폊�����L�ӂɑ������� �@4�j�f�M���C��ɋN�����̌������L�ӂɒቺ���邱�ƁA�Ȃǂ̒m������������Ƃ����B ���̒����́A����30�N�x�܂Ōp�������\��B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���Y�ƊE�̉������ʃK�X�팸�A�v���ʂ������鉻�o�Y�� �o�ώY�ƏȂ́A�������ʃK�X�̔r�o�팸�Ɍ����A�O���[�o���E�o�����[�`�F�[���ł̎Y�ƊE�̐��i�E�T�[�r�X�̍v���ʂ��u�����鉻�v���A��Y�f�Z�p�̕��y���x�����邽�߂̎w�j�����肷��B �팸�v���ʂ��ʓI�ɕ]���ł���悤�ɂ��A����܂ł���̂������ƊE���Ƃ̍l�����ꂷ��B�o�Y�Ȃ̗L���҉�ł́A�v���ʂ̒�`�E�Z����@������A�_�_�������ꂽ�B�N�x���܂łɎw�j���܂Ƃ߂�\��B ���̎w�j�́A��Ƃ�ƊE�����i�E�T�[�r�X�������O�ɓW�J����ۂ́u�팸�v���ʁv���ʉ����邽�߂ɍ��肷��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���G�A�R�������i�ފw�Z�A�ȃG�l�ǂ�����H ���ȏȁA�L���҉�c���� �����Ȋw�Ȃ́A���������w�Z�E���Z�ɂ�����ȃG�l��𐄐i���邽�߁A��̓I�ȑ��@�⋳��ψ���ɂ�����g�D�I�Ȑ��i����Ȃǂɂ��Č�������L���҉�c�������B ��������ł́A����ψ���ɂ�����g�D�I�ȏȃG�l���M�[���i����̂ق��A�w�Z�ɂ�����K�ȃG�l���M�[����P�ʊǗ��̍l�����A�w�Z���Ŏ��g�ނׂ��ȃG�l���M�[����̓I�ȏȃG�l���M�[���@�Ȃǂɂ��Č�������B 2017�N�x�́u�����w�Z�{�݂̋i��[�j�ݔ��ݒu�v�������ʂɂ��ƁA���������w�Z�ɂ�����ݒu����41.7���B���Z��49.6���������B ����ψ���ł́C�w�Z�{�݂̍��@�\���E���@�\����G�A�R���̐ݒu���ɂ��G�l���M�[�g�p�ʂ̑���������C�G�l���M�[����P�ʂ̉��P�ɋꗶ���Ă����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ł����p�S�I �������N��1000�l�����ŔM���ǂ����� �u�����s�ɂ����铀���Ǘ�̌����v�ɂ��ƁA5�N�Ԃɓs���̓����ǗႪ83������A���ʂł�12�`2����3�����őS�̂�77���A�N��ł�40�`50�オ�S�̂�63���A�j���ʂł͒j����89�����߂Ă���B�������݂�ƁA���O�E�����ł�����Ԃ�51���ł����Ƃ������B�C��11���ł������Ŏ��S�Ⴊ����B ���S�����͑���5����ɔ����������A�ߑO3�`9���܂ł̎��ԑт��S�̂̔����ȏ���߂Ă���B �����œ�������P�[�X�͍���҂ɑ����A������u�V�l����̉��ǁv�������Ǝv����B����҂͏����A�����ɑ��銴�o���݂��Ȃ�B �o�T�u�E�F�U�[�j���[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2018/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���d�͂��㉺�����������Ǘ��ł���IoT�v���b�g�t�H�[���A�T�[�r�X�J�n �ߔN�A���q����ɂ��J���l���̌����ŁA�Љ�C���t���ɂ�����n���^�]���E�Z�p�҂������Ă��邱�Ƃ�A�Ɩ��̌����������߂��Ă���B �����������A�O�H�d�@�́A�Љ�E�d�̓C���t���ݔ��̉^�p�E�ۑS�Ɩ��̌�������ɍv������AIoT��AI�Z�p���̗p�����V�J����IoT�v���b�g�t�H�[�������p�����\�����[�V���������B ���̃v���b�g�t�H�[���́A�㉺�����E�����{�݁E���H�E�͐�E�S���E�d�́i���d�A���z�d�A���q�́A���������E�����j����̃C���t���ݔ��𐧌�E�Ǘ������ՂƂȂ���̂ŁA�V�X�e���[����N���E�h��ł̃T�[�r�X�Ƃ��Ē����B �����́A 1. ���܂��܂ȃC���t���ݔ�����f�[�^�����W���A�~�ρE���� 2. AI�Z�p���p�̕��͋@�\�Őݔ��^�p�v��œK�����x�� 3. ���x�ȃZ�L�����e�B�[�@�\ �Ȃ� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ڋq�I�Ȃ��V�d�͂��D���^�u�g�p�ʖ�킸�����v����� �ƒ�����d�͏����s��ŁA�g�p�ʂ̑��ǂɂ�����炸�����ȗ����v���������V�d�͂��D�����ێ����Ă���B ������т��^�[�Q�b�g�ɎQ�������V�d�͂ł��A������ь����̃v������lj�����ȂǁA�헪���������������o�Ă���B�g�p�ʂ͌��ɂ���ĕς�邽�߁A�����̕���_������v�����ł̓X�C�b�`���O�i�����ҕύX�j�̃����b�g��i�����Â炢�B�u��Α����Ȃ��v�Ƃ������S������邱�ƂŁA����҂̐S������ł���悤���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���d�͏����肩��P�ނ����Ђ��B�G�l�`�F���W���P�ގx���T�[�r�X �G�l�`�F���W�́A�����d�C���Ƃ̓P�ނ��x������T�[�r�X���n�߂�B�P�ނ��鏬���d�C���Ǝ҂�������ڋq���A�d�͎��v�J�[�u�̓����ɍ��킹�ăO���[�v���������p����B ������͎��v�J�[�u����ɔ����f���₷���Ȃ�A�����͔��p���i�̌���ɂȂ�����B����҂̕��S�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA������͓P�ގ��Ǝ҂̗����̌n�������p���B����҂̃X�C�b�`���O�i�����ҕύX�j�葱���͕s�v�ŁA����҂̓��ӂĎ��ƎҊԂōs���B�V�T�[�r�X�u�d�͎��ƓP�ގx���R���T���e�B���O�v�͐�����V�^�̂��߁A�P�ގ��Ǝ҂ɔ�p���S�͔������Ȃ��B�G�l�`�F���W�͔��p�z�����V�����B ���p�O���[�v��́A�x�[�X�d���̑������d�͉�Ђɂ͖�Ԏ��v�̑����ڋq���Љ�A���z�����d�������͂ɑg�ݍ��ޏ����d�C���Ǝ҂ɂ͒��Ԃ̃s�[�N���v�������ڋq���Ă���B�O���[�v���ƂɃI�[�N�V�����ɂ����邱�ƂŁA���p���i�̍ő剻��_���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������I�ɉƓd����A�f�}���h���X�|���X�ł���HEMS �����d�͂����� �����d�͂ƃf���\�[�́A�ƒ�ɂ����鋋���̗����E���K���Ȃ킸�ɁA�d�͎��v��}������V�X�e�����J�����A2018�N1�����爤�m�����Ŏ��؎������J�n����B �d�͉�Ђ́A�ď�̓d�͎g�p�ʂ��������ԑтȂǂɁA�n��̓d�͎��v�}����Ɏ��g�ݕK�v������B����A�ƒ�̃G�l���M�[�̌����鉻��Ɠd�𐧌䂷��HEMS�̓�����A�G�R�L���[�g�̕��y���i��ł���B���������V�X�e���́A�����d�͂̎��v�����V�X�e���ƃf���\�[��HEMS����p�V�X�e����A�W���邱�Ƃɂ��A�G�R�L���[�g��S�ً������Ő��䂵�A�ƒ�̓d�͎��v��������́B���m���L�c�s���܂ގ���6�s�̉ƒ�i�V�X�e���ݒu�F40���A��r�ΏƁF40���j�Ƀ��j�^�[�ɂȂ��Ă��炢�A���V�X�e���������ɗ^����e����d�͎��v�̒������ѓ���������Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��������X�}�[�g�r���ʼn^�p��40���팸��--�\�t�g�o���N�Ɠ����v���Ɩ���g �\�t�g�o���N�Ɠ����v�́AIoT��{�b�g�Ȃǂ����p����������X�}�[�g�r���f�B���O�̐v�J���Ɍ������Ɩ���g�ō��ӂ����Ɣ��\�����B ��g�ɔ����A�����Ŏ��؎����������J�n����B���������̎�ȊT�v�́A 1. �l����͂Ɗ��Z���T��l���Z���T�Ȃǂ�IoT�Z���V���O�ɂ��V�������[�N�v���C�X�f�U�C�� 2. IoT�ƃ��{�b�g�̓������l������������X�}�[�g�r���f�B���O�̋������� 3. �e��IoT�Z���T�����p�����r���̃��C�t�T�C�N���}�l�W�����g�œK������ �r���̑ϗp�N����60�N�Ƃ���Ɖ^�p�R�X�g�͌��ݔ��5�{�B����̎��g�݂̎��Z�ł͂����40���قǍ팸�ł���ƌ����ށB �o�T�uCNET Japan �v |
|
|
| ���A�X�N���A�ăG�l���B��100���E�d�C�����ԗ�100���̗�����ڎw�� �A�X�N���́A2030�N�܂łɎ��Ə�����r�o����CO2�Ɣz���ɂ������CO2���[���Ƃ���uRE100�v�ƁuEV100�v�Ƃ���2�̍��ۃr�W�l�X�C�j�V�A�`�u�։��������B �����ɂ��A����Ȃ��ƊԘA�g�𑣐i���A���ޗ����B����ڋq�ւ̏��i�ג��܂ŁA�T�v���C�`�F�[���S�̂ł�CO2�팸��ڎw���u2030�NCO2�[���`�������W�v������ɑ��i�����Ă����Ƃ��Ă���B ���Ђł́uRE100�v�����ɍۂ��A���ԖڕW�Ƃ��āA2025�N�܂łɖ{�Ђƕ����Z���^�[�ł̍Đ��G�l���M�[���p����100���ɂ��邱�ƁA�܂�2030�N�܂łɎq��Ђ��܂߂��O���[�v�S�̂ł̍Đ��G�l���M�[���p����100���ɂ��邱�Ƃ�錾�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���e�h�s�I���������Ћ����Z��̗]��d�͂�ϐ��n�E�X������A�Đ��G�l�P�O�O�� �ϐ��n�E�X�́A40�N�܂łɎ��ƂŎg���d�͑S�ʂ��Đ��G�l�ɂ���Ɛ錾�����B�B���̂��߂ɉƒ�̑��z���p�l���̓d�C�B����B 2019�N�ɂȂ�ƌŒ艿�i������萧�x�iFIT�j�ɂ�锄�d���Ԃ��I���ƒ낪�o�Ă���B���Ђ��̔����AFIT���I�������Z��瑾�z���R���̓d�C�����A�Đ��G�l100������ڎw���B �Đ��G�l�̑�ʓ�����ڎw����Ƃ��������邪�A��̍�܂œ��ݍ��͓̂��Ђ����߂āBFIT���I���������z�����d�̊��p��̈�ŁA���z���̕��y�ɂ��v������Ƃ����B�d�͗Z�ʂ�u���b�N�`�F�[���Z�p������A�ƒ납��Đ��G�l�d�C�B���₷���Ȃ�B �o�T�u�Z��Y�ƐV���v |
|
|
| ���Z�u��-�C���u���Ɠ����A�S�X�܂ɂ�����G�l���M�[�f�[�^���W��E���͂��A�ȃG�l���M�[��Ȃǂ֊��p���i �Z�u��-�C���u���́A�����ƁA�X�܂̓d�͎g�p�ʂ�ݔ��̉ғ��Ƃ������G�l���M�[�f�[�^�̗L�����p�Ɍ����A���n���J�n�����B ���㗼�Ђ́A�e��G�l���M�[�f�[�^�̏W��E�����A����ɂ͕��́E���p���邱�ƂŁA�e�X�܂ɂ���������I�ȓd�͎g�p�𑣐i����ȂǁA���g�݂�i�߂�B ���e�Ƃ��āA�s���ŋ`���Â�����G�l���M�[�g�p�ʂ�CO2�r�o�ʍ팸�Ɋ֘A����e����ނɂ��āA�����ւ̋Ɩ��ϑ������B��̓I�ɂ́A��2���X�܂ɂ���ԃZ�u��-�C���u���S�X�܂̓d�͂̎g�p�ʂ̂ق��A���܂��܂ȏȃG�l�{��Ƃ��̌��ʂƂ������G�l���M�[�f�[�^�����W�E�ꌳ�Ǘ�����f�[�^�x�[�X�V�X�e�����\�z���A���ۂ̃f�[�^�̓o�^�E�W�v�ɂ�����܂ŁA�s���ւ̕��ނɌW���A�̋Ɩ����������s����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������̔M�𗘗p���a�@�̗�g�[���ғ��ցE���ƋƎ҂����̋��� �����M���g�[�ɗ��p���悤�ƁA���ƃG�l���M�[�֘A���Ƃ�W�J����V�[�G�i�W�[�́u�����M���p����v����������B�z�K�ԏ\���a�@�ł̗�g�[�Ɋ��p������̂ŁA���N4���ғ���ڎw���B���p���Ԃ͗��N�x����15�N�ԁB 2015�N�̉������@�����ŁA���ԋƎ҂��������{�݂ʼn����M�̗��p���\�ɂȂ����B�����͔N�Ԃ�ʂ��ĉ��x�����肵�Ă���A����A���p����ӏ��̐����͉���������Ă��邱�Ƃ�����u27�A28�x�ō������肵�Ă���v�Ƃ����B�����Ǔ����ɒ��a10�~���̍̔M��138�{��ʂ��ĕs���t���z�����A���̔M���g�[�ɗ��p����B�a�@�ł͌��ݒ��̊Ǘ������͂��߁A�~���~�}�Z���^�[�ȂǑS�قŗ�g�[�⋋���ȂǂɊ��p����\��ŁA10���قǁA�G�l���M�[�̌��������}��錩���݁B���Ɣ��6��2000���~�B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���u���g���ɐl�דI�v���v���A�Đ���ɉe���� �Ċ��ی��(EPA)�Ȃǂ́A�u20���I������̋C���㏸�́A�l�Ԋ����ɂ�鉷�����ʃK�X������ł���\�����ɂ߂č����v�Ƃ�����\�����g�����v�哝�̂����g����}�~���邽�߂̍��ۏ��u�p������v����̗��E��\�����Ĉȍ~�A�Đ��{�����߂Ă܂Ƃ߂����g���Ɋւ���Ȋw�I�ȕ��ŁA�l�דI�ȉ��g�����F�߂�ꂽ���ƂɂȂ�B���g����ɏ��ɓI�ȃg�����v�哝�̂̐���ɉe����^����\��������B ���͂ق�4�N���ƂɕĐ������C��ϓ��Ɋւ���ŐV�̏��I�ɂ܂Ƃ߂���̂ŁA4��ڂ̍����EPA��čq��F����(NASA)�Ȃ�13�Ȓ������͂����B���́A20���I���߂��琢�E�̋C������1�x�㏸���Ă���Ǝw�E�A�u�i��_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X�ȊO�Ɂj�����͂̂���ق��̗v���͂Ȃ��v�ƌ��_�Â����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���}�C�N���O���b�h���Ɖ��A���͒~�d�E�l��� �}�C�N���O���b�h�̏��Ɖ��ɂ́u���v�ƊԂ̃G�l���M�[����̊������v�Ɓu�~�d�r�ȂǍ\���ݔ���̒ጸ�v�������Ƃ�������A�č��A���{�Ȃ�13�J���̊֘A�c�̂���������u���ۃX�}�[�g�O���b�h�A��(GSGF)�v�i�{�������V���g���j�����̂قǂ܂Ƃ߂��B �ȈՂȌ��ϋZ�p�ł���u���b�N�`�F�[�������v�ƊԂ̓d�͎���ɓK�p���Ď���R�X�g����������A�~�d�r�⑾�z�����d�p�p���[�R���f�B�V���i�[(PCS)�Ȃǂ̍\���ݔ����u���j�b�g���v���Đ��Y�R�X�g�������邱�Ƃ��L���Ƃ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���l�K���b�g����̃K�C�h���C������グDR�ݒ�E�������ȂǂɑΉ� �o�ώY�ƏȂ́A���v�Ƃ��ߓd�����d�͗ʁi�l�K���b�g�j�ɑ��d�͉�Ђ��Ή����x�����u�l�K���b�g����v�Ɋւ���w�j���������K�C�h���C�������肵���B ����̉���ł́A�f�}���h���X�|���X�iDR�j�̂����A���v��������u�グDR�v�̃x�[�X���C���ݒ���@��A��ʑ��z�d���Ǝ҂����������̂��߂Ƀl�K���b�g�B����ꍇ�́A��p�ƕ։v�̕s��v�����邽�߂̃l�K���b�g�������̍l�����Ȃǂ�lj������B �܂��A���z�����d�E�~�d�r�E�f�}���h���X�|���X�iDR�j�Ȃǎ��v�Ƒ��̃G�l���M�[���\�[�X�����p�����G�l���M�[�E���\�[�X�E�A�O���Q�[�V�����E�r�W�l�X�iERAB�j�S�̂�ΏۂƂ������̂ɂ��邽�߁A���̂��u�G�l���M�[�E���\�[�X�E�A�O���Q�[�V�����E�r�W�l�X�Ɋւ���K�C�h���C���v�ɕύX�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցA�f���}�[�N�͒E�Y�f���Ő��E���������Ă���ƕ� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A�f���}�[�N�͌o�ς̒E�Y�f���Ő��E���������Ă���Ƃ��铯���̃G�l���M�[����Ɋւ���������\�����B �����̓d���\���͉ߋ�20�N�Ԃō��{�I�ɕω����Ă���A�ΒY�Η͔��d�̒u�����i�݁A���݂ł͕��͂ƃo�C�I�G�l���M�[����v�d���ƂȂ��Ă���B������2030�N�܂łɃG�l���M�[����̔����ȏ���Đ��\�G�l���M�[�ł܂��Ȃ��A2050�N�܂łɉ��ΔR�����g�p���Ȃ���Y�f�^�Љ����������Ƃ����ڕW���f���Ă���BIEA�ɂ��ƁA�����͂����̖ڕW�B���Ɍ��������ɐi��ł���Ƃ����B���́A�E�Y�f��������ɐi�߁A�G�l���M�[�V�X�e��������@��ɂ��Ȃ���d�v�ȗ̈�Ƃ��āA 1. �d���\���ɐ�߂�Đ��\�G�l���M�[�̔䗦�����݂�45%���獂�߂���@�� 2. �M�����E�Y�f��������@ �Ƃ����֘A����2�̈�ɏœ_�ĂĂ���B ���ł́A�R���Ɠd�͂ւ̓K���ȉېłȂǂ̌����Ȑ����[�u�A�A�����傩��̔r�o�팸�̂��߂̂���Ȃ���g�݂̕K�v�����w�E�����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��2016�N�x�i����28�N�x�j�̉������ʃK�X�r�o�ʁi����l�j�ɂ��� 2016�N�x�̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂ�13��2,200���g���ŁA�O�N�x��0.2%���i2013�N�x��6.2%���A2005�N�x��4.6%���j�B �O�N�x����̌����v���Ƃ��ẮA�ăG�l�̓����g��⌴���̍ĉғ��Ȃǂɂ��A�G�l���M�[�N����CO2�r�o�ʂ������������ƂȂǂ���������B �O�N�x�^2013�N�x�̑��r�o�ʁi13��2,500���g���^14��900���g���j��2016�N�x�̑��r�o�ʂ��r����ƁA�I�]���w�j������̑�ւɔ����A��}����ɂ����ăn�C�h���t���I���J�[�{���ށi HFCs�j�̔r�o�ʂ�������������ŁA�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��⌴���̍ĉғ����ɂ��A�G�l���M�[�N����CO2�r�o�ʂ������������ƂȂǂ���A�O�N�x��0.2%�i300���g���j�A2013�N�x��6.2%�i8,700���g���j���������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ����P�z�����D�A�Œቿ�i�͂P�V�~�Q�O�K �o�ώY�ƏȂ́A�o��2��L�����b�g�ȏ�̎��Ɨp���z����ΏۂɎ��{������P��̓��D���ʂ����\�����B8�ЁE9�������D���A�Œቿ�i��17�~20�K�������B ���D�ʁA��14���L�����b�g�ɂƂǂ܂����B2017�N�x��FIT�i�Đ��\�G�l���M�[�Œ艿�i���搧�x�j�̔�����艿�i�ɔ�ׁA4�~���x�̉��i�ጸ�ɂƂǂ܂����B���N�x�ȍ~��2����D�����{�����\��ŁA�o�Y�Ȃł͌��ʂ܂��A�ۑ�̒��o��i�߂���j�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2017/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A����PLC�Z�p�uHD-PLC�v�̗��p�͈͊g��Ɍ������؎������J�n ���Ђ́A����PLC�Z�p�uHD-PLC�v�̗��p�͈͊g��Ɍ����A���؎������J�n����B ���̎��؎����́A�H����K�͎{�݂�ΏۂɃ��[�^�[�n�̓��͗p�O���d�͐���ALED�Ɩ��Ɏg�p�����O���d�͐��Ȃǂ�ʐM�p�Ƃ��ė��p����B�����̓d�͐��𗘗p���邱�Ƃɂ��A�V���ȒʐM���̔z�����s�v�ƂȂ�A�����̕s���ꏊ�ɂ����p�ł���B �܂��A����PLC�̍��ۋK�i�ł���IEEE 1901�ɁA�}���`�z�b�v�Z�pITU-T G.9905��Ή������邱�Ɓi�ȉ��A�uHD-PLC�v�}���`�z�b�v�j�ŁA�ڑ��[����1000��K�͂̃V�X�e���������ł���B����ɂ��A�����̒[���Ԃ��z�b�v�����A�d�͐����g������Km���x�̒������ʐM���\�ƂȂ�A��K�͎{�ݓ��ł̃l�b�g���[�N���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��BEMS����CO2�Z���T�[�A�K�v�Ȏ��������C���\�� ���c���쏊�́ABEMS����CO2�Z���T�[�V���[�Y�����̂قǏ��i�������B ��ɁA�r���p�_�N�g���ɐݒu���A���j�^�����O���邱�ƂŁA�K�v�ȂƂ��������C���s���ȂǁA�r���̏ȃG�l�Ɋ��p�ł���Ƃ����B2017�N9������ʎY���J�n�����B �V�^�Z���T�[�́A�Ǝ��̌��ʐ��A���S���Y����2�g���i����p�A���t�@�����X�p�j NDIR�iNon-Dispersive Infrared�A�U�^�ԊO�z���j�����ɂ�鎩���Z���@�\�ɂ��A�������萫�ƍ������萸�x��L�������e�i���X���̌��オ���҂ł���Ƃ��Ă���B����́A���܂��܂Ȑ���V�X�e���Ƃ̐e�a�������シ�ׂ��A�o�̓C���^�t�F�[�X�̊g�[���s�����j���B��ȃX�y�b�N�́A�����0�`50���A����͈�0�`2000ppm�E0�`3000ppm�A�O�`���@��134mm�~81mm�~51mm�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ϐ��n�E�X�A���Ɨp�d�͂�100���ăG�l��2040�N�܂ł̖ڕW�\ ���Ђ́A�Đ��\�G�l���M�[100���̗��p��ڕW�ɁA���E�̊���i��Ƃ��Q�����鍑�ۃC�j�V�A�`�u�uRE100�i�A�[���C�[100�j�v�ɉ��������Ɣ��\�����B ��̓I�ȖڕW�Ƃ��āA2040�N�܂łɎ��Ɗ����ŏ����d�͂�100�����Đ��\�G�l���M�[�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���B 2019�N�x��菇��FIT���x���I�����邽�߁A�Z��̃I�[�i�[�Ȃǂ̗]��d�͂Ђ��w�����A�����œ���ꂽ�d�͓͂��Ђ̎��Ɗ����ŏ���A�d�͂̍Đ��\�G�l���M�[��������������B���Ђ�2016�N�x�̎��Ɗ�����120,533MWh�̓d�͂�����Ă���B �Ȃ��A�uRE100�v�ɂ́AIT���玩���Ԑ����܂ŕ��L���Ǝ���܂ށA���E��100�Јȏ�̊�Ƃ���������B���{��Ƃ̉����͓��Ђ�2�ЖڂŁA���ƊE�ł͍����ŏ��߂ĂƂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���f�[�^�Z���^�[�A��AI�EICT�Z�p�Ő��䂵����ȃG�l�ł��邩�H NTT�f�[�^�ANTT�t�@�V���e�B�[�Y�A�C���e���AFuture Facilities ��4�Ђ́ANTT�f�[�^�����L����s���̃f�[�^�Z���^�[�ŁA�ݔ��̏ȃG�l���M�[���Ɖ^�p���x����ڎw�������؎������J�n����B �f�[�^�Z���^�[�̋^�]����ɂ����āAICT�@�킩��ݔ��܂ł��܂߂��A�g����ɂ��S�̍œK���ɂ���āA�i�������G�l���M�[�E�^�p�R�X�g���܂߂��R�X�g�ጸ��}����́B�f�[�^�Z���^�[�r�W�l�X�̋����͋����Ɗ����גጸ��ڎw���B NTT�f�[�^��3�Ђ́A������A�f�[�^�Z���^�[�ł�IT�V�X�e���̈�Ɛݔ��i�t�@�V���e�B�j�̈�̉^�p�Ǘ��̘A�g�ɂ��S�̍œK���ɉ����AIoT�Z�p�����p�����̏�\�m��C�ۏ��Ȃǂ̃r�b�O�f�[�^�ƘA�g�����^�]����Ȃǂ̌������s���A�f�[�^�Z���^�[�̊��S�^�p�������Ɍ��������g�݂𐄐i���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��ODP�����[���AGWP1�����̐V��}�@���Ɏq��2018�N���琶�Y ���Ɏq�́A�����O�̊��K���ɑΉ������V��}��2018�N���߂ɏ��Ɛ��Y�̊J�n��\�肵�Ă���Ɣ��\�����B���̐V��}�uAMOLEA�i�A�����A�j�v�́A2017�N10���ɕč��g�[�Ⓚ�w��iASHRAE�j�̏��F���擾�����B ���̐V��}�́A�^�[�{���Ⓚ�@�E�o�C�i���[���d�@�E�r�M����q�[�g�|���v�Ȃǂ���v�p�r�Ƃ����s�R���̗�}�B�]���̗�}HFC�|245fa�̑���i�Ƃ��āA�����ȏ�̗�}���\����萫�������Ȃ���A�I�]���j��W��ODP�͎����[���ɁA�n�����g���ւ̉e���������n�����g���W��GWP�́A1,000����1�ƂȂ�u1�����v�܂ŗ}�����B �܂��A�V�K�@��ւ̓K�p�����łȂ��A�����@��ł��d�l�ɂ���Ă͑啝�ȉ��C�Ȃ��A���̐V��}�Ɍ����ł���B���̐V��}�́A�����O�̑����̋@�탁�[�J�[���琫�\�������]������Ă���A�`����M�V�X�e�����A���łɎ����^�[�{���Ⓚ�@�ւ̗̍p�����肵�Ă���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���听���݁A�̌��ƎՌ��𗼗�����V�^�u���C���h�J�� �V�^�u���C���h�́A�̌������u���C���h�㕔�ɐݒu�A�����ɂ͈�ʓI�ȃu���C���h�Ɠ��l�̎Ռ�����z�u�����B�Ռ����œ��˂��Ղ�A�����ɍ̌������牜�s��15���[�g�����x�̓V��ʂ֘A���I�ɑ��z�������Ƃ��ł���B���͎�ɓV������֏Ǝ˂���邽�߁A���p�҂͑��z���̂܂Ԃ����������邱�Ƃ͂Ȃ��B �̌����̉H�͉��ʂ���Ɍ����悤�ɂقڐ����ɔz�u�B���ʉ��H���{�������ʂő��������������V������ɔ��˂�����B �J�͎蓮�ōs���A��ʓI�ȁu�d���^�̌��u���C���h�v�Ɣ�ׂē�����p�͔��z���x�ōςނƂ����B�܂��A�V�^�u���C���h�ɓ������100�Ƃ���ƁA������15���[�g�����ꂽ�ӂ�܂ł̋�Ԃɓ͂�����60���x�ɂȂ�B�V�^�u���C���h�ɐ�ւ����ꍇ�A�Ɩ��Ɏg���G�l���M�[��10�`15���팸�ł���Ƃ������B �o�T�uSankeiBIz�v |
|
|
| ���҂̂U���u�d�͐�ւ��\��Ȃ��v�^�����A�����R���ӎ����� ���{���������g���A����i���{�����A�j�͑S���̑g������ΏۂɁA9���Ɏ��{�����d�́E�K�X�S�ʎ��R���Ɋւ���ӎ������̌��ʂ��܂Ƃ߂��B �d�͂ł́u�d�͉�Ђ�d�͗������ւ���\��͂Ȃ��v�Ƃ̉���6���ɏ�����B���{�����A�ł́A��ւ��̑��i�Ɍ����ẮA���͂��闿�����j���[�̒�Ă����҂ւ̕�����₷�������ۑ�ɂȂ�Ǝw�E���Ă���B �d�͉�Ђ��u��ւ����v�Ɖ����̂́A������2016�N5����3.7���������̂ɑ��A�����13.5���ɑ����B�����ЂŁu���j���[���ւ����v��5.6���ƂȂ�A���v�Ŗ�2������ւ����s���Ă����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������d�A��}�s�v�̎��C�q�[�g�|���v20�N�ɐ��i���� �����d�͂�2020�N���߂ǂɊ����ׂ��y������q�[�g�|���v�Z�p�����p������B �n�����g���̉e������������}��p�����q�[�g�|���v��20�N�O��̎��p����ڎw���ق��A��}�s�v�Ȏ��C�q�[�g�|���v��20�N�ɐ��i������B���C�q�[�g�|���v�͌����_�Ŏ��p������Ă��Ȃ��B �V��}�͒n�����g���W���iGWP�j��1�ȉ��̃n�C�h���t���I���I���t�B���iHFO�j�����p������B ���C�q�[�g�|���v�̓}���K���S�n�̎����̂��l�I�W�����Ȃǂɋ߂Â���Ɖ��x�㏸���A��������Ɖ��x�ቺ���鐫���𗘗p����B�q�[�g�|���v�ɑ����������₵�A�␅�����≷�x�㏸�������̗�p�Ɏg���B�����������\�B���i���Ɍ����q�[�g�|���v���狟�����鉷���Ɨ␅�̉��x�����A���p���x����40���Ɍ��シ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����R�d�́A���R�G�l100���̓d�͏����T�[�r�X�J�n�u�Ώ؏��v�Ŏ��� �Đ��\�G�l���M�[�̔��d���ƂȂǂ��s�����R�d�͂́A�V���ɓd�͏������ƂɎQ�����A�u���R�G�l���M�[100���̐��E�v��ڎw���d�̓T�[�r�X�u���R�d�͂̂łv�̒��J�n����B ���̃T�[�r�X�Œ���d�C�́A�����I�Ɂu100�����R�G�l���M�[�R���v�uCO2�r�o�ʃ[���v�ƂȂ�悤�A�u�Ύs��i�Ή��l����s��j�v�ŋ����d�͑S�ʕ��́u�Ώ؏��iFIT�܂ށj�v���w������B �Ώ؏��Ƃ́A�Đ��\�G�l���M�[�⌴�q�͂Ȃǂ̔Γd���ɂ���Ĕ��d���ꂽ�d�C�̊��I�ȉ��l�i�Ή��l�j���؏��ɂ������́B �܂��A���ЃO���[�v���ݒu���鑾�z�����d���E���͔��d���E�����͔��d���Ȃǂ̔��d������̓d�͋������s���A�����I�ɂ͂��̊��������߂Ă����v��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�C�s�v�̗�p�V�X�e�����J���A�r���Ȃǂ̓d�͍팸�� �ăX�^���t�H�[�h��w�́A���˗�p���ۂ𗘗p�����d�͂�p���Ȃ���p���u���J���A�������Ă���ƕ����B �����̋�Ⓚ�@�ɐڑ����\�ŁA��ʓI�ȏ��ƃr���ł̓V�X�e���̓����ɂ��A����d�͂�18�`50�����x�팸�ł���Ƃ���B ����J�����ꂽ��p�V�X�e���́A����Ȍ��w�ʂ������ŁA�V�X�e���ɓ��˂�������˂��A�����ɃV�X�e������O���ւ̔M���˂��\�ƂȂ�A�������ԑт̗�p��B�������B���˓������ł��A�V�X�e�������𗬂���}���O�C���x�ȉ��ɗ�p����B ��p�V�X�e���̃J�M"Photonic radiative cooler"�́A�V�X�e������C�֔M���˂���g�����u��C�̑��v�ł���8�`13��m�Ɍ��肵�A���̑��̔g�������قڑS�Ĕ��˂���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u�����O�C�����@�v��JIS���o�Y�Ȃ̐V���x�Ŏs��J��E�n�����x�� �o�ώY�ƏȂ́A���{�H�ƕW��������iJISC�j�����Ǝ҂����Ă̂������e�[�}�ɂ��āA�u�V�s��n���^�W�������x�v�����p���ĕW�������s�����Ƃ����肵���Ɣ��\�����B ���̐��x�̊��p�����肵���e�[�}�́A�_�C�L���H�Ƃ���Ă����u�q�[�g�|���v�f�V�J���g���������O�C�����@�Ɋւ���W�����v�B �q�[�g�|���v�Z�p�ƃf�V�J���g�Z�p��Z�����A�]���̃r���ō�������O�C�̎��x�R���g���[�����\�ɂȂ�A���K�ȋ�����ԂƏȃG�l�𗼗������鍂�����Ȏ��x�R���g���[�����ł���u�����O�C�����@�v�̐��\�����]���Ȃǂ�W����������́B ����́A���{�K�i����iJSA�j�����č쐬��AJISC�ɂ����ĐR�c���ꂽ�̂������W���iJIS�j�ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�G�l���M�[�w��ŏȃG�l���M�[�E����ҍs������� �䂪���ł́u�����G�l���M�[�������ʂ��v��2030 �N�܂ł�5,030 ��kL�̑傫�ȏȃG�l���M�[�ڕW���f���Ă���A�ȃG�l���M�[�̑��i���i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B �ȃG�l���M�[�̕���ŁA��������������W���s���A�n�[�h�i�@��j�E�\�t�g�i����ҍs���j�̗��ʂɂ�����ȃG�l���M�[���i����������K�v������B ���̂悤�ȏ܂��A�ȃG�l���M�[�Ɋւ��Z�p�҂�Y�w�����̘A�g������w���i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�u�ȃG�l���M�[����v�Ȃ�тɁu��������v�����A�V���Ɂu�ȃG�l���M�[�E����ҍs������Ƃ��Ċ������s�����ƂɂȂ����B ����ł͕�������W���Ă���B�o�^�͖����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����C�t�X�^�C���̕ϊv��n�o���A�ȃG�l�Ɍq����i�b�W���� ���ȁA�d�͉�ЁA�I���N���Ȃǂ��A��ʂ̉ƒ��ΏۂƂ����A�G�l���M�[�̎g�p�Ȃǂ�m�点����u�ȃG�l���|�[�g�v�ŁA�ȃG�l�ӎ��̌����ȃG�l�s���̑��i�ɁA�ǂ̒��x�L���ł��邩���E������B �{���|�[�g�ɂ́A�q���悲�Ƃ́u�d�C�E�K�X�̂��g�p�ʔ�r�v�A�u���q���܂ɍ������ȃG�l�̃R�c�v�Ȃ��ƒ�ł̏ȃG�l���M�[�Ɋ��p�ł������͂���B ����29�N12���`����30�N3���܂ł̌v4��A�u�悭�������ƒ�Ƃ̃G�l���M�[�g�p�ʔ�r�v�u�ȃG�l�̃R�c�v���L�ڂ������|�[�g�𑗕t����B���̌�A���|�[�g���t���сA���|�[�g�𑗕t���Ȃ����тɑ��A2018�N1���̃��|�[�g���t��A�d�b�ɂ��A���P�[�g���������{����B���̌��ʂ��烌�|�[�g���t��̃G�l���M�[�g�p�ʂ̕ω���������B �ƒ땔���CO2�r�o�ʍ팸�ɂ́A�e�ƒ�̍s���ϗe�𑣂����Ƃ��K�v���B�{���Ƃł͉ƒ�E�Ɩ��E�^�A���哙��CO2�r�o���ԂɌW��f�[�^�����W�A��͂��A�ʂ̎��Ԃ܂����`�ŌX�ɏ����t�B�[�h�o�b�N���Ē�Y�f�^�̍s���ϗe�𑣂��Ƃ�����CO2�r�o�팸�Ɏ�����s���ϗe�̃��f�����\�z����B �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���@�@[�@2017/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���U�����d�g���d�����X�Ń|���v�ُ̈���Ď� �G���N�g���b�g�����d�A���C�A���X�́A�U�����d�f�o�C�X�𗘗p�����U���Z���V���O�V�X�e�������J�����B�H��̃��[�^�[��|���v�̉ғ��Ď��Ȃǂł̗��p��z�肵�Ă���B �V�X�e���́A�U�������o����q�@�ƁA�f�[�^����M����e�@���琬��B�q�@�ɂ̓G���N�g���b�g���p�����U�����d�f�o�C�X�A�U�������o��������x�Z���T�[�A�������W���[���A�L���p�V�^�[���������B���[�^�[��|���v�ɐݒu����Ƃ��̐U���ɂ���Ĕ��d�����d�͂ŃZ���T�[�△�����W���[�����쓮���āA���o�����U���f�[�^��e�@�ɑ��M����B�e�@��USB��PC�ɐڑ�����B�q�@�͓d���̔z���H�����s�v�Ȃ��߁A�z��������ꏊ�ɂ��e�Ղɐݒu�ł���B�d�r�����̎�Ԃ��Ȃ���B ���i�͎q�@10��Ɛe�@1��̃Z�b�g��10���`20���~���x��z��B �o�T�u���o�G���N�g���j�N�X�v |
|
|
| �������҂̑̊����Ɋ�Â��A���K���ƏȃG�l���𗼗�����u�\���^�V�X�e���v�̋������؎������J�n �A�Y�r���Ƒ��c���쏊�A�˓c���݊�����Ђ́A�\���^�V�X�e���̋������؎������J�n�����B�{���؎����́A�A�Y�r������e�N�m�Z���^�[�ȂNJe�Ђ̎{�݂ŁA������Ԃ̉��K���ƏȃG�l���M�[����]�����邽�߂ɁA2018�N3���܂Ŏ��{�����\��B �����҂������Ă���u�����v�u�����v�Ƃ������̊������A�]����PC��X�}�[�g�t�H���ɉ����u����p�\���J�[�h�v��ʂ��Ď��W���A�������ԁA�����ɉ������œK�Ȏ������x�ɐ��䂷��B �\���^�V�X�e���́A�������i�������Ⴂ�j���Łu�����v�Ƃ����v���������ꍇ�A���̗v���͂��̐l�ŗL�̗v���ł���ꎞ�I�Ȑ\���ł���Ɣ��ʂ��܂��B �ꎞ�I�ȗv���ł���ꍇ�ɂ́A�ݒ�l����莞�Ԍo�ߌ�Ɍ��ɖ߂��܂��B�t�ɏ����i�����������j���Łu�����v�Ƃ����v���������ꍇ�ɂ́A�p���I�Ȑ\���ł���Ɣ��ʂ��܂��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��IoT�ɂ��Ǘ������{�ł̏ȃG�l������ ��앟���̕�����ȃG�l�͏d�v�ȉۑ�B���ʗ{��V�l�z�[���싽�̗���IoT�iInternet of Things�j���g���ďȃG�l��i�߂Ă���B �����̋��p���ŗ��p����Ă���@�̓C���^�[�l�b�g�Ō���Ă���B�\�ߌ��߂�ꂽ���x��ғ��E��~�Ȃǂ̉^�p��A�_�C�L���H�Ƃ���{�݂̍��@�\�R���g���[���[�ɑ����A���̏��Ɋ�Â��@�������^�]�����B �ċG�̉^�p�X�P�W���[��������ƁA���p�̃G���A�͕����̗��p�ړI�ʂ�47�ɋ敪����Ă���B���ꂼ��̕������Ƃɐݒ艷�x�̏㉺���Ǘ��A�����Y��h�~�ݒ�A�Z�b�g�o�b�N�A��~�Ȃǂ̉^�p�X�P�W���[�������߂��Ă���B �㉺���Ǘ��͐ݒ艷�x�̕��̂��Ƃ��B�Ă͂��Ƃ���25������30���̊ԂŐݒ�B��[�������x�͎������A�S�ق̘L���Ȃǂ�25���B�����A��������20���ȂǂƂȂ��Ă���B�Z�b�g�o�b�N�͎蓮�ʼn��x��ς��Ă���莞�Ԃ����ƃ��Z�b�g���ꎩ���I�ɏȃG�l�̐ݒ艷�x�ɖ߂�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A��ԍ̐��E���x����[���𗈏t���� ���Ђ́A3D�J�����ƐԊO���T�[���O���t�B�J���������ꂼ��ڂ����A2��ށi�u��ԍ̐��\�����[�V�����v�u���x�Z���V���O�\�����[�V�����v�j�̑���[�����J�������B ��ԍ̐��[���́A���ꂽ�Ƃ���i��40cm�`��10m�j�ɂ���Ώە���3D�X�L�������A�Ώە��܂ł̋������v�����邱�Ƃ��ł���B����ɂ��A���܂��܂ȗ��̕���A�߂Â��ɂ����ꏊ�ɂ���Ђъ���̒����Ȃǂ��A�f�������m�Ɍv�����A�f�[�^�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B ���x�Z���V���O�[���́A�ԊO���T�[���J�������W���[���ŁA���ꂽ�Ƃ���ɂ���Ώە����B�e���邱�ƂŁA�Ώە��̉��x�𑪒肷��B-10���`450 ���͈̔͂Ŏg�p�\�B�߂Â��ɂ����ꏊ��A�O�ς���͔��M���킩��ɂ����Ώۂ̉��x��f�������肵�A�f�[�^�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������d��EP�A�@�l�����ȃG�l���̓T�[�r�X��J�n �����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i�d�o�j�́A�R���r�j�G���X�X�g�A�A�z�e���ȂǕ����̓X�܂�W�J�����Ƃ�ΏۂƂ����ȃG�l���M�[���̓T�[�r�X�̒��n�߂��Ɣ��\�����B �����̃X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j��A��R�X�g�̓d���Z���T�[����擾�����c��ȓd�͎g�p�ʃf�[�^�Ɋ�Â��A�����X�܂̃G�l���M�[�g�p�ʂ̈ꊇ�Ǘ���A���Ƒ��ЂƂ̔�r���\�Ƃ��A���ʓI�ȏȃG�l����㉟������B���ɐ��\�ЂŐV�T�[�r�X���s�������Ă���A10������{�i�I�Ȓ�Ă��n�߂�B�V�T�[�r�X��IoT�Z�p�����p�����@�l�����\�����[�V�����̑�1�e�B ���d�d�o�͓d�C�����v�����Ƃ̑g�ݍ��킹�����łȂ��A�T�[�r�X�P�̂ł̒��s���Ƃ��Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����IoT���p�A�Ɠd�ʂɁu�����鉻�v�^���d�o�f�Ƒ哌���� �����d�̓p���[�O���b�h�i�o�f�j�Ƒ哌�����́A���d�o�f�̑��IoT�v���b�g�t�H�[�������p�������ݏZ������T�[�r�X�̋������؎������J�n�����B �֓�����20���ɃC���t�H���e�B�X�Ƌ����J��������p�d�̓Z���T�[��ݒu�B�Ɠd���Ƃ̓d�C�g�p�Ȃǂ́B��̓I�ɂ�1�b���Ƃ̓d�͂̔g�`�������k���A�N���E�h��AI�@�\�ŕ��͂���B ����f�[�^�͑ݏZ��Ǝ҂ɒ��邱�ƂŁA�����Ҍ����t�����l�T�[�r�X�̓W�J�ɂȂ���B���p���̓d����̌��o��ݔ��̏�Ȃlj��v�ێ�A�ƒ�̓d�͏���́u�����鉻�v�T�[�r�X���\�B 2018�N4���ȍ~�A�哌�������Ǘ�������ݏZ��ւ̖{�i��������������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���G�l�b�g�����̏��p���AAI�Ŏ����ȃG�l�f�f �G�l�b�g�̓I�[�X�g�����A��AI�x���`���[�ACOzero Holdings�Ƒg�݁A�@�l�����ɏȃG�l�T�[�r�X���J�n�����B�Ώۂ̓I�t�B�X��X�܂ȂǍ�������̌����B�X�}�[�g���[�^�[�́uA���[�g�v���瓾����g�p�d�͗ʃf�[�^�ƋC�ۏ���AI�ʼn�͂���ȃG�l�f�f�T�[�r�X���B AI�G���W�����ߋ��f�[�^��C�ۃf�[�^�Ƃ̑��֊W����A�ُ����P�_��������ƁA�����ɂ̓T�[�r�X���p��Ƃ̒S���҂̌��Ƀ��[��������B��Ԃ̏Ɩ��̏����Y���A�ݔ��̉^�]���Ԃ̒����ԉ��Ȃǂ������Œ��o���A�m�点��B�������A�g�p�d�͗ʂ̐��ڂ╡�����_�̈ꗗ�̓X�}�[�g�t�H����p�\�R���Ȃǂł��ł����邱�Ƃ��ł���B�d�C������}�����邽�߂̑�܂Œʒm����B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ��SDGs�Ɏ��g�ފ�ƁE�c�̂�\��2017�N�x�W���p��SDGs�A���[�h �S�t�����Q������uSDGs���i�{���v�́A�N���[���G�l���M�[�A�z�^�Љ�A���g������17����̖ڕW���f���������\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�ɂ��āA�D�ꂽ���g�݂��s����Ƃ�c�̂�\������u����29�N�x�W���p��SDGs�A���[�h�v�̌�����J�n�����B ������Ԃ�11��21���܂ŁB���̕\���́A�����Ɍf����ꂽ�D��ۑ�܂��č��A�ō̑����ꂽ�u�����\�Ȑ��E��ڎw��17����̍��ۓI�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�v�𐄐i���Ă��鍑���̊�ƁE�c�̂�ΏۂƂ��A���{�������́B���N�x����1��ڂ̊J�ÂƂȂ�B SDGs�́A�����\�Ȑ��E��ڎw�����ۖڕW�́A���E�q���A�G�l���M�[�A�C�m�x�[�V�����A�����\�ȓs�s�A�����\�Ȑ��Y�Ə���A�C��ϓ��Ȃ�17����B SDGs���{�w�j�̍���r�W�����Ƃ��āu�����\�ŋ��ՁA�����ĒN��l���c���Ȃ��A�o�ρA�Љ�A���̓����I���オ�������ꂽ�����ւ̐��҂�ڎw���v���f���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���É����AVPP�\�z�̋��c��ݒu�����A�g�ŃG�l���M�[�n�Y�n���߂��� �É����́A���z�����d�╗�͔��d�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�����p�����V���ȓd�͎��������V�X�e���u�ӂ��̂��Ƀo�[�`�����p���[�v�����g�iVPP�j�v�̍\�z�ɂ��Č������邽�߁A�����A�g�ɂ�鋦�c��𗧂��グ��Ɣ��\�����B �G�l���M�[�̒n�Y�n���̂ق��A�G�l���M�[�Y�Ƃ̐U���ɂ��n��o�ς̊�������ڎw���A�n�G�l�E�ȃG�l�E�o�ϊ�������3�̐헪�ɂ����g�݂𐄐i���Ă���B ����VPP�́A�ŐV��IoT�Z�p�̊��p�ɂ��A���U����Đ��\�G�l���M�[���d�ݔ���~�d�r�A�ƒ�⎖�Ə��̐ߓd�̎��g�݂��I�ɐ��䂵�A�n����Ō����I�Ɏ���������V�X�e���B���d�����d�͂��A�\�Ȍ���n����ŗL�����p���邱�Ƃ�����Ƃ��Ă����Ă���B ���̃V�X�e���̍\�z�ɂ��A�d�͂̈��苟���ƍĐ��\�G�l���M�[�̗L�����p�A����ɁA�~�d�r�̓����ɂ����p�d���̊m�ۂɂ��Ȃ��Ă����v�悾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����v�ʑ������K�ؕ]���A�G�l������������ �����G�l���M�[���́A���v�n�o�^�f�}���h���X�|���X�u�グ��DR�v�̐��x�����Ɍ����ċ�̓I�Ȍ����ɒ��肵���B �ē~�ɂ����钋�Ԃ̃s�[�N�J�b�g�Ȃǂ����߂�ȃG�l���M�[�@�ƁA��ɍĐ��\�G�l���M�[�d���̔��d�d�͂�������A���v������o���グ��DR�Ƃ̐�������ۂ��߁A�ϓ�����d�C�̔��d�ʂɉ����Ď��v�ʂ��ω������邱�Ƃ�K�ɕ]���ł���d�g�݂�����B�ȃG�l�@��W�@�߂̉���������Ɍ�����[�߂�B �u�G�l���M�[�������Ǝ҂̏ȃG�l�K�C�h���C��������v�ŁA�G�l�������N�x�̐R�c�����Ƃ��Đ��������B �s�[�N�J�b�g�����߂�ꍇ�A�]��̍Đ��\�G�l�d�C��L�����p����グ��DR�Q�����Ǝ҂͏ȃG�l�@��s���Ȉ������鋰�ꂪ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�Z���^�[�u�G�l�Ǘ��m�����v���ނ�d�q���A100�~����̔� �ߋ�10�N���̖�肪���^���ꂽ���Ђ�2,300�~�����A�d�q���Ђ������l�i�B �d�q���Ђ́A5�N�p�b�N��1,900�~�A3�N�p�b�N��1,600�~�B�N�x�ʁA�Ȗڕʂɂ��w�����邱�Ƃ��\�ŁA2008�N�`2012�N�x��100�~�A2013�N�x�`2016�N�x��250�~�A2017�N�x��300�~�B 1��̎����őS�č��i�ł��Ȃ��Ă��A���ނ������K�v���Ȃ���p���S���y�������B 10�N����400�y�[�W�ȏ゠�鏑�Ђ�d�q�����邱�ƂŎ����^�т��₷���Ȃ�A�p�\�R����^�u���b�g�łǂ��ł��{���ł���B������邱�Ƃ��ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��NEDO �o�C�I�}�X�G�l���M�[�A�n�Y�n������������v���E�Z�p�w�j�܂Ƃ� NEDO�́A�o�C�I�}�X�G�l���M�[���ƂɐV�K�Q����}�鎖�Ǝ҂̎��ƌv��쐬�̂��߂Ɂu�o�C�I�}�X�G�l���M�[�n�掩���V�X�e���̓����v���E�Z�p�w�j�v�����\�����B ����́A�u�o�C�I�}�X�G�l���M�[�̒n�掩���V�X�e�������؎��Ɓv�ɂ����āA�o�C�I�}�X��i�؎��n�A�����n�j���Ƃɒn��̓����������œK�ȃV�X�e���Ƃ��Ă̎��Ɛ���]�����A�o�ϓI�Ɏ����ł�����p���̍����V�X�e���̓����v����A���肵�����Ƃ��������邽�߂̋Z�p�w�j�����܂Ƃ߂����́B �\���́A�u�����\�ȃG�l���M�[���Ƃ̍\�z�v�u�����v���v�u�Z�p�w�j�v��3�́B �o�C�I�}�X�����̒��B�\��(�G�ߕϓ��A�Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�J�n��̎����o�����X�ω��̗\���Ȃǁj�A���B��A�����̎�ނƓ����A�A�����@�A�P���A���ƌv�挟���̎d���A�������B�A�����ϓ����X�N�Ȃǂɂ��ċL�ڂ���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C��G�l���M�[�\�����[�V�����Z���^�[�A��Ƃ̎Г��Y�f���i�t�����x�̓������ �C��G�l���M�[�\�����[�V�����Z���^�[�iC2ES�j�́A�C��ϓ��ɔ�����Ƃ��Г��œ������Ă���Y�f���i�t�����x�̖ړI�Ǝ�@�Ɋւ��钲�����ʂ�����B ��Ƃ̓����x�����́A�r�o�팸�A�C��֘A�̃r�W�l�X���X�N�Ɋւ��銔��̌��O�ւ̑Ή��A�����͂̋����ȂǕ����̖ړI�ōs���A�Y�f�̉��i�ݒ��CO2���Z��1�g��������2�`893�h���ƕ��L���B�܂��Г��Y�f���i�t���̎�@�Ƃ��āA�Y�f�ۋ��A�Z���̉��i�t���A���̑g�����������{���Ă���B �Y�f�ۋ��́A���i�����������̂��Y�f�r�o�̃R�X�g�ƊǗ��̕K�v���ɂ��ď]�ƈ����̈ӎ������߂���ʂ��������A�Z���̉��i�t���͒����I�ȓ�����������̂ł���A�ړI�ɉ��������@��I�����邱�Ƃ��K�v���Ǝw�E���Ă���B�ŏЉ�ꂽ�}�C�N���\�t�g�Ђ̎���ł́A�d�C�����]�ƈ��̔�s�@�ړ��ɂ��Y�f�r�o��1�g��������5�`10�h�����ۋ����A������Đ��\�G�l���M�[�̍w����G�l���M�[���������ɏ[�ĂĂ���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2017/10�@]�@�@�� |
|
|
| �������[���ő��z���d�͂��g����A�I�t�O���b�h�����T�[�r�X�o�� �A�C�E�O���b�h�E�\�����[�V�����Y�Ȃǂ́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ȃǂ̌��������̗V�x�X�y�[�X�ɑ��z�����d�ݔ���ݒu���A�����Ŕ��d�����N���[���d�͂��A���d�Ԃ�����Ɍ������ɒ��ڋ�������u�I�t�O���b�h�d�͋����T�[�r�X�v���J�n�����B �I�t�O���b�h�d�͋����T�[�r�X�ł́A���z���̓d�͂��A���v�n����100���n�Y�n�����A���z���Ŕ��d�����d�͂ƁA�n����ʂ��ēd�͉�Ђ���w������d�͂̃x�X�g�~�b�N�X��ڎw���A�d�̓R�X�g�̍팸�Ɋ�^����_�����B ���T�[�r�X�̍\�z�ɂ������ẮA���d�]����������A100�����v�ꏊ���Œn�Y�n�������邽�߁A�����̓d�͎g�p�ʂ͂��Ă����K�v������B���Ђł͊����ڋq�ȂǑS��5600�J���ȏ�̎{�݂̓d�͎g�p�ʂ͂��Ă���A���̌��ʂ����p���čœK�ȋK�͂̑��z�����d�ݔ����Ă���Ƃ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���I�������AVPP�s��E�]�蔃��I���̃j�[�Y�_����e�ʒ~�d�V�X�e������ ���Ђ́A���K�͎Y�Ǝ{�݂�ˌ��Z��̑��z�����d�V�X�e�������ɁA���Ə���j�[�Y�����łȂ�VPP�iVirtual Power Plant�j�s��ɂ��Ή��ł���A�e��9.8kWh�̒~�d�V�X�e��������B �V���i�́A�ˌ��Z��⏬�K�͎Y�Ǝ{�݂Ɍ����A�t���L�V�u���ݒu�Ɛ��E�ŏ��Ōy�ʃN���X�����������B���̃V���[�Y�́A�~�d�r���j�b�g�ƃp���[�R���f�B�V���i���Z�b�g�ɂ����V�X�e���ŁA7���Ɂu���Ə���v���T�|�[�g����~�d�r�e��6.5kWh�^�C�v�̏��i�����Ă���B ���Ə���́A���z�����d�Ŕ��d�����d�͂d����̂ł͂Ȃ��{�݁E����Ŏg�p������́B���V���[�Y�́A2009�N�ɃX�^�[�g�����Z��p�]�蔃�搧�x�̔������(10�N)�̏I�������ɂ�����2019�N�ȍ~�ɑz�肳��鎩�Ə���j�[�Y�ɂ��Ή�����B�[���d�\�͂͏]���@���1.2�{ �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����E���A�M�����o������T�[�}���J�������ڂ�CAT�u�����h�X�}�z�B�I���L���[���� �I���L���[���p�C�I�j�A�}�[�P�e�B���O�W���p���́A���E�ŏ��߂āA�M�����o���ł���T�[�}���C���[�W���O�J�����𓋍ڂ��A�����ł̓���B�e���\��SIM�t���[�X�}�[�g�t�H����10�����{�ɔ�������B ���i�̓I�[�v���v���C�X�ŁA�X���\�z���i��9���~�O��B�J�����̓��C����1,300����f��AF�ƃt���b�V���@�\�t���B�T�u��500����f�BGPS������x�Z���T�[�A�d�q�R���p�X�A�ߐڃZ���T�[�A�Ɠx�Z���T�[�A�W���C���A�C���v�Ȃǂ����ڂ���B�O�`���@��147.9�~73.4�~12.66mm(���~���s���~����)�ŁA�d�ʂ�223g�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���A�E�f�B�A�d�C�����Ԃɑ��z�d�r�������� Audi�i�A�E�f�B�j�́A��Alta Devices�Ђ̋��͂̂��ƁA�d�C�����ԁiEV�j�Ƀt���L�V�u���Ȕ������z�d�r���������Ă������j�\�����B�܂��́A���z�d�r��g�ݍ��K���X���̃��[�t�̎���i���A2017�N���܂łɊ���������\��Ƃ��Ă���B Alta Devices�Ђ́A���GaAs�i�K���E���q�f�j�n�̃t���L�V�u���ȍ������������z�d�r�̊J������|���Ă���B�����_�ŁA�P�ڍ��^�ōő�28.8���A�_�u���ڍ��^�œ�31.6���̕ϊ��������������Ă���Ƃ����B ���ʂ͎����������z�d�r�Ŕ��d�����d�͂��AEV�̋V�X�e����V�[�g�̃q�[�^�[�ɗ��p���Ă����B�ԍڐݔ��̓d�͂z���Řd�����ƂŁAEV�̑��s������L����\��������B�����̓N���}�̉����S�̂z�d�r�ŕ����A���d�����d�͂�EV�̒~�d�r�ɏ[�d�ł���V�X�e�����\�z����v�悾�Ƃ����B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
| ���d���R���Z���g���}���^�̊w�K�����R���A�d���v�������A�G�A�R���̉ғ����O�o�悩��m���ɔc�� �����N�W���p���́A�����̉Ɠd���i��IoT�����邽�߂̃A�_�v�^�[��12���ɏo�J�n����Ɣ��\�����B �X�}�[�g�t�H�����瑀��ł���ԊO���w�K�����R���̈�킾���A�����̃G�A�R���ݒu�ꏊ�̉��ɂ���R���Z���g�ɑ}���Ďg�p����B�d���R���Z���g���}���^�ŁA�d���Z���T�[����̉����Ă���̂������B�G�A�R���̓d���v���O���A�_�v�^�[�o�R�łȂ���d�g�݂ƂȂ��Ă���A�O�o�悩��ԊO�������R�����삪�s���邾���łȂ��A���ۂɃG�A�R�����ғ����Ă��邩�ǂ��������d�͗ʂ��d���Z���T�[�Ō��m�ł���B �d���Z���T�[��������邱�ƂŁA�d���̃I���^�I�t��Ԃ𐳊m�ɔc���ł���B�{�̂̑傫����70�~76�~70�i���~���s�~�����j�A�d�ʂ�140g�B �G�A�R���̂ق��A�e���r�A�Ɩ��A�I�[�f�B�I�Ȃǂ̐ԊO�������R���̑�����w�K�����邱�Ƃ��\���B �o�T�uINTERNET Watch�v |
|
|
| ���V�H��M�A�h�K�܂�����Ȃ��z�ǂ̋Ǖ��h�H�V�Z�p���J���@�ݔ��X�V�R�X�g���팸�� �V�Z�p�ł́A�h�K�܂̕ς��ɃA�j�I������������p���A���������̕��H���C�I���i�������C�I���E���_�C�I���j�ƁA�h�H���C�I���i�Y�_���f�C�I���j���������A���������u���H���ɂ������v�ɉ����ł���B �܂��A���̐��𐅒���E�t���b�V���O�̒i�K����z��ߎg�p����ƁA���H�̋N�_�ɂȂ�����q�̊��S�������\�ƂȂ�B�Ȃ��A���j�^�����O�ɂ��ApH��n���_�f�Z�x�𑪒肵�ăt���b�V���O�����������ʓI�ɔ��f����B �r����H��̗␅�E�����E��p���z�ǂ̑����Ɏg�p����Ă���Y�f�|�|�ǁA�����߂����|�ǁA�Ⓚ�@��@��Ȃǂ̔M������p���`���[�u�ɓK�p�ł���B �z�ǂ̕��H�֘A�R�X�g���ȉ��ɍ팸�ł���ƌ����܂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���x�m�o�ρA�Đ��\�G�l���M�[���d�֘A�V�X�e���E�T�[�r�X�̍����s��̓�����\���i2017�N�����j �x�m�o�ς́A�Đ��\�G�l���M�[���d�֘A�V�X�e���E�T�[�r�X�ɂ��Ē������A�����s��̓����Ɋւ���\�����ʂ\�����i�������ԁF2017�N6���`8���j�B �������́A5�̃G�l���M�[��i���z���A���́A���́A�o�C�I�}�X�A�n�M�j�̊֘A�@��E�T�[�r�X�ɎQ�����Ă����ƁE�c�̂ւ̃q�A�����O�Ȃǂɂ��A���Ђɂ��s��K�͓��̗\�����ʂ����܂Ƃ߂����́B���Ђɂ��ƁA 1�j2017�N�x�̍Đ��\�G�l���M�[�Œ蔃�搧�x(FIT)�֘A���d�V�X�e���̐V�K�����s���2��894���~�ƌ����܂�A 2�j�s���8�����߂Ă������z�����d����̏k���ɂ��A2025�N�x�̎s���1��2,061���~�i2017�N�x��6����j�ɏk������ƌ��Ă���B �Đ��\�G�l���M�[���d�V�X�e���̗v�����ʂ́A2030�N�x�̌o�ώY�ƏȂ̃G�l���M�[�x�X�g�~�b�N�X�ɂ����铱���ڕW���A���z����2020�N�㑁�X�ɒB���A���́E�o�C�I�}�X��2030�N�x���ɒB���A���́E�n�M��2030�N�x�i�K�Ŗ��B���\�z�����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��2020�N�܂ł�LED�Ɩ��������o�ה䗦100�� �����ݒu�䗦50�����ڕW ���{�Ɩ��H�Ɖ�́A2014�N10���ɁA�Ɩ������헪�uVISION 2020�v������A2020�N�܂łɏƖ����t���[�s��i�V���ɏo�ׂ����Ɩ����j��LED����100���Ƃ����ڕW���f�������A�啝�ɑO�|���ŒB�����鐨���ł���B ����́A2030�N�܂łɃX�g�b�N�s��i�����ɐݒu����Ă���Ɩ����j��LED����100�����Ƃ������{�ڕW�̑����B��������̉ۑ�ƌ�����B �������ALED�Ɩ����Ƃ���芪�����̕ω��͌������A����ɑΉ����ׂ��uVISION 2020�v�̈ꕔ���������s�����B2030�N�X�g�b�N�s���LED����100���Ƃ������{�ڕW�ɑ���{��ƃX�}�[�g�Љ�ւ̑Ή��ȂǁA2030�N�����������uVISION 2020�v���ꕔ���肵���B�ڍׂ́AJLMA�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���̂ŎQ�ƁB ��������A����d�͗ʂ�2020�N��30���A2030�N�ɂ�48���팸�ł��邱�ƂɂȂ�B�t���[100���͑O�|���ŒB���ł��錩���݁B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����A���v��A����Ɋւ��鐅��������������Ƃ�� ���A���v��(UNEP)�́A����Ɋւ��鐅�����2017�N8��16���ɔ��������ƕ����B74�̒��E�n��́A����Ɛ��≻�����̗L�Q�ȕ��o�ɂ�� ���N�Ɗ��ւ̃��X�N��ጸ���邽�߁A���C�t�T�C�N����ʂ��ėl�X�ȑ���u���邱�Ƃ�@�I�ɋ��߂���B���ɂ́A 1�j�V�K�z�R�̊J���֎~�A�����z�R�̒i�K�I�p�~ 2�j��ׁE���K�͋��̌@��H�ƃv���Z�X�A���p�i�i���ϕi�E�d���E�d�r�E���ȗp�[�U�ޓ��j�̐����ɂ����鐅��̎g�p�K�� 3�j�ΒY�Η͔��d���A�p�����ċp�{�ݓ�����̔r�o�팸 4�j����̎b��I�ۊǁE�p�����E�����n�̃��X�N�ጸ�Ɋւ���[�u�A �������荞�܂�Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����{�A�X�ё卑�Ȃ̂ɖ؎��y���b�g������25���Ƀ_�E���A�����葝�� �і쒡�́A2016�N�ɂ�����؎��y���b�g�̍������Y�ʂ�12��162�g���łقڑO�N���������Ɣ��\�����B�p�r�ʂɌ���ƁA�R���p�Ƃ��Ă̐��Y���قƂ�ǂ��߁A11.4���g���i�\����94.5���j�ƂȂ��Ă���B�����́A���ލH�ꓙ�c�ނ���̐��Y��5.2���g���i�\����43.6���j�A�ۑ��E�ђn�c�ނ���̐��Y��4.3���g���i�\����35.6���j�A���ݔ����؍ނ�2.3���g���i�\����19.1���j�B �؎��y���b�g�̗A���ʂ́A�O�N��49������34.7���g���B��ɃJ�i�_�A�x�g�i������̗A�����������Ă���B�����ɂ��؎��y���b�g�̎������́A�O�N��8.3�|�C���g����25.7���։��������B PKS�i���V�k�j�A���ʂ́A�O�N��67������76.1���g���B�؎��y���b�g�̑�֔R���Ƃ��ċ����W�ɂ���R���p��PKS�̗A���ʂ͋ߔN�}�����Ă���B��ȗA���捑�̓C���h�l�V�A�ƃ}���[�V�A�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������ȁA����28�N�ɂ�����S������E�ǖʗΉ��{�H���ђ������ʂ����\ ���y��ʏȂ́A����28�N�ɂ�����S������E�ǖʗΉ��{�H���ђ����̌��ʂ����\�����B����Ή���ǖʗΉ��́A�s�s�ɂ�����q�[�g�A�C�����h���ۂ̊ɘa�A�����������̂���s�s��Ԃ̌`���A�s�s�̒�Y�f�����̊ϓ_����A�S���I�Ɏ��g�݂��i�߂��Ă���B ����28�N���ɐV���Ɏ{�H���ꂽ����Ή��͖�27.6�w�N�^�[���A�ǖʗΉ��͖�8.7�w�N�^�[�����n�o���ꂽ�B����ɂ��A����12�N���畽��28�N��17�N�Ԃ̗v�{�H�ʐς́A����Ή�����471�w�N�^�[���A�ǖʗΉ��͖�86�w�N�^�[���ƂȂ����B����̒����ł́A����Ή���1��������̎{�H�ʐς͕���27�N�Ɣ�r���Ė�3���i62m2�j����254m2�ƂȂ��Ă���A1,000m2�ȏ�̉���Ή����s�����������͑����X���ƂȂ��Ă���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �������s�̊�����E�ڕW�E���g�݂��킩�鏬���q���쐻 �����s�́A������Ɋւ���ڕW����g�݂��Љ����q�u����i�s�s�E�����Ɍ�����CREATING A SUSTAINABLE CITY�v���쐬���A�z�[���y�[�W�Ō��J�����B ���̍��q�́A4���ڂ��Ȃ�A�u�X�}�[�g�G�l���M�[�s�s�̎����v�́A�u�����̃O���[���r���f�B���O�{��v�u������̐��i�v�u�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��v�u���f�Љ�����Ɍ�������g�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���B�Ȃ��ł��O���[���r���r���f�B���O�{��ł́A��K�͎��Ə���ΏۂƂ����u�L���b�v& �g���[�h���x�v�A�����K�͎��Ə���ΏۂƂ���u�n�����g���������x�v�A�V�z�E���z���錚�z����ΏۂƂ����u���z�����v�揑���x�v�����グ�Ă���B �u�����\�Ȏ������p�̐��i�v�ł́A�H�i���X�̍팸��g���̂Č^���C�t�X�^�C���̌������Ȃǎ������X�팸���͂��߁A�ċp�D�̃��T�C�N���ȂǃG�R�}�e���A���̗��p���i���̎��g�݂ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���B ���̑��A�u�������l���̕ۑS�Ɨ̑n�o�v�u���K�ȑ�C���ւ̎�g�v���܂܂�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ȁA2018�T�Z�v���ŏz�Љ�ɂP��516���~ ���Ȃ�2018�N�x�\�Z�̊T�Z�v���́A2017�N�x�����\�Z��3.1������1��516���~�ƂȂ����B�o�ϐ����ɂȂ��������ɏd�_��u���A�����\�ȏz�����^�Љ�̌`����ڎw���B �o�ώY�ƏȁA���y��ʏȂƂ̘A�g�ɂ��V�K�{��u�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�iZEH�j�����ɂ��Z��ɂ������Y�f�����i���Ɓv62���~�́A7000�˂�ΏۂɃG�l���M�[����������[���ɂ���y�d�g�̐V�z�E���C��p��⏕����B �܂��A�o�Y�ȘA�g�̐V�K�{��u���z�����d�̎������Ɍ������ƒ�p�~�d�E�~�M�������Ɓv84���~�́A2��7000�˂�Ώۂɉƒ�p�~�d�r��~�M�ݔ��̐ݒu��p��⏕���A2019�N�x�ȍ~�ɍĐ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i������萧�x(FIT)�ɂ�锄�d���Ԃ��I�������ʉƒ낪�o�Ă���ɔ�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2017/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���哯����������ƌo�c�҂Ɂu�d�͏������R���v�ɂ��ăA���P�[�g���� �E��4 ���̌o�c�҂��A�d�͏������R�����_�@�Ɏ��Ə��̓d�͍w����̕ύX���u���������v�ƉB�������A���ۂɕύX������Ƃ͖�1���ɂƂǂ܂��Ă����B�����̂��������́u�d�͉�Ђ̉c�Ɓv����4���ƍő��B �E�d�͍w�����I�Ԃ����ŏd�����邱�Ƃł́u���i�v����6���ƍł������A�����Łu�d�͂̈��萫�v�Ɓu�d�͉�Ђ̐M�����v����3���B �E�d�͍w����ύX��̓d�C�����̍팸�����ł́u10�������v����9���B�ύX�����o�c�҂̖�6�����ύX��̓��e�Ɂu�������Ă���v�ƉB �E�ȃG�l���M�[���i�Ɍ������ݔ������ł�LED�d���Ȃǁu�ȃG�l�^�@��ւ̔��ցv����5���A�^�p�ɂ���g�݂ł́u�s�v�ȏƖ��̏�����P���v����6���������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���Ŕ�V���[�P�[�X�ɍœK�A�����Ȃ�����LED�Ɩ� OPTILED LIGHTING�́A���nj`LED�����v�uKA�V���[�Y�v�̔̔����J�n����B ���ƊŔA�V���[�P�[�X���̏Ɩ������̐��i�B���C���A�b�v�͊Ŕł̎g�p��������20�`�A30�`�A32�`�A40�`��4��ނŁA�����̂Ȃ����Ƃƌy�ʐ��������Ƃ����B������]�@�\�t�\�P�b�g�Ō����iG13�j����]�����A�Ŕ̒[�܂Ō���͂��邱�Ƃ��ł���BLED�������v��\�ʂ��牓�����邱�ƂŁA�L�z���i1/10�r�[���p300�x�j���������A���Ƃ̃�����ጸ���Ă���B�F���x��6500K�B �d���������nj`LED�����v�ŕБ����d�����B����ɓƎ��Z�p�ɂ��A�A���~�q�[�g�V���N���g��Ȃ��V�\�����̗p�������ƂŁA�]���̌u�����ƈ����̃Z�b�g�Ɣ�r���A��5����1�̏d�ʂ����������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���y�V�A�^�C�̑��G�l���M�[��ЂƘA�g�d�͏����E�����l��������� �y�V�́ABanpu�ЂƁA�d�͏������ƂƊ����l�������ŕ�A�g���邱�Ƃō��ӂ����Ɣ��\�����B ���Ђ͍���̍��ӂɊ�Â��A�l�K���b�g�Ɗ����l����A���{�ɂ�����d�͏������ƕ���ł̃r�W�l�X���f���̊J���Ɏ��g��ł����B ��̓I�ɂ́ABanpu�Ђ̃A�W�A�����m�e���ɂ�����ΒY�┭�d���Ƃ̎��сA�y�V�̓��{�����ɂ�����d�͏������Ƃ̃m�E�n�E�⍡�H�J�ݗ\��́u�����l�v�Ɓu�l�K���b�g�v�̎��ݎ���v���b�g�t�H�[���Ȃǂ̐�i�I�Ȏ��g�݂�IoT�Z�p�Ȃǂ�g�ݍ��킹�A�e����ŁA���{�ƃ^�C�Ԃ̃N���X�{�[�_�[�Č����܂߂����Ƃ̓W�J���߂����B�d�͏������Ƃɂ���������̊g��������ށB �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���@��̓r���}���A�����@��ł�CO2��}���i�ւ̈ڍs���i�݂��� �x�m�o�ς́A�E�����@��̎s��̕��\�����B ����ɂ��ƁA2016�N�̋@��s���7��2627���~�ƂȂ����B���[���G�A�R��(RAC)�A�p�b�P�[�W�G�A�R��(PAC)�^�r���p�}���`�G�A�R���iVRF�j����������Ă���A2025�N�ɂ�2016�N��21.9������8��8552���~�Ɋg�傷��Ɨ\�����Ă���B�܂��A2016�N�̋����@��s���1��6234���~�ƂȂ����B�Z����������@�킪�A�R�Ď��ł͒���������u�Ԏ��ցA�d�C���ł͓d�C�����킩��q�[�g�|���v�������@�ֈڍs���Ă���B �����ł́A�Z���g��������VRF�ւ̐ؑ֎��v������A���v�͐��n���Ȃ����2020�N�܂ł͔������\�z�����B����܂Ńr���}���͉����ʐ�1���������[�g�����x�ł��������A3���������[�g���ł�VRF���̗p����ȂǁAVRF�̑Ή��ʐς��L�����Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���~�d�E���d�@��F�s�s�K�X���������p�A�R���d�r�~�K�X�^�[�r���̕������d�@��̔��� �O�H�����p���[�V�X�e���Y�́A�Ɩ��E�Y�Ɨp�ɊJ�������ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j�ƃ}�C�N���K�X�^�[�r���iMGT�j�̑g�ݍ��킹�ɂ������^�������d�V�X�e���i�n�C�u���b�h�V�X�e���j�̔̔����J�n�����B���U�^�d���E�R�[�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�V�X�e���Ƃ��Ẵj�[�Y�������ށB ���̃V�X�e���́A900���̍����ō쓮����Z���~�b�N�X��SOFC��MGT�̗����Ŕ��d����BSOFC�R�����͉�����Ȃ��œs�s�K�X�����̂܂ܗ��p���A��C����MGT�̈��k�@����̋�C�𗘗p����B SOFC�R�����o���̎c�R���Ƌ�C���o���̎c��C��R�Ċ�ŔR�Ă����A�����̃K�X��MGT�^�[�r�����쓮���邱�ƂŁA�������ȃV�X�e���Ƃ����B�R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e���ł́A����Ɏc��̔M�����C�܂��͉����Ƃ��ĉ������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����̓d�͌_��͂��̂܂܁A�����͖����ݒu�̑��z���d�͂��g����V�v���� ���{�G�R�V�X�e���́A�d�̓T�[�r�X�u���Ԃ�d�́v�ɁA�V���������v������lj������B ���݉������Ă���d�͉�ЂƂ̌_��͌p�����Ȃ���A�����͏Z����ɖ����Őݒu���ꂽ���z�����d�̓d�͂𗘗p�ł���B�����́A�����ȑ��z�����d�̓d�͂��w�����邱�ƂŁA�d�C�������팸�ł���B���Ԃ�d�͂́A������u��O�ҏ��L���f���v�ƌĂ�鑾�z�����d�����p�����d�͋����T�[�r�X�B ���{�G�R�V�X�e���������Ń��[�U�[�̏Z����ɑ��z�����d�V�X�e����ݒu����̂������ŁA���̌�̃����e�i���X��p�Ȃǂ����ׂĖ����ƂȂ�B�������A�ݔ��Ɣ��d�����d�͂̏��L���͓��{�G�R�V�X�����ɋA������B���[�U�[���͏Z����ɐݒu���ꂽ���z�����d�̓d�͂��A���{�G�R�V�X�e������w�����Ď���ŏ���邩�����ɂȂ�B 20�N�Ԍo�߂���ƁA�ݒu�������z�����d�V�X�e���̓��[�U�[���ɏ��n�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���g���^�ƃZ�u���A�R���r�j�^�c�Ő��f���pFC�g���b�N��~�d�r���� �Z�u��-�C���u���ƃg���^�́A�R���r�j�X�܂���ѕ����ɂ�����ȃG�l�ACO2�r�o�ʂ̍팸�Ɍ����������Ɋւ����{���ӏ�����������B �Z�u��-�C���u���͊����גጸ�ւ̎��g�݂Ƃ��āA�R���r�j�X�܂ɃG�l���M�[�g�p�ʂ̉��u�Ď��V�X�e����ALED�Ɩ��A�r�M������A���z�����d�V�X�e���Ȃǂ̓�����i�߂Ă���B���z�����d�p�l���ݒu�X�ܐ���2016�N5�������_��7624�X�ɒB���Ă���B ������{����X�܂̎��g�݂ł́A�X�܂ɔR���d�r���d�@�ƁA�����ԗp�~�d�r�����p������u�^�~�d�r������B�����āA���ɓ������Ă��鑾�z�����d�ݔ��Ȃǂƕ����ăG�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���iEMS�j�Ő�����s���A�����I�ȏȃG�l�����CO2�r�o�ʂ̍팸��}��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������s�A2015�N�x�͑O�N��2.6���ȃG�l�Y�ƁE�Ɩ�����͂��܂茸�炸 2015�N�x�̓����s���̃G�l���M�[����ʂ�629PJ�ŁA2000�N�x��ł�22�������A2014�N�x��ł�2.6���������Ă���B ����ʂ̍\����Ƃ��ẮA�Y�ƁE�Ɩ����傪2000�N�x���18�������A2014�x���0.7�������B�ƒ땔�傪2000�N�x���2.5���A2014�N�x���5.2�������B�^�A���傪2000�N�x���42�������A2014�N�x���2.6�������ƂȂ��Ă���B 2015�N�x�̓s���̉������ʃK�X�r�o�ʂ�6,598��t�|CO2�ŁA2000�N�x��ł�6.3�������A2014�N�x��ł�1.8���������Ă���B �d�͂̓�_���Y�f�r�o�W���i�s���S�d�����d���ρj�́A2000�N�x��0.328kg�|CO2�^kWh�A2014�N�x��0.499kg�|CO2�^kWh�A������2015�N�x��0.492kg-CO2�^kWh�ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEDO - �u����29�N�xNEDO�V�G�l���M�[���ʕ�v�̊J�� NEDO�ł́A�R���d�r����A���f����A���͔��d����A�C�m�G�l���M�[����A�o�C�I�}�X����A�M���p����A���z�����d����ɂ����鎖�Ƃ̉ۑ��i���Ɛ��ʂ��L�����L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���ʕ���J�Â���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v �@�@�����F 9��19���i�j�`22���i���j�A9���`18�� �@�@�ꏊ�F�p�V�t�B�R���l�A�l�b�N�X�z�[�� �@�@�\�����@�F���O�o�^���K�v�B�i�Q������j https://www.nedo-seminar.jp/nearm2017/ |
|
|
| ���G�l���A�G�l��{�v�挩���������H�@�����̐M���Ȃljۑ� �����́A���������G�l���M�[�������{�������ȉ���J���A�u�G�l���M�[��{�v��v�̌������Ɍ������������n�߂��B 2014�N�Ɍ��s�v������肵�Ĉȍ~�N�������ω��܂��č��ւ���B�V���Ȍv�����ɁA2030�N�x�B�_�Ƃ���œK�ȃG�l���M�[�~�b�N�X�i�d���\���j�̎����Ȃǂ�ڎw���B ���v��́A3�N���ƂɌ��������Ƃ��G�l���M�[�����{�@�Œ�߂��Ă���B �܂��A�G�l�������͌������i�ϓ���d�C�����ԁiEV�j�̕��y�Ȃǂ��ߔN�̑傫�ȕω��Ƃ��A���q�͔��d�̎Љ�I�M����Đ��\�G�l���M�[�̃R�X�g�Ȃǂ��ۑ�ɋ������B �����A�ψ�����́u���i��ς��Ȃ��Ƃ����O��ŗǂ��̂��v�u�����͐V���݁A���v���[�X�i���đւ��j�̋c�_�𑁂߂ɍs���ׂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ������������ӌ������������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����E�ő勉��CO2�t���[���f�H��̊J�����X�^�[�g�A������2020�N�Ɏ��� NEDO�́A���E�ő�K�͂ƂȂ�Đ��\�G�l���M�[�𗘗p����1��kW���̐��f�����H����A�������Q�]���Ɍ��݂���v���W�F�N�g���̑������B ���k�d�́A���ŁA��J�Y�Ƃ�3�Ђ��A�{�i�I�ɃV�X�e���̊J���ɒ��肷��B2020�N�x���߂ǂɎ��؉^�]���s���v�悾�B���{���f����u�����V�G�l�Љ�\�z�v���{�i�I�ɓ����o���B �����V�G�l�Љ�\�z�́u�ăG�l�̓����g��v�u���f�Љ�����̃��f���\�z�v�u�X�}�[�g�R�~���j�e�B�̍\�z�v�Ƃ���3�̒��ō\������Ă���B���f�Љ�����̃��f���\�z���x����̂��A����J�����鐢�E�ő勉�̐��f�����H�ꂾ�B �����NEDO�̍̑��Ő����Ɍ��ݒn����ъJ���̊J�n�����܂����B�v��ł͑��z�����d�𗘗p���A�N��900t�̐��f���ł���V�X�e���̍\�z��ڎw���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������œd�C�����I �C�����d���u�̎��؎����i�������V���A100kW���j NEDO��IHI�́A���āA���������\�������V�����̍����C��ŁA���E�ŏ��߂āA���ۂɊC���𗘗p����100kW�K�͂̊C�����d�̎��؎��������{�����B �p�����̂́A�V���Ȑ������V���C�����d�V�X�e���B���؋@�̒�i���d�o�͖͂�100kW�i50kW�~2��j�A�^�[�r�����a�͖�11m�B���̂͒�����20m�A����20m�B ��i������1.5m�^�b�i3�m�b�g�j�B���V�[�x�͖�30m�`50m�B ���d�̎d�g�݂́A�C��ɐݒu�����V���J�[�i���j���畂�̎����d���u���C���ɌW�����A�C���̗���ɂ���āA�^�[�r�����Ԃ���]�����邱�Ƃɂ����́B ���肵���C���G�l���M�[�����A���I�ɗ��p���邱�ƂŁA�N��60���ȏ�̍����ݔ����p���ł̔��d�ł���Ȃǂ̓���������Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ꂩ��̖؎��o�C�I�}�X�̗��p�@�_���ȁE�o�Y�Ȃ����|�[�g���\ �_�ѐ��Y�Ȃƌo�ώY�ƏȂ́A�؎��o�C�I�}�X���p�̐V���Ȏ{��ł���u�n����G�R�V�X�e���v�̍\�z�Ɍ����A���Ȃ��A�g���ĐV���Ȏ{��̌������s���Ă����u�؎��o�C�I�}�X�̗��p���i�Ɍ���������������v�̕������܂Ƃߌ��\�����B ���ł́A���{�̎R���n��ɂ����āA�u�n����G�R�V�X�e���v�̎��E���y�E�W�J���}����悤�ɁA���́u�Ώہv�u��́v�u�ڕW�v�u��@�v�u���i����v��5�ɂ��ċ�̓I�ȓ��e�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�C���Ǝ҂̔r�o�W�������\�i2015�N�x���j ����r�o�҂͗v�`�F�b�N ���Ȃ́A�������ʃK�X�𑽗ʂɔr�o����ҁi����r�o�ҁj���A2016�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂ��Z�肷��ۂɗp����A�u2015�N�x�̓d�C���Ǝ҂̎��тɊ�Â����r�o�W���ƒ�����r�o�W�����i 2016�N12��27�����\�j�v���ꕔ�lj��E�C�������\�����B �{�����ł́A2016�N�x�V�K�Q���̓d�C���Ǝ҂̌W����lj�����ƂƂ��ɁA2015�N�x�V�K�Q���̓d�C���Ǝ҂̌W���X�V�Ɨ������j���[�ɉ������r�o�W���i���j���[�ʔr�o�W���j�̌��\����]����d�C���Ǝ҂̌W�����X�V�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2017/8�@]�@�@�� |
|
|
| �������d�́A����Ҍ����Ƀf�}���h���X�|���X�J�n�O�o�Ń|�C���g�t�^ �����d�͂́A�ƒ����WEB�T�[�r�X�u�J�e�G�l�v���p�̌ڋq���A���i�̐����̒��Ŗ����Ȃ��A�y���݂Ȃ���ȃG�l�Ɏ��g�߂�悤�A�O�o�Ȃǂɂ��ȃG�l�Ɏ��g�ꍇ�ɃJ�e�G�l�|�C���g���v���[���g����A�u�\�g�G�l�v��7��1������J�n�����B �u�\�g�G�l�v�𗘗p���A�d�͎��v�����܂鎞���⎞�ԑтȂǂɁA�X�܂⎩���̂̎{�݂ɏo�������ڋq�ɂ́A�J�e�G�l�|�C���g�Ȃǂ��v���[���g����B �ڋq�́A�X�[�p�[�Ȃǒ�g��̓X�܂⎩���̂̎{�݂ɐݒu�����p�̃f�W�^���X�^���v�i�J�e�G�l�X�^���v�j�ɃX�}�[�g�t�H�����^�b�`���邱�ƂŁA�ȒP�ɃJ�e�G�l�|�C���g���l���ł���B���߂��|�C���g�́A�������̓d�C�����̎x������A��g��̃|�C���g�����A���i���ȂǂɌ����ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Y�{�݂ɂ����鎺�����̍œK����V�X�e�����J����20���̏ȃG�l���M�[���������B�听���� �H��Ȃǂ̐��Y�{�݂ł́A����܂Ő��Y�ݔ��̉ғ����ƈ��̍ݎ��ɊW�Ȃ��A�Ɩ��͏펞�_���A�E���C�͏펞�ő�ݒ�ʼn^�]���s���A���p�ȃG�l���M�[������Ă���ꍇ������B�����ŁA�{�ݓ��̃G���A���ɁA�Ɩ��E�E���C���œK�ɐ��䂷��V�X�e�����J�����A���Y�{�݂̏ȃG�l���M�[����}�����B �V�X�e���́A�G���A���ɁA��ƈ��̍ݎ��A���Y�ݔ���Ɩ��E�E���C�̉^�]�Ȃǂ̊�{���B�G���A���ł̏Ɩ��E�E���C�̏Ɠx�A���ʓ��̉^�]��Ԃ�^�]���ԂȂǂ���͂��A�蓮�ʼn^�]���[�h��ݒ肷�邱�ƂŁA�G���A���Ɏ������̍œK������s���B �{�V�X�e���ɂ́A���Y�G���A�A���Y�ݔ��Ȃǂ̒P�ʂŐ��䂷��ʐ���ƒ����Ď�����^������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���C����������́A�G�A�R�������H �ȃG�l���Ɍ��E �G�A�R����肪�������߂ɂƂǂ܂炸�A���K�ȋ�ԍ��ɖ{������ꂾ�����B����l�ɓ��Ă邩�ۂ��̑I�������ɁA�J�����i�߂��Ă���B �G�A�R������o��╗�������ɗ��т�̂����������͑����B�����ŁA�ݎ��҂������悤�ɋ�C�̗�������A�����S�̂̉��K�������߂郂�f�����J�����ꂽ�B �x�m�ʃ[�l�����̍ŐV�@��́A��C�ƕʂɁA�����Ɠ�����C�̐����o������{�̑��ʂɗp�ӂ����B��@�ɂ�镔���S�̂����������铭�����G�A�R���{�̂Ɏ�荞�B ���������C�������ʂ��������̉��K�����オ�A�J�������̎��ƂȂ����B���K�ȋC�����\������A�����p�^�[���łQ�̗���ɕ����ꂽ�B�x�m�ʓ��l�A�����S�̂̋C���𐮂���n��Ƀ_�C�L���H�Ƃ�����B����A�e�l�ɂӂ��킵�������s���|�C���g�ő���̂��O�H�d�@������Ȃǂ��B�p�i�\�j�b�N�͍��N���痼�������p�ɉ��߂��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��60���ȉ��̉������M���Ɋ��p�ȃG�l�Ɛݔ��H����̒ጸ�u�ꋓ�����v �����W�����\���R���g���[���Y�́A���Y����̔r�M�̗��p�\���x�����ቷ��ɂ܂Ŋg�債�A�]����2�{�̉��x���ŔM������\�ȁu��d���p�_�u�����t�g�z���Ⓚ�@�v�i�������B ���N�x����ȃG�l���M�[�@�Ɋ�Â�����ŁA���Y�ݔ��Ȃǂ̉^�]�Ő�����r�M�𖢗��p�M�ƒ�`���A�G�l���M�[���Ƃ��Ċ��p����G�l���M�[�g�p�ʂ��獷���������Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ����B 95���̉������g����12���̗␅��7���ɉ�����d�l�̏ꍇ�A�]���@�ł͉�����75���Ŕr�o����A20�����̉������p�������B �V���i�̔r�o���x��51���ƂȂ�A44�����̔M���G�l���M�[�Ƃ��ĉ���B���ʂ̉�������2�{�̃G�l���M�[��������邽�߁A�����𑗂荞�ޔ������͂��ł����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���啪��s�h�[����LED������[���B���Ń��C�e�b�N ���Ђ́A�啪��s�h�[���̃i�C�^�[�Ɩ��ݔ��Ƃ��āA���`���^���n���C�h�����v2kW�������͂��߂Ƃ���LED������784����A�t�B�[���h�A�q�ȁA�ۈ��Ɩ��Ƃ��Ĕ[�������B����ɂ��]����HID�������g�p�����ݔ��ɔ�ׂāA����d�͂��47���팸�����B �[�����i�Ƒ䐔�́ALED������F784��A���`���^���n���C�h�����v2kW����LED������F156��A���^���n���C�h�����v1.5 kW����LED������F456��A���^���n���C�h�����v1kW����LED������F36��A���^���n���C�h�����v400W����LED������F136��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���āA�Ƃ̒��ŏ����ĕs���Ȃ̂́u�䏊�v��... �������̖����x���� ���������މ��K��Ԍ������ƈ����T�[�`�Z���^�[�́A�u�Z�܂��̉��M���̎��ԂƖ����x�v�̒������ʂ\�����B �������ʂ̊T�v�́A 1.�ƑS�̂̉��M���i�����������A�������j�ɑ��閞���x�́A�Z�܂��̑����I�Ȗ����x���Ⴍ�A�Ă̕s���x�̍����X�y�[�X�́u�䏊�v�Ɓu�g�C���v�A�~�́u���ʏ��v�A�u�����v�A�u�g�C���v�B 2.�Z�܂��̉��M���̖����x�͖k�C�����ł������A�s���x�͍�_�����ł������B 3.�~�G�N�����̎����������Z�܂��ɕ�炷�l�̖����x�͍����B 4.�j�����������̕����A�ȃG�l�s���ɊS�������B�ȃG�l�s����1�ʂ�2�ʂ́A�ċG�E�~�G�Ƃ��u�G�A�R���̐ݒ艷�x�̏グ�����v�Ɓu�Ɩ��͂��܂߂ɏ����v�������B 5.�u���M�����ǂ��ƁA�Ƒ��̋C������g�̂ɗǂ��e���v�ɋ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���k�C���K�X�A�Ǝ��ɓd�͔��搧�x�R�W�F�l���d�̗]��d�͂�13�~�� �k�C���K�X�́A�ƒ�p�K�X�R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e���Ŕ��d�����d�C�����A����Ђ̓d�̓T�[�r�X�u�k�K�X�̓d�C�v�Œn�����������g�݂��J�n����Ɣ��\�����B ���Ђ́A�]��d�͂̔���肪�ł��鑗�d�d�l�i�t�����Ή��j��������A�V���i��8������̔��B����ɂ��킹�ēd�͔��搧�x���X�^�[�g����B�]��d�͂̔���P���i1kWh�j�́u��P���i13.00�~�^1kWh�j���������R?����P���i�k�K�X�̓d�C�Ɠ��z�j�v�B �d�͔��挏�� �d�͔���ʁiMWh�^�N�j�́A2017�N��700�� 1,200MWh�^�N�A2020�N��4,300�� 7,400MWh�^�N��������ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������ٕ̈��Z�k�E�����ŐV�V�X�e���R������1�^3�ACO2�r�o�� �������݂��J�������V�X�e���́A�ŏI������Ŕ�������Z�o����A����������E���^�����y�{�݂̒E����߉t�A�����́E���w�H�Ƃ̔p��������A�������ٕ̈�����������Z�k�E�����H���ɂ����āA���M���u��ؑւ��邱�ƂŔZ�k�������������E������������́B ��̓I�ɂ́A�����Z�x���Ⴂ�i�K�ł́u�O�����M��v��p���Č����悭���M���A�Z�x�����܂��ĉ������͏o����i�K�ɂȂ�u�W���P�b�g�����M��v�ɂ����M�ɐؑւ��A���̂܂܌p�����Ċ����܂ōs���B ����ɂ��A���̐ݔ��Ō����̗ǂ��������\�ƂȂ�A�������ƏȃX�y�[�X�������������B���؎����ł͔R������ʂ͖�1�^3�ACO2�r�o�ʂ͔��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Ȃƌo�Y�ȁA����26�N�x�������ʃK�X�r�o�ʂ̏W�v���ʂ����\ �������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�E���\���x�ɂ�鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̏W�v���ʂ����\�����B���̃f�[�^�́A�n�����g����̐��i�Ɋւ���@���i���Ζ@�j�Ɋ�Â��āA���Ǝ҂���̂������������ʃK�X�r�o�ʂ��W�v���A���܂Ƃ߂����́B �W�v���ʂɂ��ƁA���s�������Ǝҁi���j���́A���莖�Ə��r�o�҂�12,521���Ǝҁi���莖�Ə��F15,027���Ə��j�A����A���r�o�҂�1,352���Ǝ҂ł������B�܂��A���ꂽ����r�o�҂̉������ʃK�X�r�o�ʂ̍��v�l��7��1,294��tCO2�ł������B�Ȃ��A�W�v���ʋy�ъJ�������̕��@�ɂ��ẮA�������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�E���\���x�̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����ȁA�ȃG�l���i�����i�r�Q�[�V�����̔z�z���J�n ���Ȃ́A�ȃG�l���i�����i�r�Q�[�V�����u�J����de���イ����v�����J�����B���Ȃł́A����20�N�x����ȃG�l���i�����i�r�Q�[�V�����u���イ����v�ɂ��ăp�\�R���ƌg�ѓd�b�ŁA�܂�����25�N�x����̓p�\�R���A�X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�gPC�Ŏg�p�ł���悤�^�p���Ă����B ����́u�J����de���イ����v�́A�����������Ɠd���i�̓���ȃG�l���M�[���x�����X�}�[�g�t�H���̃J�����ŎB�邾���ŁA10�N�O�̐��i�Ƃ̓d�C������d�͗ʁACO2�r�o�ʂ̍팸���ʂ̔�r���ȒP�ɂł�����́B���Ȃ�COOL CHOICE�A�v�����_�E�����[�h���邱�Ƃŗ��p�ł���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��SII�A�~�d�r��EMS�����ɕ⏕��VPP�\�z�ɋ��͂��邱�Ƃ����� SII�́A�H���ƒ�Ȃǂ��L����G�l���M�[���\�[�X�����p�����o�[�`�����p���[�v�����g�iVPP�j�̍\�z�Ɍ��������؎��Ƃɂ����āA�~�d�r����VPP���\�[�X��䑕�u���̓������x������⏕���Ƃ̌���v�̂����J�����B ���́uVPP���\�[�X�������i���Ɓi���\�[�X����j�v�̑Ώۂ̓��\�[�X�A�O���Q�[�^�[�ƌ_���������A�~�d�V�X�e����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iEMS�j�A���䑕�u���������ƁB�u���\�[�X�A�O���Q�[�^�[�v�́AVPP�\�z�̂��߃��\�[�X�A�O���Q�[�V�����r�W�l�X�i���\�[�X�����v�Ƃ���W�߂鎖�Ɓj���s���҂Ƃ���SII���o�^�������Ǝ҂��w���B ������Ԃ�2018�N1��31���܂ŁB�Ώېݔ��́A1�D�~�d�V�X�e���A2�D�ƒ�pEMS�E�v���E����EIoT���@��A3�D�Ɩ��p�E�Y�ƗpEMS�E�v���E����EIoT���@��B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���|�X�g�ƒ�p�~�d�r�u�[���ɔ�����h�C�c�~�d�͐��������� �h�C�c�ł͑��z�����d�ɂ��d�͂d�ł͂Ȃ����Ə����A�|�X�gFIT����Ɉڍs���Ă��琔�N���o�B�^�[�j���O�|�C���g�ƂȂ����̂́A������艿�i��d�͗�����������2012�N�ȍ~�ƂȂ邪�A����ɍ��킹�ĉƒ�p�~�d�r�ɑ���⏕�v���O��������������A���ɂ������N�͒~�d�r�u�[���ƂȂ��Ă���B PV�p�l���Ɠ��l�A�~�d�r�ɂ����Ă��A2008�N����2014�N�ɂ����ĔN��14���̉��i���ቺ�����B�s��ł̋��������������ƂŔ��d�R�X�g�iPV�p�l���{�~�d�r�{�ݒu��p�j��������A���悻27ct/kWh�i32�~�j���x�ɂ܂łȂ�A���z���ƒ~�d�r�̍��v�R�X�g���A�d�̓R�X�g�Ɠ����ɂȂ�o�b�e���[�p���e�B�[�͒ʉ߂������ƂɂȂ�B�������A�ƒ�p�ł�70���`100�����x�̓������K�v�Ȃ��߁A�~�d�r�����ɔے�I�ȃh�C�c�����̉ƒ�̂��������߂��������i�����̗��R�Ƃ��ċ����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z��p���z�����d�́u2019�N���v�q�[�g�|���v������ʼn������錤�� �Ȋw�Z�p�U���@�\�iJST�j�́A������w�Ȃǂ��A�q�[�g�|���v�����@�ɂ��f�}���h���X�|���X���ʂƏZ��p�~�d�r�̊��p�ɂ��ƒ�p���z�����d�V�X�e���̎��Ə���ʊg��̌��ʂɂ��ĕ]�����s�����������ʂ\�����B 2019�N�ȍ~�A�Z��p���z�����d�V�X�e����FIT�ɂ�锃����肪�I�����邱�ƂŁA�ƒ�p���z�����d�ۗL���т̌o�ϐ����������邱�Ƃ����O����Ă���B �����ŁA�q�[�g�|���v�����@�ɂ��f�}���h���X�|���X���ʂƉƒ�p�~�d�r�̊��p��ړI�Ƃ��A�V�C�\���ߋ����v�E���d�ʂ����ƂɃq�[�g�|���v�����@�E�~�d�r�̗\���\�^�]�v��\�^�p���f�����\�z�B357���т̎��d�͏���ʃf�[�^��p���ĕ��͂����{�����B ���̌��ʁA�]���̖�ԉ^�]�ɔ�ׂāA���ςŔN��8���̏ȃG�l���ʂ������炷���Ƃ��킩�����B���z�����d�̎��Ə����32������45���֑��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����쌧�M�Z���A20kW�ȏ�̑��z�����d�ɋK�����O���c���̒�o���K�{�� ���쌧�M�Z���́A�u�M�Z�����z�����d�{�݂̐ݒu�Ɋւ���w���v�j�v�Ɓu�M�Z�����z�����d�{�݂̐ݒu�Ɋւ���K�C�h���C���v���{�s�����B �]���́A�y�n���p���Ƃ��s���ʐς�1,000�������[�g���ȏ�̐ݔ��ɂ��āA�͏o���K�v�ȊJ���s�ׂƂ��Ď�舵���Ă����B �������A���n�ɂ���āA���͂̏Z�����ɉe�����y�ڂ������ꂪ���邱�Ƃ���A��������J���s�ׂ𑣂����߂ɁA��i�o�͂�20kW�ȏォ�A�{�ݕ~�n�ʐς�400�������[�g���ȏ�̓y�n�Ɏ������Đݒu���鑾�z�����d�ݔ��́A���֎��O���c���̒�o���K�v�ɂȂ�B �u�M�Z�����z�����d�{�݂̐ݒu�Ɋւ���w���v�j�v�͑S16������Ȃ�A���z�����d�{�݂̐ݒu�҂����ӂ��ׂ������Ȃǂ��߂Ă���B����ɂ�葾�z�����d�{�ݒu����A���̎��Ӓn��ɂ�����ЊQ�̔����𖢑R�ɖh�~���A���Ԍn�ی�ƐX�ы@�\�A���R�i�ς�Z���̕ۑS��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2017/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���g�}�g�̃n�E�X�͔|�ɗ�[�E�����@�\�����p���A���Y���E���v���̌�������� ���k�n���ł́A��Д_�n�̗����p�Ƃ��ăn�E�X�͔|�̓������i��ł���A���ł��g�}�g�͑�^�{�݂ɂ��n�E�X�͔|�𒆐S�ɑ����X���ɂ��邪�A�n�E�X�������ɂȂ�ď�͔̍|������Ƃ����ۑ肪�������B ���k�d�͂́A�ď�̖�Ԃɗ�[�E�������s�����Ƃɂ��g�}�g�̐���ւ̉e����A�q�[�g�|���v�����p�������Y���E���v���������ł���œK�ȉ��x�E���x�������������B ��3�N�Ԃɂ킽�錟���s�������ʁA�g�}�g�̗��ʗʂ��������A�̔��P���̍��܂鎞���̎��n�ʂ�40�����x���シ��ƂƂ��ɁA���n�����g�}�g�̑傫����`�A�F�t���ȂǕi���ʂ̌�����m�F���邱�Ƃ��ł����B���̌��ʁA�N�ԃx�[�X�ł����Y���E���v���̌���ɂ��Ȃ��������Ƃ��m�F�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���n��̓d�͂��܂Ƃ߂Ēn�Y�n���@�����d�͂Ȃǂ�VPP�v���W�F�N�g�J�n �����d�́A�g���^�����ԁA�Ȃ�4�Ђ́A�L�c�s�ƂƂ��ɁA�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��d�͂̋����ɍ��킹�āA���v���𐧌䂵�A�ЂƂ̔��d���̂悤�ɋ@�\������u�o�[�`�����p���[�v�����g�iVPP�j�v���\�z����v���W�F�N�g���J�n�����Ɣ��\�����B ���s�ɐݒu����Ă��镗�́E���z���E�o�C�I�}�X�̍Đ��\�G�l���M�[�ɂ��d�͂̋����ɍ��킹�āA�ƒ���Ƃ̎��v��������G�l���M�[�}�l�W�����g���s���ACO2�t���[�d���ł���Đ��\�G�l���M�[�̒n�Y�n���̎���������������́B ��̓I�ɂ́A�ƒ���Ƃ��ۗL����PHV�A�q�[�g�|���v������A�~�d�r�Ȃǂ�ICT�ɂ��A�[���d�𐧌䂷��B���v���W�F�N�g��2020�N3���܂Ŏ��{���A�V�������Ƃ̑n�o��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��IoT�ŃG�R�L���[�g���œK����A�d�͕��ׂ��� ��a�n�E�X�H�ƂƓ����d�̓O���[�v�̃t�@�~���[�l�b�g�E�W���p���iFNJ�j�́AIoT�Z�p�����p�����u�G�R�L���[�g�v�̐���T�[�r�X���J�������Ɣ��\�����B ���T�[�r�X�͍����ꊇ��d�T�[�r�X������}���V�����ŁA�������Y�����ގ����鋏�Z���т��O���[�s���O���A�O���[�v���Ƃ̃G�R�L���[�g�ғ����Ԃ����U�����悤�ɐ��䂷��B����ɂ��A�}���V�����S�̂̓d�͕��ׂ̕�������ڎw���B �I�[���d�����̗p���Ă����ʉƒ�̓d�͎g�p�ʂɂ����āA�G�R�L���[�g����߂銄���͕���25���ƂȂ��Ă���B�}���V�����S�̂ł͓d�C�����̈�����Ԃɑ����̐��т̃G�R�L���[�g���ғ����Ă��邽�߁A�[��̓d�͎g�p�ʂ��ꎞ�I�ɑ��傷��Ƃ�������肪�������Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ȃG�l�s���A��8�����тŎ��@���dEP�Ȃ� �f���C�g�g�[�}�c�R���T���e�B���O�iDTC�j�́A�d�͒����������A�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�ȂǂƋ����ŁA�Ɠd�⎩���Ԃ̗��p�҂ɏȃG�l���M�[�s���𑣂���K�͎Љ�����n�߂�Ɣ��\�����B �����ōő��8�����т�ΏۂƂ��āA�d�C�g�p�ʂ̌����鉻��A�X�}�[�g�t�H���A�v����HEMS�Ȃǂ�ʂ��������A����҂̍s���ɋy�ڂ��e����������B ���{���Ԃ�2017�N8���`22�N3���B���Ȃ̈ϑ����Ɓu��Y�f�^�̍s���ϗe�𑣂���M�i�i�b�W�j�ɂ��ƒ듙�̎����I�����i���Ɓv�Ƃ��Ď��{����B���N�x�̗\�Z�͖�8���~�B�ƒ�ɂ�����CO2�r�o�ʂ̕���2���ȏ�팸��ڎw���Ƃ����B �i�b�W�Ƃ́A�s���Ȋw�Ȃǂ̗��_�Ɋ�Â�����M�ŁA�s���ϗe�𑣂���@�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���R���͔p�H���I ���d���M�������ł��鏬�^�R�[�W�F�l�A�����}�[������ �ƒ����H�X���Ŕp�����ꂽ�g�p�ς݂̖��ȂǁA�p�����n�o�C�I�}�X��R���Ƃ��Ĕ��d�E�M�������邱�Ƃ��ł��鏬�^�R�[�W�F�l���[�V�������J�������B �����i�́A���̂̃��^�����y�o�C�I�K�X��R���Ƃ���o�C�I�K�X�}�C�N���R�[�W�F�l���[�V�������x�[�X�ɁA���͌����f�B�[�[���G���W���ɑΉ��ł���悤�J���������́B �o�͂�25kW�Ə��e�ʂŁA���K�͂ȓX�܂�H��A�{�݂Ȃǂɂ��ݒu�ł��邽�߁A�n��Ŕ��������p�H����n�Y�n���ŗL�����p�ł���B�{�@����A�g���Đݒu���邱�ƂŁA���o�͉��ɑΉ��ł���B�̔����i��1,500���~�B�^���N���j�b�g�A�t�эH���ȂǁA�ʓr�lj���p��������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z���ƒ~�d�r�́u���z���d���v����ɐi�� �ăX�e���Ђ́A�~�d�r�̃��[�X�ƃG�l���M�[�R�X�g�팸���ƂŐ������A���E�ł����������~�d�r���g���uVPP�v�i�o�[�`�����p���[�v�����g�j�����p�������B �ŋ߂́A���z���p�l����~�d�r�������Ȃ��Ă������߁A�ʏ�̓d�C�Ƒg�ݍ��킹�Ă��܂��g���A�g�[�^���̃G�l���M�[�R�X�g��}������悤�ɂȂ��Ă����B �X�e���Ђ����Ǝ{�݂Ȃǂɒ~�d�r�����[�X�Œ��A�~�d�E���d���œK�ɐ��䂷�邱�ƂŃG�l���M�[�R�X�g��������u�X�g���[�W�E�A�Y�E�A�E�T�[�r�X�v�Ƃ����r�W�l�X��W�J���Ă���B����ɁA�U�݂���ڋq�̒~�d�r��IT�ʼn��u���삵�A��������1�̔��d���̂悤�ɉ^�p����r�W�l�X��W�J���Ă���B �X�e���Ђ̒~�d�rVPP�Z�p�́A���A���^�C���s��ŁA���g���ϓ��ɂ��Ή��ł���g�d���h�Ƃ��Ă��]������Ă���B �o�T�u���o�G�l���M�[�v |
|
|
| ���}�C�N�����͔��d���Ƃ��J�n�A�_�C�L�����q��Аݗ� ���Ђ́A�����ǂȂǂ��甭�d�ł���u�}�C�N�����͔��d�v��p���Ĕ��d���Ƃ��s���q��ЁuDK-Power�v��ݗ������B �}�C�N�����͔��d�́A����܂Ŗ����p���������K�͂Ȑ��̓G�l���M�[�𗘗p���A���d����B���������d�C�͑��z�d���ƎҌo�R�Œn��Z���Ȃǂɒ���B�����̂̓V�X�e���ݒu�ꏊ��Ƃ���DK-Power������ݗ���B �d�͏���ʂ̑����㐅���{�݂�A���𑽂������H��ւ̓�����z�肵�Ă���B�����{�݂ɓ��������ꍇ�A���d�e��22kW�̃V�X�e���Ȃ�N�Ԃň�ʉƒ�42�����A75kW�̃V�X�e���Ȃ�146�����̔��d�ʂ������߂�Ƃ����B �o�T�u�A�C�e�B���f�B�A�v |
|
|
| ���s�s�K�X�A���u���j�X�}�[�g���A�l����팸�R�O�N�x���� �X�}�[�g�K�X���[�^�[�́A���j���郁�[�^�[�ƃf�[�^�𑗐M���钆�p�����@�ō\���B�쓮�ɕK�v�ȓd�͂́A10�N�Ԍ����s�v�̃��`�E���d�r���g�p����B������30�N�x���瓌���K�X���N��10���˂̃y�[�X�Ő�s���Đi�߂�\�肾�B 4���ɍ��ەW�������ꂽ���{���̒����d�̖͂����ʐM�K�i�uWi-SUN�i���C�T���j�v���̗p�B�]���̌g�ѓd�b������g�p���Ȃ����߁A�R�X�g�������A�����̍ۂ̌_��҂̕��S�͂Ȃ����ʂ��B �X�}�[�g���ɂ�艓�u���j�Ől����팸�ł��邽�߁A�K�X�����̒l���������҂ł���B �n�k�Ȃǂ̑�K�͍ЊQ���ɂ̓K�X�R���h�����߂̈�ĕ����\�ƂȂ�ق��A�g�p�ʂ���ٕς��@�m���邱�Ƃō���_��҂̌����T�[�r�X�Ȃǂ��\�ɂȂ�B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ��AI�AIoT���g���ăG�A�R�����ȃG�l�^�]--IIJ�炪UR���݂Ŏ��؎��� UR�A���G�l���M�[�����������A���{�C�ۋ���AIIJ�ƒ����d�͂�UR���ݏZ��ŁA�C���\���Ȃǂɂ��ƂÂ��G�A�R���𐧌䂷�鋤�������Ɏ��g�ނ��Ƃō��ӂ����Ɣ��\�����B ���������ł́A�C�ۃf�[�^�ƁA�G�A�R���ɐݒu����IoT�^�b�v������W��������d�͗ʂ⎺�������̃f�[�^�����ƂɁA�����́u�G�A�R���K���ғ����f���v��p���A�G�A�R���̌����^�]�ɂ��Č�����B ��s���A�������ɂ���v100�˒��x��Ώۂɂ��Ă���A���{���Ԃ�2019�N3���܂ł�\��BUR���ݏZ��ɂ�������؎����́A10��������1�N�Ԃ��߂ǂɎ��{����B �o�T�uCNET JAPAN �v |
|
|
| ��JPEA�̎��i�uPV�{�H�Z�p�ҁv�A�V���x�֎{�H�E�ێ�_����2��� JPEA�́A��N�܂ł�2,938���́uPV�{�H�Z�p�ҁv�̔F����s�������A�����傫���ω��������߁A���z�����d�̌��S�ȕ��y�Ɏ�����l�ނ��琬������ǂ����x�ڍs���邱�Ƃɂ����B �uPV�}�X�^�[�{�H�Z�p�ҁv�́A���s�́uPV�{�H�Z�p�Ґ��x�v�őΏۂɂ��Ă����Z��p�ɉ����A�n��ݒu���܂ޑS�Ă̑��z�����d�ݔ��̎{�H��S����Z�p�҂�F���鐧�x�uPV�}�X�^�[�ێ�_���Z�p�ҁv�͕ێ�_���̒m���A�Z�p���K�����ꂽ���Ƃ�F���鐧�x�B ���x�̏ڍׁE����̎��{�X�P�W���[���́A8������JPEA�z�[���y�[�W�Ō��\�\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������I�ȃ��C�e�B���O�Őߓd�@���s�E�ؒÐ�s�Łu�X���X�}�[�g���v�̎��؎��� ���s�ƃl�b�g���[�N�V�X�e����ЂȂǂ̊�Ƃ������Ŏ��g�ށB��^���Ǝ{�ݎ��ӂ̕���������ɂ���X��23����l�b�g���[�N�����ALED�Ɩ��ɕύX�B �����̊X���ɂ͐l���Z���T�[���ݒu���āA���s�Ҍ��m�Ɠx�����ɂ��d�͏���ʂ̍팸���ʂȂǂ�������B���ł͐��ⓔ200W�i��50W��LED�A���ⓔ100W�i��30W��LED�ɕύX�B�v23��̊X�����ΏۂŁA���ꂼ��ɊX���̏�Ԃ�_���ݒ���𑗎�M����m�[�h����������B�m�[�h��Q�[�g�E�F�C���̏Ⴕ���ꍇ�́A�Ɩ���100���_������d�g�݂Ƃ����B 3��ݒu�����h�ƃJ�����́A�l�b�g�����邱�ƂŎ����������Ȃǂ̑Ή��̐v�������\�ƂȂ�Ƃ����B�J�����f������ʍs�ʂ͂��邱�ƂŁA��薾�邭����Ƃ������������ł���悤�ɂȂ�B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�u����28�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[�����j�v�����\ �o�ώY�ƏȂ́A�u����28�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[�����j�v���A�Ɋt�c���肳�ꂽ�Ɣ��\�����B����̕ł́A�ŋ߂̃G�l���M�[������������̓����܂��A���̓��e�ɂ��ďЉ�Ă���B �@1�j���������̐i���F�����{��k�ЁE�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̂ւ̑Ή����A �@2�j�G�l���M�[����̐V���ȓW�J�F�G�l���M�[�Z�L�����e�B�̋����A������Ɛ����𗼗�����ȃG�l���M�[�E�Đ��\�G�l���M�[�������A �@3�j�G�l���M�[���x���v���ƃG�l���M�[�Y�Ƃ̋����͋����F�����O�d�́E�K�X�Y�Ƃ̎��Ɗ��̕ω����B ���̑��A�G�l���M�[���������╽��28�N�x�ɍu�����{��̊T���ɂ��Ă��L�q���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA����PLC���p�֖@�K�����ꎞ�P�p�^�V���Ƒn�o���� �o�ώY�ƏȂ́A����PLC���AIoT�Љ���x����ʐM�C���t���̈�Ɋ��p���A�h�ƁE�����Ȃǂ̐������Ƃ��ƌ������Ƃ�2020�N�܂łɑn�o���邽�߁A�@�K�����ꎞ�I�Ɏ�蕥���B ����PLC�̉��O�E�������p�𐧌����Ă���d�g�@�Ɠd�C�p�i���S�@���ΏہB�V���Ƃ�v���Ɉ琬���邽�߁A�p�����˂̋Z�p���؎��͋K���������Ȃ��u���M�����g���[�E�T���h�{�b�N�X�v�iRS�A�K���̍���j���x������B ��ƌ����́A�H��̊��ݓd�͐�������PLC�ɂ���A��R�X�g�Őݔ��̉ғ���c���ł���\�������邪�A�d�g�@�͐ݔ��̓d�͐��ւ�PLC���p��F�߂Ă��Ȃ��B�܂��A�Z����ł́A�Ɠd�ւ̓d�g��Q��h���ϓ_����APLC���f���̑g�ݍ��݂��d�C�p�i���S�@�Ő�������Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������s������ƐU������LED�Ɩ����ߓd�����i������ �s���ɂ����Đ����Ƃ��c��ł��钆����Ǝҋy�ђ�����ƃO���[�v�ɑ��ď����B ���Ђ��s���ߓd�f�f�̌��ʂɊ�Â��A�ߓd���ݔ����H�ꌚ�����ɐݒu���鎖�ƂŁA�s���ɖ{�Ђ�����A�s�O�̍H��ɐݒu����ꍇ�́A��錧�A�Ȗ،��A�Q�n���A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�y�юR�����Ɍ���ΏۂƂȂ�B �����Ώېݔ��́ALED�Ɩ����A�f�}���h�Ď����u�A�i���R���f���T�A�C���o�[�^�������́A�����Ώیo���1�^2�ȓ��������x�z�́A1,500���~�i����30���~�j ��W���ԁF����29�N6��1���i�j�`����29�N11��24���i���j |
|
|
| ���@�@[�@2017/6�@]�@�@�� |
|
|
| ��30m�̐�[�x�ł��M�����ł���n���M���p�V�X�e�����J���B�{�H����40���ጸ �O�䉻�w�Y���́A�X���w��H�Ə��Ƌ����J�������A�]���H�@���ŏ\���ȔM�������\�Ȓn���M���p�V�X�e�����A�]�˓������Ă��̉��ɍ̗p���ꂽ�Ɣ��\�����B ���V�X�e���̓����́A���Ђ��V�J�������M�����p�C�v��p���邱�ƂŁA�p�C�v�݂���[�x�i�]���H�@�ł�100m�j���A30m�̐ł��\���ȔM�������\�ƂȂ����_���B ����ɂ��A�n���M���p�̑傫�ȉۑ�ł������{�H��p���A�]���H�@�ɔ�ז�30�`40���ጸ�ł���Ɣ��\���Ă���B�܂��A�����̍��Ǝ҂����L���Ă��鏬�^�̈�ˌ@��@�ł��{�H�ł��A�ėp�������܂����B ���̔M�����p�C�v�͍]�˓������Ă��̉��ł̗\�������̌��ʁA���[�x�Ŕ�r���]���i���37���̐��\���オ�m�F���ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������A���łɃ����f�B�X�E�M�A�̔������ �������쏊�Ɖp���̓����t�@���h�������ŁA���łƎY�Ɗv�V�@�\���o������X�C�X�̃X�}�[�g���[�^�[��胉���f�B�X�E�M�A�̔����𗼎Ђɒ�Ă��Ă���B �����z��20���h���i��2200���~�j���x�Ƒz�肳��Ă���Ƃ����B �����Ɠ����t�@���h�̓����f�B�X�E�M�A������100�����������Ō������Ă���B�����͉��Ăɋ��������f�B�X�E�M�A����荞�݁A�d�͊֘A���Ƃ̊C�O�W�J����������_���Ƃ݂���B ���ł͊v�V�@�\�Ƌ�����2011�N�Ƀ����f�B�X�E�M�A��23���h���Ŕ��������B���݁A���ł�������60���A�v�V�@�\��40����ۗL����B ���ł͌��q�͔��d���Ƃŋ��z�������v�サ�A���̌����߂̂��߃O���[�v��Њ�����ۗL���Y�̔��p��i�߂Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�A�H������G�l�Ǘ��ōU���B�d���s�v�̃Z���T�[���p ���Ђ��A�Ǝ��̐V�Z�p�������A�ǂ��ɂł���y�ɐݒu�ł���V�^�Z���T�[�ōH��E�Ɩ��p�{�����G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X�ōU����������B �ڋʂ̐V�^�Z���T�[�u���ȋ��d���^�����Z���T�[�v�́A����@�B�̐U���A����Ȃǂ̃G�l���M�[�Ŏ��甭�d���ē����A�d�����v�����Ė����Ńf�[�^�𑗐M����BNEDO�̊J�����Ƃ̈�Ƃ��āA�������x�Ƌ����J�������B �V�^�Z���T�[�́A�ݔ��P��P��Ɏ��t���A�d�͂̎g�p�����A���^�C���ŊĎ��ł���B�H��ݔ��Ȃ琶�Y���C���̒��ŗ��ꂪ�ؗ����Ă���ӏ���A�i���ւ��ɔ����d�̖͂��ʌ���������o����B���T�[�r�X�ł̓K�X�␅���̎g�p���c���ł��A���Y���C���Ȃ�g�[�^����5�`10���A�Ɩ��p�{�݂Ȃ�3�`8���̏ȃG�l���ʂ������߂�Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���G�l�`�F���W�A���Ǝ҂̗v�]�ɉ���������r�T�C�g���ʊJ�� �d�͔�r�T�C�g���^�c����G�l�`�F���W�͓d�C�E�K�X�̏������Ǝ҂̗v�]�ɉ����āA������r�T�C�g���J���E�^�p����T�[�r�X�̖{�i�W�J���n�߂��B �����K�X��4���̓s�s�K�X������S�ʎ��R���Ɍ����č\�z�����E�F�u�V�X�e�����������Ƃ����̂قǖ��炩�ɂ����B�G�l���M�[�̊_�����z�����������{�i�����钆�A���ЃT�C�g�̉^�p��ʂ��Ĕ|�����m�E�n�E����A�������Ǝ҂̌_��l�����㉟������B �G�l�`�F���W�͍������̓d�͔�r�T�C�g�B�S���e�n�̋C�ۏ����̈Ⴂ�܂��āA�d�C�E�K�X�̎g�p�ʂ������x�ɗ\���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����{�̃S���t��̓��K�\�[���[�ɕς���Ă䂭�B���x�͕�������44MW �W���p���E���j���[�A�u�����r�E�G�i�W�[�Ƃӂ����ܖ���������A�M�v�R�����d�͕͂����������͌S�������̃S���t��Ւn�ɂ����āA���K�\�[���[�̋N�H�����s�����B ���{�݂́A3�Ђ������o�����鍇����А��̋��\�[���[�p�[�N���A�����̋��J���g���[�N���u�̐Ւn�𗘗p���Č��݂�����́B ���d�\�͂�4��4001kW�i�p�l������25��1520���j�ŁA�v�H��͌����̑��z�����d���Ƃ��Ă͍ő�K�͂ƂȂ�B2019�N12���̊�����ڎw���B���d�����d�C�͓��k�d�͂ɔ��d����B����A70MW���̑��z�����d���A30MW���̕��͔��d���̌��݂��v�悵�Ă���B �W���p���E���j���[�A�u���E�G�i�W�[�́A�ċ��Z�@�ւ̃S�[���h�}���T�b�N�X�n�̍Đ��\�G�l���M�[���̔��d���ƎҁB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���`�h�����p�����d�C�g�p�ʂ̕��͋Z�p�̌��؊J�n�ɂ��Ē����d�� ���Ђ́A�ƒ�����̓d�͊Ǘ��T�[�r�X����Ă���Bidgely, Inc.�i�č��j�A�����AI�����p�����f�[�^��̓v���b�g�t�H�[������銔�����ABEJA�i���{�j�ƁAAI�����p���ēd�C�g�p�ʂ͂���Z�p�̌��؊J�n�ɂ��č��ӂ����B AI�����p�����d�C�g�p�ʂ̕��͋Z�p���m�����邱�ƂŁA�Ɠd���ƂɌv��������t���邱�ƂȂ��ȒP�Ɋe�Ɠd�̎g�p��c���ł��邱�Ƃ���A��肨�q���܂ɍ������ȃG�l���@��Ɠd�̎g�����̃A�h�o�C�X��������T�[�r�X��A����ĕ�炷���Ƒ��̌������s���T�[�r�X�Ȃǂ������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B����ɁAAI�����p���A�d�C�g�p�ʂ͂��邱�ƂŎ����ł���l�X�ȃT�[�r�X���������Ă����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���������������Ɂc�k�d�c�Ɩ��́u���s��v���[�J�[�e�Ђ���@���������� �}��������LED�Ɩ��̎s�ꂪ�A�Ȃ���p���}���Ă���B���v���ꏄ������ɁA�������Ƃ��������b�g�������ƂȂ��Ĕ����ւ����v�̐L�т������߂Ȃ��B���[�J�[�e�Ђ͓Ǝ��̃T�[�r�X�⏤�i�W�J�ŁA�����͂����߂����Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B ������Ђ́A�Ɩ��p��LED�Ɩ����̍����s���2015�N��4913���~�������̂��A2030�N��4278���~�ɏk������Ɨ\�����Ă���B����A���҂���Ă���̂��A�A���͔|�p���B�x�m�o�ςɂ��ƁA�����s��͂܂�10���~�i����27�N�j�Ə��������̂́A2030�N�ɂ�15�{�ȏ�Ɋg�傷�錩�ʂ����B �����Ԃ̃w�b�h���C�g���L�]������Ă���B���E�I�ɐV�Ԕ̔��͍D���ŁA���ʂ͎��v�̐L�т����҂����B �o�T�uSankeibiz�v |
|
|
| ��������ȂǁA�V���ȃj�[�Y�ɑΉ�3�Ђ���LED�Ɩ��̐V���i���\ �A�C���X�I�[���}�́A�H��A�q�Ɍ����́u���V��pLED�Ɩ�HX�|R�V���[�Y�v��{�N7����蔭������B ����������v�����y���Ă���H���q�ɂ̑�֎��v��_�����́B���V���[�Y�͌y�ʐv�i2.2kg�j���A195.3lm�^W�ƍ������i���В��ׁj�ł���A��ʓI�Ȑ��ⓔ�Ɣ�r���ď���d�͂��ő�81���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B�ʔ����ŕ������̂Ȃ�LED�A7���ɓo��B �p�i�\�j�b�N�́ALED��ʂŔ���������X�N�G�A�����^�C�v������B����d�͂́A��58���팸�ƂȂ�B �u��t�F�؏��i�v��LED�v���C���E�X�^�[�́ALED�Ɩ�������ῂ����E�ڂ̔��Ȃ�6���ڂ��]������uJMC association�F�؈�t���E���i�v�̎w������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����N�̉Ă͖ҏ��ł����vOCCTO�A�ċG�d�͎������ʂ��\ �d�͍L��I�^�c���i�@�ցiOCCTO�j�́A2016�N�x�~�G�̓d�͎������т�2017�N�x�ċG�̓d�͎������ʂ��ɂ��āA���،��ʂ����܂Ƃ߂��������\�����B ���Ă̎������ʂ��̌��ł́A����10�J�N�ōł��������C�ۏ����ƂȂ����ꍇ�ł��A�����o�����X�����i�f�}���h���X�|���X�Ȃǁj�̊��p�A�Η͑��o�͉^�]����уG���A�Ԏ���̊��p�ɂ��A�S���I�Ɉ���I�ȓd�͋����ɕK�v�ȋ����\����3�����m�ۂł��錩�ʂ��ƂȂ����B ����ɁA10�N��1����x�̖ҏ��ɂ�����ő�d�͎��v���������ɂ����āA���d�@�̒�~��d��1������̓��̒P��̏Ⴊ���������ꍇ�ɂ����Ă��A�S���ŗ\����3�����m�ۂł��邱�Ƃ��m�F�����B�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�G�l���M�[���c�����10�ЂƁu�Ή��l����s��v�̐��x�v�ɑ���� ���R�G�l���M�[���c��Apple��x�m�ʁA�\�j�[�AMicrosoft�Ȃǂ̊��10�ЂƋ����ŁA���{�����ɂ����鎩�R�G�l���M�[�̗��p�g��Ɍ����āA2017�N�x���̑n�݂������܂�Ă���u�Ή��l����s��v�̗L���������߂邽�߂̒�Ă��Ƃ�܂Ƃ߂��B ��Ƃ̍Đ��\�G�l���M�[�̊��p�𑣂����߂̊������Ɍ��������̂ŁA�ȉ���3�_�ō\�������B �@1) ���R�G�l���M�[�d�̗͂��p��錾�ł��邱�� �@2) ���R�G�l���M�[�d�͂ƌ��q�͔��d���敪���邱�� �@3) ���R�G�l���M�[���A���z���A���́A���K�͐��́A�o�C�I�}�X�Ȃǂ̋敪�����邱�� ���{���{��2030�N��CO2�r�o�ʂ�2013�N���26���팸����ڕW���f���Ă���B���̂��߂ɔΓd���i���q�́{�Đ��\�G�l���M�[�{��^���́j�̔䗦��44���ȏ�ɍ��߂���j�ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ቷ�ł̔M�d��p�������^���匤���O���[�v�A�����\�ϊ��ޗ��� ���É���w�̌����O���[�v�͂��̂قǁA�����ȉ��̕��L�����x��ŗD�ꂽ���\�������V�����M�d�ϊ��ޗ��������B �V�ޗ��̓^���^���ƃP�C�f���܂ރe���������ŁA�]���̍ޗ��ō�������}�C�i�X100���ȉ��̒ቷ�ŔM�d��p�i�y���`�G��p�j�ł���B���̍ޗ����g�����ƂŁA���d���f�q����ނȂǂ��|����ȑ��u���}���g�킸�A�Ǐ��I�ɗ�p���ē��삳����\�����J����Ƃ����B �M�d�ϊ��ޗ��͒��ڔM��d�C�ɕϊ����鐫����������A�t�ɓd�C���g���ė�p���邱�Ƃ��\�ŁA����܂ō�������ቷ�ł̔M�d��p���\�Ƃ���_�ʼn���I�ł���C��|����ȑ��u�Œቷ�ɗ�₵�Ďg���Ă����f�o�C�X��ޗ����C��}���g�킸�Ǐ��I�ɗ�p�����삳����\������́B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���u�G�R�A�N�V�����Q�P�K�C�h���C���i2017�N�Łj�v�̉����ɂ��� ���Ȃł͕���8�N���A�������Ǝғ��̕��L�����Ǝ҂ɑ��āA����I�Ɂu���ւ̊ւ��ɋC�Â��A�ڕW�������A�s�����邱�Ƃ��ł���v���@�����ړI�ŁA�G�R�A�N�V����21�����肵�A���̕��y��i�߂Ă����B����29�N�R�������݁A�S��7,791���Ǝ҂��A�{���x�Ɋ�Â��F�E�o�^���Ă���B ���Ȃ́A�G�R�A�N�V����21�̎�g�̗L��������w���߁A���Ǝ҂̉��l����ɂ������邱�Ƃ�ڕW�ɁA�{�K�C�h���C���̉�����i�߂Ă����B5�N�Ԃ�ɉ������A�u�G�R�A�N�V����21�K�C�h���C���i2017�N�Łj�v�Ƃ��Ď��܂Ƃ߂��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ɓ��̎R���ɋ���Ȉ��k��C�G�l���M�[�����{�ݕ��͔��d�̏o�͕ϓ��}�� NEDO�Ƒ���c��w�A�G�l���M�[�����H�w��������́A�V��̉e�����₷�����͔��d�̏o�͒����p�ɁA���k��C�G�l���M�[�����V�X�e���������A���؎������J�n�����B ���k��C�̗��_�́A �@1�j��R�X�g�̉\�� �@2�j������ �@3�j�p�����y �@4�j�͂ꂽ�Z�p�ŐM���������� �@5�j���ɗD���� �Ȃǂ��ƌ����B�قƂ�ǂ������̋Z�p�����Ő��藧���A�����ȕ��i��댯�ȍޗ��͎g���Ȃ��B ���d�E�[�d���j�b�g�͋�C���k�@/�c���@�A�~�M���Ȃǂ���Ȃ�A�o�͂�1000kW�i500kW��2��j�B��C�^���N�͒��a2m�ō���11m�A�ō����͂�0.93MPa�i��10�C���j�B���̋�C�^���N��52�{����A�~������G�l���M�[�e�ʂ�500kWh���Ƃ����B���k��C�̓G�l���M�[���x���Ⴂ���Ƃ����_���B �o�T�u���o�e�N�m���W�[�v |
|
|
| �������E�G�l���M�[�W�{�����p�K�C�h�u�b�N���X�V �ߋE�o�ώY�Ƌǂ́A�����E�G�l���M�[�W�{�����p�K�C�h�u�b�N���X�V�����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2017/5�@]�@�@�� |
|
|
| ����ʐ��i�̖�7.5�{�A�v����30�����Ԃ�LED�d�����V���� KK�e�N�m���W�[�Y�́A10�N�Ԋ��S�ۏ�LED�d���������B ���Ђɂ��ƁALED�d���̒��������̏�Q�ɂȂ�̂́A�����ɂȂ�₷���ӏ��ɑg�ݍ��܂��d���R���f���T���A�M�ɂ��j�����邽�߁B �V���i�́u�d���R���f���T���X�E�e�N�m���W�[�v�ɂ���L�̖����������A���̐v������30�����Ԃɂ���ԁB����͈�ʓI��LED�d��4�����Ԃ̖�7.5�{�ɂ�����B300����̃I���I�t�ɂ��ς��A�����g�p�̐M�������m�ۂ����Ƃ��Ă���B�����̎����E�J�͂������č��ꂽLED�d�����A���\�~�́u�d���R���f���T�v�̌̏�̂��߂ɁA�{���̎�����҂����ɃS�~�ɂȂ��Ă��܂��B���́u���������Ȃ��v�������i�J���̃R���Z�v�g���B ����ɁA�M��`����̂ɏd�v��LED��̃T�[�}���C���^�[�t�F�[�X�ɂ́A���M�`�����̃V���R���n�|���}�[���̗p�B���M���ɂ͍����A���~�j�E���������̗p���A���M���ƌ��S�������������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d�d�o�ƃG�v�R�A�ȃG�l���t�H�[���Œ�g�^�V��Аݗ��������� �����d��EP�́A��2,000�����̂��ƒ�̓d�͎g�p�f�[�^�ɉ����A����܂Ŏ��{���Ă����ȃG�l�Ɋւ����Ă�G�R�L���[�g���̏ȃG�l�@��̊J�����тȂǏȃG�l�Ɋւ���m����ۗL�B �G�v�R�́A100��������ݔ��v�m�E�n�E��Z��S�ʂ̃A�t�^�[�����e�i���X�ɑΉ�����J�X�^�}�[�T�|�[�g�T�[�r�X����т������x�����Ɩ��V�X�e����ۗL�B ����A�����o����Ђ̐ݗ��Ɍ����ċ��c��i�߂�ƂƂ��ɁA���Ђ͂��ꂼ��̋��݂��������A�P�Ȃ�C�U��ݔ��@��X�V�Ȃǂɗ��܂炸�A�Z��̏ȃG�l���t�H�[���̒�Ă���v�A�{�H����уA�t�^�[�T�[�r�X�܂Ń����X�g�b�v�Œ��鎖�Ƃ̎����Ɍ����Ď��g��ł����B ���Ђ́A�K�ȃ��t�H�[�����s����T�[�r�X�̒�ʂ��āA�Z�܂��ɂ����鎺���������コ���A�����K�E���N�ȕ�炵�̎����Ɏ��g�݁A�����Z��̐ϋɓI�ȏȃG�l���𐄐i����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���t���C�z�C�[���~�~�d�r�A���͔��d�̓d�͂����艻�č��̃}�C�N���O���b�h ABB�́A�č��A���X�J�ɂ����镗�͔��d�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�̃v���W�F�N�g�ɁA�~�d�r�ƃt���C�z�C�[����g�ݍ��킹���}�C�N���O���b�h�V�X�e������������Ɣ��\�����B ���̃v���W�F�N�g�́A�A���J���b�W��4�L������17MW �̗m�㕗�͔��d�Ȃǂɂ��Đ��\�G�l���M�[���A��葽���d�͌n���Ŋ��p�ł���Z�p�̊m����ڎw���Ă���B�t���C�z�C�[����Z�����ŕϓ����镗�͔��d�̓d�͂����肳���A�~�d�r�͒������̓d�͈���E�~�d�Ɏg����B�~�d�r�̗e�ʂ�500kW h�A�ő�o��2MW �B ���̃V�X�e���ɂ��A�A���J���b�W�̏Z��30���l�ւ̓d�͈��苟���̑啝�ȉ��P���߂����B ���V�X�e���́A�Ő�[�̃}�C�N���O���b�h�v���X�R���g���[���V�X�e���ɂ��A�V�X�e�����Ď����œK�ȃG�l���M�[�����o�����X���m�ۂ��邾���łȂ��A���u�Ď��@�\����[�g�����e�i���X�@�\�����ڂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�[�o���G�i�W�[�A�Ս`�p�[�N�֓d�͋����J�n�@�`�V�T�[�r�X�u�n�d���v�ɂ��p�����̗L�����p�` JFE�̎q��Ђ̃A�[�o���G�i�W�[�́A�p�V�t�B�R���l���Ǘ�����Ս`�p�[�N�ւ̓d�͋������J�n�����B ����̓d�͋����́A�p�V�t�B�R���l���Ǘ�����{�݂�����Ŏ��W�����p������R���ɂ��Ĕ�������d�͂ŗՍ`�p�[�N�̓d�͎��v�̈ꕔ��d�����̂ŁA�d�͋����ʂ͔N�Ԗ�30��kWh�B ���̔p�����́AJFE���ɂ����W�E�^������A�Y�Ɣp���������{�݂ŏċp�E���d�����B�A�[�o���G�i�W�[�́A���d�����d�͂��A�Ս`�p�[�N�ɋ�������B ����̂悤�ɁA�p�������甭�d�����d�͂��A�������{�݂�������ꍇ�ɁA�p�����̏����ʂɉ����ēd�͗�������������u�n�d���i�����ł���j�v�T�[�r�X�����{����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���V���{�u�~�[���C�œK����V�X�e���v���J�� ���Ђ́A�~�[���C�ݔ��ɂ����銷�C���ʂ��œK�ɐ��䂵�A�E���C�G�l���M�[��啝�ɍ팸�ł���ȃG�l����V�X�e�����J�������B �_�N�g���̔r�C���x�ʼnC�̎g�p�f���ĉϕ��ʑ��u�iVAV�j�������œ��삳����B�����āA1�N�Ԃ̎��������ɂ��A��30%�̈ꎟ�G�l���M�[����ʂ��팸�ł����B �����p�r�e�i���g�r���́A�P�ʖʐϓ�����̃G�l���M�[����ʂ����H�X�͎�������2�{�i�~�[��15�{�j�ȏ�̃G�l���M�[������Ă�����Ԃ�����B��ʓI�ɐ~�[�@��̎g�p���ח���20�`30�����x�ɗ��܂�ƌ����Ă���A�g�p���Ă��Ȃ����ԑт��ߏ肩���ʂȊ��C�^�]���s���Ă���̂�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���H�ƘF�̍����r�C���E�ė��p����r�C�M�z�V�X�e�����J�� NEDO�ƃp�i�\�j�b�N�́A�H�ƘF�̔r�C�M�G�l���M�[�������̂܂܍������ɍė��p����r�C�M�z�V�X�e�����J�������Ɣ��\�����B �H�ƘF�Ȃǂ̉��M������v����M�v���Z�X�H���ŏ����G�l���M�[�̓��m�Â���S�̂̑唼���߂Ă���B���̒��ŁA�S�H�ƘF�̔r�C�M������70%��200�������̔r�C����߂Ă���A�H�ƘF�̏ȃG�l�Ɍ����A�����r�C�M�G�l���M�[�̍ė��p�Z�p�̊J�����K�{�ƂȂ��Ă���B ����J�������V�X�e���́A�����r�C���Ɋ܂܂��s�v�Ȕ����q�ɓd�E�𗘗p���č������ɕ����������A�����r�C���ēx�F���ɖ߂��ė��p������́B���̃V�X�e�������t���[�F�Ɏ������A500���Ԉȏ�̘A���^�]�������ʁA�����q�̏W�o��91%�A�r�C�M�G�l���M�[�������75%�����������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����̑f�A�o�C�I�}�X���d�Ȃǂɂ��S�Ђ̃O���[���d�͉��𐄐i ���Ђ́A���{���R�G�l���M�[�Ɓu�O���[���d�͏؏��v�̍w���Ɋւ���_���������A�����c�Ƌ��_�Ȃǂ̑S�g�p�d�͂�100%�O���[���d�͉�����B ���Ђ́A�u���W���A�^�C�A�x�g�i���ɂ����ăo�K�X�i�T�g�E�L�r�̍�肩���j����݊k���������Ƃ���o�C�I�}�X���d�̗��p�𐄐i���Ă���A���ЃO���[�v�S�̂̍Đ��\�G�l���M�[�䗦��19%�i2016�N9�����݁j�ƂȂ��Ă���B����A�����̍Đ��\�G�l���M�[�䗦�̊g��Ɍ����āA�o�K�X�𗘗p�����o�C�I�}�X���d�R���̍Đ��\�G�l���M�[���g�p�����Ƃ݂Ȃ����u�O���[���d�͏؏��v�̎d�g�݂����p����B �؏��̍w���́A�o�C�I�}�X���d�ϑ��_��̌`�ԂŁA2017�N4���`2020�N3���i�p���X�V�̗\��j�̌_��B2030�N�x�ȍ~�́A�ȃG�l�̐��i��C�O���_�ɂ�����o�C�I�}�X�{�C���[����уR�W�F�l���[�V�����̓����E���݂��s���A���ЂōĐ��\�G�l���M�[�䗦50%�̎�����ڎw���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���R���d�r�ƃK�X�^�[�r����g�ݍ��킹���������d�V�X�e���̎��؊J�n ���{���ꓩ�Ƃ�������Ƃ��ĉ~���`�̌ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j�ƃ}�C�N���K�X�^�[�r����g�ݍ��킹���u�����^�������d�V�X�e���v�Џ��q�H����ɐݒu���A�^�]���J�n�����B �����G�l���M�[���������R���d�r�́A�G�l���M�[����ʂ�����ׂ̒ጸ�ɑ傫���v�����邱�Ƃ����҂���Ă���BSOFC�͍����쓮�Ŕ��d�����������A�����גጸ�ւ̊�^�������Ƃ����Ă���A�}�C�N���K�X�^�[�r���Ƃ̕������d�ł���ɔ��d�������グ�邱�Ƃ����҂����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����B�̎�v�ȃG�l���M�[��ƁA2020�N�ȍ~�ɐΒY�Η͔��d����V�݂��Ȃ����Ƃ����\ ���B�̎�v�ȃG�l���M�[���3500�Ђō�鉢�B�d�C���ƎҘA���́A�p������̖ڕW�B���Ɋ�^���邽�߁A���B�A������2020�N�ȍ~�ɐΒY�Η͔��d����V�݂��Ȃ����Ƃ����\�����B ���A���͐ΒY�̎g�p�팸�Ɏ��g�݁A2050�N�܂łɉ��B�ɂ����āACO2�̔r�o�Ƌz�����v���X�}�C�i�X�[���ɂ���Y�f������B�����A���������i�����͂�����A�M���ł���d�͋������������邱�Ƃ�����B���A���ɂ��ƁA���B�̓d�͂͒Y�f�����ւ̓��𒅎��ɐi��ł���A�����ȗ��p������A����ł͊��S�Ɏ����\�ȎY�ƂɂȂ�W�]�̂Ȃ����̕���ɂƂ��Ă��ǂ����ʂ�����Ƃ����B ���A���͂܂��AGHG�r�o�팸�ƒ�Y�f�Z�p��G�l���M�[��������ւ̓����̎h���ɂ͎s�ꃁ�J�j�Y�����ł��ǂ��c�[�����Ƃ��āAEU�r�o�ʎ�����x�iEUETS�j�̋������x�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���n�Y�n���^�̍ăG�l�E�ȃG�l69����NEPC�̉\�������E���ƌv��܂Ƃ� �V�G�l���M�[�������i���c��iNEPC�j�́A�n�Y�n���^�̃G�l���M�[�V�X�e���̍\�z��i�߂邽�߂Ɏ��{���鎖�Ɖ��\�������⎖�ƌv�������x������⏕���Ƃ�2016�N�ɍ̑�����69���ɂ��āA�e���Ǝ҂���o���ꂽ���ʕ��̗v��ł����\�����B ���ɂ́A�ݔ��T�v�⎖�Ǝ��{�̐��E���ƃX�L�[���E�X�P�W���[���A�̎Z���]���ȂǁA�����܂Ƃ߂��Ă���B ����̑�����Ă��鎖�Ƃ́A�u���Ɖ��\�������v�i�⏕�z�F��z1,000���~�ȓ��j��62���ƁA�u�}�X�^�[�v��������v�i�⏕�z�F��z3,000���~�ȓ��j��7���B ���ʕ��i�v��Łj http://www.nepc.or.jp/topics/2017/0329.html �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�O���[���G�l���M�[�؏��̔� �s�����ݒu�������z�G�l���M�[���p�V�X�e���ɂ�萶�ݏo���ꂽ100%�s���Y�̃O���[���G�l���M�[�؏���̔����Ă���B ���d���ݔ��������Ȃ��Ă��A�؏����w���������́A�؏��������̃O���[���G�l���M�[���g�p���Ă��邱�ƂƂ݂Ȃ���A�n�����g���h�~�ɍv���ł���B�؏��͎g�p�d�͂̈ꕔ�ɏ[�����邱�Ƃ��\�B �E�̔����ԁF����29�N4��3�����畽��30�N2��15���܂� �E�̔��ΏہF�O���[���d�͏؏��E�O���[���M�؏� �E�̔����i�F �O���[���d�͏؏�7�~�^kW h�i�ŏ��̔��P��1,000kWh�j�A�O���[���M�؏�26�~�^MJ �i�ŏ��̔��P��100MJ�j �ڍy�ѐ\���݂ɂ��ẮA���L�z�[���y�[�W���Q�� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v https://www.tokyo-co2down.jp/action/efforts-renewable/green_energy/ |
|
|
| ������27�N�x�i2015�N�x�j�G�l���M�[�������т����܂Ƃ߂܂����i�m��j �����G�l���M�[���́A�e��G�l���M�[�W���v������ɁA����27�N�x�̑����G�l���M�[���v�m����쐬���A�G�l���M�[�������тƂ��Ď��܂Ƃ߂��B �ŏI�G�l���M�[����́A�ȃG�l�̐i�W��O�N�x�ȏ�̗�āE�g�~�����e�����A�O�N�x��1.4%���ƂȂ�5�N�A���Ō��������B����ʂł́A��ƁE���Ə������傪��0.9%���A�ƒ땔�傪��3.3%���A�^�A���傪��1.6%���ƁA�ƒ땔��𒆐S�ɑS����Ō��������B CO2�r�o�ʂ́A�G�l���M�[���v����d�͂̒�Y�f�����ŁA�O�N�x��3.4%���ƂȂ�2�N�A���Ō����B�k�Ќ�ł͍ŏ��ƂȂ����i�d�͂�CO2���P�ʂ��A�O�N�x��0.55kg-CO2/kW h����0.53kg-CO2/kW h�ɉ��P�j�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_021.pdf |
|
|
| �����k��C�œd�͒����^�G�l���H���A����Ȃǂ��V�X�e�����؊J�n ��ʍ��c�@�l�G�l���M�[�����H�w��������NEDO�A����c�A��w�_�ː��|�́A���͔��d�̗\�����Ɋ�Â�����Z�p��p�������k��C�G�l���M�[�����iCAES�FCompressed Air Energy Storage�j�V�X�e���𓌓dHD�̓��ɓ����͔��d���Ɛڑ������A�d�͂̕ϓ����ɘa��������؎������J�n�����B CAES�V�X�e���̐���Z�p�ɂ��ẮA���͔��d�̗\�����Ɋ�Â��ϓ��ɘa����ƌv�攭�d������J������B CAES�V�X�e���̐ݔ��́A���͔��d���瓾���d�͂��g���āA���k�@�i���[�^�[�j�ŋ�C�����k�A������ԂŒ�������B�����āA�d�͂��K�v�ȍۂɁA�����������k��C�Ŗc���@�i���d�@�j����]�����A�d�͂�������B���k�̍ۂɔ�������M���������A���d���ɍė��p���邱�Ƃŏ[���d���������コ���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����ȁA����29�N�x�u�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����v�����{ ���Ȃ́A����29�N�x�u�ƒ땔���CO2�r�o���ԓ��v�����v�����{����Ɣ��\�����B�ƒ땔���CO2�r�o�ʂ́A2015�N�x��1��8,200���g���ƂȂ����B �n�����g����v��ɂ�����u�ƒ땔���2030�N�x�ɂ�2013�N�x���4���̍팸�v��B�����邽�߂ɂ́A���ʓI�ȍ팸���i���Ǘ����d�v�ƂȂ��Ă��� �B ����A�ƒ납���CO2�r�o���Ԃ�G�l���M�[������ԓ����ڍׂ��p���I�ɔc�����A�팸��̌������ɕ��L�����p���邱�ƂȂǂ�ړI�Ƃ���B �������Ԃ͕���29�N4�����畽��30�N3���܂ŁA�S��10�n����13,000���т�ΏۂɁA 1�j�Z����{�䒠����̖���ג��o�ɂ�钲���������� 2�j���Ԏ��ƎҕۗL�̒������j�^�[���璊�o�����C���^�[�l�b�g���j�^�[�����ɂ����{����B ���Ȃł́A�����̌��ʓ����W�v�E���͂��A����30�N9���܂łɌ��\����\��Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2017/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���E�V�I���C�e�B���O�A���^�E���^���́u���^LED �_�E�����C�g�v��̔��J�n ���Ђ́A��ʏƖ��A���Ǝ{�݁E�X�܂Ŏg�p����锖�^�E���^���_�E�����C�g�̔̔��J�n�����B �����́A(1)����20mm�i���ߍ��ݐ[��30mm�j�̔��^�v�A(2)�d�������i100V�d�l�j�ł���Ȃ���R���p�N�g�T�C�Y�A(3)���m�{���̐F�ʂ�N�₩�ɍČ����鍂�����F��(Ra95)�A(4)�X���[�Y�Ȓ����������B LED�d���J���Ŕ|���Ă����d����H�v�̋Z�p�A�m�E�n�E���t���Ɋ��p���A�d�������Ƃ������ƂŁA�ʓr�A�d����ݒu����X�y�[�X���s�v�B ���i�o���G�[�V�����Ƃ��ẮA4��̐F���x�o���G�[�V�����i2700K�A3000K�A3500K�A4000K�j�A��i������40,000 ���ԁB ���邳�́A��ʓI�ȏ��`�d��25�`�ɑ�������S�����i250 lm�^2700K �A290 lm�^3000K�A300 lm�^3500K�A310lm�^4000K�������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����d�s���Y�A�r���Ȃǂ̏ȃG�l�ݔ����C�Ɠd�̓T�[�r�X���Z�b�g�̔� �r�������^�c�E�Ǘ��T�[�r�X���s�������d�̓z�[���f�B���O�X��100���q��Ђ̓��Ђ́A�r�������e�i���X�E�ݔ��@�퓱���E�d�͒��B���ꊇ�Ŏ��邱�ƂŁA�ڋq�̏�����p��ጸ���ȃG�l��}��u�����ݔ����C�������T�[�r�X�v���A�J�n�����B ���̃T�[�r�X�́A��d�ݔ���ݔ��A�Ɩ��ݔ��Ȃǂ̌����ݔ��̍X�V�A�����E�O���H����ϐk�⋭�H���Ȃǂ�\�肷��r���I�[�i�[��ΏۂƂ��Ē������́B ��̓I�ȓ��e�́A�E�V�����ݔ�������ہA�I�[�i�[�̗\�Z��ݔ��X�V�v��ɂ���āA�x������юx�����@�����R�ɑI���ł���B �@�E�����d�̓O���[�v�ł��邱�Ƃ��������A�d�͂̒��B�Ɖ^�c�Ǘ���ƍ��킹�Č_�邱�ƂŁA�R�X�g�ጸ���͂���B �@�E��������^�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���@��Ȃǂ��Őݒu���A�ݔ��X�V��p��}���A�ȃG�l����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Z�F�d�H�@�J���t�H���j�A�B�ő�K�͒~�d�V�X�e���̎��؉^�]�J�n ���Ђ́A�č��J���t�H���j�A�B���{����ѕč����d�͉�Ђł���San Diego Gas and Electric�Ёi�ȉ��ASDG&E�Ёj�Ƌ��͂��A���B�T���f�B�G�S�ɂ����ĕč��ő�K�͂ƂȂ郌�h�b�N�X�t���[�d�r��p�����~�d�V�X�e���̎��؉^�]���؉^�]�̊J�n�����J�Â����B �{���؉^�]�ł́A�ϓd�����Ɍn���p�~�d�r�Ƃ��ă��h�b�N�X�t���[�d�r(2MW�@x�@4����)��ݒu���A���g�������A�d�������A�]��d�͑Ή��Ȃǂ̑��p�r�^�]���s���A���h�b�N�X�t���[�d�r�̌o�ϓI���l�����コ����z�d�E���d���p�̉^�]�������{����B ���B�ł́A���z�����d�̑����ɂ�钩�[�̋}���Ȏ��v�ϓ����ϑ��������v�Ȑ���d�͕i���ቺ�̖�肪���݉�������A�B�@�œd�͒������u�̓����`����d�͉�Ђɉۂ��ƂƂ��ɁA�~�d�r���[�h�}�b�v�����肵�A�~�d�r���K���Ȏ�������悤�Ȑ��x�v���s���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}�A�Ɩ�����V�X�e����̔�LED�Ɩ�������ɏȃG�l�� ���Ђ́A�V���ɓƎ��̖����ʐM�v���g�R�����̗p�����Ɩ�����V�X�e���ƁA�Ɩ�����̍��ۋK�i�Ŕėp���������uDALI�v�ɑΉ������Ɩ������J�������B ���e�Ƃ��āALED��̌^�x�[�X���C�g�ALED�O���b�g�Ɩ��ALED�_�E�����C�g���B�����Ɩ�����V�X�e���́A�X�}�[�g�t�H����p�\�R������Ɩ��̓��⒲�����ł���B�����𗘗p���Ă��邽�߁A�V�䗠�̑�|����Ȕz���H�����s�v�B ����ɁA�Ǝ��̒ʐM�����ł���u���b�V�������N�v���g�R���v�ɂ��ǂȂǂ̏�Q���̉e��������A���肵�������ʐM���\�B�Ɨ������Ɩ����䂪�\�Ȃ��߁A���Ȃ��Ă���ӏ��̂ݏ�������A���ԑтɍ��킹�ďƓx���������䂷��ȂǁA���ߍׂ₩�Ȑߓd�j�[�Y�ɑΉ�����B �Ɩ������LED�Ɩ��ōő�85���̏ȃG�l���ł���Ǝ��Z���Ă���B�܂�DALI�Ή��̑����[�J�[�̐��i�ł��ʐM���ł��邽�߁A�_��ȏƖ��v���\�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ł��l�K���b�g���ƂɎQ���A�ߓd�s��́g������g�� ���Ђ́A�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�i�����d��EP�j�ƃl�K���b�g�A�O���Q�[�^�[�̉^�p�Ɋւ���_�����������B����ɂ��A2017�N4������l�K���b�g�A�O���Q�[�^�[���Ƃ��J�n����B ���Ђ́A���l�X�}�[�g�V�e�B�v���W�F�N�g�iYSCP�j�ł̃f�}���h���X�|���X�iDR�j���؎��Ƃ�A�o�ώY�ƏȂ̊e��DR���Ȃǂ�ʂ��āA���v�Ƃ̓����c����V��Ȃǂɂ��팸�ʂ̕ϓ��Ɋւ���m����~�ς��Ă����B �팸�˗����s�����v�Ƃ��œK�ɑg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�d�C���Ǝ҂ȂǂƂ��炩���ߌ_���팸�ʂɑ��āA�������x�Ńl�K���b�g����邱�Ƃ��\�Ƃ��Ă���B�Ȃ��A�o�ώY�ƏȂ�2016�N�x�u���x����^�f�}���h���X�|���X���؎��Ɓv�ł́A�X���v�ƒ��A���ł��T�v�Ƃɑ��č팸�˗����s���A�ō����x101.4���̍팸�i�_��팸��4000kW h�ɑ��A�팸��4055kW h�j��B�������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ɂ��كN���E�h�d�͊�Ƃ́u�d�͍w���㗝�T�[�r�X�v���J�n ���{�d�C�ۈ������100���q��ЁA�ɂ��كN���E�h�d�͂́A���{�d�C�ۈ�����̌ڋq�Ȃǖ�2���Ђ̃X�P�[�������b�g�����đ��V�d�͉�Ђƌ����A�d�͂��������B����B ����ɁA�����̐V�d�͉�Ђł̔�r�����ƒ���I�Ȍ������ɂ��A�p���I�ȓd�C�����팸����Ă���B�팸���т͖�2000�Ђɂ̂ڂ�Ƃ����B ���T�[�r�X�ł́A�d�C�̔������i�d�͉�Ђ̑I��j�����łȂ��A�d�C�̎g�����̍H�v�������Ē�Ă��A���_�Ȃ��ł������I�ȓd�C�����팸���Ă���B�傫�ȓd���������V�d�͉�ЂƘA�g���邱�ƂŁA�ڋq�ɂ��傫�ȃ����b�g�ƈ��S�����Ƌ��ɁA�d�C���̂�d�͉�Ђ̓|�Y�Ȃǂ̔�펞�̃T�|�[�g�E���Q�����ӔC�ی��ɂ��ۏ��p�ӂ���B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| ���C�r�f��100�����z���ŃA�b�v���������ނ� ��Apple�͍Đ��\�G�l���M�[�𗘗p���Ċ�Ƃ��^�c����B����ɍŏI���i�̐������痘�p�A���T�C�N���܂ł�ʂ��āA��_���Y�f�r�o�ʂ��ŏ����ɂƂǂ߂�B �ړI�́A�d�̓R�X�g�̈��������ƁA�������ʃK�X�̔r�o�ʂ����炷���Ƃ��B Apple�́A2015�N���畔�ޒ��B��̊�Ƃɑ��āu�N���[���G�l���M�[�v���O�����v��ʂ��ċ��͂����߂Ă����B2017�N3���ɁA���v���O�����ɓ��{��ƂƂ��ď��߂ăC�r�f�����Q�������BApple�����̕��ނ�����ہA�Đ��\�G�l���M�[�ɗR������d�͂�����p���邱�Ƃ�����B100�����������������2018�N�����B �C�r�f���́AApple�������Y�ɕK�v�ȃG�l���M�[���傫��12MW ���鑾�z�G�l���M�[�d����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���l���s�́A���Ԋ�ƓI�Ȕ��z���Ƃ����A�s�{�݂�CO2�팸�ƏȃG�l������ ���s�́ACO2�r�o�ʂ�100�g���ȏ�̎�v�{�݂�136����B�����{�݂́A�{�ݑS�̂�7���ȏ�̃G�l���M�[������Ă���B �팸�v��͂��ׂĂ̐E�����������A�g�b�v�_�E���ƃ{�g���A�b�v�Ŏ��{�����B�G�l���M�[�Ǘ��̐��́A�s�����g�b�v�Ƃ������g����Ǘ��ψ���ȃG�l��̕]������j�̌���A�������Ȃǂ��s���A�����ǁi����������ہj������Ɋ�Â���̓I�Ȏw���A��Ƃ��s�����B�{�g���A�b�v�͎s�����̂��ׂĂ̕���170�ہA�����136�̎�v�{�݂ɉ��g�������i��300�l��z�u���A�u�K��A���C������{�����B�܂��A���g�������i���͎�v�{�݂̎{�݊Ǘ��V�[�g�̍쐬�A�Ǘ��W���������B ���̌��ʁA2014�N�x�̎�v�{�݂̃G�l���M�[�g�p�ʂ�2010�N�x��Ń}�C�i�X8.5���A�������Z��2857kl���̍팸��B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�L���b�v���g���[�h���x2015�N�x��CO2�r�o�ʁA�O�N��|1���� �����s�́A�L���b�v���g���[�h���x�̑��v����ԏ��N�x�i2015�N�x�j�ɂ����鑍CO2�r�o�ʂ��A��r�o�ʂ���26���팸�̍��v1,227���g���Ɣ��\�����B�O�N�x��A1�����B �����x�ł͑����v����Ԃ��A��Y�f�d�͂�M���g�p�����ꍇ�ɁACO2�팸���Ƃ݂Ȃ��d�g�݂�V���ɓ��������B2015�N�x�ɒ�Y�f�d�͓�����16���Ə��A��Y�f�M������103���Ə��������B�܂��A�n�����g����̎�g�݂����ɗD�ꂽ���Ə��́A�S��LED�A��ʓI��LED���2���ȏ�����̗ǂ�150���[�����p�[���b�g�ȏ�̍�����LED�̓����^�G�A�t���[�E�C���h�E�ALow�|E���w�K���X�̐ݒu�^���ʂɑ�K�͂Ȕ��^���z�����d�p�l���̐ݒu�^�f�W�^���T�C�l�[�W�ɂ����E�G�l���M�[���̒^�I�[�i�[�E�e�i���g�Ԃ�CO2�팸���i��c�̊J�Ái�N6��ȏ�j�APDCA�Ǘ��T�C�N���̎��{�A�Ȃǂ����{���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEDO�ƍ����M�w�H�ƂȂǁA100���ȉ��̔p�M�𗘗p�\�ȃR���p�N�g�^�����\�~�M�V�X�e�����J�� NEDO�ƍ����M�w�H�Ɓi���j�A�Ό��Y�Ɓi���j�A��˃Z���~�b�N�X�i���j�A�X���H�Ɓi���j���J������100���ȉ��̒ቷ�p�M�𗘗p�\�Ȓ~�M�ށu�n�X�N���C�v���x�[�X�ɁA����ɍ����\�������~�M�ނ̗ʎY�����Z�p�������Ŋm������ƂƂ��ɁA���쎩���ԂƓ��~�M�ނ�g�ݍ��A�]���^���2�{�ȏ�̒~�M�i500kJ�^L�ȏ�j���\�Ƃ�����R���p�N�g�^�~�M�V�X�e���������ŊJ�������B �R���p�N�g���������������Ƃɂ��A���^�g���b�N�ł̔������\�ƂȂ����B���쎩���ԉH���H��Ŕ�������p�M���A�V�c�H��̉����H���⊣���H���ŗ��p���邽�߂̎��p�����؎������J�n�����B ����NEDO�A�����M�w�Ȃ�4�Ђ́A��[�E�����E�g�[�A�����A�����H�����֓K�p����M���p�V�X�e���Ƃ��Ďs��W�J��ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������29�N�x�Łu�G�l���M�[�E���g����Ɋւ���x�����x�ɂ��āv �֓��o�ώY�ƋǑ����G�l���M�[�L��薈�N�x��������Ă��āA����29�N�x�ł����������B ���y�ъ֓��o�ώY�ƋNJǓ��̓s���A���ߎs���ɂ�����G�l���M�[�E���g����̂��߂̕⏕���E���������̎x�����x���Ƃ�܂Ƃ߂��B �f�ڂ���Ă���{��̗� �@�E�ȃG�l���M�[�������i�Ɍ������x���⏕�� �@�E������Ɠ��ɑ���ȃG�l���M�[�f�f���Ɣ�⏕�� �@�E�n��̓��������������G�l���M�[�̒n�Y�n�� ����e�Z�~�i�[��C�x���g���Ŕz�z�\��B �o�T�u�֓��o�ϋǁv |
|
|
| �����ȁA����28�N�x�n���M���p�����̌��ʂ����\ ���Ȃ́A����28�N�x�n���M���p�����̌��ʂ����\�����B�������́A�ߔN���y���i�ޒn���M���p�̎��Ԕc���ƍ���̍X�Ȃ镁�y���i�̊�b�����Ƃ��邽�߁A����22�N�x����2�N���Ɏ��{���Ă���B ����̌��ʂɂ��ƁA2016�N3���܂ł̒n���M���p�V�X�e���̐ݒu������6,877���ŁA�O���i2013�N12���܂ł̌����j��5,711������1,166���i20.4%�j�̑����ƂȂ����B �܂��A�����ʂł́A�q�[�g�|���v�V�X�e����2,230���i32.4%�j�A��C�z�V�X�e����1,919���i27.9%�j�A���z�V�X�e����1,781���i25.9%�j�ƂȂ��Ă���A����3�������S�̂�86.2%���߂Ă����B���Ȃł͈����������������s���Ă����Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���o�Y�ȁuCO2�t���[���f���[�L���O�O���[�v���v�����܂Ƃ� �ߔN�A�Đ��\�G�l���M�[�̋}���ȓ����g��ɔ����A�n���̋e�ʕs����A�Η͓d�����̒����͕s���Ƃ������ۑ肪���݉����Ă���B �����������A�d�C�G�l���M�[���K�͂������I�ɒ����\�Ȑ��f�G�l���M�[�����ڂ���Ă���B����A�d�͂𐅑f�ɕϊ�����V�X�e���iPower-to-gas�V�X�e���j�̋Z�p�i���ɂ��A�d�͌n���̈��艻���Đ��\�G�l���M�[�����g��ɍv���ł���\��������B �{���ł́ACO2�t���[���f�̗����p�g��Ɍ���������Ɖۑ�����A�ȉ��̃|�C���g�ɂ��Ď��܂Ƃ߂Ă���܂��B �@(1)�Đ��\�G�l���M�[���y�g��ւ̑Ή��Ƃ��Ă�Power-to-gas�Z�p�̊��p �@(2)���f�T�v���C�`�F�[���̒�Y�f�� �@(3)�C�O�����CO2�t���[���f�̒��B��CCS�Z�p�̊��p �@(4)CO2�t���[���f�̗��p�g��Ɍ�������g�̕����� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2017/3�@]�@�@�� |
|
|
| �������Y��p�����u�n�M�g���l�[�h�H�@?�v���s����ăG�l���p�𑣐i �V���{�́A�W���p���p�C���Ƌ����J�����������Y��p�����n���M���p�Y�H�@�u�n�M�g���l�[�h�H�@�v���s�������B �{�H�@�́A��d�点���̍̔M�ǂ��k�߂���Ԃŗ\�ߊ����Y�̓����ɐݒu���A�Y�{�H���ɍ̔M�ǂ�L�������Đݒu���邽�߃R�X�g�_�E�����\�B �{�H�����ł́A����̍̔M�ǂ̐�������������Y�̌@��N�����ɂ��A�����Y��]���݂̉e���ɂ��̔M�ǂ̌��S���A�ݒu���x�ɖ�肪�Ȃ����Ƃ��m�F���Ă���B�܂��A2�N�ȏ�̍̔M�Ɋւ��钷��������p�����{���Ă���A�D�ꂽ�̔M�������m�F���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Z��HEMS�̐V���i��AI�Ή��ŁA�Z��̌����I�ȃG�l���M�[���p���x�� �u���܂����^�]���[�h�v�́A�V�C�\����d�͏���p�^�[������A���z�����d�V�X�e���ɂ�锭�d�d�͗ʂ�]��d�͗ʂȂǂ����Z���A�~�d�V�X�e���̏[���d��G�R�L���[�g�i�q�[�g�|���v������j�̉ғ��v��𗧈āA�������䂷��B ����ɁA���s�̕ω������A���^�C���Ɍ��m���A�v������邱�ƂŌ����I�ȃG�l���M�[���p����������B �܂��A���z�����d�őn�����d�C���ł��邾���ƒ���ŏ����u���Ə���[�h�v�A���d��D�悷��u���z�����d���[�h�v�A�e�@��̐��䎞�ԑт��蓮�Őݒ肷��u�^�C�}�[�ݒ胂�[�h�v������Ă���A���p�҂̃��C�t�X�^�C���ɍ��킹�����[�h�I�����\���B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| ���ȃG�l���ɗD�ꂽ�u���Z�p�����p�����N���[���V�X�e�����J���@�������� ���̃V�X�e���́A�����C���N���[�����[���̏��ʂɌ����Đ����o���A���Y���u�Ȃǂ̓������M�ɂ�艷�܂���������C�ƒu�����邱�ƂŁA�����ƍ�ƃG���A�̐����s���B�ő�̓����́A�V�䕔�ɋݔ���ݒu����K�v���Ȃ��B �����o�������珰�ʂɌ������ċ�������鐴���C�́A������C�Ƃ̔�d���ɂ���ԉ������痭�܂��ĉ��x���w���`�����邽�߁A�̈�����ʂ���2�����x�̍����܂ł̍�ƃG���A�Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł���B����ɁA���Y���u��q�g��������M�ɂ���ĉ��܂���������C�́A�㏸�C�����`�����č�ƃG���A�ɕ��V����������q����ԏ㕔�ɔ������A�r�C�����B���Ȃ��z���ʂŊm���Ɋ��C�ł��邽�߁A�]���̋V�X�e���Ɣ�ׁA�z���ʂ��30���팸�ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���X�}�[�g���[�^�[���S����2000�����˔j�A�d�͂̎������j���i�� �����̑S�ʎ��R���𐄐i���邤���ŃX�}�[�g���[�^�[�͕s���ł���B �S���e�n�̉ƒ�⏤�X�ɃX�}�[�g���[�^�[��ݒu�����Ƃ͓d�͉�Ђ̑��z�d���傪�S�����Ă���B�S�ʎ��R������8�J�����o�߂���2016�N11�����̎��_�ŁA�S��10�n��̓d�͉�Ђ��ݒu�����X�}�[�g���[�^�[�̑䐔��2320����ɂ̂ڂ����B���y����3���ɒB���Ă���B ���Ɋ��d�͂͑��Ђɐ悪����2012�N����X�}�[�g���[�^�[�̐ݒu���J�n���āA���łɕ��y����5�������B�����䐔�ł͓����d�͂�863����ōł������A2020�N�x���܂ł�2700����̐ݒu����������\�肾�B �ł��x������d�͂�2024�N�x���ɓ�������������ƁA�S����7800���ɂ̂ڂ�ƒ�⏤�X���ׂĂɃX�}�[�g���[�^�[�����y����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���G�l���M�[�Ŋ�Ə鉺���̖���������A���{���̔M�d�����v���W�F�N�g JFE�ƐÉ����֓c�s�͋����o����Ёu�X�}�[�g�G�i�W�[�֓c�v��2017�N4���ɐݗ����A�s���ŔM�d�������Ƃ��s���Ɣ��\�B JFE���V���ɏo��3000�`5000kW ���̃K�X�G���W�����d�������݂��A�֓c�s���̊�ƂȂǂɒ�R�X�g�̓d�͂ƔM����������B��Ƃ̃R�X�g�팸�̎x���⋣���͂̋����A�ٗp�n�o�ACO2�r�o�ʂ̍팸�ȂǁA�֓c�s�̒n�抈�����ɍv������_���B �s�s�K�X�𗘗p���Ĕ��d���A���̓d�͂ƔM�i�����j���s���̏��H�ƒc�n�Ȃǂɔ̔�����B���d�ɔ������d����CO2�́A�{�݉��|�c�n�ɋ������A�A���͔|�ɐ������B����ɂ��CO2�r�o�ʂ̍팸�ɂ���^����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����C�M����90���̔M�������q�[�g�|���v�V�X�e���i�� �O�H�d�H�T�[�}���V�X�e���Y�Ɗ��d�́A�����d�́A�����d�͂�4�Ђ́A��������C�M���q�[�g�|���v���M���������u�������J�������B ����J�������q�[�g�|���v�V�X�e���ł́A��C����M����荞�ގ��O�@�ƁA�M���ڐ����ł��鎺���@�ō\�����Ă���A��C�M���q�[�g�|���v�Ƃ��ĔM�����x90���ɑΉ��ACOP3.5�̍�������B�������B����ɂ��A�H��Ȃǂ̔M�����p�H���ցA���ȒP�Ƀq�[�g�|���v�V�X�e���̓K�p���\�ƂȂ����B ��C���M����荞�ދ�C�M���q�[�g�|���v�̂��߁A�≷�����z������z�ǂ̎{�H���s�v�Ŏ��O�@�̐ݒu�̎��R�x�������B�܂��A���O�@�Ǝ����@��ڑ������}�z�ǂ͕Г�50m�܂ʼn����\�ł���A���O�@�͎����@�Ɨ��ꂽ�ꏊ�ɂ��ݒu���\���B ���؎����ł́A�]���V�X�e���ɔ�׃G�l���M�[����ʂ̖�5���팸��B�������B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| �����[�\����IoT�Ői���A�d�̓R�X�g��6���팸����V�X�� ���Ђ͌c���w�Ƌ����ŁA�o�ώY�ƏȂ́u�o�[�`�����p���[�v�����g�\�z���؎��Ɓv�̈�Ƃ��āAIoT�����p���ēd�͎��v�̐���Ȃǂ��s���V�X�܂𓌋��s���ɃI�[�v������B �d�͍w���ʂ�2015�N�x�̕W���I�ȓX�܂̕��ϒl�ɔ�ׂāA��6���팸�ł��錩���݂��Ƃ����B����̃l�K���b�g����s��̑n�݂������������g�݂��B �X�܂ɂ́A22kW �̑��z���p�l����ݒu���A10kW ���͔��d���A�c��12kW �͓X�܂̏���d�͂ɏ[������B�~�d�r�͗e��5.6kW h�B���d�����d�͂̏[���d�����u����ł��A�ߓd���ɂ����p����B ���̑��ALED�Ɩ��A���R�z���C�A�����z�C�ɂ��n�M���p�A���C�g�b�v���C�g�����A�X���̂̏ȃG�l���\�����߂Ă���BBELS��5�������ZEB�F���擾���Ă���B�܂��A��������LED�Ɩ��ACO2��}�𗘗p�����Ⓚ�①�@�A���tCO2��}�v��P�[�X�A���˃p�l���Ȃǂ��������A���u����ɂ������I�ɓX�܂̏ȃG�l��}���悤�ɂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��100���ăG�l��Ƃ�18�ЁA���{�̏���d�͂�1���� �C�O��87�Ђ��Q�����A���Ɗ����̓d�͂�100���Đ��\�G�l���M�[�Řd�����Ƃ�ڎw���uRE100�v�́A2017�N1���A100���̖ڕW�ɒB������Ƃ�18�Ђɋy�Ɣ��\�B���{��Ƃ͖��Q���B 2015�N��87�Ђ����B�����Đ��\�G�l���M�[�́A���͔��d�Ƒ��z�����d���傾�B RE100�ɂ�Apple��Google�AMicrosoft�AGM�ABMW �Ȃǂ̊�Ƃ��Q�����Ă���B RE100�̃����o�[��Ƃ��Đ��\�G�l���M�[���B�����f�������R�́A�d�̓R�X�g�̒ጸ�A���Ђ̌o��ߌ��A�����\���ڕW�̒B���A��Ɖ��l�̌���Ȃǂł���B���B���@��8����A�ł������̂��O���[���d�͏؏���59.6���A���ɓd�͍w����34.8���������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����{�̖؎��o�C�I�}�X�G�l���M�[�̗��p���������і쒡�̒������|�[�g ���̒����́A�؎��o�C�I�}�X�̃G�l���M�[�Ƃ��Ă̗��p������c�����A�؍ޗ��p�̐��i��؍ނ̈��苟���A�n��U���ȂǐX�сE�ыƎ{��̐��i���Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ɏ��{�������́B �؎��o�C�I�}�X�Ƃ́A�؍ރ`�b�v�A�؎��y���b�g�A�d�A�ؕ��i�������j�����w���B�؍ރ`�b�v��R���ʂɂ݂�ƁA�u�Ԕ��ށE�ђn�c�ޓ��v��16.9���A�u���ޓ��c�ށv��20.7���A�u���ݎ��ޔp�����i��̍ށA�p�ށj�v��60.8���B �܂��A�؍ރ`�b�v�̗��p�ړI�ʂɌ���ƁA�u���d�̂݁v��44.0%�A�u�M���p�̂݁v��17.2���A�u���d�y�єM���p�v��38.8���������B ���ɁA�Ԕ��ށE�ђn�c�ޓ��ɗR������؍ރ`�b�v�ɂ��ẮA�u���d�̂݁v��63.4%�A�u�M���p�̂݁v��8.9���A�u���d�y�єM���p�v��27.7���������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���u�������R��\�őI�Ԏ���ցv�����Ȃ��V���|�W�E���J�� ���Ȃ́A�Z��E���z���̏ȃG�l���\�\�����x�Ɋւ���V���|�W�E�����A3��1���ɓ����s���ɂĊJ�Â���B���͓s�s�Z���^�[�z�e������́u�������R��\�őI�Ԏ���ցv�B�Q����͖����B �V���|�W�E���ł́A���̕\�����x�̐��I�Ȏ�g�݂��s���Ă��鎖�Ǝ҂ɂ�鎖��̔��\��A�L���҂ɂ���u���Ȃǂ��s����B ���z���ȃG�l���\�\�����x�́A�����̏ȃG�l���\�̌����鉻���߂����A�ȃG�l���\�ɗD�ꂽ�������s��œK�ɕ]���������̐����Ɍ����A���z���ȃG�l�@�Ɋ�Â����肳�ꂽ�B 2016�N4������́A�r�������łȂ��Z����Ώۂɉ�������B�����x�Ɋ�Â��\���̌����́A2016�N12�������_��1��1�猏�ȏ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O���[���{���h�̔��s���j�ɂ��� �����s�́A����܂ŃO���[���{���h�i��Ƃ�n�������̓����A�Đ��\�G�l���M�[���ƂȂǁA�n�����g�����͂��߂Ƃ��������̉����Ɏ����鎖�Ƃɗv���鎑���B���邽�߂ɔ��s������j�̔��s�Ɍ�����������i�߂Ă���A���N�x�A���̃g���C�A���Ƃ��Čl�����s�u�������T�|�[�^�[�v�s�����B ���̓x�A���N�x�̃O���[���{���h���s�Ɍ��������j�����Z�߂� �O���[���{���h���s�̈Ӌ`�́A�s�����Ƃ̃O���[���{���h�ւ̓�����ʂ����㉟���ɂ��A�X�}�[�g�V�e�B�̎�����ڎw���s���A�]�O����s���Ă���s�̊��{��ɉ����āA�V���Ȋ��{������͂ɐ��i���邱�Ƃ��B ���͓̂����O���[���{���h�A���s�K�͂͑��z200���~���x�A���s�����F 10���`12�� �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��������Ƃ̏ȃG�l�����̎��Ԃ��������A���{���H��c�� ������Ƃ̎��Ԃɑ������n�����g����i�ȃG�l�����j�̎�g���i�Ɍ����āA�ǂ̂悤�ȃA�v���[�`�L�����������邽�߁A�����Ƃ̎��Ԃ��B�S��801�Ђ�����B�i����́u����Łv�ŁA�S�̂̏W�v�E���͌��ʂ͂R�����ɉ��߂Č��\�\��j �u������Ȃ���g�݂ł����Ă����{���͒ᒲ�v�u�R�X�g�팸�����@�v�u�܂��͉��g����̎�g���e����@�A�����b�g�̗��𑣐i����n�߂�K�v�v�u������x��g�݂����{���Ă��钆����Ƃł͂b�r�q�����@�ƂȂ�A���I�x����]��ł���v�ȂǁA����܂Ō���Ă���������Ƃ̎��Ԃ����t����ꂽ�i�D�B ������Ƃł͐l�I���\�[�X�Ȃnjo�c�����Ɍ��肪���邱�Ƃ���A��g���i�ɂ������Ă͑��ƂƈقȂ�A�v���[�`���K�v�ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���u����LED�����v�̈��S���v�̍��ۋK�i�����s�@JIS����b�@�o�ώY�Ə� �ȃG�l���M�[���\�̍�������LED�����v�̈��S������ƕ��y���i�̂��߁A���Ȃł́A�g�p�E����҂̈��S������A�ȃG�l���M�[���\�̗D�ꂽLED�Ɩ��̔��W�E���y�̊ϓ_����A��ʏƖ��p����LED�����v�̈��S���ɂ��Ă̓��{�H�ƋK�i�iJIS�j��25�N4���ɐ��肵���B ����LED�����v�̈��S���ɂ��Ă̍��ەW������25�N11���ɍ��ۓd�C��c�iIEC�j�ɂ����ē��{�����Ă��A�e���Ƌ��c���d�˂����ʁA����29�N1���ɍ��ۋK�i�iIEC62931�j�Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�B ���ۋK�i�̊T�v�́A(1)�둕���h�~�̂��߁A����GX16t-5���g�p�B(2)�����v�̗����h�~�i���x�ω��ɂ�钷���̕ω��A����݁j�B(3)���d�ɑ���ی�B |
|
|
| ���@�@[�@2017/2�@]�@�@�� |
|
|
| �����ŃL�����A�A���q�[�g�|���v���M���@�u���j�o�[�T���X�}�[�gX�v�̐V�V���[�Y�� ���Ђ́A�V�J���������E�ő勉�̑�e��DC�C���o�[�^���[�^���[���k�@�𓋍ڂ��Ȃ�����R���p�N�g�������コ�����B ���̌`��́A�C����͂��琶�܂ꂽ�A�@�\���E�f�U�C�����ɗD�ꂽX��➑̂��p�����Ȃ���A�㕔�̋�C�M������Z�N�V�����͂��̂܂܂ɁA�ꕔ�̈��k�@�Z�N�V�������㕔������300mm�R���p�N�g�ɂ����Ǝ���Edge�t�H�������̗p���A�R���p�N�g���A�{�H���A�T�[�r�X����Nj������B EDGE�V���[�Y�́A60�n�̓N���X�ōō�������IPLVc�i�ᕉ���̉^�]�������������Ԑ��ьW���j5.3�������������������f���A���k�d�͊�����ЂƂ̋����J���ɂ����M���\�������f���A���W���[�����`���[�ō����ő�N���X�ƂȂ��e��70�n�̓��f����3���f���i6�^�C�v�j��2017�N3��31����蔭������\��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�ăe�X���Ƌ��Ƒ��z�d�r�̐��Y�ō��� ���z�d�r���W���[���̐��Y��2017�N�ĂɊJ�n����\��ŁA���Y�\�͂�2019�N�܂ł�1GW�ɂ���v��B �_��̈�Ƃ��āA�p�i�\�j�b�N�̓o�b�t�@���[�H��ŕK�v�ȓ����̈ꕔ�S���A�e�X���̓p�i�\�j�b�N����A�H��Ő��Y���ꂽ���z�d�r���Ԃɂ킽��w������B �e�X���́u���z�����d�v�u�~�d�r�v�u�d�C�����ԁv�̃Z�b�g�ɒ��́B���z�����d�x���`���[�̃\�[���[�V�e�B���B10�����ɐV���i�Ƃ��āA����ȃK���X�^�C���Ƒ��z�d�r�ō\������鉮���f�ށu�\�[���[���[�t�v�Ɖƒ�����~�d�r�u�p���[�E�H�[��2�v�\�����B���z�����d�ƒ~�d�r�A�d�C�����Ԃ�g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����\�ȃG�l���M�[�V�X�e�����\�z���Ă����l�������炩�ɂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������Ȃ��Ă����z������荞�߂���_�N�g�A100mm�ɔ��^�� �听���݂Ɠ��m�|��͔��^�̐������_�N�g�V�X�e�����J�������B���������ɑ��z���������I�ɗU���ł���V�X�e���ŁA����100mm�Ə]���V�䗠�ɍ���400mm�ȏ�̃_�N�g��p�X�y�[�X���s�����������A�啝�ɔ��^����}�����B����ɂ��A�����̊K�����������邱�ƂȂ��A���̂Ȃ��L���⎩�R���̓���Ȃ������ɑ��z�������Ƃ��ł���Ƃ����B ���V�X�e���́A�����O�Ǖ����Ƀv���Y������������^�̍̌�����ݒu���A�G�߂ɂ��l�X�Ȋp�x������˂��鑾�z�����v���Y���̍�p�ɂ�萅�������̌��ɕϊ����邱�ƂŁA�_�N�g���̔��ˉ��ጸ����A�]���̌��_�N�g��2�{�ƂȂ鍂���̌����������������B �o�T�uBUILT�v |
|
|
| ���x�m�ʁAICT�̊��p�Ŗ�4000���g���̉������ʃK�X�팸 ���ЃO���[�v�́AICT���������ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�ʂ̍팸�ɂǂ̂��炢�v�����Ă���̂����ʓI�Ɂu�����鉻�v���A���̍v���ʂ̊g���}���Ă���B 2015�N�x�̓N���E�h�^�T�[�r�X��^�u���b�g�����p�����\�����[�V�����Ȃǂ��Z��Ώۂɉ��������ʁA�O���[�o���S�̂�2013�N�x����v�Ŗ�4,000���g����GHG���팸���A�ڕW��3,800���g���ȏ��B�������B ���Ə��ɂ�����GHG�r�o�ʂ̍팸�ڕW���A1990�N�x��20���ȏ�Ƃ��Ď��g��ł����B2015�N�x�́ACO2�r�o�ʍ팸��Ƃ��āA�e���Ə��ł̃C���o�[�^�[�Ȃǂ̏ȃG�l��A�����v���Z�X�̌������ƍH��C���t���ݔ��̓K���^�]�A�G�l���M�[����́u�����鉻�v�Ȃǂ��s���AGHG�r�o�ʍ팸��1990�N�x���35���ƖڕW��傫������܂����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ����R�X�g�ɑ��z���̏o�͕ϓ����ɘa�A��ёg���V�^�~�d�V�X�e���� ���Ђ́A�o�͕ϓ����ɘa���邽�߂̒�R�X�g�~�d�r�V�X�e�����J�������B�k�C�����H���Ɍ��݂�i�߂Ă��鑾�z�����d���u���H���K�\�[���[�v�ɓ�������B �J�������~�d�r�V�X�e���́A�ݔ��e�ʁi�~�d�r�p�p���[�R���f�B�V���i�A�~�d�r�̗e�ʂȂǁj���œK�����邱�ƂŁA�ݒu�R�X�g����ьŒ艿�i���搧�x�iFIT�j�Œ�߂�20�N�Ԃ̔�����Ԃɗv����^�p�R�X�g��}�����̂��������B ���V�X�e���́A�O�H�d�@��GS���A�T�������J�������B���z�����d�����L�̏o�͕ϓ����ɘa���鐧��A���S���Y���̍\�z�A�~�d�r���ɗ͗}�����邽�߂̍œK�ȉ^�p�e�ʂ̊���o���A�I�肵���~�d�r�̗ɔ����ĕK�v�ƂȂ�lj��e�ʂƒlj������̍œK���Ȃǂ̐��ʂ��B ���d�K�͂�17.9MW �A���d����i�o��14.5MW �B�~�d�rPCS�o�͂�10MW�A�~�d�r�ɂ͗e��6.75MWh�i���K���b�g���j�̃��`�E���C�I���d�r���̗p�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����C���u�̍����C���̕ω������ŊJ���鏰�����C���u "SmartFilter" ���J�� �G�A�t�B���^�́A�g�p���Ԃ̌o�߂ɂ��ߏW�����o���ɂ���Ėڋl�܂肪�����A���͑����l�i�ȉ��A�u�����v�Ƃ��܂��j����������B���̍��������e�l����ƃG�A�t�B���^�̔j���╗�ʂ̒ቺ�Ȃǂ��������߁A�������K�v�ƂȂ�܂��B�]�����̍����̓G�A�t�B���^���j�b�g�ɑg�ݍ��u�����v�v�ɂ���ă��j�^�[���Ă����B�������A�g�p�����t�B���^�̎�ނ╗���ɂ�荷���̕ω��������قȂ邽�߁A���ꂼ��̃G�A�t�B���^�̐��\�����Əƍ����Ȃ���Ύ����\�����s�����Ƃ��ł��Ȃ������B ���Ђ́A�`��L���������g�����������C���u���J�������B�C���̕ω������ŊJ����B���x���ς��ƍ������̂˂��L�k���A�������͋��C�����J���ĕ���ʂ��A�����Ȃ�ƕ��Ē~�M����B�d�C���l�̎���g��Ȃ��B�쓮�͈́F���x-45���`85�� ���x0%�`95%RH �I�A����͈́F0�`500Pa ���x�}0.25%F.S. �o�T�u�͖k�V��v |
|
|
| ���听���݂��������̔R���d�r�̓������A�n��̃G�l���M�[���œK�� �听���݂�2017�N1��17���A���l�s�˒ˋ�ɂ��铯�Ђ̋Z�p�Z���^�[�ɁA�ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j������Ɣ��\�����B SOFC���瓾����d�C�ƔM���A���Z���^�[���ɍ\�z�����X�}�[�g�R�~���j�e�B�̃G�l���M�[�Ƃ��Ċ��p���Ă����_�����B�����2017�N�x���ɕ��������̃G�l���M�[���Ǘ�����u�G���A�E�G�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���v�iAEMS�j���������A�~�n���S�̂ŃG�l���M�[�g�p�ʂ̍œK����}��B ��������SOFC�́A�O�H�����p���[�V�X�e���Y���J����i�߂Ă�����̂ŁA�o�͂�250kW �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�͎��R�����Ă��u�d�C�̎��v���i�V���g���E�d���E��d���т̕����J �d�͍L��I�^�c���i�@�ւ́A2016�N�x�ł́u�d�C�̎��Ɋւ�����v�����\�����B 2015�N�x�܂ł̉ߋ����N�Ԃ̋����G���A�ʂ̃f�[�^��p���āA���g����d������߂�ꂽ�ڕW�͈͂Ɏ��܂��Ă��邩�A��d���т��������Ă��Ȃ������ɂ��Ď��т����܂Ƃ߂��B 2015�N�x�́u���g���́A�e�G���A�̕W�����g���ƒ����ڕW�ɉ����āA�K�Ɉێ�����Ă����ƕ]���ł���v�ƕ��͂��Ă���B �@�E���ׂẴG���A�ɂ����āA�����ڕW�͈͂̑؍ݗ���100���������B �@�E0.1Hz�ȓ��̑؍ݗ��ڕW��95���Ƃ��Ă��钆���G���A�Ȑ��i�����E�k���E���E�����E�l���E��B�j�ɂ��Ă��A���̖ڕW�l�������Ă����B �܂��A�d�C���Ɩ@�Œ�߂�ꂽ�ێ����ׂ��d���i 100V�E200V�j�ɂ��āA���ׂẴG���A�ɂ����Ď����d������E�������т͂Ȃ������B 1���v�Ƃ�����̒�d�͉ߋ�6�N�ōŏ��A1���v�Ƃ�����̒�d���Ԃ͑O�N�x���l�̐����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���킩��₷���u�l�K���b�g����E�f�}���h���X�|���X�v�̓��发�o�Y�Ȃ����J �o�ώY�ƏȂ́A��Ƃ�ƒ�ȂǓd�C�̎��v�ƌ����ɁA�ߓd�����d�͗ʁi�l�K���b�g�j�����������Ɋ��p����l�K���b�g����̊T�v�E�Q�����@�Ȃǂ��܂Ƃ߂��n���h�u�b�N���쐬�����J�����B �l�K���b�g����̎��{�ɂ������ẮA���ۂɎ��v�ʂ̐�����s�����v�Ƃ̋��͂��K�v�s���ƂȂ�B���v�Ƃɂ͂��̎�g�݂ɎQ�����邱�Ƃɂ��A�ȃG�l�����ĕ�V�邱�Ƃ��ł��郁���b�g������B���v�Ƃɑ��āA�d�C�̎��v�ʂ𐧌䂷��l�K���b�g����i�f�}���h���X�|���X�j�ɐϋɓI�ȎQ�����Ăъ|���Ă���B ����29�N4���̃l�K���b�g����s��n�݂Ȃǂɂ��A����̕��y�����҂���Ă���B �l�K���b�g����́A�d�͂̎��v�𐧌䂷����v�ƂƓd�͉�Ђ̊Ԃɗ����A���v�}���ʓ������܂Ƃ߂钆�j�I�Ȗ�����S���A�O���Q�[�^�[����Ď������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������80���ȉ��̔M���ł��g����o�C�i���[���d�V�X�e���J���E���،��� �ቷ��̖����p�M���̗L�����p��}�邽�߁A�ቷ��ł����삷��o�C�i���[���d�V�X�e���̊J���E���؎��Ƃ̌�����J�n���邱�Ƃ\�����B������Ԃ�2017�N2��9���i�j��17���܂ŁB �u�ቷ�M�����p���d�Z�p���p�����i���Ɓv�́A�����ɂ�����ቷ��̖����p�M���������I�ɗL�����p�ł����Y�f�Z�p��Y�f�Z�p���m�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B ����̑ΏۂƂȂ�̂́A�ێ�80�x���x�ȉ��̒ቷ�M���ɓK�����쓮���̂�I�肵�A���Y�쓮���̂�g�ݍ��R�X�g�����I�ȃo�C�i���[���d�V�X�e���̊J���E�����s�����ƎҁB��w�E�Ɨ��s���@�l�ȂǁB 2017�N�x�̗\�Z��3���~�B1���Ƃ�����̏���z��3���~�B2018�N�ȍ~�͂��ꂼ�ꓖ�Y�N�x�̗\�Z�͈͓̔��ŏ����݂���B���{���Ԃ�3�N�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���z�e���̏ȃG�l��A�o�Y�Ȃ������N�t���� ���Ȃ͍��N�x����A�z�e�����Ǝ҂̏ȃG�l���4�i�K�ŕ]������B�⒲���A�Ɩ��Ȃǂŏ����G�l���M�[�����ȏ�ɂȂ�200�В��x��ΏۂɁA���N�̓d�͂�K�X�̏���ʂȂǂ������B 1�N�Ԃ̎��g�ݎ��т܂��A�ȃG�l�i��ł�����1�`2���̎��Ǝ҂��u�r�N���X�i�D�ǁj�v�ƔF�肷��B�A���łr�N���X�̎��Ǝ҂ɂ́A�ō��Łu�܂��v�����B ����ŁA�ȃG�l�̎��g�݂��s�\���Ȏ��Ǝ҂ɂ͊�Ɩ��̌��\�Ƃ������������݂�����B���ƎҊԂ̏ȃG�l�����𑣂��A���g����ɂȂ���ƂƂ��ɁA�֘A�̓�����グ��_��������B �@S�N���X�i�D�ǁj�@�FHP�Ŋ�Ɩ������\�A���B���Łu���v��t�^ �@A�N���X�i��ʓI�j�F���ɂȂ� �@B�N���X�i��j�@�F���ӕ����̑��t�������茟�� �@C�N���X�i�v���Ӂj�F���P�v��̍쐬���w����Ɩ��̌��\�A�s������ �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����k��w���h�b�N�X�t���[�d�r�������E��e�ʉ��ł���V�Z�p�J�� �o�͕ϓ��̑傫���Đ��\�G�l���M�[�̕��y�ɔ����A�d�̓O���b�h���艻�̂��߂̑�K�͒~�d�V�X�e�������ڂ���Ă���B ���̑�K�͒~�d�V�X�e���ɂ́A�P�ʓd�͂�����̒~�d�f�o�C�X�R�X�g�̒ጸ�E���������E���S�������߂���B�����̗v���ɉ�����f�o�C�X�Ƃ��āA�X�����[���t���[�����Ȃ���[���d���s���u�t���[�L���p�V�^�v������B ����w�̌����ł́A�����ȏ[���d���ł���L�@�ޗ��ł���L�m�����������A�����Y�̃i�m�T�C�Y��ԓ��ɖ��ߍ��ނ��ƂŁA�L�m���������̃��h�b�N�X�����e�ʂ̕t�^�ɂ��X�����[�̏[���d�G�l���M�[���x�{���i��2.5�{�j�ɐ��������B�G�l���M�[���x�̌�����ʂ́A1000W�^kg�ȏ�̋}���[���d���ɂ����Ă��ێ������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2017/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���d�͂Ɖ������ɍ�鑾�z�d�r�A���ԊO���ŃG�l���M�[����78�� �����a���J�g���j�N�X���J�� �d�͂Ɖ����̗��������n�C�u���b�h���z�d�r���W���[���̎��؎����V�X�e�����A�|��s�̉���{�݂ʼnғ������B ���̑��z�d�r���W���[���ɂ͒P�����V���R�����g�������d���̗��ʂɁA��������������H�̃|���G�`�����ǂ�z�u���Ă���B�O�����琅�����≷�𑗂荞��ŁA���z���̔M�G�l���M�[�ʼn��x���㏸�����邱�Ƃ��ł���B���z�d�r���W���[��1���̔��d�\�͂�160���b�g�ŁA���v140���̃��W���[����ݒu�����B 140���̂���112���ɂ͐�������ʂ��āA�������p�ݔ��ɋ�������B28���̃��W���[���ɂ͉��𑗂荞��ŁA40���ȏ�ɏ������đ����{�݂ɋ�������B ���O�Ɏ������ő��肵�����ʂł́A���W���[���̕\�ʉ��x��50���̏�ԂŔ��d������15.5���A�W�M������62.5�����L�^�����B���ꂼ�ꑾ�z���̃G�l���M�[��d�͂ƔM�ɕϊ��ł��銄���ŁA���������킹���G�l���M�[�ϊ�������78���̍��������ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���V�d�͂̉ƒ�����V�F�A2.2���ɁA�g�b�v�͓����K�X��2�ʂ͑��K�X �����S�ʎ��R������5�J�����o�߂���2016�N8���ɐV�d�͂̃V�F�A��11.0���Ɋg�債���B �ƒ������2.2���őO������0.4�|�C���g�L�тĂ���B���Ǝҕʂł͓����K�X���g�b�v�ɂȂ�A�����ő��K�X�AKDDI�AJX�G�l���M�[�������B�n��ʂł͖k�C���E�����E����3�n��ŐV�d�͂̃V�F�A�������B ���ʍ����E�����ł͊���17.1���܂Ŋg�債���B�����Ŗk�C����16.2���A������15.6���ŁA���̑���7�n���10����������Ă���B�ሳ�͓�����3.9���܂ŏ㏸�����ق��A����2.8���A�k�C����2.1���܂Ŋg�債���B �n��ɂ�鍷���܂��܂��J���Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������n�Ȃǂɐݒu�ł���A�s�s�^�Ɩ��p�}���`�G�A�R����V�����\�� �_�C�L���H�Ɗ�����Ђ́A�s�s���ɑ��������n�ւ̐ݒu�ɑΉ������w�X�܁E�I�t�B�X�p�}���`�G�A�R���x��2017�N4����蔭������B ���K�̓r�������W����s�s���ł́A�������ӂɏ]���̃r���p�}���`�G�A�R���̎��O�@��ݒu����X�y�[�X���m�ۂ��ɂ��������̏ꍇ�A���^�̎��O�@��������ݒu���Ă����B���̂��߁A�������ӂ�r���ǖʂȂǂɑ����̎��O�@�����сA�����e�i���X��Ƃ���������B �{���i�́A�]���̃r���p�}���`�G�A�R���ɔ�ׁA���O�@�̐ݒu�ʐς��ő��58%�팸�E���^���������Ƃɂ��A�X�y�[�X�̌���ꂽ�ꏊ�ɂ��ݒu�ł���B4�n�͂���12�n�͂܂ŕ��L�����낦�A���O�@�̐ݒu�䐔���팸�ł��A�S�����@�ɐڑ��E�ʉ^�]���ł���B ����Ɏ����@���A����Ԃł��ݒu���₷���w�X�N�G�A�J�Z�b�g�x�A�z�e���̋q���Ȃǂ̓V��ɏȃX�y�[�X�Ŕ[�܂�w�V�䖄���_�N�g�`�i�R���p�N�g�^�C�v�j�x����������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��BIM�ƃZ���T�[�Ői������r���Ǘ��A3D���Ŋ��݃r���ɂ��\�� NTT�t�@�V���e�B�[�Y�́u��1��X�}�[�g�r���f�B���OEXPO�v�ɏo�W���A�u�[�X���Ɏ��ۂɊe��Z���T�[��ݒu���A�擾��������BIM�iBuilding Information Modeling�j�œ������A���A���^�C���ɉ�������f�����X�g���[�V�������I�����B �u�[�X���ɂ́A�Ɩ��A�l���A�����ȂǁA���v22��ނ̃Z���T�[��ݒu�B�����̃Z���T�[������W�������́A�u�[�X��BIM�f�[�^�ƂƂ��ɁA���j�^�[�Ń��A���^�C���ɉ{���ł���悤�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ���f���f�[�^�̒�����Ɩ��ݔ��Ȃǂ�I������ƁA����܂ł̉ғ����Ԃ�c��̐�������Ƃ������A�ݔ������{�����邱�Ƃ��\���B �܂��A�Z���T�[�𗘗p���ĒI�ɂ�����i�̐�������u����c���ł���ȂǁA���|����i�Ǘ�������������\�����[�V�����Ȃǂ���I�����B �Z���T�[��BIM�f�[�^�����p���A��������ݔ��̉ғ��A���p���Ȃǂ̃f�[�^�����A���^�C���ɔc���ł���悤�ɂ��邱�ƂŁA���|�A�Z�L�����e�B�A�ݔ��E���i�Ǘ��ȂǁA�����Ɋւ��邳�܂��܂Ȉێ��Ǘ��R�X�g���팸�ł���B���Ђł͐l�ޕs���⍂��Ȃǂ̉e���ŁA�r���Ǘ��̏ȗ͉��j�[�Y�����܂�ƌ����ށB �o�T�uITMedia �v |
|
|
| ���I�������l�̐��ƈʒu�������x�Ɍ��o����摜�^�l���Z���T�[�� �r����H��̓V��ɐݒu���A�l�̐��ƈʒu�������x�Ō��o�ł���Ƃ����l���Z���T�[��2017�N4���ɔ�������Ɣ��\�����B ���Z���T�[�̓r����H��̓V��ɐݒu���A�������Ă���C���[�W�Z���T�[�łƂ炦���摜�f�[�^��Ǝ��̉摜�Z���V���O�Z�p�ŏ������邱�ƂŁA7.2m�~7.2m�͈̔͂ɂ���l�̐��Ƃ��ꂼ��̈ʒu�����o�ł���l���Z���T�[���B�ő�5m�܂ł̍������猟�o�ł��邽�߁A�I�t�B�X�G���A���c�������łȂ��A�r���̃G���g�����X�z�[����G���x�[�^�[�z�[���ȂǓV��̍����ꏊ�ɂ��ݒu�ł���B �擾����������ɁA��Ɩ����R���g���[��������A��c���̎g�p���œK��������ł���B�܂��A�H��ł͐l�̈ʒu�␔���u�����鉻�v���邱�ƂŃ��C����@��̃��C�A�E�g���œK�����铙�A���Y����̌�������������ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����É��s�ɓ��{����ZEH�����}���V���� �ϐ��n�E�X�i���j�́A���É��s������ŁA3�K����12�ˋK�́AZEH�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j�̕����}���V��������������Ɣ��\�����B2017�N�Ăɒ��H���A2019�N�t�Ɋ����\��B ����̌v��ł́A�������ƂȂ�ZEH���B��������z���^�̕����}���V������ڎw���BLED�Ɩ����̊e��ȃG�l�ݔ����̗p���A���̃A���~�E���������T�b�V�ɂ̓A���S���K�X�������w�K���X�̗̍p���A�J�����̒f�M���\���]����2�{�ɁA�Z�˒P�ʂ̒f�M���\��1.3�`1.6�{�܂ō��߂��B �u�n�G�l�v�ɂ����ẮA����4kW �̑��z�����d�V�X�e���ƔR���d�r�u�G�l�t�@�[���v�𓋍ځB�����ɂ��A�S�Z�˂Ńl�b�g�E�[���E�G�l���M�[��B������B����ɁA���z�����d�V�X�e���ƃG�l�t�@�[���̒�d�����d�@�\�i���d�p���j�ɂ��d�͋�����A�h�Д��~�q�ɂȂǂ̖h�Б�ɂ��A���S�E���S�ɂ��z�������Z�܂��Ƃ���v�悾�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������̑����1,500���[�����́u�H���p�[�dLED�}���`������v�� �p�i�\�j�b�N�́A�������Ȃǂ̈Ï���H������Ȃǂōs����Ǝ��ɁA�茳���Ԃ𖾂邭�Ƃ炷�A1,500���[�����̑���ʂ����������u�H���p�[�dLED�}���`������v���A2017�N2����蔭������B �{���i�́A���邳��1,500���[�����̋��i100���j�A���i��50���j�A��i��10���j��3�i�K�̐�ւ����\�Ȃ��߁A��ƌ�����ɍ��킹�Č��ʂ߂ł���B �܂��A2�ʂ̃t���L�V�u�����C�g���㉺�ɊJ���A�������270�x�܂ʼn�]�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A���܂��܂ȗp�r�ōD�݂̏Ǝˊp�x�ɐݒ肵�Ďg�p���邱�Ƃ��\���B�t���[�d�̏ꍇ�A2���Ԏォ��ő�Ŗ�33���ԘA���_���ł���B�d�ʂ�610g�ƌy�ʂŁA�R���p�N�g�v�B�d�r�p�b�N�́A3�d���i21.6V�A18V�A14.4V�j�ɑΉ����Ă���19,000�~�i�d�r�p�b�N�E�[�d��͕ʔ��j �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����d�ɂh���s�����p�����ψ���]�����f�f�V�X�e�����J�� ���V�X�e���́A�Ɩ������������A�V�������i�ރC���t������ɊĎ����邱�ƂŁA��d�ȂǑ�K�͂ȏ�Q�𖢑R�ɖh�����Ƃ�ړI�Ƃ���B�����ψ���Ɋe��Z���T�[�����t���A�擾�����f�[�^���N���E�h��ɒ~�ς��A���u�ŊĎ��Ɛf�f���s���B �����ݔ��ɂ��e�Ղɓ����ł��A���폄���_�����������ł���B1�����قǂ����čs���Ă����ψ���̖����͂��A���A���^�C���Ɏ��{���邱�Ƃ��ł���B �ψ��풆�̐≏���̗ɂ����ɗn��������̉��w�������A�����̃Z���T�[�Ōv�����A�≏���̗̒����c���B�����╔�����d�Ȃǂɂ�萶�����K�X�������v�����邱�ƂŁA���̗�c������B�ψ���I�����C���Ď����ځF�����ʐ��l�Ď��A�������^�O�C���Ď��A�����K�X�^�������́A��LTC�i���[�h�^�b�v�`�F���W���[�j�Ď��A���������d�Ď��A�����דd���Ď� �̔��J�n��2017�N4����\��B����͊����ψ����2018�N�x�ɊJ�������\��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����ۃW���p�����{�����ȂǁA�u���͔��d���ƎҌ����Z�J���h�I�s�j�I���T�[�r�X�v���J�n ���͔��d���Ǝ҂́A�s����ۂ̓��e�ɂ���ẮA����̂Ɏ��Ԃ��������Ă��܂��P�[�X��A�������Ă��Ώ����@���R�X�g���ƂȂ��Ă��܂��A���{���S�O����P�[�X������B �s��Ώ��̒x��Ȃǂ̔��f��肪�A���́E�̏�ӏ��̕��I���Q�̊g���_�E���^�C���i���ƒ�~�j�̒������ȂǁA�傫�ȑ��Q�ɂȂ���P�[�X�������A���͔��d���Ǝ҂ɂƂ��Č��Ď����ƂȂ��Ă���B ���Ђ̉Еی��ɉ������Ă��镗�͔��d���Ǝ҂ɑ��āA�Z�J���h�I�s�j�I���T�[�r�X�����B���͔��d���Ǝ҂�O��M�i�^�p�E�ێ�j�Ɋւ��鑊�k�����ɂ��āA���̓����e�i���X�T�[�r�X��Ђ�o���L�x�ȃG���W�j�A�E�L���҂Ɍ��������߁A���̈ӌ��𑍍��I�ɂƂ�܂Ƃ߉���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���K�X�^�[�r���ɁA��C��p�������̗p���d������63�p�[�Z���g�ȏ� �O�H�����p���[�V�X�e���Y�iMHPS�j�́A��C��p�����́uJAC�iJ-series Air-Cooled�j�v�`�K�X�^�[�r�����s��������B�R���o�C���h�T�C�N���^�]�ɂ��o��54��kW���i60Hz�p�j�A�܂��͓�72��kW���i50Hz�p�j�̔��d���s�����Ƃ��ł��A���d������63�p�[�Z���g�ȏ��B�������B ���C��p�����C��p�ɕϊ����邽�߁A�R�Ċ�̉����A�^�[�r�����×��̗�p�\�����œK�����A��荂���R�ĉ��x�ɑς�����悤�ɂ����B JAC�`�K�X�^�[�r���́A�����̐ΒY�Η͔��d�ݔ����A���E�ōł������I�ŐM�����̍����K�X�^�[�r���ł���JAC�`�ɒu�������邱�ƂŁACO2�r�o�ʂ�70�p�[�Z���g�߂��팸���邱�Ƃ��ł���B ���Ђ͂��ł�45���J�`�K�X�^�[�r�������A21��ғ����Ă���B����܂łɂȂ�99.3�p�[�Z���g�̍����M�������m�ۂ���33.5�����Ԉȏ�̏��Ɖ^�]��B�����Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ����ʂ̔M�G���W���̌����ƃX�s�[�h�Ɋւ��錴���I���E�̔��� �c��`�m��w�A������w�A�w�K�@��w�̌����O���[�v�́A��S�N�ȏ�̗��j�����M�͊w�̕���ŁA�u�����ł��Ȃ����v�������V���Ȍ����I���E�������B ��ʓI�ȁi�O���M����p����j�M�G���W���ɂ��āA�u�������������悤�Ƃ���ƕs��I�Ɏ��ԓ�����̏o�͂��������Ȃ��Ă��܂��v���Ƃ��A��ʓI�Ō����ȃg���[�h�I�t�̊W��V���ɏؖ����邱�ƂŁA���_�I�ɖ��炩�ɂ����B����́A�u�G�l���M�[�ʖ������p�������v�Ƃ����v�]�ƁA�u�Z�����Ԃő����̃G�l���M�[�����v�Ƃ����v�]�Ƃ��������Ȃ����Ƃ������Ă���B ����̌������ʂ͏����ɗ��_�I�Ȑ��ʂł���A�l������قڑS�Ă̔M�G���W���ɂ��Ă͂܂�B����A�ȃG�l���M�[����ւ̕��ׂ̌y�����l�������u���z���^�G���W���v�̐��\�]���̊��J���w�j�Ƃ��ĉ��p����邱�Ƃ����҂����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���}���K���P�C�����n�M�d�ϊ��ޗ��ŏ]�����2�{�̏o�͈��q������ ���݁A�ꎟ�G�l���M�[�̔����ȏオ���p���ꂸ�ɔr�M�ɂȂ��Ă���B���̂悤�Ȕw�i�̂��ƁANEDO�͖����p�M�ɒ��ڂ��A���́u�팸�iReduce�j�E����iRecycle�j�E���p�iReuse�j�v���\�Ƃ��邽�߂̗v�f�Z�p�̊v�V�ƁA�V�X�e���̊m����ڎw�����u�����p�M�G�l���M�[�̊v�V�I���p�Z�p�����J���v��2015�N�x������{���Ă���B ���̈�ŁA���k��w�́A��R�X�g�������҂ł��A���M�I�E���w�I���萫�ɗD���}���K���P�C�����n�M�d�ϊ��ޗ��ŁA���d�ʂ�\���w�W�ł���o�͈��q�Ƃ��āA�]���̖�2�{�ɑ�������2.4mW�^K2m�����������B ����̐��ʂɂ��A�����ԃG���W���̔r�M��Y�ƕ���ɂ�����H�ƘF����̔r�M���A300�`700���̖����p�M�G�l���M�[��d�͂ɕϊ����鍂�o�͔M�d���d���W���[���̎��������҂����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�ALED�d����5�N�ۏT�[�r�X�J�n�s�������Ζ������� ���Ђ́A12������V����5�N�ԁA���i��ۏ��鐧�x������Ɣ��\�����B ���i�͓��{�����Ŕ̔������SLED�d���B���ɍw���E�g�p���Ă��鐻�i���ΏۂƂȂ�B�̏�i�̌����́A�w�������̔��X�̂ق��A12��1�����V�݂���LED�d����p�����i�t���[�_�C�����E�E�F�u�j�Ŏt����B ���i�w�����͕ۏ؏���V�[�g�Ŋm�F���邪�A����炪�Ȃ��ꍇ�́A�����N�����5�N�Ԃ�ۏ؊��ԂƂ���B�����N����LED�d���Ɉ���Ă��鐻�����b�g�ԍ��Ŋm�F����B 24���ԘA���g�p�Ȃ�1��20���Ԉȏ�̒����Ԏg�p�̏ꍇ�A�ۏ؊��Ԃ������ƂȂ�BLED�d���̍������v�́A�ȃG�l�ӎ��̒蒅����w�i�ɁA�N�Ԗ�2,300���O��ň���I�ɐ��ڂ��Ă���B���y����2015�N�x���Ŗ�44���ɒB���錩�ʂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������d�͂ȂǁA�d�̓f�[�^�����p�����V�T�[�r�X�̍\�z�����J�n �����d�̓p���[�O���b�h�A�������쏊�A�p�i�\�j�b�N��3�Ђ́A�Z���T�[�����p���ďZ����̓d�C�̎g�p�≷�x�Ȃǂ̏������W���A����ɒ~�ρE���H�ł���IoT�v���b�g�t�H�[���̍\�z�Ɍ����A�������؎������J�n����B ���{���Ԃ�2016�N11���`2017�N3���܂ł̖�5�J���ŁA���؎����̑ΏۂƂȂ�͓̂����s�𒆐S�ɁA��ʌ��A�_�ސ쌧�A��t���ȂNJ֓��G���A�̖�100�˂̏Z��B ���؎����ł́A���d�Վ��ӓ��ɉƓd���i�̎�ނ��Ƃ̓d�C�g�p�̕ω������A���^�C���Ɍ��m���邽�߂̐�p�̓d�̓Z���T�[����яZ����̉��x�Ȃǂ𑪒肷����Z���T�[��ݒu���f�[�^�����W�B�Z���u���[�h�o���h����𗘗p���ăZ���^�[�V�X�e���ւ̌����I�ȓ`�����@�������鑼�A�d�̓Z���T�[�ƃu���[�h�o���h���[�^�[�ȂǂƂ̊Ԃ̒ʐM�����Ƃ��č���PLC�i�d�͐��ʐM�j�̓K�p������������ȂǁA�K�v�ȑ��u��V�X�e���S�̂̐��\�E�L������������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������d�͂�ESCO���Ɖ�ЁA�K�X�E�d�C�̏�����ɎQ�� �o�ώY�ƏȂ́A2017�N4���̓s�s�K�X������̑S�ʎ��R���ȍ~�A�V���ɃK�X��̔��ł���K�X�������Ǝ҂Ƃ��āA�����d�̓O���[�v�̓��{�t�@�V���e�B�E�\�����[�V���������O�o�^�����B ���Ђ́A����A�V���ȃG�l���M�[�T�[�r�X���j���[�Ƃ��ēd�C�E�K�X�̔̔����J�n���邱�ƂŁA����Ȃ�G�l���M�[�o�����[�`�F�[�����\�z���A�œK�ȃG�l���M�[�T�[�r�X�������X�g�b�v�Œ��Ă����l�����B�K�X�����莖�Ƃ�2017�N4������֓��ŊJ�n����\��B��ʉƒ�ւ̔̔��͗\�肵�Ă��Ȃ��B �o�ώY�ƏȂł́A�K�X�������Ƃ��c�����Ƃ���҂̎��O�o�^�̐\����t���J�n�����B�K�X�������Ǝ҂̎��O�o�^�́A���d�́A�����d�̓G�i�W�[�p�[�g�i�[�ɑ�����3���ځB����A�\���̂�����4���ɂ��Ă��A�R�����I������A�����o�^���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������{�̋@���L�斳���Őڑ��A�_�C�L�����h���s�T�[�r�X�n�o�֎��� ���Ђ̌��݂̋@�̉��u�Ď��V�X�e���ł́A�@��d�b����ɐڑ����A1��1�邢�͌̏Ⴊ�����������̂݊Ď��Z���^�[�ƒʐM���Ă���B NTT�����{�̍L�斳���ʐM��1�ł���LPWA�����p���邱�Ƃɂ��A���ׂĂ̋@�Ɖ��u�Ď��Z���^�[�������ɏ펞�ڑ����邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�̏�@��̓����̏���e�̐f�f�A�˔��̏�̑Ή��ɂ����鎞�Ԃ̒Z�k�ȂǁA�ێ�T�[�r�X�̌��オ���҂ł���B LPWA�iLow Power�AWide Area�j�́AIoT/M2M�iMachine to Machine�j�ɓK�����ȓd�́E�������ʐM����������ȓd�͍L�斳���ʐM�B��R�X�g�ōL�͈͂��J�o�[�ł���l�b�g���[�N�T�[�r�X�̂��߁A�@�B�̉^�]�ȂǗe�ʂ̏��Ȃ��f�[�^�̒ʐM�ɓK���Ă���B �g���C�A���ł́A�����{�G���A�ɐݒu����Ă��铯�Ђ̋@�̉ғ���ԁA����щ����O�̋�ԏ����펞�Ď�����B�܂��ALPWA�ɂ��@�̏���A����сA�����O�̃Z���T�[���̎��W��@���m������B ���Ђ�IoT�����p���������̐V�T�[�r�X�̑n�o�ɂȂ������l�����B �o�T�uBUILT�v |
|
|
| ���l�N�X�g�G�i�W�[�A�]���^���1�^2�Ɍy�ʉ��������z�d�r���W���[���� ���̐��i�̌��̍ő�o�͂�275W�����A�K���X�����]����1�^4�ɂ��A���ʂ����Џ]�����i�̖�1�^2�ƂȂ�10.5kg�������B�܂��A�w�ʕ⋭�o�[��W���d�l�Ƃ��A�����d�̖��ɂ�肱��܂ő��z�����d�̓���������ł������ꏊ�ɂ��Ή����邱�Ƃ��ł���B ���i�d�l�F���̍ő�o�́F275W �A���W���[���ϊ������F17.1���A�ő�V�X�e���d���F 1000VDC�A���̃T�C�Y�FW 983mm�~H1639mm�~D35mm�A�@�B�I�ωd�F�ϐ�d�F5400Pa�i�\�ʁ^�����d�܂ށj�E�����d2400Pa�i���ʁj�A�ۏF���i�ۏ�10�N �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�ώY�Əȑ�z�T�[�r�X������CO2�r�o���A�ȃG�l�{������� �ȃG�l�@�ł́A�N�Ԃ̗A���ʂ�3,000���g���L���ȏ�̉���u�����v�Ƃ��Ďw�肵�A�G�l���M�[�g�p�̕`�����ۂ��Ă���B �����̖�8���͐����Ƃ����A�d�q������i EC�j���͂��߁A�����Ɠ��̔��Ƃ̃G�l���M�[����ʂ��������Ă���A���Ԃ̔c�������߂��Ă���B �o�Y�Ȃ̎����ɂ��ƁAEC�s��́A2030�N��2015�N��2.3�{�ɂȂ�Ɨ\������Ă���B ���y��ʏȂ̕ɂ��ƁA�d�q������̋}���Ȕ��W�ɔ�����z�֎戵���͔N�Ԃ�15�����Ƌ}���A��z�ւ̖�2�����Ĕz�B�ƂȂ��Ă���B���̍Ĕz�B�ɂ��Љ�I�����́ACO2�r�o�ʖ�42���g�����Ǝ��Z���Ă���B ���Ȃ́A�V���ȏȃG�l�{��ɂ��āA���Ɂu���Ǝ҂̘g�����ȃG�l�v�u�T�[�h�p�[�e�B�����p�����ȃG�l�̐[�@��v��2�_�ɒ��ڂ��������s���Ă����B ����܂ł̋c�_���܂Ƃ߂��u���Ԏ��܂Ƃߍ��q�i�āj�v�ł́A�������Ǝ҂��A�g�����ȃG�l��g�݂�V���ȏȃG�l�̎�@�Ƃ��ĐϋɓI�ɐ��i���ׂ��ŁA�X�̎��Ǝ҂��Ƃ̏ȃG�l�w�͂ɒ��ڂ��Ă��錻�s�̏ȃG�l�@��x����ɂ��ĕK�v�Ȍ��������s�����Ƃ荞��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y��2015�N�x�G�l���M�[�������т����܂Ƃߌ��\ 2015�N�x�̃G�l���M�[�N��CO2�r�o�ʂ́A�G�l���M�[���v���ɉ����Đ��\�G�l���M�[�̕��y�⌴�q�͔��d���̍ĉғ����ɂ��A�O�N�x��3.5������2�N�A�������������Ƃ��킩�����B �G�l���M�[�N��CO2�r�o�ʂ�1,148Mt�|CO2�ŁA�k�Ќ�ł͍ŏ��B�d�͂�CO2���P�ʂ́A�O�N�x��0.56kg�|CO2�^kW h����0.54kg�|CO2�^kW h�ɉ��P�����B �ŏI�G�l���M�[�����13,403PJ�ŁA�O�N�x��1.8�����ƂȂ�5�N�A���Ō��������B����ʂɌ���ƁA��ƁE���Ə������傪��1.5�����i���̓��Ɩ�������͓�5.6�����j�A�ƒ땔�傪��3.3�����A�^�A���傪��1.7�����ƁA�O�N�x�ȏ�̗�āE�g�~���̉e���ŁA�ƒ땔��𒆐S�ɑS����Ō��������B ���d�d�͗ʂ̍\���́A�Đ��\�G�l���M�[�Ŗ�13���i��1.0���|�C���g���j�A���q�͂Ŗ�1���i��0.9���|�C���g���j�A�Η͂Ŗ�86���i��1.9���|�C���g���j�ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���r���̏Ɩ��E�̓����Ɂu�ȃG�l���C���ʐf�f�c�[���v�����s�������z�z�� �����s�ɂ��ƁA���̃c�[���́A�e�i���g�r���I�[�i�[���͂��߁A�ݔ����C�ɊW���鎖�Ǝ҂Ȃǂ��A�ȃG�l���ʂ��A�s�[������l�X�ȏ�ʂŗ��p�ł���Ƃ��Ă���B �ݔ����C�O�ɁA�����̐ݔ��ɂ��đ���ʂ��V�~�����[�V�������邱�ƂŁA�{�H���e�̌����ɖ𗧂B��ȓ��͍��ڂ́A�����T�v�Ȃǂ̊�{���A���ʐρA�G�l���M�[�g�p�ʁA�e�i���g�������A���C�O��̐ݔ����A�e�i���g��p���̏���6�B �{�c�[���ł́A���C����Ɩ��ݔ���ݔ��́A���[�J�[�J�^���O�̐��l����͂���B �f�f���ʁi�f�f���j�̎�ȍ��ڂ́A�ݔ����C��̏ȃG�l���x����A�E�Ɩ��̏ȃG�l���\����₷���}�ŕ\���B�팸�����d�͗ʂ�CO2�r�o�ʂȂǂ�\���B���̃c�[���͓����s���ǂ̃z�[���y�[�W�ɂČ��J����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�́ACO2��r�o���Ȃ����q�́E�ăG�l�ɁA�u�Ή��l�s��v��n�� ���{���{��2030�N��CO2�i��_���Y�f�j�r�o�ʂ�2013�N���26���팸����ڕW���f���Ă���B���̂��߂�CO2��r�o���Ȃ��Γd���i���q�́{�Đ��\�G�l���M�[�j�̔䗦��44���ȏ�ɍ��߂���j���B �Γd���ɂ͌��q�͂ƍĐ��\�G�l���M�[�ɉ����āA�]������̑�^�̐��͔��d�����܂܂��B����3��ނ̓d���Ŕ��d�����d�͂Ɂu�Ή��l�i�؏��j�v��^���āA���d�͎�����Ŕ����ł���悤�ɂ���B���̂��߂Ɏ�����̒��Ɂu�Ή��l�s��v��n�݂��邱�Ƃ����������B ���d�͎������ʂ��ƁA�Γd���ƉΗ͔��d�̓d�͂����l�Ɏ���������邽�߁A�Ή��l���F�߂��Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B�����Ŏ�����̒��Ɂu�Ή��l����s��v��n�݂��āA�d�͂ƕʂɔΉ��l�������ł���悤�ɂ���B�����d�C���Ǝ҂⎩�Ɣ��d���Ǝ҂͎s���ʂ��ĔΉ��l�B����CO2�r�o�ʂ̍팸�ɐ�������悤�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ۃG�l���M�[�@�ցi�h�d�`�j���\�Đ��G�l�A�ΒY�������d�e�ʍ\����g�b�v�� ���E�S�̂ő��z�����d�p�l������N�A�P����50�����̃y�[�X�Őݒu����A�����Ȃǂł͕��͔��d�@���P���ԂɂQ��̃y�[�X�Őݒu����A�h�d�`�͍Đ��\�G�l���M�[�̊g��\����啝�ɏ���C�������B ���ɂ��ƁA2010�`15�N�̐��E�̕��ϔ��d�R�X�g�͐V�^�̗��㕗�͔��d����30���A��K�͑��z�����d���ł͖�66���ቺ�����B����T�N�Ԃɕ��͔��d�̃R�X�g������15���A���z�����d����25���A����ɒቺ����ƌ����ށB ���E�S�̂ō�N�A�Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�e�ʂ�153�f�v���������B���̑唼�͂Ƒ��z������߂��B �Đ��\�G�l���M�[�����E�̔��d�e�ʂɐ�߂銄���ŐΒY���ăg�b�v�ɂȂ������A���d�ʂł͏����Ă��Ȃ��B��N�A�ΒY�Η͔��d�����E�̓d�͂�39��������������̂ɑ��A���͂��܂ލĐ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d��23���������B �h�d�`�ł�2021�N�܂łɍĐ��\�G�l���M�[�̔䗦��28���ɍ��܂�Ɨ\������B�������T�N�Ԃ̗\�����������A�Đ��\�G�l���M�[�̔��d�e�ʂ̑�������N�̗\���l����13������C�������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����E��CO2��100������ł���Η͔��d�A�č���2017�N�Ɏ��؉^�] �u���ՊECO2�T�C�N���Η͔��d�V�X�e���v�ƌĂԍŐ�[�̔��d�Z�p�𐢊E�ŏ��߂ĉ^�]������v�悾�B �J�������o�[�͓��ł̂ق��A�č��ő�̓d�́E�K�X��Ђł���G�N�Z�����iExelon�j�A���v�����g���݉�Ђ�CB&I�iChicago Bridge & Iron�j�A���ՊECO2�T�C�N���Η͔��d�̋Z�p���J�������x���`���[��Ƃ̃l�b�g�p���[�iNET Power�j��4�Ђł���B���̂������ł̓V�X�e���̒��j�ɂȂ锭�d�@�ƔR�Ċ�̊J���E������S���B ���ՊECO2�T�C�N���Η͔��d�V�X�e���͏]���̃K�X�Η͔��d�Ɠ��l�����A���d�ɔ����r�C�K�X���p����CO2�Ɛ��ɕ������ACO2�������̏�Ԃʼn�����ĔR�Ċ�ɑ���A�K�X��_�f�ƂƂ��ɔR�Ă����Ĕ��d�ɗ��p����d�g�݂��B �R���o�C���h�T�C�N�������i�K�X�^�[�r���������d�j�Ɠ����̍������d�����B1�̃^�[�r���Ŕ��d�@���\���ł��邽�߁A�v�����g�S�̂̋K�͂��������Ȃ�A���d�R�X�g��ጸ�ł��郁���b�g������B������CO2���E�������ݔ����s�v�ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���ߐ��Ɍ��ʓI�I���̏���ʂ���������X�}�[�g�f�o�C�X�uBrighTap�v�J���� �C�X���G���́uBwareIT�v�́A���̎d�l�ʂ���������v���f�o�C�X�uBrighTap�v�̊J���������߂Ă���B �uBrighTap�v�́A�L�b�`���p������V�����[�Ȃǂɑ������A����Ă��鐅�̗ʂ≷�x�A�R�X�g�Ȃǂ������I�Ɍv���ł���B�v���f�[�^�́A�{�̂̕\�����ɕ\�������ق��AW iFi��ʂ��ăN���E�h��̃f�[�^�v���b�g�t�H�[���Ɏ��W����A�X�}�[�g�t�H����E�F�u�T�C�g�ʼn{�����邱�Ƃ��\���B ����܂ł̎��؎����ŁA���̎g�p�ʂ�20%�팸�A����������25�����������B���̏���ʂ��������邱�Ƃɂ��A���[�U�[�ɐߐ��ւ̈ӎ��t�������A�]���̏K��������������������^����B �o�T�u�K�W�F�b�g�ʐM�v |
|
|
| �������r���ł��e�ՂɏȃG�l�A�G���x�[�^�[�ɍڂ�����R���p�N�g�ȕX�~�M�V�X�e�� ���z�r���̕X�~�M�V�X�e���X�V�ɂ����āA���W���[���������R���p�N�g�^�M��������q�[�g�|���v�A�C�X�W�F�l���[�^�[���̗p�����B �X�~�M�V�X�e���̗Ⓚ�@�́A�����n���Ȃǔ��o��������ȏꏊ�ɐݒu����邱�Ƃ������A����ȃN���[�����p�ɐݒu�������o���p�J����p���Ĕ��o�����s���Ă���B �r���p�}���`�G�A�R��15HP�i�����n�́j�^�̎��O�@�Ɛ��X�@�Ƃō\������Ă���A�������̐��@�͍ő吡�@�ŁA��1150�~�����[�g���imm�j�A���s��1215mm�A����195mm�A�d��360kg�B�G���x�[�^�[�ɂ��ύڂł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���j�t�e�B�ƘA�g����IoT���p���x���ցF�I�������A7�̊�������Z���T�[���\ �擾�ł�����́A���x�Ǝ��x�A�C���A�����A�����x�A�Ɠx�A���O����7�BBluetooth Low Energy�iBLE�j�ɂ��r�[�R���ʐM�ɑΉ����Ă���B �ݒu���邾����7�̊��������A���^�C���Ɏ��W�ł���B�r�[�R���ʐM�Őڑ������l�b�g���[�N����āA�N���E�h�Ȃǂɑ��M����B���M�����f�[�^�̓X�}�[�g�t�H���Ȃǂʼn��u�Ǘ����\���B ���Z���T�[�̔����Ɠ����ɁA��Ƃ�IoT�s��ւ̎Q���x����ړI�ɁA���ƃv���b�g�t�H�[���̍\�z�p�[�g�i�[�Ƃ��ăj�t�e�B�ƘA�g�\�B���Ђ̃Z���V���O�Z�p�ƁA�j�t�e�B�̃N���E�h�T�[�r�X�̋��݂����AIoT�����p�����\�����[�V�����T�[�r�X�̑n�o���x�����Ă����Ƃ����B �o�T�uEE Times Japan �v |
|
|
| �������ɂ��X�}�[�g���[�^�[���p�̔g�A�đ�肪���{�s��ɖ{�i�Q�� ���Ђ́A�����X�}�[�g���[�^�[���A�Y�������^�����F���擾�����Ɣ��\�����B�ʐM�@�\������A�����x�ȗ��ʌv�����s����B���ݐ_�ˎs�Ŏ��؎������s���Ă���B �����[�^�[�͓d�����ŁA��������Z���T�X�̖������W���[���𗘗p���āA�o�����ʐM�ɑΉ�����B15���Ԋu�̃f�[�^���\�ŁA�������j�␅�ʃf�[�^�̎��W�Ɋ��p�ł���B�v�ʔ͈͂�����R�l��800�ƍ����A1���ԓ�����1���b�g���Ƃ����Ⴂ���ʂł������x�ɑ���ł���B�����d�r�ɂ�铮�������15�N���ڈ��ƂȂ�B���{�ł�15�`40���a�܂ł�5��ނ�W�J����B ��Sensus�Ђ̓m�[�X�J�����C�i�B�̃X�}�[�g���[�^�[�̑��B�֘A����l�b�g���[�N�V�X�e���̉^�p�E�\�z�Ȃǂ���|����B���E��250����ȏ�̓������т�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u�ƒ�E��Ƃ̋@����ꊇ����v���u���������v����VPP�\�z�̎��؎��� �x�m�d�@�AGS���A�T�A�Z�F�d�C�H�ƁA���{���j�V�X�ANTT�X�}�C���G�i�W�[�A�G���[�p���[�A��ёg�A�O�H�����Ȃǂ��Q������B ���̎��؎��Ƃ́A�d�͎��R����d�̓V�X�e�����v���i�ޒ��A�Љ�S�̂Ƃ��Č����I�ȃG�l���M�[���p�C���t���̊�Ս\�z�̎�����ڎw�����́B ��̓I�ɂ́A�d�͌n���ɓ_�݂���ڋq�̃��\�[�X���A�����郂�m���C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����uIoT�v�����Ĉꊇ����B����ɂ��A�ڋq�ݔ�����P�o�ł�����������͂�L�����p���A��������1�̔��d���i���z���d���j�̂悤�ɋ@�\������d�g�݂̍\�z��ڎw���B ���؎��Ƃ́A7��21������2017�N2��28���܂Ŏ��{����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���n�M���d�Ɏg��Ȃ��M������8000���ѕ��̓d�́A2018�N2���ɋ����J�n ���������w�h�s��1995�N����ғ����Ă���u�R�씭�d���v�̍\���ɁA���C�ƈꏏ�ɕ��o����M�����g���Ĕ��d����u�R��o�C�i���[���d���v��V���ɐݒu���āA�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��d�͂̋����ʂ𑝂₷�B ���d�\�͂�5MW �A�N�Ԃ̔��d�ʂ�3000��kW h��\��B8�����ɍH���ɒ��肵�āA1�N�����2018�N2���ɉ^�]���J�n����\�肾�B �ʏ�̒n�M���d�ł͏��C�ƔM�������āA�����̏��C�������g���ă^�[�r������]���Ĕ��d����B������̔M���͒n���ɖ߂��Ă���B����ɑ��āu�o�C�i���[�����v�ł͖����p�̔M���ŁA���d�p�̔}�̂�����������M�Ƃ��ė��p����B���������}�̂Ń^�[�r������]�����Ĕ��d����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ȃG�l��ɐl�H�m�\�̊��p���n�܂����I��������̖��ʂ����Ԃ�o�� �O�H�d�@��IoT�����p�A���Y������͂��ҋ@�d�͂��Ɍ��܂ōi�荞�BIoT�ɂ�鐶�Y���P��CO2�r�o�ʂ�1��1000�g���팸�B �x�m�d�@�́A��ʂ�EMS�ƈقȂ�A�ߋ��̎g�p���т���d�͎g�p�ʂ̗\���l���o���B�\���Ǝ��тɍ�������Ɗw�K���A�\�����x�����߂�B2015�N�x�͓d�͎g�p�ʂ�13���팸�����B NEC�́A�Z���T�[�Z�p�Ə��ʐM�Z�p�iICT�j�̑g�ݍ��킹�ŏȃG�l����i�߂Ă����BEMS�ɂ��v����\���ȊO�ɂ��A���d�Ղ���@��ʂ̏���d�͂������鉻����u�d�͎w�䕪�͋Z�p�v���̗p�B�ȃG�l�@��̓������ʂ��܂߁A�d�͎g�p�ʂ������B ����2030�N�x��EMS���y���́A�H��23���i2012�N�x4���j�A�r��47���i��6���j�Ɨ\���B�ȃG�l�ɂ��ŐV�Z�p�̗̍p���z�肳���B �o�T�u�j���[�X�C�b�`�v |
|
|
| �����^�ł�3���ȏ�̘A�����d�A���f�Ŕ��d������p�R���d�r�V�X�e�� �u���U�[���J�������̂́A�ő̍����q�`�R���d�r�ŁA�����f�𗘗p���Ĕ��d����B ��i�o�͂�DC12�`21V�iAC100V�o�͂̃L�b�g���p�Ӂj�A�ő啉�חe�ʂ�880W �A�}�C�i�X15�`40���͈͓̔��ŗ��p�ł���B �d���e�ʂ�15.8kWh�B72���Ԉȏ�̘A���ғ����\�B �u���d���j�b�g�v�Ɓu�R�����j�b�g�v�ō\������B�O�`���@�Əd�ʂ͔��d���j�b�g��53�~56�~66cm�A78kg�B�R�����j�b�g��51�~42�~67cm�A�R���P�[�X�������{�݂̂̂̏d�ʂ�41kg���B���p�d���Ƃ��Ă̊��p�������ށB ��i�o�͂�DC12�`21V�i�{���g�j�BAC100V�o�͂̃L�b�g�����B�ő啉�חe�ʂ�880W �A�}�C�i�X15�`40�x�͈͓̔��ŗ��p�ł���B�d���e�ʂ�15.8kW h�B�{�݂̂̂̏d�ʂ�41kg�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���H��̏Ɩ��𐅋���v����LED�ɒu������GS���A�T�A���V�����LED�Ɩ��V���[�Y���g�[ ����d�͂�400W �����700W �̐�����v�̌����p�ɁA�ŐV��LED���W���[����p���ď���d�͂�107W �A163W ��LED�Ɩ��������B �V���i�́A���^������ƂƂ��ɁA�p�x��ς�����A�[���������B����ɂ��A�f�U�C�����Ƌ@�\���𗼗��������Ƃ����B����������6�����ԂŁA������v��1��2000���Ԃ�5�{�B�F���x��5000K�i�����F�j�ł���B ���N9���ɂ͐��ⓔ1000W �ɑ�������LED�Ɩ����������\��B����d�͂�320W�B �o�T�u���o�e�N�m���W�[�v |
|
|
| ���g���x�̗h�炬�h�͌��Ƃ�������d�Z�p�A���i�v�쓮���\�� ���̔����͐����̋z���ʂɉ����ċ��L���邽�߁A���x�ω��ɉ����ċ��L�^���������B�]���̂��̂�菭�Ȃ������ʂő傫���A�����ɋ��L�^�����s���B �����O���[�v�́A�����̈ꕔ�ɋ����������邱�ƂŁA���̋z�E�����N�����Ȃ��ꏊ���쐻����B����Ǝ��x�̗h�炬�ɑ��ē������L�^�����J��Ԃ�������Ɏ����I�ɕ���������Ƃ����d�g�݂��B �����̐����̋z���ʂ͔M����ɂ��e�����邽�߁A���ɂ����邳�܂��܂ȗh�炬�𔖖��̉^���G�l���M�[�ɕϊ����邱�Ƃ��\���B ���̔����́A2�������q��p���A�Ǝ��ɊJ��������@�ɂ��A���M���邾���Ƃ������ɃV���v���Ȏ�@�ō쐻���邱�Ƃ��\�ł���Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�͂́u�l�K���b�g����v�ō��̕��j�����܂�A����P�ʂ⒲�����̌v�Z���@�Ȃ� �������������Ȃ�ꍇ��A�����d�C���Ǝ҂��ً}�ɓd�͂̒��B��K�v�Ƃ���ꍇ�ɁA�l�K���b�g��������{����B ���{��2017�N4��1���Ƀl�K���b�g������J�n�ł���悤�ɁA�^�p�̐��̐�����i�߂Ă���B�ߓd�ʂ̎Z��⎖�ƎҊԂŔ������钲�����̌v�Z���@���K�肷��ق��A�l�K���b�g����̓d�͂����d�͎�����Ŕ����ł���悤�ɂ���B �l�K���b�g����̉^�p���[���ōł���{�I�ȓ_�́A�ߓd�����d�͂̎���P�ʂł���B���ʂ͎��v�Ƃ��Ƃ̎���P�ʂ�1kW�ɁA���v�Ƃ���l�K���b�g���W�߂Ď�����鎖�ƎҊԂ̎���P�ʂ�100kW �ɐݒ肷����j���B�ߓd�����d�͂�30���P�ʂŌv�Z���邽�߁A1kW ��0.5kW h�i�L�����b�g���j�Ŋ��Z����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������FIT�@�Ɋւ���V���[���܂Ƃ߁u�ݔ��F��v����u���ƔF��v�� �V���x�ł́A����܂Łu�ݔ��F��v�ƌĂ�Ă������x�Ɏ��ƂƂ��Ă̗v������������B �T�v�́A �@1�D�ăG�l���d���Ƃ̊�F���{�v�悪���m�ɒ�߂��Ă��邱�ƁB���K�͗e�ʕ����F��\���łȂ����ƁB�ێ�_���E�ێ��Ǘ����邽�߂̑̐����A���{���邱�ƁB10kW�ȏ�̑��z�����d�́A�F��擾����3�N�ȓ��ɉ^�]�J�n���s���v��ł��邱�ƁB �@2�D�ăG�l���d�ݔ��Ɋւ����F���d�ݔ������肵�Ă��āA�����ԓ��ɔ��d�ݔ����m�ۂ��邱�ƁB�������s���ăG�l�d�C�̗ʂ�I�m�Ɍv���ł��邱�ƁB �@3�D�ăG�l���d���Ƃ��~���E�m���Ɏ��{������F���z�d���Ǝ҂Ƃ̊ԂŐڑ��_��̒����B�ݒu�ꏊ��L���邩�A�m���Ɏ擾���邱�Ƃ��ł��邱�ƁB �V�����F�萧�x�ł́A�F������ăG�l���d���ƌv��̓��e���E�F�u�T�C�g�Ō��\�����B http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/kaisei_syorei.pdf �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�̖͂�����ς���u���\�[�X�A�O���Q�[�^�v�A���U����G�l���M�[��]�点�Ȃ� �n��ɕ��U����d�͌���1�̔��d���̂悤�ɉ^�c����u�o�[�`�����p���[�v�����g�i���z���d���j�v�̍\�z�ƏW���d�͂������d�C���Ǝ҂ɋ�������u���\�[�X�A�O���Q�[�^�v�̃��f���r�W�l�X���\�z����B ���̃��f���́A�Đ��\�G�l���M�[�̓����ʂ̍ő剻�A�d�͂̒�R�X�g���B�A�n��S�̂̓d�͂̎����o�����X�����Ȃǂɂ��A���z�d���Ǝ҂̃R�X�g�팸�ɂ��Ȃ���B���d�E���z�d�E������3���삷�ׂĂɃ����b�g�������炷���z�I�ȃV�X�e���Ƃ��Ċ��҂�������B ���{�d�C�Ⓦ���d�̓O���[�v�Ȃ�9�Ђ����؎��Ƃ��J�n�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�V�����ȃG�l������������u�G�l���M�[���P�ʁv�����P����{��Ȃ� ���Ȃ́A�ȃG�l���M�[���ψ���ɂ����āA�V���ȏȃG�l�{��̊T�v���܂Ƃ߂��B �V���ȏȃG�l����ւ̓]���Ɍ����A�u�G�l���M�[���P�ʉ��P�v�u�G�l���M�[�Ǘ��̒P�ʂ̊g��v�u�T�[�h�p�[�e�B�̊��p�v��3�̒��ł܂Ƃ߂Ă���B �u�G�l���M�[���P�ʉ��P�v�ł́A�ȃG�l�ʂ����ł͂Ȃ��A���P�ʉ��P���ɒ��ڂ����x�����x�̏[�����K�v���Ƃ��Ă���B �u�G�l���M�[�Ǘ��̒P�ʂ̊g��v�ł́A�T�v���C�`�F�[���P�ʂ�O���[�v��ВP�ʂȂǂł̏ȃG�l�𑣐i����x�����x���[�������Ă����l�����B �u�T�[�h�p�[�e�B�̊��p�v�ł́A������Ƃ����҂ɒ��ڃA�v���[�`�ł���T�[�h�p�[�e�B�ւ̓������������߁A�x�����x�̏[�����������ׂ����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2016/8�@]�@�@�� |
|
|
| ��6��ނ̃Z���T�����H���s�v��IoT�f�o�C�X�X�܂�I�t�B�X�̏ȃG�l�� IoT�T�[�r�X�́A�Z���T�f�o�C�X�ł�6�̍��ځi���x�E���x�E�C���E�Ɠx�E�����E�l�̓����j�𑪒�ł��A�N���E�h�o�R�Ń��A���^�C���Ƀf�[�^�̊m�F���s�����Ƃ��ł���B �܂��A�擾�����f�[�^�͕��̓G���W���ŏڍׂȉ�͂�A�ڋq�̃j�[�Y�ɉ������A�E�g�v�b�g���o�����Ƃ��ł���B�X�܂�I�t�B�X�̉��x�E���x�̌����鉻�ŋ̃R�X�g�̍팸��A�K�Ȑ�����s�����ƂŖ��ʂȏ���d�͂�}������B �{�T�[�r�X�̗����͌��z3,000�~����B100�䂩�痘�p�\���B�Ȃ��A�ݒu�H���s�v�Ńf�o�C�X�����^������A�A�v���P�[�V�����T�[�r�X���p�����܂ށB������p�͌ʌ��ς���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d�[����62���ŃM�l�X���E�L�^�B�����R���o�C���h�E�T�C�N���Η͔��d�� ��GE�ƃt�����X�d�͂́AGE���K�X�^�[�r����p����60.5��kW�̃R���o�C���h�E�T�C�N�����d�����ғ����J�n�����Ɣ��\�����B ���d�[����62.2���͐��E�ō������B���Ђ́A�V���Ȏ���̔��d�Z�p�ƃf�W�^���Z�p�̗Z���̂͂��܂�Ƃ��Ă���B �����d���ł́A30���ȓ��Ƀv�����g��i�o�͂ɓ��B����Ƃ����B���̂��ߌn���̃f�}���h�ϓ��ɑf�����Ή��ł��A�n���ɍĐ��\�G�l���M�[�̓d�͂̐ڑ����\�ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�͂��]���ɔ��20�����팸�F�f�[�^�Z���^�[�̋A�����x�ȗ\���ŏȃG�l ���Z�p��K�p����ƁA�@��̏o�������b�N�ʒu�̕ύX�Ȃǂɂ��̕ω���\���ł��A��ʓI�ɍs���Ă���}����p�̕K�v���Ȃ��A�ȃG�l�^�]�ɂȂ�B �d�͂��]���ɔ�ׂ�20���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ����B1000���b�N�K�͂̃f�[�^�Z���^�[��450��kWh�̏ȓd�͂ɂȂ�B �f�[�^�Z���^�[�ɂ�����d�͏���ʂ͔N�X�������Ă���A�S����d�͂̂Ȃ���1�`2�����߂�悤�ɂȂ����B���ɁA�f�[�^�Z���^�[���ŋݔ�����߂�d�͏���ʂ�30�`50���ɒB���Ă���Ƃ����B �o�T�uEE Times Japan�v |
|
|
| �������r���ł��e�ՂɏȃG�l�A�G���x�[�^�[�ɍڂ�����R���p�N�g�ȕX�~�M�V�X�e�� �����M�������̕X�~�M�V�X�e���̗Ⓚ�@�́A�����n���Ȃǔ��o��������ȏꏊ�ɐݒu����邱�Ƃ������A����ȃN���[�����p�ɐݒu�������o���p�J����p���Ĕ��o�����s���Ă����B ���Ђ́A���Ѓr���i�n��2�K�E�n��12�K���āj�Ƀ��W���[���Ή��̃R���p�N�g�^�M��������q�[�g�|���v�A�C�X�W�F�l���[�^�[�i�R���p�N�g�^�A�C�X�W�F�l���[�^�[�j�������B �����i�́A�r���p�}���`�G�A�R��15HP�^�̎��O�@�Ɛ��X�@�Ƃō\������Ă���A�������̐��@�͕�1,150mm�A���s��1,215mm�A����1,950mm�A�d��360kg�ŁA�G���x�[�^�ɂ��ύډ\�B�K�i�ł̔�����N���[���̏��^�����\���B�G���x�[�^�[�ɂ��������\�ɂȂ�X�V�����啝�ɍ��܂����B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| ��LIXIL�A�r���p���f�M�n�C�u���b�h���uPRESEA�v���� ���Ђ́A�f�M��H-6�̍��f�M�ƃf�U�C�����𗼗������r���p���f�M�n�C�u���b�h����̔��J�n����Ɣ��\�����B �����́A�όƋ��x�ɗD���A���~�ƁA�f�M���Ɩh�I���ɗD��������g�ݍ��킹���\���ŁA�����w�r���ɋ��߂���ϕ������␅�����Ȃǂ�������ō��f�M���������Ă���B �����Ƃ��ẮA�A���~�\���Ƒ��w�z���[�����`�ނɂ��t���[�������\���ɁA�K���X�����\���ƃK���X�ʐς̍ő剻��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�ƊE���̒f�M��H-6�����������B�K���X�ʐς͏]����Ŗ�30���g�傳��A���]�������悭�Ȃ�A�f�U�C���������サ�Ă���B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ���������Ǝ҂͓d���\���J���ցA��8�������J��i�߂�ӌ� �����d�C���Ƃ��s���ӌ��̂���249���Ǝ҂ɓd���\�����̏��J���Ɋւ���A���P�[�g�����{���A146���Ǝ҂���̉��B ���̓��A2016�N4��25�����_�ʼnƒ�p�����d�C���Ƃ��s���Ă��鎖�Ǝ҂�54����78���Ǝ҂������B ����s���\��̎��Ǝ҂��܂߂��115���Ǝ҂ɂȂ�B�d���\�����_���Y�f�r�o�W���Ɋւ�����̊J�����s���Ă���̂�27���ƎҁB����J������\��̎��ƎҐ���64���Ǝ҂ō��킹��Ɩ�80����91���Ǝ҂��J�����錩�ʂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���~�h�����V�R���A������40���A�b�v�̕i����ǂɐ��� �o�C�I�x���`���[�̃��[�O���i�Ɠ�����w�A�����w�������̌����O���[�v�ŁA���ב��ށu���[�O���i�i�~�h�����V�j�v�̈�`�I�ɑ��l�ȏW�c�����o���A���̒���������I�ɖ����ܗL�ʂ̑����̂�I�ʂ����@���J�������Ɣ��\�����B ���[�O���i�̍זE�ɏd�C�I���r�[���Ǝ˂����{���A���܂��܂ȓ������������זE�i�ψّ́j�����ꂽ�B���̃��[�O���i�̏W�c�̒�����A�u�����x�̈Ⴂ�𗘗p���āA���ɖ����𑽂��܂ރ��[�O���i�𒊏o�����B���̌��ʁA��40�������𑽂��܂ރ��[�O���i�ψّ̂��擾���邱�Ƃɐ��������Ƃ��� ���݁A�J�����̓���̍זE��v������R�X�g�ɔ�������͂ł��鑕�u�����p���邱�ƂŁA����ɖ������ʂɊ܂��[�O���i�𒊏o�ł���\��������Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���T�����t�H�[���ŃG�l������A�r���Ώہ@�听���� ���Ђ�8�K���āA�z10�N�̃r���ŁA�T���{�H�ŏƖ��̃��t�H�[�����s�����B �]���̌u������LED�Ɩ��Ɍ����B���C�O�̏Ɠx��700���N�X��300���N�X�ɗ��Ƃ��A�茳�Ɩ��ŁA�����700���N�X���m�ۂ����B �܂��A�l���Z���T�[�̗��p�ƁA1.8���̃}�X��1�����Ƃɐ���ł���A���S���Y���ɕύX�����B����ɁA�l�̍݁E�s�݁A�Ɩ��̖��邳�������鉻���郂�j�^�[���ݒu�����B�ȃG�l��c�����₷�����邱�ƂŁA�]�ƈ��̈ӎ������߂邱�ƂɂȂ��邱�Ƃ��ł���ƌ���B ���Ђ̃V�~�����[�^�[�ł̓G�l���M�[�̑n�o�ʂƎg�p�ʂ�\���ł��A�T�������̎{�H�̂��߁A�o�Y�Ȃ�ZEB��ł́A�ȃG�l����50���ȏ�́uZEB���f�B�v�ɑ�������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����s�s�A�G�R�h���C�u���i���Ə��o�^���x�������� ���s�́A�G�R�h���C�u���i���Ə��x�����e���č\�z���A�u�D�ǃG�R�h���C�u���i���Ə��v��F�肷�鐧�x��V���ɐ݂��A�^�p���J�n�����B�V���Ȏ�g�x����́A 1�j�G�R�h���C�u�V�~�����[�^�[�E�R��v�̑ݏo���A 2�j���C�ւ̐��u�t�̔h���ȂǁB ���Ə��F�萧�x�͑��̎��Ə��̖͔͂ƂȂ�悤�Ȉ���ȏ�̗D�ꂽ��g���s���Ă���i�]�ƈ��ւ̎��m�B����I�Ȍ��C�����{�B�R��L�^�A���P���{�B�G�R�h���C�u���i�ӔC�҂�ݒu�j�B�F�莖�Ə��ɔF��̌�t�A�F��V�[���̔z�z�A�s�z�[���y�[�W�ł̌��\���s���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| �����E�ő�K�͂�CO2�t���[���f�����ցA2020�N�ɕ������ʼn^�]�J�n ���{�́u�����V�G�l�Љ�\�z�v�̍��q�Ă����\�����B�������𖢗��̃G�l���M�[�Љ�̃��f���Ƃ��ĕ���������B�W�Ȓ��ɉ����ĕ������Ɠ����s�A�d�͉�Ђ⍑�̌����@�ւ��Q�悵�Ċ�����̂Ő��i����\�z���B ���q�Ắu�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��v�u���f�Љ�����̃��f���\�z�v�u�X�}�[�g�R�~���j�e�B�̍\�z�v��3�̃e�[�}�ō\������B2020�N�ɕ�������V�G�l�Љ�̃��f�����_�Ƃ��Ĕ��W������B ���f�֘A�̎��g�݂ł́A�������Ő����������f�𓌋��܂ŗA���E�����ł���Z�p�̎��ɂ����g�ށB���������ł����f�X�e�[�V�����̐����A�R���d�r�ԁE�o�X�Ȃǂ̓����𐄐i���Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��SII �u�G�l���⏕���v�̑����ʂ̏ȃG�l���E��p�Ό��ʂȂǂ̕��̓��|�[�g���J �������C�j�V�A�`�u�iSII�j���A27�N�x�̍����������ƍ̑����́u�ȃG�l���M�[�ʁv�E�u�ȃG�l���M�[���v�E�u��p�Ό��ʁv�Ȃǂ̊T�v���܂Ƃ߂Č��\�����B https://sii.or.jp/file/cutback28/sinsei_jisseki.pdf ������Ƃ̏ȃG�l�ʂ�7���ȏオ50kl�����B������Ƃ̏ȃG�l���M�[�ʂ̌X���́A�قړ��l�ł���B������Ƃ̔����ȏ�̏ȃG�l����10�`25���B����26�N�x�ɂ�����ȃG�l���M�[��10���ȏ�̊����͖�7���ł������B����27�N�x�ɂ�����ȃG�l���M�[��10���ȏ�̊����́A��8���܂ő������Ă���B��p�Ό��ʂ́A������Ƃł́A5���ȏオ200kl�^�疜�~�����̈Č����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����l�s�E���dEP�E���ŁA�u���z�̔��d���v�\�z�Ɍ�����{�������� ���s�Ɠ��ŁA���dEP�́A�ȑO����G�l���M�[�z�s�s�̎����Ɍ����Ď��g��ł����B ���N�x�́A�s���̏����w�Z�i�e��1�Z�A�S18�Z��\��j�ɁA10kWh�̒~�d�r�ݔ���ݒu���A�~�d�r�Q����V�X�e���ɂ��A�d�͎��v�̒����i�f�}���h���X�|���X�j���s���A�[���d���I�ɐ��䂷��B���펞�Ɣ�펞�̋@�\��A���Ɛ��A�L������]������B ���̎��g�݂��u�X�}�[�g���W���G���X�E�o�[�`�����p���[�v�����g�\�z���Ɓv�Ƃ��Đ��i����B�i�X�}�[�g���W���G���X�F��R�X�g�Ŋ����������A�ЊQ�ɋ����ݔ��E�X�Â�����\�z�����g�j ����A�����{�݂��͂��ߎs��̎{�݂ɓW�J����ƂƂ��ɁA���z�����d�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�̊��p���܂߂��u������̓r��Ȃ����_�Â���v��ڎw���B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��Society 5.0�𐢊E�ɐ�삯�Ď����ցF�Y�����A2030�N�Ɍ����������헪������ �����́A�u�Y������2030�N�Ɍ����������헪�v�����肵���B�u���X�}�[�g�iSociety 5.0�j�ȎY�ƁE�Љ�v�A�u��Y�f�A�����z����Ƃ���T�X�e�i�u���ȎY�ƁE�Љ�v�Ȃ�4�̌����ڕW���߂��B �u���X�}�[�g�ȎY�ƁE�Љ�v�Ƃ́A�Љ�C���t���A�G�l���M�[�l�b�g���[�N�A�n�����ȂǗl�X�ȕ���ō��x�ɗZ�����ꂽ�Љ�ł���B �u�T�X�e�i�u���ȎY�ƁE�Љ�v�ł́A���ΔR��������Ɉˑ������A���ʂ�p������O��I�ɔr�����邱�ƂŁA�����ׂ̏��Ȃ��Љ���������Ă����B���̂��߂̎�Ȍ����ۑ�Ƃ��āA�u�Đ��\�G�l���M�[�̓K�ȕ��y�g��v�A�u�ȃG�l���M�[�^�~�G�l���M�[�̋Z�p�v�A�u���f�̐����A�����^�A���E���p�Z�p�v�Ȃǂ̊J���Ɏ��g�ށB �o�T�uEE Times Japan�v |
|
|
| ���ȃG�l�x���̃N���X�������x���n���A��؎��Ǝ҂ɂ͗������茟���� �����x�́A������o����S�Ă̎��Ǝ҂�S�AA�AB�AC��4�i�K�փN���X��������B �uS�N���X�v�́A5�N�Ԃ̕��ό��P�ʂ�N1���ȏ�ጸ���邩�A�x���`�}�[�N���x�̑ΏۋƎ�E����ɂ����āA�������I�ɖڎw���ׂ������ł���u�x���`�}�[�N�ڕW�v��B�����邱�ƂŔF�߂���B �u�ȃG�l������Ă��鎖�Ǝҁv�Ƃ��Ă���̂��uB�N���X�v�ł���B�u�w�͖ڕW�v�����B���ł��邾���łȂ�����2�N�A���Ō��P�ʂ��ΑO�N�x�䑝�����Ă���ꍇ��A5�N�Ԃ̕��ό��P�ʂ�5���ȏ㑝�����Ă��鎖�Ǝ҂Ȃǂ�ΏۂƂ���B�uA�N���X�v�́A�uB�N���X�v�ȏ�ł��邪�uS�N���X�v�܂ł͓͂��Ȃ����Ǝ҂Ƃ���B�uC�N���X�v�́uB�N���X�v���Ǝ҂̒��œ��ɔ��f��̏�����s�\���Ȏ��Ǝ҂������Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����Đ��\�G�l���M�[�A2031�N�ɓV�R�K�X�����čő�̔��d���� �u���[���o�[�O�E�j���[�E�G�i�W�[�E�t�@�C�i���X�iBNEF�j�̕��͂ŁA2031�N�ɂ́A�č��ł͕��͂Ƒ��z�����d�̃R�X�g���ቺ���邽�߁A�Đ��\�G�l���M�[���V�R�K�X���A��v�Ȕ��d���ɂȂ�Ƃ̌��ʂ��������ꂽ�B BNEF��2040�N�ɂ����čĐ��\�G�l���M�[����������7450���h���i��79��600���~�j�ɏ��A���ΔR���̐V�K�v�����g�����������z�ł���950���h���i����j�����邽�߂Ǝw�E�B2020�N�ȍ~�́A�⏕�����x������Ȃ��Ă����z���ƕ��͂̔��d�\�͂��K�X���邢�͐ΒY���������ɂȂ�Ɨ\�z�����B �C���h�⒆���Ȃǂ̍��X�ŐΒY���畗�́E���z�����d�ւ̈ڍs���i�ނ��߁A�Đ��\�G�l���M�[��2027�N�܂łɐ��E�̎�v�Ȕ��d���ƂȂ錩�ʂ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���[���E�G�l���M�[������������{�ő�̏��Ǝ{�݁A���m���ɒa�� ���C�����z�[���Z���^�[�Ó��X�́A�����ʐϖ�1.3��m2�A�S����1�K���B�X�܂̉���ɂ�1.2MW �̑��z�����d�V�X�e����ݒu�B���d�����d�͂͑S�Ē����d�͂ɔ��d����B�S�ʔ��d�����d�͗ʂ��G�l���M�[�팸�ʂ̌v�Z�Ɋ܂߂���B �ȃG�l�ݔ��̓�����G�l���M�[�}�l�W�����g�ɂ���āA��67���̈ꎟ�G�l���M�[����ʂ��팸���A����ɑ��z�����d�V�X�e���ɂ��n�G�l�Ȃǂ�ZEB��B���ł���Ƃ��Ă���B �n�G�l�E�ȃG�l��S���u�A�N�e�B�u�R���g���[���v��A���R�̗͂����u�p�b�V�u�R���g���[���v�A�������œK�ɐ��䂷��u�G�l���M�[�}�l�W�����g�v��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�G�l���M�[������������[���ƂȂ錩���݁B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u�����X�}�[�g�R�~���j�e�B���c��v�X���тŃG�l���M�[���p�̍œK�� �����c��͐������݂□�̑f�A���M�����Ȃ�11�Ђō\������B�����d�͂ƏȃG�l���M�[�Ɋւ���p�[�g�i�[�V�b�v��������Ɣ��\�����B���N�x���ɋ����̉����Ǝ{�݂̓d�͎��v��g�p���т��c������G���A�E�G�l���M�[�}�l�W�����g(AEM)�V�X�e�����\�z�B�X���тŃG�l���M�[���p�̍œK����i�߂�B ����1�A2���ڒn��̊X��P�ʂŁA�d�͎����̕N���������܂�鎞�̃f�}���h���X�|���X�i�c�q�A���v�����j�̏�c���B�����d�͂ƘA�W���A�ȃG�l���M�[���_���Y�f�iCO2�j�팸�Ȃǂ̎{��̗L������������B�c�q���тɉ����ē����d�͂����V���A�e�{�݂̂c�q�v���x�ɉ����ĕ�V�z����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���d�͂̎掟�T�[�r�X�Ɠd�͂̌����鉻�œd�C�R�X�g�̑啝�팸���đ�ˏ��� ���Ђ́A�ȑO�����Ƃ̏ȃG�l�ɖ𗧂T�[�r�X�Ƃ���LED�Ɩ���Ɩ��R���g���[���V�X�e���A�d�͂̌����鉻�T�[�r�X�Ȃǂ�W�J���Ă����B��Ƃ̓d�C�R�X�g�͏㏸�������Ă�����A�����ɉ����ēd�͂��̂��̂̔̔��ɏ��o�����Ƃ����߂��B �V���ɊJ�n����u�d�͋����T�[�r�X�v�́A�d�͏����̃O���[�o���G���W�j�A�����O�̎掟���s���B���Ђ́u�d�͂̌����鉻�\�����[�V�����v�́A���A���^�C���ł̓d�͂̎g�p���������A�s�[�N���ɂ͌x�[���Ȃǂ𑗂�A�d�͂�}������\�����[�V�����ł���B�V�d�̗͂̍p�ɂ���{�I�ȓd�͂̃R�X�g��ጸ���鑼�A�d�͂��̂��̂��g��Ȃ��悤�ɊǗ����邱�ƂŁA�����I�ȓd�̓R�X�g�팸�ɂȂ���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����{�̑����Ԃ̉������ʃK�X�U���팸�ڕW�B���A���A�̐R�������� ���{�́A���s�c�菑�����ԁi2008�`2012�N�x�j�ɂ����āA�������ʃK�X�r�o�ʂ���N�i1990�N�x�j���6���팸����`�����Ă����B ���̍팸�ڕW��B�����邽�߂ɁA2015�N11��18���������Ƃ��āA���A�C��ϓ��g�g����ǂ��u���p�i�ڕW�B���̂��߂̃N���W�b�g�E�r�o�g�̖������j�v���s�����Ƃ����߂��Ă����B ������āA���{���ۗL����N���W�b�g�E�r�o�g�i���������ʁA�X�ыz�����A�C�O����̋��s���J�j�Y���N���W�b�g�j�ɂ��āA6���팸�ڕW�̒B���ɕK�v�ƂȂ��63��9,200���g�����̏��p��2015�N11��16���܂łɍs���A���{�̋��s�c�菑�����Ԃ̖ڕW�B�����m�肵���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���\�邾���ő����N��1400kWh���d�A���l�̃r�[���H��œ��� ���Ђ͉��l�H���90���N�ɃG�l���M�[�ɂ₳�����H���ڎw���ĉ��C�����{�B ���̒��ŁA�O���M�̉e�����鎎�����Ɍ�t�����z�����d�@�\�t���ȃG�l���̓��������߂��B ��������2�i�̑呋������A���i������75�������[�g���ɓ����B�����ɂ�锭�d�\�͂́A�N�Ԃ�1400kW h�i�L�����b�g���j��\�肵�Ă���Ƃ����B ��t���ȃG�l����1���K���X�̑��Ɍォ��K���X��\����ĕ��w�K���X�ɂ��A���̏ȃG�l���\�����߂���B2015�N12���ɔ����̓��ߗ��̍������z�d�r�ɒu�������A���z�����d�@�\�����������̂��B �X�_����ɃJ�b�g�����P�����Z���ɂ��A��57���̊J���������������d�����Ǝ��E�̗����������������i���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���m�[���c�X�s�[�h�����͂�Ɩ��p��������\�� ���Ђ́A���{�݂ȂǂɑΉ����A�X�s�[�h�����͂肪�\�ȋƖ��p�������K�X�ӂ닋������A9��1���ɔ�������B ���P�_�́A�������̔M������v���Ɩ��p�d�l�ɂ����A�ƊE���̋Ɩ��p�������K�X�ӂ닋����ŁA�������ʂ�u�o���p�C�v�v�́A�����Ԃ̏o���ɑς�����悤�A�ƒ�p��œ�����20���A�b�v�����Ă���B�܂��A�h�������𒆘a���邽�߂̒��a����Ԃ̎g�p�ɑς�����悤�ɑ�^�����A�ƒ�p��2�{�̒������������������B ���{�݂̓����ł̓��W�I�l���ۂȂǂ̍ۗނ̑��B��h�����Ƃ��d�v�Ȃ��߁A�����̂�������߂��Ƃ��̉������@�Ƃ��āu�����������v���̗p���Ă��邪�A���{�݂Łu���v�T�[�r�X�����{����Łu�z�ǂ������d�l�v���I���ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����R�[�V�d�͐i�o�ɍ��킹�A�X�}�[�g�R�~���j�e�B�[���Ƃ֓W�J�ڎw�� ���Ђ́A2015�N10���A�d�͏����莖�ƂɎQ�������B�d�͔̔������������Ɏ��W�����d�͎g�p�f�[�^�������ɁA�k�d�c�Ɩ���G�A�R���Ȃǂ̏ȃG�l�@����A�d�͂̌_��҂ɒ�Ă���B �d�͎��Ƃ͌ڋq���l����ɁA�Q���B��͐��i�̃I�t�B�X�����@���ȃG�l�����i��ł��邪�A�d�͏���ʂ̓I�t�B�X�S�̂���݂�Ƃ킸���B�d�͔̔��Ȃ�d�̓R�X�g���̂��팸�ł��A�ڋq�ɑ傫�ȍv�����ł���B�ȃG�l�@��̏Љ�����l�̔��f�Ŏ��{�B ���Ђ͑��z�����d���Ǝ҂���A�^�p�E�ێ�����������Ă���B�����@�̉ғ������u����Ď�����V�X�e�������p���A���z�����d��100�������u�Ď����Ă���B�ُ픭�����ɂ́A�����@�̕ێ�����}�s����B�S���ɒ��菄�点�������@�̃T�[�r�X�Ԃ���������Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���Ẵs�[�N���v�ɑ��鋟���̗͂\�����́A�S�����ς�8���ȏ���m�ۂ̌��ʂ� �]���́A�\������3���ŗ\�����Ă������d�͂��O�N��������ɂƂǂ߁A���ԂɌ�����6����̗\���̌��ʂ��B�ߓd���ʂɉ����ĐV�d�͂֗��E����e�����傫���B ���̂ق��̓d�͉�Ђł́A�k�C���E�k���E�����E��B��4�n��ł́A�\������10��������B���������9�n��̕��ςł�8���ȏ�̗\�������m�ۂł���B 2016�N�̉Ă���V�d�͂֗��E����e�����܂߂����ƂŁA�d�͉�Ђ̎��v���啝�Ɍ������B ���E�����ł������͓̂����d�͂ŁA���v��12�����������錩�ʂ��B�����Ŋ��d�͂������A���v��14���ɑ�������K�͂ɂȂ��Ă���B����ɖk�C���ł����v��10�����V�d�͂ֈڍs����z�肾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�ϐ�����CO2�r�o�ʂ̃f�J�b�v�����O�i��A���j���m�F���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j OECD��������2014�N�̑��G�l���M�[���Y��4���������ߋ��ō����������A�G�l���M�[����ɂ��CO2�r�o�ʂ�1.4�����������B���E�S�̂ɂ��Ă��A2014�N��40�N�Ԃŏ��߂āA�o�ς����������̂ɂ��ւ�炸�G�l���M�[�֘A��CO2�r�o�ʂ������������ƕ��Ă���B����OECD�������Ńf�J�b�v�����O�������ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B �f�J�b�v�����O�̎�ȗv���́A�G�l���M�[�����̌���ƍ��߂̋C���ɂ����OECD�������̌o�ς̃G�l���M�[���x���ቺ�����_�ƁA���͈ȊO�̍Đ��\�G�l���M�[���S�G�l���M�[�ɐ�߂�䗦��9.7�������������ƂȂǂɂ��A�d�͂�kWh������̔r�o�ʂ��ጸ�������Ƃ�����Ƃ��Ă���B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| ��NEC�Ȃǂ��]�����10�{�ȏ�̔M�d�ϊ��f�o�C�X���J�� NEC�Ɠ��k��w�͔M�d�ϊ��������]�����10�{�ȏ�Ɍ��サ���X�s���[�[�x�b�N�M�d�ϊ��f�o�C�X���J�������B �u�X�s���[�[�x�b�N���ʁv���g���Ĕ��d����d�g�݂��B�X�s���[�[�x�b�N���ʂ́A�������ޗ��ɉ��x����t���邱�ƂŁA���C�̗���Ƃ��Ắu�X�s�����v���N���镨�����ہB2008�N�ɓ��k��w�����������B ����ɁA�d�ɍޗ��Ƃ��Ĕ����ɑ���R�o���g�������J�����A�啝�ȃR�X�g�̒ጸ�ɐ��������B�����p�M�G�l���M�[�̊��p�Ɍ����āA�M�ϊ��ޗ��̌����J�����i��ł��锭�d�f�q�Ƃ��Ă̎��p���Ɍ����đ傫���O�i�����B ����A�M���ʂɔr�o����v�����g��f�[�^�Z���^�[�Ȃǂ̌����A�����ԂȂǂ̔p�M���甭�d���s���M���d�f�o�C�X�̎��p���Ɍ����A����Ȃ錤���J���𑱂��Ă����v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ϑ��q���u���Ԃ��v��C����CO2�Z�x��400ppm�������Ƃ��m�F ���E�C�ۋ@�ցiWMO�j�Ȃǂ������̋C�ۋ@�ւɂ��n��ϑ��_�Ɋ�Â��n���S�̂̌����ϒl�ł́ACO2�Z�x�͂��ł�400ppm���Ă����B �n�\�ʂ����C��[�i����70km�j�܂ł̑�C����CO2�̑��ʂ��ϑ��ł��鉷�����ʃK�X�ϑ��Z�p�q���u���Ԃ��v���ϑ������A�n���̑�C�S�́i�S��C�j�̌���CO2���ϔZ�x�ɂ��āA2016�N1���܂ł̎b��I�ȉ�͂��s�����Ƃ���A400.2ppm���L�^�������Ƃ��킩�����B�S��C�̌����ϔZ�x��400ppm�����̂͂��ꂪ���߂Ă��B����ɂ��A�n�\�ʂ����łȂ��n���̑�C�S�̂ʼn������ʃK�X�̔Z�x���㏸�������Ă���Ƃ����� �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���n�������̉����Ɍ����AG7����b��ŋ������� �C��ϓ����͂��߂Ƃ����n�������̉����Ɍ����A�V���Șg�g�̎��{�Ɍ����āA�n�C���x���̌��E������i�߂邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B�ɐ��u���T�~�b�g�Ɍ����āA��N�̑����ꂽ�u�����\�ȊJ���̂��߂�2030�A�W�F���_�v��u�p������v�̎��{�Ɍ�������g�݂����߂���ŏ��̔N�ł��邱�Ƃ܂��A �i1�j�����\�ȊJ���̂��߂�2030�A�W�F���_ �i2�j�����������E3R �i3�j�������l�� �i4�j�C��ϓ�����ъ֘A�{�� �i5�j���w�����Ǘ� �i6�j�s�s�̖��� �i7�j�C�m���� ��7�̋c���ݒ�E�c�_���A���ʂ��R�~���j�P�i���������j�Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEDO 2030�N��ڕW�ɍq�������g��̎����Ɍ����V�^�~�d�r�̊J�����v�� �����Ԃɓ��ڂł��郊�`�E���C�I���d�r�iLIB�j�̃G�l���M�[���x�̌��E��300W h/kg�O��ł��邱�Ƃ��������Ă����BEV�ŃK�\�����ԕ��̐��\����������ɂ́ALIB�̌��E���\����V�^�~�d�r�̊J�����K�v�ɂȂ�B NEDO��2030�N�ɃK�\�����ԕ��݂̑��s���\���������镁�y���i�ѓd�C�����Ԃ̎�����ڕW�ɁA2020�N�x���܂łɗe��5Ah���̐V�^�~�d�r�̎���ƌ����Y�w�A�g�ɂ��W�����������ōs���B �ڎw���̂́A���ݗ��p����Ă���ԍڗpLIB���\��5�{�ɑ�������500W h/kg�̃G�l���M�[���x���������~�d�r�̊J�����B�ԍڗp�����łȂ��A���܂��܂ȎY�Ƃō����\�Ȓ~�d�r�̃j�[�Y�����܂��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��NEDO �C���h�ō����\�H�ƘF���؎��Ƃ����{CO2�N��6��g���팸������ NEDO�̓C���h�̓S�|�ȁE�����ȁA����э��c���S���STEEL�Ƌ����ŁA���{�ŊJ�������ȃG�l���ʂ������A�����������̏��Ȃ������\�H�ƘF�̃��[�W�F�l�o�[�i�[�Z�p���C���h�̐��S���ɓ������邱�Ƃɍ��ӂ����B ����2�N�ԂŎ��T�C�g�ł���STEEL�Ђ̃��E���P�����S���̊��݉��M�F�����[�W�F�l�o�[�i�[�ɉ��C���A�R�����P�ʂ̌��エ���CO2�r�o�ʍ팸��������B�N��100���g���̐��Y���s���ۂɁA�d�����Z�ŔN��210�����b�g���̃G�l���M�[�g�p�ʍ팸���ʂƁA�N��6000�g����CO2�r�o�ʂ̍팸��������ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���X�^�����[�d�C�����O27�H��̓d�͎g�p�ʂ��W���Ǘ��A�����鉻 ���Ђ͊������o�c�v�����ɉ������ʃK�X�팸�ڕW���f���A�H��⎖�����ȂǃO���[�v��Ђ��܂ލ����E�C�O�S���_�ŃG�l���M�[�팸������i�߂Ă���B �ڕW�B���Ɍ����āA���_�S���҂����ł͂Ȃ��A�S�Ј������P�����Ɏ��g�ނ��Ƃ�A�d�͏���̎��єc�����T�⌎�P�ʂł͂Ȃ��A���⎞�ԂłƂ炦�邱�Ƃő����ɑ��ł��Ƃ��ł���d�g�݂Â�����������Ă����B���ɍH��Ԃŏ�L���s���A���ʂ𑼍H��ɓW�J����B �x�m�ʂ��W���Ď��V�X�e�����\�z�����B����A�����R�X�g�ጸ��[������A������ጸ��i������Ȃǂ̐��Y�����S�ʂ̉��P�ɂȂ�����g�݂��x�����Ă������j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�́A�K�X�̏����莩�R���ɑΉ��A�����K�X�Ɗ��d�͐헪�I�A�g�� ���Ђ́ALNG���B�┭�d���^�c�E�ێ�ȂǗl�X�ȕ���ŁA�o���̋��݂����������헪�I�A�g�Ɍ����Č�����i�߂Ă����Ɣ��\�����B ���̑����Ƃ��āA�u���݂�LNG�������E�Z�ʂ���v�g�g�݂ɍ��ӂ����B�����O�̃G�l���M�[�s�����芪����E�������������A������s���̕ω��ɏ_��ɑΉ����Ȃ���A����������͂̂���LNG�̈��蒲�B���s���Ă����B�܂��A�uLNG�Η͂̉^�]�E�ێ�ɂ�����l�ވ琬�̃m�E�n�E�̋��L�v�ȂǁA�^�c�ۑ�̉����Ɍ������Z�p�A�g���s���A���ꂼ��̈��S���A�����������߂Ă������Ƃɍ��ӂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���m�[���c�������u�n�C�u���b�h�����E�g�[�V�X�e���v���J���ACO2�r�o��51���팸 ���Ђ́A�K�X�Ɠd�C��g�ݍ��킹���Z��p�u�n�C�u���b�h�����E�g�[�V�X�e���v�\�����B�K�X������u�G�R�W���[�Y�v�ƁA�q�[�g�|���v���j�b�g��g�ݍ��킹�A�����G�l���M�[�����ł���������B �����ꎟ�G�l���M�[������143�������������B��Ԍ����̗ǂ����ɒ�������u�X�}�[�g����@�\�v�̉��ǁA�G�߂ɉ������q�[�g�|���v�o�͂̎�������A�����͂�G�l���M�[��12���팸�ł���ӂ�M����@�\�Ȃǂ��J�������B���ʁA�]�����苋�����M���66���A�N�Ԗ�6��9000�~�̍팸�����������B���ւ̉e�����ɂ߂ď��Ȃ����R��}�uR290�v���̗p�B�s�ꂪ�g��X���ɂ���uZEH�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j�v�s�ꂪ�_�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���N���E�h�Ή��u�X�}�[�gIoT�T�[�r�X�v�ŁA���푽�l�ȃf�[�^�̎��W�E�����p���\�� �������ʐM�G���W�j�A�����O�͑��ʂ̃f�[�^��v���ɓ����E���́E�������Ē�R�X�g�E�ȃG�l����������u�X�}�[�gIoT�T�[�r�X�v�̒��J�n����B ����܂ł̃��A���^�C���f�[�^���W�Ƃ��̌����鉻�ɉ����A�d�́A���x�ACO2�Z�x�Ȃǂ̊��f�[�^���͂��߁A�Y�Ɨp�@��̉ғ��f�[�^�AEMS��Y�Ɨp�ݔ��̗\�h�ۑS�ɕK�v�ȃf�[�^���W�ƊĎ����\���B����ɂ��A�ݔ���~�̉���ƕێ�R�X�g�̒ጸ���\�ƂȂ�B ���̃T�[�r�X�̓N���E�h�T�[�r�X�̂��߁A�����C���t���ݔ��E�@��E�Z���T�[�ނ��p�����Ďg�p�ł��A�����ɓ����ł���B�i�K�I�ȃV�X�e���g�����ł��邽�߁A�����K�͂����K�͂܂ŕ��L���Ή����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����[����LED���S�̏Ɩ����Ƃ��A�C���X�I�[���}������ �A�C���X�I�[���}�́A���[���̂k�d�c�Ɩ����̎q��ЃA�O���b�h���擾����B�����z��50���~�O��Ƃ݂���B���[���̏Ɩ����Ƃ͔����_�C�I�[�h�iLED�j�����S�ŁA�N�Ԕ��㍂��57���~�B��1300�i�ڂ̐��i�������Ă���B �A�C���X�I�|���}��2009�N��LED�Ɩ����ƂɎQ���B2015�N�x�̔��㍂��245���~�ŁA���[���̐��i��̘H�������邱�ƂŁA2016�N�x��400���~�ւ̊g���ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���V���[�vHEMS�A�N���E�h�~�d�r�A�~�d�r�Ɠd�Ȃǂ�ZEH�\�z��ڎw�� �V���ɃR���p�N�g�Őݒu���ȒP�ȃN���E�h�~�d�r�̐V���i�𓊓������B�d�C�̎g�p��V��ɉ����čœK�ȃG�l���M�[�}�l�W�����g���ł���N���E�h�~�d�r�V�X�e���ŁA�R���p�N�g��4.2kW h�^�C�v�ƁA��e�ʂ�8.4kW h�^�C�v��2�@���������������B ���Ђ́uZEH�i�l�b�g�[���G�l���M�[�n�E�X�j�v�����Ɍ����A�P�i�����ł͂Ȃ��\�����[�V�����Ƃ��Ă̒�Ă֓]����i�߂�B���z�����d�A�N���E�h�~�d�r�A�N���E�hHEMS�A�G�R�L���[�g�A����ɂ͒~�d�r�A�g�Ɠd�܂Ŋ܂߂��z�[���G�l���M�[�\�����[�V������i����B ����A��d���ł��^�]�ł���u��펞�Ή��①�Ɂv����������ȂǃG�l���M�[�����������g�����Ƃ�ڎw�����u�~�d�r�A�g�Ɠd�v�̃��C���A�b�v���������Ă������j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Z�F�����u���W���ŃT�g�E�L�r�y���b�g�Y�A���E�s��ɔ̔� ���Ђ��o������R�U���o�C�I�}�X�͐����ߒ��Ŕp������T�g�E�L�r�̍�肩���▢���p�̌s�A�t�Ȃǂ�Ǝ��̋Z�p�ŔR���ɂ���B�]���͖�Ă��ɂ��Ă������������p����B�o�C�I�}�X�R���Ƃ��Ă͈�ʓI�ɖ؎��y���b�g��`�b�v�����y���钆�ŁA�J�������R���́A�؎��y���b�g�����̊����ݔ��Ŏg�����Ƃ��ł���̂��������B �T�g�E�L�r�ō�����y���b�g�̐��Y�\�͂�17��5000�g�����B�H����������₵��2025�N�ɐ��Y�\�͂�200���g���܂ō��߁A500���~�K�͂̔��㍂��ڎw���B ���̂����̖�5���͉��B�ł̔̔���������ł���A�c���2���͓��{�A3���̓u���W�������ƂȂ�v�悾�B���{�֗A�����ăT�g�E�L�r�R�����g�p���Ă�CO2�̔r�o�ʂ͐ΒY�̖�6����1���Ƃ����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���V�R�X���X�d�@���a�@����{�݁A�z�e���Ȃǂł̏L�C�g�U�h�~�V�X�e���J�� �V�R�X���X�d�@�Ɛ������݂������ŊJ�������L�C�g�U�h�~�V�X�e���́A�����̃Z���T�[���䃆�j�b�g�Ƌ��r�C�t�@���Ȃǂō\������B �����̃Z���T�[�͏L�C���q�̎_���Ҍ������𗘗p���Ċ��m����B�L�C���q���܂ރK�X�́A�����̃Z���T�[�\�ʂ̎_���C�I���ɐڂ���ƁA�����̕\�ʂ̓d�C��R�l���ቺ���ēd�C�������B ���䃆�j�b�g���A����V�X�e���ɐM���𑗐M�B�e�a���̓V����ɒu�������r�C�t�@���������ɉғ����āA�L�C�������ɍL����O�Ɋ��C����B���C�\�͂́A10�����x�Ől�Ԃ��C�ɂȂ�Ȃ��L�C�Z�x�ɒቺ����B�a�@����{�݁A�z�e���Ȃǂł̗��p�������ށB�V�z�̌�����1���������50���~�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�͉�Ђ̗v���ɉ����Đߓd���A�Ή���u�l�K���b�g����v2017�N4�����J�n�\�� �o�Y�Ȃ���A�u�l�K���b�g����v�̎��������ꂽ�B�����d�C���Ɩ@�Ɋ�Â��l�K���b�g����ɂ��ẮA2017�N4��1������J�n����\�肾�B�l�K���b�g����́A�f�}���h���X�|���X�i���v�����j�̈��ŁA���Ǝ҂���̗v���ɉ����Ď��v�Ƃ����v��}�����A���̗}���ʂɉ������Ή������Ǝ҂��x�����B �����d�C���Ǝғ��Ǝ��v�ƂƂ̊Ԃɐ��̑�O�ҁi�l�K���b�g���Ǝҁj����݂��邱�Ƃɂ��A�ƒ���܂߂����l�Ȏ��v�Ƃ�ΏۂƂ��āA���L�������d�C���Ǝ҂�����ł���B����������������L���s����悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A����̋�̓I���e��ӔC���S���ɂ��āA���[���������s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������̂̃G�l���M�[�n�Y�n���̐��̊m���Ɍ����Ċ֘A4�Ȓ����A�g 2015�N8���A�����Ȃ𒆐S�Ɏ����G�l���M�[���A�і쒡�A���Ȃ�4�Ȓ����u�n�敪�U�^�G�l���M�[�C���t���v���W�F�N�g�v���Ɖ����i�Ɍ����ĘA�g�����B ���̃v���W�F�N�g�́A�e�����̂�"�G�l���M�[�̒n�Y�n��"�����邱�ƂŁA����G�l���M�[�����̐����m������Ƌ��ɁA�ٗp�n�o��A�n��o�ς̍D�z������o���ړI������B�������A�G�l���M�[�C���t���̐����Ԏ��Ǝ҂������Ȃ��ɂ́A���z�̃R�X�g�Ǝ�������܂ő����̎��Ԃ�v����ȂǕ��S���傫���B ���̂��߁A�e�Ȓ����A�g���A���������̕������x�����邱�ƂŎ��Ɖ��𑁂߂����Ƃ��Ă���B �����Ȃł́A�e�����̂Ɂu�n��̓��������������G�l���M�[���Ɠ����v��v�̍쐬���x�����A�G�l���M�[����̔������߂�M���v�̏W��i�߂Ă���B �o�T�uHOME�eS PRESS�v |
|
|
| �����Ȕ��\2014�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂ�2013�N�x��3.1�����i�m��l�j ���Ȃ́A2014�N�x�̍����̉������ʃK�X�r�o�ʁi�m��l�j��13�N�x��3.1������13��6400���g���Ɣ��\�����B�������ʃK�X�̔r�o�ʂ��O�N�x����������̂́A���[�}���E�V���b�N�ɂ��i�C���ނ̉e������2009�N�x�ȗ��B �����̉������ʃK�X�́A��������~���A�Η͔��d�Ȃǂ����������Ƃ̉e���ő��������Ă����B���������͍̂Đ��\�G�l���M�[�̗��p�g��A�ȃG�l�ɂ��d�͏���ʂ̌����Ȃǂ����R�Ƃ����B 2014�N�x�̔r�o�ʂ́A05�N�x��ł�2.4�����B�X�ыz���ʂ�5790���g���������6.5�����ƂȂ�A20�N�x�܂ł�3.8���ȏ�팸�Ƃ������{�ڕW��O�|���ŒB�������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �������G�l��2014�N�x�̃G�l���M�[�������т����܂Ƃ߂�(�m��) 2014�N�x�̃G�l���M�[����́A�O�N�x��3.2���������A4�N�A���Ō��������B����ʂɌ���ƁA��ƁE���Ə������傪��3.0�����A�ƒ땔���3.8�����A�^�A���傪��3.4�����������B �ꎟ�G�l���M�[�̍��������́A�Ζ���1.3�����ƂȂ����A�V�R�K�X��1.0�����A�Đ��\�G�l���M�[(���͊܂�)��0.5���������A�S�̂őO�N�x��4.5�����ƂȂ����B ��_���Y�f�r�o�ʂ́A�O�N�x��3.7�����ƂȂ����B�ȃG�l�i�W���ɂ��5�N�U��ɔr�o�ʌ��������B���q�͔��d���̒�~���ɂ��A4�N�A���ő������Ă������A�G�l���M�[���̓]����Η͔��d�̍��������A�ȃG�l�̐i�W���ɂ��A�ߋ��ő��ł������O�N�x��茸�������B �u2014�N�x�����G�l���M�[���v�m��T�v�v http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/stte_019.pdf �o�T�u�����G�l���M�[���v |
|
|
| ���V�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj799�Ђ̂��������d�C���Ɠo�^��2����172�� 4��1������̓d�͏�����̑S�ʎ��R���ɍۂ��āA���s�̓���K�͓d�C���Ǝ҂��珬���d�C���Ǝ҂ւƐ��x�̘g�g�݂��ύX����A�d�͋����ʂ̊m�ۂȂǂ����Ȃ���Γo�^���ł��Ȃ��Ȃ����B �����G�l���M�[����3��28�����_�œo�^����Ă����V�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj799�Ђ̂����A��8���͏����d�C���Ǝ҂Ƃ��Ė��o�^�ŁA����̓d�͎��Ƃɂ��Ă͗l�q�����P�ނ̉\��������Ǝw�E����Ă���B ���łɁA�V�d�͂̂����@�I�����⎖�ƒ�~���m�F�ł����̂́A���{���W�e�b�N�����g���A�C�[�G���V�[�AGlobal Energy Japan�̂R�Ђł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��CO2�r�o�g���i�t���h�������{�i���|�u2050�N��80���팸�v������ ��_���Y�f�iCO2�j�̔r�o�ɉ��i��t���A�r�o�ʒጸ��_�������@�̋c�_���{�i�����������B����@�́u�J�[�{���v���C�V���O�v�ƌĂсA�Y�f�ł�r�o�ʎ�����܂ށB �Y�ƊE�͔�K���̍��ɎY�Ƃ����o����u�Y�f���[�P�[�W�v�ɉ��^�I���������A�������S�y�ɂ킽��r�o������s��𗈔N�ɂ��J�݂��铮�����o�Ă��Ă���B���Ȃ�3�����A��Y�f���r�W�����̋c�_��R�c��ʼnĂ܂łɎn�߂�l�����������B�����ŃJ�[�{���v���C�V���O�ɂ��Ă���������B2���̗L���ҍ��k��̒ł́A�Ŏ����Љ�ۏ���v��@�l�Ō��łȂǂɏ[�Ă�u��^�Y�f�Łv�̓��������Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��G�l���M�[�����ŎY�����Ɂu�ȃG�l���x�v�Ȃǂ̗A�o���߂��� �����ł́A���E�̃G�l���M�[���v�͒�����C���h�A����A�W�A�����A���iASEAN�j�����łȂ��A�����Y�����ł��啝�ɑ�����Ɨ\�z�B�����Ȃǂ��ȃG�l���x�̍\�z��i�߂钆�A���g�݂��x��Ă��钆���Y�����̏ȃG�l�̏�G�l���M�[�����̓����ɉ����A�G�l���M�[�Ǘ��m���x�⎖�Ǝ҂̃G�l���M�[�Ǘ���Ȃǂ̐��x��̌n�I�ɗA�o���A�e���̒P�ʓ�����G�l���M�[�g�p�ʂ̉��P�ɂȂ���B�e���̏ȃG�l���i�W����A���ۓI�ȃG�l���M�[�����̊ɘa�ɂȂ���A���{�ɂƂ��Ă������b�g�͑����B �G�l���M�[����2015�N http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015pdf/ �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/5�@]�@�@�� |
|
|
| �����̉w�Ŗ؎��o�C�I�}�X���d�A�d�͂ƔM��n�Y�n�� �k�H�c�s�͖ʐς�83����X�т���߂Ă���B�ŋ߂ł́A�т̒��ɔ��̂�����̎c�ނ���ʂɕ��u���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���B�����ŁA�n��Ŕ������関���p�̎��������āA�d�͂ƔM��������������؎��o�C�I�}�X���d�̃v���W�F�N�g�������o�����B �����ɐݒu�ł���t�B�������h���̏��^���j�b�g8��̉w�ɐݒu���āA�؎��`�b�v��R�Ă����Đ�������K�X�Ŕ��d����B���d�\�͂�40kW�ŁA��������M����85���̉��������A100kW�����̔M�������ł���B �d�͂ƔM�����킹���G�l���M�[������78���ɒB����B �����^�]�̋@�\������Ă��āA���j�b�g�̑��ʂɂ���R���g���[���p�l���̂ق��ɁA�C���^�[�l�b�g�o�R�ʼn��u���瑀�삷�邱�Ƃ��\�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���A�[���c�[�\�����[�V�����Б��z�����d�p�l���̃����[�X�E���T�C�N���T�[�r�X���J�n ���Ђ́A�s����G���W�j�A�����O�A�l�N�X�g�G�i�W�[�E�A���h�E���\�[�X�A�ߋE�H�ƁA���T�C�N���e�b�N�E�W���p����4�Ђ������o�����A�ݗ�����������ЁB ���Ђ́A�p�����z�����d�p�l���̃����[�X�E���T�C�N�����ꊇ�ōs���ق��A�����Ƃɂ����郊���[�X�������@�̊m���A���T�C�N����p�@��̊J���A���W�^���V�X�e���̌����A���ڋq�̊J��A�����ƂɊւ���T�[�r�X�̎��Ɖ��̌����Ȃǂ��s���Ă����B �_��������ƁA�����[�X�������̂́A�O�ς�@�\�Ȃǂׂ�≏��R�����EL�����AI-V�o�͑���ȂNJe�팟�����s���A�����N�������ꂽ��Ń����[�X�i�Ƃ��Ĕ̔������B����A���T�C�N�������p�l���͈��k������A�I�ʂ���A�K���X�E�A���~�ȂǂɎ����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�O�̓��n��Ƃ̉^�p���P�ȃG�l�x�����Ƃ�W�J���@�����d�� �o�ϐ����������^�C�ł͑������H��i�o�Ȃǂœd�C�̎������N�����A�d�C�����͂���15�N�Ԃ�1.5�{�ɂ��������B�d�C��������ƌo�c�ɗ^����e���͐[�����B ���Ђ́A���n��Ƃ���̗v���ɉ����A2014�N�ɋZ�p�҂����n�Œ������J�n�����B�R���v���b�T�[��|���v�A�Ȃǂ̏��m�F���A��30�J���Ɍv��������t�����B���N�A�u������LED�ւ̐�ւ���R���v���b�T�[�̋�C�R��̕�C�ȂǂōH��̃G�l���M�[����ʂ�1���팸�ł�������쐬�����B ���Ђ́A�|���Ă����m�E�n�E�����A�ݔ��̉^�p���P���Ă���u�C�O�ȃG�l�T�|�[�g�T�[�r�X�v�Ōڋq�J��ɖ{�������Ă���B �����ł̓G�l���M�[���R���g��Ōڋq���D�킪��������Ȃ��A�����s��̊C�O�ɏ��@�����߁A�ڋq�Ƃ̊W������}��_��������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����݃r���̏ȃG�l��������������A�O���[�����[�X�E�K�C�h���\ ���݃I�t�B�X�r���̏����������S���������ɓ������A���y��ʏȂ����\�����u�O���[�����[�X�E�K�C�h�v�Ɍf�ڂ���Ă���B KDX�H�t���r���i1973�N�v�H�A�����ʐ�2979m2�j�ł́A�Ɩ��ݔ����u��������LED�ɕύX���A���̌o�ϓI�����b�g���������O���[�����[�X�_����A�r���I�[�i�[�ƃe�i���g�Ƃ̊ԂŒ��������B���g�݂́ALED���ɂ��d�C�����̒ጸ���ʂƌu����������p�̍팸���ʂ�����A������O���[�����[�X���Ƃ��ăI�[�i�[�����A����������e�i���g��������e���B �z��ʂ�A�d�C���56���ጸ���A�e�i���g�̔�p���S��3�����炷���ʂ��グ���B�H����p�͖�7.5�N�ʼn���ł��錩�ʂ��B �O���[�����[�X�E�K�C�hhttp://tochi.mlit.go.jp/kankyo/greenlease/index.html �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}LED�Ɩ��̉���E���T�C�N���̐����\�z ��Ƃ⊯���ł͌u��������LED�Ɩ��ւ̐�ւ���A���^���獂�������i�ւ̍X�V���}���ɐi��ł���B����ōĎ������͒x��Ă���A�ۑ�ƂȂ��Ă���B ���Ђ́A�Ɠd���T�C�N���Ȃǂ���|����n���^�����A�@����w�Ƌ��͂��ALED�Ɩ�������A���T�C�N������d�g�݂��m�������B�A���~�j�E���⓺�A���Ȃǂ��ׂ����I�ʂ��A�Đ������Ƃ���B ��̓I�ȗ���́A�E���Ђ�LED�̐V���i����ƂȂǂ֔[������ۂɊ����i�̈��������Ă��A�������LED�Ɩ����n���^�����ɑ���B�E�n���^�����ɂđf�ޕʂɕ����B�A���~�j�E����I�ʁB�핢���A����̓��ALED�f�q���̋M�����B�����ɑI�ʁB�E�@����w���pLED�f�q����_���K���E�����E�������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��PPS�̃V�F�A��12.1����4�J���A���őO����������d�� �ߋE�o�ώY�Ƌǂ�1�����̓d�͎��v����ł́A�������Ҍ����̓���K�͓d�C���ƎҁiPPS�j�̔̔��d�͗ʂ̊�����12.1���ŁA4�J���A���őO��������A�ō��L�^���X�V�����BPPS�̔̔��d�͗ʂ́A8��4,600kWh�őΑO�N������64.3�����ƂȂ����B�d�͂̍w��������d�͂���PPS�ɐ�ւ��鎖�Ǝ҂������Ă���B 1���̑����v�d�͗ʂ́A137��2,500��kWh�ŁA�ΑO�N������7.8�����ƂȂ�A5�J���A���őO�N���т���������B����d�͎��v�ɂ��ẮA44��3,000��kWh�ŁA�ΑO�N������3.9�����ƂȂ����B2015�N9���ȍ~�A�d�͎��v��5�����A���őO�N����������B�����ƌv�ł́A�ΑO�N������3.9�����ƂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���L�c����200lm/W�̍������Ɩ��pLED���J�� ���Ђ́A�FLED�`�b�v�ƌu���̂�g�ݍ��킹���\���ŁA���LED�`�b�v�ƃp�b�P�[�W�ޗ��̉��ǂɂ���āA200lm/W�����������������Ɩ��pLED�p�b�P�[�W���J�������B�����́A�u���^�v�u�������v�ɉ����A�M�d���������ޗ����̗p���邱�ƂŁA�ϔM���ƑσK�X���ɗD���u���M�����v���������Ă���B 3������T���v���o�ׂ��J�n����B�܂��R�X�g�Ή��͂ɗD�ꂽ185lm/W�̐��i�������ɊJ�n����B����́A�{�N�H�����ړr�ɁA�X�ɍ��������������i���J������\�肾�B������3.9�����ƂȂ����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���u�[���E�G�~�b�V�����V�X�e���v�ɂ�邲�ݎ��W�̎��؎������J�n�p�������d�����p ���s��JFE�G���W�j�A�����O�́A���ݏċp���d�{�݂Ŕ��d����d�͂����p���A�d�r�����^EV���ݎ��W�Ԃ�p�����u�[���E�G�~�b�V�����V�X�e���v�ɂ�邲�ݎ��W�̎��؎�������s���������Z���^�[�ŊJ�n�����B����̎��؎����̓����́A 1�j�p�������d�����p�����G�l���M�[�z�^�̒n�����ɂ₳�����V�X�e���F���s����CO2�r�o�ʁE�r�o�K�X���[���A�I�[���d�����ɂ��É��ȉ^�s 2�j�d�r�X�e�[�V�����̓����F�d�r�������ł��[�d�A�����d�r�̔��~�A�X�s�[�f�B�Ɍ��� 3�j�ЊQ���̔��p�d���F�d�r�����^EV���ݎ��W�Ԃ̓d�r���A�ЊQ�_�Ȃǂ̔��p�d���Ƃ��Ċ��p �Ȃǂł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ǖʐݒu�^�̒ᔽ�ˊ��z���^���z�����d�V�X�e�����J�����؎������J�n NEDO�ƃJ�l�J�́A���z�d�r���W���[���\�ʂ̉��ʍ\���ɂ���Č����U�����A�����˂�ጸ������ƂƂ��ɁA���z�d�r���W���[���̓����Ɍ�������߂�Z�p��p���Ĕ��d���������߂��ᔽ�˃��W���[�����J���B���W���[���̕\�ʍ\���̍œK���Ȃǂ̕]����i�߂Ă����B ����A���҂́A�hΉ@�\��L���A�ӏ��������߂��ǖʐݒu�^�̒ᔽ�ˊ��z���^���z�����d�V�X�e���̔��d���������m�F������؎������J�n�����B ���؎����ł́A�F�̎��R�x�����߂����ʂȒᔽ�˃��W���[���̌�������߂�Z�p�ɂ��A�N�ԓ��˂̂قƂ�ǂ��Γ��˂ƂȂ錚���ǖʐݒu�̑��z�����d�V�X�e���ŁA�N�Ԕ��d�ʂ̌����������v��B NEDO�ł́A���،��ʂ����ƂɁA����A�ǖʐݒu�^���z�����d�̕��y�Ɍ����Č�����i�߂Ă����\��B �o�T�uMONOist�v |
|
|
| �����N�x���z�����d�͔�Z��p��3�~����24�~�A�Z��p��2�~����31�`33�~�A���͂͐��u �Œ艿�i���搧�x��2016�N�x�̉��i�Ă����܂����B��Z��p�͔��d�V�X�e���̔�p���]��������������őz�肵���B���͔��d�Ȃǂ͔��承�i�𐘂��u�����A2017�N�x�ɂ͉��i����������ς��B ���{�́u���B���i���Z��ψ���v��2016�N�x�̔���i���B�j���i�̍ŏI�Ă��Ƃ�܂Ƃ߂��B�]���Ɠ��l�ɃR�X�g�팸���i�ޑ��z�����d�̔��承�i������������������e���B���̍ŏI�Ă��o�ώY�Ƒ�b���̗p���Đ����Ɍ��肷��B ��Z��p�̑��z�����d��27�~����24�~�ɉ�����A����ʼnƒ�p�̓d�C�����̕��ϒP���Ɠ��������ɂȂ�A����͉Η͔��d�̕��σR�X�g�i��11�~�j�ɋ߂Â��Ă����B ���́E�������́E�n�M�E�o�C�I�}�X���d�̔��承�i�́A�Z��w�W�̎��{��i�V�X�e����p�Ȃnj��݂ɂ�����R�X�g�j��^�]�ێ���A�ݔ����p���ɂ͕ω��������邪�A�]���̂܂ܐ����u���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����y��ʏȁA���z���̏ȃG�l���\��\�����郉�x�����O���x��n�� ���Ȃ́A2016�N4������i�K�I�Ɏ{�s���錚�z���ȃG�l�@�ɂ��A�Z���I�t�B�X�Ȃǂ�̔��E���݂��鎖�Ǝ҂ɂ͏ȃG�l���\��\������w�͋`�����ۂ����B �n�݂���鐧�x�́u�F�v�Ɓu�ȃG�l��K���F��}�[�N�v�B���z���{�̂�L�����A�_�ނȂǂɓ\�t���������ĕ\������B�F�ł́u��l�Ɣ�ׂĐv�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��ǂꂭ�炢�팸�������v��\���B ���t�Ŏ����Ƌ��ɁA�o�[�`���[�g�Ȃǂ�p���Đ}�����邱�ƂƂ���B�ȃG�l���\�̕]���ɓ������Ă͔F�ؐ��x�uBELS�v�𗘗p����ق��A�v�҂Ȃǂ����ȕ]�����邱�Ƃ��\�B�K���F��}�[�N�́A�����̌��z�����ȃG�l��ɓK�����Ă��邱�Ƃ��������x�B���L�҂��\��������s�����̔F�����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����{�������ʃK�X�A2030�N��2013�N�x��26%�팸�ڕW�Ɍ����A�u�n�����g����v��v�܂Ƃ� �G�l���M�[�����ɗD�ꂽ�f�ނ┼���̂Ȃǂ̊J���ŁA�K�X�r�o�������X���ɂ���I�t�B�X���ʉƒ�łS���팸��ڎw���B �v��ł́A��Ƃ�a�@�Ȃǂ̋Ɩ����傪39.7���A�P�g���т̑����Ŕr�o�ʂ������Ă���ƒ땔�傪39.4���A�d�́E�K�X��ЂȂǂ̃G�l���M�[���傪27.5���A�^�A�����27.4���Ƃ����B����ŁA�Y�ƕ���́A�ȃG�l�����ɐi��ł��邱�Ƃ⍡��̌o�ϐ�����������ŁA6.5�����ɂƂǂ߂��B ���̂ق��A�v��ł�2050�N�܂ł�80�����̒����ڕW���f�����B�ڕW�����ɂ́A�u�v�V�I�Z�p�̊J���E���y���ő���ɒNj�����v�Ɩ��L�B��̓I�ɂ́A������~�d�r�A�����㔼���̂Ȃǂ̊J��������������B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���ƒ�̏ȃG�l�V�w�j�o�Y�ȁA�d�͎��R���� ���Ȃ́A������d�C���Ǝ҂��ƒ�̏ȃG�l���x������d�g�݂�����B2030�N�ɉ��g���K�X�̔r�o�ʂ�13�N��26���팸����ڕW���f���A�ȃG�l�̐[�@��ŒB����ڎw���B ���t�ɂ��A�������Ǝ҂ɑ��ƒ�̏ȃG�l�Ɋւ�����𑣂��w�j��16�N�x���ɂ���B�V���Ȏw�j�ő��̉ƒ�Ɠd�C�g�p�ʂ��ׂ���d�C���g�������Ă��邱�ƂȂǂ�`����T�[�r�X�����߂�l�����B�܂��A���z�����d�ȂǂŃG�l���M�[���܂��Ȃ����M��������[���ɂ���Z��̕��y���㉟������B��Ƃ̏ȃG�l�������i�t������d�g�݂��������A�w�͕s���̊�Ƃɂ͒��ӕ�����z�z����Ȃǂ��ďȃG�l�̎��g�݂𑣂��B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ����P��G�R�`���[�j���O�Z�p�Ҏ��i�F��̕�W�J�n����A�����2��� ���Ȃł́A��Y�f�Љ�̎����Ɍ����āA�Ɩ��p�����z���́u�G�R�`���[�j���O�v�i�������ʃK�X���팸���邽�߁A�ݔ��@��E�V�X�e���̓K�ȉ^�p���P�����s���j�ɂ��팸���ꂽ���M�������v���グ��r�W�l�X���f���̊m����ڎw���Ă���A�Z�p�Ҏ��i�F�萧�x�E���ƎҔF�萧�x�̑n�݂̏��������s���Ă����B �u����G�R�`���[�j���O�Z�p�ҁv�Ɓu����G�R�`���[�j���O�Z�p�ҁv�̂Q��ނ̎��i������A�u����v�̓G�R�`���[�j���O�̌v�旧�āE�w�������ł��鎑�i�A�u����v�͌���ʼn^�p���P�̎��{�����ł��鎑�i�ƂȂ�B���̓x�A��P��G�R�`���[�j���O�Z�p�Ҏ��i�F��̕�W���J�n�����B ���i�̐\�����@�E�u�K��̓����E��u�����̏ڍׂɂ��ẮA�u�G�R�`���[�j���O���i�Z���^�[�v�̃z�[���y�[�W���Q�ƁBhttp://www.j-bma.or.jp/eco-tuning/ �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���@�@[�@2016/4�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�X���s�s�K�X��ЁALP�K�X��Ђƒ�g���A�d�͔̔��̐����\�z �����K�X����g�����̂́A�s�s�K�X���Ǝ�10�Ђ�LG�K�X�̔����Ǝ�27�ЂŁA���v�ƌ����͖�49.5�����ɂȂ�B �ȑO�ɒ�g�����K�X���Ǝ�5�Ђ̑����v�ƌ����͖�36.4�����ƁA���v����Ɩ�85.9�����ɂȂ�B�������A�����d�͂̌_������͖�3�疜���A�����K�X���̂̌_��1�疜���Ɣ�r����ƁA�J�o�[�G���A�ƌڋq���ł́A�����d�͂Ƃ͂܂��܂��傫�ȊJ��������A����ɓd�͔̔��̐��̋������K�v�ł���B �����K�X�́A2015�N12���ɂ͑��Ђɐ�삯�ė����v�����\�B���̌�A�������Ђ̗����v�����ɑR���邽�߁A2016�N2���ɂ͑������l���������\����ȂǁA�ϋɓI�ȓ����������Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���V�����̑�C�����[�����Ċ��C���u�����_�C�L���H�� ���Ђ́A�Ċ��C���u�ő��̃t�����_�[�X���500���~�Ŕ�������B�t�������_�[�X�́A�N�Ԕ��㍂�͖�360���~�B����x�����߂鍂���\�i�ӂƂ��A�Z��������A�H�i�Ȃǂ̍H������ɋ��݂����B ���Ђ́A����A��C�����̐[�����ɔ����A��C���̂ق���Ȃǂ��������銷�C���u�́A�V�����ł����v�̊g�傪�����܂�A�V���Ȑ������ƂƂ��Ĉ�Ă�v�悾�B �t�����_�[�X�����Ń_�C�L���̓����Ƃ̔��㍂�͖�1300���~�ƂȂ�A�X�E�F�[�f�����J���t�B���i��750���~�j�����������Đ��E�g�b�v�̍����m���ɂȂ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���K�y���@�V�d�͂���̓d�͒��B�ƁALED�Ɩ��̓����ŔN��1.8���~�팸�ڕW ���Ђ̓��[�����`�F�[���Ŗ����C��333�X��(������d�_��X��)��3�H��œd�̓R�X�g�̒ጸ�Ɗ��ւ̕��גጸ��ړI�ɁA�V�d�͂���̓d�͒��B��LED�Ɩ�������B �d�͍w���ɂ��ẮA�����_����e�̌��������s���A�V�d�͂̃G�l�b�g�ƈɓ����G�l�N�X�ɐ�ւ��Ă����v������Ă���B�N��60�S���~���x�̓d�̓R�X�g�ጸ��������ł���B LED�Ɩ��̓����ɂ��ẮA�X���̏Ɩ��̑��A�ŔA�O���A�~�[�̏Ɩ���LED�Ɩ���������v��ŁA120�S���~���x�̓d�C�����̍팸��������ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�l�`�F���W�@�p����Ƃ̃X�}�[�g���[�^�[�f�[�^��͋Z�p�ŃR���T�����ƓW�J �d�͗����̔�r�T�C�g���^�c���铯�Ђ́A�p����SMAP Energy�ЂƃX�}�[�g���[�^�[�f�[�^��͋Z�p�ɂ��Ē�g�����B ���Ђ͓d�͎��Ǝ҂��X�}�[�g���[�^�[����擾�����f�[�^�̉�̓T�[�r�X�uSMAP�iSmart Meter Analytics Platform�j�v��W�J����BSMAP�̒��j�Z�p�ƂȂ�̂́A�ߋ��̓d�͎g�p�ʂv���͂��A���ԑі��̓d�͎g�p�ʊm���𐄒肷��A���S���Y�����B ���̐���f�[�^�����p���邱�ƂŁA�d�͉�Ђ̔��d�R�X�g�Ɣ�r���ė��v���̍����ڋq�𒊏o�A���ԑѕʗ����Ȃǂ̏]���ƈقȂ闿�����j���[�Ƀ��[�U�[���ڍs�����ꍇ�̓d�͎g�p�ʂ̕ϓ��\���A�R�d�Ď��E�����T�[�r�X�Ȃǂ̉��p���\�ɂȂ�Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���������݁@�����K�̓I�t�B�X�����̓V���t�ˋV�X�e�����J�� ���Ђ��J�����������K�̓I�t�B�X�����̓V���t�ˋV�X�e���́A�V������ɐݒu������p���u�i�`���h�r�[���j�Ő���������C�̎��R�Η��𗘗p���A��C�ŗ�p���ꂽ�V��ʂ�����t�ˌ��ʂƁA�L�E�V��p�l��������ݏo����C�Ŏ������s���n�C�u���b�h�^���t�ˋV�X�e���ł���B �`���h�r�[���́A16�����x�̗␅�Ŏ��ӂ̋�C���p���A20�����x�̗�C��������́B��p���u��V��ʐ�30�`50m2��1��̊����Ŕz�u���邱�ƂŁA�����K�͂̃I�t�B�X�ɑΉ��ł���ő�60W/m2��[�\�͂������ł���B �ʏ�̋V�X�e���Ɣ�ׁA�r���S�̂�15�����x�̏ȃG�l�����҂ł���B��ʓI�ȃZ���g���������ɑウ�Ēlj��R�X�g�́A���ݔ�S�̂�2�����x�ɂƂǂ܂�Ƃ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����Ŕ̔����鑾�z�����d�ݔ����璲�B�_�ސ쌧���œd�͏������ ���Ђ́A�d�͂̒n�Y�n���Ə����d�͎��Ƃ�g�ݍ��킹�����f�����Ƃ��J�n�����B ���Ńv�����g�V�X�e���������ʼn^�p���鑾�z�����d�ݔ�����d�͂B���A�_�ސ쌧���̎��v�Ƃɑ��Č��݂̓����d�̗͂������5�����x�������i�œd�͂�̔�����Ƃ����B ���d�R�X�g�Ȃǂ��l����Ɠd�͔̔������ő傫�Ȏ��v�͌����߂Ȃ��B�����œ��Ђ͓����ɂ̃G�l���M�[�֘A���i�̊g�̂��}���Ă����B�w�Z��a�@�A�Z��Ȃǂ��܂��܂Ȏ{�݂�ΏۂɁA���Ő��̑��z�����d�V�X�e����Ɩ��A�V�X�e���ƁA�����ȓd�͋������Z�b�g�Œ�Ă��Ă������j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���������݊e�ƒ�̓d�͂��G�l�t�@�[���i�R���d�r�j�ŗZ�ʂ��镪���}���V������̔� ���Ђ́A�É��K�X���p�i�\�j�b�N�Ƃ̋����ŊJ�������u�s�|�O���b�h�V�X�e���v���������z���^�}���V�����̔̔����J�n�����B ���V�X�e���́A�}���V�����ꊇ��d�Ɗe�˂ɐݒu����G�l�t�@�[���Ƃ�g�ݍ��킹�A�d�͏���̏��Ȃ����d�]�͂̂���ƒ납��d�͏���̑����ƒ�ɑ��A�}���V�������œd�͂�Z�ʂ��������́B HEMS�ɂ��G�l���M�[�̌����鉻�A�É��K�X�T�[�o�[�Ƃ̘A�g�ɂ����M��̌����鉻�A�É��K�X�ɂ����M��́u�܂Ƃߐ����v�Ȃǂ���������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���X�܂ɔp���o�C�I�}�X���d���X�܂�20�������d���[�\�� �R���r�j�X�܂ŗg�����̏��i������ۂɔ�������A�����p�����g�p����B�A�����p���̈ꕔ���o�C�I�f�B�[�[���R���Ƀ��T�C�N�����A���d�@�̔R���Ƃ��čė��p����d�g�݂��B���d�ʂ͊����X�܂̏���d�̖͂�20���ɑ�������N��3��6000kWh��������ł���B �A�����p���������Ƃ���o�C�I�f�B�[�[���R���𗘗p���邱�ƂŁu�J�[�{���I�t�Z�b�g�v�̍l����K�p�ł��邽�߁A���̔��d�ɂ�����CO2�r�o�ʂ͎����[���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Y�����Ȃǂ�LED�Ɩ��̖��邳��]�����邽�߂́u�W�������v���J�� LED�Ɩ���L�@EL�Ɩ��Ȃǂ̌ő̏Ɩ��ł́A���邳��]������w�W�Ƃ��đS������F�̕]�����d�v�ł���B �����̕]���̂��߂ɂ́A��������ɂ��A���̔g�����Ƃ̋��x�������x�ɑ��邱�Ƃ��s�����B��������������x�ɍs���ɂ́A�O�ʂɂ���������˂�������ɉ����āA�����̔g���̈�S�̂ŏ\���Ȍ����x�������������߂���B �Y�����Ɠ������w���A���S�g�����قȂ镡����LED�f�q�ƕ����̌u���̂�p���āA�����S��ŏ\���Ȍ����x�����u�W��LED�v���J�������B�������̉��x����Ɉ��ɕۂ��߂̉��x����@�\�ɂ��A�W��LED�̎��͉��x�ɑ�������x�̕ϓ���0.01���^�x�ȉ��ɗ}���邱�Ƃɐ��������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����U�ăG�l��~�d�r�̐ڑ�����A���x�Ȑ����DR�ʼn��z���d���؎��Ɛ��i �����G�l���́A50MW�ȏ�̉��z���d���̐���Z�p�̊m���ƁA�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��𐄐i���A�ߓd�����d�͗ʂd�ł���u�l�K���b�g����s��v(2017�N�܂łɑn�ݗ\��)�ł̎����������������Z�p�̍��x����}�邱�Ƃ�ړI�ɁA���L�̎��Ƃɕ⏕������t����B���Ɗ��Ԃ�2016�N����2020�N�܂ł�5�N�ԁB 1�D�o�[�`�����p���[�v�����g�\�z���Ǝ��Ɨ\��z��16��4400���~�B���x�ȃG�l���M�[�}�l�W�����g�Z�p�����p���A�d�̓O���b�h��ɎU�݂���Đ��G�l���M�[��~�d�r�Ȃǂ��I�ɐ��䂵�A���z���d���Ƃ��ċ@�\������ 2. ���x����^�f�}���h���X�|���X�iDR�j���؎��Ǝ��Ɨ\��z��1��2400���~�B���z�d���Ǝ҂��v��������v�}���ʂɑ��āA�����̎��v�Ƃ�����v�}���ʂ��W�߂Ċm�x�̍����l�K���b�g����̎��؎��ƁB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����吶�Z���A��茧�ɍ������̔g�͔��d��ݒu�A�n�Y�n�����߂��� 2016�N8���Ɋ�茧�v���s�̋��`�ɁA�C�̔g�̗͂Ŕ��d����g�͔��d(�o��43kW)���ݒu����A�����I�ȓd�͋������n�܂�B�J�����������吶�Y�Z�p�������́u�����͑S���̋��`�ɐݒu���A���d�����d�͂�n���ŏ����w�G�l���M�[�̒n�Y�n���x��ڎw�������v�ӌ��B ���u�́A�u�g�v�i����2m�A��4m�j���A�g�ɂ���ĐU��q�̂悤�ɑO��ɓ����ă��[�^�[���A���d����B��ʉƒ�\�����ѕ����܂��Ȃ���B�d�͂̈ꕔ�͍`�ɂ��鋙���̎{�݂Ŏg���B NEDO�ɂ��ƁA���{�ߊC�ł́A�g�͔��d��540��kW���i����5��j���m�ۂł���Ǝ��Z����Ă���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���h�C�c�̔N�ԓd�͗A�o�ʂ�609����Wh�Ɖߋ��ō� �h�C�c�̃V���N�^���N���܂Ƃ߂�2015�N�̃h�C�c�̓d�͎s��Ɋւ�����ɂ��ƁA2015�N�̃h�C�c�̓d�͗A�o�ʂ�978��kWh�ŁA�A���ʂ�369��kWh�B ���A�o�ʂ�609��kW h�A2013�N��389��kWh�A2014�N��403��kWh�Ƒ����X���ɂ���B2015�N�̑����d�d�͗ʂ�6471��kWh���������߁A��1���A�o���ꂽ���ƂɂȂ�B �A�o�ɏ[�Ă��Ă����ȓd���͐ΒY�Η͂Ƃ݂��A�h�C�c���Q�����鉵�d�͎s��̎�����i���Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�ƂȂǂ��A�o���̗v���B2015�N�̃h�C�c�����̑����d�d�͗ʂ�2014�N���2�����ŁA�Đ��\�G�l���M�[��1941��kW h�Ŗ�3�����߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���I�o�}�����K��������30�N��96���d���������̏ȃG�l�B���̌����� �哝�̏A�C�ȗ��A30�N�Ԃ�1��7000��kWh�̓d�͍팸��ڎw���A�ȃG�l�������P�̋K����43�����肵���B �d�C�g�p�ʂ��팸�����ōł����ʓI�������̂��A�V���ȋK����ɑΉ������Ɠd���i�̓������i���B�d�͏���ʂ̑傫���d�C���i�̒��ŁA�I�o�}��������������������ύX�̉e�����Ă��Ȃ����̂͂قƂ�ǂȂ��B��ύX�̑ΏۂƂȂ����d�C���i�́A�V�[�����O�t�@���i�V���j����Ɩ����A�������̋@�܂ő���ɂ킽��B �ăG�l���M�[�Ȃɂ��A�����̌�����̕ύX�ɂ��A2030�N�܂łɓd�C�g�p����5200���h���i��58��5730���~�j�ȏ�팸�ł��鎎�Z���B �o�T�uSankeiBiz �v |
|
|
| �����Ȋ��ی�������ɉΗ͔��d�����݂̌��݂�e�F �����̎��̈ȍ~�A�����ɑ���d���Ƃ��Ċ����ȐΒY���g���V�v�悪���������B���{��2030�N�x�̓d���\���i�x�X�g�~�b�N�X�j�͐ΒY�Η͂̊������d�ʂ�26���Ɛݒ肵���B �����̐ΒY�Η͂��ێ������܂ܐV�v�悪���������26���̘g���Ă��܂����O����A���Ȃ�5���̐V�v��������~�߂��B �o�Y�Ȃ́A�V�K�Q�����܂ޑS�Ă̓d�͉�Ђɖ��N�̉��g���K�X�̔r�o���т̊J�������߁A���d�������Ⴂ�ΒY�Η͔��d�������݂ł��Ȃ��悤�ɂ���B �ŐV�s�̐ݔ��͔F�߂邪�A�Η͔��d�S�̂̂����ΒY�Η͂̊�����50���ȉ��܂łɂ��邱�Ƃ����߂�B ���Ȃ͌o�Y�ȂƓd�͋ƊE�̈�A�̎d�g�݂̏�����`�F�b�N���A�Ó��Ɣ��f����Ί��e���]���i�A�Z�X�����g�j�@�Ɋ�Â��A�V�v���e�F����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�ȓd�͏������Ǝ҂ɓd���\�������CO2�r�o�ʂ�����I�J����v���� ���Ȃ́A����҂��d�͉�Ђ�I�ԍۂ̔��f�ޗ��ɂ��Ă��炤���߂ɁA�ǂ̂悤�Ȕ��d���œd�C�������Ă���̂��������d���\�������ƂɎZ�o����C02�r�o�ʂ��z�[���y�[�W��e��}�̂ɕ\�����邱�Ƃ𑣂����j���B�߂��܂Ƃ߂鏬����c�Ƃ̎w�j�Ɂu�L�ڂ��]�܂����v�Ɛ��荞�ށB �o�Y�Ȃ���F���d�͏����莖�Ǝ҂͌����_�Ŗ�150�ЂɒB����B�������Ǝ҂͗l�X�Ȕ��d������g�ݍ��킹�ēd�C��B���ΔR����R�₷�ΒY�Η͂�Ζ��Η͂̔䗦���������CO2�r�o�W���͏㏸���A���z�����d�␅�͔��d�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�̔䗦��������ΐ��l�͉�����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȃx���`�}�[�N���x�̏[���A�����p�M���p�Ɍ����ȃG�l�@�������\�� �H�ꓙ���f����[�L���O�O���[�v�̎��܂Ƃ߁i�āj�����\���ꂽ�B �E�Y�ƕ���ɂ�����x���`�}�[�N���x�̌������F�ȃG�l�@�̒�����o����S�Ă̎��Ǝ҂�S�EA�EB�EC �̂S�i�K�փN���X�������A�N���X�ɉ����������n���̂���Ή������{����B �E�Ɩ�����ɂ�����x���`�}�[�N���x�̑n�݁F�K�Ȑ��x�v���ł܂����Ǝ킩�珇���R�c���s���A�Ɩ�����̃x���`�}�[�N���x�̓����g���}��B �E�����p�M���p���x�̑n�݁F�O���Ŕ������������p�M���w�����Ď�������s�ׁi�����p�M�w���j���A�ȃG�l��g�̈�Ƃ݂Ȃ��ĕ]�����鐧�x��n�݂���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/3�@]�@�@�� |
|
|
| ��40�ЂƓ���A�f�[�^�Z���^�[�̏ȃG�l���֘A�g �|���H���X�A�听���݂�������쏊�A�����ANEC�A�x�m�ʁANTT�f�[�^��[�Z�p�A������C���^�[�l�b�g�Ȃǃ[�l�R����DC�^�c���ƎҁA������w�炪�Q������u������f�[�^�Z���^�[����v��������J�����B ����ł́ADC�^�c���Ǝ҂̗v�]���Ƃ�܂Ƃ߂�ق��A�ŐV�Z�p�̋c�_�Ȃǂ�i�߂�B��1�`2��J�Â��A�ݔ����p���@�A�ȓd�̓T�[�o�[�̍ŐV��������B �x�m�\�t�g�͌c��Ƒg�݁A�f�[�^�����ʂɉ����ăT�[�o�[�̉ғ����_��ɒ����ł���Z�p���J������BNEDO�̏���������ɁA2022�N�Ɏ��p�����߂����B������Ђɂ��ƁA������DC�̏���d�͗ʂ�2013�N��122��5�疜kWh�B�d�͉��10�Ђ̔̔������N�ԑ��d�͗ʂ�1.4���ɂ�����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���G�l���M�[�@��̉��u����A�K�i�����֎Y�w�A�g�|44�Ђ��t�H�[���� ���z�����d�ݔ���~�d�r�Ƃ��������v�Ƒ��̐ݔ���ʐM�Z�p�ŏW�A�V���ȃr�W�l�X�߂����u�G�l���M�[�E���\�[�X�E�A�O���Q�[�V�����E�t�H�[�����iERABF�j�v�����������B ����c��w�̗ы�����ɂ��A�d�͉�Ђ�s�s�K�X��ЁA�V�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj�ȂǁA�v44�Ђ��Q���B�o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���ƘA�g���Ċ�����i�߂�B ����ɂ́A�d�͉��5�ЁA�s�s�K�X�͓����Ƒ�オ�Q�����A�d�@���[�J�[�⎩���ԃ��[�J�[�A�ʐM��ЂȂǕ��L���Ǝ킪�W�܂����B�G�l�����I�u�U�[�o�[�ŏo�Ȃ��A�N��1�`2��̉��\�肵�Ă���B �o�Y�Ȃ�VPP�i�o�[�`�����E�p���[�E�v�����g�j���\�z���ŁA�n�������Ɋ��p�̍l���ŁAERABF�̎��g�݂ƘA�g���Ă����v�悾�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����d�́A���z�����d�̂��܂߂ȏo�͐���̎������X�^�[�g����c��w������ ���؎����́A����c��w�ɐݒu�����o�͐���w�߂̔��M���s���T�[�o�ƁA��A�ዷ�������A�ዷ���l�ȂǓ��Ђ��ۗL����6�ӏ��̑��z�����d�ݔ��ōs����\��B ���̎����ɂ��A���z�����d�ݔ��̔��d�o�͂̔c�����s���Ƌ��ɁA�o�͐���̗ʂ⎞�Ԃ�����܂ł������ߍׂ������u�Ŏw�߂��邱�Ƃɂ��A�{�����䂷��K�v�̂Ȃ��d�͗ʂ��ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃ�ڎw���B ���Ǝґ��ɋً}�Ή��V�X�e���𓋍ڂ��A�Đ��\�G�l���M�[�d�C�̌n���ւ̐ڑ��ʂ��g�債�Ă��A����I�ȃG�l���M�[�l�b�g���[�N�̍\�z��ڎw���B �u�Đ��\�G�l���M�[�ڑ��ۗ��ً}�Ή��⏕���Ɓv�́A�ً}�Ή��V�X�e���̓����ɗv����o��̈ꕔ��⏕����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����d�������Ă��d�͂����苟���A�������d�V�X�e���𒆍��d�͂����V �Ǔ��̓d�͂́A�L���s�ɂ���u�������d�w�ߏ��v�Œn����̔��d�ʂƎ��v�̗\�������ƂɎ����v��𗧂ĂȂ���A�K�v�ɉ����Ĕ��d�@�̏o�͂𐧌䂵�Ď��v�Ƌ����̃o�����X���m�ۂ��Ă���B �V�����������d�V�X�e���͔��d�ʂƎ��v�̗\���l�����ƂɁA���d�R�X�g���ŏ��ɂȂ�悤�ɔz�����邱�Ƃ��ł���B���킹�Ċe���d���̏o�͒����\�͂��l�����Ȃ���A���v�̋}���ȕϓ��ɔ����Ē����p�̓d�͂������I�Ɋm�ۂ���@�\���lj������B���z���╗�͂̏o�͂��ϓ����Ă��A���炩���ߏ������Ă������Η͔��d�̏o�͂����Ď����o�����X���m�ۂ��邱�Ƃ��ł���B ���d�͂̔N�ԋ����d�͗ʂ̂����A�o�͂����₷���K�X�Η͂̔䗦��25���B�Đ��\�G�l���M�[�̔䗦��2014�N�x��3���܂Ŋg�債���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u70���̏ȃG�l��3�{�̐��Y���v�AGaN���p�̃}�C�N���g���M �O�H�d�@�A�}�C�N���g���w�A�����H�Ƒ�w�A���J��w�́A�o�͓d��500W��GaN�i�����K���E���j�����탂�W���[�������M���Ƃ��鍂�����ȎY�Ɨp�}�C�N���g���M���u�������J�������B ���̑��u�́A�}�C�N���g�������M�������̗p�A�]���̊O�����M�����Ɣ�r���āA70���̏ȃG�l��B���B�܂��A�}�C�N���g�̈ʑ�����ɂ��Ǝ˂���ꏊ���ł��邽�߁A�����F���̉��x���z�𐧌䂵�A�Ǐ��I�ȓ������M���\�ɂȂ����B���U���M���Ɣ�r���āA���ϕi��C���N�h���Ȃǂ̉��w���������̐��Y��������3�{���サ���B GaN�����탂�W���[���̏o�͂�500W�B�o��190W��GaN�f�o�C�X4���p���Ď��������B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���d�͑�����15���ጸ�|���k�d�͂Ȃǂ��V�^�����a�^�ψ��� ���k�d�͂Ɩk�œd�@�́A�d�͑����ጸ�A�����������������������a�^�z�d�p�ψ���������J�������Ɣ��\�����B �K�i�����ŕψ���̉��x�㏸���x���ɘa���ꂽ���Ƃɂ��Ή����A���M�̐��ʂ�ጸ�B�����ɂ��d�ʌ��ƃX�y�[�X���������̑������ɏ[�āA15���̓d�͑����ጸ�����������B �؎���̋z�����ɒ��ڂ��A�����̈�ł��銪���≏���̐��������炷���ǂ����{�����B���������̖�����藬��₷���\���ɕύX�����ق��A���M�v���ύX�����B�����≏���̗}���ɂ��A��i�A���^�]�ł̊��Ҏ������]���J���i�Ɣ��2�{��60�N�ɉ������B���Ђ͍؎�����܂ސA�������g�p�����z�d�p�ψ����W���̗p���A����̍X�V���ɏ����������錩���݁B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��10���[�g�������1���b�g�̃��C�����X���d������ ���Ђ́A���{��g���s����Ossia (�I�V�A), Inc. �Ƌ����ŁA���C�����X���d�Z�p�uCota (�R�[�^)�v�̎��p����ڎw���A�����J����i�߂Ă����B ���̐��ʂƂ��āA���ꂽ�ꏊ����X�}�[�g�t�H����IoT �f�o�C�X�����C�����X���d������f�����X�g���[�V�������A�č����X�x�K�X�ōs��ꂽ�uCES2016�v�ɂčs�����B Cota�́A�]���̃��o�C���f�o�C�X�͂������A�}���ɕ��y������E�F�A���u���EIoT�f�o�C�X�ɂ����郏�C�����X���d�����\�ɂ���BWi-Fi�Ɠ���2.4GHz�т̎��g�����g�p�����A�`���[�W���[(���d) �ƃ��V�[�o�[(��d) ����\������A�ő��10���[�g������Ă��Ă��ő�1���b�g�܂ł̋��d���\�ŁA�����̋@��֓����ɋ��d�ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���n���ɒ�������CO2��A���I�Ƀ��j�^�����O�����@���J�� ��B��w�A������w�A���É���w��̌����O���[�v�́ACCS�iCarbon dioxide Capture and Storage�j�v���W�F�N�g�Œ�������CO2�x�ǂ��A�܂��A���I�Ƀ��j�^�����O�����@���J�������B �����ȐU���U�������鑕�u�i�A�N���X�j�ɂ���ĘA���ɔ��U���ꂽ�g��n�k�v�Ŋϑ����A���ɕ\�ʔg�ƌĂ��n�k�g�̉�͂��s�����ƂŁA�n���Ő������ω����������x�Ń��j�^�����O���邱�Ƃɐ��������B ���Ȃ́ACCS�͐ΒY�Η͔��d���̉^�]�ɕs���Ǝw�E���Ă��邪�ACO2���A�n����������CO2�̘R�k�ɂ������āA�A���I�ɍ������x�Ń��j�^�����O����͓̂���̂����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���s�s�K�X�̏����S�ʎ��R���A���N4�����{�Ɍ���8�����玖�Ǝғo�^�J�n ���Ȃ́A�s�s�K�X�̍w��������R�ɑI�ׂ鏬���S�ʎ��R���ɂ��Ă̕��j�����\�����B2017�N4��1��������{���邱�Ƃ����肵���B8���ɓs�s�K�X��̔�����K�X�������Ƃ̎��O�o�^�\���̎�t���J�n����Ƃ��Ă���B ���̂ق��ɁA�������������̐R���̂�����^���ƕ�V�^�����S�ʎ��R��������ǐ����𑣐i���邽�߂̑����������x�^���s�̋������Ɠ������������������p�����ꍇ�ɂ���������`���̗��s���@�A�ɂ��Ă̘_�_�������ꂽ�B 100���z�����ʃK�X���Ǝ҂���A�K�X���ǂ��g�p����������������̎��O�F�\�����s����B���̂��߁A�����I�ȍ�����@�ɂ��������������̐R���̂�������J�M�ƂȂ�B �s�s�K�X�̏����S�ʎ��R���ɂ���Ė�2.4���~�i���v�Ɛ��͖�2,600�����j�̎s�ꂪ�J�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ߓd�ɂ��d�͔����v�ցA�������{�i���|�K�i�����ŎY�w�A�g �l�K���b�g����s��̑n�݂Ɍ����A����c��w�X�}�[�g�Љ�Z�p�Z�������@�\�����S�ɂȂ�A�d�͉�Ђ�s�s�K�X��ЁA�d�@���[�J�[�Ȃnjv44�Ђ��Q������B�u�G�l���M�[�E���\�[�X�E�A�O���Q�[�V�����E�r�W�l�X�E�t�H�[�����iERABF�j�v��ݗ������B �����G�l�����l�K���b�g����̃��[�������肷�邽�߁A�u�G�l���M�[�E�\�����[�V�����E�A�O���Q�[�V�����E�r�W�l�X������v��ݒu���A������ERABF�ɕA�ӌ����W�Ă����B 2016�N�x���ɒʐM�K�i�̐�����K�C�h���C���̍���A�A�O���Q�[�^�[�̗v���̍���Ȃǂ̐��x�v���s���B�l�K���b�g����s���2017�N�x�A���A���^�C���s���2020�N�x�ɂ��n�݂���錩�ʂ��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����z���G�l���M�[�̒����ۑ����\�ɁA���w�����Łu�M�v�Ƃ��Ē��� �}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j���J���������z�G�l���M�[�̉��w�I�����́A�����ɓ�����ƍ\�����ω�����A�]�x���[���𗘗p������̂ŁA�ω���������Ԃɂ킽�蕨���I�Ɉ��肪�ۂ����̂��������B �����āA�G�}�⏭���̉��x�ω��A�t���b�V���̌��Ȃǂ̎h������������ƁA�}���Ɍ��̌`�ɖ߂�A��������Ă����M�����o�����B �V�����ޗ��̐����ɂ́A2�i�K�̃v���Z�X���K�v�Ƃ���邪�A�ƂĂ��V���v���Ŋg�����̍������̂��Ƃ����B�~�M�ޗ��̔������ɐ��������̂ŁA�K���X��D���Ȃǂɑg�ݍ��ނ��ƂȂǂ��\���Ƃ��Ă���B �M������\�͂����t�B�����͓��������������߁A�����Ԃ̃t�����g�K���X�̓����h�~�Ȃǂɂ��g�p�ł���\��������Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����G�ȃX�}�[�g�n�E�X�̎d�g�݁A���Ƃ�F�肷�鎑�i���x���o�� ���{��2030�N�Ɍ����ďZ���̏ȃG�l�����߂��Ă��āA�ƒ���̃G�l���M�[���œK�ɐ��䂷��u�X�}�[�g�n�E�X�v�����ڂ���Ă���B ������́A�X�}�[�g�n�E�X�̕��y�Ɍ������l�ވ琬��ړI�ɁA�V���Ȏ��i���x�u�X�}�[�g�}�X�^�[�v��V�݂���Ɣ��\�����B�X�}�[�g�n�E�X��IoT�iInternet of Things�A���m�̃C���^�[�l�b�g�ڑ��j�ɑΉ������Ɠd���i�Ɋւ���m����F�肷�鎑�i�ŁA2016�N9���ɑ�1��̎��������{����B�ȍ~�N2��i9���A3���j�̃y�[�X�Ŏ��{����B�����Ȗڂ́u�X�}�[�g�n�E�X�̊�b�v�Ɓu�Ɠd���i�v�ɂ��Ă�2��ށB����2�Ȗڎ�9230�~�A1�Ȗڎ̏ꍇ��6180�~�ƂȂ�B ���i�͔��s��5�N�ԗL���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ȃG�l�Z���^�[�A�V�d�͂̏ȃG�l��Ă��x���|�N�x���ɊJ�n �V���Ɏ��R���̑ΏۂƂȂ�H��Ȃǂ̎Y�ƕ���A�r���Ȃǂ̋Ɩ�����Ŏ��Ɗg���ڎw���V�d�͂ɗ����v�����݂̂łȂ��A�ȃG�l��ĂȂǂŕt�����l�����߂錤�C�T�[�r�X���n�߂�B���Z���^�[�����N�~�ς����ȃG�l�̃m�E�n�E�����B�G�l���M�[�}�l�W�����g���Ǝ҂Ȃǂ���̉�����t����B ���C�́u��b���C�v�Ɓu���p���C�v�B�u��b���C�v�͉ƒ�A�Ɩ��A�Y�Ƃ̃G�l���M�[����̎��Ԃ��A�u���p���C�v�͕�����i��A��Ƃ̃j�[�Y�ɍ��킹�����e��������B���Z���^�[�́u�ȃG�l�����v���o�����A�V�d�͂ɑ���ȃG�l��Ă��s���T�[�r�X�ɂ���o���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����̓V�R�K�X�����u�\�w�^���^���n�C�h���[�g�v�A���{�ߊC700�J���ȏ�ɑ��݂� �����͕\�w�^���^���n�C�h���[�g�̎����ʔc���Ɍ����āA2014�N�x�����3�N�ɂ킽���ē��{�ߊC�̒��������{���Ă���B 2015�N�x�́A�\�w�^���^���n�C�h���[�g�����݂���\����������ٓI�ȍ\���i�K�X�`���j�[�\���j�̓����ɂ����郁�^���n�C�h���[�g�̗l�q�����ڂ����c�����邽�߁A�������B����ӂ���ѐV������z���ŁA���v��30�J���̌@�풲�����s�����B���{�C�̍L��n�������ł͕\�w�^���^���n�C�h���[�g�����݂���\��������C�ꕔ�̓��ٍ\����700�J���ȏ㔭�������Ƃ����B ����̗\��Ƃ��ẮA���،��ʂ܂��ĕ\�w�^���^���n�C�h���[�g���������Z�p�̒�����Z�p�J����@���������Ă����v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������C�̎g�������H�v�AIGCC��荂�����ȐΒY�Η͂�2030�N�Ɏ��p�� NEDO�́A�ΒY�Η͔��d�Ŕr�o����鉷�����ʃK�X�̍팸��ڎw���A������K�X���V�X�e���̋Z�p�J���ɒ��肷��Ɣ��\�����B �V���ɊJ������Z�p�́A�K�X�^�[�r���̔r�M�𗘗p���č�鐅���C�ŐΒY�̃K�X���𑣐i����B�����C���g�p���邽�ߏ��C�^�[�r���̏o�͂͒ቺ���邪�A�V�X�e���S�̂̔��d�o�͂�����Ƒ��d�[�����̌��オ���҂ł���B �d�͒����������Ɏ��ƈϑ����A�J�����́u�ΒY�K�X���������d�iIGCC�FIntegrated coal Gasification Combined Cycle�j�v�Z�p�̉��ǂ�����g�ށB �����Ɣ�5��2000���~�A���Ɗ��Ԃ�2015�`2018�N�x�B2030�N������߂ǂɎ��p���������l�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/2�@]�@�@�� |
|
|
| �����a�V�F���Ζ�49MW�́u���l�o�C�I�}�X���d���v�c�Ɖ^�]�J�n �_�ސ쌧���s�����Ɍ��݂��������d���͖؎��y���b�g��p�[�����q�k�iPKS�j��R���Ƃ���o�C�I�}�X��Ĕ��d���B ���d�o�͂�49MW�B�N�Ԕ��d�ʂ͖�30��MW���B����͈�ʉƒ��83,000���т̏���d�͂ɑ�������B�^�c�҂͏��a�V�F���Ζ�100���o���̎q��Ћ��l�o�C�I�}�X�p���[�B �����d���͍`�p�ݔ��ȂǔR������C���t���������Ă���A��w�n�������n��s���ł��邱�Ƃ���24���Ԕ��d���\�B���̂��߈���I�ɓd�͂��������邱�Ƃ��ł���B�؎��o�C�I�}�X��Ă̔��d���Ƃ��Ă͍����ő�K�́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���l�X�����{�A���ߊC�D�D�A���{�C�ۋ�����[�_���V�t�g���i�ɍ���CO2�팸�Ȃ� 3�Ђ����������������āA���[�_���V�t�g�𐄐i���A�ȃG�l���M�[�̎����╨������ɂ����ď����̃g���b�N�h���C�o�[�Ȃǂ̐l��s���ւ̑Ή���i�߂Ă������Ƃɍ��ӂ����B ���[�_���V�t�g�Ƃ́A�����ݕ��A���ʂ̂��悻9�����߂�g���b�N�A�����A�C�^�A���E�S���A���ɐ�ւ��邱�Ƃ�ʂ��āA�����R�X�g�̍팸�ACO2�r�o�ʂ̍팸��i�߂��g���B �l�X�����{�ł́A���q�D�A�����ɐ�ւ��Ɏ��g��ł������A�A�����Ԃ������Ȃ�ƂƂ��ɁA�V��̉e�����A�A���v�悪����B���̂��߁A���{�C�ۋ����2�T�Ԑ�̒����C�ۗ\������邱�ƂŁA�l�X�����{�͍ɂ̈��k�ƌ��i�̃[������i�߂���{�C�ۋ���J���̃V�X�e���́A�R������̗ǂ��q�H�I�肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ�A����4.5%�̔R��팸���ʂ�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����Z�����z�����d�ɂ��n�G�l�A�����ݔ��̏ȃG�l�ȂǂŔN��5700MWh��ߓd ���Ђ́u�����F�H��v�ɂ����āA�H��̉����ɑ��z�����d�V�X�e���̐ݒu�A�H����ł̗�p�p�̗Ⓚ�@�A��C���k�@�̑䐔����A�{�C���[�̏��^���ɂ��^�]�����̉��P�A�V���R�������F�̒f�M�����ɂ�鍂�������Ȃǂ̏ȃG�l���{�A���z�d�r�Z�������H����A��C���k�@����̔r�M�������⏃�������ݔ��̔M���Ƃ��ė��p����ȂǁA�G�l���M�[�̍ė��p�Ƃ������ȃG�l�����Ɏ��g��ł���B����ɂ��N��5659MWh�̎g�p�d�͗ʂƖ�4388�g����CO2���팸���Ă���Ƃ����B ���̑��ɁA�n���̏��w�Z�ł̊��o�O���Ƃ̊J�ÂȂǒn�����ی�ւ̍v�����������{���Ă���A6�N�A���Łu�n�����g���h�~��������b�\���v����܂����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���g���^�A��[�H��ŏȃG�l�ɍv������u���炭��@�\�v �g���^�����Ԃ́A�H����̏���d�͂��팸����J�C�[������u�G�R�v���_�N�c2015�v�ŏЉ���B �W�������̂́A�H��@�B�ʼn��H���������r���̃G���W���R�����b�h���A�g���炭��@�\�h�Ŏ��̍H���Ɏn�����鑕�u���B�]���̓x���g�R���x���[��A�N�`���G�[�^�[�ȂǓ��͋@�\���g���ă��[�N�i�H�앨�j�̉^���┽�]�����Ă������߁A�ݔ�����|����ɂȂ�����A�]�v�ȓd�͂�������肵�Ă����B ���Ђ͓��͌�������Ȃ����炭��@�\�̎n�����u�����삷�邱�ƂŁA����d�͂̏��Ȃ����Y���C�����\�z�ł����Ƃ����B ���Ђ̓N���}�̐����ߒ��ɂ�����CO2�r�o�ʂ�2050�N�Ƀ[���ɂ���ڕW���f���Ă��āA�u�����Z�p�̉��P�v�i�ȃG�l��������j�Ɓu���p�G�l���M�[�̕ύX�v�i�ăG�l�̗��p�j��������B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| �������d�͑����̑��z�����d�ݔ��̏o�͐�����؎����J�n ���Ђ́A�����̑��z�����d�ݔ��̔��d�o�͂̔c���ƃL���ׂ₩�ȏo�͐�����s���V�X�e���̍\�z��ړI�Ƃ�����؎��Ƃ�2015�N6��������{���Ă��āA���̂����o�͐���Ɋւ�����؎������J�n�����B ���؎����́A�o�͐���w�ߔ��M�T�[�o�[�ƁA���z�����d�ݔ��i8�n�_�j�̔��d�����A���^�C���Ŕc�����Ȃ���A���L���ׂ₩�ȏo�͐�����s���B����ɂ��A�o�͐���ʂ��ł��邾�����Ȃ����邱�Ƃ�ڎw���A�������I�ϓ_�ɗ������o�͐���V�X�e���̍\�z��i�߂Ă����B ����ɁAHEMS�Ƃ̘A�W�ɂ��]��d�̗͂L�����p�ɂ��Ă����؎������s���B�o�͐���w�߂��o���ꂽ�ۂɁA�ƒ���@��̗��p���Ԃ̃V�t�g��~�d���s���A���d�G�l���M�[��L�����p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���ƒ�̃G�l���M�[����ʂ𐄒�ł���V��@�uREEDA�v �uREEDA�v�́A�ƒ���ɂ����鎞�Ԃ��Ƃ̐����s���̗ʂƁA�ƒ���G�l���M�[���p�̔g�`�̑������ɒ��ڂ��A�ʔň���E����c���������E����c��w��3�҂������Ō����E�J�������ƒ���G�l���M�[�̏���ʐ���@�ł���B �ʔň���́A�d�͗ʂȂǂ̃G�l���M�[�f�[�^���Ȃ��Ă��ƒ���ł̐����s���ʂ���ɉƒ�̃G�l���M�[������Ԃ��p���I�ɐ���ł���A�V���Ȏ�@�uREEDA�i���[�_�j�v�����p�����ƒ�����G�l���M�[���T�[�r�X���A2016�N4�����{�i�I�ɊJ�n����B �d�͏����̑S�ʎ��R���Ɍ����āA�d�͂�K�X�Ȃǂ̊����̃G�l���M�[���Ǝ҂�A�G�l���M�[�f�[�^��ێ����Ă��Ȃ��V�K�Q�����Ǝ҂ɑ��āA�uREEDA�v��p���āA�ƒ�̃G�l���M�[����𐄒�B���̌��ʂɊ�Â����ȃG�l���@��œK�ȗ����v�����Ȃǂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G�v�\���g�p�ςݗp�����Đ����鑕�u�uPaperLab�i�y�[�p�[���{�j�v���J�� �����u�͎g�p�ς݂̃R�s�[���𓊓�����ƁA��3���ōĐ������o�͂���BA4�p���̏ꍇ�A1���Ԃɖ�14���̍Đ����Y�ł���B 1��8���ԉғ������ꍇ�A6720�����Y�ł���v�Z���BA4�EA3�T�C�Y�̃I�t�B�X�p���ɉ����A���h�p���Ȃǂ̌�������邱�Ƃ��ł���B�F�⍁��̂����Đ��������Y�\�ŁA�ݒu����I�t�B�X���Ŏ��̍Đ��H����S�Ċ������邱�Ƃ��ł���B �����u�̓����́A�@����̎��x��ۂ��߂̏��ʂ̐��ȊO�A��ؐ����g��Ȃ��Ǝ��Z�p�uDFT�iDry Fiber Technology�j�v�ɂ���Ď������Ă���B�����@�B�I�Ռ��ŕ��ӂ��āA���̒��ŐF���t���Ă��镔������菜���B���Ɍ����f�ނ�g�ݍ��킹�ăV�[�g��ɂ���B��͉������Đ��^���s���A�Ō�ɓK�ȑ傫���ɍْf����B�Đ���1���̐����ɂ͌Î�1.2�`1.3�����x�𗘗p����Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ȃG�l�x���`�}�[�N���x�A�D�ǎ��ƎҖ����\�� ���������G�l���M�[������́A�x���`�}�[�N���x�̍���ɂ��Č��������B2016�N�x���瓱�����鎖�Ǝ҃N���X�����]�����x�Ɋւ��A�D�ǎ��Ǝ҂��Ǝ�ʂɌ��\�������A��؎��Ǝ҂͌��i�ɒ�������B�ȃG�l���M�[�@�Ɋ�Â�������o����S�Ă̎��Ǝ҂�S�AA�AB�AC��4�N���X�ɕ����A�Ή����s���B �x���`�}�[�N�ڕW��B�����Ă��鎖�ƎҁiS�N���X�j�́A�o�Y�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ŏ��ƎҖ��Ȃǂ�\������B �ߋ�5�N�ԕ��ό��P�ʂ�5�����������Ă��鎖�ƎҁiB�N���X�j�ɂ́A���n�����◧�����茟�����d�_�I�Ɏ��{����B �iA�N���X�j�́iS�N���X�j�ɂ��iB�N���X�j�ɂ��Y�����Ȃ����ƎҁB ���ӂ�v���鎖�ƎҁiC�N���X�j�́A�iB�N���X�j�̒��œ��ɔ��f��̏�����s�\���Ȏ҂ƂȂ�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ������26�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̉������ʃK�X�̎��r�o�W���E������r�o�W���̌��\ �n�����g����̐��i�Ɋւ���@���Ɋ�Â��A��_���Y�f���̉������ʃK�X�����ʈȏ�r�o���鎖�Ǝҁi����r�o�ҁj�́A���N�x�A�������ʃK�X�Z��r�o�ʋy�сA�����㉷�����ʃK�X�r�o�ʁi���s���J�j�Y���N���W�b�g�y�сA�����F�ؔr�o�팸�ʓ��f�����r�o��)�����Ə��Ǒ�b�ɕ��邱�Ƃ��`���t�����Ă���B ���ʁA����26�N�x�̓d�C���Ǝ҂̎��тɊ�Â����r�o�W���y�ђ�����r�o�W�����ɂ��āA�o�ώY�Əȋy�ъ��ȂŊm�F�����\�����B �d�C���Ǝҕʔr�o�W���i����r�o�҂̉������ʃK�X�r�o�ʎZ��p�j�|����26�N�x���с| http://www.env.go.jp/press/files/jp/28621.pdf �o�T�u����HP�v |
|
|
| ���Y�ƁE�H�ƘF���������p�������M��������J�������p�M��L�����p�� �V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\(NEDO)�A�����p�M�G�l���M�[�v�V�I���p�Z�p�����g��(TherMAT)�A���Z�q�Ƃ́A���M�C�̉��x1300���ŏ]���i�Ɣ��3�{�ƂȂ��24%�̔M������\�̔M����������������B ���݁A�^�A�E�Y�ƁE�����̕���ɂ����āA�ꎟ�G�l���M�[�̔����ȏオ���p���ꂸ�ɔr�M�ɂȂ��Ă���B����J�����ꂽ�M������́A�����Ŏg�p�����M������ɂ����āA�g���[�h�I�t�̊W�ɂ���ύ������\�ƔM������\�̗������������邽�߁A�]���̔M������̍\���ƍގ������������B��̓I�ɂ́A����ωނ̎g�p�B2�d���Ƒ����ǂ̃n�C�u���b�h�\���ɂ��A�M�`�B�ʐς������A�����I�ȔM�`�B���\�Ƃ����B �o�T�uMy�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ��WFP�ȂNjC��ϓ��ŏ����̐��E�̐H�Ə\ ���A�̐H�Ǝx���@��WFP�Ɖp���C�ۋǂ�5�N�Ԃɂ���ԍ��������̌��ʂ��u���E�̐H�ƕs���ƋC��ϓ��ɑ���Ǝ㐫�}�b�v�v�Ƃ��Ĕ��\�����B�n�}��ŁA�u�������ʃK�X�̔r�o���x���v�ƁA�u�C��ϓ��ւ̓K����̎�g�ݓx�����v�����ꂼ��3�i�K�ŁA�u2050�N��v�u2080�N��v�̐H�Ə̗\�z��F�����Ŏ������B �C��������Ƃ���H�ƕs���i�Ǝ㐫�j���ł������̂́A�T�n�������ȓ�̃A�t���J�B�A�W�A�̑啔���͒����x�̐Ǝ㐫�ŁA����Ă̐Ǝ㐫�͒�x���ł���B�ȑO�ɔr�o���ꂽ�������ʃK�X�̉e���̂��߁A2050�N��܂ł͐��E�̑����̐l�X���H�ƕs���ɒ��ʂ���B �������̂���r�o�팸��𑬂₩�Ɏ����ł���A�H�ƕs���͈����ɃX�g�b�v��������A2050�N��ȍ~�A�����ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d���\���J���́u�w�͋`���v�|�����c�Ǝw�j�𗹏� �d�͎���Ď����ψ���́A�����ǂ���o�����u�d�͂̏����c�ƂɊւ���w�j�āv�ɂ��ĐR�c���A���������B�����d�C���Ǝ҂ɓd���\���̊J�����`���t���邩�ɂ��ẮA�z�[���y�[�W�ȂǂŊJ�����邱�Ƃ�]�܂����s�ׂƂ��A�@�I�ȋ`�����͌��������B �����A�d�͊Ď��ϊ����́A�u�i�w�j�ł́j�]�܂����s�ׂɂ��Ă͂���܂ŁA��ʓd�C���Ǝ҂͂قڑS�Ď���Ă���B���̐V�K�Q���҂��܂߂Ď����I�ȓw�͋`���ɂȂ�v�Ɛ��������B ���w�j�ẮA(1)���v�Ƃւ̓K�ȏ��A(2)�c�ƁE�_��`�Ԃ̓K�����A(3)�_����e�̓K�����A(4)���E�₢���킹�ւ̑Ή��̓K�����A(5)�_��̉����葱���̓K�������ō\���B �s���ȉ���̋K���ł́A���������z�Ȉ�����ݒ肵���ꍇ��A�����̊z�������������_����Ԃɂ��Ă͋�̓I�ɂ͋L�ڂ����A�����I�ɔ��f���邱�Ƃɂ����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���j���[���[�N�B�m��2030�N�ɓd�͂�50�����Đ��G�l �j���[���[�N�B�m���́A��N6���ɔ��\�����v�����ł͎�v��3�̖ڕW���߂Ă���B ��1�͓�_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X�̔r�o�ʂ�2020�N�܂ł�40���A2050�N�܂ł�80���팸���邱�Ƃ��B��N��1990�N�B�Y�ƁA�A���A�����̎O�̕��傪�Ώۂ��B ��2�͍Đ��\�G�l�d�͂̔䗦��50���ɍ��߂�B ��3�́A2012�N�Ɣ�r���Č����̃G�l���M�[����ʂ�23���팸����B �����̃r���̃G�l���M�[���������߁A�[���G�l���M�[�r�������邱�ƂŎ�������B ���m���́A�܂��G�l���M�[���v�r�W�������f���Ă����B�Đ��\�G�l���M�[�R���̓d�͂���葽��������邱�Ƃœ��G�l���M�[�̉��i�����������邾���łȂ��A�֘A�Y�Ƃ̔��W��ڎw���Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���t�����X�̌����@�ւ��u�i�g���E���C�I���~�d�r�v�̊J���ɐ��� �|�X�g�E���`�E���d�r�̗L�͌��̈�ɋ�������̂��i�g���E���C�I���~�d�r���B�i�g���E���̓��`�E���ɔ�ׂĒn����ɋɂ߂ĖL�x�ɑ��݂��A�R�X�g�����Ɉ��������b�g������B �t�����X�̌����@�ւ��A���`�E���C�I���d�r�ŕW����18650�^�i���a18mm�A����65.0mm�j�Ɠ����T�C�Y�̃i�g���E���C�I���d�r���J�������Ɣ��\�����J�������~�d�r�̓����́A�~������d�͗ʂ������_�S���`�E���~�d�r�̐��\�ɕC�G�����90���b�g��/�L���O�����B�����Ȑ��\�̒ቺ���������������ɏ[�E���d�ł�����B2000����A���`�E���C�I���~�d�r�ɕC�G����B�ő�̓����͏[�d�̎��Ԃ��Z�����Ƃ��B�������A�d����0.3�{���g�قǒႭ�Ȃ��Ă��܂��Ƃ����B���̂��߁A�R�X�g�̈�����g���������A��ɍĐ��\�G�l���M�[�p�̒~�d�r�Ƃ��Ă̗p�r��������ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2016/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���V���[�v�́u�̌��t�B�����v�A�Ɩ��d�͂�N��4���팸 �̌��t�B�����͕\�ʂɔ����H���{�����ƂŃt�B�����̕Б���肳�܂��܂Ȋp�x������˂�������A���Α�������̊p�x�ŏo�����Ƃ��\�ɂ��Ă���B ���̃t�B�������K���X�ɒ���t����Ȃǂ��A���̏㕔�ɐݒu���邱�ƂŁA�G�߂⎞�ԑтɉ����ĕω�������ˊp�x�ɂ�����炸�A���z���������I�ɓV������Ɏ�荞�݁A�s���ȃO���A�i�܂Ԃ����j��}���Ȃ��玺���S�̂𖾂邭���邱�Ƃ��ł���B ���Ђ̌������ŏƓx������s�������ʁA�I�t�B�X�ŋ��߂���Ɠx500lx�i���N�X�j���ێ�����̂ɕK�v�ȏ���d�͗ʂ�N�Ԃ�42.9���팸�ł����Ƃ��Ă���B���z���x���Ⴍ�Ȃ�H����t�ɂ����Ă͖�73���̍팸���ʂB �̌��t�B�������T�b�V�ɔ[�߂��u���R�̌��V�X�e���v�Ƃ��Đ��i�����A�I�t�B�X�r�����͂��߁A�w�Z�A�a�@�A�R���r�j�Ȃǂ��^�[�Q�b�g�ɓW�J���Ă������j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����ۍq�Ǝ��Ǝҗ��p�̉ƒ�����f�f�T�[�r�X��� �d�͏����̑S�ʎ��R���Ɍ����āA�d�͉�Ђ��͂��ߏ����d�C���Ǝ҂��ƒ�����̐V�����d�C�����v�����̍쐬�Ɏ��g��ł���B ���̒��ŁA���ۍq�Ƃ͎��Ǝ҂����p����f�f�T�[�r�X�����B�Z��[�J�[��d�C�@�탁�[�J�[���ƒ�ɒ���f�f���|�[�g���쐬�ł���B �f�f���@�͑�ʂ̃f�[�^���R���s���[�^�ŕ��͂���u�r�b�O�f�[�^��́v���̗p�����B�V�T�[�r�X�Ƃ��āA���z�����d�ƒ~�d�r��g�ݍ��킹���d�C�����v�����̐f�f�T�[�r�X���J�n����\�肾�B �V�T�[�r�X�ł͉ߋ��̓��˗ʂ̃f�[�^�����Ƃ�1���Ԃ��Ƃ̗]��d�͗ʂ�\�����������ŁA�~�d�r�̏[�d�E���d���Ԃ�ς��Ȃ���A�N�Ԃ̓d�C�������ł������Ȃ�p�^�[�����r���Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����B�ł̃l�K���b�g��������p���A���{��DR���ƓW�J�փG�i�W�[�v�[���W���p�� �G�i�W�[�v�[���A�V���i�C�_�[�G���N�g���b�N�A�o���Ɠ����d�͂�4�Ђ��ݗ������f�}���h���X�|���X�iDR�j�A�O���Q�[�^�[�̃G�i�W�[�v�[���W���p�����A�Y�ƗpDR���ƓW�J�̏�����i�߂Ă���B �d�͉�Ђɑ����Ď��v�Ƃɐߓd���˗����A�d�͎��������鎖�Ƃ̊J�n��ڎw���B2015�N7���Ɏ��Ƃ��J�n���A9���ɎY�Ɨp���v�Ƃ̓d�͎g�p�Ȃǂ������l�b�g���[�N�I�y���[�V�����Z���^�[�iNOC�j��ݒu�����B �G�i�W�[�v�[���̃\�����[�V�����͓d�͎��v�Ƃł��鐻���ƂȂǂ̓d�͏�����_��Ɋ��p���邱�Ƃɂ���āA���v�ƂɐV���Ȏ��v�������B���v�Ƃ̃V�X�e�����v���Z�X���Ƃ�NDC�ɐڑ����A�u�v�[���v�ƌĂ��e���v�Ƃ́u�|�[�g�t�H���I�v���A�O���Q�[�g���邱�Ƃɂ��A�O���b�h�ɂ�����s���̎��Ԃ��y�����A�d�C���Ǝ҂̃O���b�h�o�����V���O�ɂ�����R�X�g���팸����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ЊQ�����ғ����鎩���̔��@��W�J�A�T�q���� ���Ђ́A�u�}�O�l�V�E����C�d�r�����v���W�F�N�g�v�ɎQ�悵�A�}�O�l�V�E����C�d�r�݂����ЊQ���p�����̔��@��W�J����B �ȑO���玩���̔��@�����C�t���C���ł���ƍl���A�Љ�v����i�߂Ă����B����V���Ɉ����p�����̔��@�ɑ�e�ʔ��d���\�ȃ}�O�l�V�E����C�d�r�݂��邱�ƂŁA��72���Ԃɂ킽���펞�Ɉ�����������鑼�A�����ɕK�v�ȍŒ���̓d�͂��������A���C�t���C�����m�ۂ���Ƃ������̂��B2016�N1������A���������̊w�Z��a�@�Ƃ��������ꏊ�𒆐S��100���ݒu�\��ŁA2017�N�ȍ~���������ȊO�̔�Ќ��w����ւ̐ݒu����������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�ALED(�X�H����V�����B�i�����ɂ���31���̐ߓd������ ���Ђ͊X�H���̐V�V���[�Y�������B���邳��200�`(���ⓔ100�`����) �A500�`(���ⓔ250�`����)�A1000�`�i���ⓔ400�`�����j��3�^�C�v�B�z���͍L������̑S���z���^�C�v�A�ʘH�����̃��C�h�z���^�C�v�A�G���g�����X�����̃t�����g�z���^�C�v�̌v3�^�C�v�����C���A�b�v�����B �L��E�����E���Ǝ{�݁E�w�O�ȂǏƎ˂��������ꏊ�ɉ����Ĕz�����ł��܂��B�Ɩ����ɓ������ꂽ�����^�C�}�[��ݒ肷�邱�ƂŁA�_����A�����^�C�}�[�ɂ��i������50���A30���A0��(����)��3�p�^�[���̒�����ݒ�ł��A��31���̐ߓd��}���B ��]�������i�i�Ŕ��j220,000�~�`298,000�~�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���d�͉�Ђ̎��v���P�������A�㔼���̉c�Ɨ��v��1���~���� 2015�N�x�㔼���̓d�͉��10�Ђ̌��Z���܂Ƃ܂����B���㍂�����v�����9��8570���~�ŁA�O�N����2.8%��������10���~�����荞�B���̈���ʼnc�Ɨ��v��2�{�ȏ�ɑ�����1���~�����B�ꕔ�̒n��������Ĕ̔��d�͗ʂ��������Ă���ɂ�������炸�A���v�̉��P���}���ɐi��ł���B �ő��̓����d�͂�3850���~�̉c�Ɨ��v���グ���̂��͂��߁A�����d�͂�2276���~�A���d�͂�1757���~�ŁA3�ЂƂ��ɑO�N�x����1000���~���鑝�v���ʂ������B ������LNG�i�t���V�R�K�X�j�̗A�����i��1�N�Ԃɔ��l�߂��܂ʼn����������߂��B�בփ��[�g��2���قǏ㏸�������̂́A����ȏ�̉��i�ቺ�Ŋe�Ђ̔R�����傫�������������B���q�͔��d�����ĉғ����Ȃ��Ă����v���o����ɂȂ��Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u������v�Œu���������������鐅�ⓔ �u������v�͐������̂��u����Ɋւ��鐅�����v�Ƃ����B2013�N�ɍ̑����ꂽ�B�����ł́A������܂ސ��i�̐�����A�o����2020�N�܂łɌ����֎~����Ƃ���Ă���B�ΏۂƂȂ�͍̂�������i���C�j���d�����v�iHPMV�j�̔̔��������֎~�ƂȂ�B �o�͖ʂł̎�_�����P����A�\���ȏƓx�������A���p���ł��鐻�i�Q���o������Ă����B�u���V��pLED�Ɩ��v�����i�W�������Ƃ��Ċm�����Ă����B����������v�ɔ�ׂāA����d�͂�3����1����4����1���x�ɁA������4�`6�����Ԃƒ������A�u���_���A�����⒲�F�A�]�[���R���g���[���ȂǁALED�̋��݂��ł���悤�ɂȂ��Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����ȁu�G�R�`���[�j���O�ɂ��Ɩ��p�����z���̒�Y�f���E�R�X�g�팸�Z�~�i�[�v�J�� �Z�~�i�[�́A�Ɩ��p�����z���́u�G�R�`���[�j���O�v�ɂ��팸���ꂽ���M�������v���グ��r�W�l�X���f���̊m����ڎw���s������̂ŁACO2�팸��R�X�g�팸���̌��ʁA�Z�p�Ҏ��i�F�萧�x�E���ƎҔF�萧�x�ƃr�W�l�X���f���̊T�v�A����̓W�]�����Љ���B �u�G�R�`���[�j���O�v�Ƃ́A�Ɩ��p���̌��z������r�o����鉷�����ʃK�X���팸���邽�߁A���z���̉��K����Y�����m�ۂ��A�ݔ��@��E�V�X�e���̓K�ȉ^�p���P�����s�����ƁB �Z�~�i�[�̊J�ÊT�vhttps://www.env.go.jp/press/101692.html 2016�N1��15������2��18���B�S��9�J���ŊJ�ÁB�Q����͖����B���O�\�����݁B����ƂȂ莟��t���I���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������������ナ�`�E���d�r�i�V���R���|�����d�r�j�̎��p���Z�p�i�W GS���A�T�́A�����ɍނɗ����ƃV���R����p���A�G�l���M�[���x���]���̃��`�E���C�I���d�r�Ɣ�r����3�{�Ƃ��������\�Ȏ�����d�r�̎��p���Ɍ������J����i�߂Ă���B ���̒��ŏ�ǂ�1������������p���鐳�ɍނ̉ۑ���������A�[���d�T�C�N�����\�����I�ɍ��߂邱�Ƃɐ��������B����͏]���̃��`�E���C�I���d�r�Ɣ�r���āA��荂���G�l���M�[���x����������d�r�̎��p���ɂȂ���B �����̗��_�e�ʂ�1675mAh/g�ƁA�]���̃��`�E���C�I���d�r�p���ɍޗ��Ɣ�r���āA���ɍ����B���Ђ����ɍނɗ��p��������-���E���J�[�{�������̗̂��_�e�ʂ�1000mAh/g���B�������A�[���d�T�C�N���ɔ����e�ʂ��傫���ቺ���Ă��܂������̎��p���̕ǂƂȂ��Ă����B ����A�J�`�I�����������Z�p���[�^�ɗp���邱�ƂŁA�[���d�T�C�N���ɔ����e�ʒቺ���~�߂邱�Ƃɐ��������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������s�������̃o�C�I�K�X�����������f�������T�[�r�X ���s�̒����������Z���^�[�ł́A���t������p�Ԃɐ��f���������A���\�]�������Ă����B���̓x�A��ʂ̔R���d�r�Ԃɒł���̐������������߁A2016�N3�����܂Ŏ�����������B �����4������͏��p�̐��f�X�e�[�V�����Ƃ��Đ��f��̔�����v�悾�B���������̊��Ԓ��͐��f1kg������1,100�~�̋��͋�������ق��A���s�f�[�^�̒�o���`���Â���B ���s�����Ƒ��s�ꏊ�A��Ԑl����G�A�R���̍쓮�Ȃǂ̃f�[�^���W�āA���f�X�e�[�V�����ƔR���d�r�Ԃ̐��\�]���ɖ𗧂Ă�B �����������Z���^�[�ł́A1����2400�������[�g���̃o�C�I�K�X����3300�������[�g���̐��f�����邱�Ƃ��ł���B���̐��f�����k������ԂŔR���d�r�Ԃɏ[�U����B�����o�C�I�K�X����1����65�䕪�̐��f���������邱�Ƃ��ł���B �����������Z���^�[�̓o�C�I�K�X�̔����ʂ��������Ƃ���A���f�̐����̂ق��ɔ��d�ɂ����p����v���i�߂Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���v�V�I�u�i�m���b�g�v�������Ɖ��֓��k��x���`���[��ݗ� �x���`���[��Ɓu���k�}�O�l�b�g�C���X�e�B�e���[�g�iTMI�j�v�́A���Ԋ��5�Ёi�A���v�X�d�C�ANEC�g�[�L���AJFE�X�`�[���A�p�i�\�j�b�N�j�A���c���쏊�j�̏o�����ݗ����ꂽ�B �v�V�I��������́A�Ɠd�E�Y�Ɨp���̓d�C���i�ɂ����āA�]���p�����Ă����P�C�f�|�ɑ���V�f�ނł���A�G�l���M�[������1/2�`1/4�ɒጸ�ł������I�ȋ����ޗ����B �{�����̓g�����X��[�^�Ƃ��������i�ɗ��p����A�啝�ȃG�l���M�[����̍팸�Ɋ�^����Ɗ��҂���Ă���B �u�i�m���b�g�v�̐��\���X�Ɍ��コ���A�����Y�������߂��v�V�I�i�m���������̊J���E���p���y�ѐ����̔����s���B�����āA�o�����5�Ђ������̔��т╲�����g�p�������i�̊J���ɓ�����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���ăG�l���Ǝ҂Ȃǂ��x������u�ăG�l�R���V�F���W���v�T�[�r�X���J�n�����G�l�� �����́A�ăG�l�ɂ�锭�d���ƁE�M���Ƃ����悤�Ƃ��鎖�Ǝ҂⎩���̂��A�����ŃT�|�[�g����B3�̃v���O��������Ȃ�B �@(1)�ʑ��k�T�[�r�X�͎��Ǝ҂⎩���̂̑��k�ɓ�����B�ʖʒk�ɂ�鑊�k�Ή���S��9�J���ōs���B �@(2)�o�����k��T�[�r�X�͌ʑ��k���s���e�ӏ��ɑ����^�Ԃ̂�������Ǝ҂⎩���̂̑��k�ɂ����L�������邽�߁A�S��25�J���ŊJ�Â���B �@(3)�Č��`���x���T�[�r�X�́A�Đ��\�G�l���M�[�̎��Ɖ����������Ă���ꍇ�ɁA�ăG�l�R���V�F���W���͎��Ɖ��Ɍ����������A���c�A�葱���Ɋւ��鏕�����s���ƂƂ��ɁA���Ɖ��܂ł̍s���쐬�̎x�����s���B �ăG�l�R���V�F���W�����Č��`���x�����s�����ƌv��͌���ɂ�茈�肷��i�S��20�����x�j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2014�N�x�̉������ʃK�X�̔r�o�ʂ́A�O�N��3.0�����i����l�j ���Ȃƍ������������́A2014�N�x�̉䂪���̉������ʃK�X�r�o�ʁi����l�j�����\�����B2014�N�x�̑��r�o�ʂ�13��6,500���g���ŁA�O�N�x��3.0%���i2005�N�x��2.2%���A1990�N�x��7.5%���j�������B �O�N�x�̑��r�o�ʁi14��800���g���j�Ɣ�ׂ�ƁA�d�͏���ʂ̌����i�ȃG�l���j��d�͂̔r�o���P�ʂ̉��P�i�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��E�R���]�����j�ɔ����G�l���M�[�N����CO2�r�o�ʂ������������ƂȂǂ���A3.0%�i4,300���g���j���������B �܂��A2005�N�x�̑��r�o�ʁi13��9,600���g���j�Ɣ�ׂ�ƁA�I�]���w�j������̑�ւɔ����A��}����ɂ����ăn�C�h���t���I���J�[�{���ށiHFCs�j�r�o�ʂ�������������ŁA�Y�ƕ����^�A����ɂ�����G�l���M�[�N����CO2�r�o�ʂ������������ƂȂǂ���A2.2%�i3,100���g���j���������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���u���Ԃ��v�̊ϑ��f�[�^�Ɋ�Â����ʓ�_���Y�f�̑S��C���ϔZ�x�͖�398.8ppm �������ʃK�X�ϑ��Z�p�q���u���Ԃ��v�̊ϑ��f�[�^���g���āA�n�ォ����܂ł́u�n����C�S�́i�S��C�j�v�̓�_���Y�f���ϔZ�x���Z�o�����Ƃ���A���ʕ��ϔZ�x�͋G�ߕϓ������Ȃ���N�X�㏸���A����27�N5���ɖ�398.8ppm���L�^�����B���̂܂܂̏㏸�X���������A���ʕ��ϔZ�x�́A�x���Ƃ�����28�N����400ppm���錩���݂��B ����́A�u���Ԃ��v�̊ϑ��ɂ���Ēn����C�S�̂̕��ϔZ�x��400ppm�ɋ߂Â����Ƃ����߂Ď������ƂɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2015/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���x�m�o�ς��֘A�@��E�V�X�e���̍����s�꒲�����ʂ\ �֘A�V�X�e���́A��}�K���≷�����ʃK�X�̔r�o�}���̂��߁A���\�������P���i�߂��Ă���B �����ł́A�G�A�R���Ȃǂ̔M���@��9�i�ځA�G�A�n���h�����O���j�b�g�iAHU�j�Ȃǂ̋@��13�i�ځABAS/BEMS�Ȃǂ̏ȃG�l�E����@��E�T�[�r�X��5�i�ڂ̎s���ΏۂƂ����B2014�N�̉��u�Ď��T�[�r�X�̎s���157���~�ƂȂ����B2015�N4���ɉ����t�����r�o�}���@�{�s�ɂ�����_�����`�������A���[�J�[��T�[�r�X���Ǝ҂̉��u�Ď��T�[�r�X�ɂ��G�l���M�[�����@��s��́u�����鉻�v�̒�Ă��i��ł��邱�Ƃ���A2020�N�ɂ�2014�N���18.5%����186���~�ɂȂ�Ɨ\�������Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���쑺�������d�͏����莩�R���̉e�������\ �d�͉�Ђ̏�芷���v���Ƃ��ẮA�u�d�C�����v�A�u�G�l���M�[���v�A�u�葱���̗e�Ղ��v�A�u���S���v�A�u���сv��5���ڂŒ��������B ���̌��ʁA�ł��d������Ă���̂́u���i�i�������j���[�E�Z�b�g�������j�v�ŁA46���B����ɑ����̂́A�u�V�d�͉�Ђɑ�����S���i�M���x�j�v15���A�u��ւ��̎葱�����e�Ձv15���A�u�V�d�͉�Ђ̃T�[�r�X���сv��14���A�u�d�͔����������R�G�l���M�[�i���z���E���͂Ȃǁj�v��10���������B �d�C������5���̒l�������ł͏�芷���ӌ��������т�3���ɑ��āA10���̒l�����ł�16���������B���z���Z����ƁA5���l�����Ŗ�1,800���~�A10���ł́A��8,900���~�Ɛ��v�����B �o�T�uHARBOR BUSINESS �v |
|
|
| ���g�d�C�ƃK�X�h���œK�Ɏg�������ȃG�l�ɁA���u������\�ȃ}���`�V�X�e�� �����K�X�A���K�X�A���M�K�X�A�p�i�\�j�b�N��4�Ђ́A���ԑтɉ����ăK�X�Ɠd�C���g����������V���ȋƖ��p�V�X�e���u�X�}�[�g�}���`�v�̊J����i�߂Ă���B����ɓ��V�X�e���̉^�]���œK�ɉ��u����ł���T�[�r�X�uENESINOFO�i�G�l�V���t�H�j�v���J�����A2016�N4������̔����J�n����B �X�}�[�g�}���`�̓K�X�q�[�g�|���v�Ɠd�C���[�^�q�[�g�|���v���}�n���ɑg�ݍ��킹���V�����R���Z�v�g�̋Ɩ��p�V�X�e���ŏ��߂āh�d�C�ƃK�X�̃n�C�u���b�h���h�����������B ���O�@��GHP20�n�͂�EHP10�n�͂�g�ݍ��킹�����̂�1�Z�b�g�Ƃ��A1�̉��u�A�_�v�^�[�ɍő�8�Z�b�g�܂Őڑ��ł���B�G�l�V���t�H�́A�X�}�[�g�}���`������W�����G�l���M�[�g�p�ʂ�^�]�f�[�^�Ȃǂ̏���A�G�l���M�[�����A�G�l���M�[���i�i�d�C�����E�K�X�����j�Ȃǂ̃f�[�^�����ƂɁAGHP��EHP���œK�ȉ^�]�䗦�ʼn^�]����悤���u�Ő��䂷��V�X�e�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���g���^�����ԁA�u���`�������W2050�v����A2050�N�̐V��CO2�r�o��90���팸 �u�g���^���`�������W2050�v�́A�����\�ȎЉ�̎����ɍv�����邽�߂̐V���ȃ`�������W�Ƃ��Ĕ��\�����B 3�̗̈��6��ނ̃`�������W���f�����B3�̗̈��1�ڂ́A�u�����Ƃ����N���}�v��2050�N�O���[�o���V�ԕ��ϑ��s��CO2�r�o�ʂ�90���팸�i2010�N��j�B�e���n�掖��ɉ��������g�p�ʂ̍ŏ����Ɣr���̊Ǘ��B2�ڂ́u�����Ƃ������m�Â���v��2050�N�̃O���[�o���H���CO2�[���Ɛ����C���p�N�g�̍ŏ����B3�ڂ́u�������E�����Љ�v�ŁA�z�^�Љ�E�V�X�e���\�z�ƁA�l�Ǝ��R���������関���Â���Ƃ����B ���`�������W2050�̎����Ɍ��������ʂ̎��s�v��Ƃ��āA��6���u�g���^����g�v�����v��2016�`2020�N�x��5�N�ԓW�J����B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ������^�̏��ƃr���ɒ~�d�r�ƍ������X�|���X�V�X�e���œd�͏���ʂ�N��35���팸 �W�����\���R���g���[���Y���A�V�J�S�ɂ���}�[�`�����_�C�Y�}�[�g�ɕ��U�^�G�l���M�[�����Z�p��[�����A�o�b�e���[�Z�p�ƃr���Ǘ��V�X�e���̉^�p�m�E�n�E�̒��J�n�����B ���r���̓e�i���g���������Ǝ{�݂ŁA���ʐϖ�39���������[�g���ŁA1���ɂ��悻2��5000�l�����p����B ����A�V���ȃG�l���M�[�����\�����[�V���������p���邱�ƂŁA���X�ƕω�������v�ɉ����ēd�͏��������ȂǁA��荂�x�ȍ������X�|���X�v���O�����ɂ��\�ƂȂ����B�܂��A���{�݂Ɋ��ɓ�������Ă��铯�Ђ̃A�N�e�B�u���[�h�}�l�W�����g�X�g���e�W�[�ƍ����������U�^�G�l���M�[�����Z�p��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�{�ݑS�̂̔N�ԓd�C�g�p�ʂ�啝�ɍ팸�ł��錩���݁B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���J�l�J�����ʓd�ɂŕϊ�����25.1���̃V���R�����z�d�r���J�� ���Ђ́A�ϊ��g���悪�L����A�ϊ����������߂��闼�ʓd�Ɍ^�w�e���ڍ������V���R�����z�d�r�Ƃ��āA�Z���ϊ�����25.1�������p�T�C�Y�ɑ�������5�C���`�̃Z���T�C�Y�ŒB�������B���Ђ͊��ɁA����^��6�C���`�̃Z���T�C�Y�ł��Z���ϊ�����24.5����B�����Ă���B �����̐��ʂɂ͓��Ђ̍��i���A�����t�@�X�V���R����p���������V���R����̕\�ʌ��גጸ�Z�p��A�����b�L�@�ɂ��d�Ɍ`���Z�p�Ȃǂ����p���Ă���B NEDO�ɂ�����̐��ʂ͍����������V���R�����z�d�r�̎��p���ɑ傫����^����Ƃ��Ă���B����A�J�����ʂ����p���ăp�C���b�g���Y�ݔ����\�z����Ƃ��ɁA���d�Ƀw�e���ڍ������V���R�����z�d�r��2015�N�x���ɔ̔�����v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���������f�V�J���g�V�X�e�����J���|���H���X�ƃN�{�^ �������V�X�e���͑S�M�������W���[����z�������W���[���Ȃǂō\���B�z�������W���[���ɂ͍��E2�̋z�����u���b�N������A��荞�O�C�Ɣr�C�̗��H���ւ��\���B ���̂��߁A�]���̃f�V�J���g�V�X�e�����ݒu�e�ς�35�����^�������B�S�M�������W���[���ŊO�C�������̔r�C�ƔM��������B���M�ɑ��z�M���g�����������A��p�ɒn���M���g�����␅���g�p����B�]���̗≷�����g�p���������Ɣ�ׁA�O�C����������30�����シ��B �~�`�̉�]�̂��g���]���^�̃f�V�J���g�V�X�e���Ɣ�ׁA���^���ƕ��U�ݒu���\�Őݒu�e�ς����点��B�R�X�g���~�`�̉��H��s�v�ɂȂ�20���팸�ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���n��̔p�����A�n��ł����d�͂ɕ��Ɍ��̍��������ݔ��d�� �^�N�}�G�i�W�[�i���Ɍ��j�́A���ݒ��̔p���������{�݁u�N���[���p�[�N�k�A�i�ق�����j�v���甭������]��d�͂��w���������_����A�k�A�s�������g���ƒ��������B���{�݂��^�]�J�n�����2016�N8������d�͂��w������\�肾�B ���̎{�݂́A���T�C�N���Z���^�[����сA���d�o��2,850kW�̍��������ݔ��d�{�݂�����A���n��̈�ʔp�������G�l���M�[�Ƃ��ēd�͂ݏo���B���Ђ͂��̓d�͂����A�n����̌����{�݂�H�ꓙ�Ɉ����ɋ�������B�n��̔p������d�͂Ƃ��Ēn��ɊҌ����邱�ƂŁA�p���������{�݂ɑ���n��Z���̗��𑣐i��A�z�^�Љ�̍\�z�A�y�ѓd�C��팸�Ɋ�^����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȐΒY�Η͔��d���̔��d�����K�������� �����\�̐ΒY�Η͔��d���𑝂₷���ƂŁA���d�R�X�g�������ΒY�Η̗͂��p�Ɠ�_���Y�f�iCO2�j�̔r�o�ʂ̍팸�ɂȂ���B�܂��A�V�����������d���̌��đւ��𑣂����Ƃł��r�o�ʂ̍팸�ɂȂ���B �����ł�2016�N4������̓d�͏�����̑S�ʎ��R���ŁA���K�͂ȐΒY�Η͔��d���̌��v�悪�������ł��邽�߁A�����������ݔ��̐V�݂�}����_��������B �V�����ɂ́A�ŐV�Z�p���Q�l�ɐ��l���ݒ肷��B�ғ����̔��d���ɑ��Ă����l��������グ�āA�������Ȃ��ꍇ�͉��P�����߂�B2016�N3���܂łɊW�ȗ߂Ȃǂ�����������j���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���������ʃK�X�팸�ڕW�`���������肩�H �Q�������ӂ�D�� 11�����ɊJ�×\���COP21�Ɍ������Ō�̓��ʍ�ƕ���A�h�C�c�E�{���ŊJ�������B ���ĉ��⒆���Ȃǂ̎�v�r�o�����܂�147�J���E�n���1���܂łɁA2030�N����܂ł̍팸�ڕW���o�����B���E�̑��r�o�ʂ̖�9���ɑ�������B ����̐V�g�g�݂ł́A���E���̑S�Ă̍����Q����������I�ȑ̐��Â����ڎw���Ă���B �������A�������팸���[�����ۂ��A�č��̔����A���ΔR���̏���ɕq���ȎY������A���y���v�̊�@�ɂ��铇�ׁi�Ƃ�����j���ȂǓr�㍑�Ԃł��ӌ��̊u����͑傫���A�c�_���������鋰�������B ���̂��߁A�V�g�g�݂́A�S���͂͊ɂ₩�ŁA�e����2050�N�ȍ~�̒����I�ȍ팸�ڕW���f���A5�N���ƂȂǒ���I�ɍ팸���𑝂₷�ĂȂǂ����サ�Ă���B �o�T�u�Y�o�j���[�X�v |
|
|
| �����Ȃ��A�����r���̏ȃG�l���C���ʂ������f�f�A�A�h�o�C�X���Ƃ����{ ��W�́A���łɉ��C�����I�������Ə��̐f�f���s���u���C����f�f�v�Ɓu����25�N�x���͕���26�N�x�O���[���r���f�B���O���y���i�Ɍ��������C���ʃ��f�����ƈϑ��Ɩ��v�ɂ����ĉ��C�O�̐f�f�������Ə��ƁA�ߋ����N�Ԉȓ��ɏȃG�l���C�������{�������Ə���ΏۂƂ���B�������A��҂ɂ��Ă͎��Ə����ȃG�l���C�������{����O�̃f�[�^�i�G�l���M�[�g�p�A�ݔ��̉^�p�Ɋւ��鎑�����j��L����ꍇ�Ɍ���B ���̎��Ƃ̈ϑ���ł���O�H�������������A�u�����r�����C���ʃ��f�����Ɓv�Ƃ��āA�f�f����]����r���̌��储��ю����f�f�����{����f�f�@�ւ̌�����J�n�����B �o�T�uMRI�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����E�ΒY�����{�͍ʼn��ʁc�Η͐V�ݑ������m�f�n��i���]�� �p���̔{�g�D�iNGO�j�uE3G�v�́A��i7�J���iG7�j�̑��ʂ̓�_���Y�f�iCO2�j��r�o����ΒY�Η͔��d����̒E�p�x��]��������\�����B ���ɂ��ƁA�V�v�恤�����{�݂̕��������ȂǍ��ۓI�ȉe��??�̎O�̕���ŕ]���B���̌��ʁAG7�̒��ŗB��V�݂𐄐i������A�r�㍑�ɐΒY�Η͊֘A�̎����������肷����{�́A�S�Ă̕���ōł��������тƂȂ����B�V�v�悪�������ł�����{�͍ʼn��ʂƂȂ����B1�ʂ͘V�����{�݂̕����i�ޕč��ƂȂ�ȂǁAG7�e���ŒE�ΒY���i�ޒ��A���{�̑Ή��̒x�ꂪ�N���ɂȂ����B ����A�ΒY�䗦���Ⴂ�t�����X���č��ɑ����ACO2�r�o�}���̂Ȃ��V�݂�F�߂Ȃ����Ƃ����Ă���p����3�ʂȂǂƂȂ����BE3G�́u���{�͍Đ��\�G�l���M�[�ւ̓�����i�߁A�ΒY�Η͂̐V�݂���߂�Ƃ����ł���{�I�Ȏ��g�݂���n�߂�K�v������v�Ƌ�������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���Đ��\�E�댯���i�V�́u�}�O�l�V�E���R���d�r�v ������G�l���M�[�Ƃ��Ē��ڂ���n�߂��f�ނ͒n���ɖL�x�ɂ���}�O�l�V�E���ƁA����𗘗p�����}�O�l�V�E���R���d�r���B ������I�[�X�g�����A�̍����n�тō~�蒍�����z�G�l���M�[���g���āA�����ɖ��s���ɂ��鉖���}�O�l�V�E��(���Ɍ����u�ɂ���v)����}�O�l�V�E���B�B���̉ߒ��ŃJ���V�E���������ē�R�������}�O�l�V�E�������ɂ́A��ʂ̃G�l���M�[���`���[�W�����B���������n�ɉ^��Ő��ɐZ���ƁA���ߍ��܂�Ă����G�l���M�[�����o����A���d�ɗ��p�ł���B�G�l���M�[����o����������ɂȂ�����_���}�O�l�V�E���́A�Ăэ����n�тɉ^��A���z�̌��Ő��B�B�G�l���M�[���ă`���[�W�����B���f�̂悤�Ȕ����̊댯���͂قڃ[�����Ƃ����B ���k��w���_�����̏��_����ƌÉ͓d�r�A�ʔň���̋����J���ŏ��i�����ꂽ���̃}�O�l�V�E����C�d�r�́A���ɂɎ_�f����荞�ޒY�f�V�[�g�A���ɂɃJ���V�E�����������}�O�l�V�E�������̔��g�p�B2L�̓d���t(���܂��͊C��)�����e����̃|���^���N�ɒ����ƁA3����ɂ͔��d���n�܂�A�ő�Ŗ���300W��5���ԘA���Ŕ��d�ł���B����́A�X�}�[�g�t�H�����ő�30��[�d�ł���d�͂ɑ�������B �o�T�u����r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȋƖ�����̏ȃG�l�x���`�}�[�N�w�W�ݒ�A�܂��R���r�j���� �ȃG�l�x���`�}�[�N���x�ł́A����Ǝ���ŏȃG�l���r���邽�߂̎w�W�ƁA�ڕW�����l��ݒ肷��B �ȃG�l���i��ł��鎖�Ǝ҂�]���������A�x��Ă��鎖�Ǝ҂ɓw�͂𑣂��ړI�B�Ɩ�����ł͍�N�A�܂��S�ݓX�A�X�[�p�[�A�I�t�B�X�r���A�R���r�j�A�V���b�s���O�Z���^�[�Ȃ�6�Ǝ�ɓ������邱�Ƃ����܂�A�w�W�Ȃǂ̌�����i�߂Ă����B ���������G�l���M�[������H�ꓙ���f����[�L���O�O���[�v�ł܂��R���r�j������|����B�u�`�F�[���̑S�X�܂ɂ����锄�㍂������̓d�͎g�p�ʁv�Ƃ����x���`�}�[�N�w�W�Ă�ڕW�����l�̈Ă����������݁B�ڍׂ��ł܂����Ǝ킩��x���`�}�[�N���x������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2015/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���u������t���C�z�C�[���~�d�V�X�e���v�Ƒ��z�����d�Ƃ̘A�n���؎������J�n ���V�X�e���́A�R�����A�S�������������A�N�{�e�b�N�Ȃǂ��Q�����ĊJ�������B �t���C�z�C�[���~�d�V�X�e���Ƃ́A���u�̓����̑�^�̉~�Ձi�t���C�z�C�[���j�����[�^�[�ʼn�]�����邱�Ƃɂ��d�͂��^���G�l���M�[�Ƃ��Ē������A�K�v�ɉ����ĉ�]�͂��Ăѓd�͂ɕϊ�����V�X�e���B�o�͂�300kW�A�~�d�e��100kWh�A�t���C�z�C�[���i�d��4�g���A���a2m�j���A�ō�6,000��]�^���ʼn�]����B���d�����C����ɂ���ڐG�ŕ��コ���邽�߁A���������Ȃ��A�����Ԃ̈��肵���^�p���\�Ń����e�i���X��p���팸�ł���B �����̕đq�R�̖�1MW�̑�K�͑��z�����d���ƌn���A�n�����A�V��ɂ���ĕϓ����Ă��A�d�͂��z�����Ĉ��艻����������؎������s���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Z�F�d�@�H���������D�����œd�͏����3����2�ɗ}���閌���W���[�����J�� �������������D�����͒������g�����������@�ŁA�펞���C���Ė���U��������K�v������B���̂��ߑ傫�ȓd�͂�v����B �����ׂ͍�����@�ۂ̕\�ʂɔ��ׂȍE��������������߃t�B���^�[�ŁA���Ђ��J������PTFE�i�|���e�g���t���I���G�`�����j�����́A�����_��ɂ�薌���h��₷���A�P��f�ނō��ꂽ�����Ƃ��ẮA���̑f�ނ̖��Ɣ�ׂ�8�`10�{�̋��x������B���̏_��Ƌ��x�������߁A�ʏ�͍ő�2���[�g���قǂ̖��̒�����3���[�g���ɒ��ډ����A�U����傫���ł��A�����͂��啝�Ɍ��サ���B �܂��A���������x�ɔz�u���邱�Ƃɂ��A�����W���[��1�䓖����̂�ߖʐς��ő��60�������[�g���Ɗg�傷�邱�Ƃ��ł����B���̌��ʁA������������̔��C���ʂ������邱�Ƃ��ł��A�啝�ȏȃG�l���\�ɂȂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��7���̑�s�s���̓d�͔̔��ʂ��啝�Ɍ����A����5.4�����A��4.3���� �S���̓d�͉�Ђ�7���̔̔��d�͗ʂ�����ƁA��s�s���قnj��������傫���Ȃ��Ă���B�����̗������݂́A�ƒ�����́u�d���v���O�N�Ɣ�ׂ�6.3���A�I�t�B�X�����́u�Ɩ��p�v��7.7�����������B �I�t�B�X�����ł͊�Ƃ⎩���̂��V�d�͂�ւ���P�[�X�������Ă���B�Ɩ��p�̔̔��ʂ͉���ȊO��9�n��őO�N����������B���������傫���͓̂����A�k�C���A����3�n��ŁA�d�C�����̍����n�悾�B����A���k�E�k���E����͑O�N������̔��d�͗ʂ��L�^�����B��������ƒ�����̓d���̎��v���L�тĂ���B�k�C���ƒ����ł��d���̔̔��ʂ͑O�N�������������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����f�R���֘A�s���2030�N�ɂ�5447���~�Ɋg��Ɨ\�z�x�m�o�� 2014�N�x�̎s��K�͂�83���~�ɂƂǂ܂邪�A2030�N�x�ɂ�66�{��5447���~�ɂ܂Ŋg�傷��Ɨ\���B 2014�N12���ɔR���d�r�ԁuMIRAI�i�~���C�j�v�̎s�̂��n�܂�A�o�ώY�ƏȂȂǂ̐��f�����ݔ��ݒu�⏕���Ƃ��㉟�����A2015�N�x���܂ł�100�J������������j�������Ă���B ����������̒������ʂł�2016�N�x���܂łɗv��100���ŁA���{�v�����1�N�x���Ƃ����\�����B2020�N����ɔR���d�r�Ԃ̖{�i�̔����n�܂� �A�s��͑傫���g�債�A2030�N�x�ɂ͗v��1000����̐��f�X�e�[�V�������ݒu�����Ƃ̗\���Ŋ֘A�s���2014�N�x��5.9�{�ƂȂ�479���~�Ɋg�傷��Ƃ����\�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���u�ԃN���W�b�g���x�iJCM�j�v�����p���ĊC�O�H��ɏȃG�l���� �ԃN���W�b�g���x�𗘗p�����v���W�F�N�g�ݔ��⏕���Ƃɍ̑������ƁA����������1/2���⏕�����B��ƂɂƂ��Ă͐��x�����p���邱�ƂŊC�O�H��̐ݔ������̑��i�ɂȂ���B �@�\�j�[�̓^�C�̔����̍H��ɂ�����ȃG�l�^�Ⓚ�@�Ƌ�C���k�@�̓������̑����ꂽ�B�N644�g����CO2�팸�������ށB �@�������̑����ꂽ�̂̓^�C�̐D���H��ŏȃG�l�^�D�@�ɍX�V�ŁA�N646�g����CO2�팸�������ށB �@���R�[�̓x�g�i���̃����Y�H��ɏȃG�l�^�ݔ��̍X�V�ŁA�z��팸�ʂ͔N161�g���ɂȂ�B �o�T�u������ƃj���[�X�v |
|
|
| ���������g�����ȃG�l�ԗ��𓊓��B1�Ґ�10����1��180kWh���팸 2010�N10������^�]���s���Ă��鎟����ԗ����A�ꕔ�v�ύX�����ȃG�l�ԗ��̉c�Ɖ^�]���J�n�����B �ύX�_�́A�܂��A�Ɩ���ݔ��Ȃǂ̌𗬋@��ɓd�͂���������u�⏕�d�����u�v�����������B�����u�͕Ґ�������5����1����t�����Ă��邪�A�g�p�d�͂����Ȃ�����1����~���A���n���̓d���ϓ��������邱�ƂŁA1��ʼn^�]�ł���u����/�x�~�^�]�����v���J���A���������B��H�ɂ͍�������SiC�f�q���̗p���A1�����ϖ�48kWh�̏ȃG�l���ł����B ���̂ق��ɁA�q������O�Ɠ��Ȃǂ��ׂĂ̏Ɩ���LED���̗p���A��1�����ϖ�52kWh�̏ȃG�l�B�܂��A���[�^�[��H�Ɏg�p���Ă��郊�A�N�g���ɁA�d�C��R�����炵�����R�C���`���A�N�g�����̗p���āA1�����ϖ�80kWh�̏ȃG�l���ł��A1�Ґ�1���Ōv180kW���̓d�͍팸���ł����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��CO2�g�p�̐V��p�V�X�e���ň������̋@��啝�ȃG�l�@�x�m�d�@�A�f���\�[ CO2��}�͈��k���͂������A�R���v���b�T�[�̕��ׂ������Ȃ��肪�������B�����ŁA�f���\�[�ŊJ�����ꂽ�V��}�������u�ŁA�]���̂Ă��Ă����G�l���M�[�����k�G�l���M�[�Ɋ��p���邱�ƂŁA�Ⓚ���������߁A����d�͗ʂ�啝�ɍ팸���邱�Ƃɐ��������B �V��}�������u�̓J�[�G�A�R����ƒ�p�q�[�g�|���v������u�G�R�L���[�g�v�Ɏg�p����Ă����B���߂Ď����̔��@�Ɏg�p����A�啝�ȏȃG�l�ɐ��������B�]���̒P�Ȃ�CO2��}�̎��̋@�Ɣ�ׂăG�l���M�[����������p���[�h��45���A���M���[�h��24�����サ�A�N�Ԃ̏���d�͗ʂ�25���팸�ł���B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���ۍg�ƒ�g���A�y�V���ሳ���v�ƌ����d�͏�����ɎQ�� ���Ђ́A��N����d�͎���g���Ȉ�HEMS�i�ƒ�p�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���j�̋����J���ȂǂɎ��g��ł����B����A�u�y�V�s��v�̏o�X���Ǝ҂�u�y�V�g���x���v�ɉ�������h���{�݂Ȃǂ̒ሳ���v�ƂɊۍg���m�ۂ��Ă���Đ��\�G�l���M�[�Ȃǂ̓d�͋����ƃ|�C���g���p���σT�[�r�X�ȂǐV���ȃT�[�r�X�̊J����i�߂Ă����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��AI(�l�H�m�\)���ڂ�BEMS���J���A���؎�����ȃG�l�x���T�[�r�X�W�J�\�� �����M�w�́A�e�Ђ̐V�^�����Z���T�[�B���A�H��̋@�B�⌚���̒n�_���Ƃɐݒu����B�����x�A�d���A��_���Y�f�A�Ɠx�A���ʁA�U���̃f�[�^�����W���A�@�B�̎g�p�d�͂⌚�����̉��x�̃����Ȃǂ����A���^�C���ɔc���ł���BAI���L���Z���T�[���܂ރf�[�^����́E�]�����ċ@��̉^�]���@�̉��P�����B�N�Ԑ����̏ȃG�l���ł���Ƒz��B ����A�a�@�A�w�A�H��ȂǂŎ��؎��������{���A�H���r���̏���G�l���M�[���팸����T�[�r�X��2016�N�x�Ɏn�߂�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������s�A�N���E�h�������ȃG�l�f�[�^�Z���^�[�̗��p�ɕ⏕������t �����s���̒����K�͎��Ə��ɂ����ĉ^�p����Ă�����V�X�e���Ȃǂ��A�G�l���M�[�����̍����f�[�^�Z���^�[�𗘗p�����N���E�h�T�[�r�X�Ɉڍs����̂ɕK�v�Ȍo��̈ꕔ����������B �������́A�f�[�^�Z���^�[�̊����x���ɂ��A�o���1/6�i���x�z750���~�j��1/3�i���x�z1500���~�j �i�\�Z�z�F6.75���~�i����ɒB������I���j�j��ȏ����Ώۏ��� �@�@�E�ΏۂƂȂ���V�X�e�����͎��ЂŕۗL�����Г��ʼn^�p���Ă��邱�� �@�@�E�N���E�h�T�[�r�X�Ɉڍs���邱�ƂŎ��Ə��̃G�l���M�[�g�p�ʂ��팸����邱�� �@�@�E���Y�N�x���̒n�����g��������s�ɒ�o���Ă��邱�� ��W����2015�N11��24���i�j����2017�N1�����܂�http://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/cloud/ �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA���`�E���d�r�ɑ���V�����d�r�̌����J�� ���s�̃��`�E���C�I���d�r�͌��݂�2�{���x�̗e�ʂ����E�̂��߁A��e�ʁA��R�X�g���̂��߂ɂɑS���V�����~�d�r�Z�p�̊J�������߂��Ă���B 2030�N�x�܂łɁA���`�E���C�I���d�r��10�{�̃G�l���M�[���x�A1/10�̃R�X�g���߂����B NEDO��ʂ��āA��Ƃ��w�ȂǂɎ��Ƃ��ϑ��B2016�N�x�T�Z�v���ɐV�K���ƂƂ���32���~�荞�B �u���`�E����C�d�r�v�u���������~�d�r�v�u������C�d�r�v�Ȃǂ̑��A�u�������n���������g�����~�d�r�v��u�i�m�E�ʐ���d�r�v�����ƂȂ�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���Y�����u�A�����j�A�Η͔��d�v��41.8kW�K�X�^�[�r�����d�ɐ��� �A�����j�A�͒Y�f���܂܂��A���f�̊����������A���d�p�R���Ƃ��Ă̗��p�����҂���Ă���B�������A�A�����j�A�͒����ɂ����A�܂��R�đ��x���x���Ȃǂ̉ۑ肪���邽�߁A���܂��܂ȔR���𗘗p�ł���K�X�^�[�r����p�������d�̎��؎������s�����B ���̌��ʁA��i�o�͂�50kW�̃K�X�^�[�r�����d���u��p���āA���^���|�A�����j�A���Ă���уA�����j�A��Ăɂ���80���o�͂�41.8kW���d�ɐ��������B �܂��A�R�Č�̒��f�_�����iNOx�j���܂r�o�K�X��E�ɑ��u�ŏ������邱�Ƃ�NOx�����Ȃ̔r�o��i16���_�f���Z��70ppm�j�ɏ\���K���ł���10ppm�����i16���_�f���Z��25ppm�����j�܂łɗ}���ł����Ƃ����B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| �������ȁu�܂��E�Z�܂��E��ʂ̑n�~�ȃG�l���v���x�����鍡�N�x��5�n����̑� ���y��ʏȂ́A��Y�f�Љ�̎����Ɍ����āA�܂��E�Z�܂��E��ʂ̈�̓I�ȑn�~�ȃG�l���M�[���𐄐i���邽�߁A�s�s�K�́E�n��������ɉ��������f���\�z��}����j���B���̂��ߒn�������c�́E���Ԏ��Ǝғ��ɂ��擱�I�ȍ\�z������x������Č����W���Ă����B ����̑����ꂽ�T�n��́A�D�y�s�i�k�C���j�A����s�i�R�`���j�A�k�h���i���挧�j�A�n�z�s�i�啪���j�A����s�i�F�{���j�B��Ď҂͊e�����́B����s�͂���떢���Â��苦�c��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEC�ƎR�����A�X�}�[�g�H�ƒc�n�̎��p���Ɍ������������J�n ���̒����́A�o�Y�Ȃ́u����26�N�x�n�Y�n���^�Đ��\�G�l���M�[�ʓI���p�����i���Ɣ�⏕���i�\�z���y�x�����Ɓj�v�̎��Ɖ��\�������ɍ̑����ꂽ�B �H�ƒc�n���̑��z�����d�A���͔��d�Ȃǂ̒n�Y�G�l���M�[��~�d�r�A�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���̓����̌����A���ꂼ��̌����I�ȉ^�p�̐��A���ƍ̎Z���Ȃǎ������̉\���̌������s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����ꌧ�Ɗ��d�͂Ȃ�3�Ђ́A�����M�̗��p�œd�C�R�X�g30���팸�߂����B �����ƊO�C���̉��x���ɒ��ڂ��A�r�M���p�̂��߂̋����������s���A�u�����M�v���p�V�X�e���̎��p����ڎw���B �����͒n���𗬂�邽�߁A1�N��ʂ���15�`25���Ɖ��x�����肵�Ă���B�~�͉����̕����O�C���g�������ߔM��������A�H��Ŏg�����C�{�C���[�̉����⎖�Ə����̒g�[�Ɏg���B����A�ď�͉����̕����O�C�����Ⴂ���߁A�����ɔM��D�킹�ė�[�̗\��ȂǂɎg�p�ł���B ���N�x�͎��v�����⎖�Ɖ��̉\��������B �o�T�u���s�V���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��K�����g���K�X�̔r�o�ʂ������ΒY�Η͔��d�̌��݂�5���܂� �d�͊e�Ђ̉Η͔��d�ɐ�߂�䗦�����50�����x�ɗ}����ق��A�V�݂���ۂɂ͔��d�����̈����V�����d���̔p�~��ғ��x�~�����߂�B �V�K���ł͑��d�͂�V�K�Q���Ǝ҂̉Η͔��d�̍\����ɘg��݂���B�ΒY�Ȃǂ̏�����Η͔��d�S�̂�50�����x�ALNG(�t���V�R�K�X)��50���ȏ�ɂ��鋤�ʎw�W������B2016�N�x�ȍ~�A�d�͉�ЂɎw�W�̏�����`���Â�����j���B �V�݂���Η͔��d�������d�����Ɋ��݂��A���������锭�d�������݂ł��Ȃ��悤�ɂ���B���{�����߂�2030�N�x�̖]�܂����d���\���i�x�X�g�~�b�N�X�j�ł́A�K�X�r�o�ʂ������ΒY�Η͂�S�d�͗ʂ�26���A��r�I���Ȃ�LNG�Η͂�27���ɂ���v�悾�B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2015/10�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�̓I�t�B�X�r���̋j�[�Y�ɉ�����Z���^�V�X�e����̔��J�n �A�Y�r���́A�����K�̓r���̃I�t�B�X��Ԃ̋j�[�Y�ɂ��ߍׂ����Ή����A���K�ȋ�Ԃ���������Z���^�V�X�e�����J���A8��4�����̔��J�n�����B ��ʓI�ȋݒ�P�ʂ́u�]�[�j���O�v�����ׂ������߁u�Z���v�Ƃ����B�V�J���i�́A�V��B���^�r���p�}���`�G�A�R���ƋC������̐�p�@��i�Z�����ʕ��z���j�b�g�A�̊��C���ؑ@�\�t�����o���A�R���g���[���A�ݒ��j��g�ݍ��킹���B�ǖʂɐݒu�����ݒ�킩���]������i�����߁A���ʁA�g���߂Ȃǁj��ݒ肵�A�R���g���[�����A�������x�ƓV��Ɏ��t�������o���̕����╗�ʂ����ċC���𐧌䂷��B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���������̂܂ܔR���ɗ��p�ł���o�C�I�}�X���d ��܂����O���[���p���[�́A�R�Ă��ɂ������`�b�v���K�X�����A�R���Ƃ��Ĕ��d����B �R��������H���Ŕ��������^�[���́A�����גጸ�̔R���Ƃ��āA�̔������v���グ��B �Ԕ��ނȂǂ̈��苟��������Ȃ钆�ŁA���`�b�v�͈���m�ۂ����҂ł���B �{�C�������̔��d�{�݂́A��Ɍ��z�p�ނ�Ԕ��ނ������������R���`�b�v���g�p���邪�A�`�b�v�̎��v���Ȃ�тɋ������������悤�ɂȂ�A�ғ������ɉe����^�����˂Ȃ��B�������̂܂ܔR���Ɏg�p����K�X���F�{�K�X�G���W�����d�@�́A�`�b�v������������K�v���Ȃ����߁A�ыƌn�����łȂ��A�ʎ����̙���}�Ȃǂ������p�����ƂȂ�A�p���I�ȔR���������\���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ʔň���A�ƒ�̃G�l���M�[�g�p�f�f���|�[�g���쐬������؎��������{ ���Ђ́A���R�����h�i���E�j�V�X�e���uVIENES�i���B�G�l�X�j�v�����p�����T�[�r�X���g���āA���ѕʂɃG�l���M�[�̎g�p���u�����鉻�v����ƂƂ��ɁA�G�l���M�[�^�C�v�̕��ނ��L�ڂ������|�[�g�s���A������邩�ǂ�����������B ���B�G�l�X�́A�ƒ�̃G�l���M�[�f�[�^����G�l���M�[�̎g�p����s����\�����A�w���s����v���t�B���f�[�^�ƍ��킹�ĐV���ȃ}�[�P�e�B���O���\�ɂ��鎟����^�̃��R�����h�V�X�e���ŁA�x�m�ʂƋ����J�������B���؎����́A�Z��G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iHEMS�j��ݒu�������j�^�[���т���擾�����d�̓f�[�^�Ȃǂ���ɂ���B���؎�����7������2016�N1���܂Ŏ��{����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���J�J�N�R���A��ʉƒ�����ɓd�C������r���J�n ���Ђ́A���N4���̓d�͏�����S�ʎ��R���ɐ�삯�āA��ʉƒ�����̓d�C������r�T�[�r�X���J�n�����Ɣ��\�����B ���Ђ��^�c����w���x���T�C�g�u���i�D�������i�J�J�N�h�b�g�R���j�v�Ɂu���i�D������ �d�C������r�v���J�݂����B���ЊJ���̃V�~�����[�V�����@�\�����p�����u�d�C�����v�����f�f�v�ł́A�_�̗����v������_��d�́A�g�p�ʁA���ѐl���A���Ԃ̍ݑ�Ȃǂ���͂���ƁA�œK�ȃv��������ڂŕ�����B�v�����̓����◿���\�A�v�����ύX���@���m�F�ł���B�S�ʎ��R����͐V�K�Q���҂̗����v��������r�ł���悤�ɂ���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���V�d�͂̃C�[���b�N�X�A�Ċ�ƂƂ̍��ى�Ђʼnƒ�����d�͏�����r�W�l�X�Q�� ���Ђ́A�č��ɂ����ēd�́E�K�X�����T�[�r�X����|����A�X�p�[�N�G�i�W�[�ƁA���{�����̉ƒ�����d�͏�����̎Q���Ɍ����āA�Ɩ���g���A���ى�Ђ�ݗ�����Ɣ��\�����B���ƊJ�n��10��1����\��B ���ى�Ђ̎��{����4��9000���~�i�\��j�A�o���䗦�̓C�[���b�N�X��80���A�X�p�[�N�G�i�W�[��20���B �C�[���b�N�X�́A2016�N4���ɗ\�肳��Ă���d�̓V�X�e�����v�ɂ���������ሳ����i�ƒ�p�E���K�̓I�t�B�X�E���X���j�̏�������̑S�ʎ��R��������ɁA�X�p�[�N�G�i�W�[�Ɠ��{�����ɂ�����ሳ����ւ̎Q���ɂ��ĉ\�������������ōs���Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���f���\�[�A���ב��ނ��g�����o�C�I�R���̑�K�͎��ؐݔ������� ���Ђ́A�o�C�I�R���̎��p���Ɍ����A�F�{���V���s�ɔ��ב��ނ̑�K�͔|�{���؎{�݂����݂��A2016�N4�����ғ����J�n����Ɣ��\�����B ���Ђł́A2008�N4�����A�I�C�����Y�����邱�Ƃ��ł���V���[�h�R���V�X�`�X���g�����o�C�I�R���Y���錤���Ɏ��g��ł���A���m�������s�̕~�n�i300m2�j�ɂ����Ĕ|�{�������s���Ă����B ����A�o�C�I�R���̐��Y���������߂邽�߂ɑ�K�͔|�{�Z�p�̊m�����K�v�Ȃ��Ƃ���A�V���s�̔p�Z�̓y�n�E�{�݁i20,000m2�j�����p���A�V���Ȕ|�{�{�݂Ŏ��؎������s���B����A2018�N�x��ړr�ɁA�����璊�o�����o�C�I�R���̎��p���Ɍ������v�f�Z�p�̊m����ڎw���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���r�����ŕ��U�ݒu�ł���`���[�A�ȃX�y�[�X���ƍH���ȗ������\�� �_�C�L���H�Ƃ͂���܂Łu��̌^�v�����������`���[�ŁA��C�Ɨ�}�̔M�����������Ȃ��M�����j�b�g4��ƁA��}�̔M�ŗ≷�������n�C�h�����j�b�g1����}�z�ǂŐڑ�����Z�p���[�g�^���J�������B �n�C�h�����j�b�g�ƔM�����j�b�g�Ԃ̗�}�z�ǂ͍ő����100���[�g���i���፷50���[�g���j�ŁA����Ɗe�K�@�B���ɕ��U�ݒu���邱�Ƃ��ł���B����Ƀn�C�h�����j�b�g�������ɐݒu���A2�����i�����j�@�ւ̐��z�Nj�����Z�k���邱�ƂŁA�≷���|���v�̓��͒ጸ��|���v�̃T�C�Y�_�E���ɂ��v������B ���̑��A�V�^�X�N���[�����k�@�̓��ڂɂ��A�ᕉ���̉^�]���������サ�ȃG�l�����]���@�ɔ��16�����サ���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���[��50m�ő����I �u�n���M�{�G�A�R���v�̗�g�[�V�X�e���V���� �R���i�́A�n���M�Ƌ�C�M�𗘗p�����n�C�u���b�h�≷���V�X�e����2016�N1����{���甭������Ɣ��\�����B �V���i�͂���܂ł̒g�[�^�]�ɉ����A��[�^�]���ł���B1�Z�b�g�őS�ٗ�g�[���\�ŁA��ʏZ����łȂ��A�������A�c�t���A���{�݂ȂǕ��L���p�r�ɑΉ�����B �n���M�Ƌ�C�M�̃G�l���M�[���O�C���x�ɉ����āA��Ɍ����ǂ����p����B����ɂ��A�O�C���x�ɍ��E����Ȃ��������^�]����������ƂƂ��ɁA�@���p��啝�ጸ�����B8kW�̒g�[�o�́A7.5kW�̗�[�o�͂邽�߂ɕK�v�Ȍ@��[�����A�]���̒n���M�q�[�g�|���v�Ɣ�r���Ĕ�����50m�ƂȂ邽�ߓ������₷���Ȃ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���v���X�`�b�N���琅�f������ēd�͂ɁA���s�Ő��f�Љ�Ɍ��������؊J�n ���s�Ə��a�d�H�́A��Y�f�Ȑ��f�Љ�̎����Ɍ������A�g�E���͂ɂ��č��ӂ��A�������������B���a�d�H�̎g�p�ς݃v���X�`�b�N���琅�f�����o���Z�p�����p���āA��Y�f�Ȑ��f�Љ�̎�����ڎw�����j���B ���̋���Ɋ�Â����g�݂�1�Ƃ��āA�g�p�ς݃v���X�`�b�N�R���̐��f����ՊC���ŃG�l���M�[�Ƃ��ė��p��������n�܂�B���؊��Ԃ�2019�N�x�܂ł̗\�肾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Ɩ�����ɂ�����x���`�}�[�N���x�̑n�� �o�Y�Ȃ��A�u�I�t�B�X�v��u�z�e���v�u�S�ݓX�v�u�R���r�j�v�ȂǁA����Ǝ�E����̊�Ƃ̏ȃG�l�ɂ��āA�Ǝ���Ŕ�r�ł���w�W��ݒ肷��w�x���`�}�[�N���x�x�����Ă��������ŁA�������J�n�����B ����́A���łɐ����ƂȂǁu�Y�ƕ���v��6�Ǝ�10����œ����ς݂́w�x���`�}�[�N���x�x���u�Ɩ�����v�ɂ��L���Ă������ƂŁA�ȃG�l�̐��i������ɐi�߂Ă������g�݂̈�Ƃ���B �Ǝ킲�Ƃ̎��Ԃ܂��A����A�K�Ȑ��x�v�Ă��ł܂����Ǝ�ɂ��āA�����Ɍ������������s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����d�̕��y����6.6���A�������������23.9�� �����Ȃ̒��� �����Ȃ́A�u����26�N�S��������Ԓ����v�̂����A��v�ϋv������ۗ̕L�ɂ��Ď��܂Ƃ߂����ʂ����\�����B �ȃG�l���M�[�֘A�̎�v�ϋv������̕��y��������ƁA�g�b�v�́ALED�Ɩ�����33���B�����āA�������������23.9���A���z�����d�V�X�e����6.6���A���z�M�������3.4���A�ƒ�p�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e��1.3���A�ƒ�p�R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e��1.0���ƂȂ��Ă���B �ȃG�l���M�[�֘A�̎�v�ϋv������̕��y���𐢑ю�̔N��K���ʂɂ݂�ƁALED�Ɩ�����30�Ζ�����37.6���ƍł������B�����������킨��ё��z�����d�V�X�e���́A30�Αオ�ł������A���ꂼ��29.8���A11.0�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����]���A���K�͉Η͔��d���ɂ��c���݂Ɏ��~�� ���Ȃ́A�Η͔��d���̌��ݎ��Ɏ��{������e���]���i�A�Z�X�����g�j�̑Ώۂ����K�͔��d���܂Ŋg�傷����j���ł߁A�]����@�Ɋւ���L���Ҍ�����������������B �]���葱�����s�v�ȏ��K�͔��d���͌��v�悪�������A�������ʂ̂����_���Y�f�iCO2�j�̑�ʔr�o�����O����Ă��邽�߁A�]���ΏۂƂ��邱�ƂŌ��݂Ɏ��~�߂����������l�����B ���e���]���@�̐��߂ł́A�]�����K�v�ȉΗ͔��d�����u�o��11,2500kW�ȏ�v�ƒ�߂Ă���B�]���Ώۂ̔��d���̏ꍇ�A�d�͉�Ђ͊��e���Ȃǂׂđ���u���A���ɕ��Ȃ���Ȃ炸�ACO2�̔r�o��}����ŐV�Z�p�̓��������߂���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���d�͂̎�����70����˔j�A�؎��o�C�I�}�X�Œn�Y�n������������ 2030�N�ɍĐ��\�G�l���M�[�ɂ��d�͎�����100����ڎw�����쌧�Ńo�C�I�}�X���d���������B �R���̖؎��`�b�v����K�X�����āA�d�͂ƔM�̗�������������R�[�W�F�l���[�V�����̓������������Ŏn�܂����B�S���Ńg�b�v�N���X�̏����͔��d�ɉ����ăo�C�I�}�X�Ƒ��z���Ŏ����������߂�B ���쌧�̈ɓߒJ�ɂ���A�u���Ԃ���X�̔��d���v�́A���ӂ̐X�т���o��Ԕ��ނ̃`�b�v��R���ɗ��p�����o�C�I�}�X���d���ŁA���d�\�͂�360kW�ŁA���d�ʂ�285��kWh�ɂȂ�B ���ܖ�s�̖�؍H��ł́A���d�\�͂�1.9MW�B�M�̋����\�͓͂d�͂Ɋ��Z�����2�{��3.8MW�������āA���̔M�ʼn���������ăn�E�X�͔|�ɗ��p���� �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Đ��\�G�l���M�[�A�ȃG�l�@�̑ΏۂɁ|�@�����c�_�� �o�ώY�ƏȂ́A�ȃG�l���M�[�@�ō����I�Ȏg�p�𑣂��G�l���M�[�̑ΏۂɁA�Đ��\�G�l���M�[������������Ō�����i�߂�B���s�@�Ŏg�p������������͉̂��G�l���M�[�Ɍ��肳��Ă��邪�A2030�N�x�̓d���\���i�G�l���M�[�~�b�N�X�j�ōĐ��\�G�l�̔��d�d�͗ʂ�22�`24���Ɉ����グ�邱�Ƃ܂��A���E���킸�G�l���M�[�S�̂ŏȃG�l��i�߂��鐧�x�v���K�v�Ɣ��f�����B���鎖�Ə��ōĐ��\�G�l�̓����ʂ𑝂₹�A���̕����G�l���M�[�̎g�p�ʂ�����A�ȃG�l�ɂȂ���B�������������g�݂�]������ɂ͏ȃG�l�@�̉������K�v�B�H���ȍ~�ɋc�_���n�߂�Ƃ݂���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���ȃG�l�w�W�ɔp�M�w�����f�A��Ƃɗ��p�����o�Y�� �o�ώY�ƏȂ�2016�N�x����A�O���̍H�ꂩ��r�o�����p�M�̍w������Ƃɑ����d�g�݂�����B��Ƃ͎��Ђŏ�����G�l���M�[����A�w������ �p�M�̃G�l���M�[��������������悤�ɂȂ�B�ȃG�l�w�W�����P���邽�߁A��Ƃ͎Љ�I�ӔC�iCSR�j���A�s�[�����₷���Ȃ�B2015�N�x���ɏȃG�l�@�̏ȗ߂���������B �����p�M�̔������ߔM����ƍH�ꂪ�p�M�𑝂₵�A�������ăG�l���M�[�g�p�ʂ������鋰�������B�o�Y�Ȃ͂����܂ŕ����I�ɔr�o���ꂽ�p�M�ɔ��������肵�A�ȃG�l�̘g�g�݂���O��Ȃ��悤�ɒ�������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���ƒ�Ȃǂ̏ȃG�l��T�Z�v���ɖ�464���~ ���{�́A�������ʃK�X��2030�N�܂ł�2013�N�Ɣ�ׂ�26���팸����ڕW�����肵���B ���̂����ƒ��Ɩ�����ł́A�r�o�ʂ����ꂼ��40���߂��팸���邱�ƂƂ��Ă��邪�A���ѐ��̑�����d�����i�̕��y�Ȃǂ���A�r�o�팸���\���ɐi��ł��Ȃ��̂����B ���̂��ߊ��Ȃ́A���N�x�̊T�Z�v���ŁA�ȃG�l����������邽�߂̊֘A�\�Z�Ƃ��āA���悻464���~�荞�ޕ��j���ł߂܂����B ��Ȃ��̂Ƃ��ẮA���ݏZ���Ώۂ�LED�Ɩ���f�M�ނȂǂ�����ۂ̈ꕔ��⏕���鎖�ƂƂ���25���~�A�n�������̂����c�Z��ȂǂɃ��[�X�_���LED�Ɩ���ݒu���鎖�Ƃ�16���~�Ȃǂ荞��ł���B �o�T�uNHK �v |
|
|
| ���@�@[�@2015/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���J�M�͖����p�ރR�}�c�A�w���d��9�����Œn��������� �n���̖����p�ނŃG�l���M�[�����A�w���d�͂�9������B������\�\�B �Đ��\�G�l���M�[�̗��p�𑝂₷���ƂŊ����ׂ������Ȃ���A�����ɒn���o�ς̊��������}��B���@�B���̃R�}�c���A����Ȉ�Γ̊��헪�𐄂��i�߂Ă���B ���Ђ͓����{��k�Ђ̌o���܂��āA2015�N��ڕW�ɂ����u�d�͔����v���W�F�N�g�v�Ɏ��g��ł����B��i�I�ȏȃG�l�Ɛ��Y�Z�p�̊v�V�ɂ���āA�d�͉�Ђ���̍w���d�͂�啝�Ɉ��������A�����ׂ̏��Ȃ��A�ЊQ�ɋ������Y�̐����\�z����̂��_�����B�V�����g�ݗ��čH��ł��A�ȃG�l�ݔ��̓�����H�����P�Ȃǂ̐��Y������ɂ���āA�w���d�͗ʂ�2010�N�x���52���팸���邱�Ƃɐ��������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A���f�������u�ɎQ���|�ƒ�����A���G�}�Z�p�����p ���Ђ͉ƒ�ł����z���Ɛ�������Ζ��s���ɐ��f�����o���鑕�u�̊J�����n�߂��B �����̏�Ő��f�����A�R���d�r�Ŕ��d���ł���Ƃ����B���p���̎����͖��肾���A���f���R�X�g�ɐ����ł�����G�}�Z�p�ɖڐ��������B���łȂǂɑ����p�i�\�j�b�N���������グ�����ƂŐ��f�������u�̊J���������n�܂肻�����B �J������Z�p�͌��G�}����ꂽ���u�ɐ������A���z�����Ǝ˂��Đ��f�����o���B���f��R���d�r�ɑ���Ɠd�͂Ƃ���������B �V���u�͉��Ύ����̃K�X���g��Ȃ����߁A��_���Y�f(CO2)�̔������Ȃ��g�J�[�{���t���[�h�Ȑ��f�������ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���~�d�r���u�I�t�O���b�h�v�̑��z�����d�ɁA��s�Ŏg�p�ς݂�107����� �������s��NPO�@�l�́u��d���n��̐l�X�ɒ~�d�r���������v�Ƌ����Œ~�d�r�̍Đ��Ɏ��g��ł����B ��s�̓X�܂Ŕ��p�Ɏg���Ă������v107��̒~�d�r��NPO�@�l�ɒ��āA�Đ��������{�������̂z�����d�V�X�e���Ȃǂɍė��p�ł���悤�ɂ���l���� �~�d�r�Ƒ��z�����d�V�X�e����g�ݍ��킹��A���Ԃɔ��d�����d�̗͂]�蕪��~�d�r�ɒ~���Ė�Ԃɗ��p�ł���B�d�͉�Ђ̑��z�d�l�b�g���[�N����藣�����u�I�t�O���b�h�v�̏�Ԃł��A�ƒ��{�݂œd�͂��g�������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�n��ō�����d�͂�n��ŏ����u�n�Y�n���v�ɂȂ���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���x�m�d�@�̔����̍H�ꂪ�r�M���p�łP�O���ȃG�l �x�m�d�@�R�����쏊�́A�K�X�G���W��1��ƔR���d�r4��Ŕ����̐��Y�ɕK�v�ȓd�͂�d���Ă���B�V���ɃK�X�G���W���ƔR���d�r�̉^�]�Ő������r�M�ɒ��ڂ����B �r�M�͋z�����Ⓚ�@�ɑ���A�␅�����Ɏg���B�␅�͔����̍H��̃N���[�����[���̋p���B�N���[�����[���̐ݔ��͍������^�ɍX�V���A2010�N�x��30���̏ȃG�l����B���ς݂��B�₽���O�C����荞�݁A�␅�����ւ̊��p���n�߂��B ���݂̓G�l���M�[�g�p�̃f�[�^��~�ϒ����B�f�[�^��͂��i�ނƗ\�����x�����܂�A�r�M���p�̌��ʂ��������o����B�r�M�A�O�C�A�e�d�l�r�̑�����ʂ�2015�N�x��10���ȃG�l��ςݑ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����{�Ɏq���A���j�e�B�ƃg���^�A�X�܌����K���X�V�X�e������|����66���팸 ���Ђ́A�g���^�����ԂƋ����ŁA������ȃG�l�������߂���K���X�V�X�e�������삵���B �����Ԕ̔��X�ȂǃV���[���[���̊O�ǃK���X���d�����A�f�M���������߂ċ��ׂ��y������B�����Ȃǂɂ�邪�A�G�A�R���ݒ艷�x��26���̏ꍇ�A���ׂ��66���팸�ł���B �X�܂̊O�ǃK���X�̓����ɉ����K���X���j�b�g��g�ݍ��ށB�G�߂⎞�ԑсA�C���̕ω��ɉ����ē����K���X���J���A���ׂ��y������d�g�݁B�ȃG�l���ʂ��d������ꍇ�A�X�܂̓����Ɏ��[�����K���X�����o���A��d�K���X�ɂ���B�X�܂̎��F�������߂����ꍇ�A�����̃K���X�����[���Ă�������Ƃ����X�܋�Ԃ����o�ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����͂�ȃG�l�͉Ă����̉ۑ�ł͂Ȃ��|�O�H�d�@��L���m���l�i�ȂǁA�V���Ȏ��ݑ��X �d�͗����͏㏸���Ă���A���͂�ȃG�l���M�[�͉Ă����̉ۑ�ł͂Ȃ��B�Y�ƊE�ł́A�V���Ȏ��g�݂��i��ł���B �O�H�d�@�ł͐ߓd��Ƃ��čH��ɑ��z���p�l����ݒu�B31���_�ɍ��v1��5900kW�����A���d�����d�͂��H��Ŏg���ēd�͎��v��}�����Ă����B �x�m�t�C�����z�[���f�B���O�X��2014�N�x����u���ȑ����v�̐��x���g���A�֓��n��16���_�Ɏ��Ђ̕x�m�{�H��̎��Ɣ��d�̓d�͂̋������J�n�B�_��d�͂�10�������������B �L���m��MJ�ł�2003�N�Ɋ����B�ŐV�@�������Ă���ȃG�l�̗]�n�͂Ȃ��Ǝv���Ă����B���ꂪ���������40�����ȃG�l�������B�@��̍X�V�ł͂Ȃ��A�^�p���P�ɂ�鐬�ʂ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���㐅���ŏ����͔��d�_�C�L�������V�X�e�������̊ǐ��H�ɓ��� �����ł́A���Ђ��J���������d�\�͂��������^�Œ�R�X�g�̃}�C�N�����͔��d�V�X�e�����㐅���{�݂ɐݒu���A���܂Ŏg���Ă��Ȃ����������G�l���M�[�����p�������͔��d�̎��،����Ɏ��g�ށB ���d�d�͍͂ő�71.4kW�A�ő�N�Ԕ��d�ʂ�619MWh�i��ʉƒ�172���������j��������ł���A���g�p���ɂ����锭�d�\�͂�������B���؊��Ԃ�2015�N12���܂ł̗\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�P�A�A���{�ő勉�̒n���M��36���ȃG�l �n���M�������p�̔M�Ƃ��Ċ��p�����ڂ���Ă���B�C�P�A�̕����V�{�X�ɂ́A�����ő勉�̒n���M���p������B�n��100m�ɓ��B����70�{�̌@�팊����M�����ݏグ�ēX���̋ɗ��p���Ă���B �n���M���p�ƒʏ�̃q�[�g�|���v�̂Q��̋��g���������s���Ă���B�Q��Ƃ��ʏ�̋������ꍇ����36%�̏ȃG�l���ʂ��o���B �n���M���p�͒ʏ�̋����R�X�g�͂����邪�A���Ђ̓�������̊�Ɏ��܂����B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA2025�N�߂ǂɐΒY�K�X���R���d�r�������d���J���|�������͂őO�|�� ������Η͔��d�̗L�͋Z�p�ł���ΒY�K�X���R���d�r�������d�iIGFC�j���A2025�N������߂ǂɊJ������B �u������Η͔��d�̑��������Ɍ��������c��v�ŁA�Z�p�J�����[�h�}�b�v�̍��q�Ă�����B IGFC�͐ΒY���K�X�����A�R���d�r�E�K�X�^�[�r���E���C�^�[�r���Ńg���v�����d����Z�p�B�����̐ΒY�Η͔��d��蔭�d������5���ȏ���サ�ACO2�r�o�ʂ�3���ጸ�ł���B 2030�N�x�̖]�܂����d���\���Ɖ������ʃK�X�팸�ڕW���܂Ƃ܂�A�����O�|�����K�v�Ɣ��f�����B �܂������^�K�X�^�[�r���R���d�r�������d�iGTFC�A10��kW���j�̋Z�p����i�߁A���̋Z�p��IGFC�J���ւƉ��p����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���d�̓R�X�g�̍팸���ʂ͔N��2200���~�A���쌧��32�J���̎{�݂ɐV�d�� ���쌧�����߂Č��L�{�݂̓d�͌_��ň�ʋ������D�����{�����B��ʋ������D�̑ΏۂɂȂ����̂͌����w�Z��17�P���̂ق��A�d�͂̎g�p�ʂ����� ���������a�@��A�����ɂ���p���������{�݂��܂�34�J���ł���B�Ɩ��p�̓d�͓͂��{���W�e�b�N�����g�����A�Y�Ɨp�̓d�͂��g��3�J���͐V�d�͂ōő��̃G�l�b�g�����D�����B ���������a�@�Ɣp���������{�݂́A���ꂼ��l���d�͂ƒ����d�͂����D���Č_����p������B�����a�@�͌_��d�͂�2800kW�Ƒ傫���A�V�d�͂ł͋����ʂ̊m�ۂ���������\��������B 3�N�Ԃ̌_����z�͍��v��10��5100���~�ɂȂ�A�]���Ɣ�ׂ�1�N������2200���~�̍팸���ʂ������ށB �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���X�}�[�g���[�^�[�̃Z�L�����e�B�A2016�N4���܂łɃK�C�h���C������E��� �o�ώY�ƏȂ́A����A���{�ɂ����Ė{�i�I�ȓ������i�߂���X�}�[�g���[�^�[�i������d�͌v�j�ɂ��āA�T�C�o�[�U������h���Z�L�����e�B��̋�̓I�Șg�g�݂��Ƃ�܂Ƃ߂����[�L���O�O���[�v�̕������\�����B ���̕��ł́A�Z�L�����e�B��Ƃ��ď����S�ʎ��R���܂łɁA��ʓd�C���Ǝ҂ɑ��ē���I�ȃK�C�h���C���i���Łj�Ɋ�Â����s����悤�W�҂ɂ����Ď�g�݂�i�߂铙�����߂Ă���B ��̓I�ɂ́A2015�N12����ړr�ɓ���I�ȃK�C�h���C���̐��Ă����肷��B�e���Ǝ҂́A���̍���ƕ��s���ċ�̓I�ȃZ�L�����e�B���ݒ�E���{���A2015�N�x���ɃZ�L�����e�B��̌����s�����Ƃ�ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A���~�n�p�������琅�f���A�d�͂ւ̗L�����p�� NEDO ����̎��́A���T�C�N������������A���~�n�p�������玑���E�G�l���M�[�����o������I�Ȃ��̂ŁA�V�X�e���̎��p���ւ̖ڏ������������Ƃ�����ۂ̍H��Ō��ɓ���B���u�͔N���Ɋ����������N����^�p����B �A���n�C�e�b�N���J�������V�X�e���́A�A���~�t���p�b�N�ȂǁA���E�A���~�E�v���X�`�b�N�̕����ޔp��������p�b�N�p���p�[�i�����@�j�Ńp���v���������o���A�c�����A���~�t�v���X�`�b�N�������F�ʼn��M���邱�ƂŃK�X�E�I�C���ƍ����x�̃A���~�ɕ�������B ������������A���~�����A���J���n�t�Ɣ��������邱�ƂŐ��f������B�A���~�n�p����900�g�������������ꍇ�A��170��kWh�̏ȃG�l���ʂ����҂ł���B �o�T�u���X�|���X�v |
|
|
| ���a�̎R���Ɂu���z�M�𗘗p����؍ފ����{�݁v���������w������{ �L�c��؍ދ����g���E�L�c�쒬�E�a�̎R����3�҂́A���z�M�𗘗p�����؍ފ����{�݂�L�c�쒬�Ɋ��������A7��14���Ɍ��w����J�Â����B 3�҂́A���͂��č��i���ȋI�B�ނ̊����ޑ��Y��ڎw���A���z�M�𗘗p�����؍ފ����Z�p�̎��p���Ɏ��g��ł���B���̂����͎��R���������Ă���ǁE���̖؍ނƂ��Ďs��ɗ��ʂ���B �������~��ĂȂNjC������ɂ���Ă͏�肭�؍ނ����������A�ыƎ҂ɂ͎��ԂƎ�Ԃ��������Ă����B����̓��{�݂̓����ɂ��A�����̉��������҂����B ���{�݂͕���27�N�x�ыƋZ�p���n�K�������Ƃɂ���Č��݂��ꂽ���́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���r�����Ԃ̉��x�����������鉻�A�����Z���T�[�l�b�g�� �ȃG�l���̗]�n�������c���Ă����K�͏��ƃr�������̖����Z���T�[�l�b�g���[�N�V�X�e�����\�z���A10���̏ȃG�l��ڎw�����B �V�X�e���́A�s�̂̃R���^�[�}�i�������A�������Ȃǂ̓��l���}�j�쐬�p�̃\�t�g�E�G�A�����p���A�����������A���^�C���ʼn����ł���V�X�e�����J�������B���܂��܂ȃZ���T�[��ݒu�����ʒu��\�����A�������̃��A���^�C���̏��A�ЂƖڂŕ�����悤�ɂȂ����B ����ɂ���āA�����̉��x������A��₵�����A���߂����Ă���ꏊ�����āA�ȃG�l�̉��P�ɂȂ���悤�ɂ����B �َ݊҂̈ړ��Ȃǂɍ��킹�A�O�C�̎�����ʂ��œK�ɐ��䂷�邱�ƂŁA�O�C�̎�����ʂ��팸�ł���B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���u�d�͂̐敨����s��v�o�Y�Ȃ��X�^�[�g�Ɍ������������܂Ƃ� �d�͂̏����S�ʎ��R����A�d�͐敨�s��́A�����d�C���ƎҁA���d���ƎҁA�d�͎��v�ƂȂǂɂƂ��āA�����̓d�͉��i�����炩���ߊm�肵�A�d�͉��i�̕ϓ����X�N���������d�v�Ȏ�i�ƂȂ�B �����ŁA���Ȃ́A�d�̓V�X�e�����v�̋�̉��Ɍ����āA���{�ɂ�����d�͐敨�s��̖]�܂����g�g�݂������E���c���邽�߁A�u�d�͐敨�s�ꋦ�c��v��ݒu���A2015�N3������v5��J�Â��Ă����B ���̃|�C���g �@1.�]�܂��d�͐敨�s��̘g�g�� �@2.�}�l�[�Q�[���̖h�~�� �@3.�����S�ʎ��R����A�y�I���₩�ɓd�͐敨����ꂷ�ׂ� �@4.���̑��i���Z�̌������ɂ��� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2015/8�@]�@�@�� |
|
|
| ��[���z] �u���邢�v�Ɗ����銴�o�𗘗p�A����Z�p�ŏƖ��d�͂�6���팸 ��ёg ��������V�X�e����NEDO�́u�헪�I�ȃG�l���M�[�Z�p�v���O�����v�ɂ����ĊJ�����ꂽ���̂ŁA�Ɩ���̃u���C���h�����䂵�A�Ɩ��@����Ɠx�ɗ}���Ȃ���������̖��邢��ۂ��ێ��ł���Ƃ������́B ����V�X�e���́A�����̋��Ꭾ�̋P�x�J�����ʼn����Ɖ��O�̖��邳�����m���A���̏��Ɋ�Â��Ď����̏Ɩ��ƃu���C���h�����䂷��d�g�݂��B�u���C���h����ɂ��ẮA�܂����z�̊p�x��V�C�A�ȂǁA���Ԃ�G�߂ɂ���ĕω����鉮�O�̖��邳���P�x�J�����ŔF������B���ɖ��邳�ɉ����āA���V�̓��A�ܓV�̓��ɉ����ău���C���h�̉H�̊p�x���œK�ɐ��䂵�Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[�d��] �ɓ��哇�Ń}�C�N���O���b�h����������1.5MW�n�C�u���b�h�~�d�r�A�n���ڑ����J�n �������쏊�ƐV�_�˓d�@�́A1.5MW�n�C�u���b�h��K�͒~�d�V�X�e�����A�d�͌n���ɐڑ��B���؎������J�n�����B ���͔��d�⑾�z�����d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�́A��������v������̂�������A�d������g���̕ϓ��ɂ��d�͌n���ɗ^���镉�S���ۑ�ƂȂ��Ă���B���ɕ��U�^�G�l���M�[�Љ�̎�����ڎw����ŁA�����̉ۑ���������Ȃ���Ύ���������B �J�������~�d�V�X�e���́A�s�[�N�V�t�g��s�[�N�J�b�g�ɑΉ����邽�߂̓d�͒����ɗL���ȁu�����o�ͥ���������~�d�r�v�ƁA�Z�����ϓ���}������̂ɗL���ȁu���`�E���C�I���L���p�V�^�v��g�ݍ��킹���B���^�p�ɑ��ǂ̂悤�Ȑ���Z�p���K�v�ŁA�ǂ���������肪���܂��\��������̂��A�Ƃ����_�ɂ��Ă͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[���z] ��ёg���o�C�I�}�X���d�ɎQ���A������萧�x�𗘗p ���Ђ͎R�����匎�s�̖؎��o�C�I�}�X���d���ƂɎQ������Ɣ��\�����B2017�N�x�̏��Ɖ^�]�J�n�Ɍ�����10�N���珀����i�߂Ă����匎�o�C�I�}�X���d������Ђ̑S�������A��уN���[���G�i�W�[���擾���A���Ƃ��p������B �匎�s���̖�1��9000m2�̕~�n�ɁA���d�e��14MW�̔��d�������݂���B�R���͙��肵���}��Ԕ��ނȂǂō���������`�b�v�B�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i������萧�x�𗘗p���Ĕ��d���A�N�ԂŖ�20���~�̔���グ�������ށB�����z�͖�100���~�B���d���̌��݂́A��ёg���ꊇ�Ő��������B��ёg�O���[�v���o�C�I�}�X���d���ƂɎQ������̂́A���v��Ղ̑��l���𐄐i���邽�߁B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[���z] �f�M���ƒ�����ׂ𗼗����������t���d���E���^���t�H�[�� �A�L���X�́A�V���A��HFO�i�n�C�h���t���I���I���t�B���j���g�p���A�����f�M���\�Ɗ����y���̗����������������A�f�M�p�����t���d���E���^���t�H�[����S���Ŕ̔����J�n�����B �����t���d���E���^���t�H�[���́A�傫���́u��փt�����v�^�C�v�Ɓu�m���t�����v�^�C�v�ɕ������B�Ƃ��낪�A��փt�����^�C�v�͉������ʂ��������ɕ��ׂ�������A����m���t�����^�C�v�͒f�M���ɓ�_���������B�����ŁA���Ђ́A�V���A��HFO���g�p���邱�Ƃɂ��A���҂̃f�����b�g�����������B �M�`������0.026W/m�EK�ȉ��ŁA�]���̑�փt�����^�C�v�Ɠ����̒f�M���\����B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| ��[IT]�A�}�]���̍Đ��\�G�l���M�[���p����40���ɁA�Ă�80MW�̐V���K�\�[���[���� �A�}�]���̎q��ЂŃN���E�h�T�[�r�X��W�J����A�}�]���E�F�u�T�[�r�X�iAWS�j��2014�N11���ɁA���Ђ̎{�݂��g�p����d�͂������I��100���Đ��\�G�l���M�[�ɂ���Ɛ錾���Ă���B���̒B���Ɍ����Ē��X�Ǝ��g�݂�i�߂Ă���B2015�N6���ɓ��Ђ́A�č��o�[�W�j�A�B�̃A�b�R�}�b�N�S��80MW�̐V�������K�\�[���[�����݂��邱�Ƃ\�����B AWS�ł�2015�N4���̒i�K�ŁA25�����Đ��\�G�l���M�[�ɂ����̂��Ƃ��Ă���B2016�N���܂łɍĐ��\�G�l���M�[�䗦40���Ɉ����グ��_�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[�M�G�l���M�[] �H��̒ቷ�r�M���ė��p�|�x�m�d�@�u���C�����q�[�g�|���v�v ���Ђ́A�H��Ŕ��������ቷ�r�M��������čė��p�ł���u���C�����q�[�g�|���v�v������Ɣ��\�����B �d�͎���̕ω��܂��A���Y����ł̃G�l���M�[�̌����I���p�ւ̒��ړx�̍��܂�ɑΉ��B������H���A�����ԁA��ʋ@�B�A���w�H�ƂȂǁA�r�M���������鐻���Ƃ̍H��ݔ��ɕ��L���K�p���邱�Ƃ��ł���B60�`80���̉��r���Ȃǂ���M��������A100�`120���̖O�a���C����������B �����E���s��1000mm�~����1830mm�B�ō��G�l���M�[��������iCOP�j��3.5��B���B�G�l���M�[�R�X�g���_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ�啝�ɍ팸�ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��[�G�l���M�[] �K�X�ƐΖ��̍ő�肪�Η͔��d�����A�����p�݂�2021�N��110��kW �����K�X��JX���z���G�l���M�[��2001�N�Ɂu���V�R�K�X���d�v�������Őݗ����āA���݂�2��̔��d�ݔ���85��kW�̓d�͂��������Ă���B�אڂ���JX���ۗL����V�x�n������A�ŐV�s�̍������̔��d�ݔ�2���V�݂��āA�����S�ʎ��R���Ŋg�傷��V�d�͂Ɍ����Ĕ̔�����B �V�݂���3���@��4���@�͍ŐV�s�̃R���o�C���h�T�C�N���������̗p���āA���d�\�͂�55��kW���A���v��110��kW�ɂȂ錩���݂��B 2018�N�̌㔼����2019�N�̑O���ɂ����Č��ݍH���ɓ���A2021�N�ɏ����^�]���J�n����B������2��ƍ��킹���195��kW�̓d�͂���s���ŋ����ł���悤�ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[����] �����V�^�̘R���Ǘ��V�X�e����V�����ɒ�� �V�����̏E�����{�݂͐�������Ă������A�����ǂ���̘R���̂��߂ɐ������Ǝ҂����v���Ȃ�������B�܂��A�R���ӏ�����ٕ̈������Ő����̈����ɂȂ���B ���Ђ́A�����ǖԂ���̗��ʁE���̓Z���T�[���ƁA�����ǂ̍ގ���V���x�Ȃǂ̃A�Z�b�g���A����ɁA�����ǖԒ��̐����̃V�~�����[�V�������痬�ʁA�����A���͂𐄒肷��Z�p�Ƃ�g�ݍ��킹���R���Ǘ��V�X�e�����J�������B ���Ђ͘R�����̉ۑ�����������ΏۂɁA�R���Ǘ��V�X�e�����g�̂�����j���B�܂��A�Ǝ��ɊJ�������A�z���|���v�̍œK�f�o�����������䂷��z���R���g���[���V�X�e���������Ē�Ă���B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ��[�ʐM] ���d�r1�{��10�N�쓮���A���{���̖����K�i�uWi-SUN�v �uWi-SUN�v�Ƃ́uWireless Smart Utility Network�v�̗���ŁA�ő�1km��̋����ő��ݒʐM���s����ȓd�͖����ʐM�K�i�B Wi-SUN�̓����́A�p�r�ɂ���邪���d�r��10�N�Ԃ̋쓮���\�Ƃ������Q�̏ȓd�͐��ƃm�C�Y�ɋ����ʐM�i���������Ȃ���A1km��̒������ʐM���\�ȓ_���B���̂悤�ȓ��������āA�X�}�[�g���[�^�[��HEMS�ւ̓K�p�����҂���Ă���B �g�����g���т͍����ł�920MHz�т��嗬�ŁA�d�g����Q������荞�݂₷���Ƃ�������������B �o�T�u�L�[�}���Y�l�b�g�v |
|
|
| ��[�G�l���M�[] NEDO���u���f�T�v���C�`�F�[���v�\�z�֏����C�O�Ő����A���{�܂ŗA�� NEDO�́A�C�O�Ŏg���Ă��Ȃ�������G�l���M�[���g���Đ��f�����A���{�ɗA�����Ă���u���f�T�v���C�`�F�[���v�̍\�z�ɏ��o���B���Ԋ�Ƃɂ����؎��ƂȂǂ��������A2030�N����ɏ��ƃx�[�X�̑�K�̓V�X�e���m����ڎw���B���̌v��Ɍ����ď����ΏۂƂ��č̑��������Ƃ\�����B ��́A���d�H�ƁA�d���J���Ȃǂɂ����؎��ƁB���B�̊��Y�Ő��f�����A�����A�A���A���p�܂ň�̂ʼn^�c����T�v���C�`�F�[���̍\�z��ڎw���B2020�N�x�̎��؉^�]��O���ɐv���A���^�]��i�߂�B ���c���w�H�Ƃ́A���w�I���@��p���ď���n�܂ŗA���A��������T�v���C�`�F�[�����\�z����B2020�N�x�̎��؉^�]��ڎw���B �o�T�u�Y�o�j���[�X�v |
|
|
| ��[�ăG�l] 1��2000�l�̌ٗp�n�o�ցA�Đ��\�G�l���M�[�̎Y�Ɖ�����������u��B���f���v�J�n �Đ��\�G�l���M�[�Y�Ƃ���B�n��̐V���Ȍo�ϔ��W�̌����͂ɂ��悤�Ƃ����������i��ł���B��B�n��헪��c����̓I�ȃA�N�V�����v�������ł߂��B�Y�Ɖ��Ɍ����u�n�M�E����M�v�u�C�m�v�u���f�v��3����ɕ�����Ď��g�݂�i�߁A2030�N���_��5400���~�̌o�ό��ʂ�1��2000�l�̐V�K�ٗp�̑n�o��ڎw���B �n�M�E����M�G�l���M�[�֘A�Y�Ƃ̋��_����ڎw��WG�ł́A�b�܂ꂽ�n�M���������p���Ă����B �C�m�G�l���M�[�֘A�Y�Ƃ̋��_��WG�ł́A�C�m�G�l���M�[���d�̎��؎��ƂɎ��g�ގ��Ǝ҂̂���Ȃ�U�v���s���B ���f�G�l���M�[�֘A�Y�Ƃ̋��_��WG�ł́A�n�Y�n���^�̃��f���s����\�z����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��[IT] �T�C�o�[�U���Œ�d�h���c�E�C���X����`���� �o�ώY�ƏȂ́A���d�ݔ���z�d�ԂȂǂ̃E�C���X�����ɂ���d��h����̎w�j���܂Ƃ߁A���N3���܂łɓd�C���Ɩ@�̏ȗ߂���������B �d�͑��͋ƊE�̎w�j�ɉ����ăT�C�o�[�U������u���Ă���B�S�ʎ��R�����\�肳��A�Ζ���K�X�A���ЂȂLjًƎ�̊�Ƃ�A��K�͑��z���╗�͂Ȃǂ̔��d���Ǝ҂̎Q���������܂��B�d�̓V�X�e���̗��p�҂������A�E�C���X�N���̃��X�N�����܂邱�Ƃ���A����`���Â��邱�Ƃɂ����B �z�肳����Q�Ƃ��āA�u�X�}�[�g���[�^�[�v���U���ΏۂɂȂ�\��������B�T�C�o�[�U���œd�͋������Ւf����鋰�ꂪ����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ��[���{] �_�R�����ɖ���ăG�l�|�e���V�������{���㉟�� ���z����854��kWh�^�N�A�؎��o�C�I�}�X��70��kWh�^�N�A�����͂�8.9��kWh�^�N�ƁA���y�̑������߂�_�R�����ɖ��関���p�����̕����ʂ͖c�傾�B���̊��p�������㉟������B�S���̎����̂̂����A��3���ɂ�����467�����̂��_�R�����ɂ�����ăG�l���d�ɊS�������Ă���B �_�ы��Ǝ҂ɂƂ��čăG�l�͐Ζ��Ȃǂ̔R������팸���A���d�����������߂邾���łȂ��A�n��̌ٗp�̊g���Y�Ɣp�����̓K�������ɂ����ѕt���d�v�Ȗ����p�������BFIT�ȍ~�͎��ƍ̎Z���ɂ����ʂ��𗧂Ă���悤�ɂȂ�A������̎x�����܂߂��̕��y�g��Ɋ��҂����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��[���{] �ȃG�l�A�T�[�r�X�Ƃɂ��ڕW���������o�Y�Ȃ���܂Ƃ� �o�ώY�ƏȂ́A��Ƃ�ƒ�ɂ�����ȃG�l����܂Ƃ߂��B ��ƕ���̏ȃG�l�́A�Ǝ킲�Ƃɍł��ȃG�l���i���Ǝ҂���ɂ����ڕW��݂��A���̎��Ǝ҂ɒB���𑣂����x�̊g�[���f�����B �V���ȑΏی��́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g��S�ݓX�A�R���r�j�G���X�X�g�A�Ȃ�6�Ǝ�ŁA2015�N�x�ɂ�1�`2�Ǝ��������l�����B ��Ƃ̏ȃG�l�������i�t������d�g�݂�2016�N�x�ɓ�������B��Ƃ�4�O���[�v�ɕ����A�D�ꂽ��Ƃ����\���A�w�͕s���̊�Ƃɒ��ӕ�����z�z����B �ƒ땔��ł́A2020�N�ɐV�݂���ˌ��ďZ��̔����ŃG�l���M�[����ʂ��[���ɂ���v�悾�B �I�t�B�X�r���⏤�Ǝ{�݂̐V�z���ɏȃG�l��ɓK��������`�������荞�ށB �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ��[��] ���ۃG�l���M�[�@�ցA�C��ϓ��g�g���COP21�𐬌������邽�߂�4�̒���� ���ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j�́A���ʕ������\���A2015�N12���Ƀp���ŊJ�Â����COP21�𐬌������邽�߂ɕK�v��4�̒����������B ���ł́A�G�l���M�[�Ɋ֘A�����������ʃK�X�iGHG�j�̔r�o�ʂ́A���̔r�o����2�{�ƂȂ��Ă���A������ɂ�����GHG�̔r�o�팸���ŗD��Ɏ��g�ޕK�v������Ǝw�E���Ă���B 4�̒��Ƃ́A �@1�jGHG�r�o�ʂ������Ƀs�[�N�ɒB����𐮂���B �@2�j5�N���ƂɊe���̋C��ڕW���������B �@3�j�C���㏸��2�������ɗ}����Ƃ������E�̋C��ڕW���A���ʂ̒����I�Ȕr�o�팸�ڕW�Ŏ����B �@4�j�G�l���M�[����ɂ�����E�Y�f����ǐՂ���v���Z�X���m������B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ��[�Z�p] ����c��ȂǁA�M�����ɗD���u�f�M���k��C�~�d�V�X�e���v�J���ɒ��� ����c��w�A�G�l���M�[�����H�w�������y�ѐ_�ː��|���́A�u�f�M���k��C�~�d�V�X�e���v�̊J���ɒ��肵���Ɣ��\�����B ���V�X�e���́A�d�͂����k��C�ƔM�̌`�Œ������A�K�v�ɉ����Ē������ꂽ���k��C�ƔM���g���Ĕ��d����V�X�e���B �o�͂ƃG�l���M�[�����ʂ̑g���������R�A�Ƃ�����������L����B����̊J���́ANEDO�́u�d�͌n���o�͕ϓ��Ή��Z�p�����J�����Ɓv�̈�Ƃ��Ď��{������̂ŁA�Đ��\�G�l���M�[�i���ɕ��͔��d�j�̏o�͕ϓ��̗}����d�͎��v�̃s�[�N�V�t�g���̕������E��������ړI�Ƃ���B2016�N�x��MW�N���X�̎��؋@�̎��^�]���s���A2017�N�x�ȍ~�̏��i����ڎw���Ƃ����B �o�T�u���W�]��v |
|
|
| ���@�@[�@2015/7�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�X�{��B�d�́{�o����3�ИA���A��s���ɐΒY�Η͔��d�������݂� �d�́E�K�X�E�Ζ��̑��ɂ��哱�������������ɂȂ��Ă����B�d�͂̔��㍂5�ʂ̋�B�d�͂���s���̎��Ɗg��Ɍ����āA�K�X1�ʂ̓����K�X�ƐΖ�2�ʂ̏o�����Y��������3�ИA���Ŕ��d���Ƃɏ��o���B�Ő�[�̐ΒY�Η͔��d���𓌋��d�͂̃K�X�Η͔��d���ׂ̗Ɍ��݂����_�Ȍv�悾�B 3�Ђ����݂���ΒY�Η͔��d���͏o��200��kW��\�肵�Ă���B�ΒY�Η͂̔��d�����̒��ł������������u���X�ՊE���v���̗p����B5��1����3�Ђ�������SPC�i���ʖړI��Ёj��ݗ������B�^�]�J�n��2020�N��̔���\�肵�Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���ƊE���A�p�b�V�u�f�U�C���F�ؐ��x���V���ɂ��X�^�[�g �p�b�V�u�f�U�C�����c��́A�����I���q�ϓI�Ȏ��_�Ńp�b�V�u�f�U�C����]���E�F����ƊE���̎��g�݂Ƃ��āu�p�b�V�u�f�U�C���F�ؐ��x�v��n�݂���B �����c��́A���s�ȃG�l��ŕ]������Ȃ��p�b�V�u�f�U�C���̎��g�݂ɃX�|�b�g�āA������q�ϓI�ɕ]���E�F���鐧�x���X�^�[�g����B �����̔F�ł́A�p�b�V�u�f�U�C�����������̕�����]������u�v���Z�X�]���F�v�A������N�Ԓg��[���ׂɂ��Đ��l�I�ɕ]������u��ʕ]���F�v��p�ӁB���Ǝ҂̔F�ł́A���̃p�b�V�u�f�U�C�������{����̐��������Ă��鎖�Ǝ҂ł��邱�Ƃ�]������B �o�T�u�V���n�E�W���O�v |
|
|
| �����q�͂ɂ͌������ڐ��A�d�͉�БI����8���ȏオ�u���Ŕ��d���Ă��邩�v���d�� ���{���������g���A����͑S����1000�l��Ώۂɍs��������ꂩ��̓d�͂̂�����ɂ��Ă̏���҈ӎ�������̌��ʂ����J�����B ���̒��Łu�d���\���͑I���̂��߂ɕK�v�ȏ�ǂ����v��q�˂��Ƃ���u�K�v�ȏ��ł���v�Ƃ̉����l��82.9�����߂��B����ɓd�͉�Ђɑ��āu�d���\���̏����J���`���t�����ق����ǂ����v�Ƃ����₢�ɑ��ẮA88.5����9���߂��̐l���u�`���Â����ق����ǂ��v�Ɠ����Ă���B ��ʏ���҂͓d�͉�Ђ�I������ۂɓd���\���Ɋւ�������d�����Ă���A���q�͔��d�ɑ��Ă͈ˑR�Ƃ��Č������ڂ������Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��IHI �������ɑ��́g���c�h�A���E�ő勉 ���Ђ�2011�N�x����_�ˑ�ȂǂƉ��l���Ə��Ŏ������d�ˁA��ʔ|�{�Z�p���m�������B�|�{���鑔�́A�d�ʂ̔����������Łu���̔R���v�Ƃ��Ă��u�{�c���I�R�b�J�X�v�B���a�͐��}�C�N�����[�g���B��_���Y�f�iCO2�j���z�����Č������ő��B����B ����ɋZ�p�����߂邽�߁A���Ǝ��Ԃ������������s�ɁA�ʐς�1500�������[�g���A���[15�Z���`�K�͂̔|�{�{�݂����݂����B�|�{�{�݂̒�ɒ��菄�点���ǂ���CO2�̖A�𐁂��o���ă{�c���I�R�b�J�X��|�{����B���d����H��̔r�K�X�̍ė��p��z�肵�Ă���B�R�X�g�͍���5����1�Ō������݂�1���b�g��100�~�ȉ����ڕW���B2020�N�̎��p����ڎw���B �o�T�u�����{�V���v |
|
|
| ���ȃG�l���ʂ������K�X�A�ᕉ���̉^�]�������グ�Ă����ƏȃG�l �����K�X�Ȃǂ̑��s�s�K�X3�Ђ̓A�C�V�����@�A�p�i�\�j�b�N�A�����}�[�G�l���M�[�V�X�e���Ƌ����ŐV�^GHP���J�������B �Z�p���ǂɂ���ď]���@���N�ԉ^�]�����ϖ�25������A1���G�l���M�[����ʂ�N�Ԗ�20���팸���Ă���B �ᕉ��Ԃł̉^�]���������߂邽�߂ɂ̓G���W���̍쓮�E��~�ɂ��G�l���M�[���X�����炷���Ƃ��d�v���B�����ŐV�@��͍Œ�o�͂�15���ጸ�B�ᕉ���̘A���^�]���\�ɂ��ăG���W���̔���X��}���Ă���B �G���W����]���ɑ��鈳�k�@��]������œK������Ȃǂ̑���{���āA�G���W���̔���X�ጸ�������������ʁA�ᕉ�^�]���̌��������ϖ�40�����サ���Ƃ����B �u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���V���[�v�A�t���f�B�X�v���C�Z�p��p�����g���p�̌��t�B�����h�B�ȃG�l�ɍv�� ���Ђ��J�������u�̌��t�B�����v�́A���z�̔N���^���E�����^�����l���������x�Ȍ��w�v��p�������̂ŁA�t�B�����̕\�ʂɔ����H���{�����ƂŁA�Б��ɗl�X�Ȋp�x��������ė�������A���Α�������̊p�x�ŏo�����Ƃ��ł���B ���̃t�B�����𑋂̏㕔�ɐݒu����ƁA�G�߂⎞�ԑтɉ����ĕω�������ˊp�x�Ɋւ�炸�A���z���������I�ɓV������Ɏ�荞�߂�B�V��ɂ����������͊ԐڏƖ��̂悤�ɁA�����̐l�ɍ~�蒍���B���̂��߁A�̌��t�B��������̌������ڊ�ɓ��鎖�Ŋ�����A�s���ȃO���A(ῂ�����)��}���Ȃ���A�����S�̂𖾂邭�ł���Ƃ����B���Ђ̌��ł́A�N�Ԃł��悻4���̏Ɩ��p�d�͂̍팸���\�ɂȂ�Ƃ���B �o�T�uAV�E�I�b�`�v |
|
|
| �����{�R�J�E�R�[���A�u�s�[�N�V�t�g���̋@�v�̐ݒu�䐔���S����10 �����˔j ���Ђ́A�ȃG�l�^�����̔��@�u�s�[�N�V�t�g���̋@�v�̑S���̎s��ݒu�䐔��2015�N5����10�����˔j�������Ƃ\�����B �u�s�[�N�V�t�g�v���̋@�́A�u�s�[�N�J�b�g�v��A�m���t���������̔��@�̓����ȂǁA���Ή��ɂ����������g��ł������Ђ��A�����{��k�Ќ�ɕN�����������̓d�͎g�p�ւ̎����I�ȑΉ��Ƃ��ĊJ�������ȃG�l�^�����̔��@���B�s�[�N�V�t�g�e�N�m���W�[�ɂ��A�����̏���d�͂��ő�95%�팸����B ���Ђ́A�u�s�[�N�V�t�g���̋@�v��2020�N�܂łɑS���̃R�J�E�R�[�������̔��@�̔����ȏ�ݒu��ڕW�Ƃ��Ă���B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| �����}�_�d�@�\�t�g�o���N�ƒ�g�ȃG�l�Z��̔����� ���Ђ�25���t�Ŕ��s�ς݊����̖�5�����\�t�g�o���N�Ɋ��蓖�āA�ƒ�̎g�p�d�͂�K���ɊǗ����ďȃG�l����������V�X�e���̋����J���Ȃǂ�ڎw���B �Ɠd�̔����Ƃ͏��q����ȂǂŐL�єY�ނ��Ƃ��\�z�����B��g�ɂ��A�͂����Ă���Z��Ƃ���v�Ȏ��v���Ɉ�Ă�B �S���W�J���郄�}�_�d�@�̓X�ܖԂ����p���Čg�ѓd�b���܂ޒʐM�T�[�r�X�̔̔��Ȃǂ���i�Ƌ����������\�t�g�o���N�Ǝv�f����v�����B�Ɠd�ƒʐM�T�[�r�X�A�d�͂�g�ݍ��킹���V�����T�[�r�X�n�o���������Ă���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���֓��o�ώY�Ƌǁu�o�c���_����̏ȃG�l�x���n���h�u�b�N�v���쐬 �֓��o�ώY�Ƌǂł́A����25�N�x�E26�N�x��2�N�Ԃɓn��A������K�͎��Ǝ҂̏ȃG�l�o�c���i���f�����ƣ�����{�����B �{���f�����Ƃł́A�n��x���@�ւ𒆐S�Ƃ����A�g�̂ɂ�钆���K�͎��Ǝ҂ւ̎x����ʂ��āA�o�c�̓A�b�v�Ɍ��ѕt���ȃG�l�̎��g�݂��㉟�����邽�߂̎x���̐��\�z��x���̕��@�ɂ��Č����s���Ă��܂����B ���ʁA���̌��،��ʂ���ɁA�n��x���@�ւ������K�͎��Ǝ҂ɑ��ďȃG�l��ʂ����o�c�̓A�b�v���x�����邽�߂ɋ�̓I�ɉ������ׂ����A���̃|�C���g���Ƃ�܂Ƃ߂���o�c���_����̏ȃG�l�x���n���h�u�b�N����쐬�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v ��o�c���_����̏ȃG�l�x���n���h�u�b�N�(PDF:1,616KB) http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shiene/data/20150423handbook.pdf |
|
|
| �����E��CO2�u�댯����v��˔j�ē��ǔ��\ �ĊC�m��C�ǁiNOAA�j�A���E�̑�C����CO2�Z�x�̌����ϒl�����N3���ɏ��߂�400ppm�����Ɣ��\�����BNOAA�͒n�����g���̗v���Ƃ���CO2�Z�x�̏㏸���N���ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA�u�d�v�Ȑߖڂ��v�ƌx����炵�Ă���B ���E40�J���̊ϑ����ł̑��茋�ʂ��疾�炩�ɂȂ���CO2�Z�x��400.83ppm�B �����ςł�400ppm���́A�n�����g���̊댯�����Ƃ����BCO2�Z�x�̏㏸�͒n�����g���������N�����Ƃ���Ă���A2014�N��1880�N�ȍ~�ōł��C���������N�ɂȂ����BNOAA�́uCO2�Z�x�̏㏸��H���~�߂�ɂ́A���ΔR������̔r�o�ʂ�8���팸����K�v������v�Ǝw�E���Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �������s�A�u�ȃG�l�^�f�[�^�Z���^�[�v�̔F�萧�x��n�ݒ�����Ƃɂ͕⏕���� �����s�́A���{�f�[�^�Z���^�[����ƒ�g���A�V���Ɂu���z���^�f�[�^�Z���^�[�F�萧�x�v��n�݂���Ɣ��\�����B ����ɁA������Ǝғ����ۗL������V�X�e�������A�{���x�ŔF�肳�ꂽ�f�[�^�Z���^�[�ʼnғ�����N���E�h�T�[�r�X�Ɉڍs�������ꍇ�A���̌o��̈ꕔ���������鎖�Ƃ�{�N11������J�n����\��B�\�Z��6.75���~�B �s�́A�����̎�g�݂ɂ��A���ɔz�������f�[�^�Z���^�[�̕��y�ƒ����K�͎��Ə��̏ȃG�l���𐄐i���Ă����B���F�萧�x�́A���ɔz�������������ȃf�[�^�Z���^�[��ʓr��߂�F���Ɋ�Â��]���E�F�肵�A�u���z���^�f�[�^�Z���^�[�v�Ƃ��Č��\���鐧�x�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��2050�N�̎s��K�͂�160���~�B���悢�敁�y�Ɍ����ē����o�����u���f�v�Љ� ������R���u���f�v�ɑ���S�����܂��Ă���B���{���{�͍��������Đ��f�Љ�̐��i�Ɏ��g�ގp���������Ă���A�g���^�����E�ɐ�삯�Ĕ��������R���d�r��(FCV)�uMIRAI�v�����@�y�ьo�ώY�ƏȁA���y��ʏȁA���ȂɌ��p�ԂƂ��ē��������B 2020�N�ɊJ�Â���铌���I�����s�b�N�܂łɍ����̐��f�C���t�������A���f�G�l���M�[�V�X�e�����\�z���邱�ƂŁA����ׂ��u���f�Љ�v�̎p�𐢊E�Ɍ����Ĕ��M������j�������Ă���B ���f�r�W�l�X�̃`�����X��FCV�̕��y�̑��A���f�X�e�[�V�����֘A�̐��f���k����i�A�R���d�r�p���i�E�ޗ����[�J�[���傫�ȉ��b���邱�ƂɂȂ邾�낤�B �o�T�u�G�R�m�~�b�N�j���[�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�@�֘A�ŐV���ȓ����������]�����Ďx���E�D������d�g�݂Ȃ� �o�ώY�ƏȂ́A�ȃG�l���M�[���ψ���ŁA�H�ꓙ�ɂ�����G�l���M�[�̎g�p�̍������̕]���݂̍����A�ȃG�l�@�̌����ɌW�鍑�ƒn���݂̍�����ɂ��ċc�_�����B ��v�_�_�́A �@�ȃG�l��g�ݏɉ��������Ǝ҂̃N���X�����ƃN���X�ɉ����������n���̂���Ή��B �A����̕��͌��ʂ̊��p�݂̍�� �B�x���`�}�[�N���x�����p���Ď��ƎґS�̂̕]���̈����B �C�����p�M���p�̕]���Ɋւ���_�_�A�D�ȃG�l�@�̌����ɌW�鍑�ƒn���݂̍�����ɂ��Ă̕� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���r�o�ʎ���A���E�Ŋg��15�N���łɂS���~�K��
���g���K�X��r�o�ł��錠��������r�o�ʎ�������铮�������E�ōL�����Ă���B�N���̋C��ϓ���c�ŁA���x�Ɋւ��鍇�ӂ�����Ƃ̊��҂������K�͂������B ���E��s�ɂ��ƁA2015�N4�����_�őO�N�̓������Ɣ�ׂ�1������340���h���i��4��1000���~�j�������B���ĂȂǐ�i���ɉ����A������؍��ȂǐV�������������Ă���B ���ێЉ��20�N�ȍ~�̉��g����̍��ۘg�g�݂ŁA�N���Ƀp���ŊJ����21�A�C��ϓ��g�g�ݏ�����c�iCOP21�j�ō��ӂ���v��B�r�o�ʎ������ł����炩�̑O�i������Ƃ݂��Ă���B�o���Z���i�ŊJ�Â��ꂽ���g���֘A�̌��{�s�u�J�[�{���E�G�L�X�|�v�ł́A��100�̊�ƁE�@�ւ��Q�������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ����Ƃ̏ȃG�l��4�i�K�Ŋi�t���o�Y�ȁA2016�N�x���� �������Z�ŔN��1500�L�����b�g���ȏ�̃G�l���M�[���g����P��2000�Ђ�ΏۂɁA�ȃG�l�̎��g�݂̗D��ɉ�����4�̃O���[�v�����N���{����B ���ʂ̐��Y�Ɏg���G�l���M�[�̌������������u�G�l���M�[���P�ʁv��5�N�A����1���������Ă����Ƃ͌o�Y�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ō��\����B�Y�������1200�Ђɂ͕⏕���Ȃǂ�D������[�u����������B��ʓI�Ȑ����̖�1���Ђɂ͓��ʂȑΉ��͋��߂Ȃ��B ����A�G�l���M�[���P�ʂ�3�N�A��������Ȃǂ�����1200�Ђɂ͒��ӂ𑣂������𑗂�A�������茟������B���g�݂��������s�\���Ȗ�50�Ђɂ͏ȃG�l�@�Ɋ�Â������ʎw�����s���A���N�x�ȍ~�̉��P�𑣂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������ʃK�X�F2030�N��26%���A�ڕW���������ȃG�l�� ���{�͒n�����g�������i�{���ŁA��_���Y�f�iCO2�j�Ȃǂ̉������ʃK�X�r�o�ʂ��u2030�N�܂ł�13�N��26���팸�v����V���ȖڕW�Ă����߂��B����15�N�ԂŁA�Ɩ��E�I�t�B�X�Ɖƒ땔��ł��ꂼ���4���A�^�A�����3����̔r�o�ʍ팸��������ł��邪�A�J�M������ȃG�l��̎��s�͗e�Ղł͂Ȃ��B �팸�ڕW�̑O��́A�����_�C�I�[�h�iLED�j�Ȃljƒ�̍������Ɩ���30�N�ɂ͂ق�100���ɂ���B�q�[�g�|���v���ȂǍ������ȉƒ�p�������6�{�ȏ�ɂ���ق��A�d�C�����ԂȂǎ�����Ԃ̕��y����啝�Ɉ����グ��B�܂��A�K�X�X�g�[�u�̔R���A�e���r�̏���d�͂̐��\����Ȃǂ荞�B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���@�@[�@2015/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���S���Q���̍H��ȃG�l����������A�G�l���M�[�u�����鉻�v�\�t�g �H��Ȃǂ̎{�݂ɂ����āA�����I�ɃG�l���M�[�𗘗p���邽�߂ɂ́A�Ǘ�����ȂǓ���̑Ώێ҂����łȂ��A��葽���̎{�݂̗��p�҂��G�l���M�[�̎g�p��c�����A�ȃG�l�̈ӎ������߂邱�Ƃ��d�v���B���̂��߁A��葽���̏ꏊ��f�o�C�X�ŃG�l���M�[�̎g�p���ȒP�ɔc���ł���V�X�e�������߂��Ă���B �p�i�\�j�b�N���J�������̂́A�H��Ȃǂ̃G�l���M�[�g�p��ݔ��̉ғ��A���z�����d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�̔��d�ȂǁA�G�l���M�[����̏�Ԃ�ω������A���^�C���ŏ]�ƈ��ȂǂɁg������h���Ƃ��ł���G�l���M�[�����鉻�\�t���B2015�N4���ɔ̔����J�n���Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���˓c���ݎ{�H����CO2�r�o�ʂ��팸����V�X�e����web�� ���Ђ́A�{�H����CO2�r�o�ʂ��팸���銈���A��Y�f�{�H�V�X�e����2010�N����s���Ă��邪�A���̂��сAweb��ʼnғ�����V�X�e���ɉ��ǂ����B web�ł́A���ݍ�Ə���CO2�팸������̌n���A���l��������́B�S����140�J���̍�Ə��ɉ����A���͉�Ђ��܂߂��W�҂�web��ŏ������L���A�f�[�^���͂�}���_�ɓ���������B �{�H�O�ɍH�����Ԓ���CO2�r�o�ʂ��v�Z���A�팸���X�g����I�������팸��@�ɂ��팸�v��𗧈Ă���B���H��͂�������s���邪�A���{���ɍ팸���ڂ̕ύX��lj����\�B���{��ɃG�l���M�[�f�[�^����͂���A�H����CO2�r�o�ʂ�팸�ʂ�c�����ł���B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ���ΒY�w�łƂ��V�^�̓V�R�K�X�A400�����ѕ����I�[�X�g�����A���璲�B �d�͉�ЂƂ̋����Ɍ�����LNG�i�t���V�R�K�X�j�̒��B����g�咆�̓����K�X���A����܂ł͊J������������ΒY�w�̋T��ɑ��݂���uCBM�i�R�[���E�x�b�h�E���^���j�v�ƌĂԓV�R�K�X���I�[�X�g�����A�������n�߂��B 2015�N����20�N�Ԃɂ킽���čw������_�������ł���B1�N�Ԃ�120���g����LNG�B����_�B ���Ђ̓G�l���M�[�̋����̐����������邽�߁A�K�X�̋����ʂ�2020�N�܂łɖ�1.5�{�̋K�͂Ɋg�債�Ȃ���A�d�͂ƔM���ɋ����ł���R�[�W�F�l���[�V������啝�ɐL���v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�͎��R���ŊJ�������7.5���~�̍����ሳ�s��A���Ă̓d�͎��Ǝ҂����Ƃő_�� 2016�N4���ɃX�^�[�g����d�͂̏����S�ʎ��R���ɂ��A�ሳ�s�ꂪ�J������A���̎s��K�͖͂�7.5���~�ȏ�ɂȂ�ƌ����Ă���B �V�d�͂̃C�[���b�N�X�́A�č��e�L�T�X�B�ɖ{����u���d�͏������Ǝ҂�Spark Energy�Ɠ��{�����̒ሳ�s��ւ̎Q���Ɍ����āA�̎Z���Ȃǂɂ��Ă̋����������J�n����Ɣ��\�����BSpark Energy���č��Ŕ|�����ሳ�s������d�̓r�W�l�X�̒m������{�����ł����p����_�����B 1999�N�ɐݗ����ꂽSpark Energy�́A���ݕč���16�B�ɂ����ďZ��E���p�����ɓd�́E�K�X�̋����T�[�r�X��W�J���Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����ёg�e�N�m�X�e�[�V�����ŃG�l���M�[���x�[�������� ���Ђ�2010�N�A�e�N�m�X�e�[�V���������݂��A2011�N�x�ɂ�CO2�r�o�ʂ̍팸�ƃJ�[�{���I�t�Z�b�g�Ŏ��x�[���ɂ���G�~�b�V����ZEB���������Ă���B ���X�e�[�V�����ł́A�N�Ԃ̃G�l���M�[���x�[���ƂȂ�ZEB�B����ڎw���āA2014�N�x�ɍĐ��\�G�l���M�[���d�ݔ���lj����������B����ɁA�i�C�ɔ��������̉^�p���Ԃ������������ƂɑΉ����邽�߁A�V���ȑ�Ƃ��āA�A���r���A�Ɩ��@��̐���̉��P�ƍ��������A�R�[�W�F�l���[�V�����r�M�̊��p�Ȃǂ��u�����B �x���ȂǂŔ��d�ʂ�����ʂ��������ꍇ�A�d�͋t�������A�d�̓o�����X���œK������u�Z���t�f�}���h���X�|���X�v�ɂ���Ēጸ�����邱�Ƃɂ����������B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ���_�|�����R������ʂQ�T���팸�A�A�C�h�����O�X�g�b�v�ŒB�� ���Ð쐻�S���̍\����36��̃f�B�[�[���@�֎Ԃ�24���ԁE365���̐��ʼn^�]���A�R���́A�N��1600kL���g�p���Ă��邪�A�R���g�p�ʂ̒ጸ���K�v�ɂȂ����B �f�B�[�[���@�֎Ԃ̑ҋ@���Ԃ�1������12.8���ԂŁA���A�C�h�����O���Ԃ�57���i7.3���ԁj�̒�~��ڕW�Ƃ����B �܂�1��̋@�֎Ԃɑ��āA�A�C�h�����O��1������ƃG���W����������~����v���O�����ɉ��������B�܂��A�^�]�҂��C�ӂő��M�@�����~�ł���悤����M�@�̉������Ȃǂ����{�����B���̌�A36��̋@�֎Ԃɓ����������ʁA�y���g�p�ʂ�N��393kL�A�]�����25���팸�ł����B�ȃG�l���ʂ͔N��2360���~�BCO2�r�o�ʂ͔N�Ԗ�1000�g����B�������B �o�T�u�����E�C�[�N���[�v |
|
|
| ���e�X���A�����u���^�~�d�r�Q�����А��i�̔��z�ȉ� �ēd�C�����ԁi�d�u�j���[�J�[�A�e�X�����[�^�[�Y�́A�ƒ��r���A��K�͂ȑ��z�����d���ȂǂŎg���鐘���u���^�̒~�d�r��8���ɂ���������Ɣ��\�����B�d�u�����Ƀ��`�E���C�I���d�r��ʎY���Ă����o�������A���i�𑼎А��i�̔��z�ȉ��ɗ}����B���̕���Ő�s���Ă������{���ɂƂ��đ傫�ȋ��ЂƂȂ肻�����B ���i�́A�ƒ�����́A�e��10kWh�̃��f���ŁA3500�h���i��42���~�j�B�VkWh�̃��f����3��h���i��36���~�j�B�č��ł͋ƊE�̕W���I�Ȑ��i�̔����ȉ��̉��i�ƂȂ�B�Œ�10�N�A�ő��20�N�܂ʼn����ł���ۏ�����B�e��10kWh��2��h�����A�~�d�r�������I�ɕ��y����ڈ��Ƃ���Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����{�K�C�V�A�~�d�r���R�X�g�E���S��2017�N���i�� ���Ђ́A���ӂ̃Z���~�b�N�X�Z�p�����A�d�ɂɈ����Ȉ������g����悤�ɂ����B�d�r�e�ʂ�1kWh����1��kWh���x��z��B��ʉƒ�⏬�K�͍H��Ȃǂő��z�����d������Ȗ�ԓd�͂�~����d�r�Ƃ��ĕ��y��ڎw���B �J�������̂́A���ɂɃj�b�P���A���ɂɈ������̗p���鈟��2���d�r�B���`�E���C�I����j�b�P�����f�ȂNJ�����2���d�r�ɔ�ׂāA���A���^���Ȃǂ̎g�p��啝�ɗ}���邱�Ƃ��ł���B�R�X�g�ጸ�⌴�ޗ��̈��蒲�B�����₷����A�R���̓d���t���g��Ȃ��̂ŁA���p���̈��S���������B�Г������ł�600���ԘA���ŏ[�d���Ă��s����N���Ȃ������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���_���ɐV�d�͕��y�֎��؎����_���� �_�ѐ��Y�Ȃ͔_�����ł̐V�d�͕��y�Ɍ��������؎����ɏ��o���B�_�Ƃ̐��Y�{�݂ɃX�}�[�g���[�^�[��ݒu���ēd�C�̗��p��c������ȂǁA�V�d�͉�Ђ̎��v����������B�����͂�o�C�I�}�X�Ȃǔ_�����ɂ����Đ��\�G�l���M�[����āA���l�ȓd�͋������\�ɂȂ�ʂ��A�s�[������B ���Ȃ͍��āA�k�C���ȂǑS��5�`10�n��Ŏ�����i�߂���j���B�V�d�͂����y����Δ_�ƂȂǂ̓d�C�����������`1�����x�����Ȃ���ʂ�������Ƃ݂�B �e�{�݂̗��p�̃f�[�^���W�߂���A���d����������p�����Z�����肷��B�{�Y�Ƃ����̔r�����𗘗p���Ĕ��d�����d�C��V�d�͂�����������ꍇ���z�肵�A�̎Z�����������ׂ�B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���R�[�W�F�l�ȂǕ��y�x���o�Y�ȁA�u���U�^�v�Ŕ�펞�ɂ��Ή� �o�ώY�ƏȂ́A�L���҉�c�u�����G�l���M�[�������ʂ����ψ���v�ŁA���q�͂�Η͂Ȃǂ̑�^�d���ɗ���Ȃ����U�^�d���𑝂₷���j���������B ���U�^�d���́A�K�X�Ŕ��d���A�p�M���⋋���Ȃǂɗ��p�ł���R�[�W�F�l���[�V�����⑾�z���╗�͔��d�ȂǁA�l�X�Ȓn��ɕ��U����G�l���M�[���w���B ��K�͍ЊQ�Ȃǔ�펞�̃G�l���M�[�������ɂȂ�ق��A���d���ɔ�������M���ƒ�Ȃǂŗ��p�ł���̂��������B���d���ʼn����ɓd�C�𑗂�K�v���Ȃ����ߑ��d���X�����Ȃ��A�G�l���M�[�������I�Ɏg�p�ł���B ����A���U�^�d���Ȃǂł������]��d�͂��s��Ŕ���₷������ق��A�⏕���Ȃǂɂ��x���[��������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����`�E���ɑ���i�g���E���C�I���d�r ���݂̓��`�E���C�I���d�r���嗬�����A�f�ނɂȂ郊�`�E�������A���^���ō������B���̂��߁A�i�g���E�����g�����d�r�̊J�����i��ł����B �i�g���E���C�I���d�r�̌����̓��`�E���C�I���d�r�Ǝ��Ă���B�d�r�̃v���X�ɂƃ}�C�i�X�ɂ̂��������i�g���E���C�I���iNa+�j���ړ����āA�[�d�ƕ��d���\�ɂȂ�B �������ȑ�w�ł̓��`�E���C�I���d�r�����鍂���G�l���M�[���x�i500Wh/kg�O��j��B�����Ă���B�i���`�E���C�I���d�r�̃G�l���M�[���x��150�`200Wh/kg�j�B���̂ق��̑�w�⌤���@�ցA�d�r���[�J�[�̂������ł��i�g���E���C�I���d�r�̊J�����i��ł���B2020�N�܂łɂ͎��p���������܂�Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������70��kW����y�[�X�ő����A2014�N�̍Đ��\�G�l���M�[ �����G�l���M�[�����܂Ƃ߂�2014�N12�������_�̍ŐV�f�[�^�ɂ��ƁA�Œ艿�i���搧�x�̔F������Đ��\�G�l���M�[�̓����ʂ͍��v��1582��kW�ɂȂ����B2014�N�͌����ς�73��kW�����������B�ˑR�Ƃ��đ��z����9���ȏ���߂Ă�����̂́A���͂������ɐL�тĂ����B7.4��kW����23��kW��1�N�Ԃ�3�{�Ɋg�債�Ă���B ������z�ł́A2012�N7���ɐ��x���J�n���Ă���2�N����1��5078���~�ɂ̂ڂ�B���̂������z�����Z��p�Ɣ�Z��p�����킹��1��1077���~��73�����߂�B�����ŕ��͂�2341���~��16���A�o�C�I�}�X��1166���~��8���̏��ł���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������̂̃m�E�n�E���A�W�A�e���ɓW�JJCM�N���W�b�g�l���Ɍ���9���Ƃ��n�� ���Ȃ́AJCM�i�ԃN���W�b�g���x�j�N���W�b�g�l���Ɍ����āA�ȃG�l�̃m�E�n�E���������̂������@�ցE��Ɠ��ƂƂ��ɁA�A�W�A�́u�s�s�܂邲�Ɓv��Y�f�����x������B���{�̎����̂��֗^���A���������@�ցE���Ԋ�ƁE��w���ƂƂ��ɁA��i�I�Ȓ�Y�f�Z�p��x�̓��������n�̎���ɉ����Ē������A�^�c�E�ێ��Ǘ��̐����m�����邱�Ƃ�����ɒ����E�������s���B ����̑����ꂽ�̂́A�u�n�C�t�H���s�܂邲�ƒ�Y�f���������Ɓi�k��B�s�|�n�C�t�H���s�A�g���Ɓj�v�A�u���l�s�E�o�^���s�̓s�s�ԘA�g�ɂ��JCM�Č��`���x���������Ɓv�A�u�z�[�`�~���s�E���s�A�g�ɂ���Y�f�s�s�`���x���������Ɓv�Ȃ�9�����̑������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����d�A�g��̌��́u���Ə���ł���X�}�[�g�R�~���j�e�B�v�����{������ �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��Ɍ������{��݂̍���ɂ��Č������s���Ă��鏬�ψ�����J�Â����B �ψ���ł́A�u�X�Ȃ�Đ��\�G�l���M�[�̓����g��Ɍ���������̕������v�Ɓu�Đ��\�G�l���M�[�����g��Ɍ������L��I�Ȍn���V�X�e���E���[���̍\�z�v�ɂ��āA�c�_�����B ���z�����d�ݔ��ɂ��āA�����e�i���X�̐��̍\�z���A�\�Ȍ��蒷������I�ɔ��d����G�l���M�[�C���t���Ƃ��Ċ��p���邽�߂̕�����u���邱�Ƃ��K�v���Ƃ��Ă���B�ЂƂ̕������Ƃ��āA�X�}�[�g�R�~���j�e�B�̍\�z���������B���̍ہA���v�n�ɋߐڂ��ē�������鎩�Ə�������i�߂Ă������ƂŁA���z���̓�����i�߂Ă������Ƃ��ł���Ǝw�E����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�n���M���p�ɂ������ẴK�C�h���C�������Łv�����\�V�K�Q���҂̎Q�l�� ���Ȃł́A�V���ɒn���M���p�̓������������鎖�Ǝ҂Ɍ����ɂƂ�܂Ƃ߁A���\�����B ��ȉ������e�́A�n���M���p�q�[�g�|���v�ɂ��ȃG�l���ʓ�����ыߔN�̕���̔��f�ƁA�ȃR�X�g���ʂɂ��Ă͎{�ݕʂ̎��Z��̒lj��ƃf�[�^�X�V���s�����B �n���M���p�q�[�g�|���v�̓����E���p�Ɋւ���z�������ł́A�K�p�ł���n���M�q�[�g�|���v�̕����ɂ��čĐ������s���ƂƂ��ɁA�K�p�ɂ������ė��ӂ��ׂ��_�ɂ��āA��̓I�ȋL�ڂ��������B���j�^�����O���@�ɂ��ẮA���j�^�����O���ڂ���ѕp�x�̌��������s���ƂƂ��ɁA���j�^�����O�@��̑I��E�z�u��j�^�����O�f�[�^��p�����e����ʂ̕]�����@���ɂ��Đ����̏[����}�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�����Ȃ�37���~�K�v�o�Y�Ȏ��Z�A15�N��̏���1������ �o�ώY�ƏȂ́A15�N��ɏȃG�l��ō����̃G�l���M�[����ʂ�1�������炵���ꍇ�A�ȃG�l�����̓����Ȃǂ�37���~���K�v���Ƃ��鎎�Z�𖾂炩�ɂ����B�o�Y�Ȃ́u�������o�ς�����������v�Ƃ��āA������⏕���Ȃǂ̎x����ŏȃG�l���㉟������l�����B ���Ȃ�15�N��A�ȃG�l�Ōv��5�疜�L�����b�g�����i�������Z�j�̃G�l���M�[�����点��Ƃ��鎎�Z�\�����B����ł́A�H��ȂǂŎg���d���Ȃǂ̔R�������炷�ȃG�l���ʂ𑽂�������ł���A�d�C�̏ȃG�l���ʂ�2�����_���猸���Ă���B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���@�@[�@2015/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}200lm/W��B���A�u�����ƌ������Ďg���钼�nj`LED �ϊ��������\�Ȍ��荂�߂邱�ƂŁA�Ɩ��̏���d�͂�����Ɍ��点�A�u�����⋌�^��LED�����v�Ƃ̌����Ɍ����Ƃ����B2015�N6���ɔ������J�n����B LED�f�q�̕����̉��P�ɂ�����������ł����B�d����u���́A����Ȃǂ͏]���Ɠ������BG13�����𗘗p���Ă��邽�߁A�u�����̓�������̂܂ܗ��p�\���B�F���x��5000K�A���ω��F�]����Ra��80���B����d�͂�10.0W�B������4�����ԁB���i��1��4500�~�B �S������2000lm�ł���A40W�`�̌u�����ɂقڑ�������B���̏���d�͂́A40W�`�̃��s�b�h�X�^�[�g���iFLR�j�u�����Ɣ�r����Ɩ�76�������Ȃ��B ���킹�āA���a��26.5mm�ƍׂ��AHf�`�u�����̔��^����p�̋@������\�����B �o�T�u��goo�v |
|
|
| ��EMS��BEMS�̘A�g�Œn��̓d�C�A�M�A���̎������� �k��B�X�}�[�g�R�~���j�e�B�n�����ƂŁA�r���̏ȃG�l�ƒn��S�̂̓d�͎����̈���ɍv������BEMS�̎��؎������{�i�����Ă���B�������ꂽBEMS�ł́ACEMS����̃_�C�i�~�b�N�v���C�V���O�ɑΉ�������������@�\�̌����{�i�����A��M���̍œK�����H���̌����鉻���k�ɂ��邱�Ƃɂ��ȃG�l������荂�܂��Ă���B �r���̏ȃG�l�������߂Ēn��̓d�͎����o�����X�ɍv�����邽�߂ɁABEMS�́A�G�l���M�[�̎��v�\���E�v��A�d�͂ƔM�̑o���𐧌�A�^�p�f�[�^�Ɋ�Â����e�{�݂̊Ď��E�Ǘ��̂ق��A�_�C�i�~�b�N�v���C�V���O�ɉ����Ċe�ݔ���v���Ɏ�������ł���d�g�݂������������Ƃ��������B �o�T�u���o�e�N�m���W�[�v |
|
|
| ���ϐ��n�E�X���V���Ȓ���|�{��E�����s�Ń}�C�N���O���b�h���p�����u�X�}�[�g�^�E���v ���ЂƓ������s���i�߂�u�������X�}�[�g�h�ЃG�R�^�E���v�́A�s���̃S�~�ċp���K�\�[���[�Ƃ������V�d�́iPPS�j����ꊇ��d���A���c�����g���Ēn����ɓd�͂���������d�g�݁B �n����ɂ͍ЊQ���c�Z���a�@�A�W���Ȃǂ̌����{�݂����n����B���z�����d�ݔ����^�~�d�r�A���p���d�@��������Ă���A�n����G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���iCEMS�j�ōœK����B�n���d�͂̋������~�܂��Ă��R���Ԃ͂����ʂ��点��B �~�n���z���ēd�͂𑊌݂ɗZ�ʂ���̂́A�{���ł���Ό������z���Ă̓d�͗Z�ʂ͋K���������邪�A����͒n�悪�ۂ��Ǝs�̕~�n�ł��邽�ߑ��ݗZ�ʂ��\�ɂȂ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���H��ɓ��������؎��o�C�I�}�X�̔M�d�����V�X�e���A�G�l���M�[���p����70�� �R�}�c�́A���ÍH��̕~�n���ɁA�ΐ쌧�̖����p�Ԕ��ނ̖؍ރ`�b�v���g�p����M�d�����V�X�e���A�u�o�C�I�}�X���C�{�C���V�X�e���v��V���ɐݒu�����B ���V�X�e���́A�{�C������̏��C�d�ɗ��p���邾���ł͂Ȃ��A�r�M���Ȃǂɍő�����p���邱�Ƃō����G�l���M�[������70�������������B �o�C�I�}�X�{�C���i4��j�A���C�R���v���b�T�i1��^75kW�j�A���C�����d�@�i2��^210kW�j�Ȃǂ���\�������B���p�M�ʂ�3,200kW�i���d�{�r�M�j�B�؍ރ`�b�v�g�p�ʂ�7,000�g���^�N�B�w���d�͍팸���ʂ͖�150��kWh�^�N�B�ݔ������z�͖�4���~�B���N4���ɖ{�i�ғ��\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�A�d�͏����r�W�l�X�ɎQ���d�́E�K�X���R���Ɍ������X�Ə��� ���Ђ́A2016�N�x����̑S�ʎ��R���ɂ��킹���d�͏������Ƃ̊g��Ɍ����A�u����K�͓d�C���ƊJ�n�͏o���v���o�ώY�ƏȂɒ�o�����B2015�N�x�́A���O���[�v�ł́A���ω��ɑΉ����A����̐��������҂ł���̈�̎��Ƃ�����Ɋg�債�Ă����B �d�́E�K�X�V�X�e�����v�ɑ��鏀���ɒ����Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�K�X�E�d�͓��̃G�l���M�[�ɁA�K�X�@���ƒ�����G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���iHEMS�j�A�z�[���Z�L�����e�B�V�X�e���ȂǗl�X�ȃT�[�r�X��g�ݍ��킹�Čڋq�ɒ���u�����G�l���M�[���Ɓv�ւ̐i����ڎw���B�G�l���M�[�̔̔��r�W�l�X�ł́A���R���͈͂̊g��ɍ��킹�A2016�N�x���d�͏������Ƃ��g�傷��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����d�́A�ۍg�Ƌ����ŏH�c�ɑ�^�ΒY�Η͔��d�������݁|��s���ł̓d���m�� ���d�͂́A�ۍg�Ƌ����ŏH�c�s�̘p�ݒn���130��kW�K�͂̐ΒY�Η͔��d�������݂���v��𖾂炩�ɂ����B�����A�H�c���ɐ��������͂�\�����ꂽ�B65��kW�̔��d�ݔ���2��݂�2020�N��̑����ɉ^�]�J�n����B�����Ɣ��3,000���~�K�́B�֓d�q��Ђ̐V�d�͂Ɗۍg�̋������Ɖ�Ђ����݁E�^�c���A����l�߂�o���䗦�ɉ����d�͂������B ���Ђ͎�s���ȂǂŎ��Ǝ҂�A�d�͊��S���R����2016�N4���ȍ~�ɂ͉ƒ�ɂ��̔�����\��B�֓d�͎��g�����قȂ铌���{�Ɏ��Гd����z���A�ő�s��̎�s���ɖ{�i�i�o����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�C�I�K�X��������CO2�����Z�p������A�H��ȂǓ������D���h�C�c��Ƃ���擾 �������D��100���q��ЂŁA���ݏċp�E���d�v�����g�̐v�A���݁A�ێ�Ȃǂ���|����Hitachi Zosen Inova�iHZI�j�́AMT�|BioMethan GmbH�iMTB�j����o�C�I�K�X�����ɂ�����Z�p�E�m�E�n�E�A���сA�����A�H��Ȃǎ��Y�ꎮ���擾�����B �������D�́AHZI�ƘA�g���A���ݏċp���d�v�����g��o�C�I�K�X�v�����g�ȂǂōŐ�[�̋Z�p�������O�̌ڋq�ɒ�Ă��A�Đ��\�G�l���M�[�̕��y��CO2�팸�A�����z�^�Љ�̌`���ɐϋɓI�ɍv�����Ă��������l�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��10kW�d�͂��}�C�N���g�ő��d��LED�_���|�O�H�d�H�A�������d�Z�p�̒n�㎎������ ���Ђ́A�F�����z�����d�V�X�e���iSSPS�j�̎����Ɍ����A�����œd�͂𑗂閳�����d�Z�p�̒n����؎����ɐ��������Ɣ��\�����B10kW�̓d�͂��}�C�N���g�ɕϊ�����500���[�g�����ꂽ�ꏊ�Ɍ덷1���[�g���ȓ��ő���ALED��_���������B ����܂ł̍����Ő������������Ƃ��Ă͋����A�d�͂Ƃ��ɍō����x���Ƃ����B���؎����́A�d�g�̌����Ȃǂɂ��1kW����M�����B�����œd�͂𑗂�ꍇ�A�_�����ꏊ�ɓd�g���W��������K�v������B�s���|�C���g�ő��邽�߂̃r�[���𐧌䂷��Ǝ��Z�p���J�����A�����Ŋm�F�����B ���Ђ́A���d���̕~�݂�����ꏊ�ւ̑��d��A�m�㕗�͔��d���痤��ւ̑��d�ȂǁA�n��ւ̎Y�Ɖ��p��������ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����H��ȂǁA�d�͎��v�\������Ǝ��̌v�Z�����\�z���A�s�[�N�}�����鐧��V�X�e���J�� ���H��͂m�s�s�f�[�^�J�X�^�}�T�[�r�X�ȂǂƋ����ŁA�d�͎��v��\������Ǝ��̌v�Z�����\�z�����B �\���l���_��d�͂ɋ߂Â��ƁA�K�X�G���W����~�d�r�A�𐧌䂵�ăs�[�N�d�͂�}����B��d���ɂ̓K�X�G���W���Ƌ̓d�͗ʂ̃o�����X�����A�~�d�r�ƘA�g���Ď����^�]����B���U�d����ݔ��Ȃǂ̃G�l���M�[�f�[�^���A���䂷��V�X�e�������ǁB���A���^�C���̏�琔����̓d�͗ʂȂǂ�\���ł���B ���z�d�r�̔��d�e�ʂ͖�1.4MW�ɏ��B���z�d�r�̔��d���ő�̏ꍇ�A�L�����p�X�̓d�͂��15%�J�o�[�ł���B �剪�R�L�����p�X�ʼn^�p���A�\������@�퐧��̃p�����[�^�[�����Ă��K�Ƀs�[�N�d�͂𐧌�ł���d�g�݂�ڎw���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ăG�l�����ʁA2030�N�x��2100��kWh�A�����d��2����܂��Ȃ� �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��G�l�Œ艿�i������萧�x�̑ΏۂƂ��ĔF�肳�ꂽ���̂́A�܂��ғ����Ă��Ȃ����d�ݔ��Ȃǂ̔��d�\�͂𐄌v���A�����J�����G�l���M�[�~�b�N�X�̌����ψ���Ɏ������B ���z���Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�̓����ʂ��A2030�N�x���_��2100��kWh���x�ɂȂ�Ƃ̎��Z�����\�����B���Ȃ�2030�N�x�̍����d�͎��v���ő�1��1440��kWh�ƌ��ς����Ă���A2������Đ��G�l�Řd����B�������ۂɂ͍Đ��G�l��������ƁA�d�C�����̏㏸�Ȃǂ̖��ɂȂ���B���Ȃ͓����R�X�g�̖����܂߁A2030�N�x���_�́u�G�l���M�[�~�b�N�X�v�i�d���\����j�̍����ƂɌ��ʂf�����Ă����ӌ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���Y�����A���z���Ő��������f�Ɠ����Ɏ_���܂������I�ɐ�������Z�p�J�� �Y�����́A���z���G�l���M�[�Ő������A���f�Ɠ����ɉߗ��_�⎟�����f�_���Ȃǂ̎_���܂������I�ɐ�������Z�p���J�������B ���̓d�C�����ɕK�v�ȓd����ጸ���A�L�@���������̏�r�������A�Y���A���łȂǂɗp���鉻�w��i���ł���B ���E���̎_���^���O�X�e�����̔����̌��d�ɂ��쐻���A���������B�����������Č��z�����������߂邱�Ƃő��z�G�l���M�[�ϊ�����������B�ߗ��_������ꍇ�A�]���̕l�ɔ�ׂĖ�1�E6�{��2�E2%��B�������B���̌��d�ɂ��g���ƁA�]���̋����d�ɂł͗��_��2�E1�{���g�ȏ�̓d�����K�v�ȓd�C���w������0�E6�{���g����N������Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���Z���^�[��9600���~�ށA���C�n�����̔R���d�r���� ��_�s�́A�Z���^�[�Ƀo�C�I�K�X���d�ݔ������A�����̉��D�����̍ۂɔ�����������K�X��L�����p���鎖�Ƃ��J�n����B�����K�X�̎听���ł��郁�^�����^�̔R���d�r�ɒʂ��ēd�͂ɕς��A���̍ۂɐ����鍂���������p����B2017�N4���ɐݔ��̉ғ����v�悵�Ă���B 4��9800���~�𓊂��ĔR���d�r�ݔ��Ȃǂ�2�N�ԂŐݒu���A�N�Ԗ�250��kWh�̓d�͂�v�悾�B���d�ݔ��ɂ����1�N�Ԃɖ�200��kWh�̓d�͂āA���̓d�͂ڃZ���^�[���ŗ��p����Ƃ����v�悾�B�Z���^�[�������d�̖͂�25����d�����Ƃ��ł��A�N�Ԃ�2400���~�̐ߓd�ɂȂ錩���݂��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�C�I�}�X���d�Ŕ��承�i42�~�ȏ�ɁA���������ꂩ��V�d�͂��� ���R�s�̉���������ŏ����K�X��R���ɗ��p�����o�C�I�}�X���d���n�܂����B�����̏����H���Ŕ�����������K�X��R���ɂ��Ĕ��d����������B ���d�\�͂�330kW�̐ݔ�2��̍\���ŁA�N�Ԃ̔��d�ʂ͖�400��kWh��z�肵�Ă���B��ʉƒ��1100���ѕ��̎g�p�ʂɑ�������K�͂ɂȂ�B���R�s�͔��d�ʂ�4����3�ɂ������300��kWh��4��1�����甄�d����\�肾�B �G�l�b�g�̗��D���i�͓d��1kWh������42.68�~�i�Ŕ����j�ŁA�Œ艿�i���搧�x�̔��承�i39�~�Ɣ�ׂ�3.68�~�������B���R�s�̔��d�����͔N�Ԃɖ�1��2800�~�ɂȂ錩�ʂ����B���d���Ԃ�1�N�ԂŁA��������N�x������ʋ������D�Ō��肷����j���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���l��4���l�̒n���s�s���d�͏������J�n�A2018�N�ɔ���14���~��ڎw�� �������݂�s�͐l��4���l�̏��s�s�ŁA�l���̌������i�ޒ��Ŗ��͂��ӂ��X�Â����ڎw���āA�d�͂𒆐S�ɐV�����G�l���M�[�T�[�r�X���s���ɒ��Ă����B�s���o�����Đݗ������V�d�͂́u�݂�܃X�}�[�g�G�l���M�[�v�́A�����̑�1�X�e�b�v�ł͌����{�݂𒆐S�ɁA�Ă̒��ԂȂǎ��v���s�[�N�ɂȂ鎞�ԑтɑ��z���̓d�͂��������i�ŋ�������B 2016�N�ȍ~�̑�2�X�e�b�v�ł͎s�������d�������z���̓d�͂����p���Ȃ���A�ƒ�����̏������g�債�ăG�l���M�[�̒n�Y�n���𐄐i���Ă����B �݂�s�ɂƂ��Ă͎s���̃G�l���M�[�����̐��������ł���̂Ɠ����ɐV�����Y�Ƃ̐U����ɂ��Ȃ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�͏����芮�S���R���܂�1�N�|�ǂ̊�Ƃɂ��g���팠�h�A�ًƎ�d�͂͘A�g���J�M�� ���K�X�̓o�^��PPS��596�Ёi3��25�����݁j�ƂȂ����B�ŋ߂ł͏�V�d�@�A�����}�s�d�S�A���R�[��L���m���̔̔���ЁA�O�c���ݍH�Ǝq��ЂȂǁA�d�͂Ƃ̂�����肪�������Ƃ̓o�^���ڗ��B�o�^�葱���́u���ނ��o���邾���v�ƌ����邮�炢�ȒP�ŁA����ł��d�͎��Ǝ҂ɂȂ��B�������A�̔����т�����o�o�r��50�В��x�ɂƂǂ܂�B ���݁APPS�̋Ɩ��p�d�͂�3�[5���̊���������B����ł�PPS�����B�ł���d�͂͏��Ȃ��A�܂��Ĉ����d�͂̊m�ۂ͍���B�ቿ�i��ɉƒ�s��ɎQ�����Â炢�B�����ōl������̂����i�E�T�[�r�X�Ɠd�͂Ƃ̃Z�b�g�̔����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�l�K���b�g����̃K�C�h���C������ߓd�ʂ̎Z�o���@�Ȃǃ��[���� ���Ȃ́A�d�͉�Ђ̗v���ɉ����Ċ�Ɠ����ߓd�����d�C�g�p�ʂ��A�d�͉�Ђ��������u�l�K���b�g����v�Ɋւ���K�C�h���C�������肵���B �l�K���b�g����Ŏ�舵������v�팸�ʂ́A�ߓd�v�����Ȃ������ꍇ�̓d�͏���ʁi�x�[�X���C���j�Ǝ��ۂ̓d�͏���ʂ̍����ł���B�{�K�C�h���C���ł́A�u�x�[�X���C���̐ݒ�v�u���v�팸�ʂ̑�����@�v���͂��߁A�u���v�Ƃ�A�O���Q�[�^�[�ւ̕�V�v�A�u���v�Ƃ�A�O���Q�[�^�[�ւ̃y�i���e�B�v�A�u�����d�C���Ǝ҂ւ̕�V�v���ɂ��ċK�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v �Q�l�u�l�K���b�g����Ɋւ���K�C�h���C���vhttp://c.bme.jp/17/19/82/1598 |
|
|
| ���@�@[�@2015/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���u5���G�R��w�v�ɐÉ���Ȃ�6�Z�\ �G�R�E���[�O�̑S�������� NPO�@�l�G�R�E���[�O�ɂ��u��6��G�R��w�����L���O�v�̌��ʂ����̂قnj��\����A�ł��G�R�ȁu5���G�R��w�v�ɁA���A���s�H�|�@�ہA�����̌S�R���q�A�É��A���{�H�ƁA�O�d��6��w���I�ꂽ�B���s�H�@�ƐÑ�͍����̎�܂ƂȂ�B ���s�H�@�́A�w���ł̃y�[�p�[���X���Ɏ��g�݁A2013�N�x�ɂ��������p���̎g�p�ʂ�O�N�x��Ŗ�6���팸�������т������]�����ꂽ�B �Ñ�́A2013�N�ɃO���[���Ȋw�Z�p��������ݗ�����ȂǁA�l�ވ琬�Ȃǂɒ��͂���p�����F�߂�ꂽ�B �gCampus Climate Challenge�iCCC�j�h�����̈�Ƃ���2009�N������{����A2014�N�x��146�Z�������ɉ����B �o�T�u��goo�v |
|
|
| ���h�Ɠ�1��2000����LED�ɁA���������[���ŔN��2000���~�̃R�X�g�팸 �_�ސ쌧�̐`��s���ɂ͖h�Ƌ���ݒu�����h�Ɠ���1��2926�J���ɂ���A���̂���804����LED�Ɩ��ɕύX�ς݂��B�c���1��2122����2015�N4���ɂ��ׂ�LED�Ɩ���ւ���B 1���������ʂ�LED�Ɩ������邽�߂ɁA�����������s�v��ESCO�������̗p�����B�_��̑��z��3��2346���~�ŁALED�h�Ɠ��̕t���ւ��ƈێ��Ǘ��A����ɔN��50�����x�̐V�݂�ȃG�l���ʂ̌����܂ށB2013�N�x�̃R�X�g�Ɣ�ׂĔN�Ԃɖ�2000���~���팸�ł��錩���݂��B�h�Ɠ��͏���d�͂�20W�`80W�̃^�C�v������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����z���̓d�͂�1000���~�𓊓��A�A�b�v����25�N�_��Œ��B �Đ��\�G�l���M�[�̗��p��100����ڎw���A�b�v�����A�č��J���t�H���j�A�B�̑��z�����d������25�N�Ԃɂ킽���ēd�͂B����B2016�N�ɉғ��\��̔��d������130MW���̓d�͂��w������_��ɍ��ӂ����B25�N�Ԃ̒��B�z��1000���~���ɂ̂ڂ�B �A�b�v���͑S���E�̃I�t�B�X��f�[�^�Z���^�[�A�X�܂ŗ��p����d�͂��܂߂čĐ��\�G�l���M�[�ɐ�ւ���v��𐄐i�����B2013�N�̎��_��73���܂Ő�ւ����������Ă��āA���Ƀf�[�^�Z���^�[�ł͍Đ��\�G�l���M�[�̎g�p����100���ɒB���Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���Ă̗�[�ɂ�����d�C���3���팸�A�}���V�����Œʕ��ƎՔM��W���� �勞��4���ȍ~�ɒ��H����}���V�����̑S�����ɁA���R�G�l���M�[�������ꂽ�u�p�b�V�u�f�U�C���v���̗p����B���C�@�\�t���̌��փh�A��ՔM���ʂ�����O���[���J�[�e���Ȃǂ�����āA�����̉��x�㏸��}����_�����B �p�b�V�u�f�U�C�����{�����������3LDK�̏Z�˂�ΏۂɁA3�l�Ƒ����������������ݒ肵�ĉ�͂����B���̌��ʁA�s�[�N���ɂ͎�����4.9�x���Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ��m�F�ł��A�Ċ��̃G�A�R���̗�[�̓d�C�オ3,390�~�������Ȃ�A�팸����31���ɂȂ����B 4��ނ̒ʕ��@�\��2��ނ̎ՔM�@�\�����킹�āA�Z��\�\�����x�̏ȃG�l���M�[��ł͍ō������N�̓���4�ɏ�������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���A���H��ɔM��CO2����������o�C�I�}�X�{�C��LPG�ɔ�הR����7���� JFE�G���W���A�����������̃o�C�I�}�X�{�C���ݔ��́A�p�ޓ���������؎��`�b�v��R���Ƃ��ăv�����g�ɔM��CO2������������̂ŁA�v�����g�̗��n����n��ɖL�x�ɑ��݂���؎��o�C�I�}�X������L�����p����B ����܂Ńo�C�I�}�X�{�C���̔R�ăK�X�́A�s�����Ȃǂ����������ւ̋����͍s���Ă��Ȃ��������A�ݔ���Ǝ��J�����A�r�o�����CO2�͔̍|���p���\�ɂ����B����ɂ��CO2�����ʂ́ALPG�R�Ăɂ�鋟���ʂ�2�{�ȏ�ɂȂ�B �܂��A����CO2�����^�o�C�I�}�X�{�C���ݔ��̌o�ό��ʂɂ��ẮA��ʓI��LPG�����̒g�[�@�ɂ��M�����Ɣ�r���āA�R���R�X�g��3�����x�ɗ}���邱�Ƃ��ł���ƌ�����ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}�A�ō��N���X�̏ȃG�l���\����������LED�V�[�����O���C�g3�@����\�� ���������LED�V�[�����O���C�g�́A�ƊE�ō��N���X�̔��������ƂȂ�130lm�^W���������Ă���A�����x�̖��邳�ƂȂ�ی^�u�����ƒu���������ꍇ�Ŗ�65������d�͂�}���邱�Ƃ��ł���B �����������ȊO�̓����Ƃ��ẮA�����R���㕔�ɉt���p�l���𓋍ڂ��Ă���A�d�C�����̖ڈ����\���\�ƂȂ��Ă���B �V�F�[�h�����ɂ́ALED�`�b�v�̌����g�U�����Ă���߂��u����߂������O�v�𓋍ڂ��Ă���B���C���A�b�v�́A������3,800lm�ŎQ�l�X�����i24,800�~�A5,000lm��28,800�~�́A5,600lm��30,800�~���p�ӂ���Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����z���p�l����ߓd�ɂ��A�O�ǂɎg���ė�g�[�̃s�[�N�� �O��Z�F���݂͋Z�p�J���Z���^�[�ŁA���z���p�l�������p���ăr���̏ȃG�l��Ɏ��g��ł���B ���z�d�r���W���[������̉������u�O�����j�b�g�v�ƁA����1�͑��z�d�r�̐ݒu�p�x��ς�����u�σ��j�b�g�v�ŁA�r���̊O�ǂ̍ŏ㕔�ƍʼn����ɑ������āA�G�߂ɍ��킹�Č����I�Ȓʕ����\�ɂ����B�~�͂��̉������ʂ�48���팸�ł���z�肾�B����A�Ăɂ́A���R�̒ʕ��ɂ���đ��z�d�r�̉��x�㏸��}���邱�Ƃ��ł��A���d������4�����シ��B����ɊO�ǂ���̔M���Ւf������ʂɂ���ė�[���ׂ̃s�[�N��55���팸���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��YKK AP���u�G�R���[���}�[�N�F���Ɓv���擾 ���Ђ́A���y��ʏȂȂ�тɌ��v�Вc�@�l�S���ݕ�����G�R���[���}�[�N�����ǂ����{����G�R���[���}�[�N���x�ɂ����āA�u�G�R���[���F���Ɓv���擾�����B �e���_�ł̏ȃG�l�ւ̎��g�݂ƕ��s���āA����T�b�V�Ȃǂ̌��ޏ��i�̗A����i�̑��l����ϋɓI�ɐ��i���Ă���B�]���̗A����i�̑唼�̓g���b�N�A������߂Ă��邪�A�S����D�ɂ��A����i�ɏ��X�ɃV�t�g���A�����I�ɂ͓S����D�̗A���䗦�i��g���b�N�A���䗦�j��i�K�I�ɑ���������v�悾�B���̏ꍇ�g���b�N�A���ɔ�ׁA��_���Y�f�r�o�ʂ��6���팸���邱�Ƃ������߂�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����{�d�͎s����v�A�����d�̕����́u2020�N4���v �u2018�`2020�N���߂ǂɎ��{����v�Ƃ��Ă������A�d�͂̈��苟���ɂ͏\���ȏ������K�v���Ƃ��āA���Ԃ������Ĕ����d�������s�����Ƃɂ����B������ɒ�o����d�C���Ɩ@�����Ăɐ��荞�ށB ����A�K�X�s����v�ɂ��ẮA2017�N�̉ƒ�����̔̔����R���ɑ����A�����K�X�A���K�X�A���M�K�X�̑��K�X3�ЂɃK�X�Ǖ���̕��Љ����`���Â��鎞�����u21�`23�N�v�̊ԂƂ�������Œ������Ă���B ���{�͍�����ɒ�o����d�C���Ɩ@�����ĂŁA���ɑ��d����̕��Љ����`���Â��A�V�K�Q����Ƃ������Ɉ����̐��𐮂���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �������ȁA���z���ȃG�l���\����i�߂�V�@�Ă�������ɒ�o�� ���K�͈ȏ�̌��z���́u�G�l���M�[����\��v�i���́j��ݒ肵�A�K�������m�ۂ��邽�߂̋`�������x��A�ݒ肵��������鐫�\�ւ̗U����ړI�ɂ����u�G�l���M�[����\����v��v�i���́j�̔F�萧�x��n�݂���B �Z���z���ɑ���ȃG�l���M�[��̓K���ɂ��ẮA1���Ɍ��\���ꂽ�u����̏Z��E���z���̏ȃG�l���M�[��̂�����ɂ��āv�i��ꎟ���\�j�ŁA��K�͔�Z��z���̐V�z����̋`�����Ƃ������j��������Ă���B�Ώۂ��g��ɂ���ɂ������ẮA�敪��K�͂��Ƃ̓K�����A��������R�����̑̐������̐i����݂Ď��{���Ă������j���B �o�T�u�V���n�E�W���O�v |
|
|
| �����{�ACO2�r�o�ʂ̏��Ȃ��d�̓��j���[��I�ׂ�d�g�݂ɂ��ċc�_ �o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ́u���Ζ@�Ɋ�Â����Ǝҕʔr�o�W���̎Z�o���@���ɌW�錟����v���J�ÁB���݁A�u�d�C���Ǝ҂��Ƃ̓d���\���̕��ϒl����Z�o���Ă���CO2�r�o�W���v���A�u�O���[���d�́v�Ȃǂ��l�������u�������j���[�ʂ�CO2�r�o�W���ɕ����邵���݁v�ɕς��邩�ǂ����ɂ��Ĕ��f����B ��̓I�ɂ́A�������ʃK�X�r�o�ʂ̎Z��E�E���\���x�ɂ����āA�d�C���Ǝ҂��A�S�d�����ϔr�o�W���ɉ����A�������j���[�ɉ�����CO2�r�o�W�����Z��E���邱�Ƃ�A���v�Ƃ��������j���[�ɉ�����CO2�r�o�W�����g�p������̔r�o�ʂ��Z��E���邱�Ƃɂ��Č������A�K�v�ȑ[�u���u����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�ăG�l�A�n�ɔ����n��������̎��Ǝҕ��S���y���� �V���ȓd���̘A�n�ɔ����A�d�͌n���̃l�b�g���[�N���ŕ~�݁E�������K�v�ɂȂ����ꍇ�A��ʓd�C���Ǝ҂����S����u��ʕ��S�v�������ɂȂ��Ă���B����AFIT�Ɋ�Â��čăG�l��A�n����ꍇ�́A�S�z�d���Ǝ҂����S����u���蕉�S�v����{�ƂȂ��Ă���B ����A�����d�����ɂ���ēd�͌n���̌����I�ȑ��ʂ����܂邱�Ƃ��ɂ݁A���d���Ǝ҂̎�v�����ɉ����Ĕ�p�S����u��v�ҕ��S�v����{�Ƃ��邱�Ƃ������ꂽ�B �u��v�����v�Z��̍l�����Ƃ��āA���݃l�b�g���[�N���̑��z�d�ݔ��̎g�p�N�����l������Z����@��A���d���̏o��(kW)�Ǝ��v���Ŏg�p����o��(kW)�̔䗦���l������Z����@�Ȃǂ������ꂽ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���u�O���[���G�l���M�[�؏��v��CO2�팸�ʂƂ��ĔF���鐧�x�̏����i�� ���̐��x�́A�u�O���[���G�l���M�[�؏����x�v�ɂ��팸���ꂽ�������ʃK�X�̗ʂ��A�u�n�����g����̐��i�Ɋւ���@���i���Ζ@�j�v�Ɋ�Â��u�Z��E�E���\���x�v�ɂ����āA�������ʃK�X�̔r�o�̗}���Ȃǂ̓w�͂Ƃ��Ċ��p�ł�����́B����̓��D�͂��̐��x���^�c���鎖�Ǝ҂��W����B �^�c���鎖�Ǝ҂Ƃ��āA�u�O���[���G�l���M�[CO2�팸�v��̔F��v�A�u�O���[���G�l���M�[CO2�팸�����ʂ̔F�E�Ǘ��v�A�u���؋@�ւ̓o�^�E�Ǘ��A�lj��v���̏��F�̎��O�m�F�v�A�u�F�؈ψ���̉^�c�y�ё����x�ւ̊��p�̉\���������v�A�u���ψ���̉^�c�y�ё����x�ւ̊��p�̉\���������v�����s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�k�A�����f�[�^������ȂǃX�}�[�g���[�^�[�̃Z�L�����e�B��A�����J�n �o�ώY�ƏȂ́A�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͌v�j�̃Z�L�����e�B�ɂ��Đ��I���ڍׂȋc�_���s�����߂ɃZ�L�����e�B�������[�L���O�O���[�v�iWG�j��ݒu�����B ���O��������ʐM�Ɋ��p����邱�Ƃ��l����A����I�ȃZ�L�����e�B�K�C�h���C���̌��������߂���B�܂��A�V�X�e���̐Ǝ㐫����������y�l�g���[�V�����e�X�g�i�N���e�X�g�j���̎��{��PDCA�T�C�N���ɂ��p���I�ȃ��X�N�]���̎��{�A��L�E�Ǘ��̐��̍\�z�����߂���B�z�肳���Z�L�����e�B���X�N�Ƃ��ẮA���R�k�A�����f�[�^������A��d�Ȃǂ��������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�̏ȃG�l�̃|�e���V�������{���ƊE�ʂ̑X�g�Ǝ��Z�Ă����\ �o�ώY�ƏȂ́A���q�͂�ăG�l�Ȃǂ̓d�����ǂ̂悤�Ȋ����ŗ��p���Ă������������u�G�l���M�[�~�b�N�X�v�̋c�_�ɔ��f���邽�߂ɁA�����̏ȃG�l�ʂ𐄌v����c�_���s���Ă���ȃG�l���M�[���ψ�����J�Â����B ����A�����ǂ́A����܂ł̋c�_���̐��ʂƂ��āA�ȃG�l���ʂ��ʉ��ł���u�ȃG�l���M�[��v��ԗ��I�ɗ����X�g������ƂƂ��ɁA���̓����ʂ╁�y������p�����w�W����іڕW��ݒ肵�āA�����̏ȃG�l���ʂ̎��Z���s�����u��ʓI�ȏȃG�l�ʂ̎��Z�i�āj�v���������B�{�ψ���ɂ����āA���Y���X�g�y�ю��Z�̑Ó����ɂ��ċc�_�����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���Η͐V�݂ɏȃG�l�K���d�͎��R����CO2�}���h�� �o�ώY�ƏȂ́A�V�݂���Η͔��d���ɑ��A�ȃG�l�K��������BCO2�r�o�ʂ̏��Ȃ����d�����̍����ݔ��̐ݒu���`���t����B�d�͏����莩�R���Ɍ����ACO2�r�o�ʂ̑����ΒY�Η͔��d�����}������̂�h���_���B ���Ȃ͏ȃG�l�@�̍�����N���ɂ��ς���B�Η͔��d���̐ݔ��ɐΒY�ȂǔR���̔��d�����̊��݂��A��ȏ�̐ݔ��̐ݒu���`���t����B���d�������������CO2�r�o�ʂ�}���ł���B�ᔽ�����ꍇ�͊������A�������Ȃ��B�Ώۂ͐V���Ɍ��݂���Η͔��d���ŁA���đւ����܂ށB���ݍς݂̐ݔ��͑ΏۊO�ł���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2015/3�@]�@�@�� |
|
|
| �����R�[�u�������O���Ă��̂܂܌����\�A110�`�̒��nj`LED���� �u�����̓���iR17d�����j��ύX���Ȃ��Ă��A�u���ǂ����O�������Ō������\��110�`�i2367m�~30mm�j�̒��nj`LED�����v�������B �����͓��������������Ƃ��āA���C�������i���s�b�h�����j�Ɠd�q�������i�C���o�[�^�[�����j�ɑΉ��B���F����v�̖{���ɂ����4��ނ̐��i�ɕ������B�����F�̐��i�́A�F���x4900K�A�S����6000lm�A�����Ɠx�i1m�j��950lx�i���N�X�j�B���F�̐��i�́A�F���x4000K�A�S����5400lm�A�����Ɠx855lx�B4���i�ɋ��ʂ��ď���d�͂�58W�B���ω��F�]�����iRa�j��85�B������5�����Ԃƒ����B�����v�z���_�[�t���i1�{��1�j�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������K�X�@�K�X�Ɠd�́A�ʐM���Z�b�g�ŏH�ɂ��\��̔� 2016�N4���Ɏ��{�\��̉ƒ�������܂߂��d�͏�����̑S�ʎ��R���Ɍ����A���Ђ͍��H�܂łɓs�s�K�X�Ɠd�́A�ʐM�Ȃǁi�̃T�[�r�X�j���Z�b�g�Ŕ̔����郁�j���[����肽���B�Əq�ׂ��B���łɒʐM���Ǝ҂ȂǂƋƖ���g�̋��c��i�߂Ă���A���H�ɂ��\��̔����n�߂����l�����B �d�͎��v��4�����߂�ƒ�����s��ւ̎Q���ɂ��āA�����d�͂ƌ���ł���_����ւ��Ă��炤�ɂ́A�d�C�����̉��i���������ł͓���B���p�҂ɖ��͓I�ȃ��j���[���Ă���K�v������B�s�s�K�X����������ƒ�����ɁA�g�ѓd�b������d�C�����Ȃǂ��Z�b�g�ɂ������������̓����Ȃǂ�����������j���������B ���Ђ͌��݁A�N�Ԗ�100��kWh�̓d�͂�V�K�Q���̏������Ǝ҂�H��Ȃǂɔ̔��B2020�N�ɂ͉ƒ�p���܂ߎ�s���̃V�F�A1���ɑ��������300��kWh�܂Ŕ̔����g�傷��ڕW���f���Ă���B ����A�̔��p�̓d�����m�ۂ��邽�߁A���݂̎��Ђ̔��d�\�͖�130��kW���A2020�N�ɂ�2�{���̖�300��kW�Ɋg�傷��v�悾�B���̂��߁A���d�R�X�g�̈����ΒY�Η͔��d���̌��݂��A�d�͉�Ђ⏤�ЂƂ̒�g�Ŏ������������Ƃ̂��ƁB �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���V�H��M�f�[�^�Z���^�[�����u��ԃr�W���A���C�Y�V�X�e���v���J�� �T�[�o�[�̓���ւ��A�lj��ݒu�A���C�A�E�g�ύX���ɓK���ȉ��x�Ǘ����ێ����Ă������Ƃ͍���B�܂��T�[�o�[����K�ɉ��x�Ǘ����邽�߂ɂ́A�T�[�o�[���S�̂ɑ����̉��x�Z���T�[��ݒu����K�v�����邪�A�T�[�o�[�̃����e�i���X��z�u�E�@��ύX���ɏ�Q�ƂȂ�A�����I�ł͂Ȃ��B �����œ��Ђ́A���ЊJ����CFD�i���l���̃V�~�����[�V�����j��͋Z�p��p���āA�T�[�o�[���̉��x�E�C���������Łw�����鉻�x����u��ԃr�W���A���C�Y�V�X�e���v���J�������B ���̃V�X�e���ł́A�T�[�o�[�Ƌ@�̉^�]����ɂ���CFD��͂��s���A�T�[�o�[���̉��x�E�C���̏�Ԃ����Ԋu�Ŏ����I�ɎZ�o����uCFD�������s�@�\�v������A�T�[�o�[���S�̂ɑ����̉��x�Z���T�[��ݒu�����ɉ��x�E�����̕ω����p���I�ɔc�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����d�A3������X�}�[�g���[�^�[�ɂ�鎩�����j�T�[�r�X�J�n �܂��A�����s�����n��̈�ʉƒ�Ȃǖ�14�����ŃX�^�[�g���A�����͈͂��L���Ă����B 2020�N�܂łɊǓ��S���2700��̃X�}�[�g���[�^�[��ݒu����v��B���j���̐l����s�v�ɂȂ�A�N��160���~���x�̃R�X�g���팸�ł��錩�ʂ����B���Ђ́A2014�N4�����狌�^���[�^�[�̌������n�߁A����܂łɖ�95�����ݒu�����B ���̂قnjڋq�Ƃ̊Ԃœd�͎g�p�f�[�^�������ł���ʐM�V�X�e���ƁA�f�[�^�̉^�p�Ǘ��V�X�e���̉ғ��Ƀ��h�����������߁A�������j�̊J�n�����߂��B���j�̎������Ōڋq�̈����z���̍ۂɗ���Ŏg�p�ʂ��m�F����K�v���Ȃ��Ȃ�B��d���Ɍ̏����������z���Ԃ��u���ɕ����邽�߁A�����ɂ����鎞�Ԃ��Z���Ȃ錩���݂��B 2�����猟�j�[�̉{�����\�ɂ���ق��A7���ɂ�30�����݂œd�C�̎g�p���m�F�ł���悤�ɂ���v�悾�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����l�X�^�W�A���̃i�C�^�[�Ɩ����S��LED�ɁA����d�͂�56���팸 ���l�X�^�W�A���̓v���싅�`�[���u���lDeNA�x�C�X�^�[�Y�v�̃z�[���O���E���h�ŁA�t����H�܂ő����V�[�Y�����ɂ͏T3�����x�̃i�C�^�[���J�Â���B �]���̃i�C�^�[�Ɩ��ݔ��ɂ͍����F�E�������̃��^���n���C�h�����v���̗p���Ă����B�J������v���싅�̌������O�ɁA���ׂ�LED�^�C�v�Ɍ�������B ���l�X�^�W�A���̏Ɩ����͑S����6����āA�����ɍ��v708��̓�����𓋍ڂ��Ă���B���݂̃��^���n���C�h�����v�̓�����͏���d�͂�1�䂠����1500W�����A�V���ɍ̗p����LED�^�C�v�̓�����ł͖���760W�ɒጸ����B ����ɉ��F���̍����i���R���ɋ߂��jLED���g�����Ƃɂ���āA������̐���660��Ɍ��炵�Ă������ȏ�̖��邳���m�ۂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�䐔�����炷���ʂȂǂ��܂߂āA�S�̂̏���d�͂�56�����Ȃ��Ȃ�B�Ɠx�i�������Ƃ炷���ʂ̖��邳�j��100�`25���͈̔͂ŕς����钲���@�\������Ă��邽�߁A�K�v�ɉ����Ė��邳�����ď���d�͂��팸���邱�Ƃ��ł���B �v���싅�Ŏg�����Ƃ�O��Ɂu�܂Ԃ����v��u������v��}����v�ɂ����B�����@�̑O�ʂɂ͖싅�̃{�[��������130km/h�œ������Ă��ς����鋭�x�̃J�o�[������B������ɑg�ݍ���LED���W���[���̎�����4�����ԂŁA���^���n���C�h�����v�i6000���ԁj�Ɣ�ׂ�6�{�ȏ�������Ȃ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����ƁA�����̐V�d�͂ւ̐�ւ����� 2015�N1��25���l���A���������8�d�͂̍��v�ŁA2014�N�Ɍ���3��ɂ������300��kW�̎��v���V�d�͂Ɉڂ����B �Ẵs�[�N���i��1��5000��kW�j��2�������A����܂łɐV�d�͂ֈڂ����v��1200��kW��4����1���߂�B2016�N4���̓d�͏�����S�ʎ��R�����ɂ�݁A������V�d�͂̊J�Ƃ������B�o�ώY�ƏȂւ̓o�^�А��͖�480�Ђɂ̂ڂ�B �����{��k�Ќ�̌�����~�ɔ����A�Η͔��d�̔R����c����߁A��ƌ����̓d�͗�����3���l�グ�����B����ɑ��A�V�d�̗͂����͑��d�͂�萔�������ƌ����Ă���B ���d�͂̏ꍇ�A�v�Ŗ�250��kW���V�d�͂ɗ��ꂽ�B���̂�����ƌ���������17.26���l�グ����13�N�x�ȍ~�̕��͖�100��kW��4���ɋy�ԁB�֓d�͍��N4���ɍĒl�グ��\�肵�Ă���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���ȃG�l�ݔ������A�����\�����ȑf���o�Y�� �o�ώY�ƏȂ́A������ƌo�c�҂��ȃG�l�ݔ�������ۂ̕⏕���葱�����ȑf������B����܂ŕ⏕���̐\���ɂ͍H��Ȃǂ̃G�l���M�[�g�p�ʂL����ȂǑ����̎������K�v�������B���t����͕⏕�Ώۂ̏ȃG�l�ݔ����w�����邱�Ƃ��������[�J�[�̏ؖ�����Y�t���邾���ōςނ悤�ɂ���B�⏕���̗��p���L����_�����B ���Ȃ�1998�N���玖�Ǝ҂̏ȃG�l�ݔ��̓����x�����n�߁A2014�N�x��\�Z�łً͋}�o�ϑ�Ƃ��Ė�930���~���v�サ�Ă���B������ƌo�c�҂�̏ȃG�l��ߓd�̑��k�ɂ������邽�߁A�n�悲�Ƃɐ��Ƃ炪�Ή����鑊�k�������݂���Ƃ����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���ȃG�l�����l���팸�ƌ��q�͂�D��A���{���H��c���̑S�������� ���{���H��c�����u�d�̓R�X�g�㏸�̕��S���E�Ɋւ���S�������v�����{�����B��Ɛ���335�ЁB�i�S�����Ɛ���126���Ёj�d�̓R�X�g�́A�����{��k�В����1�N�ԂƔ�ׂāA���̌��1�N�Ԃł�1�Е��ς�1000���~�ȏ���d�̓R�X�g�������Ă���B�d�͂̎g�p�ʂ͉���������A1kWh������̒P����28.1�����㏸�������Ƃɂ��B ����Ȃ�d�̓R�X�g�̏㏸�͕��S�̌��E�ɒB���Ă��邱�Ƃ��ȏ�̉�Ƃ��w�E�����B1kWh������1�~�ł��㏸����ƕ��S�̌��E����Ɖ�����Ƃ�57���ɂ̂ڂ�B ������d�̓R�X�g���㏸�����ꍇ�A�ł������̊�Ƃ��������̂́u�l���A�l����̍팸�v���B�����Ȃ���ߔ�����56.5���ɒB�����B������2�Ԗڂɑ��������̂́u�ݔ������⌤���J�������̏k���E�}���v�ł���B�̑I�����ɂ́A�ߓd��̋�����ȃG�l�@��̓����Ƃ������O�����ȑΉ���͊܂܂�Ă��Ȃ��B���{��2014�N�x�̕�\�Z�ŁA�u�n��H��E������Ɠ��̏ȃG�l���M�[�ݔ������⏕���v��930���~�̋���𓊓�������j�����߂����肾���A�������鑤�̎v���Ƒ傫���قȂ�B ����ɒ������ʂ̖����ɂ́A�u�G�l���M�[�����S�ʂɊւ��钆����Ƃ̐��v��5�������Ă���B���̂���3���͌��q�͔��d���̍ĉғ������߂Ă��āA����ōĐ��\�G�l���M�[���^�⎋����ӌ������q�͂Ƃ̏d�����܂߂�3������B���̑����͐����Ƃ̈ӌ��ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����x��l�̈ʒu���u�����鉻�v����Z���T�[�̃l�b�g���[�N10���ȏ�ȃG�l NEDO�ƋZ�p�����g��NMEMS�Z�p�����@�\�́A�V���ɊJ�������O���[��MEMS�Z���T�[�i�����d�C�@�B�V�X�e���j��p�����Z���T�[�l�b�g���[�N�V�X�e�����؎������A�X�܁E�I�t�B�X�E��������Ȃǂɂ����Ď��{���A10���̏ȃG�l���ʂ��������Ɣ��\�����B ���̐��ʂ́A�O���[���Z���T�[�ɂ��X�}�[�g�Љ�̎�����ڎw���āA�ȃG�l����łȂ��A�Љ�C���t���A�_�ƁA���N��Õ��쓙�̎Љ�ۑ�ւ̉��p�����҂����B �v���W�F�N�g�ł́A�Z���T�[���g�̃O���[�����E�ȃG�l���i�������d�͉��A���^���j�Ƃ����V���ȃR���Z�v�g�̂��ƁA�����ʐM�@�\�A�����d���@�\�A�������d�͋@�\�𓋍ڂ������ڂ��� �i1�j�d���E���E�Z���T�[ �i2�j�o���ʃZ���T�[ �i3�j�K�X�iCO2�AVOC�j�Z�x�Z���T�[ �i4�j�ԊO���A���[�Z���T�[ ���J�������B�����̃Z���T�[��p�����ȃG�l���؎����ł́A�R���r�j�G���X�X�g�A�i�Z�u���C���u���j��2,000�X�܂ɖ����ؓd�^�d���Z���T�[�A�������i�����x�j�Z���T�[�A�R���Z���g���[�^��ݒu���A�ݔ��@��̏�ԁE�ݒu���A�E�H�[�N�C�����̊J���������鉻�E���P���邱�Ƃ�10���̏ȃG�l���ʂ������邱�Ƃ��������B �܂��A�����K�́i500�������[�g�������j�̃I�t�B�X�Ɏ����d���ŋ쓮�E�������M����ԊO���A���[�Z���T�[�A�R���Z���g���[�^��ݒu���A�t���A�S�̂̉��x���z�E�l�ʒu�̌����鉻�Ɋ�Â��ȃG�l�w���i�E���C�E���J�j�̎��{�ɂ��A10���ȏ�̏ȃG�l���ʂ������邱�Ƃ��������B�Ȃ��A�K�X�iCO2�AVOC�j�Z�x�Z���T�[�ɂ��Ă��A���݁A���،���i�I�t�B�X�A�t�@�N�g���j�֓������A�@�\����i�߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�s�s�K�X�̑S�ʎ��R���v���{�̕������\�A�M�����V�X�e�������v�� �K�X�V�X�e�����v�́A�����̊�������ʂ����v�Ƃɑ��l�ȑI��������A����ȗ������������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�{���ł́A2017�N���߂ǂɁA�ƒ���܂߂��s�s�K�X�̏������S�ʎ��R�����邱�Ƃ��K���ł���Ƃ��A�V���ȃK�X�V�X�e���݂̍������v�̐i�ߕ����ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���B �d�̓V�X�e�����v�ł́A2016�N�ɓd�͏�����̑S�ʎ��R�����\�肳��Ă���B�d�̓V�X�e�����v�Ǝ�������킸�K�X�V�X�e�����v��i�߂邱�Ƃ́A���ݎQ���̑��i�ɂ����v�Ƃ⎖�Ǝ҂̑I�����g��Ƃ����ϓ_������]�܂����Ƃ���Ă���B �d�́E�K�X�V�X�e�����v����ʂ��āA�Y�Ƃ��Ƃɑ��݂��Ă����G�l���M�[�s��̊_������蕥�����ƂŁA�����̃G�l���M�[���Ǝ҂̑��ݎQ����ًƎ킩��̐V�K�Q���𑣂����Ƃ��ł���B����ɂ��A�G�l���M�[�s��ɂ����鋣���̊������ƃG�l���M�[�Y�Ƃ̌������𑣐i���A�n��ɐV���ȎY�Ƃ�n�o����ȂǁA�n�抈�����֍v����ڎw���B �K�X�V�X�e�����v�̐i�ߕ��Ƃ��ẮA�����S�ʎ��R���̎��{�ɓ������āA���v�ƕۈ��ɌW���p������l�������V���ȑ����������x��v���A����Ɋ�Â����Ǝ҂�������\�����F����K�v������ȂǁA�O��ƂȂ���������s���ƂȂ�B �M�����V�X�e�����v�̕������ɂ��ẮA�K�X�́A�⋋���Ȃǂ̔M�G�l���M�[���ł���A��s���Ă���d�́E�K�X�V�X�e�����v�ƕ����A�M�����V�X�e�����v��i�߂Ă������Ƃ����߂��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2015/2�@]�@�@�� |
|
|
| �����Ń��C�e�b�NLED���p�Ɩ����̔����ɂ��� ���y��ʑ�b�F����擾����LED���p�Ɩ����38�@����A2014�N12��15�����珇�����������B���p�Ɩ�����LED���ɂ��A�{�ݏƖ��̃I�[��LED���𐄐i���Ă����B ������ 1. �S�@��Ɏ��ȓ_���@�\�𓋍ڂ��A�_����Ƃ������� �~�d�r�̎����f���鎩�ȓ_���@�\�����ׂĂ̋@��ɓ��ڂ��Ă���B�_���X�C�b�`���������Ƃɂ��A���̂����_���m�F�������ōs�����߁A���{���`���t�����Ă���A�_���E�����̍�Ƃ��������ł���B 2. LED�ŏ[�d�����_�������ȃG�l �ʏ�_���Ɣ��_���Ō��p�ł���u���nj`LED�x�[�X���C�g���p�Ɩ����i���p�`�j�v�Ȃ�A�ʏ�_�����̏ȃG�l�͂������A�������ɂ���ւ������炵�A�����e�i���X��p�̍팸�����҂ł���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ����J�Y�ƃZ�u���X�܂ɐ��f�������_��W�J 2015�N�H�܂łɓ����s�ƈ��m�����J�s��2�J���ŊJ�݁B2017�N�x�܂łɑS��20�X�܂Ɋg�傷��B���Ђ�2015�N�x���Ɍv20�J���̐��f�X�e�[�V�����ݒu���v�悵�Ă���B ��J�Y�ƂƃZ�u��-�C���u����W���p���͔R���d�r�����ԗp�̐��f�X�e�[�V�����݂����R���r�j�G���X�X�g�A��W�J������Ƃ̔��\���s�����B2015�N�H������߂ǂɐ��f�X�e�[�V�����݂������R���r�j�G���X�X�g�A�𓌋��s�ƈ��m�����J�s�ɃI�[�v�������A���セ�̐��𑝂₵�Ă������j���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����K�X�G�l���M�[�Ǘ��ɒ��� ���Ђ͍H��Ŏg�����l�ȃG�l���M�[�̊Ǘ��𐿂������T�[�r�X�ɒ��͂��Ă���B�d�C�E�K�X�̂ق����C��H�ƘF�Ȃǂɂ��Ă���ɐݔ��̏��Ď����A�ȃG�l���M�[��i�̕i��������x������B 2017�N�ɂ��K�X�����肪�S�ʎ��R������������������B���̂��߁A�K�X���g���H��𑝂₷�����łȂ��A�����ɒ����g���Ă��炤���v���X���̉��l�Ōڋq���Ȃ����߂���g�݂��n�܂����B ���Ђ̃G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X�u�t�B�b�g�V���[�Y�v�́A���C�A���k��C�A�������A�H�ƘF��4��ނō\���B���C�ȊO�͍��N�x����̔����n�߂��B�T�[�r�X�̊�Ղ͌ڋq���C���^�[�l�b�g��ʂ��ĊȒP�ɐݔ��̏��m�F�����������쐬������ł���u�����鉻�v�T�[�r�X�iTG�݂�l�b�g�j���B�H����̐ݔ��ɃZ���T�[�����t���A���C�̗��ʂ�H�ƘF�̉��x�Ƃ������f�[�^���W�߁A�^�p�̌�������ݔ����C�ɂȂ���B�����͌��z1���`3���~���x�A�t�B�b�g�V���[�Y�����Ă�10���`���\���~���x���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�q��ЃC���^�[�l�b�g���ݐڑ�����u�X�}�[�g�H��v���J�� �e���u�ɒʐM���W���[���𓋍ڂ�M2M�i�@��ԒʐM�j�Z�p�ɂ���Đڑ������B�͂���H���̌������ʂ��畔�i�̓��ڈʒu�����������ȂǁA���u�Ԃ̘A�g������\�ɂȂ�B���Y���̉��P��l����̍팸�����҂ł���B ����܂ňقȂ鑕�u����|���郁�[�J�[�Ԃł�M2M���������邱�Ƃ�����A�X�}�[�g�H��ւ̑Ή����x��Ă����B����C���^�[�l�b�g�v���g�R���ɏ��������Ǝ��̃v���g�R�����J�����A���[�J�[5�ЂƘA�g�����B ����ɐ��Y���C���╔�i�ۊnjɁA�����e�i���X�v���Ȃǂ̏����I�ɊǗ��ł���u�����t���A�}�l�W�����g�v�ƌĂԊǗ��V�X�e�����J�������B���Y���Ď����Ȃ���A�œK�ȍޗ�������l���z�u�A�����e�i���X�Ȃǂ��ł���B���E���̍H����W���I�ɊĎ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���u�~���C�v���^��4,300�~�c���f1�L����~�� JX���z���G�l���M�[�́A��ʌ����̔̔��������n�܂����R���d�r�ԁiFCV�j�̔R���ƂȂ鐅�f���A1kg������1,000�~�i����Ŕ����j�Ŕ̔�����Ɣ��\�����B �g���^�����Ԃ���������FCV�u�~���C�v�^���ɂ������̔R�����4300�~�ŁA��650km���s�ł���B JX���z���͗��N3���܂ł�11�����̐��f�X�e�[�V������ݒu����v��ŁA25���ɂ͐_�ސ쌧�C�V���s��1�X�ܖڂ��J�����B�K�\�������i�͒n��ɂ���ĈقȂ邪�A���f�̉��i�͑S���ꗥ�ɂ���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���I�������A�ƊE�ŏ��T�C�Y�̓d�͗ʃ��j�^�[���A�ő�4��H�܂Ōv�����\ ���Ђ́A�ƊE�ŏ��T�C�Y�̏��^�d�͗ʃ��j�^�[�uKM-N1�v������B�ő�4��H�܂Ōv���ł���B�I�t�B�X�r���⏤�Ǝ{�݂ȂǁA����̓d�͎��R���Ŋ������������܂��r�W�l�X�̈�ɓK���Ă���B�u�g���₷���v�u�v�����₷���v�u�{�H���₷���v�������Ƃ����A�d�͂̎��v�E�����o�����X�����̂��߂̏ڍׂȓd�͌v�����x����B �傫���͍���90mm�A��22.5mm�A���s��56mm�A�d���͖�80g�ŁA���Ђ̏]���@�Ɣ�ׂĖ�40�������������B����ꂽ�X�y�[�X����݂̏��Ȃ����d�Ղɂ��e�ՂɎ��t�����A�ݒu�ꏊ��I�Ȃ��B�]���@�ł͂ł��Ȃ������A�����قȂ镡����H�̓����v�����ł��A�d���E�I�t�B�X�@��ȂǒP��2�����͍ő�4��H�A�@�ȂǎO��3�����͍ő�2��H�܂őΉ�����B �T�[�o�[�⌻��̃l�b�g���[�N�ȂǏ�ʃV�X�e���Ƃ̐e�a�������߂��B���_�v�����\�����A�P��H�d�͗ʃ��j�^�[����������悤�ɐݒ�ł���B�����̎g���₷���̂ق��A�v�����₷���ł͏]���@��2�{�̌v�����x�����������B���u�̑ҋ@�d�͂ȂǏ��Ȃ��d�͗ʂ����m�ō����x�Ɍv������B�{�H���₷���̓R�l�N�^�[���̉��P�ȂǂŐڑ���e�Ղɂ����B 2016�N�Ɉ�ʉƒ�Ȃǒሳ�d�͂܂œd�͏����肪���R������錩�ʂ��ɂȂ�A������ɉ����Ď��������Ȃǎ��ӃT�[�r�X�A���d���ƂȂǂ̊��������\�z�����B�œK�ȃG�l���M�[���p�E���B�Ɍ����A���d�ՒP�ʂŏ���d�͂�c�����Ď��v���肷��Ȃnjv���j�[�Y�̍��܂���������ĊJ�������B���i��1��4500�~�B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ������25�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̎��r�o�W���E������r�o�W�����̌��\ ����25�N�x�̓d�C���Ǝҁi��ʓd�C���Ǝҋy�ѓ���K�͓d�C���Ǝҁj���Ƃ̎��r�o�W���y�ђ�����r�o�W�����ɂ��āA�e�d�C���Ǝ҂����o���ꂽ�������Ɋ�Â��A�o�ώY�Əȋy�ъ��ȂŊm�F���A����Ɍf�ڂ����B ��v�d�͉�Ђ̎��r�o�W���i�P�ʁFt-CO2/kWh�j�́A�����d�́F0.000530�A�����d�́F0.000513�A���d�́A��B�d�́F0.000613 ��֒l�F0.000551�B http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=19006 �o�T�u���ȁv |
|
|
| ���o�Y�ȁA�u�ăG�l�X�L���W���iGPSS�j�v������ăG�l�ƊE�̋����̌n�� �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[���d���ƂɊւ��l�ނ̐E����`���A�r�W�l�X�ɕK�v�Ƃ����X�L����m����̌n�������u�Đ��\�G�l���M�[�X�L���W���iGreen Power Skills Standard�FGPSS�j�v�����肵���\�����B GPSS�́A���l�Ȏ��Ǝ�̂����d���ƂɎQ�����Ă���ăG�l����ɂ����āA���Ƃ�K�������I�ɐi�߂邱�Ƃ��ł���l�ވ琬���x�������Ƃ��č���B�ăG�l���ƂɊ֘A����l�ނɊ��҂����v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̖�����A���̐l�ނɕK�v�ȃX�L���E�m����̌n�I����̓I�Ɏ������B �u�Đ��\�G�l���M�[�X�L���W���iGPSS�j�v�̍\���́A�T�v�ҁA�L�����A�E�X�L���̌n�ҁA�m���̌n�ҎO���\���ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141205001/20141205001.html |
|
|
| �����g�������{��53�ʁu����v ���g�����L���O���h�C�c�̊��V���N�^���N�u�W���[�}���E�I�b�`�v�Ȃǂ̌����O���[�v���C��ϓ��g�g�ݏ��̒���c�Ŕ��\�����B �����L���O�́A���g���K�X�r�o�ʂ̑���58�̍��ƒn�悪�ΏہB���g���K�X�r�o�ʂ�Đ��\�G�l���M�[���p�����ɁA�������͂̌��ʂ��������w�W�����̓_�����B �Y�Ɗv���ȍ~�̋C���㏸��2�������ɗ}����Ƃ������ۖڕW��B������̂ɕK�v�Ȑ����̑�����{���Ă��鍑�͖����������Ƃ����N���l1�`3�ʁu�Ώۍ��Ȃ��v�ŁA�g�b�v��4�ʂ̃f���}�[�N�������B�r�o�ʂ������Ɍ����Ă��邱�Ƃ�A�Đ��G�l�g��̂��߂̐������]������A100�_���_��77.76�_�ƂȂ����B ���{�͉��g���K�X�̔r�o�ʂ������X���ɂ��邱�ƂȂǂ���A�č��i44�ʁj�⒆���i45�ʁj�������Ƀ����N���ꂽ�B�O�N��47.21�_����45.07�_�Ɛ��т�������A�O�N�Ɠ��l��5�i�K�]���Łu����v�Ƃ��ꂽ����15�̍��ƒn��̒��̈�ɂȂ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����Ǝ{�݂�z�e���V�z�A�ȃG�l����B�Ȃ�F�߂������ȕ��j ���y��ʏȂ͗L���҉�c�ŁA���Ǝ{�݂�z�e���Ȃǂ�V�z����ہA���̏ȃG�l���M�[������悤�`���Â�����j���������B�܂��͏��ʐς�2�畽�����[�g���ȏ�̑�K�͎{�݂�ΏۂƂ��A��ɓ͂��Ȃ���Β��H�������F�߂Ȃ��B���N�̒ʏ퍑��ɐV�@���o���A2017�N�x�ȍ~�̋`�������߂����B �K������̂͏Z��ȊO�̌��z���ŁA�I�t�B�X�r����a�@���ΏۂƂ���B�����̑�K�͎{�݂͔N�Ԃɖ�3500�������H����A�Z��ȊO�̕����̒��H�����ɐ�߂銄����6�����x�ɂ����Ȃ��B�����G�l���M�[����ʂł݂�ƁA�ΏۂɂȂ錚�z���͖�36�����߂邽�߁A����������K�͎{�݂���K�������߂�B 17�N�x�ȍ~�́A��������a���ȂǗp�r���Ƃɒ�߂�ꂽ�G�l���M�[����ʂ̊�l�ɁA���ʐς��|�����킹�ĎZ�o�������l�����̌������B�����ׂ�����ʂƂ���B��o���ꂽ���z�v��Əƍ����A�������Β��H�ł��Ȃ��Ȃ�B ���s�̏ȃG�l���M�[�@�͊�̒B�����`���Â����Ă��炸�A���������s�\���Ƃ̎w�E���o�Ă����B�����Ȃ��������̐V�@�ł́A������Ȃ����z��ɐ������߂��o����悤�ɂ��A�]��Ȃ���Δ������Ȃ��B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���I�t�B�X�r���ȂǏȃG�l���ʖڕW�o�Y�ȁA2015�N�x�ɂ� �o�ώY�ƏȂ�2015�N�x�ɂ��I�t�B�X�r���Ȃǂ̐V���ȏȃG�l�̋��ʖڕW������B�ł��ȃG�l���i�ގ��Ǝ҂���Ƃ����ڕW������A�B���𑣂����ƂőS�̂̃G�l���M�[�g�p�ʂ̍팸�ɂȂ���B���Ɨp�{�݂����S�ݓX�Ȃǂɂ��Ǝ킲�Ƃ̋��ʖڕW�����A�T�[�r�X�Ƃ̏ȃG�l��[�@�肷��B�^�A����ւ̓������������Ă���B ���������G�l���M�[������ȃG�l���M�[���ψ���ŕ��j���������B�S���̒��݃r���I�[�i�[�ł�����{�r���a���O����A����Ƌ��c��i�߂Ă���B�r���̗��n��g�p�����A�\���ȂǂׁA�ȃG�l�łǂ��܂ŃG�l���M�[�g�p�ʂ����点�邩���Z�o���u�ߓd�̗]�n���c��0.1���v�ȂǁA�ȃG�l�̗]�n���ׂ�Ă����サ�Ă���B �ڕW��B�������r���͌��\���A���Ђ̎Q�l�ɂ��Ă��炤�B�Ǝ���ł̑��ΓI�Ȑ�����c�����Ă��炢�A��r��ʂ��ēw�͂𑣂��_��������B �ق��ɁA���{�S�ݓX����Ȃ�6�̋ƊE�c�̂Ƃ����c���A��������A�S���̃f�p�[�g�A�z�e���A�R���r�j�Ȃǂœ�����i�߂���j���B �T�[�r�X�Ƃ��܂ދƖ�����͍ŏI�G�l���M�[�ʂ̖�5����1���߁A1973�N����13�N�ɖ�3�{�ɑ������B�Ɩ��`�Ԃ�����ɂ킽�邱�Ƃ��狤�ʖڕW�̓������������Ă������A�ߔN�������X���������Ă���A���������߂��B�^�A����ւ̋��ʖڕW�̓������������Ă���Ƃ����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2015/1�@]�@�@�� |
|
|
| �������M���p�V�X�e���i���A1m������15���~���� �ϐ����w�H�Ƃ́A�����M���Ȃǂɗ��p����u�G�X���q�[�g�����M�|�ǒ�ݒu�^�v������B�����ǂ̒��ɁA�M�}�́i����s���t�j���z������p�C�v��ݒu���A�����̔M�����o���Ƃ������́B�S���Ō����@�ֈȊO�ɂ��A���Ԏ��ƎҌ����ɔ̔�����B ��C�̔M�����o���ʏ�̋�C�M�q�[�g�|���v�V�X�e���i�j�Ɣ�r���āA�d�̓R�X�g���30���팸�ł���Ƃ����B����͉����̉��x���N�Ԃ�ʂ���15�`25�x�ɕۂ���Ă���A�~�͑�C�����g�����A�Ă͑�C�����₽�����߂��B���ꂪ�����������オ�闝�R���B�ȊO�ɂ����������o���A�Z��p�̔M���Ƃ��ė��p����Ƃ������p�r������B �������ɗאڂ��Ă��Ȃ��Ă����p�ł���B�G�X���q�[�g�����M�|�ǒ�ݒu�^�́A�傫��3�̕�������Ȃ��Ă���B�����Ǔ�����M�����o���ĖړI�n�܂ʼn^�ԏW�M�ǂƁA�M���Ƃ��Ă���ɔM�ʂ𑝂₷�d���̃q�[�g�|���v���j�b�g�A�������Ɏ��t���鎺���@���B�W�M�ǂ̉��i��1m������15�`30���~�B�q�[�g�|���v���j�b�g�͕s���t����M�����o�����߁A��p�i���K�v�ł���W�M�ǂ͎������ł���A�ݒu��50�N���x�g�p�ł���Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��NEC �~�d�r���p�̓d�͒����V�X�e�����J�� �J�������V�X�e���ł́A�N���E�h�����Ƃ�ƒ�̎��g������l����ǂ̒��x����ǂ̒��x����Ă��邩�Ȃǂ����j�^�[���A��������Ƃɓd�͂��ǂꂾ������Ȃ����邢�͗]���Ă��邩���v�Z����B�ǂ��ɂ����̒~�d�r������A�ǂꂾ���̓d�C���[�d����Ă��邩�Ƃ������f�[�^���W�߂�B ���̏�łǂ̓d�r�ɂǂ̒��x�[���d�����邩�����߂āA�N���E�h����w�����o���B100���̓d�r�ɑ��Ăǂ̂悤�ȓ���������邩���v�Z���A�ʐM����ɂ͏\�����̎��Ԃ�������B���̊Ԑ��b���Ƃɍׂ��������͒~�d�r�Ɏ��t���鐧�䑕�u��ʂ��ēd�r���Ɨ����čs���B���̑��u�͉ƒ�̃G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iHEMS�j�ȂǂƘA�g���邱�Ƃ��ł���B�d�r�͑S�Ẵ��[�J�[�̓d�r���g�����Ƃ��\�ŁA���p����~�d�r�̎������k�߂Ȃ�������@�Ȃǂ����킹�Ċm�������B�e�d�r���w���Ɋ�Â��Ăǂ̒��x�[���d�������̃��O������B����ɉ����āA�d�͉�Ђ�V�d�͓͂d�C�����̊����ȂǐV�T�[�r�X�̓W�J���\�ɂȂ�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���Y�ƊE�A2030�N�܂ł�CO2�팸�ڕW�Ď��� �����Ԃ�d�C�E�d�q�A�S�|�Ȃǂ̎�v�Y�Ƃ̋ƊE�c�̂�2030�N�܂ł̓�_���Y�f�̍팸�ڕW�Ă��A�o�ώY�ƏȁE���Ȃ̐R�c��Ŏn�߂Ē����B �E���{�����ԍH�Ɖ�Ɠ��{�����Ԏԑ̍H�Ɖ1990�N�x��662���g���i33���j�̖ڕW���������B �E���{�S�|�A���͓S�|���Y�ߒ���CO2�r�o�ʂ�2005�N�x�ȍ~�ɓ��i�̑�����Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂ�900���g���i5���O��j���炷���j�B �E���{�����A�����2008�`2012�N���ςɔ��75���g���O��̍팸���߂����B �E�d�C�E�d�q4�c�̂͐��Z���̃G�l���M�[���P�ʂ�2012�N�x�ɔ�הN����1���A�v��16.55���ȏ���P������B �N����114�ƊE�c�̖̂ڕW���o���낤���ʂ����B ���g����ł�2015�N12���Ƀp���ŊJ�����COP21�ł��ׂĂ̍��A�n�悪�Q������20�N�ȍ~�̍��ۘg�g�݂̍��ӂ�ڎw���Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���h�C�c��Ƃ��C���^�[�l�b�g�ڑ��́u�X�}�[�g�H��v���ғ� �h�C�c�ł̓��[�J�[�̑��l�Ȑݔ��╨���ߒ��Ȃǂ̏����l�b�g�ł��Ƃ肵�A�S�̓I�Ȍ������ɂȂ���u�C���_�X�g���[4.0�v�ƌĂ�铮�����i��ł���B BMW�͓�4�H��ƁA�ăX�p�[�^���o�[�O�H��ɓƎ��̃G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���������B�S���E��30�H��ɍL����v��ŁA�V�݂���u���W����L�V�R�̍H��ɂ��������瓱������B �X�p�[�^���o�[�O�ł�2�N�O������؎��������{���A80�ȏ�̋@���{�b�g�ɓd�͂Ȃǂ̏����c������X�}�[�g���[�^�[��ݒu�����B�e���[�^�[�̏������Ƃɓd�̗͂��p�����̈����ݔ���o������A�ғ��̕K�v�̂Ȃ��ݔ��̓d�͂��~�߂��肵���B�d�͏���ʂ�4����1����A�ŏ���1�N�Ԃ�10��kWh�̓d�͂����点���Ƃ����B10�N�ԂŁA���H���2500�����[���i��36���~�j�̌o��팸���ʂ������ށB�}�ȓd���̒ቺ�����m���ă\�t�g��ݔ��ُ̈�𑁊���������Ȃlj~���Ȑ��Y�ɂ��Ȃ���B BMW�͎����Ԑ��Y1�䂠����G�l���M�[����ʂ�2020�N�܂ł�06�N��ōŒ�45���팸����v�悾�B�V�V�X�e����7���̍팸�������ށB �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����m���̃��[�\���V�X�܁A�ŐV�ȃG�l�Z�p�Ă����60���ߓd������ ���[�\���́A���m���L���s�ɂčŐV�ȃG�l���M�[�����X�܂��I�[�v������B���̓X�܂ł́A�X�ܑS�̂̓d�C�g�p�ʂ��A�ߋ��ő�ƂȂ�2010�N�x�Δ��60���팸�ł���\��B ����̓X�܂ɂ́A�R���r�j�G���X�X�g�A�ƊE���́A��X�ܑO�ʃK���X�̓�d���i�_�u���X�L���j���u�n���M�����p�����~�M�����˃p�l���v�u�d�C���g��Ȃ��d�͊��C�V�X�e���v�����Ă���A�܂��A���ʋƊE�ŏ��߂āA�g���^�^�[�r���A���h�V�X�e�����̒~�d�r�u�v���E�X�����[�X�o�b�e���[�v���g�p���Ă���B ���ɂ����z���p�l���ɂ�鉮���̓�d���A�ǖʂ̗Ή��A�A�[�X�`���[�u�̗̍p���A�l�X�Ȋ��z������u���Ă���B�A�[�X�`���[�u�Ƃ́A�n���ɃA�[�X�`���[�u�i�z�ǁj��ʂ����ƂŒn���̔M�����������C��X���ɋ������A���ׂ��y����������@�̂��ƁB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��EU�̎��R�G�l���M�[�ڕW�́A�d�͂��M����ʂ��܂߂�2030�N�ɍŒ�27�� ���B�A���iEU�j�́A2030�N�̉������ʃK�X�r�o�ʂ�1990�N���40���팸���邱�Ƃ����肷��ƂƂ��ɁA���N�܂ł̎��R�G�l���M�[�����ڕW���Œ�27���ƒ�߂��B ����27���ڕW�͓d�͂����łȂ��A�M���p�⎩���ԂȂnj�ʔR�����܂ރG�l���M�[����S�̖̂ڕW���B�d�͂����̖ڕW�l�͒�߂��Ă��Ȃ����AEU�̃z�[���y�[�W�ɂ́A���R�G�l���M�[�d�͂́u�Œ�ł�45���ɂȂ�v�Ǝ�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���V����6�n�悪�u�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�v���֊Ԕ��ށE�����݂ȂǗL�����p �_�ѐ��Y�Ȃ́A����25�N�x���W7�{�ȁi���t�{�A�����ȁA�����Ȋw�ȁA�_�ѐ��Y�ȁA�o�ώY�ƏȁA���y��ʏȁA���ȁj�������Ő��i���Ă���u�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�v�ɂ��āA�V����6�n���I�肵���B ����o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�ɑI�肳�ꂽ�̂́A�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�\�z��L����A�x�R���ː��s�A���Ɍ��F�{�s�A�������B��̓����A�������݂�s�A���ꌧ����s�A�啪�������s��6�n��B�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�Ƃ́A�n��̃o�C�I�}�X�̌������Y������W�E�^���A�����E���p�܂ł̌o�ϐ����m�ۂ��ꂽ��уV�X�e�����\�z���A�n��̃o�C�I�}�X�����p�����Y�Ƒn�o�ƒn��z�^�̃G�l���M�[�̋����ɂ��A�n��̓��F�����������o�C�I�}�X�Y�Ƃ����Ƃ������ɂ₳�����ЊQ�ɋ����܂��E�ނ�Â����ڎw���n��������B �W7�{�Ȃ́A�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�ɑI�肳�ꂽ�n��̍\�z�̎����Ɍ����āA�o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�W�{�ȘA����c�����p���Ȃ���A�\�z�̓��e�ɉ����āA�W7�{�Ȃ̎{��̊��p�A�e�퐧�x�E�K���ʂł̑��k�E�����Ȃǂ��܂߂��x�����s���B���������x���ɂ��A����30�N�܂łɑS���Ŗ�100�n��̃o�C�I�}�X�Y�Ɠs�s�̍\�z��ڎw���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�d�̓O���[�v�Ɠ�����w�d�͌n������Z�p�����������J�n ��K�͑��z�����d���╗�͔��d������|���鎩�R�d�̓O���[�v�́A������w�A�f�W�^���O���b�h�Ƌ����ŁA�d�͌n���ɗ^���鑾�z���Ȃǂ̉e����}�����鋤�������u�Đ��\�G�l���M�[�̍X�Ȃ镁�y�̂��߂̓d�͌n������Z�p�Ɋւ��鋤�������v�ɂ��Ċ�{���ӂ����킵���B �����̓d�͉�Ђ����z�����d�ɂ��d�͂̐ڑ���ۗ����Ă��邪�A�f�W�^���O���b�h�̋Z�p�Ōn���ɗ^����e�����ŏ����ł��A�n���ɐڑ��ł��鑾�z�����d�R���̓d�͂𑝂₷���Ƃ��ł���\��������Ƃ����B ���p����Z�p�́A������w��w�@���C�����̈����͖玁���J�������u�f�W�^���O���b�h�Z�p�v�ŁA��Ƃ̃f�W�^���O���b�h�́A�������̋Z�p�𗘗p���铌����w���̃x���`���[�B �f�W�^���O���b�h�Z�p�ł͒~�d�r�����p����B�P�ɗ]��d�͂�~�d�r�ɒ��߂�Z�p�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�Γ��Z�p�ɂ͎��g���i50Hz��60Hz�j�̕ǂ͂Ȃ��B�t�����l��t���ēd�͂߂�`�ɂȂ�Ƃ�����B �f�W�^���O���b�h�Z�p�ł����f�W�^���O���b�h�Ƃ́A�����ȃO���b�h�u�Z���v�̏W���̂��B�Z�����Ƃɑ��z�����d�V�X�e����K�X���d�V�X�e���A�~�d�r�Ȃǂ�����A�����ł��Ȃ�̒��x����������\�͂�����B�܂�n���ɗ^����e�������Ȃ��Ȃ�B�Z���̃T�C�Y�͌ˌ��Z������A�s�s�S�̂܂ŋK�͂͂��܂��܁B �Z�������Œ������ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��́A�ʂ̃Z���A���Ɋ����̓d�͌n���ɗ���B���ꂼ��̃Z���́A�u�f�W�^���O���b�h���[�^�[�v�ƌĂ�鑽�[�q�^�d�͕ϊ��������Ă���B���̑��u���d�͂̒����𗬕ϊ���𗬒����ϊ���S���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/12�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�́A�����M���p�̉����V�X�e���J���A�����ȃG�l�� ���d�͂́A�������ǂ̔M�𗘗p���ĉ��ΔR�����g�킸����������V�X�e������s����w�ȂǂƋ����J�������B �����r���Ȃǂœ~�G�̐�����18�����x�ƊO�C�����10���ȏ㍂���_�𗘗p����B�L�x�ɂ��鉺����M���Ɏg���S���ł��������Z�p�ŁA���ΔR���œ����K�X�{�C���[���ȃG�l���ɗD��Ă���B ������������悭�M�����o�����߁A�����z����X�e�����X���z�ǂɒn������|���v�őg�ݏグ�������ڐG�ꂳ���M��������������̗p���A�܂��M������������������̖����������ɂ����悤����������₷���v���{�����B���Ђ͉������̂��݂���菜���Ǝ��J���̑��u��q�[�g�|���v���܂߂��V�X�e���̈ꊇ�̔����v�悵�Ă���B���������͔��z��⏕���Řd���Ă�2790���~�ƁA�K�X�{�C���[��5�{�߂��A��p�ʂʼnۑ���c�����A2012�N�Ɂu�s�s�̒�Y�f���̑��i�Ɋւ���@���v�Ŗ��Ԏ��Ǝ҂ɂ�鉺���M���p��F�߂Ă���A����̓W�J�����҂����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��NEC �ƒ���Ƃ̒~�d�r���Ȃ��œd�͂����苟���A2016�N4���ɃT�[�r�X�J�n ���z�����d�̑������n��̓d�͎����o�����X�ɉe����^����ɂȂ��Ă������A�������1���~�d�r�̊��p���B���Ђ͉ƒ���Ƃɐݒu����Ă��鑽���̒~�d�r���l�b�g���[�N�Ő��䂷��T�[�r�X��2016�N4���ɊJ�n����\��ŁA��s����2015�N�ɓ���̒n��Ŏ��؎��Ƃ��n�߂�B ���Ђ����E�ŏ��߂ĊJ�������u���A���^�C���f�}���h���X�|���X�v�̋Z�p�𗘗p�����T�[�r�X�ɂȂ�B���̋Z�p�͉ƒ���Ƃɐݒu����Ă���~�d�r���l�b�g���[�N�łȂ��ŁA�d�͂̎����ɍ��킹�ď[�d�ƕ��d�𐧌䂷��B1�b�ȓ��̎����o�����X�ł������ł��邽�߁A���̂Ƃ�����ɂȂ��Ă��鑾�z�����d�̏o�͕ϓ��ɑΉ����邱�Ƃ��\���B �T�[�r�X�̗��p�Ώۂ͔��d���Ǝ҂⏬�����Ǝ҂̂ق��A�n��̎��������@�\���ʂ����A�O���Q�[�^�ł���B2016�N4���Ɏ��{���鏬���S�ʎ��R���ɂ���āA���d���Ǝ҂⏬�����Ǝ҂͓d�͂����苟������������]���������܂�B���d���Ǝ҂͑��z���╗�͂ɂ��o�͕ϓ��̉e�������邽�߂ɒ~�d�r�̐ݒu�����߂������A�������Ǝ҂̓f�}���h���X�|���X�Ȃǂ����{���Ď��v��}������@�\���K�v�ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���J�l�J�A����3�{��5�����Ԃ̗L�@EL�Ɩ��p�l���J�� ���Ђ̊J�������L�@�d�k�Ɩ��p�l���͏]���̓��А��i�Ɣ�ׂĖ�3�{���������ALED�Ɩ��Ɠ����ȏ�̎����ƂȂ�B �L�@EL�Ɩ��p�l���͐ԁA�A�̂R�F�̔����̂��d�˂č�邪�]���i�͐F���������₷���_�Ŏ����������Ȃ��ł����B���Ђ͊����̗L�@�����g�ݍ��킹�ė��ɂ����V�f�ނ��J���A�ɂ��F�̕ω����]����40���ɗ}�������B�����̏Ɩ��Ƃ��ĕK�v�ȋP�x�i1�������[�g��������3��J���f���j��7���ȏ�A��5�����ԕۂ��Ƃ��ł���B�N�Ԃ̐��Y�\�͂�2�������x�Ŕ̔����i��1���~��Ə]���i�Ɠ����B����̎Ő��Y�K�͂��g��ł���A�̔����i�������ȉ��ɂł���Ƃ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ����B�d�͂��u�ʋ��c�v�̗v�����J���A����9���`15���ɏo�͗}�������߂� ���Ђ͍Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ݔ��̐ڑ���ۗ����Ă�����Ɋւ��āA�ۗ����Ԓ��ł��D��I�ɐڑ��̎葱����i�߂�u�ʋ��c�v�̗v���𖾂炩�ɂ����B����9���`15���ɏo�͂�}���ł��邱�Ƃ������ŁA���z���╗�͂ł͒~�d�r�̐ݒu���K�v�ɂȂ�B ���Ђ���������ڑ��ۗ��̖��͏��X�ɉ��P�̕����ɐi�ݎn�߂Ă���B�e���̑傫�����l�����āu�ꕔ�����v�\�����̂ɑ����A�D��I�ɐڑ��̎葱����i�߂�u�ʋ��c�v�̗v�������\�����B���d���Ǝ҂͓��Ђƌʋ��c�ɓ��邱�ƂŁA�ۗ����Ԓ��ł����d�ݔ��̐ڑ��������J�n���邱�Ƃ��ł���B �ʋ��c�̗v���͍Đ��\�G�l���M�[�̎�ނɂ����2�ʂ�ɕ������B���z���╗�͂ɂ�锭�d�ݔ��ł͒~�d�r�݂��āA���Ԃɏ[�d���Ė�Ԃɕ��d���邱�Ƃ��v���ɂȂ�B�~�d�r�̗e�ʂ͑��z���̏ꍇ�ɂ͒�i�o�͂�83���A���͂ł�95���ɑ�������d�͂�6���ԕ����K�v���B��i�o�͂�1MW�̃��K�\�[���[�ł�4980kWh�̒~�d�e�ʂɂȂ�i1000kW�~0.83�~6h�j�B ����ɑ��ďo�͂��\�Ȑ��́E�n�M�E�o�C�I�}�X�̔��d�ݔ��ł͒~�d�r�݂���K�v�͂Ȃ��B�����������ł��Ȃ����d�ݔ��̏ꍇ�ɂ͒�i�o�͂�100���ɑ�������d�͂�6���ԕ��̗e�ʂ�����~�d�r�݂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B ������̏ꍇ�ł�����9���`15����6���Ԃɂ킽���Ĕ��d�ݔ��̉^�]���~���邩�o�͂�}�����邱�Ƃ����߂���B�������ڑ��ۗ����������ꂽ������������ŏo�͂�}�����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����I�ɔ��d���������邽�߂ɔ��d���Ǝ҂ɂƂ��Ă͌����������ɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�ƊE����LED���p�Ɩ����� LED�������̗p�������y��ʑ�b�F��̔��p�Ɩ�����2014�N11��1����蔭������B ���݁A���z��@�Œ�߂��Ă�����p�Ɩ����́A�u���M���v�Ɓu�u�����v�Ɍ����A��퓔�����Ƃ���LED���g�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�������A���Ђ͂��̂��сA���y��ʑ�b�F�萧�x�Ɋ�Â��A�ƊE�ŏ��߂ĔF����擾�����B �]�������ɔ�����Ȓ~�d�r�̒�������𑣐i���邱�ƂŁA�����o�ϐ����m�ۂ���ƂƂ��ɁALED�����̗p�ɂ�鍂���ȃG�l������������B ���i�i�Ŕ��j��30,300�~�`203,500�~ �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ϐ����w�����Ǖ~���ߒn���M���p�V�X�e���J�� �V�X�e��������ꍇ�A�n�ʂ�1.5m�قǐ����ɖx��A�M���������|���G�`�����ǂ�~���l�߂�B�]���̐[���G�����@��H�����s�v�ɂȂ邽�ߎ{�H���e�Ղ��B�ǂ͗ւ�`���悤�ɕ~���߂ēy��ɐڂ���ʐς𑝂₵�A�����I�ɔM���������A���M�����肷��B�ǂ̒��ɉt�̂��z�����ė��p����B �|���G�`�����ǂ�50�N�ȏ�̑ϋv��������A�ǂƌp�����d�C�Z���ň�̉����邽�߁A�ڑ����̐M�����������B����A�����ǂƔ�ׂĔM�`�������Ⴂ�B���̂��߁A�ǂ̓����𔖂����č̔M������10���قnj��コ�����B �@���ǂ̕~�ݔ�p���]�����4�����x���点��B240m2���̋G�l���M�[��n���M�ł܂��Ȃ��ꍇ�A1000���~����600���~���x�ɍ팸�ł���B��������́A�]����20�N��v��������������x�ɒZ���ł���Ƃ����B ���Ȃ̒����ł́A�n���M���p�q�[�g�|���v�V�X�e���̗v�ݒu������2011�N��990���B�Z�������{�݁A�w�Z�A�a�@�ŗ��p����Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��IPCC �C���㏸2�������A�B���Ɍ������\�� �n�����g���̏����\����e����]�����鍑�A�́u�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�v��2���A�ŐV�̓����������\�����B �����I���܂ł̋C���㏸��2�������ɗ}����Ƃ������ۖڕW�̒B���ɂ́A�Y�Ɗv���ȍ~�̐��E�S�̂�CO2�̗ݐϔr�o�ʂ��A��3���g���ɗ}����K�v������Ƃ̌����荞���B���łɖ�2���g����r�o���Ă���A���݂̃y�[�X�Ŕr�o�������A����30�N�Ō��E����Ƃ������������ʂ����������B �������́A�R�y���n�[�Q���ł̑����1���ɏ��F����A2���Ɍ��\���ꂽ�B12��1������y���[�ŊJ����鍑�A�C��ϓ��g�g�ݏ���20�����c�iCOP20�j�ŕ���A�������ʃK�X�̍팸���̉Ȋw�I�����Ƃ����B IPCC�̃p�`���E���c����2���̋L�҉�ŁA�u���g����̂��߂̉Ȋw�I�������������B���ێЉ�͐^���Ɏ~�߂Ăق����v�Əq�ׂ��B �o�T�ugreen plus�v �C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j��5 ���]���� ����������Ҍ����v�� http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_syr_outline.pdf |
|
|
| �������Ȃ��`�����Ɍ������ȃG�l���̉��A12���ɍ��q�� ���y��ʑ�b�́A�Љ�{�����R�c��Ɂu����̏Z��E���z���̏ȃG�l���M�[��̂�����ɂ��āv�����₵�A���R�c��z���ȉ�z������ŐR�c���n�܂����B 2020�N�܂łɐV�z�Z��E���z���ɑ��Ēi�K�I�ɏȃG�l����`�������邽�߂̋�̓I�ȓ��e���c�_�B����ɁA2030�N�܂łɕ��ϓI�ȐV�z�ɂ���ZEH�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j��ZEB�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���j�̎��������������ȃG�l��̂��������������B12�����ɍ��q�Ă��Ƃ�܂Ƃ߁A�N�x���ɑ�1�����o����\�肾�B �ȃG�l��̋�̓I�Ȃ�����ɂ��āA12���Ɍ��z������ō��q�Ă������A12�����{����1�����{�ɂ����Ĉ�ʂ���̈ӌ���W�����{�B�ӌ���W�̌��ʂ܂���1�����{�ɂ���1���Ƃ��āA�Ƃ�܂Ƃ߂�\�肾�B �o�T�u�Z��Y�ƐV���v |
|
|
| �����f�ōĐ��\�G�l���M�[�̏o�͕ϓ����z���A2017�N�x�܂łɎ��p�Z�p���m�� ���z���╗�͂ȂǓV��ɂ���ďo�͂��ϓ�����Đ��\�G�l���M�[�̉ۑ�𐅑f�ʼn������邱�Ƃ��ł���B�]��d�͂𐅑f�ɕϊ����Ē���������@���B 2020�N��ɐ��f�Љ���\�z���鍑�̐헪���������āA�Đ��\�G�l���M�[�𗘗p�������f�ϊ��V�X�e���Ɛ��f���d�V�X�e���̋Z�p�J�����n�܂�B NEDO��2014�N�x���Ɂu���f�Љ�\�z�Z�p�J�����Ɓi���f�G�l���M�[�V�X�e���Z�p�J���j�v���J�n����B2017�N�x�܂ł̃v���W�F�N�g�ŁA�܂�2014�N�x��3���~�̗\�Z�Ŏ��،����ɒ��肷��v�悾�B ���̃v���W�F�N�g�ŊJ�����鐅�f�֘A�̋Z�p��2����B1�͐��f�𗘗p���čĐ��\�G�l���M�[�̏o�͕ϓ����z������V�X�e���ł���B ���z���╗�͂ɂ�锭�d�ݔ��͓V��̉e�����ďo�͂��ϓ����邽�߂ɁA�d�͂̈��苟���̖ʂő傫�ȉۑ�ɂȂ��Ă���B���������o�͂̕ϓ��ɂ���Đ��܂��]��d�͂�d�C�������āA���f�����邱�Ƃ��\���B ���Ăł́uPower to Gas�v�ƌĂ�Ă��āA�e���ŋZ�p�J�����i�߂��Ă���BNEDO�̃v���W�F�N�g�ł́uPower to Gas�v�̎d�g�݂����āA�Đ��\�G�l���M�[�̏o�͕ϓ����z������V�X�e���̎��،����Ɏ��g�ށB ����1�͐��f��R���Ɏg���Ĕ��d�ł���K�X�^�[�r���Ȃǂ��J�����āACO2��r�o���Ȃ����f���d�̎��p���𐄐i����B���f���d�͍Đ��\�G�l���M�[����ϊ��������f���Ăѓd�͂Ƃ��čė��p���邽�߂̏d�v�ȋZ�p�ɂȂ�B NEDO��2�̊J���e�[�}�Ǝs�꒲�������킹�āA2017�N�x�܂ł�3�N���������ăv���W�F�N�g��i�߂Ă����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���R���d�r��2020�N�ɓs����6000�� �����s���g���^�ȂǂƑg��Ŕ��������u���f�Љ�̎����Ɍ����������헪��c�v��2020�N�ɔR���d�r�ԁiFVC�j6000�䕁�y�A���f�X�e�[�V������35�J���ݒu����ڕW������B�s�������𑣐i���āA�����ܗ֊J�Î��Ɋ���i�s�s�Ƃ��Đ��E�ɑi������l�����B �s��FVC�����p�Ԃ�Зp�Ԃ̂ق��^�N�V�[�ł̓�����������B2025�N�ɂ�10����̕��y��_���B�R���d�r�o�X���s�o�X�Ő擱�I�ɓ������邱�Ƃ��������B ���f�X�e�[�V�����͌ܗ��Z�ꂪ�W�ς���n��𒆐S�ɐ������A�s���Ȃ�15���ŃX�e�[�V�����ɓ��B�ł���悤�ɂ���B2025�N�ɂ�80�J���ɂ���B�s�֘A�p�n�̊��p�Ő���������������B �ƒ�p�R���d�r�̐ݒu�䐔��2020�N��15���ˁA2030�N��100���˂ɑ��₷�B���݂͐V�z�ˌ��Ă��唼�����A����͏W���Z�������ˌ��Ăł̐ݒu�𑣂��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���g��Ȃ����͎����ŃI�t�@�p�i�\�j�b�N�A���������ȃG�l����W���[�|�b�g �ƒ낲�ƂɎg�p�p�^�[�����L�����āA�g��Ȃ����ԑтɎ����Ńq�[�^�[���I�t�ɂ���u�w�K�ȃG�l�v�@�\�������W���[�|�b�g�B ���e��ɂ͐^��f�M�ނ��̗p����Ă��ĕۉ����\�����߂�̂ŁA�ۉ����̓d�C���}������B�܂��A�ʏ�̓��������̂悤��100���܂ŕ����������ɐݒ艷�x�œ������u���D�݉����v�@�\�����ځB ������̃��f���������ʂ�4�i�K�Œ��߂ł���ق��A�R�[�q�[�̃h���b�v�ɓK�����u�J�t�F�����v���[�h�𓋍ڂ��Ă���B�܂��A�����ŏ[�d����̂ŃR���Z���g�ɂȂ��ł��Ȃ��Ă�8�`10���Ԃ̓R�[�h���X�ŋ����\���B �o�T�u�}�C�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���u�t�̓d�r�v��600km ����ԁA�������[�d ���h�b�N�X�t���[�~�d�r�Z�p���v�V�����Ǝ咣���郊�q�e���V���^�C���ɖ{����u��nanoFLOWCELL�Ђ́A�����ԗp�V�^�d�r���J�������B �d�C�����Ԃ̏펯��ł��j��Z�p���܂�1 �o�ꂵ���B�ԍڃ^���N�ɒ~����400L�i���b�g���j�̐��n�t����d�͂������o���A600km ���s����Ԃ�����Ƃ����B �d�r��ɂȂ�����A���n�t���u�����v�i�����j���ĉ��x�ł�600km ����B�K�\�����ԂƑS�������g�������\�ɂȂ�B�l�쓮�ł���A���ꂼ��̃^�C����1 �䂸�O���U�����[�^�[�����蓖�Ă��Ă���B���[�^�[�̍ő�o�͂�170kW/�A�ő�g���N�̓��[�^�[������2900Nm�B ���̋Z�p�ł͐��n�t���̂ɓd�C�G�l���M�[���~�����Ă���B���s���ɐ��n�t�ȊO�̉���������邱�Ƃ͂Ȃ��B���n�t�Ɋ܂܂�Ă���͈̂����Ŋ��ɕ��ׂ�^���Ȃ������C�I���ł���A�M������A���^���͎g���Ă��Ȃ����߁A���n�t����R�X�g�ɂȂ�Ƃ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���X�}�[�g���[�^�[�Ɠd�͐��ʐM�A�R���Z���g�o�R�Ńp�\�R����X�}�z�� �Z�F�d�C�H�Ƃ͉ƒ���̃R���Z���g�ɑ}�����ނ����ŃX�}�[�g���[�^�[�ƃf�[�^�ʐM�ł���A�_�v�^���J�������B �R���Z���g����d�͐���ʂ��ăX�}�[�g���[�^�[�ƒʐM����u�d�͐��ʐM�iPLC�FPower Line Communications�j�v�ɑΉ�����B���i�͖��肾���A2015�N3���܂łɏo�ׂ��J�n����\�肾�B �uPLC���s�[�^�v�ƌĂԃA�_�v�^�𗘗p����ƁA�X�}�[�g���[�^�[�Ɖƒ���̋@��̂������Ńf�[�^�ʐM���\�ɂȂ�B�d�͉�Ђ��ƒ�ɐݒu����X�}�[�g���[�^�[�ł͓d�͐��ʐM�̕W���K�i�ł���uG3-PLC�v���������邱�ƂɂȂ��Ă���BPLC���s�[�^�̓p�\�R���Ȃǂ̏��ʐM�@��ōL���g���Ă���C�[�T�l�b�g��PLC�Ɛڑ����邽�߂̕ϊ��A�_�v�^�ł���B �X�}�[�g���[�^�[�̒ʐM�l�b�g���[�N�ɂ͓d�͉�ЂƐڑ�����uA���[�g�v�̂ق��ɁA�ƒ���̋@��Ɛڑ�����uB���[�g�v������B�����d�͂��͂��ߑS���̓d�͉�Ђ�2016�N4���̏����S�ʎ��R���܂łɁAB���[�g�𗘗p�����f�[�^�T�[�r�X���J�n����v��𗧂ĂĂ���B�ł������̂������d�͂ŁA2014�N9������ꕔ�̃G���A�ŃT�[�r�X���J�n������A2015�N7���ɂ͑S�G���A�ɑΏۂ��g�傷��\�肾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���I�t�B�X�e�i���g�A2014�N���ߓd���ێ��k�БO�i2010�N�j���19.3���� �U�C�}�b�N�X�����\�����u�I�t�B�X�e�i���g�d�͗ʒ����v�̌��ʂɂ��ƁA2014�N�t�G�i4�`6���j�̃I�t�B�X�e�i���g�̏���d�͗ʂ�33.8kWh�^�ŁA�k�БO2010�N�̓����G�Ɣ�ׂ�19.3�����ƂȂ�A�O�N��16.9���Ɣ�ׂ�15�`20�����̐������ێ����Ă��邱�Ƃ����������B �܂��A�u�I�t�B�X�r���G�l���M�[����ʋy�уR�X�g�����v�ɂ��ƁA2014�N6�����_�ɂ�����ߋ�12�J���̕��ϒl�ł́A�G�l���M�[����ʂ́A�k�Ќ�̐������p���I�ɐ��ڂ��A2010�N��15�����B�G�l���M�[�P���́A2010�N������т����㏸�X���͕ς�炸�A��43���㏸�B �u�I�t�B�X�e�i���g�d�͗ʒ����v�́A�S���̃I�t�B�X�r���ɓ�������e�i���g��Ώۂɍs���Ă�����́B�����d�͊Ǔ��ɂ�����d�͗ʂ́A2014�N4����33.3kWh�^�A��5����33.6kWh�^�A��6����34.5kWh�^�B �t�G�i4�`6�����ρj��1�J���Ԃŏ����1������̃I�t�B�X�e�i���g�d�͗ʂ́A2010�N41.9kWh�^�A2011�N34.3kWh�^�i2010�N��18.1�����j�A2012�N34.7kWh�^�i��17.2�����j�A2013�N34.8kWh�^�i��16.9�����j�B �u�I�t�B�X�r���G�l���M�[����ʋy�уR�X�g�����v�́A��s���̃I�t�B�X�r����Ώۂɍs���Ă�����́B�t�G�i���N4���`6���j�̃G�l���M�[����ʂ́A2010�N�t�G�Ɣ�ׁA�k�В����2011�N�t�G��28���Ƒ啝�Ɍ����������A���̌��18�����A19�����A18�����ŁA�����x�̐����𐄈ڂ��Ă���B �G�l���M�[�P���́A�k�ЈȑO����т��ď㏸���A2014�N�t�G��2010�N�t�G�ɔ�ׂ�51���㏸���Ă���B�G�l���M�[�R�X�g�́A�G�l���M�[����ʁE�P���̕ϓ����ʂƂ��āA2014�N�t�G��2010�N�t�G�ɔ�ׂ�24���㏸���Ă���B����ʌ����ȏ�ɒP���㏸�̉e���������A�t�G�Ŕ�r�����ꍇ��4�N�A���ł̏㏸�ƂȂ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�G�i�W�[�v |
|
|
| ��LED��LED�Œu�������H �ō������u190���[�����v��ł��o�� �A�C���X�I�[���}��2014�N10������12���ɂ����āALED���̗p�����e��̃����v�A�Ɩ���������B 40�^�u���������̌�����190lm/W�i���[����/���b�g�j�B�����s��ɂ����Ă͒��nj`LED�����v�Ƃ��čł��������Ƃ̂��ƁB 10.5W�Ƃ�������d�͂̓��s�b�h�X�^�[�g�����̌u�����iFLR�j��4����1�Ə������B���Ђ�2010�N�ɔ�������LED�����v�i����d��25W�j�Ɣ�r���Ă���������2.5�{�ɍ��܂��Ă���Ƃ����B190lm/W�Ƃ������\���������邽�߂Ɏ��2�_�����P�����B������LED�`�b�v�ƁA�ϊ������̍����d�����BG13�������g�����߁A�����̌u�����ƒu�������ė��p�ł���B�S������2000lm�B���F�̓I�t�B�X�ȂǂɌ��������F�i�F���x5000K�j�B���ω��F�]�����iRa�j��82�B���i��1��3500�~�B ���^���n���C�h�����v�i�������ⓔ�j�̒u�������ɓK���鍂�V��pLED�Ɩ��i145lm/W�j�́A�V�K�ݔ��Ƃ��ē��������ꍇ�A��������ɖ�1.3�N�����v���Ȃ����Ƃ���������B250W�����i�i1��850lm�j��400W�����i�i2��1700lm�j������B �V��ɖ��ߍ���Őݒu����u���C��SB�`LED�_�E�����C�g�v�i84.5lm/W�j������B�~�j�N���v�g�����̗p�i����̒u��������_���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������T�b�J�[�I�肪���d�u���W���E���I�f�W���l�C�� �Ζ����̃��C�����E�_�b�`�E�V�F�����Љ�v�����Ƃ̈�Ƃ��āA�Â��T�b�J�[������C�����B�l�H�ł̉��ɏc60�Z���`�A��45�Z���`�̃v���[�g200����~�݁B ���̃v���[�g���I�肽���̓����ɂ���Đ�����^���G�l���M�[��d�͂ɕϊ�����B�אڂ��錚���ɐݒu���ꂽ���z�d�r�Ŕ�������d�͂ƂƂ��ɒ~�����Ė�Ԃ̏Ɩ��Ɏg����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�M�������Ƃ̗����K���P�p�ցA���N�@������ڎw�� ���Ȃ́A�L���҉�c�u�K�X�V�X�e�����v���ψ���v�ŔM�������Ƃ̐��x�������Ɣ��\�B���{�ɂ�闿���K����P�p������j�ŁA���N�̒ʏ퍑��ŔM�������Ɩ@�����Ă̐�����ڎw���B �M�������Ƃ́A�����̕ύX�Ɍo�Y���̔F���K�v�ŁA�l����ȂǂɈ��̗��v����悹���ė��������߂�u�������������v���F�߂��Ă���B�����K���̓P�p�ŋ������i�ɂ�闿���̈��������A�����v�����̎��R���Ȃǂ̗������オ���҂����B ���݃r�����W�n�𒆐S�ɑS��141�n��ŔM�������Ƃ�������Ă���A�d�͂�K�X�̎q��ЂȂ�78�Ђ��Q���B������␅�Ȃǂ�1�̏ꏊ�ł܂Ƃ߂Đ����E�������邽�߁A�ȃG�l��ȃX�y�[�X�Ȃǂ̗��_������Ƃ����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ��2012�N�x�̑�K�͑��z�����d�A182��kW���ݔ��F���� �o�ώY�ƏȂ́A2012�N�x�ɐݔ��F�������Z��p���z�����d�ݔ��̂����A�{�N8�������_�ŁA������E�p�~�Ɏ��������̂�182��kW�A���㒮�����s������̂�270��kW�A�^�]�J�n�ς܂��͔F��v�����[���������̂�880��kW�ƂȂ����Ɣ��\�����B ���N�x�ɂ������Z��p���z���ݔ��̔F�葍�ʂ�9.7���ɓ�����ݔ���������E�p�~�ƂȂ������A���̊����͂���ɑ����邱�Ƃ��\�������B 5�������_�ŔF��̎�����E�p�~�Ɏ��������̂�29��kW�������B3�����ŐV���ɖ�150��kW�̐ݔ���������E�p�~�ƂȂ����B 2013�N�x�̔F��Č��ɑ��Ă��A�{�N8�����瓯�l�ɕ��������{���Ă���B2013�N�x�̕����Ώۂ́A��Z��p���z���̔F�葍�ʂ̂���63.6���ɓ�����2,821��kW�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���d�C���ƘA����A���\�@����d�d�͗ʁA8��7.9%���A5�J���A���}�C�i�X ����ɂ��ƁA8���̔���d�d�͗ʁi����A10�Ѝ��v�j�͑O�N������7�E9%����790��3200��kWh�ƂȂ�A�O�N���т�5�J���A���ʼn�������B �����{�𒆐S�ɑO�N���C�����Ⴍ��[���v���L�тȂ������B�d���ʂɂ݂�ƉΗ͂�9�E1������558��1300��kWh��2�J���A���̃}�C�i�X�B���q�͂��ғ����Ȃ��ŁA8���Ƃ��Ă�3�Ԗڂ̍����B���͂�16�E0%����70��4800��kWh�B�͐�̐��ʂ������������Ƃ��v���B���q�͂�11�J���A���̃[���ŁA�����̑S�������ғ����Ă��Ȃ��B�Η͔��d�p�R���̏���ʂ͐ΒY��571��3000�g���ŁA�N�ԉߋ��ō��BLNG��484��1700�g����8���Ƃ��ĉߋ�3�Ԗڂ̐����������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���G�l���A�u�x���`�}�[�N�w�W�v��25�N�x���ʂ��Ƃ�܂Ƃ� �����̕���25�N�x����ł́A6�Ǝ�10�����176�̎��Ǝ҂�������A�����߂Ă���10����̂����A�d�F�ɂ�镁�ʍ|�����ƁA�m�������ƁA�Ζ������ƁA�\�[�_�H�Ƃ�4����ɂ��ẮA�O�N�x�Ɣ�ׁA�x���`�}�[�N�w�W�̕��ϒl�����P�����B�O�N�x���i�������A���Y�ʂ������������߁A���Y�ݔ��̉ғ��������サ�����Ƃ⎖�Ǝ҂ɂ����鑀�Ɖ��P���̏ȃG�l���M�[�̎��g�݂ɂ��A���ϒl�����P�������̂ƍl������B���ʊT�v�̏ڍׂ͉��L�������Q�ƁB http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/ �ȃG�l�@�̕���20�N�x�����ɂ�蓱�����ꂽ�u�x���`�}�[�N���x�v�Ȍ�A�����͕���23�N�x��莖�Ƃ��s�����Ǝ҂ɑ��āA���Ǝ҂̏ȃG�l���r�ł���x���`�}�[�N�w�W�̕��ʂɂ��Č��\�����B�x���`�}�[�N�w�W�̕Ώێ��ƂŁA����22�N�x���ΏۂƂȂ��Ă��鎖�Ƃ́A�@���F�ɂ�鐻�S�ƁA�A�d�F�ɂ�镁�ʍ|�����ƇB�d�F�ɂ�����|�����ƁA�C�d�͋����ƁA�D�Z�����g�����ƁB����23�N�x���ΏۂƂȂ������ƂŐ����Ƃł́A�E�m�������ƇF�������ƁA�G�Ζ������ƁA���w�H�Ƃł͇H�Ζ����w�n��b���i�����ƁA�I�\�[�_�H�Ƃ�10����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��������������70���A���쌧���Đ��\�G�l���M�[��2013�N�x�ɔ{�� ���쌧�́u�����킹�M�B�n���v�����v��2013�`2017�N�x��5�J�N�v��Ŏ��{�����B���̈�Œn��̃G�l���M�[�����̐����������邽�߂Ɏ������̌���Ɏ��g��ł���B�N�Ԃ̍ő�d�͎��v�ɑ���70�����Đ��\�G�l���M�[�ŋ����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă��邪�A�����W�v�����b��l�ł͏��N�x��2013�N�x�ɑ�����69.8���ɒB�����B 2012�N�x�Ɣ�ׂčĐ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ݔ���23.4��kW�������������߂ŁA�킸��1�N�Ԃ�2�{�ȏ�̋K�͂Ɋg�債�Ă���B2011�N�x�܂łɉ^�]���J�n���������̐��͔��d���������206.4��kW�ɒB���āA�ő�d�͎��v��295.5��kW�̂���7����n��̍Đ��\�G�l���M�[�ŋ����ł���̐��ɂȂ����B �Đ��\�G�l���M�[�̎�ʂɌ���ƁA���z�����d���v��43��kW�ɂȂ�A2012�N�x����19��kW����2�{�ȏ�̋K�͂Ɋg�債�����Ƃ��傫���B����ɒ��쌧���S���ő�1�ʂ̓����ʂ��ւ鏬���͔��d��267kW����662kW��2.5�{�ɁA�o�C�I�}�X�E�p�������d��5755kW����7505kW�֑��������B���̐�����2014�N�x�������A��������70����˔j����̂͊m�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/10�@]�@�@�� |
|
|
| ����Ƃ⎩���̓d�C�����l�グ�ŐV�d�͂Ɉڍs����11� ���d�͉��9�ЂƂ̓d�͍w���_�������������Ƃ⎩���̂̎��v��6�������_�Ŗ�1100����W�ɒB�����B���q�͔��d��11��ɑ�������B �d�͏�����̎��R����1990�N�Ɏn�܂�A�����v��6�����߂�_��d��50kW�ȏ�̎��v�Ƃ͑��d�͈ȊO������d�͂��w���o����B �V�d�͂ɐ�ւ����5�`10�����x�����Ȃ邱�Ƃ���ANTT�t�@�V���e�B�|�Y��G�l�b�g�Ȃǂ��_���L���Ă���B�d�͑��Ɍ_�����������Ƃ���A���d�͗v3��4000���A640��kW����ꂽ�B����������A����14.9�������グ��12�N4���ȍ~�Ŗ�1��8500���A220��kW�̎��v�����������B���d�͂͗v8400���A219��kW�����E���A17.26���l�グ����13�N4������1�N�]��Ŗ�1200���A30��kW�̌_����������B�d�C�����㏸���L�������ɉ��̓������L����\��������B �_��X�������̍��N��4���ł͐V���ɑS���Ŗ�100��kW�����ꂽ�B ���{�o�ϐV���Ђ̒����ł�41���̊�Ƃ����łɐV�d�͂����p���Ă��邱�Ƃ����������B�V�K�ɓd�͎��ƂɎQ���������Ǝ҂�7�����݂̓o�^��Ɛ���302�Ђƍ�N3�������4�{�ɑ������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���V���{����w�A�N�e�B�u�X�E�B���O�x���J��7.5���̏ȃG�l������ ���Ђ́A������Г��łƋ����ŁA���K���ƒm�I���Y�����ێ����Ȃ���ȃG�l��������������@�w�A�N�e�B�u�X�E�B���O�x���J�������B �{����́A��[���ɂ����Ď����̐�Ύ��x�����ɂ�����ԂŁA�������x���㉺�ɃX�E�B���O�����A���̕��ω��x��ʏ�̉��x��萧���荂���ݒ肷�邱�Ƃɂ��A���K���ƒm�I���Y�����ێ����A�ȃG�l�^�]���s��������@�BNEDO�̏ȃG�l���M�[�v�V�Z�p�J�����Ɓ^���،����i�d�͎����ً}��j�̏������čs�������̂ŁA���K���ƒm�I���Y���̕]���ɂ��ẮA����c��w�Ɉϑ����čs���A�]���̎��������x26�� 50��RH���Ɣ�r���āA���K���ƒm�I���Y�����̏�Ԃ��ێ����Ȃ���7.5���̃G�l���M�[����ʍ팸�����������B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| ���X�i���ƁA���k�\��B�ԁA�S�ēS���A���ɁACO2�팸�A���N�x�� ���Ђ͐��i�̗A����i���g���b�N����S����ւ���u���[�_���V�t�g�v���L����B���N�x���瓌�k�\�ߋE�ԂŋƖ��p�H�i�̓S���A�����n�߂��ق��֓��\��B�Ԃ̓S���A����{������B2015�N�x���ɂ͓��k�\��B�Ԃ�S�ēS���A���ɂ���B �����A���𒆐S�Ƀg���b�N����D�ւ̃��[�_���V�t�g�������i�߂Ă����\�肾�B 2006�N�Ɏ{�s���ꂽ�����ȃG�l���M�[�@�ʼn��Ƃɂ͏ȃG�l��̐��i�����߂��Ă���B�S���A���̓g���b�N�ɔ�ׁA��ʓI�UCO2�r�o�ʂ���8����1�ɂȂ�B�ŋ߂ł͒������h���C�o�[���m�ۂł����ړI�n�ȊO�̕������_�ňꎞ�ۊǂ��鎖�Ԃ��N���Ă���B���݁A�����\��B�Ԃ͒ʏ�Ȃ�g���b�N��2���A�S������3��������A������R�X�g�ō����k�܂��Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��7���̔̔��d�͗ʂ͑O�N��3.1���������A7�J���Ԃ�̑啝���� �d�͎��v�̌����X���͍��Ă������Ă���B�d�͉��10�Ђ�2014�N7���ɔ̔������d�͗ʂ͑O�N�Ɣ�ׂ�3.1���̑啝�Ȍ������L�^�����B�ƒ�����̓d����4.1�����A��Ƃ����p����Ɩ��p��4.9�����ŁA�H��Ȃǂ̎Y�Ɨp��1.1�����������B��������3������̂�2013�N12���ȗ��ł���B 2014�N7���̔̔��d�͗ʂ͓d�͉��10�Ђ̍��v��680��kWh�ɂȂ�A�O�N7����702��kWh����3.1���̌����������B�e�Ђ̔̔��d�͗ʂ��܂Ƃ߂��d�C���ƘA����ł́A�C������߂ɐ��ڂ������Ƃɂ���[���v�̌����𗝗R�ɋ����Ă���B �p�r�ʂɌ���ƁA�ƒ�����́u�d���v���O�N��4.1���̌����ŁA5������3�J���A���őO�N�̎��т���������B��Ƃ̃I�t�B�X�Ȃǂŗ��p����u�Ɩ��p�v��4.9���̌����ɂȂ�A4������O�N����̏�Ԃ������Ă���B���̂Ƃ���i�C�̉Ŏ��v�������Ă����H��Ȃǂ́u�Y�Ɨp���̑��v�ł��O�N����1.1�����������B �o�T�u�X�}�[�g�G�i�W�[�v |
|
|
| ����a�n�E�X�A�d�͏�����Q����40���˂ɓd�͂����� ��a�n�E�X�O���[�v�́A�V��Ёu��a���r���O���[�e�B���e�B�[�Y�v��ݗ��A2016�N�̓d�͏�����̑S�ʎ��R����A�d�͂̏����莖�ƂɎQ������B �Ǘ����̒��ݏZ���40���˂̓����҂�Ώۂɂ����d�͋�����\�肵�Ă���B�V��Ђ́A�d�͂������ɒ��邾���łȂ��A���ݏZ��̓����҂����߂�T�[�r�X��ł���悤�A���R�����J�n�����܂ł̊��Ԃŏ�����i�߂�B�܂����s���āA��^�}���V�����ɓd�͂���������ꊇ��d���Ƃ�W�J����\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������@�A�H��ȃG�l��240���~�����d�͎g�p�u�����鉻�v ���Ђ͍����̎��5�H��œd�͎g�p���������߂�B2016�N�x�܂ł�3�N�ԂŏȃG�l�Ɛ��Y�������ɑ��z��240���~�𓊂��A�d�͎g�p���ڍׂɔc���ł���V�X�e������H�������ǂ��H��@�B�Ȃǂ�������������B2016�N�x���܂ł�2010�N�x��œd�͎g�p������3���ȏ���P������B �������쏊�Ƌ����J�������d�͂́u�����鉻�v�V�X�e�����A��錧���ɂ���5�H���12�����珇����������B����ł͐��Y���C���S�̂̓d�͎g�p�ʂ�ҋ@�d�͂Ȃǂ̔c���ɂƂǂ܂邪�A�e���i�̉��H�ȂǂɎg��ꂽ�d�͗ʂ܂ŕ��͂ł���悤�ɂ���B�g�p���ڍׂɔc�����A���ʂ̂Ȃ����Y�X�P�W���[���̍����@�B�ғ��ɂȂ���B �܂��A�؍푬�x���グ��Ȃǂ��ĉ��H���Ԃ�Z���ł���ݔ����H��@�B���[�J�[�Ƌ����J���B�V���������ݔ����ŐV�̐ݔ��ɐ�ւ��邱�ƂŐ��Y�������߁A�ȃG�l��i�߂�B�H����̏Ɩ��ɂ͔����_�C�I�[�h�iLED�j�Ɩ�������B �����̌��@���v�͎������i�̉�����V�����̐����݉��ŐL�єY��ł���A�d�͍팸��Y��������i�߂Ă��̂Â���͂���������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����A�T�����^�C�ōH��̐ߓd�w�� ���Ђ̋Z�p�҂��H��̔M��������_�����A�����ݔ��̔\�͂ɓK���������I�ȓd�C�̎g�������w�삷��B�ŐV�ݔ��Ȃǂւ̓���ւ����Ă���B ���z�����d�V�X�e���ɂ�鎩�Ɣ��d�̔�������Ă���B���{�ł̎��тŁA�d�C�̎g�����̉��P�ŏ���d�͂�5�`10������B����ɏȃG�l���\�̍����@��̓�����10�`20���̏ȃG�l���ʂ����҂ł��鎖���������B �^�C�̓d�͏����4�����͍H�Ɨp�r����߂Ă���B���n�̐v�E�{�H��ЂƑg��ŁA�^�C�ő��Ƃ�����n�̐H�i�H��╔�i�H��Ȃǂɔp�M���p�����������{�C���[�⑾�z�����d�Ȃǂ̓����𑣂��B�������̉e���Ń^�C�̓d�C�����͖�2�N���O�ɔ�ב��ƌ�����2�����オ�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������Ȋw�Ȃ́A�w�Z�̃[���G�l���M�[�����؎��ƁA���ꌧ�Ɗ�茧�Ŏ��{ 2014�N8��7�������Ȋw�Ȃ́A�w�Z�̃[���G�l���M�[����ڎw�����u�X�[�p�[�G�R�X�N�[�����؎��Ɓi����25�N�x�j�v�ɂ����āA��{�v�揑�i�T�v�Łj�����\�����B ��������̂͊�茧���Β��ƁA���ꌧ��R�s��2�̎����́B���������w�Z�̃[���G�l���M�[����ڎw���A�L���ҁA���E����n��Z�����Q�����郏�[�N�V���b�v�Ȃǂł̌����܂������e�ƂȂ��Ă���B���Β��͌����̒f�M����g�[�G���A�̏W��Ȃǂɂ��~�G�̏ȃG�l�A��X�M���p�ݔ��ɂ��ċG�̏ȃG�l�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA���R�G�l���M�[�����p�����n�G�l�𗘗p���āA�[���G�l���M�[����ڎw���B��R�s�͌����̒f�M���A���i����̕���n���M�𗘗p�����ȃG�l�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA���R�G�l���M�[�����p�����n�G�l�i���z�����d�ݔ��j�𗘗p���āA�[���G�l���M�[����ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�ƒ�pLED�Ɩ�����JIS�ɒlj� �o�ώY�ƏȂ́A�ƒ�p�̏Ɩ����u��������LED�}���Ɉڍs���Ă������Ƃ��āA����ҕی�̂���JIS�K�i�����������B 8��20���Ɏ��{����JIS�̐���E�����̒��ŁA�ƒ�p�̏Ɩ�����Ώۂɂ����uJIS C8115�v�������B����܂ŋK��̂Ȃ�����LED�^�C�v��lj����A�K�i�̖��̂��u�ƒ�pLED�Ɩ����E�ƒ�p�u�������v�ɕύX�����B�Ώۂ́A�����̓V��Ɏ��t����V�[�����O�`���͂��߁A����҂��̔��X�ōw�����Ď����Ŏ��t���邱�Ƃ̂ł��鐻�i�B JIS C8115�ɒlj������K��͎��3�B �@LED�Ɩ����Ɏg�p���������䑕�u�Ȃǂ̕��i�Ɋւ���v�������B �A�Ɩ��̐��\�����E����������Ɋւ�����̂ŁA���̖��邳��\�������Ȃǂ̎������ځB �BLED�Ɩ��ł͌����̎������u��������������8�`10�N���x�ɂȂ邱�Ƃ���A�����Ԃɂ킽���Ďg�p����ꍇ�̈��S�\���̋L�ڗ��lj������B �o�T�u�X�}�[�g�G�i�W�[�v |
|
|
| ���u�ȃG�l�卑�A���{�v���͂⌶�z�B�ăG�C�����[�E�a�E���r���X��ɕ��� ���{�͎��������ƌ�����B���ΔR���Ɍ��肷����������A�n�M�͐��E��3�ʂ̎����ʂŁA���Ə������b�܂�Ă���B�ʐϓ�����̍Đ��\�G�l���M�[�̎����ʂ̓h�C�c��9�{���B���������ʂ̓h�C�c��9����1�B�w�i�ɂ́A�d�͉�Ђ����d�Ԃ��x�z���A�ăG�l�d���悤�Ƃ���V�K�Q���҂�������r�����Ă������Ƃ��l������B �ăG�l�œ���ꂽ�d�͂𗘗p����Ɗ����̓d�͌n���������A�Ƃ悭�w�E�����B����́A10�N�O�̋c�_���B�m���ɋC�ۏ����ȂǂŔ��d�ʂ͕ϓ����邪�A�ăG�l�䗦�̍����h�C�c��|���g�K���Ȃǂł͓V��̗\����d�Ԃ̉��P�ʼn������Ă���B������d�͋ƊE�̌��f�����K�v���B���q�͈͂��肵���d���Ƃ��āA40�N�]��x������A�������g���h�~�̂��߂ɑI�����鍑������B�������A�������S���������߂ɃR�X�g���㏸���Ă���B �o�c�헪��A�����ɗ���I�����͂Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����B�f���}�[�N�ł�1980�N����A��K�͉Η͔��d��������n��ɗ��n����W���^���������A���݂ł͖�80���̓d�͂͂⒆���K�͂̃R�[�W�F�l���[�V�����ŋ������鏬�K�͕��U�^�Ɉڍs�����B �G�l���M�[�͈��S�ۏ�A�C��A�o�ςȂǍ��ێЉ������قƂ�ǂ̖��ɊW����B�G�l���M�[�������P�̕��݂��~�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���C��ϓ��Ď����|�[�g2013 �C�ے��́C���E�C�ۋ@�ցiWMO�j���͂��߂Ƃ��āC�����O�̊W�@�ւƋ��͂��C�C��ϓ��Ɋւ���ϑ��E�Ď�����ϋɓI�ɐ��i���Ă���B �����̐��ʂ����\���邽�߁C����8�N�x�Ɂu�C��ϓ��Ď����|�[�g�v��n�������B����́C����3�N�x�ȗ����s���Ă����u�n�����g���Ď����|�[�g�v�������p���C���̂�ύX�������́B �{���ł́A���E�y�ѓ��{�̋C��ϓ��𒆐S�ɁC�C��ϓ��ɉe����^���鉷�����ʃK�X�C����ɃI�]���w���̏ɂ��āC���N�C�ŐV�̏������\���Ă���B http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/ �o�T�u�C�ے��v |
|
|
| ���@�@[�@2014/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���������������[�^�|���J���d��2���팸 �V���i�͍��ۋK�i�uIE5�v�̔F��ɒB����96���̍������������B2015�N�x�̐��i����ڎw���B �Y�Ɨp���[�^�[�͍H��̐������C����Ȃǂ��ғ�������B���{�����̑S�Ă̓d�͏���ʂ�4�����߂Ă���B���̌�����1�����P����ƁA���q�͔��d��1��̏ȃG�l�ɂȂ�Ǝ��Z����Ă���B�V�J���̃��[�^�[���g���ƁA�]���i�ɔ�דd�͎g�p�ʂ�2������A1�N�ȓ��ɏ��p���\�ƂȂ�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������u�n���J�X�v�̔M������V�X�e���� �n���J�X�́A2014�N3���ɑS�ʊJ�Ƃ��������{�݂ŁA�w�A�S�ݓX�A���p�فA�I�t�B�X�A�z�e���A�W�]��Ȃǂ��������Ă���B���̂悤�Ȏ{�݂��W�ς�����i�I�ȗ��̓s�s�Ƃ��āA�N�Ԗ�5,000�g����CO2�팸��ڎw���A��CO2��ȃG�l���M�[����������l�X�ȃG�R��i�Z�p����������Ă���A�����̍œK������V�X�e���́A���̃G�R��i�Z�p�̈�Ƃ��Ċ��p�����B ���Ђ��[�������œK������V�X�e���́A�M���ݔ�����ғ��������A���^�C���Ɏ��W�E���Z���邱�Ƃɂ��ACO2�r�o�ʂ���j���O�R�X�g���ł��Ⴍ�Ȃ�M���@��̑g�ݍ��킹���ݒ�l���Z�o���A�����𐧌�ڕW�l�Ƃ��ĔM���ݔ��Ɏ����Ŏw�����s���������ʂ����B �n���J�X�̔M���ݔ��ɁA�ꌳ�Ǘ��E�����鉻��}��V�X�e�����g�ݍ��܂�Ă���B����ɂ��A�M���ݔ��ɗp������@��P�̂�ݔ��S�̂̃G�l���M�[���������CO2�����A�^�]�R�X�g�����Ȃǂ̊e��KPI�iKey Performance Indicator:�d�v�o�c�w�W�j�Ɋ�Â��^�]�Ǘ����\�ƂȂ�B �o�T�u���X�|���X�v |
|
|
| ����Ƃ��ł���u�U�߁v�̐ߓd�\�R�}�c�A�V���H������V �k�Ђ���4�x�ڂ̉ĂƂȂ��@���̔��܂���S�z����Ă���B���̒��A�R�}�c��2015�N�x�ɓd�͎g�p�ʂ�2010�N�x��Ŕ���������v�悾�B 300���`400���~�𓊂���V���H��̍��V���B�܂��A��͂̈��ÍH��̒z40�N�ȏソ�����g����2����1���ɏW��`�Ō��đւ������A���z����o�C�I�}�X�Ȃǂ̎��Ɣ��d�A�f�M�ޓ���̕ǂ╡�w�K���X�Ȃǂ̏ȃG�l�ݔ��A���Y���C���̐��Y�������g�ݍ��킹�ĔN�ԓd�͍w���ʂ��]����92���팸����B ���Ђ́A�u�����̐����G�l���M�[����ɂ��Ĉ��Ƃ������邱�Ƃ͖����B��Ƃ��ł��邱�Ƃ͓d�͎g�p�ʂ̍팸���B�g�p�ʂ�����A�G�l���M�[����̎��R�x���L����v�Ƃ����B ���{�ɂ͍��x�������Ɍ��Ă��H�ꂪ�����B���Y������̂��߁A���H�@�B�Ȃǂ̐ݔ��͍X�V���Ă������͂��܂肢����Ȃƌ����Ă����ƌÂ��������������c��B�����A�Z��ɖڂ�]����ƒf�M�ނȂnj��ނ̐i���͒������B�R�}�c�ł������͔��M���^������������Ă݂�Ƃ��Ȃ���ʂ�����̂����������Ƃ����B �������A�d�̓R�X�g���㏸���钆�ŌŒ����팸����_�������邪�A�d�͂̎g�p���������P���鎖�������Ă����Ƃ����B�V����5���ɉғ����n�߂�����ŁA����A���̍H��̍��V���i�߂邪�A�R�}�c�����я\���Ȑ�i������m���ł���u�U�߁v�̐ߓd�������邾�낤�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ����J�Y�ƁA���Ɍ��ō������̐��f�X�e�[�V�����̏��p�T�[�r�X�J�n ���Ɍ��̓��s�ŔR���d�r�Ԍ����ɓ��{���̏��p���f�X�e�[�V������7��14���ɃI�[�v�������B �X�e�[�V������1���Ԃ�340�������[�g���̐��f�K�X���[�Ă�\�͂�����A6��̔R���d�r�Ԃɐ��f���[�Ă�ł���B��̏�Ԃ��疞�[�Ă�܂�3���ȓ��ōς݁A�ʏ�̃K�\�����Ԃƕς��Ȃ����v���Ԃŏ[�Ă�������B���f��700�C���̍����Ɉ��k�����K�X�̏�ԂŎԍڂ̐��f�^���N�ɒ�����������B���{�̍�s�ɂ���t�̐��f�̐����v�����g����^���N���[���[�ԂŐ��f����������B �g���^�E�z���_�E���Y�Ȃ�13�Ђ�2015�N�x�܂ł�4��s�s���𒆐S��100�J���̐��f�X�e�[�V������W�J����\�z��i�߂Ă���A���Ђ�20�J�������݂���v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���C�I���A�A�W�A�ŏȃG�l�x���H��Ȃǎ{�݊Ǘ� ���Ђ̓A�W�A�ŃO���[�v�O�̏��Ǝ{�݂�H��A�}���V���������ɏȃG�l���M�[�̎x���T�[�r�X���g�傷��B �x����|�Ƃ�������ʓI�Ȏ{�݊Ǘ��Ɩ��ƍ��킹�A���Ђ̏��Ǝ{�݉^�c�ȂǂŔ|���Ă����ȃG�l�̃m�E�n�E�����B�{�݊Ǘ��T�[�r�X�̃A�W�A�ł�2016�N�x�̔��㍂��13�N�x��U�{��300���~�ɑ��₵�A�O���[�v�̃A�W�A���Ƃ̒��̈�Ɉ�Ă�B �q��ЂŎ{�݊Ǘ����A�C�I���f�B���C�g���C�O���Ƃ��g�傷��B�����ł͂���܂Ŗk���s�Ȃljؖk�n��𒆐S�ɃO���[�v���O�̏��Ǝ{�݂⍂���}���V�����A���n���[�J�[�̍H��Ȃǂ̎{�݊Ǘ���������Ă����B �����ł̓V���b�s���O�Z���^�[�iSC�j�̊J�Ƃ��������ł���B�C�I���f�B���C�g�͔����_�C�I�[�h�iLED�j�Ɩ��̓����E�Ǘ��̂ق��A��①�E�Ⓚ�P�[�X�ȂǂɌv���@���݂��A���u����Ŗ��ʂȎg�p�����炷�T�[�r�X�荞�ށB���łɃX�E�F�[�f���̉Ƌ���̃C�P�A�̒����X�܂������ȂǁA���v�͍��܂��Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����{�I���N���d�͎��R���ɂ�݁A�d�͏�����r�W�l�X�x�� �d�͏����莖�ƂɎQ������ہA�ڋq�Ǘ��◿���v�Z�̃V�X�e���\�z�ɁA�]����1�N���قǂ������Ă����B�����d�͋ƊE�ł̋��ʎg�p�����O�ݒ肵�A�����̃V�X�e�����ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��邱�ƂŎ��������B �V�X�e���̓��e�̓X�}�[�g���[�^����30�����Ƃ̏���d�͂���@�\��ڋq�Ǘ��A���ꂼ��̗����`�Ԃɍ��킹�������v�Z�V�X�e���B���̑����������A����Ǘ��Ȃǎ��Ƃ��n�߂�̂ɕK�v�ȃV�X�e�����܂ށB �X�}�[�g���[�^�Ή��̂��߁A�d�͂����łȂ��A�K�X�␅���Ȃǂ������V�X�e���ŊǗ��ł���B�V�X�e���ύX�ɂ��v���ɑΉ��ł��A���T�Ԓ��x�Ŏd�グ��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����������\�����r���̏ȃG�l���m ���Ђ����m�`���̃Z�~�i�[�u�G�R�܂��m�v���J���Ă���B�s�s�v�������A���Z�Ȃǂ̐��Ƃ��u�t�߁A�����ׂ̏��Ȃ��X�Â�����c�_����B �s������Z�W�҂ȂǁA�����Ȑl�������������݁A�����Z�ŃA�C�f�A�ݏo���Ƙb���B�V���̗[���A���݉�Ђ���Z�W�ҁANPO�̐E����40�l���o�C�I�}�X���d�Ȃǂɂ��Ęb���������B���Ђ����U����ƂȂ��Ďn�߂��G�R�܂��m�̈ꖋ���B �G�R�܂��m�͍��N5���ɊJ�u�B���N3���܂�14��J���B���Ƃ��u�����邾���łȂ�����A�m����u�t�����_���邱�ƂɎ���u���B�m����80�l��W�����Ƃ���260�l�̉��傪�������B�s���Y�E���z�ƊE�����łȂ��s����w���A�����ƂȂǑ��ʂ��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���R�[�W�F�l���[�V�����v�ݒu�d�͗e�ʁA����10��� �R�[�W�F�l���c�̒��ׂŁA2013�N�x�����_�̃R�[�W�F�l�V�X�e���̗v�ݒu�e�ʂ�1004��6��L�����b�g�ƂȂ�A���߂�1�疜�L�����b�g�����B ���q�͔��d��10��ɑ������A2012�N�x�����2�N�ԂŖ�75���L�����b�g�������B2013�N�x�̓����ʂ�36��5��L�����b�g�B�H�������32��2��L�����b�g�ƂX���߂����߂��B2013�N�x�̐V�K�ݒu�䐔��931��B�v�ł�1��5127��ƂȂ����B�����{��k�Ќ�ɂa�b�o�i���ƌp���v��j���d�������Ƃ��������ق��A�d�C������}���邽�߂̎{��Ƃ��ē�������n�������̂��������Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ŐV�̍ăG�l�M���p�V�X�e�����E�������Ƃ̐��ʕ������\ �V�G�l���M�[�������i���c��́A����25�N�x�Đ��\�G�l���M�[�M���p���x�����V�X�e���̎��؎���8���A�Č��`����������8���̐��ʕ������J�����B �{���Ƃ́A���z�M�≺���M�ȂǍĐ��\�ȔM�G�l���M�[�������{�݂ȂǂƘA�g���ė��p����V�X�e���̒����E�������s�����ƁA����ю��ؐݔ������鎖�ƁB�Ώێ��Ǝ҂͖��Ԏ��ƎҁA�n�������c�̓��B ���؎��Ƃ̐��ʕ��ł́A�������ؒi�K�ɂ���ŐV�̔M���p�Z�p�ɂ��āA���ؐݔ��̂����݂�ʁi�f�[�^�j�A����̉ۑ�╁�y�������������Ȃ� ���܂Ƃ߂��Ă���B�܂��A�Č��`���������Ƃ̐��ʕ��ł́A�Đ��\�G�l���M�[�̔M���p�|�e���V���������҂����n��ɂ����āA��̓I�ȍ��x�����V�X�e���̍\�z�Ɍ������������ʂ����|�[�g����Ă���B ���؎���http://www.nepc.or.jp/topics/2014/0725_2.html �Č��`����������http://www.nepc.or.jp/topics/2014/0725_1.html �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���m�d�c�n�A���̐��f�G�l���M�[�������\ �V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO�n�j�́A���f�G�l���M�[�̑S�̑����܂Ƃ߂��u���f�G�l���M�[�����v�����\�����B ���f�̎d�g�݂���R���d�r�Ԃ␅�f���d�Ȃǂ̌���ƁA�C�O�����܂��č���̉ۑ���Љ�B���@�\�����f�Ɋւ��锒�����܂Ƃ߂��͍̂����B�@�\�̃z�[���y�[�W���疳���őS���_�E�����[�h�ł���B���f�G�l���M�[�̍����s���2030�N��1���~�A50�N��8���~��\��������A�����ɂ͐V���ȗ��p�Z�p�̊m�����d�v���Ǝw�E�����B http://www.nedo.go.jp/library/suiso_ne_hakusyo.html �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���s�[�N���ߓd�ɋ��͋����{���� �^�ĂȂǂ̓d�͎��v�̃s�[�N���ɓd�͉�Ђ̋����͂�������v���������đ�K�͒�d���N���郊�X�N���Ȃ������߁A�H��⏤�Ǝ{�݂Ȃǂ̑�����p�҂��d�͉�ЂƂ̎��O��茈�߂ɉ����Đߓd�����ꍇ�A�ߓd�ʂɉ��������͋���d�͉�Ђ��x�����V���x�̌������n�߂�B 2016�N�x�܂łɓ�����ڎw���A�o�ώY�ƏȂ����N�x���Ƀ��[���̂�������������j���B �V���x�́A�ߓd���d�������̂ƌ��Ȃ��Ĕ������邱�Ƃ���u���z���d�v�ƌĂ�A���Ăł͂��łɓ�������Ă���B������p�҂Ɠd�͉�Ђ��A�ߓd�ł���ʂ⎞�ԑтȂǂ𒇉��Ђ�ʂ��Ă��炩���ߌ��߂Ă����A�d�͉�Ђ����v��}�����������ɁA�ߓd�����s�Ɉڂ��B ��̓I�ɂ́A�X�[�p�[�Ȃǂ̏��Ǝ{�݂��Ăɋ̉��x��1�x�グ����A�Ɩ������������Â������肵�Đߓd��ςݏグ��ق��A�H��͑��Ƃ̈ꕔ���Ԃ�x���ȂǂɐU��ւ��邱�Ƃ�z�肵�Ă���Ƃ����B�����Ђ����p�҂̓d�͗��p���C���^�[�l�b�g�Ń`�F�b�N���A�d�͉�Ђ̗v���ɉ����ė��p�҂��Ƃɏu���ɐߓd�ʂ�����U�邱�ƂŁA���\�����x�Ŏ��v��}���ł���d�g�݂�ڎw���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���l�b�g�\��̃f�[�^����d�͂̎�����\���A�u�������ʁv�̎x���V�X�e�����y�V���J���� �y�V��2013�N12������h���\��T�[�r�X�̌ڋq�ł��闷�ق�z�e���𒆐S�ɓd�͂̒��B���Ƃ�W�J���Ă���B���ق�z�e���̏h���\��f�[�^�����Ƃɓd�͂̎�����\������V�X�e���̊J���ɏ��o�����B ����܂łɎ��{���Ă����T�[�r�X�̌��ʂ���A�h���{�݂̉ғ����ƃG�l���M�[�̗��p�ɂ͋������֊W�����炩�ɂȂ��Ă���B�V���ɊJ������V�X�e���ł́A�O���܂ł̏h���\��f�[�^�Ɠ����̃L�����Z���������ƂɁA30���P�ʂ̓d�͎��v���������x�ŗ\���ł���悤�ɂ���v�悾�B �d�͂̏������Ǝ҂ɂ͎��v�Ƌ����ʂ�30���P�ʂň�v������u�������ʁv���`���Â����Ă���B�����M���b�v��3���ȏ�ɂȂ����ꍇ�ɂ́A�d�͉�ЂɃy�i���e�B�[�������Ē������Ă��炤�K�v������A�V�d�͂ɂƂ��Ă͎��Ƃ��g�傷�邤���ŏ�ǂɂȂ��Ă���B ���݂͎��ۂ̎����ɍ��킹���u���������ʁv���`���Â����Ă��邪�A�����S�ʎ��R���ɔ����āu�v��l�������ʁv���F�߂���������B�V�d�͎͂��v�v��Ɣ��d�v������Ƃɓ������ʂ����{����A�d�͉�ЂɃy�i���e�B�[������Ȃ��Ă悭�Ȃ�B���̂��߂ɂ͍������x�Ŏ��v��\������K�v������A�J������V�X�e�������ʂ����邱�ƂɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��GE�G�i�W�[���K�\�[���[�œ��{�i�o ���Ђ͓��{�ő�K�͑��z�����d�����Ƃւ̓������n�߂�Ɣ��\�����B�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i������萧�x���g���Ĕ��d����B�Čn���z�����d���Ǝ҂̃p�V�t�B�R�E�G�i�W�[�Ƃ̋����o���ŁA���R��32MW�̃��K�\�[���[�����݂���B���d�����d�͂͑S�ʂ𒆍��d�͂ɔ��d����B GE�G�i�W�[�͐��E�K�͂ŔN��10���h���i1024���~�j�����Đ��\�G�l���M�[���Ƃɓ�������v�悾�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��SAS�X�}�[�g���[�^�[�f�[�^��̓T�[�r�X�J�n 2016�N�x�ɓd�͂̏����肪�S�ʎ��R������闬����ɂ�݁A�d�͉�Ђ̐V�T�[�r�X�l�Ăɖ𗧂Ă�B �X�}�[�g���[�^�[���瑗�����ʉƒ�⎖�Ə��̓d�͎g�p�����݁A�ڋq�̎g�����͂���B�S�̎��v��\������ق��A�ǂ�Ȍڋq���ǂ������g���������Ă��邩�ׂ�B��^�̐l������Ƃɂ���l�Ȃǐ����X�^�C���ɂ����������̌n��L�����y�[���̎��{�Ɏg����B�d�͂��ǂ����璲�B����ƍœK�ɂȂ�����͂���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������ɓ��{�ő�430MW�̃��K�\�[���[�A�c�_�^��2015�N�ɒ��H�� �h�C�c�̑��z�����d���Ǝ҂ł���t�H�g�{���g�E�f�x���b�v�����g�E�p�[�g�i�[�Y�iPVDP�j�����S�ɂȂ��ē��{�ɐݗ������u�e���\�[��������Ёv�����茧�ܓ��̉F�v���ɓ��{�ő�̃��K�\�[���[���J������B �n��U���̂��ߓ���4����1�i630���������[�g���j���g���āA���d�\�͂�430MW�ɒB���郁�K�\�[���[�����݂���v�悾�B �_�n��k������n�̏㕔��Ԃ�172�����̑��z���p�l����ݒu���Ĕ_�앨�͔̍|���\�ɂ���u�\�[���[�V�F�A�����O�v�����{����B ���d�\�͂�430MW�ŔN�Ԃ̔��d�ʂ�5��kWh��z��B��ʉƒ��14�����ѕ��̓d�͎g�p�ʂɑ����A���茧�̑����ѐ���4����1���J�o�[�ł���B�N�Ԃ̔��d������200���~�������ށB �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���d�Ԃ̉d�͂ʼnw�\���ɓd�͋����A1����600kWh�̐ߓd���� �������g�����A�d�Ԃ̉d�͂��w�\���̓d�C�@��ɂ���������d�g�݂𓌐����̖��T�w�̍\���ɓ��������B ����܂œd�Ԃ��u���[�L�����������ɐ�����d�͂́A�ߗׂ̓d�Ԃɗ��p����Ă������g����Ă��Ȃ������B������1500V�ő����Ă���d�͂��w�⏕�d�����u�Ō𗬂�210V�ɕϊ��A�w�̏Ɩ���A�G�X�J���[�^�Ȃǂŗ��p����B1�̉w��1����600kWh�̓d�͗ʂ�������ł���B����ɓ��l�̎d�g�݂�2014�N�x���ɒlj���7�J���̉w�ɓ�������v��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����ёg�A�Ɩ��d�C���6���팸�A5����1�邳���� �I�t�B�X�ɋP�x�𑪂�J���������t���A���̗ʂ�5����1��v�Z�����ʂȏƖ����Ȃ��悤���䂷��B �����H�Ƒ�w�ȂǂƊJ�������B�����S�̂𖾂邭����̂ł͂Ȃ��A�����l�̖ڂɓ��閾�邳���m�ۂ���悤�v����B�������������l�����Ȃ���A�Ɩ��x������p�ɂɐ�ւ���B����̃��C�g��u���̂��O��B �I�t�B�X�̏Ɩ��ݔ��͒ʏ�A����̃��C�g�͒u���Ȃ��ŁA�V��Ɩ������Ŗ��邳���m�ۂ��悤�Ƃ���P�[�X���嗬�B���̂��߁A�����S�̂��������邳�ɂȂ邱�Ƃ������A���ۂ͖��ʂ��������B �L��2�畽�����[�g���̃I�t�B�X�̏ꍇ�A�J�����V�X�e���Ȃǐݔ��ƍH�������킹�Ė�600���~��v����B�����A�ȃG�l���ʂɂ���6�N�ʼn���ł���Ƃ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���g���^�A�R���d�r��700���~�Ŕ��� ���Ђ́A�Z�_���^�C�v�̔R���d�r�����ԁiFCV�j��2014�N�x���ɔ�������Ɣ��\�����B FCV�̓v���`�i��G�}�Ɏg���A�d�r�Ő��f�Ǝ_�f�������A�d�C���N�������͂Ƃ���B�����̔��l�i��1���~�ƌ���ꂽ���A�����ȃv���`�i�̎g�p�ʂ����炵�A�������f�^���N�̍ޗ�����H�������������ږ{����4�{����2�{�ɗ}���A�R���d�r���j�b�g�ȊO�̃��[�^�[��o�b�e���[�Ȃǂ̕��i�́A�n�C�u���b�h�Ԃ̕��i�Ƌ��ʉ��Ȃǂ��āA�啝�ȃR�X�g�팸�ŁA�̔����i��700���~���x�ɗ}�����B���{�̕⏕���ȂǂŎ��ۂ̍w�����i��500���~���x�܂ʼn�����ƌ�����B �����A�R���ƂȂ鐅�f��⋋���鐅�f�X�e�[�V�������x��Ă���B�o�ώY�ƏȂ̌v��ł�2015�N�x����100�J���܂Ő�������\�肾���l��s�s�������S�ŁA���Ԃ�S���W�J�ł��邾���̐��͔����Ă��Ȃ��B���Ԃ̃G�l���M�[��ƂȂǂ̌o�c���������������ȂǍ��S�̂Ő��f�Љ���㉟������Ԑ����������Ƃ��s�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������������ܗցA�����K�X�r�o�[���Ɋ������A�������̂̕]���͓�]�O�] ���{�́A����26�N�Ŋ������u���E�z�^�Љ�E�������l�������v���t�c���肵���B �p�����̔�����}������Z�p�̕��y�ɂ��u�O���[���o�ρv��ڕW�ɁA2020�N�̓����ܗւ��������ʃK�X�̔r�o�ʂ������[���̑���ڎw���Ƃ��Ă���B�����d�͕�����P�������̂ɂ��ẮA��N�ł́u�e���͐r��v�Ƃ̕\�����A����}���������24�N�łƓ����u�ő�̊����v�֖߂����B�܂��A�n�����g���h�~�̂��߁A���z���╗�́A�n�M�ȂǍĐ��\�G�l���M�[�̊J���Ɋ�Ƃ�s���̓����𑣂��K�v���������B��̍�Ƃ��āA�Z�����ăG�l�֏o������s���t�@���h�Ȃǂ��������B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���������A�؎��o�C�I�}�X�̏ؖ����x�w���������x���X�^�[�g���d�p�`�b�v�̎Y�n���m�F �Œ艿�i���搧�x�ɂ�蔄�d���s�����������̖؎��o�C�I�}�X���d�{�݂�������R���p�`�b�v���ؖ����邽�߂̎����戵���߂��ؖ����x�́u���������v�\�����B ����A�����̖؎��o�C�I�}�X���d�ɋ�������R���p�`�b�v�Ƃ��̌����́A���̏ؖ����x�̉^�p�̂��Ƃɗ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B �؎��o�C�I�}�X�̗R���ؖ����s�����߂ɂ́A�؎��o�C�I�}�X�̐��Y���ɊW����S�Ă̎��Ǝҁi���ؐ��Y�ƎҁA���؎s��A���ޏ��A�`�b�v���H���Ǝҁj���A�������؍ދ���̔��d���p�ɋ�����؎��o�C�I�}�X�̏ؖ��ɌW�鎖�ƎҔF����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�܂��A�R���p�`�b�v�̌��ޗ��ƂȂ�؎��o�C�I�}�X�̐��Y���甭�d���ւ̔R���p�`�b�v�̋����Ɏ���S�Ă̎���ɂ����āA�̔������̔���ɑ��ďؖ�������t����B���ꂼ��̎���Ŋm�����K�ɏؖ�������t���邱�Ƃɂ��A�؎��o�C�I�}�X�̗R�����ؖ�����B �Œ艿�i���搧�x�ł́A�؎��o�C�I�}�X���d���Ŕ��d���ꂽ�d�͂́A�R���p�`�b�v�̌��ޗ��ł���؎��o�C�I�}�X�̋敪���ƂɈقȂ鉿�i�Ŕ��������B���̂��߁A���承�i�̍����ƂȂ�؎��o�C�I�}�X�������ɏؖ����邱�Ƃ����߂��Ă���B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| �������o���d�̓V�X�e�����v �d�͂̏����S�ʎ��R���𐄐i���钆�j�̖�����S���̂��u�L��I�^�c���i�@�ցv�ł���B���łɎ��R���ɕK�v�ȏ����͐i��ł��āA�V�X�e���J����f�[�^�Z���^�[�̈ϑ����10���܂łɌ��܂�B2016�N4���ɂ͏������Ǝ҂��V�X�e�����g���ēd�͋����̕ύX�葱���������ł���悤�ɂȂ�B �d�̓V�X�e�����v�̑�1�i�K�́u�L��I�^�c���i�@�ցi���́F�L��@�ցj�v��ݗ����āA�d�͉�ЂɈˑ����Ȃ��^�c�̐���S���K�͂ō\�z���邱�Ƃ��ڕW���B���ł�1������u�ݗ������g���v���������J�n���Ă���B�g���̃����o�[�ɂ́A�d�͉��10�Ђ̂ق��ɁA�V�d�͂𒆐S�Ƃ��鏬�����Ǝ҂Ɣ��d���Ǝ҂�41�Ђ�������Ă���B �܂�2015�N4������d�͂̎��v�Ƌ�����S�����x���Œ�������Ɩ����J�n����\��ł���B �L��@�ւ̋Ɩ����T�|�[�g����V�X�e���́A�����v��Ȃǂ̎�v�Ɩ��ɕK�v�ȃV�X�e���̂ق��A�I�t�B�X���̃C���t���ɂȂ��Ɩ��n�V�X�e���A����Ɂu�X�C�b�`���O�x���V�X�e���v������B2016�N4�������3��ނ̃V�X�e�����g���ċƖ����J�n����v�悾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������25�N�x�́u�G�l���M�[�����v���t�c���� �{�N�̔����ł́A����26�N4���Ɋt�c���肳�ꂽ�G�l���M�[��{�v��܂��A�����e�w�̗�����[�߂�ׂ��A�G�l���M�[�Ɋւ��鏔�ۑ���f�[�^����p���Đ������Ă���B���Ɉȉ��̓_�𒆐S�ɋL�q���Ă���B �@1�j�G�l���M�[��{�v��̔w�i�ɂ��鏔� �@2�j�����{��k�ЂƉ䂪���G�l���M�[����̌����� ���̑��A��N�ʂ�A�����O�̃G�l���M�[�����y�уG�l���M�[�����Ɋւ��ču�����{��i����25�N�x�j�̊T���ɂ��Ă��L�q���Ă�B �ڍׂ͎����G�l���M�[���̃z�[���y�[�W���Q��http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/ �o�T�u�֓��o�ώY�Ƌǁv |
|
|
| �����傲�Ƃ̏ȃG�l����A�����J�n�|�����G�l������ ���̏ȃG�l���M�[����_�����A���傲�ƂɏȃG�l���������Ă�������̍���Ɍ������������n�܂����B �����̏�ƂȂ鑍�������G�l���M�[������i�o�ώY�Ƒ��̎���@�ցj�ȃG�l���M�[�E�V�G�l���M�[���ȉ�̏ȃG�l���M�[���ψ���̉���J�ÁB�Y�ƕ���ł́A���Ǝ҂ɑ��Ĉꗥ�ɉۂ��Ă���w�͋`���݂̍����A�x���`�}�[�N�w�W��ݒ肷��Ǝ�̊g��Ȃǂ���ȏœ_�ɂȂ肻�����B �ȃG�l�@�ł̓G�l���M�[������Ǝ҂ɑ��A�G�l���M�[����P�ʂ�N�ԕ���1���ȏ�ጸ����w�͋`�����K�肵�Ă��邪�A�ȃG�l���i��ŒB��������Ȃ��Ă��鎖�Ǝ҂��o�Ă���B�^�p�̏_�������ɓ���A�ꗥ�Ɍf���邱�Ƃ̕K�v������������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/7�@]�@�@�� |
|
|
| ��CBRE �I�t�B�X�̊����ׂ�ጸ������@���J�� ���Ђ́A�Čn�s���Y���T�[�r�X���Ƃ�W�J�B�Ј����I�t�B�X���ǂ̂悤�Ɏg���A�ǂ��ɖ��ʂ��L�邩�Ȃǂ̃f�[�^���W�ߕ��́B �f�X�N�̐������炷�ȂǏȃG�l�^�̐v�ɕς��邱�Ƃœd�C�A���Ȃǂ̃G�l���M�[�g�p�ʂ��ő�5�����炷�B ���Ђ̈ړ]���Ɏ��{�������ʁA�f�X�N�̗��p����61���A�s�[�N���ł�75�����x�B�����25���̓f�X�N�ɉו���u���ė��Ȓ��������Ƃ����B�d�����e�͏W�����K�v�ȋƖ���25%�A������ƂȂǂ�5���������B���c���������ȏオ4�l�ȉ��Ŏg���Ă����B ���̒����Ɋ�Â��V�I�t�B�X�ł͐Ȑ����Ј�����4����3���x�Ɍ��炵�S���ŋ��L����悤�ɕς����B���l���̉�c��W����v����d�������ɋ������ł���ʃu�[�X�𑽂��p�ӂ���ȂNjƖ����e�ɍ��킹���I�t�B�X�v�������B ���̌��ʁA�]���ɔ���̗��p��9���}�����A������Ƃ̃X�y�[�X�����炳���ɃI�t�B�X�̉����ʐς�2���팸�ł����ƌ����B ����܂ō�����25���J���̎������������Ƃ���A�f�X�N�̎g�p���͕���50���ɗ��܂��Ă����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���É��K�X�A�d�͎��Ƃ֎Q�� ���Ђ́A�����G�l���M�[���Ƃ𐄐i�����Ƃ��āA�d�͎��ƂɎQ�����邱�Ƃ����肵���B �É����ł́A�G�l���M�[�̒n�Y�n����ڕW�ɁA���U�^�d���̊��������߂đ�K�͏W���d�͂����ɗ���Ȃ��d�͋����̐����\�z���铮�������������Ă���A���Ђɓd�͎��Ƃւ̎Q���𑣂��Ă����o�܂�����B ���Ђ́A���Ɣ��]��d�͂�Đ��\�G�l���M�[�d�͓��̒n�掑����ϋɓI�Ɋ��p���A����Ђ̓V�R�K�X�������d�ݔ��Œ������邱�ƂŁA�l�X�Ȏ��v�ɍ��킹���d�͋������\�Ƃ̌��ʂ������A2016�N��ړr�ɁA�܂��͐É��������n�悩��d�͋������J�n���Ă����\�肾�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��YKK�A�ȃG�l���ʂ̍����������Y 2014�N�x�͍�ʌ��̎�͍H����܂߂Ď������̎�͐��i���30���Z�b�g���Y����v��B 2013�N�x�ɔ��6��������B���{�̎������̕��y����7���ɂƂǂ܂�A�č���67���A�h�C�c��60���ɔ�גႢ�B �������̓A���~�T�b�V�ɔ�הN�Ԃ̗�g�[���2�`3�����点�̔����L�тĂ���B���Y�ŐV�z��t�H�[���̎��v����荞�ށB �ؑ��̌ˌ��Ă��������{�ł͖h�Α��y�̕ǂƂȂ��Ă����B�Z�݊e�Ђ͓S���̕��ނŕ⋭����ȂǍ��̊�������i�𓊓����A����҃j�[�Y�����܂��Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���R�l�b�N�X�V�X�e���Y�[�d�\�Ȏ�����R���d�r���J�� �J������������R���d�r�u�V���g���d�r�v�͕��ɍނɓS����p����B�S�Ɛ�����_���S�Ɛ��f�ݏo���_���Ҍ����������p�����B �d�r�𗘗p������d���́A��C�������荞�_�f�Ɛ��f���R���d�r���Ŕ������N�����A�d�q�Ɛ������B�d�q�̈ړ��œd���������������ŁA���͓S���Ɣ������_���S�Ɛ��f�����B ����[�d���ɂ͐��f�Ǝ_���S�����т��Đ��ƓS�ɖ߂�B�S�����J��Ԃ��g�����Ƃ��ł���B �V�d�r�̗��_��̃G�l���M�[���x�̓��`�E���C�I���d�r��5�{�B�����܂ł̏[���d��200�`300����x�Ə��Ȃ����A�S�����J�[�g���b�W���Ō�������@�\������B�ޗ��������Ȃ��߁A�d�r�̉��i��3����1�ɗ}����v��B2017�N���߂ǂɎ��p����ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���O��Z�F���݃r���ǐݒu���z�����d�V�X�e�����J�� ���ނƑg�ݍ��킹�A���z�����d�p�l���ƕǂ̊Ԃɕ���ʂ���悤�ɂ����B�p�l���ƃr���̗������₷���ƂŁA���d�����̌���ƃr���̏ȃG�l���M�[�ɂȂ���B �r���̕ǂƃp�l���̊Ԃɂ͋�����A��C����荞�ނ��߂̉�������ǂ̉����Ə㕔�Ɏ��t����B�ď�͕����������ɒʂ��A�p�l�����₷���ƂŔ��d�������4�����コ����B�~�͕ǂ̉������畗�����A�g�܂�����C�������Ɏ�����Ēg�[�̃T�|�[�g������B�g�[���ׂ���48���팸�ł���Ƃ����B �������������{�݂ɂ�48���̃p�l����ݒu�����B���d�o�͖͂�4.6kW�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��NEC �r�b�O�f�[�^�����p���ăG�l���M�[�������I�Ɏg���V�X�e�����\�z ���x��Ɠx�ɉ����A�����A�����̊��o�A�����l�̐��Y���𑍍��I�ɔ��f���A���K���ƏȃG�l�̗�����ڎw���B2014�N�x�ɂ����Ђ̌������ɍĐ��\�G�l���M�[�̔��d�ݔ���~�d�r������B �I�t�B�X��3�t���A�ɁA�l�̂���ꏊ��l�����ׂ����c���ł���Z���T�[1160��ݒu�����B�����̉��x�⎼�x�A�Ɠx���킩��B�����ɂ���l�̓E�F�u���o�R���ď����⊦����o�^�B�Z���T�[�ŏW�߂��f�[�^�Ƃ��킹�A���炩���ߐݒ肵���ߓd�ڕW��B���ł���悤�ɓd�͏���ʂ�}����B ���Y���̕]���ɂ͐l�̖��x���g���B�l���W�܂��ċc�_�������1�l�ł����萶�Y���������Ƃ݂Ȃ��B���K���Ɗ�����l���ł��邾���������A���̒��ł����Y���̍����l�قlj��K�Ȃ悤�ɋ�Ɩ�������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ������}�֑�z�{�b�N�X�ݒu���A�g���b�N��CO2�r�o�}�� ���Ђ̎��Z�ł͉ו���1�����CO2�r�o�ʂ�60�O�����팸�ł���B�s�s���ʼnו�1�̔z�B�ɖ�5�������鎞�Ԃ��k�߁A�l�����^�����ߌ�����B ��z���ɕs�݂��������l���w�ȂǕʂ̏ꏊ�ʼnו�������T�[�r�X���L����B �����s�𒆐S�Ɏ��{���Ă���u���������v���g�傷��B�]���͒n���S�w�ƃ_�C�G�[�̌v12���_��������JR�w�𑝂₵�Ĕ{��23���_�ɂ����B �s�ݘA���[�ɕ\�����ꂽURL�Ȃǂ�ʂ��Đ�p�̃E�F�u�ɃA�N�Z�X���A�ו�����肽����z�{�b�N�X��I�ԁB��舵���͈�ʑ�z�ցB 1��g�����l��8�`9���̓��s�[�^�ɂȂ�Ƃ����B��p�Ό��ʂ����ɂ߁A��z�{�b�N�X�̐ݒu���_�𑝂₷�B ���T�[�r�X�͊��Ȃ̈ϑ����ƂŁA�I����͕��y�̓x������̎Z���Ȃǂɂ��Č��ؕ���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��CO2���팸����ݔ������̗Z���������������Ǝ҂͍̑����Z�@�ւ�v�`�F�b�N ���Ȃ́A���Ǝ҂�3�N�Ԃ�3���i����5�N�Ԃ�5���j�ȏ��CO2�팸�̐���������ꍇ�̒n�����g����̂��߂̐ݔ������ɌW��A���Z�@�ւ̗Z���ɑ��āA���̗����̈ꕔ���������鎖�Ƃ����{����B �{���Ƃ̎��{�ɓ�����A����ݒu�@�l�ł�����v���c�@�l���{������ɂ����āA�{���ƂɎQ��������Z�@�ւ̌�����J�n�����B �̑����ꂽ���Z�@�ւ͏����A�������HP�ɂČf�ڂ����B�{���ƂɌW��Z�����邱�Ƃ���]���鎖�Ǝ҂́A�Q�����Z�@�ւ֘A������悤�A�Ăъ|���Ă���B������ԁF5��8���i�j�`11��28���i���j17���K������̑ΏۂƂȂ���Z�@�ցF���z���^�Z�������{������Z�@�� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���āA���z���A�ȃG�l���y��2000���~�����A5���l�ٗp �I�o�}�đ哝�̂͑��z�����d��ȃG�l�Z�p���y�̍s���v��\�����B �A�M���{�̌����̏ȃG�l����3�N�ԂŖ�2000���~�𓊎�����ق��A���z�����d��85��kW�ȏ�̑��z�����d�ݔ������A2020�N�܂ł�5���l���ٗp����B �v��ɂ̓A�b�v����O�[�O���Ȃ�300�ȏ�̊�ƁA�����c�̂����́B�ŏI�I�ɓ�_���Y�f�iCO2�j3��8000���g�����̔r�o�팸��ڎw���B��w�Ȃǂ̋��琧�x�������A���z���Y�Ƃւ̏A�Ǝx������������B �z���C�g�n�E�X�̉����ɂ����z���p�l����ݒu�����B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���ȃG�l���M�[�Z���^�[�A�e�i���g�̂��߂̓d�C�g�p�ʎZ�o�c�[���������J ���Z���^�[�́A�����ȃG�l�@�̒�����ɂ����āA�V���ɕ��K�v�ƂȂ�e�i���g�r���ɂ�����G�l���M�[�g�p�ʂ̐��v�c�[�����J���A�E�F�u�T�C�g�Ō��J���Ă���B �֓��o�ώY�ƋǂȂǂ̃T�C�g�ł����J���Ă���A�_�E�����[�h�ł���B�����Ŏg�p���Ă���G�l���M�[�g�p�ʁA�d�C�g�p�ʂ��킩��Ȃ����Ƃ������A�r�����̃e�i���g�̃G�l���M�[�g�p�ʁE�d�C�g�p�ʂ𐄌v���邽�߂̃c�[���B�r���̃I�[�i�[���r���̌��z�E�ݔ����̎d�l����͂�����ɁA�e�i���g���؎��ʐρE�ݎ��l��������͂��邱�Ƃɂ��A�e�i���g�P�ƂŃe�i���g��p���̓d�C���v���������ԑт̓d�C�g�p�ʂ����v�ł��邽�߁A������Ɋ��p���邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A�r���I�[�i�[���r���S�̂ɂ��Ē�����s���ۂɂ́A�]���ǂ���d�͉�Г���������f�[�^���g�p���邱�ƂƂ��A���Y���v�c�[���͎g�p�o���Ȃ��Bhttp://www.eccj.or.jp/tectt/ �o�T�u���r�W�l�X�X�v |
|
|
| ���������d��2018�N�Ɏ��p���ցA���Ȃ�5�N�Ԃ̊J���E���؎��� ���Ȃ�2014�`2018�N�x��5�N�ԂŁu�������d�Z�p���p�����i���Ɓv�����{����v��B �������d�ɕK�v�ȗv�f�Z�p�̊J������n�߂āA�C���ɂ�������؎�����ʂ��āA2018�N�܂łɎ��p���Ɍ��������d�V�X�e���̊m����ڎw���B�����͓V��̉e�����ɂ����A���肵�����d�ʂɂȂ闘�_������B���Ƃ̎��Z�ɂ��ƁA��C�������Ō��q�͔��d1��ɑ�������100��kW�ȏ�̐��ݗʂ������܂�Ă���B ���N�x��2014�N�x��5��5000���~�̗\�Z�����蓖�āA5�����Ǝ҂̕�W���J�n�����B6�����Ɍ��肷�� �����̓��{�ɂƂ��ĊC�m�G�l���M�[�̊J���͏����Ɍ������傫�ȉۑ肾�B�c��Ȑ��ݗʂ������܂��C�m�G�l���M�[�̒��ŁA���Ȃ͒������d�ɏœ_�Ă��Z�p�J���v���W�F�N�g���J�n����B2018�N�̎��p����ڎw���āA���d�\�͂�500kW�ȏ�̐ݔ����g�������؎��Ƃ𐄐i���Ă����B ���Ƃ̎��Z�ɂ��ƁA��C�������Ō��q�͔��d1��ɑ�������100��kW�ȏ�̐��ݗʂ������܂�Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����͔��d2050�N�x��7500���L�����b�g��������ڕW ���{���͔��d����������̓����ڕW�����\�����B 2050�N�x�ɂ͌��݂�28�{���x�ɑ�������B���q�͔��d����70��ɑ�������B�����d�͎��v��20���ȏ�����Ƃ�����_�ȖڕW�B �����ڕW�͑S���e�n��̕��ʂ┭�d��Ђ̐ݔ��e�ʂȂǂ����ƂɎZ�o�����B2020�N�x�ȍ~�ɂ͉����ɐݒu����m�㕗�͔��d�̖{�i�I�ȓ������i�ނƂ݂Ă���B�m�㕗�͂̔䗦��2020�N�x��6�������A2050�N�x�ɂ�49���܂ō��߂�Ƃ����B ������͓����ڕW�̎Z�o�ƂƂ��ɁA2050�N�x�ɂ͍����o�ςւ̔g�y���ʂ�4.5���~�A�ٗp�n�o���ʂ�29���l�ƖڕW���������Ƃ��̍����o�ςւ̉e�����܂Ƃ߂��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���T�����ȒP�Ɍ����鉻�ł���u���b�g���j�^�[�t���R���Z���g�^�b�v�v���� �ʓ|�Ȑݒ�Ȃǂ��s�v�ŁA�R���Z���g�ɂȂ������Őڑ������@��̏���d�́E�ώZ�d�͗ʁE�ώZ�d�C�����E�d�C���������j�^�[�ɕ\�����邱�Ƃ��ł���B �d�͂◿���̓R���Z���g����{���i�����O�����ƂŎ����ŏ���������A���דd�͂�1500W����ƈ��S�u�U�[�Œm�点��@�\�����ڂ���Ă���B ��������3�p�ӂ���Ă���A��i�e��1500W�A�v���͈�2�`1500W�A0.01�`999kWh�A�ώZ����0.22�`21940�~�ŁA�d�C�����͕��ϒl�ł���22.1�~/kWh�Ōv�Z�����B�T�C�Y�̓v���O�������܂܂Ȃ��ŕ�65�~���s22�~����126mm�A�d��115g�B �̔����i��2551�~�i�ō��j�A�ۏ؊��Ԃ͍w����6�����B �o�T�u�ȃG�l�ŐV�j���[�X�v |
|
|
| ��LIXIL�̕��w�K���X�A�O�t�X�N���[���A�u���܂����悯���i�v�ɔF�� LIXIL�̕��w�K���X�ƁA�O�t�X�N���[�������{�C�ۋ�����i����u�M���ǃ[���ցv�v���W�F�N�g�̌����u���܂����悯���i�v�ɔF�肳�ꂽ�B ���v���W�F�N�g�́A�ҏ��ő����X���ɂ���M���ǂ�\�h���邽�߁A�S���̎����̂▯�Ԋ�ƂƂƂ��ɔM���ǂɊւ��鐳�����m���Ƒ���p���I�ɔ��M���Ă���B���Ђł́A�ď�A�����ɓ����Ă���M�̖�70���͑��ȂNJJ�����ł��邱�Ƃ��瑋�܂����悯���i�ɗ͂����Ă���B����F�肳�ꂽ���w�K���X�́A���O���K���X�Ɏ{��������������ŁA�Ă̋������������ő��60���J�b�g�i�ՔM���f�M�^�̏ꍇ�j���A��[���ʂ����߂��B�ق��A���O���J�b�g�œ��Ă��}�����ʁA��ʕ��w�K���X�̖�2�{�̒f�M���ʂ�����B�O�t�X�N���[���́A���悯��ړI�Ƃ��A���z�M���83���J�b�g�A��[�̎g���߂���}���A�N�ԍő��19���̐ߓd���\�ƂȂ鎎�Z�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����R�[�A�S�Ă̈����ɑΉ����钼�nj^LED�����v���� �H���s�v�őS�Ă̈����ɑΉ����钼�nj`LED�����v������B �����i�͓��Ђ��J������LED�̋쓮��H�������Ő芷����Z�p�𓋍ڂ��A���i�����^���������ƂŁA�O���[�����A���s�b�h�����A�C���o�[�^�����̂��ׂĂ̈����^�C�v�ɑΉ��\�B�����̈����^�C�v�����݂��鎖�����ɂ��A�����v�^�C�v���C�ɂ����ɓ����ł���ق��A�������ړ]�ň����̃^�C�v���ς���Ă��p�����ē����i���g�p�ł����ʂ��o�Ȃ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����Ɏq�A��t���^�ȃG�l���K���X��k��B�s�����Ŏ��؎����A�����ȃG�l���� ���Ɏq�Ɩk��B�s�́A�]�������t�H�[������������r�������ɊJ�����ꂽ�ȃG�l���K���X�̌��ʎ��؎��������{���A�����ȃG�l���ʂ��邱�Ƃ��m�F�����B ��g�[�̃G�l���M�[������Ă͖�25���A�~�͖�38���팸���A�܂����K���X�ʂ̉��x�����A�]���̑��Ɣ�ĂɃ}�C�i�X8���A�~�Ƀv���X5�����L�^�B����Ɍ��I���啝�Ȓጸ������ꂽ�B �����i�͓�������ݒu���邽�ߑ���̐ݒu���s�v�B�����̃K���X���g�p���邽�ߔp�����s�v�ŁA�܂��{�H���Ԃ�1��������30���`1���ԂƒZ���A�{�H�R�X�g���팸�ł���B�܂��A�ՔM�t�B�����ƈقȂ����I�ȓ\��ւ����s�v�Ȃ��߁A�����e�i���X�R�X�g���팸�ł���B2014�N7���ɔ̔��\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���听���݃r���̃f�}���h���X�|���X���؎����A�ő�33.2���̓d�̓s�[�N�J�b�g��B�� �u���l�X�}�[�g�V�e�B�v���W�F�N�g�iYSCP�j�v�Ŏ��{���ꂽ�~�G�i2013�N1���j����щċG�i2013�N7���`9���j�̃f�}���h���X�|���X�iDR�j���ɑ��čĐ��\�G�l���M�[��L�����p���Ȃ���A�M�Ɠd�̗͂����őn�G�l�A�~�G�l���s���X�}�[�g�~�M�E�~�d�V�X�e���ƑS�̃V�X�e�����œK�ɐ���E�^�p����X�}�[�gBEMS���p�ɂ��ADR�ɂ�����ō����x���̃G�l���M�[�}�l�[�W�����g�Z�p���m���B ���̌��ʁA�d�̓s�[�N�J�b�g�����~�G�ŕ���22.9���E�ő�24.1���A�ċG�ŕ���28.7���E�ő�33.2���Ƃ����������،��ʂ��B YSCP�r������ł�2013�N��DR���ł́A�팸�v���ɑ��Ă̓d�͍팸�ʂɔ�Ⴕ�ăC���Z���e�B�u�i���j���t�^���������Ŏ��{���ꂽ���A2014�N1������̓I�[�N�V�����`����p�����u�s��^���D�����v�ɂ��DR����i�߂Ă���A���Ђ��X�Ȃ�v��E�^�p�Z�p���\�z���邽�ߎQ�悵�Ă���B �u�s��^���D�����v�ɂ��DR�́A�e���v�Ƃւ̍팸�d�͊��蓖�ėʂ���уC���Z���e�B�u�P�����I�[�N�V���������Ō��߂�DR�����B���v�Ƃ��팸�\�ȓd�͗ʂƖ��P���ŗ��D���A����ɁA���D���ɒ����팸�d�͗ʂ�B�������ꍇ�ɃC���Z���e�B�u���x��������́B �Ȃ��A�f�}���h���X�|���X�iDR�j�́A�d�͎����̕N�����\�z�����ꍇ�ɁA�d�͎g�p�}���̋��͈˗����Ď��v�Ƒ��œd�͂̎��v������d�g�݂������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{���z�A�ƒ�����d�͔̔��Q�����{���́u�����葍���G�l���M�[��Ɓv�ڎw�� �v���p���K�X������ő��̓��Ђ́A2016�N�ɂ����R�������ƒ�����d�͔̔��ɎQ�����A���Ɏ肪���Ă���v���p����s�s�K�X�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA���{���́u������ɓ������������G�l���M�[��Ɓv��ڎw���l���𖾂炩�ɂ����B ���Ђ͍��N�ɓ����āA�s�s�K�X���Ƃ��肪����֓��̎q���4�Ђ����S�q��Љ��B����ɁA�v���p���Ƒ�z���̔̔����Ƃ��肪����A�N�A�N�����������K�X�z�[���f�B���O�X�Ǝ��Ɠ���������ɋƖ���g�̌����n�߂�ȂǁA�u�d�́E�s�s�K�X�s��̑S�ʎ��R�����������������v���������Ă���B �`�k�g�c�̑�z�����Ƃ͑S���g�b�v�V�F�A�B�d�C�ƃK�X�A���A�ʐM�A�ی��Ȃǂ��܂��܂ȉƒ�����T�[�r�X���p�b�P�[�W�ɂ��Ĕ̔��������ӌ����B �܂��A�Ɩ��V�X�e�����N���E�h�����Ă��邪�AKDDI�A�����L���s�^���Ƒg��ŁA�u�d�C��K�X�̌��j�A���̔z���A�ۈ��Ȃǂ��X�}�[�g�t�H���ňꌳ�Ǘ��ł���V�X�e���v�̍\�z��ڎw���B �o�T�uSankeiBiz�v |
|
|
| ���I�[�p���[�d�̓f�[�^��͂ŏȃG�l�A�h�o�C�X���d�ƒ�g�����ē��{�ɎQ�� ���Ђ́A�d�́A�K�X��Ђƒ�g���ăG�l���M�[�g�p�̃f�[�^����͂���B�X�}�[�g���[�^�[�Ŋe�ƒ�̃G�l���M�[�g�p�ʂ�c�����A�ȃG�l���@��d�q���[���A�d�b�A�X�ւȂǂ̗l�X�Ȏ�i��p���ĕ�����₷���ʒm����B �T�[�r�X�n���8�J����93�ЁA3200�����тɏ��B �r�b�O�f�[�^��͂ƍs���Ȋw���w�����p���ăG�l���M�[�g�p�ʂ��u�����鉻�v����B�ߗא��т̏���d�͂Ƃ̔�r�⌎�ʐ��ڂ�ʒm����B�܂��������擾�����A���S���Y����p���āA��Ɠd�ȂǃG�l���M�[�g�p�ʂ̓���������B�C���⎼�x�̏����Q�l�ɂ��ăG�l���M�[�g�p�̊������͂����o���B ��̓I�ɂ͓d�͎������Ђ���������ɏȃG�l����ƕ����x�������x�ɑ��āA�ǂ�����Γd�͏����}�����A�ǂꂾ�����������炦�邩��`����B���l�̃v���O�����𓌋��Ɏ������A�Ă̍ő�d�͎��v���������ɑ�������100��kW�������錩���݁B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���֓��o�Y�ǁA������Ƃ̊����_�������ꂽ���P����W��2�e�����J �u���v�Ƃ����L�[���[�h���o�c�Ɏ�����A�ȃG�l���M�[��Y�H���̌������i�}�e���A���t���[�R�X�g��v�j�A�g�D�̊������i���}�l�W�����g�V�X�e���j�Ɏ��g��8���Ⴊ�f�ڂ���Ă���B ����ւ̑Ή��̓R�X�g�����v����Ƃ����������ꕔ�̊�ƌo�c�҂��畷��������ŁA��������̒�����Ƃ������L�[���[�h�Ɍo�c�͂����コ���Ă���B �֓��o�Y�ǂł́A�u���v�Ƃ����L�[���[�h�̎����܂��܂ȉ��l�ɒ��ڂ��A���̎��_�i���o�c�j����Ƃ̖{�Ƃɐ헪�I�Ɏ�����Čo�c���P�����{����u�����_�������ꂽ�V���Ȃ�o�c���P��@�v�̕��y��ڎw���Ă���B 2013�N3���Ɂu������ƌ����o�c���P����W�`�����_����Ƃ�ϊv����`��1�W�v�y�сA������o�c���P�ɂȂ��邽�߂̃e�L�X�g�u������ƌ��������_�ɂ��o�c���P�e�N�j�b�N�W�`��{�ҁ`�v�u������ƌ��������_�ɂ��o�c���P�e�N�j�b�N�W�`�����ҁ`�v�s�B�܂��A�x���@�ցA�n����Z�@�ցA�ƊE�c�̂Ȃǂ���̗v�]�ɉ����āA�Z�~�i�[�J�Â�u�t�h�����s���Ă���A����25�N�x��1�N�ԂŖ�40���A�̂�2,300�����Q�����Ă���B http://www.kanto.meti.go.jp/pickup/kankyoryoku/20130318keieikaizen_technic_jirei.html �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�ȂǓd�͎��R��������Ƃɔ��M ���{�͑��s�A�V�d��10�ЂƂƂ��ɓd�͎��R���Ȃǂ̏�����Ƃɔ��M���邽�߂̘A�g�g�D�u���d�͑I�ׂ���Â��苦�c��v��݂����B�{�͐V�d�͂ւ̎Q���𑣂��A�{�̎{�݂œd�͒��B���������B�Ă܂łɕ{���w�Z167�Z�̓d�͋Ǝ҂̈�ʋ������D�����{����B ����͋��c���ʂ��ĕ{���̒�����Ƃ�ƊE�c�̌����ɍu������J���A�d�͒��B���V�d�͂ɕς���R�X�g�ጸ�ɂȂ���\�������邱�Ƃ�������Ă����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ����4���G�l���M�[��{�v��A2020�N�܂ł��u�W�����v���{���ԁv�� 2003�N�̍��肩���4���ɂȂ�u�G�l���M�[��{�v��v���t�c�Ō��肵���B http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140411001/20140411001.html ��v���e�́A ��1�Ɍ��q�͔��d�𐄐i����B ��2�͍Đ��\�G�l���M�[�̓����ڕW�̐ݒ肵���B �ߋ��Ɏ����������Ƃ��āA2020�N�̔��d�d�͗ʂ̂����Đ��\�G�l���M�[���̊�����13.5���i1414��kWh�j�A2030�N�̊����͖�2���i2140��kWh�j�A�Ƃ����ڕW�l�𒍎߂ŋL�ڂ����B�i���łɌ����_�ł��Đ��\�G�l���M�[�̊�����10�����Ă���B�j ��3�́A2020�N�܂ł��u�W�����v���{���ԁv�Ɉʒu�Â����B �u�d�̓V�X�e�����v���n�߂Ƃ��������̐��x���v���i�W����ƂƂ��ɁA�k�Ă����LNG���B�ȂǍ��ۓI�ȃG�l���M�[�����\���̕ω����䂪���ɋ�̓I�ɋy��ł��鎞���i2018�N�`2020�N��ړr�j�܂ł��A����I�ȃG�l���M�[�����\�����m�����邽�߂̏W�����v���{���Ԃƈʒu�t���A���Y���Ԃɂ�����G�l���M�[����̕������߂�B ���ł�2016�N�ɂ͉ƒ���܂߂ēd�͂̏�����S�ʎ��R�����鏀�����i�݁A�����2018�N�`2020�N�ɂ͔����d�����ɂ��s��J�����\�肳��Ă���B �G�l���M�[��{�v��ʼn��߂ĕ����������������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����m���A���H�E�`�p�{�݂Ȃǂ̏Ɩ���3��700�������[�X�����ɂ��LED�� ���m���́A�����Ǘ�����S�Ă̎x�������H�Ɩ�����30,000���y�э`�p�E���`�{�݂̏Ɩ�����700���ɂ��āA����d�͂̍팸��ړI�ɁA����27�N2����������ڕW�ɁA�V���Ƀ��[�X�����̗̍p�ɂ��LED�Ɩ�������B �����ɂ������ẮA�����̎x�������̂܂܊��p���A�]������̐�����v��i�g���E�������v�̓�����ȃG�l���ɗD�ꂽLED����Ɏ��ւ���B����ɂ�����d�͂ł͔N�Ԗ�1,500��kWh�i��ʉƒ��3,100 ���т̔N�ԏ���d�͗ʂɑ����j�ACO2�ł͔N�Ԗ�5,500t�i�X�M�̖ؖ�390,000�{�̋z���ʁj�̍팸���ʂ����҂ł���B �Ȃ��ALED����̃��[�X�����Ɋւ��葱���́A4�����{��莖�������Ƃɏ����������n�߁A6�����{�܂łɑS�Ă̈Č��̌_����������\��B�܂��A�_������ɂ��ẮA�ʏ�̓�Ҍ_��ɉ����āA��O�Ғ��ݕ������I���ł���������̗p����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/5�@]�@�@�� |
|
|
| ��CO2��99���A���^���ɁA�������D�����A�����v�����g�J�� ��_���Y�f�iCO2�j���A�Y�Ɨp�K�X�Ƃ��Ďg���郁�^���ɍ������œ]������Z�p���������Ɣ��\�����B �^�C�̎����J�����PTTEP�ЂȂǂƋ����ŁA2012�N1�����珬�^�v�����g�Ŏ������Ă����B���̂ق�CO2���99���A���^���ɓ]���ł��邱�Ƃ��m�F�����B����͑�^�v�����g�ł��g����悤�Z�p�����ǁA18�N�x�����h�Ɏ��Ɖ�����B CO2�Ɛ��f�����ȐG�}�Ŕ��������ă��^�������B���_���CO2�ʂ̃��^���ɓ]���ł���Ƃ����B���^���͎Y�Ɨp�K�X�Ƃ��Ďg���A�����ł�1�������[�g��������20�~�قǂŎ������Ă���B ���Ђ́A���ɓV�R�K�X�̍̌@���ɑ�ʔ�������CO2�����^���ɓ]�������^�v�����g�Ƃ��Ĕ��荞�݂����l�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���q�[�g�|���v�������g�[�A�n���M�Ƌ�C�M�����p�A�R���i�A�O�C���Ŏ����I�� �C�����Ⴂ�Ƃ��͒n���̔M���g���A�C���������Ƃ��͋�C�Ő������ߒg�[�ɗ��p����B ��������@��͊O�C���ɉ����Ēn���M�Ƌ�C�M�̌����̗ǂ����������őI���ł���B��C�M�ŏo�͂̈ꕔ��₦��悤�ɂ������ƂŁA����܂ł��g�[�̏o�͂������ł��A�n���M�̗��p�̂��߂ɕK�v�Ȍ��̐[������ɂł���B �]���A�n���M�̗��p�̂��߂ɂ͖�100���[�g���̌����@��K�v���������B���y�̉ۑ肾�����n���@��̔�p��啝�ɍ팸�ł���Ƃ����B�K�X�Ő������߂�^�C�v�̒g�[�V�X�e���Ɣ�r���ăR�X�g����3����1�ɂȂ�B �g�[�̏o�͂�8kW��11kW��2�^�C�v��p�ӁB8kW�̃^�C�v�ʼnƂP�����ۂ��ƒg�߂���B11kW�̕��͑傫�Ȍ�����n�E�X�͔|�A���H�̓����h�~�̂��߂̃��[�h�q�[�e�B���O�Ȃǂ̗p�r�ł����p�\���B���i�̓j�@��Ƃ�90���~�i�Ŕ����j�̗\��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����ׂȖA�A�d�͔����ŁA�O�@�H�ƁA��������������V���u ���Ђ͉��������ɕK�v�ȍׂ��ȖA����肾���u�U�C���u�v�荞�ށB����������̑唼���������Ă���]�����u������d�͂��ł���^�C�v�œ��Ђ͍����V�F�A��4�����߂�ő��B�V���i���o���ăV�F�A�ێ���}��B ����������ɑ���ꂽ�����͑傫�ȃS�~����������A�������̗͂��g���ėL�@��������B�������ɂ͎_�f���K�v�ŁA�u�����[�i�����@�j�ő�������C���U�C���u��ʂ��ď������A�ɕς��A�����Ɏ_�f��n�����܂���B�u�����[�̏���d�͉͂���������S�̂�3�`5�����߂�B ���Ђ��J�������V���i�͓���ȃ|���E���^���̃V�[�g�ɂ���������ʂ��ĖA�����B�A�̒��a��1�~�����[�g���ƁA�����̉���������ŕ��y����U�C���u�̔������x�B�\�ʐς��傫�����ߎ_�f�����ɗn�����݂₷���A�u�����[�̏���d�͂����点��B ���Ђ̊������i�����ǂ��A���̌`���ψ�ɂ���ȂǏ��Ȃ���C���ł��A�����ݏo����悤�ɂ����B���v���c�@�l�̓��{�������V�Z�p�@�\����Z�p�F�����ߖ{�i�̔�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���d�́A�Η͐V���݂ɃJ�W�A�����̍ĉғ��A�s�����ŁA��R�X�g�ΒY���ɋ����� �����d�͂͌��q�͔��d��10��ɑ�������1000��kW���̘V�����d�����đւ��鎖�Ǝ҂�����D���J�n�B���d�͂⒆���d�͂�100���`150��kW���x����D�ɂ�����B �����̍ĉғ������ʂ��Ȃ����ʼnΗ͔��d���̌o�N���͐i��ł���A���d�R�X�g�̈����ΒY�𒆐S�ɋ����͂��m�ۂ���B �u�i��Ɉ��̓d�͂���������j�x�[�X�d��������Ȃ��v�B�ډ�������ۗL����d�͉�ЂɂƂ��ċ��ʂ̔Y�݂��B�����͉ғ���80�����x�ň��肵�Ĕ��d�ł��邽�߁A�d�͊e�Ђ͌�������ՂɎ��v�ɉ����ăK�X�Η͂�Ζ��Η͂ŋ��������Ă����B����������P�������̌�A�e�n�̌����͑�������~�B��R�X�g�̈���d�����s�����Ă���B �����[���Ō}�������~�͉Η͔��d���̉ғ��𑝂₵�ď��������̂̎��Ԃ͍j�n��̋����������B�^�]�J�n����40�N�ȏソ�����Â����d����{�������̒������u�~�h���d���v�Ƃ��Ďg���K�X�Η͂��t���ғ��B �����Η͂̐V���݂�i�߂邤���ł͉ۑ������B�����~�n���Ɍ��݂��錚�đւ��̏ꍇ�A�H�����̓d�����m�ۂ���K�v������B ���D�ɂ�钲�B�̐��ۂ��s�������B�o�ώY�ƏȂ�12�N�ɉΗ͔��d���̐V�݁A���đւ��͌������D�Ŏ��Ǝ҂����ăR�X�g��}�����邱�Ƃ�d�͉�Ђɋ`���t�����B�����D�łǂ��܂œd���B�ł��邩��s�������鐺�͑����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���n���o���̎��R�G�l���M�[���d���Ǝ҂����X�a���d���A�ɑR�A�u21���I�̓d���A�v�������� �S���ōĐ��\�G�l���M�[�i���R�G�l���M�[�j�̔��d�Ɏ��g��35�̎��Ǝ҂��u�S�������n�G�l���M�[����v�i���́j�̐ݗ��Ɍ����ē����n�߂��B2014�N3��11���ɂ͔��N�l����𓌋��ŊJ�����B �k�C�������B�܂ŁA�s����n����ƂȂǂ��o�����ĉ^�c���鏬���ȓd�͉�Ђ̏W�܂肾���A�����d�͂ȂǑ��d�͉�Ђ̋ƊE�c�́u�d�C���ƘA����i�d���A�j�v�ɑR���A�s���ڐ��́u21���I�̓d���A�i�݂�Ȃ̓d���A�j�v��ڎw���Ă���Ƃ����B ���N�l����́A�����{��k�Ђ���3���N�ƂȂ�u3.11�v�ɍ��킹�ĊJ����A��Ód�͂̍����\�E�q��В����u��������Ƀc�P�����A���j�I�ȓ]������������Ƃ����v�������߂āA�w�S�������n�G�l���M�[����x�𗧂��グ�����v�Ɛ錾�����B ������̎����NJ����߂�ѓc�N��E���G�l���M�[�����������́u���z���╗�͔��d�Ȃǂ̎��Ƃ��n�߂����Ă��A���d�͉�Ђւ̐ڑ����Ő��������A���Z�@�ւ���̎����ȂǂŌ˘f�����Ƃ������B�S���̒��Ԃ��o���ƒm�������L���邱�ƂŁA�S���Łw�����n�G�l���M�[�x�����݂��Ɏx�����A�̔��l�b�g���[�N���L���Ă��������v�ƌ���Ă���B����̐����Ȕ�����5���O��ɂȂ錩�ʂ��B �o�T�uJ-CAST�j���[�X�v |
|
|
| ���ߓd�����i�C������H�A10�N��̎��v�����������ޓd�͉�� 10�Ђ�3��31���܂łɌ��\����2014�N�x�̋����v�������ƁA10�N���2023�N�x�܂ŔN��0.2�`1.0���̃y�[�X�Ŕ̔��d�͗ʂ������Ă������Ƃ�\�z���Ă���B2023�N�x�Ɍ����Ĕ̔��ʂ̌�����z�肵�Ă���d�͉�Ђ�1�Ђ��Ȃ��B �����2013�N�x�̔̔��d�͗ʂ͒����E��B�E�����3�Ђ������O�N������A���̂ق���7�Ђ͌�����������B�����2014�N�x���k�C���E���k�E������3�Ђ�������������ł��邪�A�c��7�Ђ͌�����z�肵�Ă���B�����E�k���E���E�l����4�Ђ�2�N�A���Ŕ̔��ʂ����錩�ʂ����B��ƂƉƒ�Őߓd�i�݁A�d�C�@��̏���d�͂��N�X�������Ȃ��Ă���B �Ƃ��낪�e�Ђ�2015�N�x����Ăю��v�����邱�Ƃ�������ŁA��������Ƃɋ����͂̑�����}����j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������26�N�x�Łu�G�l���M�[�E���g����Ɋւ���x�����x�ɂ��āv�i����26�N3���ҏW�j http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ondanka/shien_seido_26fy.html �֓��n��G�l���M�[�E���g�������i��c�����o�[���̋��͂ŁA���y�ъ֓��o�ώY�ƋNJǓ��̓s���A���ߎs���ɂ�����G�l���M�[�E���g����̂��߂̕⏕���E���������̎x�����x���Ƃ�܂Ƃ߂����́B �Ȃ��A���q�łɂ��܂��ẮA����e�Z�~�i�[��C�x���g���Ŕz�z�\��B �o�T�u�o�ώY�ƏȊ֓��o�ώY�Ƌǁv |
|
|
| �����g���������\�ցAIPCC����J���A�e���ƓK����c�_ ���A�̋C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�j�̑��25���A���l�s�ŊJ�������B100�J���ȏォ��Ȋw�҂�{��\���500�l���Q���B5���Ԃɂ킽��A���g���̉e���\�����Q��}����u�K����v�������ċc�_���A31���ɒn�����g���̍ŐV�������\����B ���{�ł̑���J�Â͏��߂āBIPCC�̃��W�F���h���E�p�`���E���c���́u���̕����C��ϓ��Ƃ������G�Ȗ��𗝉����鏕���ɂȂ�v�Ƌ����B�Ό��L�W�����͎�Í����\���u����҂͋C��ϓ����ɑ��āA�����ϊv���邱�Ƃ��K�v���ƔF�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B ���͉��g�����b���������ی��̊�b�����ƂȂ�B ���Ȋw�I�������e���ƓK���h�~�Ɍ������u�ɘa��v�\�\�̊e��ƕ���ɕ�����đ�����J���A�e�[�}���Ƃ̕����܂Ƃ߂�B����J���ꂽ�̂́A���g���̉e���ƓK������c�_�����2��ƕ���̑���B ���̍ŏI���Ắu���ׂĂ̑嗤�ƊC�m�ŋC��ϓ��̏d��ȉe�����ϑ�����Ă���v�Ǝw�E�B�C�ʏ㏸�⍂����Q�̑����ɂ�鐔���l�̈ڏZ�̂ق��A�C���㏸�Ȃǂɔ����������Y�ʂ̌����A��s�s�ł̍^����Q�̑����Ȃǂ���̓I�Ȉ��e���Ƃ��ċ����Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������s�̒������Ə�2012�N�xCO2�r�o�ʂ͐k�В���̏�Ԃ��ێ� �����s�́A���Ǝ҂����o���ꂽCO2�r�o���̕������ƂɁA����24�N�x�ɂ����钆���K�͎��Ə��̉������ʃK�X�r�o�ʂ̏W�v���ʁi����l�j���Ƃ�܂Ƃ߁A���\�����B ����23�N�x����3�N�A���Œ�o���Ă����2��7�玖�Ə��i��o���Ə��̂�����8���j��CO2�r�o�ʂ��W�v�����Ƃ���A����24�N�x�̔r�o�ʂ́A�k�Ќ�̎��g�݂ő啝�ɔr�o�ʂ�������������23�N�x�Ɠ����x�ł���A�ߓd�E�ȃG�l���M�[��̎��g�݂��p������Ă��邱�Ƃ��킩�����B �����{��k�Ќ�̕���23�N�x��CO2�r�o�ʂ́A�k�БO�̕���22�N�x�Ɣ�ׂ�12�������B����24�N�x�́A�k�Ќ�̐ߓd�E�ȃG�l��̌p���ɂ��A����22�N�x�Ɣ�ׂ�11�����������B��̖߂�͂�����̂́A�����K�͎��Ə��̐ߓd�E�ȃG�l���M�[��̒蒅���݂�ꂽ�B ��ȗp�r�ʂɂ݂�ƁA����22�N�x��ŁA�e�i���g�r���i�I�t�B�X�n�j��19�����A�e�i���g�r���i���ƕ����n�j��11�����A���̓X�i�����X�[�p�[�E�S�ݓX�j��18�����A���H�X�i�H���E���X�g�����j��8�����B�e�i���g�r���i�I�t�B�X�n�j�ƈ��H�X�i�H���E���X�g�����j�͕���23�N�x��ł��팸�ƂȂ����B�e�Ǝ�Ők�БO�Ɣ�ב啝�ȍ팸���Ȃ���Ă���A�ڋq��ΏۂƂ���X�܂ɂ����Ă��팸���p������A�ߓd�E�ȃG�l���M�[�蒅���Ă��Ă��邱�Ƃ��f�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���V�d�͂Ƃ̌_���7���Ɋg��A���Ɍ����N��1��2200���~���팸 �����̂ɂ��E�E�d�͉�Ђ̓������S���ɍL�����Ă����B ���Ɍ���334�J������{�݂̂����A��7���ɂ�����239�J���̓d�͋����_������d�͂���V�d�͂�ւ��邱�Ƃ����肵���B 2014�N4��1�������1�N�_��ŁA���z��22��5600���~�ł���B�]���̂܂܊��d�͂ƌ_��𑱂����ꍇ�̓d�C������23��7800���~�ɂȂ�A�N�Ԃ�1��2200���~�̍팸���ʂ����҂ł���B ���Ɍ���2014�N�x�̓d�C������}�����邽�߂ɁA�d�͒��B�̓��D�������{�ݒP�ʂ���O���[�v�P�ʂɕύX���Č_��̋K�͂�傫�������B���D�Ώۂ�248�{�݂̂���237�{�݂�17�O���[�v�ɂ܂Ƃ߁A�K�͂̑傫��11�{�݂����͒P�Ƃœ��D�����{�����B ���̌��ʁA�Œ�z������V�d�͂�239�{�ݕ��𗎎D���āA���d�͂����D�ł����̂�9�{�݂����������B����܂ŕ��Ɍ����V�d�͂ƌ_�Ă����{�݂�16�J���ŁA�S�̂�6���ɉ߂��Ȃ��������A2014�N�x�͈�C��76���֊g�傷��B�����44�J���̎{�݂œ��D��\�肵�Ă���B ���Ɍ��͓��D�����̕ύX�ɉ����āA�_��N�����N����P�N�x�ɉ��߂��B���݂̃G�l���M�[������l����ƁA�e���Ǝ҂̒��B�R�X�g������ǂ��Ȃ邩�肩�ł͂Ȃ����߁A�댯���S���y������B����2015�N�x�̌_������D�����{���āA�\�Ȍ���̃R�X�g�ጸ��}����j���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�d�@�A�p�M������A�d��3���팸�A�G���^�z�ǂŎ��� ���Ђ́A�̔M������̔z�ǂ��]���̉~���^����G���^�ɕύX���邱�ƂŁA�M�����̌�����3���ȏ㍂�߂��BAPF�i�ʔN�G�l���M�[��������j�ƌĂ��ȃG�l���l��8�n�̓N���X��5.9�ƂȂ�A�ƊE�ō���B�������B �M������͋����̃t�B���ɗ�}�����炷�z�ǂ����������\���ŁA�t�B�����O�C����荞�ݔz�ǂɐG��邱�Ƃŗ�}�ƔM����������B�G���^�ɂ������ƂŁA���ʂ����ێ����Ȃ���z�ǂ̖{���𑝂₵�M�����ʂ��������B�܂��A�M���������߂邽�߁A�M���`������t�B���Ɣz�ǂ̐ڐG���ʐς��A�z�ǂ����ɒ����ȉ~�đ��₵����A�ǂ̓������c�ɕ������ė�}�����ڊǂɐG���ʐς𑝂₵���B����ɁA�ʉ߂��镗�ʂ��傫���ď�������M�ʂ�����������̏㕔�ɗ�}���W���I�ɗ����悤�ɂ��A���ʂ������B�M���������̌���ŁA��[���ɂ́A����܂ł��7�x�����Z��50�x�܂Ŏg����悤�Ȃ�A����܂őΉ��ł��Ȃ����������̃r������ɂ��Ή��\�ɂȂ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ɓ����q��Ђ��ƒ�����d�͂ɎQ�����O�̐ΒY�Η͂��V�� �ɓ��������̎q��ЂŐV�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj�̈ɓ����G�l�N�X�́A2016�N�̓d�͏�����̑S�ʎ��R�����ɂ�݁A�ƒ�����̓d�͏�����ɎQ������B ������p�d�����m�ۂ��邽�߂ɁA�V���ɓ��k�ȂǂłQ�ΒY�Η͔��d����V�݂���ق��A�����Η͂����݂���B �V�݂���ΒY�Η͖͂�10��kW�ŁA�������2016�N�x�Ɍ��݂̖�12��4000kW�̎��������d�ʂ��3�{��38��kW�Ɉ����グ��v��B�����z�͖�500�`600���~��������ł���B ���Ђ���̓d�͒��B���܂ߔ̔��d�͗ʂ�3�N��ɖ�10�{��10��kWh�Ɉ����グ��B ���Ђ͉ƒ�����̉t���Ζ��K�X�iLPG�j��100�����т̘̔H�����B2200�J���̌n��K�\�����X�^���h�̔̔��Ԃ����p���A�ڋq���J�A�d�͏����莖�ƂƉΗ͂ȂLj���d���m�ۂ𗼗ւŐi�߂�B��菤�Ђł͊C�O�̉Η͔��d���Ƃ̃m�E�n�E�����A�����d�͎��Ƃɖ{�i�Q�����铮�����������A�������������Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N���E���̃}�C�N���g�Ő��䂷�钴���^�d�͕ϊ��V�X�e�����J�� �J�����ꂽ�d�͕ϊ����u�͎��E�������ɂ�郏�C�����X�d�͓`���Z�p�����p�������̂ŁA���d���œ��삷��o�����^GaN�p���[�f�o�C�X�ƁA�}�C�N���g�ɂ���ڐG�d�͓`����p�����≏�Q�[�g�쓮��H���̃`�b�v�ɏW�ω��B���͂����𗬂�ʂ̐U���E���g���̌𗬂ɒ��ړd�͕ϊ�����B �]���̓d�͕ϊ��V�X�e���ɔ�ׂēd�͑��������Ȃ��ق��A�T�C�Y��1/100�ƒ����^�ƂȂ�A�d���R���f���T���s�v�Ȃ̂�10�N�ȏ�Ƃ����������ȓ��삪�\�Ƃ����B�܂��A�o�����^GaN�p���[�f�o�C�X�ɂ��}�g���N�X(3?3)�R���o�[�^�������̗p���Ă��邽�߁A�𗬃��[�^�[���̑f�q�����ŋ쓮�ł���ȂǁA�쓮�n��啝�ɃV���v�����E���^���ł���B �o�T�uASCII�v |
|
|
| ���Œ�o�͂ח�25���܂Œጸ�ȃG�l�K�X�����ȈՊї��{�C���������J�� ���K�X�̂ق��A���K�X�A���M�K�X�A�O�Y�H�Ƃ�4������̔����J�n����B���i�́A�R�Ď��ɏo��r�K�X�𗘗p���ċ��������M����G�R�m�}�C�U�������uVS�v��468���~�i�Ŕ����j�B �{���i�́A�Œ�o�͂��]���@��50������25���ɂ܂Œጸ���邱�Ƃɂ��A�]���@�ɔ�גᕉ�ׂł̔R�Ă��\�Ƃ��A�R�Ă̔���iON/OFF�̕p�x�j�������������B�܂��A�R�Ď��ɏo��r�K�X�𗘗p���ċ��������M����u�G�R�m�}�C�U�v�������^�C�v�ł́A�G�R�m�}�C�U�̓`�M�ʐς𑝂₷���ƂŁA�r�K�X����̔M����ʂ��15�����������A��i�{�C��������97���܂Ō��コ�����B �܂��A�����@���[�^�[�̐���ɃC���o�[�^���g�p���A�]���@�������[�^�[�̉�]����Ⴍ�ݒ肵���B �����̌��ʁA�]���@�Ɣ�ׁA�{�C���^�]�������1�`5������A�����@�̏���d�͂��25�`50���ጸ�����A�����j���O�R�X�g�̔R���K�X����1�`5���ጸ����ƂƂ��ɁA�����גጸ�Ɋ�^���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����[���A�ƊE�ō����������A���nj`LED�Ɩ��J�� 2008�N��LED�Ɩ����ƂɎQ���������Ђ́A2���ɁALED�f�o�C�X�Z�p��A���Ђ̍ő�̓����ł����鍂�����ȓd����H�v�Z�p���������A�ƊE�ō��̔�������190lm/W��B���������nj`LED�Ɩ����J�������B �����i�͔������������コ�������ƂŁA����d�͖ʂ����ɗD��Ă���A�]���̒��nj^LED�Ɩ��Ɣ�r���Ĕ���������35�`6���A�b�v�A����d�͂�24���_�E���A�C���o�[�^�[���u�����i�������^�C�v�j�Ɣ�ׂ�ƁA����d�͖�60���_�E���̏ȃG�l���\�����������B �]����LED�Ɩ��͌�����_�ɏW�����ĖڂɗD�����Ȃ��C���[�W�����邪�A�����i�͋ψ�Ȗʔ������������A���̊g�U�Z�p�ɂ���Ă܂Ԃ�����}����B�I�t�B�X�̂悤�Ȓ����Ԏg�p��������ł��A�ڂւ̕��S���ŏ����ɂȂ�悤�ɔz������Ă���Ƃ����B�܂��A���Ђł̓Z���T�Z�p�△���ʐM�Z�p�ȂǂƑg�ݍ��킹�A���K�Ȑ�����Ԃ�ڎw�����g�[�^���\�����[�V������Ă��s���\��B �o�T�u�G�R�m�~�b�N�j���[�X�v |
|
|
| ���������݁A�I�t�B�X�E�a�@�̏ȃG�l���C��p�E���ʃl�b�g�Z�o �������݂͒�����Ƃ�a�@�����ɁA�����̏ȃG�l��ړI�Ƃ������C�H���̌��ʂƍH����Z�o����E�F�u�T�C�g���J�݂����B�Ɩ���Ȃǂ̉��C�����[�����R�ɑg�ݍ��킹�ăV�~�����[�V��������T�C�g�ŁA���p�͖����B��p�Ό��ʂ���₷���������ƂŁA���C���v���@��N�����B ���p�҂̓I�t�B�X��a�@�A�X�܂Ƃ����������̗p�r�A�L���A�����ȂǁA���C���������Ă��镨���̊�{������͂���B�T�C�g�͍ő�40��ނ̉��C����Ă��A���ꂼ��̏ȃG�l���ʂ��p�Ȃǂ��\�������B ���l�̃T�C�g�͂���܂ŋ@���u���C���h�Ȃǂ̃��[�J�[���肪�������̂����������A����̐��i�╪��ɍi���Ă����B�r����Ώۂɂ��A�l�X�ȉ��C���j���[�����ł���T�C�g�͏��߂ĂƂ����B �]���̓��j���[�A���H���̑��k���A���̓s�x�ڍׂȒ�ď���p�ӂ��Ă�������2�J�����x�����邱�Ƃ��������B�ȈՂȐf�f���ʂ������T�C�g�����J���邱�ƂŁA����܂Ŏ���̖����������Ǝ҂̈Č�����荞�ޑ_��������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����ŁA�č���LNG�Γ��A�o�� ���Ђ́A�Đ��{����č��Ő��Y����LNG�̑Γ��A�o�̏��F�����B2019�N�ɂ������ȃV�F�[���K�X�ł���č��YLNG����{�Ɏ������ށB�d�@���[�J�[��LNG�������͎̂����㏉�߂āB������220���g���̈������ʂ́A�����d�͂Ⓦ�M�K�X�̗A���ʂɎ����K�͂��B ���������Ђ̑_����LNG�̔��ł͂Ȃ��B�����܂œd�C���[�J�[�̖{���ł���LNG�𗘗p���镡�����d�ݔ��̒�Ăɂ���B2016�N�̓d�͑S�ʎ��R���œd�͉�Ђ̋����͌�������B�����ɏ��������ɂ͍X�Ȃ�R�X�g�팸���s�����B�K�X���d�̏ꍇ�A���d������8���͔R����Ƃ����B�V�F�[���K�X�ł���LNG�́A�d�͉�Ђ�����A�W�A�⒆������A������LNG�Ɣ�ׁA����ł�3�����x�����B���Ђ́A�����ȃK�X�ƍŐV�^�K�X�^�[�r���Ƒg�ݍ����ĔR����̑啝�팸���Ă���_�����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���L�@�������z�d�r�p�ޗ��̐V���������@�����ϊ�����������I�ɃA�b�v �}�g��w�Ȃǂ́A�L�@�������z�d�r�ɗp���鍂���x�ȍ����q�ޗ����ȕւɐ�������V�����������@���J������ƂƂ��ɁA�����x���̒B���ɂ��A�L�@�������z�d�r�̌��d�ϊ�������0.5������4���Ɍ���A�������������炩�ƂȂ����Ɣ��\�����B �L�@�������z�d�r�́A�ߔN�ł͕ϊ�������10����������邪�A�{���ʂɂ��A����ɍ��i���ȑ��z�d�r�ޗ����R�X�g�ɐ����\�ƂȂ邱�Ƃ����҂����B ���̕��@��p���āA�����ϊ������������Ő�[�ޗ��������x�ō�������A����ɕϊ����������コ���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�܂��A��ʐ��Y�ɂ��K����������@�ł��邱�Ƃ���A�ėp�������߂邱�ƂŐV���Ȑ����Z�p�ɂȂ�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����z�����Ɛi�߂Ȃ��ƎҁA670���F������� ���z���Ŕ��d�����d�C�̌Œ艿�i������萧�x������A�o�ώY�ƏȂ́A���d�̔F������̂Ɏ��Ƃ�i�߂悤�Ƃ��Ȃ�670���̋Ǝ҂̔F����������B �Ǝ҂��玖�������ŁA3���ɂ����̎����������ɓ��ݐ�B���d�p�̓y�n�Ɛݔ��̂����ꂩ�����������Ă��Ȃ���780���ɂ��Ă��A8�����܂łɗ������m�ۂ��Ȃ���ΔF������������j���B �����x�́A���Ǝ҂��F�莞�ɐݒ肳�ꂽ���i�œd�͂�d�͉�Ђɔ����d�g�݁B���x���n�܂���2012�N�x�̑��z���̔�����艿�i��1kWh������42�~�ƍ��߂ɐݒ肳��A�d�C�����ɏ�悹����Ă���B ������艿�i�͂��̌�A�ቺ���Ă��邪�A�F�莞�_�̍������i�œd�͂�邽�߁A�����̊�Ƃ��Q����\���B�������A���������傫���Ȃ�悤�ɁA���z���p�l�����l�����肷��܂Ŏ��Ƃ��n�߂Ȃ��Ǝ҂����o���Ă����B�F�萧�x�ɂ͔��d�J�n�̊����͂Ȃ����A�o�Y�Ȃ͑��z���̕��y�̖W���ɂȂ�Ɣ��f�����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���ȃG�l�̎���͏���҃r�b�O�f�[�^�������ӎ��v�� �킪���ł͎Y�ƁA�^�A�A�Ɩ��E�ƒ�Ƃ������G�l���M�[���p����ɉ����ďȃG�l���M�[���W�J����Ă��ăn�[�h�ʂł̖@�����͒����ɐi�W���Ă���A���т�����̃G�l���M�[����ʂ�1990�N�㔼�����ɂ��Č����X���ɓ]���Ă���B ����A�ȃG�l���M�[�s���̎��H�ɐϋɓI�ȉƒ�Ƃ����łȂ��ƒ���ׂ�ƁA��҂͑O�҂��3�����x���G�l���M�[����ʂ������A�Z�ݎ�̍l������s���ɂ���đ傫�ȍ������Ă���B�@��������P�ɂ��n�[�h�ʂ̏ȃG�l���d�v�����A������g���Z�ݎ�̃G�l���M�[����s���̉��P�Ƃ������\�t�g�ʂ���̎��s�������āA���߂ďȃG�l���M�[�̐��ʂ������邱�ƂɂȂ�B �����{��k�Ќ�̐ߓd�s���ɂ��đ傫�Ȑߓd���B�����ꂽ���A�ȍ~���X�ɒቺ�X���������Ă�����̂́A�ߓd�ӎ��̌���ƍs�����H���ȃG�l���M�[�ɋɂ߂đ傫�Ȑ��ʂ������炵�Ă���B �ߔN�̓X�}�[�g���[�^�[��HEMS�iHome Energy Management System�j�Ȃǂ̐V���ȋZ�p�ɂ��ȃG�l���M�[�����҂���Ă��邪�A�����͂����܂œK�ȃG�l���M�[����s���𑣂��Ă����⏕�I�ȃV�X�e���Ƒ�����ׂ��ł���A���ǂ͂������g�����Ȃ��͍̂ŏI����҂ɂق��Ȃ�Ȃ��B����͂킪���ɂ����Ă��Z���Ɠd���i�Ƃ������n�[�h�ʂ���̏ȃG�l���M�[�̐��i�ƂƂ��ɁA����������҂̍s���ɏœ_�Ă��������܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă���Ǝv����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2014/3�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�V�u�����h�őS���ɓd�͔̔��ցc���̃C���[�W��� �����d�͂��V�������ʎ��ƌv��i�Č��v��j�Ŏ��v������̒��Ɉʒu�Â������d�͊Ǔ��ł̓d�͏����莖�Ɓi�S���̔��j�ɂ��āA���d�Ƃ͕ʂ̐V�u�����h��ݒ肷����j�ł��邱�Ƃ����������B��������n���ȂNJNJO�ł̓d�͋����ɓ�����A�n��Ɛ�F�������A������P�������̂ň����������d�u�����h�����A�V�u�����h�œW�J���������ڋq�Ɏ�����₷���Ɣ��f�����ƌ�����B���d�ł�2014�N�x�ɐV�u�����h���Ȃǂ����߂���ŎГ��g�D���A�c�Ɗ������n�߂�B �V�Č��v��œd�͏����莖�Ƃɂ��āu�S���ň��̃V�F�A���m�ۂ���v�Ɩ��L�B�����͊NJO�̎��Ɣ��d�ݔ������H��Ȃǂ���d�C���w���������͂��m�ۂ�����A2014�N�x���ɐV�u�����h�Ŋ�ƂȂǑ�����v�ƌ����ɉc�Ɗ������n�߂�B�����I�ɂ͊NJO�ɉΗ͔��d����V�݂��邱�Ƃ��������Ă���B�ƒ�����ɂ́A�d�C�ƃK�X����̂Ŕ����Ă��炤���Ƃŗ����������ɂȂ�v�����Ȃǂ��Ă��Ă����B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ��JX ���f���i�A�K�\�������݂ɔR���d�r�Ԍ㉟�� ���Ђ͔R���d�r�Ԍ����ɒ�R�X�g�̐��f�����ɏ��o���B���f�����S�ő�ʂɗA���ł���Z�p���J���A2020�N�����h�ɐV�Z�p���g���������Ԃ̐������n�߂�B�����R�X�g��3�����x�팸�A�K�\�������݂ɗ��p�ł��鉿�i������ڎw���B ��_���Y�f(CO2)��r�o���Ȃ��R���d�r�Ԃ̓G�R�J�[�̖{���Ƃ���A�g���^�����Ԃ�z���_��2015�N����ʎY�E�̔�����B���{��2015�N�x�܂łɃK�\�����X�^���h�ɑ�������u���f�X�e�[�V�����v������100�J���ɐ�������v��B�����A�������s�����Ɋ��Z�������i���K�\������2�{�ȏ�Ƃ����R�X�g�ƁA1�J��������3���`5���~�����鐅�f�X�e�[�V�����̌��ݔ���y�̉ۑ�ɂȂ��Ă����B ����̐��f�̐��Y�E���ʃR�X�g�͂P�������[�g��������145�~�B����J��������R�X�g�̐��f�����̐��������ƁA�R���d�r�Ԃ̕��y�̖ڈ��Ƃ���铯100�~�ȉ�����������B�X�e�[�V���������ȂǂŐ��f�̐��Y�ʂ𑝂₷���Ƃł���ɃR�X�g�����������A�������s�����ŃK�\�������݂ƂȂ铯��60�~�ɋ߂Â���v��B ���łɐ_�ސ쌧�C�V���s�Ȃ�5�J���ɐ��f�X�e�[�V�������J�݁B2015�N�x�܂ł�40�J���ɑ��₷�v��B���̒i�K�ł͏]���Z�p���g�����A�R���d�r�Ԃ����y���ɓ���Ƃ݂���2020�N����t�̗A�������p���B��C�ɋ����Ԃ��L������j���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �������}�[�A�R�[�W�F�l�ŁA�]���������A��[�ɂ��A�����A�v���C�A���X�� �����}�[�G�l���M�[�V�X�e���͓��Ђ̔M�d�����V�X�e���u�}�C�N���R�[�W�F�l���[�V�����v�Ɠ����A�v���C�A���X�̋z���≷���@�u�W�F�l�����N�~�j�v��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�]����������g�[�����łȂ���[�ɂ����p�ł���V�X�e�������������B �]���A�����}�[�̃}�C�N���R�[�W�F�l�ɂ���Đ�������鉷���͓~�ɂ͒g�[�Ɏg���邪�A�ď�͎g���ꂸ�̂Ă��Ă����B����A�����A�v���C�A���X�̃W�F�l�����N�~�j�͗�[�p�̃K�X�̉t���ƋC���ɉ����𗘗p����B�}�C�N���R�[�W�F�l�̉������W�F�l�����N�~�j�ɍė��p���邱�ƂŁA���ʂȂ���[���s���d�g�݂��B �}�C�N���R�[�W�F�l��25�`35kW�̓d�͂d�ł��A���i��800�`1200���~�B�W�F�l�����N�~�j��60�`100�g���̗�[�\�͂������A���i��2600���`3400���~�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����{�s�[�}�b�N�A�@��U���ȓd�́A�r���⏤�Ǝ{�����A�����x�A�P��Œ��� ���Ђ́A�ʏ�2�̑��u���K�v�ȉ��x�Ǝ��x�̒�����1��łł���@����J�������B�@������^�����������ŁA���x�̒����Ő��܂��M�����x�̏グ�����ɂ��g���A���������B�]���i������6���d�͎g�p�ʂ��팸�ł���Ƃ����B �V���i�͉��x�߂�����M�E��p���u�ƁA�������u�u�f�V�J���g�v����̉������B �ˊO���珋����������C����荞�މẮA�܂���p���u�ʼn��x�������A���Ƀf�V�J���g�ɒʂ��B���x���Ⴂ�قNj�C���ɑ��݂ł��鐅���̗ʂ͏��Ȃ��Ȃ邽�߁A���x��������ΐ������]��B����𐅕��z�����ɗD�ꂽ�����܂��t�����f�V�J���g���z�����d�g�݁B�f�V�J���g�ɕt���������́A���C�̍ۂɗ�p���u�ʼn��x��������ۂɔ��������M���g���āA���O�ɕ��o����B �������Ċ����~�͋t�̓���������B�r�C����ۂɗ�p���u�ʼn��x�������ăf�V�J���g�ɐ������z���B�z�C�̍ۂɂ��̍۔��������M��p���ĉ��M����ƂƂ��ɁA�f�V�J���g��ʂ��Đ�������荞�݁A�����ɑ��荞�ށB���x������ł��s������ꍇ�ɂ͉�������g���B �z�ǂ���@�Ȃǂ̔z�u���H�v�������ƂŁA��p�E���M���u�ƃf�V�J���g����̉��E���^�������B��ʂ̃r����{�݂ł��g����悤�ɂ����B�܂��A�l�X�ȋV�X�e���Ƒg�ݍ��킹����悤�ɂ��Ă���A�����̋K�͂�p�r�ɂ��킹�đΉ��ł���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��YKKAP�A�����T�b�V���̒f�M����45������ ���Ђ͐��E�ō������̒f�M���\���������T�b�V�̑���4��1���ɔ�������B3���̃K���X�ō\���B�Ԃɂ����C�w��M�`����}����A���S���K�X�Ŗ��������B �����Ȃlj��g�Ȓn��ł́A�A���~�T�b�V���w�K���X�̑��ɔ�ח�g�[���3�����点��Ƃ����B�Z���ЂȂǂɔ��荞�݂�ڎw���B �V���i��3���̃K���X�̊ԂɌ���16�~�����[�g���̋�C�w��2�݂��A�A���S���K�X�𒍓������B���̒f�M���������w�W�̔M�ї����́A���E�g�b�v�N���X�̒f�M���\�ŔM�ї���(U�l)�F0.91W�^(m2�EK)�Ɠ��Ђ̍ŏ�ʐ��i�ɔ��45�����コ�����B�h�C�c�̊�������A���E�ō����x���Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���O�H�d�H�ƃy�����[�^�]�[���Ή��̋@���� �r���̑��ە�(�y�����[�^�]�[��)�Ή��̋@�̌��s2���f�����t�����f���`�F���W���A3��������J�n����B���C���i�b�v�́A���@�\���j�b�g�E�H�[���^�C�v�iACW�j��16�@��A�E�H�[���X���[�^�C�v�iWT�j��16�@��ŁA�S32�@��ƂȂ�B ���̃V���[�Y�́A�r���ǖ@�i���z���q���@�j�ɑΉ����銷�C�^�]�@�\�ƊO�C��[�@�\�𓋍ڂ������@�\�^8�@��͓��P���A�����č��@�\�^����r�C�@�\�Ȃǂ̈ꕔ�t���@�\���������V���v���ȕ��y�^8�@���V���Ƀ��C���A�b�v�����B ���������̂��߁A���V���[�Y�Ƃ��ɍ����\�c�C�����[�^�����k�@��DC�t�@�����[�^��V���ڂ��AACW�V���[�Y2.5kW�^�C�v�i��i�g�[�\�́j��APF�i�ʔN�G�l���M�[��������j�l4.7�A���N���XWT�V���[�Y��5.1�ƁA��������]���@��Ŗ�30�����サ�Ă���B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| �����z�����d�̐ݔ��F��A400kW�ȏォ��y�n�m�ۏ��ނ��K�{�� �Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�ɂ����āA�^�p�ύX������A1��14���i�j��t������A400kW�ȏ�̑��z�����d�̐ݔ��F��\�����s���ꍇ�́A�y�n�̊m�ۏ��m�F���鏑�ނ̒�o���K�v�ƂȂ�B�����500kW�ȏオ�ΏۂƂȂ��Ă���B ��̓I�ɂ́A�y�n�m�ۏ��m�F������̂Ƃ��āA���̂����ꂩ�̏��ނ��K�v�ƂȂ�B �ݒu�ꏊ�����L���Ĕ��d���Ƃ��s���ꍇ �@�o�L�듣�{�i�ʂ��ł��j �@�����_�̎ʂ� �ݒu�ꏊ�ɂ����݁E�n�㌠�ݒ���Ĕ��d���Ƃ��s���ꍇ �@���ݎ،_�E�n�㌠�ݒ�_�̎ʂ� �\�����_�ŁA�ݒu�ꏊ�̏��L�A���͒��݁E�n�㌠�ݒ���Ă��Ȃ��ꍇ �@�����҂̏ؖ��� �{���x�ɂ����Ĕ��d���邽�߂ɂ́A���O�ɐݔ��̔F�����K�v������B�ݔ��F��Ƃ́A�@�߂Œ�߂�v���ɓK�����Ă��邩���ɂ����Ċm�F������́B����24�N12��10���̉^�p�ύX�ł́A500kW�ȏ�̑��z�����d�ݔ��̐\���ɁA�y�n�̊m�ۏ��m�F���鏑�ނ�K�{�Ƃ��Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�\�[���[���K���R�z�s�A�i�ϕی�֏�ቻ �啪���R�z�s�c��́A�Վ��c����J���A�s�������R����i�ςɗD�ꂽ�n����K�͑��z�����d���i���K�\�[���[�j���݂́u�}�����v�Ɏw�肵�A���Ǝ҂ɒ��~�����߂邱�Ƃ��ł�����Ă�S���v�ʼn������B29������{�s����B���͂̌i�ς��Ȃ��悤���̎��~�߂�������_���B����̃��K�\�[���[���݂ɉe�����y�ڂ��������B ���������̂́u���R�����ƍĐ��\�G�l���M�[���d�ݔ��ݒu���ƂƂ̒��a�Ɋւ�����v�B5�畽�����[�g���ȏ�Ń��K�\�[���[�ȂǍĐ��\�G�l���M�[���d�{�݂����݂��鎖�Ǝ҂ɑ��A���O�Ɍv����s�ɓ͂��Ďs���Ƌ��c���邱�Ƃ�A�n��������̊J�Â��`���t�����B�}�����ł�5�畽�����[�g�������ł��A���Ǝ҂Ɍ��݂��Ȃ��悤���͂����߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �܂��A���ᔽ�Ȃǂ��������ꍇ�A�s�������Ǝ҂Ɏw���⊩�����s�������荞�B�v��̓͂��o���Ȃ�������A���U���������肵���ꍇ�͎��ƎҖ������\�ł���Ƃ��Ă���B ���s���z�@���ˌ��ŁA�����̍�����ЂȂǂɂ�镡���̃��K�\�[���[���v�悪����B���ӏZ����ʑ��̏��L�҂��i�ϔj��𗝗R�Ɍ��݂�}��������Ă̐�������߂Ă����B �o�T�u�����{�V���v |
|
|
| ���d�͏�����A16�N�߂ǂɑS�ʎ��R���o�Y�ȁA���v��2�e�̊T�v��
�o�ώY�ƏȂ́A������ɒ�o����d�C���Ɩ@�����Ă̊T�v���A�����}�̌o�Y����Ǝ����E�G�l���M�[�헪������̍�����c�ɒ����B3�i�K�Ői�߂�d�̓V�X�e�����v�̑�2�e�ŁA2016�N���߂ǂɉƒ낪�d�͉�Ђ����R�ɑI�ׂ�悤�ɂ���d�͂̏�����S�ʎ��R�������ŁA�V�K�Q���𑣂��ăT�[�r�X�̑��l���◿������������ڎw���B �����Ăł́A�d�͉�Ђd���Ǝ҂Ƒ��z�d���ƎҁA�����莖�Ǝ҂ɋ敪���鐧�x�����B�d�͑�肪�n��Ɛ肷��K�����Ȃ��Ȃ�A����҂͑��n��̓d�͉�Ђ�V�K�Q���̓d�͉�ЂȂǂ����R�ɑI�Ԃ��Ƃ��\�ɂȂ�B�o�Y�Ȃ́A���R���œd�͑�肪�Ɛ肷��7��5000���~�K�͂̎s�ꂪ�J�������ƌ����ށB �����A���ʂ͓d�C�����̋K�����p������ȂǁA����҂�ی삷�邽�߂̌o�ߑ[�u���Ƃ�B���R������A�������s�\���Ȓi�K�œd�͑�肪�l�グ�ɑ���悤�Ȏ��Ԃ�h���̂��_�����B ���H�̗Վ�����ł́A�d�͉��v�̑�P�e�ƂȂ�����d�C���Ɩ@�������B�S���K�͂̓d�͎���������S���u�L��n���^�p�@�ցv���A2015�N���߂ǂɐݗ�����̂����ŁA�t���ɓd�͏�����̑S�ʎ��R���ƁA2018�`2020�N���߂ǂɓd�͑��̔��d�Ƒ��z�d�����ʉ�Ђɂ��锭���d�����̎��{�L���Ă���B �o�T�uSankeiBiz �v |
|
|
| �����s�s�̊X���A3�N�ȓ��ɂ��ׂ�LED���\�Z�Ă�8��7700���~ �\�Z�Ґ��ɂ������āA���s��6�̎{��Əd�_�\���Ă���A���̒��̂ЂƂu���ɂ₳�����z�^�Љ�A�����\�ȃG�l���M�[�Љ�̎����v�ɂ��āA��13��3,800���~�̗\�Z�����L�̓���Ō�����ł���B ���̓��uLED���H�Ɩ����̐ݒu�v�i8��7,700���~�j�Ɋւ��āA�������H�̂قڂ��ׂĂ̌u������67,000����2016�N�x�܂ł�LED������Ƃ��Ă���A����͓����v�悩��3�N�Z�k�̗\��Ŏ��{����邱�ƂƂȂ�B �������H�ɂ��Ă��V���ɐ��ⓔ��10,000���𗈔N�x����2�N�Ԃ�LED�����錩�ʂ��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2014/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���_�C�h�[�h�����R�̏ȃG�l���̋@�A�f�M���\����ŏ���d��2���� �_�C�h�[�h�����R�́A2013�N���̂��̂�������d�͂�N��20���팸�ł���ȃG�l���̋@���J�������B2014�N1������S���W�J����\�肾�B ����A���Ђ��J�������̂́u���@�\�f�M�@�\���ڂ̏ȃG�l���̋@�v�B���̋@�̕\�ʓS�ɐ^��f�M�ނ�������A����ɂ����f�M�d��ŕ������Ƃɂ���āA���̋@���̉��x���ߋ@�\�̉ғ����Ԃ����Ȃ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�ċG�ɂ́A�����①�@�\���Ւf���ꂽ��ԂɂȂ��Ă��A�ō���8���Ԃ͏��i�̉��x���ۂ����B �^��f�M�ނ̓O���X�E�[���Ȃǂ�^��p�b�N�������t�B�����Ȃǂŕ��������̂ŁA���߂��M���C�����G�l���M�[���������コ���邱�Ƃ��ł���B �]����莩�̋@�̏���d�͂�}���邽�߁A���̋@�Ƀs�[�N�J�b�g�@�\��q�[�g�|���v�@�\���̗p���A�܂��^��f�M�ނ�LED�Ɩ����g�p����ȂǁA���̋@�̏ȃG�l���M�[���ɓw�߁A2000�N�����r����Ɩ�75���̏ȃG�l���M�[�����������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�g�[���[�J�h�[�A�S���̓X�܂�LED�u������4���{��������d��4���팸 �I�v�e�B���b�h���C�e�B���O�́A�S���̃C�g�[���[�J�h�[��160�X�܂�LED�u������4���{��[�������Ɣ��\�����B����ɂ��Ɩ��̏���d�͂�40���ȏ�̍팸�������ށB�܂��A�Ɩ��d�͂̍팸�����łȂ��ALED�Ɩ��̕��M�ጸ�ɂ����ׂ̍팸�����҂����B ���Ђ��[�������͎̂�͐��i�̒��nj`LED�����v�B �C�g�[���[�J���͓d�C�����̒l�グ�ɂ��������Ή����A2012�N6�����瓌���d�͊NJ��n����͂��ߊe�G���A�̓X�܂֖{LED�Ɩ��ւ̐�ւ����J�n���A�S��181�X�܂̂�����160�X�܂ŁA��K�͂�LED�Ɩ��ւ̐�ւ��H�������{�����B �{���g�݂ɂ����āALED�Ɩ��ɋ��߂��@�\�́A�u�O�t���d���v�ƁA���d�͂��팸�ł���u�����Ή��v�������B ���nj`LED�����v�A�O�t���d�������̗̍p�ɂ��A�����v�̓����\�����V���v�������A�M��������v�Ɠd���̃g���u�����ŏ����ɗ}�����Ă���B����ɁA�M�������ŏ����ɗ}���A�l�X�ȕ��M��ō������ƒ������������B�܂��A�����������̗p���A���p���g���ɉ��������̑����ɂ��`����������Ȃ��r�����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����a�n�E�X���ȃG�l�����{�݂��J�������؎����� �Ȃǂ��ꌳ�Ǘ�����V�X�e���ŏȃG�l���������������{�݂��J�������Ɣ��\�����B���͌��s�̎{�݂Ŏ��؎������A���ʂ���������ŁA���Ђ̕����ɍ̗p����B �V�J�������V�X�e���ŁA��ƈ��̑̊����x���ς��Ȃ����x�ɋ��~�߂���A���C�̋������������߂����肷��B�ċG�ɂ͒n������₽����C����荞�݁A��[�ɗ��p����B����ɂ͑��z�����d�ݔ���݂��A�d�C�͓����d�͂ɔ���B�Ɩ��͑S�Ĕ����_�C�I�[�h�iLED�j�Ƃ����B��_���Y�f�iCO2�j�̔r�o�ʂ��]���Ɣ�ז�25���팸�ł���B���؎�������{�݂�5�K���Ăʼn����ʐς͖�10���������[�g���B �o�T�u�Y�o�j���[�X�v |
|
|
| ���I�t�B�X�̉Ă̐ߓd�͒蒅�X���A�k�Ќ�͖��N10���ȏ�̓d�͍팸 ���Ɨp�s���Y�̌����������s���U�C�}�b�N�X�s���Y�����������́A�I�t�B�X�̉Ă̐ߓd��͒蒅�X���ɂ���Ɣ��\�����B 2011�N�̉Ă���3�N�A���ŁA�I�t�B�X�e�i���g�d�͗ʁi�I�t�B�X�r���ɓ�������e�i���g��1�J���Ԃŏ����1������̓d�͗ʁj�͐k�БO���10���ȏ㌸�̐������ێ����Ă���B �����d�͊Ǔ��ɂ�����ċG�̃I�t�B�X�e�i���g�d�͗ʂ́A2010�N��50.3kWh/�A2011�N��42.0kWh/�i2010�N��16.5�����j�A2012�N��42.8kWh/�i2010�N��14.9�����j�A2013�N��43.8kWh/�i2010�N��12.9�����j�ƁA3�N�A���Ők�БO���10���ȏ㌸�̐������ێ����Ă���B���̂��Ƃ���ċG�̐ߓd���蒅�A�p�����Ă��邱�Ƃ�������B ������2010�N1���`2013�N9���i����1�x�j�Ɏ��{�B�U�C�}�b�N�X�O���[�v���^�c����S���̃I�t�B�X�r���ɓ��������ʎ������p�r�e�i���g�̂����A�L���ȃf�[�^������ꂽ�e�i���g�i��300���A��3000�Ёj���ΏہB�e�i���g���Ƃɖ����̓d�͗ʁikWh�j���W�v���A�y���j������������ʓI�ȉc�Ɠ����ŕ���āA1�ؓ�����̓d�͗ʁikWh/�j�����߁A�d�͉�ЊNJ��n��ʂɕ��ϒl�����߂�A�Ƃ����Z�o���@���̗p�����B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
| ���ؑ����H�@�����p�p�M�ė��p�̏ȃG�l�f�f�T�[�r�X���J�n ���w����i�A�H���Ȃǂ̍H��Ŕ���������C�̔M�������悭�ė��p����u�ȃG�l�ݔ��f�f�T�|�[�g�T�[�r�X�v���n�߂�B �|���Ă����G���W�j�A�����O�̃m�E�n�E�Ōڋq�H��̃v���Z�X��f�f�B�����p�p�M���q�[�g�|���v�ŏW�߂ă{�C�����������߂�œK�Ȏd�g�݂����邱�ƂȂǂŔR�������啝�Ɍ��点��B ���T�[�r�X�̓��[�U�[���H��Ŏg�����C�̗ʂ��팸�������p�p�M��L�����p����B 1���Ԃ�����20�g���̐������C�ɂ����ʓI�ȍH��̏ꍇ�A�q�[�g�|���v�����ʓI�ɔz�u�����1�䂠����ő�ŔN��2000���~���x�̔R����팸�ɂȂ�Ƃ����B���[�U�[�ɑ���A�M���p�̏��͂�p�M���p�ݔ��̔z�u�A�{�H��z�̂ق��A�ȃG�l�⏕���Ƃ̏������̐\���葱���Ȃǂ���s����B���[�X��ЂƘA�W���āA�����������ŏ��ɗ}���ē����ł���d�g�݂���Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������K�X�A�d�͔̔��Q���ցc�����莩�R���� �����K�X�́A�ǔ��V���̃C���^�r���[�ɉ����A2016�N�ɗ\�肳���d�͏�����̑S�ʎ��R���ɍ��킹�āA�ƒ�����̔̔��ɎQ��������j�𖾂炩�ɂ����B ���Ђ��c�Ɗ�Ղ�����s���ł̔̔���z�肵�Ă���B�K�X�ƊE�ő��̓d�͂ւ̖{�i�Q���ŁA����A�����l�������܂߂��T�[�r�X�������������������B �d�͂ƃK�X�̏���������K�͂Ȃ��q�l�ւ̑Ή����܂߂Ă���Ă������j�ŁA�ƒ�����ւ̎Q���ɋ����ӗ~�������Ă���B �����K�X�́A�����ł���d�͗ʂ𑝂₷���߁A�t���V�R�K�X�i�k�m�f�j�̎����n�����ݒ��̈�錧�����s�ɁA �K�X��R���Ƃ���Η͔��d���̐V�݂��������Ă���B���i�����͂����邽�߁A���d�R�X�g�̈����ΒY�Η͔��d���𑼎ЂƋ������݂������l�����B |
|
|
| �����Ȃ��d�͉�ЁE�d�C���Ǝ҂�CO2�r�o�W���i����24�N�x�j�����\ �n�����g����̐��i�Ɋւ���@���Ɋ�Â��u�������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�E���\���x�v�ɂ��A��_���Y�f���̉������ʃK�X�����ʈȏ�r�o���鎖�Ǝҁi����r�o�ҁj�́A���N�x�A�������ʃK�X�Z��r�o�ʁA�y�ы��s���J�j�Y���N���W�b�g�⍑���F�ؔr�o�팸�ʓ��f�����u�����㉷�����ʃK�X�r�o�ʁv�����Ə��Ǒ�b�ɕ��邱�Ƃ��`���t�����Ă���B ���̂����A���l���狟�����ꂽ�d�C�̎g�p�ɔ���CO2�r�o�ʂ̎Z��Ɋւ��A�������ʃK�X�Z��r�o�ʂ̎Z��ɂ����ẮA����r�o�҂̎��Ɗ����ɔ����������ʃK�X�̔r�o�ʂ́u���r�o�W���v�y�сu��֒l�v���A�܂��A�����㉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̎Z��ɂ����ẮA�u������r�o�W���v��p���邱�ƂƂ���A�����̔r�o�W���ɂ��Č��\���ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȎ��Ɨp���d�ɂ��d�C�𗣂ꂽ�H�ꓙ�ɑ��d����u���ȑ����v�w�j���\ ��Ƃ����Ɨp���d�ݔ���p���Ĕ��d�����d�C���A�d�͉�Ђ̑��z�d�l�b�g���[�N����ĕʂ̏ꏊ�ɂ���H�ꓙ�ɑ��d����u���ȑ����v�𗘗p���₷�����邽�߂ɁA���ȑ����Ɋւ���w�j���\�����B ����A���\���ꂽ���ȑ����Ɋւ��w�j�́A���ȑ����𗘗p���邱�Ƃ��ł���҂͈͓̔��m�����邱�Ƃɂ��A���ȑ������~���ɗ��p���邱�Ƃ��ł����������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���B�{�w�j�͕���26�N4��1������{�s�����B ����܂Ŏ��ȑ����́A����25�N2���Ɏ��܂Ƃ߂�ꂽ�d�̓V�X�e�����v���ψ�����ɂ����ẮA�u���ȑ����̐��x���́A�l�b�g���[�N���p�̌������m�ۂɎ�������̂ł���A�܂��A�����Ђ��������\�t�g�o���N���_���j���[�r�W�l�X�\ ������E�^�p��[���̎Y�Ɨp�d���`���ɂ��Ă̈��̊ɘa�[�u�̍l�����ȂǁA���ȑ����̋�̓I�Ȑ��x�v�ɂ��Ă̋c�_���s��ꂽ�B�o�ώY�ƏȂ́AWG�ɂ�����c�_�܂��Ė{�w�j���Ƃ�܂Ƃ߂��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȍH��r�M�̗��p�x�� �o�C�i���[���d�̓����������Ɍ����A�o��300kW�����̏��^�o�C�i���[�ɂ��ċZ�p�v���̑I�C��H���v�揑�̒�o�A��������Ȃǂ�Ə�����͈͂̊g�����������B �M���p�Z�p�ɂ��Ă킪�����D�ʐ���������̊֘A�Z�p�̕��y�̌㉟��������l���B�����헪�̃c�[���Ƃ��ĊC�O�W�J������ɍ����œ����𐄐i����B ���݁A100���ȉ��̏��C�Ŕ��d���鏬�^�o�C�i���[�͏��������{�C���E�^�[�r����C�Z�p�҂̑I�C�A�H���v��̓͏o�Ƃ������`����Ə����Ă���B �������A�H��ł͍L�����x��̔M���v������A�g������Ă��Ȃ��B���̂��߁A100���ȏ�̃o�C�i���[�̓������e�ՂɂȂ�悤150���`200�����x�ɉ��x����g�傷������Œ�������B ����܂Ŗ����p�������r�M��������A���d�Ȃǂɂ����p�ł���ݔ��̓������x������Ƃ��āA2014�N�x�\�Z�Ă�410���~��[�u�B2013�N�x��Ōv�サ��130���~�Ƃ��킹�A560���~�K�̗͂\�Z���m�ۂ���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���Đ��\�G�l���M�[�Z�p������啝�����\�e����̓����A�ۑ�A�Ή���L�\ NEDO�́A�Đ��\�G�l���M�[�̊e�Z�p����̍����O�̓�����ۑ�A�Ή����������܂Ƃ߂��uNEDO�Đ��\�G�l���M�[�Z�p�����v�̉����ł����J�����B ��������2010�N�ɑ��ł����\���ꂽ���A���̌�̏ω����܂����e���ŐV���ɍX�V�B����Ɋe�ۑ�ɑ���Z�p�A����A�l�X�Ȗʂ���̑Ή�������܂Ƃ߂��B�����̃|�C���g�́A �k1�l�䂪������芪���G�l���M�[��̕ω��܂��ŐV�̏��ɃA�b�v�f�[�g�����{��k�Ќ�̍Đ��\�G�l���M�[������c�_�̌o�܂����A���҂����܂����u�Đ��\�G�l���M�[�v�ɂ��āA�u�����̈Ӌ`�v�ƌ��ʂ�������Ă���B���̏�ŁA�e����̍Đ��\�G�l���M�[�Z�p�̉���ɗ��܂炸�A�䂪���̃G�l���M�[�����̑S�̑��y�ыߔN�̕ω����ŐV�̏��������ċL�ڂ����B �k2�l�Đ��\�G�l���M�[���y�������ۑ�ƍ���������f�� ���y�ɔ����Љ�R�X�g���c��ނƂ������O�A�n���ڑ��e�ʂ̐���A�J�����Ԃ̒������Ƃ�������ʓ����ɔ������݉����Ă����ۑ�ɂ��āA�Z�p�I�ۑ�ƁA �����̉ۑ���������邽�߂ɕK�v�ƂȂ��R�X�g����n���ϓ������̋�̓I�ȍ��������ԗ����Čf�ڂ�����B �k3�l�g���Ղ������㏉�ł���\�����������A���z�����d�╗�͔��d�̑��AFIT���x�̑ΏۂƂȂ����n�M���d�⒆�����͔��d���̎�v�ȋZ�p���얈�ɍ\����ύX�����B �܂��A���얈�Ɂu�Z�p�̊T�v�v�A�u�����|�e���V�����A�����ڕW�A�������сv�A�u�s�ꓮ���v�A�u�Z�p�J�������v�A�u����Ɍ������ۑ�ƍ�������v�����܂Ƃ߂��B�n���A�n�\�ʂ̐���ɑΉ����邽�߂ɕK�v�Ȏ�g�Ƃ��āA�u�n���T�|�[�g�Z�p�v��V���ɒlj������B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2014/1�@]�@�@�� |
|
|
| �������ɃX�}�[�g�I�t�B�X�ݐȏɍ��킹�ďƖ��E���������� MID�s�s�J���́A�Ɩ�����������䂷��V�X�e����LED�Ɩ��Ȃǂ������ꂽ�ȃG�l�r���u�V�E����MID�r���v��v(����)�����݂���BCO2�팸��46%�������ނق��A�����s�̏ȃG�l���M�[�]�������x�ōō������N�ɑ�����������\�����r���ƂȂ�B �ԊO���𗘗p�����u������l���m�Z���T�[�v�ŁA�l�̂̉��x�����m���č݁E�s�݂�c���B��������ƂɃI�t�B�X���̏Ɩ���A���C���������䂵�A���ʂ��Ȃ����B�]���^�̃Z���T�[�ł͍���������A���^�C���̍ݐȏ𐳊m�ɑ����邱�Ƃ��ł���B �܂��A�O�t���Ƃ��Ă͍������́u�A�j�h���b�N���[�o�[�v�Ȃǂ��̗p����B�]���^�̃��[�o�[�͕��ʂ⎞�ԑтɂ���č̌��ʂ��ϓ����Ă����B����́A���[�o�[�Ȗʂ̌��w�I�����𗘗p���邱�Ƃő��z���x�ɍ��E���ꂸ�A��l�Ȓ�����������邱�Ƃ��\�B����ɂ��A�����̐l�H�Ɩ��̌���������𑣂��B ���̂ق��A�Ɩ��͑S��LED�Ƃ���BBEMS�����̂ق��A�e�i���g�S�]�ƈ��̃p�\�R���ŃG�l���M�[������m�F�ł���悤�ɂ���B �����́A�n��12�K�E�n��1�K���ĂŁA�����ʐϖ�1��1800�������[�g���̃e�i���g�r���B �o�T�u�Z��V��v |
|
|
| ���|���H���X ���U���d�ɗ��p�̃��C�����X�Z���T�[�l�b�g���[�N�V�X�e�����J�� ���Ђ́A�l�̕��s��ݔ��@��Ȃǂɂ���Č������œ���I�ɔ������Ă�����U���̃G�l���M�[��d�͕ϊ����A�Z���T�[�d���Ƃ��Ċ��p���Č������̊����I�[�g���j�^�����O���郏�C�����X�Z���T�[�l�b�g���[�N�V�X�e�����J�������B �{�V�X�e���̗��p�@�̈��Ƃ��āA�_�N�g�̔��U���𗘗p�����I�t�B�X��Ԃ̉����x���j�^�����O���؎����ЋZ�p�������ōs���A���N�Ԃɂ킽���ēd�������^�̃V�X�e�����ғ����邱�Ƃ��m�F�����B ����́A�K�p���p�r�ɉ����ėl�X�ȃf�o�C�X���[�J�[�Ƃ̋Ɩ���g���������Ȃ���A�U�����d�𗘗p�����Z�p�E�V�X�e���̊g���ڎw���B �{�V�X�e���́A�U�����d�f�o�C�X�ƃ��C�����X�Z���T�[���W���[�����p�b�P�[�W�������A�d���E�d�r���s�v�ȐU�����d�Z���T�[�V�X�e�����B�~�c�~�d�@�̋��͂ɂ��A�J�������������B �U�����d�f�o�C�X�́A�������̐��U���u�Ƃ��čL���g���Ă���uTMD�iTuned Mass Damper�j�v�𗘗p���邱�ƂŁA�L�͈́i12�`41Hz�j�̐U���������悭�d�͕ϊ��ł���悤�ɂȂ��Ă���A�ݔ��@���_�N�g�ɂ��U���ł���A�ݒu�ꏊ�i�U�����j��I�Ԃ��ƂȂ��Z���T�[�d�����m�ۂ��邱�Ƃ��ł���B ���C�����X�Z���T�[���W���[���́A�����ȓd�͂������ǂ��g��������d�͌^�ŁA���x�Ǝ��x�̃Z���T�[�𓋍ڂ��Ă���A����Z���T�[�̎�ނ𑝂₵�Ă����\�肾�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���������̎��g�݁\�\�g�p�ςݑ��z�d�r��������čĎ��������� ���z�����d�V�X�e���Ӓ苦��́A�g�p�ς݂̑��z�d�r��������čĎ���������T�[�r�X��2014�N1���ɊJ�n����B ����2�`3�N�Ŕp���ʂ��}������Ɨ\���ł��邽�߁A�Љ���ɂȂ�O�ɖ��Ԃ̗͂ŃT�[�r�X���n�߂�B�W���I�Ȍˌ��Z��ɓ��ڂ��ꂽ���z�d�r���W���[���̉���ɂ́A�����_��10���~�ȏ��v���邪1��1200�~������B�Ď�������������Ɗ�ƂƋ��͊W��z�������ƂŎ����ɂȂ������B ���Ȃ͎g�p�ς݂̍Đ��\�G�l���M�[�ݔ��֘A�̃����[�X�A���T�C�N���ɂ��Ă̎��g�݂�i�߂Ă���A2012�N�x�ɂ́u�g�p�ύĐ��\�G�l���M�[�ݔ��̃����[�X�E���T�C�N����b�����ϑ��Ɩ����v�����J���Ă���B �������A�@�K���ɏ]���Ĕp������ƁA�����̒n��ő��z�d�r�͈�ʔp������Y�Ɣp�����ɕ��ނ���A������������Ă��܂��B���z�d�r�ɂ͎��o���\�ȗL�������܂܂�Ă��鑼�A�Â����i�𒆐S�ɉ��͂��܂܂�Ă���B���̂��߃T�[�r�X�ł͗L���������o���\�ł���A���͂����o���H�����܂܂�Ă���B �ƒ�p�̐��i�̓��[�J�[��^�Ԃ����ł���A�����[�X������B���K�\�[���[�ȂǑ�K�͂ȏꍇ�́A�ڎ������ɉ����āi�����C���s�[�_���X�̑��肪�\�ȁjTDR�iTime Domain Reflectometry�F���ԗ̈攽�ˁj�Z�p���g���B�ʓd���Ȃ��Ă����z�d�r���W���[���̓����𑪒�ł��邽�߁A��Ǝ��Ԃ��Z���A�����[�X�ɂȂ���₷���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����a�R���T��������50�Z���`�ł����d�ł��鏬���͔��d�ݔ����J�� ��B�H��Ƌ����Ŋ����̔_�Ɨp���H�ȂǂɁA��|����ȍH���Ȃ��Őݒu�ł��鏬���͔��d�ݔ����J�������B �x�m�{�s��1��ݒu�����B������1.2m�ōő�o�͂�1.4kW�B�J�������̂́u�����]�����v�ƌĂԎd�g�݁B���������鐨���𗘗p���āA���O�ɏd�Ȃ�2�̃��[�^�[���ɋt�����ɉ�]�����A���d����B�u�����]�����v�ł͋t��]��������ƊO���̃��[�^�[���݂��ɗ͂�ł����������A�O�̃R�C�����Œ肷��K�v���Ȃ��B�܂��A��]���x�͎����I�ɏ]��������2�{�ɂȂ�A���͔��d�ł͓���Ƃ���闎��1.5m�ȉ��ł����d�ł���B���i�͏o��1.5kW�̔��d�@�ƃp���[�R���f�B�V���i�[�̖{�̉��i�A�ݒu��p���܂߂Ė�500���~ �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ăG�l�d�͂̎��g���ϓ���~�d�r�Œ�����������A�V�X�e���̎d�l�����J GS���A�T�̃��`�E���C�I���d�r�V�X�e�����A��B�d�͂����ӕϓd���i���茧���s�j�ōs���A���؎����ݔ��ɍ̗p���ꂽ�B ���؎����́A�����̌n�����g���ϓ���~�d�r�ɂ��}������œK�����@������������̂ŁA���ݔ��͍��N��3�����ғ����Ă���A�����؎�����2014�N�܂ōs����\��ƂȂ��Ă���B ���`�E���C�I���d�r�V�X�e���́A���͂⑾�z���Ȃǎ��R�G�l���M�[����̔��d�ʂ��}�ς����ۂɁA�[���d���s�����Ƃɂ��A��������d�͗ʂ����肳���A���g���̕ϓ���}�����������S���B ����̗p���ꂽ���`�E���C�I���d�r�V�X�e���́A96���W���[�����[�����~�d�r��8���j�b�g�ō\������Ă���A����10���[�g���~���s��7���[�g���̒~�d�r���[����2���ɐݒu����Ă���B ���R�G�l���M�[�̈��苟���Ɋւ��āA���E���Ŏ��؎����⓱���ɑ��錟�����i�߂���Ȃ��A���`�E���C�I���d�r�͈��苟���Ɋւ��L�[�f�o�C�X�ƔF������Ă���A���Ђ́A����̎��R�G�l���M�[�̓����g��ɂ́A�����\�ň��S���ቿ�i�̃��`�E���C�I���d�r���s���ł���Əq�ׂĂ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���A�Y�r���A���C�̊����x�������肷��Z���T�[�J���|�{�C���̏ȃG�l��ɓ� ���E�̃Z���T�[�̊Ԃɏ��C�ƌ��߂����A�����x�����𑪒肷��B �{�C���ŏ��C�����ہA�z�ǂ��ڑ����̏��C���M��D���Ĉꕔ�����ɖ߂邱�Ƃ�����B���������C�̂ɉt�̂�����������Ԃ��g�����x�h�Ƃ��đ��肷��Z���T�[���J�������B�������C�Ɛ��ɓ��߂����A���̏�Ԃ̕ω�����Ɋ����x������o���B �Z���T�[�ɂ���ď��C�̃G�l���M�[�ω������A���^�C���Ɋώ@���邱�ƂŁA�ڑ����̏��C�̈ꕔ�����ɖ߂邱�Ƃɂ��G�l���M�[�̑����������鉻���A�ȃG�l����u������B���C�̃G�l���M�[�ω������A���^�C���Ɋώ@�ł��邽�߁A�ȃG�l�ɂȂ���B������Ќ����ł́A���̊����H���̕i�����艻�ɂ����p�ł���B �����x�𑪒肷���@�ł́A���C��c�������đO��̉��x�ƈ��͂��r�����@�����������A���C�̏�Ԃ�ς��Ă��܂��A����Ɏ��Ԃ�������Ȃǂ̌��_���������B���𑪒��i�ɗp���邱�Ƃɂ��A���������������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���������ǂ̔M�ŋ������s�A���{���̎��؎��� �}���z�[���̉��ɂ��鉺�����ǂ���M���������o���A���̔M�ʼn�Ђ�ƒ�Ŏg�����������B ����ȐV�����Đ��\�G�l���M�[�̗��p�@�����s�Ŏ������悤�Ƃ��Ă���B�s�Ɛϐ����w�H�Ƃ͎��؎������J�n�B�����{��k�Ќ�̔�Вn�̐V���ȃG�l���M�[���Ƃ��Ă̊��p�����҂����B �k�Ќ�̍��y��ʏȂ̑�ψ���ŁA�������ǂɐV���ȉ��l��t������\�z���o��B�����E�ϐk�H���̍ۂɁA�������̔M���G�l���M�[�Ƃ��ė��p�ł���d�g�݂����t���邱�Ƃ�����A���̕⏕���Ɛϐ����w�H�Ƃ̋Z�p�x�����Đ��s�����؎����ɓ��ݐ����B �����͕��C�̎c�蓒��������A�O�C�ɂ��炳��Ȃ����Ƃ���A�~�ł���15�`20�x��ۂB�s�ɂ��ƁA���l�̎��g�݂͈ȑO���璍�ڂ���A����������œ������ꂽ��͂��邪�A�s�X�n�̉������ǂ𗘗p����̂͏��߂āB����̌����ŃR�X�g�ʂ◧�n�����Ȃǂ̉ۑ���N���A����A���ԗ��p���\�Ƃ����B ���؎����͑�^�X�[�p�[�Ŏ��{����Ă���B�߂��𑖂�S��45���[�g���A���a��1�E2���[�g���̉������ǂ̓����ɁA�ϐk�H���̂��߂点���ɕ⋭���ނ������t����ہA���ނ̒��Ɂu�M����ǁv��ʂ����B���̊ǂɕs���t���z�����ĉ����ʼnt�����߂���A���̔M���q�[�g�|���v�ɑ����ď㐅���̐������߂�d�g�݂��B�s�ɂ��ƁA�X�̒�����ȂǂłP���Ɏg�p����4600���b�g���̂������\���܂��Ȃ��Ă���Ƃ����A�K�X�ɂ�鋋���Ɣ�ׂ�25���̓�_���Y�f�팸�A78�����̔�p�ߖ�ƂȂ�B�s�͎��،����ł̌��ʎ���Łu��ƂȂǂɂ�铱��������ɓ���A�V���ȍĐ��\�G�l���M�[����Ƃ��Ďs�ɕ��y�����Ă��������v�Ƃ��Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���u�F�����z�����d�v���傪��K�͎{�݂Ŏ��� �F����Ԃɕ����ׂ����z���p�l���Ŕ��d���A�n��ɑ��d����u�F�����z�����d�v�̎��p���Ɏ��g��ł���B�p�l���̔��^����F����Ԃł̑g�ݗ��Ď�@�̊J���ȂǕK�v�ȗv�f�Z�p�͑���ɂ킽��B��Z�p�̖������d�Z�p�Ɋւ��ē������o�Ă����B �u�F�����z�����d�v�̓���1�����3��6000km�ɂ��鑾�z���p�l���Ŕ��������d�C��n��ɑ��d����u�������d�v�̋Z�p���B����͓d�q�����W�ɂ��g���}�C�N���g�������������B�_�������Ă��}�C�N���g�͌������Ȃ��̂ŁA�V��ɊW�Ȃ��d�C�����闘�_������B ���p���Ɍ����āA���E�ő�K�͂ƂȂ���؎����{�݂�10���~�ォ���ĉF���L�����p�X�ɐ��������BJAXA���ł��グ���������P�b�g���g���A�n��Ƀ}�C�N���g�𑗂�����ɂ��������Ă���B 14�N�ɂ́A5.8�M�K�w���c�ŋ��x��1.6kW�̃}�C�N���g���o���A50m��̃A���e�i�Ŏ�M��������ɂ����g�ށB �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��COP19���A�V�g�g�ݍ��։ۑ肪�R�� �|�[�����h�̃����V������11������J����Ă������A�̋C��ϓ��g�g�ݏ��̑�19�����c(COP19)��23���A�������B ����́A2020�N�ȍ~�̎����g�g�݂̓y����Ƃ������Ƃ�����A�N���[�W���O�E�v���X�E�����[�X�́u2015�N�Ƀp���ŊJ�����COP21�ōŏI���ӂ����V���ȍ��ӂɌ����č�Ƃ̓����t�����v�Ƃ������̂́ACO2�팸�Ɍ������傫�Ȑ��ʂ͂Ȃ������B �C��ϓ��ɑ�����g�݂́A���̐��N�̐��E�I�Ȍi�C��ނ̒��Œ���Ă����B2012�N�ɑ�1��(�R�~�b�g�����g)���Ԃ��I���������s�c�菑(1997�N�̑�)�ȍ~�̘g�g�݂͌��܂炸�A��N��COP18�h�[�n���ӂŋ��s�c�菑��2020�N�܂ł��2���ԂƂ��ĉ������ꂽ���A����������{���E���B�팸�`�������͉��B�𒆐S�ɐ��E�̔r�o�ʂ̂킸��15���ɂƂǂ܂��Ă���B 2020�N�ȍ~�̘g�g�݂́A�r�㍑���܂߂����ׂĂ̍����������ʃK�X�팸�̎���I�ȖڕW���߁A���̖ڕW���Ó��Ȃ��̂��A���O�҂��]������d�g�݂ɂȂ�B �V�g�g�ݍ��ӂɌ����ẮA���ׂĂ̍�������I�ɖڕW�E�v������߂�K�v������B�����1�������������ɁA�悤�₭�܂Ƃ܂������ӕ����́A�ڕW�̂�������o����������A�����܂������c�����B ���{�́ACOP19�ŁA�Ό��L�W�������A����������2020�N��2005�N��3.8���팸�Ƃ����V�ڕW�\�����B1990�N��Ŋ��Z�����3�����Ƃ�������f�����V�ڕW�ɑ��A���E����͎��]�������������o���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2013/12�@]�@�@�� |
|
|
| ���d�͊Ǘ��̃I�����C���w�K�v���O�����uEnergy University�v�����{��� �V���i�C�_�[�G���N�g���b�N�́A�N�ł��ǂ�����ł���u�\�ȁA�����̃G�l���M�[��������уG�l���M�[�}�l�W�����g�Ɋւ���I�����C���w�K�v���O�����uEnergy University�v�̓��{��Ή��ł��J�݂����B �uEnergy University�v��2009�N�ɊJ�݂���A���݁A�S���E��35���l�ȏオ���p����B�G�l���M�[�����̉��P��R�X�g�팸�Ȃ�200�ȏ�̐��v���O������ʂ��āA�x���_�[�Ɉˑ����Ȃ�����c�[���ƃg���[�j���O����Ă���B�܂��uEnergy University�v��10�ȏ�̐��@�ւƒ�g���A���i���̔F�萧�x�Ƃ������Љ�l����ɂ�����P�ʕt�^�ɂ����p����Ă���B ���{�����̌ڋq��ΏۂƂ������{��Ή��łł́A�uEnergy University�v�̃R�[�X�̒��ł��ł��l�C�̍����G�l���M�[�č��A�f�}���h���X�|���X�A�O���[���r���f�B���O�Ȃǂ��e�[�}�Ƃ����R�[�X�𒆐S�ɁA���W���[�����̂���{��ɂ����B���S�҂�����Ƃ܂ŒN�ł���u�ł���悤�A�f���≹�������p���Ă���B �uEnergy University�v�́A�G�l���M�[�Ǘ��Ɋւ���ӎv����A�Ǘ��A�v�����j���O�A�v�A���݂Ɋւ�邷�ׂĂ̐l���T�|�[�g����B�I�����C���Ŗ�������邽�߁A���ԁA�ꏊ�A�\�Z�̐�������Ɋw�K���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v http://www.schneider-electric.co.jp/sites/japan/jp/products-services/training/energy-university/energy-university.page |
|
|
| ���Q�[�����o�ŏȃG�l���������A�H�ƒc�n�Ń��j�[�N���� �������쏊�������D�y�s�̌���ɂ��H�ƒc�n�̏ȃG�l���M�[���f�����Ƃ̃V�X�e���̉^�p���n�܂�B�������35�Ђ̃G�l���M�[�g�p�ʂ��������������ŁA�ȃG�l�Ɍ����āu�撣��d�g�݁v�����ꂱ��ƍH�v�������j�[�N�Ȏ��g�݂��B ���Ƃ̑Ώۂ͖k�C���d�͂��狤����d���Ă���u�����n���Q�H�ƒc�n�v�B�����H�����A�������i�����̒�����Ƃ��������Ă���B �����̃N���E�h�V�X�e�������p���A�e�Ђ������g�p����d�͎g�p�ʂ���������B35�Ђ̂���3�Ђɓd�͗ʂ��v������Z���T�[��ݒu�B���A���^�C���œd�͂̎g�p�ʂ��v�Z���A�\���ł���d�g�݂𐮂����B���̂ق���32�Ђ��ʏ�̗����v�Z�p�̌��j���ʂ��ē������������W���A�����̓d�͎g�p�ʂ��܂Ƃ߂Ē���B �c�n����Ƃւ̏ȃG�l�x���g�p�ʂ̔c����ڕW�ݒ���x���A���`�[���ɂ��ȃG�l�T�|�[�g���s���B���̂����œ�����Ƃ����̘A�g�������Ȃ���ȃG�l�ւ̈ӎ������߂鑽���̍H�v���Â炵�Ă���B�u�X�}�[�g�ȃG�l�}���\���v�Ɩ��ł��A�e�Ђ����߂��ȃG�l�̖ڕW�ɉ������B�����̏�ʎЂ̏��ʂ��Q�Ƃł���d�g�݂��\�z�����B �ȃG�l�ɂ��_��d�͗ʂ������A���̕����C���Z���e�B�u�Ƃ��ĕ��z����d�g�݂����N�ȍ~�Ɏ��������j���B�B�����̏�ʎЂɎx������ق��A���A���^�C���\���̂��߂̌v���������Ă��Ȃ�32�Ђ��V���ɐݒu�����p��⏕����Ă����サ�Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���f���\�[���^�r�M���p��[�V�X�e�����J�� ���̏����𗘗p���╗������u�z�����Ⓚ�@�v�ő��Ґ��i��3����2�ɏ��^�������B �ݒu��p��3����1�ɗ}�����B��ʓI�ȋǏ���[�@�ɔ����d�͂�8�����Ȃ��A�u��������ꍇ�͖�3�N���œ�������ł���B �z�����Ⓚ�@�͐��Ȃǂ̗�}����������ۂɁA���͂̔M��D���C���M�̌����𗘗p����B ���Ђ͋z���ނɌ����I�ɔM��`����u�}�C�N���t�B���\���v���J�������B�]���͔M��`��������̊Ԋu��1mm���x�܂ł����ׂ����ł��Ȃ��āA��[�\�͂��m�ۂ��邽�߂ɂ͑��u���^�ɂ���K�v���������B �[�I���C�g�n�z���ނƁA�z���ނɔM��`���铺���Ƃ������ďĂ��ł߂�B����ɂ��A1�Ӑ��\�}�C�N�����x�̋z���ނ̗����ׂ��������̃J�S����ݍ��݁A�M���`���₷���Ȃ�B2017�N�ɗʎY�����v��B���i��100���~���x��z��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����d�A�X�}�[�g���[�^�[�ݒu���Ԃ��R�N�O�|�������R�Q�N�x�܂łɊ����� �d�͎g�p�ʂ�30�����Ƃɔc���ł��鎟����d�͌v�i�X�}�[�g���[�^�[�j�̐ݒu���v�悩��3�N�O�|�����āA����32�N�x�܂łɊǓ��S�̂Ŗ�2700����̐ݒu������������Ɣ��\�����B ���킹�ē����A�ƒ�p�G�l���M�[�f�[�^��͂��肪����ăx���`���[�A�I�[�p���[�i�o�[�W�j�A�B�j�ƋƖ���g���邱�ƂŊ�{���ӂ����B �X�}�[�g���[�^�[�œ����f�[�^�����p���Đߓd�����������V�T�[�r�X��26�N7������J�n����B ���d�͕���26�N�x����X�}�[�g���[�^�[�̐ݒu��{�i��������v��B���N�x��190�����ݒu����B�V���Ȍv��ł́A28�`30�N�x��3�N �ԂɔN570���䂸�ݒu����Ȃǂ��āA���Ԃ�Z�k����B �I�[�p���[�͕č��Ȃ�8�J���ŁA��90�̓d�͎��Ǝ҂ƌ_�A2�疜���шȏ�̉ƒ�p�G�l���M�[�f�[�^���Ǘ��B�Ɩ���g�ɂ��A�Ƃ� �Ԏ���l�������ʂ����ƒ��ߗא��тƗ������ׁA�ߓd���œK�̗����v�������Ă���T�[�r�X���\�ƂȂ�B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �����{�Ɏq3���d�˃K���X�ŋR�X�g6���� �K���X��3���d�ˁA�ՔM���\����������A�M��`���ɂ����A���S���K�X���Ԃɕ��������B�]���i�Ƃ͖��̑g����ς���Ȃǂ��Đ��\�����߂��B �f�M���\�������w�W�u�M�җ����v�͕ǂȂǂ̒f�M�ނƂ��Ďg����O���X�E�[��5cm�̌����ɑ�������Ƃ����B���ɓ~��Ɏ����̉��x��ۂ��\�������Ƃ����B �ݔ���Ȃǂ��������K���X�̕W�����i��1m2������5��3500�~�B���̏ȃG�l�K���X�Ƃقړ������i�ɗ}�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��1��8000�l�̒����V�d�͂�ݗ��A�Đ��\�G�l���M�[�ŏ������� ���V��6���ɒ��c��̌��c���āu�Đ��\�G�l���M�[�̂܂����V���v��錾�����B ���̐錾�ɉ����ĐV�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj�́u��ʍ��c�@�l���V��d�́v��ݗ����āA10��2������d�͂̏������Ƃ��J�n�����B���ʂ͒�����⏬���w�Z�Ȃǂ̌����{�݂�Ώۂɓd�͂�����������j���B �d�͌��Ƃ��Ē�����3�J���Ƀ��K�\�[���[�����݂���ق��A�����͔��d��o�C�I�}�X���d�ɂ����g�݁A�Đ��\�G�l���M�[�̒n�Y�n���𐄐i����B �̔�����d�͂͒����Ŕ��d����B���ł�3�J���Ń��K�\�[���[�̌��݂�i�߂Ă��āA�������2013�N�x���ɉ^�]���J�n����\��ɂȂ��Ă���B3�J�������v����Ɣ��d�\�͂�5MW�i���K���b�g�j�ɂȂ�A��ʉƒ�Ŗ�1500���ѕ��̓d�͂��������邱�Ƃ��ł���B ���̂ق��ɂ��_�Ɨp���H�𗘗p���������͔��d���������ŁA2014�N�x�ɍH�����J�n����v�悾�B����ɒ�����86�����߂�X�т���o��Ԕ��ނ����p���āA�o�C�I�}�X���d�Ɏ��g�ނ��Ƃ��������Ă���B���V�ɂ͑S���I�ɗL���Ȏl���i���܁j������A�n�M���d�̉\�����傢�ɂ���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����H�ցA���z�d�r�ݒu���\�ɁA����őS�����̎��g�� ���ꌧ�͗L���C���ݓ��H�𗘗p�������z�����d�̎��Ǝ҂��W����B���̑_����2013�N4��1���Ɉꕔ�������ꂽ���H�@�{�s�߂������������p���āA���z�����d�̕��y�ɂȂ��邱�Ƃ��B�s���{���̊Ǘ����铹�H�ŁA���z�d�r��ݒu���锭�d���Ǝ҂����傷��͍̂��S�������Ƃ����B ���H�ɂ͓d���̂悤�ɖ{���̌�ʂƂ͖��W�ȍ\���������Ă��Ă���B���H�@�{�s�߂̉����ɂ��A�V���ɖ��Ԏ��Ǝ҂̑��z�d�r��ݒu�ł���悤�ɂȂ����B ��W����͖̂�2.0km�̋�ԁB���̋�Ԃ͎��͂̓y�n���������ʒu�𑖂��Ă���A���H�Ǝ��͂̊Ԃ����ԎΖʂł���u�̂�ʁv�������Ă���B�̂�ʂ̖ʐς͖�1��m2����A���̎��Z�ɂ��Ζ�1MW�̑��z�d�r���W���[����ݒu�\���B ��W�����́A�̂�ʂ͌����p�n�������A�������L����y�n�����A��p���i�n��j�͕s�v���B����A��p���̒P�����肪�������ꍇ���������������ɂ�����j�Ő�p���ȊO�ɂ����ւ̎x�����`���͂Ȃ��A���d�ʂ̃��j�^�[�`���Ȃǂ��t���Ă��Ȃ��B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����ёg�Ƃm�d�b�A�r�b�O�f�[�^���͋Z�p�����p���ăr���̃G�l���M�[���v��\��������؎��������{ ���Ђ̋Z�p�E�m�E�n�E��g�ݍ��킹�āA�r���̃G�l���M�[���v��\�����邽�߂̃f�[�^���͕��@�������Ō������A�{���������{�����B �����ł́A��ёg�̋Z�p�������ɂ�����A�ߋ�2�N�Ԃ̓d�͎g�p�ʁA�ɗp�����M�ʁi�����M��/�␅�M�ʁj�A�C�ہA�c�Ɠ��A���t�A�ݐЎҐ��Ȃǂ̊e��f�[�^����ɁA�����̓d�͎g�p�ʂ���єM�ʂ�\�������B���͂ɂ����ẮA�r�b�O�f�[�^�ɍ��݂��鑽���̋K�����������Ŕ�������ANEC�́u�َ퍬���w�K�Z�p�v�����p�����B �����̌��ʁA���W�����c��ȃf�[�^����u�~���c�Ɠ��̒��ԁv�A�u��ԁv�A�u�Փ��v�ȂǂňقȂ�K�����������I�ɔ������A24���Ԍ��1������Ȃǂ̓d�͎g�p�ʁE�M�ʂ��A�l��ɂ�镡�G�ȃf�[�^������Ƃ��s�����ƂȂ��\���ł����B ���̌��ʂ܂���ёg�́A2014�N11���̓�����\�肵�Ă���Z�p���������̂��ׂẴr����Ώۂɂ����G�l���M�[�X�}�[�g���v���W�F�N�g�ɂ����āA�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���̍\���v�f�̈�Ƃ��āA�َ퍬���w�K�Z�p�����p�����m�d�b�̃G�l���M�[���v�\���V�X�e�����̗p����\�肾�B �܂��A�m�d�b�́A�َ퍬���w�K�Z�p�����p�����ڋq�Ƃ̎��؎�����i�߂�ƂƂ��ɁA���Z�p��p�����G�l���M�[���v�\���\�����[�V�����̃��j���[����\�肵�Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���v���C�X�E�H�[�^�[�n�E�X�N�[�p�[�X���{�Łu�d�̓V�X�e�����v�x�����v�V�ݓd�͎Q����Ƃ��x�� ���x�����́A�d�͏����̎��R���E�����d�����ȂǓd�̓V�X�e�����v�̓����ɑΉ�����d�͉�Ђ�A�d�͎s��V�K�Q�����v�悷���Ƃɑ��A�헪�����x�ύX�Ή��Ȃǂ̗̈�ő����I�ȃR���T���e�B���O�T�[�r�X�����B ��40���̑̐��ŃX�^�[�g���邪�A����3�N�Ԃ�3�{�̐l�������v��B�����3�N�Ԃ�15���~��ڎw���B �d�̓V�X�e�����v���Y�ƊE�ɗ^����e���͐��삪�L���A��ƂɕK�v�Ƃ������m��������ɂ킽��B����V�݂���铯�x�����́A�p���𒆐S�ɐ��E50�J���ȏ��20�N�ȏ�ɂ킽���ēd�͎��R�����x�����Ă���PwC�iPricewaterhouseCoopers�j�O���[�o���̓d�͉�ЁA�V�K�Q����ЁA�K�����ǂȂǂւ̃T�[�r�X�o�������p����B �����{��k�Јȍ~�A�d�͎����̕N���Ɠd�C�����̍����ɒ��ʂ������{�̓d�͎s��́A����A��ʓd�C���Ǝ҂̐�����ё̐��ƒn��Ɛ���������A�����s��̊m���Ɍ������{�i�I�ȓd�̓V�X�e�����v���n������B�d�͋ƊE�͂��܂��܂ȋƊE����̐V�K�Q���𑣂��A�K���� �s�ꋣ���̊m����ڎw�����\���ϊv�̎������}����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2013/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���u�V�d�́v�A100�ЎQ���S�ʎ��R���ɂ�ݑ������� ��Ƃ⎩���̂ȂǑ�����p�҂ɓd�C�������肷��u�V�d�́v���A100�ЂɒB�����B �����d�͕�����1�������̂̌�A�����̓d�͉�Ђ��������Œl�グ�������߁A�����������ȐV�d�͂ւ̒��ڂ����܂������Ƃ��w�i�ɂ���B2016�N�ɗ\�肳��鏬����̑S�ʎ��R�����ɂ�݁A���l�ȋƎ킩��̎Q���͍���������������B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���R�X�g40���팸YKK AP�̃r����p���� ���Ⴂ��2�����A3�����A4�����AFIX����g�����A�l�X�ȑ��ւ̎��t�����\�B��t�H���́A���ݑ��̎������Ɍ�t�����邾���Ŋ����B �u���Ⴂ���v��9��12���AFIX����11���ɔ����\��B���Ⴂ���i2�����j�̉��i��3��6,200�~�B �Z��G�R�|�C���g��k�Јȍ~�̏ȃG�l�ӎ��̍��܂肩��A�ؑ��ˌ��Z��̑����ɓ������ݒu�����悤�ɂȂ����B��d�����ɂ���ċݔ��̔N�ԓd�C�g�p�ʂ��ő��40���팸���鍂���f�M���ƏȃG�l���ʁA���O�̑������ő�35dB�ጸ����Չ����\�̌�������������̂������B���Ђ́A�I�t�B�X�r�����ɒ��a����A���~���ނ��̗p�����r����p�̃G�R�����ɂ��A�Z���z���ɂ������ӏ����Ɖ��K�ȋ�Ԃ����������y�ȏȃG�l�������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ����C�҂����Ȃ��Ă��N���E�h�A�g�ŏ��K�̓r���̃G�l���M�[���Ǘ��A���P�ł��� �u�r���Ǘ��V�X�e���������̂͂悢���A����ꂽ�f�[�^���ǂ����p���Ă�����������Ȃ��v�u�����̂ւ̏ȃG�l���Ɩ�����������v�\�\ �ꕔ�̑�K�͂Ȍ����������A�r���Ǘ��ɐ�C�̃I�y���[�^���t���P�[�X�͂܂�ł���A���������Y�݂������{�݂͏��Ȃ��Ȃ��B�����ŁA�W�����\���R���g���[���Y�́A�a�@��w�Z�A���K�̓I�t�B�X�Ȃnj����ɁA�r���Ǘ��V�X�e���ƃN���E�h�^�̃T�|�[�g�T�[�r�X��A�g�������V�����\�����[�V���������B ���V�X�e���́A�Ď��Ώۂ̌�������擾�����d�͂≷�x�A���x�A�ݔ��^�]�A�x��Ȃǂ̃f�[�^���A�ڋq�T�C�g�����łȂ��A�����I�ȃf�[�^�Ƃ��ē��Б��T�[�o�ɒ~�ς��邱�Ƃ��ł���B�~�ς����f�[�^�̓C���^�[�l�b�g�𗘗p���A�O���t�Ȃǂ̕�����₷���`�ŁA�ڋq��p�̃R�~���j�e�B�T�C�g��ʂ��ĒB�ڋq�̓|�[�^���Ƀ��O�C������A�G�l���M�[�g�p�ʂ��m�F�ł��A�������s�����G�l���M�[���|�[�g��𗧂Ă邱�Ƃ��ł���B �V�X�e���̔����i�i�G���W�j�A�����O�H����ʁj��100���~����B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| ���C�[�E�R�����Y50kW�̑��z���V�X�e����980���~�AkW�P����20���~��� �@�ރZ�b�g�ꎮ�ɂ͕K�v�ȋ@�ނ��S�Ċ܂܂�Ă���B���z�d�r���W���[���ƒ����𗬕ϊ��ɕK�v�ȃp���[�R���f�B�V���i�[�A���z�d�r���W���[����ݒu����ˑ�Ȃǂ��B ���Ђ̐��i�̓����͉ˑ���ڋq�̗v�]�ɉ����Đv���邱�Ƃ��B���@����܂�����{���j�b�g��g�ݍ��킹��̂ł͂Ȃ��A�y�n�̌`���N���A���z�d�r���W���[���̊p�x�Ȃǂ��ڋq�̗v�]�ɉ����čœK�Ȍ`�ɐv�A�[���ł���B�Ȃ��A�Z�b�g�ꎮ�̉��i�ɂ͍H����p�͊܂܂�Ă��Ȃ��B �n���t�@Q�Z���Y�W���p���̎Y�Ɨp������Si�i�V���R���j���z�d�r���W���[���i�o��250W�j��200���p����B���˖h�~�R�[�e�B���O���{����Ă���A�ϊ����������サ�����A�ݒu�ꏊ���ӂł̔��ˌ��̉e����}�����B�p���[�R���f�B�V���i�[�Ƃ��ăI����������9��p����B�X�C�b�`���O�m�C�Y��}�������߁A���X�L�[�g�������Ȃ��@�킾�B�O���t�@���𗘗p���Ȃ����R���v�ł��邽�߁A�������x����29dB�ƒႢ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���I���b�N�X�A�č��̏ȃG�l�T�[�r�X��Ђ��A�W�A�ł̎��Ƃ����� �擾����Enovity�Ђ́A2002�N�̐ݗ��ŁA�č��J���t�H���j�A�B�𒆐S�Ɍ����̃G�l���M�[�}�l�W�����g�T�[�r�X����|����B�J���t�H���j�A�B�ɂ����āA�������{�݁A��K�͂ȃI�t�B�X�r���⏤�Ǝ{�݂Ȃǂ̓d�́E�K�X��Ђ̑���ڋq��ΏۂɁA�����̏ȃG�l���M�[�v����G�l���M�[�g�p�̎����Ǘ��V�X�e���̓����A�ݔ��̈ێ��Ǘ��܂ŁA������含�����ƂɌ����̃��C�t�T�C�N���S�Ăɂ�����G�l���M�[�R�X�g�̍œK����}��T�[�r�X����Ă���B �I���b�N�X�́A���{�����ɂ����āA���z���A�n�M�A�؎��o�C�I�}�X�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�ɂ�锭�d���Ƃ�d�͏������ƁAESCO�Ȃǂ̏ȃG�l���M�[�T�[�r�X�ȂǁA���L���̈�ŃG�l���M�[�֘A���Ƃ�W�J���Ă���B �C�O�ɂ����ẮA2013�N6���Ƀt�B���s���̃G�l���M�[���Ɖ��Global Business Power Corporation�Ɏ��{�Q������ȂǁA����o�ϐ����ɔ����������v�������܂��A�W�A�ɂ����Ă��A�G�l���M�[�֘A���Ƃ̊g����v�悵�Ă���B ���Ђ́A����̃A�W�A�ɂ�����ȃG�l�s��ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɐ������Ă���B�����A�č����͂��߃O���[�o���Ɏ��Ƃ�W�J���鑽���Њ�Ƃ𒆐S�ɁA�����I�ȃG�l���M�[���i�̏㏸�ւ̔���������ׂ̒ጸ��ړI�Ƃ��Ď��Ɗ����ɂ�����G�l���M�[����ʂ�CO2�r�o�ʂ̍팸�ڕW�����肷���Ƃ������Ă���B ����A�A�W�A�Ȃǂ̐��Y�E���Ƌ��_�ł����̑���ɐi�ނ��̂ƍl������B�܂��A�A�W�A�ł́A2015�N�܂ł�GDP������̃G�l���M�[����ʂ�2010�N���16���팸����Ƃ������ƃ��x���̖ڕW���f���Ă��钆����A��K�̓r�������ɏȃG�l���z�F�̎擾���`���t���Ă���V���K�|�[���A�o�ϔ��W�Ȃǂɔ����d�͎��v�̐L�т��\�z�����t�B���s���Ȃǂɂ����āA�ȃG�l���M�[�Ɋւ���}�[�P�b�g�̊g�傪�����܂�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����e�N�A�����r����25���ȏ�ȃG�l�A�⏕���\�����x������ZEB���T�[�r�X��� �G���W�j�A�����O���Ђ̓��e�N�́A�����r���f�B���O�i�����ʐ�1���������[�g�������j��ΏۂɁA�]���̃G�l���M�[����ʂ�25���ȏ�팸����ZEB�i�[���E�G�l���M�[�E�r���j���\�����[�V�����T�[�r�X�̒��J�n�����B ����J�n����T�[�r�X�́A�O���[�v4�ЂƂƂ��ɁA�⏕���\������i�K�̃R���T���e�[�V��������H�������A�{�H�A�����āA�H���̉^�c�Ɏ���܂ŁA���ߍׂ����Ή�����B����ɁA�]���Ɣ�ׂăG�l���M�[����ʂ�25���ȏ�팸�ł���\�����[�V�����Ƃ��Ē���B �ȃG�l�Ɍ��������g�݂ł́A�V�X�e���Ԃ́u�A�g����v���L�[���[�h�ɂ����Ă���B��̓I�ɂ�BEMS�ɂ�鐧��ƂƂ��ɁA�u�Ɩ��ƘA���������v��u�Z�L�����e�B�V�X�e���ƘA���������v�i�Z�L�����e�B�V�X�e���ɂ��l�̑ޏo����n���p���̏ȃG�l��������Ɍ���j���āB�܂��A�ݔ����C�A���R�G�l���M�[�̊��p���A�œK�Ȑ��i�E�Z�p��g�ݍ��킹���u�A�g����v�ɂ��ȃG�l����������B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����ȗ��N�x����d�q���i�̏ȃG�l���x�� �T�Z�v����6���~�v�サ���B�x���ΏۂƂȂ��w��[�J�[�v������j�ŁA�ڍׂ͍���l�߂�B �Ɩ��E�̂ق��T�[�o�[�A���̓��[�^�[�A�p���[�R���f�B�V���i�[���͂��߂Ƃ����@��Ɏg������i�̃G�l���M�[���������߂�B�e�@�킲�Ƃɕ��i�̌�����3�N�Ԃłǂ��܂ň����グ���邩��̓I�ȖڕW��ݒ肵�A�����Ɏs����ł���悤�J�������Ȃ����B ���P�ʓ�����̎g�p�G�l���M�[�̍������ł���ȃG�l�͍L�����Ă��邪�A����̓G�l���M�[����̐�Ηʂ��팸����u���G�l�v���K�v�Ƃ̗��ꂾ�B���s�̋Z�p���x�[�X�Ƃ����Љ���l����̂ł͂Ȃ��A�����̃G�l���M�[�̐�����l�����A�d�v�ȋZ�p�v�V�𑣐i����l�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������r���A�ȃG�l�i�܂��B���P�]�n�傫�� �����Ȃ̖@�l���������i2008�N�x�j�ɂ��ƁA�@�l���ۗL���錚���̂����A�ؑ����������Ɩ��p�̌�����63��3000���B����9�������q���ʐ�1���������[�g�������̒����r�����B ���{�r���a���O������N�A�������̋@������Ă���䗦�ׂ��B����ɂ��ƁA�����ʐ�2��5�畽�����[�g���ȏ�̑�^�r����44.6%�������̂ɑ��A���������[�g�������̒����r���ł�33.4%�ɂƂǂ܂�B �����r���̏ȃG�l���i��ł��Ȃ��w�i�ɂ́A��Ɩ��Ŏg���d�C��͈�ʂɃe�i���g���S�ŁA�r���̎����傪�ȃG�l�@������铮�@�ɖR�������Ƃ���������B�ȃG�l�Z�p�̓������ƒ��������グ����A�e�i���g���������߂��肷��ޗ��ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ��傫���B �������������āA���Ȃ�14�N�x�̊T�Z�v���ɒ����r���̏ȃG�l���C�̉��l��]�����邽�߂̎��ƂƂ���8��5�疜�~�荞�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��2010�N�x����r�o�҂�CO2�r�o�ʁA�O�N��5,000���g������6��6,400���g�� ���x�J�n��5��ڂƂȂ�2010�N�x�̉������ʃK�X�r�o�ʂɂ��āA����r�o�҂���̂������������ʃK�X�Z��r�o�ʁi�ȉ��u�Z��r�o�ʁv�j�����ƎҕʁA�Ǝ�ʋy�ѓs���{���ʂɏW�v���A���܂Ƃ߂܂����B ���s�������Ǝҁi���Ə��j���́A���莖�Ə��r�o�҂�11,034���Ǝҁi���莖�Ə��F12,846���Ə��j�A����A���r�o�҂�1,399���ƎҁB�������ʃK�X�̔r�o�ʂ́A���莖�Ə��r�o�҂�6��3,226��tCO2�A����A���r�o�҂�3,239��tCO2�ŁA���v�l��6��6,464tCO2�i����21�N�x��5,044��tCO2���j�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��IPCC���č����I���C���ő�4.8���A�C��81�Z���`�㏸ ���̎��܂Ƃ߂͍����5��ځB9�����{�ɊJ����镔��ł͐���Ҍ����̗v��ł����c���A���e���C�����ꂽ��A���\�����B ���Ăɂ��ƁA�n���̕��ϋC����20���I�ɓ����Ă���100�N������0.79���ŁA2007�N�Ɍ��\���ꂽ��4������0.74�����㏸�����L�����Ă���B���ϋC���̏㏸�̔����ȏ�͐l�Ԋ����������N�������\�����ɂ߂č����A���̊m�����u95���ȏ�v�ƕ]���B�O���90���ȏ�������グ���B �ł�CO2�Z�x���Ⴂ�V�i���I�ł͍ő�1.7���̏㏸�ɗ}�����邪�A�팸�����炸�ACO2�Z�x���オ�葱����V�i���I�ł͍ő�4.8���オ��Ɨ\�����Ă���B���g���ɔ����A�C�ʂ�20���I�ɓ����Ă���A19cm�㏸���Ă���BCO2�Z�x���Ⴂ�V�i���I�ł͍ő�54cm�A������Ȃ��ƍő�81cm�㏸����Ɨ\�������B���Ȃɂ��ƁA�C�ʂ�65cm�㏸����ƁA���{�̍��l��8������������Ƃ����B �܂��A�����I���ɂ͐��E���̂قƂ�ǂ̒n��ŔM�g�⍋�J��������\�������ɍ����ƕ��͂��Ă���BCO2�팸������Ȃ��ƁA�����I���܂łɊC�X�͏��ł���\���������Ǝw�E���Ă���B9��27����IPCC���琳���ɕ������\���ꂽ�Bhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17176 �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�P�����ђP�ʂŃX�}�[�g���[�^�[���|�̎Z���ȂNJm�F �o�ώY�ƏȂ͒n��P�ʂŃX�}�[�g���[�^�[�i�ʐM�@�\�t���d�͗ʌv�j�����p�����G�l���M�[�Ǘ��̎����n�߂�B 2014�`15�N�x��2�N�v��B�ĊJ�������Z��n�Ȃǐ���\1�����ђ��x�����Z������n����w�肵�A�ȃG�l�T�[�r�X�̒�A���^�C���ʼnƓd��d�͎g�p�̏Ȃǂ�c������X�}�[�g���Ɏ��g�ށB���{�̓X�}�[�g�V�e�B�[�i��������s�s�j���\������X�}�[�g���[�^�[�̕��y�𐬒��헪�̈�ɖ��L���A���i���Ă���B��K�̓}���V�����P�ʂŃX�}�[�g���[�^�[��ݒu����ȂNJ����̕⏕���Ƃ̐��ʂ܂��ēK�p���L����B �o�Y�Ȃ͎���ʂ��A�X�}�[�g�V�e�B�[����������x���`�}�[�N�ƂȂ�A�T�[�r�X���p�҂̃����b�g�ƃA�O���Q�[�^�[�i�G�l���M�[�Ǘ����Ǝҁj�̎��ƍ̎Z�������ʂ��邱�ƂȂǂ��m�F����B2�N�v��̏��N�x�ł���14�N�x�̗\�Z�T�Z�v���ɖ�140���~���v�サ�A�����̈قȂ�3�n���I�肵�Ď����n�߂���j�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/10�@]�@�@�� |
|
|
| ���m�o���e�B�X�t�@�[�}�A�H��̓d�͂��o�C�I�}�X���d�E���͔��d����w�� �����B��̍H��ł���S�R�H��Ŏg�����ׂĂ̓d�͂��Đ��\�G�l���M�[�ɓ]������Ɣ��\�����B����ɁA�O���[���d�͂ɉ����āA��������V�R�K�X�ւ̔R���]�����s���A������G�l���M�[����r�o�����CO2�̑��r�o�ʂ��A2014�N�ɂ�2004�N���83������313�g����ڎw���B ���Ђ́A���N6���ɓ��{���R�G�l���M�[����2��ނ̃O���[���d�͏؏����w������_�����������B�w������d�͗ʂ́A�S�R�H��̔N�ԓd�͏���ʂɑ�������190��kWh�B���̓���́A180��kWh���o�C�I�}�X���d�A10��kWh�����͔��d�B�O���[���d�͏؏��V�X�e���ɂ��A�w�����̃O���[���d�͂��g�p�����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��A�S�R�H��ł̓d�͎g�p�ɂ��CO2�r�o�ʂ������[���Ƃ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B �e��Ђł���f���}�[�N�̃m�o���e�B�X�́A2006�N��WWF�i���E���R�ی����j�ƌ�����ŁA���E�̐��Y���_�ɂ�����CO2�r�o�ʂ�2014�N�܂ł�2004�N���10���팸���邱�Ƃ���Ă���B���̖ڕW��B�����邽�߂̐헪��1�ɍĐ��\�G�l���M�[�ւ̓]��������A���݂ł̓f���}�[�N�ɂ����邷�ׂĂ̊������_�ŗm�㕗�͔��d���狟�������O���[���d�́i�؏��j�𗘗p���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O�쐻�쏊��C�Ɛ���M���Ƃ���q�[�g�|���v����������J�� ���Ԃ͐���M���ɂ��ĉ����Ɨ␅�����A��Ԃ͔M�����O�C�ɐ�ւ��ĉ�������邱�Ƃ��ł���B ��E�������g���H�i�H��ȂǂŁA�{�C����␅�`���[�̉ғ������点��B�d�C��͍����Ȃ邪�A�d���Ȃǂ̔R�����啝�ɍ팸�ł��邽�߁A�g�[�^���ł̉^�p�R�X�g���ɗ}������B�Ⴆ�A�N�Ԗ�6000���ԉғ�����ꍇ�A�N�Ԃ�400���~���x�̃R�X�g���팸�ł���B�����O�ɔ�ׂ��CO2�̔r�o�ʂ�7�����点��B ���i�͍H����݂�1500���~���x�Ƃ݂���B�ғ����Ԃɂ���邪3�N���x�ŏ�����p������ł���Ƃ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��NEC�A�f�[�^�Z���^�[�̋d�͂��팸����ȃG�l��p�Z�p���J���A�ő��50�� �f�[�^�Z���^�[�ɐݒu����郉�b�N�Ɏ������ꂽICT�i���ʐM�Z�p�j�@��̔r�M�������悭��菜���B���̋Z�p���f�[�^�Z���^�[�ɓK�p���邱�ƂŁA�d�͂��ő��50���ጸ�ł���B�@�킩��r�o�����M���g�U����O�ɉ�����Ē��ډ��O�ɉ^�сA���ׂ�}����B �J�������ȃG�l��p�Z�p�́u���i����������p�Z�p�v�ƌĂԁB�@����ɓ��ڂ��Č����I�ȗ�p���\�ɂ���u���ω���p�Z�p�v���A�����̋@������e���郉�b�N�ɉ��p�����B���ω���p�Z�p�́A��}���t�̂���C�̂ɕω�����ۂɔM�G�l���M�[���ړ����錻�ۂ𗘗p���ė�p����Z�p�ŁA�G�l���M�[�̕ω��ʂ��傫���A�������̗�p���\�ɂȂ�B ���i����������p�Z�p�́A���b�N�̍ŏ�i����ʼn��i�܂ŁA�@��̔r�C�M�������I�ɋz�����ė�}���C�̂ɕς���B���b�N�w�ʂɔz�u������M���𑽒i�ɂ��A�e�@��̔r�M�ʂɍ��킹�ė�p����B���i�ɂ������b�N�e�i�̋z�M���ɁA���M�ʂɉ����ė�}�z���ďz������B�Ǝ��̗��H�v�ɂ���Ď��R�z�����Ŋe�i�ɗ�}��K���ɋ�������B ���b�N������12kW�̏���d�͂̏ꍇ�A�����ƗⓀ�@�̓d�͂����킹���d�͂��ő�50���팸�ł��A�����ł́A10��̋@��𓋍ڂ������b�N�w�ʂ���̔M�ʂ̖�50�������O�ɔM�A���ł��邱�Ƃ��������B����A���i����������p�Z�p�̎��p���Ɍ������J����i�߁A�@���V�X�e���̏ȓd�͂ƌ����I�ȃf�[�^�Z���^�[�^�p��ڎw���B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ��IHI�A�H��r���Ŕ��d�|���^�R�W�F�l�ݔ��J�� �H�i�H��Ȃǂ���r�o�����L�@���r�����uIC���A�N�^�[�i�����z�^�����e��j�v�ŏ������A��������o�C�I�K�X�ŃK�X�G���W���������^�R�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�ݔ����J�������B �啪���Ŏ��؎�����i�߂Ă���A�H��r���𗘗p�������d�V�X�e���Ƃ��č����ŏ��߂čĐ��G�l���M�[�̌Œ艿�i������萧�x�iFIT�j�̑Ώېݔ��Ƃ��ĔF����擾�����B�����̃o�C�I�}�X���d�ݔ����Ƃɖ{�i�Q������B IC���A�N�^�[�̋Z�p���C�Z���X�����I�����_�E�p�P����A�����Ă������j�@����������Y�ɐ�ւ��A�啝�ȃR�X�g�_�E���ɐ����B�K�X�G���W����g�ݍ��킹�A�P���~���x���瓱���ł�������Ȑݔ����J�������B���Z�ł́A�u�W���������D�@�v�ɔ�ێ���͖�20����1�A�ݒu�ʐς�100����1���x�ōςނƂ����B�������������ł���L�@���Z�x�iBOD�j���חʂ�1��200kg�`300kg���x�܂œK�p�ł��AFIT���x���p�ɂ�锄�d���v���܂߁A3�`5�N�œ�������ł��錩���݁B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����ŁA���w���Ӓn��Ńr���Q�G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X���H���؎��� �����̃r�����Q�Ǘ����邱�ƂŁA�n��S�̂ŏ�����G�l���M�[���u�����鉻�v���A���ƁE�Ɩ��{�݂ȂǁA���l�Ȏ{�݂��W�ς��������s�X�n�ɑ���n��G�l���M�[���p�̍�������}�邽�߂̎��؎��Ƃ����H����J�n����B ��̓I�ɂ́A10���ɊJ����\�肵�Ă���u�X�}�[�g�R�~���j�e�B�Z���^�[�v�ɓ���BEMS������B�����𒆐S���_�Ƃ��āA���s���ɂ��͂��ߐ��w���ӂ̕����̃r�����C���^�[�l�b�g�Őڑ����A�e�r���ɑ��āA�d�͎g�p�̉�����ݔ��f�f�̃T�[�r�X�Ȃǂ����{����B�������̒��ɂƖ��ԃr���̕����A�܂��w���ӂ̏��Ǝ{�ݖ��W�n��ɑ���r���Q�Ǘ��T�[�r�X�͍������߂ĂŁA����̎��؎��Ƃɂ����āA�ő�20���̏ȃG�l���邢�̓s�[�N�d�͍팸��ڎw���B ���Ђ́A����̎��؎����œ����m�������ƂɁA�n��G�l���M�[�̃X�}�[�g���ɍv������Ƌ��ɁA�X�}�[�g�R�~���j�e�B�Z���^�[�𒆊j���_�Ƃ��āA�X�}�[�g�R�~���j�e�B���Ƃ̎��g�݂��������Ă����B �����_�Ŏ��؎��Ƃւ̎Q���\���E�������̎��Ǝ҂͎������݁A��菤�H��c���A���A�[���A�A�����K�X�A���s�Ȃǂ�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���x�m�d�@�A�A�����ψ�����g�́|���z���A���^�������H���؎��� ���Ђ́A�≏���Ƀp�[�����V�����b�_�G�X�e�����g�p�����ψ���̊g�̂�}���Ă���B�����̐≏���Ɏg����z���Ƃ̔�r�ŁA����������x�Ǝ_�����萫�A�≏���\���B�z������ψ���Ɣ�ׂė�p���\�����シ�邽�߁A�R���p�N�g�������������B ���ɓd�S��Ђ␅�͔��d���ł̗̍p���т����邪�A�p�r�W�J���������A���ӎ��̍�����Ƃ𒆐S�Ɉ�w�̗̍p�g��������ށB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�ȃK�X������A�S�ʎ��R�����������������_�� ���H�ɂ��L���҂ɂ��ψ���𗧂��グ�A�����̌��ߕ���n��Ɛ�̑̐����������B�ق��̋Ǝ킩��Q���𑣂��A�������������ɂȂ���B �V���Ɍ������͔̂N�Ԏg�p�ʂ�10���������[�g�������̏����_��B��ʉƒ�⏤�X���ΏۂɂȂ�B�K�X���Ƃ͂��ł�10���������[�g���ȏ�͎��R�����Ă���A���p�҂ƃK�X���Ǝ҂̌��ŗ��������߂���B �ƒ�����̃K�X�����͌��݁A���Ǝ҂̕K�v�o��Ɉ��̗��v����悹���鑍�����������Ō��܂�B�o�Y�Ȃ̓K�X�������x���ψ���ŁA�����ɎZ������ �l�����R������������}����V�����������܂Ƃ߂��B�ݔ����B�͈�ʋ������D�������Ƃ��A�L������t���̎Z�����F�߂Ȃ��B �o�Y�Ȃ͗��N�x�ɒl�グ��\���������Ǝ҂���V����������j������B�u�S�ʎ��R���ւ̑�P�e�ɂȂ闿���R���̉����ɂ߂ǂ��t�����v�Ƃ��A����͐V�K�Q���𑣂����߂Ɋ����̃p�C�v���C����݂��ۂ̗��p���ȂǁA��̍�̋��c���n�߂�B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA26�N�x�\�Z�̊T�Z�v�������\�ȃG�l�E�ăG�l�����ɏd�_�z�� �o�ώY�ƏȂ́A����26�N�x�\�Z�̊T�Z�v���ŁA�O�N�x��1.2�{�i3,099���~���j�ƂȂ�1��7,470���~��v��������j���B �{�T�Z�\�Z�ł́A�u�G�l���M�[�Ő�i���v�����Ɍ����A�ȃG�l�E�Đ��G�l�������i�ɏd�_�z�����Ă���B�܂��A�H��A�r���A�ƒ�A�����ԓ��̏ȃG�l��������啝�ɉ��������邽�߁A1,955���~�i25�N�x�\�Z�z929���~�j��v������B �d�_�z�����鎑���E�G�l���M�[����̊�{�I�ȕ������ɂ��ẮA�G�l���M�[���̑��p���A����I������ȁu���Y�i���B�j�v�ƁA�œK�E�����I�����x�ȃG�l���M�[�́u���ʁv�A�X�}�[�g�ȁu����v�ɂ��A�u���l�ȋ����̐��ƃX�}�[�g�ȏ���s�������G�l���M�[�Ő�i���v��ڎw���B �ȃG�l�A�Đ��\�G�l���M�[�Ɋւ���T�Z�v���z�� �i1�j�Đ��\�G�l���M�[�̍ő���̓���1,981���~�i1,221���~�j �i2�j�G�l���M�[�R�X�g�ጸ�ɂȂ���u�ȃG�l�����v�̉�����2,288���~�i1,267���~�j �E�Y�ƕ���ɂ�����ȃG�l�E�s�[�N�������̑啝������814���~�i376���~�j �E�ƒ�E�I�t�B�X�A�^�A����ł̏ȃG�l���M�[��̋���744���~�i435���~�j �u�Z��E���z���̏ȃG�l�E�~�d�r���s�[�N��̐��i�v�A�u�N���E�h��ʂ��������E������Ƃ̏ȃG�l�̐��i�v�A�u�����㎩���Ԃ̕��y�x���v�� �E�ȃG�l���̂��߂̋Z�p�J���E���ؓ��̐��i730���~�i456���~�j http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2014/index.html �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��CO2�r�o�̔c���A���Ƃɂ��L����Q�l�ɂ��铊���Ƒ��� ���g���K�X�r�o�ʂ̔c���E���\���A������̈�Ƃ���@�֓����Ƃ��C�O�𒆐S�ɑ����Ă���B���ی�ւ̈ӎ�����������҂ɂ��A�s�[���ł��邱�Ƃ���A�ϋɓI�ɏ��J�����铮�����Y�ƊE�S�̂ʼn������������B �e�Ђ��Ή�����̂̓T�v���C�`�F�[���i�����ԁj�S�̂̉��g���K�X�r�o�ʂ��Z�o���鍑�ۊ�u�X�R�[�v3�v�B�H��Ȃǂł̒��ڂ̔r�o�����łȂ��A�]�ƈ��̒ʋ�o���ȂNJԐړI�Ȕr�o���܂߂Čv�Z����B ���D�O���12�N�x�̉��g���K�X�r�o�ʂ̎Z�o�ŁA���ЕۗL�D�����[�X�����ۂ̔r�o�ʂȂǃX�R�[�v3�Ɋ܂܂��7���ڂ̉��g���K�X�r�o�ʂ��Z�o�����B7���ڂ̂����A�ł����������͕̂ۗL����D����݂��o�����ۂɏo�鉷�g���K�X�BCO2�Ɋ��Z���Ė�800���g���ƁA�{�Ƃł���D���̉^�q�Œ��ړI�ɏo���Ă��鉷�g���K�X�i��2000���g���j�Ɣ�ׂĂ��A�傫�ȋK�͂ƂȂ����B �C�I����12�N�x������̔��������i�̎g�p��p���Ƃ�����9���ڂ�Ώۂɉ�����B�听���݂��p�������o���ۂ�ʋA�o�����ɏo�鉷�g���K�X��V���ɎZ�o����B����҂�������鏤�i�g�p����p�����̐��l���o�����ƂŁA��Ǝp�����A�s�[���ł���Ƃ̑_��������BKDDI�������̒ʐM���Ǝ҂Ƃ��ď��߂Đ��l�����\�����B �N������Ȃǒ����I�Ȏ����^�p������@�֓����Ƃ́A����Љ�ɑ���v���������u���E�Љ�E��Ɠ����iESG�j�v�̔���������d������X�������܂��Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���X�}�[�g���[�^�[�A5300���J���Ɂ|�p�������v��A���z2���~ �p�����{�͂��̂قǁA�S�y�ւ̃X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j�����v������肵���B ���{�~�ő��z��Q���~�𓊂��A2020�N�܂łɓd�͂ƃK�X���v������X�}�[�g���[�^�[��S�y5300���J���ɐݒu����B�ʐM�ԃV�X�e���́A�k���ł͓����ʐM��Ђ̃A�L�[�o���A�����E�암�̓X�y�C���ʐM��Ђ̃e���t�H�j�J��D����҂ɑI�肵���B���̂ق��A�f�[�^�Ǘ��V�X�e����A�G�l���M�[�ƊE�����f���ăX�}�[�g���[�^�[���Ǘ����鎖�Ǝ҂Ȃǂɂ��Ă��D���������߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���m�[���c�����ꎟ�G�l���M�[����125���̌ˌ��Z��p�u�n�C�u���b�h�����V�X�e���v���� �w�n�C�u���b�h�����V�X�e���x�́A�K�X�̃G�l���M�[�Ƌ�C�̔M�̗����𗘗p�������̂ŁA���ГƎ��̐V�Z�p�ɂ��ƊE�ŏ��߂Ẵm���t������}�i���R��}�j�uR290�v���̗p�����B�܂��A�������j�b�g�̉��s�����@��300mm�Ɣ������߁A�����n�Z��ւ̐ݒu���\�ɂȂ����B �����ꎟ�G�l���M�[�����́A�]���^�̃K�X���������50���A�q�[�g�|���v���������18�����サ�Ă���A���Z�ł͏]���^�K�X������ŔN��10.1���~�������������M����A4.1���~�܂ō팸�ł���Ƃ����B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ��IHI���o��20kW�̏��p�d���Ɍn���A�n�\�ȏ��^�o�C�i���[���d���u �{���u�́A�g�p���鉷���E��p���̉��x�E�ʂɂ��A��kW�`20kW�̔��d���\���B �쓮�}�̂ɂ́A�d�C���Ɩ@�̏��^�o�C�i���[���d�̋K���ɘa�ɓK�������s�����K�X���g�p���A70���`95���̉����Ŕ��d���\�ŁA��p���̉��x��30���i��ʓI�ȍH��̗�p���̕��ϓI�Ȑ����j�ł��A������95������ő唭�d�o�͂邱�Ƃ��ł���A�܂��A���p�d���ɐڑ��\�Ȍn���A�n�@�\��W���������邱�ƂŁA���d�����d�͂̕i�����グ��ƂƂ��ɓd�̗͂p�r���L���A����ł̍Đ��\�G�l���M�[�̌Œ蔃�搧�x�̓K�p��H��ł̏ȃG�l�ɂ��v������B �����̔M�G�l���M�[��d�C�G�l���M�[�ɕϊ�������@�Ƃ��āA�g�I�[�K�j�b�N�����L���T�C�N���h���̗p���Ă���B �ő呗�d�[���d�o��20kW�̏��^�^�C�v�B���d�ɕK�v�ȉ����ʂ����Ȃ����߁A�M�G�l���M�[�̉��������Ƃ���Ă����A�H��Ȃǂŕ��U���Ĕr�o����Ă���70�`95���̉������A�W���ɔ��d�ɗ��p���邱�Ƃ��\���B�^�[�r�����d�@�ɂ́A�쓮�}�́iHFC-245fa�j��p�̐V�J���^�[�r�����̗p�����^�������������B �H���ċp�{�݂̉����A����ȂǁA��ʔM�̗L�����p���\���B�܂Ƃ܂����������r�o�����H��≷��ł́A�{���u����ݒu���A�������e���u�ɕ��U�����Ĕ��d���邱�Ƃ��\�ŁA�����e�i���X���ɂ͈�䂸��~���Ċe���d���u�̒�~���Ԃ��ŏ����ɗ}���邱�ƂŁA�����ǂ��^�p�ł���B��2050�~���s1360�~����1600 (mm) �i�ˋN�����܂܂��j �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����c�}�d�S�̒n���S�w�Œn���M���p�R�X�g3���� ���d�S�̓��k��w�Ɛ��c�J��c�w�ŁA�J��H�@�Ō@�蔲�������`�g���l�������łɃR�C���^�����M�������~�݂��A�z�[���̈ꕔ�ɗ��p�B����ɂ���C�M���q�[�g�|���v�Ɣ�ׂ�CO2�r�o�ʂƃ����j���O�R�X�g��N��30���팸�ł��錩���݁B ���Z�p�́A�y��̒f�M�@�\�ɂ���C���̉��x�ω��̉e�����ɂ����A��N��ʂ��Ăقڈ��ł���n���M���q�[�g�|���v�̔M���Ƃ��Ċ��p���邱�ƂŁA��g�[��Z��E�����Ȃǂɗ��p������́B�Ċ��͗₽���n���ɔM����M�i��[�^�]�j���A�~���͉������n������̔M�i�g�[�^�]�j���邱�ƂŁA�q�[�g�|���v�̎d���ʂ����炵�ďȃG�l����}��B ���̒n���M�𗘗p���邽�߂ɕK�v�ȔM���������ɂ́A�{�[�����O�}�V����p���čE����@�킵�A�M�������}������u�{�A�z�[�������v�A������b�Y���ɔM�������ݒu���M�����Y�Ƃ��Ċ��p����u��b�Y�����v�A�y���ψ��ŁE�g���l�������œ��ɔM��������L���~�݂���u���������v��3��ނ�����B �O�H�}�e���A���e�N�m�́A��L3��ނ̂��ׂĂ̒����E�v�E�{�H�Z�p��ۗL���A�������̎{�H���т������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���\�t�g�o���N�A�R���d�r�̍��ى�Ђ�ݗ����U�^�d���̕��y�𐄐i �\�t�g�o���N�O���[�v�ƃu���[���G�i�W�[�i�č��J���t�H���j�A�B�j�́A���{�����ɂ����Ď��v�����܂�N���[���E����I�E���U�^�̓d�͋����Ɍ����āA�R���d�r�ɂ��d�͂̋����A�̔����Ƃ��s�����ى�Ђ�ݗ������Ɣ��\�����B ���ى�Ж��́A�u���[���G�i�W�[�W���p���B���{����10���~�ŁA�o���䗦��50�����B�V��Ђ́A���S�ŃN���\���E����I�E���U�^�̑�֓d�͂Ƃ��āA�R���p�N�g��24����365���ғ���������A�Ǝ��̔R���d�r�uBloom�G�i�W�[�T�[�o�[�v��̔�����B�{�T�[�o�[�����Ђɓ������邱�Ƃɂ��A�Y�f�̔r�o�ʂ����炵���̎g�p�ʂ�}����Ɠ����ɁA�G�l���M�[�R�X�g��d����~�̃��X�N���y���ł���Ƃ����B Bloom�G�i�W�[�T�[�o�[�́A�����̔R�������p�ł���A�N���[���ō������A���U�ݒu�^�̉���I�Ȍő̎_�����`�R���d�r�B�{�Z�p�́ANASA�̉F���v���W�F�N�g��ʂ��ĊJ�����ꂽ���̂ŁA�]���̐��f�R���d�r�Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�Ƃ����BBloom�G�i�W�[�T�[�o�[�̓o�C�I�K�X��s�s�K�X�ʼnғ����A���d�����̍����ɂ����đ��ɕ��Ԃ��̂��Ȃ��A�ݒu����e�i���X���ȒP�ɍs�����Ƃ��ł���B�܂��A�_��Ŋg�����̂��郂�W���[���Z�p�ɂ��A�ڋq�̃j�[�Y�ɍ��킹�����d�e�ʂŐݒu���\�B �u���[���G�i�W�[�́A�č��ɂ����Ă��ł�5�N�ȏ�ɂ킽��ABloom�G�i�W�[�T�[�o�[��ݒu���Ă���B���U�^�d���Ƃ��āA7��kWh����d�͂��������Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���C�I���A2014�N�x���ɑS��490�J��1,150���EV�[�d�X�e�[�V���� �����X��470�J���ƁA���N�x�ȍ~�ɊJ�X���邷�ׂẴV���b�s���O�Z���^�[�Ƒ�^�����X�[�p�[�̓X�܂ɁAEV�i�d�C�����ԁj�[�d�X�e�[�V����������Ɣ��\�����B ����ɂ��A���Ђ�EV�[�d�X�e�[�V�����́A2014�N�x���ɑS����490�J��1,150��i�}���[�d��500��A���ʏ[�d��650��j�ƂȂ�A���{�ő�K�͂�EV�[�d�X�e�[�V�����ԂƂȂ�B ���Ђ́A2012�N�ɁA�G�l���M�[�̎g�p���u�ւ炷�v�A�Đ��G�l���M�[���u����v�A�ЊQ���ɒn����u�܂���v�𒌂ɂ����A2020�N�܂ł̃O���[�v���ڕW�u�C�I���̃G�R�v���W�F�N�g�v�����肵���B���̒��ŁAEV�APHV�i�v���O�C���n�C�u���b�h�ԁj���ЊQ���ɗL���Ȉړ���i�ƂȂ蓾�邱�Ƃ���A���ۑS�ɍЊQ��̎��_�������āA2008�N���[�d�X�e�[�V�����̓����Ɏ��g�݁A���݁A�u�C�I�����[���v�Ȃ�43�J����95��̏[�d�X�e�[�V������ݒu���Ă���B ����́A�p���I�����肵���T�[�r�X�̒A�ݒu���g��̎��i�K�Ƃ��āA�L����������ɓ���A2014�N�x��ڏ��ɁA�C�I���̓d�q�}�l�[�uWAON�v�𗘗p����x�����V�X�e�����\�z���A�S�[�d�X�e�[�V�����ŗL�����ɂ��T�[�r�X�����{����v��B����ɐ旧���A���N�x���ɁA���ꌧ�̃}�b�N�X�o�����{�Ó�X�ʼn^�p�������J�n����\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ������23�N�x�y�ѕ���24�N�x������G�l���M�[�Z�p���؎��Ƃ̐��ʕ����J ����23�N�x�y�ѕ���24�N�x������G�l���M�[�Z�p���؎��Ɣ�⏕���i������G�l���M�[�Z�p���؎��Ɓj�̐��ʕ����⏕���Ǝ҂���o���ꂽ�̂ŁA���̌��J�ł�B http://www.nepc.or.jp/topics/2013/0717.html [�p������] �@�O�d���Îs�O�d��w�L�����p�X���A�A�n�E�X�e���{�X���A�B�����s�A�C���s�A�D����s�A�E�L�������R�s�A�F���̗t�L�����p�X�w���ӂS�X�� [�I������] �@�����s�u�V�G�l���M�[�������i���c��v |
|
|
| �����z�����d�V�X�e���Ӓ苦��p�����鑾�z�d�r�A�ꎞ�ۊǃT�[�r�X���J�n ���݁A���z�����d�p�l���̏������@�ɂ��ẮA���ɂ��K�C�h���C�����͒�߂��Ă��Ȃ��B���̂��߁A������ł́u���d�ʂ̒ቺ�v�A�u�����̎��ɂ��P���v�A�u�V���i�ւ̃��v���C�X�v�Ȃǂ̗��R�œP������鑾�z�����d�p�l�����ꎞ�ۊǂ���T�[�r�X�������Ȃ��B ������́A���z�����d�V�X�e���̓_���E�����������Ȃ���O�ҋ@�ւƂ���2012�N7���ɐݗ����ꂽ��ʍ��c�@�l�B �T�[�r�X���p�Ɋւ��ẮA�d�b�E���[���œP�����鑾�z���p�l���̃��[�J�[�E�^���E������`����ƁA�����̌��ς肪�����B���̌�A�ۊǂɊւ���_�������A�����p�i1�N�ԁj�U����ɁA���z���p�l�����������q�ɂɂĕۊǂ���Ƃ�������B ����_����Ԃ�1�N�Ԉȍ~��1�������̎����X�V�ƂȂ�B�܂��A���������ł��邱�Ƃ��_������ƂȂ��Ă���B ���݁A���z�����d�p�l���́A�L�Q�������O����镨�����ܗL���鑾�z�d�r�����y����\��������A�g�p����p�����ɐl�̌��N����ɑ���e�����y�ڂ��Ȃ��悤�A�K���Ȏg�p�E�p���Ɍ���������������K�v������Ƃ���Ă���B�܂��A���z�d�r�̒������i20�N�`30�N�Ƃ����j�̓��������A�����[�X��T�C�N�����]�܂����Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�\�[���[�̐ڑ����͑S���ʼn����ցA���Ǝ҂͍H����S �e�d�͉�Ђ����\�����H����S���̒P�����r����Ɩ�3�{�̊J��������B�ō��͓��k�E�����E�����d�͂�3�ЂŁA���d�ݔ��̍ő�o��1kW������3465�~�̕��S�������Ǝ҂ɐ�������B1MW�i���K���b�g�j�̃��K�\�[���[�ŕ��S����346��5000�~�ɂȂ�B���S�����ł������̂͋�B�d�͂�1260�~�ł���B ����͔��d�ݔ��𑗔z�d�l�b�g���[�N�ɐڑ����邽�߂́u�A�n���c�v�̏�ŁA��̕K�v���f���āA�K�v�ȏꍇ�͎��Ǝ҂����S�����x�������ƂɂȂ�B �����A���K�\�[���[�̌��ݔ�Ɣ�r���ĕ��S���̊����͏������A���Ƃɑ���e���͏������Ƃ݂���B �����G�l���M�[���̒����ł́A���K�\�[���[�̌��ݔ��2012�N���̎��_�ŏo��1kW������28���~�ɂȂ��Ă���B���S���̍ō��z3465�~�ł����ݔ��1�����ɂƂǂ܂�B���Ǝ҂ɂƂ��Ă̓��K�\�[���[�����݂ł���ꏊ�������郁���b�g�̂ق����傫�����낤�B �]���̓��K�\�[���[�̂悤�ȑ�K�͂Ȕ��d�ݔ����瑗����d�͂ɂ���ĕϓd���ɋt�����̓d���i�o���N�t�����j�������邱�Ƃ��֎~���Ă����B2012�N7���Ɏn�܂����Œ艿�i���搧�x�ɂ���ă��K�\�[���[�̌��݃v���W�F�N�g���}���������ƂŁA�o���N�t�����ɂ��K�����������K�v�������サ���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �����z�������y�����h�C�c�A�Œ艿�i���搧�x���u���Ɓv���O�� �Đ��\�G�l���M�[���y�̂��߂̎x����̌Œ艿�i���搧�x�iFIT�j�̖ړI�́A�Η͔��d�ȂǂƓ����܂ő��z���̔��d�R�X�g�����������邱�Ƃ��B��{�I�ȍl�����͋K�͂̌o�ς��B���z�d�r���W���[���̐��Y�ʂ�2�{�ɂȂ�Ɖ��i�͖�20�������邱�Ƃ��������Ă���B ���̋K�͂̌o�ς��������邽�߂Ƀh�C�c�ł�FIT�̐����ꂽ�B FIT�ɂ���āA���z�����d�V�X�e������ʓ������ꂽ���Ƃ͂ǂ��Ȃ邩�B�h�C�c�͊��ɂ��̒i�K�ɒB���Ă���B ���z���֘A�̋ƊE�c�̂ł���BSW-Solar�̒������ʂł́A�h�C�c�ł͐V�K�ɐݒu���ꂽ���z�����d�V�X�e���̏o�̖͂�3����1���A�ݒu��̉ƒ���ƂŎ��Ə����Ă��� BSW-Solar�ɂ��A�����u���^�̑��z�����d�V�X�e���ɑ���FIT�̉��i��0.15���[��/kWh�i��19.5�~�A130�~���Z�j�B�ƒ�p�̓d�͗�����0.27���[��/kWh�i��35.1�~�j�Ȃ̂ŁA�n���ɐڑ����Ĕ�������Ă��炤�����A���Ə���������u�ׂ���v�B ���̂悤�ȓ����ƕ��s���āA2013�N5���A�h�C�c���{�͏��K�͒~�d�V�X�e���ɑ��鏕�������x���J�n�����B���������K�͒~�d�V�X�e���̓����͂悢���Ƃ����߂ł͂Ȃ��B�h�C�c�̗�ł̓V�X�e���e�ʂ̌��ɂ߂�������Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă���B��e�ʂ̃V�X�e��������Α��z�������L���ɗ��p�ł��邪�A���R�X�g�ɂȂ��Ă��܂��B�t�̏ꍇ�͑��z�������ʂɂȂ�A��ԂɌn�����獂���ȓd�͂��w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邩�炾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�n����邭�Č������ȃG�l�A�V�ۃr���̏Ɩ��Ńf�}���h���X�|���X��T�� �V�ۂ̓��r���f�B���O�̃e�i���g���2�ЂƋ����ŁA�Ɩ���ΏۂƂ����f�}���h���X�|���X���؎��Ƃ��J�n����B ���A���^�C���������A�e�i���g��Ƃ̏]�ƈ��̖����x���ێ�������d�͂������������@��T�鎎�݂��B�����s����W�����u�e�i���g�r���ɂ�����f�}���h���X�|���X���؎��Ɓv�ɉ��������́B ���؎��Ƃ̑ΏۂƂȂ�̂́A�V�ۃr������4�t���A�B1�t���A�������3000m2����B�r�����L�҂ƃe�i���g���o���ł��Ƃ肵�Ȃ���A�r�����L�҂���p���̏Ɩ��@��ڐ��䂷��B �Ɩ��̃��j���[�Ƃ��āA��ʓI�ȃI�t�B�X�ɕK�v�ȏƓx�ł���500�`600lx�i���N�X�j�ƁA400lx�A����ɂ�10������13��������400lx�Ȃǂ��l������B �e�i���g�̏]�ƈ�����1�̃��j���[��I�сA2�`3�T�ԓ������j���[���p������B�B����������艸�₩�ȃ��j���[�ɕύX����A�e�Ղł������ɐߓd����Ƃ������悤�ɁA�ȃG�l�p�^�[����ς��Ă����B ���؎��Ƃ̓��e��3�ɕ������B�����A�����Ђ������A�ЊQ�����B�����Ђ������ɂ̓C���Z���e�B�u��^���āA����ɐߓd���\���ǂ����ׂ�B�C���Z���e�B�u�̓��e�͎O�H�n���̃e�i���g�̏��i����D�҃`�P�b�g���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| �������K�X�K�X�g�p������ƌ���BEMS���ƊJ�n �d�C���@�Ɠ��l�ɐݒ艷�x�╗�ʂȂǂ��ׂ�������ł���悤�ɂ����B�ݒ艷�x���z����Ǝ����ŋ̕��ʂ𗎂Ƃ��B�Ɩ��̒��߂��\�B �r���Ǘ���Ђ̃G�l���M�[�S���҂̓^�u���b�g�ŁA�r���S�̂����łȂ��A�e�i���g�̎g�p���c���ł���B �K�X�͒��߂�����A�ڋq����d�͂̂悤�ɏȃG�l�Ǘ����������Ƃ̗v�]�����������B BEMS�̃V�X�e�����i�́A�K�X�@10����ȃG�l���䂷��ꍇ��250���~����B�g�p�ʂ̑����̏ȃG�l����œ��������5�N���x�̌��ʂ��B���H�ɂ��o�Y�Ȃ̕⏕���ΏۂɂȂ�\��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�Ɠd�ʎY��3D�v�����^�[���p �������i�̐��Y�ɕK�v�ȋ��^����@�ō��A���Y�R�X�g��3�����x�팸����B �V���Ȑ��Y�Z�p�Ƃ��Đ��E�Œ��ڂ����3D����@���Ɠd�ȂǑ�ʐ��Y�i�Ŏg�����߂ẴP�[�X�ƂȂ�B ���^�͗l�X�ȍH��@�B�ŋ�����������薁�����肵�č���Ă���B�������x�Ƌ��x�����߂��邽�߂ɏn���Z�\���K�v�ŁA�ʏ�͐���ɏ��Ȃ��Ƃ��P�J�����x������B�V���i���J�����邽�тɐV�������^���K�v�Ȃ��߁A�����Ƒ��ł͋��^�̔�p���N���S���~���x�ɂȂ��Ă���B ���^�̐�����Ԃ��ɒZ�k���Ĕ�p�����炵�A�������i�̃R�X�g���팸����B������@�̈��Łu�����ϑw���`�@�v�Ƃ��������\�@�ŋ����̕���n�����������Ōł߂ċ��^�ɂ���B �R���Z���g�⊷�C��̃t�@���Ȃǂ̋��^�Y��������^�C�Ȃǂɂ��A�o����B���^����5000���邪�A�����߂���3D����@�ō�肽���l�����B ������@���g���A�����̗�p���Ԃ�Z�k�ł������ȍ\���̋��^�����邽�߁A���i�̐��Y�������܂�R�X�g����������B�h���C���[��V�F�[�o�[�Ȃǂɂ��L���Ă����B����A�����ԎY�ƂȂǂł��L����\��������B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ��NTT�t�@�V���e�B�[�Y�ƃG�l�b�g���}���V���������f�}���h���X�|���X �_�тɐݒu�����X�}�[�g���[�^�[���g���A���ԑѕʗ����T�[�r�X��ݒ肵�Ă���B���ɁA�d�͎����Ђ������ɂ͐ߓd�ʂɉ����ă|�C���g���Ҍ�����ߓd�|�C���g�T�[�r�X�����B���̐ߓd�|�C���g�T�[�r�X�͓d�C�����̎x�����ɂ��̃|�C���g�����p�ł���B 2013�N7������͐V�������݂�lj������B�ċG�̌ߌ�ɓd�͎������Ђ��������ꍇ�A�_�т̏���d�͗ʂ��i�荞�݂����ꍇ�A�X�l�����������{�݂ɗU�����āA�ƒ�̏���d�͂̍팸��U������B ���̂悤�ȍs���͌X�l�̐����̒m�b�Ƃ��Ă͊��ɂ���B���Ȃ͂��̂悤�ȍs���Ɂu�N�[���V�F�A�v�Ƃ������O��t���Ă���B NTT�t�@�V���e�B�[�Y�̎��g�݂ł́A�����Ђ������Ɂu�ߓd���o�������v��z�M����B�ߓd���K�v�ɂȂ�^�C�~���O�Ō��藘�p���\�Ȋ����N�[�|���Ȃǂ������Ă���A���ꂪ�V�����ߓd�̓��@�t���ɂȂ�B���ۂɊO�o����ƁA�]���̐ߓd�|�C���g���L���ł��邽�߁A���@�t���̋�����������B �ߓd���o�������ɋ��͂����Ƃ͓�����6�Ђł���B�G�v�\���i��A�N�A�X�^�W�A���A�R�j�J�~�m���^�v���l�^���E���i���V�A�V��j�A�T���V���C�������فA�ȂǁB�����s�Ɛ_�ސ쌧�̎{�݂����p�ł��邱�ƂɂȂ�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��2013�N�x�̓d�͎��v��0.7�����ɂƂǂ܂�A�d�������\�� �d�͒����������́A2013�N6���A�Z���o�ϗ\���Ɠd�͎��v�\���\�����B����ɂ��A2013�N�x�̓d�͎��v�͑O�N�x��0.7�����ƐL�т邪�A2014�N�x�͓�0.3���ɂƂǂ܂�Ƃ����B�����2012�N�x���̋C���Ɛߓd�̌p���������Ƃ����\�����B �d�͎��v���������闝�R�͌o�ϏƁA�C���A�ߓd�ɂ���B�o�Ϗł͓����}�C���h���キ�A�����I�������Ƃ����T���ł���B�Ƃ͂����A2013�N�x�͎���GDP���O�N�x��2.6�����Ɖ�������B����͉~���Ɛ��E�o�ωɂ��O���A���������̑����A����ŗ������グ�O�̋삯���ݎ��v��z�肵���������B2014�N�x��0.5�����Ɠ݉�����B�삯���ݎ��v�ƌ����������̔������l���ɓ��ꂽ���߂��B�Ȃ��A2012�N�x�͑O�N�x��1.2�����������B �d�͎��v�͋C���̐����ɋ����e�����邽�߁A�ċG�Ɠ~�G�̋C�������Ɋ�Â����V�~�����[�V�������ʂ����炩�ɂ����B�o�Ϗ��\���ʂ�ł���A2013�N�x���ҏ������������ꍇ�A�d�͎��v�͑O�N�x��1.4�����܂ŐL�т�B����͐�قǂ̗\������0.7�|�C���g�������l���B�ċG�̋C����2000�N�ȍ~�ł���������2010�N�x���A�~�G���������ł���������2011�N�x���̋C���������Ƃ��̌��ʂł���B ��Ēg�~�������ꍇ�́A�O�N�x��1.6�����ւƏk������B����͉ċG��2000�N�ȍ~�ł�����������2003�N�x���A�~�G���������ł��g��������2006�N�x���Ƃ����ꍇ�̗\�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA����24�N�x�G�l���M�[�ւ���N���u�G�l���M�[�����v�����\ 10��ڂƂȂ�{�N�̔����ł́A�ȉ���2�{���Ăő�1�����\���B �E��P����P��/ �G�l���M�[�����鐢�E�̉ߋ����Ⴉ��̍l�@ �@�G�l���M�[�����鐢�E�̉ߋ����Ⴉ��̍l�@���s���A����̉䂪���̐ӔC����G�l���M�[����\�z�Ɍ����Ă̎�����B �E��P����Q��/ �����{��k�ЂƉ䂪���G�l���M�[����̃[���x�[�X����̌����� �@�����{��k�Ќ�ɍu������Ȏ{��Ɖ䂪���G�l���M�[����̃[���x�[�X����̌������ɂ��āA2012�N8���`2013�N3�������܂ł̏������B ��2012�N7���������̏ɂ��ẮA2012�N�Ŕ����ɋL�ځj�B �E��2���ł͍����O�̃G�l���M�[�������A��3���őO�N�x�ɍu�����{��̊T�����L�ځB �@����24�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[����2013�jhttp://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2013/index.htm |
|
|
| �������s�A�ȃG�l�ݔ��̕⏕���Ƃ��J�n�A�ƒ�����ł͔R���d�r�E�~�d�r�EV2H���Ώ� �d�͎g�p�́u�����鉻�v�Ǝ�������ɂ��s�[�N�d�͗}���𐄐i����s�̎��g�݂̈�Ƃ��āA���v���c�@�l�����s�����ЂƘA�g���A���z��100���~�̊������⏕����B �ƒ�����ł͏Z��G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iHEMS�j�Ȃǂ̓����������ɁA�R���d�r�Ȃǂ̃R�[�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j��~�d�r�A�d�C�����ԁiEV�j�Ɖƒ�œd�C�𑊌�������r�[�N���E�g�D�E�z�[���iV2H�j��Ώۂɂ���B ���Ə������ł̓I�t�B�X�r���̃R�[�W�F�l���[�V�����ƁA�����e�i���g�r���̃r���G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iBEMS�j��2��ƂȂ�B �ƒ�����̕⏕�z�́A�R�[�W�F�l���[�V�������@���p��4����1�A�~�d�r����6����1�ŁA���ꂼ������22��5000�~�A50���~�ɂȂ�BV2H�͒�z��10���~��⏕���AEV�Ƃ̓����w���ł�25���~�ɐݒ肵���B�����̕⏕�Ώۋ@��z�����d�V�X�e���ƂƂ��ɓ�������ꍇ�́A���z���p�l���̔��d�o��1kW������2���~���z����B �I�t�B�X�r���̃R�[�W�F�l���[�V�����͐ݒu�o���2����1�i���3���~�j�A�����e�i���g�r����BEMS�͓�4����1�i��250���~�j��⏕����B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���G�l���A�X���ɂ��ȃG�l�V�]���������|�s�[�N���̐ߓd�u���葝���]���v �d�͏���s�[�N���}���鎞�ԑтɊ�Ƃ��H��E�I�t�B�X�Őߓd���A���d�͉�Ђ̔��d���S���y�������ꍇ�A���̕������ۂ��������ߓd�����ƌ��Ȃ��B �g���Ȃ��]���h���C���Z���e�B�u�Ƃ��ēd�͎������Ђ�������ď�Ȃǂ̐ߓd�𑣂��A�~�d�r�⎩�Ɣ��d�Ƃ������X�}�[�g�R�~���j�e�B�[�i������Љ�C���t���j�֘A�Z�p�̕��y���㉟������B �o�Y�ȁE�G�l���͍�����ʼn����ȃG�l���M�[�@�������������Ƃ��A���x�^�p�̏ڍאv�ɓ���B2014�N4���ɉ^�p���J�n����\��B�G�l����7�����{�ɂ��A���������G�l���M�[������̏ȃG�l�֘A�ψ�������W���A��Ƃ̓d�̓s�[�N���ԑт̐ߓd�w�͂��u���葝���]���v�ł���悤�ɂ���Z�o���@�̍���ɓ���B �{�{�ꌾ���� �ߓd�̊��葝���]���͌��ʂ����肻���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ߓd����ő�2000�~�v���[���g�A���l�s�̍x�O�Łu�l�K���b�g�v���J�n �l�K���b�g�ɂ��ߓd�v���W�F�N�g�����{����̂́A���}�d�S�́u���܃v���[�U�w�v�̖k���̒n��ł���B ���l�s�̒��ł͐V�����J�����ꂽ�x�O�^�̏Z��n�ŁA�w�̎��ӂɂ͏��Ǝ{�݂�����������B�n��̏Z�����ߓd�v���W�F�N�g�ɋ��͂���ƁA�n���̏��X�Ŏg����n��ʉ݂����炤���Ƃ��ł���B�Q����\�����߂Γo�^�|�C���g500�~���A����Ɍ��Ԃ̓d�͎g�p�ʂ�O�N�����������点�ΐߓd�|�C���g��500�~���A�`�P�b�g�Ŏ�邱�Ƃ��ł���d�g�݂��B3�����Ԃōő�2000�~���̃C���Z���e�B�u�ɂȂ�B ���̃v���W�F�N�g�ɎQ�����邽�߂ɂ́A�����d�͂��C���^�[�l�b�g�Œ���u�łƌv��v�𗘗p����K�v������B�łƌv���ʂ��Ė����̓d�͎g�p�ʂ�O�N�Ɣ�r���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �l�K���b�g�͐ߓd�ɂ��C���Z���e�B�u�𗘗p�҂�������_�Łu�f�}���h���X�|���X�v�Ɠ��l�����A�Ώۊ��Ԃ̐ݒ�ȂǂɈႢ������B�f�}���h���X�|���X�͓d�͉�ЂȂǂ��ߓd���˗��������ɂ����L���ł���̂ɑ��āA�l�K���b�g�͂��炩���ߌ��߂�ꂽ���Ԃɐߓd���邱�ƂŃC���Z���e�B�u�邱�Ƃ��ł���B �ꎞ�I�ȃs�[�N�J�b�g�����p���I�Ȏ��v�̗}���Ɍ��ʂ�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ��BEMS�⏕���̐\��������5000����˔j�A2013�N�x���̖ڕW�B���Ȃ邩 BEMS�i�r�������G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���j�̕⏕�����^�c��������n�C�j�V�A�`�u�iSII�j�̏W�v�ɂ��ƁA6��21�����݂Ő\��������5311���ɒB�����B ��1�������O��5��7���̎��_�ł�3642�����������Ƃ���A�Z���Ԃ�1.5�{�Ɋg�債�����ƂɂȂ�B�o�ώY�ƏȂ�2012�N�x��2013�N�x��2�N�Ԃ�1�����̎��Ə���BEMS��ݒu����ڕW���f���Ă����B���N�x�͕⏕���̐\���������L�єY���A�悤�₭2�N�ڂɓ����Đ��������Ă����B ����5������d�C�������l�オ�肵�����𒆐S��BEMS�̓����@�^�����܂��Ă���B�\���������A�O���Q�[�^�ʂɌ���ƁA�g�b�v�͏]�����瑱���ăG�i���X�����A2�ʂ̓������쏊��3�ʂ̓��{�e�N�m���啝�Ɍ�����L�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/7�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�H�j�b�P�����f�d�r���p���G�l���M�[�Ǘ� �d�͎��v�̃s�[�N���Ɏ����Ǘ��V�X�e���Ƒg�ݍ��킹�A�H��̔��p�d���⑾�z���A���͔��d�ȂǕs����ȓd�͂̒����p�̓d���Ƃ��Ė𗧂Ă�B����܂Ŋ��d�͂ȂǂƑg��Ŏ��؎�����i�߂Ă����B���N�x�͉���̓�哌���ő��z���╗�͔��d�Ƒg�ݍ��킹���V���ȃG�l���M�[�Ǘ��V�X�e���̎��؎������n�߂��B�d�r24��i���o�͖�122kW�j��ݒu���A���݂̔��d�@�̏o�͂�⊮�ł���悤�ɂ���B �j�b�P�����f�d�r�͍����ŏ[���d���ł��A��d���̏o�͒������\�B�H��̐��Y���C�������肵�ĉғ������邱�Ƃ��ł���B1kWh������̃R�X�g�͖�10���~�Ń��`�E�����C�I���d�r�̔����Ƃ����B ���d�r�́A�]���A�S���ԗ��̉G�l���M�[�̗p�r���傾�����B��d���Ɏԗ����Ŋ��w�܂ő��s�ł���Ƃ������g�������ł��AJR�����{����s��ʋǁA�C�O�̒n���S�Ȃǂɂ��[�����т�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������K�X�H����C�ݔ��̉��P��� �K�X�{�C���[�̔̔�����C�ݔ��̃����e�i���X���Ƃ���|���Ă���A���̉ߒ��Ŕ|�����m�E�n�E�����p����B�o�N�ω��ɂ��{�C���[�̏��C�����������ቺ������A�z�ǂ�����C���R�o�����肷��ȂǁA�����e�i���X�����30���ȏ�̃G�l���M�[���X�������Ă���P�[�X���L��B �܂��A�M�ʂɑ�����C�����ʂ̊�����������i������96���ȏ�̍������{�C���[��ݒu����B�����̃{�C���[�𐧌䂷��Z�p�Ȃǂɂ����C�̐����i�K�Ŋ����ݔ��ɔ�ׂ�8�����x���������܂�B ����ɔz�ǂ�M������ȂǏ��C�ݔ��̊e���ɃK�X����C�̎g�p�ʂ��v������@���ݒu���A�����^�]��Ԃ��`�F�b�N����B�ێ��Ǘ��̎�Ԃ��Ȃ��Ɠ����Ƀ��X�̔����A���P�Ɋ��p���A���C�̔����B���p�i�K��7�����x�̏ȃG�l�������ł���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���������邩�A�u�ƒ��ESCO�v �I���b�N�X��NEC�A�G�v�R��3�Ђ��V��ЁuONE�G�l���M�[�v��ݗ����A�ƒ�����G�l���M�[�T�[�r�X�̊J�n�\�����B NEC���̒�u�pLi�i���`�E���j�C�I���~�d�r�i5.53kWh�j�ƃG�v�R���J�������X�}�[�g�t�H�����g�����ƒ�����N���E�h�^�G�l���M�[�T�[�r�X��g�ݍ��킹�A�V�X�e���ꎮ�����z5145�~�Ń����^������BHEMS(�Z��G�l���M�[�Ǘ��V�X�e��)�ݒu�ւ̕⏕���x�̂��铌���s���ł���Ό��z3045�~�ɂȂ�B ONE�G�l���M�[�́A�d�͗����̒���Ԋi�������p���āA��̈����d�C�߂Ē��Ɏg���R�X�g�팸�������߁A�s���ł�����q�l�̎������S�͂Ȃ��Ȃ�B�����s�łȂ��Ă��w���z��������v�����x���Ɍ_��A�������S�[���ōЊQ���Ȃǂɔ��p�d�����m�ۂł���ƁA�V�����G�l���M�[�T�[�r�X�̗��_����������B ���M��̊z�����ΓI�ɏ������ƒ�s��ł��AICT�̊��p�ʼnƒ�̃G�l���M�[���������I�Ɏ��W�ł���悤�ɂȂ������Ƃɉ����AHEMS�ւ̕⏕����FIT�Ȃǐ��{�⎩���̂��ƒ�̏ȃG�l�𑣂����x�𑱁X�Ɠ������n�߂����ƂŁA�ƒ�����̏ȃG�l�x���r�W�l�X�ɒǂ����������Ă���B ���z�����d�ʂ�\�����Ȃ���A�~�d�r���������䂵�ēd�C���ߖ�B���̂ق��ANEC�̃N���E�h�ƘA�g���āA�d�͎g�p�ʂ̃f�[�^��~�ς��A���Ԃ��ƂɃO���t������Ȃǁu�����鉻�v�ɉ����A�u�ߓd�i�r�Q�[�V�����v�Ƃ����@�\�Ō��M��̍팸���@���A�h�o�C�X���Ă����B �o�T�u���oBP �v |
|
|
| ���I�[�W�X����GE���X�}�[�g���[�^�[�ƘA�g�����N���E�h�^�T�[�r�X��� ���T�[�r�X�́A�u�莞���j�l�̎��W�v�ɉ����āA�u���ʂ̓d�͎g�p�ʂ̌����鉻�v�u�d�͎g�p�ʂ̃I���f�}���h���j�v�u���[�^�[�̉��u����v�Ȃǂ̋@�\������Ă���B���[�^�[���ɉ����������̌n�ɂ��A�r�W�l�X�K�͂ɉ��������p���\�ŁA�ߏ�Ȑݔ��������}���ł���B�܂��A���ەW���ɂ��������Ă���A���V�X�e���Ƃ̘A�g���\�B ���Ђ́A�}���V�����E�I�t�B�X�r���̃X�}�[�g���Ɍ����ēd�̓X�}�[�g���[�^�[�������������Ă����Ƃ�A�����ꊇ��d�T�[�r�X���Ǝ҂�Ώۂɔ̔�������W�J���Ă����B����ɁA���Z�Ҍ��������鉻�T�[�r�X���͂��߁A�d�͎g�p������ڋq�Ǘ��A�f�[�^���͂Ȃǂ̕���ɂ�����T�[�r�X�g�[�ɂ��Ă�������i�߂Ă����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���T���\���A���K�X�Ȃǂ������\�K�X�����ȈՊї����C�{�C�����J���` �O�ʒu����ŏȃG�l�` ���e�ʂ̊ȈՃ{�C���́A����܂ŔR�ėʂ�100����0���i�^�]��~�j��2�i�K�Ő��䂷��V�X�e���iON/OFF����j���̗p����Ă���A���C�̎g�p�ʂ����Ȃ��Ȃ��100����0���̉^�]���J��Ԃ��ď��C�ʂ����Ă����B�{�C���́A��~��A�ċN������ہA���S�̂��߂Ƀ{�C���̘F�������C����K�v������A���̎��A�M���{�C���O�ɔr�o����邽�ߔM��������������B �J�������V�^�{�C���́A�R�ėʂ�100���A50���A0����3�i�K�Ő��䂷��R�ĎO�ʒu�����V���ɍ̗p�����B����ɂ��A���C���ׂ�100�`50���܂ł�100����50���^�]�ɂ���āA���ׂ�50���������ꍇ��50����0���^�]�ɂ���ď��C�ʂ����邽�߁A�]���@�����A�{�C���^�]�����̒ቺ��Ⴍ�}����B�܂��A�R�ăK�X�t���[�����ǂ��ĐڐG�`�M�ʂ����コ�����V�^�ʑ̐v�ɂ���i���̃{�C���^�]������90���܂ŃA�b�v�������B�����̌��ʁA�{�C���^�]�������]���@����7������i50�������j�����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����d�H�A������g������R�X�g�o�C�I�R�������Z�p���m�� ���Ђ́A�H�c���_�ƌ��ЂƂƂ��ɔ_���Ȃ̌��厖�Ɓu�\�t�g�Z�����[�X�����p�v���W�F�N�g�v�Ɏ��g��ł����B��H�p�o�C�I�}�X�ł�����炩���R�X�g�o�C�I�G�^�m�[��������V�Z�p�u�M�����o�C�I�G�^�m�[�������Z�p�v���m�������B���Z�p�́A�o�C�I�G�^�m�[���������؎����̈���̓����H���ɂ����āA�M���݂̂œ����������s�����Ƃ��ł�����̂ŁA�����E�o�ϐ��ɗD��Ă���̂������B�܂��A�M���̏�����ύX���邱�Ƃɂ���āA����ȊO�̃\�t�g�Z�����[�X�̓����������\�B 2009�N11���ɂ́A�H�c������s�ɓ��Y200���b�g���̐��Y�\�͂����������v�����g��v�E���݂��A2010�N10���ɂ͏H�c���̑劃���\�[���[�X�|�[�c���C���ŁA���v�����g�Ő��������o�C�I�G�^�m�[�����g�p���������Ԃ̑��s���؎����ɐ����B ���̌���A����̑O�����A�����A���y�A��������і������܂ň�т������v�����g��A���ғ������AJIS�ɓK�������o�C�I�G�^�m�[�������肵�Đ����\�ł��邱�Ƃ��m�F���A���ƋK�͂�1���b�g��������40�~�̐����R�X�g����������o�C�I�G�^�m�[���̐����Z�p���m�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ƒ�̓d�͏���ʁA���Ă�2.7�������� 2012�N�Ċ��̉ƒ�ɂ�����ߓd�ECO2�팸�s���ɂ��āA�C���^�[�l�b�g�ɂ��A���P�[�g�������s�������ʂ����܂Ƃߌ��\�����B���Ẳƒ�̓d�͏���ʂ́A2011�N�Ċ��Ɣ�ׂ�2.7���팸�ƂȂ�A����͉ƒ�ꐢ�ѓ������CO2�r�o�ʂ̖�1�����̍팸�ɑ������邱�ƂȂǂ��킩�����B 2012�N�Ċ��ɐߓd�������ӎ����Ă������т͑S�̂�32���ŁA�k�ЈȑO��11���Ɣ�ׂ�21�|�C���g�������Ă���A2011�N�̓������ƂقƂ�Ǖς��Ȃ������B �k�Јȍ~�A��2���̐��т��ȃG�l�E�ߓd�̂��߂ɐ�@���w����������ŁA���̐��т���[�̉��K����}���Ă����B �k�Јȍ~�ɏƖ������v���ȃG�l�^�C�v�ւƌ����������т͑S�̂�44���A�ł����������ւ����E�w�������@��͐�@�i3���j�ŁA�����Ńe���r�i1.5���j�A�G�A�R���i1���j�A�①�Ɂi1���j�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������ʃK�X�̔r�o������|���{�u2���ԁv�Ɋ��H ���{��2���Ԃōs���r�o��������x�u2���ԃI�t�Z�b�g�E�N���W�b�g���x�iJCM�^BOCM�j�v�̐��i�ɗ͂����Ă���B���{���r�㍑�Ɋ��Z�p��i�Ȃǂ���ĉ������ʃK�X�̍팸���x���������ɁA�팸�ł����������ʃK�X�̔r�o�g���擾�ł��鐧�x���B����܂łɃ����S���ƃo���O���f�V���Ƃ̊ԂŎ��{�ɍ��ӂ��A�������ʃK�X�팸�̗L���Ȑ�D�Ƃ��ăA�W�A�𒆐S�ɓW�J���Ă������j���B 2���ԃI�t�Z�b�g�E�N���W�b�g���x��ʂ��Ă킪���̊�Ƃ����D�ꂽ�Z�p�����A�r�㍑��CO2�팸�����J�E���g���Ă��������Ɗ����́AJCM�^BOCM�̗L�p�����A�s�[�������B ���s�c�菑�̑�2���ԁi2013�\20�N�j�ւ̎Q���������������߁A�u�N���[���J�����J�j�Y���iCDM�j�v�̊��p�͐������邩�炾�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����C����CO2�ʂ����j�I������˔j�A���Ƃ炪�s�����Ăт��� �ăn���C�B�}�E�i���A�ɂ���C�m��C�ǂ̊Ď��Z���^�[���C���^�[�l�b�g��Ō��\�����f�[�^�ɂ��ƁA�����m��̓��ԕ���CO2�ʂ́A5��9����400.03ppm���L�^�B�܂��A�ăT���f�B�G�S�̃X�N���b�v�X�C�m�������́A400.08ppm��CO2�ʂ��ϑ������B �C�ۊw�҂�́A���̐ߖڂ͏ے��I�Ȃ��̂ŁA�����꒴���邱�Ƃ͗\�z����Ă����Ƙb���Ă���B�������A���ΔR���̑�ʎg�p�ɂ�菝����ꂽ����������K�v������Ƃ̏d�v�ȃ��b�Z�[�W���Ƃ����B ��C����CO2�ʂ́A�l�ނ����݂���͂邩�ȑO��300���`500���N�O����400ppm�������Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�����̒n���́A���݂��C�������x�����A�C���ʂ�20�`40���[�g�����������Ɛ��肳��Ă���B �p�����h����w�o�ϐ����w�@�O�����T���C��ϓ����������̃{�u�E���[�h�����S�������́A�u����ꂪ���A���ݏo������̂͐�j����̋C��ł���A�l�ԎЉ�͖c�傩�j�œI�ȉ\�����߂����X�N�ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�v�Əq�ׂ��B �o�T�u�`�e�o�v |
|
|
| ���Y�����A�Z�F���w���ċG�Ɠ~�G�ő��z�����������߂���ȃG�l�����V�[�g ���̒����V�[�g�́A�ċG�Ɠ~�G�ő��z���̓��ˊp���ω����邱�Ƃ𗘗p���āA�S���ˌ��ۂɂ���ĉĂ͑��z�����Օ����A�~�͓��߂�����B���̒����V�[�g�ƈقȂ�A�O���̌i�F�͏�Ɍ�����ɂ�������炸�A���B���˂̓��߂𐧌�ł���B�܂��A�����V�[�g���g�͉����ω����Ȃ��ɂ�������炸�A�G�߂ɂ���Ď����I�ɒ����ł���Ƃ��������������Ă���B �����̑��ɂ��̃V�[�g��\�邾���Œ������ł��邽�߁A�����悭�����ł���A��g�[���ׂ�傫���ጸ���邱�Ƃ̂ł���ȃG�l�V�[�g�Ƃ��Ċ��҂����B ���������V�[�g�́A���ʂ̊W�ɂ��铧���V�[�g��2�����킹���\���������A���K���X�ɂ��̃V�[�g��\��t����ƁA�i�F�ɑ��Ă͏�ɓ����ɂ�������炸�A���x�̍����Ă̑��z���͎Օ����A���x�̒Ⴂ�~�̑��z���͓��߂���Ƃ����ω������R�ɋN����B �Y�����ł́A�����̂̊E�ʂł̑S���ˌ��ۂ�p���邱�ƂŁA���z���̓��ˊp�̈Ⴂ�Œ����ł���K���X�������ł���ƍl���A���z���̔��ˁE���߂���͂����p�̃v���O�������J�����č\���̍œK�����s���A�i�F���炭����͂ł��邾�����߂����A�ċG�̒��B���˂��ł��邾���Ղ邱�Ƃ̂ł��钲���V�[�g�̍\���������������B ���̍\���������������V�[�g�����p������ɂ́A���ۂ̓����V�[�g���ǂ̂悤�ɉ��H���邩�����ɂȂ邽�߁A���̉��H�Z�p�ɂ��ċ��݂����Z�F���w�ŊJ�����s���A�v���g�^�C�v�̑S���˒����V�[�g�̍쐻�ɐ��������B �o�T�u�Y�����v |
|
|
| ���@�@[�@2013/6�@]�@�@�� |
|
|
| �����{�����A�{�C���[�ł̖؎��o�C�I�}�X�R���̍��ė����グ��V�Z�p���J�� ���{�����́A�؎��`�b�v��؎��y���b�g���Ƀg���t�@�N�V�����i���Y���j�Z�p��p�����V�K�o�C�I�}�X�Ō`�R�����J�������B���R���́A�ʏ�̒Y���ł͔����ȉ������c��Ȃ��M�ʂ��9���c�����Ƃ��ł��A�����ĕ��Ӑ��A�ϐ��������サ�A�����Y�{�C���[�ł̃o�C�I�}�X���ė���啝�Ɍ���ł���\��������B �����Y�{�C���[�ō��Ď��������{�������ʁA�ő啉��25���i�d�ʔ�j�̐V�K�o�C�I�}�X�Ō`�R�����������A�ΒY�����Ӑݔ��̑��Ɛ��A�{�C���[�̔R�Đ��ɖ�肪�Ȃ����Ƃ��m�F�����B �ߔN�̐ΒY�Ἠ{�C���[�́A�R�Č��������߂������Y�{�C���[���嗬�ŁA���Ђ��܂ߊe�Ђ�CO2�����ʒጸ�̂��߁A�؎��o�C�I�}�X�R���̍��Ă�i�߂Ă���B�������A�����̔R���͌����I�ɕ��ӂł��Ȃ����Ƃ≮�O�ۊǎ��̑ϐ����Ȃǂ��ۑ�ƂȂ�A�����Y�{�C���[�ł̍��ė���2�`3�����x�ɂƂǂ܂��Ă����B �Ȃ��A�g���t�@�N�V�����́A�R�[�q�[�������ɗގ�����Z�p�B��r�I�ቷ�Ŗ؎��o�C�I�}�X��Y�������邱�ƂŁA�ʏ�̒Y�����M�ʂ�啝�Ɏc�����Ƃ��ł���B����ɁA�y���b�g�����邱�ƂŁA�؎��`�b�v�R���ɔ�ׂėe�ς��������A�A�������������シ��B �u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������d�͂̎�����d�͌v�V�X�e���A���ŁE�m�d�b�����D �����d�͂́A2015�N�x����{�i�^�p���鎟����d�͌v�u�X�}�[�g���[�^�[�v�Ɋւ��A���ł�m�d�b�������J������ʐM�V�X�e�����̗p����Ɣ��\�����B �C���^�[�l�b�g�ɂȂ��œd�͏���Ȃǂ̃f�[�^������肷�钆�j�V�X�e���ŁA14�N�x���ɓ�������B�����z�͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ����A���S���~�Ƃ݂���B���d��14�N�x����X�}�[�g���[�^�[�̐ݒu���n�߁A23�N�x�܂łɊǓ��̑S2700�����тɓ������I����v��B�S�̂�3�牭�~�K�͂̎s��ɂȂ�Ƃ݂���B���̑O����ƂȂ鍡��̒ʐM�V�X�e���͌���̌`�ō����O�̓d�@�E���ʐM�֘A��Ƃ��畝�L����Ă����Ă����B �����͓̂��łƂ��̎q��Ђł��郉���f�B�X�E�M�A�ANEC�ANTT�h�R���Ȃǂ̊�ƘA���B���[�^�[�[���͍��H�ɒ��B����������D�őI�肷��\��B �u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���H��ɂ͖��ʂȔp�M�������A�ቷ�ł�150kW�̔��d���\ �ȃG�l���M�[�Z���^�[����������2000�N�x�́u�H��Q�̔r�M���Ԓ����v�ł́A100������500���܂ł̒ቷ�r�M�̂����A300�������̒ቷ�r�M�̗��p�������ɒႭ�A�N��20��T�J�����[���̔M�����̂܂ܑ�C���Ɏ̂Ă��Ă���B�Ǝ�ʂł͉��w�A�S�|�A�@�B�A���|�i�H��j�A���p���v�ɔp�M�������B �o�ώY�ƏȂɂ��A�����̖����p�M�G�l���M�[�̍��v�͔N��1��kWh�ɒB����Ƃ����B����͔N�ԑ����d�ʂƓ������̃G�l���M�[�����ʂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B ���̂悤�ȃ��_���Ȃ��N����̂��B1�͌����I�Ȗ�肾�B�M�G�l���M�[��S�ēd�C�G�l���M�[�ɕϊ����邱�Ƃ͂��������ł��Ȃ��B����ɁA150�������̔M��9���ȏオ���������������Ƃ����Ă���B����͊�Ƃ̈ӎ����Ⴂ���߂ł͂Ȃ��A����Z�p�������B�����炾�B �������D�́A300�����x�̔p�M�������ǂ��d�͂ɕϊ����鑕�u�̎��v�����g�����m���|�̋��͂āA�������J�n����B�Z�p�́A��ʂɃo�C�i���[���d�ƌĂ�Ă���Z�p�ɑ�������B�L�@�n�}�ł���V���R�[���I�C���𗘗p���ĔM��������邽�߁A����������80���ȏ�ɂȂ�Ƃ����B��150kW�̔��d���v�悵�āA�v�����g���̂͐�m�p�Ə�������p��}���邱�Ƃ��\�ł���B �u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ���鍑�z�e���ɖ���G�l���M�[�A�r���Ȃ�ł͂̏����͔��d �鍑�z�e���^���[����5�K�ŗ��p�����@�p�̐��͒n��4�K�̗␅�~�M���܂�35m�𐂒��ɗ��ꗎ����B�~�M������5�K�܂ł̓|���v���g���Đ������ݏグ�Ă��邪�A���ꗎ���鐅�ɂ͂���܂ŊS�������Ă��Ȃ������B ���Ђ́A�V���{�ɏ����͔��d�p�̔��d�@�A����ՁA���䑕�u�ȂNj@��ꎮ�̐v�ƁA�{�H���˗��B�o��3kW�̏����͔��d�����������B�N��1��5000kWh�̔��d�������ށB�ݔ���24����365���ғ����Ă��邽�߁A���肵���d�͌��Ƃ��ė��p�ł���B�n���Ƃ��A�n���Ă���A���܂��܂ȗp�r�Ɏg����Ƃ����B �d�C�������Z�ŔN��24���~�ACO2�r�o�ʍ팸��5.6�g���Ƃ��������͈ꌩ�����������邪�ALED�Ɩ��ւ̒u�������Ȃǂ��܂��܂ȏȃG�l��Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�r���̏���G�l���M�[���������ɖ𗧂B �u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ����ʌ��Ƀz���_�̐V�H��FEMS�⑾�z�����d�A���T�C�N���ȂǂŊ��֔z�� ���݂ɂ������ẮA�]���̂ĂĂ����M��V���ɒg�[�p�̔M���Ƃ��ăq�[�g�|���v�Ⓚ�@�ɗL�����p���邱�ƂŁA�]���̃{�C���[�M���݂̂Ɣ�r����CO2���60���ጸ�A�~�n�ʐς�30���̗Βn�ɖ�1.6���������[�g���̃r�I�g�[�v��ݒu����ȂǁA�G�l���M�[�����̌������ƃ��T�C�N���A�������l���ɔz���������̍����r�I�g�[�v�A�Ή��ւ̎��g�݂��s�� ���̑��̎��g�݂́A�G�l���M�[�����̌������ƃ��T�C�N���ŁA�G�l���M�[�̎g�p��ݔ��̉^�]��Ԃ��Ď����A�ڕW�Ǘ���ُ탊�X�N�̑���s�����Ƃ��ł���G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���uFEMS�v�����A�G�l���M�[�̈��苟����CO2�ጸ�Ɋ��p�B�]���^�̎�����ԑS�̋ɑ���A�l��Ƌ�Ԃ݂̂�����C���V�X�e�������邱�ƂŁA�G�l���M�[���]�����������40���ጸ�B2.6MW�̃\�[���[���d���u�̐ݒu�ɂ��CO2�r�o�ʖ�1,200t/�N��ጸ�B���T�C�N���\�ȍH�@�⌚�ނ��g�p���邱�ƂŁA�����̃��C�t�T�C�N�����T�C�N����98���ȏ��B���߂����B �u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���h�C�c��Ƃ�����܂łɂȂ����僁�K�\�[���[�茧�Ɍ��ݗ\�� �v�悵���̂̓h�C�c�̑��z�����d���Ǝ�Photovolt Development Partners�ŁA���[���b�p��13�̃��K�\�[���[�����݂������т̂����ƁB ��B�����̌ܓ��̖k�[�̉F�v���ɏo��475MW�̃��K�\�[���[�����݂���B���K�\�[���[�͕����̃u���b�N�ɕ����ꂽ�`�Ō��݂���B��50km���ɗ��ꂽ�{�y�Ƃ̊Ԃ��A��R�����̏������C�ꍂ�d���������d�P�[�u���Őڑ����A��B�d�͂ɔ��d����v�悾�B������ԂƂ���20�N��\�肷��B 2015�N����2016�N�ɂ����Ĕ��d�J�n��\�肵�Ă���B ���Ђ͉F�v���ȊO�ɂ�����8�J���ō��v450MW���̃��K�\�[���[���v�撆���B�k�C���A�{��A�����A�ȖA��t�A����A�L���A�F�{�ւ̗��n��\�肷��B2014�N����2015�N�ɂ����đ��d���J�n����\�肾�B�F�v���ƍ��킹��ƍ��v925MW���̃��K�\�[���[�Q���������邱�ƂɂȂ�B �u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
| ������LED�����v��p����GX16t-5��JIS�K�i������둕���Ȃǖh�~ ���nj`LED�����v�́A�������]���̒��nj`�u�������v�Ɠ������̂�����A�ꕔ�̎g�p�҂Ɍu�������v�̒��ړI�ȑ�֕i�ł��邩�̂悤�Ɍ�F����A����ɋN���������������Ă���B �܂��ALED�����v�̐����Ǝҋy�є̔��Ǝ҂̒��ɂ́A�Ɩ����u�ɑ�����S���y�ѐ��\�ɑ���F�����K�������\���łȂ����Ƃ���A���i�ւ̋����������Ă���B�����ŁA�g�p�E����҂̈��S������A�ȃG�l���\�̗D�ꂽLED�Ɩ��̔��W�E���y�̊ϓ_����A�{�K�i�𐧒肵���B ���݂̂Ƃ���A����LED�����v�́A�d�C�p�i���S�@�̑ΏۊO�����A����LED�����v���p�Ɏg�p������̂�LED�Ɩ����Ƃ��ēd�C�p�i���S�@�̑ΏۂƂȂ�B �܂��A����LED�����v�̍��ۋK�i�Ƃ��ẮAIEC 62776����������Ă��邪�A���̋K�i�����Ɏ������ƁA���S��̏d��ȏ�Q�ƂȂ�\���������B�����ŁAIEC 62776�̐R�c�ɎQ�����A���{�̎���f�ɖ��߂�ƂƂ��ɁA�{JIS��IEC�i���ۓd�C�W����c�j�ɒ�Ă��A���ەW������i�߂Ă���B �u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������s�̔r�o�ʍ팸�`�����A15���`17����2015�N�x����K�p �����s�́A���m�ۏ��Ɋ�Â��u�������ʃK�X�r�o���ʍ팸�`���Ɣr�o�ʎ�����x�v�̑�2�v����ԁi2015�N�x�`2019�N�x�j�ɂ�����팸�`�����������肵���\�����B ��K�͎��Ə��ւ̑�2�v����Ԃ̍팸�`�����i2015�`2019�N�x�̕��ρj�́A��r�o�ʔ�i�����F2002�`2007�N�x�܂ł̂����ꂩ�A������3�J�N�x���ϒl�j�ňȉ��̒ʂ�B �y�敪�T-1�z�I�t�B�X�r�����ƒn���g�[�{��17���i��1�v�����8���j �y�敪�T-2�z�I�t�B�X�r�����̂����A�n���g�[���𑽂����p���Ă��鎖�Ə�15���i��1�v�����6���j �y�敪�U�z�敪�T-1�A�敪�T-2�ȊO�̎��Ə��i�H��A�㉺���{�݁A�p���������{�ݓ��j15���i��1�v�����6���j �A���A���ʂ̔z���Ƃ��āA(1)������Ɗ�{�@�ɒ�߂钆����Ǝ҂�1/2�ȏ�����L�����K�͎��Ə����ɑ��ẮA�`���̑ΏۊO�Ƃ���B�A���A��v��̒�o�����߂�B(2)��2�v����ԂɌ���A��Î{�݂�Љ���{�ݓ���4���ɁA�Ⓚ�①�q�ɂ�q��ۈ��{�ݓ���2���ɍ팸�`�������ɘa����B(3)��2�v����Ԃ���V���ɍ팸�`���ΏۂƂȂ鎖�Ə��́A��P�v����ԂƓ����̍팸�`�����i8������6���j��K�p����B �܂��A�D�Ǔ���n�����g���Ə��i�g�b�v���x�����Ə��j�Ƃ��āA�s����߂�F���i�F����2013�N���ɉ���j�ɓK������ƔF�߂�ꂽ�Ƃ��́A���Y���Ə��ɓK�p����팸�`������1/2����3/4�Ɍ�������B 2011�N�x�����_�ł̑ΏۂƂȂ�s����K�͎��Ə���1392���A���̂����I�t�B�X�r������1168���A�H�ꓙ��224���ƂȂ�B http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/04/20n48200.htm �u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���O���[���������ł�2�N�����A���@�퓱���Ŗ@�l�ł�啝�ߖ�R�W�F�l��~�d�r���Ώۂ� ���Ǝ҂��������ȏȃG�l�E��Y�f�ݔ���Đ��\�G�l���M�[�ݔ��������Ƃ��ɁA�Ő��D���[�u������O���[���������Łi�G�l���M�[�����גጸ���i�Ő��j�ɂ����āA4��1�����A�������p�̑Ώېݔ��ɔM�d�����^���͔������u�i�R�[�W�F�l���[�V�����ݔ��j���lj����ꂽ�ق��A�K�p���Ԃ�2�N�������ꂽ�B �K�p���Ԃ̉����ɂ��A����25�N4��1�����畽��28�N3��31���܂ł̊��ԓ��Ɏ擾���āA���̓�����1�N�ȓ��Ɏ��Ɨp�Ɏg�p�����ꍇ�A���̎��ƔN�x�ɂ����ē��ʏ��p���ł���B�܂��A���z�����d�ݔ��A���͔��d�ݔ��A����lj����ꂽ�M�d�����^���͔����ݔ��ɂ��ẮA����27�N3��31���܂ł̊��ԓ��Ɏ擾���āA���̓�����1�N�ȓ��Ɏ��Ɨp�Ɏg�p�����ꍇ�A���̎��ƔN�x�ɂ����đ������p���ł���B �܂��A�Ώېݔ��ɒ�u�p�~�d�ݔ�����������ƂƂ��ɁA�Ώېݔ�����⏕���̌�t���Ď擾���������̂����O���铙�̌��������s��ꂽ�B �O���[���������ł́A�F�\�������o����@�l���͌l���Ǝ҂��A�O���[���������őΏېݔ����擾���A���P�N�ȓ��Ɏ��Ɨp�Ɏg�p�����ꍇ�ɁA 1.�擾���z��30�����ʏ��p�i�ꕔ�̑Ώېݔ��ɂ��Ă͑������p�j 2.7���Ŋz�T���i������Ǝғ��̂݁j �̂����ꂩ��I�����Ő��D�������鐧�x�B�O���[���������ł̓K�p�Ώېݔ���31�ݔ��B http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/green-list.html �u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2013/5�@]�@�@�� |
|
|
���O�Y�H�ƍ������́u�K�X�������^�ї����C�{�C���v�� �����K�X�A���K�X�A���M�K�X��3�ЂƋ����ŊJ�������B�K�X�����{�C��SQ�V���[�Y�́A�R�Ď��������Ȃ��m���t�@�[�l�X�ʑ̂ƁA��^�\�����o�[�i�ɂ�铯�ГƎ��̐V�R�ē`�M�V�X�e���𓋍ڂ��Ă���̂������ŁA�G�R�m�}�C�U�\���̉��ǂɂ���ē`�M�ʐς������A�r�K�X����̔M����ʂ���10�����サ�����ƂŁA�{�C������97����B�����Ă���B �܂��A�{�C���R�ĕ��̋�C�ʂƃK�X�ʂ�����قƍ\�������ǂ��A�^�[���_�E����i�Œ�o�͂ƒ�i�o�͂̔�j���]����1�F2����1�F4�ɂȂ������ƂŁA��o�͎��ł��R�Ă����肳���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���ח�30�����ł̎��ۂ̉^�]������3�����サ�Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
���u�g�b�v�����i�[�v�Ɍ��z�ޒlj��ȃG�l�@�����Ď��Ɣ����i��� ���ƂȂ�̂́A�G�l���M�[��������̌�������߂�u�g�b�v�����i�[���x�v�̑ΏۂɁA�f�M�ނȂnj��z�ޗ��̐V�K�lj��ƃs�[�N���̓d�͎��v�}�����㉟�������̓������B �o�ώY�ƏȂł́u���z�ނ̏ȃG�l���\���オ��A�Z���r���ł̃G�l���M�[���p��ጸ�ł���v�Ƃ݂Ă���B�@�Ă��������ꎟ��A�ΏۂƂȂ錚�z�ނ̎�ނȂǏڍׂ̌����ɓ���v��B ����A�s�[�N���̓d�͎��v��}�����邽�߁A��ƂȂǂɎ��Ɣ��d�Ȃǂ̊��p�𑣂����߂̎d�g�݂�����B�����Ăł́A�s�[�N���ԑтɎ��Ɣ��d�Ȃǂ����p�����ꍇ�A�G�l���M�[�g�p�ʂ���葽���팸�����ƔF�肷��B���Ɣ��d�̂ق��A�~�d�r��A�Z���T�[��h�s�i���Z�p�j�̋Z�p�����p���ĉƒ���̃G�l���M�[������Ǘ�����uHEMS�i�z�[���E�G�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���j�v�̊��p��z�肵�Ă���B�o�Y�Ȃ́A�����ĉғ��ȂNj����ʂł̑�ƏȃG�l�Ȃǂɂ����v�ʂł̑���G�l���M�[�������艻�̗��ւƈʒu�Â��Ă���B �o�T�uSankeiBiz �v |
|
|
�������A�X�}�[�g�O���b�h�����Ɍn���d�����艻�Z�p��V�J�� �������쏊�́A�Đ��\�G�l���M�[�̓����ɍۂ��Đ��E�I�ȉۑ�ƂȂ��Ă���n���d���̈��艻�A�Ȃ�тɐV�����ɂ�����d�͌n���̈���^�p��ړI�Ƃ��āA��R�X�g�Ŋg�����ɗD�ꂽ�n���d�����艻�Z�p���J�������Ɣ��\�����B �{�Z�p�́A�����̔z�d�n����ɂ��鎩���d��������(SVR)��Î~�^�����d�͕⏞���u(SVC)�Ȃǂ̊e�@��̓d���E�d�����A�n�����ʐM�l�b�g���[�N��p���Čv�����A����Ɋ�Â��n���S�̂̓d���𐄒肵�A�\�ߐݒ肵���ڕW�l�Ƃ̕�����������悤�Ɋe�@��̓d���U�I�ɐ��䂷��Z�p�B �����̔z�d�n���ł́ASVR��SVC�Ȃǂ̓d�������@����ʂɐ��䂵�āA�d�����K��͈͓��Ɉێ����Ă���B����A�z�d�n���ɑ��z���╗�͓��̍Đ��\�G�l���M�[����ʂɓ��������ƁA�V��ɂ�蔭�d�ʂ��傫���ϓ����A�K��d���̈�E���z�肳���B ����A�v�������e�@��̓d���E�d������n���S�̂̓d���𐄒肷��@�\(��Ԑ���@�\)�ƁA���̋@��̓���𐄒肵�ēd�������ʂ��œK�z������@�\(���萧��@�\)����\�������A��搄�蕪�U����Z�p���J�������B �{�Z�p�ɂ��A�z�d�n���ɂ�����G���A���Ƃ̍Đ��\�G�l���M�[�̓����ɍ��킹���i�K�I�Ȑݔ��������\�ƂȂ�A�d�������@����W���I�ɐ��䂷����������ȃR�X�g�Ōn���d���̈��艻�������\�ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����~�̍ő���v��3.6�`8.2�������A���{���z�肵���u�蒅�ߓd�v�����g�� �d�͂̎�����������ψ���J���ꂽ�B�k�C�������B�܂�9�d�͉�Ђ̍��~�̍ő���v�͐k�БO��2010�N�x�Ɣ�ׂČ������������B�������ł͊���8.7�����ő�ŁA������3.6�����ŏ��������B ���~��9�d�͉�Ђ̓d�͎���������ƁA�e�n��Ƃ��ɗ]�T�̂��������Ƃ����߂Ė��炩�ɂȂ����B�ő���v�ɑ��鋟���̗͂\�����́A�����d�͂��ł��Ⴍ��5.4���������B����Ő����{�̊e�n��͌����ݗ\������������ԂŁA�����d�͂ł�16.7�����������قǂ��B �\������3���������Ɠd�͕s���̊댯�������܂�B���~�͋�B���ł���������3����ɂȂ�Ɨ\�z����Ă����B�k�C���ł�5����܂ʼn�����\�����������A���ۂɂ�9.9�����ł��Ⴍ�A�����͋ɂ߂Ĉ��肵�Ă����ƌ�����B ����قǓd�͂̎����ɗ]�T�����܂ꂽ�ő�̗v���́A�d�͉�Ђ�{�̗\���������Đߓd���ʂ��������ꂽ���Ƃɂ���B�ߓd���ʂ𑪂邤���Ŕ�r�ΏۂɂȂ�̂��k�БO��2010�N�x�ł���B2�N�O�̓~�Ɣ�ׂ�ƁA�e�n��Ƃ��ő���v�͒����Ɍ����Ă���B �ł��啝�Ɏ��v�����������̂͊���8.7���ŁA�ŏ��͒�����3.6�����B������̒n��̌����������Ă��A��N�̈ψ���u�蒅�����ߓd�v�Ƃ��đz�肵�����l�����傫���B�u�蒅�ߓd�v�ɂ����v�̌������͔N�X�傫���Ȃ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�G�i�W�[�v |
|
|
�����{���ƘA����k�d�c�Ɩ����Ɋւ���@�K�E���ӓ_�����܂Ƃ߂� ���Y�ψ���ݔ�������{�H��啔��ł́A�}���ɕ��y���i��ł���uLED�Ɩ����v�Ɋւ���@�K���y�ђ��ӓ_�����Z�߂܂����B LED�Ɩ����́AJIS���͂��߂Ƃ���K�i������A�@�����͐i��ł��邪�����̏�ԂƂ͌����Ȃ��B�ڍׂ͉��LPDF���Q�ƁB LED�Ɩ����Ɋւ���@�K��http://www.nikkenren.com/rss/pdf/376/LED_law.pdf LED�Ɩ����Ɋւ��钍�ӓ_http://www.nikkenren.com/rss/pdf/376/LED_attention.pdf �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
�������G�l���A�G�l��{�v�����ɒ���N���߂� �����ǂ������_�_�ł͓����{��k�ЂƓ����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̌�̊��ω��܂��A���Y�E���ʁE����̊e�i�K�ɕ������ۑ���B�d�͎�����o�b�N�G���h���܂ސ���c�_��ΏۂƂ����B��͓��ʌ��P����x�J�Â��A�N�����߂ǂɂƂ�܂Ƃ߂�B �ψ�����́u���q�͂̃V���O���C�V���[�i�P����j���������ׂ��v�u�o�b�N�G���h�̋c�_�͕s���v�u�Z���ƒ������̐�����čl����ׂ��v�Ȃǂ̈ӌ���A�u�����̓����ɕK�v�ȗ\�������l�����Ƃ��A���̃r�W�����������ׂ��v�Ə������̖��m�������߂鐺���������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
��IPCC��T���]������ƕ�����E�������쐬�X�P�W���[�� IPCC�͐ݗ��ȗ��A�����̊j�Ƃ��āA5�`6�N���ɂ��̎��X�̋C��ω��Ɋւ���Ȋw�I�m�����Ƃ�܂Ƃ߁A�]�����s���A���̌��ʂ��܂Ƃ߂��uIPCC�]�����v�̔��\���s���Ă���B2008�N4���̑�28��IPCC����i�u�_�y�X�g�j�ɂāA��5���]�����̍쐬�����肵�A���̌�A2��̑���ƁA���Ƃɂ��X�R�[�s���O����o�āA2009�N10���̑�31��IPCC����i�o���j�ɂāA�e��ƕ�����̍��q�����肵�A2010�N10���̑�32��IPCC����i���R�j�ɂāA�������̍��q�����肵���B �e��ƕ�����y�ѓ������̊����E���\�\�莞���͈ȉ��̂Ƃ���B �EWG1���F 2013�N9���X�g�b�N�z�����E�X�E�F�[�f�� �EWG2���F 2014�N3�����l�E���{ �EWG3���F 2014�N4��TBC�E�h�C�c �E�������F 2014�N10���R�y���n�[�Q���E�f���}�[�N ���F�ύX���������߁A�s�x�AIPCC�E�F�u�T�C�g���Q��http://www.gef.or.jp/ipcc/AR5/3WGs+SYR_schedule.html �o�T�u�n���E�l�Ԋ��t�H�[�����v |
|
|
���і쒡�A�_�ѐ��Y�i�Ȃǂƌ����ł���u�؍ޗ��p�|�C���g�v���Ƃ��J�n �n��ނ̓K�ȗ��p���m�ۂ��邱�Ƃ́A���{�ɂ�����X�т̓K���Ȑ����E�ۑS�A�n�����g���h�~�A�z�^�Љ�̌`�����ɍv�����邱�Ƃ���A���Y�ނ��̑��̖؍ނ̗��p���i��}�邱�Ƃ��d�v�ƂȂ��Ă���B �����ŁA�n��ގ��v��傫�����N�����Ƃ��āA�؍ނ̗��p�ɑ��|�C���g��t�^���A��ꎟ�Y�Ƃ��͂��߂Ƃ����n��Y�ƁA�Ђ��Ă͌o�ϑS�̂ւ̔g�y���ʂ��y�ڂ����g�݂ւ̎x����ړI�Ɏ��{����B�T�v�͈ȉ��̂Ƃ���B �؍ޗ��p�|�C���g�̕t�^�Ώۂ́A�n��ނ���ȏ㗘�p���邱�ƁA�����ʂɈ��e����^���Ȃ����Ɠ��̏����������Ɍf������́B �@�ؑ��Z��̐V�z�E���z���͍w���A�A�Z��̏��A���Njy�ъO�ǂ̖؎����H���A�B�؍ސ��i�A�؎��y���b�g�X�g�[�u���؍ޗ��p�|�C���g�̐\���́A�|�C���g�̕t�^�ΏۂƂȂ鐻�i�̏��L�ғ����A�X�����͊e�n�ɐ݂�����\�������ɂčs���B�؍ޗ��p�|�C���g�́A�n��̔_�ѐ��Y�i�A�_�R�����̌��^���s�A���i���A�X�тÂ���E�Â����ɑ���A�����������Ɍ����ł���B ���Ƃ̏ڍׂɂ��ẮA���܂莟��A���\�����B�܂��A����A���Ǝғ������̐�������J�Â��邱�Ƃ�\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�������s�̎��Ə����e�i���g�r���ɓ�������ۂ̊�Ƀr���̒�Y�f���x����V�݁B �\��Y�f�r�����]�������s���Y�s��̌`����ڎw���ā\ �s�́ACO2�r�o�̏��Ȃ���Y�f�r���Ɋւ���]����i��Y�f�r���x���`�}�[�N�j���쐬���A��Y�f�r���̕��y�𑣐i���Ă����B ��Y�f�r���̂���Ȃ镁�y��}�邽�߁A�e�i���g�r���ɓ�������ۂ̐�����Ƃ��āA�u��Y�f�r���x���`�}�[�N�敪��A1�����W�ȏ�v���A�����s�O���[���w���K�C�h�ɐV�݂��邱�Ƃɂ����B������������s���ɂ��A�e�i���g�r����I�肷��ۂ̈�ʓI�ȑI���Ƃ��Ē�Y�f�r���x���`�}�[�N�̒蒅��ڎw���A��Y�f�r���������]������s���Y�s��̌`���𑣐i���Ă���B �u��Y�f�r���x���`�}�[�N�v�́A�n�����g���������o���Ă����2,000�̃e�i���g�r���ɂ��āA�����ʐς������CO2�r�o�ʂ�7�i�K�ɋ敪���āA�r���̒�Y�f���x�������������́B�i���ό��P�ʈȉ��ƂȂ�A1�����W�ȏオ�ACO2�r�o�ʂ̏�������Y�f�r���̖ڈ��ƂȂ�B�j �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
���C�ے�������{��ΏۂƂ���ڍׂȒn�����g���\���ɂ��� �`�u�n�����g���\������W���v�̌��\�` �C�ے��́A�V���ɊJ�������ڍׂȋC�f���ɂ��A���{��ΏۂƂ���n�����g���\�������{���A���{��ΏۂƂ���ڍׂȒn�����g���\���ɂ��ā`�u�n�����g���\������W���v�����\�����B ��Ȍ��ʂ̊T�v�́A�ȉ��̒ʂ�B �E�N���ϋC����2.5�`3.5���㏸����B�ҏ����̓����͑S���I�ɑ�������B �E1���ԍ~����50�~���ȏ�̒Z���ԋ��J�̔����p�x���S���I�ɑ�������B �E�N�~��ʂ͌�������B���~���̖k���{�ł́A���g�����i�s���Ă��ˑR�Ƃ��ĐႪ�~��̂ɏ\���Ȓቷ�ł��邽�ߍ~��ʂ̕ω��͏������B �ȏ�̂ق��A�~����M�і�̓����A���~�����̓����A���Ύ��x���̕ω��ɂ��Ă��\���̑ΏۂŁA�ڍׂȗ\�����ʂɂ��ẮA�C�ے��z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���Bhttp://www.jma.go.jp/jma/press/1303/15a/gwp8.html �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2013/4�@]�@�@�� |
|
|
���x�m�d�@�ȂǁA�����͂�ȃz�e���Ńr���G�l���M�[�̍œK�������� �x�m�d�@�A�É͓d�C�H�ƁA�É͓d�r�A�����͂�Ȃ́A�u�����͂�ȃG�R�V�e�B������G�l���M�[�E�Љ�V�X�e�����v���W�F�N�g�v�̈�Ƃ��āA�������Ǝ{�݁u�����͂�ȃv���U�v�ɂ����āABEMS�iBuilding Energy Management System�j�̑�K�͎����X�^�[�g����B ���؏ꏊ�ƂȂ邯���͂�ȃv���U�́A�I�t�B�X�A���X�g�����A�z�e�����A�l�X�Ȏ{�݂ō\������镡���r���B�����o���̑�O�Z�N�^�[�ł���u�����͂�ȁv���^�c���Ă���B BEMS�Ɋւ���{���ł́A�G�l���M�[�Ǘ����s���G�l���M�[�R���g���[���A���`�E���C�I���~�d�r�A�X�}�[�g�q���[�^�E����\����A���̑��֘A�@����B�{�ݓ��@��̌����^�p��f�}���h���X�|���X�Ȃǂ̎��v�ґ��̋��͂ɂ��A���ו������A�ȃG�l���M�[�A��CO2�𐄐i����ƂƂ��ɁACEMS�i�n��G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���j�Ƃ̘A�g�ɂ��n��S�̂̃G�l���M�[�œK����}��B ��̓I�Ȏ��g�݂Ƃ��ẮA2012�N9����BEMS���������r���Ǘ��V�X�e���ƘA�g�����f�[�^���W�A11���ɑ���\����y�уX�}�[�g�q���[�^���80�e�i���g�ɐݒu���G�l���M�[�������鉻�A�܂��ACEMS�Ƃ̘A�g�ɂ��A2012�N11���`2013�N1���ɒn��G�l���M�[�œK���̂��߂̃f�}���h���X�|���X���E�ȃG�l�������{�A12���ɍ����ő�K�͂̒�u�^���`�E���C�I���~�d�r�i30kWh�����j�ɂ��A�n���A�n�ł̕��ו��������ʌ����J�n���Ă����B ����̌����x�[�X�ł́ABEMS�ƃf�}���h���X�|���X�ɂ��ȃG�l���ʂ͖�30���ƌ�����ł���B�����̓z�e���ƃe�i���g��ΏۂɁA�ۋ��x�[�X�̃f�}���h���X�|���X�ɂ��{�ݓ��̕��וW�����̎���A��u�^���`�E���C�I���d�r���������̃c�[���Ƃ�����g�݁A�����ς݂̑���\���@��p�����t�����l�T�[�r�X�����{����\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����ŁA�ăf�}���h���X�|���X�֘A��Ђ� �č��œd�͉�Ќ����Ƀf�}���h���X�|���X�i�c�q�����v�����j�֘A�́A�\�t�g�E�G�A�J����V�X�e�����s���R���T�[�g�Ёi�e�L�T�X�B�T���A���g�j�I�j�������Ɣ��\�����B ���Ђ͊��ɕč��łc�q�V�X�e���̗̍p���т������Ă���A���łł͎��瓾�ӂƂ���X�}�[�g�O���b�h�i�����㑗�z�d�ԁj�֘A�Z�p�ɃR���T�[�g�Ђ̂c�q�\�����[�V�����������A�č��ł̎��Ɗg���ڎw���B�����z�͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ����\�����~�K�͂Ƃ݂���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
���t�@�~���[�}�[�g�A�ŐV�s�̏ȃG�l�ݔ����������������^�t���b�O�V�b�v�X ��t���D���s�ɍŐV�s�̏ȃG�l�ݔ����������������^�t���b�O�V�b�v�X�܂��J�X����Ɣ��\�����B���X�̓d�C�g�p�ʂ́A�ʏ�̃t�@�~���[�}�[�g�X�܂Ɣ�r���Ė�30%�팸���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���B ���X�̓����Ƃ��āA�����גጸ���ЊQ���Ή��Ƃ��āA�u���z�����d�{���`�E���C�I���~�d�r�V�X�e���v���̗p�B���z���Ŕ��d�����d�C�̈ꕔ��X���Ɩ��Ȃǂɗ��p���A�]�蕪�͒~�d�r�ɒ��߁A��d���̔��d���Ƃ��Ĕ����APOS���W��Ɩ��ɋ������邱�ƂŁA�X�܂̉c�ƌp�����\�ɂ���B �����גጸ�Ƃ��āA�u�n���M�q�[�g�|���v�v�ɂ��A�n���M���ɗ��p���A�d�C�g�p�ʖ�30%�팸����B�܂��A�u�m���t����CO2��}�|�①�Ⓚ�V�X�e���v���̗p���ACO2��}���p�V�X�e���ɂ��m���t�������ɂ��n�����g����}�����A�d�C�g�p��30%�팸����B ���̂ق��A�ė��p���\��100%�d�����f�ނłł��Ă��鏤�i��I�u�d�������T�C�N����I�v��A���ԑт�G�߂œX���Ɩ��̖��邳�ƐF���ϐ���ȁu�������FLED�Ɩ��V�X�e���v�A�u������L�@EL�Ɩ��v�Ȃǂ����p���铯�X�ł́A�u�����גጸ�v�A�u�ЊQ���̉c�ƌp���v�A�u�V�Z�p�̊��p�v�̌���ړI�Ƃ��A�����̌����d�˂����ʁA���X�ɂ������\�ȋ@��Ɋւ��Ă͐ϋɓI�Ɋg�債�Ă����Ƃ����B �o�T�u�}�C�i�r�j���[�X�v |
|
|
�����{IBM���H��p�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e����J�n�ߓd�v���ɂ��Ή� �H��̃G�l���M�[��c�����������Ǘ����邱�Ƃɂ��G�l���M�[���p�̍œK����}��u�H��G�l���M�[�Ǘ��\�����[�V�����v�\�����B ���T�[�r�X�́A�]���̃T�v���C�`�F�[���̍œK�������łȂ��A��������̉��H���d�ˍ��킹���G�l���M�[�p�r��c�����팸�v�������ł���̂������B ������500���~�`�i�H��G�l���M�[�Ǘ��\�����[�V�����݂̗̂����j�B ��̓I�ɂ́A�H��Ŏg�p���鑕�u�̃��W���[�����Ƃ̏ڍׂȃG�l���M�[�̎g�p�́u�����鉻�v���s���B����ɂ��H��S�̂̏ȃG�l�����̂��߂ɕK�v�ȁu�G�l���M�[�Ď��v�A���Y�v��E���т��l�������u�G�l���M�[�̌������v�A�����\���ɂ��u�R�X�g�œK���v�A�d�͏�Q�ɂ��u���Y�e���̍ŏ����v�Ȃǂ̋@�\����A���z���^�H��̎�����ڎw���B �܂��A���Y�Ǘ��V�X�e���Ƃ̘A�g�ɂ��A���̎��̉��H���d�ˍ��킹���G�l���M�[�p�r��c�����A�H��S�̂̃G�l���M�[�œK�����������邱�Ƃ��\�B �G�l���M�[�Ď�����n�߁A�ȃG�l�^�p�̎�������G�l���M�[���p�v��̍œK���Ȃǂ�i�K�I�ɐi�߂Ă������Ƃ��ł���B ���\�����[�V�����́A�T�v���C�`�F�[���œK�����x�����鐶�Y�Ǘ��\�����[�V�����̋@�\���g�������V�X�e���BIBM�̕č����̍H��ʼnғ����Ă�����̂ŁA���Ђ�����܂Œ~�ς��Ă����G�l���M�[�����Ǘ��̃m�E�n�E��̌n�����Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
���O�H�d�@�A�����̎��O���j�b�g�𐧌䂵�Đߓd����ƊE���̋Ɩ��p�G�A�R���� 1�̎�����ԂɑΉ����镡���̎��O���j�b�g��A�g���䂵�Đߓd����X�܁E�����������Ɩ��p�p�b�P�[�W�G�A�R����������������B�̊����x�ɍ��킹�ĉ^�]����ߓd�@�\���V���ɓ��ڂ���B ���O���j�b�g�̘A�g����́u�p���[�V�F�A�^�]�v�ƌĂԁB�����̋@��1�̎����ʼnғ�������ƁA�ݒu�ꏊ�ɂ���Ď��O���j�b�g�̈��k�@�̉^�]�����ɍ����o�āA�d�͂ʂɏ����ꍇ�����邱�Ƃɒ��ځB���k�@�͈��\�͈ȏ�̉^�]�ŏ���d�͂��傫���������邽�߁A�ݒ艷�x�ɋ߂������ʼn^�]���Ă��鎞�ɌX�̔\�͂�Z�ʂ������B ����ɂ���ČX�̎��O���j�b�g�������I�ɉ^�]�����A�ŕK�v�Ȕ\�͂𗎂Ƃ����ƂȂ��A�@�S�̂̏���d�͂�}����B��[���Ŗ�15���A�g�[�ł͖�10���̐ߓd����������Ƃ����B�A�g����͒g�[�^�]�̑����^�]�ɂ��K�p�B�����̎��O���j�b�g�������ɑ����^�]�ɓ����Ԃ��Ȃ����A�����I�Ɏ��Ԃ����炵�Ď����̉��x�ቺ��}����B �̊����x�ɍ��킹���^�]�́u�l���n�C�u���b�h�^�]�v�̖��ŁA�̊����x�f���Đݒ艷�x�ɂȂ�Ɨ�[�̓X�C���O�����ɁA�g�[�͐��������ւ̑����Ɏ����I�ɐ�ւ���B��~���̑ҋ@�d�͂��Ǝ��̐���ŏ]���@�Ɣ�ׂĖ�50���팸����B�Ɩ��p�G�A�R���͓X�܁E�������̏���d�͂�50�����߁A��w�̏ȃG�l�����߂��邱�Ƃ���J�������B �o�T�u�oBP�v |
|
|
���O�H�d�@�����K�̓r�������̃R���p�N�g�ȃr���ݔ��I�[�v�������V�X�e���� �NJ|���^�C�v�ŁA�X�y�[�X�ɐ����钆���K�͂̃r���ł��ݒu���₷���ȒP������������Ă���B �p�\�R���ɂ����Ď��ɂ��Ή����A�ݒu�ꏊ�����łȂ����ꂽ�Ǘ��������������\�B�e�ݔ��̃G�l���M�[�g�p�ʂ̃O���t�\����f�}���h���䂪�\�r���p�}���`�G�A�R���Ƃ̐ڑ��ŁA�X�P�W���[���̕\���E�ݒ�ȂNjݔ��̂��ߍׂ��Ȑ����A�ݔ��̉ۋ��Ɏg�p����d�͗ʂ̃f�[�^���W�Ȃǂ��\�܂��ʓr�A�_��A�N���E�h�����p���Đݔ��f�[�^�����W�E���͂��A�ݔ��̉^�p��ȃG�l��Ȃǂ̒�Ă��邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
�������d����5�`7�N��A�����莩�R����3�N����ρA�d�͉��v�֍H���\ �o�ώY�ƏȂ̓d�̓V�X�e�����v���ψ���́A�d�̓V�X�e�����v�̍H���\�荞�����܂Ƃ߂��B�d�͂��ƒ�ȂǂɎ��R�ɔ����u������̑S�ʎ��R���v��3�N�ォ��n�߁A�d�͉�Ђ��瑗�z�d�����藣���u�����d�����v��5�`7�N��ɓ��ݐ�B����ŁA�e�ƒ낪�����┭�d���@�Ȃǂœd�͉�Ђ�I�Ԋ��������A���d�͉�Ђ��n�悲�ƂɓƐ肵�Ă����̐��������B �Ζؕq�[�o�Y���͎����}���̋c�_���o�čŏI���肵�A������ɓd�C���Ɩ@�����Ă��o����B�����d�����͖@�����̍�ƂɎ��Ԃ������邽�߁A�@���̎�Ȏ����i�{���j�ł͂Ȃ��A�t���ɐi�ߕ��⎞���Ȃǂ荞�ޕ��j���B �o�T�u�����V���v |
|
|
�����������w�h�s��MW���̉��d�{�݂̌��݊J�n ���d�Ƃ����A�ݔ����p�����������d�����͗ǂ����A�o�͂�100kW���x�̏��K�͂Ȃ��̂������B ���d�ݔ��̌��ݗ\��n�́A�V���{�Ȋw���w�h�s�ʼn^�c���Ă����Ê֘A�{�݁u���f�B�|���X�w�h�v�̕~�n���B ���݂�����JFE�G���W�j�A�����O�ɂ��ƁA���݂͊Ԃ��Ȃ��n�܂�B�ғ��J�n��2014�N�̏H��\�肵�Ă���B���E�e�n�ō̗p���т�����ăI�[�}�b�g�E�e�N�m���W�[�Y�Ђ̐ݔ���������r�W�l�X�ŁA�N�Ԕ��d�ʂ͂��悻900��kWh�ƌ�����ł���B�ݔ����p�����v�Z����Ɩ�68.5���ɒB����B���̐ݔ��͏o��1��5000kW�����̒n�M���d�ݔ��Ƃ��������ɂȂ�A1kWh������42�~�Ƃ����������i�Ŕ��d�ł���B���݂���ݔ��ł��Œ艿�i���搧�x�𗘗p����\�肾�B �o�T�u�X�}�[�g�W���p�� |
|
|
���k�C���ŏ��A�n�M���d�̌Œ艿�i���搧�x���p�����Ή���� ����F�肳�ꂽ�̂́A�����Ή���M���p���x�����d�{�݁B�o�͂�100kW�B�^�]�J�n�͍��N9��1����\��B���d�ݔ��敪�ɂ�钲�B���i��42.00�~�B���B���Ԃ�15�N�B ����̉��x�����d�Ɏg����o�C�i���[���d�́A����̔M���Ȃǔ�r�I�ቷ�i�Z��70�`150�x�j�̔M�G�l���M�[�𗘗p���A����蕦�_�̒Ⴂ��փt������A�����j�A�Ȃǂ̔}�̂������^�[�r�����Ĕ��d��������́B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
��2020�N�ɓd�͂̃x�X�g�~�b�N�X�������A�����}�̌������3�N���� ���̃G�l���M�[�헪�𗧈Ă��邽�߂ɂ́A�����̓d�͂̍\������ǂ����邩�A�����߂�K�v������B�ΉA���q�́A���́A�����čĐ��\�G�l���M�[�B4��ނ���d�͂��œK�Ȕ䗦�ɂ���u�x�X�g�~�b�N�X�v�̎����Ɍ����āA�o�ώY�Ƒ�b��7�N���2020�N��ڕW�ɐݒ肵���B ���{�����i����o�ϐ����H���̒��ŁA���E�����}�����͌��q�͔��d���̍ĉғ���O��ɂ����V�����헪���������Ă���B �헪���Ă̒��S�ɂȂ�Ζؕq�[�o�ώY�Ƒ�b�́u�G�l���M�[�Ő�i���v�ɂȂ�ڕW���f���āA���Y�i���d�j�A���ʁi���z�d�j�E����i�����j��3�i�K�ŋ�̓I�Ȑ���𐄐i���邱�Ƃ�\�����Ă���B���Y�ɑ������锭�d�Ɋւ��ẮA���q�͂̈ʒu�Â����܂߂āA�ǂ̂悤�ȓd�͂̔䗦�ŏ����̎��v�ɉ����Ă������A�����߂�K�v������B ����Ɏ�������������3�N�������������邽�߂ɂ͓d�͂̍\����𑁊��Ɍ��߂đ�����{���Ă����K�v������A2013�N���܂łɍ��肷��u�G�l���M�[��{�v��v�̒��ŋ�̓I�ȖڕW�l��ݒ肷�錩���݂��B�J�M������̂͌��q�͂̔䗦�ł���B 2011�N�x�̍\���������ƁA�N�Ԃ̔��d�d�͗ʂł͉Η͂�78.9���A���q�͂�10.7���A���͂ƍĐ��\�G�l���M�[��10.4���ɂȂ��Ă���B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
�����{ �ȃG�l�H��֍ő�2����1�⏕ �ŐV�ݔ������� ���{��1���Ɍ��肵���ً}�o�ϑ�̒��ł���ȃG�l���M�[���\�̍����H��ւ̐V�⏕�����x�̊T�v�����߂��B���Y����啝�Ɍ��コ���钆�j�I�ȍŐV�ݔ��ɑΏۂ��i�荞�݁A�ݔ������ɂ������p�̍ő�2����1��⏕����B �V���x�ɂ�2012�N�x��\�Z�ő��z2�牭�~���m�ہB�Y�ƊE�̋����͋�����ڎw���A���z1���~���閯�ԓ����̌Ăѐ��ɂ���B 2014�N�x���ɓ����������ł���ݔ����ΏہB�⏕�����{����v���Ƃ��āA�����ߒ��̃G�l���M�[�g�p�ʂ����炷���Ƃ�i�̕t�����l���グ�邱�ƂȂǂ��������B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���@�@[�@2013/3�@]�@�@�� |
|
|
��NEC���C�e�B���O���n���Q���d�����ւł��閾�邳�d����LED���J�� �X�܂�V���[�P�[�X�Ȃǂ̏��Ǝ{�݂̏Ɩ��́A�X�|�b�g���ő傫�Ȗ��邳���K�v�ƂȂ邽�߁ALED��������n���Q���d�����嗬���������A�{���i�Ńn���Q���d���̒u���������\�ƂȂ�A����d�͂�50W����6W��1/8�ɒጸ���邱�Ƃ��ł���B�܂��A�����̓n���Q���d����10�{��3�����ԂƂȂ�A�Ȏ������ɂ���^����B �{�v���W�F�N�g�ł́A���x�Ȍ��w�v�ɂ�郌���Y�����̌����A�œK�ȃq�[�g�V���N�v�ɂ����M�����̌���ɂ��A����̃n���Q���d���Ɠ����̃T�C�Y�ł���Ȃ���A�ő���x�Ńn���Q���d��������ƊE�ō���3,300cd�i�J���f���j�����������B�܂��A���А�100�`�n���Q���d���Ɠ����̑傫���Ƃ��邽�߂ɁA�d������V�K�J�����ď��^���BLED�����v�̏ȃG�l���M�[�������シ���ŁA�X�C�b�`���O���X�̒ጸ��LED�̏��d���̍œK�����̉ۑ�������K�v���������A�{�v���W�F�N�g�ʼnۑ�̉��P��}�邱�Ƃɂ��A�ƊE�ō��ƂȂ�A90�����z����d�������������������B ��������̂́A�n���Q��100�`�������p�^�C�v2�@��ƍL�p�^�C�v2�@��̌v4�@��B��]�������i��4�@��Ƃ�7,700�~�i�ŕʁj�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
����d�ƒ�����d�C�����s�[�N����Ԃ�5�{ 4������V���ȗ������j���[������B�ď�̃s�[�N���̗����������ɂ��邱�ƂŁA���ԑт��Ƃ̎g�p�d�͂̕�������i�߂�B �V���ɓ�������u�s�[�N�V�t�g�d���v�́A�d�͎��v���}������7�`9���̌ߌ�1�`4���̓d�C������1kWh������52.5�~�ɐݒ肷��B����A�ߌ�10�`�����ߑO8���̗�����10.29�~�ɗ}����B���̎��ԑт͎g�p�d�͗ʂɉ����ĒP����ς���B���s�ł����Ԃ̗������j���[�����邪�A�ߑO10���`�ߌ�5���܂łƎ��ԑт��L�������A�����͉ď��33.2�~�Ɩ�ԗ�����4�{��B �s�[�N�V�t�g�d���͑S���ѐ\�����݉\�B�d�͌v��ʐM�@�\�t���̃X�}�[�g���[�^�ɐ�ւ��������ŐV������K�p����B ��N�āA�ߌ�1���`4���̓d�C�������ő��1kWh������A126�~�ƒʏ�ɔ�ׂ�6.3�{�ɐݒ肷����؎��������{�����B���̌��ʁA��ʉƒ�ɔ�ׂēd�͎g�p�ʂ�17�����Ȃ��Ȃ���ʂ��������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
��LIXIL �ȃG�l�f�M���t�H�[���̌��ʂ��H���O�Ɋm�F�ł���\�t�g���J�� ���ꂩ��ȃG�l�f�M���t�H�[������������ڋq�����ɁA���Z��ł���Ƃ̒f�M���\�ƁA���t�H�[����̒f�M���\�����O�ɐ��l�Ŕ�r���邱�Ƃ��ł���V�~�����[�V�����\�t�g�u�R�R�G�R�f�f�v��V���ɊJ�������B�����A���̃\�t�g��p�����f�f�T�[�r�X���J�n����B ����J�������u�R�R�G�R�f�f�v�́A���Ђ��W�J����G�R���t�H�[���H�@�u�R�R�G�R�v�̌��ʂ��A���l�E�O���t�E�T�[���O���t�B�摜�ȂǂŁA�킩��₷��"�����鉻"���邱�Ƃ��ł���V�~�����[�V�����\�t�g�B �Ƃ̒��ƊO�̉��x�����傫���Ȃ�11���`3���̑���ŁA���ۂɍ��Z��ł���Ƃ̒f�M���\�𑪒肵�A���t�H�[���O��̑����f�M���\���r�ł���ق��A�i1�j�̊����x�A�i2�j�����̒g�����A�i3�j���̌��I�A�i4�j�����̕ۉ��́A�i5�j��g�[���5���ڂ̔�r�f�f���ʂ�f�f���Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ڋq�͂��̐f�f�������t�H�[���H���O�Ɋm�F���邱�ƂŁA���t�H�[����̌��ʂ���薾�m�ɗ���������ŁA�H���̌��������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B �u�R�R�G�R�v�����̖{�T�[�r�X�́A���Ђ̉^�c���郊�t�H�[���X�l�b�g���[�N�uLIXIL���t�H�[���l�b�g�v�̔F�萧�x�Ɋ�Â����}�C�X�^�[�o�^�X������B �܂��A�u�R�R�G�R�v�Ώےn��ł���A������ȃG�l���M�[��Y�n��ȓ삪�f�f�Ώےn��ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����ŁA�Z��p���z�����d�̕ۏؐ��x����50kW�����̃V�X�e���ɑΉ� �Z��p���z�����d�V�X�e���̐V�T�[�r�X�Ƃ��āA���z�d�r���W���[���̏o�͂��Œ�20�N�ԁA���z�d�r���W���[���E�p���[�R���f�B�V���i�E�ڑ����Ȃǂ̍\���@���15�N�ԕۏ��钷���ۏؐ��x�u�p���t���ۏv��3��1������J�n����B �{�ۏ͉����\�����K�v�ȗL���T�[�r�X�ŁA�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�ɂ����ė]�蔃��̑ΏۂƂȂ�ݒu�e��10kW�����̃V�X�e���ɉ����A�S�ʔ���̑ΏۂƂȂ�10kW�ȏ��50kW�����̑�e�ʂ̃V�X�e���ɂ��Ή�����B�܂��A2010�N4���ȍ~�ɓ��ЏZ��p���z�����d�V�X�e����ݒu�������[�U�[���������邱�Ƃ��ł���B �u�p���t���ۏv�́A���z�d�r���W���[���̏o�͂��ۏؒl����������ꍇ��V�X�e�����\������@�킪�̏Ⴕ���ꍇ�ɓ��Ђ��o���E�_���C���A�@�������p��S�z���S����T�[�r�X�B�Ⴆ�ΐݒu�e�ʂ�5kW�ŁA���z�d�r���W���[���̏o��20�N�ԁA�@��15�N�Ԃ̕ۏ̏ꍇ������p��4��2,000�~�i�ō��j�ɂȂ�B ���z�d�r���W���[���̏o�͂ɂ��ẮAJIS C 8918��6.(���\)�ŋK�肷��������ɂ����āA�ۏؒl�����ɂȂ����ꍇ�ɕۏ���B�Ȃ��A�Ώۋ@��́A���z�d�r���W���[���A�p���[�R���f�B�V���i�A������A�ڑ����A���Џ����ˑ�Ɍ���B�\�����R�~���j�P�[�V�������j�b�g�͂P�N�Ԃ̕ۏƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���I���������[�^�̉d�͍ė��p����@����J�� �@�B�̓��͌��̃��[�^�������d�͈͂�ʂɍH��S�̂�25���ɑ�������B���[�^�͋N�����ɏ����d�͂��ł��傫���B����@��œd�͂�40����������A�d�͂Ń��[�^�̋N�����̓d�͂�₦��A�s�[�N�d�͂�������A�d�����u�̏��^�����ł��A�d�C�����̈����������\�ɂȂ�B ����@��ɂ͏[�E���d���Ǘ�����d���̕ϊ����d�̓f�[�^�̑����A�~�d���u�A�ʐM�@�\������H��S�̂̓d�͏���܂��Đ��䂷��B ���ЍH��ɂ��鐬�^�@�ȂǂŎ��؎��������A���[�^�[�̏o�͂ɉ������~�d���u�̗e�ʂȂǂ����ɂߐ��i��������j���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
�����I�p���X21�A���z�����d�ݒu�A�p�[�g5,000���˔j�v47MW�� ����́A���ЊǗ��A�p�[�g�̑��z�����d�V�X�e�����ݒu�\�Ȗ�22,000���̂���22�����銄���B���v���d�e�ʂ�47MW�ƂȂ�A����͈�ʉƒ��1��5,000���ѕ��̓d�͎��v�ɑ�������B ���d�����d�͂͌Œ艿�i���搧�x�ɂ�蔄�d���A�A�p�[�g�̃I�[�i�[�����d�����邵���݁B�ʏ프�d���Ă���d�͂́A����̍ۂɂ͔��p�̓d�͂Ƃ��Ă��L�����p�ł��A�����҂̈��S�����m�ۂ��Ă���B 2011�N4�����V�z�y�ъ����̓��ЊǗ��̒��݃A�p�[�g�ɁA�u���z�����d�V�X�e���v�̖{�i�I�ȓ������i���J�n�B�����̃A�p�[�g�̃I�[�i�[�̋��͂��A2�N�ɖ����Ȃ��Z���Ԃ�5,000����B�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���o�Y�ȁA�Đ��\�G�l���M�[�̐��i�ȂǕ���25�N�x�\�Z�Ă����\ 25�N�x�\�Z�ċy��24�N�x��\�Z�Ă����킹�����z�͖�2���~����K�͂ƂȂ�B�d�_�����镪��Ƃ��āA(1)�����E�h�Б�A(2)�����ɂ��x�̑n�o�i���ԓ����̊��N�A������ƁE���K�͎��Ǝґ����j�A(3)��炵�̈��S�E�n�抈�����A��3�̒����������B ���25�N�x�G�l���M�[�֘A�\�Z�Ă̊T�v�͈ȉ��̒ʂ�B �E�u�Y�Ɖ��f�I�ȏȃG�l���M�[�������̑��i�v�Ƃ��āA�H��E���Əꓙ�ɂ�����ȃG�l�ݔ��ւ̓���ւ��ɑ��ĕ⏕���s���u�G�l���M�[�g�p���������ƎҎx���⏕���v310���~�i����24�N�x�����\�Z�z298���~�j�A �E�ȃG�l���M�[��d�͎����̈��艻���Ɏ�����K�X�R�[�W�F�l���[�V�����⎩�Ɣ��d�ݔ����̕��U�^�d���̐ݒu�𑣐i����u���U�^�d���������i���Ɣ�⏕���i�⏕�j�v249.7���~�i�V�K�j�Ȃǂ��v��B �E�u�N���[���G�l���M�[�֘A�Y�Ƃ̑n�o�v�Ƃ��āA2015�N�̔R���d�r�����Ԃ̎s����ɐ�삯�āA�����Ԃɐ��f���[�U���鐅�f�X�e�[�V�����̐����ɑ��ĕ⏕���s���u���f�����ݔ��������Ɣ�⏕���v45.9���~�i���V�K�j �E����4�n��i���l�s�A�L�c�s�A�����͂�Ȋw���s�s�i���s�{�j�A�k��B�s�j�ɂ����ĕ��U�^�V�X�e���̎����s���u������G�l���M�[�E�Љ�V�X�e�����؎��Ɣ�⏕���i�X�}�[�g�R�~���j�e�B���j�v86���~�i��106���~�j �E���ԓ����̊��N�ɂނ����A������ƁE���K�͎��Ǝґ�ł́A�u�Z��E�r���̊v�V�I�ȃG�l�Z�p�������i���Ɣ�⏕���i�⏕�j�v110���~�i��70���~�j�ŏZ��E�r���̃l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�𐄐i���邽�߁A�����\�ݔ��@�퓙�i�E�Ɩ��E�������j�̓������x������B �܂��A����24�N�x��\�Z���ƂƂ��āA �E�u�X�}�[�g�}���V�����������������i���Ɓi�⏕�j�v130.5���~�ŁA�}���V�����S�̂̃G�l���M�[�Ǘ����s�����ƎҁiMEMS�A�O���Q�[�^�[�j��ʂ��ē�������� MEMS�i�}���V�����E�G�l���M�[�E�V�X�e���j�̐ݒu��p�̈ꕔ��⏕����B �y�Q�l�zhttp://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���r���ȃG�l�֊����t�@���h���ȁE�����ȋ����� ���Ȃƍ��y��ʏȂ͋����ŁA�ϐk��������\���������z���ւ̉��C��i�߂邽�߁A�����t�@���h��n�݂���B ���Ȃ������t�@���h�𗧂��グ��̂͏��߂āB���Ȃ�50���~���x�A�����Ȃ�300���~���x��2012�N�x��\�Z�ŗv�����錩���݂ŁA���Ԃ���̏o�����܂߂��K�͂�1�牭�~����Ƃ݂���B�s���Y�s��̒���ɂ���ăr���̘V�����i�܂Ȃ����ŁA���������ďȃG�l���M�[���Ȃǂ�i�߂�B �ϐk���Ɗ����\�̂ǂ��炩�Е��̌���ł��ΏۂƂ��邪�A���������コ����Č���D�悳������j�B�܂��A���C����ɂ��邪�A�V�z�⌚�đւ����ΏہB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
����K�̓r���œd�͒����s���A�g�����؎����A�ő�20���̍팸�ڕW�^���l ���؎����́A�o�ώY�ƏȂ��I�肵���u���l�X�}�[�g�V�e�B�v���W�F�N�g�v�̈�B���l�s�͖��Ԋ�ƂƂƂ��ɓ��v���W�F�N�g�𐄐i���Ă���A����̎����͓��ŁA�听���݁A���d�ɁA�����A�ۍg�A�O�H�n���A�O��s���Y���Q�����Ă���B 1��8���`2��22���܂ł̊Ԃ�10�����x�s���B�~�G�̓d�͏���ʂ��s�[�N�ƂȂ镽���̌ߌ�5�����瓯8�����Ώێ��ԁB���{�͍ō��C����8�x�ȉ��i�O��̗\��Ɋ�Â��j�̓���z�肵�A�s�[�N���̎g�p�d�͗ʂ��ő�20���팸���邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���B ���Ǝ{�݂��K�̓r����������G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iBEMS�j��BEMS�Ɛڑ��B����BEMS�́A�e�{�݂̃G�l���M�[������펞�Ď����A�ߓd�\�ʂɉ����ēd�͂̍팸�ڕW��z�����A���ꂼ��ɗv������B ����̎����ł́A�d�͂̍팸�ʂɉ����������݂���B�����͌o�Y�Ȃ̕⏕�����[�Ă�B ���؎����͉Ăɂ��\�肵�Ă���A���{�̋C�y�ɂ������V�X�e���̍\�z��ڎw���B �o�T�u�J�i���R�v |
|
|
���r���ȃG�l���s������n�t���Ǝ҂����� 2013�N�x����A�r���ȂǑ�^�{�݂����L�����ƂɏȃG�l�̃m�E�n�E�̂���Ǝ҂��Љ�A��Ƃ����������Ȃ��Ő������M����팸�ł���T�|�[�g���Ƃɖ{�i�I�Ɏ��g�ށB ��Ƃ͐������M����z���ꂽ�ꕔ���u��V�v�Ƃ��ďȃG�l�ݔ���d�g�݂�����Ǝ҂Ɏx�����B�������M��N��1�疜�~���̊�Ƃ����p����ƁA�ȃG�l�Ǝ҂����N�œ�����p������ł����v���o����Ǝ��Z�B������~�ɂ��d�͂̋����s����d�C�����l�グ�̓���������A�s�S�̂̃G�l���M�[����̐ߖ�ɂȂ��郆�j�[�N�Ȏ��ƂƂ��Ē��ڂ����B ���ƌv��ɂ��ƁA�܂��s���I�肵���R���T���^���g���A�r�����L�҂�Ǝs�ɓo�^�����ȃG�l�Ǝ҂𒇉�B�����̋Ǝ҂��r���̋ݔ��Ȃǂ̌�������A�������M��̍팸�v��荞����ď����o����B�r�����L�҂͒�ď����r���ċƎ҂�I�сA��V�̊����Ȃǂ����߁A3�`5�N�̌_����������B�_����Ԃ��I������A�r�����L�҂͕�V���x�����`�����Ȃ��Ȃ�B �s�́A�r�W�l�X�𒇉�邱�ƂŏȃG�l�Ǝ҂̐M�p��ۏ��邱�ƂɂȂ�B�N��1�疜�~���̐������M����x�����Ă���̂́A�����ʐς�3�畽�����[�g���ȏ�̃r���ȂǂƂ���A�s���ɂ͑�����������ƌ����ށB���Ƃ�1�N�قǑO���玎�s���A���ɕa�@��w�Z�@�l���܂ߖ�40�ЁE�c�̂��Ǝ҂ƌ_������Ƃ����B �o�T�u�����{�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/2�@]�@�@�� |
|
|
���~�T���z�[���uECO�ɂȂ�Ƃ̉�v�ɂ��CO2�r�o�팸���Ƃ��u�����N���W�b�g�v�F�؎擾 ��ʉƒ�ł̑��z�����d�ɂ��CO2�r�o�팸���ʂ��������d�g�݂Ƃ��āA2009�N�ɁuECO�ɂȂ�Ƃ̉�v�����A����ł���~�T���z�[���̃I�[�i�[���CO2�r�o�팸�ʂ����܂Ƃ߂Ĕr�o���i�����N���W�b�g�j��������g�݂�i�߂Ă����B �uECO�ɂȂ�Ƃ̉�v�́A2010�N�ɑ��z�����d�Z���CO2�r�o�팸���ƂƂ��Ď��ƔF���A����ɏ�������\�ȁu�v���O�����^�r�o�팸���Ɓv�Ƃ��Ă����ƔF���擾���A�������2012�N11�������_��1,959�g�ƂȂ��Ă���B���̂��сuECO�ɂȂ�Ƃ̉�v�́A2011�N�x��CO2�r�o�팸���ɂ��āA�u�����N���W�b�g�v�̔F���擾�����B����F���ꂽ�����N���W�b�g421t-CO2�ɂ��āA�uECO�ɂȂ�Ƃ̉�v����S�ʂ��A���̎��v���ɂɂ�����n�����ϑ������ւ̎x����ړI�Ƃ����Љ�v�������ɑS�z��t����\�肾�B �o�T�usuumo�W���[�i���v |
|
|
���Z�C�R�[�C���X�c��920MHz�ѓ��菬�d�͖������g�p���������Z���T�[�l�b�g���[�N�̐V���i�\ �����Ȃ̎��g���ڍs���i�[�u�ɏ]���āA����A�V����LAN�ڑ����\��Ethernet�x�[�X����@��Ƃ̐ڑ����\��Modbus�i���h�o�X�jRTU�m�[�h�\�����BModbus�v���g�R����L����e��@��Ƃ̐ڑ����\��ModbusRTU�m�[�h���g�p���邱�ƂŁA�@���̖������䂪�\�ɂȂ�B���x�A���x�A�Ɠx�ACO2�Ȃǂ̊e��Z���T����������m�[�h�i�q�@�j�ƁA�m�[�h���瑗���Ă��鑪��f�[�^����M����x�[�X�i�e�@�j����ђ��p�Ɏg�����[�^�i���p�@�j�ō\������Ă���B �����́A �E���d�g���B�F2.4GHz�тƔ�r���āA�d�g�̓��B�����������A��Q���������Ă��d�g����܂�����������邽�߁A���ʂ��̈������ł��������悭�`�d����B �E�����d�́F���Ȃ��o�͂ő��M�ł��邽�߁A�ȓd�͂̃V�X�e���\�z���\�B�����x�m�[�h��1�������̑��M�œd�r�����͖�10�N�B �E��F920MHz�т́A����LAN�Ȃǃu���[�h�o���h�p�r�̖����V�X�e���̉e�������Ȃ��A�e��m�C�Y����̓d�g�������Ȃ����߁A���肵�������V�X�e�����m���ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
�����s�c�菑8�N����COP18���ӐV�̐��֍�ƌv�� ���g�����b���������A�C��ϓ��g�g�ݏ�����c�iCOP18�j��8���A�e�����Q������2020�N�ɔ���������V�̐��Ɍ�������ƌv��𒌂Ƃ��鍇�ӂ��̑������B�Η����������r�㍑�ւ̎����������́A��i�������z�ɓw�͂���Ƃ����B�܂��A���s�c�菑��8�N��������B��c�͗\����P���x��ŕ������B �J�^�[���ł�COP18�͍�N���ӂ����V�g�g�݂Â���̋�̉�����v�e�[�}�����A��i����3�N�O�Ɋm���x���̑��z�ɂ��ēr�㍑����̍�����߁A���S�̂���q�����B�c����8�����ɍŏI���ӈĂ������Ċe���ɗ��������߂����A�e���̌������������A���ӂ͓�����܂ł��ꍞ�B ���ӂł́A2015�N�܂łɒ��g���ł߂邱�ƂɂȂ��Ă������s�c�菑�ɑ����V�̐��ɂ��āA2014�N��COP20�܂łɌ������̍��ڂ��ł߁A2015�N5���܂łɕ������쐬�A�ȂǂƂ����ƌv�悪�����ꂽ�B2020�N�܂ł̉������ʃK�X�팸�ڕW�̈����グ�ɂ��āA�e�������N����2014�N�̍�ƌv������A�Ɏ������Ƃ����荞�܂ꂽ�B �o�T�u�����V���v |
|
|
�������M�w�H�Ƃ��a�@�ɂ�����G�l���M�[�T�[�r�X���Ƃɖ{�i�Q�� �ȃG�l���M�[�A�R�X�g�팸�ɍv������G�l���M�[�T�[�r�X���Ɓi�M���@��̐ݒu�H������шێ��E�Ǘ����ꊇ�Ő��������T�[�r�X���Ɓj�ɖ{�i�Q�����A�_�ސ쌧�ɐ����s�ɂ����Čv�撆�́uJA�_�ސ�����A�ɐ��������a�@�v����G�l���M�[�T�[�r�X���Ƃ������B �G�l���M�[�T�[�r�X���Ƃ́A�{�C����Ⓚ�@�Ȃǂ̔M���@������L���āA���q�l�ɃG�l���M�[����������ƂƂ��ɁA���q�l�̃G�l���M�[�g�p����c�����A�j�[�Y�i�C�j�V�����R�X�g����єN�ԉ^�]��̍팸�E�����e�ۏE�^�]�Ǘ��j�ɍ��킹�ăG�l���M�[�̍œK�ȉ^�p���s���B �T�[�r�X�̊T�v�̓{�C����Ⓚ�@����ۗL���Č����I�ȉ^�]���s���A���q�l�ɃG�l���M�[����������B�ݔ���24���ԁA365���ɂ킽���ĉ^�]�Ǘ����s���B�~�M���u�����p���邱�ƂōœK�ȋ@��̉^�]���s���ƂƂ��ɁA�O�C���ɍ��킹�ė␅�E�����̉��x�߂��A���M����1���팸����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
���V���[�v�����z�����d�̃R�X�g��5����1�ɁA�G�l���M�[�ϊ�����40���ւ̒��� ���z���̃G�l���M�[����d�C�ݏo�����Ƃ����z�d�r�̖����ł���B�ʏ��1�����Z���`���[�g���̖ʐςɓ����鑾�z���̃G�l���M�[��100mW�i�~�����b�g�j�Ƒz�肵�āA�������瓾����d�͂̑傫���ɂ���đ��z�d�r�̃G�l���M�[�ϊ��������Z�o����B ���݂̂Ƃ�����p���x���̑��z�d�r�̕ϊ�������15�`20�����x�ɂƂǂ܂�B�܂�1�����Z���`���[�g���̑��z�d�r���瓾����d�͂�15�`20mW�ł���B���̕ϊ�������2�{�ɂł���A�����̉�����K�\�[���[�ɐݒu���鑾�z���p�l�����瓾����d�͗ʂ�2�{�ɂȂ�B ���������V�������z�d�r�͕ϊ�������37.7���ŁA�܂��Ɍ��݂�2�{�̐��\������B1�Z���`�p�̃Z��1������37.7mW�̓d�͂���邱�Ƃ��ł��A�������x���ł͌����_�Ő��E�ō��ł���B2030�N�ɂ͔��d�R�X�g�����݂�5����1�ɒጸ�ł��錩�ʂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
���g�Â߂̏Ɩ��h�œǂݏ����A�c���A�����b�N�X�ɖ��Ȃ��c�cLIXIL������ ����̎����́A�g���{�̏Z��ɂ�����Ɩ��͖��邷����̂ł͂Ȃ����H�h�Ƃ̋^�₩��A�����V�[���ɂ��킹���œK�ȏƖ���Ԃ�Nj����A�S�Ƒ̂ɂ₳�����Ɩ��A�d�C��̂�����Ȃ��G�R�ȏƖ����������邽�߁A�Ɩ��̌��ʂ����������B ����̓��k��w�����w�������̂��Ǝ��{�����w�Z���Ԃɂ�����Ɩ��̌��ʎ����x�ł́AJIS�i���{�H�ƋK�i�j�Łu�Ǐ��E���v�ɕK�v�Ƃ���Ă���500�`1000lx�i���N�X�j���Â�250�`350lx�̖��邳�ŁA�l�́u��ƌ����v�u�C���̕ω��v�u�����_�o�n�̎w�W�v�������B ���̌��ʁA�w�����x�̗̈�A���Ȃ킿�C���͖��邳�̉e�����Ă������A�w�m���x�̗̈�A���Ȃ킿�F�m�@�\��A�w�g�́x�̗̈�A���Ȃ킿�����_�o�@�\�ɂ́A�e����^���Ă��Ȃ����Ƃ������ꂽ�BLIXIL�ł́A�����̓d�C�����l�グ�̗�������܂��A�]���̏Ɩ��v���Ă��������A�ڋq�̃��C�t�X�^�C���ɍ������S�Ƒ̂ɂ₳�����G�R�ȕ�炵�������ł���Ɩ����߂����B �o�T�uRBB TODAY �v |
|
|
��NTT�t�@�V���e�B�[�Y���d�Ǔ��Ɩk�d�Ǔ��Łu�l�K���b�g�A�O���Q�[�V�����v�T�[�r�X���J�n �X�̌ڋq�̐ߓd�w�͂̌��ʂ����ł͂������K�͂Ȃ��̂ɂ����Ȃ�Ȃ����ANTT�t�@�V���e�B�[�Y���e�ڋq�̐ߓd�w�͂̐��ʂ��܂Ƃ߂ēd�͉�Ђɒ��邱�ƂŁA��K�͂Ȑߓd���ʂ����҂ł���BNTT�t�@�V���e�B�[�Y�͂��łɍ��Ăɓ����d�͊Ǔ��Ɗ��d�͊Ǔ��œ��l�̃T�[�r�X�����{���āA���Ȃ�̌��ʂ����邱�Ƃ��m�F���Ă���B �l�K���b�g�A�O���Q�[�V�����͓d�͉�Ђ���������d�͂ɑ��Ď��v���N������\�������܂������Ɏ��{����B�d�͉�Ђ���g�p�ʂ�}�����Ăق����Ƃ����˗���NTT�t�@�V���e�B�[�Y���A�ڋq�ɓd�q���[���Őߓd���˗�����B �ڋq���˗��ɉ����Đߓd����ƁANTT�t�@�V���e�B�[�Y�͂��ꂼ��̌ڋq�̐ߓd�K�͂����Z���A�d�͉�Ђ��狦�͋���B���̋��͋��������ɂ��āA�e�ڋq�ɑ��Đߓd�K�͂ɉ��������͋��z����d�g�݂��B�����������d�͂̏ꍇ�͌ڋq�Ƃ̒��ڌ_��ɂȂ�B ���͋��͓����d�͊Ǔ��ł�1kW������45�~�ŌŒ肾���A�k�C���d�͊Ǔ��ł�1kW������ő��160�~�ɂȂ�B�k�C���d�͂̏ꍇ�͌ڋq�S�̂̐ߓd�B���ɂ���ċ��͋��̑��z���ϓ�����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
����a�n�E�X�ACO2�r�o���ő�50���팸������z���^�H��� ���R�̗͂��������u�p�b�V�u�R���g���[���v��n�G�l�E�ȃG�l�E�~�G�l���s���u�A�N�e�B�u�R���g���[���v�A���z�ݔ���Y�ݔ��̃G�l���M�[�𑍍��I�ɊǗ�����FEMS�iFactory Energy Management System�j�A�u�X�}�[�g�}�l�W�����g�v���̗p���ACO2�r�o�ʂ��ő��50���ȏ�팸�\�B �p�b�V�u�R���g���[���F�H��̉�����ɁA���ˎՕ��⍂�f�M�Ȃǂ̊��z���Z�p�����A���n�����ɉ������ʕ�����C�v��ȂǁA���R�G�l���M�[�̗��p�Ɖ��K���̌����}���Ă���B�i��F�g�b�v���C�g�i�V���j�A���f�M���w�K���X�A����Ή���ǖʗΉ��Ȃǁj �A�N�e�B�u�R���g���[���F���z�����d�V�X�e����`�E���C�I���~�d�r�ȂǁA��i�̃V�X�e���Ŋ����ׂ�ጸ����B�i��F���z�����d�V�X�e���A���`�E���C�I���~�d�r�ALED�Ȃǂ̍������Ɩ����Ȃǁj �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���Z�F�d�H�A�������^�~�d�r�u���h�b�N�X�t���[�v�ʎY�|���ɐݔ����� 2013�N�x���Ɏ������^�~�d�r�ł���u���h�b�N�X�t���[�d�r�v�����Ɖ�����B2013�N4���܂ł�10���~�𓊂��Ď����C����ݒu�A���N�㔼�ɗʎY����v��B2020�N�x�Ɏ��Ɣ��㍂1000���~��ڎw���B���d�r�̓i�g���E�������iNAS�j�d�r�ƕ���ŁA�~�d�e�ʐ���L�����b�g���ł̎��p���������܂��B�ϓd���ȂǓd�͐ݔ��p�ւ̗̍p�����҂���A�X�}�[�g�V�e�B�[�i��������s�s�j�̎����ɍv������B �[���d��S������i�ł���Z���X�^�b�N�̗ʎY�Z�p��������B���������C���ɂ�荂�i�����ێ����Ȃ�������I�ɗʎY���邱�ƂŃR�X�g�ʂ����P����B ���،�A�ʎY�ݔ��\�z�ɒ��肷����j�B�����͊���ނ̐�������g�ݗ��Ă܂ł̈�ѐ��Y�̐����\�z����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
���d�͎s��̑S�ʎ��R���Ɍ����āA�V���x�̐v���i�� �ł��d�������_�́A���������R������Ă��m���ɓd�͂̋���������u�ŏI�ۏ�T�[�r�X�v�ƁA�S���e�n�̓d�C�����Ɋi�������Ȃ��悤�ɂ���u���j�o�[�T���T�[�r�X�v�̎������B���̂��ߋ������̓d�C���Ǝ҂ɑ��čŏI�ۏ�ƃ��j�o�[�T���T�[�r�X���`���Â��鐧�x�Ȃǂ�݂���l�����B �c��͓̂X�܂�ƒ�Ȃǂ�Ώۂɂ����u�ሳ�v���������A���v�Ƒ��̗͂����ΓI�Ɏア���Ƃ���A�s���v����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̕ی�K�v�ɂȂ�B �ψ���̈Ăł́A�d�C���Ǝ҂ɑ��ē��ʍ����E�����E�ሳ���Ƃ̔̔��d�͗ʂƔ��㍂�̕��`���Â��A���������̊i�����ł���悤�ɂ����Ȃǂ����荞�܂�Ă���B �����̎��R���ŏd�v�Ȗ�����S���̂��V�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj�ł���B�ʏ�͓d�͉�Ђ̑��z�d�l�b�g���[�N���g���Ď��v�Ƃɓd�͂��������Ă���B ������\�ɂ���̂��u�������x�v�ŁA���z�d�𐿂������d�͉�Ђ͎��v�Ƒ��̎g�p�ʂ�c�����Ȃ��狟������d�͂����邱�Ƃ����߂���B���̂��߂ɂ͒ʐM�@�\���������X�}�[�g���[�^�[�����v�Ƒ��ɐݒu����K�v������B�S���ŃX�}�[�g���[�^�[�̐ݒu���{�i�I�Ɏn�܂�̂�2014�N�x����ɂȂ錩���݂ŁA�d�͉�ЈȊO���狟��������v�Ƃɑ��Ă͗D��I�ɃX�}�[�g���[�^�[��ݒu���邱�Ƃ���������B�N��������͏ڍׂȎ��{�X�P�W���[�����l�߂邱�ƂɂȂ�B����܂Œ��ۓI�ɂ�������Ă��Ȃ������d�͎s��̑S�ʎ��R�������X�Ɍ�������ттĂ����B �o�T�u�X�}�[�g�W���p���v |
|
|
���ǂ��Ȃ�LED�Ɩ��K�i�A�ƊE�c�̂����� ���nj^LED�ɂ́A�傫�������āuJEL801�v�ƁA�uG13�v�̂Q�����݂���B2�̕����̋�̓I�Ȏs��ł̔���グ�́AG13�̗D������A���X�ɝh�R��ԂɈڍs���Ă���Ƃ̌����������A����ǂ���̕������嗬�ɂȂ��Ă����̂��ɂ��āA�K�i���̉e���������ł��Ȃ��ƂȂ��Ă���B�܂��A�������̓��D�ɂ����ẮAJIS�K�i���������D�����ɂȂ�\��������B �܂��A�����ɂ��ẮAJEL801��JIS�����������n�߂Ă���B2012�N9��26���A���{�d���H�Ɖ����LED�����v��JIS���Ă��쐬���A���{�K�i����ɒ�o���Ă���B2013�N�x�̑��������̔��s��������ł���B ���ۓI�ȋK�i�ɂ��ẮA2012�N9������A�d�����i�̍��ەW�������߂�u���ۓd�C�W����c�iIEC�j�v�ŐR�c���X�^�[�g���Ă���B���ەW����JEL801���̑�����Ȃ��ꍇ�́A���{�s�ꂪ�u�K���p�S�X���v���郊�X�N�����邱�Ƃ���A�o�Y�Ȃ��o�b�N�A�b�v�̐����Ƃ��Ă���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2013/1�@]�@�@�� |
|
|
�����F���A�����r�������e�i���g�d�͗\���V�X�e�����J�� �r���̕��d�Ղɓd�̓Z���T�[�����t���A�e�i���g���Ƃɖ����̓d�͎g�p�ʂƓd�̓s�[�N�𑪒肵�A���z�I�ȓd�C�������Z�o����B�s�[�N�d�͂�}�����ꍇ�͊�{������������B �f�[�^�̓N���E�h��̃T�[�o�[�ɏW��B�I�[�i�[��e�i���g�̓l�b�g�ɐڑ������p�\�R���ȂǂŃO���t�������f�[�^��������B �������u�����鉻�v���邱�ƂŁA�e�i���g�̐ߓd���d�C�����ɔ��f����Ȃ��Ƃ������s���������ł���B�I�[�i�[�̓V�X�e��������p�S����K�v�����邪�A�e�e�i���g�̐ߓd�ɂ�闿���팸���̈ꕔ�����Ε��S��}������B �V�X�e�����i��8�K���ăr���̏ꍇ�Ŗ�350���~�B���̕⏕��������������200���~���x�ɂȂ�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
���_�C�L���A�Z��̎��x�߂��銷�C���j�b�g�u�f�V�J�z�[���G�A�v�� ���x���R���g���[������d�g�݂́AHB�f�V�J�f�q�����A�M��������Ƌz��������������o���鐫���𗘗p����B�Ⴆ�Ύ�������������ꍇ�́A�q�[�g�|���v�ɂ���p�ʼn��O�̋�C�Ɋ܂܂�鐅�����z���E����������AHB�f�V�J�f�q�����M���A�z�����������������ɕ��o����B �M������ɐ�������t�܂ł��܂����ꍇ�A�܂��͕��o���鐅�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�́A�q�[�g�|���v�̎l�H�ق]���āA������8�̃_���p(�d��)�œ����̋�C���ɘH���ւ���B����ɂ��A�A���I�ɉ����Ə������ł���d�l�ƂȂ��Ă���B �{���i���g�����Ƃɂ��A�����̎��x��K�x��40�`60%�Ɉێ��ł��邽�߁A�~�J��Ă̏���������A�~�̉ߊ����ɂ��s������}���A�N�Ԃ�ʂ��ĉ��K�Ȋ����ł���Ƃ����B ���Ђɂ��ƁA�f�V�J�z�[���G�A�ƃG�A�R���p�����ꍇ�̏���d�͂��A���C��ȂLj�ʓI�Ȋ��C�ƃG�A�R���p�����ꍇ�Ɣ�ׂ�ƁA�N�Ԃ̏���d�͂��30%�팸�ł���Ƃ����B����ɁA�^�āE�^�~�ɂ�����d�͏���s�[�N���̋E���C�̏���d�͍��v���A�āE�~�Ƃ��ɖ�25%�팸�ł���Ƃ����B �Ȃ��A�f�V�J�z�[���G�A���g�p����ۂɂ́A�������̃h�����z�ǂ�������̋����z�ǁA�������͕s�v�ƂȂ�B �������̏���d�͂�520W�ŁA1���ԓ�����̏����\�͂�2.7kg�B�������̏���d�͂�280W�ŁA1���ԓ�����̉����\�͂�1.5kg�B �o�T�uImpress Watch�v |
|
|
�����Ń��C�e�b�N�A�H��A�q�ɂȂǂ̍��V���Ԍ���1kW�`LED�Ɩ��� 1kW�`���^���n���C�h�����v���V����Ɣ�r���ďȃG�l�Œ������̂��߁A�����ԓ_������ꏊ�⍂���Ȃǂ̃����v������Ƃ�����ȏꏊ�ɓK���Ă���B �����i�̓����͈ȉ��̒ʂ�B �y1�z�ȃG�l�E��������65%�̑啝�ȏ���d�͍팸���\�B������6������ �y2�z�����Ɠx��@�\�Ɩ�5���`100���̘A�������@�\�𓋍� �y3�z���͉��x�ő�50���܂Ŏg�p�\�B �Ȃ��A1kW�`�̂ق��ɁA���`�E�y�ʃ^�C�v��250W�`�y��400W�`���^���n���C�h�����v���V������̃��f���������ɔ����B�e���邳�Ƃ��ɁA�ǖʂȂǂ��L���Ƃ炵�Ė��邳�������߂���u�L�p�^�C�v�v�ƁA���ʏƓx���d�������u���p�^�C�v�v��2�^�C�v�̔z����p�ӁB����ɃI�v�V�������i�Ƃ��āu���ʃK�[�h�v�u�g�U�J�o�[�t�K�[�h�v�u���~���u��t����v�u�����h�~�p���C���[�v����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���p�i�\�j�b�N�u�X�}�[�g���[�^�[�v���ƎQ���Ċ�Ƃƒ�g�A���d���D�ɎQ�� �X�}�[�g���[�^�[���Ƃ�130�J���œW�J���A���E�Ŗ�2���̃V�F�A�����đ��A�C�g�����i���V���g���B�j�ƁA���T�ɂ��Ɩ���g�ō��ӂ��錩���݂��B����d�͂Ȃǂ̃f�[�^��d�͉�Ђɑ��M����p�i�\�j�b�N�̒ʐM�@��ƁA�A�C�g�������肪����v�����u��g�ݍ��킹�A�p�i�\�j�b�N�̃u�����h�Ŕ̔�����B�����I�ɂ͍��������łȂ��A�A�W�A�𒆐S�Ƃ����C�O�W�J������ɓ����B �����͔N�Ԗ�200���~�̔��㍂��ڎw���B�s�U�̔��^�e���r�Ȃǃf�W�^���Ɠd�ւ̉ߓx�Ȉˑ�����E�p���A���������҂ł�����E�G�l���M�[����ɒ��͂��Ď��v�̉��P��ڎw���B �X�}�[�g���[�^�[�͑o�����̒ʐM�@�\�������������^�̓d�͌v�B�d�͂̏�����ׂ����c���ł��A�ƒ���Ƃł̐ߓd���ʂ����҂ł���B���d��2014�N�x����10�N�Ԃň�ʉƒ��I�t�B�X�A�H��Ȃǖ�2700�����̑S�_��҂ɃX�}�[�g���[�^�[������v�悾�B ���B��͈�ʋ������D�őI�ԕ��j�ŁA�V�K�Q���̉\�����L�������B�p�i�\�j�b�N�̎Q���ɂ��A�X�}�[�g���[�^�[�̉��i��\���߂���J����������i�Ɖ������������B �o�T�uSankeiBiz �v |
|
|
�������K�X�E�O�Y�H�ƁA���Y�H���Ŕr�o�����p���������C�ɕϊ����鑕�u���J�� �{���u�ł́A�]���̃V�X�e���ł͌ʂɐݒu���Ă����M������ƈ��͗e��i�t���b�V���^���N�j����̉������B �]���̃V�X�e���ł́A�܂��M��������g���Ĕp�����ŋ��������߁A���߂��������͗e��ɑ���A�����ŏ����������邱�Ƃŏ��C��������B�{���u�ł́A�����̍����M����������͗e������ɑ������Ĉ�̉����A�M�����������������͗e��i�������j�̓����Ŕp�������琅�ɔM��`���邱�ƂŌ����悭���C�������邱�Ƃ��ł���B �������ȔM������ƈ��͗e��̈�̉��ɂ��A�ȃX�y�[�X�A�{�H��̍팸�������B�܂��A�{���u�́A�u���^���͗e��v�͈͓̔��̈��͗e���4�g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�]���́u���툳�͗e��v�łȂ���Γ����Ȃ������ʂ̏��C���u���^���͗e��v�Ƃ��Ĕ��������邱�Ƃ��ł��邽�߁A�N��1�x�̐��\���������s�v�ƂȂ�A�ێ��Ǘ�����팸�ł���B ��̉�����āA�W���I�ȏꍇ�Ŗ�6���̐ݒu�X�y�[�X���팸����ƂƂ��ɁA�{�H�������コ���{�H��̒ጸ��}�����B���N4������̔����J�n���� ����A�{���u�����p���A�K�X�G���W���R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e���̔p�M�������ł͂Ȃ����C�Ƃ��ĉ������V�X�e���̊J���Ɏ��g�ށB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����{�R�J�E�R�[���A�u�s�[�N�V�t�g���̋@�v��2013�N�x����25,000��ݒu �Ă̓�������d�͂�95%�팸����ƂƂ��ɁA�~�̓d�͗}���ɂ��v������u�s�[�N�V�t�g���̋@�v���A2013�N1������S���Őݒu���J�n����Ɣ��\�����B���N�x�̐ݒu�ڕW�䐔��25,000��B �u�s�[�N�V�t�g���̋@�v�͓d�͕N���ɑ��鎝���I�ȑΉ��Ƃ��ĊJ�����������̔��@�B1�N�̂����œd�͏���s�[�N�ƂȂ�Ă̓����ɁA�R�[���h���i��p�̂��߂̓d�̓[����B�����邱�Ƃ�ړI�ɒf�M������ыC���������߂��B�����̃s�[�N�V�t�g�e�N�m���W�[�̗̍p�ɂ��A��p�̂��߂̓d�͎g�p���A��ʓI�ɓd�͎g�p���u�s�[�N�v�ƂȂ��������A��r�I�d�͂ɗ]�T�������Ɂu�V�t�g�v���Ă���B ���̌��ʁA�Ă̓����ɗ�p�p�̓d�͂��g�킸����d�͂�95%�팸���Ȃ���Œ�16���ԗ₽�����i����邱�Ƃ��\�ɂ����B����ɁA�~�Ɉꕔ���i����������ۂ��A�g�p����q�[�^�[�̏���d�͂��]���@�Ɣ�ׂ�20%���Ȃ��Ȃ�A��p�Ɏg�p�������d�͂Ƃ��킹�Ă��A68%�̏���d�͍팸�ƂȂ邱�Ƃ��킩���Ă���B�s�[�N�V�t�g�e�N�m���W�[��������������̓I�ȍH�v�́u�S�̗�p�v�u�f�M���ʌ���v�u�C��������v��3�ɂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
��2011�N�̐��ECO2�r�o�ʂ͉ߋ��ō��A1�ʂ͒��� 2011�N�̐��E�̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ͑O�N����8���g������340���g���Ɖߋ��ō��ɂȂ�A�������ʃK�X�r�o�ʂ��ł��������͈��������������������Ƃ��A�h�C�c�ɖ{����u�����ԃV���N�^���N�A���یo�σt�H�[�����Đ��\�G�l���M�[�iIWR�j��13���̔��\�ŕ��������B ���l�͉p�G�l���M�[���BP�����J�������E�̉��ΔR������ʃf�[�^�Ɋ�Â��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�B�����̔r�o�ʂ�89���g���ŁA2�ʂ̕č��i60���g���j��啝�ɏ������B3�ʈȉ��̓C���h�i18���g���j�A���V�A�i17���g���j�A���{�i13���g���j�A�h�C�c�i8��400���g���j�Ƒ������B ���E��CO2�r�o�ʂ�2009�N�Ɍo�ϊ�@�̉e���ňꎞ�����������A�Ăя㏸�ւƓ]���Ă���BIWR�̃m���x���g�E�A���m�z�����͐����Łu���݂̌X���������A���E��CO2�r�o�ʂ�2020�N�܂ł�20�������A400���g���ɒB����v�Əq�ׂĂ���B �o�T�uAFP�v |
|
|
������23�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[����2012�j �t�c���� �o�ώY�ƏȎ����G�l���M�[���́A�t�c���肳�ꂽ����23�N�x�G�l���M�[�Ɋւ���N���i�G�l���M�[����2012�j�̓��e�����\�����B ���\�ɂ��ƍ���̔����ł́A��1�͂ŁA�����{��k�ЂŖ��炩�ɂȂ����ۑ���T�ς��A��2�͂ł͐k�Ќォ�炱��܂Łi2012�N7�����܂Łj�ɍu����ꂽ�d�́A�ȃG�l���M�[�E�V�G�l���M�[�Ɋւ����Ȏ{��A��3�͂ł͌��q�͔��d�����̂Ɋ֘A���čs��ꂽ��g�̊T�v�A����A����ւ̉ۑ蓙�����グ�Ă���B�����āA��4�͂ɂ����Č��s�̃G�l���M�[������[���x�[�X�Ō������ɓ������Đݒu���ꂽ�G�l���M�[�E����c�A���������G�l���M�[�������{���ψ�����͂��߂Ƃ���W�R�c��̍\���A�������ʓ����T�ς��邱�ƂŁA����܂ōs���Ă����G�l���M�[����̌������̌o�܂𖾂炩�ɂ��Ă���B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
��2011�N�x�̍ŏI�G�l���M�[����A�ߓd���ʓ��őO�N�x��2.9������ �o�ώY�ƏȂ́A�e��G�l���M�[�W���v�������ƂɁA�G�l���M�[�������т̑�������܂Ƃ߂Ĕ��\�����B ����ɂ��ƁA�u�ŏI�G�l���M�[����v�́A���Y�ʂ̌�����ߓd���ʓ��ɂ��A�O�N�x�䁣2.9���Ō����i1990�N�x��ł́{4.7���j�B �u�G�l���M�[�N���̓�_���Y�f�r�o�ʁv�́A���q�͔��d�̏�����~�A���ΔR������ʑ������ɂ��O�N�x��{4.4���ő����i1990�N�x��ł́{0.7���j�ł����B �܂��u�G�l���M�[���ʂ̍ŏI�G�l���M�[����v�́A���Y�ʂ̌�����ߓd���ʓ��ɂ��d�͂��傫�������i�O�N�x�䁣6.2���j�B����A�s�s�K�X�������i���{2.4���j�B�u�ꎟ�G�l���M�[���������v�́A���q�͂��O�N�x�䁣64.5���̌����B����A���q�͑�ւ̂��߂̉Η͔��d�̑������̉e���ɂ��A�V�R�K�X�i���{15.9���j�ƐΖ��i���{2.9���j�����������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���d�C�����i�K�I�ɋK���P�p�o�Y�Ȉ� �ƒ�����̎Q����ǂ������A�����̐ݒ�͒i�K��Ŏ��R������B���ʂ͊�]����ƒ�ɂ͍��̋K�������ł̋������`���Â��A�K�������Ǝ��R�����������Ă����A�������i���_�Ŏ��R�����Ɉ�{������B ������A���N�̒ʏ퍑��ɓd�C���Ɩ@�̉����Ă��o���� �܂��A�Q���K�����Ȃ����A�V�d�́i����K�͓d�C���Ǝҁj�Ȃǂ���ʉƒ�ɋ����ł���悤�ɂ���B�����K����3�`5�N�قǂ̈ڍs���Ԃ��o�Ė������B �K�����ꎞ�I�Ɏc�����A�d�͊e�Ђ͎��R������V���ɐݒ�ł���B�Đ��\�G�l���M�[�̓d�C����������A���͍��������肷�闿�����o�ꂵ�����ŁA����҂̑I�����͑�����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/12�@]�@�@�� |
|
|
�����R�[�A�H���s�v�̒��nj`LED�����v�� ����܂ŁA�I�t�B�X�ōł����v���傫��40�`���E�̔����Ă������A����40�`�̌�p�@��̔����ɍ��킹��110�`��20/16�`�������A���C���A�b�v�̋�����}��B����ɂ��A�]���̈�ʃI�t�B�X�A�w�Z�A�X�܂����łȂ��H���q�ɂȂǂ̑�^�{�݂ւ̓����E�g�̂�i�߂Ă��������l�����B �V���i�̓����́A �i1�j�O���[������s�b�h�����A�C���o�[�^�����̌u��������u���ǂ��͂����āA���̂܂ܑ����������Ɏg�p���\�B�H���s�v�ŁA�������̃R�X�g�Ǝ��Ԃ̍팸�ɍv������B �i2�j�}�O�l�V�E����������M�t���[���Ƃ��č̗p�BLED��������M�������I�ɕ��M���邱�ƂŁA�M�ɂ��p�Ȃ�h���A�������̂𖢑R�ɖh�~����B�{�f�B�ɂ͌y���Ċ���ɂ������������|���J�[�{�l�[�g�f�ނ��̗p�B �]���̌u�����Ɏg���Ă���G13�����ɒʓd�X�C�b�`�@�\���v���X�������R�[�Ǝ��J����G13���d�h�~�������̗p�B�ݒu����O�������S�ɍs�����Ƃ��ł���B �i3�j���R�[�Ǝ��̃A�i���O�d���Z�p�̗̍p�ɂ��A�_�����̂������}���B�E���O���i�g��400nm�ȉ��j���o�����A��Ȃǂ̒������t���ɂ����A����Ɉߕ��Ȃǂ̐F�������}����B �i4�j�u�����Ƃقړ������邳��CO2�Ə���d�͂̍팸�ɍv���B�܂��A��4�����Ԃ̒������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���p�i�\�j�b�N�ҋ@�d�͂��[���ɂ����������֍��� �g�C�����g�p���Ă��Ȃ��Ƃ��̑ҋ@�d�͂��[���ɂ����������֍����B�l�̏o������Z���T�[�Ŋ��m���ďu�ԓI�ɉ��߂�Z�p���J�����A�ҋ@�d�̓[�������������B �ꕔ�̋@��ɂ́A����������ĕ֍��̊J�Ȃǂ��ł��郊���R���𓋍ځB�s��z�艿�i��6���~�`10���~�O��B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
���p�b�V�u�n�E�X�E�W���p���A�Z��̏ȃG�l�E���M���\���r�ł���}�b�v���E�F�u��Ō��J ���}�b�v�́A�����ɏZ�1�N�Ԃɏ����Ɨ\�������G�l���M�[�ʁi�����A�g�[�A��[�A�Ɩ��A�����A���C�y�т��̑����́j�A�c���ɏZ��̋�̂�1�N�ԂɕK�v�Ƃ���g�[���ׂ�������A���ɗD�����Ƃ��ǂ����A���x�����ƌ��N���X�N�̑召���q�ϓI�ɔc�����邱�Ƃ��ł���B ���{�ŏZ������Ă悤�Ǝv���ƁA�����̏Z��[�J�[�̐��\��r���s���ɂȂ邪�A�Z��̏ȃG�l���\�⌚�����̉��M���\�ɂ��ĕ�����₷�����f�ޗ����Ȃ����߁A�f�M���ʂ̒Ⴂ�Z��ɏZ�݁A�����̃G�l���M�[������Ă���̂�����B ���݁A���R�G�l���M�[�ւ̃V�t�g������Ă��邪�A�܂��͏ȃG�l����{�Ƃ��A���ɏZ��Ɋւ��ẮA�f�M��p�b�V�u�f�U�C���Ȃnj����̋�̋����ɂ��ȃG�l���K�v���B�����ŏZ��̏ȃG�l�@�\����₷���\������ڈ��Ƃ��āu�����̏ȃG�l�~���N�}�b�v�v�̊J���Ɏ������B �Ȃ��A�p�b�V�u�n�E�X�E�W���p���́A�h�C�c���˂̒��ȃG�l�Z��A�p�b�V�u�n�E�X���������A���{�̋C��A�����l���ɍ��킹�����{�^���ȃG�l�Z��̊m����ڎw����c���^��ʎВc�@�l�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���匎�s�������a�@�F�n���M���p����g�[�A������CO2�ƋR�X�g�팸 �V�V�X�e���͗��N���܂łɊ����\��̐V�a���ɐ݂��A1�K�t���A�i�O���ҍ��A�z�[���Ȃǖ�630�������[�g���j�̋ɓ�������B �~�n�̒n��100m�܂Œ��a��17cm�̌���15�{�@���Ĕz�ǂ�ʂ��A�n��ƒn���̊Ԃɉt�̂��z�����A�q�[�g�|���v���O�@�Ƒg�ݍ��킹�ė�g�[���s���B �����̋C���́A�Ă�35���܂łɂȂ�A�~�͎R�ԕ��ŕX�_��10�x�߂��ɂȂ�ȂNJ��g�����������B����A�n���̉��x�i�n���M�j�͂ǂ��ł��N�Ԃ�ʂ���10�`14���Ƃقڈ�肵�Ă���B���̂��߁A�G�߂⒋��ɂ�����炸���肵���M���p���ł���Ƃ����B �����Ɣ��5670���~�ŁA���̂���2670���~�͍��́u�n��Đ��\�G�l���M�[�M�������Ɓv�̕⏕����������B�s�ɂ��ƁA�n���M���p�ɂ��A�N�z��100���~�A��_���Y�f�̔r�o�ʂ͔N�Ԗ�20�g���̍팸�������܂��B �o�T�u�����V���v |
|
|
���f�[�^�Z���^�[�͎���x��̊��K����E�p���\�\�O���[���E�O���b�h �f�[�^�Z���^�[�̏���G�l���M�[�������Ɏ��g�ދƊE�c��Green Grid�́A�f�[�^�Z���^�[�̉��x�A���x�����݂����啝�ɍ������Ă��A�ݔ��S�̂̌̏ᗦ�ɉe����^���邱�ƂȂ��^�p�ł���Ƃ̌������������B Intel�͌ڋq�ɑ��A�f�[�^�Z���^�[�̉��x���グ��悤���߂Ă����B���Ђ͍��N���߁A��Ƃ͉��x��1���グ�邲�ƂɁA�G�l���M�[�E�R�X�g��4�����ߖ�ł���ƌ���Ă���B Dell�͌��݁A���O�̋�C���p�ɗ��p����uFresh Air�v�\�����[�V�����𐄐i���Ă���BDell�̍ŐV����T�[�o�ł́A�]���̃T�[�o�E�C���t������10���������x�œ���ł���悤�ɐv����Ă���B�������쉷�x�ɑΉ����ă��[�N���[�h���C���e���W�F���g�Ɍ��m�A��������d�g�݂ɂ���āA�����������삪�\�ɂȂ��Ă���B ����܂ł͑����̏ꍇ�A35�������쉷�x�̏���������B��������鉷�x�ł̓���e�X�g�͍s���Ă��Ȃ������B�������A�ŐV�V�X�e���́A45���ł����삳���邱�Ƃ��ł���B����ɁA�ڋq�́A���x�������Ȃ肷�����ꍇ�A���A�v���P�[�V�����������I�ɕ�����悤�Ƀ|���V�[��ݒ�ł���Əq�ׂ��B�T�[�o���̃t�@�����A���x�̋}���ȕω��Ɏ����I�ɑΉ�����悤�Ƀv���O���~���O�\���Ƃ����B �o�T�uGreen Grid �v |
|
|
���Z�F�����A�Z�F���w�Ȃǂ�CO2�������Ƃ��s���V��Ђ�ݗ��A�u�������@�v�𗘗p �K�X���ߖ��J���x���`���[�̃��l�b�T���X�E�G�i�W�[�E���T�[�`�ȂǂƋ����o���ŁACO2�������Ƃ��s���V��Ђ�2012�N���ɐݗ�����B ���f������V�R�K�X�����Ȃǂ̃v�����g�Ŏ��p������Ă���]���̕��@�Ɣ�ׁA�G�l���M�[�����啝�ɍ팸����u�������@�v�𗘗p���A1�N�ȓ����߂ǂɖ{�i�I�Ȏ��Ɖ���ڎw���B �V��Ђ́A���{��8���~�ŏZ�F�����ƏZ�F���w��47.5�����A���l�b�T���X��5���o������B�Ɨ��s���@�l�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO�j�Ȃǂ̎x�����ă��l�b�T���X���J������CO2��I��I�ɓ��߂��閌����ɁA���E�ō������̕����\�͂��������J���B�D�ʐ����m�F�ł������Ƃ���A�����グ��B �������@�͖��ō����K�X����e�C�̂�����B�H�����ȑf�ŃG�l���M�[����ጸ�ł��ACO2��������Ēn���ɒ�������Z�p�uCCS�v�ł��ACO2�̕����E����R�X�g��}���ł�����@�Ƃ��Ċ��҂���Ă���BCO2�������Ƃ̎s��͐��E�ŔN�Ԗ�3���~�Ƃ���A�V�����ł̊g��������܂��B�V��Ђ́A�ʎY�̐��⎖�ƃ��f���̌����Ǝ��؎�����i�߂�B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
�����z���E�؎��y���b�g�֎s���o����2.5���~�A�u�n��MEGA���Ђ��܃t�@���h�v ���Ђ��ܐi���G�l���M�[�́A���z�����d�ݔ��ƃy���b�g�X�g�[�u�̓�����ړI�ɁA8���ɕ�W���J�n�����s���o���t�@���h�u�n��MEGA���Ђ��܃t�@���h�v�ɂ��āA��W3�J���Ԃ�250����荇�v��2.5���~�̏o�����Ɣ��\�����B ���Ђ́A�s���̏o���ɂ��u���Ђ��܃t�@���h�v��ʂ��āA���z���A���͔��d�A�X�ю����Ȃǒn��̃G�l���M�[�����p�������R�G�l���M�[���Ƃ��������A���g���h�~�ƒn�Y�n���̏z�^�̒n��Â�����s�����Ƃ�ڎw���Ă���B ��̓I�ɂ́A�{�t�@���h�ł́A1��10���~��50���~��2��ނ̌_��ň�ʂ̎s�����o������A���쌧��M�B�𒆐S�ɁA�����O�̘A�g�n��ɂ����āA���z�����d�ݔ��ƃy���b�g�X�g�[�u�̓������s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��W���z��4���~�B�ڕW���z�����2.0�`3.0����\�肵�Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���o�Y�ȁA�R�W�F�l�̓������i�Ɍ����ēd�C���Ɛ��x�̋�����ɘa �H�ƒc�n�ȂǂŃR�W�F�l�ɂ�蔭�d�����d�C����������ꍇ�A�d�C���Ɩ@��́u���苟���v�̋�����K�v�����邪�A���s�̐R����ɂ����ẮA�����҂̔��d�ݔ��ɂ����v��100%�������Ƃ��v���Ƃ���Ă���B����A�R�W�F�l���܂ޕ��U�^�d���̓������i��}�邽�߁A���Y���d�ݔ��ɂ����v��50%�ȏ�����A�s�����͓d�͉�Г�����o�b�N�A�b�v���邱�ƂőS�Ă̎��v�����`�ł̋������s�����Ƃ��\�Ƃ��鐧�x�̉^�p���P���s���B �d�C���Ɩ@�ɋK�肳���u���苟�����x�v�́A �i1�j�d�C�̋����҂Ǝ��v�҂ɐe��ЂƎq��Ђ̊W������ꍇ��A �i2�j�����̎҂��g����g�D���ăX�}�[�g�R�~���j�e�B���`������ꍇ�ȂǁA ���҂ɖ��ڂȊ֘A��������ꍇ�ɁA���҂����ӂ����_��Ɋ�Â��A���c����p���ēd�C�̋������s�����Ƃ�F�߂Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���J�[�{���E�f�B�X�N���[�W���[�E�v���W�F�N�g�����{��Ƃ̒������ʂ����\�g�b�v�̓\�j�[ �{���ł́A��Ƃ̋C��ϓ��ւ̎��g�݂��u�f�B�X�N���[�W���[�i���J���j�v�Ɓu�p�t�H�[�}���X�i���сj�v��2�̎��ŕ]�����Ă���B���J������Ńg�b�v�ɂȂ����̂̓\�j�[�A�����œ��X�R�A�Ńp�i�\�j�b�N�A�z���_�A�c������3�Ђ�2�ʂŕ��Ԍ��ʂƂȂ����B�ȉ��A5�ʂ͓��{�X�D�ƕx�m�ʁA7�ʂ͏��D�O��A8�ʂ͑听���݂ƂȂ��Ă���B�܂��A�p�i�\�j�b�N�́A�p�t�H�[�}���X�i���сj����ł��g�b�v�ƂȂ����B ����A���{��Ƃ�Ώۂɂ������⏑�ɂ�233�Ђ������B���͑O�N��4������47���A���J���X�R�A�̕��ς͑O�N��6�|�C���g����67���ƂȂ�A�Ƃ��ɑO�N�����サ�Ă���B �������A���E�̑����500�Ёi��81���A�X�R�A����77�j�Ɣ�ׂ�ƁA�ˑR�A���P�̗]�n�͑傫���Ȃ��Ă���B ���{��Ƃ͖ڕW���f���Ă���ɂ�������炸�A�����I�Ȏ�g�݂ł͌�������Ă�����Ԃ����炩�ƂȂ����B�܂��A�������3�N���̐ݔ��������s�����{��Ƃ��������Ă���A�����I�Ȏ��_�ʼn��g����Ɏ��g��ł���X�������炩�ɂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���X�܉c�Ƃɂ����閳�ʂȃG�l���M�[�g�p�̔r���ƏȃG�l���M�[�̂����������܂Ƃ� �s���E���Ǝ҂̏ȃG�l�ӎ������܂�A�l�X�ȏȃG�l�E�ߓd�̎�g���i�ވ���ŁA��K�͓X�܂�`�F�[���X�ɂ�����J�������Ȃǂ̖��ʂȃG�l���M�[�g�p�ɂ��Ė���N���Ȃ���Ă���B�����������Ƃ܂��A�s�ł́A�X�܉c�Ƃɂ����閳�ʂȃG�l���M�[�g�p�̔r���ƏȃG�l�̂�������ɂ��āA�������d�˂Ă����B���̌��� �i1�j�����Ȃ��X�܂�A����߂邱�Ƃ�����X�܂ł����Ă��A�o������t�߁i2���[�g�����x�j�̋��~���邱�Ƃ��L���B���ɁA��K�͓X�܂⓯�l�ȓX�܌`�Ԃő��X�ܓW�J����`�F�[���X�Ȃǂɂ����ẮA���悵�����������K�v�B �i2�j���߂ׂ̍����ȃG�l��́A���i�Ǘ��̓O���A���܂߂ȋǗ��Ȃǂ�ʂ��āA�ڋq�T�[�r�X�┄�グ�̌���ɂ��v���E���i�W���ɂ́A���͂�3�{�ȏ�̏Ɠx�����K�v�B�ʘH���̏Ɠx�������邱�ƂŁA�Ɠx�����߂Ȃ��Ƃ����i���ڗ��悤�ɂȂ�B �ȂǁB ����A�X�܂ɂ�����ȃG�l���M�[�ƓX�܂̖��͌���̍l�����y����ƂƂ��ɁA��̓I�ȑ�����ȂǁA�X�܂ɂ�����ȃG�l���M�[�𐄐i����B http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2012/11/DATA/40mb5100.pdf �o�T�u�����s���ǁv |
|
|
�����ȁA�d�͉�ЂƓd�C���Ǝ҂�CO2�r�o�W�������\ ����23�N�x�̓d�C���Ǝҁi��ʓd�C���ƎҁA����K�͓d�C���Ǝҁj���Ƃ̎��r�o�W���y�ђ�����r�o�W���������\�����B �n�����g����̐��i�Ɋւ���@���Ɋ�Â��u�������ʃK�X�r�o�ʎZ��E�E���\���x�v�ɂ��A��_���Y�f���̉������ʃK�X�����ʈȏ�r�o���鎖�Ǝҁi����r�o�ҁj�́A���N�x�A�������ʃK�X�Z��r�o�ʁA�y�ы��s���J�j�Y���N���W�b�g�⍑���F�ؔr�o�팸�ʓ��f�����u�����㉷�����ʃK�X�r�o�ʁv�����Ə��Ǒ�b�ɕ��邱�Ƃ��`���t�����Ă���Bhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15912 �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2012/11�@]�@�@�� |
|
|
���c��A�p�\�R��1�䂾���Łu�d�͎��v�\���v���\�ȃ\�t�g���J���c�c��Ƃ�EMS�ŗL�� ������̊�b���_�Ƃ��čL�����p����Ă���u�t�B���^�����O���_�v�ɂ��p�����[�^����Z�p��p�����Ǝ��̃A���S���Y���ɂ��A��Ƃɂ�����Z���Ԃ̓d�͎g�p�f�[�^��PC1��ŁA�d�͎��v�\�����\�Ƃ����B��Ɠ��̃G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���iEMS�j�ł��L�����p�ł���Ƃ̂��ƁB �܂��A�d�͎��v�Ȑ��̓������l�����A�\���ɗL�p�ȏ��ʂ���f�[�^���������s�B���ɁA�ߋ��̔��d���f���Ɋ�Â��A�t�B���^�����O���_��p���ė\���l���v�Z����B�啝�ɏ��Ȃ��f�[�^�ʂ���A�]����@�Ƃقړ����x�̐��x�ŗ\���ł����@�ƂȂ��Ă���B �����O���[�v�ł́A����A�d�͎��v�\���l�̐��x�����コ���Ă������A�u���d�ʂ̗\���v�\�t�g�̍쐬�ɂ����g�ޗ\��B �o�T�uRBB TODAY�v |
|
|
���f�W�^���O���b�h�R���\�[�V�A�����n����œd�͂�Z�ʂ���d�̓��[�^�[���J�� �d�̓��[�^�[�́A�Đ��\�G�l���M�[�ō�肾�����d�͂�n��������ŗZ�ʂ��������ƂŁA�n���d�͂ւ̕��ׂ��y��������A��d�Ȃǂ̂Ƃ��͓���̎{�݊Ԃœd�͂�Z�ʂ����肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ�B ���z���╗�͂Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�����y����ƁA�n���d�͂ւ̕��S���傫���Ȃ邽�ߐݔ��̕��S���d���Ȃ�Ƃ���Ă���B�n���d�͂���d���Ă��܂��ƁA�n����̓d�͂��S�̂ɋ����ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����ۑ������B ���N�x���ɕč��Ŏ�����B�܂��͉ƒ��r���ȂǏ��K�͂̎{�݂Ŏ����A�X�}�[�g�V�e�B�ցi���z���^�s�s�j�̎��ȂǂɍL���A5�N��̎��p�����߂����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
���O�H�d�@�Ɩ��A���ⓔ�����ݖ��邳��LED�Ɩ��� ���ⓔ700���b�g���Ɠ������炢�̖��邳���\�ɂ��������_�C�I�[�h�iLED�j�̓V��p�V�[�����O������B���邳�����߂���H��Ȃǂł̎g�p�ɓK���Ă���B���i�͏����Ɠx��^�C�v��24��8000�~�A�A�������^�C�v��25���~�B ����d�͂������邱�Ƃ��ۑ肾�������P�x���d���iHID�j����̑�֎��v�������ށB������3��1000���[�����ŁA����d�͂�308���b�g�B����������6�����ԁB�F���x��5000�P���r���ŁA�A�������⑦���_���ɑΉ������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
�������A�v���C�A���X���nj^LED�ŐV�K�i��ł��o�� �V���ɊJ�������̂́uJEL802�v�Ƃ����K�i�B�����̌`��͊����̌u�����Ƃ��Ȃ������A���̃\�P�b�g�̕������������Ȃ��Ƌ��d�ł��Ȃ��d�g�݂��̗p�����B ����Ďg�����ۂɔ��Ύ��̂Ȃǂ��N���Ȃ��v�ɂȂ��Ă���B���S�̂���������K�v���Ȃ����߁ALED������ۂ̔�p��}������B ���N3���ɓ��{�d���H�Ɖ�̋K�i�Ƃ��Đ����ɔF����Ă���B�������������߁A1���b�g������110���[�������̖��邳�����������B�Ɠx�������ŕ���鐻�i���p�ӂ����B�uJEL801�v�ƁuG13�v�Ƃ���2�̋K�i�����݂��邪�A�d�l�ʂȂǂœ������Ȃ����S�ʂȂǂ�s�������鐺������B�����2�̋K�i�̗ǂ��Ƃ������荞�݁A�ڋq�̕��L���j�[�Y�ɑΉ����A�g������ƈ��S���𗼗������Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
���O�H�������J���d�C�g��ʗ�[�Z�p�����C�z���ށuAQSOA�v�ɒ��ڏW�܂� �]���̋z���ނ́A��������o���邽�߂�100���ȏ�̔M��������K�v�����������A�A�N�\�A�͌����̍\�����ψ�ɂ��邱�Ƃ�60�`80���̔M�ŕ��o�ł���悤�ɂȂ����B �A�N�\�A���������z�����悤�Ə����������ۂ̋C���M��5�`15���̗␅����邱�Ƃ��ł��A�H��Ȃǂ̔r�M�ŋz�����������C�𐅂Ƃ��ĕ��o�����ďz�����邱�Ƃŗ�[�ݔ��Ƃ��ċ@�\���邱�ƂɂȂ�B �܂��A�����̋z���A���o�𐧌䂷�邱�Ƃʼn����A�����Ȃǂ̋Ƃ��Ă����p���邱�Ƃ��ł���B���̋V�X�e���́A���x�����ɕۂ����܂܁A���x�������R���g���[���ł���B���̂��߁A�����I�ɂ̓I�t�B�X�Ȃǂւ̗p�r�g���ڎw���Ă���B�O�H�����́A�A�N�\�A���g�p�����M�������@�̕��ނ��肪���Ă���A���Ǝ{�݂�w�Z�A�H��ȂǁA���łɍ����O�ő����̔[�����т����B���ˍH��i�_�ސ쌧���ˎs�j���̌����ݔ��̈�p�ɁA�A�N�\�A���g������̊��ł���X�y�[�X���J�݂��Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
���o�Y�ȍĐ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�ɂ����郂�f���_�����\ �P�D�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�ł́A�Đ��\�G�l���M�[�𗘗p�������d���Ƃ��s�����Ǝ҂́A�d�C���Ǝ҂ƌ_������������ŁA�Đ��\�G�l���M�[�R���̓d�C����Ԃɂ킽���Ĕ��承�i�Ŕ�������Ă��炤���Ƃ��ł���B �Q�D���ʁA���̍ۂ̌_�ɂ��āA�Đ��\�G�l���M�[���d���Ǝ҂Ɠd�C���ƎҊԂł̉~���Ȍ_������Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ɍo�ώY�ƏȂłP�̃��f�����������ƂƂ����B���̃��f���_�́A�Đ��\�G�l���M�[���[�@�₻�̊֘A�@�߂̋K��Ƃ̐����������A���Z�@�ւ���̎������B�ɓ������Ă̎�����̗v���������܂��쐬���Ă���B �i���j�Ȃ��A����쐬�������f���_�́A�ȉ��̏ꍇ��O���ɒu���č쐬���Ă���B �@�@�d�C������Ă��炤������Ɠd�C���Ǝ҂ƌn���A�n�̘A�n��̓d�C���Ǝ҂����� �@�A�ݔ��F�����500kW �ȏ�̑��z���y�ѕ��͔��d�ݔ��𗘗p �@�B�ݔ��F��������d�ݔ��̌��ݒ��H�O�ɓ���_��y�ѐڑ��_������ �@�C���d���Ƃ��s���ɂ�����A���Z�@�֓�����̎������B�����{ |
|
|
���d���`LED�Ɂu���S���v�̐V������Ŏc���ꂽ�ۑ� 2012�N7��1���A�����d�C�p�i���S�@���{�s���ꂽ�B���̔w�i�ɂ́ALED�Ɩ��s��ŁA�V�K�Q���̊�Ƃ��������A�e���i�����ʂ��郊�X�N�����܂��Ă������Ƃ�����B���ۂ̕s�����͑����͂Ȃ����̂́A����ł��Ĉ��S����S�ۂ���K�v���������B ���{�d���H�Ɖ�̎��哝�v������ƁA�d���`LED�����v�̏o�ׂ��{�i�I�Ɏn�܂����̂�2009�N�ŁA���N�x�͖�200�����������A���N�ł�5�{��1,000���ƂȂ�A3�N�ڂ�2011�N�͖�2.4�{��2400���ƂȂ�ȂǁA�{�X�Q�[�����鐨���Ő������Ă���B ����܂œd���Y���Ă����̂́A��K�͂Ȑ��Y�ݔ�����������ꂽ���[�J�[�������B�Ƃ��낪�ALED�̏Ɩ��͏��肪�قȂ�B��������f�q��������ł���A�g���Ăɑ傪����Ȑݔ��͕K�v�Ȃ��A�Q����ǂ��]���̃K���X�̓d�������Ⴍ�Ȃ��Ă���B�܂�A�ǂ̂悤�ȃ��[�J�[���Q�����邩������Ȃ��B���̂��߁A�ߋ��Ɠ����悤�Ƀ��[�J�[�̎���K���ɔC���Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��B���������w�i������A�ٗ�Ȃ܂łɑ����^�C�~���O�ł̈��S���m�ۂ̃��[�����ɂȂ������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����Ȓ����r���̏ȃG�l�x�� ��s�ȂNj��Z�@�ւɒ����r���̏ȃG�l���C���t�@���h�̐V�݂𑣂��B���̃t�@���h���r�������A���C���������Ŕ��p����B �⏕�\���͐V�݃t�@���h�����{����B������ƂɏȃG�l���͂����߂�_������邱�ƂȂǂ�⏕�����Ƃ���B�⏕���z�͂P��������5000���~�O��ɂȂ錩�ʂ��ŁA�N��10�`20����ڎw���B ���C���������r���ɂ́u�����\���D��Ă���v�Ƃ��āA��Y�f���C�̔F���^���A�����̔��������₷������B�����\�̊i�t���̓L���X�r�[�Ȃǂ��Q�l�ɓƎ��ɍ��B���^�@����������Ή��ɍX�V���Ă��銄���́A��^�r����46.5%�ɑ��A�����r����30.5%�ɂƂǂ܂�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
��8�������_�̍ăG�l�ݔ��F��A130��kW�� 2012�N8�������_�ł̍ăG�l�ݔ��F��i�����A�o�́j�����\�����B����ɂ��ƁA2012�N�x�ɂ����āA4���`8�����܂łɖ�68��kW�������ς݁A���̂���9���ȏオ���z�����d�ƂȂ��Ă���B ���N�x�㔼�ɂ����đ�K�͂ȃ��K�\�[���[�������^�]�J�n����\��ł���A��Z��z���̐L�т��傫���Ȃ錩���݁B�܂��A�Œ艿�i���搧�x�J�n�Ȍ�A�o�ώY�Ƒ�b�ɂ��ݔ��̔F������V�K�ݔ��́A8�������_�Ŗ�130��kW�Ə����Ȋ���o���ƂȂ��Ă���B ��̓I�ɂ́A�u���z���i�Z��j�v��4�`8�����܂łɉ^�]�J�n�����ݔ��e�ʂ́{60.0��kW�A8�����܂łɔF������ݔ��e�ʂ�30.6��kW�ŁA�N�x���܂ł̓����\���́{��150��kW�ƂȂ��Ă���B�u���z���i��Z��j�v��4�`8�����܂ł̐ݔ��e�ʂ́{5.5��kW�A8�����܂ł̐ݔ��e�ʂ�72.5��kW�A�N�x���܂ł̓����\���́{��50��kW�ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
����N�x�̃R�[�W�F�l�����A�@��̐V�ݑ䐔�قڔ{�� �R�[�W�F�l���[�V�����E�G�l���M�[���x���p�Z���^�[��2011�N�x�̃R�[�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�������тɂ��ƁA�V�K�ݒu�䐔�͑O�N�x��96�E9������447��A���d�e�ʂ�8�E3������9��4673�L�����b�g�������B �R�����i�̍����ő䐔�A���d�e�ʂƂ���5�N�x�ȍ~�����𑱂��Ă������A�����{��k�Ќ�̐ߓd�ӎ��̍��܂�ŕa�@��V�l�z�[���ȂǏ����̗��p�҂����������Ƃ���A�䐔�ɂ��Ă�7�N�Ԃ�ɑ����ɓ]�����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
���~�M�E�f�M�p�̐V�f�ފJ�����ȏȁA�T�Z�v��70���~ ������G�l���M�[���p�Z�p�J���̈�Ƃ��Ď��g�ނ��̂ŁA�H��p�M�d�ɗ��p������A�d�C�����Ԃ̎ԓ������f�M���ł���f�ނ��J���������l�����B 2013�N�x�T�Z�v���Ƃ���70���~���v��B���̈ꕔ�����p���A����őI�肵����w�⌤���@�ւȂǂɂ��~�M�E�f�M�V�f�ނ̊J�����Ƃ��㉟������B �H�ꂩ��o��p�M�����������͗l�X�Ȍ`�ŗ��p���i��ł���B�������ቷ�ɂȂ�ƁA���̂܂̂Ă���ꍇ�������B�������ꂽ�P���G�l���M�[�̑唼���g����Ă��Ȃ����Ƃɏœ_�āA�H��p�M��200�`300�x�̒�����Ԃŕۉ��E�����ł���~�M�ނ��J���������l���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/10�@]�@�@�� |
|
|
���U�C�}�b�N�X�r���e�i���g���ƂɓK���ȏ���G�l���M�[�ʂ̎Z���@���J�� ���s��w�Ƌ����ŊJ�������B�r���Ǘ��E�^�c�Ɩ��Ȃǂ�ʂ��ďW�v�����s��144��990�e�i���g���̃f�[�^�Ɖߋ��̃G�l���M�[�g�p�ʂ̎��т�˂����킹�K���ȃG�l���M�[����ʂ�����o���������l�Ă����B �ʗv�f�ɐ��荞�ނ̂́A�����ϋC���̗\����e�i���g�̋Ǝ�A�I�t�B�X�̗p�r��]�ƈ����x�A���ؖʐςȂǂ𐔒l�ɒu�������Đ����ɂ��Ă͂߂�B�r���̏ȃG�l���M�[�̐��v�́A�����̒f�M���\��Ɩ����̏ȃG�l���\�ƌ������u�n�[�h�̑��ʂ���G�l���M�[����ʂ�����o���̂���ʓI�B����A������i�߂Ȃ��獡��̐����I��@���A���Ђ̃r�����L�Ҍ����̃R���T���e�B���O�T�[�r�X�Ȃǂɐ��������j�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
������OKI���Ռ��l�b�g�ōH��̋�2���ߓd ��2400m2�̍|�S���̉�����2000m2�̎Ռ��f�M�f�ށu�N�[�����[�t�l�b�g�v��ݒu�����B �|���G�X�e����R�����g�����Ԗڂׂ̍����l�b�g�ŁA�����\�ʂւ̔M�`�����������Ȃ�������ɗ��܂����M�������ʂ�����B�H��̉����̕\�ʉ��x���20���A������3����������ʂ��������B7���̍H��S�̂̏���d�͗ʂ�O�N��3��2000kWh�i14���j�팸�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
�����̊J�����Œʕ�10�{�|LIXIL�A�E�C���h�L���b�`���[���ʂ����� ���؎����͓����ꃊ�T�[�`�L�����p�X���ɂ�����؎����Z��uCOMMA�n�E�X�v�ōs�����B �E�C���h�L���b�`���[���ʂ��鑋�J�����@�Ƃ��̌��ʂ������Ȃ����J���̕��@���قړ�������Ō������Ƃ���A��10�{���̊��C�ʂ̍������邱�Ƃ����������B���̌��ʂ܂��A����A���R�G�l���M�[�����p�����������x�������悭������u�p�b�V�u�Z��v�̊J���Ɏ��g�݁A���K�ȏZ��Ԃ̎�����i�߂�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
����ʂ肻�ȋ�s�A���z�����d�ƏȃG�l�������x������l�������[�����J�n ��ʂ肻�ȋ�s�́A�n�����Z�@�ւƂ��đ��z�����d�ݔ��̓������x�����邽�߁u��ʂ肻�ȃ\�[���[���[���i���S�ی^�j�v�̎戵����9��3�����J�n����B �����i�́A��ʌ��́u�d�͎����Z����y���i���ƕ⏕���x�v�̏������āA�l�ڋq������ɐݒu���鑾�z�����d�ݔ��ƁA����ɔ����ȃG�l��̓���������Z���ΏۂƂ������́B�ʏ�̃��t�H�[�����[�������Ⴂ���������Ŏ�舵���A�S�ہE�ۏؐl���s�v�ł��邱�Ƃ������B�Z�����z�́A10���~�ȏ�1000���~�ȓ��i1���~�P�ʁj�B�Z�����Ԃ́A1�N�ȏ�15�N�ȓ��i1�N�P�ʁj�B�ؓ������́A�ϓ�����2.350���B�ԍϕ��@�́A���������ϓ��ԍρB �Ȃ��A���p���ɂ͍�ʌ������{����⏕���̌���ʒm�����K�v�ƂȂ�B�ΏۂƂȂ铱���@��͉��L�̒ʂ�B �y����24�N�x�d�͎����Z����y���i���ƕ⏕���x�z�i�`2012�N12��14���܂Łj ���z�����d�V�X�e���ALED�Ɩ��A�������@�A�������①�ɁA�����z�^���z�M���p�V�X�e���A�n���M���p�V�X�e���A�G�R�E�B���A�G�l�t�@�[�� �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
��NTT�A���{���}���V���������f�}���h���X�|���X�T�[�r�X�Őߓd�x�� NTT�t�@�V���e�B�[�Y�ƃG�l�b�g�́A���p�T�[�r�X�Ƃ��ē��{���ƂȂ�d�͂̋����T�C�h�Ǝ��v�T�C�h����̂ƂȂ����}���V���������f�}���h���X�|���X�T�[�r�X�uEnneVision�i�G�l�r�W�����j�v��{�i�g�傳����Ɣ��\�����B EnneVision�́A����܂Łu�}���V���������d�͒T�[�r�X�v�𗘗p����ꕔ�̓����҂݂̂Ɏ��s���Ă������A���T�[�r�X��V���ɓ�������S�Ẵ}���V�����Ɋg�債�A�ߓd���x������B EnneVision�́A�}���V�����ɐݒu�����X�}�[�g���[�^�𗘗p���A�d�͎g�p�ʂ��������邱�ƂŏȃG�l�������x������u�����鉻�T�[�r�X�v�A���Ԃ̃s�[�N���ԑт̓d�͎g�p��}�������ӁE��ԂɃV�t�g���邱�Ƃœd�C�����������Ȃ�u���ԑѕʗ����T�[�r�X�v�A�d�͎����N�����ɁA���p�҂Ƀl�K���b�g����Ă��炢�A�l�K���b�g�ʂɉ������|�C���g���Ҍ�����u�ߓd�|�C���g�T�[�r�X�v����Ă���B ��N7�����玎�s�̌��ʁA���ԑѕʗ����T�[�r�X�ɂ��ẮA�ċG�ɂ�����s�[�N���ԑт̎g�p�d�͂��O�N���20���팸�B�ߓd�|�C���g�T�[�r�X�ɂ��ẮA�g�p�d�͂��O���̓����ԑт��ċG�͖�25���A�~�G�͖�39���팸���ꂽ�B ���N7������́A�V���j���[�Ƃ��āuCO2�|�C���g�T�[�r�X�v���J�n�B���T�[�r�X�́A�O�N�����Ɣ�r���ď���d�͗ʂ��팸����ƁA�팸����CO2�r�o�ʂ̊����l�����̃|�C���g�������̂ŁA���p�҂��l�������|�C���g�́A�����ȍ~�̓d�C�����̎x�����ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����ۃW���p���A���z�����d���ƎҌ����ɔ��d�����⏞����A���R�ЊQ���̃��X�N�y�� ���Q�ی��W���p���́A���z�����d���ƎҌ����ɁA�Еی��ɃZ�b�g����u���d�����⏞����v��10��1�����甭������B ���z�����d�V�X�e�����Ђ⎩�R�ЊQ�Ȃǂɂ�葹�Q����A���ƌv���̔��d�ʂɒB���Ȃ��ꍇ�̉c�Ɨ��v�̌�������⏞����ی����i�ŁA������1�N�ԂŁA�_��1,000���A�ی���������2���~�������ށB �{�ی����i�́A�_�Ɏ��ƌv���̓��N�x���d���������݂���ɂ��ĕی������Z�o����B���ƌv��l�����锄�d�������������ꍇ�̒lj��ی����͕s�v�ŁA���d���������ƌv��l����������ꍇ�́A�ی����̈ꕔ��Ԗ߂��邱�Ƃ�����B�⏞���e�Ƃ��ẮA�Ђ⎩�R�ЊQ�Ȃǂ̎��̔�����ɐ������c�Ɨ��v�̌������i�r�����v�j�Ǝ��v�����h�~��p�i�Վ��Ŕ��������l����j���A�_�ɒ�߂��ی����z�����x�ɕی������x�����B ���z�����d���Ƃł́A�C��̕ϓ�����˗ʂ̕ω��ɂ�蔭�d�ʂ��������邽�߁A���̂��������Ȃ������ꍇ�̗\�z���d�����̎Z�o������ƂȂ�P�[�X������B�����ŁA���Ђ�NEDO�����\���Ă���A���{�S��837�n�_�ɂ����鏊�ݒn�ʁA���ʂ̉ߋ��̔��d�ʂ���Ƃ��ė\�z���d�������Z�o���A���d���������ɔ������Ԃɑ������c�Ɨ��v�̌��������Z�o���邱�ƂƂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
�����z�����d����Z������̎{�H�ŁuPV�{�H�m�F�萧�x�v�������� ���z�����d�p�l���̐ݒu�Ɋւ��Ă͌����_�ŁA�e���[�J�[�����ꂼ��{�H�Ҍ����Ɍ��C�����{���āA�C���҂ɁuID�v�ƌĂԁg�{�H���i�h�s����P�[�X����ʓI���B�p�l���̐ݒu���@�ɂ͂����܂��ɁA�p�l�����[�J�[���J�������d�l�Ɖˑ䃁�[�J�[���J�������d�l�Ƃ�����A���ꂼ�ꃁ�[�J�[���Ƃɂ��ׂ��ȈႢ������B������́A���������d�l���K�Ɏ���Ă��Ȃ����Ƃ��A�N���[���ɂȂ���{�H�~�X�̌����Ƃ݂Ă���B ������͐V���ȁuPV�{�H�m�F�萧�x�v���e���[�J�[�̌��C�EID�F��̑O�i�K�Ɉʒu�t����B��萅���̉��f�I�ȋZ�\�E�m�����{�H�҂ɐg�ɕt���Ă��炤���Ƃ��_���ŁA�F��̎擾�͋`�������Ȃ����j���B��̓I�ɂ́A3���Ԓ��x�̊��Ԃō��w��{�H���K�Ȃǂ荞�J���L���������v�悵�Ă���B ���e�ʂł͑��z�����d�V�X�e���̃n�[�h���̂ɂƂǂ܂炸�A���ˏ����Ɣ��d�ʂ̊W��Z��\���i���ɉ����Ȃǁj�A�������֘A�@�K����S��Ƃ̒��ӓ_�ȂǂɎ���܂ŁA����ɂ킽���ăJ�o�[������j���B�u�W���d�l�Ŏ{�H�ł��Ȃ���������ɂǂ��Ώ����邩�ȂǁA�K�ɔ��f����ɂ͋@��̐ݒu��d�C�H���Ɋւ���m���ɉ����āA�Ⴆ�ΏZ��̉����ɂ��Ă��\���ȗ������K�v�BPV�{�H�m�̔F��擾�͋`���ł͂Ȃ����̂́A�{�H�Ҏ��g���~�X��N���[���̔����������ł��}�����邤���Ō��ʂ������߂�͂����v�B������̒S���҂͂����b���B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
���Œ艿�i���搧�x7�����̐ݔ��F�茏�����z��3��2000���ōő� �F�茏���́u���z���i10kW�����j�v��32,659���ōł������A���Łu���z���i10kW�ȏ�j�v1,027���A�u���́i20kW�ȏ�j�v6���A�u���́i200kW�����j�v3���ŁA���v33,695���ƂȂ��Ă���B����A�F��o�͂́u���z���i10kW�ȏ�j�v��300,705kW�ōł������A���Łu���z���i10kW�����j�v143,933kW�A�u���́i20kW�ȏ�j�v122,000kW�ŁA���v566,853kW�ƂȂ��Ă���B �F�茏����n��ʂŌ���ƁA�u�֓��v��11,876���ōł������A���Łu�ߋE�v5,426���A�u��B�v4,887���B�s���{���ʂł́A�u���m���v��2,032���ōł������A���Łu��ʌ��v1,841���A�u���{�v1,532���ƂȂ��Ă���B �F��o�͂�n��ʂŌ���ƁA�u��B�v��142,186kW�ōł������A���Łu�k�C���v142,047kW�A�u�֓��v132,492kW�B�s���{���ʂł́A�u�k�C���v��142,047kW�ƍł������A���Łu���������v81,368kW�A�u�V�����v24,540kW�ƂȂ��Ă���B �Ȃ��u�ݔ��F��v�́A�����x�𗘗p���������s���ɂ������āA�@�߂Œ�߂�v���ɓK�����Ă��邩���ɂ����Ċm�F������́B�e�d�����ʂ́u�����e�i���X�̐��v��u�K���Ȍv�ʂ��\�ȍ\���v�Ȃǂ̂ق��A�d�����Ƃ̊���݂����Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
���o�Y�ȃ}���V�����̐ߓd��⏕������j �ː��������W���Z��ɏƏ����߁A�ߓd�𑣂��B��̍�Ƃ��ẮA�}���V�����Ǘ��g�����֘A�̃V�X�e�������t������p���ő�Ŕ��z�⏕������j�B �����̃}���V�������ΏۂɂȂ錩�ʂ������A�Ǘ��g���œ����҂��瓯�ӂ�K�v������B �}���V�����̓d�͂̎g�p�͌o�Y�Ȃ��I�Ԑ��̊�ƌQ���_������B����ʂ��}�ɑ�����ƁA���p�X�y�[�X�̏Ɩ��𗎂Ƃ�����A�ꎞ�I�ɃG���x�[�^�̉^�]���~�߂�悤�}���V�����ɘA������B�ߓd�̓x�����ɉ����ĊǗ��g��������҂��d�͉�Ђ���������d�g�݂�z�肵�Ă���B����������Ƃɂ͈��̎萔��������B �x���Ώۂ�1��������100�ˑO��Ɣ�r�I�傫���}���V�����Ƃ��A���N�x�̗\�Z�v���z��300���~���x��\��B3�N�ōő�2�瓏�̎x���������ށB�V�z�}���V�����ː���3���オ100�ˈȏ�̋K�́B �o�T�u���{�o�ώY�ƐV���v |
|
|
���o�Y�ȁALED�d���ɏȃG�l� ��������̂́u�g�b�v�����i�[�v���x�B���łɉƓd�⎩���ԂȂǂł͍ł��ȃG�l���\���������i����Ƃ��Ē�߁A5�N���x��ɂ͎s�̂���Ă��鐻�i���� ������悤���߂Ă���B �o�Y�Ȃ͍��N�x���ɂ��X���Ŕ����Ă���LED�d���̐��\���v�����A��̓I�ȏȃG�l�������B���ȗ߂̉������o�āA������Η��N�x�̐��x�������߂����BLED���g�����V����t���^�Ɩ��i�V�[�����O���C�g�j�̊�Â������������B ���x�����������A�e���[�J�[�͎��Џ��i���ȃG�l����ǂꂾ�������Ă��邩�����x���Ŏ�����B����҂͉Ɠd�ʔ̓X��C���^�[�l�b�g��ŁA���i���Ƃ̐��\���ȒP�ɔ�ׂ���悤�ɂȂ�B����s���ʂ��ďȃG�l���i�����y���₷���Ȃ�B LED�d���͐V�������i�̂��߁A���ނ�d�q��H�Ȃǂ����P�ł���]�n���傫���ƌo�Y�Ȃ݂͂Ă���B���x������5�N��ɏ��i�S�̂�3�`4�����x�A���\���オ��Ƃ̎��Z������BLED�d���̏���d�͔͂��M�d����2���ōςށB���ɂ��܂���d�������ׂ�LED�Ȃǂ̏ȃG�l�^�Ɩ��ɐ�ւ��A140�����ѕ��̎��v�ɂ�����N50���L�����b�g���̐ߖ���ʂ�����Ƃ����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/9�@]�@�@�� |
|
|
| �������̗�p�p�d�̓[���̎��̋@�o��@���{�R�J�E�R�[�� �x�m�d�@���e�C���V�X�e���Y�Ƃ̋����J���ŁA��p�̂��߂̓d�͂��Œ�16���Ԏg�p���Ȃ��s�[�N�V�t�g�^�����̔��@���J�������B �����́A �@�@�^��̒f�M�ނ��������p���邱�ƂŒf�M���\�����߂āA�O�C���̉e�����ɂ����������ƁB �@�A��C�������ɂ������邽�߂ɁA���̋C���������߂���ǂ��������ƁB ���̋@���①�ɂƓ����ŁA�f�M���\���グ����A�C���������߂邱�Ƃ��|�C���g�̂悤�ŁA�d�͂ɗ]�T������[��сi23:00�`07:00�j�ɗ�p���Ă����A�����i7:00�`23:00�j�͗�p�@�\���~�ł���B �o�T�u�M�Y���[�h�E�W���p���v |
|
|
| ���G�R�Ōo�ϓI�ȕǒg�[�I�@�V�^�C�v���o�� �ǂɔz�ǂߍ��݁A�����̉��x�߂ł���V�����^�C�v�̕ǒg�[�����\���ꂽ�B�]���̓|���v���s�����ǂ��g���Ă������A�M�`�����̍��������g�p���邱�Ƃɂ��A���ɂ₳���������ȕǒg�[�����������B �ǒg�[�͏��g�[�Ɠ����V�X�e���ƂȂ��Ă���A�ǂ����M���邱�Ƃŕ�����g�߂邱�Ƃ��ł���B�M�`�����̍��������̔z�ǂ��g�����V�^�C�v�̕ǒg�[�́A�M�������A�����I�ɕǂ����M���邱�Ƃ��ł���B�܂��A���x��1�������邲�ƂɁA�G�l���M�[����ʂ��6���팸���邱�Ƃ��ł���B �������A���z�����d���͂��߂Ƃ��鑼�̍Đ��\�G�l���M�[�Ƃ����p�\���B�ǂɌ����J����Ƃ��ɔz�ǂ������Ȃ��悤�ɒ��ӂ���K�v�����邪�A�̂ɕ��S�������Ȃ��A���ɂ₳�����g�[���Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���B �o�T�ugoo�j���[�X�v |
|
|
| ����������^�c�ɉ��[�l�R���@���R�G�l���M�[�Q���̎v�f ���z�����d�╗�͔��d�Ȃǂ̎��R�G�l���M�[�̑S�ʔ�����萧�x���X�^�[�g����1�J���B���[�J�[�����ЍH��̉����Ƀ\�[���[�p�l����ݒu������A�����̂��V�x�n������肷��ȂǁA��Ƃ����d���ƂɎQ�����铮�������X�Əo�Ă���B �����������A�{���͔��d�{�݂Ȃǂ̌��݂𐿂��������ꂾ�����͂��̃[�l�R�����A���@��k�����ĉ^�c���鑤�ɉ�铮�����o�n�߂Ă���B ���̗��R�́A���v���̍����ɂ���B���z�����d�̏ꍇ�A1�L�����b�g������42�~�Ŕ�����邱�Ƃ����߂��Ă���B�Η͂̂��悻4�{�̍��l���B���������Ԃ�20�N�B�֘A�ƊE�̗v�]�f���������i�Ɗ��ԂɂȂ��Ă���A���R�G�l���M�[�y�����邽�߂̑�ՐU�镑���Ƃ�����B �o�T�u�_�C�������h�E�I�����C���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�u�݂Ȃ��ߓd�v���p�|�k���H�ꂩ��֓d�ɑ��d �p�i�\�j�b�N�͉Ă̓d�͕s����Ƃ��ēd�͉�Ђɗ]��d�͂�������������ߓd���Ƃ��ĔF�߂Ă��炤�u�݂Ȃ��ߓd�v���x�̗��p���n�߂��B �k���n��̍H��Ŕ��d�����d�͂����d�͂ɗZ�ʂ��邱�Ƃɂ��A�֓d�Ǔ��̎��Ə��Őߓd�����ƔF�߂Ă��炤�B���x�̊��p�ɂ���ē��Ђ͊֓d�Ǔ���1.7���ߓd�ł��錩�ʂ��B �d�͕s�����[���Ȋ֓d�Ǔ��ɖ{�Ђ�H�ꂪ�W�����邽�߁A���x�̗��p���n�߂��B�����̂Y����k���H��i�x�R���v�g�s�j���R�W�F�l���[�V�����i�M�d�����j�V�X�e���Ŕ��d���A�]�����d�͂�k���d�͂̓d�͖Ԃ�ʂ��Ċ֓d�ɑ���B �����\�͂�6000�L�����b�g�B���ۂ̋����ʂ��֓d�Ǔ��ł̓��Ђ̐ߓd�ʂɊ��Z�����B ���ɂ����{��^�s�ɂ���{�Вn��ł�8���̉ċx�݂ɉ����A7��21�`29����9�A�x�ɂ��Ďg�p�d�͂����炷�B�܂��S���̍H��œd�͂̎����Ǘ��̓O��A��Ԃւ̐��Y�V�t�g��Y�̑O�|���A�ȃG�l���M�[�f�f�A���Ɣ��d�̉ғ����ԉ����A��Ē莞�ގЂⒼ�s���A�̊g��Ɏ��g�݁A�e�d�͉�Ђ���̐ߓd�v���ɉ�����B2011�N�x�͈�A�̊����œd�C���O�N������10���i2��5000���~�j�팸�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���G�l���M�[��̔��I�u�\�[���[�L�I�X�N�v���G�`�I�s�A�ɃI�[�v���B���W�r�㍑�̃G�l���M�[�������� �G�`�I�s�A�E�����K�m�̋߂��ɁA���E���ƂȂ�u�\�[���[�L�I�X�N�v���I�[�v�������B ����́A���ۓI�Ȍ��z�f�U�C����ЁuGraft�v�ɂ���ĊJ�����ꂽ���̂ł���B���́u�\�[���[�L�I�X�N�v�̂˂炢�́A�d�͎���̈����n��ɏZ�ސl�X�ɁA���S�Ōo�ϓI�ȃG�l���M�[����邱�ƁB�]������d�͌��Ƃ��ė��p����Ă���f�B�[�[�����d�@�ⓔ���Ȃǂ́A�n�����ɂ����e�����B �u�\�[���[�L�I�X�N�v�̉����ɂ̓\�[���[�p�l�����ݒu����Ă���A�n���Z�������͂����ŏ[�d���ꂽ�\�[���[�G�l���M�[���w�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B�g�ѓd�b�E�R���s���[�^�[�E�Ԃ̃o�b�e���[�ȂǁA�p�r�͗l�X���B �������A���̃L�I�X�N�Ŕ����Ă���̂̓G�l���M�[�����ł͂��B�\�[���[�����^���Ȃǂ̃G�R���i����A�g�ѓd�b�₻�̃��`���[�W�J�[�h�Ȃǂ̐����G�݁A�L�I�X�N�ɂ͒�Ԃ̃h�����N��y�H�܂ŁA���낢��ȏ��i����葵���Ă���B�L�I�X�N�̒��ɂ͗①�ɂ������t�����Ă���̂ŁA�ً}���p�̖�i��N�`���Ȃǂ�ۊǂ��Ă������Ƃ��ł���B �o�T�u��goo �v |
|
|
| ��NTT�t�@�V���e�B�[�Y���ȃG�l�A�ȃX�y�[�X�̃f�[�^�Z���^�[�p�@��̔��J�n ���O�ւ̕��M�����́A�u���v�ƁA�������㓙�̐ݔ��X�y�[�X�W���\�ɂ���u��p�����M�i����j�v������B�����@�́A�œK�ȋC���������I���ł���悤�A��d�������p�́u�����^�v�A�����o�����p�́u�㐁�^�v������B �����́A�V�J���̍��È��E�������^�[�{�t�@���ւ̕ύX�A�������ɔ������[�^�[�̏��^���ɂ��A����̑����ʂ邱�Ƃ��ł��A��[�\��(���M)�̌���Ǝ������j�b�g�̏ȃX�y�[�X�������������B�܂��A���O���j�b�g���M�����퓙�̔z�u���H�v���A�����\�͂̌�������������B �����ɂ��A�������j�b�g����ю��O���j�b�g�Ƃ��ɐݒu�ʐς�����̏����\�͂����コ���邱�ƂŁA�X�y�[�X�����̌�������������B ����ɁA�ȃG�l���M�[���ɂ��ẮA�������ȃ^�[�{�t�@���̗̍p�ƃt�@�����[�^�[�̒������ɂ��A����COP�̔N�ԕ��ς�4.5��B�������B��ʓd�Z�p�@�ɑ��ĔN�ԏ���d�͗ʂ��40���ጸ����B ���̑��A�ߏ��p�̉����M���܂���������鑽�_���x���䓙�A�f�[�^�Z���^�[�̓����܂����ȃG�l���M�[�Z�p��A���O�C�����ł��̏��~���������\���@�\�t���������䓙�A�f�[�^�Z���^�[�̃T�[�r�X�p�����x����M�����E�p���Z�p������Ă���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������K�X�A�K�X�q�[�g�|���v�̏ȃG�l�^�]�����u�Ŏ����A�V�T�[�r�X���J�n �풓�̐ݔ��Ǘ��҂��s�݂̂��߁A���ߍׂ����@�̉^�]�Ǘ��E���䂪�ł��Ȃ��Ƃ����ڋq�ɑ��āAGHP�����̕t�����l�Ƃ��āA�{�T�[�r�X���Ă���B���p����GHP���O�@1�䓖����N�z21,000�~�i�ō��j�B�{�T�[�r�X�ɂ��A�N�ԃK�X����ʂ̖�20���̍팸��}��B 3�̃T�[�r�X�𒌂Ƃ��Ă���B �@�u���C���ȃG�l�^�]�@�\�v�ł́AGHP�̉^�]����̊�ƂȂ�ڕW���x��\�ߌڋq���w�肷��B���Ђ́A���ۂ̎������x��ڕW���x�Ɉێ����Ȃ���ȃG�l�������ł���悤�A�C�ۏ����⎺���̐l���Ȃǂɂ���ĕϓ�������ׂɉ������œK��GHP�̉^�]��������u�ōs���B �@�u�p�g���[���@�\�v�ł́A��60�����Ƃ�GHP�̉^�]��c�����A�ڕW���x�ƈقȂ鉷�x�ɁA�����@�̉��x�ݒ�̕ύX���s��ꂽ�ۂɂ́A���u�Ŏ����@�̉��x�ݒ�����ɖ߂��B����ɁA�ڋq���\�ߎw�肵�������ɉ��u�Ŋm���ɉ^�]��~���s���A�����Y��̖h�~�����邱�Ƃ��ł���B �@�u�����鉻�T�[�r�X�v�ł́A�ڋq�́AGHP�̉^�]�A�K�X�g�p�ʂ̎��сA�{�T�[�r�X���p�ɂ��K�X�g�p�ʂ̍팸���ʂȂǂ��A��p�̃C���^�[�l�b�g�z�[���y�[�W�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{2020�N�x�܂łɐV�z�����̏ȃG�l�`������ �Z���r���ȂǑS�Ă̐V�z�����ɑ��A2020�N�x�܂łɒf�M���̍����Ȃǂ̏ȃG�l������悤�`���t������j�����߂��B�G�l���M�[�g�p�ʂ̗}�����_���B �L���҂���Ȃ�u��Y�f�Љ�Ɍ������Z�܂��ƏZ�܂������i��c�v�̒��ԕɐ��荞�B����`�����Ɍ������@����������ɓ����B ���݂̏ȃG�l��́A�����ʐ�300�������[�g���ȏ�̌��z���ɂ��ē͏o���ƂȂ��Ă���A�`���t���͂���Ă��Ȃ��B���ԕɂ��ƁA��K�͂̌��z������i�K�I�ɋ`������i�߂�B��̓I�ɂ́A2015�N�x���납�牄���ʐ�2,000�������[�g���ȏ�A2017�N�x���납��2,000�������[�g�������`300�������[�g���ȏ�̐V�z�����ŋ`���t�����A2020�N�x�܂ł�300�������[�g���������ΏۂƂ�����j�B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| �������̓d�̓V�X�e�����v�̊�{���j�����܂Ƃ߁B�����d������2�ĕ��L�A�ƒ����������͑S�ʎ��R���@�o�Y�Ȑ��� ���{�͊�{���j�����Ăɂ܂Ƃ߂�u�v�V�I�G�l���M�[�E���헪�v�ɔ��f�B���ς͏H�ȍ~�A���x�v������ւ̍H���\���c�_���A�N�����߂ǂɌ��_�����������݁B �œ_�̔����d�����ł́A���d�Ԃ̉^�p��Ɨ��@�ւɈς˂�u�@�\�����v�ƁA��������ЎP���ɔ��d��ЂƑ��d��Ђ��Ă����u�@�I�����v��2�Ă�B �l���𗬂�\�Z�̋K���Ȃǂ��c�_���A�N���ɂǂ���̈Ă��̗p���邩�����߂�B���d���Ƃɂ����鋣�����m�ۂ��邽�߁A�V�K�Q���Ǝ҂̋����s�����������d�͂Ȃǂ��₤�u���������v�̃K�C�h���C���������B �H���I�t�B�X�r���ȂǑ�����v����i��ł����d�͏�����̎��R���́A�ƒ��R���r�j�ȂǏ������܂ߑS�ʓI�ɔF�߂���j�B����ɁA�����d�͂̒l�グ�R���ł��ᔻ���オ���Ă���d�C�����́u�������������v�͓P�p���A���R�ȗ����ݒ�ɂ�鋣�����㉟������B ����ŁA�����R�X�g�����������Ȃǂł́A���R���œd�C�������l�オ�肷�鋰�ꂪ���邽�߁A�����̕�������������B�d�͉�Ђ̔j�]��P�ނɔ����A���K�͈ȏ�̏����莖�Ǝ҂Ȃǂ��ŏI�I�ȋ����Ǝ҂ƒ�߂�ȂǗ��p�ҕی������荞�B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �����q�͈��S�E�ۈ��@�A�����݂��ɂ�鑾�z�d�r���d�ݔ��̎戵���Ɠd�C��C�Z�p�҂̉^�p�m�� �{�݃p�^�[���Ɠd�C���Ɩ@��̎�舵���ł́A�{�݃p�^�[���͑��l�ł���Ƒz�肳��邪�A��Ƃ��āA�ሳ�Ŏ�d������v�ݔ��i��ʉƉ��ȂǁB�܂��A��d�_�i�ӔC���E�_�j�͍\���ɂ���j�̉����ɔ��d���Ǝ҂�50kW�����̑��z�d�r���W���[�����A�����E�O�Ƀp���R�����@���ݒu���邱�Ƃ�z�肷��B���d���s���ۂ̑��d�o�H�ɂ���āA�p���R�����̋@��E���z�d�r���d�ݔ��̈����ɍ��ق������邽�߁A�{�݃p�^�[���y�ѐ}�A���ꂼ��̃p�^�[������������B �܂��A�����݂��ɂ��ẮA��ʉƉ����̎��v�ݔ��ɂ����Ď�d�ɌW��d�C���g�p���邽�߂̓d�C�H�앨�Ƒ��z�d�r���d�ݔ����d�C�I�ɐڑ�����Ă��炸�A���A�_���⎖�̓��̍ۂ̗������肪�S�ۂ����Ȃǂ̑[�u���u�����Ă���̂ł���A�����Ƃ��āA1�\��2�������݂�F�߂���̂Ƃ���B 7���ɍĐ��\�G�l���M�[�̑S�ʔ��搧�x���{�s���ꂽ���Ƃ��A�Z��̉����ɏZ��L�҂Ƃ͈قȂ�ݒu�҂����z�d�r���d�ݔ���ݒu����A�����鉮���݂��̐ݒu�`�Ԃ��������邱�Ƃ��\�������B�܂��A�{�N4���̓d�C���Ɩ@�{�s�K������ɂ��A�ăG�l�ݔ����ɂ��Ă�1�\��2�������݂��F�߂�ꂽ�B�����ŁA����܂ł͑z�肳��Ă��Ȃ����������̐ݒu�`�Ԃɂ��āA�ۈ���̈���������K�v�����邽�߁A�d�C���Ɩ@��38���̋K��ɏ]���A��ʗp�d�C�H�앨�ƕ��ނ���鑾�z�����d�̐ݒu���@�̐������s���ʒm�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2012/8�@]�@�@�� |
|
|
| ������d�@���ȃG�l���������鍂�͗��d���R���o�[�^��̔� �ȃG�l�ɍv�����鍂�͗��d���R���o�[�^���J���A�̔����J�n�����B �G�l���M�[��d���ɖ߂��@�\(�d����)�ɂ��ė��p�ł��邽�߁A�G���x�[�^��N���[���ȂNj@�B�ݔ��̐ߓd�Ɍq����B�͗��̉��P�ɂ��d���ݔ��e�ʂ̏��^�����������A�d�������g���X�ŃK�C�h���C�����N���A�B�����̃C���o�[�^���Ɛڑ��\�ň��肵���d�͂̎��ł���B�}�g���N�X�R���o�[�^�́A���H�̔��J�n�\��̓d�����j�b�g�Ƌ��ɐߓd���T�|�[�g����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ������{����A���R����Ɩ��������ʓI�ɔ��ˁE�g�U������ȃG�l�^�����p�l���J�� �����̓��ǂ�V��Ɏg�p���邱�ƂŊԐڌ�����Ԃ̋��X�Ɋg�U�����A�ꏊ�ɂ�閾�Â̍���ጸ����Ɠ����ɏƓx���グ��B���Ȃ����ł��L�͈͂ɏƎ˂��A�]���̓����p�����p�l���Ɣ�ׁA����d�͂�10�`13���팸�ł���B �ȃG�l�^�����p�l���́A�\�ʂɓƎ��̔��ׂȉ��ʂ��{�������F�̋����p�l���B���ʂ����������I�ɔ��˂��čL���͈͂ɊԐڌ����g�U�����A�Ɩ��̏���d�͍팸���\�ɂ���B�w����������LED�i�����_�C�I�[�h�j�Ɩ��ł��A�����f�荞�ނ��ƂȂ��p�l���\�ʂɌ��U�����Ĕ��˂����A�_�炩�ȊԐڌ��ɂȂ�B�����p�l�������A���ׂȉ��ʂɂ���Ď�G��ɂ͉����݂�����B �I�t�B�X�r���A�z�e���A�S���̉w��ԗ��A���Ǝ{�݂Ȃǂ̓��ǁA�V��A�Ɩ����j�b�g�ȂǂɓK���Ă���B�|�ɉ����A���~��X�e�����X���p�l����ނɂ������i���p�ӁB�y�ʉ����K�v�ɂȂ�S���ԗ��ł����p�ł��A���k�V�����́u�͂�Ԃ��v�ȂǂɎg����E5�n�ԗ��̓V��ɍ̗p���ꂽ�B���z��@�̕s�R�ޗ��F��ƁA�S���ԗ��p�ޗ��R�Ď����ł̕s�R��������擾���Ă���B ���R���������ꂽ��Ɩ����Ԉ����ߓd���{��������A�Ɠx�s���ň��S������K�������Ȃ��邱�Ƃ�����ALED�Ɩ��ł͎w�����̍�������A�ꏊ�ɂ�閾�Â̍��������₷����肪�������B �o�T�uECO JAPAN �v |
|
|
| ���x�m�ʁA�������z�̃��A���^�C�������ŋ���d�͂�N�Ԃ�20���팸 ���k�d�͂̃f�[�^�Z���^�[�ɂ����āA���t�@�C�o�[�����_���x�Z���V���O�Z�p��K�p���A�����̉��x���z�̃��A���^�C���Ő��k�ȉ������s���A���̌��ʂ�p���āA���������̑啝�ȉ��P�����������Ɣ��\�����B ����ɂ��A��N�Ԃ̓d�͏���̖�20%�ɂ�����ő�35��kWh�̓d�́ACO2���Z��120t�̍팸�������ށB ���x�Z���T�ƂȂ�1�{�̌��t�@�C�o�[���A�T�[�o���b�N�̑O�ʁE�w�ʁA�V��ʁA�����ɕ~�݂��A�f�[�^�Z���^�[���̉��x���z���k�i10cm�Ԋu�j�����A���^�C���i30�b���Ɓj�ɑ��肵���B����ɂ��A�M���܂�ɂ��z�C���x�̏㏸�A�ߗ�p�Ȃlj��x���z�̕ω������A���^�C���Ɋώ@���Ȃ���A�t�@�V���e�B�ʂ�A�@ ��̔z�u�Ȃǂ̕ύX��Ȃ��̍œK����̎��s������J��Ԃ����B����ɂ��A�@��5���~���Ă��A�K���ȋz�C���x�ɂ��T�[�o���K���ȉ��x��ێ������悤�ɂȂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���_�C�L���A�ۉ����̏���d�͂�啝�팸������^�Ɩ��p�q�[�g�|���v������� ������1�_�ڂ͍����̂���������ɉ��M��������ɗD��Ă���A��x�����グ���������ĉ��M���ďz�ۉ�����ۂ̏���d�͂�啝�ɒጸ���A�ƊE�g�b�v�̏z�ۉ�COP3.0��B���B ����ɁA�����グCOP���ƊE�g�b�v�N���X��4.1���������A�N�ԏ���d�͗ʂ��]����24���팸�����B�܂��A�������ׂ��������ċG�ɒ�i���M�\��35kW�́u�ʏ탂�[�h�v����u�ȃG�l���[�h�v�ɐݒ肷�邱�ƂŁA���M�\�͂��ő�30kW�ɗ}���A����d�͒ጸ���\�B�u�f�}���h����@�\�v�ɂ��A�A������������̃q�[�g�|���v������̒��ʼn^�]����䐔�𐧌��ł��A�ݒ肵�����ԑт̊m���Ȑߓd���\�B 2�_�ڂ́u�O�C�|20���ł�90���̍��������グ���\�ȋ����p���[�v������_�B ��O�C���ł̕����グ�ɗD�ꂽ�ȃG�l���̍���R410A��}�ƁA�������̕����グ�ɗD�ꂽR134a��}��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�t������}�ł͍�������O�C���|20����90���̍��������グ���\�ƂȂ�A����n�ł̎g�p�͈͂��g�債���B�܂��A�q�[�g�|���v�������12��܂ŘA�����邱�Ƃ��ł��A�ő�120�g��/���̋����ʂő�K�͎{�݂ɂ��Ή��ł���B 3�_�ڂ́u���S�@�\�Ō̏�X�N���y���v�ł���_���B ���O�̋�C����M����荞�ށu�M�����j�b�g�v�ƁA��荞�M�Ő������߂�u�J�X�P�[�h���j�b�g�v�̂��ꂼ��ɃC���o�[�^���k�@��2�䂸���ڂ��A1�䂪�̏Ⴕ���ꍇ�ł�����1��̐���Ȉ��k�@�Ŕ\��50���̃o�b�N�A�b�v�^�]���s���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������L���s�^���r�j�[���n�E�X�̒f�M�H�������[�X �{�݉��|�p�r�j�[���n�E�X�̏ȃG�l�Z�p�y������B�����̒g�[�ɂ�����R�����N�ԂŖ�5���팸����f�M���H�������[�X�_��Ŏ��{���A���Ǝ҂̎������S���y���B �R����̍팸�z�Ń��[�X����d�����x�v��̍�����x������B�o�c�̌������ŐV�K�Q���𑣂��A�_�Ƃ̒S����s�������ɂ��v������B�����L���s�^���̓O���[���V�X�e�����ۗL���鉷���̒f�M���Z�p���A���ЂƂ̋����o���Őݗ������O���[�����P�[�V�����ƘA�g���ĕ��y�����Ă����B ���n���t�����[�X�_��ɂ���āA�H������Ŏx������悤�ɂ��A���Ǝ҂̎������S���y������B�f�M���Z�p�̢�O�����d����̓t�b�\�t�B������2�w����ɂ��A2�w�̊Ԃɋ�C�w��݂��ĎՔM����f�M�������߂��B990m2�̉����Ȃ�R�����N�ԂŖ�45���팸����B�H�����375���`400���~�B�R���̎g�p�z���N150���~�ȏ�ł���A�{�H��̔R���팸�z�Ń��[�X�����܂��Ȃ���B�����������p����A�R���̎g�p�z���N100���~�O��ł��R���̍팸�z�Ń��[�X�����J�o�[�ł���B�����̑ϋv�N����15�`20�N�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ��LIXIL�A58�J���̃V���[���[�����u�N�[���V�F�A�X�|�b�g�v�� ���ȂƘA�g���Đi�߂Ă���u�N�[���V�F�A�v�Ɏ^�����A7��1������8��31���܂ł̕����A�S��58�J����LIXIL�V���[���[�����u�N�[���V�F�A�X�|�b�g�v�Ƃ��ĊJ������B �u�N�[���V�F�A�v�Ƃ́A�������p��w�f�U�C���w�Ȃ̖x�����O�����̃[�~�ŁA�u�����{��k�Ќ�̏ɑ��āA�f�U�C�i�[�͉����ł��邩�v�Ƃ����₢�����ɑ��ďo���A�C�f�A���B ��l���̃G�A�R�����g���Ƃ������ʂ���߁A�݂�Ȃŗ������ꏊ�ɏW�܂�A�y�������������V�F�A���邱�ƂŁA�ƒ땔��ł̃G�A�R���ɂ��ď�̃s�[�N����d�͂����炻���Ƃ����v���W�F�N�g�ł���B LIXIL�́A���́u�N�[���V�F�A�v�̍l���Ɏ^�����A�ҏ����ɃV���[���[���ɋC�y�ɗ�������Ă��炦��悤�Ɂu�N�[���V�F�A�X�|�b�g�v�Ƃ��ĊJ�����邱�Ƃɂ����B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| �����ŋ@�B���H��@�B1�䂲�ƂɁu�d�͂̌����鉻�v �J�������V�X�e���́A�@�B�̓d�͗ʂ��v��@���Ď����j�^�[�A�f�[�^����������\�t�g�ō\������B�d���A�d���A���x�A�ғ����ԂȂǂ��v���A�d�͗ʂ����Ƃɓd�C��������v�Z����B �@�B�̓d�������ɓd�͌v�����t���A���d�͖����ʐM�ŊĎ��V�X�e���ɓd�͎g�p�ʂ�ғ����ԂȂǂ̃f�[�^�𑗂�B����ꂽ�f�[�^�͐��b���ƂɊĎ����j�^�[��ɍX�V���ĕ\��������A�f�[�^�x�[�X�ɒ~���ĕ��͂ɗ��p�����肷��B���؎����̌��ʁA�H��S�̂œd�͎g�p�ʂ�2�����x�팸�ł���Ƃ������Z�ɂȂ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��2013�N�ȍ~�̏ȃG�l�{��Z��x�����O�擾�̋`���������� ����̒n�����g����̑I�����Ƃ��āA���{�̃G�l���M�[�E����c�ɒ�o����2013�N�ȍ~�̎{��Ɋւ���Ƃ�܂Ƃ߂��s���A���e�͑�ŗ������ꂽ�B 2030�N�̌��q�͔��d�����Ɖ��g����̐��i�x�����i�{��̑�_�Ȑ��i�A�{�����i�j�ɉ����āA�ŏI�I��6�̑I�������Ă�����B������̈Ăł��A2020�N�̉������ʃK�X�̔r�o�ʍ팸���͊�N�i����1990�N�j��Ń}�C�i�X5���`�}�C�i�X15���ɂƂǂ܂�B�T���ɂ��G�l���M�[�E����c�ɕ���B �Z��E���z������ł́A2050�N�̏������Ƃ��āA�G�l���M�[�����҂ƈ�̓I�Ȏ��g�݂ɂ��A�X�g�b�N���ς�CO2�̃[���G�~�b�V������ڎw���B�����Ɍ����A �i�P�j�f�M�E�C�����\�̑啝�Ȍ��� �i�Q�j�ȃG�l���M�[�@��̕��y���i �i�R�j�Đ��\�G�l���M�[�̐ϋɓI���p �̑��i�߂�B ��̓I�ȋ����{��̗�Ƃ��ċ��������̂́A�ȃG�l��̒i�K�I�����グ��x�����O�擾�̋`�����A�n�G�l�@��ݒu�̌����`�����ȂǁB �܂��A�x��Ă�������Z��̏ȃG�l����i�߂邽�߂̕���Ƃ��āA�G�l���M�[�����҂ɑ�����v���̏ȃG�l�x���`���t����A���Z�Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��������ݏZ��̒f�M���K���̋�����U�������荞�܂�Ă���B �o�T�u�V���n�E�W���O�v |
|
|
| ���~�d�r�A�u�Z��͕��y���i�A�����{�݂͌��������v�o�Y�Ȃ����j �o�ώY�ƏȂ́u�~�d�r�헪�v���W�F�N�g�`�[���v���܂Ƃ߂����ɂ��ƁA�Z���r���ɂ��Ă͌��ݒi�K����~�d�r�̐����𑣂��Ƌ��ɁA�a�@�E�w�Z�E���ɂȂǂ̒n��̋��_�ƂȂ�����{�݂����݂���ۂɂ́A�����Ƃ��Ē~�d�r�̐ݒu�����߂Ă������j���B �Z���r���ւ̋�̓I�ȕ��y��ɂ��Ă͍��㌟�����Ă������A�`������K���Ƃ����������ł͂Ȃ��A�⏕���̊��p��u�~�d�r�����^�����Ɓv�Ƃ������V���Ȏ��Ƃ̈琬�ɂ��s��̂�������L������e�Ƃ�����j���B�����{�݂ւ̓����ɂ��ẮA���y��ʏȂƂ̋��͊W�̒��Ő��i���Ă����B �o�T�u�Z��V��v |
|
|
| ��SII�ABEMS�A�O���Q�[�^����̐\���\�G�i���X���ő�458�� �����n�C�j�V�A�`�u�iSII�j�́A�����r�����ɑ���BEMS�̓�����⏕���鎖�Ƃɂ����āABEMS�̓����ƃG�l���M�[�Ǘ����x������BEMS�A�O���Q�[�^��ʂ����ABEMS�����\���i6��22�����_�j�����\�����B BEMS�A�O���Q�[�^23���Ǝ҂̂����A�����\���i���Ə����j�g�b�v�́A�G�i���X��458���B�����ş��z�d�@��135���A���ł�116���ƂȂ��Ă���B�{���Ƃ͖{�N4���ɃX�^�[�g�B�܂��A1�`10���Ƃ���BEMS�A�O���Q�[�^�������A0���Ƃ���BEMS�A�O���Q�[�^��5���Ǝ҂������B �{���Ƃ́A����23�N�x�u�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���������i���ƕ⏕���iBEMS�j�v�Ƃ��Ď��{����Ă�����̂ŁA�����r�����̍��������̓d�͎��v�Ƃ�ΏۂɁA�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���uBEMS�v�̓����ɕ⏕������t������́B���Ɗ��Ԃ͕���24�N4�����畽��26�N3��31���܂ŁB�{���Ƃł́ASII�ɓo�^�����uBEMS�A�O���Q�[�^�v���A�����r�����ɑ���BEMS������ƂƂ��ɁA�G�l���M�[�Ǘ��x���T�[�r�X���s�����Ƃ��v���ƂȂ��Ă���BBEMS�A�O���Q�[�^�ɂ���āABEMS�A�G�l���M�[�Ǘ��x���T�[�r�X�̔�p�A�@�\�E���e�A�T�[�r�X�̊J�n�����A�����ڕW�������قȂ�B �G�i���X�́A�����ڕW�l�Ƃ��čő���16,107�����f���A���[�U�[�ڐ��̉��i��ł��o����BEMS�����B���z�d�@�̓����ڕW�l��1,163���BESCO���ƁE�ȃG�l���j���[�A�����Ƃ�S���œW�J���Ă����m�E�n�E���������ABEMS��������^�p���P�E�ȃG�l���j���[�A���܂Ń����X�g�b�v�Œ���B�{���ƑS�̂ł́ABEMS�����v��̖ڕW�l�Ƃ��āA���Ə���65,216���A�_��d�͍��v9,241,742kW���f����B6��22�����_�ł̐\��������850���ƂȂ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�f�}���h���X�|���X�W���� �o�ώY�ƏȂ͓d�͉�Ђ���̐ߓd�v���ɉ�����ƕ��Ȃǂ���f�}���h���X�|���X�Z�p��W��������B �����d�͂Ɗ��d�͂����Ă���f�}���h���X�|���X�T�[�r�X���v�撆�����A�ߓd�v���Ȃǂ̃f�[�^��������炾�ƃf�}���h���X�|���X�T�[�r�X���Ǝ҂◘�p�҂ɕs���v�������鋰�ꂪ���邽�߁B �X�}�[�g�R�~���j�e�B�A���C�A���X�ɐݒu�����u�X�}�[�g�n�E�X�E�r���W���E���Ƒ��i������v�ŕW�����Ȃǂ̍H���\��9���ɍ��肷��B2012�N�x���̊�����ڎw���B�܂����Ȃ̓X�}�[�g���[�^�[�⑾�z�����d�Ȃǂ̃X�}�[�g�n�E�X�d�_8�@�����肵�A�@��̑��ݐڑ����ɕK�v�ɂȂ�`�����f�B�A�i����LAN��Bluetooth�Ȃǁj�ꂷ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/7�@]�@�@�� |
|
|
| �����d�u���ԑѕʗ����v�����֎g�p�ʏ��Ȃ���ԗ����͈��� 7������10�����x��\�肵�Ă���ƒ�����d�C�����̒l�グ�ɍ��킹�A�d�͎��v�����Ȃ���Ԃ̓d�C����������������u���ԑѕʗ����v��������j�����߂��B �V���x�ł́A�d�͎g�p�ʂ�������ċG�̌ߌ�P������S���̎��ԑт��s�[�N�����Ƃ��č��߂ɐݒ肵�A�g�p�ʂ̏��Ȃ���Ԃ̗����͈�������B��ԓd�͂�~�d�r�Ȃǂɂ��߂ē����ɗ��p������@���㉟�����邱�ƂŁA�d�͎��v�̃s�[�N��}����B ��Ԃ̓d�C�����������3����1���x�Ɋ���������j���[�͊��ɂ��邪�A�ݔ���ݒu�����ƒ�ȂǂɌ����Ă����B�V���x�ł́A�S�Ẳƒ�Ŗ�Ԋ������g����d�g�݂�z�肵�Ă���B�܂��A�d�͂̎g�p�ʂ����Ȃ��ƒ�ɂ��Ă͓d�C�����̒l�グ�����P�O�������ɗ}��������B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���a�@�ɑ��z�����d�V�X�e���ƒ~�d�r���Őݒu����T�[�r�X���o�� �d�C�ʐM�H���A���z�����d�V�X�e���̐ݒu�Ȃǂ��肪����R�����́A�S���̕a�@��ΏۂɁA���z�����d�ɂ����p���Ɣ��d�ƃo�b�N�A�b�v�d�����u��g�ݍ��킹���X�}�[�g�E�o�b�N�A�b�v�E�V�X�e���iSBS�j���Őݒu���鎖�Ƃ��J�n�����B �ЊQ�̔����Ȃǂɔ�����d���Ƀo�b�N�A�b�v�d���Ƃ��ė��p�ł��A�d�͂̈���I�Ȋm�ۂ���������B�a����200�ȏ�̋K�͂̕a�@��Ώ�SBS��100kW�̑��z�����d���W���[���█��14kW�̒~�d�r�A�p���[�R���f�B�V���i�[�ō\������A�a�@�̉���Ȃǂɐݒu�B���Ǝ��͑��z���Ŕ��d�����ő�100kW�̓d�͂𗘗p���A��ԓ�����Ǝ��͒~�d�����d�C�𗘗p����B���Ў��̃o�b�N�A�b�v�d����R����̐S�z�Ȃ��m�ۂł��邽�߁A�a�@���ɂƂ��ẮA�ЊQ���A��d���ɂ��p����Â��ł���a�@�Ƃ��ăA�s�[���ł��郁���b�g������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{���d�͎�����ɕ��U�^�E�O���[�����d�s���n�݁A���K�͓d�����Q���\�� �{�s��̊J�݂́A���{�́u���Ă̓d�͎�����ɂ��āv�Ɍf����ꂽ�����T�C�h�̎��g�݂Ƃ��āA�����͂����ʓI�ɕ�W���A���d�͎���s��ւ̏������܂ޕ��U�^�d���̎Q�����\�Ƃ���̂��ړI�B ���Ă̓d�͎�������A���{���d�͎�����ɁA���U�^�E�O���[�����d�s���n�݂��A�s����J�݂���B ����ɂ��A���Ɣ��d�p���d�ݔ���R�W�F�l���d����1,000kW�����̏����̗]�蔭�d����A���d�ʂ����łȂ��A������u�o�Ȃ�d�C�v�����d���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B ����́A���d���̑��d�i�t���j�ł���]��d�͂ł���A�N�ł��̔��\�B��������i��160���~�j�͕s�v�ŁA���ʂ͎萔�����s�v�ƂȂ�B������́A��v�ȓd�C���Ǝ҂̑������������铯������̉���ŁA��������͎���̃}�b�`���O�̈�����A�����Ƀm�E�n�E�̃A�h�o�C�X�������{����B�����͖{�s���ʂ��Ĕ���̌f�����s���A�����肪���D���s���B�����͎��ЂŔ������T����Ԃ��Ȃ��Ȃ�A�����I�ɂ����������̔������I�����邱�Ƃ��ł���B �����́A�̔����i�A�̔��ʁA��������i���ԁA�j���w��A��������A���Ԏw�蓙�j����C�ӂŐݒ肷�邱�Ƃ��\�B�܂��A���̓��ɂ�锭�d�s�����i�C���o�����X�j�ɂ�镉�S�̗L����ݒ肷�邱�Ƃ��ł���B�A���A���̏ꍇ�́A�����肪���X�N�����ƂɂȂ�̂ŁA���̑��̏������ɍH�v�����߂���B���K�͓d�͂ł������A�ȃG�l�̓w�͂Ɍ��т��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ߓd�ʁv�A���D�Ŕ�����聁�r���̗}������֓d ��ƂȂǑ���_��҂�Ώۂɐߓd�ʂ���D�Ŕ������u�l�K���b�g����v��d�͉�ЂƂ��ď��߂Ď��{����Ɣ��\�����B �����̌��������ɁA�ߓd�̎��ԑтƐߓd�ʂ���āA�֓d����̎��z���ň��l�̌_��҂��痎�D���Ă����B �܂��A�r����H��Ȃǂ̋�Ɩ��𐧌䂷��Ǘ��V�X�e����������Ƃ�Ώۂɐߓd�𑣂��D�������������B��������Ǔ��Őߓd��v������7��2���`9��7���Ɏ��{����B �l�K���b�g����̑Ώۂ͖�7000���B�d�͋����̗\������3�������ɂȂ�ƌ����܂���������A�֓d�͑O�T�̋��j������N�����̑O���܂ŁA�ߓd���Ăق������ԑтƗʂ����B��Ƒ��͐ߓd�\�ʂƊ�]���i�L���ĉ��D���A�֓d�͉��i�̈������ɗ��D�҂����߂�d�g�݁B ���D���ߓd�ڕW�ɒB���Ȃ��ꍇ�́A�s�����̓��D��O���܂ŌJ��Ԃ��B���D������Ƃ̎��ۂ̐ߓd�ʂ����D��������9�������ɂƂǂ܂����ꍇ�́u�����v���Ȃ��B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���n���M�G�A�R���R���i�������V�� �n���̔M���g�[�ɗ��p���]���̈�ʓI�ȃG�A�R���ɔ�דd�C����ł���u�W�I�V�X�G�A�R���v������B �n���M�𗘗p�����ƒ�p�G�A�R���͍����ŏ��߂ĂƂ����B�Z��[�J�[�ȂǂƋ��͂��ďȃG�l�ւ̊S����������Ҍ����Ɏ��v���J�A���N�x200��̔̔���ڎw���B �V���i�́A�n��ɔ��15�x���x�ʼn��x�����肵�Ă���n���M���q�[�g�|���v�ł��ݏグ�ė�g�[�ɗ��p������́B14�������̕����ɑΉ�����@��ŁA���i��57��7500�~�B����Ƃ͕ʂɁA�n��80�`100���[�g���Ɋǂ�ʂ��Ȃnj@���ƂȂǂ��܂߂��H����Ƃ���150���~�O�ォ����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���p�M���d�A���y�ɔ��ԁ|�u�ቷ���^�o�C�i���[�v�ɎQ�������� �H���ċp��̔p�M���d���}�C�N���O���b�h�i���K�͓d�͖ԁj�̎����ɐ��������Ɗ����������n�߂��B�H��p�M�𗘗p����u�o�C�i���[���d�v�Ɋւ��A���{��100���O��̒ቷ�M���ŏo��300kW�����̏��^�ݔ�������v�����S���Ɋɘa�����̂��A���d�H�ƂƐ_�ː��|�����ቷ���^�o�C�i���[���d�s��ɖ{�i�Q������B ���K���b�g���̒n�M���d�v�����g���ł���O�H�d�H�Ƃ��Q���̌������n�߂��B�p�M���d�̕��y�ɂ��A�n��̓d�������l�����A�X�}�[�g�R�~���j�e�B�[�i��������n��j�̎��p���ɂ��e�݂��t���B �ቷ���^�o�C�i���[�s��́A���{�̋K���ɘa���āA2012�N�x�㔼����13�N�x�ɂ������オ�錩���݁B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������s�A�Z��p�~�d�V�X�e���̕⏕���J�n �����s�ł́A2011�N5��27������́u�����s�d�͑�ً}�v���O�����v�܂��A�ƒ�̓d�͕s���ւ̑Ή��y�іh�Ћ@�\�̋�����}�邽�߂ɁA�ƒ�ɂ�����n�G�l���M�[�@��̓����⏕�����{���Ă���B �{�⏕���Ƃł́A����܂ŁA���z�����d�V�X�e���A���z�M���p�V�X�e���A�K�X�R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e���̐ݒu���Ώۂ��������A����A�~�d�V�X�e���̐ݒu���ΏۂƂ��Ď�t���J�n����B ��ȕ⏕�Ώۗv���́A�������{�����u�p���`�E���C�I���~�d�r�������i�Ƃɂ�����⏕�Ώۋ@��Ƃ��ĔF�߂��Ă���A���s���ɐV�K�ɐݒu���ꂽ�Z��p�~�d�V�X�e���i�ˌ��E�W���A�l�E�@�l�����܂ށj�B �⏕���̒P���͒�i�o��1kW������10���~�B�⏕�z�̏����50���~�B��t���Ԃ�5��8����蕽��2013�N3��31���܂ł̗\��B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Đ��G�l�����ݔ����������ցD�D�D�Œ艿�i������萧�x �o�ώY�ƏȂ́A�Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i������萧�x�ɂ��āA�V�K�̔��d�ݔ��ɉ����A�����ݔ��̔��d�������������j��\�������B �����x�́A�d�͉�ЂɍĐ��G�l���Ǝ҂̔��d�����擾�����A�R�X�g�͓d�C�����ɏ�悹����B�V�K�ݔ�������Ώۂɂ�����A�����ȍĐ��G�l�̔�����肪�����邽�߁A�����̏�悹�z���c��ނ��ƂɂȂ�B �����x�͓d�͉�Ђɑ��A�Œ艿�i�ŁA15�`20�N������邱�Ƃ��`���t����B�����͐V�K�ݔ�������Ώۂɂ���������������A��s���ēw�͂����l���s���ɂȂ�͖̂]�܂����Ȃ��Ƃ̎w�E������Əq�ׁA���j�]������B �����A�����ݔ��͐ݒu���ɕ⏕�����Ă���P�[�X�������B�V�K�Ƃ̌�������}�邽�߁A�擾���i������������A���Ԃ�Z������Ȃǂ̑[�u�������j���B�o�Y�Ȃ́A�����x�ɔ���������悹�ɂ��āA12�N�x�ɕW���ƒ�Ō�70�`100�~�Ǝ��Z�B�����������Ώۂɂ���A�����100�~�ɋ߂Â��������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �������G�l���M�[���͕���24�N�x�ċG�̏ȃG�l���M�[������\ �Z��E�r�����̏ȃG�l���M�[�Ή��Ƃ��āA�V�z�A�����z�A���C���ɓ������ẮA�O�ǁE������ʂ��Ă̔M�̑����̖h�~��}�邽�߁A�ȃG�l�@�Ɋ�Â��Z��y�ь��z���̏ȃG�l���M�[��܂��A�f�M�ނ̗��p�A�v�E�{�H��̍H�v�ɂ��M���ׂ̒ጸ�ȂǓI�m�Ȑv�y�ю{�H���s�����ƁB�ϋɓI�ȃG�R�Z��̐V�z��f�M���C�Ȃǂ̃G�R���t�H�[���ɓw�߂邱�ƁB�G�l���M�[�g�p�@����œK�ɐ��䂷�邽�߁A�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iBEMS�EHEMS�j�̓����ɓw�߂邱�ƁB �r�����ɂ����ẮA�ȃG�l�f�f��ESCO�f�f�������p���A��荂�����Ȑݔ��E�@��̓�����K�ȉ^�]���@�̌��������ɂ��A�ȃG�l���M�[����i�߂�悤�v�����Ă���B �܂��A�Ɠd�@��AOA�@�퓙�̍w���ɓ������ẮA���ۃG�l���M�[�X�^�[���S�̕\����A���{�A���Ǝғ�������G�l���M�[��������Ɋւ�������Q�l�Ƃ��A���ȃG�l���M�[���\�̍����@���I�����邱�ƁB ���ɁA�G�A�R���A�①�ɁA�e���r�A�Ɩ��̍w���ɓ������Ă͓���ȃG�l���x���ɂ��ȃG�l���\�\���ɗ��ӂ��A�ȃG�l���M�[���\�̍������i��I�����邱�ƁB����҂ɂ���L��g�𑣂����߁A�G�l���M�[����@��̐����E�A�����ƎҁE�������Ǝ҂́A�@��̃G�l���M�[�������������҂ɂ킩��₷�������ƂƂ��ɁA�@�킪�G�l���M�[����̍팸�ɂǂ̂悤�ɖ𗧂̂��A�ǂ̂悤�Ȏg�������ł��G�l���M�[�g�p�ʂ����Ȃ����ɂ��Ă��ߍׂ��ȏ��ɓw�߂邱�ƁB �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| ���X�܂̃G�A�R�����ʌ����ɍő�20���~�̉ߗ��^�\�E�� �\�E�����\����ɉ؊X�̍]��▾���G���A�ł́A�h�A���J�����܂܃G�A�R�������ĉc�Ƃ��Ă���X�������A�s�͎����܂���s�����ƂŁA�����������s���Ȃ��Ȃ���̂Ɗ��҂��Ă���B �s�͎����I�ɁA���撡�i������j�A�؍��d�͌��ЁA�G�l���M�[�s���A�тƋ��͂��A24���ߌ�2�����疾���G���A�̓X�܂����A�����K�����x�i26�x�j�̏�����w������v�悾�B�܂��A�d�͎��v�̑����ߌ�2������5���܂ł́A�G�A�R���̎g�p���T����悤�Ăъ|����B��������́A�w���͈̔͂��s���S��Ɋg�傷��B �s�͎����܂�ɏ��o���w�i�ɂ��āu��������N��葁���K��A�d�͎��v���}�����Ă���A�ꕔ�����̉ғ���~���d�Ȃ��ēd�͕s�������O����Ă��邽�߁v�Ɛ��������B�����܂ł͎��m���ԂƂ��邪�A7������͎�����Ƌ��͂��A���������X�܂�300���E�H���i��20���~�j�ȉ��̉ߗ����Ȃ����j���B �o�T�u���N������{��Łv |
|
|
| ���m�g�j�ƍݍ㖯��5�ǁu�d�͕N���v���Ƀj���[�X���� ���āA���d�͊Ǔ��ŁA�d�͂��u�����N���v���A���Ԃɓd�͋������~�߂�u�v���d�v�̎��{��������ꂽ�ꍇ�ɁA�j���[�X����Ȃǂ�ʂ��čL����������j�ł��邱�Ƃ����������B �����N����v���d�̎��{�����łȂ��A����Ȃ�ߓd�̌Ăъ|������������ǂ�����B�����ǂً̋}���́A�L�͂������ɗ����邱�Ƃ���A��Ƃ�s�����f�����ߓd�Ɏ��g�݁A���d�Ȃǂ̍������M���M���ʼn��������ʂȂǂ����҂����B �����]�́i�\�����j���R�������ƂȂ�u�����N���v�Ɏ������ꍇ�ɁA�ǂƂ��Ďs�����Ƃւ̎��m���@���u���������v�u�������v�Ƃ����͖̂��������������T�ǁB �T�ǂ́u�ʏ�̃j���[�X�g�v�u�j���[�X����v�őΉ�����B�����������u���ʂȏ����͂Ȃ����A�ʏ�̃j���[�X��j���[�X����Ȃǂœ`����v�Ƃ��Ă���A�����I�ɂ͑S�ǂ��������Ă���`���B ����A�u����֓d����̏�S���Ȃ��B���O�ɏ����ꂽ�ꍇ�͑Ή��v�i�e���r���j�ƍ���֓d�ɑ����Ɍv���d�Ɋւ�������J�����߂鐺�������������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���\�j�[�A�����ő�K�͂́u�O���[���M�؏��v�w���N�Ԗ�8,000�g��������CO2���팸 ���{���R�G�l���M�[������Ђƃo�C�I�}�X�n�����Ɩ��ϑ��_���3�N�_��Œ������A�؎��o�C�I�}�X�M�d�����ݔ�����������M�ɔ��������l�u�O���[���M�؏��v�̍w�����J�n����B �w�����ʂ́A�N��133,333GJ�i�M�K�W���[���j��\�肵�ACO2���Z�ŔN�Ԗ�8,000�g���ɑ�������B��1,650���ѕ��̔N��CO2�r�o�ʂɂ�����B�؎��o�C�I�}�X�M�d�����ݔ��́A�ݔ����ӂ̖؍ލH�ꓙ�Ŕ����������E���ދ��̖؎��o�C�I�}�X�𗘗p���Ĕ��d����єM�������s���ݔ��ŁA���ݔ�����̓d�͂ɔ��������l�u�O���[���d�͏؏��v�̍w����2007�N���p�����čs���Ă���B ���̓x�A���d�Ɠ����ɐ��ݏo�����M�i���C�j�ɂ��Ă��A���c�@�l�O���[���G�l���M�[�F�Z���^�[���u�O���[���M�؏��v�Ƃ��ĔF����A���{���R�G�l���M�[������Ђ��w�����J�n���܂��B�w�������u�O���[���M�؏��v�́A�\�j�[�O���[�v�ɂ�����G�l���M�[�g�p�ɔ��������ׂ̒ጸ�Ɋ��p���Ă����B�u�O���[���d�͏؏��V�X�e���v��2001�N��藘�p���Ă��āA�����\�j�[�O���[�v�e�Ђ�2011�N�̔��d�Ɩ��ϑ��ʂ́A���v6080��kWh�i2012�N3�������_�j�ɂȂ�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��TMY�A��ʓI�Ȑ�@���̊����x��3�x�Ⴍ�ł���~�X�g�t�@�� �^���[�^�̐�@�ɁA������o����@�\���g�ݍ��܂ꂽ���i�B���݂̂𑗂��@�ɔ�ׂāA�̊����x������ɖ�3�x�����邱�Ƃ��\�B �╗��ł́A�@��̓����Ő����C�������邱�Ƃŋ�C�̉��x�������邪�A�~�X�g�t�@���͖���̐���畆�ɓ͂��A�畆��Ő����C�����邱�Ƃő̊����x��������d�g�݁B �G�A�R���ƕ��p���邱�ƂŁA���ȃG�l�����K�Ȏ���������邱�Ƃ��\���Ƃ����B�~�X�g�̓f�o�ʂ�110ml/h�B�e��2.5L�̃^���N����������Ă���A�A���Ŗ�22���ԃ~�X�g����o���邱�Ƃ��ł���B�O�ʂɂ���O�K�[�h(�H����ی삵�Ă��镔��)�̕����̌`��ƁA�O�K�[�h�����̂������ʼn�����悤�ɂȂ��Ă���B���̋@�\�ɂ��A��U��@�\���������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���ʂɑ��č��E45�x����(�v90�x)�͈̔͂ɕ����͂��B��]�������i��12,800�~�B �o�T�u�}�C�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���A�Y�r���҂艷�x�����g�ݍ��u�t�@���R�C�����j�b�g�p�R���g���[���v�� �w�҂艷�x����^�C�v�x�́AFCU�̏o���i�҂�j�����x���A�z�Ǖ\�ʉ��x�Z���T�𗘗p���Čv�����A�Ґ����x�����l�ƂȂ�悤�ɐ���o���u���R���g���[�����邱�Ƃʼnߗ��ʂ�}��������́B �u�҂艷�x���䃍�W�b�N�v�Ƌ��Ɂu�������x���䃍�W�b�N�v�����ڂ��Ă���A�������x�𐧌䂵�Ȃ��痬�ʐ�����s�����Ƃ��ł���B�t�@���R�C�����j�b�g�̏ꍇ�A�≷���̉��x�����v�ʂ�ɉ^�]����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��̂�����ł���A���́u�҂艷�x���䃍�W�b�N�v��g���ނ��ƂŁAFCU�ɗ����≷���ʂ̉ߗ��ʂ�}�����AFCU��䂠����̑����ʂ��ő�45���팸�ł���Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���_�C�L���H�ƁA�s�[�N�J�b�g�ȂNJe��ȃG�l�@�\���ڂ̋Ɩ��p�u�G�R�L���[�g�v���� �s�[�N�J�b�g�^�]�́A�ݒ肵�����ԑтɉ��M�\�͂𗎂Ƃ����ƂŒʏ�^�]�Ɣ�r���ď���d�͂�23���ጸ����B�̔�����͉̂��M�\�͂�7.5kW��15kW��2�@��ŁA7.5kW�̋@��ł�6.0kW�ɉ��M�\�͂�}���ăs�[�N�J�b�g����B ��Ԃ̕����グ�́u��~�^�]����v�ƌĂсA�K�v�ȓ������ׂĖ�ɕ����グ�A�����̋������ׂ��ɃV�t�g�B�ߌ�10������n�߂�^�]�ƁA�ߑO8���ɕ����オ��^�]����I���ł���B�g�p����Ǝ�ɍ��킹���v���O�����́A���H�X�A�����e�A�����{�݁A��ʂ�4��ނ�p�ӂ����B�Ǝ킲�ƂɍœK�ȕ����グ���x�Ǝ��Ԃ��v���O�����Őݒ肵�Ă���A�����R���ŗe�ՂɑI�Ԃ��Ƃ��ł���B 1�T�Ԃ̎g�p���т��m�F���邱�ƂŁA���ꂼ��̗��p�p�^�[���ɍ��킹�ē��̗ʂ߂��A�������߂��ⓒ������Ԃ�h�����Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B1�̃V�X�e���Ń^���N��4��܂ŘA���ł��A40�l�K�̘͂V�l��앟���{�݂Ȃǂ̒��K�͎{�݂ɂ��Ή��B�������͂��]���̖�1.8�{�ɍ��߁A�����ꏊ�������A�����z�ǂł����K�Ɏg�p�ł���悤�ɂ����B���M�\��7.5kW�̋@���95���~�i�ŕʁj�A��15kW�̋@���150���~�i���j�B�������j�b�g�e�ʂ͂ǂ����460L�B �o�T�uECO JAPAN �v |
|
|
| ���A�N�Z�X�����z�����d���C�t���y���ށg�\�[���[���d��厏�h�n�� �\�[���[���d��厏�wSOLAR JOURNAL�x�ł́A���ӎ��̍����t�@�~���[�w�Ɍ����ă\�[���[�p�l����X�}�[�g���C�t�Ȃǂ̍ŐV�����킩��₷���A�X�^�C���b�V���ɔ��M���Ă����B �n�����ł́A�^�����g�ʼn̎�̂�̍��m���\�[���[�ɂ��Ċw�ԁu��̍��m�A�\�[���[�ɒ��݂܂��I�v��A���卑�ł���h�C�c�ƃf���}�[�N�̃\�[���[������Љ�B�܂��A���{�̃G�l���M�[�������}�b�v�A�Ă���͂��܂�S�ʔ��搧�x�Ȃǂɂ��Ă����W����B�����́A�G���i1�E4�E7�E10��15���j���s�\��Œ艿300�~ �o�T�u�I���R���v |
|
|
| ���C���e���W�F���X�V�G�l���M�[�����h�� 7������̍Đ��\�G�l���M�[�̑S�ʔ��搧�x�̊J�n���T���A�֘A����l�ގ��v�������߂邱�ƂɑΉ�����B �l�ނ͌_��Ј��Ƃ��č̗p���A���C�ŋƖ��ɕK�v�Ȓm����X�L�����K����������Ōڋq��Ƃɔh������B�����͕⏕���\���֘A�̎���������₢���킹�ɑ���R�[���Z���^�[�����Ȃǂ̎��v��������ł���B���̌�A�����Ή��̈���L����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���Z�F�d�H�A��^�~���d�V�X�e���J���V��������؉^�] �d�͒����Ɏg����[�d�r�u���h�b�N�X�t���[�d�r�v�ƁA���d�����̍����W���^�̑��z�����d���u��g�ݍ��킹����^�̒~���d�V�X�e�����J�����A2014�N���߂ǂɖ{�i�̔�����Ɣ��\�����B ���Ɖ��Ɍ����A���ʐM�֘A�̎�͋��_�ł��鉡�l���쏊�ɖ�10���~�𓊂��Ď����p�̃V�X�e����ݒu���A�V��������؉^�]���J�n����B���؉^�]�ł͉��l���쏊�̕~�n���Ɍv28��̏W���^���z�����d���u�i�ő唭�d��200kW�j�ƁA���d�����d�͂��Ԃɓd�͉�Ђ���w�������d�͂����߂郌�h�b�N�X�t���[�d�r�i�~�d�e��5000kWh�j��ݒu�B�[�d�r�ɂ��߂��d�͂��g�����ƂŁA�s�[�N���ɓ����쏊�̎g�p�d�͗ʂ̖�1���ɂ�����ő�1000kW��}���ł���Ƃ����B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ��210���~�̕⏕���A����1/3���S�Œ�u�p�~�d�r�s�ꂪ�n�� �o�ώY�ƏȂ́A����23�N�x��O����\�Z�ɂ��u��u�p���`�E���C�I���~�d�r�������i�Ɣ�⏕���v�Ɋւ����ʍw���҂̐\���i�\��\���j���J�n�����B ���Ɗ��Ԃ͕���25�N�x�i2013�N�x�j���A�������͌�t�z���\�Z��210���~�ɒB����܂łƂȂ�B�⏕�͌l�Ɩ@�l�ł̐\�����\�ł���A�⏕����1/3�ƂȂ�B�ǂ�����e��1kWh�ȏ�̒~�d�V�X�e�����ΏۂŁA�l�����͍ō�100���~�܂ŕ⏕�B����A�@�l������1.0kWh�ȏ��10kWh�����͒~�d�V�X�e���݂̂��⏕�ΏۂƂȂ�B10kWh�ȏ�̒~�d�V�X�e���̏ꍇ�́A�ݒu�H����ƒ~�d�V�X�e���ɕt������➑́i�L���[�r�N���j��\�����u�Ȃǂ̕t�ѐݔ���܂ŕ⏕�ΏۂƂȂ�B�@�l�����ł͍ō�1���~�܂ŕ⏕�B�⏕���̐\�����t�Ȃǂ̋Ɩ��́A�����n�C�j�V�A�`�u�iSII�j���S������B�⏕�ΏۂƂȂ�̂́ASII�̔F�����@��݂̂ƂȂ�B�������A���݂̂Ƃ���Ώۋ@���3��7���i�B������R���𑱂���Bhttp://sii.or.jp/lithium_ion/file/setsumeikai.pdf �o�T�u���o�G���N�g���j�N�X�v |
|
|
| ���V�z�Z��E���z���̏ȃG�l��K�����`�����A�܂��͑�K�͌��z������ �H���\�i�āj�́A��荂���ȃG�l���\�̏Z��E���z���̌��z���i�ɁA���z�����d���ɂ��G�l���M�[�n�o�ʂ��͂��߁A�Z��E���z���̃��C�t�T�C�N���̊e�i�K�ɂ�����CO2�r�o�ʂȂǂ������I�ɕ]������w�W�Ƃ���B 2012�N�x�ȍ~�����ɁA�Z��\�\�������������B�V�z�Z��E���z���̍Œ���̏ȃG�l���\���m�ۂ��邽�߂ɁA�V�z�Z��E���z���̋K�͂��K�́i2,000m2�ȏ�j�A���K�́i300�`2,000m2�j�A���K�́i300��2�����j�ɕ����āA�܂��́A��K�͂̌��z�����瓱�����Ă����B��K�́E���K�͂̌��z���͓͂��o�`���A���K�͌��z���͓w�͋`���Ƃ���B�`�����̐����́A��������̏ȃG�l�����{�ɁA�`�����������_�ł̏ȃG�l��B���������Ă��Đݒ肷��B�ȃG�l��̉����́A��Z���2012�N�x���ɁA�Z���2012�N�x�ȍ~�����Ɏ{�s����B�Z�p�ҁE�̐����̐����ł́A�����H���X���ɑ��āA5���N�v��ŏȃG�l�{�H�Z�p�K���x�������{����B�܂��A��K�͂̌��z���ɑ���ȃG�l��ւ̓K���`�����Ɍ����āA���ށE�@��̐��\�E�i����S�ہE�\�����鐧�x������������B �Z�܂����̉��P��Ƃ��āA�X�}�[�g���[�^�[�ƘA�g�����AHEMS�EBEMS���̓����x���A���ԑї������̏_��ȗ������j���[�̓����ɂ��C���Z���e�B�u�̕t�^�Ȃǂ����{���Ă����B2020�N�܂łɂ́A�Z��ɂ��āA�W���I�ȐV�z�Z���ZEH�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�n�E�X�j���A���z���ɂ��ẮA�V�z�������z������ZEB�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���j���������邱�ƁA2030�N�܂łɂ́A�V�z�Z��̕��ς�ZEH���A���z���ɂ��ẮA�V�z���z���̕��ς�ZEB�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���j���������邱�Ƃ��A�ڎw���ׂ��p�Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���������ʃK�X�����[���ł��u25%���v���ȁA2030�N���Z�����\ �����d�͕�����1�������̂��A�������ʃK�X�̍팸�ڕW�̌��������������Ă�����Ȃ̒������R�c��ψ���́A2030�N�̎��_�Ŕ��d�d�͗ʂɐ�߂錴���̊������[���ɂ��Ă��A�������ʃK�X�̔r�o�ʂ�1990�N��ōő�25%�팸�ł���Ƃ̎��Z�����\�����B ���Z�͍����������������{�����Ƃ̂��ƁB2011�`2020�N�x�̕��ϐ�����������2%���x�ŁA����ҕ����㏸�����������I��2%�Ő��ڂ���u�����V�i���I�v�ƁA���ϐ�����������1%���ŁA����ҕ����㏸����1%���x�Ő��ڂ���u�T�d�V�i���I�v��z��B���V�i���I���A�ȃG�l�̑��i�⑾�z�����d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�̓�����̋��x�ɉ����Ă����3���ނ��A���ꂼ��ɂ��āA�����̊�����0%�A20%�A25%�A35%��4�p�^�[���Ŏ��Z�����B���̌��ʁA1990�N��̉������ʃK�X�̍팸�\�ʂ́A�������̊���0%=�����V�i���I5�`20%�A�T�d�V�i���I10�`25%����20%=�����V�i���I14�`29%�A�T�d�V�i���I19�`33%����25%=�����V�i���I16�`30%�A�T�d�V�i���I21�`35%�� ��35%=�����V�i���I20�`34%�A�T�d�V�i���I25�`39%�ƂȂ����B �o�T�ugreen plus�v |
|
|
| ���֓��o�ϋǂ�������Ɠ��̏ȃG�l����������Љ� �P�D������Ɠ��ɂ��w�A�g�x�ȃG�l��������W�{����W�́A�ȃG�l�Ɋւ�����s�����������邽�߁A�����̒�����Ƃ����͂��Ȃ���ȃG�l���������{���Ă��鎖���A����23�N�Ă̓d�͕s���ɑΉ����邽�߁A�n��S�̂Őߓd�Ɏ��g�ގ���Ȃǂ��f�ڂ��Ă���B �@�ȃG�l�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���ƊE�c�� �A�I�[�i�[�ƃe�i���g�o�������͂��ďȃG�l�����{���Ă���e�i���g�r�� �B�ȃG�l�̐��i����̎x���Ƒ����A�n�悮��݂Ŋ������Ă���Y�Ǝx���@�� �C�w�ȃG�l������x�����p���A�A�g�����ȃG�l���������{�����g���ȂǁB �Q�D������Ɠ��̏ȃG�l���M�[��g����W������Ɠ����ȃG�l���������{���Ă��鎖��ɂ��Ē������A���̌��ʂ�����W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B ������Ƃ��⏕�������p���Ȃ���ݔ��������s���A�ȃG�l���������Ă�����A�ݔ��̉^�p�ʂɂ����āA�p�������ȃG�l���������{���Ă��鎖��Ȃǂ��f�ڂ��Ă���B http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/3-2syoene_jirei.html �o�T�u�ߓd�[���}�K�W���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���f�d�x�m�d�@���[�^�[�A����^�X�}�[�g���[�^�[�J���|�}���V�����d�C���ጸ �}���V�����P�����Ȃnj���ꂽ����̓d�͂��Ǘ����郍�[�J���^�X�}�[�g���[�^�[�i�ʐM�@�\�t���d�͌v�j���J�������B�d�͉�Ђ��狟�����������d�͂̓����e�˂ւ̋����Ǘ��ȂǂɎg���B�^���F���҂��ď��i������B ���[�J�����p�ɓ��������X�}�[�g���[�^�[�͍��Y���Ƃ����B�}���V�����Ǘ���ЂȂǂƒ�g���A�d�C�����ጸ�ɂȂ���d�͊Ǘ��V�X�e���Ƃ��Ĕ���o���B ��ʂ̃}���V�����́A�����҂��Ƃɓd�͉�Ђƒሳ�i100�{���g�j�_������ԁB������H���I�t�B�X�r���Ɠ��������i6000�{���g�j�Ō������ƂɎ�d���A�e�˂ɋ�������Ɠd�C�����͊����ɂȂ�B����ɃX�}�[�g���[�^�[��g�ݍ��킹��A�e�˂̓d�C�g�p�ʂ̃��A���^�C���v����A�s�[�N�������������ɂ��邱�Ƃŕ��ׂ����炷���Ƃ��\�ƂȂ�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���J�}�N�������̋C�����M�𗘗p���ė�p����u�C�����M���������u�v�� �L���X�^�[�t�̋C�����M���������u�́A�C���������h���K�v�Ȏ��ԑт́A�\�z�ȏ�Ɏ��x���Ⴂ���Ƃɂ��A�����̉��x�͊O�C�����傫��������A�C�����������������~�������ԑтɁA�����͍ő�̌��ʂ����A�M���ׂ̑傫���|�C���g�ɑ��ăX�|�b�g�I�ɗ������������邱�Ƃ��ł��A�X�|�b�g�G�A�R���Ɣ�r���āA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɗD��邾���łȂ��A�ғ����ɔr�M���������Ȃ��B ���Z�ł́A�G�A�R���Ɣ�r���āA����d�͂�80���팸�ł��A�����������܂߂������j���O�R�X�g�ł�70���J�b�g�ł���Ƃ����B �����e�i���X�̕p�x�͎g�p���ɂ��قȂ邪�A�g�p�V�[�Y���̊J�n���ƏI������2��A���|�y�ѓ_�����K�v�B �����߂̐ݒu�ꏊ�Ƃ��āA�H��E�q�ɁE���Z��E�r�A�K�[�f���E���X�X�E�C�x���g�E�S���t���K��E�h�b�O�����E�������E�V���n�E�_�앨�W��E���V��Ȃǂ������Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����}�_�d�@�A��d���ł��_������o�b�e���[�������̒��nj^LED�Ɩ���̔� ���}�_�d�@�ƃT�C�o�[�R�C���́A��퓔�@�\����������nj^LED�Ɩ��̋����̔��Ɋւ��Ē�g�������Ƃ\�����B�T�C�o�[�R�C�������Y���s���A���}�_�d�@���@�l�����ɓƐ�̔����s���B�Ȃ��A���Y�ƂȂ��Ă���A���i�̖ڈ���19,800�~���x(�H�����)�ƂȂ錩���݂��B ���`�E���C�I���o�b�e���[���������ꂽ���nj^LED�Ɩ��B��d���Ɏ�����400�`800lm(���[����)�̔�퓔���[�h�Ɉڍs���A2�`12���Ԃ̓_�����\�ƂȂ��Ă���B �܂��A����̎g�p���ɂ́AAC�d���ɂ��_���ƃo�b�e���[�[�d���ɍs���u���[�hA�v��3���ԉғ����A���̌�̓o�b�e���[�ɂ��_�����s���u���[�hB�v��2���ԉғ����邽�߁A�ȃG�l�E�ߓd�ɂ��v���B���[�hA���̏���d�͂�25W�ŁA���[�hB���͒ʓd���Ȃ����ߏ���d�͂�0W�ƂȂ�B�u(25W�~3����+0W�~2����)��5=15W�v�ƂȂ�A���}�_�d�@�ɂ��Ɓu����15W�Ƃ����̂́A��ʓI�ȓ��^��LED��26W�Ƃ�������d�͂��ȃG�l���ʂ��傫���v�Ƃ̂��ƁB ��Ȏd�l�́A������G13�ŁA��i�d����100�`260V AC�A����d�͂�25W(�_��+�[�d��)�A�S�������O���d���_����(���[�hA)��2,600lm�A�ʏ�̃o�b�e���[�_����(���[�hB)��2,100lm�A���_������400�`800lm�ƂȂ��Ă���B�F���x��5,000K�A�g�U�̈��270�x�A�v������50,000���ԁB �o�T�u�}�C�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���E�C���R���������K�X�����ɏȃG�l�ʐM�[�����J�� �ʐM�p�����̂̊J���E��������|����G�C�r�b�g�ȂǂƐV����PHS�`�b�v�Z�b�g���J�������B�ő�̓����́A�]���`�b�v�Z�b�g�ɔ�ׂĖ�4����1�̏���d�͂œ��삷��_�B�W���I��2400mA�i3V�j�̓d�r���g�����ꍇ�A10�N�ȏ�쓮�ł��A�d�r�������ӎ������Ɏg�p�ł���B ���̃`�b�v�Z�b�g�𓋍ڂ����K�X���[�^�[�p�ʐM�[�����J���B�K�X�̋��������u�ŎՒf������A�����Y��̊m�F��ُ��m�点��u�}�C�c�[�z�[���v�T�[�r�X�Ɋ��p����B5�����琔�S���тŎ��؎������n�߁A���H�ȍ~�Ɂu�}�C�c�[�z�[���v�����Ă���ƒ�̈ꕔ�ɐ�s��������v�悾�B���ݖ�71�����т��u�}�C�c�[�z�[���v�ɉ������Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������V���b�^�[���f�M���\�����߂��Y�Ɨp�V���b�^�[�� �p�l���ނ�3��ށi�X�`�[���E�A���~�E�X�e�����X�j�p�ӂ��A�p�l������60mm �Ƃ����B�����ɍd�����A�E���^�����[�U���邱�ƂŒf�M�������߂�ƂƂ��ɁA�p�l���̂Ȃ��ڂɓ��ГƎ��̎����g���{�����Ƃŋ������m�̔M�̓`�����Ղ�M�≏�\���Ƃ��Ă���B ���[����3�d�\���̃G�A�p�b�L���i�t�B���t���V�[���j�Ŗ��������߁A�N�x�ێ��ȂǕi���Ǘ��ɋ��߂��鎺���̒艷�����������A�@��̉ғ�����}������ȓd�́E�ȃG�l���M�[�i�ƂȂ��Ă���B�p�l���͓��O�Ƃ��Ƀt���t���b�g�Ȍ`��ŁA�z�R���⌋�I�����܂�ɂ�������̂ӂ������e�Ղȃf�U�C�����B�V��̎��[���Ƀh�A�p�l����܂肽���ނ��ƂȂ��A���̂܂ܓV�䕔�ɃX���C�h�����Ď��[���J����B����ɁA�����̉��x����ێ����邽�߁A�A���ԗ��ւ̔��o����ƒ��ł��O�C�̗�����}������ӏ��i�����C���i�b�v���A�ۊǂ���A���ɂ�����܂ň�т����艷�l�b�g���[�N�̍\�z�ɍv������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���V���[�v�����d���Ƃ�W�J�� ���K�\�[���[3�J���ɐݒu �Ȗ،��Ɩk�C����3�J���Ɏ��А����z�d�r�ɂ�郁�K�\�[���[�i��K�͑��z�����d���j��ݒu���A���d���Ƃ������W�J���邱�Ƃ����������B ���Ђ́A�v��i�K�Ŏ~�܂��Ă����H��i��s���j�̃��K�\�[���[���݂��ϋɓI�ɐi�߂�l���B�Đ��\�G�l���M�[�̑S�ʔ�������d�͉�Ђɋ`���t���鐧�x��7������n�܂�̂��A����I�Ȏ��v�������߂�Ɣ��f�����B �Ȗ،���s�̎Y�ƒc�n�ɂ��錧�L�n6.8�w�N�^�[������A�o��2000kW�̔��d����ݒu����B�k�C���k���s�͎s�L�n2�w�N�^�[�������1500kW�A�N�ʒ��͒��L�n����1500kW�̔��d�������݂���B�����������s���Ɠy�n�̎�����܂��Ă���B 3�J���Ƃ����ݎ����͖���ŁA�ғ���7���ȍ~�ɂȂ�Ƃ݂���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����z�� ���[�t���[�X���ƁA���{�ł� ���{�����R�G�l���M�[�̑S�ʌŒ艿�i���搧�x�J�n�ɍ��킹�ē����Ɍ��y���Ă���u������v���x�́A���d��Ђ���ʉƒ�̉�������Ĕ��d���Ƃ��s����悤�ɂ���Ƃ������́B ��ʉƒ������3�`4kW�K�͂̑��z���p�l���̐ݒu��p�́A200���~�`300���~�ŁA���d���Ă���������ɂ�10�`20�N���x������B�����ŁA��Ƃ����z���p�l���̐ݒu��p����e�i���X�̌o��S�B�ƒ�͉����̒������A��Ƃ͔��d�ɂ�闘�v��Ƃ����d�g�݂������莖�ƁB �p���̃u���e�B�b�V���K�X�́A��ʉƒ�̉��������u���[�t���[�X�X�L�[���v���Ƃ�W�J���Ă���A����i���̃h�C�c�ɂ́A�������肽�����Ǝ҂Ƒ݂������l���}�b�`���O����R�~���j�e�B�T�C�g������B ���{�����ł��A�H����K�͏��Ǝ{�݂̐ܔ������◤�����ɓ������������莖�Ƃ��o�Ă��Ă���B��ʉƒ�̉����莖�Ɠ��l�A�݂����Ƃ͎��ȕ��S�[���ŁA�ݒu�������z�����d�̋K�͂ɉ����āA15�N�ԁA���̎�����������Ƃ������f�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�X�}�[�g�ߓd�v�s���Ŏ��� �����ɉ����@�퐧�� �d�͂̎����ɉ����ă^�C�����[�Ɏ��v��}������ �u�X�}�[�g�ߓd�v �̎��؎������s���Ŏn�܂����B �����d�͂ƕs���Y�A���ʁA�w�Z�Ȃǂ̂X�@�l�ō�� �u�X�}�[�g�ߓd���l�����v �ɂ����̂ŁA���d����̎��v�}���˗��Ɋ�Â��A�������̋�Ɩ��@��Ȃǂ����炩���ߐݒ肵���ߓd�^�]���[�h�Ő��䂷��B 500kW�����A500kW�ȏ�̌����ł��ꂼ����ۂɕ��ׂ�}�����鎎�������{���A�A���̐��̊m�F��ߓd���ʂ̌����s���Ă���B �X�}�[�g�ߓd���l�����ɎQ�����Ă��铌�������ł́A���L���铌�a�J�r���Ŏ����s�����B�̐ߓd�ɂ͉��x�̐ݒ��ύX������@�����邪�A�e�i���g��L���ɂ���@��̐ݒ艷�x�𒆉�����ł���r���͏��Ȃ��B���ł͋@��̋N���E��~�𒆉����䂷��@�\���g���A���炩���ߓo�^���Ă������X�P�W���[���łP�̃t���A�ɂ���@����u���b�N���ƂɎ��Ԃ����炵�Ē�~�����邱�ƂŁA���̐ߓd���ʂ������邩��������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�� �d�͏����s���V�݂̕��j ���d�͎���͑��d�͎��v��1���ɂ������Ȃ��B��������ۂ̍ŏ��P�ʂ�1000kWh�Ƒ傫���A���Ɣ��d��R�[�W�F�l�̗]��d�͂�̂�����B ���Ăɂ������d�͐��̎s��𗧂��グ�A���K�͂Ȏ��Ɣ��d�̓d�C�̎���𑝂₷�B�V�s��̖��̂́u���U�^�E�O���[�����d�s��v�Ƃ�������B���͂⑾�z�����d�ȂǂŋN�������d�C���V�s���ʂ��Ĕ���������j���B �����̓d�͉�Ђɑ��Ă��A�]�����d�C������s���ʂ��Ĕ̔�����悤�@���ŋ`�����邱�Ƃ���������B���d�C���Ǝ҂́A�d�͉�Ђ���d�C�̋��������߂�ꂽ�ꍇ�A�f��Ȃ��u�����`���v���@���Ō��܂��Ă��āA�d�C�̑唼��d�͉�Ђɔ����Ă��邪�A������O�����ƂŐV�d�͂Ȃǂւ̔̔��@��𑝂₷�B�����̂��Ǝ��ɉ^�c���Ă��鐅�͔��d�́A�d�͉�ЂɌ��肵�Ă���̔����V�d�͂Ɋg�傷��B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �������s�A������Ƃ̎��Ɣ��d�E�~�d�r�������x���A��Вn���Ə����Ώۂ� �{���Ƃ́A�u����23�N�x�ً}�� ������ƌ����d�͎����^�o�c���i�x�����Ɓv�Ƃ��Ď��{���Ă�����́B ����̏����Ώۊg��̋�̓I�ȓ��e�͈ȉ��̓�_�B��_�ڂƂ��āA�s��������Ǝ҂��A�u�����{��k�Ђɂ�钼�ړI�Ȕ�Q�ɂ��d�͎��v�}�������n��v�ɂ���s�O�̎��Ə��Ɏ��Ɣ��d�ݔ��E�~�d�r��ݒu����ꍇ���A�����������p�ł���悤�ɂȂ�B��_�ڂƂ��āA�~�d�r�i1��2kW���ȏ�B�V�i�Ɍ���B�j�y�т��̕��ѐݔ����̓����ɂ������������p�ł���悤�ɂȂ�B�~�d�r�̗v���́A�@���d���ɂ��펞�d�C��~����d���ɑΉ��ł�����́A�A�ߓd���͎{�ݐݔ����̓d�͂̃o�b�N�A�b�v��ړI�Ƃ��āA�v���d�Ȃǂ̏ꍇ�Ɏ{�ݐݔ������p�����ĉғ������邱�Ƃ��ł�����́A�Ƃ��Ă���B ����������W���鏕�����̓��e�́A������ƒP�Ƃ̏ꍇ�́A������2����1�ȓ��i3����2�ȓ��j�A�������x�z1,500���~�i2,000���~�j�A������ƃO���[�v�̏ꍇ�́A������3����2�ȓ��i4����3�ȓ��j�A�������x�z��5���~�i5.6���~�j�B���ʓ��͕���23�N�x���ɐ\�����������ꍇ�ɓK�p���鏕�����y�я������x�z�B�������x�z�ɂ��ẮA�����Ƃ��ăO���[�v�\����Ɛ���2,000���~�i2,250���~�j���悶�����z�Ƃ��Ă���B�����Ώۊ��Ԃ͕���23�N3��11�����畽��25�N3��31���܂ŁB�\�����Ԃ͕���24�N2��8�����畽��24�N9��30���܂ŁB �o�T�u ���r�W�l�X�v |
|
|
| ���I�o�}�đ哝�́A�w���̏ȃG�l�Z�p�{���Ɗ�Ƃ̃G�l���M�[�R�X�g�ߌ�����������Y�ƕ]���v���O�����𐄐i �}�C�A�~��w�ł̃G�l���M�[����Ɋւ���u���ŁA�G�l���M�[�Ȃɂ��Y�ƕ]���v���O�������Љ���B ���v���O�����́A�S��24��w�����_�Ƃ����u�Y�ƕ]���Z���^�[�iIAC�j�v���x�����A�H�w�n�w�����n��������Ƃ̐������Y�ݔ��̃G�l���M�[�]�����s���A�Q����Ƃ̃G�l���M�[�R�X�g�팸��}��Ƃ������́B����܂ł�530��BTU�i�p���M�ʒP�ʁj����ȃG�l�A56���h�����̃G�l���M�[�R�X�g�ߌ��ݏo���Ă���Ƃ����B IAC�́A�G�l���M�[�]���Ŋ�Ƃ��x���������A�w���ɑ��Ă��Y�ƍH���A�G�l���M�[�]���̎菇�A�G�l���M�[�Ǘ��̌��������Ɋւ��錻��̌����K����Ă���A�G�l���M�[�Ȃ͂��̃v���O�����ɂ��A�����̃N���[���G�l���M�[�Z�p�҂̗{���A�č���Ƃ̃G�l���M�[�������P�A�����Ƃ̑ΊO�����͋�����ڎw���Ă���B �o�T�u EIC�l�b�g �v |
|
|
| ���@�@[�@2012/4�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�X�Ɠ����A�v���C�A���X���R�[�W�F�l�p�M�𗘗p����[�W�F�l�����Nmini]�� �V���i�́A�R�[�W�F�l���[�V�����p�M��L�����p����p�M�����K�X�z���≷���@�Ƃ��Ă͋ƊE�ŏ���[�\�͂�211kW(60USRT)�@���͂��߁A246kW(70USRT)�A281kW(80USRT)�352kW(100USRT)��4�@�킪���C���i�b�v����A�p�M����(88��)�𗘗p�����ꍇ�A��i��[�^�]���̃K�X�g�p�ʂ�20���팸�ł���B �܂��A�����A�v���C�A���X���]���@�̏��^�K�X�z���≷���@�ɔ�ׂ��(��i��[�^�]��)�A�p�M�������ŃK�X�g�p�ʂ�40���팸�ł��A�p�M���Ȃ��ꍇ�ł�25���팸�ł���B����ɁA�ᕉ�^�]��(��[�\�͂���i�̖�35���ȉ�)�́A�p�M���������ŗ�[�^�]���s�����Ƃ��ł���Ƃ����B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���O��s���Y�����̗t�n��ŃX�}�[�g�V�e�B�W�J�K�X���d�ƒ~�d�r��CO2 6���� ���s�Ⓦ����w�ȂǂƘA�g���āA���̗t�L�����p�X�̖�273���������[�g���̕~�n�ɐl��2��6000�l�̃X�}�[�g�V�e�B�J�����Ƃ�i�߂Ă���B ���R�G�l���M�[�̓����ȂNJ��z���^�̏Z������Ă�Ɠ����ɁA�X�S�̂Ō����I�ȃG�l���M�[�Ǘ���i�߂�X�}�[�g�V�e�B�̕��y��i�߂Ă���B2014�N�t�܂ł�2000kW�̑�K�̓K�X���d��~�d�r������Ɣ��\�B�G�l���M�[�̗L�����p�Ȃǂƍ��킹��2030�N�ɁA��_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ��]���̊X�Â���Ɣ��6���팸����B ��K�̓K�X���d��~�d�r������̂́A���G�N�X�v���X�̔��̗t�L�����p�X�w�O�̃z�e������ݏZ�����X��ŁA�ЊQ�A��d���ɂ�3���ԁA�����̖�6�����̓d�͋������s����悤�ɂ���B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���\�j�[�A���p�ҁE�@�킲�Ƃɓd�͂��Ǘ�����u�F�،^�R���Z���g�v�J�� �d�C�𗘗p����ۂɕK���ʂ�C���t���ł���u�R���Z���g�v�ɒ��Ⴕ�A���[�U�[���\���I�ɓd�͊Ǘ���d�͐�������Ȃ��痘�p�ł���u�F�،^�R���Z���g�v���J�������B �F�،^�R���Z���g�́A�@�푤�̃v���O�֔�ڐGIC�`�b�v�𓋍ڂ��A�R���Z���g���ɔ�ڐGIC�J�[�h���[�_�[/���C�^�[��R���g���[���A�ʐM�C���^�t�F�[�X�Ȃǂ�g�ݍ��ނ��ƂŁA�d�C�@�킪�R���Z���g�ɐڑ����ꂽ�ۂɁA�d�C�@��/���p�҂ʂ��ĔF���A�d�͂Ƃ̊֘A�t������������B��̓I�ɂ́A��ڐGIC�J�[�h�Z�pNFC/FeliCa�����p���ēd�C�@��F���s���uFeliCa�^�C�v�v�ƁA�V�Z�p�u�d�͐��d���ʐM�Z�p�v�ɂ��A�d���P�[�u������ēd�C�@��F���s���u�d�͐��d���ʐM�^�C�v�v��2��ނ��J�����ꂽ�B �F�R���Z���g��p���邱�ƂŁA�u�r���̋��p�����ɔF�؋@��ȊO�͒ʓd���Ȃ��w���d�h�~�x�R���Z���g�̐ݒu�v��u�w���`�ȂǂŁA���o�C���[����ΏۂƂ����g���������Ɏg�������ʂ̓d�͂𗘗p�ł���R���Z���g�̐ݒu�v���\�ɂȂ�B �o�T�u�}�C�i�r�j���[�X�v |
|
|
| ���x�m�o�ρA�G�l���M�[���R���s����APPS���ƍs�l����w�E 2011�N�x�́A��ʓd�C���Ǝ҈ȊO�̎��Ǝҁi����K�͓d�C���Ǝ�PPS�j�̔̔��d�͗ʂ́A�O�N�x��0.5������200.6��kWh�ƂȂ錩���݁B �k�Ќ�Ɉ����������}���������A�d�͒��B��Ɗ����ڋq�̐ߓd�ɂ��قډ����ɂȂ�Ɨ\������B �G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���^�T�[�r�X�iEMS�j�s��́A2011�N��1,901���~�i�O�N��103.9���j�A2015�N��2,515���~�i2011�N��132.3���j�ƂȂ錩�ʂ��B 2011�N�͓d�͋����s�����āA��Ƃ��ߓd�ւ̎��g�݂��������Ă���B�Z���I�ȑ�Ƃ���ASP�^SaaS�^EMS�f�}���h�Ď����u�ȂǁA�[�����Z�������ŊȈՂȃV�X�e���̓�������C�ɐi�B�������A�d�͋����s���̒������Ɗ��K���̋����ɂ��A�p���I�Ȏ�g�݂����߂��Ă���A�V�X�e���P�̂̓����ɂ��ꎞ�I�ȑ��łȂ��AASP�^SaaS�^�T�[�r�X��BEMS�Ȃǂ̃G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���^�T�[�r�X�iEMS�j�ɂ��^�p���P�Ȃǂ̕K�v�������܂�Ɨ\������B �ً}�̐ߓd�E��d��Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�V�X�e����2011�N�s��́A���Ɣ��d�V�X�e�����O�N��133.4���A�K�X�q�[�g�|���v�G�A�R���iGHP�j���O�N��133.8���A�d�̓��j�^���O�N��150.0���A�f�}���h�Ď����u��334.8���ƂȂ錩�ʂ��B�������A2015�N��2011�N��ŁA���Ɣ��d�V�X�e����8.18���A�K�X�q�[�g�|���v�G�A�R���iGHP�j��84.2���A�d�̓��j�^��90.7���A�f�}���h�Ď����u��58.1���ɂȂ�Ɨ\������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������d�́A�ߓd�Ŋ����A������ƌ������Ă̊����v�����\ 2012�N�ĂɌ����āA������ƂȂǂ̐ߓd���͂ɑ��āA�d�C��������������3�̗������j���[�u�T�}�[�A�V�X�g�v�����v�\�����B �ߓd����������������v������A�����Ɍv��I�ɋx�Ƃ����ꍇ�Ɋ�������v�����Ȃǂ荞�݁A������ƂȂǂɐߓd���͂𑣂��B�����d�͂�4�������ƌ����̓d�C������l�グ���邪�A�{�v�����̊��p�ɂ��A�I�t�B�X�r���A�����ƁA���Ǝ{�݂Ȃǂ̃��f���P�[�X�ŁA�l�グ�����30�`37���ɘa�ł���Ǝ��Z���Ă���B�_��d�͂�500kW�����ŁA�ő���v�d�͂ɂ��ƂÂ��_��d�͂����肵�Ă���ڋq���ΏہB������Ƃ⒆�K�͂̍H��A�X�[�p�[�ȂǑΏۂƂȂ�B���\�����������j���[��3�B �u�f�}���h�_�C�G�b�g�v�����v�́A2012�N�āi7�����`9�����j�̊e���̍ő���v�d�́i�ő�f�}���h�j���_��d�͂���������ꍇ�A����������̓d�͂ɉ����āA�d�C����������������j���[�B �u�T�}�[�z���f�[�v�����v�́A�ċG�ɂ����āA�y�E���j���A�j���̋x�Ɠ����ɕύX����ȂǁA�����ɐV���ȋx�Ɠ����v��I�ɐݒ肷��ꍇ�A�x�Ƃɂ��d�͂̍팸�ɂ��ēd�C�������������郁�j���[�B �u�E�B�[�N���[�v�����v�́A�d�C�̎g�p���s�[�N�̎��ԑсi�ċG�̕����ߌ�P���`�S���j�ɁA�T�P�ʂł���Ɉ��K�͈ȏ�̓d�͂̍팸���\�ȏꍇ�A�팸����(kW)�ɉ����ēd�C�������������郁�j���[�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������G�l���A�ȃG�l�@�����̕������d�̓s�[�N�}���ȂLj�v ���������G�l���M�[������ȃG�l���M�[����́A�d�͎��v�̃s�[�N�}���⌚���̗�g�[���������B�����邽�߂̏ȃG�l���M�[�@�����̕������ɂ��Ĉ�v�����B�o�Y�Ȃ͉����@�Ă̍�����ւ̒�o��ڎw���A�̍쐬��i�߂�B ���s�̏ȃG�l�@�́A��ƂɃG�l���M�[�̎g�p�ʂ�N���ςP���팸����悤���߂Ă���B��������Ƃ��s�[�N���ԑтɎ��Ɣ��d���s���ēd�͍w�������炵���ꍇ�́A���Ɣ��d�ɔR�����g���Ă��邱�Ƃ���G�l���M�[�g�p�ʂ��팸�������ƂɂȂ炸�A���Ɣ��d�̓������i�܂Ȃ�����Ƃ���Ă���B ���̂��ߓ�����͏ȃG�l�@���������A�G�l���M�[�g�p�ʂƂ��ăs�[�N���ԑт̓d�͍w�����s�[�N�ȊO�̎��ԑт̓d�͍w�������傫���Z�����邱�ƂŁA�s�[�N���ԑт̓d�͍w�������炷�悤�ɑ������Ƃō��ӁB����ɁA�s�[�N��̂��߁A���ԑѕʂ̓d�͎g�p�ʂ��v���ł���X�}�[�g���[�^�[�i������d�͌v�j�̕��y���x�����邱�Ƃł���v�����B �܂�������͌����̒f�M�������߁A��g�[�̌�������}��������������B����f�M�ނ̃��[�J�[�ɐ��\���P�𑣂����x�̓��������߂��ق��A2020�N�܂łɐV�z�����̏ȃG�l��K�����`�������邱�Ƃ̏d�v���ł����ӂ����B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ������K�͓d�C���ƎҁiPPS�j�̐V���Ȓʏ̂��u�V�d�́v�o�Y�Ȃ��ʏ̂�ύX �������̌�A�d�͎��R���ɂ��č����I�ȋc�_�����܂钆�APPS�ł͕�����ɂ����Ɣ��f�����B����A�o�Y�Ȃ��쐬���鎑���╶���ȂǂŐV�d�͂ƕ\�L�����߂�B PPS�́u�p���[�E�v���f���[�T�[�E�A���h�E�T�v���C���[�v�̗��B��ʂ̓d�͉�ЈȊO�̓Ɨ��n���Ǝ҂̈��ŁA����50kW�ȏ�̍����d�͂d���A�d�͉�Ђ̑��d�Ԃ�ʂ��čH����K�͓X�܂ɋ��������Ƃ��w���B 1999�N�̓d�C���Ɩ@�����œd�͎��Ƃ̐V���Ȍ`�ԂƂ��ĔF�߂��A���N2�����_��JX���z���G�l���M�[�A�p�i�\�j�b�N�A���Y�����ԂȂ�52�Ђ��F�肳��Ă���B�o�Y�Ȃ́u��ʂ̓d�͉�ЈȊO�̓d�͎��Ǝҁv�Ƃ����Ӗ��ŁA�u�V�d�́v�Ɩ��������B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���d���A�A�v���d�Ȏ��g���ϊ��ݔ����X�O���L�����b�g���� �����{��k�Ђł͕ϊ��ݔ��̐���ɂ��A�d�͕s���Ɋׂ��������d�͂Ⓦ�k�d�͊Ǔ��ɐ����{����\���ȓd�͂������ł����A�v���d��]�V�Ȃ����ꂽ�B���̔��Ȃ���A�o�ώY�ƏȂ͌������݂��ĕϊ��ݔ��̑������������Ă���A�d���A�͂��̌��ʂ����܂��Ē��肷��B ���g����ς�����ϊ�����3�J������A�ϊ��\�͍͂��v��100���L�����b�g�B�����2012�N�x����120���L�����b�g�܂ő�������邱�Ƃ����܂��Ă���B �d���A�́A�����{��k�ЂȂljߋ��ɔ���������K�͒n�k�Ȃǂ���A�n�k�ɂ���Ď����锭�d�ʂ�50�w���c�A60�w���c�т��ꂼ��Ōn���e�ʂ�10�����x�ɂȂ�Ƒz��B�d�͎��v�ɑ��鋟���]�͂������\����3�����m�ۂ���ɂ͕ϊ��\�͂������90���L�����b�g��������K�v������Ǝ��Z�����B �T�Z�H�����1320���`3550���~�Ǝ��Z�A�Η͔��d�ݔ�������ꍇ�������ςރP�[�X������Ƃ����B�����A�p�n�����Ȃǂ̖�������A�H���͍ŒZ�ł�10�N���x��z��B���{�C���ɕϊ��ݔ���V�݂���ꍇ�ł�20�N�ȏ�ɋy�ԉ\��������Ƃ��Ă���B �o�T�uSankei Biz�v |
|
|
| ���ƒ�����d�͎��R���ցA���t�ɂ��@������ �u�d�̓V�X�e�����v���ψ���v�͉ƒ�ȂǏ��������d�͔̔��̎��R���Ɍ����A��̓I�Ȏ��܂Ƃߋc�_�ɓ������B���{�����Ăɂ܂Ƃ߂�V���ȃG�l���M�[��{�v��ɐ��荞�݁A���t�ɂ����R���荞�d�C���Ɩ@�����Ă�����ɒ�o�������l�����B����́A�o�Y���ɂ�闿���̔F�����ǂ����邩���œ_�ƂȂ�B �ƒ�����̎��R������������A�����̈���������A���l�ȗ������j���[�̒ɂȂ���\��������B��N�̓d�͕s���̌o����A�����d�͂Ȃǂ��\�肷��d�C�����̒l�グ�܂��A����҂ɂ����l�ȑI������^����ׂ����Ƃ̈ӌ������܂��Ă���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/3�@]�@�@�� |
|
|
| �������i�C���G�l���M�[�g�p�ʂ́u�����鉻�v�@�\����������^���������R���� ����ƍ����̋�����Ŏg�p�����K�X�₨���A�ƒ��̓d�C�g�p�ʂ◿���ACO2�r�o�ʂ�\������u�G�l���b�N�v�𓋍ڂ��A����ɁA1���̏ȃG�l�ڕW�������Őݒ肵�A�ڕW�l�ɑ��Ăǂ̂��炢�̏���LED�̃J���[�\������uEco�K�C�h�v��A���ݎg�p���Ă��邨���̗ʂ�ƒ��̓d�C�g�p�ʂ�\������u�G�lLIVE�v�A�V�O�i���̓_���E�_�łŁA�œK�Ȃ����g�p�ʂ̖ڈ���m�点��uEco�V�O�i���v�Ȃǂ��̗p���Ă���B �܂��A���j�o�[�T���f�U�C�����̗p���A����҂Ȃǂɔz�����ă{�^���╶���̃T�C�Y��啝�Ɋg�債�A��ʂ̉��x�\���T�C�Y���]���̃����R���ɔ�ׂ�160���Ɋg�傳��Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �������d�́A4��������{�����ƌ����d�C�����̊T�v�\ �V���ȓd�C�����̒P���́A�S�ݓX�A��K�͎��Ə��r���ȂǓ��ʍ����i�_��d��2,000kW�ȏ�j�̌ڋq��1kWh������2�~58�K�A�����K�̓X�[�p�[�A�������ȂǍ����i�_��d��50kW�ȏ�2,000kW�����j�̌ڋq��1kWh������2�~61�K���A���s�̓d�͗ʗ����P���Ɉꗥ�ɏ�悹����B ����̗����l�グ��K�p�����ꍇ�̓d�C�����̃��f���P�[�X�ł́A�S�ݓX�A��K�͎��Ə��r���ȂǓ��ʍ����i�_���ʁF���ʍ����G�ߕʎ��ԑѕʓd��A�A�_��d�́F4,000kW�A���Ԏg�p�ʁF160��kWh�j�ł̒l�グ����18.1���B���z�����Ŗ�413���~�A�N�z�����Ŗ�4954���~�̕��S���ƂȂ�B�����K�̓X�[�p�[�A�������ȂǍ����i�_���ʁF�Ɩ��p�d�́A�_��d�́F150kW�A���Ԏg�p�ʁF33,000kWh�j�ł̒l�グ����13.4���B���z�����Ŗ�9���~�A�N�z�����Ŗ�103���~�̕��S���ƂȂ�B ����̒l�グ�ɂ���Ƃ̕��S�����͔�����ꂸ�A���Ɣ��d�̓�����A�d�͂������肷�����K�͓d�C���ƎҁiPPS�j�Ƃ̎�������������Ƃ������������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������A�v���C�A���X�A3�̃G�l���M�[���g�[�ɍœK���p����ȃG�l�p�M���@�� �p�M���@�u�����E���C�����^�K�X�z���≷���@�v8�@�������B�K�X�G���W�����d�@�Ƒg�ݍ��킹�A�K�X�G���W�����甭������p�����Ɣp���C�A����ɕʓr��������s�s�K�X��3�̃G�l���M�[���œK���p�ł���B�Ⓚ�\�͂�300�`1000�Ⓚ�g���B �������g���č\������R�[�W�F�l���[�V�����E�V�X�e���́A�]���V�X�e���Ɣ�r���āA�p���C�͗�M�ϊ��������������߁A�]���V�X�e���ɔ�ׂāA��[�Ɏg���G�l���M�[����ʂƓ�_���Y�f�r�o�ʂ��25���ጸ�ł���B�����i�̓G���W����~���ł��G�l���M�[���Ƃ��ēs�s�K�X���g����̂ŁA�]���V�X�e���ł͕��݂��s���������K�X�z���≷���@�Ȃǂ̔M���@��s�v�ɂł��A�ݒu�X�y�[�X��}������B �o�T�uTech-on�v |
|
|
| ����p�̏����ȋZ���𗬓_����LED�f�q���J��3���ȃG�l �V���������́A�d�C���z��������������p���[�����̂́u�c�F�i�[�_�C�I�[�h�v����Ƃ��A���̏�ɔ����@�\���������锖���̌����w���`���B�d�C�𗬂��Ɣ����̑w������d�g�݁B ��́u�c�F�i�[�_�C�I�[�h�v���R���f���T�[�̖��������ˁA�����ɕK�v�ȓd�C��~�ς�����A�d���������肷��B�V�����͌𗬂����̂܂g�����߁A�����ϊ��p�̃��W���[���s�v�ɂȂ�A���i�R�X�g��3�����x��������B�������̏]����LED�Ɠ����̔������\���m�ۂ��Ȃ������d�͂�3�����点�錩�ʂ��B �V�^LED�̐������u�̉��i�́A1���Ԃɑf�q��120���鑕�u��5000���~���x��z��B�߂����{�ł̎��Ƌ��_��݂��A�������u�������O�̏Ɩ����[�J�[�Ȃǂɔ��荞�ށB �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ȃG�l�@�����f�ĂɃs�[�N��̎��_ �~�d�r��G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iEMS�j�A���Ɣ��d�ݔ��̊��p�ŁA�s�[�N���ԑт̌n���d�͎g�p�ʂ�ጸ�����ꍇ�A���P�ʂ����߂���@�́A�Ⴆ�s�[�N���ԑт�1.5�A�s�[�N���ԑшȊO�̎g�p�ʂ�1�Ƃ������������W�����|���ĎZ�o����B����ɂ��A�g�p�ʂ������ł��A�s�[�N���ԑт̕����A�g�p�ʂ������Z�肳���d�g�݁B �s�[�N���i�߂邽�߂ɂ͎��v�Ƃ��g�p�ʂ̎��ԕω���c���ł��邱�Ƃ��K�v�B���̂��߁A�n���S�̂���v�Ƃ��Ƃ̎g�p�ʂ����A���^�C���ŏ�����`����d�͉�Ђɉۂ����Ƃ������B�X�}�[�g���[�^�[�̑������y��ʂ��Ď��ԑѕʗ����̌n���\�z�A�s�[�N�R���g���[�����s�����Ƃ��d�v�Ƃ��Ă���B�N�ԕ���1���ȏ�Ƃ��Ă���G�l���M�[�g�p�ʌ��P�ʂ̉��P�ڕW�͈ێ����邪�A���s�ł�1�N�Ԃ̕]�����Ԃ�5�N�Ԓ��x�ɍL����B �@������́A�������N�x�̎g�p���P�ʂ���l�Ƃ��Đݒ肵�����B�܂��A���Ǝ҂����N�x��o���Ă��������̕������ȑf�����A�n�ӍH�v�ɂ��l�X�Ȏ��g�݂������o���B 3����{�Ɋt�c���肵�A������ł̐�����ڎw���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�~�d�r�헪����֕��lj��f�ŐV�g�D �ȓ��̕��lj��f�Œ~�d�r�̐헪�����肷��̐��𐮂����B�����G�l���M�[���⏤�����ǁA�����Y�ƋǂȂǑ���35�l����Ȃ�u�~�d�r�헪�v���W�F�N�g�`�[���v��ݒu�B �Ă܂łɁA�n�����艻�̂��߂̑�^�~�d�r�Ə��K�͂̒�u�p�~�d�r�A�����ԓ��ڗp�̒~�d�r�̂��ꂼ��Ŏs��n���Ɠ��{��Ƃ̋����͋�����}��헪�����肷��B �n�����艻�̒~�d�r�́A�Đ��\�G�l���M�[�̑�ʓ������x������̂ŁA�i�g���E�������iNAS�j�d�r����\��B����ɑ���u�p�́A�Ɩ��p�E�ƒ�p�����œd�͎��v�̃s�[�N�}�����d���̃o�b�N�A�b�v�p�̂��̂ŁA��Ƀ��`�E���C�I���d�r���g���B �����{��k�Јȍ~�A���v���̐��䂪�d������Ă���A���z�����d�p�l���A�ƒ�p�̃G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iHEMS�j�ƕ��ԁu�V�O��̐_��v�Ɩ��t���Đ����ł��o���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �������Ȃƌo�Y�ȁA�X�}�[�g�V�e�B�[�����֔M���ǖԂ̐����x�� �H��p�M�⑾�z���Ƃ����������p�E�Đ��\�G�l���M�[�̃C���t���������X�Â���ƈ�̂Ői�߂閯�Ԏ��Ƃ̎x���ɏ��o���B �����{��k�Ќ�̃G�l���M�[����͓d�͂�M���g�n�Y�n���h�ł܂��Ȃ��X�}�[�g�V�e�B�[�i��������s�s�j�̎������������Ȃ��B�����Ȃƌo�Y�Ȃ͌n���d�͖Ԃ�K�X�ǂȂNJ����̃G�l���M�[�C���t���ɉ����A�H��Ȃǂ���o��M���X�ɏz������M���ǂ�n���̋����a�ɑ�K�͐������閯�Ԍv����㉟�����A�X�}�[�g�V�e�B�[����������J�����f�������������Đ��i����B �����Ȃ�2012�N�x�\�Z�ŃX�}�[�g�V�e�B�[�����̑O��ƂȂ�A�M���ǃC���t���������܂ޖ��Ԏ��Ƃ̍ĊJ���v��̍���x����Ƃ���3��5000���~���蓖�Ă����B�v���W�F�N�g�͌���őI�ԁB���̗\�Z�g�͔M���ǐݒu�̈ꕔ�⏕��A�v���W�F�N�g���i�̂��ߍĊJ�����̈ꕔ�Ŏ������p�̕⏕�Ƃ��Ă����p�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ������22�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̎��r�o�W���E������r�o�W���������\ �d�C���Ǝҁi��ʓd�C���Ǝҋy�ѓ���K�͓d�C���Ǝҁj���Ƃ̎��r�o�W���y�ђ�����r�o�W�����ɂ��āA�e�d�C���Ǝ҂����o���ꂽ�������Ɋ�Â��A�o�ώY�Əȋy�ъ��ȂŊm�F���A����Ɍf�ڂ��ꂽ�B http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14702 ��v�d�͉�Ђ̎��r�o�W���F �����d�́@���r�o�W��0.000375 �it-CO2/kWh�j ���d�́@�@�@�@�@�@�@�@�@0.000311 ��֒l�@�@�@�@�@�@�@�@�@0.000559 ���Ζ@�Ɋ�Â����{�y�ђn�������c�̎��s�v��ɂ����鉷�����ʃK�X���r�o�ʎZ��ɗp���镽��22�N�x�̓d�C���Ǝ҂��Ƃ̔r�o�W�� http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14708 �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���[�d��̓d�͏����}����`���B�A2013�N����S�ď��̏ȃG�l������� ���T���[���X�E�^�C���Y�ɂ��ƁA�B�G�l���M�[�ψ���͂��̂قǁA�����1��7000�̏[�d���W�I�ɂ����G�l���M�[��������������B �ƒ�p�d���ɐڑ����ꂽ�܂܂̏[�d��́A�g�p�d�͂̍ō�60����Q���ƌ�����B �����ɂ͉Ɠd�ƊE�Ȃǂ���R�������A35�����ѕ��̓d�͂�ߖ�ł��錩�ʂ����B���Z�E���p�{�݂̓d�C��̐ߖ���ʂ́A�N��3��600���h���Ɛ��肳���B �ψ���ɂ��ƁA���ݔ̔�����Ă���[�d��̑����͐V������Ă���B�ȃG�l���ʂ������[�d�@�\��������d�����u���V�̏ꍇ�A�w���ł͏]���^���40�Z���g�]�v�ɂ����邪�A�ϋv���Ԃ�ʂ����d�C���1.19�h���ߖ�ł���Ƃ����B �V��́A�ƒ�����̏[�d���Ώۂ�2013�N2��1������A�t�H�[�N���t�g�ȂǎY�ƌ����ɂ�2014�N1������A�o�[�R�[�h�ǎ摕�u�ȂǏ��p�����ɂ�2017�N1�����瓱�������B �d�r�œ������p�i���[�J�[�̋ƊE�c�̂́A���i�̏ȃG�l���i�Ƃ����ψ���̖ړI�ɂ͎^���������A�ȃG�l���ʂ̎��Z���ʂɂ͋^��������A�G�l���M�[�Ȃ��i�߂�S�Č����̏[�d��ȃG�l��̍����҂ׂ����Ƒi���Ă���B �o�T�uU.S. FrontLine�v |
|
|
| ���V�z�����ɏȃG�l��`�������{�A�f�M���\�̍��ې����ڎw�� ���{�͐V�z�̃r����Z��ɑ��A�����̒f�M���\�̍����ȂǂŋK�肷��ȃG�l���M�[��̓K�����`���Â�����j���ł߂��B �����̒f�M�������߂邱�Ƃŗ�g�[�̌������グ�A�d�C��K�X�Ȃǂ̃G�l���M�[�̎g�p�ʂ�}����̂��_���B���s�̏ȃG�l��̈����グ�ɂ��Ă���������B�`�����͌����̑傫���Ȃǂɉ����Ēi�K�I�ɐi�߁A2020�N�̑S�ʋ`������ڎw���B �V�z�̌����̂����ȃG�l��̓K�����́A�r���Ȃǂ�7�`8�����x�A�Z���3�`4�����x�ɂƂǂ܂�B�܂��A�����Z��̂Ȃ��ŏȃG�l������Z��̊�����5���ł����Ȃ��B�����ȏ�ł͒f�M�[�u���قƂ�ǂƂ��Ă��炸�A�����̉��x��ۂ��ɂ����Z������̂����B ���{�́A�V�z�̌����ɑ��ďȃG�l��������Ƃ��`���Â�����j�B�`�����͏��ʐς��L����������i�K�I�ɐi�߁A2020�N�ɂ͂��ׂĂ̐V�z�r����Z��ɏȃG�l��ւ̓K�������߂�B������ɏȃG�l���M�[�@�̉����Ă��o����̂ɂ��킹�āA��̓I�ȍH���\�m�����A�`�����Ɍ������@�����ɒ��肷��B ���B��؍��͂��łɏȃG�l��K�����`�������Ă��邤���A��̌����������{�̌��s������鐅���ɂ���B���{�͋`�����Ɗ�̈����グ���čs�����ƂŁA���ې����ɒǂ��������l�����B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���@�@[�@2012/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���I���b�N�X�d�͂̓d�͈ꊇ�w���A�d�C���̖��������K�̓}���V�����ł��T�[�r�X�� �d�͈ꊇ�w���T�[�r�X�́A�I���b�N�X�d�͂��A��ʉƒ낪�ʂɌ_����������P���̈��������d�͂�d�͉�Ђ���ꊇ��d���A�}���V���������ɒሳ�ɕψ����Ĕz�d������́B�Z���̓d�C���p�����̍팸���}���B ����܂Ŏ�ϓd�ݔ���ݒu����d�C������������}���V�����݂̂�ΏۂƂ��Ă���A80�˖����̓d�C����݂��Ă��Ȃ����K�̓}���V�����Ȃǂ́A��ϓd�ݔ��̐ݒu�ꏊ�m�ۂȂǂ̖�肩��T�[�r�X�̑ΏۊO�������B ����A�d�C����ݒu���Ă��Ȃ��}���V�����ɑ��ăL���[�r�N���Ƃ������O�ɐݒu�\�Ȏ�ϓd�ݔ����g�p���邱�ƂŃT�[�r�X�̓������\�ɂ����B�L���[�r�N���̓����́A�d�C�����ɐݒu�����ϓd�ݔ��Ɣ�ׂĐݔ��R�X�g����������̂́A���K�͕����ɑ��A�ėp���������ȃX�y�[�X�Őݒu���\�B ���Ђ́A���T�[�r�X�ɂ��d�C���p�����̍팸�ɉ����āA�ꊇ��d�V�X�e�������p�����z�����d�V�X�e����g�ݍ��킹���R�X�g�팸�ƏȃG�l���Ɏ�������T�[�r�X�ȂǁA�t�����l�̍����T�[�r�X�����Ă����B �o�T�u���X�|���X�v |
|
|
| �������ė��A��g�[�Ȃ��œK���ۂn���M����^�V�X�e���W�J �n���Ɏ��t�����p�C�v�Œn���M��������邱�ƂȂǂœK����ۂd�g�݁B����23�������ȑΏۂƂ��A���Ђ��肪����V�z�Z��̃I�v�V�����Ƃ��ēW�J���Ă����B�I�v�V�������i��50���~����B �n����4�J���A����������32���[�g���̉����r�j�[���������M����p�C�v��ݒu�B�������[�^�[��p���A�������ȂǂŎ�荞��C���p�C�v�����ړ�������B�p�C�v������n��4���[�g���t�߂̒n�����x�͔N�Ԃ�ʂ���17���O��ɕۂ���邽�߁A�M�����ɂ��A�K���ێ��ɂȂ���B �~��́A����ɕ��C�̎c�蓒�M�������A�~��20���O��A�Ă�26�`28���Ɏ�����ۂĂ�Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ����a�n�E�X�A���z���^�I�t�B�X��CO2�r�o��50����ڎw�����؎������J�n ���R�̗͂��������u�p�b�V�u�R���g���[���v�A�n�G�l�E�ȃG�l���s���u�A�N�e�B�u�R���g���[���v�A����ɂ�����K���ɐ��䂷��u�X�}�[�g�}�l�W�����g�v��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�]�����z�Ɣ�ׂ�CO2�r�o�ʂ��55%�팸�ł��鍂�������\������Ă���B ��̓I�ɂ́A�p�b�V�u�R���g���[���́A���Ԃ̑��z�����_�C���N�g�ɗ��p����u���_�N�g�v�A�����S�̂Ɍ���͂���̌��u���C���h�A�Ǝ��̈ێ��Ǘ��V�X�e����������ǖʗΉ��V�X�e���Ȃǂ��B�A�N�e�B�u�R���g���[���́A���ʔ����^�����A��Ɠx�ł����K�Ȗ��邳���m�ۂł���uLED�����Ɩ��v�A���������˔A9.84kW�̑��z�����d�V�X�e���A�K�Ȏ��x�Ɖ��x����������u�f�V�J���g�v�Ȃǂ����A�����I�ȑn�G�l�E�ȃG�l������������́B �����2�̃R���g���[���@�\�𐧌䂷��X�}�[�g�}�l�W�����g�́A�G�l���M�[���œK�ɐ��䂵�Č����鉻����uBEMS�v��u�l���E�����Z���T�[�v�̓����Ȃǂɂ��A����d�͂̃��_����������@�\���ʂ����B ���؎����ł́A�]�ƈ��������A�^�p���Ȃ���A1�N�Ԃ����Ċ��z���Z�p�̌��ʌ������{�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����K�X�ȂǁA�H�i�֘A�ƊE���������ȃo�C�I�K�X���V�X�e�����J�� �]���̃o�C�I�K�X���V�X�e����5t�`10t/���ȏ�̐H�i�p������r�o�����K�͎{�݂�ΏۂƂ��Ă���A10kg�`1t/�����x�̏��ʂ̐H�i�p������r�o���鏬�K�͐H�i�H�ꓙ�ւ̓�������������B ���V�X�e���́A10kg�`1t�̐����݂���0.7m3�`70m3/���̃o�C�I�K�X������B������ꂽ�o�C�I�K�X�́A�R���Ƃ��ăK�X�R�[�W�F�l���[�V�����V�X�e���A�K�X�{�C���[�A�K�X�z�����≷����ȂǑ��p�r�ŗ��p�ł���B ���؎����́A����23�N12���`����24�N6���܂Ŏ��{���A10kg/���̐����݂��������邱�Ƃɂ��A1��0.7m3�̃o�C�I�K�X������I�ɔ������邱�ƂȂǂ��m�F����\��B�������̌��ʂɂ��A���N�x�ɂ�100kg/�����x�̐����݂���������H�i�֘A���Ǝ҂̕~�n���ł̎��؎����s���ƂƂ��ɁA���^�o�C�I�K�X���V�X�e���̎��p�����������A����25�N�x�̏��i����ڎw���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��OM�\�[���[�����z���p�l���Ŕ��d�E�g�[ �����ɐݒu�������z���p�l���̉��ɋ�C���z������z�ǂ�t�����B���z�������������ۂɃp�l����������M��L�����p����B ���z�d�r�͒P�����^�C�v�ōő�o�͂�112W�B���d�V�X�e���S�̂̕ϊ�������12.8���B �p�l���ɕt�����z�Ǔ��̋�C�z�M�ʼn��߂�B���܂�����C�͋ݔ���ʂ��Ď����g�[�Ɋ��p����B�p�M���Ƃ��đ��z���G�l���M�[��22���𗘗p�ł���B���d�ƒg�[�����킹�āA���z���G�l���M�[��35%��L�����p�ł���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���d�t�A���͔��d�ʼn������ʃK�X�r�o�ʂ�30���팸�\ ���E���͉�c�iGWEC�j�́A���݂̐�������2020�N�̗\���Ɋ�Â��A���͔��d�Y�Ƃ͕��͔��d���R�y���n�[�Q�����ӂւ̐����70���܂ł��ǂ��������邩�������f�[�^�\�����Ɠ`�����B ���B���̓G�l���M�[����iEWEA�j�����\�����ŐV�̕��́A���͔��d�����ŁA���݂�EU�̍팸�ڕW�ŋ��߂��Ă��鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ�31���팸�ɂ����Ɋ�^���Ă����̂��������Ă���B ���B�ɂ����镗�͔��d�̑���ȍv���́AEU���������ʃK�X�r�o�ʂ̍팸�ڕW��20������30���Ɉ����グ�邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ������Ă���B ���͓��̍Đ��\�G�l���M�[�Z�p�́A���N�O�N���\�z�����Ȃ������قǑ傫�Ȗ�����S���Ă��邪�A��_���Y�f�r�o�ʂ̃M���b�v�߂邽�߂ɂق��ɂ��K�v�ȕ���𑣐i����ׂ��A�ӗ~�I�Ȕr�o�ʍ팸�ڕW���K�v�B�ŐV�́w���E�̃G�l���M�[�W�]�x�iWorld Energy Outlook�j�ō��ۃG�l���M�[�@�ցiIEA�j���w�E�����悤�ɁA5�N�Ԃŗ����ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ���A�Y�Ɗv���Ȍ�̋C���㏸��ێ�2�x�ȓ��ɗ}������u�Q�x�ڕW�v�ɂ́A�����㓞�B�ł��Ȃ����낤�B �o�T�u���g���V���v |
|
|
| ��CO2�r�o�ʂ͓��{�����E�Ń��[�X�g5�� ���A�C��ϓ��g�g�ݏ��E��17�����c�ł́A�������ʃK�X�r�o�ʂ̍��ʃ��[�X�g�����L���O�����\����āA���{�����[�X�g5�ʂƂ���Ă���B �Ȃ��A���[�X�g5�͒����A�č��A�C���h�A���V�A�A���{�̏��ŁA����5�����łȂ�ƑS���E�̔r�o�ʂ̔����ȏ���߂Ă���B �܂��̒��ł́A���N�͐��E�e�n�ŋɒ[�Ȉُ�C�ۂ�����ꂽ�N�ł��������Ƃ���Ă���B �@�Ⴆ�c �@�@�@�@�E���V�A�k���ł́A�t�̕��ϋC�������N����9�������Ȃ��� �@�@�@�@�E�t�B�������h�A�A�����J�A�����A�����J�A�X�y�C���ŋL�^�I�Ȗҏ� �@�@�@�@�E�䕗12���I�ɔ�����1800mm���z����L�^�I��J �@�Ȃ�30�N�Ɉ�x�N����悤�Ȉُ�C�ۂƌĂ����̂��������B �ُ�C�ۂ̌����́w���g���x�������̈���ƌ����Ă���B�ǂ̒��x���l�Ԃ̊����̉e���Ȃ̂��A�����ɋ�ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�w�n�����g���x���A�C����C������ω������A�C�ʂ��㏸�����A��J�������炵�A����ɂ��̋C��V�X�e���ɉe����^���邱�Ƃ͎����ŁA�l�Ԃ̊����ɂ���đ������������ʃK�X���w�ُ�C�ہx�ɔ��Ԃ������Ă���ƍl�����Ă���B �o�T�utenki.jp �v |
|
|
| ��COP17���A���{�͋��s�c�菑�̑����ԂɎQ������ ��A�t���J���a���_�[�o���ɂ����āACOP17�i�C��ϓ��g�g����17�����c�j�ACMP7�i���s�c�菑��7�����j�����s��ꂽ�B����̉�ł́A�����̘g�g�݂ւ̓��A���s�c�菑�����ԂɌ��������ӁA�̋C�����A�y�э�NCOP16�ō��ӂ��ꂽ�J���N�����ӂ̎��{�̂��߂̈�A�̌���A�Ƃ���4�̐��ʂ��B�Ȃ��A�����COP18�̓J�^�[�����z�X�g���A�h�[�n�ŊJ�Â���邱�ƂƂȂ����B ���{�́A�r�㍑�����߂Ă������s�c�菑�̑����Ԃɂ��ẮA�Q�����Ȃ��Ƃ̗�����т����B�܂��A���̍ő�̏œ_�ł�����2013�N�ȍ~�̘g�g�݂݂̍���ɂ��ẮA�V���ȍ�ƕ����ݒu���邱�ƂȂǂ̌��ݓI�Ȓ�Ă��s�����B ����̉�̐��ʂƂ��āA�����̘g�g�݂Ɋւ��ẮA�@�I�������쐬���邽�߂̐V�������ʍ�ƕ���𗧂��グ�A�x���Ƃ�2015�N���ɍ�Ƃ��I���A���Ӑ��ʂ�2020�N���甭�������A���{�Ɉڂ��Ƃ̓��ɍ��ӂ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����{�A16��̓d���ʔ��d�R�X�g�ŏI�����\�ߓd�R�X�g���Z�o ���d�R�X�g�́A2010�N��2030�N�̃��f���v�����g�ɂ�����1kW������̒P�����������B ���̃��X�N�Ή���p���܂߂��Z�o�ő��_�ƂȂ��Ă��������̔��d�R�X�g�́A2010�N���_�ŁA�Œ�8.9�~�Ō��������B2010�N���_�ł́A���q�́A�ΒY�ΉALNG�Η͂���9�`10�~�ŁA���z�����d�i���K�\�[���[�A�Z��j�͖�30�~�`45�~�O��Ɗ����ƂȂ����B���z�����d��2030�N���_�ł͖�10�`25�~�O��ƂȂ�Ǝ��Z�����B �ȃG�l���i�̍w����ȃG�l�̐ݔ��̓����ɂ���āA1kWh�̓d�͂�ߖ邱�Ƃ́A1kWh�̓d�͂d���邱�ƂƓ������ʂƈʒu�t���A�ȃG�l���i�A�ȃG�l�����̐ߓd�R�X�g�ɂ��Ă����Z�����B�ƒ땔��ł́A���M�d����LED�ɒu����������̂�0.0�`0.1�~�A�Ɩ�����ł́A�������̓�����8.9�`28.7�~�ƂȂ����B����p���������f�[�^��Z�莮����̃G�N�Z���V�[�g�����Ɛ헪���̃E�F�u�T�C�g��Ō��\�����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �������Q�S�N�x�\�Z�ďȃG�l���⎟���㎩���ԂȂNJg�[ �������ʃK�X�r�o�ʍ팸�ڕW�̒B���Ɍ����A�Z��̏ȃG�l���⎟���㎩���Ԃ̊J���Ɋւ���\�Z���g�[�����B�n�����g���h�~�Ɍ����������I�ȃG�l���M�[���p��ڎw���B ���{�͋��s�c�菑�ŁA����20�`24�N�̔r�o�ʂ�2�N��6������������ڕW��B32�N�ɓ�25���팸��B������ڕW���ێ������܂܂��B�����������d�͕�����P�������̌�A�S���̌����Œ��������̍ĉғ�������ƂȂ�A�ȃG�l�ɂ��r�o�ʍ팸�w�͂��s���ƂȂ��Ă���B 24�N�x�\�Z�Ăł́A����ǂ̒f�M�������߁A���z�����d�Ȃǂ̐ݔ���������Z��Ȃǂ̐��i���Ƃ�70���~��V�K�v�サ���B�d�C�����Ԃ�n�C�u���b�h�ԂɎg�p����鍂�������[�^�[�p�̎��̊J���ɂ�20���~��V���ɐ��荞�B �Η͔��d�ȂǂŔ��������_���Y�f���C���ɏo��O�ɉ������Z�p�iCCS�j�̎��؎�����J���Ɋւ���\�Z���O�N�x�����\�Z�̖�2.1�{�ɂ�����102���~�ɐςݑ������B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2012/1�@]�@�@�� |
|
|
| ��LIXIL�A�����̕ǂƏ��̎������Ɏ��t���邾���̏ȃG�l���t�H�[���H�@�̒�ĊJ�n ��ʓI�Ȍ���215mm�̒f�M�ނɑ������鐫�\��������12mm�̐^��f�M�ނ�f�M�p�l���Ɏg�p���A�����̕ǂ⏰�̏�ɐݒu���A�g�[�����Ă��������g�܂�Ȃ�������A�Ă̐����������G�A�R���̌����������Ƃ�����������������B �f�M�p�l�����������Ƃ���A�ǁA���̎������Ɏ��t���Ă������������Ȃ邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ������A�ǎ���t���[�����O���V�����Ȃ邱�Ƃŕ����̔����������シ��B��̍H���̕K�v���Ȃ�������{�H�̂��ߍH�����Z���A�ʏ�ʂ��炵�Ȃ���1�������ƂɃ��t�H�[���ł���B �]���̈�ʓI�Ȓf�M���t�H�[���Ɣ�ׂ�ƁA�]���@���ƑS�̂ōH����1�`2�����A��p����1,000���~�Ȃ̂ɑ��A�K�v�ȕ��������ł��A�H����1����3���`1�T�ԁA��p��1��10���`15���~(6��Ŗ�60���`90���~)�ƂȂ�B�����ł͓~�̎����̏㉺���x����7������3���ȓ��ɉ��P����A�~�̒�₦���ɘa�����B�ؑ��Z��ƓS�R���N���[�g�̏W���Z���Ώۂɂ���B �o�T�u�u���oBP�v |
|
|
| ���Z��̔R��\���u�G�l���M�[�p�X�v���{�ł����t�n�� �G�l���M�[�p�X�Ƃ́A�����̔R��\��\�����鐧�x�B�Z��w������������ۂɔN�Ԃ̌��M����܂߂��g�[�^���R�X�g�Ŕ�r�ł��邽�߁A�Z��̏ȃG�l�𑣐i������ʂ����҂����B���ʐ�1�������[�g��������̕K�v�G�l���M�[(�g�[�A��[�A���C�A����)�Ȃǂ��^�R���[�^�[�����ŕ\������B �G�l�p�X�쐬�̌v�Z�c�[���́A���C(�L��)�̎�u�������Ƃ��������Ŗ�������\��B������̓G�l�p�X�̎擾�҂ɂ��āA�u���z�E�v��������Z��֘A���[�J�[�̏]���҂����S�ɂȂ邾�낤�v�Ƃ̌����������������ŁA�u�R���T���e�B���O�\�͂����߂������ʎ��Ǝ҂̎��v��������ł���v�Ƃ���B http://energy-pass.jp/ �o�T�u�Z��V��v |
|
|
| �����c���쏊���d���̂���Ȃ��X�C�b�`������p���Ɍ������؊J�n �O���d���̗v��Ȃ��Ɩ�����p�����X�C�b�`�V�X�e���́A�l���X�C�b�`���������͂�d�͂ɕϊ����A���̔����d�͂�p���Ė����M���𑗐M������́B����A�����d�ˁA2012�N������ʎY���J�n����v��B ��d�C�A���r���Ȃǂ̐ݔ����R���s���[�^�[�ő����I�ɊǗ�����u�r���I�[�g���[�V�����v�Ȃǂ̕���ŁA�����̔z�����s�v�Ȗ����ɂ��Ɩ�����̎��v�̑����ɑΉ����邽�߁A���Ђ̍����g��H�v�Z�p��\�t�g�E�G�A�J���Z�p�Ȃǂ����A�U���Ȃǐg�߂ȃG�l���M�[��d�͂ɕς���u�G�l���M�[�E�n�[�x�X�e�B���O�v�ƌĂԖ����Z�p��p�������i�����p�����邱�Ƃɂ����B ���V�X�e�������p�������ƁA�X�C�b�`���ɓd�r��O���d������̓d�͋������s�v�ɂȂ邾���łȂ��A�����z�����s�v�ɂȂ�Ƃ��������_�̂ق��A��Q���̂Ȃ���Ԃ�200�`300���[�g���̒ʐM���\�ɂȂ�Ƃ��Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���O�H�n�����W�f���X���}���V���������̑��z�M���p�����V�X�e�����J�� �O�H�n�����W�f���X�ƃ��b�Neco���C�t���J�������A���z�M���p�^�̋����V�X�e�������̂قǁA�����s�����{����u�V�z�Z��ւ̑��z�M�V�Z�p����Ď��Ɓv�ɍ̑����ꂽ�B �}���V�����̉���Ȃǂɑ��z�M�W�M���ݒu���ĉ��������A���M����^������(�G�R�W���[�Y)�Ƒg�ݍ��킹�ăK�X����ʋy��CO2�r�o�ʂ����炷�d�g�݁B ���z�M�̗��p�͌ˌ��ďZ����S���������A(1)�S�˂̐��������ꊇ�w���A(2)�W�M��̓��b�Neco���C�t�����L�A������̓��[�X�����A�Ƃ��邱�Ƃœ������̋��Z�ҕ��S���y�����A�}���V�����ł̗̍p��e�Ղɂ����B9�K����32�˂̃}���V������z�肵���ꍇ�A�����ɗ��p����M���̖�20���z�M�Řd�����Ƃ��ł���ق��A�K�X����ʂ�12�`15���ACO2�r�o�ʂ�N��5,843kg�팸�ł���Ƃ����B�܂��W�M����̉����́A�ЊQ���ɐ����p���Ƃ��Ă̗��p���\�B �o�T�uAsahi.com�v |
|
|
| ���l�M�V���C�̗]�M���p�A�~�M�}�b�g�̔� �~�M�ނɊւ��錤���J�����т�y��ɁA�M�����ߍ��ށu�|�_�i�g���E���v�����p���Ē~�M�}�b�g�i�������B�}�b�g�̑傫���͒���630mm�A��250mm�B�_�炩���V�[�g��̂��ߕz�c����Ȃɕ~���₷���B7245�~�B �Ⴆ�A41�`42�x�̓����͂��������Ƀ}�b�g���35�`40���ԕ����ׂĕ��C��̗]�M���z�����A����������o�����}�b�g�̓���@�����A�z�c�̒��ɓ����B����ƁA�̉��i��37���j���1�`2�x�������x���Ԏ����ł���B �S�n�悢�g������ۂ��߁A�c���⍂��҂����S���Ďg����B����Ƀ}�b�g�͓d�C��K�X�𗘗p�����ɉ��߂��邽�߁A�ߓd�ɂ��L���Ƃ����B �������������ގԓ��Œ~�M�����}�b�g���^�]�Ȃ̒g�[�p�V�[�g�Ƃ��Ē�Ă���ȂǁA�p�r�J��ɂ��͂�����B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���ȃG�l�@���{�������A�s�[�N�d�͂�}���E�E�E�o�Y�� ���Ă̓d�͕s�������P�ɁA����܂ł̏ȃG�l�@�ł͑Ή����Ă��Ȃ������s�[�N���̍ő�g�p�d�̗͂}����}��B���N�̒ʏ퍑��ɂ��ȃG�l�@�����Ă̒�o��ڎw���B�u�s�[�N�J�b�g�i�ő�g�p�d�͂̍팸�j�������ɍs�������|�C���g�ɂȂ�v�Ƌ��������B 1970�N��̐Ζ��V���b�N�����������ɐ��肳�ꂽ���s�@�́A�N�Ԃ̃G�l���M�[�g�p�ʂ����炷�̂��ړI�B�������A�d�͂��s���������ẮA�G�A�R�����t���ғ�����s�[�N���̍ő�g�p�d�͂̍팸�̂��ߊ�Ƃ�ƒ�ɑ啝�Ȑߓd�����߂���Ȃ������B ��̓I�ɂ́A���z���p�l����~�d�r�A���Ɣ��d���u�Ȃǂ������Ƃ�ϋɓI�ɕ]�����鐧�x����������B�d�͉�Ђɑ��ẮA�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͌v�j�̕��y�Ȃǂ̑�����߂�B�ƒ�Ńs�[�N���̎g�p�d�͂��c���ł��A�G�A�R���Ȃǂ̌����I�ȗ��p�ɂȂ���ق��A���z���p�l���̓������i���}��₷���Ȃ邽�߂��B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����g�����ŁA2012�N�x������ �| ���{�Œ� ���{�Ő�������́A�S�̉���J��2012�N�x������Łi�n�����g�����Łj��������j�����߂��B2012�N�x�̐Ő�������j�ɐ��荞�ށB ���ł͐Ζ��ΒY�ł������A�ߑւ���������́B�����͌��܂��Ă������̂�2011�N�x�͐k�Ќ�ɗ������ތi�C�Ȃǂւ̔z�����猩����ꂽ�B���ł�2011�N�H�ɓ������A3�N�������Ēi�K�I�ɐŗ��������グ����j�������B �K�\�����̏ꍇ�ɂ́A���Ŋz�͏��N�x��1���b�g��������0.25�~�A���S���{���_��0.75�~�ɂȂ錩���݁B�Ŏ��͊��ȁA�o�Y�Ȃ��ȃG�l��Ɏg���\�肾�B�_���Ȃ͐X�ё�ւ̔z�������߂Ă���A����͐��{���Œ�����i�߂�B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| �������R�X�g�͉Η͔��d���݂Ǝ��Z�c���{���؈� ���{�̃G�l���M�[�E����c�œd�����Ƃ̔��d�R�X�g���v�Z���Ă��錟�؈ψ���́A�����̎��̔�p��1kWh������0.5�~�ȏ�Ƃ��鎎�Z�����\�����B���n���i�̕⏕���Ȃǂ�������ƁA�����̃R�X�g�͓�10�~���x�ƂȂ�A���s���{���Z��5�`6�~����㏸�A�Η͔��d���݂ɂȂ錩�ʂ����B �����̎��̃R�X�g�ɂ��Ă͓��t�{���q�͈ψ��11���A�����d�͕�����1�������̋��̔����m���ɉ�����0.006�`1.6�~�Ǝ��Z�B�ő�P�[�X�ł͌���1��ɂ�500�N�ɂP�x�A�d�厖�̂���������O��Ō��ς������B ���؈ς͂�����Č������A���̊m�����u������40�N��1�x�v�i����1��ɂ���2000�N��1�x�j�Ɛݒ�B�����������̂̐��v�����Ƃ�1�x�̎��̂�5.7���~�̔�p��������ƌ��Ȃ��Ď��Z�����B�����A��p���v�ɂ͒��ԏ����{�݂Ȃǂ̐�����܂܂�Ă��炸�A���̔�p��1���~������A���d�R�X�g��0.09�~��ς݂����B���؈ς͎���̉�ŁA�e�d���̃R�X�g�v�Z���ʂ������j���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ��IEA�A�C��ϓ���ً̋}���������A5�N�ȓ��̌��I�Ȑ����]�����K�v 2011�N�ł́w���E�G�l���M�[�W�]�iWorld Energy Outlook�j�x�\���A���E���ϋC���̏㏸��2�x�ȓ��ɗ}���邽�߂̓����������B �u2�x�v�͒n�����g���ɂ��Ō�������邽�߂ɑ����̍������ӂ������l�ڕW�ł���B���d����r���A�H��Ȃǐ��E�e���̃C���t���ݔ��́A���ΔR������ȃG�l���M�[���Ƃ��Ă���B��v�������ʃK�X�ł���CO2�r�o�̑����͉��ΔR���̔R�Ă��������B ���݂��ꂽ�C���t���́A�V��������܂ʼnғ���������B���̂��߁A���\�N�Ԃ�CO2�r�o�����u���b�N�C���v�i�Œ艻�j������IEA�͎w�E����B�܂�A�����E�v�撆�̃C���t�������킹��ƁA���㐔�\�N�Ԃ̔r�o���e�g��80�������ɖ��܂��Ă���B �]���̃y�[�X�ŃC���t�����݂≻�ΔR������i�߂A5�N��ɂ͔r�o���e�g�̎c�肷�ׂĂ����b�N�C������A2017�N�ȍ~��CO2�r�o�ʂ��[���łȂ�����C���t����V�݂ł��Ȃ��Ȃ�B �ڕW�B���ɂ́A����V������������G�l���M�[���̔����ȏ���A���z�����d�╗�͔��d�Ȃǂ̍Đ��\�G�l���M�[�ɕϊ�����K�v�������IEA�͗\������B�Đ��\�G�l���M�[�̐v���ȕ��y�ɂ́A���z�̕⏕���������K�{�ƂȂ�A2035�N�܂łɔN�ԓ����z�͌��݂̖�4�{�A2,500���h���i��19���~�j�ɒB���錩���݂��B �o�T�uNational Geographic News�v |
|
|
| �����E��CO2�r�o�ő��2010�N334���g���O�N��5.9���� ���n�������Ȃǂ̍��ۋ��͑g�D�u�O���[�o���J�[�{���v���W�F�N�g�v�����A���ƂȂǂ̌��\�f�[�^����r�o�ʂ��Z�o�����B���E�S�̂̔r�o�ʂ́A2009�N�A2008�N�̃��[�}���V���b�N�ɂ��o�ϊ������ނ̉e���őO�N��1.4���������Ă����B�������A2010�N�́A���Ă𒆐S�Ƃ�����i���ŁA�o�ς̕����ɍ��킹��3.4�����B���Z��@�ł��������݂������Ȃ����������Ȃǂ̓r�㍑�ł�7.6���̐L�т������A�S�̂�5.9�����ɂȂ����B ��C����CO2�Z�x��2010�N����389.6ppm�ƂȂ�A�O�N����2.4��ppm�����ĉߋ��ō��������B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA��Ƃւ̐ߓd�v�����Ɏ��Ɣ��̗]��d�͂��A�ߓd���ɂ��J�E���g �o�ώY�ƏȂ́A�ߓd�v�����ɂ������Ɠ��̎��Ɣ��d�ݔ��̊��p�g���\�����B���l�ڕW���ߓd�v�����ɁA�ߓd�̎�g�̑I�������g�債�A��Ƃ̐��Y�������ւ̉e�����ɗ͗}���邪�_���B ���~�́A���{��10���ȏ�̐ߓd��v�����Ă�����d�͊Ǔ��A5���ȏ�̐ߓd��v�����Ă����B�d�͊Ǔ��Ȃǂ��ΏۂƂȂ�B ��̓I�ɂ́A���l�ڕW�t�̐ߓd�v��������Ɠ����A���Ɣ��d�ݔ������p���Đߓd�ڕW��B���������ƍl����ꍇ�A���Ɣ��d�̗]��d�͂�d�͉�Ђɔ�������Ă��炦��ƂƂ��ɁA����蕪��ߓd�ڕW�B���̂��߂ɃJ�E���g���邱�Ɓi�ߓd�݂Ȃ��j���ł���悤�ɂ�����́B�ߓd�v�����s���Ă��Ȃ��ʂ̓d�͉�ЊǓ��ɂ���A���Ђ�q��Г��̎��Ɣ��d�ݔ����ΏۂƂ���B ���Ɣ��d�̗]��d�͂̔����ɂ��ẮA��Ɠ����ߓd�v�����s���Ă���d�͉�ЂɈ˗��B���承�i�́A�������i������������ɗv����R�X�g�������T������������ڈ��ɁA�����ҊԂ̋��c�ɂ���Č��肷��B�܂��A���̓d�͉�ЊǓ��ɂ��鎩�Ɣ��d�ݔ������p����ꍇ�́A���s�U�������[������јA�n�����p���[���͈͓̔��ł̑Ή���O��Ƃ��A�U�����ɔ����⋋�d�͂ɂ��ẮA�����Ƃ��Ĕ����葤�d�͉�Ђ̕��S�Ƃ���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/12�@]�@�@�� |
|
|
| �����}�_�d�@�A���z�����d�V�X�e���̎{�H���C�A���i�擾�̂��߂̎{�݂��J�Z ���}�_�d�@�O���[�v�̃X�}�[�g�n�E�X�r�W�l�X�ɂ�����n���������g�݂̈�Ƃ��čs������̂ŁA���z�����d�V�X�e���{�H�Ɋւ���m���A�Z�p�A�e���[�J�[�̎{�H�F��ID ���擾�ł��錤�C�{�݁B �����́A�܂��A���z�����d�r�W�l�X�V�K�Q���҂ɂ�������₷���J���L�������\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���������B��b�m����Z�p�擾�̂��߂̍��w�A���n�ɂ�錤�C�ɉ����āA�ߋ��̎{�H�����{�H�i���Ǘ��̃|�C���g���w�Ԃ��Ƃ��ł���B�܂��A�T���e�b�N�A�V���[�v�A���ŁA�q�����_�C�A�O�H���̑��z�����d�V�X�e��7�Ѓ��[�J�[�̎{�HID���Ɏ擾�ł��錤�C�����{�B ����ɁA���C�C�����ւ̃T�|�[�g���s������A���N�x�ɂ́A���z�����d�̔̔��c�Ƃ̌��C���s���\��B2012�N�ȍ~�A�����A���C�{�݂̊g���}��Ƃ����B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���o���~���[�_����g�[���K���I�O���[���t�@���E�T�[�L������ �o���~���[�_�Ǝ��̓�d�\���̉H���u�O���[���t�@���e�N�m���W�[�v���̗p�B���̉H���ƕ��̒��i�������߂�t�@���K�[�h�ɂ���āA��ʓI�ȃT�[�L�����[�^�[�Ƃ͈قȂ鎿�̕����������A15m��̋�C�����������|�I�ȑ������\�����B ���ʐ�ւ���4�i�K�B1��30��܂ł̕����ɑΉ�����̂ŁA�I�t�B�X�ł��\���Ɏg�p�ł���B �ŏ�����d�͂́ADC�u���V���X�E�f�W�^�����[�^�[���ڂɂ��A�킸��3W�B�ő啗�ʂ̏ꍇ�ł�20W�ƁA��ʓI�ȃT�[�L�����[�^�[�̏���d�́i��20�`40W/���В��ׁj��舳�|�I�ɒႢ�B���i��1��9800�~�B �o�T�unikkei TRENDYnet �v |
|
|
| ���V���S�G���W�A�ΒY��֔R���̃o�C�I�R�[�N�X�ʎY�� 2013�N�t����}���[�V�A�Ő��Y���J�n���A�����͔N��3000�g���Y���A�����I�ɂ�1���g�����ɂ܂ň����グ��B�o�C�I�R�[�N�X��CO2�팸���ʂɉ����A�ߔN���i���㏸�X���ɂ���ΒY�̎g�p�}���ɂȂ�����̂Ƃ��ĕ��y�������܂�Ă���B �o�C�I�R�[�N�X�͌���ł͐ΒY�ɔ�ׂĊ��������A�ʎY���邱�Ƃʼn��i������������B�V���S�G���W�ł́A�����̃S�~�ċp��̃K�X���n�Z�F�̔R���Ƃ��Ĕ��荞�݂�}��l���B �p�[�����Y����ߒ��Ŕ������郄�V�k�́A�}���[�V�A�����ŔN��350��?400���g���Ƒ�ʔ������Ă���A�L�����p���ۑ�ƂȂ��Ă����B �o�C�I�R�[�N�X�̓��V�k�����M�A�������Đ��Y������̂ŁA���M�ʂ�M�ԋ��x�Ȃǂ͐ΒY�Ƃقړ������\�����B �o�T�ugreen plus�v |
|
|
| ���V����T�[�r�X���C���M���p�̐V�^�╗�@�� ���u�����̃^���N�̐����|���v�ŋz���グ�A�ԏ�̕��ނɎU������B�z���������荞�����̋�C���Ԃ�ʉߎ��ɐ����ɐڐG�B�C���M�ŗ�₵����A�����ɐ����o���d�g�݁B ���Z�ł͏]���̃G�A�R����10��̎�����26���ɕۂ��߂�2200�`2600Wh�̓d�͂��K�v�����A�V�^�╗�@�ł�300Wh�ɗ}���ł����B �d�ʂ�55kg�B�g�[�@�\�͂Ȃ����A�~�G�͉�����Ƃ��Ďg����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��JFE�G���W�j�A�����O�A�R���r�j�X�܂ɒn���M���p��������؎��Ǝ��{ ��������n���M���p�V�X�e���́A���x��17���̒n���ɓ��ꂽ�|�ǍY�ɏz����s���t�𗬂��Ēn���M�����o���A�q�[�g�|���v��ʂ��ċɎg���d�g�݁B�̏���d�͂�CO2�r�o�ʂ��A�]���Ɣ�ׂĖ�30���팸�ł���B ���ł́A�n�����瓾����M�ʂ̊ȈՓI�Ȍv�����@���m������ق��A�M�����o���ǂɌ������x����|�ǍY�����p�����R�X�g�^�ݔ��̓K�����ƗL������������B �����āA���R�G�l���M�[�ł���ꂽ�M�����ȃG�l�E��CO2�̊��t�����l�����؏��ɂ��A�s��Ŏ���ł���悤�ɂ����u�O���[���M�؏��v�̊��p�Ɋւ��āA�擾�̌o�ϐ���������B ���~�J�X�\��̃Z�u��-�C���u���E�W���p���̊֓��A���A��B�n��̌v3�X�܂�ΏۂɓW�J����B �o�T�uECO JAPAN �v |
|
|
| �������H�Ƃ��X�[�p�[����ESCO��S���W�J �①�E�Ⓚ�V���[�P�[�X�Ȃǂ�����X�[�p�[�ɓd�͍팸�Ȃǂ����点��œK�ȉ^�p���@���Ă��A�d�C��ȂǃG�l���M�[��̐ߌ��������V��ȃG�l���M�[�x���T�[�r�X��W�J����B �ڋq�͐ݔ������̏�����p��}�����A�ߓd���Ȃ���ʏ�ʂ�c�Ƃł���B�ȃG�l�x���̐ߓd�ڕW��25���ȏ�ɐݒ�B�ڋq�����������ݔ��̉^�p�E�Ǘ����H�Ƃ���|����B�]�����ߓd�ł����G�l���M�[��̈ꕔ�𐬌���V�Ƃ��Ď��B�ݔ��̓d�͎g�p���Z���T�[�ŊĎ����A���x�Ȃǂ�������������V�X�e�������p����B �d�͎g�p��24���ԊĎ����A�ڋq���ł��ߓd���ʂȂǂ̃f�[�^�𒀎��m�F�ł���B�ݔ��̃��[�X���Ԃ�7�`8�N��z��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ȃG�l�A�s�[�N�}���Ɏ����o�Y�Ȃ��K�������� �ȃG�l�K���{�I�Ɍ������B�H���X�܂̃G�l���M�[���g�p�ʂɏœ_�����ĂČ������P�����߂Ă������A����̓s�[�N���̎g�p�ʗ}���Ɏ������ڂ��B �d�͕s���̒��������ɂ�݁A���Ɣ��d��~�d�r�Ȃǂ̊��p�𑣂��_���B�ƒ�̃G�l���M�[�����}���邽�߁A�V���ɏZ��ނɏȃG�l�K������������B���N�̏ȃG�l�@�������߂����B 11����{�ɑ��������G�l���M�[������i�o�Y���̎���@�ցj�ȃG�l����ŋc�_���n�߂�B���N�̒ʏ퍑��ɏȃG�l�@�̉����@�Ă��o��������Ō������Ă���B �@�����̂�����̒����ƒ��I�t�B�X�Ȃǖ�������̏ȃG�l�����B�f�M�ށA���A�����Ȃǂ̌��ނ��u�g�b�v�����i�[���x�v�̑ΏۂɊ܂߂邱�Ƃ���������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���G�l���M�[����c�A�X�}�[�g���[�^�[�����u�����ȏ�T�N�Łv �d�͕s�������Ɍ������u�G�l���M�[��������s���v��v�̈�ŁA�d��9�Ђ̑��ςݏグ���A�N�V�����v���������肵���B ���v��̒��ƂȂ�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j�́A�u����5�N�Ԃō����ȏ�̃��[�^�[�̃X�}�[�g�����قڊ�������v�Ɩ��L�B �ሳ���܂߂����v�ƑS�͓̂����A�����A����3�Ђ�5�N���8���̓�����B���A�c��6�Ђł�6�`7���œ����������܂��Ƃ��Ă���B�A�N�V�����v�����͓d�͂X�Ђւ̃q�A�����O�ɂ��ƂÂ��A���v��A������A�R�X�g�A�b�v�}�����3����Ŋe�Ђ̑���܂Ƃ߂����́B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���d�t�A���s�c�菑��������Ē���̎Q���ȂǏ��� ���B�A���i�d�t�j��10���J��������������ŁA�������ʃK�X�팸���i���ɋ`���Â����u���s�c�菑�v�̊��������2013�N�ȍ~�ɂ��āA�����t���œ��c�菑�̉���������邱�Ƃō��ӂ����������B �č��⒆���A�C���h�Ȃǎ�v�r�o�����팸�ڕW�̘g�g�݂ɎQ�����邱�Ƃ�A���c�菑�Ō��߂��r�o�ʎ���Ȃǂ̎�Ȏ��g�݂��ێ��E���W�����邱�ƂȂǂ������̏����ɋ������B �c�菑�����͓r�㍑���x�����Ă���̂ɑ��A���{�A���V�A�A�J�i�_�������Ă���B�d�t�̒�Ă͑o���̕��݊��𑣂��A13�N�ȍ~�ɍ��ۓI�ɍS���͂̂���@�I���ӂ��Ȃ��Ȃ�u���ԁv���������_��������B �d�t����27�J���́A�����̎�]��c�ŕ��j�𐳎��Ɍ��߁A11�����{�̓�A�t���J�ł̍��A�C��ϓ��g�g�ݏ�����c�iCOP17�j�ɗՂޕ��j�B �o�T�ugreen plus �v |
|
|
| ��CO2�A1�g��1���~�Ŕ����܂��B��ʉƒ���ΏہA���s�s�̃N���W�b�g���x ���s�s���uDO YOU KYOTO�H �N���W�b�g���x�v�𗧂��グ���B�������Ǝ҂��ȃG�l�Ɏ��g�ꍇ�ACO2�팸�����N���W�b�g�i�F�ؔr�o�g�j�Ƃ��Č�t���A�s��1�g��������1���~�Ŕ������Ƃ����d�g�݂��B ����́A�ȃG�l���o�ω��l������_�Ő��{�����{���Ă��鍑���N���W�b�g���x�Ⓦ���s�̓s�������N���W�b�g���x�ƍl�����͓��������A���{�I�ɈقȂ�_������B ���{��s�̐��x�ł́A�������̋�{�C���[�ݔ��A���߂��ݔ��̓��������i�u���@�_�v�Ƃ����j�������ꍇ�ɂ����A�N���W�b�g�͐��܂�Ȃ��B����ɑ��A���s�s�̐��x�ł͐V���Ȑݔ�������Ȃ��u�^�p���P�v�ɂ��CO2�팸���N���W�b�g�ɂȂ�B�����Ĉ�ʉƒ���ΏۂɂȂ�̂��傫�ȈႢ���B ���s�s�́ACO2�팸�ʂ�d�C��K�X�g�p�ʂ̑O�N�����Ɣ�r��������������N���W�b�g�����Z����B �����A���������P���ȑO�N�Δ�ł́A�q�����A�E�⌋���œƗ����A�Ƒ��\�����ς�����ꍇ�ȂǁA�{���̈Ӗ��ł̏ȃG�l�w�͂�Ȃ��팸�ʂ��܂܂�鋰�ꂪ����B �o�T�u���oBP�N���[���e�b�N�������v |
|
|
| ���������{�A�G�l���M�[����ʂ̒n�����������{�� �߂������A�G�l���M�[����ʂɂ��āA�n�����Ƃ̊����������{����B���ƃG�l���M�[�ǔ��W�K��i�̘b�Ƃ��āA�V�؎Ђ��`�����B���E�ő�̉������ʃK�X�r�o���Ƃ��āA�g�傷����v�ɏ����݂��邱�Ƃ��ړI�B ��̓I�Ȋ����ʂ͌��\����Ă��Ȃ����A�������{�����i��}�鐅�͂╗�́A���z���Ƃ������Đ��\�G�l���M�[�͊������̑ΏۊO�ƂȂ錩���݁B �k���ŊJ���ꂽ�t�H�[�����ŁA�������̊T�v���Љ�B���x�̎��{�ɂ͍����@�̏��F���K�v�ɂȂ�Ƃ��Ă���B �o�T�u���C�^�[�v |
|
|
| ��������Ƃ̐ߓd���800���~���{�A�ȃG�l�ݔ��������� �o�ώY�ƏȂ�3����Ɨ��N�x�\�Z�ŗv�����Ă���G�l���M�[�֘A�\�Z�ŁA�Đ��\�G�l���M�[�̊��p�ƕ���Œ��ƂȂ�̂��ߓd�B 3����ł́A�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͌v�j�ƘA�g���A�d�͎��v�}����}��u�G�l���M�[�Ǘ��V�X�e���iBEMS�j�v�̓����x����̐V�݁i300���~�j���f����B �s�[�N���̎g�p�d�͂��O�N��15���팸�����A���{���Вc�@�l�Ȃǂ�ʂ��Ĕ�p�̂R���̂P��⏕����Ƃ������e�B BEMS�͋Ɩ��p�r����H��Ȃǂ̃G�l���M�[�ݔ��S�̂̏ȃG�l���Ď����A�����I�Ɏg�p�G�l���M�[�𐧌䂷��V�X�e���B�H����̓d�͎��v���ꌳ�I�ɔc�����A���v�\���Ɋ�Â��^�]���\�ŁA�����S�̂̃G�l���M�[������ŏ����ł���B����Ƃł̓����͐i�ނ��A������Ƃ͂��ꂩ�炾�B ���N�x�\�Z�ł́A�ȃG�l�����̊������x�����346���~��v������B������Ƃ̐V���ȓ����v������債�A�ȃG�l���ʂ̍������Ƃ��x������B ���N�x��230�Ђɑ�100���`50���~���x�̕⏕������t�B���N�x��LED�Ɩ��̓�����{�C���[�������Ȃǁu�ߓd�v���d�_�I�ɐR������̂��������B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���u�d�͕s����Ƃ̈ꏕ�Ɂv�_�|�������M���̊ȈՌ^���d���u������ �o�C�i���[���d���u�́A�H�ꂩ��r�o���ꂽ������A���Ȃǂ𗘗p���A���������_�̒Ⴂ��փt���������������A���̏��C�Ń^�[�r������]�����A���d����d�g�݁B �ő�o��70kW�B��225cm�A���s��260cm�A����225cm�A�d��6,500kg�B���E�L���̈��k�@�A�Ⓚ�@�̋Z�p���x�[�X�ɊJ�������^�[�r�����g���A�������Ȕ��d���\�����������B�{�̉��i��2,500���~�̗\��B �_�ː��|���́A130���ȉ��̏��C��M���Ƃ���o�C�i���[���d�V�X�e���̊J���ɂ����肵�Ă���A���N�H�̔̔���ڎw���B�d�͕s���ɔY�ފ�Ƃ≷��{�݂Ȃǂւ̔̔���ڎw���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ��LED�Ɩ����y�ɂ�� �d��10�Ђ��d�C�����ɏȃG�l�敪�\�� LED�i�����_�C�I�[�h�j�Ɩ���L�@EL�i�G���N�g���E���~�l�b�Z���X�j�Ɩ��ȂǏȃG�l�^�Ɩ��̕��y���ɂ�݁A10kW�܂ł̓d���ɑΉ�����V���ȓd�C�����敪������Ɣ��\�����B �����t�Ōo�ώY�Ƒ��ɔF��\���A�\�����F�߂����12��1��������{����B �V�敪������̂́A��Ƃ̊Ŕ��Ȃǂ�ΏۂƂ���u��z�d���v�ƁA�����̂̊X�H����M���Ȃǂ́u���O�X�H��A�v�ŁA��������]���敪���ו������Đ݂���B�K�p����ɂ͌_��ύX�Ȃǂ̎葱�����K�v�ƂȂ�B�d�C�����͏]���敪�ɔ�ׂČ��z30�`40�~���x�Ⴍ�}������\��������B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���A�C���X�I�[���}�͔�������100lm/W�̒ቿ�i���nj`LED�� ECOLUX HE�́A�u�����Ɠ����`��̒��nj`�^�C�v��LED�ŁA100lm/W�̍������������ƁA2000lm��12,500�~�Ƃ����ቿ�i�����������B ECOLUX�Z���T�[�́A�l���Z���T�[�tLED�d���̐i���`���i�ŁA���̖͂��邳���Z���T�[�����m���Ď����I�ɒ����ł���B 40�`�̃����v������3300lm�A2500lm�A2000lm�A1500lm��4�o�[�W�����B�F���x�A���F�����ɂ��o���G�[�V�����������A�����F�Ɣ��F��2��ނ���I�ׂ�B���nj`2�{�Z�b�g�ł��ꂼ��ʂɖ��邳���R���g���[���ł���̂������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�������x�������Ă��d�͏�����v�U�T�� �����{��k�Д������甼�N���T���A�S�����_������ʐڕ����ōs�����B �����d�͕�����P�������̂��A�d�͋��������̂������q�˂��Ƃ���A�u�������x�͒Ⴍ�Ȃ��Ă��d�͏�������Ȃ����ׂ����v��65���ɏ��A�u�������x���ێ����邽�߂ɓd�͋����𑝂₷�ׂ����v��32�����������B ����̓��{�̌����ɂ��Ắu�댯���̍������̂���^�]���~���A�������������炷�v��60���ƍł������A�i�K�I�Ȍ����팸�u��������������B �u�������x�͒Ⴍ�Ȃ��Ă��d�͏�������Ȃ����ׂ����v�Ɖ����l�𐫕ʂł݂�ƁA�j��60���A����70���B�N��ʂł͎�N�w�̍������ڗ����A30���71���A20���67���Ƒ������B�������x���d�͏���̌�������D�悷��l�̂����A�����ɂ��āu�������������炷�v�Ɠ������l��66�����߂��B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���������D�̓V���R���I�C�������p�����p�M���d�ݔ����J���J�n ���S���Ȃǂœ�������Ă���p�M���d�́A��������p�M���g���ă{�C���[�Ő����C�����̂���ʓI�ŁA�e�ʂ�����kW�ȏ�Ƒ�^�B�J���@���300�`1000kW�A250�`400���̔p�M�𗘗p����B �V���R���I�C�����g�����ƂŁA��葽���̏��C������ꔭ�d������3�`4�����������}��A18�`19�����x�̎��d��ڎw���B�ݔ����i��1kW������40���~���x�ƂȂ錩�ʂ��B �����p�p�M��2020�N���_�ŁA�ő�3���e���W���[���O��ŁA�d�͂Ɋ��Z����ƁA����1��̔N�Ԕ��d�ʂɕC�G����K�͂��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �I�������A���Ə����e�G���A�̃s�[�N�d�͂������ɗ\���E�Ď����鑕�u������ ���ẮA���Ɣ��d�̉ғ���H��̗֔ԑ��ƁA���Y�̃V�t�g�ȂǂŐߓd���s���P�[�X�����������B�����������������@�͋Ɩ����S���傫���A��p�������邱�Ƃ���A400�Ђ�15���팸��B���ł��Ȃ����Ə����������B���Ăɑ����A���~�◈�Ă��d�͕s�����\�z����邱�Ƃ��A�}���`�s�[�N�d�͊Ď����u���J�������B �e�G���A��1���̃s�[�N�d�͂̐��ڂ��Г�LAN��ʂ��ĕ\�����A���ꂼ��̏����L�ł���B �s�[�N�d�͂������ȃG���A���������ۂ́A���[����x�u�Őߓd�S���҂ɒʒm����B�Z���T�[�͍ő�30��܂Őڑ��\�B1�̃G���A�ɋ��������z������������ꍇ�́A���Z���ĊĎ��ł���B���i��18��6000�~�B �o�T�uECO �W���p���v |
|
|
| ��LIXIL�͉ƒ�̐����̐��i�̐��ʂ��v���A���䂷��V�X�e�����J���� ������w���Y�Z�p�������Ƌ��L�����p�X�ŋ����J�������ȃG�l�Z����Ŏ����ɒ��肵���B �g�C���A�o�X�Ȃǂ̋@����̃}�C�R����Z���T�[�Ő��g�p�ʂ��펞�c������B�f�[�^����HEMS�̃R���g���[���[�֑���A�C���^�[�l�b�g��ʂ��ĉ����O�̃p�\�R����X�}�z�ɐڑ����A�@�킲�Ƃ̎g�p�ʂ��c���ł���悤�ɂ���B �ƑS�̂Ƌ@�했�̐��ʂ̖ڕW��[������ݒ肵�A�������Ǝ����I�ɐ��ʂ���������d�g�݂Ȃǂ��v�悷��B���ʂ̌����鉻���������ŁA�@��̐ߐ��@�\�̊J�����i�߂�B���ʂ�}����ȃG�l���[�h�����������V�����[��z��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���F�����z�����d�����ցA���傪��K�͎��؎{�� ���s��w�́A�u�F�����z�����d���v�̎����Ɍ����āA�F���L�����p�X�Ɋ��������}�C�N���g�G�l���M�[�`�������{�݂����J�����B �{�{�݂ɂ́A���ϓd�͓d�g�z���̂�������d�g�Î��⑪�莺�Ȃǂ���������Ă���A���E�ő�K�͂̑�d�̓}�C�N���g�G�l���M�[�`���������s�����Ƃ��ł���B �F�����z�����d���Ƃ́A�l�H�q���Ɏ��t��������^�̑��z�d�r�p�l�����F����ԂɍL���A���z�����d�ɂ���ē����d�͂��}�C�N���g�ɕϊ����āA�n���ɑ��d���邱�Ƃ������B�{�{�݂ł́A�F������̑��M��z�肵�A�����x�̋����̃}�C�N���g���o���A�����[�g�����ꂽ�A���e�i�Ŏ��A�d�C�ɕϊ�������؎������s���B�d�͂���}�C�N���g�ւ̕ϊ������Ȃǂ����ƂȂ邪�A�G�l���M�[���ő���Z�p�́A�d�C�����ԂɃP�[�u�����g�킸�A��ڐG�ŏ[�d����Z�p�Ƃ��Ă����ڂ���Ă���B ����A�{�{�݂��10���~�����Ċ����������B5�`10�N��ɂ́A���a10m�̑��z���p�l��������������q����ł��グ�����Ƃ��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���ȃG�l�Z��E���z���ɔF�萧�x�A�ŗD���ƃZ�b�g�Ő��i�����ȕ��j �F�萧�x�́A�ȃG�l�@�Ɉʒu�t���A�@���x�Ƃ��čs���\��ŁA���@�����Ă�2012�N�ʏ퍑��ɒ�o����l���B 2012�N�x����̐��x�J�n��ڎw���B�F��Z��E���z���ւ͐Ő��D�����s�������ӌ��B�o�^�Ƌ��ł�s���Y�擾�ŁA�Œ莑�Y�łȂǂ̗D�����������Ă���B�C���Z���e�B�u�ƃZ�b�g�ōs�����ƂŁA�ڕW�Ƃ��Čf����2020�N�܂łɏȃG�l��K����100���ւ̎��g�݂𑣐i����B �F�萧�x�́A���z��Ȃǂ����z���̌��z�E�ێ��ۑS�̌v����쐬�A���Ǎs�����ɐ\�����A����s�������F�肷��`��\�肵�Ă���B���x�̑Ώۂ́A�V�z�Ɗ����̗�����z��B�F���́A�ȃG�l��Ƌ�����Ȃǐݔ��̊����Ȃ�g�b�v�����i�[����P�̖ڈ��ƍl���Ă���Ƃ����B �o�T�u�Z��V��v |
|
|
| �������̑�12���܃J�N�v����ԁA�G�l���M�[�����16���팸 �����@�����̂قǔ��s�����u��12���܃J�N�v��̏ȃG�l�E�r�o�팸�̑����I�Ɩ��v�����v�Ɋւ���������s���A��12���܃J�N�v����Ԓ��̏ȃG�l�E�r�o�팸�ڕW�Ƃ��āA2015�N�܂łɁA������GDP1����������̃G�l���M�[�����W���Y���Z��0.869�g���܂ō팸���A2010�N�i1.034�g���j���16�����Ƃ��A�W���Y6��7000���g�����̐ߖ���������邱�ƂȂǂ𖾂炩�ɂ����B �{�v�����͉��i�E�����E�Ŏ��E���Z�̖ʂ���A�ȃG�l�E�r�o�팸�ɂȂ���o�ϐ��������B����ɂ́A���������i���i�̉��v�̋����A�d�͏��������Ȃ���Ƃ�ΏۂƂ���u�������d�C�����v�̎��{�A���ʼn��v����ъ������ӔC�ی����̑[�u�̐��i���܂܂��B ��11���܃J�N�v����ԁA������GDP����Ƃ���G�l���M�[�����19.1�����ő�11���܃J�N�v��̋����I�ڕW��B�������B �o�T�u�l���ԓ��{��Łv |
|
|
| ���Z��E���z���̏ȃG�l�`�����̓��� ��N�i2010�N�j11���ɊJ�Â��ꂽ��2��w��Y�f�Љ�Ɍ������Z�܂��ƏZ�܂������i��c�x�ŁA���\���ꂽ�|�C���g�͈ȉ��̂R�_�B �@�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��l����������������Ƃł���B�C������f�M���A���R�G�l���M�[���p��A�g�[�E��[�A�������̌��z�ݔ��̃G�l���M�[����ʂ�ΏۂƂ���������邱�Ƃł���B �A��K�͌��z������i�K�I�ɋ`������i�߁A2020�N�܂łɑS�Ă̐V�z�Z��E���z���̏ȃG�l���`��������Ƃ�����̓I�ȍH���������ꂽ���Ƃł���B �B�{�H�ҁA�v�҂ɑ��āA�ȃG�l�Z�p�K���̂��߂̎x����ȃG�l�v���x������v���O�����̊J���x���ȂǁA���ށE�@�탁�[�J�[�ɑ��ẮA���₩��JIS�}�[�N�₻��ɏ�����F���擾�ł���悤�ɂ���B �H���\�ł�2011�N�x���Ɍ��z���ɂ��Ă̐V�����ȃG�l������\�����\��ł���B����ɂ��ȃG�l�`�����Ɍ������傫�Ȉ�������ݏo����邱�Ƃ����҂����B���y��ʏȂ��V�z�����̏ȃG�l�`�����Ɍ�������̍�����c�����c���J�Â���|���V�����ꂽ�B��c�ł́A�k�Ќ�̏ω��܂������j�ɂ��Ă̋c�_��V������̓��e�ɂ��Ă̋c�_���s����Ǝv����B �o�T�uMRI Weekly�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/10�@]�@�@�� |
|
|
| ���Z���v�挤�A�ƒ��CO2�팸�ʂ���Ƃɔ��p���郂�f�����Ƃ��J�n ����܂Œ��ڂ���Ȃ������ƒ�̍팸�ʂɊ����l�����������A���g����̂��߂ɗL�����p����B�����͏ȃG�l�Ɠd�̕��y���i��Ƃ��č팸�ʔ��p�v���ƒ�ɊҌ����邱�Ƃ�z��B�܂��A���f�����Ƃō팸�ʂ̎Z����@�Ȃǂ̉ۑ��������B ���f�����Ƃ͌o�ώY�ƏȂ���̈ϑ��ŏȃG�l���M�[�Z���^�[�Ƌ����Ői�߂�B��s���̉ƒ��ΏۂɏȃG�l�^�̃G�A�R���A�①�ɁA�e���r�ɂ��ē���������1000����W�B���̂������̉ƒ�ɓd�͎g�p�ʂ̌v�����ݒu���ȃG�l���ʂ���������B�����f�[�^����ɂ��ׂĂ̎Q���ƒ��CO2�팸�ʂ�����o���B2012�N1�����܂łɍ팸��40�`50�g���̏W����v��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���R���A�J�[�{���}�l�W���[�琬 �ٗp�n�o���ʂ����҂����ȃG�l�≷�����ʃK�X�팸�ȂǂɊւ���厑�i�u�J�[�{���}�l�W���[�v�̎Г��琬�ɏ��o���B ���t�{�����H����L�����A�A�b�v�헪�u�J�[�{���}�l�W���[�E���[�L���O�E�O���[�v�v�����債���u�J�[�{���}�l�W���[���Ǝ�́v�ɉ��債�A7��12���ɑI�肳�ꂽ���Ƃ����[�u�B�J�[�{���}�l�W���[�́A��_���Y�f�iCO2�j���팸���邽�߂ɒn�����g����ɂ��Ă̐��m����m�E�n�E���q�ϓI�ɕ]���ł���l�ނŁA���{��2012�N�x���瓱����ڎw���Ă���B���x��1�`7�Ԃł�7�i�K�ƂȂ��Ă���A�Ⴆ���x��1�͏ȃG�l�@�𗝉����Ă�����x�ŁA���x��7�ɂȂ�ƊC�O�ł�����ł���l�ނƂ����悤�ɕ]�����������Ă���B ����̎��ƌ���́A�����i�Ɋւ����̓I�Ȕ\�͕]����ƈ琬�v���O�����̑��₩�ȍ���A����������邽�߂̎��؎��ƂŁA���Ђ͎��Ǝ�̂Ƃ��đS�ʓI�ɋ��͂��邱�ƂɂȂ����B����A�Г��̑I�������o�[�ɂ�邅���[�j���O��������т̕]���A�W�����C�Ȃǂ��o�āA���x��1�`4�ɑ�������l�ނ̈琬���s���B���ʂ̖ڕW�Ƃ��āA3�N���1000�l�̗L���i�҂�ڎw���B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ��JFE�G���W���n���M�𗘗p����Ɩ��p�̔ėp�q�[�g�|���v���j�b�g���B ����܂Œn���M�q�[�g�|���v�@�̊O�ɐݒu���Ă����z�|���v��c���^���N�Ȃǂ̕�@�ނ��@�����ɑg�ݍ����̂ŁA�]���̒n���M�ɔ�ׁA�ݒu�X�y�[�X��1/2�ɏk�����A���n�ł̐ݒu���Ԃ�1/3���x�ɂ܂ŒZ�k�����i�n���M�z�ǍH���͏����j�B �@��\�͂́A�n���M22.4kW�A��C�M14.0kW���ŏ��P�ʂƂ��郂�W���[�������R�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�K�v�ȋ\�͂�I��ł���悤�ɂȂ��Ă���A�O�C��n���M�̉��x�����j�^�����O���A�ߋ��̉^�]�L�^�f�[�^���Q�Ƃ��邱�ƂŁA���ГƎ���AI�i�l�H�m�\�j��24���Ԑ�܂ł̏�\�����āA�œK�����^�]���s���悤�ɂȂ��Ă���B �n���M�́A�N�Ԃ�ʂ��ĉ��x�ω����������i�s�s�ߍx�Ŗ�17���j���R�G�l���M�[�ŁA�]���̋@�Ɣ�r���āA����d�͗ʂ����CO2�r�o�ʂ�30�`40���ጸ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �o�T�u���z�ݔ��j���[�X�v |
|
|
| �����������㉷�x20�x�}������R���N���[�g�p�l�����J�� �߂����i������B�����Ԃ���������f�ނ��g���A�ՔM���̍����h����\�ʂɎ{���ĕ��M���\�����߂��B�����ł́A����̕\�ʉ��x��15�`20�x�}������ʂ��������Ƃ����B �p�l����60�Z���`�l���Ō�����5�Z���`�B�d����25�L���ƁA�ʏ������40���y�ʉ������B�ې�����ʋC���ɂ��D���B ����A���鉮��Ή��Ɣ�ׂ�Ɛݒu���ȒP�ŁA���܂���̊��荞�݂Ȃǎ�Ԃ��s�v�Ȃ��߈ێ��Ǘ��R�X�g���قƂ�ǂ�����Ȃ��Ƃ����B�����́A���x�Ǘ����d�v�ȃf�[�^�Z���^�[�Ȃǂւ̎��v�������߂�Ƃ݂āA���荞�݂�}��B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| ���I���b�N�X�d�́A�}���V�����̏ȃG�l���M�[�Ɠd�C�����팸������ �u�d�͈ꊇ�w���T�[�r�X�v�Ƃ́A�����ȍ����d�͂�d�͉�Ђ���ꊇ��d�A�}���V���������ɒሳ�ɕϊ����z�d���邱�Ƃŗ��p�҂̓d�C�������팸�ł���Ƃ����B ����A�V���ɑg�ݍ��킹���T�[�r�X�ɂ���āA���z�����d�V�X�e���Ŕ��d�����d�͂��A�d�͈ꊇ�w���ɂ���d�V�X�e�������p���e�Z�˂ɔz���B����ɂ��e�Z�˂̏ȃG�l���M�[���Ƃ���Ȃ�d�C�����̍팸���Ɏ�������Ƃ����B �]���A�}���V�����ő��z�����d�V�X�e��������ꍇ�A�e�Z�˂ւ̌˕ʔz�d�ݔ��̓����R�X�g�Ȃǂ̐���A���d�����d�͂����L���ŗ��p���邱�Ƃ���ʓI�������B�������I���b�N�X�d�͂́A�ꊇ��d�V�X�e�������p���A���z�����d�V�X�e���Ŕ��d�����S�d�͂��A��L�ʐςɉ����Ċe�Z�˂ɔz�����邱�ƂŁA�˕ʂ̐ݔ��������S���y���B���z�����d�V�X�e���̔��d�e�ʂɊւ�炸�e�Z�˂ł̗��p���\�ƂȂ����Ƃ����B����ɂ��A�e�Z�ˁi��L���j�̓d�C�������A�d�͈ꊇ�w���T�[�r�X�̍팸���ƍ��킹�Ă��悻10���ȏ�팸�\�ƂȂ����B�e�Z�˂̓d�C�������24���팸����Ƃ����B �o�T�uIBTimes�v |
|
|
| ��������Ȃǂ��ؒY�̏Z��ނŖ�24���̐ߓd���� �o�_�J�[�{���������E�̔����鎼�x�������ʂ����߂��ؒY���g�p����B �f�M����Ă��Ȃ��V�䗠�̋�Ԃɒ����ؒY��f�M�ނƂ��Đݒu���邱�Ƃŗ�[���ʂ����܂�Ƃ����B�e��Ђ̏o�_�y���͒����ؒY�����p�����H�@�̓������擾���Ă���A���H�@�ŏZ��݂��s���F���Ђ�S�������W���Ă���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����s�u�n�d�v�r�W�l�X�ɖ{�i�Q����5�N�ȓ��ɖ��F�ɍ������̔��d�V�X�e�� �����d�͕�����P�������̂��āA���s���Ǝ��ɓd�͂ݏo���u�n�d�v�r�W�l�X�ւ̖{�i�Q���ɏ��o�����Ƃ����������B ������ւ̍ŗL�͌��Ƃ����A�V�R�K�X��R���Ƃ����������̔��d�V�X�e���uGTCC�v���B�^�Ăł��s����̏���d�͑S�̂�1�����x���m�ۂł���K�͂Ōv��B ���ݏo�����d�͂́A�n���S��o�X���^�c�����ʋǂȂǓd�͎g�p�̑��������ɗD��g�p��������A�]��d�͂��֓d�ɔ̔������肷�邱�Ƃ��������Ă���B���ݔ�͐��S���~�K�͂Ǝ��Z�B���Ԋ�Ƃɂ����ƎQ�����Ăт�������j���B GTCC�́A�K�X�^�[�r������C�^�[�r����Ǝ��ɑg�ݍ��킹�����d�V�X�e���B�s�Ȃǂɂ��ƁA�M�����������̖�2�{�ɂ�����50�`60���ƍ����A�ݔ��̍H����2�`3�N�ƒZ���B���݃R�X�g�͌�����10����1�ȉ��Ƃ���A��_���Y�f�̔r�o�ʂ��ΒY�Η͂̔������x�ɗ}���邱�Ƃ��ł���B �o�T�uSankei Biz�v |
|
|
| ���G�l�����d���ʃR�X�g���Z�@�ߓx�̉Η͈ˑ��Ɍx�� �d�͊e�Ђ̉ߋ�5�N���̗L���،����ɂ��ƂÂ��Ď��Z�������q�͂ƉΉA�n�M�̔��d�R�X�g�����\�����B���q�͂̃R�X�g�͂����ނ�7�~�i1kWh������j���x�ƈ���I�������̂ɑ��A�Η͔͂R����̗������ɂƂ��Ȃ���9�`12�~�i���j�Ƒ傫���ϓ��������Ƃ����������B �G�l���͕]�����ʂ���u�Η͂̃R�X�g�͔R�����i�ϓ��̉e���ړI�Ɏ����A���q�͉͂e�����ɂ����v�ƕ]���B�G�l���M�[�Z�L�����e�B�[�̊ϓ_����A�Η͂ւ̉ߓx�Ȉˑ��Ɍx����炵�Ă���B �����͍����̈�ʓd�C���Ǝ҂���щ��d�C���Ǝ�12�Ђ��ΏہB2006�`2010�N�x�̗L���،����ɂ��ƂÂ��A�d���ʂ̔��d�R�X�g�����Z�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Y�����A�����ȓd�͌v������J���|�g�p�d�͂������鉻 �J�������d�͌v�����1���4�_�̓������肪�ł���B�s�̂̓d���Z���^�[�ƃ}�C�R���`�b�v�ō\���������̂ŁA�P�_������2500�~���x�Ő���ł���B �N���E�h�T�[�o�Ƒg�ݍ��킹�ĎY�����̌v�Z�T�[�o�����ɐݒu�����B�v249�_���v�����v�Z�T�[�o���ƂɎg�p�d�͂������鉻�ł���V�X�e����Z���Ԃō\�z�ł����B�H����̂��܂��܂ȋ@�B���Ƃ̎g�p�d�͏��������鉻�ł���V�X�e���Ƃ��ĉ��p�ł���Ƃ����B �ȒP�ɐݒu���邱�Ƃ��ł��A���Ə���H��Ȃǂœd�͎g�p�ʂ̍팸�ɖ𗧂Ƃ����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�X�}�[�g���[�^�[�ɂ��ߓd�ڕW�B���ɕ� �������Ǝ҂́A�T�[�r�X���Ǝ҂̃A�h�o�C�X�����ƂɁA�X�}�[�g���[�^�[��BEMS�����A�ߓd�Ɏ��g�݁A�ڕW��B�������ꍇ�́A���������x�����B���́A�⏕����G�R�|�C���g�̂悤�ȓ_��������悤�Ȏd�g�݂ɂ���B �{����ɂ��ߓd�̐��ʂ��A������ƂȂǂ����Ƃ̋��͂ĉ������ʃK�X�̔r�o�팸���Ƃ��s���u�����N���W�b�g���x�v�ɗ��p���邱�Ƃ��������Ă����B �{����Ă̗\�Z�Ƃ��āA2011�N�x3����\�Z��2012�N�x�\�Z�T�Z�v�������킹�A���S���~�K�͂ŗv��������j���ł߂��B �C���Z���e�B�u�ɂ��ȃG�l�̐��i�{��ɒ��͂��Ă���B��ʉƒ�p�����ɂ́A�ߓd�j���[�����Љ��u�ߓd�A�N�V�����v�̃T�C�g���J�݁B�u�ƒ�̐ߓd�錾�v�ɎQ������ƁA���^��Ƃ̓X�܂�{�݂œ��T��������u�Q���܁v�A����ɁA��N��15%�̓d�͍팸��B�������ƒ�́A���^��Ƃ�����ܕi�ɉ���ł���u�B���܁v�Ȃǂ�݂��Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/9�@]�@�@�� |
|
|
| ���I���������ȈՓd�̓��K�[�� �펞�v������O�i�K�ł̈ꎞ�I�ȓd�͗ʂ̊m�F��A�펞�d�͌v�����Ă���ꏊ�����ڍׂɊm�F�������Ƃ������A�����d�͗ʂ�c���������Ƃ�������̃j�[�Y�ɉ����郍�K�[�B �d���z�����s�v�ŁA��pCT��d�����Ɏ��t���邾���ŁA�b�P�ʂ�����P�ʂ܂ŗp�r�ɍ��킹���d�͗ʂ̊m�F���A���u��C�����~�߂邱�ƂȂ��ȒP�ɍs����B�d�r�쓮���\�Ȃ��ߓd���z�����s�v�ŁA���d�Ղ̓����ȂǂɎ��ŊȒP�ɐݒu�ł���B�\����𓋍ڂ��Ă���{�݂̂̂œd�͗ʁi���Z�l�j���m�F�ł���B�܂��A�{�̓�����SD�J�[�h�ɓd�͗ʃf�[�^���L�^���Ď����o�������\�ŁA�t���̐�p�\�t�g�ŁA�L�^�����d�͗ʂ͂���܂łɋL�^�����d�͗ʂƎ����I�ɔ�r�������L���O�\���ł��邽�߁A�e���u��C�����œd�͗ʂ̑召��r������ŊȒP�ɍs�����Ƃ��ł���B�܂��A��莞�Ԃ��Ƃ̓d�͗ʂ̔�r���\�Ȃ��߁A�d�͗ʂ��s�[�N�ɒB�������Ԃ��ȒP�Ɋm�F�ł���B�W�����i�F39,800�~ �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����[�J�[10�ЁAHEMS�̋��������̐��𗧂��グ KDDI�A�V���[�v�A�_�C�L���H�ƁA�����d�́A���ŁA���{�d�C�A�p�i�\�j�b�N�A�������쏊�A�O�H�����ԍH�ƁA����юO�H�d�@��10�Ђ́AHEMS�iHome Energy Management System�j�̎s��m���ƕ��y��ړI�Ƃ��āA���������̐��iHEMS�A���C�A���X�j�𗧂��グ���B �{�A���C�A���X�ł́AHEMS�A�v���P�[�V�����i�v���O�����j����X�}�[�g�Ɠd�Q�ւ̐���̂�������͂��߁AHEMS�A�v���P�[�V�����̊J���E���ʁA�X�}�[�g�Ɠd�̕ێ�ɕK�v�Ȏd�g�ݍ��ȂǁA"���S"���L�[���[�h�ɁAHEMS�y�уX�}�[�g�Ɠd���y�̊������Ɍ����āA���ʂ̉ۑ�����Ɏ��g�ށB ��Y�f�Љ�̎����Ɍ����āA�܂��A�S���I�ȓd�͎����N���ւ̑�Ƃ��āA�ƒ�ł̏ȃG�l���M�[�̐��i�����߂��Ă���B�����������A����A���[�J�[�e�Ђ��J�����鍂�@�\�ȃX�}�[�g�Ɠd�Q���A�z�[���R���g���[���[��HEMS�A�v���P�[�V�����Ȃ�ICT�����p���邱�Ƃɂ���đ��݂ɐڑ����A�e�@��̎g�p�̉����⎩�������ʂ��āA�ƒ�S�̂̓d�͎������œK���䂷�邱�Ƃ��s���ƂȂ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���u�ߓd�v���\�E�ޓ��ɂ����ӁI �v���d�ɏ悶���K��̔��\�l�A��Ɩ�킸���U �Ď��{�̉\�����c��v���d�B�ҏ��̉āA�u�ߓd�v������������ɂ��������ȖK��̔���s�R�ȓd�b�Ȃǂ��������ł���B ���d�Ȃǂ̓C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W�Œ��ӊ��N�u�s�R�Ɋ������炷���ɖ₢���킹�Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B ���d��֓d�ɂ́A�����{��k�Ќ�A�Ј���W��ЎЈ��𖼏���Đߓd�@��⏬�^�ψ���̍w�����������ꂽ��A�ȃG�l���M�[�̃A���P�[�g���ĉƑ��\���Ȃǂ��o�����Ƃ��ꂽ�肵���ڋq����₢���킹���������B�v���d�Ȃǂɏ悶������ŁA�u���[�J�[�����Ȃǂ̖��ڂŎ���ɏオ�荞�݁A���i�𓐂ގ������N���Ă���Ƃ����B �����d�͂ł��u���[�^�[��u���[�J�[�̎�芷���H����𐿋����ꂽ�v�Ȃǂ̑��k���������A���Ђ́A�����Q��������\��������Ƃ��AHP�Œ��ӂ��Ăъ|���Ă���B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�d�HSUNX�A�G�A�̌����鉻�ɖ𗧂G�A���ʃ��j�^���o�J�n�� �H��̓d�C�g�p�ʂ̖�25���̓R���v���b�T�ւ̋����d�͂Ƃ���A���̖�40�����G�A�̘R�k�∳�͑����A�R���v���b�T�̃����e�i���X�s���Ȃǂɂ�閳�ʂƂ��ď����Ă���B���̂��߁A�ȃG�l���M�[���̎����Ɍ����ẮA�G�A�̊Ǘ���G�A�̖��ʌ����̒ጸ���d�v�ƍl�����Ă���B �G�A���ʃ��j�^�́A�����g���̌��o�������̗p���邱�ƂŃI�C���~�X�g��ق���ɂ��듮���ጸ���A�����e�i���X�t���[�������������i�B�R���v���b�T�f�o����A�H����e�����ւ̔z�ǁA�������C�����̔z�ǂƂ��������L���z�nja�ɑΉ�����@��i���a��25�`200mm��9�@��j�����낦�Ă��邱�Ƃ������B�f�[�^���K�[�o�R�ŃG�R�p���[���[�^�ɐڑ����邱�Ƃɂ��A�d�͂ƃG�A�̎g�p�ʂ��ɑ���\�B �z�[���y�[�W���疳���̌����鉻�\�t�g���_�E�����[�h���Ďg���A����f�[�^���ȒP�ɃO���t�����Ċm�F���邱�Ƃ��ł���B �G�A�̑̐ς͈��͂≷�x�ɂ���ĕς�邱�Ƃ��l�����A0���A1�C���̒l�ɑ̐ς����Z����m���}�����Z�@�\�������B���[�v�z�ǂɂ��Ή����A�����E�t���̌v�����\�B���i�́A���a50mm�̃^�C�v��16��5000�~�B �o�T�u���o���̂Â���v |
|
|
| ���d�C�����������x���g��|���Ɛ헪���A���H�ɂ��������� ���t����Y���Ɛ헪�S�����́A�G�l���M�[�E����c�i���t�c���j���܂Ƃ߂��u�v�V�I�G�l���M�[�E���헪����Ɍ��������ԓI�����v�őł��o���Ă���d�C�������x�̌������ɂ��āA�H���ɂ���̉��������l�����������B �d�͎��v�s�[�N�̎��ԑтɓd�͋��������炷�_�������ƁA�ƒ�ɑ��Ă̓d�͗����̊������x���g�傷�邱�Ƃœd�͕s���̉����ɂȂ���B ���{�̓d�͎��v�͗�[�^�]������ɂȂ�ď��13�`14���O��ɏW������B���̎��ԑт̓d�͋����ɐ�����݂��A���Ԃ�Ƃ��ēd�͗�������������B��Ƃ⊯���A������ȂǑ�����v�Ƃ͂��̓��ʗ������x��d�͉�Ђƌ_�Ă���Ƃ��낪��������A����̊g��𑣂����Ƃœd�͏���̕������Ɠd�͕s�������}��B �s�[�N���̎��v������Γd�͒����p�̉Η͔��d�̉^�]�����点�A��_���Y�f�iCO2�j�팸�ɂȂ�����ʂ�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��H��r�M�̗��p�𑣂����߂ɗΒn�K���̊ɘa������ �r�M�����ݔ��̐�����p�C�v���C���̒ʂ蓹�ɂȂ�H�ꂾ���̗Βn�ʐϗ��������ĕs���ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�H��Ԃ�H�ƒc�n�S�̂ŕK�v�ȗΒn�ʐϗ����m�ۂ���悢�Ƃ������Ɠ���[�u����������B �܂��A�r�M�����ݔ���p�C�v�Y�{�݂Ƃ��Ď�舵��Ȃ������T��A���Y�{�ݖʐϗ��̋K���̏�������ɓ������₷������B ���y��ʏȂƋ�����2012�N�x�ɂ��A�����p�G�l���M�[��L���Ɏg���X����𐄐i���閯�Ԏ��Ƃ̔F�萧�x�𗧂��グ��v��B����ɁA�H��Ԃ̔r�M�Z�ʂ𑣂��K���ɘa��g�ݍ��ށB �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����ȂƃG�l���A�n�����M���g�[�Ɋ��p�|�K�C�h���C������� ���Ȃƌo�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���͒n�����̔M���A�n��Ȃǂŗ�g�[�Ɋ��p����K�C�h���C������ɏ��o���B �n�����͗�g�[���̓d�͕��ׂ����炷���R�G�l���M�[���̈�Ƃ��Č�������Ă��邪�A��˂���̉ߏ�ȗg���͒n�Ւ����̋��ꂪ����Ǝw�E����Ă���B ���Ȃ�2011�N�x���ɒn�ՂɈ��e�����Ȃ��g�����@�̃K�C�h���C���������A�n�������p�̋Z�p�I�Ȋ�Ղ��B����A�G�l���̓K�C�h���C������▯�ԂƎ����̂ɂ��n�������j�^�����O�Ȃǂ��x������B �n�����̔M���r����n��Ŋ��p����ꍇ�A�r���͊��Ȃ����ǂ���u���z���p�n�����̍̎�̋K���Ɋւ���@���i�r���p���@�j�v�A�n���g�[�͊��Ȃƌo�Y�Ȃ������Ŋē���u�H�Ɨp���@�v�ɂ�鋖���x�Œn�Ւ�����h�~���Ă���B���Ȃ͒n�Ւ�����h�����ꂩ��g�����@�̃K�C�h���C�����������ƂŁA���R�G�l���M�[�ł���n�����̔M�����S�Ɋ��p���邽�߂̓����J���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����t�{�A�ȃG�l���l�ނ��琬�|�������猤�C �������~�̓d�͕s����ߓd�w�͂⎩�Ɣ��d�ݔ��ŏ���l����\���A��������t�{�́u�J�[�{���}�l�W���[�v�l�ނ̈琬���}���B�ȃG�l���_���Y�f�iCO2�j�팸�ɐ��m�������l�ނ���Ă邱�ƂŊ�ƂȂǂ̏ȃG�l�����𑣂��A�g�p�d�͍팸�ɂȂ���B �J�[�{���}�l�W���[���Ǝ�̂ɑI�肵���V���ƎҁE�O���[�v�𒆐S�ɓ��}�l�W���[�̏����E�����ɑ������郌�x��1����4�܂ł̈琬�v���O�������쐬�A8�����猤�C���n�߂�B9�`10�������Ƃ�c�̂ł̎������n�߂����l���ŁA���~�܂łɌv100�l�̐l�ވ琬��ڎw���B �J�[�{���}�l�W���[���x�́A��������2012�N����̓�����ڎw���Ă����B�ȃG�l��CO2�팸�Ȃǂ̐��m�������l�ނ����x���P����V�܂łV�i�K�ŋq�ϓI�ɕ]�����邱�ƂŊ��r�W�l�X��������l�ޑ����𑣂��A�K�J���҂̏A�E�ɂ��𗧂Ă�_��������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����z�M�@�핁�y�֎{�H�m�F�萧�x�� �\�[���[�V�X�e���U������́u�\�[���[�{�H�m�F��o�^���x�v��n�݂����B���z�M������ȂǑ��z�M���p�@��̎{�H�ɂ��āA���x�ȕi���ێ���}�邱�Ƃɂ��A�@��y������̂��_���B���ʂ�300�l�̎{�H�m�̓o�^��ڎw���B������ɂ͓����K�X���葍�ƂȂ�13�Ђ�����Ƃ��Ė���A�˂Ă���B ���̐��x�͉���e�Ђɑ��A�w�����u�K�����{�B�w�����͎{�H�Ǝ҂ɑ����C���s���B���̏�ŊȒP�ȃe�X�g���s���A���̓_�����N���A����Ǝ{�H�m�Ƃ��ĔF�����t�����B���x�̉^�c�̓\�[���[�{�H�F��o�^���x�^�c�ψ���S���B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���ȃG�l���M�[�Z���^�[���u�ƒ�̏ȃG�l�G�L�X�p�[�g����v���J�n �u�ƒ�̏ȃG�l�v����퐶�����ƁA�n��̊����ȂǂŐϋɓI�ɐi�߂邱�Ƃ̂ł���l�ނ̔��@�E�琬���˂炢�Ƃ��āA���炽�Ȍ��萧�x��n�݂��A���N�x������{����B ��̓I�ɂ́A�u�G�l���M�[�̊�b�Ɖƒ�̏ȃG�l�v�A�u�@��ɂ��ȃG�l���M�[�v�A�u�Z��̏ȃG�l���M�[�v�Ȃǂɂ��đ����I�Ȓm�������w�ƒ�̏ȃG�l�G�L�X�p�[�g�x������ɂ���ĔF�肷����̂ŁA���N�x�̌��莎���́A2011�N12��11���Ɏ��{�����B ����̏ڍׂ́Ahttp://www.eccj.or.jp/residential-expert/index.html �܂��A2012�N�x����́A�ƒ�̏ȃG�l��f�f���A���P��Ă����H�I�ɍs�����Ƃ̂ł���w�ƒ�̏ȃG�l�f�f�G�L�X�p�[�g(����)�x�����C�ɂ���ĔF�肷��B �o�T�u���z�ݔ�̫��сv |
|
|
| ���@�@[�@2011/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���G�l�b�g�Ƃm�s�s�|�e�A�V������}���V���������ɐV���ȓd�̓T�[�r�X���J�n �T�[�r�X�ł́A�ߓd�𑣂����ߒ��Ԃ̓d�͗����P�����������A���E�ӂ��������Ď��v�U���鎞�ԑѕʂ̗����ݒ��A���v�Ƃ̏ȃG�l���M�[�w�͂ɉ������C���Z���e�B�u���|�C���g�Ƃ��Ďx�����_�������B ���ԑѕʗ����ݒ�̂��߂̓d�̓f�[�^�̎擾�́A�m�s�s�t�@�V���e�B�[�Y���e�}���V�����ɐݒu���Ă���30���v�ʂ��\�ȃX�}�[�g���[�^�[�ōs���B�C���Z���e�B�u�́A�K�v�Ȏ��ԑтɓd�͏����}���E���U�����ڋq�ɑ��A�����ȍ~�̓d�C�����̎x�����z������������Ƃ��ł���|�C���g�Ƃ��Ē���B�m�s�s�t�@�V���e�B�[�Y�����Ă����s����9�}���V�����E��3�琢�т�Ώۂɖ����Œ��n�߁A�����Ώۓ������L����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���t�@�~�}�A���߂Ȃ��Ă����������g�ߓd�ٓ��h�̔̔��J�n �ٓ��̋�ނ⒲���@�Ȃǂ��H�v���A�R���r�j�G���X�X�g�A�̓X���ɐݒu���Ă���d�q�����W�ʼn��M�����ɐH�ׂ���悤�ɂ���B �Ă̓d�͕s���ɑΉ������ߓd���{�i�����鎞���ɍ��킹�Ė��̓��ٓ��Ȃǐ���ނ��A���i�͒ʏ�ٓ̕��Ɠ������x�ɂ��錩�ʂ����B �ٓ��ɓ�����ގ��̂��������ق��A�ϕ��Ȃ�Ύύ��ݎ��Ԃ�ύ��ݕ����H�v����Ȃǂ��āA��߂Ă����������Ɗ����钲�����@���J���B�ߓd�ӎ��̍����ڋq��A�C���������ď�ɔM���ٓ��͐H�ׂ����Ȃ��l�ɂ��A�s�[������B �R���r�j�X���̓d�q�����W�͗��X�q���w�������ٓ������߂邽�߂ȂǂɎg����B�����W���g��Ȃ��Ă����������H�ׂ���ٓ������ēX�܂̐ߓd�̈ꏕ�ɂ���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���_�C�L�������[���G�A�R���̐ߓd�R���g���[���[���B �R���g���[���[�́A1997�N�ȍ~�̓��А����[���G�A�R���Ɏg�p�ł��A�\�߁u�������߁v�u�s�[�N�J�b�g�v�u�J�X�^���v�̂R�̉^�]�R�[�X���v���O���~���O����Ă���A�u�������߁v��I�������ꍇ�́A���Ў��Z�ł͂P���̏���d�͗ʂ��12���팸�ł���Ƃ����B �ݒ艷�x�̕ω��̓R���g���[���[�̃��j�^�[�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��A����ɁA�\�����ꂽ�����R�[�h���p�\�R���Ő�p�T�C�g�ɓ��͂���ƁA���X�̐ߓd���ʂ⑼���[�U�[�̕��ϒl�ȂǂƂ���r�ł���B���i��12,800�~�i����2000��j�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���d�͉�Ђ��K�v�ʌ��偨��Ƃ��ߓd�ʐ\���@���Ăɂ����s�ꊈ�p�́u�l�K���b�g�v���� �d�͎�����Ƃ��āA��ƂȂǑ�����v�Ƃ̐ߓd����d�͉�Ђ�������鐧�x�̊T�v���P���A���炩�ɂȂ����B �����̓d�͉�����s����g���Ȃǂ��Ď������u�l�K���b�g�v�ƌĂ�鐧�x�ŁA�o�ώY�ƏȂ����Ă̓�����ڎw���B���Ă͓d�͎g�p�����߂��������A���Ă͊�ƕ��S����菭�Ȃ����@�Őߓd�𑣂��B �l�K���b�g�́A�d�͎������N���i�Ђ��ς��j�������ȓ���d�͉�Ђ��\�����A�K�v�ȍ팸�ʂ����Z�B�l�K���b�g�ւ̎Q�����_����Ƃ�Ώۂɔ�����艿�i����Č��傷��B����ɑ��A��Ƃ��ߓd�\�ȓd�͗ʂ�\�����A�K�v�ʂ��m�ۂł���܂ŁA�d�͉�Ђ����剿�i�������グ�Ĕ������B����̎d�g�݂ɓ��{���d�͎�����̊��p����������B �l�K���b�g�́A2000�N�̃J���t�H���j�A�B�̑��d�����P�ɁA�d�͋����s�������̎�@�Ƃ��ĕč��ō̗p���n�܂����B��Ƃ͐ߓd���̓d�C�����������I�Ɋ��������郁���b�g������B����A�d�͉�Ђ͎��v���̂����炷�ƂƂ��ɁA���d����d����V�݂�����������R�X�g�ŁA�K�v�ȓd�͋����ʂ��m�ۂł���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ���R���i���n���M�𗘗p�����Z��p�̃q�[�g�|���v�����g�[�V�X�e���� �n���ɍ̔M�ǂ݂��A���̒��ɏz�t���z�����邱�ƂŒn������M�����ݏグ�Ă���A���̏z�V�X�e���̐���ɂ́A�����̒g�[���ׂɍ��킹�|���v�̉�]���i�K�ɐ��䂷��V�J���̋Z�p�uSDR�i�ߓd�́j�v���̗p���Ă���B �g�[�[���Ƃ��āA���g�[�p�l���A�p�l���R���x�N�^�[�A�p�l�����W�G�[�^�[�Ȃǂ�ڑ����邱�Ƃ��ł��A�P��̃��j�b�g�ōő�o��6kW�̒g�[�\�͂�����A�K�X�������g�[�V�X�e���ɔ�ׂāA�g�[�̃����j���O�R�X�g�͖�1/3�ACO2�r�o�ʂ͖�1/2�ȉ����Ƃ����B���i�́A714,000�~�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���X�̔����Ƃ��������擾�A�ȈՋ�ō��C�� �����͋ɂ߂ĊȒP�ŁA�R���v���b�T�[���g���Ƃ̒��̋�C�����A�Ƃ̊O�����ق�̏��������ݒ肷�邾���B�ǂ�ȍו�����̌��ԕ����h�~�ł��A�Ă̓N�[���[�́A�~�͒g�[�@�̌�����2�`3���A�b�v�ł���Ƃ������́B �Ƃ̒��͑��z�M�ŏ�ɏ㏸�C�����������Ă��āA���ꂪ�������Ȃǂ���O���ɗ��o���Ă���B���̂��߁A���̕������Ԃ�ʂ��ĉƂ̒��ɗ������Ă���B���̂��߁A�~�͒g�[�@�Œg�߂Ă��O���̗₽����C���N�����Ă���B�Ă�1�K�ŃN�[���[�������Ă��A2�K���O�C���ʼn��܂�㏸�C���������A���l�ɊO�̏�����C���������ނ��ƂɂȂ�B����������h���ɂ́A�Ƃ̒��̋�C���ق�̏��������O����荂�߂�A�O���ƒf�₵�����C����Ԃ��ێ��ł���Ƃ����B ���̌����𗘗p����A�����č��C�����f�M�Z��ɂ��Ȃ��Ă��A�قړ��l�̌��ʂ������ł���Ƃ����B�������A���̂��߂̃R�X�g�̓R���v���b�T�[�̎擾��i�P��5000�~���x�j�ƁA�d�C��i����50�~���x�̗\��j�݂̂ƂȂ�B ���݁A���p���Ɍ������������i�߂��Ă��邪�A���y����ƏZ��ƊE�Ɉ�𓊂���\��������B �o�T�u�Z��V��v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�z�ǂɂ�����ʂ��Ĕ��d����u�M���d�`���[�u�v���J�� �M�G�l���M�[��d�͂ɕς���u�M�d�ϊ��v�Z�p�𗘗p�����`���[�u�B �`���[�u�́A�M������ɂ����M�d�ϊ��ޗ��ƁA�M������₷���������A�X���Č��݂ɐϑw�A�Ǐ�ɂ����\���ƂȂ��Ă���A�`���[�u���͂ɗ␅��������ԂŁA�`���[�u���ɂ����𗬂����ƂŁA�M�̗���Ɛ����ȕ����ɓd�C�������d�g�݂ƂȂ�B���Ђ����삵������10cm�̃`���[�u�̏ꍇ�A��1.3W�̓d�͂����o�����Ƃ����B �M���d�`���[�u�̓����Ƃ��āA�]���̃Ό^�\���̔M���ϊ��f�q���g�����ꍇ�Ɣ�ׂ��ꍇ�A4�{�̔��d�ʂ������ł���_�ƁA�������@���ȒP�Ŕz�ǂɂ��̂܂g����`��ł���_�������Ă���B���Ђł͂܂��A�`���[�u�ɗ��������E�␅�̉��x�ⓒ�ʂɉ��������d�������V�~�����[�V��������Z�p���\�z�����Ƃ��Ă���B�n�M�E����M�̔��d�ɓW�J���邱�Ƃ����҂��Ă���B �o�T�uImpress Watch �v |
|
|
| ���G�l��������d�̏������v��28�����ɐߓd�T�|�[�^�[�h���n�߂� �o�ώY�ƏȁE�����G�l���M�[���́A�ď�̃s�[�N���Ԃ̎g�p�d�͗ʂ�15���J�b�g���邽�߁A�u�ߓd�T�|�[�^�[�v�h�����n�߂��B �����d�͂Ɠ��k�d�͊Ǔ��̏������v�ƂɁA�d�C��C�Z�p�҂��ߓd���@����������B�����ɐߓd�Ɋւ���d�b���k�����u�ߓd�_�C�����v�i0570-064-443�j���ݒu�����B���_�C�����͕����A�y���j���Ƃ���9������17���܂ŁB �_��d��500kW�����̏������v�Ƃ̂����A�H���I�t�B�X�r���ȂǍ�����d�_���28�����ɁA�d�C��C�Z�p�҂��ʂɖK��B�Ă̐ߓd�s���v������肷��B�쐬�����v��𐭕{�̐ߓd�|�[�^���T�C�g�u�ߓdgo.jp�v�ɓo�^���A���\�����������v�Ƃɂ́A������Ȃǂɓ\���u�ߓd�錾�X�e�b�J�[�v��z�z����B�܂��A��N7�`9���̎g�p�ő�d�͂Ɣ�r���āA�ߓd�ڕW���l��B���������v�Ƃɂ́A�u�ߓd�B���i���́j�v��z�z����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y��BEMS�AHEMS�����ɕ⏕�����������Ă̓d�͗}���� ���Ă��d�͕s���������\�������邽�߁A���K�͎��v�Ƃ̓d�͎g�p�ʂ��}�����ޕK�v������Ɣ��f�����B IT���g���Ď����I�ɉƓd���i�̓d�����I���I�t������A�d�C�̎g�p���m�F�ł���悤�ɂ���V�X�e���B���̂ق��A��Ƃ�ƒ낪�K�X���g������[�⎩�Ɣ��d�A�Z��p���z�����d�Ȃǂ̐ݔ�������ꍇ����p�̈ꕔ��⏕������j�B ���N�x�̕�\�Z�ĂŁA�֘A�\�Z�v����߂����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���d�͎��R���ŕ��Ɛi�ޕč����v�}�����T�[�r�X�̈�� �č��ł́A���v�}���ɑ���v�������{��������I�ł���A���ɓd�͉�Ђɑ��Ď��v�}���̃T�[�r�X������Ƃ����݂��A���̂�������Ă���B�ăG�i�[�m�b�N�Ђ����̈�B���Ђ́A���v�}���ɋ��͂����Ƃ����ă��X�g�����Ă���B �d�͎��v���������l�������ɂȂ�Ɠd�͉�Ђ��G�i�[�m�b�N�ЂɃA���[�g�i�x���j���o���A�G�i�[�m�b�N�Ђ͎��Ђ̃��X�g��ƂɎ��v�}����v�����āA�d�͎g�p��}����B�d�͉�Ђ̓G�i�[�m�b�N�ЂɑΉ����x�����A�G�i�[�m�b�N�Ђ͎��v�}���ɋ��͂�����ƂɑΉ����x�����B �I�[�p���[�Ђ́A�ȃG�l�̂��߂̃A�h�o�C�X������҂ɗX���ő�������A�E�F�u�T�C�g��d�b�ŏ�������肵�āA�d�͎g�p��}������B����܂ŃI�[�p���[�Ђ̃\�����[�V�����������d�͉�Ђ́A���ς���2.5���̎��v�}���ɐ��������Ƃ����B ���l�Ƀe���h�����Ђ��d�͗}���T�[�r�X��S�Ă�30�Ђ̓d�͉�Ђɒ��Ă���B���[�^�[���ɂ���3000���ȏ�ŁA�e���͓͂d�͉�Ђ��傫���B ����A�č��̓d�͎��v�ɑ傫�ȕω��������炷�Ɨ\�z�����̂��A�d�C�����ԁiEV�j�̕��y���B�����ԂŒʋ���l�������č���EV�����y����ƁA�A���ɏ[�d���W�����āA�d�͎��v�̃s�[�N�����邱�Ƃ��\�z����A���ɂ�����������邽�߂̃\�����[�V��������Ă���Ă���B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/7�@]�@�@�� |
|
|
| ��NTT�����{�E�I�������ƒ�����ȃG�l�x�����s�����ى�Ђ�ݗ� �ʐM�Ɛ����A�g�����邱�ƂŁA��ʉƒ�̏���d�͂⑾�z���p�l���ł̔��d�d�͂��u�����鉻�v����ƂƂ��ɁA�ƒ���ł̏ȃG�l�y��CO2�팸���T�|�[�g����e��T�[�r�X�����B���ى�Ђ̎��{����4.5���~�A�o���䗦��NTT�����{��66���A�I��������34���B ��Ȏ��Ƃ̓��e�́A�i1�j�ƒ�ł̏���d�͗ʂ⑾�z���p�l���̔��d�d�͗ʂ��ȈՓd�̓Z���T�[��\���[���A��pWeb�T�C�g���g���āu�����鉻�v����T�[�r�X�̒Ƌ@��̔̔��B�i2�j�����N���W�b�g�F�؈ψ���珳�F�����A���z�����d�ɂ��CO2�r�o�팸�ʂ�c�������@�őn�o���������N���W�b�g�i�r�o���j�𗘗p�������ۑS�����B�i3�j�ƒ�̑��z�����d�ɂ�锭�d�d�͂��l�b�g���[�N�ƃZ���T�[���g���Č����T�[�r�X�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��NEC�����Ȃ���ƃf�B�X�v���C�����I�t�A�ߓd�@�\�[���̖@�l����PC���� �@�l�����m�[�g�Ƃ��Ă͍����ŏ��߂ĂƂ������ȃZ���T�[�𓋍ځB���[�U�[���ƂɈقȂ�p���╞���Ȃǂ̕ω���c�����A�ݐȁ^���Ȃ��������x�Ŋ��m���ăf�B�X�v���C���I���^�I�t����B �m�[�g�^�C�v�́A�d�������炩���ߐݒ肵�����ԂɎ����I�Ƀo�b�e���[�ɐ�ւ���u�s�[�N�V�t�g�v�@�\���\�t�g�E�F�A�Ŗ�������\��B�܂��A���[�U�[�̎g�������w�K���Ė��ʂȓd�͂��팸����Ƃ����\�t�g�u�G�l�p��PC�v��3�J�������̌��ł�Web�T�C�g�ŒB�I�v�V�����ŁA�ҋ@�d�͂�}���邽�߂�AC�A�_�v�^����̓d�����J�b�g����uAC�茳�X�C�b�`�v�����B1���̏���d�͂��ő��84���팸�ł���Ƃ����B �o�T�uITmedia News�v |
|
|
| ���{�d�ƍH��A�d�g��d�C�ɍ������ŕϊ�����Z�p���J���� �p������Ă����d�g�G�l���M�[�������I�ɍė��p���邽�߂ɁA�d�g(�����d��)��d�C(�����d��)�ɕϊ�����Z�p(���N�e�i�mRectifyingantenna�n�Z�p)��p���A��������(2GHz�тɂ�����90���ȏ�)�A�y�є��^(����0.2�g���ȉ�)�̌y�ʉ����ꂽ�A���e�i���J���B�܂��A�ᑹ���E�������ȃt�B���^�ŁA������H����̕s�v�g�̍ĕ��˂�-50dBc�ȉ��܂łɒጸ���邱�Ƃɐ��������B �����g�𗘗p����@��Ŏg���Ȃ������d�g��d�͕ϊ����邱�Ƃő��u�̏���d�͂��ő�40���팸���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂��A���ꂽ�ꏊ�̓d�r�𓋍ڂ��Ȃ����C�����X�Z���T(�o�b�e���[���X�Z���T)�ւ������ŋ��d���邱�Ƃ��ł���B�����Ő��\���[�g����܂ő��d�ł��邱�Ƃ��m�F�����B�G�l���M�[�n�[�x�X�e�B���O(�����d)����ł̉��p�����҂ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���O�m�d�@�A�ߓd�ɐV��@�J�����Ől���c�����E�Ɩ��������� �r���S�̂̓d�͂��Ď�����V�X�e���ɃJ������g�ݍ��ނ��Ƃɐ��������B�Ď��J������p���邱�ƂŎ����ɂ���l���Ɣz�u�A���邳��c�����A�l�����Ȃ��G���A�ł͏Ɩ�����������A�ݎ��l���ɉ����ĊO�C�̗ʂ������������邱�Ƃ��\�ɂ����B���ۂ̖��邢�ꏊ�̏Ɩ����キ���邱�ƂȂǂ��ł���B �Ď��J�����P��ŏc20���[�g���A��20���[�g���͈̔͂��J�o�[�B����ɋƏƖ��͈̔͂�F�����������ŁA�������������̃G���A�ɋ敪�����A�Ⴆ�ΐl������]�[�������Ɩ���_������B���̎���̃G���A�̏Ɩ��𔖂����A����ɂ����艓���G���A�͏�������Ƃ��������߂��\�ɂȂ�B�H��̃I�t�B�X�G���A�Ȃǂɓ��������Ƃ���A���ł�30���̏ȃG�l���ʂ�ꂽ�Ƃ����B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| ��Google��LED�ƊE�ɎQ���H Android�P�[�^�C�Ő���ł���LED�Ɩ����J�� 2030�N�܂ł̊��v���W�F�N�g�uClean Energy 2030�v�ŁA�����\�Ȗ����ɐ�i�I�Ȏ��g�݂�ϋɓI�ɍs���Ă��āAAndroid�Ő���ł���LED�d�����J�������B�ő�̓����́AAndroid�����ڂ��ꂽ�X�}�[�g�t�H���A�^�u���b�g�[���A���b�v�g�b�vPC���g�����R���h����ɂł��邱�ƁB �d���ɂ͖����ʐM���g�ݍ��܂�Ă���AGoogle�̖����l�b�g���[�N�v���g�R�����g���āAAndroid�f�o�C�X�ƒʐM����d�g�݁B����I��LED�d���́A2011�N12���A���E�Ŕ����J�n����錩���݁B���i�́A60W�����̂��̂ŁA20�`35�ăh�����x�B �o�T�u�O���[���Y�v |
|
|
| ���A���o�b�N���H�A90���̂�����3kW���̔��d���\�Ȕ��d�V�X�e�����J�� ���d�V�X�e���́A150���ȉ��̒ቷ�M���ŁA3�`12kW�̏��K�͔��d���y�g���b�N�ʼn^���\�ȃT�C�Y�A���ᑛ���ɂ��A�M���Ɏ�y�ɐݒu���邱�Ƃ�ڎw�������́B3�`12kW�̓d�͈͂�ʉƒ�Ɋ��Z����ƁA5�`20���ѕ��̏���d�͂ɑ�������Ƃ����B ����@�́A100mm�~800mm�~1400mm�̃T�C�Y�ŁA�d�ʂ͖�200kg�B�t�̂ƋC�̂̓ő��݂���쓮�}�̂�p���A�M�G�l���M�[���@�B�I�G�l���M�[�ɕϊ�����v���Z�X��1�ł��郉���L���T�C�N������Ȃ�A3kW���̉��^���^���d�V�X�e���ƂȂ��Ă���B �����Ɨ�p����p���Ĕ��d�������s�����Ƃ���A��Ƃ��āA����91���A����43L/min�A���x��69��(��p����22��)�ŁA�G�l���M�[������7.2%�A���d�o��3.8kW��B�������B �o�T�u�}�C�R�~�W���[�i���v |
|
|
| �����ꌧ���b�n�Q�r�o���������グ�ŐX�ѕۑS ���L�ьv119�w�N�^�[����2010�A2011�N�x��2�N�ԂŊԔ��B���Ȃ̐R���ƔF������A2012�N�x����r�o���Ƃ��Ĕ̔�����B �Ԕ��ɂ���āA�c�������͑��z������������Ő������A��葽����CO2���z������Ƃ���Ă���A875�g�����̋z���ʂ�440���~�O��Ŕ̔�����B����グ�́A�����̕ʂ̐X�т̊Ԕ���p�ɂ��Ă�l���ŁA�X�̍Đ���ʂ��Ēn�����g���h�~�Ɏ��g��ł����B 2008�N�x����X�ъ��ł����A�X�ѕۑS�Ɏ��g��ł��邪�A������̐l�H�т������B���X�ѐ����ۂ́u���NJx�E�L���C�̐X�Ԕ����i�v���W�F�N�g�v�Ɩ��t���A�����O�̊�ƂɍL�����͂��Ăт�����l���ŁA�u�L���C������Ă���X�̂��߂ɁA��Ƃ̗��������v�Ƙb���B �o�T�u����V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�ߓd�ڕW�B���̉ƒ��15���팸��LED��f��ӏ܌���i�悷�鐧�x������ �Ώۂ́A�����d�͊Ǔ��̉ƒ��1900�����сB6�����ɃC���^�[�l�b�g��ɐ�p�T�C�g�𗧂��グ�A���d�̌ڋq�ԍ�����͂���ƍ�N�ƍ��N�̏���d�͂��r���邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��A7������A����d��15���팸��B���������тɔ����_�C�I�[�h�iLED�j�d���̌������Ȃǂ́u�i�i�v��i�悷�鐧�x���n�߂�B �i�i�ɂ�LED�������̂ق��A�O�o���邱�ƂŐߓd�𑣂��f��ӏ܌��Ȃǂ������B�o�^���邾���ŏȃG�l�O�b�Y�����炦��Q���܂��݂�����j���B�o�Y�Ȃ͓��{�o�c�A������Ƃɋ��^�����߁A�i�i�Ȃǂ̋��͂����߂Ă���B �o�T�uSankeibiz�v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ̃G�l�����f�Ė��炩�ɋ@���Ɂu���S�v�lj� ����܂Ő���̊�{�����ɂ��Ă����u3E�v�i���苟���A���K���A�o�ό����j�ɉ����A�uSafety�i���S�j�v��V�@���ɐ�����B���q�͓͂��ʁA�K�����������܂ވ��S��Ɏ�����u���A3E�B���̏]���̈ʒu�Â����������B �Đ��\�G�l���M�[�E�ȃG�l���M�[�{�I�ɋ���������j�B�k�Е����v���W�F�N�g��A�S�ʔ��搧�x������ʂ��čăG�l�g��ɒ��͂���ق��A���s�̏ȃG�l�@���������A��ƂȂǂɏȃG�l�ƍăG�l�E�~�G�l���p�b�P�[�W�ŋ`���Â���@�K���̓�������������B�G�l���M�[���ƎҊԋ����𑣂����߁A�������x�≵�d�͎�����̌������Ɏ��g�ށB���v�Ƒ��Őߓd�����d�́i�l�K���b�g�j�̎�����A����̌������ڂɋ������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���s�ƍ�ʌ��A�r�o�ʎ���ŋ�̍�|�n��z���Ċ��p�\�� �����s�ƍ�ʌ��́A�������ʃK�X�̔r�o�ʎ�����x�ő��ݗ��p�ł���r�o�g�i�N���W�b�g�j�ɂ��āA���ߍ팸�ʂƒ����N���W�b�g��2��ނ��̗p����ƂƂ��ɁA���؎葱���̋��ʉ��𒌂Ƃ���A�g��̏ڍׂ��ł߂��B ���s���͎����̂̊_�����z�����r�o�ʎ���̓�����ڎw���Ă���B�����N���W�b�g��2012�N�x�������ł���悤�ɂȂ�B �ڍׂ��ł܂������ƂŁA��_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ̏���i�L���b�v�j��ݒ肵�A�ߕs���������Ə��ԂŎ���ł���L���b�v�E�A���h�E�g���[�h�^���x����s���̎����̂ɔg�y��������g�݂������o���B���s���ő��݂Ɏ���ł���悤�ɂȂ�r�o�g�̂����A���ߍ팸�ʂ�CO2�̑��ʍ팸�`������K�͎��Ə����ڕW�ȏ�ɍ팸�������B�`���̗��s���m�F��Ɏ���ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����R�G�l���M�[��26���{���ȏオ�A�g�� ���R�G�l���M�[���c��̓\�t�g�o���N�̑����`�В��������B���c���7����{�ɐ�����������\�肾�B �����{���B�Ȃǂ�19�������u���R�G�l���M�[���c��v�ɎQ����\�������B����A���{�̋����O�m������L��A���ψ����7�m���������ŋL�҉���J���A���l�̕��j�\����ƌ�����B���В��͂���ɐ旧��23���A�Q�c�@�̍s���Ď��ψ���ŁA�k������n�ɑ��z�����d�p�l�������݂��ēd�͕s����₤�u�d�c�i�ł�ł�j�v���W�F�N�g�v�̎��{���Ă����B �܂��A���q�͔��d�ɂ��āu10�N��ɂ͏��Ȃ��Ƃ��d�͈ˑ������݂̔������x�Ɍ��炳����Ȃ��v�Ƃ�����Łu������10�N�Ԃő����d�ʂɐ�߂鎩�R�G�l���M�[�̊�����20�����₷�ׂ��v�ƌ�����B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/6�@]�@�@�� |
|
|
| ���ʔ̃T�C�g405�A��d���������ł���[�d�����@�\�T�[�L�����[�^�[�� �t������2�̏[�d���o�b�e���[���t���[�d�����ꍇ�ɁA��^�]�Ŗ�12���Ԃ̑������s����B�t���[�d�ɕK�v�Ȏ��Ԃ͖�18���ԁB �܂��A��Ԃ̒�d���ɖ𗧂��P�xLED���C�g24����A������肷���i�Ƃ��Ă�FM���W�I�����ځB�{�̏㕔�Ɍʂ�`���悤�ɔz�u���ꂽLED�́A�L�͈͂��Ƃ炷���Ƃ��\�ƂȂ��Ă���BLED���C�g�݂̂ł͖�15���Ԃ̘A���_���AFM���W�I�݂̂ł͖�24���Ԃ̘A���g�p���\�B�܂��A��@�ALED���C�g�AFM���W�I�̑S�@�\�𗘗p�����ꍇ�ł��A��6���Ԃ̘A���g�p���s����B���i��9,800�~�B �o�T�u�}�C�R�~�W���[�i���v |
|
|
| ��Schneider��Micropelt�A�d�r�����s�v�̉��x�Ď��Z���T�������J�� ����J�����������Z���T�E�m�[�h�́A�G�l���M�[�E�n�[�x�X�e�B���O�Z�p�𗘗p�����B��d���𑗂銲���V�X�e���u�o�X�_�N�g�v�ɗ��p�����u�o�X�o�[�v�̕ێ�E�_���Ɍ��������́B �o�X�o�[�̗�ڍ����̊ɂ݂Ȃǂ����m���A�v���I�ȏ�Q���N�����O�ɕs��������o�����߂ɊJ�������B�o�X�o�[�̐ڍ����̊ɂ݂╅�H�́A���ׂ��|�����čŏI�I�ɒv���I�ȏ�Q���N�������O�ɁA��R���M�̏㏸�Ƃ��Č����B���̉��x�ω��̃f�[�^���Ŏ��W���ăo�X�_�N�g�̏�Ԃ�c�����A�̏�̃��X�N���y��������B �o�X�o�[�̕\�ʉ��x�����͂̉��x���5���ȏ㍂����A�����̔M�d�ϊ��f�q�̔��d�Ńo�X�o�[�̉��x�b���肵�ăf�[�^�𑗐M���邱�Ƃ��ł���B�M�d�ϊ��f�q�́A1���̉��x����140mV�̋N�d��������B�����ʐM�ɂ́AMicropelt�Ђ��v�����Ǝ��v���g�R���i���̗p���Ă���B �o�T�u���o�G���N�g���j�N�X�v |
|
|
| �����t�[�d�C�̎g�p���\���ł���u�d�C�\��v�����J �u�d�C�\��i�x�[�^�Łj�v�́A�����d�͔��\�̎g�p�O���t�̎��т�A���{�C�ۋ���\�̃f�[�^�Ȃǂ����ƂɁA���Ђ��Ǝ��̏W�v���@�ŎZ�o�������̂ŁA�u������24���Ԃ̐���d�͎g�p�v�Ɓu1�T�Ԑ�܂ł̐���ő�d�͎g�p���ԑт���юg�p���̗\�z�v�̏�����Ă���B ���Ђł́A�����{��k�Ќ��3��22�����A�����d�͔��\�̎g�p�̏����O���t�������u�����d�͂̓d�͎g�p���[�^�[�v���f�ڂ��Ă����B�{���[�^�[�ł́A�����\�͂ɑ��Ă̎g�p�ʂ��O���t�ɂ���ĉ������Ă���B�������A�g���݂̎g�p�h�Ƃ������тɊ�Â����߁A���A���^�C���ł̏�������A���f�ڂɍۂ��čő��1����20�����x�̒x�ꂪ�����Ă����B �����ŁA���Ђł͗��p�҂��������I�Ȑߓd�������ł���T�[�r�X�̒�ڎw���A����A�u�d�C�\��i�x�[�^�Łj�v�̌��J�Ɏ������B�{�T�[�r�X�́AYahoo!�f�x���b�p�[�Y�l�b�g���[�N��API�̌��J���J�n���Ă���B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���Ăɓ��{�R�J�E�R�[�������̋@25����̗�p��֔Ԓ�~ �Ă̐ߓd��Ƃ��āA�֓��n���̎��̋@��25����ŁA��p�@�\�����Ŏ~�߂�Ɣ��\�����B���Ԃ͂U����{�`�X�����B�g�p�d�͂��s�[�N����33���팸�ł���Ƃ��Ă���B �d�͎g�p�ʂ�������ߑO10���`�ߌ�9���ɁA���̋@���Ƃɗ֔ԂŁA�v5�`6���ԗ�p���~�߂�B����܂ł��Ă͌ߌ��3���ԁA��p���~�߂Ă������A��~���Ԃ������B��p���~�߂�ƁA�P�䂠����̎g�p�d�͂�300���b�g����17���b�g�Ɍ���Ƃ����B�S�����������H�Ɖ�ɂ��ƁA�����d�͊Ǔ��̎��̋@�͖�87����ŁA�g�p�d�͍͂ő��26���L�����b�g�B1���̏���d�͗ʂł͈�ʉƒ��25�����ѕ��ɂ�����Ƃ���A���̈����e�Ђ��팸�Ɏ��g�ޕ��j���B���̋@�������ẮA�����s�c���}���A�ߓd��w�͋`���Ƃ�����Ă��܂Ƃ߁A�ߑO10������ߌ�9���Ɏ��̋@�̗�p�@�\���~�߂�悤���߂Ă����B �o�T�uAshahi.com�v |
|
|
| �����y�C���g�A�����\�ʂQ�O��������ՔM�h����̔� �����ǂ��ԊO���˂������痿����h��h���Ɖ��h��h���ɔz���B2�w�ɂ��邱�ƂŁA��h��߂����ꕔ�̐ԊO�������h��Ńu���b�N����悤�ɂ��A�ƊE�g�b�v�N���X�̎ՔM�������������B����ɂ��A�����̕\�ʉ��x��10�`�\20�������āA�������x�̏㏸��}����B ��ĐF��20�킾���A����ȊO�̒��F���ł���B�܂��A�����ɓh�����ꍇ�̎������x��G�A�R������d�͍팸���ʂ̃V�~�����[�V�����\�t�g����������B���Ў��Z�ɂ��ƁA�������x�̏㏸��}���A�ď�̃G�A�R���g�p���̓d�C�������ő�40���팸�ł���Ƃ����B���i�͎{�H��݂�1�������[�g��������3300�`4900�~�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���X�r�����e�i���g�̓d�͏���c���E�V�X�e�����ȃG�l�x�����_�� �r���S�̂̎g�p�d�͗ʂ�6�`8�����e�i���g����߂Ă��āA�ȃG�l�ɂ́A�e�i���g�Ƃ̘A�g���������Ȃ��B ��������V�X�e���͕��d�Ղ̉ۋ��p���[�^�[����e�i���g���Ƃ̓d�͏���f�[�^���W�߁A�C���^�[�l�b�g�o�R�Ő�p�T�[�o�[�ɏW��B�e�i���g�͖����Ńl�b�g�o�R�Ńf�[�^���{�����Ď��Ђ̓d�͏�����m�F�ł���B�d�͏���f�[�^��1���Ԃ��ƂɍX�V����B�e�e�i���g�͎��Ђ̓d�͎g�p�̃s�[�N�ɂȂ鎞�ԑт̏���ʂ�c���ł��A�ߓd��𗧂Ă₷���Ȃ�B������p�͐��疜�~�K�͂ɂȂ���悤�����A�X�r�����S�z���S����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ƒ�ł�CO2�팸�Ɍ����x���A�L���s�Ŏn�܂� 2010�N�x�́A�O�N�����Ɣ�r�����d�C�E�s�s�K�X��11����12���A2�������̎g�p�ʂ��ΏۂƂȂ�B���O�ɎQ���\����������1000���т̂����A�g�p�ʂ�����s���Ɏg�p�ʍ팸�̗L���ɌW�炸HOPES��2�����x���B�팸��1�L���ɂ�5�~�ƌv�Z���A���v���Z�z��200�~�ȏ�̏ꍇ�͍팸�ʂɉ������������x�����A200�~�����̏ꍇ��HOPES���P�����x������B �ƒ�ō팸����CO2�팸�ʂ͍���A�s���̊�Ƃɔ̔����A��Ƃ͍w������CO2�팸�ʂ����Ђ̔r�o�ʂ��獷���������Ƃ��ł���B�Q�����i��20�Έȏ�̍L���s���ŁA�P�N�ȏ�p�����Č��݂̏Z���ŕ�炵�Ă���l�B�s�͗��N�x�ȍ~�A���Ԃ�K�͂��L���čs�����j��2012�N�܂Ŏ��{�̗\��B �o�T�u�W���p���t�H�T�X�e�i�r���e�B�v |
|
|
| ��NZ�A���R�G�l���M�[�X�O����ڕW�� �j���[�W�[�����h���{�́A�I�[�N�����h�k���ɉ������J�C�p���p�ɁA200���K���b�g�̏o�͂��\�ƂȂ钪�͔��d�������݂���v������F�����B ��������A25�����т̓d�͂�d�����E�ő�̎{�݂ƂȂ�B�j���[�W�[�����h��2025�N�܂łɓd�͋�����90�p�[�Z���g���Đ��\�G�l���M�[�Řd�����Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���A���͔��d���v�����邱�ƂɂȂ肻�����B ���ۃG�l���M�[�@�ւ�3���ɔ��\�����G�l���M�[�������ɂ��ƁA�j���[�W�[�����h��2009�N�x�Ɏ��R�G�l���M�[�������d�͋�����73�p�[�Z���g���߂Ă���B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| ���n���M�����{�̕⏕���[���ŋr�� �n���̉��x�͔N�����肵�Ă��āA�Ⴆ�Γ����Ȃ��ɖ�17���B�Ă͗������~�͒g�����B�n���M���p�̃G�A�R���́A��C�M���̃G�A�R���̖������d�͂�����Ȃ��B �g�[�ȏ�ɗ�[�ł̐ߓd���ʂ��傫���A�r�M���O�C�Ɏ̂ĂȂ����߃q�[�g�A�C�����h���ۂ̊ɘa�ɂ��v������B ����܂Ō@���q�[�g�|���v�ȂǏ����R�X�g�����y�̃l�b�N���������A���{�̕��j�ŏ������x���}���ɐ����Ă����B �o�T�u�I���^�i�v |
|
|
| ���o�c�A�A�ߓd����s���v��̒��ԂƂ�܂Ƃ߁A�Q�T�������唼 �����_�̎Q����Ɛ���543�ЁE�c�́B�Q����Ƃ̓���͓����E���k���d�͊Ǔ��̐�����281�ЁA���̑���262�ЁB�ߓd�ڕW�ł�35�Ђ��u25�����v�A383�Ђ��u25���v�A�������v�ƂȂǂ�99�Ђ��u25�������v�̓d�͎g�p�ʂ̍팸�ڕW�l���f�����B ��̓I���g�݂Ƃ��ẮA���ƌ`�ԁi��ԁE�������ƁA�y���̊��p�A�����{�G���A�Ȃnj��O�V�t�g�A�Ċ��x�ɂ̑�^���E���U���Ȃǁj�̑��l����Ɩ��E�G�A�R���A�G���x�[�^�[�̒����A�ȂǂőΉ�����X���������B�܂��A�~�d�r�̊��p�Ȃǂ������Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����ȁA�H��Ȃǂł̉������ʃK�X�팸��ߓd�Ɍ������f�f�����{��---��]���Ǝ҂����� ���̃v���W�F�N�g�ł́A���Ȃ���ϑ����ꂽ�@�ւ��H���r���ɂ�����ݔ��̓����E�^�p��f�f���ACO2�r�o�ʂ̍팸��ߓd�ɗL���Ǝv����ݔ��̓�����A�ݔ��^�p�̉��P�@�Ȃǂ��w�삷��B �d�͎������N�����Ă��邱�Ƃ���A���Ȃł͂��̂悤�Ȑf�f�̃j�[�Y�����܂��Ă���ƍl���A��N�Ɉ����������{���邱�Ƃɂ����B�f�f�͖����B ���̃v���W�F�N�g��ʂ��ē���ꂽ�m�����L���L�Ă������Ƃ���������B���{���Ԃ�2011�N6����{�`8�����{�B���N5�����珇����������J�Â���ƂƂ��ɁA�Q�����Ə������傷��B �o�T�uTech on�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/5�@]�@�@�� |
|
|
| ���x�m�ʃR���|�[�l���g�A���������ʂɏ���d�͂��u�����鉻�v����d���^�b�v���� �X�}�[�g�R���Z���g�́A����������4�����A4���v��1500W�܂łȂ�����B�e�����������Ƃ�1W�P�ʂŏ���d�͂����o���A���o�����f�[�^��USB��ʂ��ďo�́B�t������ȈՑ���\�t�g���g���ăf�[�^���p�\�R���ɕ\������B�e���������̏���d�͂̍ő�l�A�ŏ��l�A���ϒl��������B ���o�����f�[�^���l�b�g���[�N�o�R�Ō�����悤�ɂ��邽�߂̋@����ʔ���ŗp�ӁB���Ԃ�������Ǘ�����X�P�W���[���\�t�g�ƘA�g���ăR���Z���g���p�҂̋Ɩ��Ə���d�͂��֘A�t���ĕ\�����A�g�p�҂ɏȃG�l�s���𑣂���B�e���������ɂ́A�d���̃I���E�I�t�X�C�b�`������B�X�}�[�g�R���Z���g�{�̂̏���d�͍͂ő�0.5W�B�I�t�B�X�Ŏ��p�������s�����Ƃ���A����d�͂�15���팸�ł����B �o�T�uECOJAPAN�v |
|
|
| �����m�{�̐V�m�[�gPC�A�d�̓s�[�N���Ƀo�b�e���[�쓮�ɐ�ւ� ��ƌ����m�[�g�p�\�R���uThinkPad�v�ɂ���4��ނ̃V���[�Y�ŐV�@��\�����B�V�@��͂��ׂāA�o�b�e���[�Ǘ��@�\�̈�Ƃ��āu�s�[�N�V�t�g�@�\�v�𓋍ڂ���B PC�̃o�b�e���[�쓮 or AC�d���쓮���A�X�P�W���[���Ɋ�Â��Đݒ�ł���B�d�͏���s�[�N�ɂȂ鎞�ԂɃo�b�e���[�쓮����悤�ɂ���A�d�͎��v�̕��U�������҂ł���B�s�[�N�V�t�g�@�\��ThinkPad�̓����\�t�g�ł���u�ȓd�̓}�l�[�W���v�Őݒ肷�邪�A�����@��̓A�b�v�f�[�g���Ă��s�[�N�V�t�g�@�\�ɂ͑Ή��ł��Ȃ��B �o�T�uITpro�v |
|
|
| �����c���쏊�Ȃǂ��~�d��4�{�̃|�X�g�u���`�E���C�I���d�r�v�Z�p���J�� ���ݎ嗬�̃��`�E���C�I���d�r�͓d�ɂ̕��q1�ɂ�1�̓d�q��d�ɂɕ��o����B�V�d�ɂ́A�����⒂�f�A�Y�f���听���Ƃ���u���x�A���_�v�ƌĂԗL�@�ޗ������Ƃɐ��ɂ��쐻�B �d�r���������d�������œK�ɂ���A�d�ɂ̕��q1���畡���̓d�q����o�����邽�߁A���e�ʂ̓d�r�����������B�ȒP�Ȏ����p�d�r�����A���\�ׂ��Ƃ���A���ɍޗ�1kg�������600A�Ə]����4�{�̓d�C�����߂�ꂽ�B���q�\����ς��邱�ƂŁA����ɐ��\�����߂��錩���݁B���\����ƕ��s���Ē��������ɂȂ���Y���܂Ȃǂ��T�����j�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���G�A�o�X���o�C�I�R���̊J���ɒ��� ���q�@�̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�K���͍��㋭�������Ƃ݂��A�q��@���[�J�[���Ή��𔗂��Ă���B�v��ɂ̓��[�}�j�A�̃^�����q���u�J���X�g��w�A�o�C�I�}�X�R���֘A��ƂȂǂ��Q������B �J�����i�ƌĂԐA���������ɂ����o�C�I�P���V���ŃG�A�o�X�̋@�̂��s�����A�G���W���ւ̉e����R��A�o�ϐ��Ȃǂ�]������B ���[�}�j�A�ł̓J�����A�̌��ʓI�ȍ͔|���@��o�C�I�P���V���̐����@�̌�����i�߂�B���n�ł̐��Y�\�͂������A���Ɖ��Ɍ����Đ����Z�p�ƈ��苟�����m������B�J�����A�̓��[�}�j�A���Y�̐A���ŁA��v�Ő����������G�l���M�[�ܗL�ʂ������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���O�H�d�@�A�d�C�q�[�^�[�g��Ȃ��ȃG�l�^�̗��������E�g�[�V�X�e�� ���̗��������E�g�[�E���C�V�X�e���̍ő�̓����ƂȂ�u�������v�́A���C�̕��Əz�����镗�̕��ʂ̃o�����X��ς��邱�ƂŁA�����̗͂����œ�����̗���������������B �d�C�q�[�^�[�ł̉��������Ɣ�ׂ�ƁA�������Ԃ�2�{��3���Ԃɉ��т���̂́A����d�͗ʂ�0.17kWh�Ɩ�10����1�ɂȂ�A�����g���Ă�1�����̓d�C���100�~���x�ł��ށB��������̊������ɗ��p����ߗފ����ł́A�V�@�\�̏ȃG�l�����œd�C�q�[�^�[�̏o�͂�}������B2kg�̐��̊������Ԃ�3����40���ƁA�]���@��2����20����蒷�����A�����ŕK�v�ɂȂ����d�͂�15�����Ȃ��Ȃ�B�o�͂�}�������₩�ȉ����Ŋ��������邽�߁A�f���P�[�g�ȑf�ނ̈ߗނɂ��K���Ă���B �o�T�uECOJAPAN�v |
|
|
| �������A������ő��z�����d��{�i������ ������̉��ݎ������̉����Ȃǂɑ��z���d�ݔ���ݒu���A�������̎g�p�d�͂̈ꕔ�ɏ[�Ă�v���W�F�N�g��2011�N�x����{�i�W�J����B 3�N���50�ȏ�̌���ŔN��15��kWh�̔��d��ڎw���B�u�����g����de�\�[���[�h�v���W�F�N�g�v�Ɩ��t����2010�N�x�ɒ��肵�Ă����B ����14�̌����60kW�̑����d�e�ʂ�����A����A�S���e�n�̌�����ɓ������Ă����B ���̃v���W�F�N�g�́A���z�����d�p�l����������Ɏ��t���A���d�����d�͂𗘗p���邱�Ƃ�CO2�r�o�ʍ팸�ɂȂ���B�p�l����1�̌��ꓖ����3�`4kW�ŁA���ꂽ���Ȃ�1����10�`20kWh���d�ł���B�ݒu�K�͂ɂ���ĈقȂ邪�A�������Ŏg���d�͗ʂ�10�`20�����x�ɂȂ�B �o�T�uECOJAPAN�v |
|
|
| ���C�M���X�A�Đ��\�G�l���M�[�M������萧�x�̏ڍׂ����\ �G�l���M�[�E�C��ϓ��ǂ́A�Đ��\�G�l���M�[�ɂ��M���Y�ɑ��锃�����⏞���߂��u�Đ��\�G�l���M�[�M�C���Z���e�B�u�iRHI�j�v�̏ڍׂ����\�����B ������2�i�K�ōs���A�܂��͑�K�͏���҂ł���Y�ƁA���ƁA���I������A���ɉƒ땔���Ώۂɂ���Ƃ��Ă���A�o�C�I�}�X�ݔ��⑾�z�M���p�ݔ��A�o�C�I���^���ݔ��Ȃǂɂ��M���Y�ɑ��A1kWh������̔�����艿�i����߂��Ă���B�C�M���X�ł́A�������ʃK�X�r�o�ʂ̔������M���Y��v���Ƃ�����̂ł���A���d�ɂ��r�o�ʂ��������Ȃ��Ă���BRHI�̓����ɂ��A2020�N�܂ł�4400���g���̉������ʃK�X�̍팸�A���̕���ɂ�����15���l���̌ٗp�̊m�ہA8��6000���|���h�̗\�Z�ɂ��2020�N�܂ł�45���|���h�̊������̑n�o�A�Y�ƁA���ԁA���I����ɂ�����M�����ݔ��̓����ʂ�2020�N�܂ł�7�{�ɑ���������Ƃ��Ă���B �o�T�uEIC�l�b�g�v |
|
|
| �����B�ψ���A���z���̃G�l���M�[���p���������߂�v���W�F�N�g�\ �v���W�F�N�g�uEnergy Efficiency Plan�v�́A2020�N�܂łɊe��̃G�l���M�[���p������20���܂ō��߂�Ƃ����ڕW���f���Ă��邪�A�܂��A�]��ł���قǂ̃G�l���M�[�����������ł��Ă��Ȃ����߁A���g�݂��������Ă����Ƃ����B �����̃G�l���M�[���p���������シ�邽�߂ɍs�����z��A�X�}�[�g�O���b�h/�X�}�[�g���[�^�[�̓������x������Ƃ����BEU����̃G�l���M�[���p��40���́A���z�����甭�����Ă���B���v�����ł́A���{�Ȃǂ����p������p���z����3�����A���N���z���Ă����ڕW���������B����ň�ʂ̃r���⌚�z���ł��G�l���M�[���p�������Ɍ��������z���x�����邽�߁A���炩�̋K����������j�B�Ȃ��ł��A�G�l���M�[�������Ǝ҂����̌ڋq��Ƃ̌��z�������z���邽�߂̏����Ȃǂ��Ă��Ă���B���z�����ŗ��p���鑕�u�̃G�l���M�[���������シ�邽�߂̋K�����������Ă���BEnergy Efficiency Plan�̎����ɕK�v�Ȋe��@�ẮA2011�N�Ă���ɉ��B�c��ɒ�Ă���\��Ƃ����B �o�T�uBP�l�b�g�v |
|
|
| ���ƒ�̐ߓd�����u�d�C�\��v�����@���āA�o�Y�Ȃ����� �����d�͊Ǔ��œd�͕s�����\�z����鍡�āA�o�ώY�ƏȂ��A�e���r��W�I�œV�C�\��Ȃ�ʁu�d�C�\��v�̕������������Ă���B �d�C�\��̓j���[�X�ԑg�Ȃǂŕ��������V�C�\��ɑ����āA�����◂���̓d�͂̎��v�Ƌ����̗\�������ԑѕʂɓ`������@���������Ă���B�ҏ��œ����Ɏ��v�����܂肻���ȏꍇ�A�u��[�̐ݒ艷�x���グ�āv�u�g��Ȃ��Ɠd���i�̓d�����āv�Ƃ������R�����g���Y���A�����҂ɐߓd������悤���ӂ𑣂��B���v���}�ɒ��ˏオ���ċ���������A�\�����ʑ��d���N���肻���ɂȂ�A�u�j���[�X����v�œd�͎g�p���������ɍT����悤���߂�e���b�v�𗬂��Ă��������Ă���B�V����C���^�[�l�b�g�ł��A�d�C�\�ł��Ȃ�����������B����ɁA�����̂ɂ��[��������w�Z����ł́u�ߓd����v���i��ʂ��āA�s�����x���Őߓd�ӎ��̐Z����}����j�B �o�T�uAsahi.com�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/4�@]�@�@�� |
|
|
| �������K�X�ƃp�i�\�j�b�N�͉ƒ�p�R���d�r�u�G�l�t�@�[���v�̐V���i�� �V���i�́A��i���d����40%���������A���E�ō��̒�i���d����37%�ȏ��L�������s�i�����A����ɔ��d���������コ�����B�܂��A���d���s�Ȃ��u�R���d�r���j�b�g�v�̃V�X�e���\���̑啝�Ȋȑf����}��ƂƂ��ɁA���d���s�Ȃ��u�X�^�b�N�v�Ȃǂ̊���i�����^�����邱�ƂȂǂɂ��A���s�i������70���~�ቿ�i�́A��]�������i2,761,500�~�i�ō��A�ݒu�H����ʁj�����������B �Η͔��d������̓d�C�ƁA�s�s�K�X�����g�[�@����̋����E�g�[���s�Ȃ������Ɣ�ׁA�u�G�l�t�@�[���v�́A��i���d����CO2�r�o�ʂ��48���팸�A�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��35���팸�ł���B�܂��A�N�Ԃ̌��M����5�`6���~�ߖ�A�N�Ԃ�CO2�r�o�ʂ��1.5�g���팸�ł��錩���݁B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ��3��̓d�r�������G�R�Z���3�N�Ԃ̋��Z���؎��� ���K�X�Ɛϐ��n�E�X�͓d�r��g�ݍ��킹�ďȃG�l��}��G�R�Z��u�X�}�[�g�G�l���M�[�n�E�X�v�̋��Z�������J�n����Ɣ��\�����B ���Z�����Z��́A700W�̔R���d�r��5.08kW�̑��z�d�r�A�~�d�e��3.5kWh�̒~�d�r��ݒu����B2014�N3���܂�3�N�Ԃɂ킽���ĉƑ�3�l�����ۂɐ������A���ۂ̋��Z���ł̏ȃG�l�A���K���E�����̌���̎��Ɏ��g�ށB �܂��A�����Z��ɂ́AHEMS�i�z�[���E�G�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���j�A���g�[�ALED�Ɩ��Ȃǂ̐ݔ�������A��������ȂǂŏȃG�l������B����ɋ��Z�҂����p����d�C�����Ԃ̒~�d�r���u�^�~�d�r�̑�ւƂ��ė��p���A�d�C�����Ԃ��܂߂�CO2�r�o�ʂ����������[���ɂȂ�V�X�e����ڎw���B2015�N�ɂ͎��p���x���̊Ǘ��E����Z�p�̊J�����������A�s�ꓱ����i�߂����l���B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| ���J�l�J���E���A5�F�̗L�@EL�Ɩ��f�o�C�X�������Ɖ��B�Ŕ̔� ���E�ŏ��߂Ĕ��i���g�F�j�A�ԁA��A�A��5�F�����C���A�b�v�����L�@EL�Ɩ��f�o�C�X���A�����ł�3��22������A���B�ł�4�����{���珤�Ɣ̔����J�n����B ���X�g�����E�z�e���Ȃǂ̓X�Ɩ���A�����Z��p�̏Ɩ��ȂǍ����i�s��𒆐S�Ɏ��Ƃ�W�J���A���\����ƃR�X�g�_�E����}��A��ʂ̏Z��E�I�t�B�X�Ɩ��⎩���ԓ����Ɩ��Ȃǂ̎s��ɂ����Ƃ��g�傷��B�L�@EL�Ɩ��́A���^���ł��f�U�C�����������A���g�F�̂��炩���F��������A�Ȃǂ̓����̂ق��A�ʌ����Ŋg�U�Ȃǂ̌��w���ނ��s�v�A�G�l���M�[�����������ȃG�l�A������g�p���Ȃ����ߊ��ɗD�����A�Ȃǂ̃����b�g�����킹���B���ɉ��B�ł͔��M���̂悤�Ȃ��炩���F�����D�܂��X���ɂ��邽�߁A�f�U�C���Ɩ��s��𒆐S�ɔ̘H�J����s�����j�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���t�W�N���u�������Ŕ��d����F�f�������z�d�r���W���[�����J�� �F�f�������z�d�r�́A���ݎs�̂���Ă��鑾�z�d�r�Ƃ͌������قȂ�A�A���̌������Ɏ��������w�����Ɋ�Â��Ĕ��d����B�]���̑��z�d�r�����Ƃ��鎺�����i500lux�ȉ��j�ɓK�����Ɠx�p�F�f�������z�d�r���W���[�����J�������B �����Â������ł��Z���T�̓d���Ȃǂւ̗��p���\�ȃG�i�W�[�n�[�x�X�e�B���O�p�r�Ɍ��������z�d�r���W���[���Ƃ��āA2011�N�x�ɃT���v���i�̒��J�n����\��B �{���W���[���́A��ʓI�Ȍu�������ł���200lux���x�ł́A5cm�p�i25cm2���x�j�ŁA210��W�̏o�͂�����ꂽ�B����́A���̃^�C�v�Œ���ʂɋ����A�����t�@�X�V���R���^�̑��z�d�r����1.3�{�ȏ㑽���B�܂��A���Ȃ薾�邢���ł���3000lux���x�̌u�������ł́A1m2������120��W�̏o�͂�����ꂽ�B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���G���e�B�[�A�C���Z�u��-�C���u���ɗU�����̑�֕i�����J�n ���N���ɏ��h�����A�Вc�@�l���{�t�����`���C�Y�`�F�[�������̗v�]���A���ւ̈ӎ������܂钆�A�����S�����m�ۂ�����ŁA���Ǝ҂̃j�[�Y�ɍ��킹���K�������̕K�v��������Ɣ��f���A�@�߉����Ɏ������B���̉������h�@�ɓK�������X�e�b�J�[�^�C�v�̏��h�ݔ��F��W���������B �u���U�����v�͓d�C���g�p��365��24���ԓ_�����āA����I�Ƀo�b�e���[�̌�����v���邽�߃o�b�e���[���A���i�ێ��҂ɂ�������Ƒオ�K�v�B����Ɉ��������A���P�x�~�����U���W���́A���i���i��7,800�`15,300�~�ƁA�U������30,000�`100,000�~�Ɣ�r���Ă������ŁA�ݒu�́u�\�邾���v�A�u�ێ��R�X�g�[���v�̉���I�Ȑ��i�B �o�T�uAsahi.com �v |
|
|
| ��INAX�����E�ŏ����ʂ̒��ߐ�4���b�g���^�C�v�� 4���ɔ�������u���ߐ�ECO4�v�g�C���͂P��ɗ������̗ʂ�4���b�g���ƁA���C�o��TOTO��4.8���b�g�����X�V���鐢�E�ŏ����ʃg�C���B �^���N���X�^�C�v�ł͓��ꍇ�����g�����d���o�l�Ő��������͉��B�^���N������^�C�v�ł́A�ʏ��i�Ŕr�����ɗ���鉹��}���邽�߂ɍ̗p�ς݂�������C����V�X�e����ߐ��p�r�ɓW�J�A�����̋�C����V�X�e����d��������@�B���ɂ����B�@�B���ɂ������Ƃœd�����Ȃ��ꏊ�ɂ��ݒu�����₷���B13���b�g���^����4���b�g���^�ɕς���ƁA�N�Ԗ�1��4700�~�̐����オ�ߖ�ł���Ƃ����B �������̖R�����č��⒆���ł�6���b�g���ȏ�̃g�C���͐��Y�E�̔����ł��Ȃ��ߐ��K��������B�č��ł͍��N�A�J���t�H���j�A�B�ł���Ɍ�����4.8���b�g���K�����n�܂�B �o�T�u�_�C�A�����h�E�I�����C���v |
|
|
| ���C�g�[���[�J�h�[��CO2�팸���ʂ̂���₽���u�����uCCFL�v�̓��������� LED�Ɩ��Ɠ����ȏ�̒����d�́A�������ɂ��CO2�r�o�ʂ��팸���A�����R�X�g���啝�ɒጸ�\�ȁuCCFL�v�u������2010�N11��������؎��������{���A4������̓��������肵���B LED�Ƃ̔�r�ɂ��A�]����LED�ł͉����ł��Ȃ������Ɠx��̖����Ȃ��A�����ȓ����R�X�g��CO2�팸���\�ɂȂ����B ��ʂ̌u�����͓d�ɂ����M���邱�Ƃɂ��A�d�q����o����̂ɑ��A�uCCFL�v(Cold Cathode Fluorescent Lamp�F��A�Ɋ�)�͉��M�����ɓd�q����o����B���̂��߁A�uCCFL�v�͓_�ʼnɂ��������Ȃ��A�����d�͂̂��߁A�����v�̉��x�㏸��ጸ�ł��A��i�����͖�50,000���ԁB���݁A�m�[�g�p�\�R����t���e���r�̃o�b�N���C�g�Ƃ��đ����g�p����Ă���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����Ă���u�D�拋�d�v�ց\���z���E���͔��d�o�Y�ȁA�Đ��G�l�g��œd�͌n�����[�������� �����G�l���͍Đ��\�G�l���M�[�d�������g��̂��ߓd�͉�Ђ̑��z�d�n���ւ̐ڑ��E���d�ɂ�����郋�[���{�I�Ɍ������A���͔��d�Ƒ��z�����d�ɗD�搫����������u�D�ʋK��v������B �d�͂̋����͗]�莞�̑�Ƃ��āA���苟���Ɏx����y�ڂ��Ȃ��͈͂ŁA�d�͉�Ђ����B����50kW�ȏ�̎��Ɨp�d�́A���z���̏o�͗}�����u�Ō���v�Ɉʒu�t����B�Ɨp�̏Z��p���z�����d�Ȃǂɂ��ẮA�S���x�[�X�ő��z���̓����ʂ�1�疜kW���x�ɒB����܂ł̓��ʂ̊ԁA�o�͗}���̑Ώۂɂ��Ȃ����j�B ���B�ł͂��łɍĐ��G�l���M�[�̗D�拋�d����������Ă���A���G�l���M�[�̕��y�ɂȂ����Ă���B �o�T�ugreen plus�v |
|
|
| �����nj`LED�����v�ɐV���ȓ�����2�A��3�̋K�i���a���� ��N�A���{�d���H�Ɖ�͒��nj`LED�����v�V�X�e���̋K�i�𐧒肵���B ����A�O�H�d�@�I�X�����͓Ǝ������̐��i�����Ă��āA���̕��������݁A�H�Ɖ�ŐR�c�����B�A�C���X�I�[���}���Ǝ��ɊJ���������S���u�t�����nj`LED�����v�����A�H�Ɖ�ɋK�i�����Ă���l���B���{�d���H�Ɖ�́A���S�ŕi���I�ɗD�ꂽ��Ă�����K�i�����Ă������j�ŁA���nj`LED�����v�Ɋւ��ĕ����̋K�i����������\��������B ���nj`LED�����v��10�N�ȏ�ғ�����̂ŁA�����̌u�����̂悤�ɕp�ɂȃ����v�����͕s�v�Ȃ��߁A�����v���������ւ���ۂ̌݊����͂���قǏd�v�ł͂Ȃ��B�����̋K�i����������ƍ����������ƍl�����������A���p�҂ɂ͂ނ���v���X�ʂ������B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| ������23�N�x�u�ȃG�l�Ɠd�������ɂ���_���Y�f�r�o�팸�v���E�F�؎��Ɓv �ƒ땔���CO2�r�o�팸�̂��߂ɂ́A�ȃG�l�Ɠd���i�ւ̔������͋ɂ߂ėL���ł���A�������ɂ��팸�����CO2�r�o�ʂ�]�����A�N���W�b�g�����Ă������Ƃł���Ȃ�ȃG�l�Ɠd���i�̕��y�𑣂����Ƃ��K�v�B �{�ϑ����Ƃɂ����ẮA�ȃG�l�Ɠd���i�ւ̔������ɔ���CO2�r�o�팸�ʂ̐��m�Ȕc���Ɋւ���Z�p�I�_�_�A�v�����@�ɂ��������s���ƂƂ��ɁA�e�ƒ�ɂ�����팸�ʂ̑�����s���A�팸���������N���W�b�g�����邱�Ƃ�ڎw���B �Ώۋ@��̓e���r�A�G�A�R���A�①�ɂ�3�i�ځB����̒n��ɂ����āA�Ώەi�ڂ̔��������s���A�N���W�b�g���ɏ\���ȍ팸�ʂ��m�ۉ\�Ȍ����A���Ȃ��Ƃ���450���i�e�i�ږ�150�����x�j�͌v���@������t���팸�ʂ̎������s���B �o�T�u�v���X�����[�X�v |
|
|
| �������A�ȃG�l���i�S�l��łT�J�N�v�� �����͕č��ƕ��Ԑ��E�ő�̃G�l���M�[����ƂȂ�A�����̗A���ˑ��x�̋}�㏸�ɑ��Čx���������܂��Ă���B �ȃG�l�������������A���������̊Ǘ��ƊJ���������BGDP������̏ȃG�l�ڕW�͑O5���N�v���20���팸���16���팸�Ƃ����B�v��ʂ�GDP��7����������ƒ����S�̂̃G�l���M�[����ʂ�2015�N�ɂ�2010�N��Ŗ�2��������B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| �����Ȃ̒������ʂł́A�d�͂̉����͉ƒ�ł͌��ʂ����� 2010�N11�`12���Ɉ�ʉƒ��200���т�ΏۂɁA�d�͂̉����V�X�e���̓����̗L���ŁA�ǂ̒��x�d�͏���ω����邩��r��������������s�����B �H����~�ւ̕ς��ڂł�����A���O���[�v�Ƃ��d�͏���ʂ͑��������B�������́A�J�n��1�T�ڂł́A�����V�X�e�������Ȃ��������т�14���A�������Ȃ��������т�16���������B�J�n3�T�ڂł͉����V�X�e���������т̕����d�͏���ʂ̑�������10���������Ȃ����B�����V�X�e���������т��A�u�d�͏���̎��Ԃ��ƒ���Řb��ɂ��Ă���v�O���[�v�Ɓu���Ă��Ȃ��v�O���[�v�̔�r�ł́A�u���Ă��Ȃ��v�O���[�v�̕����傫���������A����10�����Ȃ������B�������ʂ���A�d�͏���̎��Ԃ�m�邱�ƂƁA�ƒ�̏ȃG�l�s���̊Ԃ̑��ւ͏������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2011/3�@]�@�@�� |
|
|
| �������v�����g�e�N�m���W�[���z�M�����p�����ȃG�l�V�X�e�����J�� �Ǝ��̑��z���W�M����̗p�����V�X�e���u���z���M���p�V�X�e���v���J�������B �|�C���g�ƂȂ鍂�����̃p���{���g���t�����z���W�M��́A����V���ɓƎ��J���������́B���W�M��́A�V���v���ő��삵�₷���\���ɂ���ƂƂ��ɁA�V�~�����[�V�����Z�p��p���āA���Ȃǂ̉e���ɂ��œ_�̃Y����}������\���ɂ����B�W�M���������߂Ă��鑾�z���W�M�킩����o�����M�G�l���M�[�Œ��ڗⓀ�@���쓮�����āA�p�̗␅����������B����ɂ��A���ΔR����CO2�r�o�ʂ̍팸���\�ɂȂ�B����A��ɒn���C���݂�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̓��Ɨʂ̑����n��𒆐S�Ƃ��āA�r����H��A�n���[�����ɐϋɓI�Ɋg�̂�ڎw���B �o�T�u�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ��UR�s�s�@�\��K�͂ȏȃG�l���𐄐i�A���p�Ɩ�100�����LED���Ȃ� �u�Ɩ���LED���v�ł́A�S����76���˂̒��ݏZ��ɂ����āA���p�L����K�i�A���O�����ȂNj��p�����̏Ɩ�����100���������LED������B����ɂ��A2020�N�x�ɁA�N�ԓd�͏���ʂƂ��Ă͖�12,800���ѕ��̏���ʂɑ��������4,600��kWh�̍팸�������ށB ������́A���^�ɔ�ׂĖ�15�������������ȃG�l�^�u�G�R�W���[�Y�v�Ɏ�芷���A2020�N�x�ɔN�ԂŃK�X����ʖ�370��m3�ACO2�r�o�ʂ͖�8,500t�̍팸�������ށB �u�̃J�[�e���v�́A�����������̊ɘa�ɂ��A2�����x�̎������x�}�����ʂ�����A8���̓d�C�g�p�ʂ�2�����x�ጸ����Ȃǂ̒������ʂ�����Ă���B ���̑��̎��g�݂ł́A��p�Z����ւ̃s�[�N�A���[���@�\�t���d�Ղ̐ݒu��A�G���x�[�^�̃C���o�[�^�[����i�߂�B�G���x�[�^�̃C���o�[�^�[���ł́A2020�N�܂łɔN�Ԃ�CO2�r�o�ʖ�640t�̍팸�������ށB�����̎��g�݂ɂ��A10�N���2020�N�x�ɁA�ő�ŔN�Ԗ�27,000t��CO2�r�o�팸��ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������ʼnƒ�̓d�͊Ǘ�100�����тɃX�}�[�g���[�^�[ �d�͊e�Ђ͏��Z�p���g���ēd�͂������I�ɋ������鎟���㑗�d�ԁi�X�}�[�g�O���b�h�j�̎����Ɍ����A2012�N�x����ƒ�̓d�͏�����ʐM�ŏ�ɔc���ł��鎟����d�͌v�i�X�}�[�g���[�^�[�j��{�i��������B �����Ȃ�2012�N�ĂɃX�}�[�g���[�^�[��p�̎��g���т����蓖�Ă���j���ł߂����Ƃ��A2012�N�x���ɖ�100�����тɐݒu����B2020�N�����h�ɑS���̖�5000�����тɕ��y������v��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����Ɏq�A�d�C�s�g�p�Ō��I��h�~������z���^�Ⓚ�V���[�P�[�X�p�h�A�� �R���r�j�A�X�[�p�[�̃V���[�P�[�X�͐ݒ艷�x���Ⴍ�A�K���X�̃h�A�\�ʂ̌��I��h�����߂ɓd�C��ʂ��ĕ\�ʂ�g�߂�K�v������B�e�Ђ���̗v�]���ĊJ���ɒ���B�f�M���\����������ȃK���X���g�p���Ēf�M�������߂邱�ƂŁA���ʓd���\�ɂ����B�ʓd�^�Ɣ�ׁA1�X�܂�1�N�Ԃɖ�1t��CO2�r�o���팸����B�Z�u��-�C���u���ō̗p���ꂽ�B �Z�u��-�C���u���́A����J�X����X�܂ł��̖��ʓd�^�̗Ⓚ�V���[�P�[�X�p�h�A��W���̗p����B���ɃZ�u��-�C���u���S�X�܂Ŏg����ƁACO2�r�o�팸�ʂ͔N��1��3000t�ɂȂ�B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���O�䉻�w�����g�������b�n�Q��������̃}�W�b�N ���^�m�[���͎������͂��߁A���i��R���d�r�A�@�ۂȂǂ̌����Ƃ��ĕ��L���g���A���E���Y�ʂ͔N��4000���g���ɒB����B���̖�9���͓V�R�K�X���������ē�����_���Y�f�iCO�j�Ɛ��f�������Ă���B ����ɑ��A�O�䉻�w�̋Z�p�͍����E��������CO2�Ɛ��f��������BCO2�͑��̕����Ɣ������ɂ����A�H�Ɨ��p������B�����œ���ȋ����G�}�ɔ����𒇗���������B����20���g����CO2��3���g���̐��f������A8���g���̐���15���g���̃��^�m�[����������B �����A��ʂ̐��f�������ɁA���肵�Ē��B������@�̊m��������B�����ł����A�V�R�K�X���g���ꍇ�ɔ��1.5�{�̗ʂ��K�v�ŁA���Y�R�X�g��2�`3�{�B�V�R�K�X����u��������ɂ͂���Ȃ�ጸ�w�͂��K�v���B �o�T�uMSN�j���[�X�v |
|
|
| �����吻�쏊���d�r�쓮�Ńo�b�N���C�g�t�t�����ڂ̓d���������[�^�[���J�� �d�r���d���������[�^�[�i�d�r�d���j�́A�R�������������[�^�[����ѓd�����ʌv�̋Z�p�E�m�E�n�E��Z�����������̂ŁA�����d�r��9�N�Ԃ̋쓮���������Ă���A�v�ʖ@�Œ�߂��Ă��錟��L�����Ԃ�8�N�Ԏg�p���邱�Ƃ��ł���B �]���̋@�B�����[�^�[�ɔ�ׂďd������1/10�ƌy�ʂŁA�{�H�̍�ƕ��ׂ��y������A�\�����ɂ̓o�b�N���C�g�t�t�����̗p���A���₷��������180����]�����邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ����茧�����L�т̊Ԕ��ŔP�o�����b�n2�z���ʂ�J-VER��ʂ��Ĕ̔��� �����x��2008�N������{�B���́u���L�тɂ�����X�ыz���ʎ���v���W�F�N�g�v�Ƃ��Đ\�����ACO2�̋z���ʂ�����\�ȁu�N���W�b�g�v�Ƃ��ĔF���ꂽ�B 2008�A2009�N�x�ɐ����s�̍��v107�w�N�^�[�����Ԕ��������ƂŎ����������A2010�N10���܂łɋz������CO2��1469�g�����N���W�b�g�Ƃ��Ĕ��s�����B 1�����{���߂ǂɁA�����O�̊�ƂȂǂɃN���W�b�g�̔̔����n�߂�\��B���������͌��L�т̕ۑS��p�ɏ[�Ă�B�v���W�F�N�g���Ԃ�2008�N4���`2013�N3���ŁA����4500�g���̔��s�������ށB �o�T�u������v |
|
|
| ���؍��ł́A�劦�g�ʼn��x�����ᔽ�͔��� �؍��͘A�������������������A16���͓암�E���R�ōŒ�C�����X�_��12.9�x�ƁA1915�N�ɕX�_��14�x���L�^���Ĉȗ�96�N�Ԃ�A�\�E���͕X�_��17.8�x��10�N�Ԃ�̊����ƂȂ����B ���{�͊��Ɍ����@�ւ̎�����18�x�ȉ��ɂ���[�u�𑱂��Ă��邪�A18���ɂ́u�G�l���M�[���v���ʂ��y�ё�v�\�B1��24���`2��18���̊ԁA�d�͂��ʂɎg�p����S��441�J���̑�^���Ǝ{�݂�z�e���Ȃǂɂ��āA������20�x�ȉ��ɋ`���Â����B2�x�E��������300���E�H���i��22���~�j�̉ߗ�����������B�������A�z�e���̓��r�[��X�g�����Ȃǂ��ΏہB �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����ȁA�V�G�l�̓����}�b�v�����J �n�M�␅�͔��d�Ȃǂ̐V�G�l���M�[�𗘗p�ł���\������ڂŕ�����n�}�����C���^�[�l�b�g��Ō��J�����B���{�n�}��ɐ��ݓI�ȐV�G�l�����ʂ������̂͏��߂āB �쐬�����̂́A�u�Đ��\�G�l���M�[�����|�e���V�����}�b�v�v�B���Ȃ̃T�C�g�̉{���{�^�����N���b�N���A�q���摜�������閳���\�t�g�u�O�[�O���A�[�X�v���N��������ƁA�s���{���P�ʂŁu����Ɨm��̕��͔��d�v�u�n�M���d�v�u�����K�͂̐��͔��d�v�̐��ݓ����ʂׂ���B�Ⴆ�A�k�C���̒n�}��ɁA���n��̓y�n�����Ȃǂ��l�������v���ꂽ���㕗�͔��d�̐ݔ��e�ʂ�\���ł���B https://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/index.html �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��Y�Ɨp���[�^�[�ɏȃG�l�K�������� �K���̑ΏۂƂȂ�̂́u�O���U�����[�^�[�v�ƌĂ��Y�Ɨp���[�^�[�B����A���������G�l���M�[������̏ȃG�l���M�[�����ɏ��ψ����ݗ����āA���[�^�[�̋@�킲�Ƃ̌������ڕW��B�������Ȃǂɂ��ċc�_����B �O���U�����[�^�[�͍����Ŗ��N1000�����o�ׂ���Ă���A�Y�Ɨp�d�͏���ʂ̖�75�����߂Ă���Ƃ����B�o�Y�Ȃ͑������2012�N�x�ɂ��K�����J�n���A�����Ŕr�o����Ă��鉷�����ʃK�X��0.4�������팸���邱�Ƃ�ڎw���B�Y�Ɨp���[�^�[���߂����ẮA���E�I�ɋK�������̓������i��ł���B�č��͍�N���ɍ��ۓI�ɂ��������ȃG�l����̗p���A���B��2015�N����K���������s���B���̂��߃��[�^�[�����ĂɗA�o���Ă�����{��Ƃ����łɋK�������ւ̑Ή��𔗂��Ă����Ԃɂ���B �o�T�uSankei Biz�v |
|
|
| �������̂����g����̒��S�ɁA�S��66�����̂��A�g�Ɍ����W�� �n�����g����̃m�E�n�E�������̊Ԃŋ��L���A�A�g��}�邱�Ƃ�ړI�Ɂu�n�����g�����S�������̉�c�v���J���ꂽ�B�����s�A��ʌ��A�_�ސ쌧�A���{�A���s�{��5�s�{���̌Ăт����ɉ����A47�s���{����19���ߎw��s�s�����킹��66�����̂̎����S���҂�������낦���B ��c�ł́A��Â���5�s�{�������ꂼ��̎��g�݂��I�����ق��A�����s���C�O�������Љ�B�v�揑���x�́A�ڍׂȃ��[���͎����̂��ƂɈقȂ邪�A35�̎����̂����łɓ����ς݁B���Ǝ҂���o�����v�揑�̓��e�����A�w���⏕�����s���悤�ȑΉ��́A�n��ɍ������������̂ɂ����ł��Ȃ��B�_�ސ쌧���v�揑���x�̐��i�ɂ������āA���l�s�E���s�Əd�����鎖�Ǝ҂ɓK�p���O�K���݂���Ȃǒn��ԘA�g�̓���������B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| ���@�@[�@2011/2�@]�@�@�� |
|
|
| ���A�[�X�N���[�����k���u�ł����v�����̐V�^���J��
�����Ɏ������t�B���^�[����d�ɂ��d�ˁA�ׂ荇�������ԂɌ��݂Ɏ����C�ƊO�C�������\���B�O�C������鑤�̃t�B���^�[�\�ʂ𐅂ŔG�炵�A���̏������ɔ��Α��̎����C����₳���B 1��̑傫���́A�c4cm�A��48cm�A����40cm���x�B1���1���Ԃ�600m3�̋�C�̉��x��10�����x��������B�f�[�^�[�Z���^�[�̃T�[�o�[20���p����̂ɕK�v�ȗ�C�������ł���B�K�v�ɉ����ĕ�������d�˂ė��p����B�O�C�Ǝ����C�𗬂����߂Ƀt�@���������̓d�͂��g�p����B�g�p���鐅�ʂ�1�䂠����1���Ԃ�60�~�����b�g���B�t�B���^�[��4�`5�N�Ō������K�v�B1���Ԃ�1000m3�̋�C���₷�\�͂̐��i��30���~���x�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����R�[�A�Ј��̃G�R�Z����C�x����������[����
���z�����d�V�X�e���̐ݒu��f�M�������߂�H��������ꍇ��CO2�̔r�o�g�t���̒�������[�������B �r�o�g�͕W���ƒ��1�N�Ԃ�CO2�r�o�ʂɑ�������2.5�g�����ŁA�����ŕt�^����B��ˌ��Ă̎����Ƃ��ΏۂŁA3000�˒��x�̗��p�������ށB�ȃG�l���C��CO2�팸���ʂ͔N6000�g�����x�B���R�[���[�X�����[�������B�����I�ȋ����͕W���I�ȃ��t�H�[�����[���̔N��4�����x���Ⴍ�}����B��Ƃ��H���I�t�B�X�����łȂ��Ј��̕�炵�̏ȃG�l�x���ɓ��ݍ��ނ̂͒������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���L�������u�ȃG�l���_�l�v�Z�o�A���тƔ�r���A���P���{
�u�G�l���M�[�\����́v�ƌĂ��\�t�g��Ǝ��ɊJ�������B�d�g�݂͂܂��A�唞��z�b�v�Ȃǂ������Ĕ��`�����u�d���݁v���߁A�[�U�A��Ƃ������H�����ƂɁA�ݔ��̔\�͂�g�p�\��̐��̗ʁA���M���̐ݒ艷�x�Ȃǂ̊�b�f�[�^��ł����ށB�\�t�g�͓��͂��ꂽ�e�H���̃f�[�^����A���_�I�ɍł����Ȃ��G�l���M�[�g�p�ʂ��Z�o����B ���̗��_�l�ƁA�G�l���M�[�g�p���тƂ��r���A���_�l������H����o���A���P������B����������ʂ�����A���M�̂��߂̔R��������ȂǁA���Y�R�X�g�ጸ�Ƃ����������₷���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ��TOTO�����d�@�ƃT�[���X�^�b�g�𓋍ڂ����I�[���C�������̎���������
�]���̖�3����1�̗e�ς̔��d�@�Ɩ��̒����̃T�[���X�^�b�g���j�b�g���J�����邱�ƂŁA���������̋@�\�������^�����A�X�p�E�g�i�f�����j�����ɓ��ڂ������߁A�J�E���^�[���ւ̋@�\���̐ݒu���s�v�ƂȂ����B �܂��A�茳�ʼn��x���߂��\�ȃT�[���^�C�v�́A�f�����̉��x�ɂ��킹�Č��̃O���f�[�V�����ŃX�p�E�g��ʂɐ�����\������悤�ɂȂ��Ă���A���̉��x��F�ł��m�F�ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���R�����I�t�B�X�������̋���z���̃��C�����X������������V�X�e�����J��
�I�t�B�X�r�������Ƃ��āA�������̋z�����S���C�����X������������u���C�����XVAV�i�u�C�G�[�u�C�j�^FCU�i�t�@���R�C�����j�b�g�j�V�X�e���v���J�������B ���̃V�X�e���́A����p���x�Z���T�u�l�I�Z���T���C�����X�v�A�Z���T�t���̐ݒ��u�l�I�p�l�����C�����X�v�A����p�R���g���[���u���C�����XVAV�^FCU�v�ō\������A���C�����X���ɂ���āA�����ݒu�ꏊ�̐�������ɉ��x�v�����ł��A���C�A�E�g�ύX��Ԏd��ύX�ɂ��e�ՂɑΉ��ł���B�V�X�e���̎Q�l���i�́A����p�R���g���[��10�䓱���̏ꍇ��200���~�i�H����ʁj�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����K�X���s���ώ@��@�����p�����I�t�B�X�r���̏ȃG�l��
�k�����Ə��̉��C�H���ɂ�����A����܂ł̏ȃG�l�ݔ������ɂ��n�[�h�ʂ̎�g�݂����ł͂Ȃ��A�v�v���Z�X�ɍs���ώ@��@��������A�ݔ��𗘗p��������҂Ȃǂ̍s���������l������CO2�r�o�ʂ̍팸�Ɏ�g�ނ��Ƃɂ����B ��̓I�ɂ́A�v�O�ɓ����҂Ȃǂւ̍s���ώ@����уC���^�r���[�E�A���P�[�g���������{���A�����҂Ȃǂ̏ȃG�l��j�Q����s���Ƃ��̗v���͂����B���̌��ʁA���[�N�X�^�C���E���ʂȂǂɂ�鉷�⊴�̈Ⴂ�A�����҂ƃr���Ǘ��҂̃R�~���j�P�[�V�����s���A�����҂̏ȃG�l�ɑ���S�̒Ⴓ�Ȃǂ���ȗv���ł��邱�Ƃ��������B�����ŁA�̐��������҂̓����ɍ��킹�ēK�ɍs����IP�d�b�𗘗p�����ݎ����m�V�X�e����A�����҂ƃr���Ǘ��҂̃R�~���j�P�[�V�����𑣐i���A�����҂ɏȃG�l�A�h�o�C�X�Ȃǂ��s��BEMS�Ȃǂ����邱�Ƃɂ����B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����G��������ăG�l�M���p�̌v���@�̍��q��
�����G�l���M�[���́u�Đ��\�G�l���M�[�̔M���p�Ɋւ��錤����v�͑�6�����J���A�M�ʌv�����@�̊m���⓱���x����̏[���A�O���[���M�؏��̊��p�Ȃǂ荞���܂Ƃߍ��q�Ăő�؍��ӂ����B �M�̗��p�ʂɉ����Ďx������u�����j���O�����v�ɂ͔M�ʌv���������Ēʂ�Ȃ��Ƃ������A�v�ʂ̃R�X�g���S���y�����邽�ߊȈՂȌv�ʂ�@��̐��\�Ɋ�Â����Ȃ��v�ʂ��l������K�v�����w�E���Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���s�F���z�M�@��̏W���Z��ݒu�ɕ⏕���N�x����5�N�Ԃ�5000�˕��^����
����������g�[�ȂǑ��z�M�̗��p�@����W���Z��ɐݒu�����ꍇ�A��p�̈ꕔ��⏕���鐧�x������B 2011�`2015�N�x��5�N�ԂŁA�V�z�̃}���V�����Ȃǂ̉������ʃK�X�̍팸��i�߂�_���B�s�ł́A���N�x���瑾�z�M�̋Z�p�J���𑣂����߁A���[�J�[����A�C�f�A������B�I�肵���Z�p��⏕�̑Ώۂɂ���B�s���������Ђ��s�̗\�Z20���~��������B1��������̕W���H�����100���~���x�Ƃ݂��A2����1�`4����1��⏕������j�B���z�M�̗��p�́A���z�����d�ɔ�ׂăp�l���̐ݒu�ʐς�5����1�ōςރ����b�g������B����ŁA�����������߈ێ��Ǘ��ʂʼnۑ肪����A���z�����d�ɔ�ׂē������x��Ă���B �o�T�u�����V���v |
|
|
| �����ŁA2011�N10���ɓ����B���N�x���ł�350���~�K��
���{�Ő�������́A�n�����g�����Łi���Łj��2011�N10�����瓱�����邱�Ƃ𐳎��Ɍ��߂��B �Ζ��E�ΒY�ł̐ŗ��������グ�A��悹�������łƂ���B���ł͓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂɉ����A�R�����Ƃɐŗ��������グ��B3�N�������Ēi�K�I�ɑ��₵�A5�������グ�A���S���{�ƂȂ�2015�N�x�̐Ŏ���2400���~�B�Ŏ��̓G�l���M�[�����ʉ�v�ɌJ�����āA�ȃG�l��ɏ[�Ă�B�ŏI�I�ȑ��ŕ��́A�����E�Ζ����i��1�L�����b�g���������760�~�A�t���V�R�K�X�iLNG�Ȃǂ�1�g���������780�~�B�ΒY��1�g���������670�~�̑��łɂȂ�B�������ł�y������łȂǂɏ�悹���Ă��鋌�b��ŗ��́A���������������߁A��N�̏O�@�I�}�j�t�F�X�g�Ŗ����u�P�p�v��������A���s�����𐘂��u���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���q�[�g�|���v�r�M�������M���ɓ��H��Ȃǂ��������
�����H�Ƒ�w���������@AES�Z���^�[�Ɠ����d�́A�O�H�d�@�A�O�H�����A�����M�w�H�Ƃ̖���4�Ђ́A�q�[�g�|���v�̉��r�M�������p�M���Ɏg��������V�X�e���̎��p���ɂ߂ǂ������B �V�X�e���J���́A���Z���^�[��������G�l���M�[��Ղ̊m����ڎw���ēW�J����T�u�v���W�F�N�g��1�Ƃ��ĎY�w�������������Ă�����̂ŁA��1���]�������I����A�ڕW�ł����[���̑����V�X�e���ł̃G�l���M�[���ьW���iCOP�j4.8��B���ł���Ƃ̌��ʂ����B���d�Ȃǂ͍���A�������̏���������p�ጸ�ȂǁA���y�Ɍ������ۑ�ւ̑Ή�����l�߂Ă����\��B���V�X�e���́A�����z�����\�����f�V�J���g�ނƁA�q�[�g�|���v��g�ݍ��킹���B�f�V�J���g�ނ���C���̐����z���ނɂ��ď������\����������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���S�ʔ��搧�x�̏ڍאv���炩�ɁA���͂ȂNJ���15�N
���͔��d�ȂǑ��z�����d�ȊO�̔��������Ԃ�15�N�����Ƃ���B15�`20�N�Ō������Ă������A�����̊��Ԃ̈Ⴂ�͓������f�Ɍy���ȉe�������y�ڂ��Ȃ��Ɣ��f�����B �H��⎖�Ə��ɐݒu���鑾�z���ɂ��Ă��S�ʔ������̑ΏۂƂ��A���͔��d�ȂǂƓ����̔��������ԂƂ���B�Z��p���z���̔�����艿�i�E���Ԃ͌��s�̗]�蔃����萧�x�̗�����p������B�Z��p���z���ȊO�̔�����艿�i�͊�{�I�ȍl���������A����A�ڍׂ��l�߂Ă����B���搧�x���ψ���ŕ��Ă����B���ςŗ�����������A�p�u���b�N�R�����g���o�čŏI�ƂȂ錩���݁B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����K�\�[���[�̌��z�K���A�d���@�Ɉ�{��
���y��ʏȂ́A�p�l���̍�����4���[�g�����鑾�z�����d�ݔ��ɂ��āA2010�N�x���Ɍ��z��@�̑ΏۊO�Ƃ��邱�Ƃ����߂��B ���݂́A�ݔ��̌��ݎ��ɓ��@�Ɠd�C���Ɩ@��2�d�̐R���E�m�F���K�v�ƂȂ��Ă��邪�A�����d�C���Ɩ@�Ɉ�{������B��̍�͌����������A�ȗ߂ȂǂőΉ���������Œ�����i�߂Ă���B���Ή��ݔ��̕��y��ړI�Ƃ������{�̋K���E���x���v�̈�ŁA��Ƀ��K�\�[���[�i��K�͑��z�����d���j���K���ɘa�̑ΏۂƂȂ�B���ݎ��̐\���葱���̊ȗ����ɂ��A���z�����d�ݔ��ւ̓������i�������ށB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2011/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���T���f������C�M�E�n���M���p�̉ƒ�p�V�^�q�[�g�|���v�V�X�e���̊J�����J�n
�C���ɍ��킹�ė������g�������邵���݂ŁA��C�M������M���Ƃ���]���i�ɔ�ׂăG�l���M�[������1.5�{�ȏ�ɍ��߂�̂��ڕW�B ��ɑ�C�M���\���ɓ����Ȃ�����n�ł̗��p��z��B�C�ۏ����ɉ����đ�C�M�ƒn���M�������I�Ɏg��������m�E�n�E�Ȃǂ��m�����������ŁA2012�N�x���܂łɊ�{�I�ȃV�X�e�����J���B2014�N�̎��p����ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���H��Ŏ̂ĂĂ������d�ɁBNPC���H��������͔��d�V�X�e������
�t�@���̔r�o���ɕ��͔��d�t�@�������t���A�r�C��L�����p���Ĕ��d����B���R�̕��𗘗p����̂Ƃ͈Ⴂ�A�t�@���͏펞�ғ����Ă��邱�Ƃ��������ߕ��ʂ͈��ŁA���肵�����d���\�ɂȂ�B ���V�X�e���́A�o��400W���邢��1kW�̔r�C���p���d�t�@���Ɨe��105Ah�̃o�b�e��8��A�d���X�N�[�^���琬��B���d�����d�C�͂�������o�b�e���ɒ��߂�B�Ɩ��̕⏕��A�H����̈ړ���i�ł���d���X�N�[�^�̏[�d�Ȃǂɗ��p����B���d�J�n������1.2m/s�ŁA3�`4m/s����Ώ\���Ƃ����B���d�t�@���̃u���[�h�͔r�C�ǂ̌`���\���A���������Ă��Ȃ���v����B�������������ꍇ�ɂ͑������ʂ̂���f�B�t���[�U�^�C�v�̃u���[�h���̗p����ȂǁANPC���F�̃R�[�f�B�l�[�^�[���œK�ȃV�X�e�����Ă���B����ɁA�r�C�����ł͂Ȃ��A�r���𗘗p���邱�Ƃ��\�Ƃ��Ă���B ���i�́A�H����A������݂�158���~����B���d�t�@���̒��a��400W�^�C�v��1.17m�B �o�T�uTech on�v |
|
|
| ��JFE�G���W�����S������������CO2�������C�Z�p���J��
CO2���܂ރK�X�𐅂ƍ����A�L�f�Ȃǂłł�������ȗL�@��������������ƁA�قڏ퉷�E�툳�ŃV���[�x�b�g��ɂȂ鐫�������p�����B�����������ĉ��x�����グ���CO2�͍ĂыC�̂ɂȂ�B ���̌�A�n���Ȃǂɒ�������BCO2 1�g�����E�������R�X�g��2,500�~���x�B����܂ł̉��w�����ɋz����������@�̔����ōςނƂ��Ă���B�߂��A�N�Ԑ���g����CO2������ł���e�X�g�ݔ������݂��A���؎���������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���X�}�[�g�G�i�W�[���V�l�Ј��������������T�[�r�X���J�n����\��
���Ј���������̈�ʏ펯����ʂ�����邱�Ƃ����҂����Ƃɔ��荞�ށB����20���Ԓ��x�̐��J���L�������������j�B ���ۑS�̏d�v��������l���̌o�ω��l�A���łȂNJ������S�ʂ̊�b�m���ɂ��Ă̈�ʂ�̐����ƁA���Ζ@��ȃG�l�@�ȂǁACO2�r�o�K���Ɋւ��Ă͏d�_�I�ɐ�������B1�Ђ����萔�\�l���x�̎�u�ŁA��u���͈�l�����萔��~���x�̌��ʂ��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ����{���쏊��25���ߐ��̋Ɩ��p����@��
����A�����ĐA������@�ŁA1���Ԃ�1.2�g���̐���鐫�\�ŁA�]���i��10�g���̐���ɖ�80�g���̐����g���Ă����̂�60�g���ɗ}������B �u�\��v�A�u�{��v�A�u�������v�̍H���Ő�p�Z���T�[�����̗ʂ��܂̔Z�x���`�F�b�N�������悭�B�u�������v�Ŏg��������\��ōė��p����d�g�݂��̗p�B�����@�ł͐����������M���̗���ɍH�v���A���ʂ��팸�B�M��������̂Ɏg�����C�̗ʂ��30�����点�A����@�ƕ����Ĕ���o���B �o�T�u��goo�v |
|
|
| ���l���x���ł̔r�o�ʎ���������ցB�E�E�E�����ŋ��c��ݗ��A���t���؎���
ICT�����p�����V���Ȕr�o�ʎ����@�̎��p����ڎw���u�T�v���C�`�F�[�����v���Z�p�������c��v���A�������w�������i�m�h�h�j�Ɠʔň���i���j�A���{���j�V�X�i���j�A�i���j�Z�u�����A�C�E�z�[���f�B���O�X��3�ЂŐݗ����ꂽ�B���N2���ɂ́i���j�|�b�J�R�[�|���[�V�����ȂLj������[�J�[�̋��͂āA���E���ƂȂ�l���x���̔r�o�ʎ���Ɋւ�����؎������C�g�[���[�J�h�[�̓X�܂ōs���\�肾�B �����r�o����\���h�b�^�O��o�[�R�[�h�����i�ɓ\�邾���ŁA�r�o���t�����i���T�v���C�`�F�[���S�̂ŗ��ʂ���d�g�݂��l�āB�r�o���̐����葱�́A���i����͂������o�[�R�[�h�Ȃǂ�X���ŕԋp���邾���ŁA�r�o�����w���҂̐�p�����֎����I�Ɉڂ����B����̎��؎����ł́A�w�Z�P�ʂʼn�����Ĕr�o����n��w�Z�֊�t������@����������Ă���B�Y�t�̔r�o���̓I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g(J�|VER)�̑ΏۂɂȂ�B �o�T�u��goo�v |
|
|
| �����{�Œ��A�ȃG�l�ݔ��ɗD���[�u����
2011�N�x�Ő������Ɍ��������{�Ő�������ŁA�ȃG�l���M�[���z�ݔ��̕��y�Ɍ������Ő������̋c�_���{�i�����Ă���B���y��ʏȂȂǂ͊�Ƃ��ȃG�l�ݔ��������ꍇ�̐Ő��D���[�u�̑n�݂�v�����Ă���A�@�l�ŗ����̂̈��������̋c�_�Ȃǂƕ��s���Ď��{�̉ۂ����������B �D���[�u�́A�����E�Ɩ��E���E�E���C�E���~�@�ݔ���6�̏ȃG�l�ݔ��̂���1�ł��ݒu����A�擾�z��40���̊����œ��ʏ��p�A������Ƃ�7�������z�̐Ŋz�T��������Ƃ������́B��������A�ȃG�l�ݔ��ƊE�ɂƂ��Ă͏��@�̊g��ɂȂ��肻�����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����䌧��CO2�팸���������x�������r�o�ʂ�F��
�N�x�������ڎw�����n�����g�����n��v��̑̌n�Ă������ꂽ�B�ƒ���ƂŎ��g��_���Y�f�iCO2�j�팸����r�o�g�Ƃ��Ĕ����ł���N���W�b�g���x�̓����荞�B �̌n�ẮA4���ڂ̊�{���j���f���A�����z�����d�E�ȃG�l�ݔ��̓����������㎩���Ԃ̕��y�����Ԏ��Ə��̏ȃG�l���\�Ȃǂ̎{����܂Ƃ߂��B �N���W�b�g���x�́A��ƂȂǂ�CO2�r�o�g���ł��鍑�̐��x�̊��p��z��B��Ƃ̏ȃG�l�ݔ��̓�����A�ъ����Ȃǂō팸���ꂽCO2�r�o�ʂ������F���A�����O�Ŕ����ł���悤�ɂ���d�g�݂���������B�S���ł͎O�d���≪�R���ȂǂœƎ��̔F�ؐ��x��݂��Ă���B �o�T�u����V���v |
|
|
| �����Ȃ������Ǝ҂ɔr�o�g�lj��̎d�g�ݓ���������
�����i�K�����łȂ��A���i�̎g�p�i�K�܂œ��܂������C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�iLCA�j�Ŕr�o�팸���ʂ�]������l���������ꂽ�B�r�o�ʎ�����x�̓����ɂ�萻�i�̐�����j�Q����\���������Ƃ��ΏہB �r�o�팸���ʂɗD��Ă��鐻�i����肵�A�]�����i������ꍇ�ɔ�ׁA�������ɔr�o�ʂ������������ɂ��Ĕr�o�g��lj���t����B�Ώې��i�̗�Ƃ��āA�������Ɠd�⎩���ԁA�����\���z���d�r�p�l���Ȃǂ������Ă���BLCA�ɂ��ẮA�r�o�ʎ�����x������ۂ̔z���_�Ƃ��ĎY�ƊE�����߂Ă���B ���ۋ����͂�Y�f���[�P�[�W�ւ̔z�������B�����z�����s���ꍇ�ł��A���ۋ����͂ւ̌��O�������Ƃɑ��ẮA�r�o�g��lj���t����l��������B�܂��A�n�������̂Ő�s���Ă��鑍�ʍ팸�`�����x��r�o�ʎ�����x�܂��A�������Ȃ�Ȃ��悤�ɁA���Ƃ̊W������K���荞�ލl���\��ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����ŁE�r�o�ʎ���̑����������B�\ OECD�����{�̊���������r���[
�uOECD���ۑS���ʃ��r���[�����\�C�x���g�v�́AOECD�����{�̊��ۑS�ɑ�����g�݂̐i���Ȃǂ�R���������ʂ��܂Ƃ߂����r���[�̌��\���Ď��{���ꂽ�B �C�x���g�ł́AOECD���������̃A���w���E�O���A���́uNo Price ,No Solution�i���i�t���Ȃ��ɉ����Ȃ��j�v�ƁA�⏕���ł͂Ȃ��s��x�[�X�̌o�ϐ��L���ł���Ƌ����B���{���{�������Ɋ��ł⋭���I�Ȕr�o�ʎ���̓����ɓ��ݐ邱�Ƃ����߂��B �܂��ANPO�@�l������21��\�̉����O�Y���́A������ɂ��ē��{�l�ƊC�O�̐��Ƃ����F���̊Ԃɑ傫�ȗ��������邱�Ƃ�A���G�����鍑���@�̖��_�Ȃǂ��w�E�����B�����r���[�̓��e�͏��ЁuOECD���|�[�g���{�̊�����v�Ƃ��āA�����@�K�o�ł���N���Ɋ��s�����\�肾�B �o�T�u��goo�v |
|
|
| �����B�ρA�r�o��������x�������F2��̎Y�ƃK�X�ɂ��r�o�������O
2013�N�ȍ~�A��_���Y�f�iCO2�j�����i�i�ɉ������ʂ�����2��ނ̉��g���K�X�팸�ɂ��r�o���͓����x�̑Ώۂ��珜�O����B���Ǝ҂͓r�㍑�ł����̃K�X�̔r�o�}�����Ƃ����{���邱�Ƃő����̔r�o�����l�����邱�Ƃ��ł��A�ꕔ��Ƃ͐��x�̗��p�ɂ��s���ȗ��v�������Ă���Ƃ�����肪�w�E����Ă����B�����������x�̔�������h���_��������B �ΏۂƂȂ�̂̓t�����K�X�̈��ł���HFC23�Ɖ��w�����̃A�W�s���_�̐��Y�H������o���_���f�B���A�̋��s�c�菑�ɂ́A��Ƃ��r�㍑�Ŏ��{����r�o�팸�v���W�F�N�g�ɂ��팸���������̍팸�ʂƂ݂Ȃ����Ƃ��ł��鐧�x������B���s�̉��B�r�o�����x�ł́A���̍��A���x�ɓK�������r�㍑�v���W�F�N�g�̍팸����������邱�Ƃ��F�߂��Ă���B �o�T�uNNA�v |
|
|
| �������A�o�Y�Ȃ��V�z�Z��ΏۂɏȃG�l��ւ̓K����2020�N�x�`�����̌���
���ׂĂ̐V�z�Z��E���z���ɂ��āA2020�N�x�܂łɏȃG�l��ւ̓K�����`���t��������Ō������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B��ʉƒ��I�t�B�X�̓�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ��팸����̂��_���B �����ʐς�2000�������[�g���ȏ�̌��z������K�����n�߁A�Ώۂ������g�傷��B�����̕����͏��O����B���Ȃ͋`�������~���ɐi�߂邽�߁A�H���X�̋Z�p�擾�A���ރ��[�J�[�̏ȃG�l���i���Y�Ȃǂ��x������ӌ��B�V���ȏȃG�l��݂̍���Ƃ��āA�N���ɂ����肷��B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/12�@]�@�@�� |
|
|
| ������d�@���]��G�l���M�[����V�X�e�������Ɖ���
���Y�ݔ��ł̏ȃG�l�͕s�\���Ȃ̂�����B�ݔ��ғ����ɏ]���̂ĂĂ����G�l���M�[���ė��p����d�g�݂��\�z���A�H��S�̂̏ȃG�l���߂����B ��̓I�ɂ́A�ݔ��̌������≺�~���ȂǂɃ��[�^�[�����d���A�d�͂������I�ɓd���ɖ߂����߂̐�pDC/DC�R���o�[�^�|���J�����A���{�b�g��쓮�p���[�^�[�A����p�C���o�[�^�[�ȂǂƑg�ݍ��킹��B ��������d�͂�~�d���邽�߂̃��`�E���C�I���d�r��d�C��d�w�L���p�V�^�[������B�ȃG�l���ʂ͐ݔ��ɂ���ĈقȂ邪�A�t���������u�ɓ��������ꍇ�A30�����x�̓d�͂��팸�ł���Ƒz�肵�Ă���B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| �������K�X�Ȃ�3�Ђ�90���̉�����160�����x�̏��C�ɕϊ�����V�X�e�����J��
�ʏ�90���̉����͖����p�̂܂ܔr���ƂȂ邪�A�}��ƂȂ�L�����`�E�����n�t�����M���A�ሳ���C�ɕϊ�����d�g�݂Ȃǂ𗘗p���A���C�����M��E�ۍH���Ɏg����悤�ɂ����B �Z�x60���̏L�����`�E�����n�t�ɐ����C���܂܂��A�z���M��������B���̔M�Ő�������133���̒ሳ���C�̈��͂��㏸�����A�ŏI�I��159���̍������C���o���B�ʏ�̍������C���g���{�C���[�ɔ�ׁA���C�ʂ�3�����₹��B1���ԓ�����1��kg�̏��C�ʂ��o�͂���ꍇ�A�N�Ԃ�CO2�r�o�ʂ͖�24���팸�ł���B�K�X����ʂ�����A�N�Ԗ�680���~�̐ߖ�ɂȂ�B�V�X�e�����i�͖�3�疜�~�A�{�H����܂߂�5�N���x�̓���������\�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������M�w���ݒ�ύX��^�p���P�ɂ��V�K���S�̂Ȃ��ȃG�l�x���T�[�r�X���J�n
�r���̃G�l���M�[����̌�������ߍׂ����c�����A�G�l���M�[�����̉��P�𗧈āB���̌�A1�N�Ԃ�2�`3��K�₵�V�X�e���̐ݒ��^�p���P�����s�A��������B ��̓I�ɂ̓t���A�⎞�ԑт��ƂɃr�����ɂǂ̒��x�̐l�������邩�ׂ���ŁA�t���A�E���ԑтɉ����ċ̐ݒ艷�x�ύX�B���^�]�̎��ԁA���C�ʂȂǂ��œK�̐����ɒ��߂���B�^�p���P�ɂ��S�̂̃G�l���M�[�����10�`20���팸�ł���ƌ��Ă���B�ȃG�l�Ō������G�l���M�[�R�X�g��20�����萔���Ƃ��Ē�������B����Ȃ������ꍇ�A��{�����Ȃǂ͒������Ȃ��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���O�H�d�@�Ɠ��d�A�ȃG�l���\�����߂��p����������`���[���J��
����`���[�́A�r����H��Ȃǂ̋Ɏg�p����␅������@��ŁA��[�̔r�M���p���֕��M����M������������B�V�J���̐���R���p�N�g�L���[�u�́A13�l���̃G���x�[�^�[�Ŕ����\�Ȑ���`���[�Ƃ��Ă͍����ō������̗�p�^�]������B�������B �X�V�����}���Ă���␅�Ɖ�����s�s�K�X�Ȃǂł�����݂̔M���@�A�z���≷���@�Ɣ�r���ė�[�^�]��CO2�r�o�ʂ�54���A�^�]�R�X�g��24���팸����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�E���ŁA�����K�i�̐�����A�N���ɒ��nj`LED�Ɩ���
����܂Œ��nj`LED�Ɩ��̋K�i�́AJIS�i���{�H�ƋK�i�j�ȂǂŕW��������Ă��炸�A�d�C�p�i���S�@�̑Ώۂɂ��Ȃ��Ă��Ȃ������B10���ɓ��{�d���H�Ɖ�ɂ��K�i�iJEL801:2010�j�uL�`�����t���nj`LED�����v�V�X�e���i��ʏƖ��p�j�v�����肳�ꂽ���Ƃ��āA���d�@���[�J�[�����nj`LED�Ɩ��̏��i���ɏ��o���B ���Ń��C�e�b�N�́A20�`�����40�`�u�������v�����̖��邳�ŁA���nj`LED�Ɩ��V�X�e��3��̔N��������ڎw���B �p�i�\�j�b�N�ƃp�i�\�j�b�N�d�H�́A�u���nj`LED�����v�v�Ɓu���nj`LED�����v��p�Ɩ����v�����N���ɔ�������\��B �����߂�ꂽ�uJEL801:2010�v�̏ڍׂ́AL�`�����t���nj`LED�����v�̏ꍇ�A������L16�A�S������2,300lm�ȏ�iN�F�j�A���F����80�ȏ�A�d����DC350mA�A�d����45�`95V�A�ő�d�͂�33.3W�A�z���ɂ��Ă�120���ȓ��̌�����70�������B �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| �����c���쏊���킸���ȐU������Ŕ��d��������d���i��2011�N�Ɉ�Ĕ̔��\��
�ア���Ŕ��d���鑾�z�d�r�g�ݍ��ݕ��i�́A��ʓI��400���N�X�̌���100�}�C�N�����b�g�̓d�C�ށB�����ȓd�C�����^�R���f���T�[�Ȃǂ̒~�d���i�ɂ��߂Đ����b�g�ɑ�������Z���T�[�△�����i���쓮��������B ��Ōy���U����x�̐U����100�}�C�N�����b�g�̓d�C�����镔�i�A���x���Ŕ��d����M�d�ϊ��f�q�ƈ��͂�d�C�ɕϊ����鈳�d�f�q�𓋍ڂ������i���J���ς݁B����T���v���o�ׂ��J�n���A���N���ɐ��Y�A�̔�������j�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȂ͒�����Ƃ̒�Y�f�^�ݔ��ɏ����B�팸��2�N�������O�Ɏx��
��_���Y�f�iCO2�j�̔r�o���팸�ł���{�C���[�Ȃǂ̐ݔ�������������Ƃ�ΏۂɁA�팸�ʂɌ��������̏��������x������V���x��n�݂���B �팸��1�g��������̏����z�͔r�o�g�̍��ێ�����i��2�{���x�̖�3000�~�ɐݒ肵�A�ݔ���������2�N���̍팸�ʂɌ��������z���x������B������Ƃɐݔ������𑣂����Ƃʼn��g����ƌo�ϊ��������ɐ��i����B���N�x��\�Z��10���~���x�荞�B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ́A2���Ԕr�o�g������i��
���{��Ƃ���V�����ւ̋Z�p�ړ]��ʂ��A2���Ԃł̉������ʃK�X�̔r�o�g������肷��d�g�݂�����15�v���W�F�N�g��I�o�����B�v���W�F�N�g�Ō�������̂́u2���ԃI�t�Z�b�g���J�j�Y���v�Ƃ����d�g�݁B���{����̋Z�p�ړ]�ŐV�����̉������ʃK�X�r�o�ʂ�����A���{�����̕��̔r�o�g���擾����B �����d�͂��x�g�i���ł̌��q�͔��d���̌��݁A�O�H�����Ȃǂ̏ȃG�l�Ɠd�̕��y������̑ΏۂɂȂ邩����������B������x�̊m���œ��{�̏ȃG�l�E�C���t���Z�p���x������_�����B�������������A���A�����F���鐧�x�̑ΏۊO�ƂȂ��Ă���A���{���Ǝ��ɐ��x����ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ݔ����Z��G�R�|�C���g�ΏۂɁA���f�M�����Ȃǒlj���
���{�́A�Z��G�R�|�C���g�̑Ώۂɐݔ��@���lj�������j�����肵���B������g�[�̋@�\�����Z��p�̑��z�M���p�V�X�e���A�ߐ��^�֊�A���f�M������3��ނŁA�������1���ɂ�2���|�C���g�i1�|�C���g��1�~�����j�ɂ���\��B ���z�M���p�V�X�e���͐V�z�A���t�H�[���ɂ�����炸�ΏۂƂȂ�B�֊�Ɨ����̓��t�H�[���Ɍ����ă|�C���g�̑Ώۂɉ�����B�ߐ��^�֊�ɂ��Ă͓��{�H�ƋK�i�iJIS�j�Ɂu�ߐ�I�`�v�i��̗ʂ�1��ɂ�8.5���b�g���ȉ��j�Ɓu�ߐ�II�`�v�i��6.5���b�g���ȉ��j�̋K�i�����邪�|�C���g�̑Ώۂ�II�`�Ɍ���ƂȂ錩���݁B ���f�M�����ɂ��ẮAJIS���������ċK�i��V�ݗ\��B ���z�M���p�V�X�e���́A�����ɏW�M��A�n��ɒ����^���N��u���u�����z�^�v�̐��i������ΏۂƂ��錩���݁B�֘A�\�Z��2010�N�x��\�Z�Ăɐ��荞�݁A�������2011�N1��������{�\��B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| ��EU�F���s�c�菑��2013�N�ȍ~���������t���Ŏ����
�č��⒆���Ȃǎ�v�o�ύ��ɂ�鉷�����ʃK�X�r�o�ʂ̍팸�������BEU�͋��s�c�菑�ɑ���P��̖@�I�����i�V�c�菑�j�̑��������ڎw���Ă������A���ی��̓�q�őÌ��̌��ʂ��������Ă��Ȃ����߁A���j�]�������B �̑����ꂽEU������c�̑���������2013�N�ȍ~�̑�2���Ԃ��u��������ӎv�v���m�F����ƂƂ��ɁA�Ē��Ȃǂ��܂ޕ�I�Șg�g�݂����A�r�o�ʎ���̎d�g�݂����P����K�v�����w�E���Ă���B 11�������烁�L�V�R�E�J���N���ŊJ����鍑�A�C��ϓ��g�g�ݏ���16�����c�iCOP16�j�ɗՂ�EU�̑Ώ����j�ƂȂ�BEU�����s�c�菑�ɉ����悤�@������i�߁A�u2020�N�܂ł�1990�N���20���팸�v�̖ڕW���߂Ă��邱�Ƃ���A�u��2���Ԃ��������v�Ɛ��������B �o�T�u�����V���v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȂ̓X�}�[�g���[�^�[�W�����ցA������̂Ŏ��g��
�X�}�[�g�R�~���j�e�B�̐��i��ڎw���������c�́u�X�}�[�g�R�~���j�e�B�E�A���C�A���X�v�iJSCA�j�ƘA�g���A�X�}�[�g���[�^�[�i������d�͗ʌv�j���܂ރG�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���iEMS�j�̕W�����Ɏ��g�ށB JSCA�̍��ەW�������[�L���O�O���[�v�̉��ɁA�o�Y�Ȃ������ǂ߂�3�̐��`�[����݂��A������̂�EMS�ɂ�����鍑���W���̍���⍑�ۓW�J�ɗՂޕ��j�B �V���Ɂu�n��G�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���iCEMS�j�v�A�u�r���f�B���O�E�G�l���M�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e���iBEMS�j�v�A�u�X�}�[�g���[�^�[�v�Ɋւ���R�`�[����ݒu��������Ō������B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����s��CO2�r�o�ʎ�����x�̏��̌�����c�J��
���s�{�Ƌ��s�s�������őn�݂�ڎw���u���s��CO2�i��_���Y�f�j�r�o�ʎ�����x�v�̌�����c���J���ꂽ�B ��c�ɂ͑�w�̌����҂�o�ϒc�́A��ƁANPO�Ȃǂ̈ψ�17�l���o�ȁB�u�o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ̎�����x�̗ǂ��Ƃ�������ݎ��ׂ����v�u�V�������x�������Ă��A�M�������Ȃ��Ɗ�Ƃ͎肪�o���Ȃ��v�Ȃǂ̎w�E������A������Ƃ��Q�����₷���悤�葱����萔���̈������������߂�ӌ����o���B ���x�̑n�݂ɂ���āA�{���Ŕr�o�ʂ�3�����߂钆����Ƃ̔r�o�ʍ팸��NPO�Ȃǂɂ��X�ѐ����̑��i��_���B������Ƃ��ȃG�l�ݔ��̍X�V�ȂǂŌ��炵���r�o�ʂ��K�͊�Ƃɔ��邽�߂̒���@�ւ̐ݗ��Ȃǂ���������B2011�N3���ɍŏI�Ă��܂Ƃ߁A���N�x���琧�x���X�^�[�g��������j�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/11�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�@�H�Ƃ�CO2�팸��Ă̐��ʂ��|�C���g�����A���ۑS�����Ɋ�t���鐧�x��
���Ђ̍s�����ݔ��H���ŏȃG�l���M�[�����������ꍇ�A�팸�ʂ�Ǝ��̃|�C���g�iCO2�팸1�g���ɂ�100�~�j�Ɋ��Z���āA�N�Ԃ�ʂ��đS�ЏW�v���A���ۑS�̔�c�������֊�t���Ă����Ȃǂ̏������s���Ƃ������́B ���N�x�́A�ȃG�l���M�[��Č���400���ACO2�Ƃ���130,000�g���i��t�z���Z��1300���~�j�̍팸��Ă�ڕW�ɂ��Ă���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ����K�X�A���d�@�\�t��GHP���p�ő��z���̏o�͈��艻����
���s���T�[�`�p�[�N���^�c������݃I�t�B�X�r���ɁA���z�����d�V�X�e���i�o��9kW�j��GHP8���ݒu�B���v8kW�z�����d�̏o�͂̒����Ɋ��p����B �������Ԃ�1�N�B��d�d�͂Ƒ��z�����d���v�����A�I�t�B�X�̏Ɩ��ɕK�v�ȕ⊮�d�͂��v�Z���A�K�v�ȓd�͂ɉ�����GHP�̔��d�𑝂₷�Ȃǂ̐�����s���B�܂�GHP�ŕs������ꍇ�́A�Ɩ��̖��邳����������B���؎����ł͓�_���Y�f�iCO2�j�팸�Ȃǂ̃����b�g�������A���z�����d�Ɣ��d�@�\�t��GHP�̃_�u�����d�V�X�e���Ƃ��ď��i����ڎw���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���É����ŁA������Ɠ��m�ŏ�CO2�r�o�����
����̎���ŐÃK�X�́A�É��s���̐H�i��ЂƓd�C���b�L���H��Ђ�2�Ђ̏d���{�C���[��s�s�K�X�ɓ]������Z�p��B�v371�g����CO2�r�o��}���ł��A���̂���40�g������Ë�ɔ��p�����B �Ë�͂���܂ō팸�ł��Ȃ����������A�r�o���w���Ŗ��ߍ��킹��B�É��K�X�́u�����N���W�b�g�̒n�Y�n���������ł����v�Ƃ��Ă���B �o�T�u�Y�o�V���v |
|
|
| �����{�C�g�~�b�N��75kW�̑�^�G�R�L���[�g�𓊓�
��^�Ɩ��p�G�R�L���[�g�̗ގ��N���X�ł͍ŏ��E�Ōy�ʁA�ȃX�y�[�X�̃R���p�N�g�v�Ƃ��A�]����3kW�@�Ɣ�r����ƁA1�䓖����̉��M�\�͂�2.5�{�Ɍ��コ���A�ݒu�X�y�[�X��1.2�{���x�ɗ}�����B COP��4.0�Ɠ��������B�����^���N�͖����ŁA�W���e�ʂ�4800L�A6000L��2��ށB�������������ւ̐ڑ����\�Ȏd�l�����낦��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���R���i�A�ȃG�l�Z����P���܂邲�ƒg�߂�q�[�g�|���v���̉����g�[�V�X�e����
�ȃG�l�Z�����܂邲�ƒg�߂邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�g�[�o�͂�11.6kW�܂ō��߂��Ă���A���g�[�A�������[���q�[�^�[�A�p�l���R���x�N�^�[���A���L���g�[�[���Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���B ���O���j�b�g�ɂ͓����h�~�q�[�^�[�������f�������C���A�b�v����A�O�C�����}�C�i�X25���̊����ł��K���\�ŁA�ቷ���̕⏕�M���Ƃ��āA�ʔ��i�̃q�[�^�[���j�b�g(2kW)�����t���ł���B�܂��A�z�|���v���j�b�g�͖��z�ǎ��Ɣ����z�ǎ���ݒ肵�A2�@��4���f������I���ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���ɓ����A�V�X�R�ƃG�l���M�[�Ǘ����ƂŒ�g
�H���I�t�B�X�r���̋�Ɩ��ݔ��̃G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X�ɃV�X�R�̋Z�p�������AIT�@����܂߂Ĉꊇ�ŊǗ��ł���悤�ɂ���B�N���ɓs���̃I�t�B�X�r���ȂǂŎ��؎������s���A2011�N1�����߂ǂɃT�[�r�X���n�߂�\��B�����ȃG�l���M�[�@�̎{�s��w�i�ɍ��܂��Ƃ̏ȃG�l�E�ȃR�X�g�������㉟������B �ɓ����̃N���E�h�^�G�l���M�[�Ǘ��T�[�r�X�u�G�R�t�H���e�v�ɁA�V�X�R��IT�@����������䂷��Z�p���������u�G�R�t�H���e-CRE�v�������ŊJ���E�̔�����B�V�X�R�̃��[�^�[�i���p�@�j��ʂ��āA��Ɩ��̂ق��p�\�R����v�����^�[�Ȃ�IT�@��̊Ď��E���䂪�\�ɂȂ�BIT�@��̓d�͎g�p�ʂ��]����20�`30���팸�ł���Ƃ����B���z���p���͓X�܂ȂǏ��K�͎{�݂�2���`3���~����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�A�r�M��~���Ēg�[�Ɏg���G�A�R����
�r�M��~���Ēg�[�ɗ��p������@�́u�G�l�`���[�W�V�X�e���v�Ɩ��t�����B�V�����J�������~�M���j�b�g������A�~�M������ɂ���ăG�A�R���̔r�M���G�l���M�[�ɕς��Ē~�ρB�����X�^�[�g���ɂ͂��̃G�l���M�[���g���B�����o�����x�́A�]���̃G�A�R������23���������̂ɔ�ׁA��50���Ƒ傫���㏸�����B �~�����M�́A���O�@�̔M������ɕt��������n���������^�]�ɂ����p����B�]���@�ł͒g�[���ꎞ�~�߂đ�����邽�߁A���̊ԉ������~�܂��Ď�����5�`6���ቺ���Ă������A�~�����M�ő������Ȃ���g�[������@�����������B����莞�̉��x�ቺ�́A1�`2�����x�ɗ}������B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| �����������ނ��f�M����2�`5���������ނ��J��
���̉��ɕ~�����g�݂̊Ԃɕ~���l�߂Ďg���B�ǂȂǂ̒f�M�ނ����ǁB�����ɒf�M�K�X������߂��C�A���܂ނ��Ƃ���f�M���������A������45mm�ɗ}���邱�Ƃɐ����B ���Ɏg���₷�����邽�߁A�����̔z���������A�_�炩�������������B���g�H�@�ɂ��ؑ��Z��̏ꍇ�A���g�݂̌��݂�45mm����ʓI�B�������A�ȃG�l�Z��̍ō��N���X���擾����ꍇ�A45mm����ꍇ�������A�����̍����̍Ē��߂���Ȃǂ̎�Ԃ��������Ă����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���O���[���؏������Ζ@�ɔ��f�G�l���������J�n
�O���[���d�͏؏���n�����g�������i�@�i���Ζ@�j�̎Z��E�E���\���x�œ�_���Y�f�iCO2�j�r�o�팸�ʂƂ��Đ��荞�ނ��߂̌����ɒ��肵���B �G�l���ϑ��������ƂƂ��ĊO���@�ւɗL���҂���Ȃ錟�����ݒu�A�F�X�L�[����Ώ۔͈́A�F�؊�ACO2�팸�ʂ̊��Z�W���Ȃǂɂ��ĔN�����߂ǂɌ������ʂ��܂Ƃ߂�B���Ζ@�ł͍��N3���̍����ŁA�����N���W�b�g�A�I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g�iJ-VER�j�����x�ł�CO2�r�o�팸�ʂ��V���ɎZ��ΏۂƂȂ�������A�O���[���d�͏؏��͑ΏۂƂ��Ė��L����Ȃ������B�G�l���͍��̈ϑ����ƂƂ��Č��I�ȔF�ؑ̐����\�z���邱�Ƃʼn��Ζ@�ւ̔��f��ڎw���A�ăG�l�̕��y�g��ɖ��߂�\�����B������i�߂�ψ���́u�O���[���G�l���M�[�F�؉^�c�ψ���v�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ��������Ƃ̏ȃG�l�����i��ڎw���u���ŃJ�[�{���E�I�t�Z�b�g���x�v
�{���̒�����Ƃ̏ȃG�l���M�[��𐄐i���邽�߁A�ȃG�l�w�͂Ő��܂ꂽ�uCO2�r�o�팸�ʁv�i�ȉ��u�N���W�b�g�v�j����ƂƂ̊ԂŔ������邱�Ƃ𒇉��u���ŃJ�[�{���E�I�t�Z�b�g���x�v��2009�N�ɑn�݂����B ���{�͂��̐��x���ŏ��Ɋ��p���鎖�Ǝ҂��A���ȂփI�t�Z�b�g�E�N���W�b�g�iJ-VER�j���x�Ɋ�Â��u�N���W�b�g�v�̐\��������Ɣ��\�����B���{�͍���A�N���W�b�g�̔������T���Ă����l���B�u���ŃJ�[�{���E�I�t�Z�b�g���x�v�ł́A�����i�������Ǝҁj�̃V�[�Y�Ɣ�����i��K�͎��Ǝғ��j�̃j�[�Y���}�b�`���O������{�Ǝ��̒���@�ցB���{�Ƒ��{�n�����g���h�~�������i�Z���^�[���A�g���Đݒu�E�^�c���Ă���B �o�T�uJFS News�v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȂ́A�r�o�ʎ���œƎ��Č����B���ȂɑΈ�
���g����̏d�v�{��ƈʒu�t���鍑���r�o�ʎ���ɂ��āA�ʊ�Ƃ̎��Ԃ܂��āA�����I�ȍ팸�ڕW��ςݏグ��u�{�g���A�b�v�^�v�̐��x�v�ɒ��肷��B �Y�ƊE���߂����\����2013�N�ȍ~�̎���s���v����x�[�X�ɁA���Ǝ҂�����ݒ肵���ڕW�����ɐ\���B�����R���E�F����s���X�L�[�����������Ă���B���S�̂̍팸���ʂɂ��ƂÂ��A��Ƃ��Ƃɔr�o�g�����蓖�Ă�u�g�b�v�_�E���^�v�̐��x���u��������Ȃւ̑ΈĂƂ��đł��o���_��������B�Y�ƍ\���R�c��̐����@���[�L���O�O���[�v���J���A�{�g���A�b�v�^�̖ڕW�ݒ��A�]���E���̂�����Ɋւ��錟�����J�n����B11�������߂ǂɌo�Y�ȂƂ��Đ��x�Ă��܂Ƃ߂�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/10�@]�@�@�� |
|
|
| �����{�G���N�\�����Ɠd�̏���d�͂��X�}�[�g�t�H���ŊǗ�����V�X�e�����J��
�R���Z���g�ɍ������މƓd�̃v���O�����ɃZ���T�[�����t���A����d�͂𑪒肷��B�ƒ���ɐݒu�����u�z�[���^�[�~�i���v��ZigBee�ŒʐM���A����d�͂̃f�[�^���W�ăT�[�o�[�Ȃǂɑ��M����B �f�[�^�̓O���t������A�_��҂̃X�}�[�g�t�H���ɑ�����B��ʂ̑���ɂ��A����d�͌n�������̒�~��A�d�͎��v����萅�������ꍇ�A�G�A�R���̐ݒ艷�x�������I�ɂ������萧����ł���B�č��ł͖���LAN��p���Ɠd�̎g�p�d�͂��R���g���[�����鎟���㑗�d�Ԃ̎��p�����i��ł���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���i�w���z���G�l���M�[�́A�}���V�����p�˕ʑ��z�����d���n�߂�Ɣ��\
�V���ɊJ�������p���[�R���f�B�V���i��p���邱�ƂŁA�}���V�����e�˖��̑��z�����d���\�Ƃ����B ���}���V���������660���̑��z���p�l����~���A�e�˂ɏo��1.2�L�����b�g�������蓖�Ă���̂ŁA�e�ƒ�ł́A�ˌ����[�U�[�Ɠ��l�ɓ����d�͂Ƃ̒��ڌ_��ɂė]��d�͂̔��d���\�ƂȂ�A�ߖ̃����b�g������ł���B���Z�ł́A���z�����d�V�X�e�����Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׁA�d�C�������������4,000�~���x�����Ȃ�B�܂��A�e�˂̃��r���O�ɔ��d�ʂ�CO2�팸�ʂ���ڂŕ����郂�j�^�[��ݒu���邱�ƂŁA���Z�҂̏ȃG�l�ӎ������߂邱�Ƃ����҂����B �o�T�u�W���p���}�[�P�b�g�v |
|
|
| �����d�C���z�����������A������6�����Ԃɉ�����LED���H����
�V�������傤�̂́A�~���[�v�ƏƎˊp�x�ݒ�̋Z�p����g���A�z�����̗����ʂƁA�V��ʂ̑O�≜��LED�̊p�x��ς��Ĕz�u�B���ʂ���̌��ʼn����܂ŏƂ炵�A�V��ʂ���̌��ōL��������������B ���傤�̂̓����Ƀ��u��݂��A�\�ʐς𑝂₵�ĕ��M�������߂��B����ɂ���āALED�Ɠd���̐v������6�����Ԃ܂ʼn����A�����e�i���X�R�X�g���팸����B���ⓔ400W�����̖��邳�́u400�V���[�Y�v�A300W�����́u300�V���[�Y�v�A250W�����́u250�V���[�Y�v�Ōv14�`�������낦���B���݂̃|�[���i�}���a�͒��a60.5mm�~120mm�j�Ɏ��t���\�ŁA����{�̂������j���[�A���ł���B�|�[���g�b�v�^�C�v�ƃA�[���^�C�v�ɑΉ�����B���i�̓I�[�v���ŁA�]���̐��ⓔ��3�{���x�ɂȂ錩���݁B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| ���p�i�d�H�A�G�l�g�p�ʌv���ƊȈՐf�f�Z�b�g�����z3���~�Œ�
�ȃG�l��̗��Ăɂ̓G�l�g�p�ʂ̏ڍׂȌv�����������Ȃ����A��p�@��̓����Ȃǂō��z�ȏ�����p���l�b�N�ɂȂ�B���̂��߁A���Ђ͔��N�ȂǒZ���̒�����O���ɒ�z���T�[�r�X����A���Ə��̏ȃG�l�����ɂ�����R�X�g�}�����x������B �V�T�[�r�X�͓d�͂ɉ����ăK�X�A�����̎g�p�ʂ��v16�J���܂ő��肵�A����ʂ̐��ڂ�������O���t�ƊȈՐf�f�����Z�b�g�Œ���B�_����Ԃ�6�`24�J���B�I�t�B�X�r���̃e�i���g��`�F�[���X�܂Ȃǂɒ�Ă���B���Ђ̌��݂̏��i�E�T�[�r�X�Ō���ƁA�ڋq���v���@����w�������ꍇ�A�H����݂Ŗ�60���~������ق��A�ʐM�E�T�[�r�X���p���ȂǂŌ�9000�~���K�v�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����j�E�`���[���A���{���̍����N���W�b�g���x�����p�����J�[�{���I�t�Z�b�g�����{
�x�r�[�p�̎��I���c��Ώۂ�1�`2���ɃJ�[�{���I�t�Z�b�g�L�����y�[���Ƃ��Ĕ̔������uCO2�r�o���t�x�r�[�p�����ނv�ŁA�u�����N���W�b�g���x�v���g���ăJ�[�{���I�t�Z�b�g�����{�����B ����13���Ə��̃o�C�I�}�X�ɂ��CO2�r�o�ʍ팸���Ƃɂ���Ė�2300t��CO2���I�t�Z�b�g�����B���L�����y�[���ł́A���ԓ��̎��I���c�̔��ʂɉ�����1�p�b�N�ɂ�CO2��1kg�I�t�Z�b�g����r�o�����w���B�ߋ���1�A2��ڂ̃L�����y�[���́A�C�O�Ŕr�o�팸�����CO2��Ώۂɂ������A�����3��ڂ͍����̊����P��ړI�ɁA�����ł�CO2�r�o�팸�ɍv�����邱�Ƃɂ����B1�`3��ŃI�t�Z�b�g����CO2�̍��v�́A3��ڂ�2300t�������A���̖ؖ�70���{��1�N�Ԃɋz������ʂɂ������1��t�ɒB�����B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| ��BSI�W���p������{�X�N���[���ɐ��E���̔F�BISO50001�̕��y���i�}��
���N���s�����\��̐V���ۋK�i�uISO50001�v�i�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���j�̔��s�ɐ�삯�āA���̂قǐ��E���ƂȂ�ISO50001�̍��ۋK�i�āiDIS�j�ƁA���{���ƂȂ�uBS EN16001�v�iEU�̃G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���j�̔F�؎��^�����{�X�N���[�������ɑ��Ď��{�B ����{�X�N���[�������͑��Ђɐ�삯�ē��F�؎擾�ւ̎��g�݂�i�߂��B�F�؎擾�̖ړI���i1�j���傲�Ƃ̏ڍׂŐ��m�ȃG�l���M�[�g�p�ʂ�c�����Ǘ����邱�ƂŁA�ǂ̕���̂ǂ̍s���ŃG�l���M�[���ʂɎg�p���Ă��邩������i2�j����CO2�r�o�ʎ���ɎQ�����邽�߂ɁA���Ђ�CO2�r�o�ʂ𐳊m�ɔc���ł���̐�����鄟�����ƂȂǂƂ��Ă���B�G�l���M�[�}�l�W�����g�V�X�e���\�z�Ɍ����A������ݔ��֘A�̕���ɐ��������֘A��ЎЈ�����������G�l���M�[�ψ����ݒu���A�Г��̃G�l���M�[�g�p�S�ʂɊւ���������̌������s���Ă����B �o�T�u���V���v |
|
|
| �����ȁA�r�o�ʎ����3�Ē֎Y�ƊE�z���̕�����
�ő�̏œ_��������Ƃɔr�o�g�����蓖�Ă���@�ɂ��ẮA3�Ă���邱�Ƃɂ����B���Ȃ͂���܂ő��ʕ����������咣���Ă������A�ꕔ�Y�ƊE�ɔz�����āA3�Ă̂���2�ĂɁA�Y�ƊE������₷�����P�ʕ����荞�B ���x�̑ΏۂɂȂ�̂́A�d�͉�Ђ�[�J�[�Ȃlj������ʃK�X���ʂɔr�o���Ă����ƂŁA2013�N�x������{����B�K����������Ƃ̊C�O�ړ]��h�����߁A�S�|��ЂȂnj��������ۋ����ɂ��炳��Ă����Ƃ�A�r�o�ʂ̑�����Ƃɂ͔r�o�g�̗D���������B�G�R�J�[��ȃG�l�Ɠd�ȂǁA�r�o�ʍ팸�ɍv�����鐻�i�������Ƃւ̗D������l����B����̈Ă̂����A��͓d�͉�Ђ����Ɍ��P�ʕ��������A���̂ق��̊�Ƃ͑��ʕ����ɂ��āA�ƊE���Ƃ̊��ߋ��̔r�o���тɊ�Â��č����r�o�g�����蓖�Ă�����B ������̈ẮA�d�͉�Ђ��܂߂����ׂĂ̑Ώۊ�ƂɌ��P�ʕ���������āB �O�ڂ͑Ώۊ�Ƃ��ׂĂ̔r�o�ʂ𑍗ʕ����ŋK�����A����Ȃ��r�o�g�͌��J���D�Ŕ��킹��āB �o�T�uAsahi.com�v |
|
|
| ���L���s�A�s���Q���̔r�o�ʎ�������s
�Q���҂̕�W������͍̂L���s�̓����ꏊ��1�N�ȏ�ݏZ���Ă���1000���сB��t�͐撅���B�d�C�Ɠs�s�K�X���ΏۂŁA���N�x��11����12�����̎g�p�ʂ�O�N�����ɔ�ׂĂǂꂾ���팸�����������j�[�Ŋm�F���Ďx������B �s�͍팸���̂b�n2��1kg������5�~�Ŕ������A�s���̊�Ƃɔ̔�����B�s�͎Q���҂ɍ팸�ʂɉ��������z�������U�荞�݂Ŏx������B�����̂��s����CO2�팸�ɑ��Č������x�����鐧�x�͑S���ł��������Ƃ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������s�ƍ�ʌ���CO2�r�o�ʎ���ŘA�g����
���݂̐��x�ł͂��ꂼ��̓s�����Ɍ����Ă��钆�����Ə��̔r�o�g�̎���𗼒n��̂������ł��F�߂�B ����͈͂��L���邱�ƂŎs������������A���̒n��ɂ�CO2�팸�̎��g�݂��L����l���B�����s�ƍ�ʌ��̍팸�`���̑Ώۂ͑�K�͂ȃI�t�B�X�r����H��ȂǂŒ������Ə��͊܂܂�Ă��Ȃ��B�s���̋����z�����r�o�g�̎���͒�����Ƃ̐��x�ւ̎Q���𑣂��_��������B��̓I�Ȑ��x��^�c�ɂ��Ă̏ڍׂ͍���A��������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����s�s��������ƌ����ɏȃG�l�A�h�o�C�U�[��h��
NPO�@�lKES���@�\�̋��͂āA�o��팸��ȃG�l�̖�������钆����Ƃɔh�����A���ߍׂ����A�h�o�C�X����B ���Ə��̂ǂ��ɃR�X�g���������Ă��邩������悤�ɂ��邽�߁A�G�l���M�[�g�p�ʂ̊Ǘ��̎d������A�h�o�C�X����B�ݔ����C���l���Ă��钆���ɂ́A�����ȃG�l�f�f��⏕�E�Z�����x�Ȃǂ��Љ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/9�@]�@�@�� |
|
|
| �����ŃL�����A���Y�Ɨp�ɂ��Ή������V�^�q�[�g�|���v�M���@���J��
�����d�͂Ƌ����ŁA�]���̋�⎮�`���[�ɔ�ב啝�ȍ���������^�]�͈͂̊g��Ȃǂ������������q�[�g�|���v���M���@���J�������B ��e�ʂ̃C���o�[�^�[�c�C�����[�^���[���k�@���̗p���邱�ƂŁA����̃^�[�{�Ⓚ�@���݂̗�pCOP�i���ьW���j6.30�����������ق��A25�`35���̒��ԉ��x��̑������\�B�Y�Ɨp���^�{�����ȂǁA����܂Ń`���[�ł͑Ή�������������L������ɍ̗p�ł���Ƃ��Ă���B���W���[����A�����A�ő�4800�n�͂��ꊇ����ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���听���݂Ɠ����d�C���l�����m���ďƖ�����œK���䂷��V�X�e�����J��
�u������^�l���m�Z���T�v�������J�����A�l�̍ݐȏɉ����ă]�[���P�ʂŋƏƖ��𐧌䂷��u����������V�X�e�����J�������B ���̎�����^�̐l���m�Z���T�́A�l�̂������鉷�x���̂��̂�F�����APC�̔��M����˂ɂ�鉷�x�ω��Ƃ̎��ʂ��\�ŁA�]���̐l���Z���T�ɔ�ׂČ�F�������Ȃ��A�Î~���Ă���l���܂߂āu�݁^�s�݁v���m���Ƀ��A���^�C���ŔF�����邱�Ƃ��ł���B�s�݃]�[���ł́A�ݒ艷�x��^�]���[�h�̌y�����s���A�ݐȗ��ɉ������O�C�ʗ}�����s���ċ��ׂ�ጸ����悤�ɂȂ��Ă���A�Ɩ��̐���ƕ����āA�]���̈�ʓI�ȃI�t�B�X�Ɣ�ׁA�����S�̂ł��悻50���̏���G�l���M�[�팸���ʂ������߂�Ƃ����B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �����c���쏊���d���R���f���T�E���X��LED�Ɩ��p�d����W��
���o�̓R���f���T�ɓ��Ђ̐ϑw�Z���~�b�N�E�R���f���T�iMLCC�j��p���Ă���A���nj^��LED�Ɩ��̊Ǔ��ɓ����ł���B�A���~�d���R���f���T��p����ꍇ�Ɣ�ׂď��^���ł���ق��A�������������Ƃ��\�B���͂�AC100V�����200V�̗����ɑΉ�����B LED�Ɩ��̒�d������̂��߂�DSP�}�C�R�����g�p�B�X�C�b�`���O���g����200kHz���x�B�o�̓R���f���T�͖�5��F��MLCC��2�g�p�B���̗e�ʂ�MLCC�ł̓��b�v���d�����z��������Ȃ����ADSP���ł̐�����H�v���邱�ƂŁA�Ɩ��̂�������������Ȃ��悤�Ɏd�グ�Ă���B���H�͔�≏�̏��~���^�ŁAPFC�i�͗����P�j��H�݂͐��Ă��Ȃ��B�O�`���@�́A180mm�~19.4mm�~6.5mm�B �o�T�uBP�j���[�X�v |
|
|
| ���J�[�{���t���[�R���T���e�B���O���s�������̔r�o�n�o�x�����Ƃ��J�n
�����K�͍H��̔r�o�g���F�߂���ɂ́A�팸���Ƃ̑O��œs�ɐ\�����ނ̒�o���K�v�ŁA�팸�ʂ̎Z��ɂ͓o�^���ꂽ�@�ւ̌����K�v�ŁA50���~���x������Ƃ݂��Ă���B�����̍�Ƃ̎�Ԃ�R�X�g�̕ǂ��������߁A�葱���A�����ň�����B �������A�N�Ԃ��悻200�g���ȏ��CO2�팸���ł��A�n�o�����r�o�g�͔�����邱�Ƃ������Ƃ��Ă���B�N��100�����x�̃T�[�r�X���p�ŁA2���`5���g���̔r�o�g�̒��B���߂����B�`�����Ԃ��I������5�N��ɔr�o�g�̕s����������Ƃ݂Ă��āA������r�o�g�̌@��N�������n�߂�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N���u���E�G�l���M�[����v���O�����v���J��
���{��������̔��{�I�[����}�邽�߂�2009�N�x�ɑł��o�����u�X�N�[���j���[�f�B�[���v�̈�ŁA���݁A�����w�Z�ւ̑��z���p�l���ݒu����������Ă���B�w�Z�ł͑n�E�~�E�ȃG�l���M�[�̎��H�ɗ��܂炸�A���z���p�l�������p����������̏������i�݁A�L���Ȋ�����v���O�����̎��v�����܂��Ă���B ���z�����d�𒆐S�Ƃ����n�G�l���M�[��~�G�l���M�[�̎d�g�݂�������A�ȃG�l�Ɋւ���m���Ȃǂ����w���ɂ킩��₷���`���鋳�ނŁA���Ƃ����ʓI�Ɏ��H���邽�߂̃K�C�h�u�b�N�A���[�N�V�[�g�A�X���C�h���J�����A�����Œ���B�܂��A��������s�����������́A���E�G�l���M�[���ƌ��C������{�\��B7������e�n�̋���ψ���ƘA�g���A2010�N�x�͏��w�Z3�Z�ł̃g���C�A�����s���A2011�N�x�ɖ{�i�����\��B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| ���啪����CO2�r�o�ʎ�����J�n
��ʉƒ�ɐݒu�������z�����d�ɂ���_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ̍팸�����u�����N���W�b�g���x�v�����p���Ċ�Ƃɔ̔�����r�o�ʎ�����x���n�߂��B���̔F�؈ψ���Ɏ����̂̎��g�݂Ƃ��ď��߂ď��F���ꂽ�B ����ɑ��z�����d��ݒu���Ă��鐢�т�����Ƃ���u�����������z����y���v��ݗ��B��������N3���ɕ��鑾�z�����d�̑����d�ʂȂǂ����CO2�r�o�ʂ��Z�o���A�W���팸�����N���W�b�g�����đ��ƂȂǂɔ�������Ă��炤�B���z�����d�ɂ��1���ѓ�����̔N��CO2�팸�ʂ͕��ϖ�0.7�g���ŁA���ۑ���ł͖�700�~���ƂȂ�B����10���т̉���𗈔N3���܂ł�300���сA2012�N�x���܂ł�2500���тɑ��₷�ڕW���f���Ă���B���v�͌��̊��ۑS����Ɋ�t���A�A�тȂnj����̊����Ƃɏ[�Ă�\��ŁA���R�ɂ₳�������z�����d�̕��y�Ɗ��ۑS�́g�ꋓ�����h��_���B �o�T�u�����j���[�X�v |
|
|
| ������̏ȃG�l�A���R���V�F���W�����w�����
��_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂ����炷�̂ɁA�}�C�J�[�A�Ɠd�A�Ɩ��Ȃǂ�CO2�r�o�ʂׁA�u���C�̎����ۉ����T����v�u���z�����d�̓����v�u�f�M�H���v�ȂNJe�ƒ�ɍ��������g������ŃA�h�o�C�X���鎖�Ƃ荞�ށB �ȃG�l�@�̌��C������1��l���u���R���V�F���W���v�ɔC���B�ƒ�̔r�o��ȃG�l�@��ւ̔����ւ��ɂ���10�����тɎw�삷��v��ŁA���N�x�̊T�Z�v����20���~���v�シ��B���H����3��`4�琢�т�ΏۂɎ��s����B�R���V�F���W���ɂ́A�d�͉�Ђ�K�X��ЁA���t�H�[���Ǝ҂̎Ј���������ށB���А��i�̔��荞�݂����Ȃ��Œ����I�ȗ���Ő�������悤�A���Ȃ͗ϗ��K���݂���Ȃǂ̕��@���������Ă���B �o�T�uasahi.com�v |
|
|
| ���F�{�����u�G�R�ʋv�u�ȃG�l���C�v�ɕ⏕���x�n��
4���{�s�̌��n�����g���h�~���Ɋ�Â��ă}�C�J�[�ʋ̌����Ȃǂ�i�߂�u�G�R�ʋv�ƁA�Ɩ���LED���Ȃǁu�ȃG�l���C�v�Ɏ��g�ގ��Ə��ւ̕⏕���x��n�݂����B 11�����܂Ō�t�\�����t���Ă���B�u�G�R�ʋv�⏕�͉������ʃK�X�r�o�팸���ړI�ŁA1�J����300�l�ȏ�̏]�ƈ������鎖�Ǝ҂��ΏہB(1)���֏��d�����]�ԂȂǂ̏[�d�ݔ��̐����A(2)�G�R�h���C�u���H�̂��߂̔R��v�w���A(3)�]�ƈ����C�Ȃǂ̌o���3����1�����150���~�ŕ⏕����B�u�ȃG�l���C�v�⏕�̓{�C���[�A�H�ƘF�A�Ɩ��A�Ȃǂ̐ݔ��X�V�⎖�Ə����C�����钆����Ƃ��ΏہB�������ʃK�X�r�o�팸���ʂ��ݔ��P�̂�20���ȏ�A���Ə��S�̂�10���ȏ゠��̂������B1�疜�~������ɔ�p��3����1����������B�G�R�ʋ�717���~�A�ȃG�l���C��5�疜�~�̗\�Z�z�ɒB�������_�őł���B �o�T�uPRO�v |
|
|
| ���A�����J�G�l���M�[�ȁiDOE�j�A�A�M���{�r���́u�N�[���E���[�t�v���i��\
�N�[���E���[�t�́A�����̉����ɖ��F�̑f�ނ����ȓh���܂��g���A���z�M�������悭���˂����Č����̊����\�����}����̂ŁA���V���g����DOE�{���r���ł����āA�v�ɒ��肷��B���ł�DOE�̍��Ɗj���S�ۏᒡ�iNNSA�j�ł́A����200�������t�B�[�g���N�[���E���[�t�����A�G�l���M�[�R�X�g��N50���h���ߖĂ���B �A�����J��2020�N�܂łɉ��g���K�X�r�o��28%�팸��ڕW�Ƃ��Ă���ADOE�ł́A�N�[���E���[�t���i�͂��̎�i�Ƃ��Ă���߂ėe�Ղň����ȕ��@���Ƃ��A�������������Ă���r���̂��߁A�K�ȉ����f�ނȂǂ��������w�j�����\���Ă���B �s�s�ł͖ʐς�50�`65%�������ƕܑ����H����߂Ă���A�q�[�g�A�C�����h���ۂ̑傫�Ȍ����Ƃ����B�N�[���E���[�t�ɂ��A�q�[�g�A�C�����h���ۂ��ɘa����A��[��̐ߖ�A�Y�f�r�o�팸���\�ɂȂ�B�����҂ɂ��ƁA���E���̓s�s�̉������N�[���E���[�t�ɁA���H���N�[���ܑ��ɂ���A���E�S�̂̒Y�f�r�o��2�N���ɑ���������M���ʂE�ł���B �o�T�uEIC�j���[�X�v |
|
|
| ��NEDO�A�u���\�G�l���M�[�Z�p�����v�\
�Đ��G�l�̊e����ōŐV����������ƂƂ��ɁA��v����ɂ��Ă͋Z�p���[�h�}�b�v���܂Ƃ߂��B�����āA�Đ��\�G�l���M�[�̓������x����X�}�[�g�O���b�h�i�����㑗�z�d�ԁj�����荞��ł���B NEDO�ł́A�Đ��G�l�̓����g�����{��Ƃ̍��ۋ����͋����ɖ𗧂ĂĂق����Ƃ��Ă���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȂ��ăG�l�S�ʔ������Ɋւ��鐧�x�Ă��
�Đ��\�G�l���M�[�͑S�Ă�ΏۂƂ��A���K�\�[���[�Ȃǂ̔��d���Ƃ̓d�C���������B ��������p�͓d�C�����ɓ]�ł���B�V�݂̔��d�ݔ��̓d�C�̑S�ʔ���������{�Ƃ���B����10�N��̔�������p�̑��z��4600���`6300���~�ŁA�W���I�ȉƒ�̕��S�z�͌��s��102�~����150�`204�~�ɏオ�錩���݁B�������A�d�͌n���̈��艻����p�͊܂܂Ȃ��B�����K�͍H��̕��S�́A25��kWh/���Ō��z12.5���`17���~�A�b�v�B2400���`2900���g����CO2�팸�̌����݁B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/8�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�d�@��SAP�A�����Ƃ̏ȃG�l���M�[�\�����[�V�����������J���ō���
����������N�_�Ƃ����o�c���P��ڎw���A���Y���ƃG�l���M�[�����������邱�ƂŁA�ȃG�l���Ƃ�TCO�iTotal Cost of Ownership�F�����L�R�X�g�j�팸�ƕi��������x������ue��eco-F@ctory�v�𐄐i���Ă���B �܂��ASAP�ł́A�uSAP Perfect Plant�v�\�z�̂��ƁA���E�e���̐����Ɛ��Y����ŁASAP�\�t�g�E�F�A�ɂ��������ƃR�X�g�팸���x�����Ă����B ����A���Ђ́A�O�H�d�@�̐�������ł̃G�l���M�[�Ǘ��Z�p�ƁA���Y�Ǘ��E�o�c����̉������x������SAP�\�����[�V������A�g�����邱�ƂŁA�������ꂩ��o�c�ɂ�����G�l���M�[�Ǘ��\�����[�V�����������ŊJ������B �o�T�ujapan.internet.com�v |
|
|
| ���I�������A�ȃG�l��f�[�^�̎��W�E�~�ς�e�Ղɂ���l�b�g���[�N�R���g���[���[����
�d�͎g�p�ʂ≷�x�ȂǏȃG�l���p�̃f�[�^���W�E�~�ς�e�Ղɂ���u�Z���T�l�b�g���[�N�R���g���[��EW700�v���B LAN�|�[�g�AWEB�T�[�o�[�@�\�A�d�����j�b�g�ASD�J�[�h���j�b�g�ȂǃG�l���M�[�Ď��ɕK�v�ƂȂ�@�\����̉��B�e��̃Z���T�[�Ōv�����������W�߁A����I�ɃT�[�o�[��SD�J�[�h�ɕۑ�����B�I�[���C�������@��̂��ߐݒ肪�e�ՁB�ȃG�l��ړI�ɂ����G�l���M�[�́u�����鉻�v�V�X�e�����A���[�U�[��Ǝ��g�ŃX�s�[�f�B�[�ɍ\�z�ł���B�ő�124��̃Z���T�[�Ɛڑ��\�ŁA�d�́A���x�̂ق����ʁA���͂Ȃǂ̃f�[�^���ꌳ�Ǘ��B���肷��Ώۂɍ��킹�Čv������Ԋu��擾��ڂ����ݒ�ł��A���P�]�n�������I�ɒ��o����V�X�e���ƂȂ����ƂŁA����킩��B �o�T�uECO Japan�v |
|
|
| ���p�i�\�j�b�N�́A�H��܂邲�ƏȃG�l�x���T�[�r�X�J�n
CO2�팸�̃m�E�n�E�����p���A�H��̏ȃG�l�ɕK�v�ȋZ�p�E�ݔ��E�l�ށE�������I�ɒ���ȃG�l�x���T�[�r�X���J�n�����B �]���̃T�[�r�X���A�d�C�A�K�X�Ȃnj����ݔ���ΏۂƂ���̂ɑ��A���T�[�r�X�ł́A�����ݔ��ɉ����A���Y�ݔ��̉ғ��Ȃǂ𑍍��I�ɔ��f���A�H��S�̂̏ȃG�l��}��̂������B��N�x�A���T�[�r�X�̊�Z�p�ƂȂ�SE-Link��a�̎R�H��ɓ������A�����O�Ɣ�ׂ�CO2�r�o�ʂ�15���팸�������т�����B �ȃG�l�x���T�[�r�X���Ƃ̓��e�́A�@�ȃG�l�f�f�A�A�����鉻�x���A�B�ȃG�l�\�����[�V�����Z�p�A�CSE-Link �iSave Energy Link�j���Y�ݔ��ƌ����ݔ��̏������A���^�C���ŏW�A���Y��G�߁A�V��ɉ������ȃG�l���[�h���œK���䂷��Z�p�uSE-Link�v�����p���A�H��̕�I�ȏȃG�l���������B�D�H��܂邲�Ɗ������p�b�P�[�W�T�[�r�X�ȃG�l�����łȂ��A�r�������A���r�����T�C�N���A�r�K�X�����A�������T�C�N���A�y��n�����A���z�����d�ȂNJ��E�G�l���M�[�Z�p���g�[�^���ŒB �o�T�u���r�W�l�X�v |
|
|
| ���t�W�N�����q�[�g�p�C�v�ɂ��T�[�o�[�ȃG�l�V�X�e�����J��
�T�[�o����d��8800kW�̃��f���ł͓d�͎g�p�����iPUE�j���]�����ɔ�ׂ�7���ጸ�ł���V�X�e�����J�������B �V�ȃG�l�V�X�e���̓X�e�����X���̃q�[�g�p�C�v���T�[�o�����ׂ̗ɐݒu���A�ꕔ���n��ɏo��\���B�T�[�o�����̉��x�ɔ�ׂĊO�C�����Ⴂ�ꍇ�Ƀp�C�v���̍쓮�t�i��փt�����j���ÌłƏ������J��Ԃ��B�p�C�v����ꂽ�^���N���̐����X��␅�ƂȂ��ăf�[�^�Z���^�[���p����d�g�݁B �o�T�uAsahi.com�v |
|
|
| ����CA�e�N�m���W�[�A�d�́ECO2�r�o�Ǘ����|�[�e�B���O�\�����[�V�����\
�T�X�e�C�i�r���e�B�i�����\���j�\�����[�V�����uCA ecoSoftware 2.0�v�́A�d�͂␅�̏���ACO2�r�o�ʂ𑪒�E�Ǘ�����\�����[�V�����ŁA���ʑ���ƃv���Z�X�̎������ɂ���āA�g�D�̃T�X�e�C�i�r���e�B�v���O�����Ǝ��ƖڕW��A�g�����邱�Ƃ�ڎw���B SaaS�`���̃��|�[�g�E�t�H�[�L���X�g�c�[���uCA ecoGovernance 2.0�v�Ɠd�͊Ǘ��\�t�g�E�F�A�uCA ecoMeter 2.0�v�ō\�������B CA ecoGovernance�́A�T�X�e�C�i�r���e�B�̍��ۃK�C�h���C���ł���uGlobal Reporting Initiative�iGRI�j�v�uCarbon Disclosure Project�iCDP�j�v�A�p���̏ȃG�l���M�[���x�uCRC Energy Efficiency Scheme�v�Ȃǂ̊�ɉ������N�������쐬�ł���B CA ecoMeter�́A���܂��܂ȃf�o�C�X��V�X�e�������āA�n���I�ɕ��U�����ݔ�����G�l���M�[�֘A�̏������W����c�[���BModbus TCP�ABACnet�ASNMP�ȂǁA���܂��܂ȃv���g�R���ɑΉ����A�ً@�퍬�݊��ɃA�N�Z�X����Q�[�g�E�F�C�������A�����̃r���Ǘ��V�X�e���Ƃ������ł���Ƃ����B �o�T�uEnterprise Watch�v |
|
|
| ���O�c���݁A�H��CO2���ғ������ʂɔc������V�~�����[�V�����Z�p�J��
�����̐��Y���C�����������߂�V�~�����[�V�����Z�p�ƁACO2�r�o�ʎZ�o�v���O������A�������邱�ƂŁACO2�̌��ʓI�ȍ팸��@���m������BCO2�팸�̋@�^�����܂钆�A�����ԁA�H�i�A���i���[�J�[�̍H��V�݂�ȃG�l���C�̒�Ă�CO2�팸�c�[���Ƃ��Đ��荞�ށB �J������CO2�r�o�ʂ̃V�~�����[�V�����Z�p�́A�H��̐��Y�ݔ��̃G�l���M�[����ʂȂǕ����������v���O�����Ɏ�荞�݁A���f���ƂȂ�CO2�r�o�ʂ��Z�o�B���Y�ʂ�C���Ґ��Ȃǂ̕ϓ��v���ɉ�����CO2�ʂ��V�~�����[�V��������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ��Cisco�C����HEMS�s��Q���𐳎����\
Cisco Home Energy Management Solution�͎�ɓ�̗v�f�ō\�������B�܂��A�^�b�`�E�X�N���[���t���t���f�B�X�v���C�������[���uHome Energy Controller�i���i�ԍ�CGH-100�j�v�����[�U�[�̏Z��ɒ���BHome Energy Controller�̓��[�U�[�̃G�l���M�[���p�ɂ���������\������ȊO�ɁA�Ɠd���i�̃T�[���X�^�b�g�Ȃǂɐڑ����ăG�l���M�[���p���Ǘ�����@�\������B���̂��߁AZigBee�△��LAN�Ƃ����������ʐM�ɑΉ����Ă���B�Ⴆ�A�①�ɂ������e�i���X����K�v�����邱�Ƃ�A�①�ɂ��Ȃ������������ɂȂ�Ƃ����������A���[�U�[�ɒł���悤�ɂȂ�B ���̒[���ȊO�ɁA�d�͎��Ǝ҂ɁuCisco Energy Management Services�v�ƌĂ�SaaS�isoftware as a service�j�����B���̒[����SaaS�̑g�ݍ��킹�ɂ��A�d�͎��Ǝ҂͕K�v�ɉ����ă��[�U�[�̃G�l���M�[���p�������I�ɊǗ�������A���Ђ̃l�b�g���[�N���̃G�l���M�[���p�̏ڍ̃��|�[�g��Ƃ������T�[�r�X���\�ɂȂ�B �o�T�uTech-On�v |
|
|
| �����ŃL�����A���Y�Ɨp�ɂ��Ή������V�^�q�[�g�|���v�M���@���J��
�����d�͂Ƌ����ŁA�]���̋�⎮�`���[�ɔ�ב啝�ȍ���������^�]�͈͂̊g��Ȃǂ������������q�[�g�|���v���M���@���J���B ��e�ʂ̃C���o�[�^�[�c�C�����[�^���[���k�@���̗p���邱�ƂŁA����̃^�[�{�Ⓚ�@���݂̗�pCOP�i���ьW���j6.30�����������ق��A25�`35���̒��ԉ��x��̑������\�B�Y�Ɨp���^�{�����ȂǁA����܂Ń`���[�ł͑Ή�������������L������ɍ̗p�ł���Ƃ��Ă���B���W���[����A�����A�ő�4800�n�͂��ꊇ����ł���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���o�Y�ȁA�����S�̂̏ȃG�l���\�Z�o���@��JIS��
���{���ށE�Z��ݔ��Y�Ƌ����JIS�̌��Ă�����B�l�̑̂ɍ��킹���`��ɂ��邱�Ƃœ��̗ʂ����Ȃ��Ă��\���Ɍ��܂ł����ߓ������A���f�M�����A���Ȃ����Ő�����ߐ����ʂ̍����V�����[������Ώۂɂ���B��������Ȃǂ̑�s�s�����܂ޓ��C������R�z�n���ɂ������n��ɏZ��4�l�Ƒ����A�����E�V�����[�̉��x��40���Ŏg���ꍇ��W���P�[�X�ɐݒ肷�錩���݁B �����̒n��̕��ϊO�C���x�̒��Ő������ĕ������̂ɕK�v�ȃG�l���M�[�ʂ��v�Z����B�ȃG�l����{���������Ǝ{���Ă��Ȃ������̔N�ԃG�l���M�[����ʂ̔�r�ɂ��G�l���M�[����ʍ팸�����Z�o����B2011�N3�������߂ǂɓ��{�H�ƋK�i�iJIS�j�Ƃ��Đ��肷��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����{�́A�������ʃK�X�A�r�o�g�̊C�O�w�����~���A�����g�[
������Ƃ�_�ƕ���Ȃǂō팸�ł�������d�͂Ȃǂ̑��Ƃ��������u�����N���W�b�g���x�v�ɂ��팸�ʂ��c�菑���Ԓ��Ɍ��݂�100�{�ɓ�����1���g���܂ő��₷�B�e�n�ŏ����̏ȃG�l���Ƃ����������A�֘A�Y�Ƃ̊������A�ٗp�̊g���_���B ���{�̉������ʃK�X�̔r�o�ʂ́A���[�}���E�V���b�N��̌o�ϒ���ŁA2008�N�x��1990�N�ɔ�ׁ{1.6���Ɣ����̂��߁A�z������C�O����w�������r�o�g�����܂߂�A�ڕW��B���ł���\�������邪�A�m���ɂ���ɂ́A����ɐ��疜�g�����̔r�o�g�̒lj����B���K�v�Ƃ����B���̂��߁A���{�́A�lj����B�ɉ�镪�������N���W�b�g���x�ɐU���������j�����߁A�܂��d�͉�Ђɍw����v�����邱�Ƃɂ����B �����N���W�b�g���x�́A2008�N�̊J�n�ȗ��A����74�Ђ��x�����Ē���295�Ђōs���ȃG�l���Ƃ����F����A�i�߂��Ă����B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����{�G�l���M�[�w��Ǝ����w��l�b�g�Łu�G�l���M�[����v���J�n
�G�l���M�[�ɂ��Đ������m�����L�����������Ƃ��_���B����͖����ŎQ���͎��R�B ����́u�����ҁv�Ɓu�����ҁv������B30��̏o���30���̐������ԓ��ŁA80���ȏ�ō��i�B4���̃N�C�Y�`���B�o�肳�����͖������ւ��B�����́u�㋉�ҁv���n�߂�\��B���́u�G�l���M�[�̊�b�m���v�A�u�G�l���M�[�̉Ȋw�v�A�u�G�l���M�[�̃G�s�\�[�h�v�Ȃǎ��R�Ȋw�A�Љ�Ȋw��10�̈悩��o�肳���Bhttp://www.ene-kentei.jp/ �����e�L�X�g�u�G�l���M�[����i���Ɖ���j�v�i�o�ŁF�G�l���M�[�t�H�[�����ЁA1,260�~�j�ŏo�肳���S�Ă̖��Ɖ�����f�ځB �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/7�@]�@�@�� |
|
|
| ���I���b�N�X�Ƒ勞���V��Аݗ��B�}���V�����Ɋ����d�͋���
�����ȍ����d�͂�d�͉�Ђ���ꊇ���B���āA�}���V�����̊Ǘ��g���⋏�Z�Ҍ����ɔ̔�����B �����d�͂��ƒ�p�d�͂ɕϊ�����ϓd�ݔ��́A���Ђ������ƃ����e�i���X���s���A�Ǘ��g����e���Z�҂̕��S�͂Ȃ��B �d�͗����̍팸���́A�}���V�������L�����̊Ǘ���̌y����d�͗����ɏ[�Ă�B���Z�ɂ��ƁA���Z��100�˒��x�̃}���V�����ɓ��������ꍇ�A���p������2���ȏ�A�܂��͊e�Z�˂�5�����x�̓d�͗������팸�ł���B3�N�Ԃ�3���˂ւ̓�����ڎw���B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| ���O�m�d�@�̋���R���g���[���[�����j�N����400�X�܂�������
�g�����̖��ʂ��Ȃ����Ƃ��ړI�ŁA�@��̏W������ɂ��A�����I�ȋ@�̉^�]���\�ɂ���B �ő��Ŏ������j�b�g64����ꊇ�ŃR���g���[�����邱�Ƃ��\�B�X�܂ł̔�r�����ł́A�u�ݒ艷�x�������^�[�����[�h�ŁA�ݒ艷�x�ύX60����ɗ�[�ݒ艷�x24���ɖ߂��v�A�u�����Y��h�~���[�h�ŁA�X���Ԃɋ@��̉^�]���~���A�X���Ԓ��ɍĉ^�]�������ꍇ60���Ԋu�Ŏ�����~�v�A�u�ݒ艷�x�͈͐������[�h�ŁA��[�������x��22���ɐݒ�v�����Ƃ���A�p�b�P�[�W�G�A�R���Ŗ�18���A�K�X�q�[�g�|���v�G�A�R���Ŗ�20���̍팸���ʂ�����A����G�l���M�[�ʂ̍팸�Ɍ��ʂ��������Ƃ������ꂽ�B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���o���[���ȃG�l�����X���J�ƁA�n�M�ŋACO2�A35����
�S�������Ō��z�ʐ�2860m2�B�V����������ꂽ���R���𗘗p���Ĕ�����LED�Ɩ��̏Ɠx������B �o������t�߂̕ǂɂ͒f�M���ʂ̍��������J���A���W�߂��̓_�������炷�B�X���̒ʕ��͒n���ɖ��߂��g���l����ʂ��A�t�G�E�H�G�̓G�A�R�����g�킸�n�M�ʼn��x���߂���B����ɑ��z�����d���u�i�ő�o��32�L�����b�g�j�A���ԏ�ɑ��z���p�l���Ŕ��d����O����݂����B���ɓV��̌��˂���Z���~�b�N��p���A�Ɩ���}����d�g�݂Ȃǂ������B���K�͂̓X�܂ɔ�ׂď���d�͔͂N��700���~���������ށB NEDO�̎�����ȃG�l���M�[�����z�V�X�e�����؎��Ƃɗ��ʋƊE�̃��f���Ƃ��ĕ⏕�����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���X�^�[�o�b�N�X��������900�X�܂̃G�l���M�[���Ǘ����邽�߂ɓ�����SaaS�^�T�[�r�X���̗p
�X�܂̓d�C�A�K�X�A�����̎g�p�ʂ������v������@��̏������W�E�Ǘ�����\�t�g�E�F�A�̋@�\���C���^�[�l�b�g�o�R�ŗ��p����B ���̂��߁A��_���Y�f�r�o�ʂȂǂ��Z�o����e�튷�Z�W���̃����e�i���X�Ȃǂ̍�Ƃɂ���Ԃ͌���B�e�X�܂ɂ���������W�E�Ǘ��Ɩ����������ł��A�ē����ւ̊e��͏o������̍쐬�Ɩ��̐��x�����シ��B�܂��A�Ǘ��W���쐬�A�������v��̍쐬�x��������B �o�T�uITmedia�v |
|
|
| ���s�s�K�X�O�Ђ����z�M���[�ɗ��p����u�\�[���[�z���≷���@�v���J��
���z�M���p�̂��߂ɐ�p�v���ꂽ�z���≷���@�ŁA���z�M���W�߂�W�M��Ƒg�ݍ��킹���Ɩ��p�V�X�e���i�\�[���[�N�[�����O�V�X�e���j�́A4,000m2�i3�`4�K���āj�̃r���̏ꍇ�ŁA���z�M��g�ݍ��܂Ȃ��]���̃K�X�V�X�e���Ɣ�ׁA��g�[�̔N�Ԉꎟ�G�l���M�[����ʂŖ�24���ACO2�r�o�ʂ��21��(��34�g��)�ጸ���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| ���u�f�[�^�Z���^�[�̋�27���ŏ\���v�\�\�O�[�O�����������ȓd�͑�
�f�[�^�Z���^�[�̏ȃG�l��̑����́A�T�[�o���p���邽�߂̗�C�ƁA��p��ɔ�������g�C�Ƃ����邱�ƁB �T�[�o�E���b�N�Ԃ̒ʘH��Ƀv���X�`�b�N���̓V������t������A�ʘH�̏o������ɏd���r�j�[���E�J�[�e����ݒu�����肵�āA�z�b�g�E�A�C���i�g�C�ʘH�j�ƃR�[���h�E�A�C���i��C�ʘH�j��蕪����B �܂��A�ʏ�A�f�[�^�Z���^�[�̎�����21���ȉ��ɐݒ肳��Ă��邪�AGoogle�ł�27���ɐݒ�B�T�[�o�̒�i�z�����x��32���܂őΉ��ł���悤�Ȃ�A27�����邢�͂�����������������ł���B�����ݒ��27���ɂ��邾���ŁA���ƊE���ςŁw2.0�x�������Ă���PUE�i�d�͎g�p�����j���w1.5�x�Ɉ��������邱�Ƃ��ł���B 3�ڂ̓d�͐ߌ���Ƃ��āA�����̊O�C�������A���⎮�̗�p���������肵�ė�[���u��₤�悤��Ă��Ă���B�܂��A���z���Z�p�����ăT�[�o�̗��p�������コ����A�d���Ǘ��c�[��������A���d�͌����̍����V�^�@����w������Ƃ�����������������Ă���B �o�T�uCOMPUTERWORLD.jp�v |
|
|
| ���I���������Pcm�p�̑��@�\���W���[���g�����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e�����J��
�v���A����A�d���A�ʐM�̋@�\���W�ς���1cm�p�̃��W���[�����g�����G�l���M�[�Ǘ��V�X�e�����J������B �ݔ���V��A�ǖʂȂǂɃ��W���[����ݒu�B���x�A���x�A����x�ȂǗv���������������Ȃ���A�̉^�]�A��������M�t�@���̋쓮��K�v�Ȏ��Ɍ���Ȃǂ��ăG�l���M�[�����}����B��F���Ə��̃N���[�����[���ŏȃG�l���M�[���ʂ̎��؎������n�߁A���\���̃G�l���M�[�팸���ʂ������ށB2011�N�x�ɂ����p����ڎw���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ăA�v���C�h�}�e���A���Y���ӎ������d�C�������Ă��Đ��G�l���p67��
�d�͉�Ђ����z���Ȃǂ̍Đ��G�l���M�[�̗��p�𑝂₷�Ȃ�A�d�C�����̎x�����������Ă��ǂ��Ɖ����l��67���ɒB�����B �܂��A��5�h���ȏ�̓d�C�����̈����グ��e�F�ł���Ɠ������l�͑S�̂�49�����߂��B�Ζ��ɑւ��G�l���M�[�̓��������߂鐺����������ɂȂ��Ă��Ă���B ��������6��10�`13���ɕč��̐��l1000�l��Ώۂɓd�b���������{�����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| �����c�s���ƒ��CO2�팸��1�N�Ԍ���
2020�N�x�܂ł�CO2�r�o�ʂ�1990�N�x���25���ȏ㌸�炷�����̈�B�G�l���M�[����ʂ̂�����ʉƒ낪��߂銄���������ACO2�팸�ڕW�B���̃J�M������B�l����\���҂̈قȂ�200���тŎ��W����B �Ԃɏ������炷�Ȃǐ����V�[���ɉ����Ă��ߍׂ�����������B���f���d���Ȃǃl�b�g�Љ�̉e���ɂ��Ă���������B2011�N�x����n�߂�팸�v��ɔ��f����B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���pBP���u���E�G�l���M�[���v�v���\�A�����̉��g���K�X�r�o�ʁA09�N�ɋ}�������E�S�̂͌���
���ΔR���R�Ăɂ��CO2����Ƃ���2009�N�̒����̉������ʃK�X�r�o�ʂ�75���g���ɒB���A�O�N��9%�����������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�����͉ߋ�10�N�ԁA�}���Ȍo�ϐ������x���邽�ߐΒY�Η͔��d���𑽂����݂������Ƃ���A�������ʃK�X�r�o�ʂ��}�����Ă���B �č��̔r�o�ʂ�59���g���ɂƂǂ܂�A�O�N��6.5�����������B�����1995�N�ȗ��̍Œ�B ���E�r�o�ʂ�2008�N��315��5000���g���Ƌ�O�̋K�͂ɂȂ������A���E�I�Ȍi�C�������ōz�H�Ɛ��Y�ƔR������������A�K�X�r�o�ʂ�1998�N�ȗ����߂Č����B2009�N��311��3000���g���ƑO�N��1.1�����������B �o�T�uGreen Car View�v |
|
|
| ���o�ώY�ƏȂ͍Đ��\�M�G�l���M�[�̊��p������
�Đ��\�G�l���M�[���y��̈�Ƃ��āA���z�M��o�C�I�K�X�A�n���M�Ȃǂ̔M���p���i�Ɍ����������ɒ��肷��B �Đ��\�G�l���M�[�̔M���p����ɂ�����ۑ��A�x����A�K���̂�����Ȃǂ��������錤�����V���ɗ����グ����j�B�Đ��\�G�l���M�[�̓d�͗��p�ɂ��ẮA�ݔ��������̕⏕����A���㓱���������܂��Œ艿�i�S�ʔ�����萧�x�Ƃ���������x�������݂��邪�A�M���p�̌����͏\���i��ł��Ȃ��������Ƃ���A�������ʂ��ċ�̓I�Ȏx������c�_����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���@�@[�@2010/6�@]�@�@�� |
|
|
| �����K�X�����z�M��g�[�ɂ����p�����ˌ��ďZ������K�X�����V�X�e����
�W�M��ƐV���ɊJ�������������j�b�g����\���B�W�M�킩�����������z�M�͒������j�b�g�̃^���N�ɉ����Ƃ��Ē~�M�B�����^���N�̉����͑䏊����ʏ��A���C�ւ̋����Ɏg�p���邾���łȂ��A�Z���g�[����z�p�̉����Ƃ��Ă��g�����߁A�W�M�����G�l���M�[�����ʂȂ����p�ł���B �������j�b�g�ɂ́A�������̃K�X������u�G�R�W���[�Y�v��������A���z�M�����ŋ�����g�[�p�̔M������Ȃ����Ɏg�p����B���Z�ł́A�����ʐς�150m2��4�l�Ƒ��̏ꍇ�A�����Ɖ����g�[�ŕK�v�ȔM�ʂ̖�2���z�M�Řd���邽�߁ACO2�r�o�ʂ�N�ԂŖ�510kg�팸�\�B�K�X��R�Ă������z�M�𗘗p���������݂̂���������u�G�R�v�@�\�����ځB���z�M�̗��p�ɂ��CO2�팸�ʂ�K�X�팸�ʂ̊m�F�@�\��CO2�팸�ʂ����l��O���t�\�����ł���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���p�C�I�j�A���u�G�R�E���[�g�T���v�𓋍ڂ̃J�[�i�r��V����
�Ԃ̔r�C�ʂƏd�ʁA���A�����A���x���R������ʂ𐄒肷��u�R���Z�p�Əa�ؗ\���@�\���A�Ԃ��Ƃɂ��R������ʂ̏��Ȃ����[�g��T�����ē�����B�^�]���Ȃ��瑖�s���ɔR��𐄒肵�A�ߋ��̕��ϒl�Ɣ�r�����G�R�w���ACO2�팸�ʂ␄��R����Ȃǂ𐔒l��O���t�B�b�N�ŕ\������G�R�^�]�̓x�������m�F���邱�Ƃ��ł���B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �������d�͂��uCO2�ƌv��v�œd�C�g�p�ʂ̎������f�T�[�r�X���J�n
CO2�ƌv��́A�z�[���y�[�W��Ō��X�̓d�C�E�K�X�E�����g�p�ʂ�x���z����͂��邱�ƂŁA�ƒ납��r�o�����CO2�ʂ������Ōv�Z�ł���B ������T�[�`�T�C�g�uTEPORE�i�e�|�[���j�v�ɉ���o�^����Ζ����ŗ��p�ł���B�������j�������ĉƒ�ɒm�点��u�d�C���g�p�ʂ̂��m�点�v�i���j�[�j�̏����A���j�����猴��3�c�Ɠ���ɓo�^�����CO2�ƌv��Ɏ������f����B���j����CO2�ƌv��Ɏ������f�������Ƃ�����Ƀ��[���Œm�点�A�p���g�p�𑣂����ʂ��_���BCO2�ƌv��̗��������シ�邱�Ƃň�w�̗��p�𑣂��A����҂̏ȃG�l�ECO2�팸�ɑ���ӎ������߂Ē�Y�f�Љ�̎����ɂȂ������l���B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ���������쏊���u��}���R�z�V�X�e���v�Z�p�Ńf�[�^�Z���^�[��7���ȃG�l
��}���R�z�V�X�e���́AIT�@��̔M���z��������}���C�����ď㏸����͂ƁA�M������ŗ�p����ĉt��������}���A�ݔ��̍��፷�Ȃǂɂ�艺�~����͂𗘗p����B���̂��߁A���͌��Ȃ��ŗ�}���z�����邱�Ƃ��ł��A��}�z�̓d�͂��s�v�ɂȂ�B �O�C����10���ȉ��̏ꍇ�́A�O�C�݂̂ŗ�}���p���ċV�X�e���̓d�̓R�X�g������ɒጸ�ł��A�����̎��Z�ł͍팸���́A�]���̋����ɔ�ׂčő�67���B���킹�ăf�[�^�Z���^�[�̃��W���[�����̉ғ����Ǘ��E�Ď����鐧�䑕�u�ɁA�@�̐芷���������I�ɍs�����f�����lj��B�@���̏Ⴕ���ꍇ�ɗ\���̋@�ɐ芷����B �o�T�u���oBP�v |
|
|
| ����ёg�AJ�G�i�W�[���Ⓚ�@��CO2��25�����̒~�M�V�X�e�����J��
�Ǝ��̒~�M�ނ�g�ݍ��^���N�����p�B��Ԃ�16���O��ɉ�����������������ۂ��A�Ⓚ�@�̉^�]��}����B �������@�ƕ��p����K�v������A�S�̂̓����R�X�g�͂����ނ��A��ʋ̂悤�ɁA5���O��܂Ő����₳���ɍς݁A�d�C����7�����点��B��Ԃ͋C�����Ⴍ�A�Ⓚ�@�̉ғ��������܂�B�~�M�ނ͓��鉷�x��3�`30���͈̔͂Ō��߂���B�~�M�ނ͕X���~�M���\�ɗD��Ă���A���u�̗e�ς�X�����̖�4���ɏ��^�������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �������d�@�Y�Ƃ��C������1.5�{�ɍ��߂��V�[�g���V���b�^�[���J��
�V�[�g�Ƙg�̖����x�������B�J���x�͖��b�ő�3���[�g���B��ƎԂȂǂ��V�[�g�ɐڐG�����ꍇ�̓V�[�g���O��A�j����h���A�O��Ă��ȒP�ɕ����ł���B���i�͍����ƕ������ꂼ��3���[�g���̕W���I�ȏ��i�Ŗ�90���~�B �C���������߂����ƂŁA�����̍H��̓�����́u�G�A�V�����[�v�ȂǐV���ȗp�r���J��B�]���̐H�i�A��i�A����ƊE�ɑ��Ă��A�{�^���ɐG�ꂸ�ɃX�C�b�`���������u��ڐG�X�C�b�`�v�ȂǐV���ȋ@�\���o�q���Ċg�̂���B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ���s���{���Ȃǂ�6�������g����ɂ��u�r�o�g�v�̔��p���g�݂𐄐i
���R�G�l���M�[�̓�����X�ѐ����ɂ���Č��炵��CO2�ʂ��A�r�o�ʎ���Ŕ����ł���u�r�o�g�v�ȂǂƂ��Ċ�Ƃ�c�̂ɔ��p������g�݂��A�S���̓s���{���Ɛ��ߎw��s�s�̖�6�����n�߂Ă��邱�Ƃ��A�����V���Ђ̒����ŕ��������B�n���Ɏ������Ăэ��ސV���Ȏ�@�Ƃ��čL�����Ă���B �o�T�u���s��V���v |
|
|
| �������s�������K�͎��Ə��ȃG�l���i�E�N���W�b�g�n�o�̂��߁A�ȃG�l�ݔ��̓�����p���ꕔ����
�����s�̏ȃG�l�f�f����ESCO���Ƃ̃p�t�H�[�}���X�_���O��Ƃ����ȃG�l���M�[�f�f���O��ŁA�������M���@��Ȃǁu�s�������N���W�b�g�Z��K�C�h���C���v�Œ�߂��F���ɊY������ݔ��Ȃǂ������Ώېݔ��ƂȂ�B �����Ώۂ́A������Ǝ҂ŁA�ݔ�������ɂ��팸���E�팸�ʂ�6���ȏォ��10�g���ȏ�ŁA������4����3�i���x�z7,500���~�j�B������Ǝ҈ȊO�̎��{��10���~�����̉�Ђł́A�팸���E�팸�ʂ�12%�ȏォ��100�g���ȏ�ŁA��������2����1�i���x�z5,000���~�j 5�����`6�����ƎҌ���������̊J�ÁA8���ȍ~�\���J�n�B �o�T�u�j���[�X�����[�X�v |
|
|
| �����{���Z��̏ȃG�l��`�����ցA�@�I�[�u������
���s�́u������ȃG�l��v��1999�N�ɍ���B�Z��̒f�M���\�̐��l��Ȃǂ��߂Ă��邪�A�Z��̎{�H��ɑ���S���͂͂Ȃ��A�K������Z��͐V�z��1�`2���ɂƂǂ܂�B�����Ȃƌo�ώY�ƏȂ͗L���҂̌�����𗧂��グ�A�N�����߂ǂɊ�̌������Ă�V�z�E���C�̏ȃG�l���x����A�`�����̑Ώۂ⎞�������߂�B �`�����ɂ��ẮA�{�H��ւ̎w���┱���Ƃ��������@����������B�V��ł́A���s�̒f�M���\�ɉ����A���z���p�l����ȃG�l�^�̗�g�[�E�����ݔ��Ȃǂ��]������B�V���`�����̓}���V�����Ȃǂ̑�K�͌��z�����珇���K�p���Ă������j�B �o�T�uAsahi.com�v |
|
|
| �����Ȃ����[�X�x���Łu���z�M�v�Z���\�����
���Ȃ̎x����́A�ƒ�p���z�M���p�V�X�e�������[�X�����ŏZ��ɐݒu���悤�Ƃ��鎖�Ǝ҂��㉟��������́B �\�Z�K�͂�15���~�B���[�X���Ǝ҂�ΏۂɁA�V�X�e���ݒu�ɕK�v�Ȕ�p��2����1������ɕ⏕����B���[�X���Ԃ�6�N�ȏ�B���̎d�g�݂𗘗p���ē��ʁA8���̃��[�X���Ƃ��x���B�x����ʂ��āu�ݒu�҂Ɉ��S����^�����y�ɂȂ������v�l���B �����́A������d�C�≷���ɕς���G�l���M�[���p�����́A���z�����d�͌�����10���䂾���A���z�M����3�{�ȏ��40�`60���B�W�M�p�l����u���ʐς��������ł��A��ʉƒ�Ŗ�4�`6m2�̃X�y�[�X������ΐݒu���\�B�ݒu�R�X�g����30���`90���~�Ɣ�r�I�����ŁA����������Ԃ����z�����d�ɑR�ł���Ƃ��Ă���B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| �����Ȃ��ƒ�̏ȃG�l�����u�R���V�F���W���v���琬�S���ɔh����
���R���V�F���W���̖����́A�e�ƒ낪�n�����g����ʼnʂ��������ɋC�Â��Ă��炤���ƂƁA�������̓I��CO2�팸�s���Ɍ��т��邱�ƁB �琬���Ƃ̎�̂́A�u�n�����g���h�~�������i�Z���^�[�v�B�d�C�X��d�́E�K�X��ЂȂǂ̋��͂Ēm�������l�ނ@�B�ƒ�̃G�l���M�[��������g����̊ϓ_���番�͂��A�ƒ�ւ̏���������C����B ��1000���ыK�͂Ɋg�債�����f�����Ƃ����Ăɂ��J�n���A�L���Ȍ����鉻������������T��B���N�x���畁�y�����Ɉڍs����B�������A�u�l�̓w�͂�ӎ��ω������҂��錩���鉻�̐���́A�C���Z���e�B�u���Ȃ���Ԃł͌��ʂ�����I�v�Ǝ茵��������������B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/5�@]�@�@�� |
|
|
| ����K�X���d�C�E�K�X�E�����g�p�ʂ��P���Ԃ��Ǝ����v���ʼnƒ�̐ߖ�x��
1���Ԃ��ƂɎg�p�ʂ������v�����A�W���g�p�ʂƂ̔�r��u�g�[�̎g�p�ʂ��������悤�ł��v�Ȃǂ̕��͂��E�F�u�T�C�g��[���Œʒm����B �u�G�R�ȉƁv�Ƃ��ĕs���Y��ЂɕK�v�ݔ���������}���V���������ĂĂ��炢�A��K�X�����z���S�~�ŃT�[�r�X�����B��2�{4���̑�K�X�c�ƊǓ��ŐV�z�}���V���������Ɏ��{����B���d�͂��ʐM�@�\�t���̌��j��u�X�}�[�g���[�^�[�v�����ďȃG�l�f�f�T�[�r�X���������Ă���̂ɑR����_���B �o�T�u���o�l�b�g���v |
|
|
| ���V���{������}�ւ́uCO2�r�o���t����z�ցv��
�V���{����̒ʐM�̔��ōw�����ꂽ�S���i���ACO2�r�o���t����z�ւŔz�B�B���i�z��1�ɂ��A�V���{����2�~�A����}�ւ�1�~�����ꂼ�ꕉ�S����B �Ȃ��A1�~�ő�z��1������̗A���ɂ�����CO2�r�o��383�O�����ɑ�������B�����̍��v1149�O�����i3�~�����ʁj��CO2�r�o�����A����}�ւ�����{���{�ɖ������n�B���n���ꂽCO2�r�o���́A���s�c�菑�œ��{���팸���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ʃK�X�́u�}�C�i�X6���v���ɃJ�E���g�����B �o�T�u�ʔ̒ʐM�v |
|
|
| ����ёg�����ȂŋƏƖ����N������ȃG�l�V�X�e�����\��
�Ј��ɂ�RFID�^�O���g�ݍ���ł���A�e���̊��ɂ͋����͈͂œd�E��������u���^�g���K���j�b�g�v�����t����B RFID�^�O�́A���̓d�E���ɓ���ƁA�Ј��l�̏���d�g�Ŕ��M�B��������̘e�ɐݒu�����uRFID�A���e�i�v���L���b�`���A�����Ď��V�X�e���ł͒��Ȃ������Ƃ��m�F�B��Ɩ��̃X�C�b�`�������I�ɓ���d�g�݁B2010�N�H�����\��̑�ёg�Z�p�������ɓ����\��B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| ���r�b�N�J�������k�d�c�d���w���ґΏۂɔ��M�d�������
�����z��1��50�~�B���������o���ALED�d���ւ̔����ւ��𑣂��B �S����30�X��LED�d��1�̍w���ɂ��A���M�d����3�܂ʼn���肷��B�ڋq��LED�d�����ő�150�~����������悤�ɂ���B���M�d���͎g�p�ς݂ł����g�p�ł��t����B �o�T�u���{�o�ϐV���v |
|
|
| ��INAX�����Ώ�̕ې��~�ݍނ��J���B�C���M�Œn�\�ʂ̉��x��20���ቺ
�^�C���̌����̃P�C���̍̌@���̕��Y�����Ă��ł߂����ŁA���E���̓����ɏd�ʂ�6���ȏ�̐������܂ނ��Ƃ��\�B ������������ۂɎ��͂̋C���㏸��}����B���H������ɗe�Ղɕ~���l�߂邱�Ƃ��ł���̂Ńq�[�g�A�C�����h��ɎłƓ��l�̌��ʂ��]�߂�B�r���̉���ɕ~�݂���A�̎��O�@�̋z�C���x�������A�ғ��������߂��A�ȃG�l�ɖ𗧂B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���x�m�ʌ������^�ȃX�}�[�g�d���^�b�v���J��
AC100�{���g�d���ɔ�ڐG�œd���𑪒�ł����p�Z���T�[���J���B���S�����^�Z���T�[�̓��ڂŁA�^�b�v�̃T�C�Y���R���p�N�g���B�R���Z���g�P�ʂŎ��W��������d�͏��́A���[�U�[�̃X�P�W���[���ƘA�g�����ĕ\������ȂǁA������₷�������B �R���Z���g���Ƃ�1W�P�ʂōő�2kW�܂ő���B�\�����H�v���ėאڂ���R���Z���g�̉e�����ɂ������A4�̃R���Z���g�̌ʓd�͑�����\�ɂ����B�Г��̈ꕔ�I�t�B�X�ɓ��������Ƃ���A��2���̏ȓd�͉��ɐ��������Ƃ����B �o�T�uITmedia News�v |
|
|
| �����{�K�����F�苦��iJAB�j�������K�X���؋@�ւ̐M�����ɍ��ۊ�ŐR��
�������ʃK�X�̔r�o�ʂ�팸�ʂ�������@�ւ̌�������M�����A�͗ʂ�F�肷�鎖�Ƃ��n�߂�B ���؋@�ւɑ���v���������߂����ۋK�i�uISO14065�v�Ɋ�Â��ĐR���A�F�肷��B�N�x���ɂ����K�i�̔F�茟�؋@�ւ��a�����錩�ʁBISO14065�F��͂��łɕč���t�����X�A�X�y�C���ȂǂŎn�܂��Ă���BJAB�͍���A�����������̊W�c�̂Ɠ��F��̑��ݏ��F�̋��c��i�߁A���{�ŔF��������؋@�ւ��C�O�̌��؋Ɩ��ɂ��Q���ł���悤�ɂ���B �r�o�ʂ̌��͔r�o�ʎ�����x�ɕK�v�Ȏ葱���B�����ł͊��Ȃ̎���Q���^�����r�o�ʎ�����x�iJVETS�j��I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g�iJ-VER�j���x�A�o�ώY�ƏȂ̍����N���W�b�g���x�A�����s�̔r�o�ʎ�����x�Ȃǂ�����K�{�Ƃ��Ă���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��G�l��{�v�挴�ĂŁA�����G�l�����䗦7���Ɉ����グ�ڎw��
�G�l���M�[��{�v��̉���Ɍ����A�o�ώY�ƏȂ��������Ă��鍜�i���Ă����炩�ɂȂ����B ���q�͂Ȃǂ̍��Y�E�����Y�G�l���M�[�⎩��J���̊C�O�������v���܂߂������I�ȃG�l���M�[�����̔䗦��2030�N��7�����x�܂ő啝�Ɉ����グ��ڕW��ݒ肷������Œ�����i�߂Ă���B�ߔN�̃G�l���M�[����͊��ʂɕ肪�����������A�G�l���M�[���S�ۏ�ɂ��d�_��u�������ł������B���q�͂�Đ��\�G�l���M�[����Ȃ�[���G�~�b�V�����d���̔䗦�Ȃǂɂ��Ă�2030�N���_�̐V���ȖڕW���f������j�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �������G�l���������r���̏ȃG�l���i�ŐV���ȃG�l���M�[�Ǘ����f�����
2009�N7���ɗ����グ���u�ȃG�l�r�����i�W�����R���\�[�V�A���v�������܂Ƃ߁A�uSBC�����r�����f���v�Ɩ��t�����V���ȃG�l���M�[�Ǘ����f�����J���B�v���@��E����̃C���^�[�t�F�[�X��ȃG�l�]���p�f�[�^�̕W�����𐄐i�B �����O������̏ȃG�l�Ǘ���e�Ղɂ���V�X�e���Â���𑣂��B�Ή����i�܂Ȃ������r���̏ȃG�l��̋����ɂȂ���ӌ��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ����z�����d�{�݂����{�݂ɋK���ɘa
���z�����d�{�݂́A�H����ӂ̏Z���̐�����������͂Ȃ��A��ʓI�ɂ��u����z�������ݔ��v�Ƃ̃C���[�W���Z�������邽�ߍH�ꗧ�n�@�̌����������߂��B ���Ă܂ł̏ȗ߉�����ڎw���B�@�ł́A���K�͈ȏ�̓���H��ɑ��Ĉ��̊����ŗΒn���m�ۂ��邱�Ƃ����߂Ă���B�H����́u�Βn���܂ފ��{�݁v�̖ʐς�25���ȏ�A�Βn��20���ŁA�c��5���͗Βn�������A���O�^���� ���Ɣ����قƂ������{�݂ō\������B����A���́u���{�݁v�ɐV���ɑ��z�����d���������B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���āA�ƒ�����r�o������X�^�[�g
�j���[���[�N�B�̓d�͒����2�Ђ��ƒ�ŏ�����G�l���M�[�̍팸���Ɋ�Â��u�J�[�{���I�t�Z�b�g�g�v��̔����钇��v���O�����AMyEex��Earth Aid�𗧂��グ���B ������ł́A�r�o�g��1�g������21.5�h���i��2000�~�j�Ŕ̔��B�萔�����v��4.3�h���i��400�~�j�B����܂łɖ�2000���т��o�^�B���������̐������ɂ���Ċe�ƒ�̃G�l���M�[�팸�ʂ��m�F���A�I�t�Z�b�g�g�����蓖�Ă�B �o�T�uAFPBB News�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/4�@]�@�@�� |
|
|
| ���O�H�n���͑��z�����d�ݔ��ƍ�����d�ݔ���ݒu�������z���^�}���V�����̕������J�n
�Z�ː�50�ˁB�����5kW�̑��z�d�r�Ő��ݏo�����d�C�G�l���M�[�����p���ɗp���A���z�d�r�̊��p��CO2�r�o�ʂN5�g�����x�팸�ł���B �ƒ�Ŏg�p����d�C�̓}���V�����ɍ�����d�ݔ���ݒu���A�d�C����������������B���̔�p�z�d�r�̓����R�X�g�ɂ��Ă�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���m�s�s�h�R����CO2�r�o�ʍ팸�̂��ߌ��ؐݔ��ōő�66%��CO2�r�o�ʍ팸���ʂ�����
NTT�t�@�V���e�B�[�Y�Ƌ����ŁA2009�N�Ɍ��ؗp�f�[�^�Z���^�[�Ƃ��āA����ICT�G�R���W�[�Z���^�[��ݗ����AICT�ݔ��A�E�d�͐ݔ��̏ȃG�l���M�[�Z�p�̓����������{���B 2009�N2������J�n������1�����ł́A���p�l�b�g���[�N�œ����\��̏ȓd�̓T�[�o�[�A�ݔ�(��������/�A�C���L���b�s���O)�A�������d�V�X�e�����œK�ɑg�����邱�ƂŁA�����ڕW�̏]�O�ݔ���50%������ő�66%��CO2�r�o�ʍ팸���ʂ����B2010�N3������J�n�́A��2�����ł́A����d�͐���Z�p�𓋍ڂ����ȓd�̓T�[�o�[���ICT�ݔ��̉ғ�����A�W�����邱�ƂŁA�\�͂����ߍׂ₩�ɐ��䂷��������\��B �o�T�u�}�C�R�~�W���[�i���v |
|
|
| ���쑺�s���Y�����͔��d�@���}���V�����ɓ���
���͔��d�@3������A���d�����d�͂��}���V�������p���̈ꕔ�ɗ��p����B���ϕ�����1�b������4m�������ꍇ�A3��ŔN�Ԗ�1800kWh���d�B���ɔz�������ݔ����}���V�������O�ɗl�X�Ȍ`�œ����B �S���Ɂu������ȃG�l��v�ɓK�����f�M����4���擾�������w�K���X���̗p�B������������G�R�W���[�Y��G�l���M�[����ʂ�CO2���Z�Ŋm�F�ł���G�l���b�N�����R���ALED�d���Ɠd���^�u�����ǂ�������t������}���`�����v�E�_�E�����C�g�A�ߐ��֊�Ȃǂ��B�܂��A�n�C�u���b�h�J�[�ɂ��J�[�V�F�A�����O����^�T�C�N�����B �o�T�u�P���v���b�c�v |
|
|
| �����d��10������X���ˑΏۂɐV�^�d�q�����[�^�[���؎���
�����s�̐����s�Ə����s�̈ꕔ�Ŗ�9���˂�ΏہB�������Ԃ�2�`3�N���x��\��B�ʐM�@�\�ȂǐV�^���[�^�[�̊e��@�\��Ɩ����e�Ȃǂ�������B �d�C�̎g�p�����ԑѕʂɕ�����Ȃnjڋq�T�[�r�X�̌���ɉ����A���j��_��I���E�ĊJ�A�_��ύX�Ȃǂ̋Ɩ��������ɂ��Ȃ��錩���݁B�V�^���[�^�[�͌v�ʋ@�\��ʐM���u�A�J�������B�d�C�̎g�p��30���P�ʂŋL�^����B�u���c�����}���`�|�b�v�A�b�v�����v�ƌĂ�閳�������ɂ���ă��[�^�[���m�ŒʐM���A�d���ɂ���W�u�܂Ōv�ʃf�[�^�[��`������B�W�u����x�ЂȂǂ̎��Ə��܂ł͎�Ɍ��t�@�C�o�[��������p����B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���T���W�F���}���A�Ɩ��pLED�d���ɎQ��
�H���i�Ȃǂ����R���ɋ߂��F�ŏƂ炷���F���̍���LED�d�����J���B�����ڂ����i�̔���s�������E������H�X��X�[�p�[�Ȃǂɔ̔���ڎw���B ���R������l100�Ƃ����ꍇ�A���̌��ɋ߂��قlj��F�w���iRa�j�������A�����̐F�ɋ߂��B�V���i��Ra��90�O��̍����F�������������B�ƒ����LED�d����Ra��70�`80����ʓI�BRa��90�ȏ�̏Ɩ��́A���F�����d�v�ȗՏ���������p�قŎg�p�\�Ȑ����Ƃ���A���Ɠd���[�J�[�����i�����Ă��Ȃ��B���i�͒�����Ή���40���b�g���M�d�������^�C�v��5000�~�O���\��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��ȃG�l��E���x�����O���x�\�z�ŃA�W�A�e���x����
�����ŁA�Ɠd�@��Ȃǂ̓d�͎g�p������ق��A���\���莎���̔\�͌����}��B�^�C��C���h�l�V�A��O���ɁA���̓r�㍑�ł����x�\�z�Ɍ��������i�̐��̐����ɋ��͂��Ă����B�r�㍑�ł̐��x�����̂ЂȌ^�쐬���߂����B ���{���|���������x�֘A�̃m�E�n�E�����p���A�r�㍑�̉������ʃK�X�r�o�팸�ɍv������ƂƂ��ɁA�r�㍑�ł̏ȃG�l�s��n�o�ɂȂ���B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����{�A�G�R�|�C���g���x�ł̂k�d�c�d���������u���z�v��
���{���F�肷��u�T�|�[�g�̔��X�v�X���ł̔����_�C�I�[�h�iLED�j�d���Ƃ̌��������i�̔����̃|�C���g���łł���悤�ɂ���B4��1��������{����B �d���`�u�������v�Ə[�d���j�b�P�����f�d�r�̓X�����������l�ɕK�v�|�C���g�����ɂ���B�G�R�|�C���g�Ώۂ̃G�A�R���A�①�ɁA�n��f�W�^�������Ή��e���r�̍w���҂͂��̏�ŁA�_����LED�d���Ȃǂƌ����ł���B4������͗Ⴆ��4000�~��LED�d���ƌ�������ꍇ�A2000�_�̃|�C���g�ōςށB �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ������r���ȃG�l���l�ށE�Z�p�s���x���K�C�h���C���������܂łɍ���\��
�����̒����r���̏ȃG�l���M�[�����㉟�����邽�߁A���ʓI�ȃG�l���M�[�Ǘ����@�荞�K�C�h���C��������B �����ʐ�1���������[�g���ȉ��̒����r�����Ǘ������Ƃ�ȃG�l�T�[�r�X���Ǝ҂Ȃǂ��Q�l�ɂ���w�W�B�W���I�ȊǗ��菇�́A�G�l���M�[�g�p�ʂ�E�Ɩ��@��̉^�p�Ȃǂ̃f�[�^�����W�B�����Ǘ��҂�R���T���^���g���r���̏ȃG�l�]����e�Ղɍs����悤�f�[�^�����H�B���ɁA�ꌳ�I�ȉ��u������\�Ƃ���u�r���R���g���[���[�v�Ɗe���E�����̋@���ڑ����闬��B�O���̐��Ƃ��C���^�[�l�b�g��p���ĉ��u�ŏȃG�l���̎菕�����s���₷������B �o�T�u�r�W�l�X�A�C�v |
|
|
| ���Ă��ٗp�n�o���ʑ_���ȃG�l�Z��ւ̕⏕���x�̋�̍�\
�ʂ̏ȃG�l�@��̍w���ƏZ��S�̂̉��C��ΏۂƂ���2�̐��x��p�ӁB�ȃG�l�@��Ȃǂ̐��Y�����ɂ���āA�����l�̌ٗp�n�o���ʂ�����Ƃ݂Ă���B �I�o�}�哝�̂́u�č��̃G�l���M�[��40���͏Z���r���ŏ���Ă���v�Əq�ׁA�Z��̏ȃG�l���̏d�v���������B�G�l���M�[�������ŏ�ʋ��̒f�M�ނ�V�X�e���Ȃǂ��w������ꍇ�A�����50����⏕���A�P�i�ڂ�����ő�1500�h���i��13��5000�~�j���x���B�i�ڂ�g�ݍ��킹�邱�Ƃōő�3000�h���܂ʼn\�B�Z��S�̂����C���A20���̏ȃG�l��B������ꍇ�ɂ�3000�h���̕⏕���x������B�ȃG�l��20������ꍇ�ɂ͒lj��̕⏕������B �o�T�u���o�G�R���~�[�v |
|
|
| ��CO2�r�o�����t�B�b�V���O���\�ɁB��Q���z��300�����[����
����͉ˋ�̔r�o��������ǂ̃z�[���y�[�W���쐬���A���E���̊�ƂɋU�̓d�q���[���𑗂�t����Ƃ������́B�h�C�c�ł́A�W�I�ƂȂ�����2,000�Ђ̂���7�Ђ��Ɣr�o������ǁiDEHSt�j�Ƃ�������̃T�C�g�Ō���������Ă��܂��A6�Ђ��v25���g���̔r�o���𓐂܂ꂽ�B �`�F�R�ł���Q������Ă���B������A9�J���̓��ǂ�2���ɃT�C�g����B���A�͊e�����ǂƘA�g���A�o�^�V�X�e���̈��S�����m�F�\��B �o�T�uEC JAPAN�v |
|
|
| ���O�[�O�����d�͗��p�ʂ��l�b�g�ʼn{���\�t�g������
�ƒ�̓d�͎g�p�ʂȂǂ��{���ł���l�b�g�T�[�r�X�u�O�[�O���E�p���[���[�^�[�v�̃\�t�g����d�͌v���[�J�[�Ȃǂɖ�������Ɣ��\�B ���[�J�[�e�Ђ͎��Ђ̓d�͌v���ȒP�ɃO�[�O���̃T�[�r�X�ƘA�g�ł��A�ƒ�ł͏���d�͂����ߍׂ����c���ł���B�O�[�O���͂h�s�i���Z�p�j���g���������㑗�d�ԁi�X�}�[�g�O���b�h�j�s��̊J���i�߂�B �o�T�u���oNET�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/3�@]�@�@�� |
|
|
| ���V�W�H�Ƃ�70���ቷ�r�M���p�����@���J��
�f�V�J���g�ɍ����q�̋z���܂��̗p���A�эnj��ۂ̂悤�ȍׂ����ǂ̊ԂŐ����̋z���ƕ��o���J��Ԃ��B 70���̉��x�ł���������o����B���̂��߁A140���̍������s�v�ōH��Ŏ̂ĂĂ����p�M���g����B�]���̎�@�ɔ�ׂď���G�l���M�[�͖�30���팸���\�B�q�[�g�|���v�Ƒg�ݍ��킹���CO2�̔r�o�ʂ�50���팸�\�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���ؑ��H�@����C��}���ˎ��V�X�e�����J��
���O�@���瑗�荞�g�C���C���A�V��ɐݒu�����A���~���p�l���ɐ���������ƁA�p�l�������̃A���~���ꎞ�~������A�����ɕ��B�Η����ɔ�ׁA�����̏ꏊ�ɂ�鉷�x�����o�ɂ����B �p�l�����ɂ́A�����̔����A���~��n�ʂƐ��������Ɉ��̊Ԋu�ŕ��ׁA�\�ʐς�傫�����A�~�M���ʂ����߂Ă���B�ŏ��p�l���ŁA���˂���M�ʂ�1.1�`1.2kW�B����}�̏]���p�l����0.2�`0.3kW�ɔ�דd�͏���ʂ͑啝�ɏ��Ȃ��B����}�����ł͌��I�������邪�A��C�����ł͎����̋�C���z������\���B50m2�̕����Ńp�l�����i�͖�50���~�ƈ����B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���I���������ڑ��@�킲�Ƃ�CO2�r�o���u�����鉻�v����R���Z���g���J��
8�̏o�̓R���Z���g������A��p�Z���T�[�Ȃǂŏo�̓R���Z���g�ʂɐڑ��@��̏���d�͗ʂ��v������CO2�Ɋ��Z����B ���茋�ʂ́A�f�[�^�擾�p�\�t�g���g���ĐώZ�l���Ǘ����A�O���t�Ŋm�F�B�p�\�R������̉��u����́A�C���^�[�l�b�g��ʂ��Đڑ��@��̏�Ԃ��Ď�����ƂƂ��ɁA�E�F�u�u���E�U���g���A�ɉ����Čʂɋ@��̓d���̃I���E�I�t���\�B1�N���̉^�]�X�P�W���[���P�ʂŐݒ�\�B���i��23��6250�~�B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| �������i�C���G�R�W���[�Y�ƃG�R�L���[�g��g�ݍ��킹���n�C�u���b�h�������
�K�X�Ƌ�C�̔M�G�l���M�[���œK�Ɏg�p���邱�ƂŏȃG�l�������߁A�ꎟ�G�l���M�[������124����B���B �N��CO2�r�o�ʂ́A�G�R�W���[�Y����20���A�G�R�L���[�g460L�^�C�v����30���팸�ł���B�R���p�N�g�ȔM���@�E�^���N��̃^�C�v(756,000�~)�ƁA�{�H���ɂ����ꂽ�M���@�E�^���N�Z�p���[�g�^�C�v(735,000�~)��2�@��B�N�Ԃ̃����j���O�R�X�g�́A�G�R�W���[�Y�̖��ŁA�����R�X�g���V�N�ŏ��p�ł���B �o�T�u���z�ݔ��t�H�[�����v |
|
|
| �������K�X�Ɠ����A�v���C�A���X�������p�G�l���M�[�ƃR�[�W�F�l�p�M�����p����@���J��
������������͐쐅�A�n�����Ȃǂ���܂Ŏg���Ă��Ȃ������ቷ�����p�G�l���M�[���Ă͗�p���Ƃ��ė�[�ɁA�~�͔M�����Ƃ��Ēg�[�Ɋ��p���A�]���V�X�e���Ɣ�הN�Ԃ�29���̏ȃG�l�ECO2�팸����������B �g�[���͏��C�̏���ʂ�55���팸����B����ɁA�ቷ�����p�G�l���M�[�ƃR�[�W�F�l�p�M�����킹�Ċ��p���邱�ƂŁA�{�C���[�̏��C����ʂ�61���팸���A�N�Ԃ�42���̏ȃG�l�ECO2�팸���\�ɂȂ�B�R�[�W�F�l�p�M�̑���ɑ��z�M�𗘗p���邱�Ƃ��ł���B �o�T�uECO JAPAN�v |
|
|
| �����H�傪�R���ɑ��z�M���d�{�݂��v��B30�N�Ԃ荑������
���z�M���d�͋��̔��˂𗘗p���đ��z�����W�����u�ɏW�߂�u�r�[���_�E���^�v�ƌĂ�A�]���͏��ɂ������W�����u��n��ɒu�����ƂŁA�ێ��E�^�p���y�ɂȂ�B �W�����u�ɂ���~�M�ނ�500?1000���ɒg�߁A���̔M�ŏ��C�������ă^�[�r�������d����B�~�M�ނ̔M�������Ȃ��悤�ɒf�M���邱�ƂŖ�Ԃ����d�ł���B �k�m�s�͔N���ϓ��Ǝ��Ԃ�2200���Ԉȏ゠��A���z��������m�ۂł���B���d�K�͂�300kW���x��������ł���B���ݔ��15���~���x�̌��ʂ��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����������V�N�x��CO2�u�r�o���v�̔�������
��������r�o���̔��̎d�g�݂͊��Ȃ�����20�N�ɑn�݂����u�I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g�iJ?VER�j���x�v�����p������j�B �����̃y���b�g�X�g�[�u�̎g�p���т���ɓ�_���Y�f�r�o�팸�ʂ��܂Ƃ߁A���̔F�؋@�ւ����s����u�N���W�b�g�v����Ƃɍw�����Ă��炤�\�z�B�̔����v�͐X�ѐ����Ȃǂ̎����Ƃ���l���B �o�T�u���������v |
|
|
| �����Ȃ�������Ƃ̊������ɕ⏕
�R���]����X�ъǗ��Ȃǂ̉������ʃK�X�r�o�팸�E�z�����ƂɎ��g�ޒ�����ƌ����̐ݔ������⏕�����{����B �J�[�{���I�t�Z�b�g�i�Y�f�̑��E�j�p�̔r�o�팸�E�z���ʁi�N���W�b�g�j�������ł���o���I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g(J-VER)���x�𑣐i����̂��_���B�����x�����p�����Ƃ̐ݔ����������5000���~�A�⏕��3����1�̏����Ŏx������B60���̕⏕��\��B2009�N�x��2����\�Z�Ɏ��Ɣ�10���~�荞�B����Ƃ͕ʂ�J-VER���x�̐\���葱����A��O�ҋ@�ւɂ��r�o�팸�E�z�����т̌��ؔ�p��⏕���邽�߂̎��Ɣ�10���~���v��A110���̎x����z��B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ�������ƌ����ȃG�l�ݔ����[�X�̐V�ی����x��n�݂�
���z�����d�p�l����ȃG�l�^�H�ƘF�A�������{�C���[�Ȃǂ���Ƃ֑݂��o�����[�X��Ђɑ��A���{���w�肵�����I�@�ւ��ی��_������ԁB ��Ƃ��|�Y�ȂǂŃ��[�X�������x�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�A�c���̏��Ȃ��Ƃ������ȏ��ی��������肷��B������ƂɏȃG�l���𑣂��̂��_���B2010�N�x�\�Z�Ă�80���~���v��B �o�T�uSankeiBiz�v |
|
|
| �����Ȃ��s���\�f�Ă����\�B���g���K�X�A�ƒ�ōő唼����
2020�N�܂łɉ������ʃK�X�r�o�ʂ�1990�N���25���팸���邽�߁A�Z��̒f�M����G�R�J�[���y�Ȃǐ����ɐg�߂ȕ���Œn�����g����������B �ƒ납��̔r�o�ʂ�����i2005�N�j��ŁA�ő唼�������邱�ƂȂǂ��v�悵�Ă���B���{��3�����܂łɍs���\���܂Ƃ߂�B2020�N���_�ł̕��傲�Ƃ̔r�o�ʂɂ��āA�ƒ�ł�1990�N��ōő�31�����i2005�N��49�����j�A�I�t�B�X�Ȃǂœ�21�����i��45�����j�A�^�A�œ�25�����i��37�����j�A�H��Ȃǂ̎Y�Ƃœ�24�����i��20�����j�Ƃ���B2005�N��Ō���ƁA�ߔN�r�o�ʂ������Ă���ƒ�̍팸�����ł��傫���B �o�T�u�����ʐM�v |
|
|
| ���p���A�w�Z����r�o������_���Y�f�r�o�ʂ��[����
2016�N�܂łɁA�V�����ݗ������w�Z����r�o������_���Y�f�����S�Ƀ[���ɂ���B �g�p�G�l���M�[��r�o��_���Y�f�ɂ��ă��j�^�����O���s���A���̏������J����B�w�Z����r�o������_���Y�f�ʂ́A�p���S�̂̂��悻15�����߂Ă���A�����ő啝�ȃJ�b�g�������ł���A���S�̂̉������ʃK�X�r�o�ʂ̍팸�ɂƂ��đ傫�ȍv���ɂȂ�B����̒��j�ƂȂ�̂́A�G�l���M�[�̎g�p�ʂ����A���^�C���ɑ���ł���X�}�[�g���[�^�[�̐ݒu�v���O�����ŁA�g�p�����G�l���M�[�����t��k���ӎ����A�S�̂̃G�l���M�[�g�p�ʂ̍팸�ɂȂ���v��B �o�T�uEcool�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/2�@]�@�@�� |
|
|
| ������������CO2�r�o�ʂ��Ɛѕ]���ɘA��
�u�J�[�{���]���V�X�e���v�͋@�\���ޗ��⎩���ԕ��i�A�d�q�ޗ��̐��Y�@�\�����S12���ƕ���ƁA��v�q���9�Ђœ����B�r�o�g��2008�N�x�̔r�o���тƌ��P�ʂł̐��Y�\������ɁA2010�N�x�̗ʂ��Z�肵�e����Ȃǂɓ`�����B �e�N�x�Ŕr�o�g���������ꍇ�́A���ߔr�o�ʂɈ�艿�i���������������Ƃ݂Ȃ��A�ڕW������팸�ł������͗��v�Ƃ݂Ȃ��B�r�o�ʂ̉��i�͉��B�̔r�o�ʎ���s��̉��i��荂�߂ɐݒ肷��B�����̃O���[�v��CO2�r�o���ʂ�2015�N�x��1990�N�x��15���팸����ڕW���f����B���ƕ��P�ʂ̖ڕW�ݒ�Ō���̈ӎ�����ɐ������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| �����������S�XLED�Ɩ���2012�N�܂ł�15���A�d�C��5����1
2012�N�܂łɔ��M�d���̈��ł���n���Q�������v���_�C�I�[�h�iLED�j�Ɩ��ɐ�ւ���B �����s��4�����瓱�������^�{�݂�Ώۂɂ�����_���Y�f�iCO2�j�r�o�K���ȂǂɑΉ����A�ȃG�l�^�Ɩ����̗p�A�R�X�g�팸���˂炤�B�����z��30���~�O��B�S�ݓX��CO2�r�o�ʂ̂�����4�����Ɩ��B�n���Q���S�p�œd�C����]���̖�5����1�Ɉ��k���A��[�����̌����CO2�r�o��7���ȏ�팸����v��B�N��5���~���̃R�X�g�팸�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���؍�VB�̃e�N���N�X���H���s�v�̌u�����`LED����{�Ŕ̔�
�_���s�ǂ�h�����߁A�����̎�v�Ȉ����̉�H�����ׁA�u�����`LED�ɓ��������A���s�b�h���Ȃ�3�^�C�v�ɑΉ��ł���悤�i�����B ��i����d�͂̓��s�b�h�^�C�v��2���p���̏ꍇ��46W�A�d�q���ł�48W�B�V���i�Ŏ��̂��N�����ꍇ�́A�ő�100���h����⏞�B���}�_�d�@��ʂ��Ĕ̔��B�P�{24000�~���x�B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���勞�����z�d�r�{�~�d�r���}���V�����Ŋ��p����
�����s���̒n��8�K���āA���ː���50�˂̃}���V�����B�~�d�r�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŒ��Ԃ����łȂ���Ԃł����z���G�l���M�[�����p�B�d�͏�����Ď�����V�X�e���������B �d�͏���̏��e���т��C���^�[�l�b�g��ʂ��Ċm�F�ł��A�ȃG�l��i�߂₷������B���d�������z���G�l���M�[��L�����p���邱�ƂŃ}���V������CO2�r�o�ʂ�50�����x�팸���邱�Ƃ�ڎw���B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���~�T���z�[�������z�����d�Z��́u�����N���W�b�g���x�v�̎��Ə��F�擾
���z�����d�V�X�e�����ڏZ��I�[�i�[�̉���g�D�������A������疈�N�x���ɑ����d�ʂƔ��d�ʂ̕��A���Ə���d�͕������܂Ƃ߂āA�����N���W�b�g�F�؈ψ���ɕB�r�o�g�Ƃ��ĔF����d�g�݁B 1���т̕��ϓI��CO2�r�o�ʂ͖�1�g���������ށB�r�o�g�̔��p�����z�͐A�тȂǂ̊��v�������ɐ������\��B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���������`�F�[���̃}���V�F�����j���[��CO2�r�o�ʕ\�����J�n
12�������_�őS630�X�ɓ����������B�r�o�ʂ́A�X�܃I���W�i�����j���[�������S�t�[�h���j���[�ɂ��āA�d�ʁ~�A���������~�r�o�W���i�A����i�j�Ƃ����Ǝ��̕��@�ŎZ�o�������l���g�p�B �{�Џ��ݒn�ł��������ɂ��āA�S������Ő��l���L�ځB����̎Z�o���@�ł́A���{���琔�\�{������͔|���@�̈Ⴂ�ɂ��G�l���M�[����ʂ̍������f����Ă��Ȃ����A�����I�ɂ́A�J�[�{���t�b�g�v�����g�̕\���ɂ����g�ވӌ��B �o�T�u�O���[���v���X�v |
|
|
| �����������V�N�x��CO2�u�r�o���v�̔�������
��������r�o���̔��̎d�g�݂͊��Ȃ�����20�N�ɑn�݂����u�I�t�Z�b�g�E�N���W�b�g�iJ-VER�j���x�v�����p������j�B �����̃y���b�g�X�g�[�u�̎g�p���т����CO2�o�팸�ʂ��܂Ƃ߁A���̔F�؋@�ւ����s����u�N���W�b�g�v����Ƃɍw�����Ă��炤�\�z�B�̔����v�͐X�ѐ����Ȃǂ̎����Ƃ���l���B �o�T�u���������v |
|
|
| �����{�����g�����@�ĂŁu�Đ��G�l���M�[20���ȏ�v�̕���
�G�l���M�[�����ɂ��ƁA������2006�N�̍Đ��\�G�l���M�[�̊����͖�1.8���ŁA�A�����J�i3.7���j��h�C�c�i5.3���j��������Ă���B ����}�͐�������Łu2020�N�܂ł�10�����x�Ɉ����グ��v�Ƃ��Ă����B���E�ł͍Đ��\�G�l���M�[�̊�Ƃ��L�тĂ��āA�Y�ƂƂ��đ傫�Ȑ��ݗ͂�����B�����ڕW�ݒ肪�Y�ƈ琬�ɂȂ���Ƃ̔F���B���ɂ��Đ��\�G�l���M�[�̕��y�ւ̎x����A�d�͂̔�����萧�x�̏[�����d�v�Ƃ̍l���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �������s�̐V�N�x�\�Z��CO2�팸��1096���~
3���N�v��̎��s�v���O�����̎�v���Ƃ̈�Ƃ��āA�s�͒����K�͎��Ə���CO2�r�o�팸�����͂Ƀo�b�N�A�b�v������j�B 2010�N4������S���ŏ��߂đ�K�͎��Ə��ɑ���CO2�̍팸���`���t���邪�A�ΏۊO�̒����K�͎��Ə��ɑ��Ă��r�o�팸�𐄐i���邽�߁A2010�N�x����2�N�v���80���~�̊���𓊓�����500���x�̒����K�͂̎��Ə��ɑ��ȃG�l�̋@��ɐ�ւ��邽�߂̎����I�������s�����Ƃ�����B��p��4����3�A���7500���~��⏕����B�����K�͎��Ə���CO2�r�o�ʂ͎Y�ƕ���̂������悻6�����߂Ă��āA���ɔz�������s�s�Â���𐄐i���邽�߂ɖ����̏ȃG�l�f�f���ϋɓI�Ɏ��{�\��B �o�T�uTokyo MX NEWS�v |
|
|
| ����s���P�s�R����Ώۂɂ��������̔r�o�ʎ�����x�̑n�݂�����
�����̒P�ʂł́A�����s�ƍ�ʌ����Ǝ��̔r�o�ʎ�����x��2010�N�x�ȍ~�ɓ���������j�B�����1�s3���œ����E���ʉ����A�����̂̋��E���z���Ċ�Ɠ��m�Ŕr�o�g������ł���悤�ɂ���\�z�B �����̐��x���������Ă���͓̂����s�A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�ɁA���l�s�A���s�A��t�s�A�������s��������8�s���s�B8�s���s�͋��ʂ̐���ۑ�Ɏ��g�ށu��s���L��A���v�i���́j��ݒu���邱�Ƃō��ӁB������ł͋����̔r�o�ʎ�����x�̑n�݁A�L���b�v�E�A���h�E�g���[�h�����̎d�g�݂������B�����s��2010�N�x����A��1400���Ə���ΏۂɁA��ʌ���2011�N�x����A600���x�̎��Ə���Ώۂɓ��l�̐��x���J�n����\��B8�s���s�́A���������������2011�N�x�ȍ~�A������x����s���S�̂ɍL���Ă������Ƃ�ڎw���B �o�T�u�ǔ��V���v |
|
|
| �����E�̔r�o������A1360���h���K�͂ɁB�O�N��68����
�|�C���g�J�[�{���Ёi�{�Ѓm���E�F�[�E�I�X���j��2009�N�̔r�o������̎s��K�͂Ɋւ��钲�����ʂ\�B���E�I�Ȍi�C����ɂ��r�o�����i�̒ቺ�ɔ����A����z��2008�N��1330���h������1360���h���Ƃ킸���ȐL�т��������A����ʂ�68���̑������L�^��82���g���ƂȂ����B �s��ʂł́A���B�A���iEU�j�̔r�o�ʎ�����x�iETS�j�A�����č��A�����{����N���[���J�����J�j�Y���iCDM�j�A�č��k�����œW�J����Ă���n�扷�����ʃK�X�E�C�j�V�A�e�B�u�iRGGI�j���s��������B���ł�ETS�̎���z�͐��E�s���68�����߂��B �o�T�uECOOL�v |
|
|
| ���@�@[�@2010/1�@]�@�@�� |
|
|
| ���_�C�L�����ȃG�l���ʂ̒�ĂŃt�b�f�ՔM�h���g�̂��߂����B
������O�ǂɓh�邱�Ƃœ����ɔM��`���ɂ���������������A�̓d�͕��ׂ��y���ł�����Z�p�Ƃ��Ē�āB �H���Ζ��^���N�A�D�������̉c�Ɗ�����{�i���B�C�O�ł��g�̗\��B���̎ՔM�h���͔��˗��̍����痿�̓����ɂ��A�h���ʂ����z���˂��A�����̉��x�㏸��}���B�ό������������ȃt�b�f�h���̓����ɂ��A�����ԁA���O���Ȃǂɂ��炳��Ă��}���ɗ����A�ՔM���ʂ��ێ��ł���B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���j�c�c�h�������I�ɓd�͋������䂷��Z�p�J���B
���z���p�l���Ŕ��d�����d�͂Ɛ[��d�͂ŏ[�d�����~�d�r�̓d�́A���p�d�͂̎O�𐧌䂵�A���ԑт��Ƃɍł������I�ȓd�͋�������������u�g���C�u���b�g�����d�͐���Z�p�v���J�������B 12�����{����au�g�ѓd�b�̊�n�ǂɎ�����������B���ʂ�10�ǂʼn^�p���A���ʂ�ۑ�����B�ʐM�ǎɂ�f�[�^�Z���^�[�A�ƒ�ւ̓K�p���͍��\��B�V�Z�p�̊��p�ŁA�d�͎g�p�ʂƓ�_���Y�f�iCO2�j�r�o�ʂł��ꂼ��20�`30���̍팸���ʂ������ށB �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���{�X�g���R���T���e�B���O�O���[�v��ROC(���^�[���E�I���E�J�[�{��)�w�W�ɂ���Ɣ�r���ʂ����\�B
��Ƃ�2008�N�x�̍����c�Ɨ��v���A�����Ŕr�o����CO2�ʂŊ���Z�o����2006�N�x�̋Ɛт��r�����O�ʂƔ�r����ƁA�u��CO2�����v�v��Ƃ��Œ艻����X��������������B ������ROC��ʊ��(2008�N)�@(1)�L���m���@(2)���c��i�H�Ɓ@(3)���{�����Y�Ɓ@(4)���R�[�@(5)�L����HD�@(6)�A�T�q�r�[���@(7)�R�}�c�@(8)�O�H�d �@�@(9)�p�i�\�j�b�N�d�H�@(10)�O�H�d�H�� �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���C�[�X�N�G�A�����ʂ̂b�n2�r�o�g�𒆏�����W�u�܂Ƃߔ���v���Ƃ��v��B
�{�C���Ŏg�����ΔR�����o�C�I�}�X�i���������j�R���ɓ]������Ȃ�CO2�팸�Ɏ��g�ޒ�����Ƃ�A�X�ёg������鍑���N���W�b�g�Ȃǂ����r�o�g�͂P��������N���S�g���Ə��ʂŁA�܂Ƃ܂����ʂ̔r�o�g���K�v�ȑ��Ƃɂ͎g���ɂ��������B20�J�����x�̎��Ƃ��痈�t�ɂ͂P���g�������W�߂�\��B �̔����i�͔r�o�g�P�g��������3000�`5000�~�̌����݁B�ϐ����w�H�Ƃ⑹�Q�ی��W���p�����w��������B �o�T�u���o�Y�ƐV���v |
|
|
| ���o�����Y�������E�V�ۃr���Ɏ��R�G�l�̓d�C�̔��B
�����s�Ȃǂ̊��K�������ɑΉ����A����܂ł̓d�͂��͊��������A���R�G�l���M�[�ɂ��d�͂ŐV�ۃr���̏���d�͂̑S�ʂ��܂��Ȃ��v��B �N��3���g����CO2�r�o�ʂ̂����A�Q���g�������팸�ł�����ʂ�����B���͔��d�̓d�C���m�`�r�d�r�ɗ��߂Ď�����������Ŋ����d�͖ԂɂȂ��ق��A���͔��d�A�o�C�I�}�X�Ȃǂ͑��Ђ���w�����A�܂Ƃ߂ċ�������B �o�T�uSankei Biz �v |
|
|
| ���O�H�d�H�����ő��z�M���d�̎��v�����g�����݁B2013�N��10���K���b�g���p���B
���B�A�M�Ȋw�Y�ƌ����@�\�iCSIRO�j�Ƌ����Ō��݁B���@�\�̑��z�M�̎����ݔ����g���āA�܂�2010�N��600�L�����b�g�̑��z�M�W�M�V�X�e���̎��������{�B 2012�N�ɂ�1���K�`2���K���b�g�̎��v�����g��ݒu����B2013�N�ɂ�10���K���b�g�̃v�����g�����������ď��p������v��B�߂�CSIRO�Ɛ����Ɍ_��\��B600�L�����b�g�̎������s���܂ł̊J����p��20���~�́A���B����3����1�S�B���̌�̊J���͎O�H�d�H�����S�B��C�ŃK�X�^�[�r�����h���C�V�X�e�����������p����B�����s�v�Ȃ��ߍ����ł��v�����g���ғ��\�B �o�T�u�����H�ƐV���v |
|
|
| ���ۈ��@���n�M���d�֘A�̕ۈ��K���ɘa�ցB���S�������A�N�x���ɊJ�n�B
���q�͈��S�E�ۈ��@�́A�n�M���d�Ɋ֘A����ۈ��K���̊ɘa�ɏ��o���B �n�M���d�̃o�C�i���[�E�T�C�N�������̃^�[�r�����d�@�͓d�C���Ɩ@�ŁA�K�͂̑召�ɂ�����炸�A�{�C���[�E�^�[�r����C�Z�p�҂̏풓���`���Â����Ă���B���{�̋K�����v��c�����N�x�A�����V���ɎQ����ǂƕ]���B�o�ώY�ƏȂƂ��āA�K���ɘa�Ɍ����Ĉ��S���̋Z�p�I�Ȍ�����N�x���Ɏn�߂���j�����߂��B���N�x�̒lj��o�ϑ�ɂ��܂߂��B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| �����Ɍ������G�R�f�f���c��ƒ�̃G�R�x�f�f�B
���c��́A����u�n�����헪�����@�֊������Z���^�[�v�A���Ԋ�ƂȂǂō\���B���̔F������f�f�����ƒ��K�₵�A��p�̐f�f�\�t�g�Őf�f�B �Ɠd���i�̌`����N���A���p���ԂȂǂ��ڂ����A���P�[�g�������ACO2�ʂȂǂ��Z�o�B�①�ɂ̉��x�ݒ�̕ύX�ȂNJe�ƒ�ɉ������팸����Ă���B�{�N�x��200���т�ΏۂɎ��{�B �o�T�u�_�ːV���j���[�X�v |
|
|
| ���o�Y�Ȃ��r���̏ȃG�l�K�������̕��j�`�r���S�̂̏���ʂ𑍍��]���B
����A�G�l���M�[����ʂ��r���S�̂ő����]������d�g�݂����A�ȃG�l��𑁋}�Ɉ����グ����j�B �V���ɔ��\�́uZEB�i�l�b�g�E�[���E�G�l���M�[�E�r���j�̎����ƓW�J�Ɋւ��錤����v�̕��ł̒܂��A������i�߂�B�y�d�a�ł́A�ȃG�l�A�G�l���M�[�̑��ݗZ�ʁA�Đ��\�G�l���M�[�̊��p�Ȃǂňꎟ�G�l���M�[����ʂ������I�ɂقڃ[���Ƃ���B2030�N���܂ł̋Z�p�i���̌��ʂ��Ȃǂ����ƂɁA����w�̃I�t�B�X�r���ł���AZEB�̎����͋Z�p�I�ɉ\�Ǝ��Z�B�V�z���z���S�̂�30�N�܂ł�ZEB���������邱�Ƃ��r�W�����Ƃ��Čf�����B��������A30�N�̋Ɩ�����̃G�l���M�[����ʂ́A�����ނ˔����Ɨ\�z�B�lj��K�v�����z�͔N��8�牭�~���x�B �o�T�u�d�C�V���v |
|
|
| ���Z��ŃG�R�|�C���g���x�V�z��ˌ��ďZ���30���~�B
�ȃG�l���M�[���\�������V�z��ˌ��ďZ��̍w���ɂ͒�z��30���~�����̃|�C���g��^����Ȃǂ��āA�ȃG�l�Z��̐V�z��t�H�[�����㉟���A�Z��s�������������_���B �\�Z�͖�1�牭�~�B����21�N�x��2����\�Z������������ɍH���������������n���ꂽ�Z��ΏہB�V�z�Z��͗��N1������P�N�ԂɍH���ɓ����������ŁA�ȃG�l������������̋����@��������ȂǁA�Z��̃g�b�v�����i�[��ɑ�������Ƒ�O�ҋ@�ւ̔F�肪�K�v�B����A���ÏZ��̃��t�H�[���ł́A�����d�T�b�V�╡�w�K���X�Ɍ����A�O�ǂ�V��A���ɒf�M�ނ����t����H����ΏہB���̃|�C���g�͑傫���Ȃǂɂ���ĈقȂ邪�A1�J������1��5��~�����B �o�T�uSankei Biz �v |
|
|
| ���o�c�A����Y�f�Љ�v������\�B
�u���s�c�菑�v���Ԓ��̎���s���v��ɑ�����̂Ŋe�ƊE��2020�N�܂łɍŐ�[�Z�p�����A�v�V�Z�p�̊J����r�㍑�ł̔r�o�팸�x���Ɏ��g�ށB ����s���v��ł͎Y�ƁE�G�l���M�[�]����34�Ǝ킪�Ώۂ��������Ɩ��A�^�A����Ȃǂ̋ƊE�ɂ��Q�����Ăт�����B�e�ƊE�́A�ݔ��̐V�݁E�X�V���ɍŐ�[�Z�p���ő���������邱�Ƃ�O��Ƃ��āA2020�N�i�K�̔r�o�팸�ڕW��ݒ�B�o�c�A�͐��{�Ƃ��A�g���ĖڕW�̐i����`�F�b�N����B�v��ł́A�ڕW�B�����ł��Ȃ��ꍇ�A�C�O�̔r�o�팸���ƂŐ��܂��r�o�g�w���ȂǂŒB�����m���ɂ��邱�Ƃ����߂���B �o�T�uSankei Biz �v |
|
|
| �������h���s�ʼnƒ납���CO2�팸�ɐV���x�X�^�[�g�B
�����h���̉������ʃK�X��3����1�́A��ʉƒ납��̔r�o�B�e���т̃G�l���M�[�������グ�邱�Ƃ��}���B ���̐��x�́A�G�l���M�[����̏��Ȃ��u�����ւ̎�ւ���X�^���o�C�X�C�b�`�̐ݒu�A�ǂ≮�����ւ̒f�M�ނ̓����ȂǁA�e���т��ȃG�l�̂��߂̑[�u���ōs����B�܂��̓����h���k���J���f���n��Ɠ쐼���L���O�X�g���n��Ȃ�9�n��̐��т�ΏۂƂ��ăX�^�[�g�����A2015�N�܂łɃ����h���S���120�����т֍L����v��B�{�i�����ɂ��A�����h���s�̈�ʉƒ납���CO2�r�o�ʂ́A2015�N�܂ł�120���g���ȏ�̍팸�����ҁB �o�T�uecool�v |
|
|
| ���j���[���[�N�s�c��͉������ʃK�X�팸�ŏ��B�r�����L�҂ɉ��C���߂�B
����5�������t�B�[�g�i��4650�������[�g���j�ȏ�̍L�����������̏��L�҂�10�N��1�x�́u�G�l���M�[�č��v�����{���A�z�ǂ̎�芷����ǂ̕�C�Ȃǂ̕K�v�ȍH�����s���悤�v���B �V��ɉ����āA2025�N�܂łɌ����̏Ɩ����u���X�V���邱�ƂȂǂ����߂�B �o�T�u�����ʐM�v |